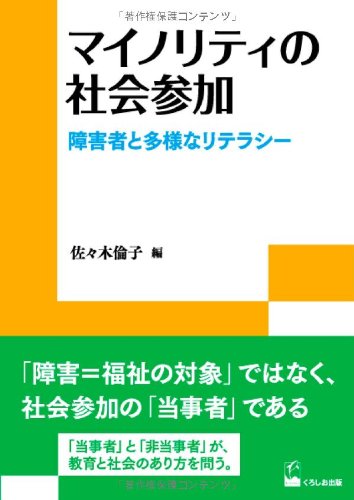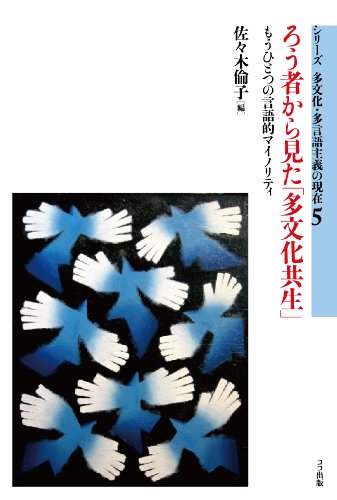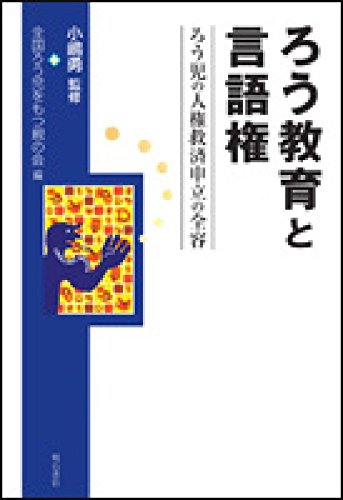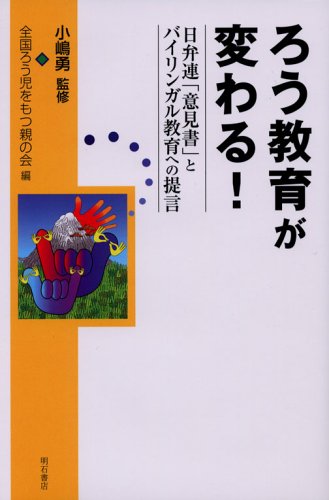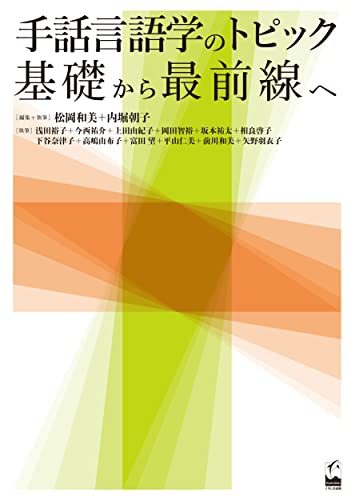【2025年】「手話」のおすすめ 本 71選!人気ランキング
- オールカラー やさしくわかる はじめての手話
- しくみが身につく手話1 入門編《DVD付》
- DVDつき ゼロからわかる手話入門―手の動きがすぐにマネできる「ミラー撮影」採用
- 〈文法が基礎からわかる〉 日本手話のしくみ
- オールカラー すぐに引ける 手話ハンドブック
- 実用手話辞典【第2版】
- すぐ使える手話 (ABCブックス)
- わくわく! 納得! 手話トーク
- 動画つき気持ちが伝わるはじめての手話
- 早引き 手話ハンドブック
基礎から子どもと一緒に学べる手話を掲載。耳の聞こえない人や手話への理解の輪が広がる一冊。 ★ みんなで覚えて会話しよう! ★ 手話で広がるコミュニケーション! ★ 子どもたちが使える単語や文章を 基礎からわかりやすく解説します! ◆◇◆ 監修者からのコメント ◆◇◆ みなさんは「手話」を知っていますか? 最近はテレビで見かけたり、学校で勉強したことのある人も多いと思います。 では、手話は「聞こえない人たちのことば」であることは知っていますか? 2006年に国連で障害者権利条約が採択され、手話は言語であると定められました。 その後、日本でも手話言語法を制定する運動が広がっています。 国の法律はまだできていませんが、全国各地で手話言語条例が次々に成立し、 手話を言語として認め、手話を普及させる運動が広がっています。 手話は、日本語を手や指の形に置き換えたものでなくひとつの言語です。 外国語を学ぶような気持ちで楽しく学んでもらいたいと思います。 この本には、手話の動きをイメージするイラストがたくさん載っています。 手の動きそのものをイラストから理解してどんどん手話であらわしてみてください。 学校でまだ教わっていない難しい漢字もたくさん載せました。 手話には漢字の形をあらわすものがたくさんあり、 聞こえない人に音であらわすひらがなより漢字の方が理解しやすい場合があります。 ふりがながふってあるので、たくさんの漢字を知るきっかけにしてみてください。 そして意味がわからなかったら辞書を引いて調べてみてください。 たくさんのことばを知り、様々なことに関心を持ち、疑問に感じたことは調べてみる。 それはあなたの大切な宝物となります。 この本を読んで、ぜひ手話サークルに足を運んでください。 そして、聞こえない人たちから手話を学んでください。 今まで知らなかった世界への扉が待っています。 たくさんの方が、この本を手にしてくれますように。 そして聞こえない人への理解が広がり、たくさんの人が手話という言葉を知ってくれますように。 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆1章 自己紹介をしてみよう *マンガ第1話 「アヤミとユウタの出会い 手話って・・・?」 * 「あいさつ」「名前」「指文字」「数字」・・・など ☆2章 学校の話をしてみよう *マンガ第2話 「ろう学校って知っている?」 * 「学校」「科目」「学校での生活」・・・など ☆3章 いっぱい話してみよう *マンガ第3話 「ユウタの家に遊びに行って」 * 「時間」「食べ物」「四季」・・・など *マンガ第4話 「聴導犬ってどんな仕事をするの?」
人気のWEB小説『オーバーロード』が書籍化されました。オンラインゲーム“ユグドラシル”がサービス終了を迎える中、プレイヤーがログアウトせず、意思を持つノンプレイヤーキャラクターが現れます。主人公は孤独な青年で、骸骨の姿を持つ大魔法使い“モモンガ”となり、ギルド『アインズ・ウール・ゴウン』を率いて異世界での冒険が始まります。著者は丸山くがねです。
最新言語学の成果も取り込んだ「ろう文化」入門の決定版で、アメリカでは手話を学ぶ際の必須文献として、教科書にもなっている。2003年、晶文社から刊行された翻訳書(絶版)を大幅に改稿した新版。 新版に寄せて まえがき はじめに――「ろう文化」への招待 第1章 ろうであることの発見 第2章 ろうのイメージ 第3章 異なる中心 第4章 聴者の世界で生きる 第5章 手話への新しい理解 第6章 音のもつ意味 第7章 歴史的創造物としてのろうの生活文化 訳者あとがき 訳者あとがき――新版にあたって 参考文献
アメリカのろう者の置かれている状況と,英語とは別の言語・ろう者自身の文化としての「アメリカン・サイン・ランゲージ(ASL)」の使用を主張する。 1 ろう社会とろう者の文化 2 生きた心地のしなかった夜 3 〈ろう〉コミュニティの内側 4 「目の見える人」からの覚え書き 5 音楽がなくても踊ることができるのですか 6 われわれの世界でもあるのだし 7 異なる次元 8 私の将来,私たち自身 9 〈ろう〉者には面白くても,聴者には面白くない 10 もしかりにアレグザンダー・グレアム・ベルの思いどおりになっていたら
序章 日本のろう教育は手話をどのように位置づけてきたか 日本手話によるろう教育をめざして. 1 フリースクール「龍の子学園」開校前史 日本手話によるろう教育をめざして. 2 フリースクール「龍の子学園」開校とその展開 学校法人「明晴学園」の設立とその特色 日本手話によるろう教育に立ちはだかるもの バイリンガルろう教育の再検討 終章
聾をめぐるディスコース空間 会話場面にみる聾者と聴者の関係性の検討 「手話・口話論争」の構造的把握 聾学校というディスコース空間 指導法におけるクレイムの方向性に関する分析 他学部教員からみた幼稚部に関するディスコースの検討 幼稚部部会における合意形成プロセス A聾学校における「聴覚手話法」構築過程 聾学校における日本手話導入をめぐる議論の検討 通常学校における情報保障としての手話通訳の可能性に関する検討 聾重複児への対応をめぐる手話の使用に関する検討 大学における合意形成プロセスに見る「聴覚障害学生支援」の性質 財源の確保と情報技術の活用の陥穽 情報保障としての手話通訳の性格 G大学における「手話通訳」導入の構築過程 本研究で得られた知見から示唆されること 本研究の方法論上の意義 今後の課題 構築主義アプローチによる聾教育の実践研究の可能性
はじめに ろう学校について ろう児と聴者教員の関係性と低学力 ろう児・者への英語リスニング試験 口話法と近代的言語観 言語権とバイリンガルろう教育 リテラシー論の現状と射程 ろう児のリテラシー論の特徴と課題 ろう児の日本語リテラシー実践 本研究のまとめ
はじめに 手話が言語だということは何を意味するか 手話言語条例と手話言語法 日本手話言語条例を実現させて ろう教育における手話のあるべき姿 手話言語条例が制定された県の取り組み 手話の言語法の意義 手話を言語として学ぶ・通訳する
手話話者の権利を訴えた『手話を言語と言うのなら』(2016)が刊行されて7年が経つが、日本手話を第一言語とするろうの子どもたちが学ぶ環境は依然として厳しい状況のままである。札幌聾学校において日本手話で学ぶ権利を求める訴訟が起こる中、国内外のろう・聴の研究者がともにその専門的見地からろう教育における自然言語としての手話の重要性を訴える。執筆者:オードリー・クーパー、菊澤律子、クリステル・フォンストロム、佐々木倫子、佐野愛子、ジム・カミンズ、杉本篤史、田中瑞穂、デボラ・チェン・ピクラー、戸田康之、富田望、ポール・ドゥディス、松岡和美、明晴学園、森壮也 この本を読んでくださる方へ 序章 日本手話をないがしろにし続けるろう教育―札幌聾学校訴訟まで― 田中瑞穂・佐々木倫子・佐野愛子 1. 日本のろう教育の流れ 2. 隠された当事者の声 3. 札聾の二言語教育 3.1 聴能主義下の日本手話クラス 3.2 二言語で学ぶ子どもの成長 3.3 成長する二言語教育 4. 暗転する二言語教育 第1部 ろう教育における「手話」 第1章 日本手話とはどういう言語か 森壮也 1. はじめに 2. 日本手話 3. 日本手話と手指日本語(日本語対応手話) 4. まとめ 第2章 ろう児の発達における日本手話の重要性 松岡和美 1. はじめに 2. 日本手話と日本語対応手話(手話アシスト日本語) 3. 動画に見られる違い 4. ろう教育におけるろうコミュニティの手話の重要性 5. おわりに 第3章 日本手話と日本語対応手話の特徴と違い 菊澤律子 1. はじめに 2. 「日本語」「日本語対応手話」「日本手話」の共通点と相違点 2.1 「日本語」「日本語対応手話」「日本手話」の概要 2.1.1 「日本手話」の言語としての構造と特徴 2.1.2 「日本手話」と「日本語対応手話」の違い 2.1.3 「日本手話」と「日本語対応手話」の違いが認識されづらいのはなぜか 3. 誰もが輝ける社会につながる教育の実現を! 第2部 ろう教育で用いられるべき言語 第4章 札幌聾学校の授業言語について ジム・カミンズ(訳 佐野愛子) 1. 札幌聾学校における方針転換 2. 自然手話の能力と他の学力との関係 3. さいごに 第5章 自然手話とろう教育 デボラ・チェン・ピクラー,ポール・ドゥディス,オードリー・クーパー(訳 松岡和美・佐野愛子) 1. はじめに 2. 自然な手話言語への早期アクセスはろう・難聴児に対する公平な教育機会への第一歩である 3. 自然手話+同じ地域の音声言語に基づく書記言語のバイリンガル教育環境は、着実な学力の発達を支えるものである 4. 音声言語に対応させた手指システムは、言語処理・理解の面で自然言語としての手話と比べて不十分であり、ろう・難聴児の教育に使用されるべきではない 第6章 スウェーデンのバイリンガル教育から クリステル・フォンストロム(訳 佐野愛子) 1. はじめに 2. なぜ自然手話のバイリンガル教育がろう児に不可欠なのか 3. 手話は本当に本物の言語なのか 4. 日本語対応手話と日本手話はどう違うのか 5. スウェーデン手話を授業言語とするスウェーデンのバイリンガルろう教育の経験とはどのようなものか 第7章 米国におけるアメリカ手話を用いたろう教育 富田望 1. はじめに 2. 手話を言語として認めた国 3. アメリカにおけるアメリカ手話を用いたろう教育の普及の現状 4. 自然言語である手話言語を 5. 聾学校での日本語対応手話が日本手話児に与える影響 第8章 明晴学園のバイリンガル・バイカルチュラルろう教育 学校法人 明晴学園 1. はじめに 2. 明晴学園の教育課程 3. 乳幼児教育における言語環境 4. 日本手話による教科学習 5. 自己肯定感を育てる教育 6. 手話科の成果 7. 第三者の評価およびまとめ 第9章 バイリンガルろう教育を阻むもの 佐々木倫子 1. はじめに 2. 従来型のろう教育の限界 (1) 「手話は言語ではない」とする誤解 (2) 「手話はひとつ」とする誤解 (3) 「聾学校では手話で教えている」という誤解 (4) 「手話は使っていれば自然に育つ」という誤解 (5) 「テクノロジーがろう児をなくす」とする誤解 (6) 「手話言語法制定が手話を社会で確立する」という誤解 第3部 権利としての日本手話 第10章「日本手話」と明記した手話言語条例 戸田康之 1. はじめに 2. 「朝霞市日本手話言語条例」の施行 3. 手話通訳を「日本手話」で 4. 「日本手話」を使用するろう通訳者の有効性について 5. 手話言語として「日本手話」を獲得するろう児たち 第11章 ろう児が日本手話で学ぶ権利について 杉本篤史 1. はじめに 2. 言語権とは 2.1 国際人権法における言語権概念の受容と発展 2.1.1 宣言 2.1.2 日本国が批准した条約 2.2 国際人権法における言語権概念(小括) 2.2.1 第1言語(L1:First Language)に関する権利 2.2.2 民族継承語(HL:Heritage Language)に関する権利 2.2.3 ある地域で広く使用されている言語(CSL:Commonly Spoken Language)に関する権利 2.2.4 言語権を保障するための国や自治体の責務 3. 言語権と日本の国内法制 4. ろう児が日本手話で学ぶ権利について 4.1 日本国憲法における根拠 4.2 日本の締結する国際人権条約上の根拠 4.3 「L1 を剥奪されない権利」の重要性 提言 これからのろう教育のあり方について 佐野愛子・佐々木倫子・田中瑞穂 1. 日本手話に堪能なろう者を、幼児児童生徒もしくはその保護者から希望の出たすべての教室に配置する体制を整えること 2. 日本手話に堪能なろう者の教員免許取得に向けた支援・養成の対策を早急に講じること 3. すでに教員免許を持っている現職の聾学校教員に対し、日本手話の運用能力を高め、バイリンガルろう教育の専門性を高められるような研修の取り組みを強化すること 4. 聾学校における教育課程に「日本手話」の学びを位置付けること 執筆者一覧
ビジュアル・リテラシーの重要性 テクノロジーとリテラシーの多様性 聴者の家庭に生まれた1ろう者の声 デフファミリーに生まれた1ろう者の声 モンスターの分析 ろう者がろう者に聞く 当事者と非当事者 デフ・インタープリター入門 ろう児に対する教育政策 情報のユニバーサルデザイン ろう児のバイリンガル・リテラシーの育成 マイノリティと多様なリテラシー
日本手話話者の道のり 日本手話を第一言語とするろう者の道のり ろう親をもつコーダの道のり・手話通訳者の道のり ろう児をもつ親たちの道のり 言語権をめぐる道のり 自然言語としての日本手話 脳が示す自然言語としての日本手話 文法が示す自然言語としての日本手話 世界における自然言語としての手話 「多文化共生」を標榜する社会を変えるために ろう教育のこれから ろうコミュニティのこれから 言語教育政策のこれから
2003年5月,ろう学校で「日本手話」による教育を求める人権救済申立が行われたが,その申立を裏づける根拠を言語習得,言語教育政策,言語権などの研究における第一人者たちが論じるとともに,人権救済申立書の全文,さらに申立に関するQ&Aも掲載。 はじめに(全国ろう児をもつ親の会・代表 岡本みどり) 1 言語学からみた日本手話(市田泰弘) 2 ろう児の母語と言語的人権(古石篤子) 3 なぜ二言語教育なのか——言語権の観点から(木村護郎クリストフ) 4 言語権について——国際人権と日本国憲法(小嶋勇) 5 言語抹殺とろう者(トーヴェ・スクトナブ=カンガス著/中村成子訳) 6 学年相応のカリキュラムへ——ろう児に内容が伝わるためのろう教育の基本原理(ギャローデット研究所紀要/澁谷智子訳) 7 水俣学という鏡に映し出す「ろう教育」(板垣岳人) 8 人権救済申立書 9 人権救済申立に関するQ&A(小嶋勇) 付録 人権救済申立とその後(全国ろう児をもつ親の会) おわりに(小嶋勇) 索引
2005年2月に日弁連により出された「手話教育の充実を求める意見書」を掲載するとともに,法律,教育,言語,歴史等の様々な方面の専門家およびろう者自身の立場から,意見書の意義・問題点を分析。手話と日本語のバイリンガルろう教育のあり方を探る。 はじめに(全国ろう児をもつ親の会・副代表 玉田さとみ) 1 手話言語と言語政策(イ・ヨンスク) 2 日本手話はろう者の魂(羽柴陽介) 3 明治後期の東京盲唖(聾唖)学校における教育内容の歴史的一考察(野呂 一) 4 ろう児の言語発達と教育——言語教育の観点から(佐々木倫子) 5 日弁連「意見書」と人権救済申立(小嶋 勇) 6 手話教育の充実を求める意見書 おわりに(小嶋 勇)
「手話」に関するよくある質問
Q. 「手話」の本を選ぶポイントは?
A. 「手話」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「手話」本は?
A. 当サイトのランキングでは『オールカラー やさしくわかる はじめての手話』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで71冊の中から厳選しています。
Q. 「手話」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「手話」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。