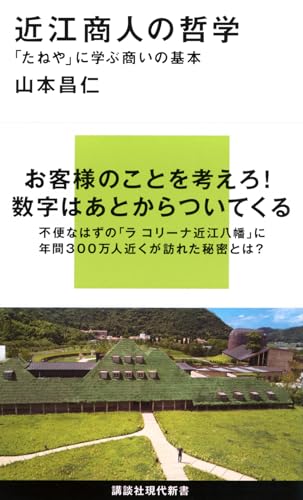【2025年】「福沢諭吉」のおすすめ 本 64選!人気ランキング
- 独立国家のつくりかた (講談社現代新書 2155)
- 福沢諭吉「学問のすすめ」 ビギナーズ 日本の思想 (角川ソフィア文庫 330 ビギナーズ日本の思想)
- 福沢諭吉 (おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 15)
- 福沢諭吉の『学問のすゝめ』
- こども「学問のすすめ」
- 子育ては諭吉に学べ! (単行本)
- 福沢諭吉 (伝記を読もう 26)
- 福沢諭吉 変貌する肖像 ――文明の先導者から文化人の象徴へ (ちくま新書 1745)
- 福沢諭吉 (世界の伝記 コミック版 7)
- 新訂 福翁自伝 (岩波文庫 青 102-2)
福沢を取り巻く世論の変化がわかれば、日本近現代史がわかる。百年にわたる毀誉褒貶の系譜をたどり、福沢の実像を浮かび上がらせる。 福沢の思想は毀誉褒貶にさらされてきた。その世論の動向を見ていけば日本近現代史が見えてくる。福沢評価の変遷の系譜をたどり、福沢の実像を浮かび上がらせる。 福沢の思想は毀誉褒貶にさらされてきた。その世論の動向を見ていけば日本近現代史が見えてくる。福沢評価の変遷の系譜をたどり、福沢の実像を浮かび上がらせる。 福沢の思想は毀誉褒貶にさらされてきた。それは福沢の議論の変化というよりも、福沢をとりまく世論の側の変化によるものといえる。福沢を評価した徳富蘇峰は、晩年には福沢が日本の伝統的な良風美俗を破壊したと罵倒。戦後は丸山眞男から原則ある実学思想家として賞賛されるも、朝鮮蔑視の脱亜論者として批判もされ、他方で一九八〇年代半ば以降は一万円札の肖像となり、文化人の象徴となった。福沢評価の変遷をたどり、その過程を詳細に考察。福沢の実像を浮かび上がらせる。
国家の発展に必要なものとは何か――。福沢諭吉は生涯をかけてこの課題に挑んだ。今こそ振り返るべき思想。解説 細谷雄一 国家の発展に必要なものとは何か――。福沢諭吉は生涯をかけてこの課題に挑んだ。今こそ振り返るべき思想を明らかにした画期的福沢伝。解説 細谷雄一
明治5年、福沢諭吉は西洋の道徳的な物語を集めたイギリスの"Moral Class-book"という本を、『童蒙おしえ草』という題名で日本に紹介しました。「ひびのおしえ」は、福沢諭吉が38歳の時、自分の息子たちに毎日一つずつ、家庭での約束や決まり事を半紙に書いて与えたものです。 本書は、慶應義塾幼稚舎教諭の訳者が、今の子どもたちに、保護者の方や先生方といっしょに読んで、いっしょに考えてもらいたいと願って、わかりやすい現代の言葉づかいに直したものです。 童蒙おしえ草 巻の一第一章 生き物を大切に(イ)少年たちとかえる(寓言[たとえ話])(ロ)兄弟と小鳥の巣(ハ)少年と顕微鏡(ニ)刑務所のラ・テュードとねずみ〔解説〕第二章 家族を大切に(イ)親を背負うねずみ(ロ)親を大切にする若者(アナピアスとアンフィノムス)(ハ)アレキサンダー大王と母(ニ)フレデリック大王とその家来(ホ)ポルトガルの兄と弟〔解説〕第三章 いろいろな人との交流(イ)君主アルフォンソ(ロ)主人の言葉(ハ)お手伝いのメアリ(ニ)プランクスの友情(ローマの古い大統領)(ホ)主人を助けた従者〔解説〕第四章 働くこと(イ)考えた遺言(寓言)(ロ)ケレシンの魔法(ハ)よく働く大工(ニ)ベンジャミン・フランクリン(ホ)貧しいリチャードの諺(ヘ)暇にしていられない(ト)暇すぎた人の話〔解説〕第五章 自分の子ことは自分でする(イ)ヘラクレス神(ロ)麦畑のひばり(寓言)(ハ)貴族ロバート・アイネスの独立(ニ)「行け」と「来い」との違い〔解説〕第六章 あわてないこと(イ)考えの違う二人の婦人(ロ)娘の機転(ハ)火 薬〔解説〕童蒙おしえ草 巻の二第七章 自分で考え自分で判断し実行すること(イ)動くものは月か雲か(ロ)インディアンの機転(ハ)ねずみと卵(ニ)遭難した水夫(ホ)画家の助手の投げた皿(へ)フランス人を捕らえた少年〔解説〕第八章 威張ったり、うぬぼれたりしないこと(イ)仮着をしたカラス(ロ)アイザック・ニュートンの人柄〔解説〕第九章 礼儀のこと(イ)一杯の水(ロ)イギリス人の親切(ハ)フランス国王ルイ十四世の礼儀〔解説〕第十章 飲食こと(イ)二匹の蜜蜂(ロ)ルーイス・コーナロの発心(ハ)ジャック・スィムキンの禁酒(ニ)美味は粗食にあり〔解説〕第十一章 健康なこと(イ)湿気深い家(ロ)胃の病気を治す名高い医師(ハ)若い男の風邪〔解説〕第十二章 自ら満足すること(イ)黄金の卵を生むガチョウ(寓言)(ロ)イギリスの宰相ダンダス(ハ)御殿のねずみと田舎のねずみ(ニ)貧院の婦人(ホ)かえるの仲間に王様を(寓言)〔解説〕第十三章 お金を無駄に使わない(イ)ありときりぎりす(寓言)(ロ)英雄の倹約(ハ)質素で倹約な家庭(ハンエルの文)(ニ)ハーフ・ア・クラウンのお金の値うち〔解説〕童蒙おしえ草 巻の三第十四章 思いやりのある心(イ)ジョン・ハワードの収容所の改革(ロ)騎兵隊長フィリップ・シドニの心(ハ)市長ジョージ・ドラモンドの親切(ニ)ポーランドの将軍コシューシコの馬(ホ)ローマの皇帝ティトゥスの一日(ト)日々つとめること〔解説〕第十五章 怒ったり、我慢したりすること(イ)ギリシャの哲学者ソクラテスの忍耐(ロ)気だてのよい人の話(ハ)我慢でまとまった家族(ニ)恨みを忘れてその罪を許した人(ホ)海賊とラーティング(へ)ウベルトの我慢(ト)トービーおじさんとハエ〔解説〕第十六章 穏やかなこと(イ)風と太陽と旅人と(寓言)(ロ)ジョーゼフ・ホルトと囚人(ハ)君主アルフォンソのやさしさ〔解説〕第十七章 自分の物と他人の物(イ)つばめの巣を盗んだすずめ(ロ)ミラノの門番の拾い物(ハ)レナードの判断(ニ)モーゼス・ロートシルト(ドイツの国際金融業者)〔解説〕第十八章 他人の名誉(イ)ソクラテスを陥れたこと(ロ)美人ヘレン・プライム〔解説〕童蒙おしえ草 巻の四第十九章 自由と権利(イ)フランスの「ジャックリーの一揆」(ロ)トーマス・クラークソン(奴隷廃止論者)〔解説〕第二十章 仕事を誠実にすること(イ)目の見えない人と盲導犬(ロ)ジョージ・ワシントン(アメリカの初代大統領)(ハ)裁判官ギャスコイン(ニ)誠意のある選挙人〔解説〕第二十一章 お金の貸し借り(イ)バレイスの君主ジョージ・ルーイスの倹約(ロ)アメリカ商人デナムの返済(ハ)貴族ウェルズリーの義理がたさ〔解説〕第二十二章 品 格(イ)ジョージ・デイドの品格〔解説〕第二十三章 買物をするとき(イ)正直な少年(ロ)うそをついた商人〔解説〕第二十四章 約 束(イ)ムーア人のしきたり(ロ)フランス王ジャン二世の約束〔解説〕第二十五章 人の邪魔や悪戯(イ)蜜蜂と黄蜂(寓言)(ロ)象と洋服屋のいたずら〔解説〕第二十六章 うそや偽りのいけないこと(イ)羊飼の少年が「狼」と叫んだこと(ロ)正直とうそ(ロバートとフランク兄弟)(ハ)アメリア・バーフォードのうそ(ニ)ヘレン・ウォーカーの真実〔解説〕童蒙おしえ草 巻の五第二十七章 心の広い人(イ)マケドニアの君主フィリップ(ロ)ウィリアム三世とゴドルフィン(ハ)マダム・ヴィラサーフ(ニ)若い画家三人(ホ)やせ犬のわずらわしさ(ヘ)ハバナの市長(キューバの港)〔解説〕第二十八章 勇気のある人(イ)グレイス・ダーリング(ロ)瓦職人の子トム〔解説〕第二十九章 わが国を大切にし、外国と仲よくすること(イ)ギリシャの将軍テミストクレス(ロ)フランスのカレーの義士〔解説〕ひびのおしえ 一編おさだめ(七つの大切なこと)本を読むひどいことをしない子どもの独立人の心の違い心の障害体と衣類を清潔に勇気とはゴッド(神、創造主)の心人間と動物との違い桃太郎と鬼が島心の怪我数を知ること一日の時(昔の時)おだやかにすること難しい仕事をする人、易しい仕事をする人人のふりみて我がふりなおせひびのおしえ 二編おさだめ(六つの大切なこと)天道さまのおきて学問をすべし日本の時と西洋の時時 刻矩尺とくじら尺一歩、一畝、一反、一町雪は白く、墨は黒い社会のために役立つこと色の白と黒
日本文化論に関する重要かつ基本的なキーワードと代表的な古典を,歴史的・相対的な視点からわかりやすく解説した書。 日本文化論に関する重要かつ基本的なキーワードと代表的な古典を,わかりやすく解説。「両立型」という概念を軸に,歴史的・相対的な視点から選び出された125のキーワードで,日本文化を読み解く。日本文化論を学ぶ学生,日本に関心をもつ留学生にお勧め。 総 論 第1章 日本文化のキーワード 第2章 古典を通して「日本」を読む 第3章 日本文化はどう論じられてきたか 第4章 日本文化論はイデオロギーか 第5章 外から見た「日本」 引用・参考文献一覧 事項索引 人名索引
近代日本社会におけるあるべき宗教の姿を福澤はどのように捉えていたのか。その宗教観の変遷を著作を年代順にたどりなから、時代背景、海外の思想家(J.S.ミル、F.ウェーランド)との影響などを含め考察する。 自ら無信仰を公言してはばからなかった福澤が、晩年になって到達した独自の宗教哲学ともいうべき境地の思想的意義を検証。現代日本人にも通じる、その思想の新たな側面が明らかにされます。 第一章 宗教における西洋と日本との出会い 第二章 福澤諭吉とキリスト教 第三章 フランシス・ウェーランドと福澤諭吉 第四章 ジョン・スチュアート・ミルと福澤諭吉 第五章 福澤諭吉と仏教 第六章 『福翁百話』における実学思想と宗教哲学
この書籍は、日本の伝統がどのように形成され、私たちがそれをどのように受け入れてきたかを探る内容です。初詣や神前結婚式などの具体例を通じて、「伝統リテラシー」を身につけることを目的としています。目次には、季節や家庭における伝統、地域の特徴、神社仏閣や祭り、外国の影響などが取り上げられています。著者は藤井青銅で、作家や脚本家として活動しています。
1946(昭和21)年4月に発表された「堕落論」によって、坂口安吾(1906‐1955)は一躍時代の寵児となった。作家として生き抜く覚悟を決めた日から、安吾は内なるとの壮絶な戦いに明け暮れた。他者などではない。このこそが一切の基準だ。安吾の視線は、物事の本質にグサリと突き刺さる。 ピエロ伝道者 FARCEに就て ドストエフスキーとバルザック 意欲的創作文章の形式と方法 枯淡の風格を排す 文章の一形式 茶番に寄せて 文字と速力と文学 文学のふるさと 日本文化私観 青春論 咢堂小論 墜落論 墜落論(続墜落論) 武者ぶるい論 デカダン文学論 インチキ文学ボクメツ雑談 戯作者文学論 余はベンメイす 恋愛論 悪妻論 教祖の文学 不良少年とキリスト 百万人の文学
著者の網野善彦は、日本中世の歴史を再評価し、農業中心社会のイメージや商工業者、芸能民の賤視について考察しています。文明史的大転換期における貨幣経済、階級差別、権力、信仰、女性の地位、多様な民族社会の実態を明らかにし、均質な日本社会像に疑問を呈しています。書籍は続編と共に文庫化され、歴史の多様な側面を平易に語ります。
本書は、與那覇潤による日本史の新たな視点を提供する作品で、従来の「西洋化」や「近代化」の枠組みを捨て、「中国化」や「再江戸時代化」という概念を用いて日本の歴史を再構築します。源平合戦から東日本大震災までを俯瞰し、歴史の流れを新しい視点で描き直す内容です。また、宇野常寛との特別対談も収録されています。著者は愛知県立大学の准教授で、日本近現代史を専門としています。
日本軍がなぜ戦争に負けてしまったのかを分析し、それを元に日本の組織における問題点を浮き彫りにしている書籍。責任の所在の曖昧さと、臨機応変に対応できない官僚主義が蔓延した日本組織は危機的状況において力を発揮できない。少々歴史の話は冗長だが一読する価値のある書籍。
「福沢諭吉」に関するよくある質問
Q. 「福沢諭吉」の本を選ぶポイントは?
A. 「福沢諭吉」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「福沢諭吉」本は?
A. 当サイトのランキングでは『独立国家のつくりかた (講談社現代新書 2155)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで64冊の中から厳選しています。
Q. 「福沢諭吉」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「福沢諭吉」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

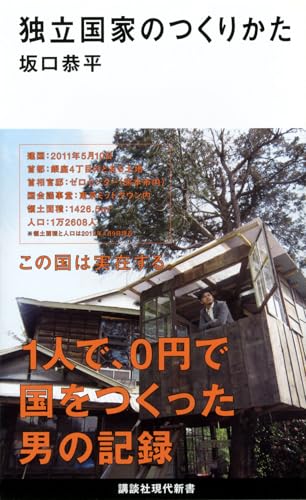















































![『「甘え」の構造 [増補普及版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51DUHuVS+NL._SL500_.jpg)