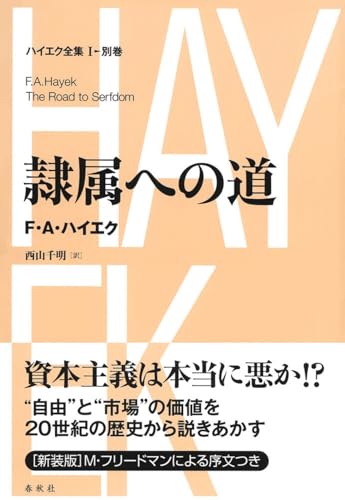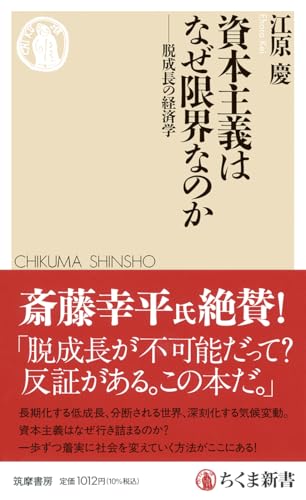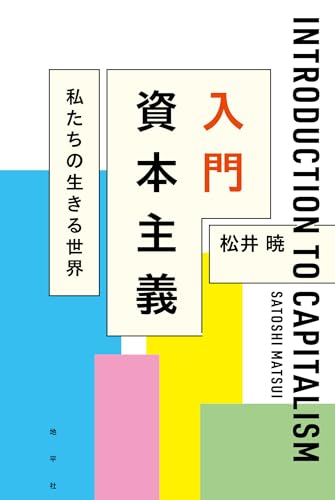【2025年】「共産主義」のおすすめ 本 105選!人気ランキング
- 新版 増補 共産主義の系譜 (角川ソフィア文庫)
- 反共と愛国-保守と共棲する民主社会主義 (単行本)
- ハイエク全集[Ⅰ-別巻]隷属への道〈新装版〉
- 人新世の「資本論」 (集英社新書)
- ノスタルジア酒場
- AMERICAN MARXISM アメリカを蝕む共産主義の正体
- 中国の歴史認識はどう作られたのか
- 毛沢東 大躍進秘録
- 肩をすくめるアトラス 第一部
- 自分の意見で生きていこう――「正解のない問題」に答えを出せる4つのステップ
この書籍は、環境危機の時代「人新世」における資本主義の限界を論じ、気候変動を防ぐためには無限の利潤追求をやめる必要があると主張しています。著者の斎藤幸平は、晩期マルクスの思想を基に、脱成長コミュニズムが豊かな未来社会を実現する道筋を示しています。内容は、気候変動、資本主義の問題、マルクスの再解釈、そして気候正義についての議論を含んでいます。著者は経済思想の専門家であり、社会の持続可能な発展に向けた具体的な提案を行っています。
全米120万部!ニューヨークタイムズ・ベストセラー1位 Amazonオールジャンル1位の驚愕の書!! 全米120万部!ニューヨークタイムズ・ベストセラー1位 Amazonオールジャンル1位(3万3000以上のレビュー)驚愕書の邦訳!ニューヨークタイムズで7回1位を獲得したベストセラー作家、フォックスニュースのスター、マーク・R・レヴィンが、もっとも共産主義とはかけ離れているイメージのアメリカという国が、じつは共産化しているという事実を解き明かす衝撃の書。マルクス主義思想の核となる要素が、学校、報道機関、企業、ハリウッド、民主党、バイデン大統領など、アメリカの社会と文化にいかに浸透しているか、そしてそれが「進歩主義」「民主社会主義」「社会運動主義」などの欺瞞に満ちたラベルで隠蔽されていることを解説。レヴィン氏ならではの鋭い分析で、これらの運動の心理や戦術、学生への広範な洗脳、批判的人種理論やグリーン・ニューディールの反米的目的、反対する声を封じ込め適合性を強制するための弾圧や検閲のエスカレートなどを掘り下げていく。必ず知っておくべきアメリカという国の真実!
人気ブロガーによるベストセラーシリーズの最終巻では、「正解のない問題に答えを出す力」、つまり「自分だけの意見を持つこと」の重要性とそのトレーニング方法が解説されています。具体的には、意見の価値やリーダーシップとの関係、SNS時代における自己表現の方法などが取り上げられています。著者はちきりんで、社会派ブログを運営しています。
本書は、カール・マルクスの『資本論』を現代社会に生かすための新しい入門書です。資本主義の構造やメカニズムを理解することで、格差社会の形成や自己啓発の限界を考察し、労働者階級の意識を喚起することを目的としています。具体的には、「商品」「包摂」「剰余価値」などの重要概念を通じて、現代の資本主義の問題点や階級闘争の重要性を解説しています。著者は、資本主義を内面化した人生からの脱却を促し、読者に新たな思考法を提供します。
この書籍では、生産性の重要性と向上方法を多くの事例を交えて解説しています。日本のホワイトカラー業務の長時間労働が経済低迷の一因であることを指摘し、忙しい管理職や家庭と仕事の両立に悩む母親、フリーランス、起業家の物語を通じて、現代の働く人々の問題点を明らかにします。著者は高生産性社会の必要性を説き、働き方の見直しを提案しています。
経済が発展しても、私たちは決して豊かになれない。資本主義にあらかじめ組み込まれた根本的矛盾を、世界的政治学者が明らかにする。 資本主義は私たちの生存基盤を食い物にすることで肥大化する矛盾に満ちたシステムである。世界的政治学者がそのメカニズムを根源から批判する。(解説・白井聡) 資本主義は私たちの生存基盤を食い物にすることで肥大化する矛盾に満ちたシステムである。世界的政治学者がそのメカニズムを根源から批判する。 なぜ経済が発展しても私たちは豊かになれないのか。それは、資本主義が私たちの生活や自然といった存立基盤を餌に成長する巨大なシステムだからである。資本主義そのものが問題である以上、「グリーン資本主義」や、表面的な格差是正などは目くらましにすぎず、根本的な解決策にはなりえない。破局から逃れる道はただ一つ、資本主義自体を拒絶することなのだ――。世界的政治学者が「共喰い資本主義」の実態を暴く話題作。解説 白井聡
ソ連型社会体制の崩壊を経験した現在、先進資本主義国において福祉国家を推進してきた社会民主主義こそがもっとも期待できる社会主義の潮流であり、新自由主義によって縮小された福祉国家を再建することが社会主義の当面の課題である。 しかし、グローバル化と情報化の段階にある今日の資本主義のもとで福祉国家を永続化させることは不可能であり、われわれは再建福祉国家からさらに生産手段を社会的所有にした共産主義社会へと進まねばならない。したがって今日の社会民主主義に求められるのは、マルクス派社会主義へと自らを刷新することなのである。 本書ではこの展望の根拠を、今日の福祉国家が直面する四つの問題、すなわち経済成長か定常状態か、「労働の解放」か「労働からの解放」か、国家の存続か廃絶か、ナショナリズムかコスモポリタニズムかに取り組むことを通じて提示する。 まえがき 第1章 社会民主主義の再生 1 はじめに 2 マルクス主義と四つの論点 3 福祉国家 4 社会民主主義の分岐 5 社会民主主義の再生とマルクス主義 6 社会民主主義から社会主義へ 第2章 生産力の発展 1 はじめに 2 生産力の概念 3 生産量:P1 4 自然制御能力:P3 5 生産性:P2 6 小括 第3章 労働の廃絶 1 マルクス主義的な労働観のアポリア 2 社会発展論における労働と自由時間 3 疎外された労働 4 『資本論』における「労働日の短縮」 5 人間本質としての労働 6 マルクス主義と労働 第4章 所有・労働・生産手段 1 問題の所在 2 所有と労働の定義 3 労働所有論:TL 4 生産手段所有論:TOMP 5 二つの理論の関係 第5章 疎外態としての国家 1 問題の所在 2 疎外国家論 3 階級国家論 4 アナーキズム 5 自由主義国家論 6 小括 第6章 グローバル化 1 反グローバル化運動 2 社会主義への移行についてのマルクスの学説 3 非資本主義的発展の道 4 資本主義の発展としての社会主義 第7章 結論 参考文献 あとがき 事項索引 人名索引
技能実習生・アインをめぐる小説と、ベトナムで教鞭をとる専門家による解説で、技能実習制度の問題点と解決策を明らかにする一冊。 技能実習生・アインをめぐる小説と、ベトナム国立大学で教鞭をとる専門家による解説で、技能実習制度の仕組みと問題点を明らかにする一冊。リスクを負って来日する実習生の実情と、新たなキャリア教育の必要性が明らかになる。 ■定価 1,980円(本体1,800円+税) ■小説×解説で、技能実習制度の本質がわかる。 ──夢やぶれた技能実習生が、未来を取り戻す物語。 ベトナム中部、フエ。現地の大学を卒業したアインは、金銭の魅力と日本への憧れから、技能実習生として日本で働く道を選んだ。いわれるままに学歴を詐称し、大卒者であることを隠して日本で働くアインは、単純労働の繰り返しの果てに、ひとつの事実に気づく。彼女の将来の可能性は、もうどうしようもないほどに行き詰まってしまっていた。 米国国務省によって、制度を悪用した強制労働の存在を指摘されるなど、さまざまな視点から問題が提起されている日本の技能実習制度。本書では、行き詰まる実習生たちの挫折と再起を描く「小説」と、ベトナムで教鞭をとる著者自身の手による「解説」という両面から、技能実習制度の本質が描かれる。 一時の金銭と引き替えに、技能実習生たちは何を失うのか。そして、日本という国の将来に、技能実習制度はどのような影響を及ぼしていくのか。ベトナムで元・実習生の再教育に携わってきた著者の紡ぐ物語と解説が、日本の「いま」を明らかにする。 ■映画『縁の下のイミグレ』原案作品 実写映画『縁の下のイミグレ』(なるせゆうせい監督作品、2023年公開)原案作品。映像を通して、本書が提起する技能実習制度の問題をより深く理解できる。 ■目次 はじめに 主な登場人物 第1部 碧い空の上。trên bầu trờixanh. 解説Ⅰ アインの決断──ベトナム技能実習生 解説Ⅱ 技能実習制度──「現実」の歪み 解説Ⅲ 「問い」から見えるもの 解説Ⅳ 呪縛 第2部 碧い空の中。trên đường đến bầu trờixanh. 解説Ⅴ 行政書士と在留資格制度 解説Ⅵ 「ベトナム人犯罪」 解説Ⅶ 評価されるキャリア 解説Ⅷ 技能実習制度の歪み、その正体。あるいは、文化資本のギャンブル的変容。 第3部 碧い空の下。dưới bầu trờixanh. 解説Ⅸ 在留資格制度における〈実務経験〉と〈上陸拒否期間〉 解説Ⅹ 評価されるキャリアと日本の実像 解説Ⅺ 日本の「簿外債務」=負の社会関係資本 エピローグ アインが見た、碧い空。 あとがき はじめに 主な登場人物 第1部 碧い空の上。trên bầu trờixanh. 解説Ⅰ アインの決断──ベトナム技能実習生 解説Ⅱ 技能実習制度──「現実」の歪み 解説Ⅲ 「問い」から見えるもの 解説Ⅳ 呪縛 第2部 碧い空の中。trên đường đến bầu trờixanh. 解説Ⅴ 行政書士と在留資格制度 解説Ⅵ 「ベトナム人犯罪」 解説Ⅶ 評価されるキャリア 解説Ⅷ 技能実習制度の歪み、その正体。あるいは、文化資本のギャンブル的変容。 第3部 碧い空の下。dưới bầu trờixanh. 解説Ⅸ 在留資格制度における〈実務経験〉と〈上陸拒否期間〉 解説Ⅹ 評価されるキャリアと日本の実像 解説Ⅺ 日本の「簿外債務」=負の社会関係資本 エピローグ アインが見た、碧い空。 あとがき
『妊娠小説』は、妊娠をテーマにした文学作品を分析した評論で、著者の斎藤美奈子が妊娠小説の歴史や構造、内容を探求しています。文庫化されたこの作品は、妊娠小説の進化や分類、物語の類型を考察し、意表をついた視点で読者に新たな理解を提供します。
本書は、人気ブロガーちきりんが「人生を二回生きる」という新しい働き方を提案するもので、定年延長や社会の変化に対応した人生設計のヒントを提供しています。内容は、働き方の現状、未来の変化、若者の新たな働き方、発想の転換、そしてオリジナルな人生を設計する方法について論じています。著者は自身の経験を基に、楽しく自分らしい生き方を追求する重要性を説いています。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
歴史学の大家による通史の決定版、世界的ベストセラー待望の邦訳。起源から現在までが一気に分かります。 歴史学の大家による、厳密にして明晰、そして驚くほどコンパクトな資本主義通史。その起源から現代の金融資本主義に至る長大な歴史と、アダム・スミスからシュンペーターに至る広範な分析理論までが一冊に凝縮。 通史の決定版 歴史学の大家による、厳密にして明晰、そして驚くほどコンパクトな資本主義通史。その起源から現代の金融資本主義に至る長大な歴史と、アダム・スミス、マルクス、ヴェーバーからシュンペーター、ポメランツに至る広範な分析理論までが一冊に凝縮。世界史的視野と、資本主義の本質に迫る深い考察が絡み合い、未来への展望をも示唆する名著。世界9か国で翻訳されたベストセラー。 第一章 資本主義とは何か 一 論議のつきまとう概念 二 三つの古典――マルクス・ヴェーバー・シュンペーター 三 他の諸見解と作業のための定義 第二章 商人資本主義 一 端緒 二 中国とアラビア 三 ヨーロッパ――ダイナミックな遅参者 四 一五〇〇年頃の時代についての中間的総括 第三章 拡大 一 ビジネスと暴力――植民地支配と世界交易 二 株式会社と金融資本主義 三 プランテーション経済と奴隷制 四 農業資本主義・鉱業・プロト工業化 五 資本主義・文化・啓蒙主義――時代の文脈におけるアダム・スミス 第四章 資本主義の時代 一 工業化とグローバル化――一八〇〇年以降の時代のアウトライン 二 オーナー資本主義から経営者資本主義へ 三 金融化 四 資本主義における労働 五 市場と国家 第五章 展望 「数百年におよぶ発展のなかで、資本主義はその姿を大きく変えうることを示してきた。歴史的概観とグローバルな比較が示すのは、それがきわめて多様な社会的・文化的・政治的諸条件のもとで存在しうることである。それは、社会、文化、政治にきわめて深い影響をおよぼす。しかし逆にそれは、政治の介入、社会的諸行為によって影響され、姿を変えうる。資本主義は定められた運命ではない。それは、過去においてきわめてさまざまな目的のために投入され、また現在でも投入されている強力な資源なのである。」(本書より) 日本語版のための序文 第一章 資本主義とは何か 一 論議のつきまとう概念 二 三つの古典――マルクス・ヴェーバー・シュンペーター 三 他の諸見解と作業のための定義 第二章 商人資本主義 一 端緒 二 中国とアラビア 三 ヨーロッパ――ダイナミックな遅参者 四 一五〇〇年頃の時代についての中間的総括 第三章 拡大 一 ビジネスと暴力――植民地支配と世界交易 二 株式会社と金融資本主義 三 プランテーション経済と奴隷制 四 農業資本主義・鉱業・プロト工業化 五 資本主義・文化・啓蒙主義――時代の文脈におけるアダム・スミス 第四章 資本主義の時代 一 工業化とグローバル化――一八〇〇年以降の時代のアウトライン 二 オーナー資本主義から経営者資本主義へ 三 金融化 四 資本主義における労働 五 市場と国家 第五章 展望 訳者あとがき 文献一覧 索引
終焉が予感されつつも〈その先〉が見えない資本主義。精神的・社会的現象として再定義し、〈その先〉へ行くための原理を示した渾身作 終焉が予感されつつも〈その先〉が見えない資本主義。精神的・社会的現象として再定義し、資本主義概念を刷新。〈その先〉へ行くための原理を示した決定的論考! 終焉が予感されつつも〈その先〉が見えない資本主義。精神的・社会的現象として再定義し、資本主義概念を刷新。〈その先〉へ行くための原理を示した決定的論考!
「文章読本」の歴史とその変遷を描いた作品で、名文家たちの指導や文章教育の変化を探求しています。著者は、文章読本のジャンルや内容、形式、読者層の影響を分析し、明治から現代までの作文教育の進化を考察。文庫化に際しては、ネット時代の文章について新たに執筆されています。著者は文芸評論家の斎藤美奈子で、小林秀雄賞を受賞しています。
著者ちきりんが、個人の思考力を高めるための方法を紹介する本。内容は、決定プロセスの重要性や、疑問を持つことの意義、情報のフィルターの重要性など多岐にわたる。著者は自身の経験を基に、思考を整理する方法やデータの活用法を提案し、読者が自分なりの答えを見つける手助けをする。
著者は、飽食の国での「食」に対する苛立ちから異境へ旅し、様々な食文化や状況を体験するルポルタージュを描く。ダッカの残飯やチェルノブイリの放射能汚染スープを含む多様な食の現実を通じて、人々との深い「食」の交わりを探求。文庫化に際し、新たに書き下ろしの独白とカラー写真が追加され、感動的な内容がさらに充実している。
資本主義はなぜ行き詰まるのか。経済成長というテーゼを根底から問い、一歩ずつ社会を変えていくための具体的な道筋を描き出す。 拡大する経済格差、気候変動、エネルギー問題……資本主義はなぜ行き詰まるのか。経済成長の前提条件を根底から問い、一歩ずつ社会を変えていく道筋を描き出す。 斎藤幸平氏 絶賛! 「脱成長が不可能だって? 反証がある。この本だ」 長期化する低成長、分断される世界、深刻化する気候変動。戦後日本の経済成長の条件であった労働力人口は減少、資源は枯渇し、待ったなしの環境問題に直面しつつある。資本主義はなぜ行き詰まるのか。持続可能な未来はいかにして可能か。「成長」を中心目標に掲げてきた経済学を根本から見なおし、際限なき利潤追求と再投資によって肥大化した経済システムを徹底解明。資本主義のからくりを読みとくマルクス経済学を手がかりに、一歩ずつ着実に社会を変えていく方法がここにある! はじめに 第一章 経済学の歴史――経済成長はいかにとらえられてきたか 経済学とはいかなる学問か/近代以前の経済とその変質/ポリティカル・エコノミーの成立/労働の学としてのポリティカル・エコノミー/古典派経済学にとっての「経済成長」/資本蓄積としての経済成長/マクロ経済学の成立 第二章 脱成長とは何か――経済成長概念の限界 経済成長の測り方/家事労働をどう考えるか―経済成長概念の限界①/国民経済という単位―経済成長概念の限界②/脱成長かGNDか/「反成長」でも「ゼロ成長」でもなく、脱成長を/脱成長の経済学としてのマルクス経済学 第三章 高度経済成長の条件――資本・労働・環境 経済成長の三つの条件/日本の高度経済成長/高度経済成長の影としての公害/日本におけるマルクス受容/マルクス経済学の帝国主義論/公害の政治経済学/エントロピーの経済学 第四章 低成長の時代――帝国主義的世界像の瓦解 ニクソンショックとオイルショック/帝国主義のあだ花としての「ジャパン・アズ・ナンバーワン」/情報化と金融化/グローバリゼーション/惑星規模の環境問題/公害の政治経済学の先へ 第五章 惑星の限界――プラネタリー・バウンダリー下での再生産 待ったなしの環境問題―プラネタリー・バウンダリーという考え方/再生産の考え方/再生産の拡大/資源制約と廃棄制約/資源制約が成長を押しとどめる?/廃棄制約は徐々に姿を現す/スループットと廃棄物処理過程を備えた再生産/プラネタリー・レベルの再生産/脱成長の必要性 第六章 脱成長論の基本構造 成長なくして利潤なし?―略奪による蓄積と利潤による蓄積/イノベーションは利潤の源泉ではない/労働力の搾取―労働者は企業に何を売り渡しているのか/「マルクスの基本定理」/二つの脱成長―利潤の追求と成長は別物/脱成長コミュニズム/脱成長市場経済―利潤の使い道をどうするか/脱成長へのルート/フローの社会化と商品の社会化 第七章 企業の価値を問いなおす――脱成長株式市場論 脱成長と株式市場は両立しうるか/株式とは何か/出資と貸付はどう違うか/創業者利得/割引現在価値/株価の理論値/株価はどうやって決まるのか/株式市場のルール/ESGインテグレーション―非財務情報を株価に反映する/成長にはコストがかかる/脱成長インテグレーション 第八章 貨幣の価値を問いなおす――脱成長貨幣論 貨幣の価値はどこからくるのか/貨幣の価値は貨幣の量で決まる?―貨幣数量説/貨幣の価値は国が決める?―表券貨幣説/貨幣の価値は商品の価値に由来する―商品貨幣説/国債に頼る貨幣発行/国債にはなぜ価値があるのか/国はどこまで借金できるのか―国債の上限/金融商品としての国債/経済成長と貨幣価値を切り離す/脱成長貨幣論と財政民主主義 第九章 資本主義の先へ――成熟した社会と脱成長 資本主義の爛熟と社会の成熟/資本主義と利他/利他としての人口問題/実は何も期待されていない経済成長/略奪による蓄積と脱成長市場経済との間で揺れ動く資本主義/脱成長市場経済という橋頭堡 参考文献/あとがき
この書籍は、古今東西の名作132冊を最後の一文から読み解く文学案内であり、意外なエンディングを探求しています。目次は青春、女子の選択、男子の生き方、不思議な物語、子どもの時間、風土の研究、家族の行方といったテーマに分かれています。著者は斎藤美奈子で、文芸評論家としての経歴を持ち、受賞歴もあります。
資本主義とは、そもそもどんな社会なのか? 私たちが当たり前だと思っているさまざまな現象を取り上げながら、わかりやすく解説。 資本主義とは、そもそもどんな社会なのか? 「会社と仕事」「就職活動」といった身近な問題から、「格差と競争」「経済政策」といった大きな問題まで、「常識」を問い直す批判的な目で解説していく。目から鱗の経済入門。 資本主義とは、そもそもどんな社会なのか? 「会社と仕事」「就職活動」といった身近な問題から、「格差と競争」「経済政策」といった大きな問題まで、「常識」を問い直す批判的な目で解説していく。目から鱗の経済入門。 1 資本主義 2 会社と仕事 3 就職活動 4 豊かさ 5 格差と競争 6 経済政策 7 国家と税金 8 社会主義へ
本書は、漱石の『吾輩は猫である』やサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』など、137冊の名作文学のラストを分析し、文豪のセンスや生き方を批評するブックガイドです。各章では、恋愛、少年少女の物語、童話、歴史小説、ミステリー、現代の奇譚、旅、社会問題など多様なテーマを扱い、意外な結末や深い洞察を提供します。著者は文芸評論家の斎藤美奈子で、楽しく知識を得られる内容となっています。
この書籍は、十五年戦争中の婦人雑誌に掲載された料理記事を通じて、戦時下の人々の食生活を描写しています。配給食材を使った工夫や節米料理、防空壕での携帯食など、極限状況でも維持された食の知恵を紹介。また、再現料理もカラーで掲載されており、「食」を通じて「戦争」を考察するための実用的なガイドブックです。文庫版には、敗戦後の食糧事情についての情報も追加されています。著者は文芸評論家の斎藤美奈子です。
「男の中に女がひとり」は、メディアにおける「紅一点」ヒロイン像を分析した評論です。著者は、魔法少女や紅の戦士、悪の女王といったキャラクターを通じて、女性の役割やイメージを探ります。目次にはアニメや伝記における紅一点のテーマが含まれ、著者は斎藤美奈子で、評論家としての経歴も持っています。
歴史にいかに向き合うべきか?サミュエル・ジョンソン賞受賞の女性歴史学者が 歴史と民族・アイデンティティ、歴史的戦争・紛争、9.11、領土問題、従軍慰安婦問題など豊富な実例から歴史の誤用、濫用を戒めた好著。 歴史にいかに向き合うべきか? サミュエル・ジョンソン賞受賞の女性歴史学者の白熱講義! 歴史と民族・アイデンティティ、歴史的戦争・紛争、9.11、領土問題、従軍慰安婦問題…。歴史がいかに誤用、濫用に陥りやすいか豊富な実例からわかりやすく解説。一方で、真摯に、取り扱いに注意しながら歴史を利用し学ぶことで、過ちを回避し、世界認識と相互理解を深める可能性を提示。世界史と、今日的国際問題を概観し、その関連を知り、理解を深め、安直な歴史利用を戒めた好著。 《本書の内容》 歴史ブーム 癒やしのための歴史 過去は誰のものか 歴史とアイデンティティー 歴史とナショナリズム 歴史濫用の収支勘定 歴史戦争 ガイドとしての歴史
資本主義とは何かを根源的に問い続けてきた理論経済学の第一人者による、学問諸領域を横断する知的魅力あふれるエッセイの集大成。 貨幣とは何か、資本主義とは何かを鋭く問い続け、従来の経済学の枠組みを超える新しい理論を構築してきた第一人者による、知的魅力あふれるエッセイの集大成。 貨幣とは何か、資本主義とは何かを鋭く問い続け、従来の経済学の枠組みを超える新しい理論を構築してきた第一人者による、知的魅力あふれるエッセイの集大成。
この本は、混迷する日本の現状を観察し、未来に向けた洞察を提供する内容です。目次には、リーダーシップや若者論、文化ブームの分析が含まれており、著者の斎藤美奈子は文芸評論家としての視点からこれらのテーマを掘り下げています。著者は1956年生まれで、1994年にデビューし、2002年には小林秀雄賞を受賞しています。
コロナ禍で露呈したのは、日本の貧困とみんなの不安。一億総中流は過去の夢。なぜこうなったのかを本を読んで考え続けた同時代批評。 コロナ禍で露呈したのは、日本には生活困窮者がこんなにいるということだった! 一億総中流は過去の夢。なぜこうなったのかを本を読んで考え続けた同時代批評。 コロナ禍で露呈したのは、日本には生活困窮者がこんなにいるということだった! 一億総中流は過去の夢。なぜこうなったのかを本を読んで考え続けた同時代批評。
戦争の最前線で、幼い少女ターニャ・デグレチャフが敵を撃ち落としながら軍を指揮する。彼女は実はエリートサラリーマンが神の暴走により幼女として生まれ変わった存在で、効率化と出世を重視し、帝国軍の危険な魔導師となっていく。
この本は、若者の投票率が低い理由を「ひいきのチーム」がないことに結びつけ、政治参加の第一歩として自分の立場を見つけることの重要性を説いています。内容は、体制派と反体制派、資本家と労働者、右翼と左翼など、政治的な二元論を探求し、リアルな政治を学ぶ方法を示唆しています。著者は文芸評論家の斎藤美奈子です。
この書籍は、文庫本に付随する解説の魅力を探求し、名作やベストセラーの背後にある解説の価値を再評価しています。著者の斎藤美奈子は、夏目漱石や太宰治などの作品を例に挙げ、解説が読者に新たな視点や発見をもたらすことを論じています。目次には、異文化や知識人についての考察も含まれており、現代文学における解説の重要性を強調しています。
この本は、過去50年間の日本の文学の変遷を振り返り、作家や読者がどのような作品に触れてきたかを探ります。政治やメディアの変化、社会問題を背景に、小説がどのように書かれ続け、読まれてきたのかを解説しています。目次には、1960年代から2010年代までの各時代の特徴が示されています。著者は文芸評論家の斎藤美奈子です。
株価の乱高下、都市部不動産の高騰と地方衰退、近代英国労働者のような低賃金、人口減少。令和バブル崩壊で露呈する資本主義の限界。 株価の乱高下、不動産高騰と地方衰退。近代英国労働者のような低賃金と貧富の差。労働力不足と未曾有の人口減少。令和バブル崩壊で露呈する資本主義の限界とは。 令和バブルともいうべき株や都市部不動産の高騰、急速に進行する地方経済の衰退。近代英国の労働者のような低賃金に貧富の差が拡大している。老後への不安に付け込み、税優遇などの誘惑によって引きずり込まれた危険なマネーゲームの乱高下はチキンゲームの様相を呈してきた。バブルは壊れて消えるのが必定。マルクスは、資本主義には貧困が必要なことを喝破したが、日本はいま未曾有の労働力不足、人口減少社会に直面している。――日本の末期的状況を、マルクスやエンゲルスの枠組みで読み解く。 第Ⅰ部 貧困がもたらす全国民的危機 第一章 迫りくる人口減の認識は決定的に不十分 第二章 貧困化と株価・地価バブルの同時存在 第三章 迫りくる財政破綻という全国民的危機 第四章 地方経済の崩壊を期待する原発企業と軍事基地 第Ⅱ部 貧困の原因を解明した『資本論』 第五章 中間層の貧困化で始まった資本主義 第六章 資本主義の継続に必要だった貧困 第七章 奴隷・農奴と同じ現在の労働者 第Ⅲ部 バブルと貧困の解消を主張する経済学 第八章 古くて新しい階級論 第九章 バブルの原因を問う数理マルクス経済学 第十章 賞味期限切れの資本主義
人気文芸評論家の斎藤美奈子が、過去のベストセラー48作品を現在の視点から評価し、その「賞味期限」を判定する書籍です。作品は、古典に昇格するものと忘れ去られるものに分かれ、名作度や使える度に基づいて評価されています。目次には、住井すゑや村上春樹などの著作が含まれ、それぞれの作品に対する感想やテーマが紹介されています。
この書籍は、子ども時代には気づかなかった少女小説の新たな魅力を大人になってから再発見する内容です。『小公女』や『若草物語』などの名作を通じて、戦う少女たちの物語とそのテーマを探求しています。各章では、少女たちが直面する課題や成長を描き、少女小説の意義を考察しています。著者は文芸評論家の斎藤美奈子です。
ケインズ研究の世界的権威による喜びのある労働と意味のある人生の実現に向けた経済政策の提言。目指すべきは、労働生産性の低下である。解説 諸富徹 ケインズ研究の世界的権威による喜びのある労働と意味のある人生の実現に向けた経済政策の提言。目指すべきは、労働生産性の低下である。解説 諸富徹 === 資本主義の下では資本の蓄積が自己目的化し、大企業は利益拡大にひた走る。結果、富める者だけが富み続け、雇用は不安定になり、格差が拡大する。成長の果実のおこぼれが一般庶民にもたらされないことは、ここ数十年の現実が証明済だ。であるならば政府が目指すべきは経済成長ではなく、国民の暮らしの質を上げることなのではないのか。著者らはその実現のために、余暇を生む労働時間の短縮、一定水準の暮らしを保障するベーシックインカムの導入、際限なき人間の欲望を抑えるための広告課税等の法整備を提案する。成長神話が叫ばれ続ける日本でこそ読まれるべき提言。 解説 諸富徹 === 富の使い先を変える 根源的な資本主義批判の書――諸富 徹 === 【目次】 はじめに 序論 第1章 ケインズの誤算 第2章 ファウストの取引 第3章 富とは―東西の思想を訪ねて 第4章 幸福という幻想 第5章 成長の限界 第6章 よい暮らしを形成する七つの要素 第7章 終わりなき競争からの脱却 原注 索引 訳者あとがき 解説 「善き人生」を支える資本主義のあり方を考える(諸富徹) はじめに 序論 第1章 ケインズの誤算 第2章 ファウストの取引 第3章 富とは―東西の思想を訪ねて 第4章 幸福という幻想 第5章 成長の限界 第6章 よい暮らしを形成する七つの要素 第7章 終わりなき競争からの脱却 原注 索引 訳者あとがき 解説 「善き人生」を支える資本主義のあり方を考える(諸富徹)