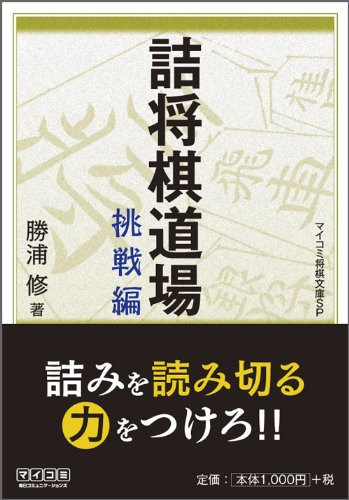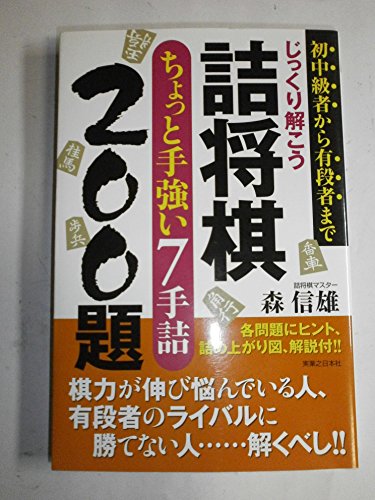【2025年】「詰将棋」のおすすめ 本 149選!人気ランキング
- 1手詰ハンドブック
- 3手詰ハンドブック 新版
- どんどん強くなる こども詰将棋1手詰め
- 改訂版 どんどん強くなる こども詰め将棋 3手詰め
- どんどん強くなる こども詰め将棋 5手詰め
- マンガではじめる! 子ども将棋
- 子ども詰将棋 チャレンジ220問
- 藤井聡太推薦! 将棋が強くなる基本3手詰
- 羽生善治の実戦詰将棋 戦術眼を極める超難問100選 (コツがわかる本!)
- 羽生善治の1手・3手・5手ステップアップ詰め将棋
本書は、詰将棋の問題集で、300題の多様な詰パターンを収録しています。初心者向けに1手詰めから始められるように構成されており、駒の動かし方や反則についての解説も含まれています。著者は将棋のプロであり、多くの賞を受賞しています。
この問題集は、将棋を始めたばかりの子ども向けに作られた詰将棋の問題集です。初心者が楽しみながら棋力を向上できるよう、易しい問題から段階的に難易度が上がっていきます。基本ルールや「詰み」の重要性についての解説も含まれており、安心して取り組めます。内容は、基本の30問と詰め将棋ドリルの2部構成で、段階的に学べるようになっています。著者は中村太地で、実績豊富な将棋のプロです。
この書籍は、3手詰め将棋の基礎力を強化するための解説と問題集です。詰ませる手順をパターン別に解説し、実戦問題に取り組む流れを提供しています。基本問題30問と、レベル別の問題69問を通じて、3手詰めのスキルをマスターできる内容となっています。著者は中村太地で、将棋界での実績が豊富です。
この書籍は、将棋を学ぶための指南書で、トップ棋士たちの上達法を紹介しています。内容は、将棋の基本ルールや駒の特性、攻防の基本、序盤から中盤の攻め方、詰め方、さらにレベルアップのための戦術まで多岐にわたります。著者は羽生善治で、彼の将棋のキャリアや成績も紹介されています。
羽生善治九段が初心者の子どもたちに向けて書いた将棋入門書です。詰将棋を通じて、将棋の基本を学ぶ内容で、漢字にはふりがなが付いているため、幼稚園から小学生中学年の子どもが一人で読めます。1手、3手、5手の詰将棋に挑戦しながら、将棋の楽しさと技術を身につけることができます。
将棋の実力向上を目指すための書籍「将棋が強くなる実戦1手詰」の続編が登場。基本的な詰手筋を3手詰を通じて学ぶ内容で、初めての人向けにステップアップや解法のコツも解説。全200問の詰将棋問題を収録しており、繰り返し解くことで終盤力を高められる。目次には、ステップアップ、解くコツ、パターン別問題、基本問題、卒業問題が含まれている。
本書は、トップ棋士・羽生善治が監修した詰将棋のバイブルで、11~15手詰を中心に、17手詰までの高レベルな問題を収録しています。詰将棋の魅力や妙手を通じて、実戦での勝つための戦術を学ぶことができる内容です。初級から上級までの問題が用意されており、読みの力を養うことで実戦力向上が期待できます。
本書は、将棋を学びたい初心者向けに、勝つための5つのコツを解説した改訂版の入門書です。内容は、駒の特徴や勝利をつかむ方法、詰め将棋の練習法などが含まれています。具体的な対局の手順を示しながら、将棋の基本をわかりやすく説明し、読者が将棋を楽しめるように導いています。著者は羽生善治で、彼の豊富な経験を基にした内容です。
将棋が藤井聡太七段の活躍により注目を浴び、子どもに人気の習い事となっています。本書は「ふみもと子供将棋教室」の文本力雄先生が、初心者から上級者まで強くなるための独自のノウハウを紹介した一冊です。
マンガで楽しく学べて、めきめき上達!詰将棋の神様・神谷広志八段と髙橋香代先生が出題した、初心者のための1手詰将棋、全50問。 マンガとかわいいキャラクターで楽しく学べて、めきめき上達!詰将棋の神様・神谷広志八段と髙橋香代先生が出題した、初心者のための1手詰将棋、全50問。ピタ―っと開いて、使いやすいコデックス装。本文2色、総ルビ付き。 マンガとかわいいキャラクターで楽しく学べて、どんどん解けて、めきめき上達! 詰しょうぎの神様・神谷広志八段と髙橋香代先生が出題した、初心者のための1手詰しょうぎ、全50問 この1冊で、友達に差をつけろ! TBSドラマ『JIN-仁-』の医療指導・監修者で脳神経外科学会専門医、前田病院副院長 医学博士 前田達浩先生が、「しょうぎで伸びる3つの力(集中力、思考力、判断力)」も解説。 ピタ―っと開いて、使いやすいコデックス装。本文2色、総ルビ付き。 【もくじ】 これからしょうぎをはじめるきみたちへ 脳神経外科医が教えるしょうぎで伸びる3つの力 1手詰のもんだいと答えの見方 パート1 盤と駒について 盤 駒 パート2 駒の動かし方をおぼえよう 金将 銀将 桂馬 香車 歩兵 飛車 角行 王将 パート3 詰しょうぎ 基本のきまりごと 詰しょうぎとは? きまりごと① 駒を「成る」 きまりごと② 持ち駒の使い方 きまりごと③ 玉方はむだな合い駒をしません きまりごと④ 禁じ手 パート4 はじめての1手詰 金将 しょうぎ格言・手筋マンガ 銀将 しょうぎ格言・手筋マンガ 桂馬 しょうぎ格言・手筋マンガ 香車 しょうぎ格言・手筋マンガ 歩兵 しょうぎ格言・手筋マンガ 飛車 しょうぎ格言・手筋マンガ 角行 しょうぎ格言・手筋マンガ パート5 神谷八段からのチャレンジ1手詰に挑戦! 解くためのポイント3つ チェレンジ問題15 パート6 おぼえておきたいしょうぎ用語 【もくじ】 これから しょうぎをはじめる きみたちへ 脳神経外科医が教えるしょうぎで伸びる3つの力 1手詰のもんだいと答えの見方 パート1 盤と駒について 盤 駒 パート2 駒の動かし方をおぼえよう 金将 銀将 桂馬 香車 歩兵 飛車 角行 王将 パート3 詰しょうぎ 基本のきまりごと 詰しょうぎとは? きまりごと① 駒を「成る」 きまりごと② 持ち駒の使い方 きまりごと③ 玉方はむだな合い駒をしません きまりごと④ 禁じ手 パート4 はじめての1手詰 金将 しょうぎ格言・手筋マンガ 銀将 しょうぎ格言・手筋マンガ 桂馬 しょうぎ格言・手筋マンガ 香車 しょうぎ格言・手筋マンガ 歩兵 しょうぎ格言・手筋マンガ 飛車 しょうぎ格言・手筋マンガ 角行 しょうぎ格言・手筋マンガ パート5 神谷八段からのチャレンジ1手詰に挑戦! 解くためのポイント3つ チェレンジ問題15 パート6 おぼえておきたいしょうぎ用語
藤井聡太竜王監修の「藤井聡太の将棋入門」が出版され、初刷り限定で藤井竜王の写真付き特製しおりをプレゼントするキャンペーンが実施されています。しおりは全3種類で、ランダムで1枚が付いてきます。本書は将棋の基本から戦略までをやさしく解説し、子どもでも読めるように工夫されています。将棋を始めたい人に最適な内容です。
この書籍は、将棋のルールと戦法を楽しく学べる入門書です。「まんが」「解説」「練習問題」の三つのステップで構成されており、五つのステージをクリアしながら学ぶロールプレイングゲームの形式を採用しています。読者は将棋の基本、手筋、駒の特性、序盤から中盤の攻め方、終盤の戦い方を段階的に習得できます。著者は将棋界の名人である羽生善治をはじめ、さまざまな分野で活躍する作家たちです。
この文章は、詰将棋の基本やルールを解説する書籍の目次と著者情報を紹介しています。序章では詰将棋と本将棋の違いや基本ルールが説明され、続いて1手詰めから5手詰めまでのチャレンジが提案されています。著者は将棋界の著名な棋士である羽生善治と、将棋専門紙の記者である上地隆蔵です。羽生は多くのタイトルを獲得し、将棋界での地位を確立しています。
この文章は、将棋に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、将棋の戦術や技術に関する12の章が列挙されており、著者の金子タカシは東京都出身の将棋アマチュア界での実績を持ち、理数系の研究者としての整理能力が評価されています。彼の処女作『寄せの手筋168』は将棋ファンにとって必読の書とされています。
本書は、日本将棋連盟が発行した将棋入門書で、将棋の基本を学ぶための決定版です。著者は将棋界の第一人者、羽生善治プロで、写真や図を多く用いて分かりやすく解説しています。内容は、駒遊びから始まり、将棋の指し方や対局の進行、反則についても触れています。巻末にはおさらい問題が30問収録されており、学んだ内容を確認できます。この本を通じて、家族や友人と将棋を楽しむことができるようになります。
この書籍は、将棋の楽しさを詰め将棋を通じて学ぶことを目的としたもので、加藤一二三が著者です。内容は、詰め将棋の基本を解説する第1章、1手詰めに挑戦する第2章、3手詰めに挑戦する第3章から構成されています。合計80問の詰め将棋を通じて、誰でも将棋のスキルを向上させることができる内容です。著者は長年プロ棋士として活躍し、多くのタイトルを獲得した実績があります。
本書は、現役高校生棋士の藤井聡太七段を含む棋士たちの活躍を背景に、詰将棋の基本を子ども向けに学べる内容です。オールカラーのイラストとマンガを用いて、詰将棋の魅力やルール、基本形、さまざまな問題を解く練習を通じて、実戦で役立つ形を学ぶことができます。著者はオールラウンドプレイヤーの及川拓馬です。
「ふみもと子供将棋教室」が監修した詰将棋の続編で、初級から上級までの240問を収録しています。特に「目隠し詰め将棋」ができるのは本書のみで、ふりがな付きの解説や明確なトレーニング目標があり、子どもたちが将棋を楽しみながら強くなれる内容です。著者は将棋指導に長年携わる専門家たちです。
本書は、2012年に放送された『NHK将棋フォーカス』の「藤井猛の“初出し”攻め方フォーラム」を基にしたもので、将棋の攻め方を初心者向けに解説しています。内容は、持ち駒を増やす方法、敵陣の突破、動けない駒を攻めるテクニックなどに分かれており、実践的な攻めの形を自然に作るためのテクニックが紹介されています。著者は藤井猛で、将棋界での経歴も記載されています。
本書は、将棋の戦法における駒組み手順を「次の一手」形式で解説しており、矢倉や角換わりなど全9種類の戦法を網羅しています。将棋のルールを学んだ後に次のステップに進みたい人に最適で、実戦を通じて自分に合った戦法を見つけることができる一冊です。著者は長岡裕也です。
本書は、将棋の強化に役立つ詰将棋の解説書で、藤井聡太四段が推薦しています。将棋の基本ルールから始まり、王手や詰みの概念を詳しく説明。1手詰問題を200題収録し、基本例題50問、実戦形式の140問、難問10問を含んでいます。詰将棋の楽しさを体験しながら棋力向上を目指す内容です。
この文章は、羽生善治による将棋の戦法に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、居飛車と振り飛車の各戦法の特徴や定跡が章ごとに分類されています。著者の羽生善治は、埼玉県出身の著名な棋士であり、数々のタイトルを保持し、将棋界での多くの業績を持っています。
著者初の3手詰め問題集で、A級在籍36期の大棋士・加藤一二三による202題の詰将棋を収録。玉の位置を右側と左側に分けて出題し、居飛車と振り飛車のトレーニングが可能。初級者が読みの基本を身につけるのに最適な内容。
将棋ファン待望のDVD付き戦法書が登場。 戸辺誠七段が映像と次の1手問題集で中飛車の指し方を解説。 動画で予習してから本の問題を解くので、 初級者、級位者、観る将の方にも分… 将棋ファン待望のDVD付き戦法書が遂に登場。 攻めの棋風と明快な解説で人気の戸辺誠七段が DVD映像と次の1手形式の問題集で中飛車の指し方を徹底解説。 動画で予習してから本の問題を解くので、 初級者、級位者、観る将の方にも分かりやすく、 楽しんで強くなることができます。 【DVDコンテンツ】 1章 先手中飛車 5筋位取り(約49分) ・対棒銀 ・対△7三銀型 ・対△6三銀型 2章 先手中飛車 角交換型(約24分) ・駒組み編 ・仕掛け編 3章 後手ゴキゲン中飛車(約60分) ・対△8六歩急戦 ・対超速▲3七銀 ・対丸山ワクチン 4章 相振り飛車(約53分) ・対四間飛車 ・対三間飛車 ・相中飛車(1) ・相中飛車(2) トークコーナー、その他特典映像(約23分) DVD聞き手/藤田綾 女流二段 優しい語り口が人気の女流棋士で、将棋番組の出演多数。 2016年よりテレビ棋戦の司会を務める。 【書籍 次の1手形式問題】※3手進める問題もあります 1章 先手中飛車 5筋位取り…49問 2章 先手中飛車 角交換型…31問 3章 後手ゴキゲン中飛車…77問 4章 相振り飛車…73問 書籍は問題を解きながら読み進める形式です。 図面から次の図面へと移る際も 一度に手数が進みすぎないようにしてあるので、 はじめて戦法書を読む方でも無理なく読める作りになっています。 また、タイトルにもあるように“攻める手”を多く扱っているため、 気持ちよく問題を解いていくことができます。 DVDで学んだことを本の問題を解くことで定着させ、 分からないところはDVDでまた復習。 繰り返し観て、解くことでしっかりと戸辺攻めをマスターし、 パンチ力十分の中飛車を身につけよう! 【この本とDVDが向いている方】 ・級位者〜二段くらい ・初級者 ・観る将の方 ・初めての戦法書 ・振り飛車党 ・初めての振り飛車 第1章 先手中飛車 5筋位取り 第2章 先手中飛車 角交換型 第3章 後手ゴキゲン中飛車 第4章 相振り飛車 ※付属DVDも上記4章構成 (DVDは戸辺誠七段と藤田綾女流二段による解説動画で、収録時間は210分以上)
本書は、井上慶太九段による棒銀戦法の解説書で、初心者にも分かりやすく、敵陣を打破する方法や反撃への対処法を丁寧に紹介しています。目次には、相掛かり棒銀、矢倉棒銀、角換わり棒銀、そして四間飛車に対する棒銀の戦い方が含まれており、実践的な攻め方を学べる内容です。著者は将棋界での指導力も高く、新鋭棋士の育成にも力を注いでいます。
将棋ブームの中、新たなファン層を意識した親切な内容の新刊が登場。前作の成功を受け、級位者から有段者まで幅広く学べる四間飛車の講義を提供。著者は藤井猛で、彼の理論を基にした実践的な内容が特徴。目次には駒組みの基本から攻め方、持久戦まで多岐にわたるテーマが含まれている。
本書は将棋初心者や初級者向けに、実戦でよく使われる手筋を部分図と次の一手形式で解説しています。内容は駒別の手筋、囲い崩し、端攻め、受けの手筋、必死の形など多岐にわたり、勝ち方を学ぶのに役立つ一冊です。著者は将棋界のトッププレイヤー、渡辺明です。
本書「駒別手筋事典」は、将棋の8種類の駒の特性を生かした多彩な手筋を紹介するガイドです。各駒の動きや技を学ぶことで、対局での戦略を向上させることができます。内容は、歩、香車、桂馬、銀、金、角、飛車、玉それぞれの手筋に分かれており、問題を通じて手筋を習得することができます。著者は大平武洋で、将棋界でのキャリアを持つ実力者です。
この文章は、将棋の手詰問題に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には1手詰、3手詰、5手詰の問題が含まれており、著者の飯野健二は東京都葛飾区出身で、昭和50年に四段、平成10年に七段に昇段したプロ棋士です。
本書は、将棋の基礎を子ども向けにわかりやすく解説した改訂版で、累計50万部を超える人気シリーズの一つです。将棋の魅力を伝えるために、駒の使い方や強くなるための5つのコツ(進む、取る、成る、詰める、守る)を紹介しています。トレーニング問題も収録されており、将棋を楽しみながら学ぶことができます。著者は将棋界の名人、羽生善治と指導棋士の小田切秀人です。
この将棋マスターブックは、将棋に興味を持つ子供向けに、楽しくルールを学べる内容になっています。ページをめくりながら自然に理解できるよう工夫されており、保護者向けのサポートも充実しています。レッスンでは基本的な駒の動かし方や対局方法が紹介され、コラムでは将棋の用語やプロ棋士についても学べます。著者は女流棋士の北尾まどかで、教育活動にも力を入れています。
将棋界では新たな戦法や囲いが生まれることが珍しく、最近「エルモ囲い」が注目されています。これはコンピュータ将棋ソフト「elmo」に由来し、対振り飛車において急戦を可能にする新しい囲いです。著者の村田顕弘六段は、この新戦法の詳細や実戦での活用法を解説した本を執筆しました。エルモ囲いは持久戦には不向きですが、攻撃的な戦略を提供し、居飛車党に新たな勝利の可能性を示します。
棋士、女流棋士75名が詰将棋で競演! 日本将棋連盟ホームページの人気コーナー書籍化!日々更新されている「まいにち詰将棋」は、取り組みやすく実力向上につながる問題の宝庫です。本書では、その中からすぐれたもの200題を厳選しました。作者はすべて棋士、女流棋士。75人が登場する豪華な顔ぶれです。あなたの推し棋士を探してみませんか?監修は「1手詰ハンドブック」などのシリーズでもおなじみの浦野真彦八段にお願いしました。
本書はアマチュア将棋プレイヤー向けに、中飛車戦法を実戦で使えるように解説した指南書です。著者の石川泰は、アマチュアに人気のある中飛車の戦法を、具体的な形や対策を通じて学べるように構成しています。菅井竜也八段も推薦しており、実践的な内容が詰まっています。目次には、後手の形や対策が含まれています。
著者羽生善治が、勝負における集中力と決断力の重要性を解説し、直感力の磨き方や勝負の極意を初めて公開します。彼は、精神力が勝敗を分ける瞬間や、深い集中力の獲得方法、情報の選択と捨て方、そして才能とは持続的な情熱であることを強調しています。羽生は将棋界で数々のタイトルを獲得した天才棋士として知られています。
主人公のススムは、将棋教室のリュウイチに勝つため、将棋の精霊チャトラに教わることに。チャトラの世界では将棋の駒が動物に変身し、ダイナミックな戦いが展開される。中村太地先生が登場し、ススムとリュウイチの対決がこども将棋トーナメント決勝で繰り広げられる。書籍は将棋の基本や戦法、テクニックを楽しく学べる内容で、特に「棒銀戦法」や「四間飛車戦法」などの指し筋や格言も紹介されている。将棋の楽しさを伝える入門書。
藤井聡太棋士が通った「ふみもと子供将棋教室」が監修した将棋の指南書です。マンガとイラストを用いて、駒の動かし方や戦法、上達のポイントを楽しく学べる内容になっています。目次には将棋の基本、駒の特性、基本戦術、強くなるための方法が含まれています。著者は日本将棋連盟の支部長で、子どもたちに合わせた指導を行っています。
この書籍は、将棋の基本や駒の動かし方、駒取りの技術を初心者向けに解説しています。目次には、将棋の基本、駒の点数、各局面の考え方、指し直しのルールなどが含まれています。著者はプロ棋士の木村一基で、彼の経歴や棋風も紹介されています。
著者の得意な1手3手の詰将棋を368問収録したハンディ版の本。直感を試す1手150問と、読みを鍛える3手218問が含まれており、解くことで将棋の実力向上が期待できる。著者は森信雄氏で、詰将棋の創作に定評がある。
将棋の人気が高まる中、特に子どもや親に向けて、シナモロールを主人公にしたマンガとイラストで将棋のルールをわかりやすく解説した本が紹介されています。入門者でも簡単に理解できる内容で、勝つためのコツや練習問題も含まれています。さらに、遊べる厚紙の将棋盤と駒も付属しており、将棋の世界への第一歩を踏み出す手助けをします。
この本は、子ども向けに将棋の「手筋」を解説した入門書です。将棋のルールを理解した後に、局面ごとの巧妙な手を学ぶことで、強くなり、楽しさが増します。具体的には序盤・中盤・終盤の手筋を紹介し、実際の局面での応用を通じて、勝利に近づく方法を学びます。著者はプロ棋士の中村太地で、手筋を覚えることで駒の使い方や守りが上達することが強調されています。
詰みに役立つ「詰手筋(つめてすじ)」を徹底的に解説した1冊が登場! 詰将棋の人気シリーズ「ハンドブック」の著者である浦野真彦八段が、 1手詰、3手詰、5手詰を題材に詰みのコツを伝授。 まず1章では、1手詰を使ってそれぞれの駒を使った 詰み形(つみがたち)や、基本となる詰みのパターンを紹介。 続く2章と3章では、3手詰と5手詰を使って 「危険地帯に誘え」「逃げ道に捨てよ」といった詰手筋を詳しく解説。 さらに4章では応用編として、覚えた詰手筋を さまざまな場面で役立てる方法についても紹介しています。 また、本書はDVDによる動画解説もあるので 幅広い棋力の方にわかりやすく、役立つ内容となっています。 動画を観る、解説を読む、問題を解く。 3つの方法で詰手筋を自分のものにし、 実戦で玉をつかまえたり、詰将棋を解く楽しさを実感してください。 【書籍の内容/計248ページ、問題総数193問】 第1章 1手詰で覚える詰み形 解説つきの例題…36問 練習問題…48問 第2章 3手詰で覚える詰手筋 解説つきの例題…14問 練習問題、復習問題…計60問 第3章 5手詰で覚える詰手筋 解説つきの例題…10問 練習問題…20問 第4章 詰手筋はさまざまな場所で役立つ 解説つきの例題…5問 計193問の問題のうち、65問は 図面を多めに使って詰み形や詰手筋を詳しく解説。 残りの128問は練習問題で、ハンドブックシリーズのように 2ページに4問ずつ問題と解答が続く構成となっています。 【DVDの内容/計190分以上】 第1章 1手詰で覚える詰み形(約72分) 第2章 3手詰で覚える詰手筋(約50分) 第3章 5手詰で覚える詰手筋(約36分) 第4章 詰手筋はさまざまな場所で役立つ(約18分) トークコーナー(約15分) DVDは浦野真彦八段と山口恵梨子女流二段による 詰み形、詰手筋の講座がメイン。 大盤を使い、書籍で例題として扱った65問を さらにかみくだいて解説します。 3手詰と5手詰については、解説前に問題にチャレンジする 「シンキングタイム」も設けてあります。 DVD聞き手/山口恵梨子 女流二段 将棋番組だけでなく、バラエティ番組や情報番組への出演も多数。 わかりやすい解説を引き出してくれる聞き手として人気の女流棋士。 【この本とDVDが向いている方】 ・初心者〜初段くらいの方 ・詰みのコツが知りたい方 ・終盤力をアップさせたい方 ・詰将棋を解きたい方 ・逆転勝ちしたい方 ・将棋の動画が好きな方 第1章 1手詰で覚える詰み形 第2章 3手詰で覚える詰手筋 第3章 5手詰で覚える詰手筋 第4章 詰手筋はさまざまな場所で役立つ ※付属DVDも上記4章構成 (DVDは浦野真彦八段と山口恵梨子女流二段による解説動画で、収録時間は190分以上。書籍で扱う193問のうち、約3分の1の問題を解説)
本書は、振り飛車の「さばき」をテーマに、藤倉五段がその重要性や具体的な手筋を解説しています。美濃囲いを活かし、居飛車の攻撃を受け流す技術を学ぶことで、実戦での勝利に繋げることを目指します。各章では四間飛車から向かい飛車までのさばきの手法を紹介し、初心者にも理解しやすく構成されています。
本書は、将棋初心者向けの改訂版で、駒の動かし方やルールを学んだ後、序盤での攻めと守りの形を作ることに焦点を当てています。多様な戦法を紹介し、実践を通じて理解を深め、自分の得意な戦法を見つける楽しさを伝えています。内容は、戦法の基本や具体的な戦法、囲いの作り方などを含み、将棋の楽しさを広げるための情報が満載です。著者は羽生善治と小田切秀人で、将棋界の著名な存在です。
将棋を知らない子ども向けのマンガ版入門書で、主人公の小学生5人組が将棋の基本ルールや駒の動かし方を楽しく教える。内容は「王手」「詰み」「必至」といった基本用語、駒の効率的な動かし方、合駒や両取りのテクニック、囲いの種類などを含む。詰め将棋のクイズもあり、バラエティ豊かな内容となっている。
ひと目の定跡がバージョンアップ! 「序盤でいつも困る」、「定跡は長くて覚えにくい」戦法の勉強を始めたときに、誰しも同様につまずいたことがあるのではないでしょうか。無理なく定跡を覚えたいですよね。本書は、定跡次の一手問題集です。多くの方にご好評いただいた『将棋・ひと目の定跡』の内容を刷新し、バージョンアップしまいた。現代将棋の中から特に重要な手を厳選し、出題しています。居飛車、振り飛車、相振り飛車の基本を総まとめ!問題を楽しく解いて、序盤のニガテを克服しましょう! 第1章 相掛かり 第2章 角換わり 第3章 矢倉 第4章 雁木 第5章 横歩取り 第6章 居飛車力戦 第7章 四間飛車対急戦 第8章 四間飛車対持久戦 第9章 三間飛車 第10章 石田流 第11章 ゴキゲン中飛車 第12章 角交換振り飛車 第13章 対右四間飛車 第14章 振り飛車力戦 第15章 相振り飛車
この書籍は、「端棒銀」と呼ばれる奇襲戦法を中心に、序盤から積極的に攻める将棋の戦法を紹介しています。目次には、単純棒銀や筋違い角棒銀、振り飛車穴熊への端棒銀などが含まれています。著者は森下卓で、彼は多くの将棋大会での優勝経験がある実力派棋士です。
この書籍は将棋の戦術を3つの章に分けて解説しています。第1章では終盤の戦い方、第2章では中盤の競り合いの戦略、第3章では序盤の駒組みの技術を中心に、考え方や具体的なテクニックを紹介しています。著者は木村一基で、将棋界での実績を持つプロ棋士です。
この書籍は、居飛車を指す際に知っておくべき要点をまとめたガイドブックであり、相掛かり、横歩取り、角換わり、矢倉などの戦型について解説しています。著者は佐藤慎一氏で、将棋の指導者としても活動しています。
「詰将棋」に関するよくある質問
Q. 「詰将棋」の本を選ぶポイントは?
A. 「詰将棋」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「詰将棋」本は?
A. 当サイトのランキングでは『1手詰ハンドブック』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで149冊の中から厳選しています。
Q. 「詰将棋」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「詰将棋」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。