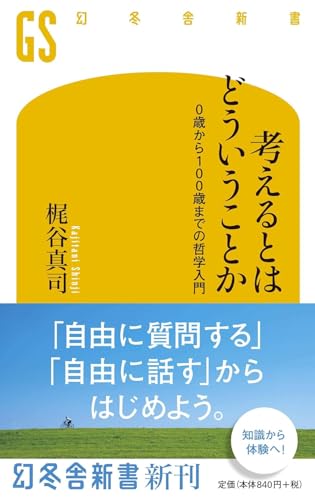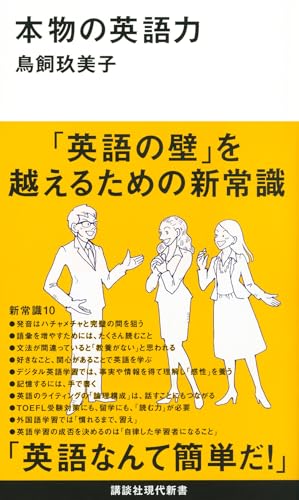【2025年】「教育格差」のおすすめ 本 46選!人気ランキング
- 教育格差 (ちくま新書)
- 生まれが9割の世界をどう生きるか 遺伝と環境による不平等な現実を生き抜く処方箋 (SB新書)
- 教育格差の経済学: 何が子どもの将来を決めるのか (NHK出版新書)
- 社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
- 教育 目標4 (SDGsのきほん未来のための17の目標 5)
- 教育投資の経済学 (日経文庫)
- 地球村の子どもたち 途上国から見たSDGs 1格差
- 小論文 書き方と考え方 (講談社選書メチエ 676)
- 「学力」の経済学 (ディスカヴァー携書)
- 3000万語の格差――赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ
親の学歴や居住地域など「生まれ」によって、子どもの学歴は大きく変わる。就学前から高校まで教育格差を検証し、対策を提案する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本の教育の実態を俯瞰的に捉え直した数少ない正攻法の力作である。 読後感は重いが説得力は半端ではない。 教育に興味のある人にぜひとも一読してもらいたい一冊だ。 ――出口治明さん (立命館アジア太平洋大学(APU)学長) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 就学前、小学校、中学校、高校、国際比較… データで「緩やかな身分社会・日本」の実態を克明に描き出す! ◆小学校入学時にすでに学力格差が存在! ◆公立の中学校同士でも大きな「環境」格差がある!? ◆親が大卒/非大卒で、就学前~高校まで格差が存在。 出身家庭と地域という本人にはどうしようもない初期条件によって子供の最終学歴は異なり、 それは収入・職業・健康など様々な格差の基盤となる。 つまり日本は、「生まれ」で人生の選択肢・可能性が大きく制限される「緩やかな身分社会」なのだ。 本書は、戦後から現在までの動向、就学前~高校までの各教育段階、国際比較と、 教育格差の実態を圧倒的なデータ量で検証。 その上で、すべての人が自分の可能性を活かせる社会をつくるために、採るべき現実的な対策を提案する。 朝日新聞:出口治明さん評 (2019.9.7) 日経新聞:小塩隆士さん評 (2019.9.14) 毎日新聞:大竹文雄さん評(2019.12.8「2019年この3冊」)で大絶賛!! ほか、『週刊東洋経済』2019年11月16日号、『文學界』2019年1月号、『サイゾー』2020年1月号 『都市問題』2019年12月号、『内外教育』2019年11月15日合併号、『週刊教育資料』1546号などで紹介! 第1章 終わらない教育格差 第2章 幼児教育――目に見えにくい格差のはじまり 第3章 小学校――不十分な格差縮小機能 第4章 中学校――「選抜」前夜の教育格差 第5章 高校――間接的に「生まれ」で選別する制度 第6章 凡庸な教育格差社会――国際比較で浮かび上がる日本の特徴 第7章 わたしたちはどのような社会を生きたいのか
所得の影響、保育園と幼稚園の差、遺伝と環境の関係、塾の効果などを格差研究の第一人者がコストとリターンの観点から徹底分析する! いったい何が教育格差を生み出しているのか。親の所得の影響、保育園と幼稚園の差、遺伝と環境の関係、塾や習い事の効果などを、格差研究の第一人者がコストとリターンの観点から徹底分析。特に0歳から小・中学校期を中心に、子どもの将来を決める決定的要素を、豊富なデータとともに読み解く。公教育で格差を乗り越える方法や、格差社会・学歴社会の未来についても考察した決定版!
本書は、教育におけるデータ分析と経済学の視点を用いて、教育投資や政策の効果を論理的に解説しています。著者は、教育の効果を高めるための家庭や学校の役割、教育制度の設計について分析し、特にコロナ禍の影響や日本の事例を取り上げています。幅広い読者層を対象に、教育の最適化に向けた具体的な施策を提案しています。
この書籍は、相手に伝わる文章を書くための方法と「文章を書く」ことの意義について解説しています。著者は、論理的ライティングは「異和感」から始まるとし、教育現場での経験を基に、思考と文章の相関関係を鍛える方法を提供。小論文執筆法を通じて「自分の言葉を持ってリアルに生きる」ための基本的な教養を伝授する内容です。目次では、論理的思考の始まりや社会問題への向き合い方、社会通念への懐疑、日常の中の論理について触れています。著者は大堀精一で、高校生向けの教育に長年従事しています。
算数や国語の学力、粘り強さ、自己制御力、思いやり……、生まれた瞬間から最初の数年間に、親や保育者が子どもとどれだけ「話したか」ですべてが決まる。日本の子育て、保育が抱える課題とその解決策を、科学的な裏づけと著者自身の具体的な実践から示した書。 第1章 つながり:小児人工内耳外科医が社会科学者になったわけ 第2章 ハートとリズリー:保護者の話し言葉をめぐる先駆者 第3章 脳の可塑性:脳科学革命の波に乗る 第4章 保護者が話す言葉、そのパワー:言葉から始めて、人生全体の見通しへ 第5章 3つのT:脳が十分に発達するための基礎を用意する パート1:科学から実践へ パート2:「3つのT」の実際 第6章 社会に及ぼす影響:脳の可塑性の科学は私たちをどこへ導くのか 第7章 「3000万語」を伝え、広げていく:次のステップ エピローグ 岸に立つ傍観者であることをやめる 解説 子どもの言葉を育む環境づくり(高山静子) 訳者あとがき(掛札逸美)
この書籍は、明治以降の日本が経験した四つの対外戦争を通じて、指導者や一般市民がどのように国家の未来を考え、参戦を決断したのかを探る内容です。中高生向けの5日間の集中講義を通じて、戦争の背後にある論理や歴史的事実を考察します。著者は加藤陽子で、作品は小林秀雄賞を受賞しています。目次には日清戦争から太平洋戦争までの各章が含まれています。
少人数学級制度は、子どもや教員にどんな影響をもたらすのか。小学校での35人学級の教育的・経済的効果を実証的に分析する。 少人数学級制度は、子どもや教員にどんな影響をもたらすのか。現在導入が始まっている小学校での35人学級の教育的・経済的効果を実証的に分析。教育経済学の新地平を切り開く。 因果推論に基づいた現代的分析 未来を担う子どもたちを育む学校教育。本書は経済学をベースに社会学・心理学・認知科学等からの知見を取り入れ、少人数学級がもたらす学力・非認知能力の向上、学校教員の過重労働の軽減、教員不足解消への採用方策、教員のウェルビーイング、政策のコスト・パフォーマンス分析などの論点を、エビデンスを重視して検証する。教育経済学の新地平。 少人数学級制度は、子どもや教員にどんな影響をもたらすのか。 現在導入が始まっている小学校での35人学級の教育的・経済的効果を実証的に分析。生徒レベルの詳細なデータを用い、因果推論の手法を活用して、35人学級に代表される少人数学級教育は子どもの学力を向上させるのか、そして近年その重要性が認識されている子どもの「非認知能力」を伸ばす効果はあるのかを解き明かすとともに、少人数学級はいじめや格差を縮小・是正するか、といった「効果の異質性」についても言及する。 また、少人数学級の導入がもたらす教員配置数の増加によって教師の就業環境が改善し、労働時間の減少やストレスの低減をもたらすことを、著者自身の研究成果に基づいて明らかにする。さらに、少人数学級政策の導入には、教員の増大に伴う巨額の費用が発生する。第5章ではやや視点をマクロの財政面に置き、少人数学級は巨額の費用負担に見合うほどの効果を持つのかについて、費用対効果の視点から国内外の研究成果をもとに試算する。 EBPM(科学的根拠に基づく政策形成)の波は教育行政にも押し寄せている。教育領域におけるEBPMは、他領域におけるそれと同様に考えてよいのか、それとも教育領域に独自の性質があるのか。これまでの研究に基づきながら、EBPMを教育分野に適用することの必要性を論じる。 2021年のノーベル経済学賞は、実験が難しい経済学において、自然実験などを活用した因果推論の手法を確立・発展させた研究者に贈られた。中でも、受賞者の一人であるアングリスト教授は,1999年に少人数学級の効果を検証した論文を発表し、その後の研究を切り開いたことが評価された。本書はアングリスト教授の分析手法を応用して日本の実情に適用した分析結果を提示するなど、現代的な因果推論に基づく実証分析の結果を提示するという点で学術的な貢献を持つ。 序章 日本の学校教育の現状と少人数学級――教育経済学の視点 教育経済学の視点:日本の児童・生徒の学力と学校環境/教育格差の視点:家庭環境の影響/学級規模と少人数学級政策 第1章 少人数学級は学力を向上させるのか 「すし詰め」解消への道程――戦後日本が歩んだ学級編制の推移/学級規模研究の歴史/少人数学級の学力向上効果――近年の研究成果/効果の異質性:少人数学級は教育格差を縮小するか/少人数学級の学力向上効果 第2章 少人数学級と非認知能力 高まる非認知能力への注目/非認知能力とは何か/少人数学級は非認知能力を伸ばせるのか/筆者自身による分析結果/非認知能力研究の重要性 第3章 少人数学級はいじめの低減につながるか 学校生活面への視点/これまでの研究例/筆者による分析結果/少人数学級は万能ではない 第4章 少人数学級と教員の就業環境 厳しい学校教員の就業環境/学校教員の勤務の実態/少人数学級は教員の勤務実態の改善につながるか/筆者による研究結果――生徒・教師比率と労働時間・ストレスの関係/学級規模の縮小が教員にもたらす効果 第5章 少人数学級政策のコスト・パフォーマンス 少人数学級政策の「コスパ」/少人数学級政策のコスト/少人数学級政策のパフォーマンス/少人数学級政策のコスト・パフォーマンス/少人数学級政策のコスパは決して悪くはない 第6章 教員を確保できるか――教員採用の経済学 少人数学級政策に不可欠な教員採用/教員採用および教員不足の現状/教員採用の経済学/教員は幸せか――ウェルビーイングの観点からの検証/教員志願者確保に向けた方策の検討 終章 少人数学級政策のあり方とEBPM EBPMの考え方/少人数学級政策におけるEBPM/教員確保の議論を/教育分野におけるEBPMの先頭として
本書は、教育に関する一般的な思い込みに科学的根拠を持って反論し、教育経済学の視点から「成功する教育・子育て」についての知見を提供します。内容は、ゲームの影響やご褒美の効果、非認知能力の重要性、少人数学級の効果、良い教師の条件など多岐にわたります。著者は、個人の経験よりもデータに基づく教育の重要性を強調し、教育関係者や親にとって必読の一冊とされています。
調査で聞いて、分析で考えて、理論で表現する。この社会のことをみんなで考えてなんとかしたい人のための、基礎が身につく入門書。 調査は聞くこと、分析は考えること、理論は表現すること。この社会のことをみんなで考えてなんとかしたい人のための、三つの基礎が身につく入門書。 調査は聞くこと、分析は考えること、理論は表現すること 社会学をはじめるための、3つの基礎を身につける 社会学は、みんなにとって大事なことについて、しっかりしたデータにもとづいて考え、それを表現する営みです。 ・自殺を少なくするにはどうすればいいだろうか? ・どうしたら、みんなにとって居心地のよい職場ができるだろうか? ・災害からの復興って、何がゴールなのだろうか? 社会学は、たとえばこんな問題に取り組んできました。 さあ、次はあなたの番です。この社会の複雑な問題をなんとかしたいと思ったら、社会学があなたの力になります。 第1章 世界は意味に満ちあふれている――やっかいな問題としての社会 社会は二重に複雑/社会は意味から成り立っている/意味は言葉で成り立っている/やっかいな問題/社会問題に解決はない/社会は存在するの?/デュルケムの「社会的事実」/社会と社会学の共進化/社会学は社会主義/社会学は社会の解決力を擁護する/社会をプロセスとして考える/固定的な見方を解きほぐす 第2章 社会学って何だ?――みんなで規範の物語を作るいとなみ 飯島伸子の「被害構造論」/社会学は対話から成り立っている/社会学は社会の外に出られない/社会学は規範的な学問/規範を前面に出した「サードブレイス」論/意味は身体的な行為の中から生まれる/共同の規範をつくるいとなみとしての社会学/環境問題はどう解決できるかという問い/ヒントとしての順応的管理/順応的なプロセスとしての社会学 第3章 聞くことこそが社会学さ――対話的な社会認識としての調査 意味を集める/ソロモン諸島の経験から/対話的に社会認識が進む/対話の試行錯誤/社会学は全体性を手放さない/インタビューは認識を更新するプロセス/ライフストーリーを聞く/個人の中の複雑な社会を聞く/観察という「聞く」/文献・資料調査という「聞く」/統計調査という「聞く」/アンケート調査という「聞く」/アンケート調査にも対話プロセスが必要/社会学は「聞く」の組み合わせ 第4章 社会学は泥臭い分析技法を手放さない――圧縮して考える データ集めと分析は同時並行/分析の基本は「圧縮」/数値化という圧縮/コード化という圧縮/図表化という圧縮/図表化することで気づく/見通しをよくして考える/四つの分析パターン/被災住民調査から/分類・傾向・比較・関係/広義の比較に意味がある/演繹と帰納/アブダクションという推論方法/いいアブダクションのためにはいい圧縮を 第5章 理論って何だ?――表現の技法としての理論と物語 言葉で表現するということ/「感情労働」論のインパクト/ソロモン諸島研究の理論化/いろいろな水準の理論がある/グランド・セオリーより中範囲の理論/理論とは共同で考えるためのフレームワーク/欠如モデルに陥らないために/冗長性をもった理論と物語/理論・物語としての記述/関係性まで描き出す厚い記述/理論を利用する 第6章 みんなソシオロジストになればいいのに――人びとの共同のいとなみとしての社会学 「協議会」の失敗/合意形成の困難/社会学実践をしよう/聞くことが基本的な姿勢/対話を継続し蓄積する/共同で分析し提言する/社会学することの喜び
自分と世界の見え方が変わる! 社会の影響を受けて複雑にかたちづくられる「私」の成り立ちを、社会学のさまざまな観点から考える。 なぜ「私」は今のような「私」であるのだろうか。社会学のさまざまな観点からその成り立ちについて考え、「私」と社会をめぐる風通しをよくする手がかりを示す。 社会学の奥深さがわかる 「私」はもっと他でもありえるのかもしれない。 「私」はこんなにも社会とつながっているのか―― 自分と世界の見え方が変わる! なぜ「私」は、今のような「私」であるのだろうか? 他者との関係性からより広い社会的状況までに影響を受け、「私」という存在は複雑にかたちづくられている。 社会学のさまざまな観点からその成り立ちについて考え、「私」と社会をめぐる風通しをよくする手がかりを示す。 第1章 数字でみる「私」 1 時代のなかの「私」 2 社会的状況による「私」の違い 3 「私」のあり方と「社会」への向き合い方の関係 第2章 他者と「私」 1 「役割」と自己――ジョージ・ハーバート・ミード 2 「相互行為」と自己――アーヴィング・ゴフマン 3 発達課題としての「アイデンティティ」――エリク・H・エリクソン 第3章 現代社会における「私」 1 「心」への傾斜 2 自己の多元化 3 後期近代と自己の再帰性 第4章 つくられる「私」 1 「自己」を歴史的に捉える 2 ミシェル・フーコー――言説・テクノロジー・主体化 3 現代における主体化のテクノロジー 第5章 語られる「私」 1 「物語」としての自己 2 自己はどこでどう語られるのか――制度とアイデンティティ・ワーク 3 自己と社会をめぐる循環へ
本書は、イギリスの格差研究の第一人者によるレポートで、格差が私たちの心や社会に与える影響を探求しています。主な主張として、格差が人々の不安やうつ病を引き起こし、社会全体の学力を低下させることが挙げられています。また、社会階級に関する誤解を解消し、平等な社会の重要性を説いています。著者は、格差と環境問題の解決を同時に考える必要性を強調し、持続可能な社会の創出を目指しています。
この書籍は、個性を大切にしながらも、集団の中での他人の視線や先輩への従属に悩む人々に向けたアドバイスを提供しています。著者は「世間」のルールや同調圧力について考察し、自己を大切にしつつ生きる方法を探ります。特に、他人の頼みを断ることや、仲間外れを恐れないことの重要性を強調しています。最終的に、より自分らしく生きるためのヒントを提示しています。
この書籍は、大学入試や社会人の学び直しに役立つ社会学の入門書であり、高校で学んだ内容を復習しながら理解を深めることを目的としています。著者は、社会学が歴史や政治だけでなく、さまざまな社会問題を考える学問であることを伝えています。各章では、スポーツ、人種、ツーリズム、文化、ジェンダー、恋愛、家族、食、障がい、コミュニケーション、環境、ボランティア、自己とアイデンティティ、資本主義、グローバル化など、多様なテーマが扱われています。
現代社会の様々なトピックが,社会学の理論や概念とどのように関係しているのかを楽しく学べるよう工夫した,充実の社会学入門。 現代社会の様々なトピックが,社会学の理論や概念とどのように関係しているのかを,楽しく読み進めながら学べるよう工夫しました。付録でレジュメ・レポート・卒論の書き方や質的調査・量的調査の基礎知識も解説。今までありそうでなかった充実の社会学入門。 第1章 アイデンティティのよりどころ──個人化する社会のゆくえ(山田真茂留) 第2章 日本社会の就職の仕組み──働く力をどう養い,評価するか(有田伸) 第3章 メディアでスポーツを見ること──女子サッカーにおける「ゲームの楽しみ」に向けて(是永論) 第4章 社会の中の宗教──宗教のトリセツ(永井美紀子) 第5章 〈移民〉とは誰なのか──社会学の視点で考える(森千香子) 第6章 共在と身体の両義性──他者とともにいるとき/ところ(草柳千早) 第7章 資本主義社会を理解する──自分の「社会的位置」を知る(中村英代) 付録1 レジュメ・レポート・卒論の書き方 付録2 質的調査とは何か 付録3 社会調査データの計量分析
初めて社会学を学ぶ大学生や,教養として社会学を学びたい人に,厳選したベーシックな知識を提供する入門テキスト。 初めて社会学を学ぶ大学生や,教養として社会学を学びたい人に,厳選した基礎知識を提供する入門テキスト。社会学のベーシックなテーマと考え方を学ぶことで,「個人的なこと」と「社会的なこと」のつながりを理解する「社会学的想像力」を養える1冊。 序 章 社会学の誕生と展開 第1章 個人と社会 第2章 自己と他者 第3章 家族と親密圏 第4章 仕事と産業 第5章 病と医療 第6章 福祉と貧困 第7章 犯罪と逸脱 第8章 グローバル化と開発 第9章 メディアと文化 第10章 社会階層と不平等 第11章 ジェンダー 第12章 都市・地域 第13章 権力と自由 終 章 方法としての社会学
近代社会における恋愛の社会的機能 日本の家族社会学はいかに「出会いと結婚」を扱ってきたか 恋愛・結婚における親の影響 1980年代の「恋愛至上主義」 若者の恋愛の優先順位 リスク社会における恋愛と結婚 恋愛は結婚において「必要」か、「オプション」か 「異同探し」の誘惑を飼い慣らす 片思いと加害の境界を探る アイドルに対する恋愛感情を断罪するのは誰か 2次元キャラクターへの恋愛 ジェンダー平等な恋愛に向けて
日本企業の人事担当者が新卒採用で最も重視する「コミュニケーション能力」という概念について探求する内容です。調査によると、企業が求めるのは異文化理解を含むグローバルなコミュニケーション能力ですが、実際には上司の意図を察するなどの従来型の能力も求められており、若者は矛盾した要求に直面しています。著者はこの問題を解明し、コミュニケーションの本質を考察しています。
この文章は、社会学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、社会学の基本概念やグローバル化、社会的相互行為、家族、健康、貧困、セクシュアリティ、教育、労働、犯罪、政治、環境など、幅広いテーマが取り上げられています。著者は早稲田大学大学院で社会学を専攻し、それぞれ異なる大学で教授や研究職に就いている専門家たちです。
「私を丸ごと受け入れてくれる人がきっといる」という幻想の中に真の親しさは得られない。人間関係を根本から見直す実用的社会学。 全国1000人以上の先生が選んだ、中高生にいま一番読んでほしい本 「キミに贈る本(キミ本)大賞」(読売中高生新聞主催)第1位! NHK「おはよう日本」 日本テレビ系列「世界一受けたい授業」(又吉直樹さん) TBS系列「林先生が驚く初耳学!」 朝日新聞「売れてる本」(武田砂鉄さん) 各メディアで紹介されて話題沸騰! ! 「みんな仲良く」という重圧に苦しんでいる人へ。 人付き合いのルールを知り少しの作法を身に付けるだけで、複雑な人間関係の中で必要以上に傷つかず、しなやかに生きられるようになる処方箋のような本! 友だちは何よりも大切。でも、なぜこんなに友だちとの関係で傷つき、悩むのだろう。人と人との距離感覚をみがいて、上手に“つながり"を築けるようになろう。 「みんな仲良く」という理念、「私を丸ごと受け入れてくれる人がきっといる」という幻想の中に真の親しさは得られない! 人間関係を根本から見直す、実用的社会学の新定番書。 これでもう、「みんな仲良く」のプレッシャーとはさようなら。 【反響の声、ぞくぞく! 】 まずは目次を見てほしい。 友だち、人との付き合い方のすべてが書かれています。 この本に書かれているのは、生きていくために大切なことのすべてです。 人間関係とは何か。どうすればいいか。 カンタンで深い答えがここにあります。 齋藤孝さん(明治大学教授) わたしは、人付き合いが苦手。 でも「他者と共存することはできる」とこの本は教えてくれました。 多くの人が独りでいたいし、皆といたい…… そんな矛盾の原因と対処法を教えてくれる本です。 壇蜜さん(タレント) 近いと大変で遠いとさびしい他人との「間合い」のとり方。 共感という幻想から自由になる方法。 刊行から10年の「現代の古典」には、生きる上で大切な「心の智慧」が詰まっている。 茂木健一郎さん(脳科学者) 私たちは世間という幻想の中に住んでいる。 中でも厄介な「友だち」について、これほど明快に解説した本は他にない。 読めば心が軽くなる。世界がスッキリ見えてくる。 小島慶子さん(エッセイスト) かつて同調圧力に服する共同体的な作法は、生存戦略と結びついたリアリズムであった。 だがシステムが生存戦略を用済みにした今、意外にも若者の同調圧力は強くなるばかり。作法を知らずに多様性が不安なのが背景だ。 本書は不安を超えるべく新たな作法を示す。 これを読めばあなたの人生は変わるはずだ。 宮台真司さん(社会学者) 『友だち幻想』は、ひとりを怖がり、だけど人と繋がっていることに息苦しさを感じている人=わたしに必要な一冊だった。 南沢奈央さん(女優)『サンデー毎日』2018年8月19-26日夏季合併号 お互いを縛る、窮屈な友だち関係になっていませんか? 自分たちの「関係」を見つめなおす視点を、菅野さんは鮮やかに提示してくれます。 西研さん(哲学者) 第1章 人は一人では生きられない? 第2章 幸せも苦しみも他者がもたらす 第3章 共同性の幻想―なぜ「友だち」のことで悩みは尽きないのか 第4章 「ルール関係」と「フィーリング共有関係」 第5章 熱心さゆえの教育幻想 第6章 家族との関係と、大人になること 第7章 「傷つきやすい私」と友だち幻想 第8章 言葉によって自分を作り変える
この書籍は、児童精神科医の著者が「反省以前の子ども」と呼ばれる、認知力が弱い子どもたちに焦点を当てています。特に「境界知能」の人々に注目し、彼らを社会生活に適応させるための実践的なメソッドを提供します。著者は非行少年との経験を通じて、教育システムや社会での支援の必要性を訴えています。目次には、子どもたちの特徴や教育方法についての章が含まれています。著者は立命館大学の教授であり、子どもたちの支援活動を行っています。
計量/質的調査という対照的な方法を使う2人の社会学者が各トピックについて考え方を示し,社会学的な思考法を立体的に伝える。 「出生」「労働」「老い」といった誰もが体験しうる「人生のイベント」について,計量手法と質的研究という対照的な方法論者が各々の考え方を示し,社会学的に考える道筋を立体的に描きだす。新世代の社会学入門。 序 章 人と「社会」のかかわり方 第1章 出生 第2章 学ぶ/教える 第3章 働く 第4章 結婚・家族 第5章 病い・老い 第6章 死 第7章 科学・学問 終 章 「社会」と人とのかかわり方
スタンダードな社会学教育を1冊に。欧米の大学教科書の「ベーシック」を意識し,社会学の基本的な見方・考え方を学ぶテキスト。 英語圏の大学教科書の「ベーシック」を念頭に,社会学の基本的な見方・考え方を学ぶテキスト。広範な領域を扱う学問の中で,どのような共通のヴィジョンをもって研究がなされ,各領域ではどのように考えを深めていくのか。スタンダードな社会学教育を1冊で。 Prologue 社会学とは?(松本康) Ⅰ 社会のみかた Chapter1 理論と方法(松本康) Chapter2 文化と社会(本田量久) Chapter3 社会化と相互行為(前田泰樹) Chapter4 集団と組織(山田真茂留) Chapter5 逸脱と統制(岡邊健) Ⅱ 不平等と多様性 Chapter6 社会階層(中澤渉) Column1 グローバルな不平等(太田麻希子) Chapter7 人種とエスニシティ(石井香世子) Chapter8 ジェンダーとセクシュアリティ(高橋幸) Column2 年齢とエイジング(原田謙) Ⅲ 社会の諸制度 Chapter9 家族とライフコース(阪井裕一郎) Chapter10 宗 教(小池靖) Chapter11 経済と労働(貞包英之) Chapter12 政治と社会運動(丸山真央) Column3 健康と不平等(原田謙) Ⅳ 社会変動 Chapter13 共同体と都市(高木恒一) Chapter14 情報化とメディア(木村忠正) Chapter15 環 境(関礼子) Column4 社会変動(中澤渉)
殺戮部隊を駆り立てた様々な要因を組織社会学の視点から解明したホロコースト研究の金字塔。 殺戮部隊を駆り立てた様々な要因を組織社会学の視点から解明したホロコースト研究の金字塔 「普通の男たち」と「普通のドイツ人」、そして「悪の凡庸さ」を超えて ナチ体制下で普通の人びとがユダヤ人の大量虐殺に進んで参加したのはなぜか。ブラウニングが先鞭をつけたこの問いをさらに掘り下げ、殺戮部隊を駆り立てた様々な要因——イデオロギー、強制力、仲間意識、物欲、残虐性——の働きを組織社会学の視点から解明した、ホロコースト研究の金字塔。 普通のドイツ人男性は組織の成員資格という枠組みの中ではじめて、多くの人びとが抱いていた潜在的な反ユダヤ主義を強制移送、ゲットー解体、大量射殺への具体的な関与に転化する姿勢を身につけたのだった。しかし、だからといって――ここにハンナ・アーレントの伝統に則った説明アプローチとの決定的な違いがあるのだが――組織のメンバーが機械の歯車のように機能したということにはならない。〔……〕つまりホロコーストの遂行を可能にしたのはまさに、組織メンバーの逸脱、再解釈、イニシアティブの力であった。 (「序章より) 原書:Stefan Kühl, Ganz normale Organisationen: Zur Soziologie des Holocaust, Suhrkamp Verlag Berlin 2014. ◎目次 序 章 第一章 「普通の男たち」と「普通のドイツ人」を超えて 1 単純な回答の限界 2 動機追求から動機呈示へ 3 組織メンバーの動機づけ 第二章 目的への共感 1 反ユダヤ主義的なコンセンサスの虚構の形成 2 反ユダヤ主義的なコンセンサスの虚構の確立のための世界観教育の役割 3 「無関心な受容」から「積極的な参加」へ 第三章 強制 1 強制徴集と脱退防止 2 強制組織における成員資格問題の回避 3 自由裁量の限界 4 強制の中の自由 第四章 同志関係 1 同志関係の圧力とインフォーマルな規範の形成 2 同志関係形成の諸次元 3 同志規範はどのように広まったのか 4 自由の付与による同志関係の動員 第五章 金銭 1 大隊員の正規給与の機能 2 ユダヤ人資産の収用による合法的な横領 3 正式な報酬・報償以外の利得 4 横領の機能性 第六章 行為の魅力 1 殺害へのためらいとその克服のための組織的戦略 2 動機の創出——犠牲者の非人間化 3 残虐性の組織文化 第七章 動機の一般化 1 個人的関与の様々な呈示方法 2 自己呈示の管理 3 目的と動機の分離 第八章 殺人者から加害者へ 1 国家の暴力行使の合法化 2 合法性のグレーゾーンにおける暴力行使 3 ナチズム下の法概念の変化 4 合法化による殺害の促進 第九章 普通の組織と異常な組織 1 「異常な組織」のイメージを超えて 2 組織における無関心領域の拡大 3 組織を理解する――結論 補 遺——社会学的アプローチと経験的基盤 訳者解題 文書館史料 文献一覧 事項索引 人名索引 序 章 第一章 「普通の男たち」と「普通のドイツ人」を超えて 1 単純な回答の限界 2 動機追求から動機呈示へ 3 組織メンバーの動機づけ 第二章 目的への共感 1 反ユダヤ主義的なコンセンサスの虚構の形成 2 反ユダヤ主義的なコンセンサスの虚構の確立のための世界観教育の役割 3 「無関心な受容」から「積極的な参加」へ 第三章 強 制 1 強制徴集と脱退防止 2 強制組織における成員資格問題の回避 3 自由裁量の限界 4 強制の中の自由 第四章 同志関係 1 同志関係の圧力とインフォーマルな規範の形成 2 同志関係形成の諸次元 3 同志規範はどのように広まったのか 4 自由の付与による同志関係の動員 第五章 金 銭 1 大隊員の正規給与の機能 2 ユダヤ人資産の収用による合法的な横領 3 正式な報酬・報償以外の利得 4 横領の機能性 第六章 行為の魅力 1 殺害へのためらいとその克服のための組織的戦略 2 動機の創出——犠牲者の非人間化 3 残虐性の組織文化 第七章 動機の一般化 1 個人的関与の様々な呈示方法 2 自己呈示の管理 3 目的と動機の分離 第八章 殺人者から加害者へ 1 国家の暴力行使の合法化 2 合法性のグレーゾーンにおける暴力行使 3 ナチズム下の法概念の変化 4 合法化による殺害の促進 第九章 普通の組織と異常な組織 1 「異常な組織」のイメージを超えて 2 組織における無関心領域の拡大 3 組織を理解する――結論 補 遺——社会学的アプローチと経験的基盤 訳者解題 文書館史料 文献一覧 事項索引 人名索引
「教育格差」に関するよくある質問
Q. 「教育格差」の本を選ぶポイントは?
A. 「教育格差」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「教育格差」本は?
A. 当サイトのランキングでは『教育格差 (ちくま新書)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで46冊の中から厳選しています。
Q. 「教育格差」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「教育格差」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。