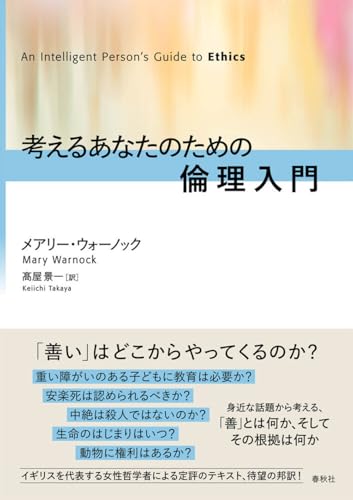【2025年】「道徳」のおすすめ 本 111選!人気ランキング
- たいせつなきみ
- 倫理学入門-アリストテレスから生殖技術、AIまで (中公新書 2598)
- みえるとか みえないとか
- 頭を「からっぽ」にするレッスン 10分間瞑想でマインドフルに生きる
- 自由進度学習の課題から考える 「自立型往還学習」のススメ
- ぼく東綺譚 (新潮文庫)
- 霧のむこうのふしぎな町 (新装版)
- 今さら聞けない!倫理のキホンが2時間で全部頭に入る
- 入門・倫理学の歴史 24人の思想家
- ありがとう (至光社ブッククラブ国際版絵本)
本書は倫理学の基本理論を紹介し、「善い」とは何か、助け合うべき理由や限界について考察します。アリストテレスやカントの理論を平易に解説し、現代の課題(医療、人工知能、戦争、環境問題など)を倫理学の視点から探求します。社会契約論や功利主義に関する図解や思想家のコラムも含まれています。著者は哲学・倫理学を専門とする品川哲彦です。
この絵本は、宇宙と地球の違いを楽しみながら探求する内容で、「違いを考える」ことをテーマにしています。著者のヨシタケシンスケは多くの賞を受賞した絵本作家で、伊藤亜紗は美学と現代アートを専門とする准教授です。
本書『頭を「からっぽ」にするレッスン』は、著者アンディ・プディコムによるマインドフルネス入門書で、瞑想を通じて心を整え、より良い生活を送るための具体的な方法を提供します。ビル・ゲイツや人気YouTuberからも推薦されており、特に忙しい人にとって瞑想の重要性を説いています。10分間の瞑想を日常に取り入れるためのヒントや体験談も紹介されており、瞑想を身近なものとして実践する手助けをします。
6年生のリナは夏休みに一人旅に出かけ、霧の谷の森を越えた先に、赤やクリーム色の洋館が並ぶ風変わりな町に辿り着く。そこで出会った個性的な人々との交流が描かれたファンタジー作品で、『千と千尋の神隠し』に影響を与えた名作。著者は柏葉幸子と杉田比呂美。
「霧のむこうのふしぎな町」題名を見るだけで興味引いちゃう!(霧の向こうは…)と考えてしまう子もいるのかも…
この本は、宮崎駿が千と千尋の神隠しを制作する際に参考にした物語だと言われています。別世界に行く所、仕事をしたり、取り仕切るお婆さんがいたり…リンクする箇所は多いです。
この文章は、哲学者の一覧と著者情報を提供しています。著者は柘植尚則で、倫理学を専門とし、慶應義塾大学の教授です。彼は1964年に大阪で生まれ、1993年に大阪大学大学院を退学しました。
小学五年生の少年たちの微妙な心情を描いた十七篇のショートストーリー集。転校、死別、友情、恋心など、成長過程の様々な出来事が美しい四季を背景に展開される。著者は重松清で、彼は多様なジャンルで高く評価される作家。
本書は、子どもが主体的に漢字を学ぶための新しい指導システムを提案しています。受け身の学習から脱却し、自立した学習者として成長できるようにすることが目的です。内容は、漢字指導の方法や効果的な学習活動のアイデアを紹介し、全員が漢字を定着させるためのシステムを解説しています。著者は教育者であり、数々の教育賞を受賞しています。
三百万年前の地球に現れた謎の石板がヒトザルに与えた影響や、月面での発見が人類にとっての意味を探る。宇宙船ディスカバリー号のコンピュータ、ハル9000の反乱と唯一の生存者ボーマンの行く先について描かれる。発表から25年を経て、アーサー・C・クラークの新版序文を加えた完全決定版が登場。
話題の「まんがで知る教師の学び」に続く新シリーズスタート! 教育書の枠を超え、未来に向かって生きる全ての日本人が少なからず抱く問題意識をあらためて掘り起こし、投げかけます。 いまこの国で行われつつある「教育改革」が目指すものとは何か? 受験と部活動に明け暮れる中学校と時代に取り残される地域社会。 働き方も生き方も新たな局面を迎えたいま、学校と社会全体が向かうべき方向とは――。 教師(元小学校教頭)である著者が実感を込めて描くリアル・ストーリーです。 1分で読める! 水先案内的コラム「未来の社会を考えるビジネス書」では課題解決のための参考図書を紹介。 第1章 部活動と教育課程――教育課程とは何か 第2章 学習指導要領――社会に開かれた教育課程 第3章 新しい時代に求められる資質・能力――学習の基盤となる資質・能力 第4章 社会の変化――学び続ける力 第5章 学ぶ意義の明確化――なぜ学び、どういった力が身に付くのか 第6章 学習者の視点――教える側から学習する側へ 第7章 学習評価の充実――相互評価と自己評価 第8章 問題発見・解決能力――持続可能な社会づくりの担い手を育む
この書籍は、算数授業のさまざまな要素を網羅しており、効果的な授業を行うための方法や工夫について解説しています。内容は、授業の準備や進行方法、子どもの思考を引き出すための課題提示、話し合いや発表の工夫、ノート指導や板書の重要性、教科書の扱い方、テストの意義、能動的な学習態度の育成など多岐にわたります。著者は新潟県出身の教育者で、算数教育において豊富な経験を持つ専門家です。
この本は、著者の宮澤悠維が10年間の教師経験を基に学級経営のエッセンスをまとめたもので、150の基本的な心得を紹介しています。学級経営に悩む教師たちに向けて、心構え、原則、技法の三つの視点から実践的なアドバイスを提供し、何度でも読み返すことで学び直せる内容となっています。著者は、学級満足度を高めるためのノウハウを広めることを目指しています。
現代倫理学の基本文献。利他性が生物学的な起源を超えて普遍的な倫理へと拡張していくプロセスを鮮やかに描きだす。 理性の力がひろげる〈利他の輪〉 倫理とはなにか? 謎を解く鍵はダーウィン進化論にある。家族や友人への思いやりは、やがて見知らぬ他人へ、さらに動物へと向かう──利他性が生物学的な起源を超えて普遍的な倫理へと拡張していくプロセスを鮮やかに描きだす現代倫理学の基本文献。日々の選択から地球規模の課題にいたるまで、よりよい世界を願うすべての人に。 二〇一一年版へのまえがき まえがき 第一章 利他性の起源 第二章 倫理の生物学的基盤 第三章 進化から倫理へ? 第四章 理性 第五章 理性と遺伝子 第六章 倫理の新しい理解 引用文献に関する注 二〇一一年版へのあとがき 訳者解説 索引
本書は、道徳的な善悪について哲学的に探求する内容で、二人の大学生と猫のアインジヒト、M先生が対話を通じて「人は幸福を求めるのか」「社会契約は可能か」「なぜ道徳的であるべきか」といったテーマを議論します。プラトンやアリストテレス、ホッブズ、ルソー、カントなどの思想を紹介しながら、倫理学の新たな視点を提供する不道徳な教科書です。著者は永井均で、哲学・倫理学を専攻する教授です。
「北栃木愛犬救命訓練所」の所長、中村信哉氏は、人を咬む危険な犬を専門に訓練する犬の訓練士です。中村氏の訓練方法は時に体罰を伴い、賛否が分かれていますが、彼は殺処分の運命にある犬たちを救うために立ち向かっています。このノンフィクションは、彼の訓練士としての活動や、犬と飼い主の苦悩を描いています。著者はノンフィクション作家の佐藤真澄氏です。
この書籍は、算数授業を変えるための14の「しかけ」を紹介し、それぞれに5つの事例を提供しています。授業を通じて子どもたちの学びを深める方法を探る内容で、具体的な事例を通じて実践的なアイデアを提供します。著者は北海道教育大学附属札幌小学校の教諭、瀧ヶ平悠史氏です。
この書籍は、人工知能(AI)に関する過大視や悪夢のシナリオを乗り越え、AIが引き起こす倫理的疑問に対して具体的な回答を提供し、受け入れ可能な統合的な視点を提示しています。技術的、哲学的、実践的な側面がバランスよく扱われ、AI社会の人間中心なデザインのためのアイデアも提案されています。著者はAI倫理の第一人者であり、専門的な背景を持つ教授たちです。
堀田健一さんは、40年間で2600台以上の体の不自由な人々のための自転車を手作りしてきた。彼の少年時代からの物作りへの情熱や、逆境を乗り越えながら人々の願いを叶えてきた軌跡を描いた感動的なノンフィクションである。著者は高橋うららで、命の大切さをテーマにした児童書を中心に執筆している。
本書は、AIやロボット技術の進化に伴う倫理的問題を考察し、人間の道徳について探求する入門書です。著者たちは、ロボットやAIとの関係における倫理学の知恵を提供し、道徳的行為者性や責任、プライバシー、労働の未来などのテーマを扱っています。著者は名古屋大学や南山大学、金沢大学の教授陣で構成されています。
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづける永遠の名著!一年生担任のおののきと驚きの実録!一年生を知って、一人前の教師になろう! 一年生を迎える準備 ドキュメント・入学式当日-緊張の二五分間 入学後一週間のようす 入学後一カ月 給食始まる 係の仕事に意欲をもたせる 授業を知的に 保護者とのかかわり方 一人一人への配慮を具体的に 児童の活動を生き生きと 一年生を終える
本書は、世阿弥の「風姿花伝」に基づき、教師の授業実践と学びのあり方を探求します。著者の佐藤学氏は、授業技術を指南するのではなく、教師の「学びの思想」と「身体技法」を伝えることを目指しています。内容は、教師としての成長や創造的な授業技法、実践例を通じた教師の役割についての考察が含まれています。佐藤氏は教育界で高く評価されている専門家です。
日常のささやかで愛おしいものについてのショートエッセイ集。著者の江國香織が、輪ゴムやレモンしぼり器など身の回りの60のアイテムにまつわる記憶や思いを、柔らかな言葉で綴っています。ユーモアと深い想いが漂う、楽しめるエッセイです。
町外れに住む老人を観察していた少年たちが、彼の死を見届けることを目的としていたが、次第に老人との深い交流が生まれていく。物語は、失われるものと失われないものに触れる少年たちの成長を描いている。
第一歌集『サイレンと犀』につづく 5年ぶりの第二歌集、ついに刊行! 「自分が見落としていた記憶を 連れて来てくれる とてもやさしく 体験を(こんなに簡単に) 捏造してくれる とてもあたたかく 大嗣くん あの時間を 丸ごと カプセルに閉じ込めたような言葉達は それぞれの経験が誰のものにもなり得る そんな可能性(未来)を 示唆しているかも知れないよ」 国府達矢(ミュージシャン) 「21世紀前半のなにげない日常に潜む、 こわれやすい奇跡を、琥珀の中に永遠に 閉じ込めてしまうような作品の数々。 ポップスのように、映画のように。 短歌って今もこんなに アクチュアルなものだったのか。」 七尾旅人(シンガーソングライター) 【著者選】 写メでしか見てないけれどきみの犬はきみを残して死なないでほしい 返信はしなくていいからアメリカっぽいドーナツでも食べて元気だして もう一軒寄りたい本屋さんがあってちょっと歩くんやけどいいかな ゆぶね、って名前の柴を飼っていたお風呂屋さんとゆぶねさよなら 二回目で気づく仕草のある映画みたいに一回目を生きたいよ
師弟のようなクラスメートのような3人の創作とお話の本。 師弟のようなクラスメートのような3人の創作とお話の本。 国民的詩人と新鋭歌人の詩と短歌による「連詩」と「感想戦」を収録。読み合いと読み違い、感情と技術、笑いとスリルが交わります。 【連詩とは】 詩人同士が、詩を順々に読みあいひとつの作品を合作する創作の形式です。今回は、詩人と歌人が紡ぐ、詩と短歌による「連詩」。歌人側は2人が交代しながら受け、具体的には、次の順で行いました。 岡野大嗣(歌人)→谷川俊太郎(詩人)→木下龍也(歌人)→谷川俊太郎 →岡野大嗣 →谷川俊太郎 →木下龍也 →谷川俊太郎 →岡野大嗣……と、これを36番目までつづけ、ひとつの連詩としての作品をつくります。 はじめに 詩とは? 短歌とは? 連詩とは? 紹介 詩人と歌人とそれぞれの詩と短歌 連詩 今日は誰にも愛されたかった 感想戦 連詩について語り合った三人の記録 エッセイ 木下龍也「ひとりだと選んでしまう暗い道」 エッセイ 岡野大嗣「ここがどこかになる時間」 あとがき 谷川俊太郎「コトバ」について
この文章は、構造化の重要性とその実践方法についての書籍の目次を紹介しています。第1章では構造化の利点や教育現場での意義を述べ、第2章では物理的、時間、活動の構造化に関する支援ツールを紹介。第3章では具体的な支援ツールの作り方を説明しています。著者は特別支援教育や福祉に関連する専門家です。
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづける永遠の名著!技術があれば授業がうまくなり、子供たちは学校が好きになる。 第1章 授業の原則(趣意説明の原則 一時一事の原則 ほか) 第2章 教師の技量(子供に好かれる教師 子供が教わりたい教師 ほか) 第3章 授業の腕を上げる法則(根拠をもって実態をつかめ 教師の技量を向上させる常識的方法 ほか) 第4章 新しい教育文化の創造(「授業分析・授業解説」の力を付ける 教師の共通問題への挑戦 ほか)
この書籍は、WordとExcelを使った資料作成の効率を高めるための実践テクニックを提供します。著者は2000人以上の受講生を指導した経験を持ち、資料作成における「美しさ」「スピード」「共有性」を重視しています。内容は、基本操作の習得から、作成速度の向上、見栄えの整え方、そして他者との共有方法まで多岐にわたります。特に、誤った使い方や効率の悪い方法を避けることに焦点を当て、ビジネスシーンで恥ずかしくない資料作成を目指します。新入社員やビジネスパーソンに最適な一冊です。
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづけるスーパー名著!新卒の教師でもすぐに子供を動かせるようになる「法則」。 第1章 子供を動かす原理原則編(子供を動かす法則(群れとして動かす場合)-一つの法則と五つの補則 子供を動かす原則(組織として動かす場合)-三つの原則と九つの技能 新卒教師の教室は、なぜ混乱するか 「いじめ」の構造を、まず破壊せよ! 「プロの目」は、修業によって培われる 存在感が実感できてこそ子供は動く) 第2章 子供を動かす実践編(厳しく「教える」だけが動かす方法ではない 朝会に全校児童を集合させる 応援団の子供たちを動かす 指導方法を工夫して子供を動かす やるべきことを一人一人に示せ-卒業式よびかけの練習)
この書籍は、Excelの実務に役立つ知識を提供する入門書で、5年ぶりに全面リニューアルされました。内容には、グラフの使い方や「神Excel」の問題解決策、Office 365とWindows 10に対応した最新のテクニックが含まれています。著者の吉田拳は、Excel業務改善の専門家であり、実務直結の指導実績があります。読者は、効率的なExcelの使い方や関数の活用法を学び、仕事をよりスムーズに進めることができます。
『浮雲』は、明治20年に発表された二葉亭四迷の処女作で、言文一致の新しい文章スタイルで当時の人々を驚かせました。物語は、秀才で世間知らずな青年官吏・内海文三の内面的な苦悩を描写し、知識階級を人間として描いた作品であり、日本近代小説の先駆けとされています。著者の二葉亭四迷は1864年生まれで、東京外国語学校で学び、後に作家として活動しました。
道徳的価値って、そもそも何だろう? 文部科学省教科調査官(当時)として学習指導要領改訂に携わった著者が、道徳的価値について様々な観点から解説。道徳的価値への確かな理解がよりよい道徳授業を創る! 学習指導要領では特別の教科 道徳の教科目標として「道徳的価値の理解を基に・・(中略)・・道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」ことが示されました。では、道徳的価値とはそもそも何でしょう。 「自律」「自由」「責任」「個性の伸長」「社会正義」・・・など、大人でも説明が難しいような「道徳的価値」について、その見方・考え方を徹底解説。子どもたちの発達段階に合わせてどのような指導をしたらよいかが分かります。 ●著者について 赤堀 博行(帝京大学大学院教職研究科教授) 1960年東京都生まれ。都内公立小学校教諭、調布市教育委員会指導主事、東京都教育庁指導部義務教育心身障害教育指導課指導主事、同統括指導主事、東京都知事本局企画調整部企画調整課調整主査(治安対策担当)、東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事、東京都教育庁指導部主任指導主事(教育課程・教育経営担当)、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官を経て、現職。 教諭時代は、道徳の時間の授業実践、生徒指導に、指導主事時代は、道徳授業の地区公開講座の充実、教育課程関係資料の作成などに尽力する。この間、平成4年度文部省道徳教育推進状況調査研究協力者、平成6年度文部省小学校道徳教育推進指導資料作成協力者「うばわれた自由(ビデオ資料)」、平成14年度文部科学省道徳教育推進指導資料作成協力者「心のノートを生かした道徳教育の展開」平成15年度文部科学省生徒指導推進指導資料作成協力者「非行防止教育実践事例集」、平成20年度版『小学校学習指導要領解説 道徳編』の作成にかかわる。 第1章 学校の道徳教育における道徳的価値の考え方 1 道徳授業が目指すもの 2 道徳的価値の見方・考え方 3 道徳的価値と徳目 4 道徳の内容項目と道徳的価値 第2章 道徳の内容項目と道徳的価値 1 A主として自分自身に関すること ⑴善悪の判断、自律、自由と責任 ①正義 ➁自主自律 ➂自信 ④自由 ➄責任 ⑵正直、誠実 ①正直 ➁素直 ➂明朗 ④反省 ➄誠実 ⑶節度、節制 ①健康 ②安全 ③物持 ④節約 ➄整理整頓 ⑥自立 ⑦思慮 ⑧節度 ⑨節制 ⑷個性の伸長 ①個性伸長 ②向上心 ⑸希望と勇気、努力と強い意志 ①勤勉 ②努力 ③不撓不屈 ④希望 ➄勇気 ⑥克己 ⑹真理の探究 ①探究心 ②創意 ③進取 2 B主として人との関わりに関すること ⑴親切、思いやり ①親切 ②同情 ⑵感謝 ①尊敬 ②感謝 ③報恩 ⑶礼儀 ①礼儀 ②真心 ⑷友情、信頼 ①友情 ②協力 ③信頼 ④異性尊重 ⑸相互理解、寛容 ①相互理解 ②寛容 ③謙虚 3 C主として集団や社会との関わりに関すること ⑴規則の尊重 ①規則遵守 ②公共心 ③公徳心 ④権利 ➄義務 ⑵公正、公平、社会正義 ①公正 ②公平 ③社会正義 ⑶勤労、公共の精神 ①勤労 ②奉仕 ⑷家族愛、家庭生活の充実 ①家族愛 ・孝行 ・友愛 ⑸よりよい学校生活、集団生活の充実 ①愛校心 ⑹伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度 ①郷土愛 ②愛国心 ⑺国際理解、国際親善 ①国際理解 ②国際親善 ③人類愛 4 D主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること ⑴生命の尊さ ①生命尊重 ⑵自然愛護 ①動植物愛護 ②自然愛護 ③環境保全 ⑶感動、畏敬の念 ①畏敬 ②敬虔 ⑷よりよく生きる喜び ①高潔 おわりに 道徳科の特質を生かした授業を行うために
私、小説苦手でした。文字多いのは苦手でも、これ読んだら小説大好き‼️皆さん‼️ ぜひ、読んでみてね😊
この本は、つまらないと思うけど、何回も読んでみると、面白いなって感じました。この本は、結構本読むのが好きな人が読むと面白く感じるかも。苦手な人が読むと、文字が多いので、途中で飽きると思います。頭の中で、情景を考えてみると面白いよ!(これは個人の感想ですので、自分で試してみてください)
本書は倫理学が哲学の中心であることを強調し、古代ギリシアから20世紀までの思想家たちの倫理に対するアプローチを三つの潮流に分けて解説します。アリストテレスやエピクロス、ストア派から始まり、功利主義やカント、ヘーゲルに至るまでの人間性の探求を通じて、倫理が人間の行動や思索をどのように規定するかを明らかにします。著者は宇都宮芳明で、哲学・倫理学の専門家です。
「道徳読み」=教科書の読み物教材を徹底活用した、どの教科書でも使える授業法。 準備物はありません。教科書と鉛筆、そして考える頭だけ。 「道徳読み」は次の5つのパートで構成されます。 1、普通に読む 2、道徳読み(道徳さがし・道徳みつけ)をする →子どもたちは、主体的に、真剣に、教材と向き合います。 3、みつけた道徳を発表する →子どもたちは、対話を通じて自分が気づかなかった道徳を獲得。 4、登場人物に通知表を付ける →子どもたちは、自分とは異なる考え方を学びます。 5、自分を省みる →子どもたちは、自分自身への深い学びを体験します。 この授業法を学べば、誰でも、主体的・対話的で深い学びのある道徳授業ができるようになります。 本書では「道徳読み」の基本から実践までを1冊に収録しました。実践パートでは、おなじみの教材を使った授業が、学習指導案から実際の授業のながれまで全学年分掲載されています。 Ⅰ 「道徳読み」の基本 1 道徳の基本的な考え方 ①道徳脳で教材を読む/②心は自分から/③第二の天性を豊かにする/④他人には優しく。自分には? 2 「道徳読み」の方法 ①普通に読む(通読)/②道徳さがし・道徳みつけ/③発表をする/④通知表を付ける/⑤省みる(自分の心に落とす) 3 評価(子どもに対する評価) ①「特別な教科 道徳」の評価/②「道徳読み」での評価 4 「道徳読み」の効果 ①子どもへの効果/②広がる目/③教師の教材分析力がつく Ⅱ 「道徳読み」の実際 1 学年別・授業実践 第一学年 「はしのうえのおおかみ」 第二学年 「七つぼし」 第三学年 「ヒキガエルとロバ」 第四学年 「ブラッドレーのせい求書」 第五学年 「手品師」 第六学年 「ブランコ乗りとピエロ」 2 「道徳読み」をより豊かにするために 発展例① 「道徳ってどんな勉強?」 発展例② 「読み物教材以外で『道徳読み』」 Ⅲ「道徳読み」に困ったらQ&A コラム●「道徳読み」と学級づくり ① 子どもを観る視点にする/② 5分間の小さな「道徳読み」/③「法治」と「徳治」
著者伊藤亜紗は、視覚が人間の情報取得において重要な役割を果たす一方で、視覚を失った場合の身体や世界の捉え方について探求しています。視覚障害者の空間認識や感覚の使い方、コミュニケーション方法、ユーモアを生き抜く戦略として分析し、「見る」ことそのものを再考する内容です。目次では、空間、感覚、運動、言葉、ユーモアに関する章が設けられています。
アルジェリアのオラン市で医師リウーが鼠の死体を発見し、原因不明の熱病者が続出する。これはペストの発生を示しており、孤立した市民たちが「悪」と闘う姿を描くことで、人間性や不条理に直面した時の人間の様々な反応を表現している。著者カミュは、文学と反戦活動を通じて評価を受け、ノーベル文学賞を受賞した。翻訳者の宮崎嶺雄は多くのフランス文学を紹介した。
この本は、子どもから大人までが一緒に考え、議論できる道徳に関する問題を扱っています。嘘や勉強の意義、正義についての難しい質問を通じて、家族や友人と意見を交わすことが重要だと説いています。著名人の意見も掲載されており、巻末には対話の記録を残せるワークシートがあります。著者は広告業界で活躍するクリエイターたちです。
この本は、シリーズ累計40万部を誇る天気に関する知識をやさしく紹介するもので、著者は気象研究者の荒木健太郎氏です。雲、雨、雪、虹、台風、竜巻など、空に関する興味深いトピックが満載で、子どもから大人まで楽しめます。各章では雲の種類や性質、空の色や虹の形、気象現象の詳細などが解説され、最近の気象問題にも触れています。読者は「天気・気象のなぜ?」についての理解を深めることができます。
この文章は、学級づくりに関する書籍の目次を紹介しています。内容は、学級の構築や仕組みづくり、集団の高め方、個別対応、交流活動、秩序ある教室づくりのコツについて触れています。著者は野中信行氏で、教育学の専門家です。
小川三四郎は熊本の高校を卒業し、東京の大学に入学する。そこで、自由奔放な女性里見美禰子と出会い、彼女に惹かれていく。青春の中での学問や友情、恋愛の不安や戸惑いが描かれ、三四郎の恋愛から失恋に至る過程が物語の中心となっている。この作品は、夏目漱石の三部作「それから」「門」の序曲となる。夏目漱石は1867年生まれの著名な日本の作家で、多くの傑作を残した。
本書は、新任教師向けに「仕事のやり方」「新年度・新学期の準備」「学級経営」「授業」「子どもとのコミュニケーション」「保護者との関わり方」についての基本的なコツを紹介しています。特に初任者が直面する課題や失敗例に焦点を当て、学級崩壊を防ぎながら1年目を乗り切るための実践的なアドバイスが提供されています。著者は元教師で、初任者指導の経験が豊富です。
本書は、クラスの落ち着きのなさややんちゃな子の扱いに悩む教師に向けて、ベテラン教師の習慣を紹介し、クラスをまとめる方法を提案しています。内容は、普通の子に注目すること、授業や休み時間に子どもとつながること、給食や掃除の時間を活用すること、教師同士の絆を深めることなど、多岐にわたります。著者は兵庫県の公立小学教諭で、「笑育」を提唱している俵原正仁氏です。
小型警察犬のアンズは、殺処分寸前のトイプードルで、ベテラン指導士に引き取られた後、警察犬としての訓練を受けます。シェパードたちと共に努力を重ね、最終的に警察犬として活躍するまでの実話を描いたノンフィクションです。著者は警察犬指導士の鈴木博房氏で、30年以上の経験があります。
・20世紀を代表する哲学者、バーナード・ウィリアムズによるカリフォルニア大学の名講義。 ・西洋哲学が見落としていた「倫理」をギリシア古典に発見し、近代道徳の呪縛から解放する〈反道徳的な倫理学〉。 ・解説=納富信留(東京大学大学院教授) 近代以降の進歩主義的な見方では、古代ギリシア人は未開の心性をもち、より洗練された道徳が人間性を陶冶してきたと捉えられてきた。 ウィリアムズはこのような道徳哲学の提示する人間が、生きられた経験から切り離された、無性格な道徳的自己であるとして批判する。それとは対照的に、具体的な性格と来歴をもつ人々を描く、ホメロスの叙事詩やアイスキュロス、ソポクレスらの悲劇作品を読み解き、そこに流れる豊かな倫理的思考を明らかにする。 道徳哲学やプラトン、アリストテレスらの哲学を批判的に参照しながら、恥と罪、必然性(運命)と義務、運命と自由意思、責任と行為者性といった概念をめぐる議論を通して、古代と現代を通じてこの現実を生きる人間の生の姿を描き出す、カリフォルニア大学の名講義。 はじめに 二〇〇八年版への序文 A. A. ロング 第一章 古代の解放 第二章 行為者性のいくつかの中心 第三章 責任を認識すること 第四章 恥と自律 第五章 いくつかの必然的なアイデンティティ 第六章 可能性・自由・力 解説 古代ギリシアから私たちが学ぶこと 納富信留 訳者あとがき 古典文献一覧 参考文献一覧 附録1/附録2 注 索引
本書は、大人が子どもに対して身につけるべき応援スキルを35紹介しています。具体的には、ほめる、しかる、伝える、励ますスキルが中心で、イラストやエピソードを交えて解説されています。著者は、支援を行う大人がまず変わるべきだと強調し、子どもたちが大人の行動をモデルに成長することを示唆しています。各スキルは、子どもの気持ちに寄り添うことや、ポジティブな言葉かけの重要性を含んでおり、自己反省を促す内容となっています。
本書は、教師1年目から効果的に働くための仕事術を紹介しています。学級づくりや日々の働き方を考えるための思考法や、仕事に追われないための3つのステップ(ビジョンの明確化、多様なアイデアの提示、実行の継続)を提案。内容は、仕事のデザイン、学級の1日・1年の計画、時間を生み出すタスクデザインなど多岐にわたります。著者は15年間の公立小学校教諭を経て、オルタナティブスクールで活動する青山雄太氏です。
この本は、異年齢の子どもたちの遊びが学習能力を向上させる理由を探求し、狩猟採集時代の生活技術や著者の子どもに対する教育経験を通じて、学校教育のあり方を考察しています。著者は、自由な遊びが学びの重要な要素であることを人類史に基づいて説明し、遊びが子どもの社会的・感情的発達や自己教育力に与える影響を明らかにしています。全体として、良き学び手になるための知恵が詰まった内容です。
朋子は結婚三年目の30歳で突然亡くなり、残された「僕」は一人で娘・美紀を育てる決意をする。物語は、美紀の初登園から小学校卒業までの成長を、季節の移り変わりとともに描いている。著者は重松清で、数々の文学賞を受賞している。
「道徳」に関するよくある質問
Q. 「道徳」の本を選ぶポイントは?
A. 「道徳」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「道徳」本は?
A. 当サイトのランキングでは『たいせつなきみ』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで111冊の中から厳選しています。
Q. 「道徳」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「道徳」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。