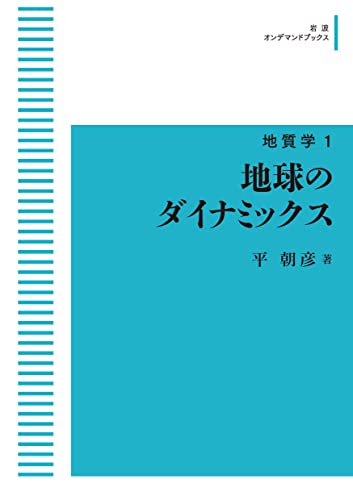【2025年】「地質学」のおすすめ 本 104選!人気ランキング
- 構造地質学
- 岩石学 (現代地球科学入門シリーズ 16)
- フィールドジオロジー入門
- すごい地層の読み解きかた
- 岩石学 I 偏光顕微鏡と造岩鉱物 (共立全書 189)
- 岩石学II―岩石の性質と分類 (共立全書 (205))
- 岩石学概論 上 記載岩石学(CD-ROM付): 岩石学のための情報収集マニュアル
- 岩石学概論〈下〉解析岩石学―成因的岩石学へのガイド
- ジオパークを楽しむ本—日本列島ジオサイト地質百選—
- はじめての地質学―日本の地層と岩石を調べる
本書は、地球内部の観察が困難な中、岩石学の基礎を学ぶための教科書です。著者は名古屋大学の榎並正樹教授で、岩石や鉱物の性質、火成岩や変成岩の成因などを解説しています。内容は、結晶化学や岩石熱力学も含み、地質学や固体地球化学を学ぶ人々に向けています。各章では、岩石の構成、造岩鉱物、相平衡、火成作用、変成作用などの重要なテーマを扱っています。
本書は、偏光顕微鏡を使用して造岩鉱物を観察・鑑定するための基礎から応用までの知識を詳述しています。内容は、結晶の光学的性質、偏光顕微鏡の構成や調整方法、各種造岩鉱物の光学的性質について解説されており、具体的には結晶光学の初歩や屈折率の測定法などが含まれています。
本書では、火成岩と変成岩の成因論の概要と、それに関連するデータ解析方法について詳述しています。変成岩の成因を理解するためには、個別の変成岩だけでなく、広域の変成帯や接触変成域全体を解析することが重要です。内容は、マグマの生成機構、さまざまな火成岩の種類、変成作用の基礎、相平衡、温度・圧力・時間経路など、多岐にわたるテーマをカバーしています。著者は岩石学の専門家であり、地質学の研究に基づいた内容となっています。
足元を見つめることから始まり、日本列島のなりたち、地下資源、地震や火山について考察し、地形風景の見方・楽しみ方も紹介する。 いま立っている(座っている?)地面は何でできているでしょうか。 アスファルトでしょうか、土でしょうか、それとも砂でしょうか。それでは「土」や「砂」って何でしょうか。それは「鉱物」です。鉱物とは、天然でできる無機物質のことで、土はおもに粘土鉱物からなり、砂は石英などの硬い鉱物からなります。鉱物は地層や岩石をつくる最小単位で、地層や岩石の集まり・集合体が「地質」となります。 本書では、足元の下がどうなっているのかから始まり、地球の奥深くを探りながら、地質学の歴史、日本列島のなりたちや地下資源、地震や火山について考察し、日本の地質の特徴、地形風景の見方・楽しみ方も紹介していきます。 第1章 地面の下はどうなっているのだろうか 第2章 地球の内部はどうなっているのか 第3章 地質学が歩んできた歴史 第4章 日本列島はどのようにしてできたのだろうか 第5章 大地のおくりもの地下資源 第6章 地震国・火山国に暮らし大地に根ざして生きる 第7章 日本各地の地層・岩石の特徴と地形風景の見方・楽しみ方
この書籍は、日本列島を横断する巨大な地溝「フォッサマグナ」の成因や構造について解説しています。フォッサマグナは約1500万年前に形成され、深さ6000m以上の独特な地形であり、日本の地質や生態、文化に大きな影響を与えています。著者は地球科学の専門家で、フォッサマグナの謎を解き明かすための研究を行い、その重要性を強調しています。目次には、ナウマンの発見からフォッサマグナの成り立ちや影響についての章が含まれています。
「人新世」の正体を、あなたはまだ何も知らない――。 「人新世」の正体を、あなたはまだ何も知らない――。 人文学界で最も名誉ある「タナー講義」を、読みやすい日本語へ完訳。 地質学から歴史学まで、あらゆる学問の専門家の知見を総動員し、多くの分断を乗り越えて環境危機をファクトフルに考えるための一冊。かりそめの答えに満足できない現実派の読者におくる。 山崎直子さん(宇宙飛行士)推薦 「我々はどこへ向かうのか、その考え方の土台となる本。宇宙に学校が出来たら、この本はきっと人類共通の教科書となるでしょう」 ◆そもそも地質年代は誰がどう決める? ◆「大加速グラフ」が示す未来とは? ◆途上国と先進国の分断は乗り越えられる? ◆立場を超えてもつべき新たな「時代意識」とは? ◆人間は技術圏(テクノスフィア)の部品にすぎない? ◆地球の半分からヒトを撤退させるべき? ◆大きな歴史(ビッグ・ヒストリー)は人類を結束させる? 講義1 時代意識としての気候変動 講義2 人間が中心ではなくなるとき、あるいはガイアの残り 日本版特別インタビュー 『人新世の人間の条件』に寄せて 訳者あとがき
グローバル・ネットワークが地球を覆い尽くす「人新世」時代においてその網の目からこぼれ落ちる他者の営みに人類の可能性を見出す。 近代のプロジェクトが推し進めてきたグローバル・ネットワークが、地球全体を覆い尽くす「人新世」時代と呼ばれる今日。近代化の網の目からこぼれ落ちる、過剰なる他者たちの営みから、人類の想像力の可能性を見出す。 近代化の網の目からこぼれ落ちる、過剰なる他者たちの営みから、いかに人類の想像力の可能性を見出すか――。 総勢12名の人類学者が対話・インタビュー形式で「人新世」時代を語る、最新の研究動向に迫る論集。 近代のプロジェクトが推し進めてきたグローバル・ネットワークは、地球全体を覆い尽くすまでに拡大した今日。それは、もはや地球の存在そのものが危ぶまれる、「人新世」時代へと突入したと呼ばれるようになった。 このような21世紀初頭の時代において、人類のさまざまな文化のあり方をつぶさに研究してきた文化人類学もまた、大きな岐路に立たされている。文化人類学という学問が、80億人に達した人類について、その過去と現在を問い、その未来の限界と可能性を探究するという壮大な規模の問題を扱う実践である以上、その担い手である人類学者の立場も関心も見解も多様にならざるをえないだろう。 本書は、こうした豊かな多様性を孕みつつ共通の感性でゆるやかにつながれた文化人類学という学問の実情をできる限りそのままに提示する試みた、文化人類学者たち自身による文化人類学という学的実践の実験的な民族誌である。 対話の形式で紡がれる本書は、現在進行中の文化人類学の実践の目的、対象、方法、意義などの一端が、地域・フィールドを異にする文化人類学者たち自身によってさまざまに語られると同時に、問答を応酬しながら相互に触発し合うことで、新たなパースペクティヴの予感を宿しながら未来の可能性を孕む種子や胚を懐胎してゆく姿を提示していく。 はじめに 序 章 「人新世」時代の文化人類学の挑戦(大村敬一) 第Ⅰ部 グローバル・ネットワークの外部からの挑戦 第1章 多重に生きる ―― カナダ・イヌイトの挑戦(大村敬一) 第2章 先住民運動の挑戦 ―― 新たな政治制度を目指して(深山直子) 第3章 アナーキズム社会の挑戦 ―― マダガスカルのヴェズの戦術の可能性(飯田卓) 第Ⅱ部 変質しゆくグローバル・ネットワーク 第4章 科学技術と気候変動の人類学――近代の「自然/人間」の二元論の再考(森田敦郎) 第5章 グローバル・エコノミーの隙間からの挑戦(中川 理) 第6章 プラネタリーヘルスの挑戦 ――「人新世」時代の医療と公衆衛生(モハーチ ゲルゲイ) 第Ⅲ部 変質しゆく人類 ―― 非人間との出会い 第7章 災害の人類学 ―― 近代を凌駕する他者の力に向き合う(木村周平) 第8章 人類の可変性 ―― 非人間とのもつれ合いのなかで(モハーチ ゲルゲイ/久保明教) 第Ⅳ部 人類の創造力の可能性 第9章 芸術 ―― 「仮構作用」の創造力(中谷和人) 第10章 日常に潜む「生きる力」 ―― 人類社会の根っこにある宗教(土井清美) 第11章 進化史のなかの人類 ―― 人類の創造性と可変性の進化史的基盤(入來篤史/河合香吏) 終 章 人類と地球の未来―― 多様性の苗床になる(大村敬一)
環境の大変化が起きた人新世。優れた観察者で記録者だった画家たちはその変化をどう描いたか。新たな西洋美術の見取り図を提案する。 人類の発展で地球規模の環境変化が起きた時代・人新世。優れた観察者で記録者だった画家たちはその変化をどう描いたか。新たな西洋美術の見取り図を提案する。 人類の発展で地球規模の環境変化が起きた時代・人新世。優れた観察者で記録者だった画家たちはその変化をどう描いたか。新たな西洋美術の見取り図を提案する。
「人新世 大絶滅」問題を哲学的に掘り下げた力作。人類を「絶滅種」と捉えその問題点をあぶり出す。人類に残された時間はわずかだ。 私たちは人類の絶滅というとんでもない状況下にある。 本書は「人新世 大絶滅」の問題を哲学的に掘り下げた力作で、人類をはっきり「絶滅種」と捉えその問題点をあぶり出している。残された時間はわずかだ。ここに提起された警鐘に是非とも耳を傾けたい。 はしがき 第Ⅰ篇 形而下の絶滅学 第Ⅰ部 預言 第1章 人類絶滅の預言 人類は「絶滅生物」である 単一種の人類が「大絶滅」を起こす 啓蒙思想が「大加速」を惹起した 気候攻撃が「大絶滅」を起こす 最終叡智の「絶滅学」 哲学が明かす「絶滅の公理」 第Ⅱ部 覚醒 第2章 「人新世」の絶滅科学 生物・人類絶滅の科学原理 「人新世」の伝説 CO2急増と気候変動 “Big Five”の大絶滅要因 CO2濃度の「絶滅危機」レベル 「六〇年後の今世紀末」に迫る絶滅危機 短期急進性の「大絶滅」 気温急上昇による「絶滅の惨状」 高温化と植物・哺乳類の熱死 「人類絶滅」の近未来シナリオ 第3章 「地球地質改悪と惑星限界」の科学研究 「地球地質構造」の改悪 人類絶滅後の「人工物廃棄・痕跡」 「地球惑星の限界」が到来 第4章 「地球資源枯渇」の科学研究 「成長の限界」の現実化 ピーク・オイルと石油の枯渇 「石油文明」の黄昏 「金属資源」の枯渇迫る 「水資源・食糧資源」の危機 「生物資源喪失」の危機 第Ⅲ部 罪業 第5章 「文明絶滅」の科学研究 文明絶滅シナリオ1─自然資源の枯渇 文明絶滅シナリオ2─資本主義の終焉 文明絶滅シナリオ3─大恐慌の壊滅打撃 文明絶滅シナリオ4─産業革命の途絶 文明絶滅シナリオ5─再生可能エネルギーの挫折 第6章 「人類絶滅」の科学研究 人類絶滅シナリオ1─気候危機の経済損失 人類絶滅シナリオ2─気候危機が起こす食糧危機 人類絶滅シナリオ3─気候危機による生物絶滅 人類絶滅シナリオ4─パンデミックの衝撃 人類絶滅シナリオ5─気候危機による人命損失 第Ⅱ篇 形而上の絶滅学 第Ⅳ部 審判 第7章 人類・文明の絶滅学 人類・文明絶滅の未来展望 絶滅必定のフィードバック・ループ 「人新世」の気候科学 「絶滅預言」の先駆性 人新世の「絶滅学」 第8章 人新世の「崩壊哲学」 「啓蒙哲学」の絶滅衝動 人新世の「崩壊哲学」 崩壊哲学の「実在公理」 崩壊哲学の「観念公理」 第9章 「地球気候」の実在論 「地球気候」の実在公理 「地球気候」の観念公理 「地球気候」の交叉思考 「無秩序激発カオス力動性」 第Ⅴ部 懺悔 第10章 人類悪性と文明衝動 「人間学」が暴く人類悪性 「人類悪性」の哲学 「驕慢・錯乱」の人間性 「文明衝動」の哲学 「分裂症とリビドー」の資本主義 「絶滅便乗型」資本主義 第Ⅵ部 鎮魂 第11章 人新世の絶滅学 「絶滅学」の統合研究 「絶滅哲学」の構想 絶滅哲学の「実在公理」 絶滅哲学の「観念公理」 ニヒル・リアリズム 「涅槃」の地球惑星 第Ⅶ部 救済 第12章 最後のユートピア 絶望と希望のせめぎあい 脆弱性のユートピア 復元性のユートピア 超越性のユートピア 心のレジリエンス あとがき 人名索引 星野 克美;0305;01;環境問題を哲学的に掘り下げ、人間を「絶滅種」と捉えその問題点をあぶり出す。人類に残された時間はわずかだ。警鐘に耳を傾けたい。;20221102
1960年代後半に登場したプレートテクトニクスは,欧米では70年代初めには地球科学の支配的なパラダイムとなった.しかし,日本の地質学界ではその受容に10年以上の遅れが見られた.なぜこのような事態が生じたのか? 多くの資料をもとにその謎を解明する.初版2008年. 新装版へのまえがき まえがき 序 章 プレートテクトニクスと日本の科学史 第1章 大陸移動説からプレートテクトニクスへ——地球科学の革命 第2章 戦前の日本の地球科学の発展とその特徴 第3章 戦後の日本の民主主義運動と地学団体研究会 第4章 「2つの科学」と地学団体研究会 第5章 日本独自の「地向斜造山論」の形成 第6章 プレートテクトニクスの登場と日本の地球科学 第7章 「日本列島=付加体」説の形成とプレートテクトニクスの受容 終 章 プレートテクトニクスの受容とそれ以降の日本の地球科学 あとがき 年表/参考資料/事項索引/人名索引 Rejection and Acceptance of Plate Tectonics: A History of Earth Science in Postwar Japan [New Edition] Jiro TOMARI
沖積低地を知る 沖積低地はどのような場所につくられるか 沖積低地を構成する地層はどのようにしてできてきたか 沖積低地の地形の特徴と成り立ち 微地形と浅層地質から読み解く地形環境変化 沖積低地と水害 沖積低地と地震 航空機レーザ計測データと沖積低地の地形環境 世界のデルタ 濃尾平野の形成場 濃尾平野の表層堆積物 越後平野の地形特性と高精度地形発達史構築への課題 矢作川沖積低地における地形環境変遷と遺跡の立地 珪藻分析を用いた浜名湖周辺の沖積低地の地形環境復原 液状化現象と地形・地質条件との関係 海岸平野における地形と津波の挙動 マレー半島海岸平野の地形発達と酸性土壌 衛星リモートセンシングでみる洪水と微地形
本書は、21世紀の「人間とは何か」との問い直しと、新たなヒューマニズムの構築を〈ビッグヒストリー〉の視点から行う試みである。 「人新世(じんしんせい)」と呼ばれる現代にあって、本書は21世紀の「人間とは何か」との問い直しと、新たなヒューマニズムの構築を〈ビッグヒストリー〉の視点から行う試みである。 人工知能が人間の知性を超えようとする今、 人間は他の生命に対して優越性があるといえるのか。 「人新世(じんしんせい)」と呼ばれる現代にあって、 本書は21世紀の「人間とは何か」との問い直しと、新たなヒューマニズムの構築を 138億年という〈ビッグヒストリー〉の視点から行う試みである。 序論 ビッグヒストリーの人間像とコモンズ像 第1章 宇宙飛行士による〈宇宙的視点〉の諸相 第2章 ディープタイム思考 第3章 宇宙的ヒューマニズム 第4章 複雑性を再考する 第5章 銀河人の経済学 第6章 歌う惑星
本書は、名作『不思議の国のアリス』の原文を読み解くためのガイドであり、英文法を通じて作者ルイス・キャロルの真意を理解する手助けをします。英文学者の勝田悠紀が案内役となり、英文法の知識を深めることで、アリスの物語をより楽しむことができる内容です。また、マンガ家のはしゃによるあらすじも掲載されており、英文読解に不安がある読者も安心して挑戦できます。音声もダウンロード可能です。
「人新世」の政治的リアリズム 惑星政治とは何か 国際政治学はマテリアル・ターンの真意を受けとめられるか? 領土と主権に関する政治理論上の一考察 石油から見る惑星限界の系譜学 構造的暴力論から「緩慢な暴力」論へ ノン・ヒューマンとのデモクラシー序説 脱人間中心のガイア政治 人新世のアナーキカル・ソサイエティ ノン・ヒューマン〈と〉の平和とは何か
本書は、フランス現象学の巨人マルク・リシールが自身の哲学を多様なテーマについて語る大対談録です。プラトンやカント、ハイデガーから物理学や神話学、音楽に至るまで幅広く探求しています。著者リシールはベルギー出身の現象学者で、数多くの著作を残し、2015年に逝去しました。サシャ・カールソンが日本語版の序文を執筆し、村上靖彦が内容を紹介しています。全体は哲学の伝統との関わり、現象学的アプローチ、象徴制度に関する考察の三部構成になっています。
本書は固体地球、大気海洋、天文の3部構成で、それぞれの専門家が基礎から最新の知識まで、わかりやすく解説。 本書は固体地球、大気海洋、天文の3部構成で、それぞれの専門家が基礎から最新の知識まで、わかりやすく解説。文系・理系問わず、すべての大学生に向けた新しい地学テキスト! ▼現代人に必須の教養書 身の周りの景観や気象、防災、環境問題、そして日進月歩で解明されつつある宇宙の姿まで、地学は実に幅広く魅力的な学問です。 本書は固体地球、大気海洋、天文の3部構成で、それぞれの専門家が基礎から最新の知識まで、わかりやすく解説します。 地球と人間の関係から生じる多様な問題に対し、科学的な事実を踏まえて取り組む能力を身につけましょう。 文系・理系問わず、すべての大学生に向けた新しい地学テキスト! はじめに 第1部 活動する地球の姿 1.地球の概観と内部構造 1-1. 地球の認識 1-2. 地球の大きさの計測 1-3. 地球の精密な形 1-4. ジオイドとGPS測量 1-5. 地球の内部構造を探る 1-6. 地殻とマントル 1-7. 地殻の厚さの分布 1-8. アセノスフェアとリソスフェア 1-9. 地磁気 コラム 残留磁気と松山基範 2.プレートテクトニクス 2-1. プレート理論の誕生 2-2. プレート境界 2-3. プレート運動の原動力とプルームテクトニクス 3.地震と地震災害 3-1. 地震という現象 3-2. 地震発生のしくみ 3-3. 地震学の勃興と発展(昭和南海地震まで) 3-4. 空白域とアスペリティ(2011年まで) 3-5. 東日本大震災と南海トラフ巨大地震(2011年以降) 3-6. 地震災害と防災 コラム 稲むらの火と津波てんでんこ 4.岩石と鉱物 4-1. 岩石をつくる鉱物の特徴と分類 4-2. ケイ酸塩鉱物 4-3. 固溶体 4-4. 火成岩の分類 4-5. 堆積岩と変成岩 5.マグマと火山 5-1. 火山の噴火と火山の姿 5-2. 火山の分布とマグマの成因 5-3. 沈み込み帯におけるマグマの成因 5-4. マグマの多様化 5-5. 花こう岩の謎 6.地形と地層の成り立ち 6-1. 地球内部エネルギーがもたらす地表の景観 6-2. 太陽エネルギーがもたらす地表の景観 6-3. 二つのエネルギーの相互作用による地形 6-4. 海面の上下変動と氷期・間氷期 6-5. 堆積物と地層 6-6. 地質時代区分 6-7. 放射年代測定法 コラム 氷床コアが保存する過去の気温変動 7.地球の生命の歴史 7-1. 地球の誕生(46億~40億年前:冥王代) 7-2. 生命の誕生(40億~35億年前:太古代前期) 7-3. 光合成生物の登場と地球環境の激変(35億~25億年前:太古 代) 7-4. 動物・植物の登場と繁栄(25億~7.3億年前:原生代) 7-5. 全球凍結事変(7.3億~6.3億年前:原生代) 7-6. 生物の爆発的な繁栄(6.3億~4.4億年前:原生代末~古生代前 期) 7-7. 生物の陸上進出と大量絶滅事変(4.4億~2.5億年前:古生代中 期~後期) 7-8. 恐竜など爬虫類の繁栄(2.5億~6600万年前:中生代) 7-9. 白亜紀末の大量絶滅事変(6600万年前:中生代末) 7-10. 寒冷化する地球と人類(6600万年前~現在:新生代) 8.人間社会と地球の関わり 8-1. 地下資源の分類 8-2. 鉱床の形成 8-3. レアメタルの特性 8-4. リサイクルと都市鉱山 8-5. エネルギー資源の形成 8-6. 地球上で人間が暮らすということ 第2部 地球をめぐる大気と海洋 1.大気の構造 1-1. 気体の性質 1-2. 大気の組成 1-3. 気圧と層構造 コラム オーロラの発生のしくみ 2.雲と降水 2-1. 安定、不安定、中立の概念 2-2. 潜熱と湿潤断熱減率 2-3. 雲の形成 2-4. 降水のしくみ 3.地球の熱収支 3-1. 熱放射 3-2. 短波放射 3-3. 赤外放射 3-4. 温室効果 コラム 惑星などの放射平衡温度 4.大気の運動 4-1. ニュートン力学 4-2. 風の要因 4-3. コリオリ力 4-4. 風の力のバランス 4-5. ハドレー循環と偏西風 4-6. 傾圧不安定とフェレル循環 5.海洋の構造 5-1. 海水の組成 5-2. 海洋の層構造 5-3. 海水の振動 6.海洋の大循環 6-1. 風成循環 6-2. エクマン輸送 6-3. 西岸強化 6-4. 深層循環 コラム ホッケ柱 7.大気と海洋の相互作用 7-1. 世界の気候と日本 7-2. 日本の四季 7-3. エルニーニョと北極振動 7-4. 物質循環 8.大気・海洋と人間 8-1. 天気予報 8-2. 気象災害 8-3. 気候変動と地球温暖化 8-4. 環境問題 8-5. 持続可能性 第3部 地球を取り巻く天体と宇宙 1.天体の運動と暦 1-1. 地球の運動と1日 1-2. 均時差 1-3. 天体の位置の表し方(赤道座標) 1-4. 年周運動と暦 1-5. 月とひと月 1-6. 天体の運動と時間単位 1-7. 地球自転の証明 1-8. 地球公転の証明 コラム 年周視差をめぐるタイムレース 2.惑星の運動と宇宙観の変遷 2-1. 惑星の運動 2-2. 惑星現象 2-3. 宇宙観の変遷とケプラーの法則 2-4. ケプラーの法則 2-5. 調和の法則から惑星の軌道半径を知る 2-6. 1天文単位の決定 2-7. 地球を1円玉の大きさに縮小すると 2-8. 調和の法則の証明 3.太陽系の姿と惑星探査 3-1. 太陽系の形成 3-2. 太陽系の天体 3-3. 太陽系生命圏 3-4. 系外惑星 コラム 太陽系外からの来訪者 4.恒星としての太陽 4-1. 核融合反応 4-2. 太陽の構造 4-3. 太陽活動と地球 コラム 地上の星 核融合炉 5.恒 星 5-1. 恒星までの距離 5-2. 恒星までの明るさ 5-3. 恒星のスペクトル 5-4. フラウンホーファー線と恒星のスペクトル型 5-5. HR図 5-6. 恒星の進化 コラム ベルのパルサー発見 6.宇宙の距離はしご 6-1. ケプラーの第3法則の利用 6-2. 年周視差の利用 6-3. HR図の利用 6-4. セファイド 6-5. ハッブル・ルメートルの法則 6-6. Ⅰa型超新星 コラム 聴覚障がい者が活躍したセファイド研究 7.最新探査が描く宇宙の姿 7-1. 銀河の姿 7-2. 銀河系の周辺 7-3. 宇宙の大規模構造 7-4. 見ることのできる宇宙の果て 7-5. WMAP衛星の活躍 7-6. 私たちは星の子 コラム 重力波とブラックホール、そしてマルチメッセンジャー天文 学 索引
過去の津波の実態を解き明かす鍵=津波堆積物を扱った最初の体系書.地震と津波の基礎,津波による侵食・堆積過程から,具体的な調査法・同定法,そして津波の規模の復元にいたるまで,具体的な事例を基に丁寧に解説する.古地震学・堆積学研究者だけでなく広く防災・土地計画関係者にも必携の書. はじめに 1 津波堆積物とは 1.1 津波堆積物とは何か 1.2 津波堆積物の形成と保存 1.3 イベント堆積物としての津波堆積物 1.4 津波堆積物の研究が注目されるようになったわけ コラム1 津波の観測 第1章引用文献 2 津波堆積物の研究史 2.1 1980年代以前 2.2 1983年日本海中部地震以降 2.3 2004年インド洋大津波以降 2.4 2011年東北沖津波以降 第2章引用文献 3 地震と津波 3.1 海溝型地震と津波 3.2 津波による災害 第3章引用文献 4 津波による侵食と堆積 4.1 津波による侵食 4.2 津波による堆積 4.3 津波が作るベッドフォーム 4.4 津波堆積物の地層への保存 4.5 津波堆積物の発掘と古地震・津波研究 コラム2 堆積構造から古流向を復元する コラム3 流れの停滞と再開—マッドドレイプはなぜ保存されるか 第4章引用文献 5 津波堆積物の調査 5.1 調査地の選定 5.2 古津波堆積物の観察 5.3 津波堆積物を識別する指標 5.4 津波堆積物の識別 コラム4 地層の剥ぎ取り試料 第5章引用文献 6 さまざまな津波堆積物 6.1 火山噴火による津波堆積物 6.2 津波石 6.3 生物遺骸の集積からなる津波堆積物 6.4 縄文時代の内湾(溺れ谷)に堆積した津波堆積物 6.5 海底地すべりによる津波堆積物 6.6 1495年明応関東地震を示唆する津波堆積物 コラム5 恐竜は超巨大津波を見たか? 第6章引用文献 7 津波の古生物 7.1 津波による貝類の打ち上げと集積 7.2 沼層の津波堆積物に含まれる貝類群集 7.3 津波堆積物中の微化石 コラム6 津波で形成された化石層 第7章引用文献 8 津波による堆積モデル 8.1 垂直方向のモデル−津波の波形に注目する 8.2 海−陸方向のモデル 8.3 水底の津波堆積物 8.4 湾内での水平変化 8.5 似て非なる堆積物 第8章引用文献 9 津波の規模の復元 9.1 津波の高さなどの定義 9.2 古津波の規模を推定する コラム7 津波堆積物の層厚は津波規模を表すか?−元禄と大正の関東地震による津波堆積物の例 第9章引用文献 10 津波堆積物研究の今後 10.1 分布と年代に関するデータの整備 10.2 津波堆積物の識別 10.3 最大クラスの地震・津波 10.4 より正確な震源や地震規模の復元へ向けて 第10章引用文献 推薦図書 索引
生命の星地球の137億年の軌跡と、それを解き明かしてきた科学探偵の物語。上巻は宇宙の誕生から生命入植以前の地球の進化を扱う。 さまざまな生命を育む地球は,どのようにして生まれ,現在の豊かな環境を作り出したのだろうか? ビッグバンによる宇宙の創生から,太陽系の誕生,地球の進化,人類文明の台頭に至るまで137億年の地球の歩みと、それを解き明かそうとする科学者たちの挑戦を綴る壮大な物語。上巻は宇宙の誕生から生命入植以前の地球の進化を扱う。 著者まえがき 訳者まえがき 選書版刊行にあたって 第1章 序論 自然システムとしての地球と生命 はじめに 科学的還元主義の力と限界 カオス 「システム」 「自然システム」の特徴 自然システムは平衡状態ではない 自然システムは外部のエネルギー源によって維持される 「非平衡定常状態」はフィードバックと循環によって維持される まとめ 参考図書 第2 章 背景 ビッグバンと銀河の形成 はじめに ビッグバン 赤方偏移:速度を測る 距離を測る 速度— 距離の関係:始まりの年代を定める ビッグバン仮説に対するさらなる証拠 膨張する宇宙とダークエネルギー ビッグバン直後の時期 まとめ 参考図書 第3章 原材料 恒星の元素合成 はじめに 太陽の化学組成 水素,ヘリウム,銀河,恒星 記述的原子物理学 ビッグバンの間の元素合成 恒星内元素合成 中性子捕獲による元素合成 恒星の元素合成仮説を支持する証拠 まとめ 参考図書 第4章 予備加工 有機分子と無機分子の合成 はじめに 分子 物質の状態 揮発性 密度 分子の二大グループ:無機分子と有機分子 鉱物 有機分子 分子合成の環境 まとめ 第5章 重量構造物 太陽系星雲から惑星と衛星をつくる はじめに 惑星の重要な統計 惑星の質量 惑星の密度 惑星の組成 隕石からの証拠 太陽系形成のシナリオ 地球型惑星の化学組成を理解する まとめ 参考図書 第6章 スケジュール 放射性核種によるタイムスケールの定量 はじめに 放射性崩壊を用いる年代測定 Column 地球の年齢に関する19世紀の議論 アイソクロン法による放射年代測定 コンドライト隕石と地球の年齢 元素の年齢 消滅放射性核種を用いた太古の短寿命過程の解明 26Alと太陽系星雲付近の超新星の存在 まとめ 参考図書 第7章 内装工事 コア,マントル,地殻,海洋,大気の分離 はじめに 地球の構造 地球の層の化学組成 元素の化学的親和性 地球の層の起源 マントルからコアの分離 コア形成の時期 地殻の起源 Column 岩石の融解 大気と海洋の起源 まとめ 第8章 近くの天体と争う 衛星,小惑星,彗星,衝突 はじめに 太陽系の天体の多様性 月の起源 衝突を用いて惑星表面の年代を決定する 月の内部構造の形成 太陽系における衝突の歴史 地球への影響 将来の衝突 まとめ 参考図書 第9章 環境を快適にする 流水,温度制御,日よけ はじめに 惑星の揮発性物質の収支 40億年前の水の証拠 安定同位体の分別 表面の揮発性物質の制御 宇宙への大気の散逸 地球の表面と内部の間の揮発性物質の循環 表面温度 地球の長期のサーモスタット 金星に学ぶ スノーボールアース 日よけ まとめ 参考図書 第10章 循環を確立する プレートテクトニクス はじめに 静的な地球という観点 大陸移動説 海洋底からの新しいデータ 古地磁気からの証拠 地震活動度の全球分布 プレートテクトニクス理論 プレートテクトニクス革命 時間を通した運動 まとめ 参考図書 第11章 内部の循環 マントル対流とその表面との関係 はじめに 地球内部の動き 地球の地形とマントルの流動 マントル対流 マントルは対流するか? プレートの形状はマントルの対流セルに対応しているか? マントルの能動的上昇流:プルームの頭と尾 拡大中心における海洋地殻の生成 まとめ 参考図書 第12章 層と層を結びつける 固体の地球,液体の海,気体の大気 はじめに 全球的システムとしての海嶺 拡大中心での熱水循環 海嶺と生存可能性 海水組成の謎 沈み込み帯への元素の輸送 収束境界における地球化学過程 収束境界での融解と火山活動の原因 大陸地殻への元素の輸送 プレート再循環の最終結果 まとめ 参考図書
生命の星地球の137億年の軌跡と、それを解き明かしてきた科学探偵の物語。下巻は地球上に生命が誕生して以降の劇的な変化を扱う。 地球上にひしめく様々な生物は,どこから来たのか? 地球と同じような「生命の惑星」は他にも存在するのだろうか? 宇宙の創世以来137億年の地球の歩みと,それを解き明かそうとする科学者たちの奮闘とともに綴る物語。下巻では,生命を可能にした惑星条件の謎と,地球上に生命が誕生して以降の劇的な変化を扱う。地球の舵をとった人類は,この惑星をどこに導くのか。 第13章 表面に入植する 惑星過程としての生命の起源 はじめに 生命と宇宙 生命の単一性 生命は細胞である すべての生物は同じ種類の分子を用いる すべての生物は同じ化学マシンを用いる 最初の生命 生命はいつ始まったのか? 生命の起源 生命に至る道程 元素と簡単な構築ブロック分子 必須の生物化学原料をつくる 複雑な分子をつくる 細胞の容器 ミッシングリンク 生命の起源に関する一般的考察 まとめ 参考図書 第14章 競争を生き抜く 生物多様性の創造における進化と絶滅の役割 はじめに 岩石記録からあきらかにされた生命と地球の歴史 化石と現在の生命を結びつける:進化論 DNA革命 Column 言語の進化 進化の半面としての絶滅 まとめ 参考図書 第15章 表面にエネルギーを与える 生命と惑星の共進化による惑星燃料電池の形成 はじめに 電流としての生命 還元的な初期地球 最初の3つのエネルギー革命 惑星の燃料電池 まとめ 第16章 エクステリアの改装 惑星表面の酸化の記録 はじめに 地球と酸素 炭素:酸素生産の記録 炭素:岩石記録からの証拠 鉄と硫黄:酸素消費の記録 鉄:岩石記録の証拠 硫黄:岩石記録の証拠 顕生代の高い酸素濃度の証拠 20億年前から6億年前までの酸素 酸素の全球収支 まとめ 参考図書 第17章 惑星の進化 破局的事変の重要性と定向進化の問題 はじめに 顕生代の惑星進化 絶滅事変の原因 白亜紀— 第三紀境界の絶滅 ペルム紀— 三畳紀境界の絶滅 プレートテクトニクスと進化 惑星進化の原理とは? 関係と複雑さの増加 時間にともなうエネルギー利用の変化 定向進化の可能性に関する考察 生存可能性の進化 まとめ 参考図書 第18章 気候に対処する 自然の気候変動の原因と結果 はじめに 中期間の気候変動:氷河期 軌道周期 急激な気候変動 海洋のベルトコンベア 人類の衝撃 まとめ 参考図書 第19章 ホモ・サピエンスの興隆 地球の資源を利用した惑星支配 はじめに 人類時代の夜明け 人類のエネルギー革命 地球の宝箱 資源の分類 リサイクル時間が短い資源:空気と水 リサイクルの可能性があるばく大な資源:金属 リサイクルできない有限の資源 化石燃料 土壌 生物多様性 まとめ 第20章 舵を取る人類 惑星の文脈における人類文明 はじめに 地球に対する人類の衝撃 気候 海洋酸性化 生物多様性 将来の予測 歴史的視点から見た将来 可能な解決策 温室効果ガスの蓄積を解決する 太陽,風,および原子のエネルギー 二酸化炭素の捕集と貯留 深海貯留 極地の氷床への貯留 堆積層深部への貯留 炭酸マグネシウムへの変換 より広範な問題 人類代? まとめ 参考図書 第21章 私たちはひとりぼっちか? 宇宙の生存可能性についての疑問 はじめに 比較惑星学:金星と火星に学ぶ 惑星探査 ケプラーからの新しい結果 銀河系の生存可能な惑星の数:確率論アプローチ 惑星の文脈における人類文明:宇宙の進化と生命 まとめ 参考図書 用語集 索 引
本書は、美しいカラー写真で約250種の鉱物・宝石を紹介し、基礎データに加えて採集方法、クリーニング、観察・分類、標本作り、保管、展示のテクニックを詳しく解説しています。著者は、京都大学教授の下林典正氏と、益富地学会館の研究員石橋隆氏で、両者は鉱物研究や教育普及に積極的に取り組んでいます。
本書は、鉱物学の基本原理や地球科学的な考え方を、他分野の人々にも理解できるように解説している。鉱物学は古くから体系化された学問であり、新しい結晶学や無機化学の発展にも寄与している。