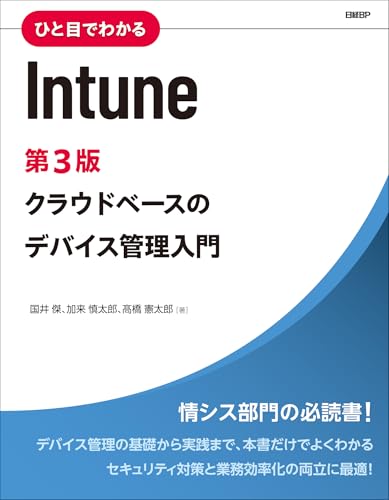【2025年】「基本情報技術者」のおすすめ 本 114選!人気ランキング
- 令和04年 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室 (情報処理技術者試験)
- 令和05年 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室 (情報処理技術者試験)
- キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 令和07年
- キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 令和05年
- 令和07年 基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集
- キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 令和03年
- ニュースペックテキスト 基本情報技術者 2023年度 [科目A 科目B 一冊でしっかり対策!](TAC出版)
- 令和07年 イメージ&クレバー方式でよくわかる かやのき先生の基本情報技術者教室
- 令和05年【下期】基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集
- ニュースペックテキスト 基本情報技術者 2024年度 [シラバスver.8.1 対応](TAC出版)
この参考書は、基本情報技術者試験合格を目指す人向けのオールインワンタイプの教材で、最新の出題傾向に基づいて重要ポイントをイラストや図解を用いてわかりやすく説明しています。令和04年版はシラバス7.2に完全対応し、試験対策や背景知識の提供も行っています。全問題には正解率が示されており、実力養成に役立ちます。さらに、スマホで読める「厳選英略語100暗記カード」が特典として付いています。著者はIT試験対策の講師経験を持つ栢木厚です。
「キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 令和07年」は、きたみりゅうじ氏による基本情報技術者試験対策の書籍で、全ての解説がイラストを用いて行われているため理解しやすい。専門的な知識が必要な試験に向けて、仕組みや用語に慣れることができる内容となっている。また、金子則彦氏による過去問の練習問題も収録されており、スマホやWebアプリでの問題演習が可能で、自己採点機能も備えている。最新のシラバスに対応し、独習や授業での使用にも適している。
この問題集は、2024年10月から適用される「シラバス9.0」に対応した基本情報技術者試験の対策書です。科目Aと科目Bの両方に焦点を当て、過去の出題分析に基づいた問題と解説を提供しています。科目Aでは頻出問題を厳選し、科目Bではアルゴリズムやプログラミングの解説を図解を交えて行っています。また、過去問題のPDFや問題演習Webアプリ、用語集などの特典も充実しており、試験対策に最適な内容となっています。
売上1位!基本情報技術者【科目B】対策の定番書!■本書の特徴・新試験体系【科目B】の新傾向に完全対応!・「擬似言語」「情報セキュリティ」の両分野とも掲載。・プログラム経験ゼロでも大丈夫。やさしく丁寧に解説。・前提知識+解き方+試験問題を掲載。効率よく学習できる。・付録として,計45問の解説PDFファイルをダウンロード提供。■目次第1部 擬似言語 第1章 文法 第2章 一次元配列 第3章 二次元配列 第4章 ありえない選択肢 第5章 再帰 第6章 木構造 第7章 オブジェクト指向 第8章 リスト 第9章 スタック・キュー 第10章 ビット列 第11章 問題演習第2部 情報セキュリティ 第1章 虎の巻 第2章 問題演習付録 解説PDFファイル サンプル問題・模擬問題など、計45問以上■基本情報技術者試験(FE)とは・経済産業省が行う国家試験「情報処理技術者試験」等(13試験)の中の1試験。・試験会場でコンピュータに向かって行うCBT方式で行われ,ほぼ毎日受験可能。・不合格でも1か月後に再受験可能。毎月約1万人が応募。合格率は40%台。・2023年から従来の「午前問題」は「科目A」に,「午後問題」は「科目B」に改定された。■[科目B]とは・擬似言語分野から16問(8割),情報セキュリティ分野から4問(2割)出題される。・100分間で20問出題される試験のため,1問あたりの解答時間はわずか5分。・科目Bの方が,科目Aよりも合格点に達しにくく難しい。科目Bが合否を分ける。・科目Bの擬似言語は,トレース力を問う試験問題が大半を占める。■傾向と対策は・擬似言語は,再帰・オブジェクト指向・ビット列など,プログラム経験者でも未経験の出題内容が多い。 →本書では,科目Bの新傾向にあわせて「トレース」という解法を徹底解説。・情報セキュリティは,従来の出題内容から大幅に改定。過去問題とは全くの別物。 →本書では,新傾向の出題内容をまとめた「虎の巻」でポイントを詳しく解説。 ■目次 第1部 擬似言語 第1章 文法 第2章 一次元配列 第3章 二次元配列 第4章 ありえない選択肢 第5章 再帰 第6章 木構造 第7章 オブジェクト指向 第8章 リスト 第9章 スタック・キュー 第10章 ビット列 第11章 問題演習第2部 情報セキュリティ 第1章 虎の巻 第2章 問題演習付録 解説PDFファイル サンプル問題・模擬問題など、計45問
本書は、基本情報技術者試験の午後試験における「アルゴリズム分野」を、文系初学者やプログラム未経験者向けに対話形式で解説しています。アルゴリズムの基本から応用まで、身近な例を用いて理解を深める内容で、擬似言語問題の攻略法や過去問演習も含まれています。また、解説動画やまとめページも充実しており、スキマ時間での学習にも適しています。著者はわかりやすい解説で定評があるコンピュータ系ライターです。
本書は、令和5年度からの新試験に対応した基本情報技術者向けの予想問題集です。科目B試験は擬似言語に統一され、過去問題がないため、オリジナルの問題を60問収録しています。科目A試験は出題内容に大きな変更はなく、過去問から再構成した3回分の問題も収録しています。問題には出題予測率が付いており、効率的に学習できるよう工夫されています。また、電子版やスマホ単語帳も利用可能です。
IT系資格の登竜門となる,基本情報技術者をめざす方のためのやさしいオールインワンタイプの参考書&問題集です。最新の傾向を分析し,出題頻度の高い分野を中心に,イラストや豊富な図解・例え話を駆使して理解しやすく・記憶に残りやすいように説明し,「〇〇とくれば××」方式で重要ポイントを再確認。さらに関連の本試験問題をすぐ解くことで,知識が定着し応用力もつきます。 令和03年版ではシラバス7.1に対応し,紙面をリニューアルし大幅増ページ。試験攻略のためのアドバイスや,背景を理解するための参考など新コーナーを増やしました。また,全問題に正解率を掲載し,実力養成を後押しします。 収録問題数は,令和の過去問含めたっぷり273問。無駄なく効率よく短時間で合格レベルに到達することができる,受験者必携の1冊です。 ■第1章 コンピュータ構成要素 1-01 情報の表現 1-02 コンピュータの構成 1-03 CPU 1-04 CPUの動作原理 1-05 CPUの高速化技術 1-06 半導体メモリ 1-07 補助記憶装置 1-08 入出力装置 1-09 入出力インタフェース ■第2章 ソフトウェアとマルチメディア 2-01 ソフトウェア 2-02 ジョブ管理とタスク管理 2-03 記憶管理 2-04 ファイル管理 2-05 マルチメディア ■第3章 基礎理論 3-01 基数変換 3-02 補数と固定小数点数 3-03 浮動小数点 3-04 誤差 3-05 シフト演算 3-06 論理演算 3-07 半加算器と全加算器 3-08 計測と制御 3-09 オートマトン 3-10 AI 3-11 線形代数 3-12 確率・統計 ■第4章 アルゴリズムとプログラミング 4-01 アルゴリズム 4-02 配列 4-03 リスト 4-04 キューとスタック 4-05 木構造 4-06 データの整列 4-07 データの探索 4-08 計算量 4-09 プログラムの属性 4-10 プログラム言語とマークアップ言語 ■第5章 システム構成要素 5-01 システム構成 5-02 クライアントサーバシステム 5-03 RAIDと信頼性設計 5-04 システムの性能評価 5-05 システムの信頼性評価 ■第6章 データベース技術 6-01 データベース 6-02 データベース設計 6-03 データの正規化 6-04 トランザクション処理 6-05 データベースの障害回復 6-06 データ操作とSQL 6-07 SQL(並べ替え・グループ化) 6-08 SQL(副問合せ) 6-09 データベースの応用 ■第7章 ネットワーク技術 7-01 ネットワーク方式 7-02 OSI基本参照モデルとTCP/IP 7-03 ネットワーク接続機器 7-04 IPアドレス 7-05 IPアドレスのクラス 7-06 ネットワーク管理 ■第8章 情報セキュリティ 8-01 情報セキュリティと情報セキュリティ管理 8-02 脅威とマルウェア 8-03 サイバー攻撃 8-04 暗号技術 8-05 ネットワークセキュリティ ■第9章 システム開発技術 9-01 情報システム戦略とシステム企画 9-02 ソフトウェア開発 9-03 業務モデリング 9-04 ヒューマンインタフェース 9-05 モジュール分割 9-06 オブジェクト指向 9-07 テスト手法 ■第10章 マネジメント系 10-01 プロジェクトマネジメント 10-02 工程管理 10-03 ITサービスマネジメント 10-04 システム監査 ■第11章 ストラテジ系 11-01 ソリューションビジネスとシステム活用促進 11-02 経営組織と経営・マーケティング戦略 11-03 業績評価と経営管理システム 11-04 技術開発戦略 11-05 ビジネスインダストリ 11-06 品質管理手法 11-07 会計・財務 11-08 知的財産権とセキュリティ関連法規 11-09 労働・取引関連法規と標準化 11-10 オペレーションリサーチ
本文オールカラー刷りならではの新学習機能をわんさか搭載! 午後試験にもしっかり対応! 本試験で狙われる論点を、新学習機能によって効率よくマスターすることができる基本テキストです。午後の出題範囲・配点の変更にもシッカリ対応。よりパワーアップしました。 気になる「CBT方式」対策法も掲載しています。 ★学習と試験対策の手引き 巻頭の「スタートアップ講座」で、学習の道筋から本試験の攻略法までをガイダンス。情報満載の目次でどこに何が載っているか、ひと目でわかる! 目的意識を持って学習を効率的に進めることができます。 ★インプットしやすい 午前試験対策と午後試験対策で解説方法を分けました。 →午前対策:側注つきレイアウト。実戦知識をすっきり解説。 →午後対策:一段組みレイアウト。“専用ページ”を設けしっかり解説。 ★イメージしやすい 見てすぐ理解につながるカラー図解と本試験に直結した色別の側注。 →図解は、考え方のプロセスを覚えやすいよう、彩色しています。 →知っていればよい知識は表組みにまとめました。 →側注でも、頻出論点を、重要度で色分けし、解説しています。 ★アウトプットもできる →章末問題(午前対策)と本文:午後対策頁で取り上げた午後問題を全文掲載。実践力を磨くことができます。 ★午前だけでなく午後試験にもしっかり対応 →午後試験では「各種プログラム言語または表計算」計5問から1問を選択して解答しなくてはなりませんが、類書も含め従来の基本テキストではほとんど解説がなく、基本書として不親切でした。そこで本書ではもっとも解答者が多い「表計算」対策の章を設けてあります。1冊で午前・午後両方の試験に対応しています。
本書は、基本情報技術者試験の午後問題に特化した問題集で、CBT試験にも対応しています。近年の出題傾向を反映した頻出問題をテーマ別に収録し、丁寧な解説を提供。受験者が苦手分野を集中して対策できるように工夫されており、試験の時間配分を考慮した速読・解答テクニックも含まれています。内容は情報セキュリティ、ハードウェア、ソフトウェア、データベース、ネットワーク、ソフトウェア設計、マネジメント、ストラテジ系、アルゴリズムの各章に分かれています。著者はシステムエンジニアであり、教育支援や企業向け研修を行っています。
基本情報技術者試験、午後問題を完全対策! 本書は、基本情報技術者試験のうち、「午後問題」に的を絞ったテーマ別頻出問題集です。 令和02年試験からの出題数/配点変更にともない、より重要となったテーマの問題数をアップ。 手厚く対策でき、合格へと着実に近づくことができます! ●本書の特徴 ・近年の出題傾向を踏まえて、よくでる問題を厳選収録 ・頻出問題をテーマ別に掲載。苦手な分野を集中対策できる ・設問ごとのていねいな解説で、解き方がしっかりわかる ・単なる解き方だけでなく、各設問の技術的な背景もわかりやすく解説 ・試験の時間配分を考慮した速読&解答テクニックも掲載 ■受験ガイダンス 「基本情報技術者」試験とは? 午後試験では何が出題される? 午後問題の速読テクニック アルゴリズム問題の解き方 例題を使い、アルゴリズム問題を解いてみよう! 合格したら、上位試験に挑戦! ■第1章 情報セキュリティ 01 VPNとVDIによるセキュリティ対策 02 利用者認証 03 攻撃と防御 04 パスワード管理 05 SSHを利用した通信 06 情報漏えい対策 07 ネットワークのセキュリティ対策 08 ログ管理 ■第2章 ハードウェア 01 論理回路 02 A/D変換と割込み 03 浮動小数点数 04 機械語命令 ■第3章 ソフトウェア 01 仮想記憶方式 02 タスク管理 03 コンパイラの機能 04 リスト構造 ■第4章 データベース 01 関係データベースの設計と運用 02 データベースのデータ抽出 03 派生表とビュー表 04 SQL-DDLと制約 05 データベースの運用 ■第5章 ネットワーク 01 セッション管理 02 ネットワークの障害対策 03 無線LANのデータ送信 04 イーサネットを介した通信 05 インターネットプロトコル ■第6章 ソフトウェア設計 01 WebAPI 02 マスタファイルの参照 03 コントロールブレイク処理 04 シーケンス図による設計 05 決定表による設計 ■第7章 マネジメント 01 プロジェクトの時間 プロジェクト管理手法 02 プロジェクトの資源 工数と要員数 03 プロジェクトのリスク リスクの特定と評価 04 プロジェクトの時間 進捗管理 ■第8章 ストラテジ 01 システム戦略 システムの統合 02 システム戦略 在庫量の削減 03 経営戦略・企業と法務 財務諸表の分析 04 経営戦略・企業と法務 業務改善の効果 ■第9章 アルゴリズム 01 文字列検索 02 文字列圧縮 03 意味解析処理 04 配列と文字列探索 05 最短経路の探索 06 配列と関数の処理 07 文字列の照合 08 整列アルゴリズム 09 グラフの最短距離
基本情報「午後」対策のベストセラーの改訂版! 【こんな方のための本です】 ・試験間際で焦っている人 ・学習時間をなかなか取れない人 ・直前対策・要点整理をしたい人 【本書のポイント】 ・「出る順」で「出るところだけ」掲載。短時間で得点力がグンと上がる。 ・合格するためにテーマを16に厳選。これだけやれば大丈夫! ・前提知識+解き方+過去問題を丁寧に解説。 ・新シラバスに完全対応。 ・今回の改訂により配点増となる「擬似言語」「情報セキュリティ」を手厚く解説。 【本書で「午後」試験を学習するとよい理由】 ・午後試験の合格率は午前試験に比べて低く、午後試験は合格・不合格の分かれ目になる。 →午前試験とは異なる「午後に特化した学習」が必要 ・午後試験の過去問は、午前試験と異なり再出題されることはほぼない。 →過去問だけの学習では非効率。 →過去問の「解き方」にこだわった学習をし、類題を解けるようにしている。 →新しく見える問題にも対応できる力がつく。 ・試験範囲が広く、どこまで学習するか迷う。 →非常に長い期間の過去問を分析し、「出るとこだけ」のテーマ・内容に厳選。 基本情報技術者試験とは 学習法 出る順 分野別傾向分析 本書の構成 長文問題の対策 トピックス|なぜ同じテーマを再出題? 出る順1位 SQL1 結合 内部結合 SELECT こう解く|結合条件式1 こう解く|結合条件式2 左外部結合 右外部結合 集合関数 COUNTとSUMの違い COUNTの種類 こう解く|集合関数の入れ子 日付 MAXを使った表現 GROU PBY こう解く|GROUP BY GROUP BYとDISTINCT GROUP BYと集計結果 HAVING GROUP BYとHAVING こう解く|HAVING こう解く|HAVINGとWHERE 練習問題 出る順2位 SQL2 副問合せ IN ANY =(副問合せ)と=IN(副問合せ) ビュー AND・OR ORDER BY ワイルドカード BETWEEN 練習問題 出る順3位 暗号と認証 公開鍵暗号方式 ハイブリッド暗号 ハッシュ関数 ディジタル署名 ディジタル署名と暗号化 公開鍵基盤 練習問題 出る順4位 文字列処理1 文字列処理 擬似言語 条件式 選択処理 繰返し処理 こう解く|トレース for 配列 関数 見落としがちな文法 こう解く|問題文・プログラム・表の対応付け 練習問題 出る順5位 文字列処理2 比較演算子 こう解く|条件の変換 こう解く|当てはめ法 こう解く|境界値検査 練習問題 出る順6位 文字列処理3 ありえない選択肢 こう解く|無限ループは不正解 こう解く|連続格納は不正解 練習問題 出る順7位 情報セキュリティ対策 ファイアウォール DMZ プロキシサーバ リバースプロキシ その他の情報セキュリティ製品 練習問題 出る順8位 データベース設計 データベース設計 列設計 正規化 こう解く|正規化と整合性 こう解く|正規化の決まり文句 練習問題1 練習問題2 出る順9位 ネットワークセキュリティ プロトコル 電子メールのプロトコル セキュアプロトコル その他のプロトコル 送信側の迷惑メール対策 受信側の迷惑メール対策 メールによる被害への対策 練習問題 出る順10位 スケジュール管理 プロジェクトマネジメント スケジュール管理 こう解く|こせきの式 練習問題1 練習問題2 出る順11位 サイバー攻撃 パスワードクラック パスワードクラックへの対策 スクリプト攻撃 スクリプト攻撃への対策 標的型攻撃 標的型攻撃への対策 その他のサイバー攻撃 練習問題 出る順12位 浮動小数点数 浮動小数点数 正規化 こう解く|仮数と指数を調整する こう解く|ビットに格納する こう解く|ビットから取り出す 練習問題 出る順13位 機械語命令1 機械語 基数変換 機械語命令の構造 図 命令語の形式 表 記号の説明 こう解く|ビット分割 表 実効アドレスの算出方法 こう解く|実効アドレスの算出 表 命令の仕様 こう解く|機械語命令のトレース 練習問題 出る順14位 機械語命令2 機械語命令を実行する手順 機械語命令の種類 練習問題 出る順15位 オブジェクト指向設計 オブジェクト指向 UML クラス図 集約 多重度 こう解く|クラス図の多重度 汎化 練習問題1 練習問題2 出る順16位 決定表 決定表 条件の省略 練習問題
本書は、基本情報技術者試験の科目Bに特化したアルゴリズムと擬似言語のトレーニング本の改訂版です。16問のアルゴリズム問題を中心に、過去問やオリジナル問題を多数収録し、実践的なトレーニングを提供します。内容は、変数やデータ構造、擬似言語プログラミング、基本例題、応用例題、サンプル問題に分かれており、特にアルゴリズムに自信のない受験者におすすめです。著者はIT企業での経験を持つ教育者です。
◎どうしても午後問題が苦手で……とお悩みの方に,手にしていただきたい1冊です。 ◎ますます比重が高くなった必須問題の「情報セキュリティ」と「アルゴリズム」を詳細解説! ◎「情報セキュリティ」を丁寧に解説しています。2022年版では演習問題を増やしました! ◎「アルゴリズム」と聞いただけで諦めたくなっている方も,階段を一段一段上がるような感覚で理解できるようになります。 ◎テクノロジ系の選択問題,マネジメント系・ストラテジ系の選択問題についても,テーマごとの解説と演習問題を掲載しました。 ◎本書で重要ポイント,テクニックを身に付ければ本番でも動じない実力を養うことができ,合格がグッと近づきます。 必須問題の「情報セキュリティ」の演習問題の数を増やしました。 必須問題の「データ構造とアルゴリズム」も頁を割いて丁寧に解説しています。 この二つの分野は,合格のためには避けて通れません。 (プログラム言語のPythonには対応しておりません) 第1部 試験制度の解説 第1章 基本情報技術者試験の概要 第2章 基本情報技術者試験の出題範囲 第3章 午後問題の対策 第2部 情報セキュリティ(必須問題) 第1章 情報セキュリティ問題への取組み方 第2章 情報セキュリティ 第3部 知識の応用(テクノロジ系の選択問題) 第1章 ハードウェア 第2章 ソフトウェア 第3章 データベース 第4章 ネットワーク 第5章 ソフトウェア設計 第4部 知識の応用(マネジメント系・ストラテジ系の選択問題) 第1章 マネジメント系 第2章 ストラテジ系 第5部 データ構造とアルゴリズム(必須問題) 第1章 アルゴリズム問題への取組み方 第2章 擬似言語によるアルゴリズムの表記 第3章 基本アルゴリズム(整列・探索) 第4章 配列処理,文字列処理 第5章 アルゴリズムの解法力 第6部 演習問題 解答・解説
ご好評いただいている基本情報技術者試験の定番テキストの改訂版です。最新のシラバスVer.7.2(2021年10月26日発表)を圧倒的に網羅した内容で、試験範囲を体系的にしっかりと理解し合格を目指します。図解を豊富に使ったわかりやすい解説で学習を進め,随所に掲載された過去問からの例題や出題分析、そして章末問題でしっかりと知識を定着させて理解を深めることができます。体系立てた学習ができるため、独習にはもちろん、授業で使用するテキストとしても最適です。これから上位試験受験を目指す方の知識の土台づくりにもばっちりです。 読者特典として、スマホやPCから利用できる「問題演習Webアプリ」を提供。20回分の過去問題を収録し、いつでもどこでも問題演習が行えます。午前問題は間違えた問題のみを出題したり類似問題を出題したりできるため、苦手問題を繰り返し演習できます。自己採点機能により得意/不得意分野がひと目でわかり、苦手克服や直前対策に役立ちます。 ■■第1章 基礎理論 ■基礎理論 01 コンピュータで扱う「数」の工夫 02 2進数によるさまざまな数値の表現 03 シフト演算 04 集合と論理演算 05 確率と統計 06 その他の応用数学 07 情報に関する理論 08 通信に関する理論 09 計測・制御に関する理論 ■アルゴリズムとプログラミング 10 データ構造 11 アルゴリズムと流れ図 12 探索のアルゴリズム 13 整列のアルゴリズム 14 文字列処理のアルゴリズム 15 ファイル処理のアルゴリズム 16 再帰とプログラム構造 17 プログラミング 18 プログラム言語 19 マークアップ言語 【章末まとめ問題】 ■■第2章 コンピュータシステム ■コンピュータ構成要素 01 コンピュータの構成と動作 02 プロセッサの性能と高速化技術 03 メモリの種類と特徴 04 メモリシステムと記憶階層 05 バスと入出力インタフェース 06 入出力装置 07 補助記憶装置 ■システム構成要素 08 システムの処理形態 09 システム構成 10 システムの性能指標 11 システムの信頼性指標 ■ソフトウェア 12 オペレーティングシステムの種類と特徴 13 OSの役割と機能①-ジョブ管理とタスク管理 14 多重プログラミングと割込み 15 OSの役割と機能②-記憶管理 16 OSの役割と機能③-データの管理とファイルシステム 17 開発支援ツール 18 言語処理ツール 19 オープンソースソフトウェア ■ハードウェア 20 ハードウェアと論理回路 【章末まとめ問題】 ■■第3章 技術要素 ■ヒューマンインタフェース 01 ヒューマンインタフェース ■マルチメディア 02 マルチメディア技術 ■データベース 03 データベース方式 04 データベース設計 05 データベースの操作 06 トランザクション処理 07 データベースの応用 【章末まとめ問題】その① ヒューマンインタフェース/マルチメディア/データベース ■ネットワーク 08 ネットワーク方式 09 ネットワークアーキテクチャ 10 通信プロトコル 11 IPアドレスの役割と機能 12 ネットワーク管理 13 電子メールとネットワークサービス 【章末まとめ問題】その② ネットワーク ■セキュリティ 14 情報セキュリティ 15 暗号技術 16 利用者認証 17 情報セキュリティ管理とセキュリティ技術評価 18 情報セキュリティ対策 19 セキュリティの実装技術 【章末まとめ問題】その③ セキュリティ ■■第4章 開発技術 ■システム開発技術 01 システム開発のプロセス 02 業務分析や要件定義に用いられる手法 03 構造化設計に用いられる手法 04 オブジェクト指向設計 05 モジュール設計 06 コーディングとモジュールテスト 07 システム統合テストとソフトウェア統合テスト 08 導入と受入れ支援および保守・廃棄 ■ソフトウェア開発管理技術 09 ソフトウェアの開発手法 10 システム開発に伴うさまざまな管理 【章末まとめ問題】 ■■第5章 プロジェクトマネジメント ■プロジェクトマネジメント 01 プロジェクトマネジメントの全体像 02 プロジェクトのスコープ 03 プロジェクトの時間 04 プロジェクトのコスト 05 プロジェクトの品質 06 多角的に管理するその他の対象群 【章末まとめ問題】 ■■第6章 サービスマネジメント ■サービスマネジメント 01 サービスマネジメント ■システム監査 02 システム監査と内部統制 【章末まとめ問題】 ■■第7章 システム戦略 ■システム戦略 01 情報システム戦略と業務プロセス 02 ソリューションビジネス 03 システム活用促進・評価 ■システム企画 04 システム企画 【章末まとめ問題】 ■■第8章 経営戦略 ■経営戦略マネジメント/技術戦略マネジメント 01 経営戦略 02 経営分析の手法 03 マーケティング 04 ビジネス戦略と技術開発戦略 ■技術戦略マネジメント 05 技術開発戦略 ■ビジネスインダストリ 06 ビジネスシステムとエンジニアリングシステム 07 e-ビジネス 08 民生機器と産業機器 【章末まとめ問題】 ■■第9章 企業と法務 ■企業活動 01 企業活動と組織 02 OR・IEと業務分析 03 品質管理とQC七つ道具 04 企業会計と財務 ■法務 05 企業が関わる法務 06 セキュリティに関する法規とガイドライン 07 企業の責任と標準化 【章末まとめ問題】 ■■付録 ■CBT試験の受験テクニック ■計算問題の実践演習
ご好評いただいている基本情報技術者試験の定番テキストの改訂版です。最新のシラバスVer.8.1(2023年8月1日発表)を圧倒的に網羅した内容で、試験範囲を体系的にしっかりと理解し合格を目指します。図解を豊富に使ったわかりやすい解説で学習を進め,随所に掲載された過去問からの例題や出題分析、そして章末問題でしっかりと知識を定着させて理解を深めることができます。体系立てた学習ができるため、独習にはもちろん、授業で使用するテキストとしても最適です。これから上位試験受験を目指す方の知識の土台づくりにもばっちりです。今年度版では、付録として科目B対策となる擬似言語の攻略もまとめてあります。また、読者特典として、スマホやPCから利用できる「問題演習Webアプリ」を提供。平成22年春期~令和元年秋期までの20回分の午前過去問題(科目A問題に該当)および、科目A・科目Bの公開サンプル問題を収録し、いつでもどこでも問題演習が行えます。間違えた問題のみを出題したり分野を選択して出題したりできるため、苦手分野を集中的に演習できます。自己採点機能により得意/不得意分野がひと目でわかり、苦手克服や直前対策に役立ちます。 ■■「基本情報技術者」試験 受験ガイダンス ■■CBT試験の攻略法 ■■第1章 基礎理論 ■基礎理論 01 コンピュータで扱う「数」の工夫 02 2進数によるさまざまな数値の表現 03 シフト演算 04 集合と論理演算 05 確率と統計 06 その他の応用数学 07 情報に関する理論 08 通信に関する理論 09 計測・制御に関する理論 ■アルゴリズムとプログラミング 10 データ構造 11 アルゴリズムと擬似言語 12 探索のアルゴリズム 13 整列のアルゴリズム 14 文字列処理のアルゴリズム 15 ファイル処理のアルゴリズム 16 再帰とプログラム構造 17 プログラミング 18 プログラム言語 19 マークアップ言語 【章末まとめ問題】 ■■第2章 コンピュータシステム ■コンピュータ構成要素 01 コンピュータの構成と動作 02 プロセッサの性能と高速化技術 03 メモリの種類と特徴 04 メモリシステムと記憶階層 05 バスと入出力インタフェース 06 入出力装置 07 補助記憶装置 ■システム構成要素 08 システムの処理形態 09 システム構成 10 システムの性能指標 11 システムの信頼性指標 ■ソフトウェア 12 オペレーティングシステムの種類と特徴 13 OSの役割と機能①-ジョブ管理とタスク管理 14 多重プログラミングと割込み 15 OSの役割と機能②-記憶管理 16 OSの役割と機能③-データの管理とファイルシステム 17 開発支援ツール 18 言語処理ツール 19 オープンソースソフトウェア ■ハードウェア 20 ハードウェアと論理回路 【章末まとめ問題】 ■■第3章 技術要素 ■ヒューマンインタフェース 01 ヒューマンインタフェース ■マルチメディア 02 マルチメディア技術 ■データベース 03 データベース方式 04 データベース設計 05 データベースの操作 06 トランザクション処理 07 データベースの応用 【章末まとめ問題】その① ヒューマンインタフェース/マルチメディア/データベース ■ネットワーク 08 ネットワーク方式とデータ制御 09 ネットワークアーキテクチャ 10 通信プロトコル 11 IPアドレスの役割と機能 12 ネットワーク管理 13 電子メールとネットワークサービス 【章末まとめ問題】その② ネットワーク ■セキュリティ 14 情報セキュリティ 15 暗号技術 16 利用者認証 17 情報セキュリティ管理とセキュリティ技術評価 18 情報セキュリティ対策 19 セキュリティの実装技術 【章末まとめ問題】その③ セキュリティ ■■第4章 開発技術 ■システム開発技術 01 システム開発のプロセス 02 業務分析や要件定義に用いられる手法 03 構造化設計に用いられる手法 04 オブジェクト指向設計 05 モジュール設計 06 コーディングとモジュールテスト 07 システム統合テストとソフトウェア統合テスト 08 導入と受入れ支援および保守・廃棄 ■ソフトウェア開発管理技術 09 ソフトウェアの開発手法 10 システム開発に伴うさまざまな管理 【章末まとめ問題】 ■■第5章 プロジェクトマネジメント ■プロジェクトマネジメント 01 プロジェクトマネジメントの全体像 02 プロジェクトのスコープ 03 プロジェクトの時間 04 プロジェクトのコスト 05 プロジェクトの品質 06 多角的に管理するその他の対象群 【章末まとめ問題】 ■■第6章 サービスマネジメント ■サービスマネジメント 01 サービスマネジメント ■システム監査 02 システム監査と内部統制 【章末まとめ問題】 ■■第7章 システム戦略 ■システム戦略 01 情報システム戦略と業務プロセス 02 ソリューションビジネス 03 システム活用促進・評価 ■システム企画 04 システム企画 【章末まとめ問題】 ■■第8章 経営戦略 ■経営戦略マネジメント/技術戦略マネジメント 01 経営戦略 02 経営分析の手法 03 マーケティング 04 ビジネス戦略と技術開発戦略 ■技術戦略マネジメント 05 技術開発戦略 ■ビジネスインダストリ 06 ビジネスシステムとエンジニアリングシステム 07 e-ビジネス 08 民生機器と産業機器 【章末まとめ問題】 ■■第9章 企業と法務 ■企業活動 01 企業活動と組織 02 OR・IEと業務分析 03 品質管理とQC七つ道具 04 企業会計と財務 ■法務 05 企業が関わる法務 06 セキュリティに関する法規とガイドライン 07 企業の責任と標準化 【章末まとめ問題】 ■■巻末付録 擬似言語の攻略> ■■
「出るとこだけ!」がリニューアル。ベテラン講師の最短合格テクニックが満載。模試1回分・解説動画・Webアプリ・赤シートつき。 「出るとこだけ!」がリニューアル!ベテラン講師の最短合格テクニックが満載!2023年4月からの新試験制度に完全対応! 2022年12月・2023年7月に公開されたサンプル問題で、問題演習ができます。本当に出るところだけを効率よく学ぶことができるので、1冊で最短合格を狙えます。新試験制度の頻出ポイントを著者がわかりやすく紹介する「オリジナル解説動画」とスマホで頻出問題が解けるWebアプリ付き!【ここがオススメポイント!】●ベテラン講師が「試験に出るとこだけ」を徹底解説!→著者が年間100回程度行っている基本情報処理技術者の試験対策講義のノウハウをベースに、これまで繰り返し出題されているテーマを中心に解説!●フルカラーでさらに見やすく、効率よく学べるようになった!→全ページオールカラーでレイアウトも刷新し、紙面がますます見やすく、パワーアップしました! 羊のイラストといっしょに、試験に「出るとこだけ」効率よく学べます。●オリジナル解説動画付き!→基本情報試験の対策を著者が徹底解説したオリジナル解説動画付き!試験の概要や科目A&科目B分野の対策、科目A免除制度に至るまでわかりやすく解説しています!●模擬試験1回分と過去問題5回分が解ける!→2022年12月に公開されたサンプル問題(模擬試験)と平成29年秋~令和元年秋の過去問題(5回分)の解答解説をWeb提供! 過去問題を解きまくって合格力アップ!●Webアプリでいつでもどこでも学習できる!→過去の午前&科目A試験の問題&解説をWebアプリで提供。PCはもちろん、スマホやタブレットでいつでも学習できる!【こんな方へおすすめ!】・新試験制度に即した対策をしたい人・時間がないので、パパッと効率よく学習したい人・重要なポイントだけをおさえて、最短でサクっと合格したい人・他の学習書が厚すぎると感じた人【目次】第1章 受験ガイダンス第2章 2進数第3章 論理演算第4章 データベース第5章 ネットワーク第6章 セキュリティ第7章 アルゴリズムとデータ構造第8章 テクノロジ系の計算問題第9章 マネジメント系とストラテジ系の要点第10章 マネジメント系とストラテジ系の計算問題第11章 科目Bの対策Appendix 基本情報技術者模擬試験のご案内(ダウンロード提供)模擬試験1回分・過去5回分の過去問題など 第1章 受験ガイダンス 1.0 なぜ基本情報技術者試験を受けるのか? 1.1 基本情報技術者試験の内容 1.2 情報処理推進機構のWeb ページから入手できる情報 1.3 問題解法テクニック 1.4 学習方法と学習スケジュール第2章 2進数 2.0 なぜ2進数を学ぶのか? 2.1 10進数と2進数の変換 2.2 2進数と16進数および8進数の変換 2.3 2の補数表現と小数点形式 2.4 シフト演算と符号拡張 2.5 2進数の練習問題 2.6 2進数の練習問題の解答・解説第3章 論理演算 3.0 なぜ論理演算を学ぶのか? 3.1 論理演算とベン図の関係 3.2 論理演算で条件を結び付ける 3.3 論理演算によるマスク 3.4 論理演算による加算 3.5 論理演算の練習問題 3.6 論理演算の練習問題の解答・解説第4章 データベース 4.0 なぜデータベースを学ぶのか? 4.1 E-R図 4.2 関係データベースの正規化 4.3 SQL 4.4 トランザクション処理 4.5 データベースの練習問題 4.6 データベースの練習問題の解答・解説第5章 ネットワーク 5.0 なぜネットワークを学ぶのか? 5.1 ネットワークの構成とプロトコル 5.2 OSI基本参照モデル 5.3 ネットワークの識別番号 5.4 IPアドレス 5.5 ネットワークの練習問題 5.6 ネットワークの練習問題の解答・解説第6章 セキュリティ 6.0 なぜセキュリティを学ぶのか? 6.1 技術を悪用した攻撃手法 6.2 セキュリティ技術 6.3 セキュリティ対策 6.4 セキュリティ管理 6.5 セキュリティの練習問題 6.6 セキュリティの練習問題の解答・解説第7章 アルゴリズムとデータ構造 7.0 なぜアルゴリズムとデータ構造を学ぶのか? 7.1 基本的なソートのアルゴリズム 7.2 基本的なサーチのアルゴリズム 7.3 基本的なデータ構造 7.4 アルゴリズムとデータ構造の練習問題 7.5 アルゴリズムとデータ構造の練習問題の解答・解説第8章 テクノロジ系の計算問題 8.0 なぜテクノロジ系の計算問題が出題されるのか? 8.1 コンピュータシステムの計算問題 8.2 技術要素の計算問題 8.3 開発技術の計算問題 8.4 テクノロジ系の計算問題の練習問題 8.5 テクノロジ系の計算問題の練習問題の解答・解説第9章 マネジメント系とストラテジ系の要点 9.0 なぜマネジメント系とストラテジ系の要点を学ぶのか? 9.1 マネジメント系の要点 9.2 ストラテジ系の要点 9.3 マネジメント系とストラテジ系の要点の練習問題 9.4 マネジメント系とストラテジ系の要点の練習問題の解答・解説第10章 マネジメント系とストラテジ系の計算問題 10.0 なぜマネジメント系とストラテジ系の計算問題が出題されるのか? 10.1 マネジメント系の計算問題 10.2 ストラテジ系の計算問題 10.3 マネジメント系とストラテジ系の計算問題の練習問題 10.4 マネジメント系とストラテジ系の計算問題の練習問題の解答・解説第11章 科目Bの対策 11.0 なぜ擬似言語の読み方と情報セキュリティのポイントを学ぶのか? 11.1 疑似言語の読み方 11.2 情報セキュリティのポイント 11.3 科目Bの対策の練習問題 11.4 科目Bの対策の練習問題の解答・解説Appendix 基本情報技術者模擬試験のご案内 Appendix 01 なぜ試験問題の全問を解くのか? Appendix 02 模擬試験のダウンロード方法と実施方法
累計60万部を突破した「スッキリわかる入門シリーズ」の新世代C言語入門書に、待望の進化改訂版が登場! この第2版では、クラウド学習環境「dokoC」に対応し、初学者がつまづきがちな開発環境導入の手間を省いて、すぐに学習を開始できるようになりました。本書は、通常の解説文の中に、適度な間隔で、学び手役の新人と指導役の先輩の対話を織り交ぜる展開と、豊富な図解で、わきあがる疑問を置き去りにせず、じっくり楽しく正確に、難所ポインタですらスッキリ理解できる、他の入門書では見られない、唯一無二の構成となっています。
IT初心者向けの合格支援本で、挫折しにくい内容が特徴。重要なポイントをわかりやすく解説し、試験に出る内容を効率的に学べる構成。目次にはハードウェアから情報化と経営までの幅広いテーマが含まれている。
この書籍は、基本情報技術者試験を目指すためのオールインワンタイプの参考書と問題集で、シリーズ累計140万部を突破しています。最新のシラバスに対応し、重要なポイントをイラストや図解を使ってわかりやすく解説しています。関連の本試験問題を解くことで知識を定着させ、効率的に合格レベルに到達できる内容です。読者特典として英略語の暗記カードや重要用語集も提供されています。受験者にとって必携の一冊です。
午後問題を解くために必要な着眼点,問題文の読み方を丁寧に解説!◎問題演習を通して,関連知識を復習!◎絶妙に心地よい解説で,理解力アップ!◎多くの学習者が感じる疑問点をFAQで解決!◎読みやすさを考慮し,解説での問題引用文は全て,枠で抜き出しを行っていますので,問題に立ち返らなくても確認ができます!◎黒太字,緑文字を追っていくだけで,要点がわかる仕掛けになっています!分かりやすく丁寧な解説に定評があり,「AP午後対策といえば重点対策!」と,毎年多くの学習者の方に支持されています。分厚いし難しいのでは…?と思われた方もご安心ください。重要ポイントや解答にたどり着く工程を省きすぎることなく,納得しながら読み進められるように丁寧に書かれている本書だからこそ,合格に必要な力が身に付きます! 第1部 本書の使い方 第1章 応用情報技術者試験の出題範囲 第2章 学習の進め方 第3章 本書の学習方法 第2部 午後記述式問題の対策 第1章 情報セキュリティ 第2章 システムアーキテクチャ(システム構成技術と評価) 第3章 ネットワーク 第4章 データベース 第5章 情報システム開発 第6章 プログラミング(アルゴリズム) 第7章 組込みシステム開発 第8章 マネジメント系の問題 第9章 ストラテジ系の問題 巻末資料
この参考書は、効率的に合格点を目指すための問題主導型のコンパクトな教材です。重要事項を厳選し、短くまとめているため、細切れ時間での学習や試験直前の確認に最適です。問題を通じて暗記・理解を深めることができ、受験テクニックや早解きのコツも豊富に掲載されています。著者の福嶋先生は、受験指導経験が豊富で、わかりやすい解説が定評です。また、問題解説動画も用意されています。ポケットサイズで持ち運びやすく、いつでも学習可能です。
本書は,受験者の方が短期間で効率良く試験対策できるように構成されています。 ◎「学習前診断テスト」で,苦手分野を確認してから効率的に学習を進める構成です。 ◎「学習のポイント」と「ポイントの解説」では,午前問題の知識について, 重要なテーマの頻出ポイントを解説しています。 ◎「理解度チェック」で各章のポイントを穴埋め形式で確認。何度も解いて知識を定着させましょう。 ◎「問題で学ぼう」では, 厳選された学習効果が高い問題を例題として掲載。基礎概念をより深く理解できるよう,オリジナルに書き下ろした詳細な例題解説でしっかり学習しましょう。 また演習問題を,最近の試験傾向に合わせて差し替えました。 特に,出題数が増えた応用数学,セキュリティなどは,よく出る内容を含めています。 強化学習,GPGPU,PCIe,エッジコンピューティング,VUI,WCAG,UXデザイン,DBMS,デッドロック,データレイク,MIMO,5G,SEOポイズニング,SIEM,利用者管理,WPA3,アクティビティ図,サービス要求管理,ワークフローシステム,RPA,超スマート社会,SDGs,オフバランスなども取り入れました。 新Webコンテンツ「IT用語スペルチェック」で,用語を覚えたかを確認できます。 さらに分かりやすく解説した動画も,アイテック公式YouTubeチャンネルにあります。ご覧ください。 第1部 本書の学習方法と試験のポイント 第1章 本書の学習方法 第2章 基本情報技術者 午前試験のポイント 第2部 午前試験の出題ポイント 第1章 基礎理論 第2章 コンピュータ構成要素 第3章 システム構成要素 第4章 ソフトウェアとハードウェア 第5章 ヒューマンインタフェースとマルチメディア 第6章 データベース 第7章 ネットワーク 第8章 セキュリティ 第9章 開発技術 第10章 ITマネジメント 第11章 ITストラテジ
◎試験対策のプロが過去の本試験を徹底的に分析! ◎午前問題は,「分野」,「出題年度」,「頻出度」など多角的な分析の結果,選び抜かれた問題を掲載! →試験対策に最適な問題で,効果的な演習ができる! ◎午後問題はテーマ別に出題傾向を分析 →重点テーマの学習ポイントを確認! →「MYカルテ」を使って繰返しの復習もばっちり! 1.合格へのアプローチ 2.午前問題の対策 第1部 基礎理論 第2部 コンピュータシステム 第3部 技術要素 第4部 開発技術 第5部 プロジェクトマネジメント 第6部 サービスマネジメント 第7部 システム戦略 第8部 経営戦略 第9部 企業と法務 3.午後問題の対策 第1部 必須問題(情報セキュリティ) 第2部 選択問題(コンピュータシステム,ソフトウェア設計,マネジメント,ストラテジ) 第3部 必須問題(データ構造及びアルゴリズム) 第4部 選択問題(ソフトウェア開発) 4.巻末資料
午前試験の要点に絞った、対話形式のテキスト。著者Webサイトで17回分(全1360問)の過去問解説動画を配信。 基本情報技術者試験の【午前試験】で出題される内容を対話形式で解説したテキストです。 解説動画で解き方がわかる! 対話形式だから初学者も安心! ◆こんな方にオススメ! ・文系でプログラムの経験がない ・自分のペースで勉強したい ・丸暗記でなく、ちゃんと理解したい ◆読みやすい対話形式 文系初学者のキャラクターと先生のやりとりで講義が進みます。 学生「フローチャートの分岐って、ゲームなんかで、Aルート、Bルートに分かれるアレですか?」 先生「正解。行き先が分かれることです」 ◆動画連携で解き方がわかる! [動画]アイコンの付いた問題は、解説動画を著者Webサイトにアップしています。 動画の視聴方法は、本書の14ページを参照してください。 ※動画を視聴できるのは、2022年11月30日までです。 ◆1単元4ページのきっちり構成 短期間でざっと学びたい。 少しずつじっくり学びたい。 それぞれの学習スケジュールにあわせて使いやすい構成です。 章ごとに「演習問題」と「問題文で覚える」を収録。 ◆スマホで見られる1,360問! 17回分(全1,360問)の過去問解説動画を著者Webサイトに用意しました。 問題文に登場する設定や数式を動かしているので、解き方や間違えやすい点がわかり、理解が深まります。 第1章 情報技術の基礎 第2章 データ構造とアルゴリズム 第3章 ハードウェア 第4章 ソフトウェア 第5章 ネットワーク 第6章 セキュリティ 第7章 データベース 第8章 ソフトウェア開発 第9章 マネジメント 第10章 ストラテジ 特別補講 数学対策
本書は、初心者向けにPythonを使ってアルゴリズムの基礎を学ぶ入門書です。Pythonの基本とデータ構造を解説し、具体的なサンプルコードを用いてアルゴリズムの考え方や計算量についても詳しく説明します。アルゴリズムをゼロから学びたい人や、基本情報技術者試験の準備をしている人におすすめです。内容は、Pythonの基本から、探索方法、データの並べ替え、実務に役立つアルゴリズムまで幅広くカバーしています。著者は増井敏克氏で、技術士としての豊富な経験を持っています。
大人気シリーズの最新刊! 令和4年(2022年)最新版! 本書は『基本情報技術者』試験に、短期間で一発合格するための試験対策本です。 「試験に合格すること」のみを目的に企画・構成されています。 ITの知識がまったくない、未経験者や学生、新社会人の方々でもスラスラと学習を進めることができるよう、 初歩の初歩からとことん丁寧に解説しています。 「最短で」「確実に合格」するためのノウハウを完全解説! とことん丁寧な解説 & 頻出の過去問を徹底研究。 だから、この一冊で合格できます! ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 本書の4つの特徴 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ (1) とことん丁寧な解説 これから学ぶ人でも安心して読み進められるよう、豊富なイラストや具体例を用いて、とにかくやさしく解説しています。 (2) 過去問を徹底研究 過去問を徹底研究し、繰り返し出題されている頻出の過去問(類似問題)のみを厳選して掲載しています。 (3) 効率のよい学習方法を採用 本書では、暗記が苦手な人、集中力が続かない人でも安心の「効率のよい学習方法」を採用しています。 (4) 万全の読者サポート 読者専用サイトで、読者の「わからない! 」をサポート。疑問・質問に回答します。だから挫折することなく合格できます! ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ■本書の対象読者 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ・基本情報技術者試験に一発で合格したい人 ・試験勉強を効率よく進めたい人 ・ITの知識がない初心者の方々 ・できるだけラクに合格したい人 序章 基本情報技術者試験の概要と効果的な学習方法 第1章 基礎理論① 第2章 基礎理論② 第3章 アルゴリズムとプログラミング 第4章 コンピュータの構成要素 第5章 システムの構成要素 第6章 ソフトウェア 第7章 ハードウェア 第8章 ヒューマンインタフェースとマルチメディア 第9章 データベース 第10章 ネットワーク 第11章 情報セキュリティ 第12章 システム開発 第13章 ソフトウェア開発手法 第14章 プロジェクトマネジメント 第15章 サービスマネジメントとシステム監査 第16章 システム戦略 第17章 システム企画 第18章 経営戦略マネジメント 第19章 ビジネスインダストリ 第20章 企業活動 第21章 法務 第22章 [午後試験]完全対策 【付録】 寝る前10分&試験直前の確認リスト
この問題集は、応用情報技術者試験の午後問題に特化し、頻出テーマや基礎知識を厳選して解説しています。最新の試験問題や過去の出題傾向を分析し、図解を用いた明確な解説を提供。章構成は試験問題に対応しており、各分野を集中的に学習できます。また、補足解説や「Try!問題」で理解を深めることができ、解答用紙のダウンロードも可能です。この書籍は、応用情報技術者試験受験者にとって必携の一冊です。
この本は、基本情報技術者試験のための基礎知識(2進数、論理回路、アルゴリズムなど)を、専門学校の講師が身近な例や親しみやすい語り口でわかりやすく解説しています。著者は、受験者が理解しやすいように工夫された内容で、試験対策のスタートに最適な一冊です。目次には、2進数、記憶、計算、CPU、ソフトウェア、ネットワークの各章が含まれています。
シラバスVer.6.3に対応!広い出題範囲をこの一冊に凝縮■本書の概要情報処理技術者試験「応用情報技術者(AP)」の令和6年度春期・秋期試験の対策書です。システム監査基準、システム管理基準の改訂に伴うシラバス変更(Ver6.3)に対応しています。試験を知り尽くしたベテラン講師が、よく出るポイントを丁寧に解説します。■対象読者基本的には、基本情報技術者(FE)試験の合格者またはそれと同等の知識をもつ方を想定していますが、近年、FE試験を受験することなく、AP試験を受験する方が増えていることに配慮し、数学系の基礎理論も解説しています。■本書の特長◎午前・午後の両試験に対応◎知識解説と過去問演習で幅広い出題範囲を網羅◎基本情報を受験せずに応用情報を受験する場合に配慮して、基数変換、シフト演算などの基礎理論も解説◎技術者に馴染みの薄いストラテジ分野を手厚く解説◎令和5年度春期試験の解説を掲載◎特典PDFをWebダウンロードで提供(1)過去問解説19回分(平成25年度春期試験~令和4年度秋期試験)(2)スマホでも読める「よく出題される重要ポイント100」※ダウンロード期限は2024年12月31日までです。■本書の構成・第1章~第12章 分野別の解説:解説+問題で幅広い出題範囲を網羅 節末問題:午前試験の過去問から頻出テーマを厳選 章末問題:午後試験の過去問を収録・第13章・第14章 令和5年度春期試験の午前問題(第13章)・午後問題(第14章)を丁寧に解説・付録A 応用情報技術者になるには 試験の概要、出題傾向、学習方法、受験の手引きなど■目次第1章 基礎理論第2章 コンピュータ構成要素第3章 システム構成要素第4章 ソフトウェアとハードウェア第5章 ヒューマンインタフェースとマルチメディア第6章 データベース第7章 ネットワーク第8章 セキュリティ第9章 システム開発技術第10章 ソフトウェア開発管理技術第11章 マネジメント第12章 ストラテジ第13章 令和5年度春期試験 午前第14章 令和5年度春期試験 午後付録A 応用情報技術者になるには 第1章 基礎理論 1.1 計算の基礎理論 1.2 情報の基礎理論 1.3 数理応用 1.4 プログラム言語 1.5 問題向きデータ構造 1.6 アルゴリズム第2章 コンピュータ構成要素 2.1 プロセッサ 2.2 メモリアーキテクチャ 2.3 入出力装置と入出力デバイス第3章 システム構成要素 3.1 システム構成技術 3.2 システムの性能・信頼性第4章 ソフトウェアとハードウェア 4.1 OSの基本機能 4.2 記憶管理と同期・排他制御 4.3 ハードウェア第5章 ヒューマンインタフェースとマルチメディア 5.1 ヒューマンインタフェース 5.2 マルチメディア第6章 データベース 6.1 データベース方式と設計 6.2 関係代数とデータベース言語 6.3 トランザクション処理 6.4 データベース応用第7章 ネットワーク 7.1 通信プロトコル 7.2 符号化と伝送 7.3 ネットワーク 7.4 ネットワーク応用第8章 セキュリティ 8.1 情報セキュリティ 8.2 情報セキュリティ管理第9章 システム開発技術 9.1 開発環境と開発手法 9.2 要求分析・設計技法 9.3 テスト・レビューの方法第10章 ソフトウェア開発管理技術 10.1 アプリケーションシステムの構築 10.2 システム構築の関連知識 10.3 システム運用・保守第11章 マネジメント 11.1 プロジェクトマネジメント 11.2 サービスマネジメント第12章 ストラテジ 12.1 情報システム戦略とシステム企画 12.2 経営戦略マネジメント 12.3 技術戦略マネジメント 12.4 ビジネスインダストリ 12.5 企業活動 12.6 法務 12.7 標準化第13章 令和5年度春期試験 午前 13.1 問題 13.2 解答・解説第14章 令和5年度春期試験 午後 14.1 問題 14.2 解答・解説付録A 応用情報技術者になるには A.1 応用情報技術者試験とは A.2 試験の攻略ガイド A.3 受験の手引き
◆ポイントを押さえて,ていねいに説明。短期間で効率よく学習できる! ◆マクロの問題も詳しく解説! 本書は,基本情報技術者試験 午後問題「表計算」の対策書です。 全章を通して,ワークシートの図を豊富に掲載するとともに, 【ポイント】【補足】【注意】といったアイコンを用いて説明を 補っています。これにより,「表計算は初めて」という方も 関数やマクロをスムーズに学習することができます。 また,学習した内容をより深く理解して頂くために,過去問に もとづいた問題やオリジナル問題を多数収録しているのも, 本書の特徴です。 「表計算」問題を攻略するためには,関数の理解が必要不可欠です。 本書では,比較的わかりやすい基本的な関数から,応用的な関数 (試験に頻出の関数),その他の関数まで,一つ一つ順を追って, ていねいに説明しています。 また,苦手意識を持たれている方が多いマクロについて,擬似言語の 読み方から問題の解き方まで,練習問題を織り交ぜながらくわしく 解説しています。 さらに総仕上げとして,本書の最終章に過去問を精選し掲載しています。 過去問を解くことで,これまで学習した内容が理解できているかどうか, 確かな実力が身についているかどうかを確認することができます。 第1章 表計算ソフトの仕様 第2章 基本的な関数 第3章 応用的な関数 第4章 その他の関数 第5章 マクロ 第6章 実戦問題
初心者だって合格できる!科目B対策の決定版! ●●●こんな人におすすめ●●● ・IT初心者でも1発で合格したい・・・ ・文系でプログラミングをしたことがない・・・ ・アルゴリズムがさっぱり理解できない・・・ ご安心ください! 大ベテランの講師がプログラミング[完全初心者]に、 限界まで「わかりやすく」解説します。 ●●●本書の2つのポイント●●● ①確実に実力アップ~基礎固め+本番レベルの演習~ 基礎の基礎から、つまづかないように丁寧に解説。 必要な知識を体系的に学習⇒本番演習の順番できちんと実力が身につきます。 IPAが公開しているサンプル問題をすべて徹底解説。本番試験に最も近い対策を実現しました。 ②新試験CBT方式を[完全]攻略~時間配分&解く順番~ 絶対に知りたい!合格するための「CBT方式の必勝攻略法」を掲載。 実際に受験した著者だから伝えられる、試験当日のテクニックを余すところなくお伝えします。 第1部 アルゴリズムとプログラミング 第1章 基本的なアルゴリズム 1-1アルゴリズムとは 1-2変数 1-3三つの制御構造 1-4関数 第2章 データ構造 2-1配列 2-2リスト 2-3スタックとキュー 2-4木構造 第3章 様々な分野のプログラミング 3-1定番アルゴリズム 3-2サーチとソート 3-3ビット演算 3-4再帰処理 3-5データサイエンス 3-6オブジェクト指向 3-7文字列 第2部 情報セキュリティ 第1章 セキュリティ管理 1-1セキュリティの目的 1-2セキュリティ管理 1-3法規と取組み 第2章 セキュリティ上の脅威 2-1マルウェア 2-2攻撃手法 第3章 セキュリティ対策 3-1セキュリティ対策 3-2暗号化 3-3認証 3-4対策技術
基本情報技術者試験の午後の必須問題に役立つ!出題が予想されるアルゴリズムを網羅し、詳解!単なる試験対策で終わらないスキルが身につく! 第1章 アルゴリズムの基礎 第2章 擬似言語と構造化プログラミング 第3章 変数とデータ構造 第4章 簡単なアルゴリズム 第5章 番人を使ったアルゴリズム 第6章 ソートのアルゴリズム 第7章 探索アルゴリズム 第8章 再帰を利用したアルゴリズム 第9章 その他のアルゴリズム 第10章 アルゴリズムの評価
この書籍は、基本情報技術者試験「科目B」の「アルゴリズムとプログラミング(擬似言語)」に特化した対策本です。プログラミング未経験者を対象に、アルゴリズムの基本から擬似言語プログラムの解説を行い、試験問題を短時間で解けるスキルを身につけることを目指します。豊富な図解や例題を用い、段階的に学べる構成になっており、特に初学者や再学習者に適しています。各章には確認問題もあり、理解度をチェックできます。
「基本情報技術者」に関するよくある質問
Q. 「基本情報技術者」の本を選ぶポイントは?
A. 「基本情報技術者」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「基本情報技術者」本は?
A. 当サイトのランキングでは『令和04年 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室 (情報処理技術者試験)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで114冊の中から厳選しています。
Q. 「基本情報技術者」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「基本情報技術者」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。







』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/514ieT63xfL._SL500_.jpg)


』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51PKb9-diVL._SL500_.jpg)
![『情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者[科目B]第4版 (EXAMPRESS)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ceaObjANL._SL500_.jpg)

![『うかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編] 2022年版 福嶋先生の集中ゼミ』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/518uVuO7yAL._SL500_.jpg)












![『情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者[科目A][科目B]2025年版 (EXAMPRESS)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ca62t3rkL._SL500_.jpg)
![『情報処理教科書 出るとこだけ! 基本情報技術者[午後]第2版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ru-o8S5iL._SL500_.jpg)
![『情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者[科目B]予想+過去問題集 (EXAMPRESS)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51y8nNQrdsL._SL500_.jpg)
![『[改訂新版]基本情報技術者【科目B】アルゴリズム×擬似言語トレーニングブック』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51wsJbI7KbL._SL500_.jpg)




![『(全文PDF、過去問アプリ付き)[令和7年度]基本情報技術者 超効率の教科書+よく出る問題集』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51CK7Ypvm5L._SL500_.jpg)




![『うかる! 基本情報技術者 [午後・表計算編] ver.2.0』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/512tE8BgSWL._SL500_.jpg)


![『情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者 テキスト&問題集[科目A][科目B]2024年版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/515zkd1oX4L._SL500_.jpg)










』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41gkXN4ncFL._SL500_.jpg)





![『情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者[科目B]第3版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51BQ4-GBjPL._SL500_.jpg)



![『[改訂3版]要点・用語早わかり 基本情報技術者 ポケット攻略本』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51JlyuBC-ZL._SL500_.jpg)







』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51yMHPq4u2L._SL500_.jpg)


![『うかる! 基本情報技術者 [午前編] 2022年版 福嶋先生の集中ゼミ』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/5187l6N1UiL._SL500_.jpg)

![『うかる! 応用情報技術者 [午後] 速効問題集』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51-qb2tNyhL._SL500_.jpg)



![『(全文PDF・単語帳アプリ付き)徹底攻略 基本情報技術者の科目B実践対策[プログラミング・アルゴリズム・情報セキュリティ]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ViHeqJS+L._SL500_.jpg)

![『情報処理教科書 出るとこだけ!基本情報技術者 テキスト&問題集 [科目A][科目B]2023年版 (EXAMPRESS)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51BM8Ukz0BL._SL500_.jpg)




![『基本情報技術者[科目B]アルゴリズムとプログラミング トレーニング問題集(第2版)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/512kPfyw++L._SL500_.jpg)










![『初心者が合格できる知識と実力がしっかり身につく 基本情報技術者[科目B]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51e8b2nnPuL._SL500_.jpg)


![『うかる! 基本情報技術者 [科目A編] 2023年版 福嶋先生の集中ゼミ』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51J4Zd8cIfL._SL500_.jpg)
![『うかる! 基本情報技術者 [科目B・アルゴリズム編] 2024年版 福嶋先生の集中ゼミ』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51150FQRH8L._SL500_.jpg)
![『うかる! 基本情報技術者 [科目B・セキュリティ編] 2023年版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51VGv9oVJYL._SL500_.jpg)
![『基本情報技術者試験 図解でわかるアルゴリズムの基本と仕組み[第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51A3TpORSrL._SL500_.jpg)
![『うかる! 基本情報技術者 [科目B・アルゴリズム編] 2023年版 福嶋先生の集中ゼミ』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51rfXO1tW5L._SL500_.jpg)
![『うかる! 基本情報技術者 [科目B・セキュリティ編] 2024年版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51MSwfRhHlL._SL500_.jpg)


![『[改訂新版]基本情報技術者【科目B】ゼロからわかるアルゴリズムと擬似言語』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51WMYacg5SL._SL500_.jpg)