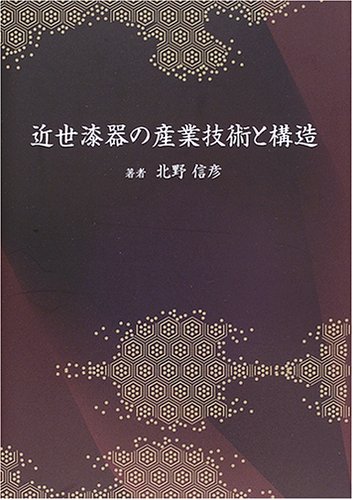【2026年】「美術史」のおすすめ 本 107選!人気ランキング
- 鑑賞のための 西洋美術史入門 (リトル キュレーター シリーズ)
- 美術の物語
- いちばん親切な 西洋美術史
- 増補新装 カラー版 西洋美術史
- 西洋美術史(美術出版ライブラリー 歴史編)
- 武器になる知的教養 西洋美術鑑賞
- 絵を見る技術 名画の構造を読み解く
- 366日の西洋美術 (366日の教養シリーズ)
- 東京藝大で教わる西洋美術の見かた (基礎から身につく「大人の教養」)
- 世界アート鑑賞図鑑
本書は、美術鑑賞の入門書であり、ギリシャ美術から現代美術までの歴史を簡潔にまとめています。専門用語や美術の概念をQ&A形式でわかりやすく解説し、学芸員の対話や猫の素朴な質問を通じて読者の理解を深めます。美術館での作品鑑賞をより楽しむための知識を提供し、特に海外旅行前に読むことで美術館体験が豊かになることを目的としています。
この書籍は、美術史を洞窟壁画から現代美術までの視点で物語のように描き出しており、絶えず変化しながらも繋がっている美術の流れを紹介しています。目次には、先史時代や古代文明、ギリシャ・ローマ時代、ビザンティン、イスラム、中国など多様な文化の美術が含まれています。著者エルンスト・H・ゴンブリッチは20世紀の著名な美術史家であり、彼の作品は明瞭で説得力があり、美術への深い愛情が表れています。
この書籍は、4000年にわたる西洋美術の歴史を時代や特徴ごとに紹介しています。各時代(エジプト、ギリシャ、ローマ、ルネサンス、バロック、印象派など)について、見開き2ページでテーマを解説し、代表的な作品を幅広く紹介。美術館巡りの前に全体像を把握するのに役立つ内容です。著者は美術史の専門家とライターたちです。
この書籍は、古代から20世紀末までの西洋美術の流れをまとめた美術史入門書で、340点のカラー図版を掲載しています。用語解説やカラー年表、関連地図も含まれており、美術愛好者や学生にとって参考になる内容です。目次には、原始美術、古代オリエント、美術の各時代(ギリシア、ローマ、中世、ルネサンス、バロック、近代、現代)に関する章が含まれています。
「西洋美術史」の決定版が刊行され、古代から現代アートまでの通史を全11章で学べる内容です。700点以上のビジュアルを用い、重要項目を見開きで紹介することで、読みやすさを追求しています。美術系大学でも教科書として採用されており、第一線の研究者11名による最新の視点から解説されています。美術を学ぶ初心者にも、知識を深めたい人にも適した一冊です。
本書は、東京藝大美術館の館長が厳選した23作品を通じて、西洋絵画の「革命」を解説し、絵画鑑賞の常識を変える内容です。ルネサンスからポップ・アートまでの西洋美術の歴史を探りながら、知的教養を深める方法や美術館の楽しみ方を紹介しています。著者は、東京生まれの美術館長で、アートライターとしても活動してきた秋元雄史氏です。
本書は、絵画をより深く理解し楽しむための指南書です。著者は、絵の「意味」と「形」の二本柱からアプローチし、特に造形面に焦点を当てています。読者は、名画の主役やバランス、色の使い方、構図などを学びながら、絵を観察する力を養うことができます。理系の人や理論を好む人にも適しており、絵をパズルのように読み解く楽しさを提供します。最終的に、名画が名画たる理由を理解し、個々の感想と客観的な分析を結びつけることを目指します。
本書は、ミケランジェロやダ・ヴィンチなどの名画を366作品紹介し、1日5分で美術の基礎知識を学べる内容です。1週間で7つのテーマ(美術史、主題、ジャンル、画家の逸話、技法、謎・フェイク、周辺)を通じて西洋美術の見方を深めることができます。著者は美術評論家の瀧澤秀保氏で、長年にわたり美術教育に携わってきました。
本書は東京藝術大学の講義に基づく西洋美術の入門書で、著者が選んだ個々の作品を通じてそのメッセージをわかりやすく解説します。ビジュアルを多用し、読者が楽しみながら鑑賞眼を鍛えることを目的としています。全15回の講義形式で構成され、作品同士の関連性を示しながら、美術鑑賞の実践的なアプローチを提案。著者は東京藝大の准教授で、美術史の専門家です。
本書『世界でいちばん素敵な教室』シリーズ第10弾は、古代ギリシャからアール・ヌーヴォーまでの西洋美術を理解するためのガイドです。著名な画家や作品を通じて、美術の歴史や技法、文化的背景を解説し、名画をより深く楽しむための知識を提供します。具体的な質問形式で、さまざまなテーマについて掘り下げており、美術鑑賞をより豊かなものにする内容です。
本書は、西洋美術史の巨匠たちの超絶技巧を高画質のフルカラー図版で紹介しています。フェルメールやダ・ヴィンチなどの名作を拡大し、細部にわたる技巧や主題の背景を解説。視覚的な楽しさに加え、西洋絵画の知識も深められる内容です。特に、だまし絵や遠近法、大理石彫刻など多様な技術が取り上げられています。著者は美術史家の池上英洋氏です。
本書は、西洋美術の誕生と発展を歴史的背景とともに解説したもので、名作の誕生に関する時代背景をビジュアル年表を用いて詳述しています。古代から現代までの美術と歴史の関係を300点以上の名作を通じて探り、当時の社会や人々の暮らしについても触れています。美術史に興味がある人に最適な内容です。著者は美術史家の池上英洋とライターの青野尚子です。
この本は、西洋画家たちが描いた「へんな絵」を120点紹介し、美術評論家の山田五郎氏がそのユニークさを解説しています。笑いを交えながら西洋美術の知識を学べる内容で、面白い絵を楽しみたい人や美術の教養を深めたい人におすすめです。目次には、可愛くない子どもや未確認生物など多様なテーマが含まれています。
本書は、西洋美術に苦手意識を持つ入門者向けに、豊富な図版を用いて美術史をオールカラーで解説するガイドです。古代から現代までの美術を1時間で理解できる内容で、教養としての基礎知識を提供します。著者は美術史家の宮下規久朗氏で、各時代の美術様式や巨匠のエピソードも紹介されています。ビジネスパーソンにも役立つ情報が満載です。
本書は西洋美術史に関する基礎的な知識を最新の研究成果に基づいてまとめたもので、美術作品の制作背景や歴史的文脈を明らかにし、理解と鑑賞のための信頼できるガイドとなる。内容はオリエントから現代までの美術の流れを網羅しており、美術史研究の多様性を踏まえた作品の身許調べが重要であることを強調している。
本書は、古代から20世紀末までの日本美術の流れをコンパクトにまとめた美術史入門書です。297点のカラー図版を掲載し、用語解説やカラー年表、仏像や寺院建築の名称図も含まれており、美術愛好者や学生に最適です。著者は多摩美術大学の学長、辻惟雄氏です。
この短編集は、19世紀から20世紀に活躍した美術の巨匠たち(モネ、マティス、ドガ、セザンヌ)と彼らと共に生きた女性たちの視点を通して、彼らの葛藤や夢を描いています。各物語は、芸術家たちの人生や作品への真摯な姿勢を色鮮やかに蘇らせています。著者は原田マハで、彼女は作家デビュー以来、多くの賞を受賞しています。
この書籍は、日本美術史を第一線の研究者が最新の情報でまとめたもので、視覚的にわかりやすく、読みやすい内容になっています。目次には、縄文時代から現代までの各時代が網羅されています。
ポップアート以降の芸術論を牽引し、現代美学に多大な影響を与えた著者の遺作。1984年の重要論文「アートの終焉」を特別収録 何が作品を芸術にするのか? ポップアート以降の芸術論を牽引し、現代美学に多大な影響を与えた著者の遺作。アートを理解するためのコンパクトな歴史と理論が詰まった一冊。 何が作品を芸術にするのか? ポップアート以降の芸術論を牽引し、現代美学に多大な影響を与えた著者の遺作。1984年の重要論文「アートの終焉」を特別収録。アートを理解するためのコンパクトな歴史と理論が詰まった一冊。 「包括的な特徴など何も存在しないがゆえ、アートの定義は不可能であると、指導的な美学者たちは基本的に定めてきた。そこにおいてアートとは、せいぜいのところ一つの開かれた概念にとどまる。しかし、私見によれば、アートは一つの閉じられた概念である必要がある。ある形式(フォーム)のアートがなぜ普遍的であるのかを説明するような、何らかの包括的な特質が存在しなければならない。」(本書より) 緒言 第1章 目覚めながらの夢 第2章 修復と意味 第3章 哲学とアートにおける身体 第4章 抗争の終焉――絵画と写真の間のパラゴーネ 第5章 カントとアート作品 第6章 美学の未来 附論 アートの終焉(一九八四年) 訳者あとがき 人名索引
本書は、西洋絵画の名作を深く理解するためのガイドで、作品の背景や画家の思いを知ることで絵画がより面白くなることを目的としています。281点の有名作品を紹介し、超有名作品の解説や西洋絵画の基礎知識、ギリシャ神話や聖書の影響、印象派の画家について詳しく解説しています。著者は美術史家の田中久美子氏です。
この書籍は、西洋美術史を通じて約2500年の美術と関連する世界史をわかりやすく解説しています。読者は名画の背景や欧米の歴史、文化を理解し、グローバルスタンダードの教養を身につけることができます。内容は、神中心の世界観やルネサンスの影響、フランスの美術発展、近代社会の文化変化などを扱っており、美術の見方が変わる一冊です。著者は西洋美術史家の木村泰司氏です。
この書籍は、西洋美術史をビジネスマンにとっての必須教養として、池上英洋教授が簡潔に解説しています。1日30分の学習で全20項目をカバーし、技法やジャンル、主要テーマ(アレゴリー、聖書、神話)を学ぶことができます。美術史を楽しむための基礎知識を提供し、名画の見方を実践的に教えています。著者は東京造形大学の教授で、美術史の専門家です。
「A Short Guide to Writing About Art」(第7版)の日本語版は、美術に関する文章を書くための必携書で、学生や美術ブロガーなど幅広い読者に向けて、美術を言葉で表現するテクニックを解説しています。内容は、作品の見方や具体的な文章技術に至るまで多岐にわたり、レポートや論文、展覧会レビューなどの執筆方法を詳しく説明しています。著者は美術史に詳しいバーネットと竹内順一で、各章には美術を書くための具体的な指針が示されています。
この書籍は、ゴッホや印象派、歴史画などを通じて美術の魅力を紹介する内容で、YouTubeで人気の解説が書籍化されたものです。著者は美術解説員の山上やすおで、エンタメ美術講座を運営し、楽しく美術を学べる情報を発信しています。目次にはギリシャ神話や旧約聖書の絵、王室史、印象派、ゴッホの作品などが含まれています。
『怖い絵』シリーズの第1弾が文庫化され、名画の隠れた魅力と新しい鑑賞法を紹介しています。特に、恐怖とは無縁と思われていた作品に潜む怖さを探求し、絵画の背景にある歴史を理解することで新たな楽しみ方を提案。全22作の魅力を取り上げています。著者は中野京子で、彼女は作家でありドイツ文学者です。
本書『室内画の世界』は、美しい部屋の情景を描いた366点の「室内画」を紹介し、フェルメールやマティスなどの巨匠から知られざる名作まで幅広く取り上げています。著者の海野弘氏が各作品のテーマや画家について楽しく解説し、絵画の見方や知識を深める内容です。1日1作を楽しむ形式で、画家たちの自邸に招かれたような体験が提供されます。
本書は、美しい人物が描かれた絵画作品40点を通じて、彼らがなぜ描かれたのかを探求し、その魅力と背後にある光と影を考察します。目次は、古典の美、貴族、才能ある芸術家、創作のインスピレーションを与えるミューズに分かれています。著者の中野京子は、西洋の歴史や芸術に関する専門知識を持つ作家であり、多くの作品を発表しています。
ベンヤミン,シャーカフスキー,バッチェン,バルト.これまで写真について紡がれた代表的な言説をたどり直し,そこに伏在する二項対立を撹乱し「逆撫で」することで見えてくる写真理論の新たな相貌.イメージ=写真がますます遍在し覆い尽くす世界に近づく橋頭堡の構築のために.著者待望の写真論. 序 章 写真論の「現在」――写真の語りにくさ 1 写真の語りやすさ 2 写真の語りにくさ 3 写真論の抗争 4 語りやすさ/語りにくさを超えるために 第1部 モダニズムの分岐 第1章 ヴァルター・ベンヤミン――『写真小史』再考 1 鏡としての写真 2 事物の/である写真――『世界は美しい』という鏡 3 写真における顔と回帰――箔としての写真アーカイヴ 4 歪曲と閃光――ベンヤミンにおける事物,顔,写真 5 鏡とフリップブック 第2章 ジョン・シャーカフスキー――もうひとつのモダニズム 1 モダニズムの写真――グリーンバーグとの並行性 2 写真の透明性と不透明性――シャーカフスキー批判 3 自然史としての写真史――ヴァナキュラー写真の形態学へ向けて 第2部 コンテクストの間隙 第3章 アラン・セクーラ――写真を逆撫ですること 1 芸術写真/写真芸術への批判 2 写真の普遍性と等価性 3 写真アーカイヴ論へ 4 もうひとつのアーカイヴの構築へ 第4章 ピエール・ブルデュー――『写真論』を読む 1 写真による統合と拡散 2 庶民の美学と否定的極としての純粋美学 3 写真の中間性,反復と混乱 4 『写真論』の再接続のために 第3部 メディアの溶解 第5章 ハンス・ベルティンク――写真イメージの人類学 1 イメージ論への転回 2 イメージ=メディア=身体という図式 3 イメージ人類学の写真論 4 写真イメージの人類学へ 第6章 ロザリンド・クラウス――メディア(論)の憑依 1 憑依されるメディア 2 憑依するメディア 3 メディア論の憑依 4 霊媒=メディアとしての写真 5 写真をメディアに/メディアを写真に憑依させること 第7章 ジェフリー・バッチェン――写真の系譜学 1 写真論の抗争――複数の写真と単数の写真 2 写真理論への介入――写真の着想と欲望 3 もうひとつの写真史/写真論 4 写真の終わり(?)以後 第4部 デジタルの脈動 第8章 デジタルの指し示すもの/90年代 1 ユートピアとしてのデジタル写真 2 ディストピアとしてのデジタル写真 3 ゾンビとしての写真 4 デジタル写真は存在しない 5 デジタル写真の指し示すもの 第9章 デジタルの現在/00年代 1 草創期のデジタル写真(論) 2 Web2.0以後のデジタル写真――収斂,フロー,自動化 3 平凡さ,モメント,インデックス 4 JPEGとアクター 5 写真のストック/フロー 6 デジタル写真の参照性とは? 終 章 ロラン・バルト――『明るい部屋』の遡行と転回 1 「明るい部屋」という外部 2 アマチュアとして写真を選ぶこと 3 アマチュアとして写真を見ること(第一部) 4 アマチュアとして写真を見ること(第二部) 5 写真と情動 6 『明るい部屋』の遡行と転回 Photography Theory against the Grain Osamu MAEKAWA
この書籍は、西洋美術史を年代ごとに紹介し、名画の鑑賞ポイントや背景をカラー写真で分かりやすく解説しています。美術鑑賞の基礎知識を提供し、巨匠たちの意外なエピソードも豊富に掲載。著者は美術ライターの佐藤晃子で、絵画を優しく紹介する作品を多数執筆しています。
この書籍はロマノフ家の300年にわたる歴史を全点オールカラーで紹介しており、様々な著名な作品やアーティストによる作品が収められています。著者は作家でドイツ文学者の中野京子で、目次にはロシアの歴史的な人物や出来事に関する作品が並んでいます。
動物行動学者デズモンド・モリスが、古代エジプトから現代のストリート・アートまでの猫の絵134点を紹介し、そのポーズの秘密を解説する書籍です。猫好きやアートファン、動物愛好者が楽しめる内容で、著者は動物行動学の権威であり、シュルレアリスムの画家でもあります。
木村伊兵衛,土門拳,森山大道,荒木経惟から藤岡亜弥まで,日本写真史を駆動してきた力学のひとつはスナップという美学だった.そのスナップ美学の変遷と実態を多様な言説と具体的な写真作品を精査することで浮かび上がらせる,気鋭の研究者による写真研究の成果. 序 論 第1章 スナップショットの誕生:瞬間のイメージ 1 写真用語「snapshot」の登場 2 外来語としてのスナップショット 3 『写真芸術』とスナップショット 第2章 新興写真と小型カメラ:新たな視覚世界 1 スケッチ写真 2 ライカの登場と「新しい視覚」 3 異化と自然さ 第3章 被写意識と反演劇性:木村伊兵衛の肖像写真 1 木村伊兵衛の《文芸家肖像》 2 被写意識 3 スナップ美学と反演劇性 第4章 「道楽から実用へ」:戦時下のスナップ 1 街頭スナップというジャンル 2 窃視するアマチュア 3 スナップとプロパガンダ 第5章 スナップと生活記録:戦後の木村伊兵衛 1 民衆芸術としての写真 2 木村伊兵衛とアンリ・カルティエ=ブレッソン 3 曖昧さと非実用性 第6章 非演出の倫理:土門拳とリアリズム写真 1 リアリズムの「基本的方法」としてのスナップ 2 「黙って撮る権利」 3 スナップのジレンマ 第7章 身振りとしてのスナップ:東松照明・森山大道とアメリカ的なもの 1 スナップの新たな表現 2 東松照明とアメリカ化のイメージ 3 森山大道と異種混交的風景 第8章 スナップと日常:荒木経惟・牛腸茂雄の記念写真構図 1 眼差しから逃れる世界 2 記念写真構図 3 出会いと距離の視覚化 第9章 〈もの〉のスナップ:中平卓馬・石内都・赤瀬川原平らによる物体への眼差し 1 スナップと非生物 2 〈もの〉との出会い 3 事物の歴史性 第10章 反省的転回:一九八〇年代以降の路上スナップ 1 顔への再接近 2 素朴写真家という虚像 3 反省的スナップ The Artless Image: The Snapshot Aesthetic in Japanese Photography Yoshiaki KAI
パートナーたちは画家の生涯と作品にどのような影響を及ぼしたか。そこには様々な葛藤やドラマがあった。印象派を中心とした15人。 画家たちのパートナーに焦点を当てながら、彼らが画家の生涯と作品にどのようにかかわり、影響を及ぼしたかを探ってゆく。そこには実にさまざまな葛藤やドラマがある。印象派を中心とするフランスの著名画家ら15人を取り上げる。 はじめに 1 ヴィジェ=ルブラン──王妃マリー・アントワネットに愛された美貌の女流画家 2 カウフマン──名声と失意の女流〝歴史画家〟 3 グルーズ──悪妻に悩まされ続けた風俗画家 4 ダヴィド──激動の時代に君臨した巨匠 5 アングル──保守・伝統主義を貫いた〝良き夫〟 6 マ ネ──フランス近代絵画の先駆けとなったパリジャン 7 モ ネ──生活の苦しさ、創作の苦しさを支えたふたりの妻 8 ルノワール──多くの女性を愛し描いた「バラ色の人生」の画家 9 モリゾ──男社会での制約に悩みながらも、〝最も純粋な印象派〟を貫いた紅一点 10 ピサロとシスレー ピサロ──長年貧困に苦しんだ、印象派の「農民画家」 シスレー──終始不遇な人生だった〝晴の日〟の画家 11 モローとシャヴァンヌ モロー──ひとり〝象牙の塔〟に生きた世紀末の隠者 シャヴァンヌ──名家出身の貴婦人との遅すぎる結婚 12 セザンヌ──絵画において人もリンゴも同価値と見做した〝不器用な天才〟 13 ゴーガン──都会を捨て、未開の〝楽園〟に創造の源泉をもとめて おわりに 主要参照文献
本書は、「天使と悪魔」「天国と地獄」をテーマにした絵画を集め、魅惑的なビジュアルと共にその背景にある伝説や文学を紹介しています。内容は「最後の審判」の特集を含む三章構成で、天国と地獄、天使と悪魔の系譜を探求。美術作品を通じてキリスト教の神秘的な世界を楽しむことができる一冊です。元は2015年に刊行された書籍の再編集版です。
誰が一番ヘンタイか?ルネサンス、バロック、新古典、ロマン、写実、印象派まで。12人の天才が集まってガチンコ対決! 1 ルネサンス三大巨匠-いちばんのヘンタイは誰!?(三大巨匠、とりあえずいちばんエライのは誰だ!? ダ・ヴィンチは一発屋!? ほか) 2 やりすぎバロック-誰がいちばんToo Much!?(豪華すぎ!派手すぎ!ドラマチックすぎ!バロック文化 エロいか?エロくないか?バロック彫刻の劇的演出 ほか) 3 理想と現実-どっちがヘンタイ?(社会もアートも解体!?激動の時代を生きたヘンタイたち コテン古典のラスボスキャラ!?ドミニク・アングル ほか) 4 2文字ネーム印象派-ヘンタイ王者決定戦(マネは「たけし」で印象派は「たけし軍団」 実は古典リスペクト!物議を醸した『草上の昼食』 ほか)
本書は、美術初心者や中級者向けに、絵画の鑑賞方法を「問題形式」でわかりやすく解説しています。著者は国内トップクラスの美術系YouTuberで、感情的および論理的な視点から絵画を楽しむためのドリルを提供。名画の魅力や画家の意図を理解する手助けをし、読者がより深く美術を楽しめるように導きます。
本書は、美術ファンの増加に応じて、美術史を深く学びたいというニーズに応える美術入門書です。著者ナカムラクニオ氏は、画家の人脈や系譜をチャートで解説し、画家同士の関係性を視覚的に理解できるようにしています。内容は西洋美術と日本美術の2章構成で、ルネサンスや印象派、浮世絵などを中心に美術史を解説。著者の独自の視点やイラストも特徴的で、幅広い美術の流れを網羅しています。
〈東洋芸術〉とは何か──。学術界・美術商・展覧会のグローバルな動向を結びつけ、歴史像の成立過程を解明。 〈東洋芸術〉とは何か──。近代日本において歴史像が刷新されるなかで、「東洋」は拡大・変容していった。ペルシア芸術を焦点として、伊東忠太・黒板勝美ら学術界、美術商や展覧会、メディア・思想などのグローバルな動向を結びつけ、今日の美術史が確立されていく過程を丹念に掘り起こした挑戦作。 序 章 1 日本における「東洋美術史」の形成 —— 日本美術の源流としての「東洋」 2 奈良の美術の起源探究と「西方伝来」 3 欧米と日本におけるペルシア美術の受容 (1) ペルシアとイラン (2) ペルシア美術という流動的な概念 (3) 日本における先行研究と本書の視点 4 本書の意義と構成 第Ⅰ部 サーサーン朝芸術の受容と「東洋芸術」の形成 第1章 美術史・建築史における東西の枠組みとペルシア 1 日本における「東洋美術史」の範囲とペルシアの不在 2 日本における「西洋美術史」とアケメネス朝ペルシア 3 西欧の美術史と建築史における「古代ペルシア」 4 日本の建築史におけるペルシアと伊東忠太の独自の枠組み (1) 三橋四郎と伊東忠太の東西建築史 (2) 伊東忠太とフレッチャーの建築史 —— 日本人の視点と「世界的」な視点の交錯 第2章 伊東忠太とサーサーン朝の芸術 ——「法隆寺建築論」から『文様集成』へ 1 伊東忠太とサーサーン朝ペルシアの建築 —— 留学から1910年代まで (1)「支那・印度・土耳其」留学の概要とペルシア旅行の願望 (2) 叶わなかったペルシア旅行 (3)「野帳」に描かれたサーサーン朝の遺跡 (4) 帰国後に紹介されるサーサーン朝の建築 2 伊東忠太とサーサーン朝の文様 (1) 三宅米吉と四騎獅子狩文錦 (2) 伊東忠太と四騎獅子狩文錦 ——「法隆寺建築論」がヨーロッパに渡った背景 3 「東洋」の一部としてのペルシア ——『文様集成』の編纂と伊東忠太 (1)『文様集成』発刊の経緯とその編集過程 (2)『文様集成』発刊の目的とその背景 (3)『文様集成』における「東洋」の射程 (4)『文様集成』におけるサーサーン朝の文様 (5) 1910年代におけるサーサーン朝の芸術 ——ヨーロッパと日本の研究の展開 第3章 明治大正の建築界における「東洋芸術」 1 工科大学建築学科展覧会と「東洋芸術」へのまなざし (1) 展覧会の始まり (2) 第2回展(東洋芸術の部) (3) 第3回展から第5回展まで (4) 展示物と建築の関係 —— 建築家たちの考古学研究 2 『東洋芸術資料』(1909~11年)と『文様集成』(1911~16年) (1)『東洋芸術資料』とその射程 (2)『東洋芸術資料』から『文様集成』へ 3 「東洋芸術」への注目の背景 —— 過去への関心と将来への道 (1)「東洋芸術」を研究すること —— 欧米の研究者に対する競合意識の中で (2) 芸術創作に応用されるための「東洋芸術」 第Ⅱ部 まなざしが交差する地点 —— 展覧会・博物館におけるペルシアと「東洋」 第4章 1920年代日本の美術商とペルシア美術工芸品展 1 山中商会 2 日仏芸術社 (1) 仏展におけるペルシア美術工芸品 (2) 日仏芸術社の「古陶器展」 3 忘れられた美術商 —— 村幸商店、蒹葭堂、フタバ商店 (1) 村幸商店 (2) 蒹葭堂 (3) フタバ商店 4 美術市場から学術界へ ——「西洋」から「東洋」へ 第5章 黒板勝美のペルシア旅行と東京帝室博物館の復興 1 黒板勝美と海外旅行 2 ペルシア旅行の概要 3 サーサーン朝遺跡の見学とその背景 4 西アジアにおける古美術蒐集と啓明会創立十年記念展覧会への出品 5 東京帝室博物館の復興と「東洋」の拡張 第6章 啓明会創立十年記念展覧会にあらわれるペルシア観 1 啓明会の活動とペルシア研究の支援 (1) 啓明会創立とその活動の概要 (2) 先駆者への助成 —— 啓明会におけるペルシア研究 2 啓明会の創立十年記念展覧会におけるペルシアの芸術 (1) 展覧会の概要 (2) 展覧会における「東洋」とペルシアの枠組み —— 伊東忠太・矢代幸雄・田辺孝次の言説 終 章 1 本書の総括 2 啓明会の創立十年記念展覧会の余波 (1) ペルシアを含んだ「東洋美術史」 (2) 青山新のペルシア美術研究 注 あとがき 付 表 参考文献 図表一覧 索 引
この書籍は、西洋美術史を学ぶための新しいアプローチを提供し、名画のメッセージを読み解くことで絵画鑑賞を楽しむ方法を紹介しています。目次には、美術史の意義、絵画の読み方、社会との関わり、美術の多様性、歴史的な流れが含まれています。著者の池上英洋は、西洋美術史の専門家で、社会構造や思想背景を明らかにする方法論に定評があります。
本書は、フィレンツェを中心としたイタリア初期ルネサンスの巨匠たちの芸術を紹介するもので、マザッチョ、ボッティチェリ、フラ・アンジェリコの絵画や、ブルネッレスキ、アルベルティの建築、ドナテッロの彫刻など460点を収録しています。全28巻からなる人類の美術遺産を集大成したもので、修復された作品を最新の技術で撮影し、鮮明なカラーで再現しています。また、初期ルネサンスの美術と社会についての序論や各章に分かれた詳細な解説も含まれています。
『闇の西洋絵画史』は、アルケミスト双書シリーズの一部で、西洋美術の「闇」の側面を探求するフルカラーの絵画史です。著者は編集者で評論家の山田五郎で、シリーズは全10巻のうち第1期5巻がセットになっており、テーマは「黒の闇」です。セット内容は「悪魔」「魔性」「怪物」「髑髏」「横死」で、美麗なケースに入れて提供されます。
東京大学の講義をベースにした『まなざしのレッスン 1西洋伝統絵画』の続篇.印象派以降,伝統的な絵画の枠組みが崩れていくなか,画家たちは何をめざしたのか.難解な近現代絵画を解きほぐし,まったく新しい視点から実践的に読み解く.美術館に行くのが楽しくなる決定版テキスト第2弾. 第1章 西洋近現代絵画をいかに見るか 第1部 主題とテーマ 第2章 物語表現の変容 第3章 現実の表象I 近代都市の諸相 第4章 現実の表象II 人間と自然の新たな表現 第5章 幻視の世界 第2部 造形と技法 第6章 空間と平面 第7章 色彩と筆触 第8章 抽象と超越性 第9章 引用と遊戯性 第3部 受容と枠組み 第10章 制度と運動 第11章 異文化の受容,逸脱の系譜 第12章 絵画という枠組み 掲載図版一覧 画家名索引
「アルケミスト双書」シリーズの第2期【白の闇】篇が完結し、全10巻が揃いました。著者は山田五郎で、西洋美術の「闇」の側面を探求するフルカラーの絵画史です。第2期では「白の闇」をテーマにした5巻がセットで提供されています。
拳と花 マユの黒髪、繭の白 すべては「にがおえ」になる 動物と植物に触れる 魔法少女たちの舞台装置 呪泉郷の潜勢力 「古街」世界のナビゲーション キャラクターと対象性 水木しげるの新しい学 切片と投擲 異界の構造と変わっていく神話 ミッシング・リンク 『仮面ライダーディケイド』、旅の途中
本書は、先史美術から現代アートまでの美術史を網羅的に学べる一冊です。美術史を深く理解することで、作品の背景や文化、哲学などを学び、感性を豊かにすることができます。内容は、先史・古代・中世から近代、20世紀の美術、さらには日本の美術にまで及び、各時代の特徴や重要な運動を紹介しています。著者はナカムラクニオで、美術家として活動しています。
国家、制度、性、ジャンル、主体……。外在的な近代化から内在的なモダニズムへ。日本における「美術」概念の成立に迫った画期的論集。解説 中嶋泉 国家、制度、性、ジャンル、主体……。外在的な近代化から内在的なモダニズムへ。日本における「美術」概念の成立に迫った画期的論集。解説 中嶋泉 === 現在の美術を作り出した「境界」が引かれ、社会に浸透していく過程を、制度史的視点から捉えた画期的論集。近代において「美術」概念や日本画をはじめとする諸ジャンルは、いかにして形づくられ、純化へと向かっていったか。衝突や動揺を引き起こしつつも、五感の秩序における視覚の優位、工業社会の到来、固有の造型芸術への意志、これら三つが推進力となって「美術」は成立した。だが、その境界は画定し切ったわけではない。裂け目を孕みながら、未完の運動体として今もわれわれの目の前にある。『眼の神殿』と対をなす本書は、新たな作品創造と歴史記述の可能性へと読者を導く。 === 何が美術を規定したのか 概念とジャンルの成立、そしてその先へ── 『眼の神殿』と対をなす画期的論集 === 序章「美術」概念の形成とリアリズムの転位 Ⅰ 国家と美術 「日本美術史」という枠組み 文展の創設 国家という天蓋――「美術」の明治二〇年代 美術における「日本」、日本における「美術」――国境とジャンル Ⅱ 性と国家 裸体と美術――違式?違条例を軸に 美術における政治表現と性表現の限界 Ⅲ 美術の境界――ジャンルの形成 「日本画」概念の形成に関する試論 「工芸」概念の成り立ち 「彫刻」ジャンルの形成 Ⅳ 制度から主体へ 工業・ナショナリズム・美術 印象と表現――日本印象主義のアポリア 終章「分類の時代」の終わりに 初版「後記」 文庫版あとがき 解説(中嶋泉) 初出一覧 「美術」形成史関連年表 主要人名索引
本書は、西洋絵画に描かれる「アトリビュート」や「シンボル」の意味を解説し、名画に込められたメッセージを読み解く内容です。ギリシャ・ローマ神話やキリスト教、寓意に関する情報を幅広く取り上げ、花、果物、樹木、動物などの章に分かれています。著者は美術評論家の平松洋です。
本書は、20世紀以降の現代美術の難解さを、特に第二次世界大戦後の社会との関わりを通じて解説し、その意義を探る内容です。アートが現代社会をどのように映し出し、影響を与えているかを、欧米、日本、トランスナショナルな視点から主要な理論やアーティストの作品を通じて紹介します。著者は、山本浩貴氏で、ロンドン芸術大学で博士号を取得し、現在は香港理工大学で研究を行っています。
この書籍は、美術館を舞台に、深夜に絵画の人物が動き出すというテーマで、世界の名画80作品を紹介し、その鑑賞ポイントやモチーフの意味、画家からのメッセージを解説しています。目次では、西洋絵画の変遷や各時代の名画の特徴を解説し、西洋絵画を楽しむ方法も提案しています。著者は美術史の専門家であり、漫画家も参加しています。
外来文化の模倣と、独自の熟成。その繰り返しから名作は生まれた。目からウロコの知識満載、カラー図版多数。面白すぎる日本美術史。 外来文化の模倣と、独自の熟成。その繰り返しの中から、名作の数々が生まれた。目からウロコの楽しい知識満載、カラー図版多数。面白すぎる日本美術史入門。 外来文化の流入×独自の熟成 日本の美術は面白すぎる! 日本美術史の流れには、大きな波がある。 外来文化をひたすら取りいれ真似する時代と、それを熟成させる時代と。 ほっそりした飛鳥仏も、ハッタリの天守閣に合う金箔べったりの屏風絵も、すべての名作は、そうした繰り返す時代の波の中から、登場してきた。 楽しくて目からウロコの知識満載。役に立つコラムに、カラー図版多数。 ――こんな授業が受けたかった! はじめに――日本美術史の波 0 仏教伝来以前――何を拝んでいたか? 見えない神々/神の姿を形作らない/仏像を見てびっくりする…ほか 1 飛鳥時代の仏像――どうして細い? 聖徳太子のために/アルカイックスマイル/細い仏像を貧弱に見せないために/お手本は北魏/横から見たほうがきれい/絵画もほっそり…ほか 2 奈良時代――美の基準はなぜ変わった? 白鳳時代のかわいい仏像/中国のかわいい仏像/中国のマッチョな仏像/白鳳か天平か/東大寺大仏建立/鑑真とともに伝わったもの…ほか 3 異色の仏教――密教とは何なのか? 迫力で勝るヒンドゥー教/大日如来という新キャラクター/空海、密教に出会う/東寺講堂の立体曼荼羅/色っぽい仏像…ほか 4 浄土信仰――死後のために頑張る? 末法思想/阿弥陀の誓願/阿弥陀浄土図/浄土堂/阿弥陀如来像/阿弥陀来迎図/臨終掛け/地獄絵と六道絵……ほか 5 一二世紀の絵巻――なぜ大人が熱狂する? 「女子供」のための絵巻から/絵巻マニアの後白河上皇/絵巻のジャンル(女絵)/劇画のような絵巻/嗚呼絵というジャンル…ほか 6 慶派――奈良仏師なぜ成り上がった? 売れない奈良仏師/運慶の野心/販路を東国へ/東大寺大仏炎上/巨像を造る/運慶とその息子たち/ちょっと違う快慶…ほか 7 肖像画――禁忌からブームへ 肖像画はタブー/僧侶ならOK/一人の天才が流れを変える/似絵の家系/新仏教のカリスマたち/武士だって絵に残したい…ほか 8 水墨画――新技術をいかに学ぶか 瓢?から駒/モノクロで3D/留学僧だけが描ける絵/将軍も参加した詩画軸/売れない雪舟/遅い再スタート/中国帰りで売り出す/模写から得たもの……ほか 9 戦略としての絵画――ハッタリの天守閣に合う絵とは? なんともタフな狩野派/時代が変われば絵も変わる/天主閣に似合う絵とは/ライバル長谷川等伯の台頭/楓図と桜図/松林図?風…ほか 10 狩野派その後――徳川時代を生き抜くためには? 狩野派の三面作戦/スター誕生/時代に似合う絵/データベース『探幽縮図』/ファミレス化する狩野派/かわいそうな探幽/狩野派からはみ出した画家たち…ほか 11 琳派――出身も時代も場所もばらばらで? 芸術目利き:本阿弥光悦/扇屋の発想:俵屋宗達/呉服屋のぼんぼん:尾形光琳…ほか 12 浮世絵の始まり――「かけそば一杯分」になるまで 大名が熱を上げる:寛永風俗画/少しはお求めやすい価格に:寛文美人図/はじまりはエロ版画:菱川師宣/墨摺り手彩色/絵暦オタクたちの功績:鈴木春信/歌麿の販売戦略/幕末の美学/京都の変な画家たち…ほか 13 北斎と広重――風景のなにが面白い? 浮世絵の規制から/江戸の旅行ブーム/あれもこれも:葛飾北斎/その後の北斎/火消しから浮世絵師へ:歌川広重/開化錦絵/ジャポニスム/歌川国芳…ほか 14 西洋画の導入――なぜ日本人はミレーと印象派が好き? 南蛮画/西洋画にあって日本画にないもの/洋風画/黒田清輝の帰国/二種類の油絵/東京美術学校西洋画科/裸体画論争/優等生の反逆:萬鉄五郎/西洋美術を遡る:岸田劉生…ほか 15 日本画のゆくえ――西洋画にあって日本画になかったものは? 京都の写生画:円山応挙/明治の日本美術:フェノロサと岡倉天心/新たな日本画/明治の超絶技巧/美術学校騒動と日本美術院…ほか 豆知識①仏像の種類 如来・菩薩・天・明王/豆知識②東洋画の絵具/豆知識③絵は何に描くか おわりに 現代美術 ―― あなたにとっての美術
著者トム・ガニングの初の論文集が日本語版として刊行され、映画、写真、アニメーションにおける「動く」イメージの視覚文化論を展開しています。ガニングは、映画をアニメーションの一ジャンルとするデジタル化の時代における議論に反論し、写真的リアリティとグラフィックの二項対立を超えた視点を提示します。本書は、2000年代以降の約100篇の論考を精選し、多数の図版を含んでいます。ガニングはシカゴ大学名誉教授で、映像文化の研究を続けています。
この文章は、松嶋雅人による著書の目次と著者情報を紹介しています。目次は「東西のあやし」と「広がるあやし」の二部構成で、各地域や時代の「やし」について述べています。著者は大阪出身で、金沢美術工芸大学と東京藝術大学で学び、現在は東京国立博物館で研究を行っています。
本書は、近代京都日本画史を最新の知見に基づいて解説する入門書で、54名の巨匠の名作をオールカラーで紹介しています。幕末から戦後までの日本画壇の変遷を、主要な時代ごとに分けて詳述しています。著者はそれぞれ文化施設での経験を持つ専門家たちです。
本書は、高橋由一が構想した未完の「螺旋展画閣」について、制度論を通じて近代日本の美術を再考察する内容です。明治洋画の先駆者である由一の事業背景や美術制度の形成過程を詳細に分析し、「美術」という言葉の生成とその時代的意義を明らかにします。この研究は、美術史に大きな影響を与え、第12回サントリー学芸賞を受賞しています。著者は美術評論家の北澤憲昭です。
この書籍は、ポピュラー音楽を理解するための理論を実用的な視点からまとめた教科書です。内容は、読譜や音楽理論の基礎、コードの基本知識、コード・スケールの相互関係、さらにはその応用方法までを網羅しています。著者の北川祐は、音楽教育や理論書の執筆を行いながら、ビッグバンド・ジャズなどの作編曲にも携わっています。
本書は、作家原田マハと漫画家ヤマザキマリがアートへの情熱を語る一冊です。彼らのアートヒストリーや影響を受けたアーティスト、創作の裏話、美術館のおすすめ、絵画鑑賞の秘訣などが紹介され、名画にまつわるエピソードが豊富に盛り込まれています。全6章で構成され、アートの魅力に浸ることができる内容となっています。
本書は、西洋と日本の美術の歴史を図版や解説、コラムを通じて包括的に理解できる内容です。目次は、西洋美術史、日本美術史、さらに詳細な情報を提供するセクションに分かれており、色彩や画材、技法についても触れています。
19世紀後半のパリ、美術界で活躍する画商・林忠正と助手の重吉が浮世絵を売り込む中、日本に憧れる無名画家ゴッホと彼を支える画商テオとの出会いが「世界を変える一枚」を生み出す。孤高の男たちの矜持と愛を描いたアート・フィクション。著者は原田マハ。
現代美術の入門書。抽象表現主義、ポップアート、ミニマリズム、フェミニズム・アート等の定番からポスト3.11の美術まで。 現代美術の入門書。ポップアート、抽象表現主義、ミニマリズム、コンセプチュアル・アートから、フェミニズム・アート、メディア・アート、写真、建築、工芸を包括し、ポスト3.11の美術まで、10人の気鋭による論考。 現代アートの入門書。ポップアート、抽象表現主義、ミニマリズム、コンセプチュアル・アートから、フェミニズム・アート、メディア・アート、写真、建築、工芸を包括し、ポスト3.11の美術まで、なぜそれが出現したのかを真剣に考えることによって、私たちの社会が抱える問題の本質がえぐり出される。いつの時代にも「現代アート」は存在する。アートは常に私たちの価値観を攪乱し、制度に揺さぶりをかけ、視座の見直しをせまるのだ。 1 美術作品とそうでないもの――デュシャン、ポップ・アート、クーンズ 田中正之 2 メディウムの探求 ――ミニマリズムとポストミニマリズム 松井勝正 3 抽象表現主義と絵画、あるいは絵画以上のもの――ポロック、ニューマン、ロスコ 沢山 遼 4 コンセプトが前景化するとき――コスースから始める 橋本 梓 5 美術における身体表象とジェンダー――眼差しの権力とフェミニズム・アート 天野知香 6 アート&テクノロジーの様相――メディア・アート、マクルーハン、パイク 畠中 実 7 現代アートと写真 ――アプロプリエーションの時代からティルマンスまで 土屋誠一 8 現代建築を語るために――モダニズムと5つの建築をめぐって 岡山理香 9 現代工芸とデザインの地平――クレイワークとうつわ 木田拓也 10 ポスト3.11の美術――美術と社会はどう関わるべきか 蔵屋美香 参考文献 アーティスト・グループ/人名索引
近代日本演劇史における〈小劇場演劇〉の位相 アングラ演劇とその時代 回想の遠近法、転形劇場と太田省吾と クニのレキシを語ること "3・11"以後の寓話/フィクション 読解と翻訳 演劇批評の「死滅」に抗うために ドイツ語圏と日本の小劇場演劇 韓国の小劇場演劇 小劇場演劇の現在・未来
「美術史」に関するよくある質問
Q. 「美術史」の本を選ぶポイントは?
A. 「美術史」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「美術史」本は?
A. 当サイトのランキングでは『鑑賞のための 西洋美術史入門 (リトル キュレーター シリーズ)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで107冊の中から厳選しています。
Q. 「美術史」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「美術史」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。