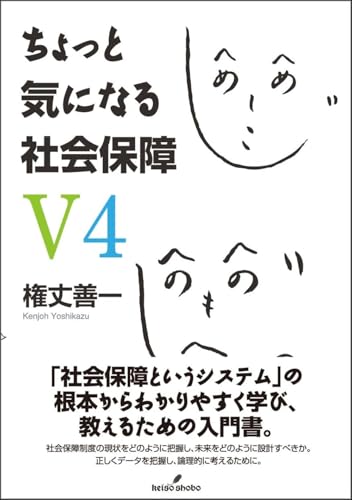【2025年】「社会保障制度」のおすすめ 本 143選!人気ランキング
- わかりやすい社会保障制度 改訂版 ~はじめて福祉に携わる人へ~
- 図解即戦力 社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本
- 15歳からの社会保障 人生のピンチに備えて知っておこう!
- 現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド: ケアマネ・相談援助職必携
- いちばんわかる! トクする! 社会保険の教科書
- 図解入門ビジネス 最新 生命保険の基本と仕組みがよーくわかる本[第3版]
- 書類・様式名からすぐ引ける 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本
- NEWよい保険・悪い保険2023年版 (タウンムック)
- 社会保障制度指さしガイド (2024年度版)
- 現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド 2022年版: ケアマネ・相談援助職必携
この書籍は、日常生活で直面する困難を描いた10人のストーリーを通じて、社会保障制度について学ぶことができる内容です。家族や健康、仕事などの問題に対処するための知識が、読者や大切な人を守る力になることを伝えています。著者は社会福祉士であり、社会保障制度の改善に取り組んでいます。
<<援助職のための 超わかりやすい社会保障制度解説>> ①生活保護、②障害者福祉、③医療保険、④権利擁護、⑤年金、⑥子ども家庭福祉の 6つの社会保障制度について、その概要やサービス利用の流れ、活用事例を豊富なイラストと図表で わかりやすくまとめました。ケアマネジャーや相談援助職必携の1冊です。 ▶“オールカラー”でわかりやすい! 『社会保障制度活用ガイド』は、2022年版より、オールカラーに生まれ変わりました! 2021年版までも好評だった、手続きの流れなどに関する図表がさらに見やすくわかりやすくなりました。 既に2021年版を持っているという方も、要チェックです! ▶現場の実践に即した活用ポイントを紹介! 範囲が広く、必要な書類・手続きも複雑な社会保障制度。 「こんなとき、どんな制度が使えるの?」 「どこに相談すればいいの?」 「申請に必要な書類は?」 こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 本書では、フロー形式で求められる手続きや書類を整理。すぐに実践に活かせる内容が満載です。 ▶新たに「子ども家庭福祉」に関する情報を掲載! 生活困窮に陥っているひとり親家庭や、親に代わって祖父母が孫を養育しているケースなど、 家族のあり方は多様化しています。 相談援助職が押さえておきたい、事態の改善へとつながる社会資源に関する情報を網羅しました。 【主な目次】 早わかり! ケース別活用できる制度一覧 各制度の最新の動きをチェック! 第1章:生活保護 第2章:障害者福祉 第3章:医療保険 第4章:権利擁護 第5章:年金 第6章:子ども家庭福祉 早わかり! ケース別活用できる制度一覧 各制度の動きをチェック! 第1章:生活保護 第2章:障害者福祉 第3章:医療保険 第4章:権利擁護 第5章:年金 第6章:児童福祉
本書は、社会保険に関する基礎知識を易しく解説した超入門書で、特に総務・労務や経理担当者に役立つ内容です。図解を用いて社会保険制度を分かりやすく説明しており、初心者でも理解しやすいように工夫されています。2011年の初版以来、改訂を重ね、最新の制度変更にも対応した「改訂6版」として新版化されています。医療や介護・福祉分野の現場や社会保険労務士を目指す人にも適しています。著者は、社会保険労務士としての経験を持つ専門家です。
この本は、ケースワークにおける援助関係を説明、定義、分析することを目的としています。目次は二部構成で、第一部では援助関係の本質や形成の原則について述べ、第二部では具体的な原則(個別化、感情表現、情緒的関与、受容など)を詳しく解説しています。著者は、ソーシャルワークや福祉学の専門家たちです。
この本は、医療、年金、介護、労災、失業、障がい、子育て、生活保護などの社会保障制度を、悩み別のフローチャートを使って分かりやすく説明しています。イラストや図表を用いて、複雑な制度を誰でも理解できるように工夫されています。最新の法改正にも対応しており、役所での相談時に役立つ内容が盛り込まれています。著者は福岡大学法学部の教授で、社会保障法の専門家です。
この書籍は、訪問看護ステーションの開設・運営・評価に必要な最新情報を網羅しており、2021年の介護報酬改定に対応しています。経営関連の内容が刷新され、感染症や災害対応に関する業務継続計画(BCP)やICTセキュリティ対策についても新たに取り上げています。また、科学的介護情報システム(LIFE)の活用についても触れています。新規開設を含む全ての訪問看護ステーションにとって必携の一冊です。
本書は、給与計算や病気、出産、失業、年金受給などに関連する社会保険・労働保険の制度や手続きを分かりやすく解説しています。内容は、社会保険・労働保険の全体像、労働保険や各種保険のしくみについての詳細が含まれており、最新の改正にも対応しています。著者は特定社会保険労務士の小島彰氏で、労務相談やIPO支援など幅広い業務を手掛けています。
この文章は、ソーシャル・ケース・ワークに関する目次を示しており、ソーシャル・ケース・ワークの定義、相互依存、個人差、意図的な行為の基礎、家庭や学校、職場、病院、裁判所との関係、ソーシャル・ワークの形態と相互関係、そしてケース・ワークと民主主義についての内容が含まれています。
信頼できる最新情報と,叙述のわかりやすさが好評のロングセラー・テキスト。基本的な考え方を通して制度の立体的理解へと導く。 信頼できる最新情報と,叙述のわかりやすさが好評のロングセラー・テキスト。「なぜ」「どうして」と考えていくうちに,制度の構造を立体的に理解できる。1つの制度の構造がつかめたら,比較して学ぶことにより社会保障の全体像が立体的に見えてくる決定版。 序 章 社会保障の見取り図 第1章 医療保険──病気やけがをしたら 第2章 生活保護と社会福祉制度──人らしい生活を保障する 第3章 介護保険──介護サービスを利用しやすく 第4章 年 金──老後の生活費は 第5章 雇用保険──失業したら 第6章 労働者災害補償保険──働く場でけがをしたら 第7章 社会保険と民間保険──2つの保険,その特徴は 第8章 社会保障の歴史と構造
この本は、社会保障に関心のある人々に向けて、複雑な社会保障制度をライフサイクルに沿って解説しています。内容には、手続き方法や問い合わせ先など、役立つ情報が豊富に含まれています。目次には妊娠・出産から高齢者、死亡に至るまでの各章が設けられています。
初学者から、社会人の学びなおしまで。 社会保障のキホンを学びながら、問い直す、新しい入門書! 【本書の特徴】 (1)“リアル“にこだわった解説 これから社会に出る学生・若者や、いままさに職場や家庭で困っている人など、さまざまな人が現実に遭遇する問題に焦点をあてながら、社会保障の制度やもととなる考え方について解説しています。ぜひ自分自身を重ね合わせながら読んでみてください。 (2)わかりやすい叙述と読みやすいレイアウト 平易な文章なのはもちろん、カラフルなレイアウトで、図版やミニコラム、注釈なども充実しています。社会福祉士や看護師の国家試験でよく出る重要ポイントも押さえていますので、試験対策のための最初の一冊としても最適です。 (3)最新の論点も収録 社会保障制度は、個人や国家、社会、時代の変化により、つねにゆらいでいる存在でもあります。たとえば「ギグワーカーは労災保険に加入できるのか?」など、最新の論点を可能な限り盛り込みました。 はじめに 第1部 社会保障って何だろう? 第1章 社会保障の目的・機能・法体系 ❶社会保障って、そもそも何なの?―社会保障の定義 ❷社会保障は何を目指しているの?―社会保障の「目的」 ❸社会保障を支えるもの―社会保障の「理念」 ❹社会保障があると、どんないいことが?―社会保障の「機能」 ❺社会保障といっても、いろいろある?―社会保障の全体像・範囲 ❻社会保障と憲法・法律上の権利 ❼社会保障の救済手続き 第2章 社会保障の歴史と現代社会の変化 ❶ヨーロッパ ❷日本 ❸社会保障を取り巻く環境変化 ❹社会保障はどこへ向かっているの? 第3章 社会保障の財政 ❶国の「おサイフ事情」を知ろうとすること ❷社会保障の財源 ❸国と地方、それぞれの費用負担 ❹社会保障関係費と社会保障給付費のちがい ❺社会保障給付費の最新データ ❻「公共財」としての社会保障 第4章 保険って何? ❶保険って、そもそもどういうしくみ? ❷民間保険と社会保険の違い 第2部 いざというときの「助け合い」―年金・医療・介護 第5章 年金制度 ❶公的年金って何? ❷公的年金の加入に関するアレコレ ❸公的年金の給付に関するアレコレ ❹公的年金に関するその他の論点 第6章 医療保険 ❶医療保障って何? ❷健康保険制度 ❸国民健康保険制度 ❹高齢者医療制度 ❺医療保障に関するその他の論点 第7章 介護保険 ❶介護保険をめぐる問答 ❷介護保険と高齢者にかかわる要介護認定 ❸介護保険の全体像 ❹地域支援事業 ❺介護保険制度を取り巻く課題 第3部 働くうえでの困りごとには―労災・雇用 第8章 労災保険 ❶労働災害補償制度のしくみ ❷業務上外認定 ❸脳・心臓疾患の労災認定―いわゆる「過労死」 ❹精神障害の労災認定 ❺通勤災害 ❻その他の労災補償制度 第9章 雇用保険 ❶雇用と社会保障 ❷失業時の所得保障―求職者給付 ❸雇用継続・安定のための給付―雇用継続給付、就職促進給付、教育訓練給付 ❹失業の予防のために―雇用保険2事業 第4部 生きているとイロイロあります 第10章 生活保護 ❶「生活保護」ってなあに? ❷不服審査請求と今日的課題 第11章 社会福祉 ❶「社会的弱者」ってだれ? ❷児童福祉 ❸障害者福祉 ❹高齢者福祉 ❺各分野の棲み分け 第12章 災害福祉 ❶増え続ける災害のなかで ❷自然災害と社会保障 ❸コロナ禍と社会保障 ❹見えてきた問題点 第13章 住まいの支援 ❶住宅って必要ですか? ❷日本の住宅政策 ❸なぜ日本の住宅政策は乏しいのか ❹量から質の時代へ ❺住宅だけ提供すれば問題は解決するの? 第5部 社会保障を、いろんな角度から考えてみよう 第14章 貧困・格差・平等論 ❶餓死するまで助けてもらえない現実 ❷「本当の貧困者」「本当に助けを必要としている人」って誰? ❸大学や子育てはぜいたく? ❹「弱者の救済」と「普遍的な福祉」の違い 第15章 多国籍社会の社会保障 ❶「外国人」ってだれのこと? ❷社会福祉・社会保障の法政策と外国人 ❸生活保護制度と外国人 第16章 ジェンダー ❶ジェンダー視点からみる社会保障 ❷シングルマザーの社会保障 ❸LGBTQの生活の困難 ❹夜職は女性の社会保障たりうるか おわりに 索引 コラム❶ 社会福祉基礎構造改革とは? コラム❷ 地域包括ケアシステム、どう活かす? コラム❸ ヤングケアラーを沖縄から見ていくと コラム❹ ベーシックインカムは究極の社会保障か? コラム❺ 生理の貧困
日本の社会保障はなぜ使いにくいのか。複雑に分立した制度を整理し、その根底に渦巻く「働かざる者食うべからず」の精神を問う。 日本の社会保障はなぜこんなに使いにくいのか。複雑に分立した制度の歴史を辿り、日本社会の根底に渦巻く「働かざる者食うべからず」という倫理観を問いなおす。 病気やケガをしたとき、出産や育児、そして介護が必要になったときの生活を保障する社会保険。働けなくなったときや老後の生活を支える年金制度。毎月の給料から天引きされているものの、いざというとき自分がどの給付を受けられるのかわかりにくく、申請するのもどこか後ろめたい。日本の社会保障はなぜこんなにも使いづらいのか。複雑に分立した制度の歴史から、この国の根底に渦巻く「働かざる者食うべからず」の精神を問い、誰もが等しく保障される社会のしくみを考える。 はじめに 複雑で使いにくい社会保障/問題はどこにあるか/法律学というアプローチ/社会保障と法解釈/「勤労の義務」を問いなおす/人々の意識と法的権利/理想の社会保障に向けた共同作業 第一章 なぜ働き方によって社会保障が違うのか――労働者と自営業者 1 社会保障の全体像 老後四八八〇万円問題?/「労働」とは何か/「労働者」と「自営業者」/日本の社会保障の体系 2 公的年金における違い 公的年金の構造と老齢期の差/同業者同士での対応の限界 3 医療における違い 公的医療保険の構造/自営業者への対応 4 失業時・雇用継続対策における違い 雇用保険の適用関係による違い/求職者支援制度 5 労働災害における違い 労災保険という仕組み/労災保険の適用の有無による違い/労災保険への特別加入 第二章 なぜ働き方で分立しているのか――四つの社会保険 1 制度がつくられた時代 戦後日本の就業構造/農林業が中心だった時代 2 公的年金はなぜ分かれたか――国民年金と厚生年金 公的年金の歴史/労働者年金の設立と厚生年金への改組/国民年金の設立をめぐって/自営業者の所得を把握するのは難しい?/なぜ公的年金は分かれたか 3 公的医療保険はなぜ分かれたか――国民健康保険と健康保険 現在の公的医療保険/国民健康保険の制定・改正をめぐって/なぜ自営業には傷病手当金等がないか 4 雇用保険はなぜ自営業者には適用されないか 雇用保険とは何か/「自発的な」失業? 5 労災保険はなぜ自営業者には適用されないか 労災保険とは何か/特別加入とその例外性 6 社会保険はなぜ分かれたか 制度分立の理由/労働者中心の社会保障 第三章 なぜ使いにくいのか――社会保障と情報提供義務 1 社会保障と情報提供義務 申請しないと給付は受けられない?/情報提供義務をめぐる先駆的裁判例/その後の裁判例 2 行政以外の情報提供義務 民間主体と情報提供義務/行政の肩代わり? 3 他分野との比較 企業年金分野との違い/厚生年金基金と情報提供義務/確定給付年金と情報提供義務/社会保障法領域との比較 4 情報提供義務のどこが問題か 情報提供義務の意義/情報提供義務の限界 第四章 生活保護のうしろめたさ――社会保障と「勤労の義務」 1 生活保護を受給できるのは誰か 働かなくても生活保護を受けられる?/「稼働能力」とは何か 2 行政による「指導・指示」 受給中は「指導・指示」を受ける/働きながら生活保護を求めたXさんの事案/職業選択の自由?/裁判所の判断内容/「勤労の義務」と生存権 3 生活保護と不正受給 最低生活費はどう決まるか/不正受給は増えているのか/不正受給の事案/不正受給の背景にあるさまざまな事情/「働くこと」をめぐる規範意識 4 「勤労の義務」という精神 法の根本にある「勤労の義務」/「勤労の義務」という倫理観 中間のまとめ 「勤労の義務」という呪縛 「勤労の義務」と生活保護/「勤労の義務」と社会保障/「勤労」の中身?/時代状況の変化と「勤労」/「働かざる者食うべからず」という倫理観/倫理観が権利を阻害する/問題の根本はどこにあるか 第五章 「勤労の義務」の意味―日本国憲法制定時の議論を読む 1 なぜ「勤労の義務」を検討するか 「勤労の義務」規定と法的な効力/法解釈に唯一の正解はない 2 日本国憲法制定時の帝国議会の議論 帝国議会の推移と衆議院本会議での議論/衆議院帝国憲法改正委員会での議論 3 衆議院帝国憲法改正小委員会による勤労義務の挿入 小委員会の構成と生存権への言及/「勤労」か「労働」か/「勤労」とは何か/「法的義務」か「道徳的義務」か/道徳的義務としての見解の一致/文言の確定 4 勤労の義務の法的意義 イデオロギーを超えた合意/「勤労」と「義務」 第六章 働くことと社会保障を切り離す 1 変化する働き方 働き方と社会保障の関係を問いなおす/非正規労働者などの状況/変化する自営業者の就業実態/労働者という働き方の変容 2 社会保障をめぐる論争史 公的年金――民主党の年金一元化案/医療保険――コロナ禍による部分的な実現/雇用保険とその周辺をめぐる動向/労災保険における特別加入 3 働くことと社会保障を切り離す 依然として残る労働者中心主義/働き方の順位付けと法解釈問題/「働くこと」と社会保障を切り離す/技術的な問題 終章 新しい社会保障のために 1 現行制度とどうつなげるか 問題点のおさらい/現行制度をベースとした年金と医療の構想/現行制度をベースとした雇用保険の構想/現行制度をベースとした労災保険の構想/技術的な問題をどう乗り越えるか/複雑であっても利用しやすい社会保障/生存権の実現―「働かざる者食うべからず」を問いなおす 2 まったく新しい社会保障へ 社会保険を編みなおす/最低生活保障を編みなおす ブックガイド あとがき 参考文献
本書は、中小企業の経理・労務に関する実務マニュアルで、2024年4月の法改正に対応しています。初めて経理を担当する人向けに、基本知識や年間業務スケジュールを解説し、給与計算や賞与計算の実務も詳述しています。さらに、年金や健康保険、雇用保険、労災保険、年末調整、ケース別手続きについても具体的に説明し、届出書式の記入例を多数掲載。実務に役立つ情報が網羅されています。著者は人事・総務の専門家で、実務経験に基づいた内容となっています。
年金、医療、介護保険……。現状と今後を分析する。 年金、医療、介護。複雑でわかりにくいのに、この先も不透明。そんな不安を解消すべく、ざっくりとその仕組みを教えます。さらには、労災・生活保障の解説あり。
本書は、地域共生社会の実現に向けた介護保険法等の改正(令和2年改正法)を詳しく解説しています。改正法は、介護保険制度の見直しや市町村の支援体制の構築を目的としており、令和3年4月からの実施内容を図表で視覚的にまとめています。主な改正点には、介護予防の推進、保険者機能の強化、地域包括ケアシステムの推進、認知症施策の強化、持続可能な制度の構築が含まれています。また、社会福祉法の改正による新たな支援体制の整備も紹介されています。
『訪問看護ステーション必携』は、訪問看護ステーションの運営に必要な介護保険と医療保険の業務を解説したガイドです。ステーションの開設から訪問看護の実施、請求手続きまでを図表を用いてわかりやすくまとめています。また、業務に関連する様式や法令、通知を網羅しており、介護保険制度の概要やサービスコード表も含まれています。
この書籍は、相談面接技術に関する内容を扱っており、主に以下の三つの章で構成されています。第一章では、面接の環境や時間の使い方について説明し、第二章では面接技術の具体的な方法を紹介しています。第三章では、逐語的に相談面接技術を学ぶことに焦点を当て、実際の面接の進め方や援助関係の構築について述べています。著者は岩間伸之で、大阪市立大学の准教授であり、社会福祉学の専門家です。
保険会社が教えない本当の選び方 生命保険は「妻」を中心に、が正解! 日本で数少ない「保険評論家」として有名な著者がはじめて書き下ろす、保険見直しに潜む罠から損得、見直しのポイントまでわかりやすく教えてくれる本。 第1章 保険の見直しに潜む大きなカン違い 第2章 見直すなら「妻」を中心に、が正解! 第3章 20年後に後悔しない保険商品選び 第4章 担当者が言わない本当の保険の選び方 第5章 老後の不安に効く正しい保険選び 巻末付録 ちょっと聞きにくい保険のQ&A
この書籍は、社会福祉事務所や自治体の相談業務に従事する人々が、相談者のニーズに応じた適切な社会サービスを紹介できるように、さまざまな社会保障制度をまとめた実務書です。2025年版では、診療や障害、介護報酬の改定に加え、最新の施策情報を提供し、未施行の改正内容も参考として掲載しています。主な目次には、高齢者、障害者、児童、生活保護など、幅広い福祉関連のテーマが含まれています。
この文章は、援助職者に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、援助職者の基本的な視点や援助関係、アセスメント、相談面接のプロセス、高齢者への援助、燃えつき防止策、介護の現実、ケアマネジメントについての章が並んでいます。著者の渡部律子は、社会福祉学や心理学の専門家で、日米での臨床経験と教育歴を持っています。
この書籍は、社会保障のあり方が日本の未来に与える影響について論じたもので、元厚労官僚の著者が社会保障制度の改革や維持の必要性を提起しています。内容は、社会保障の基礎、税改革の課題、年金や医療・介護の維持、少子化対策の家族支援、経済・財政の立て直し、そして民主主義のための社会保障についての考察が含まれています。著者は数々の政策を担当し、社会保障と税制の一体改革に関与した経験を持っています。
創業から15年で年間売上30億円、社員数600人超! 訪問看護のパイオニアは、いかにして急成長を遂げたのか。 独自の高品質サービスで高収益を生み出し、 東京都城南エリアで最大規模の在宅医療事業者へ拡大した ソフィアメディ株式会社の創業者が明かす事業成功の秘訣。 地域シェアNo.1を獲得するための営業戦略、マーケティングの判断基準、 女性スタッフが輝く職場環境づくり、長期事業計画の立て方など、 在宅医療・介護サービスの経営者・従事者が知りたい経営ノウハウが満載! 第1章 訪問看護の業界事情と事業成功の基本条件 1 経営の実務目線 2 ソフィアメディ創業時の経営戦略 3 質の高さは利益に直結する 4 儲かる訪問看護ステーション3つの秘訣 5 スケールメリットで経営の安定化を図る 6 専門職との一体感・人間関係バランスの取り方 7 商圏の考え方と市場占有率の特性 第2章 訪問看護ステーションの立ち上げ方 安定・成功への方策 1 マーケティングの判断基準 2 競合の実情把握と手の打ち方 3 売上配分比率と概算損益計算書で経営のパターンを検討する 4 次年度の売上配分を検討する3つのモデルケース 5 訪問看護ステーションにおける訪問リハビリの考え方とリスクヘッジ 6 内装や什器、備品、IT設備などデコレーションのこだわり 7 女性8割の医療職集団のマネジメント要領 第3章 地域シェアNo.1を実現するための社長の営業・販売姿勢 1 社長自らがお客様のところを回る 2 お客様の要求を掴む(お客様や紹介先、地域活動からの情報収集等) 3 得意先をABC分析に基づき判断する 4 ランチェスター戦略を踏まえた営業戦略 5 営業方法を駆使して差別化 清掃ボランティアの恩恵 6 クレーム処理とトラブル対処の徹底 第4章 内部体制づくりと現場環境整備の要諦 1 内部体制のつくり方 2 人事・総務部門の体制づくりにおけるポイント 3 組織体制と現場環境の整備 4 訪問看護・リハビリにもICT化の波 5 ソフィアメディにおける問題解決の実務 第5章 訪問看護ステーションの繁栄に向けた社長の経営計画 1 ただの熱い想い、粗野な望み、漠然とした夢を経営理念に昇華させる 2 戦略を構成する経営思想と実務の概念化 3 訪問看護ステーションの超簡略長期事業計画のつくり方 第6章 ソフィア経営塾で将来の幹部・起業家を育成 1 健全経営を継続できる経営者を育成する 2 弟子の成長が何よりうれしい
労働・社会保険法規を表欄形式でまとめた実務マニュアルで、令和6年4月施行の裁量労働制やフリーランス新法、改正育介法に関する内容を含んでいます。構成は「労働法規の部」、「社会保険の部」、「関連法規の部」に分かれ、巻末には手続き一覧が付いています。最新の法令に対応し、労務相談にも役立つ内容となっています。
この入門書は、健康保険と厚生年金保険に焦点を当て、社会保険の仕組みと給付内容を初心者向けに詳しく解説しています。内容は、健康保険の給付(診療、療養費、傷病手当金など)や年金給付(老齢、障害、遺族給付など)、手続き、電子申請、関連する制度(国民健康保険、介護保険など)について網羅されています。また、年金機関や相談窓口の情報も提供されています。
生活保護、年金、医療、公衆衛生、介護保険、労災保険と雇用保険、子育て支援、財源としての消費税など、その最新事情から課題まで。 生活保護、年金、医療、公衆衛生、介護保険と高齢者福祉、労災保険と雇用保険、子育て支援、障害者福祉、財源としての消費税など、その最新事情から課題まで。 最新の法改正から判例、いま指摘される高額療養費などの課題まで。 社会保障の全体像をこの一冊で把握する 年金、介護、医療、労災、障害者福祉……現状と展望 私たちはいつ、病気で働けなくなったり、障害を負ったり、会社が倒産して仕事を失ったりするかわからない。個人の努力ではどうしようもない場面に遭遇した時にも健康で文化的な最低限度の生活が維持できるように憲法の生存権を保障する仕組みが社会保障だ。自分の力や家族や地域での支えあいではどうにもならないことが多いからこそ、この仕組みが必要である。では、法律と運用はどうなっているか。生活保護、年金、医療、公衆衛生、介護保険と高齢者福祉、労災保険と雇用保険、子育て支援、障害者福祉、社会保障財源としての消費税など、その仕組みと財政の最新事情から課題まで網羅する一冊。 序章 広がる貧困と生存危機 第一章 社会保障とは何か 1 社会保障の発展史 2 社会保障の定義と内容 ── 国民の生存権と国の義務 3 主要5制度 ── 公的扶助、社会保険、社会福祉、社会手当、公衆衛生 第二章 生活保護(公的扶助) 1 生活保護の現状と攻撃されるセーフティネット 2 どのような場合に、生活保護が受けられるのか ── 基本原則と仕組み 3 「健康で文化的な最低限度の生活」の水準とは? ── 保護の基準 4 8つの法定扶助 ── 生活保護の種類と方法 5 権利救済の仕組みと生活保護裁判のゆくえ 6 生活保護と生活困窮者対策の課題 第三章 年金 1 日本の年金制度の仕組みと特徴 2 給付 ── 老齢年金、障害年金、遺族年金 3 年金財政と年金積立金 4 年金改革の展開 5 年金改革の動向とゆくえ 6 安心できる年金制度の確立に向けて 第四章 医療 1 医療保険のあらましと公費負担医療 2 保険給付と診療報酬制度 3 医療保険財政と保険料 4 高齢者医療と特定健診・特定保健指導 5 病院再編・統合、病床規制 ── 医療提供体制のゆくえ 6 医療制度改革の動向と医療の課題 第五章 公衆衛生 1 重要性が再認識された社会保障としての公衆衛生 2 感染症法 3 予防接種法 4 地域保健法と母子保健法、母体保護法 5 精神保健福祉法 6 機能不全を招いた教訓と公衆衛生の課題 第六章 介護保険と高齢者福祉 1 介護保険のあらまし 2 介護保険財政と介護保険料 3 介護保険制度改革の展開 4 利用者からみた介護保険の問題点 ── 負担増と介護の再家族化 5 事業者・介護職からみた介護保険の問題点 ── 介護報酬減と深刻な人手不足 6 介護保険と高齢者福祉の課題 ── 介護保険から安心の介護保障へ 第七章 労災保険と雇用保険 1 労働保険の現状 2 労働保険と保険料 3 労災認定の仕組み 4 労災保険の給付と社会復帰促進等事業 5 雇用保険の給付と雇用保険事業 6 劣化する雇用と労働保険の課題 第八章 児童福祉・保育と子育て支援 1 児童福祉法 2 保育政策と少子化対策の展開 3 児童手当と児童扶養手当 4 児童虐待を防ぐには 5 保育の規制緩和がもたらしたもの ── 保育士不足と保育事故の増大 6 児童福祉・保育と子育て支援の課題 第九章 障害者福祉と障害児の療育 1 障害者福祉の改革史 2 障害者総合支援法 3 障害者福祉各法と障害者の雇用促進 4 障害児の療育 5 障害者・障害児への社会手当 6 障害者福祉と障害児の療育の課題 ── 重い家族負担の解消を! 第十章 社会保障の財政 ── 税制改革と社会保険改革の方向性 1 社会保障財政の特徴 2 歳出削減の最大ターゲットは社会保障費 3 消費税による財源確保の問題点 4 どんどん増える社会保険料負担の問題点 5 消費税はどこに消えた? 6 税制改革・社会保険改革の方向性 終章 社会保障はどこへ向かうのか 1 財源確保のための税制改革・社会保険改革の実現可能性 2 社会分断を煽る議論に抗して 3 政策転換の岐路
本書は、地域を基盤としたソーシャルワークの理論と実践について、著者の岩間伸之氏が解説しています。「行政」「専門機関」「地域住民」が協力して住民主体のソーシャルワークを展開するための指南書であり、地域の総合相談拠点の取り組みを紹介しています。目次には、本人主体のソーシャルワーク理論、地域を基盤としたソーシャルワークの全体像、総合相談の実践、ソーシャルワークにおける価値についての章が含まれています。著者は社会福祉の専門家であり、理論書として今後の社会福祉の方向性を示しています。
戦後日本の社会保障の形成において社会保障制度審議会(1949?2001年)が果たした機能と役割を分析し、その有識者委員――近藤文二、末高信、大河内一男、隅谷三喜男――の理念が勧告・建議を通じて社会保障の発展に及ぼした影響を論じる。日本の社会保障のあり方に示唆を与える社会政策史。 はじめに 戦後日本社会保障の理念と政策過程 第Ⅰ部 社会保障制度審議会の軌跡 序 第1章 社会保障制度審議会の創設 第1節 設置の契機──ワンデル勧告(1948年)等の指摘 第2節 制度審設置法閣議決定案の作成──日米の交錯した思惑 第3節 法制上の主要論点 (1)制度審の性質 ①独立性の源泉──内閣総理大臣の所轄等 ②能動性と受動性──自らの建議と「あらかじめ」の諮問 ③役割の変遷の根源──所轄と権限の問題 (2)審議対象の範囲 ①法制定時の経緯──思惑が交錯したもう一つの論点 ②具体的な対象の内外──省庁との駆け引きと運用 (3)定めのない設置期限 (4)事務局の設置と幹事 ①事務局の設置──制度審の重要性の表れ ②幹事の扱い──後年の「実益」 第4節 国会議員の参画──社会保障への理解と支持 第5節 委員及び会長の選定──大内兵衛という牽引者 第2章 社会保障制度審議会が果たした役割の変遷 第1節 制度審の審議スタイル──不文律の確立と継続 第2節 制度審の果たしてきた機能と役割 (1)所与の機能──設置法が付与した権限 ①制度所管省庁から離れた立場からの提言等 ②例年の諮問への答申 (2)3期にわたり変遷した役割 (3)データで見る変遷の様子 ①勧告等の数 ②起草委員のシェアの変遷 ③国会での言及 ④小委員会制の変遷 (4)社会保障の成長・成熟と役割の変遷 ①第1期 社会保障の「推進役に回った」時代(創設~国民皆保険・皆年金) ②第2期 社会保障を「育成」する時代(総合調整~昭和の終期) ③第3期 社会保障を「護る」時代(平成前期) ④社会保障の性質と役割の変遷 (5)役割の変遷と政治構造の変質 ①自民党内における部会・族議員の台頭、及び与野党の構図の固定化 ②日本医師会等の一時の「不在」 (6)委員の属人性と役割の変遷──大内兵衛、近藤文二、今井一男 第3章 社会保障制度審議会の歴史の今日的意義 第1節 制度設計の妙と政争の具からの隔離 (1)制度設計に関わる点1──設置法と不文律の継続 (2)制度設計に関わる点2──第2条第2項を設けた意義(定期的な答申の重み) (3)政争の具からの隔離 第2節 制度審の廃止とその後の社会保障政策の展開 第3節 各論への貢献の分析 第II部 社会保障制度審議会委員における社会保障・社会政策の理念 序 第1章 日本における社会保障概念の確立──近藤文二による1950年勧告の起草 序 1950年勧告に向けた理論的格闘 第1節 社会保障概念を導いた論考の概観 第2節 近藤の概念と1950年勧告 (1)社会保障の範囲 ①近藤の系譜的整理と社会保障の範囲 ②1950年勧告と近藤の概念の関係 (2)社会保険中心主義 ①自主的責任の論理 ②社会保険の社会事業化の防止 第3節 時代状況の影響 (1)公衆衛生(特に結核)と貧困の関連 (2)社会主義との距離 (3)GHQの意向 第4節 近藤の論考の意義、及び今日的課題への示唆の追究 第2章 社会保険の本質及び接続領域 ──末高信の社会保障概念と社会保険制度調査会(1946年設立)を中心とした活動 序 末高の画期性と柔軟性 第1節 末高の社会保障概念の分析 (1)社会保険と社会保障の相違 (2)幅広い社会政策概念 (3)社会保険における保険事故の領域と限界 (4)社会保険とその接続領域──社会保障の萌芽 (5)ビバリッジ報告(1942年)と末高との近似性 (6)末高の社会保険概念の変転 第2節 終戦直後期の末高の活動 (1)社会保障研究会、社会保険制度調査会と社会保障制度要綱のまとめ(1947年1 月まで) 178 (2)社会保障制度要綱(1947年10月)への末高の評価 (3)ワンデル勧告(1948年)への末高の共感 (4)1950年勧告と末高──当初の批判,そして後の推進 (5)米国へのシンパシー 第3節 末高の論考と活動の評価 第3章 社会保障の基本理念としての生存権 ──1950-60 年代における近藤文二、末高信、平田冨太郎の論争 序 異なる生存権概念の捉え方 第1節 第1期(1950年前後)における論争 (1)生存権の具体化としての社会保障──末高の所論 (2)基本的人権としての生存権──平田の所論 (3)「生存権」を「生存権」として認めない資本制社会──近藤の批判 第2節 第2期(1960年前後以降)における論争 (1)国の努力義務としての生存権──近藤の提起 (2)生存権を援用した社会保障──末高の所論 (3)生存権を目的とする社会保障──平田の所論 第3節 末高、平田の妥当性 第4節 近藤の意図とその背景 (1)純粋経済学的な視点の貫徹 (2)社会保障充実のための負担の必要 第5節 負担の合理性の意義,権利論の展開という課題 第4章 「労働力の保全・培養」から「新しい社会政策」へ ──1970-80 年代における大河内一男の転回と社会保障制度審議会 序 「大河内理論」と社会保障制度審議会 第1節 「大河内理論」の転回 (1)基本的な考え方の提示 (2)社会政策と社会保障の連続 (3)ライフサイクル、非労働・消費生活、雇用関係以外の者 (4)「働く」を基本理念とした社会政策と社会保障、公的扶助、社会福祉の総合化 (5)資本主義社会での人間観の一貫性 第2節 大河内の転回の制度審への影響の検討 第3節 「総合社会政策」の今日的有効性 補 論 1995年勧告と隅谷三喜男──大河内からの継承と発展、及び射程の限界 序 理論的研究への注力 第1節 会長就任前の隅谷と社会保障(理論への関心) (1)1960年代の隅谷と社会保障 (2)社会保障の理論再訪(1980年の論考) 第2節 「広く国民」の社会保障 (1)「社会保障の新しい理論を求めて」(1989年及び1991年) (2)「広く国民」の社会保障 (3)隅谷の理論の評価──生存権を超える水準の必要 第3節 自立と社会連帯──大河内からの継承と発展 (1)大河内からの継承と発展 (2)理念や哲学の洞察──制度審の意義再訪 第4節 新たな時代への展開と射程の限界 (1)公的介護保険制度創設を提唱した意義 (2)射程の限界──社会保障と雇用政策 第5節 制度各論へのインパクト、隅谷の研究と信仰の関係という課題 おわりに 制度審の指向性と委員の理念が共存する場 あとがき
この書籍は、給与計算や社会保険制度、労働基準法について初心者にも理解しやすく解説しており、ベテランにも役立つ内容です。給与計算と社会保険事務の関連を示し、月ごとの手続きの流れを学べるようになっています。また、令和6年度の最新の法改正に関する情報も網羅しており、特に「定額減税」に関する事務手続きのポイントも解説されています。著者は社会保険労務士であり、実務に役立つ知識を提供しています。
この文章は、地域社会における多様な課題や支援体制についての内容を示しています。具体的には、地域共生社会の実現、福祉ガバナンス、多機関の協働、地域基盤のソーシャルワーク、災害時の支援体制、福祉計画の重要性とその運用、福祉行財政システムに関する章立てが紹介されています。
本書は、社会保険・労働保険に関する手続きや必要書類を、具体的な場面ごとに整理して解説しています。法改正や最新の書式にも対応し、実務に役立つ詳細な記載例を多数収録。企業の担当者や専門家が参照しやすい構成になっており、巻末には参考資料も含まれています。各章では、新規加入手続き、保険料手続き、入社時や退職時の手続き、ケガや病気、出産・育児・介護休業など多様なテーマが扱われています。
この文章は、ソーシャルワークに関する書籍の目次を示しており、以下の7つの章から構成されています。1章では総合的な支援の実践、2章では援助関係の形成、3章ではネットワークの形成、4章では社会資源の活用と調整、5章ではカンファレンス、6章では事例分析・検討・研究、7章では関連技法について述べられています。
この書籍は「ヤングケアラー」、すなわち家族の介護を担う子どもたちに焦点を当て、その実態や支援の必要性を探求しています。著者は、高校生への調査を通じて、日本のヤングケアラーの状況を明らかにし、孤立や負担を抱える子どもたちの声を紹介しています。社会的背景として少子高齢化や家族主義が挙げられ、支援の重要性が強調されています。最終章では、地域や学校、福祉専門職による支援の具体策が提案されています。著者はヤングケアラー研究の第一人者であり、実践的な支援のあり方を模索しています。
この本は、マイナンバーに完全対応した社会保険と労働保険の手続きガイドで、届け出や手続きに関する基礎知識を提供します。働き方改革に基づいて内容が改訂され、実務に役立つ情報が豊富に盛り込まれています。目次が見やすく、必要書類のサンプルも多く掲載されており、初心者でも理解しやすい詳細な解説が特徴です。また、実用的なチェックシートも充実しています。著者は行政書士で、セミナー講師としても活動しています。
本書は、健康保険、厚生年金、国民年金、介護保険、後期高齢者医療などの社会保険制度について、Q&A形式で解説しています。改正法にも対応しており、一般的なケースや特異な事例を通じて、実務に役立つ内容を簡潔に説明しています。各章では、健康保険法や年金制度などの具体的な法律が取り上げられています。
本書は、現代の精神医療の変化を反映した第2版で、特に「統合失調症」への病名変更などの重要な修正が加えられています。ケアの基本もさらに向上され、看護師だけでなく全ての医療者にとって有用な内容となっています。
この本は、税金や社会保険について子どもたちの視点からわかりやすく解説しています。税金の必要性、使い道、種類、そして社会保険の役割についてマンガを交えながら説明し、少子高齢化問題にも触れています。各章には調べ学習のテーマが設けられ、学校の課題や自由研究にも役立つ内容です。著者は元国税専門官で、現在は芸人として活動しながら執筆や講演も行っています。
この書籍は、身体障害認定に関する基準や要領、疑義解釈を障害種別ごとに整理し、診断書の記載例や解説を豊富に収録しています。医師や自治体関係者に向けて、平成30年7月からの視覚障害基準の見直しにも対応した内容となっています。目次には法令や通知、各障害に関する認定事務が含まれています。
トピック欄で問題を提起、基礎知識をわかりやすく解説。社会保障法を最新情報で実践的に学ぶ。最新の法改正に対応した充実の第19版 トピック欄で問題を提起、基礎知識をわかりやすく解説。社会保障法を最新情報で実践的に学ぶ。最新の法改正に対応した充実の第19版 ◆好評テキストが今年も最新アップデート!―初学者から各種試験用まで、幅広く利便の書◆ みぢかなトピックで問題を提起し、最新の基礎知識をわかりやすく解説。第19版では、雇用保険、生活保護の大幅改訂に加え、各章きめ細かく法改正・制度改正等をアップデート。コラムを随所に配し専門的な学習へと導く。英文による留学生のための補論も充実。初学者、ゼミ生、社会人、各種福祉系の資格試験学習に便利。最新の法改正に対応した、毎年改訂の2025年第19版。 『トピック社会保障法〔2025第19版〕』 本沢巳代子・新田秀樹 編 【目 次】 ・第19版 はしがき ◇オリエンテーション ◆1 医療保障 トピック 窓口でもらった診療明細書 1 医療保険の保険給付の種類と内容 医療保険の保険給付の種類 療養に関する給付と業務災害 療養に関する保険給付とその種類(健康保険制度を例に) その他の保険給付 2 保険診療の仕組み 医療機関の開設 保険医療機関の指定 保険診療の仕組み 診療報酬の支払い 3 医療保険の保険関係 医療保険制度の体系 医療保険の保険関係 4 医療保険の保険財源 トピック 国民医療費と医療保険料 医療保険の保険財源 保 険 料 STEPUP ◆2 介護保障 トピック 一人暮らしの祖母の介護 1 給付の手続きと内容 給付の手続き 保険給付の種類と内容 介護サービス提供機関 2 介護保険の保険関係と財源 トピック 介護保険の被保険者証はいつ貰えるの? 介護保険の保険者と被保険者 介護保険の財源と保険料負担 3 介護保険法と老人福祉法の関係 STEPUP ◆3 年金保険 トピック 若者と障害 1 障害年金給付 障害基礎年金 障害厚生年金 例 外 2 老齢年金給付 トピック 年金の保険料を払いたくない! 老齢基礎年金 老齢厚生年金(報酬比例部分) 年金生活者支援給付金 3 遺族年金給付 トピック 遺族年金って必要なの? 遺族基礎年金 遺族厚生年金 4 年金保険の併給調整 遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給 障害基礎年金と各厚生年金との併給調整 5 年金保険の保険関係 世代間扶養と3つのリスク 年金保険の保険者と被保険者 6 年金財源 年金財源と財政方式 免除と納付猶予 年金財源に関する問題点 STEPUP ◆4 労災補償 トピック アルバイトの過労死 1 労働災害―「補償」と「保障」 アルバイトと怪我 アルバイトと「労働者」 「補償」から「保障」へ 2 労災補償・労災保険給付 労災補償と安全衛生体制 労災保険給付 労災保険法の仕組み 業務上・外認定 3 通勤災害 トピック アルバイトと通勤災害 通勤災害の保護 通勤災害該当性 通勤災害と単身赴任・マルチジョブホルダー 4 労災民事訴訟―使用者の安全配慮義務 5 「補償」・「保障」再論 STEPUP ◆5 雇用保険 トピック 退職してはみたものの…… 1 就職や雇用継続を支える給付―失業等給付 求職者給付 就職促進給付 教育訓練給付 雇用継続給付 2 育児休業等にからむ給付―育児休業等給付 3 保険関係 トピック 雇用保険に入れない? 保 険 者 被保険者 適用除外 4 労働保険の適用関係と財源 適用関係 財 源 STEPUP ◆6 子ども支援 トピック 子どもが生まれたら 1 子育て支援と児童虐待への対応 子育て支援 児童虐待の発見 調査・判定 相談援助活動 親子分離 家庭再構築 自立支援 2 サービスの利用(種類や内容) トピック 同じ子育てなのに,利用するサービスが違う? 教育・保育施設 地域型保育事業等 3 サービスの利用関係 教育・保育の利用時間の認定 利用調整 利用可能な施設のあっせん,要請 利 用 料 STEPUP ◆7 家族支援 トピック 先立つものがない 1 子どもの貧困 2 子どもの貧困対策法 3 児童を育む場としての家庭の安定 児童手当 特別児童扶養手当・障害児福祉手当 4 ひとり親家庭の経済的な生活保障 経済的な生活基盤の維持 経済的支援 養育費の支払─私的扶養義務の履行確保 就労を通じた自立に向けた支援 生活支援・子育て支援 5 家族を対象とする諸施策 トピック 家族って何だろう 社会保障制度が前提としてきた家族像 制度横断的な性格 6 家族や児童の概念 家族の概念 児童の概念 STEPUP ◆8 障害者福祉 トピック 大学が提供する合理的配慮とは? 1 障害と障害者―個人モデルから社会モデルへ 国際機関における従来の定義 日本における定義 個人モデルから社会モデルへの障害(者)観の転換 障害者権利条約 障害者法制の見直し 差別禁止と合理的配慮 2 障害者法制の体系 トピック 重度障害者に対する介護サービスは十分か? 障害者基本法 障害者福祉法制 3 障害者総合支援法の概要 目的・基本理念・対象・市町村等の責務 自立支援給付 地域生活支援事業 STEPUP ◆9 社会福祉 トピック 会社によってサービス内容に違いがあるのだろうか? 1 社会福祉における登場人物とその役割 事 業 者 利 用 者 制度の調整役─国と地方公共団体 社会福祉の地域応援団─社協・共同募金・民生委員 2 福祉サービスの提供事業者 事業者の多様化 第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業 社会福祉法人 事業者の公共性 3 福祉サービスの従事者 職種と資格 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 ケア従事者の確保 4 福祉サービスの利用者 トピック 契約って難しそうだけど,わかるのかな? 利用者の選択を支える情報提供に関わる制度 判断能力が不十分な人に対する支援制度 220 契約締結 苦情解決手続 事業者規制と権利擁護 家族によるケア 家族の介護責任 STEPUP ◆10 生活保護 トピック リストラの果てに…… 1 保護の種類および内容 保護の種類および内容 世帯単位の原則 2 生活保護の目的と基本原理 生活保護の位置づけと目的 生存権保障の意義と生活保護 最低生活保障 無差別平等 3 保護の要件と申請・受給 トピック 福祉事務所で 保護受給のための手続き 申請保護の原則 保護の補足性 資産調査 収入認定 保護の実施機関・実施責任 不服申立て 家庭訪問と被保護者の権利義務 施設における保護 生活保護の費用負担 4 生活保護における「自立」 自立助長 就労による自立の促進 5 生活困窮者自立支援法 概要と法の理念 生活困窮者自立支援法に基づく事業と実施主体 STEPUP ◆11 社会保障 トピック 社会保障と社会保険 1 社会保障制度の成立と発展 先進諸国における社会保障制度の成立と発展 日本における戦後の社会保障制度の展開 2 社会保障の目的と機能 社会保障の目的 社会保障の機能と意義 3 社会保障の中心である社会保険の機能と意義 社会保険と民間保険 社会保険とそれ以外の社会保障給付 社会保険と公費負担 4 21世紀の社会保障制度改革 トピック 少子高齢社会と社会保障 経済財政諮問会議と社会保障制度改革 社会保障国民会議最終報告 民主党政権と社会保障改革 第2次安倍内閣と社会保障改革法 第3次安倍内閣と消費税率引上げ ニッポン一億総活躍プランと地域共生社会の実現 全世代型社会保障 STEPUP ◆補論 留学生の皆さんに知ってもらいたい日本の社会保障制度 Major social security programs to know for international students 1. Social Security for foreigners in Japan 2. National Health Insurance 3. Industrial Accident Compensation 4. National Pension system 5. Pregnancy and childbirth Medical examination and notification of pregnancy Unintended pregnancy- counseling, abortion and other options Maternal and Child Health Handbook (母子健康手帳/boshi-kenko-techo) Supports for health check-up and prenatal classes Lump sum payment for childbirth and childcare 6. Birth registration and the Status of Residence of the newborn child Birth notification in Japan Acquiring a Status of Residence (zairyu-shikaku) for the child in Japan Birth registration at Embassy or Consulate of the parent’s home country Childcare for pre-elementary school children 7. Social Security Agreements Elimination of dual coverage Totalization of coverage periods for Old-age Benefits ・事項索引 ・判例索引 ・参考文献
15年にわたるヨーロッパ海外視察調査の成果。イタリア、フランス、ドイツ、オランダの医療と介護の内容と現場での取り組みを紹介。 15年にわたるヨーロッパ海外視察調査の成果。イタリア、フランス、ドイツ、オランダ――4ヵ国の医療、介護、社会保障政策や制度改革の内容と現場での取り組みを紹介。その違いとそれぞれの意義を考察する。 15年にわたるヨーロッパ海外視察調査の成果。 イタリア、フランス、ドイツ、オランダ――4ヵ国の医療、介護、社会保障政策や制度改革の内容と現場での取り組みを紹介。その違いとそれぞれの意義を考察する。 序 視察調査の概要と本書の構成 第Ⅰ部 イタリアの国民保健サービス 第1章 イタリアの医療制度 第2章 家庭医とイタリア医療の課題(ミラノ) 第3章 オスペダーレ・マッジョーレ(Ospedale Maggiore)・ボローニャ――ボローニャ市Auslの地域医療政策 第4章 地区高齢者介護施設と薬局 第Ⅱ部 フランスの医療と介護 第1章 フランスの医療保険制度 第2章 フランスの介護保険と在宅入院制度 第3章 フランス赤十字社アンリ・デュナン病院老年科センター 第4章 フランスの訪問看護 第Ⅲ部 ドイツの社会保障 第1章 ドイツの介護保険 第2章 ミュンヘン・カリタス・ゾチアルスタチオン 第3章 プロテスタント・ディアコニークランケンハウス・フライブルク 第4章 デンツリンゲン・森の自然幼稚園 第5章 ダッハウ強制収容所 第Ⅳ部 オランダの医療と介護 第1章 オランダの医療 第2章 オランダの介護保険 第3章 新しい医療保険制度 第4章 オランダの病院とナーシングホーム――フリースランド州とアムステルダム市の病院視察を中心として
多角的な視座から社会保障法学の発展を目指す学術雑誌、2025年5月刊行の第22号。本号は、3つの特集に7論稿と座談会を掲載。 多角的な視座から社会保障法学の発展を目指す学術雑誌、2025年5月刊行の第22号。本号は、3つの特集に7論稿と座談会を掲載。 ◆多角的な視座から社会保障法学の発展を目指す学術雑誌、2025年5月刊行の第22号◆ 本号は、3つの特集を掲載し、特集1「ソーシャルワーク・ケースワークと社会保障法」として、幅広い執筆陣の論稿4本と座談会を掲載。また、特集2「行動経済学と社会保障法」では経済学者による論稿を掲載。特集3は「コロナ禍における緊急対応と生活困窮をめぐる諸課題―第5回社会保障法フォーラム」として2論稿を掲載。計7論稿と座談会で、本号も充実の刊行。 『社会保障法研究 第22号』 岩村正彦・菊池馨実 編集 【目次】 ◆特集1: ソーシャルワーク・ケースワークと社会保障法 ・日本におけるソーシャルワーク論の到達点と課題/空閑浩人 ・ソーシャルワークの法的分析―実定法におけるソーシャルワークと法的課題/西村淳 ・支援・ソーシャルワークのプロセスにおける協議/前田雅子 ・生活保護行政実務におけるケースワークの機能と課題/池谷秀登 ・〈座談会〉生活保護ケースワークをめぐる課題と展望/菊池馨実・池谷秀登・新保美香・原田大樹 ◆特集2: 行動経済学と社会保障法(その1) ・行動経済学と社会保障法/大竹文雄 ◆特集3:コロナ禍における緊急対応と生活困窮をめぐる諸課題―第5回社会保障法フォーラム(その1) ・新型コロナウイルス感染症の中の生活福祉資金貸付/太田匡彦 ・コロナ禍における子ども・子育て支援と社会保障制度/橋爪幸代
日本の社会保障システムの理念、制度のあり方、将来の課題等をコンパクトに解説する定評あるテキスト。制度改正等に伴う動きをフォローし、最新データを押さえたかたちで改訂。年金、医療保険、介護保険、社会福祉など、身近な生活に関わる重要な仕組みを丁寧に説明する。 まえがき 第1章 日本の社会保障システムの理念(渋谷博史:東京大学名誉教授、中浜 隆:小樽商科大学商学部教授) 第2章 年金システム――市場経済と労使関係を基盤として(吉田健三) 第3章 医療保障システム――国民皆保険と持続可能性(長谷川千春) 第4章 介護保険と高齢者福祉――財政調整と財政資金の投入(加藤美穂子) 第5章 社会福祉システム(木下武徳、渋谷博史) 終章 21世紀の福祉国家のグローバル展開(渋谷博史、河﨑信樹:関西大学政策創造学部教授) あとがき 索引
社会保障分野における判例教材の決定版。重要判決を多数取り入れるとともに,収録判例を更に厳選し件数を絞り込んだ。 社会保障分野における判例教材の決定版。第5版刊行以降に出された重要判決を多数取り入れるとともに,収録判例を更に厳選し件数を絞り込んだ。全113件中32件が新収録・差替判例。解説内容にも一層の充実を図った,学習者必携の一冊。 Ⅰ 社会保障と憲法 生存権と生活保護基準,老齢加算廃止と生活保護法・憲法25条,年金減額改定の憲法適合性など(12件) Ⅱ 医 療 被保険者資格取得確認の基準日,混合診療,医療市場への独占禁止法の適用など(25件) Ⅲ 年 金 障害基礎年金の支給要件と「初診日」の意義,中小企業退職金共済法の配偶者の意義など(17件) Ⅳ 労 災 歓送迎会参加後の送迎行為の業務遂行性,特別加入の保険関係の成立など(17件) Ⅴ 雇用保険 雇用保険法上の労働者,事業主に対する助成金等の返還請求など(5件) Ⅵ 生活保護 永住外国人と生活保護法の適用,生活保護法にいう「世帯」の意義など(16件) Ⅶ 児童福祉・児童手当 児童相談所長の行政指導による両親への面会通信制限と国家賠償責任など(9件) Ⅷ 障害者福祉 障害福祉サービスの支給量,ボランティアの民事責任など(8件) Ⅸ 介護保険・老人福祉等 介護保険法22条3項による介護報酬の返還請求など(4件) 計113件
わが国の社会保障法の概要をコンパクトにまとめた標準テキスト。変動を続ける社会保障の諸制度を過不足なく、わかりやすく解説。 わが国の社会保障法の概要をコンパクトにまとめた,定評あるスタンダードテキスト。変動を続ける社会保障の諸制度を過不足なく,わかりやすく解説する。前版刊行後の制度見直しや法改正に対応して内容を改め,新たなテーマのコラム等も加えた。 第1章 社会保障とその特質 第2章 社会保障法の理論と課題 第3章 年 金 第4章 社会手当 第5章 医療保障 第6章 労働保険 第7章 社会福祉 第8章 公的扶助