【2025年】「機械製図」のおすすめ 本 117選!人気ランキング
- はじめて学ぶAutoCAD 2025 作図・操作ガイド 2024/2023/2022/LT 2021/2020/2019/2018/2017対応
- 図面の描き方がやさしくわかる本
- JISにもとづく機械設計製図便覧(第12版)
- はじめての治具設計
- はじめて学ぶ AutoCAD 2022 作図・操作ガイド LT2021/2020/2019/2018/2017/2016対応
- JISにもとづく 機械設計製図便覧(第13版)
- AutoCAD LT 標準教科書 2022/2021/2020/2019/2018対応
- 図面って、どない読むねん! LEVEL 00 第2版―現場設計者が教える図面を読みとるテクニック―
- 初心者のための機械製図(第5版)
- はじめてのAutoCAD 2025/2024 作図と修正の操作がわかる本 AutoCAD LT 2025~2009にも対応!
本書は、AutoCAD 2025の入門書で、初心者が作図の基本操作をスムーズに習得できるように構成されています。1本の線や円の描き方から始まり、図形の編集や補助機能の使い方を段階的に学べる内容です。練習問題や平面図の作成例も提供され、効率的な作業方法にも触れています。AutoCADの基本操作から印刷までを丁寧に解説しており、他のバージョンにも対応しています。著者はCADの経験豊富なインストラクターです。
この書籍は、機械製図の基本ルールや描画のコツを学ぶためのガイドです。内容は、図面の描き方、寸法記入のルール、幾何公差、材料や溶接の表示方法など多岐にわたります。著者は生産技術コンサルタントの西村仁氏で、豊富な実務経験を持っています。
この書籍は、エンジニア向けに60年間の経験を基に、機械の設計、製図、製作に必要な知識を提供します。最新のJIS規格に準拠しており、さまざまな設計要素や工作知識について詳しく解説しています。目次には、数学、力学、機械材料、設計要素、CAD製図などの重要なトピックが含まれています。
本書は、モノづくり現場における「製造品質」「製造原価」「生産期間」を向上させるための治具設計に関する入門書です。治具は作業を楽にし、結果として品質向上、作業効率化、コスト削減を実現します。著者は生産技術コンサルタントの西村仁氏で、治具の導入目的や設計のコツなどを解説しています。
初心者から実務者まですぐに役立つ!25年以上にわたる企業講習と職業訓練校での教育実績に基づく解説の決定版! 初心者から実務者まですぐに役立つ! 25年以上にわたる企業講習と職業訓練校での教育実績に基づくAutoCAD LT解説の決定版! 初心者から実務者まですぐに役立つ! 25年以上にわたる企業講習と職業訓練校での教育実績に基づくAutoCAD LT解説の決定版! スマホ対応の音声付き動画(400本以上)とクラウド教科書、サンプルプログラムをWeb専用ページで無料で利用可能 最新のAutoCAD LT 2022完全対応版、本文オールカラー、524頁。
「図面って」シリーズの「レベル00」にあたる本の第2版。著者の10年間の指導経験を反映し、内容をアップデート。図面の基本知識や読み解き方、特殊な図示法、寸法記号、公差、幾何公差、溶接記号、専門用語、図面管理に必要な記号について解説。著者は山田学。
本書は、2020年版の最新JISに基づく機械製図の基礎知識を「網羅的に」「やさしく」解説しています。視覚的に理解できるよう図面にポイントを示し、実践的な題材を用いてものづくりを意識した学びを提供します。正しい図面の描き方や間違いやすい例を示すことで、基礎をしっかり身につけることができます。著者は同志社大学の名誉教授などで、内容はISOに準拠した図面作成の要点を含んでいます。目次には、図形、寸法、幾何公差、材料記号など多岐にわたるテーマが含まれています。
「これからはじめるAutoCADの本」は、最新のAutoCAD/AutoCAD LT 2020に対応した入門書で、初心者向けに基本的な作図方法を丁寧に解説しています。サンプルファイルのダウンロードが可能で、実践を通じて学べる構成になっています。内容は、基本操作、図形作成、修正、文字や寸法の記入、現尺および縮尺の図面作成など多岐にわたります。著者は長年のCAD講師経験を持つ稲葉幸行です。
本書は、機械設計エンジニアが複雑な動作を実現するためのメカニズム設計のヒントを提供します。さまざまな機構を目的や動作に基づいて分類し、比較・選択を容易にする内容で、具体的な動作解析も含まれています。若手からベテラン設計者まで幅広く活用できる資料で、直線運動や回転運動など8つの章に分かれています。著者は岩本太郎氏で、機械工学の専門家です。
せっかくAutoCADを持っているなら3Dを使わないなんてもったいない!汎用CAD「AutoCAD」に標準搭載されている「3D機能」にフォーカスした解説書。AutoCADの3D機能を使って「やりたいこと」の目的別にその操作方法をやさしくていねいに解説します。「すでにAutoCADで2次元の図面は描いているが、3D機能にも触れてみみたい」「AutoCADの3D機能を使い始めたが、もう一歩踏み込んだノウハウを知りたい」など、より3Dを使いこなしたい人、脱・入門者を目指す人にぴったりの内容です。《CONTENTS》●第1章 基本操作3Dモデルの種類や画面操作、3D作成の基本操作などの方法を解説。●第2章 輪郭・3Dの線の作成3Dモデルを作成する際のベースとなる輪郭や3Dの線の作成方法を解説。●第3章 サーフェスの作成サーフェスの3Dモデルを作成する方法や、サーフェスをさまざまな形状に編集する方法を解説。●第4章 ソリッドの作成ソリッドの3Dモデルを作成する方法や、ソリッドをさまざまな形状に編集する方法を解説。●第5章 3Dモデルの配置3Dモデルをの配置・反転・回転方法や、点群データや他の3Dデータの読み込み方法などを解説。●第6章 3Dモデルの表示3Dモデルの表示、マテリアルの設定、カメラの設定、レンダリングなどの方法を解説。●第7章 検討・図面作成3Dモデルに寸法を作図する方法や、面積・体積の確認、投影図や断面図の作成方法などを解説。●第8章 トラブル解決&操作のヒントAutoCADの3D機能を使ううえで直面しがちな問題を解決する方法を解説。
この書籍は、JIS製図に関する基本的なルールや技術を解説しています。各章では、投影図の描き方、寸法の入れ方、寸法配列と公差の関係、幾何公差、加工記号の使用法、機械要素図面の作成、そして図面管理について詳しく説明しています。著者は兵庫県出身の山田学氏です。
本書は、AutoCAD 2025の操作を初めて学ぶ人向けの学習書で、集合研修や自習に利用可能です。実習が豊富で、手順を示した動画や必要なファイルはWebからダウンロードできます。2025版では新たに「スマートブロック」の章が追加され、基本的なWindows操作が前提となっています。内容は基礎からエキスパート、マネージャ向けまで幅広くカバーしています。著者はCADのトレーニングに豊富な経験を持つ井上竜夫氏です。
「幾何公差」の理解と指示方法を解説した書籍の第2版で、最新のISO規格に対応しています。実用的な幾何公差の使い方に重点を置き、図面作成に役立つ内容です。著者はリコーでの豊富な経験を持ち、技術指導や研修活動を行っています。目次には基本事項や各種公差の使い方が含まれています。
本書は、1972年から続く「JIS機械製図」の完成図例集で、最新のJIS B 0001:2019に対応した改訂版です。機械系教育機関や技術者に好評で、通算64刷、累計12万部を超えています。改訂では、製図法や図例の見直しが行われ、設計製図に必要な各種規格も付録として掲載されています。内容は、機械製図法と具体的な図例22例を含み、基礎知識を解説しています。
本書は、AutoCAD 2023の基本操作を無理なく習得できる入門書で、初心者向けに作図の基礎から効率的な作業方法までを丁寧に解説しています。線や円の描き方、図形の編集、画層管理などを学び、練習問題を通じて実践力を養います。また、AutoCADの過去のバージョンにも対応しており、CAD製図を始めるための足がかりとなることを目的としています。著者はCADオペレータやインストラクターとしての経験を持つ鈴木孝子です。
この書籍は、ポンプの歴史や構造、性能、設置方法など、ポンプの幅広い活用について紹介しています。著者の外山幸雄はポンプの設計や開発に長年従事してきた専門家で、技術士事務所を運営しています。ポンプは電力や医療、災害時など多様な分野で重要な役割を果たしています。
本書は、機械図面の基本を初心者向けにやさしく解説したロングセラーの入門書です。改訂3版では最新のJISに準拠し、学生や若手エンジニアに必要な知識をシンプルに説明しています。内容は、図面の役割、見方・描き方の基礎、図面の作成・管理、CAD・CAM・CAEの活用、機械要素や溶接の製図など多岐にわたります。著者は機械工学の専門家で、技術者育成にも力を入れています。
本書は熱処理技術の基礎を平易に解説し、鋼の変化や実例を紹介する入門ガイドです。内容は鉄材料、金属の性質、熱処理装置、手法、恒温変態、表面処理、鋼の熱処理、管理と品質に関する章で構成されています。著者は工学博士で、熱処理に関する豊富な経験を持つ坂本卓教授です。
本書は、設計者が材料選択と加工方法を理解するための入門書で、材料加工学を中心に解説しています。機械材料の分類、特性、加工法、熱処理、接合技術について詳しく説明し、実践的なポイントを提供します。著者は材料力学の専門家で、実用的な知識を学ぶのに役立つ内容となっています。
この書籍は、機械設計に初めて関わる若手技術者や設計アシスタント、工業系の学生向けに、機械設計の基本知識やコストダウンの方法、材料と加工のポイントをわかりやすく解説しています。内容は、設計の目的、メカ機構、締結部品、機械要素、アクチュエータ、材料の性質、機械加工、コストダウン、センサと制御、品質と標準化についての章で構成されています。著者は生産技術コンサルタントの西村仁氏で、豊富な経験を持つ専門家です。
この文章は、モーターに関する書籍の目次と著者情報を提供しています。目次には、モーターの種類や特性を説明する6つの章が含まれています。著者の森本雅之は、慶應義塾大学で学び、三菱重工業での勤務を経て、東海大学の教授を務めています。
この文章は、3次元CADによる設計に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、3次元CADの基本や設計プロセス、良いモデリングと悪いモデリングの違い、実践的なモデリング講座が含まれています。著者は、キャディック株式会社の代表取締役である筒井真作氏と、同社の最高技術責任者である西川誠一氏で、両者ともにCAD教育やコンサルティングに豊富な経験を持っています。
この公式ガイドブックは、CAD利用技術者試験2次元1級(建築)の受験者向けに、建築図面の基本知識とCADの使い方を学ぶための教材です。受験資格は2級合格者で、主に建築系CADを実務で使用している人を対象としています。内容は、建築製図の基礎知識、電子情報、CADによる図面作成、過去問題などが含まれ、2023年度の試験問題と解答も掲載されています。また、関連資料は協会のWebページからダウンロード可能です。巻末には用語集もあります。
この公式ガイドブックは、コンピュータ教育振興協会が主催する「CAD利用技術者試験 2次元1級(機械)」の受験者向けで、機械製図の基本知識やCADの活用法を学ぶことを目的としています。受験資格は2級合格者で、内容は基礎知識、実践例、過去問題を含み、2023年度の試験問題と解答も掲載されています。巻末には用語集もあります。
著者は、海外留学や帰国子女ではないものの、独学で技術英語を習得した経験を基に、本書でそのノウハウを共有しています。内容は、英語のEメールやドキュメント、プレゼンテーションに関する実践的な勉強法や、技術英語の基礎知識、文書作成のテクニックなどが含まれています。著者は技術士であり、さまざまな資格を持つ専門家です。
この書籍は、初心者向けのJw_cad入門書で、2017年10月時点の最新版に対応しています。手取り足取りのステップ・バイ・ステップ方式で、パソコンが苦手な人でも理解しやすい解説が特徴です。基本操作から建築図面、敷地図や日影図の作成方法までを網羅しており、付録CD-ROMにはJw_cadバージョン8が収録されています。内容は、基本操作、図面の作成、さまざまな図面の描き方、Q&Aセクションで構成されています。
この書籍は、設計のプロセスと意義について解説しており、価値の発掘から機能、構造の決定までの流れを説明しています。目次には、設計の手順や構想の作成、具体化、必要な知識や材料の選定、製作方法、設計手段、具体例、技術の将来についての章が含まれています。著者の畑村洋太郎は、工学博士であり、設計や生産に関する研究を行っています。
「AutoCAD」の解説書で、初心者向けに基本操作や便利な機能、トラブルシューティングを詳しく説明しています。付属のCD-ROMには練習ファイルが含まれており、実際の操作を体験できます。2023/2022版に対応し、424の技術を厳選して解説しています。目次には基本操作から図形作成、印刷までの内容が含まれています。
本書は、すべての失敗が41の原因から生じることを示し、それを理解することで過去の失敗を繰り返さない方法を提案しています。著者は、タイタニック号の沈没やコンコルドの墜落など、178の有名な失敗事例を取り上げ、それらの失敗のシナリオを解明しています。内容は「失敗百選」の概念と、その学び方に分かれており、技術的および組織的要因について詳述されています。著者は中尾政之氏で、工学の専門家です。
本書は、JIS B 0001:2019に準拠した機械製図の指導書で、設計製図技術者向けに製図法の理解を促進することを目的としています。初版は1952年に発行され、累計100万部を超える人気を誇ります。内容は最新の規格に基づいて見直されており、日本のモノづくりを支えるための重要なリソースです。主なトピックには、製図の基礎、寸法記入法、CAD機械製図などが含まれています。
この文章は、CAD(コンピュータ支援設計)に関する書籍の目次を示しており、以下の6つの章で構成されています:CADシステムの基礎知識と応用、CADを動作させるコンピュータシステム、ネットワークの基礎知識、情報セキュリティと知的財産、製図の基礎、図形の基礎。
この入門書は、プラスチック材料を用いた機械設計について、必要な図表や式を解説し、理解を深める内容です。目次には、プラスチックの特性やものづくりの概要、設計のポイント、トラブル防止策などが含まれています。著者の田口宏之は、機械技術士としての経験を持ち、中小企業やスタートアップへの支援も行っています。
本書は、3D CADを活用した効果的な設計手法を紹介し、設計手戻りの撲滅を目指す内容です。設計対象を機能で分類し、再現性のある設計を実現するための具体的なノウハウを提供しています。目次には、手戻りのない設計プロセス、3D CADによる設計検証、モデリングメソッド、ケーススタディが含まれています。
本書は、建築以外の分野で無料のCADソフト「Jw_cad」を使用したい人向けの入門書です。基本的な作図操作から、機械・木工・プロダクトの製図に必要な技術、三面図やアイソメ図の描き方までを解説しています。付録にはJw_cadバージョン8が収録されており、すぐに実践可能です。内容は基本操作、ハッチング、図面作成、アイソメ図作成、トラブルシューティングの章に分かれています。
この文章は、強度検討に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は五つの章から成り、設計の重要性、材料力学の基礎、応力集中、強度評価、安全率、CAE理論について詳述しています。著者の遠田治正は、東京大学で学び、三菱電機での研究や教育に従事した経験を持ち、特に有限要素法や機械設計の効率化に貢献してきました。
本書は、電子回路の仕組みや動作をイラストを交えてわかりやすく解説し、理解を助ける内容です。基本素子や半導体素子、電源回路、増幅回路、フィルタ回路、発振回路、マイコンとの接続など、さまざまなトピックを取り上げています。また、電子回路に関する基本的な知識や実用的なアドバイスも提供されています。
この公式ガイドブックは、コンピュータ教育振興協会が主催する「3次元CAD利用技術者試験」を受験する人向けに作成されています。試験は1級、準1級、2級の3種類があり、1級と準1級は実技問題、2級は筆記問題が出題されます。1級は半年以上の利用経験者、準1級は経験が浅い人を対象とし、2級は受験資格がありません。本書では、3次元CADの概念、機能、データ管理、活用法について詳しく解説し、2021年度の試験問題と解答も掲載しています。
この書籍は、土木業務に従事する人々のためのAutoCAD入門テキストです。基本操作から土木図面の作成方法を解説し、練習用データを用いたチュートリアル形式と、コマンドの機能を説明するリファレンス形式の2つのアプローチでAutoCADを学べます。2021年版のAutoCADに対応し、過去のバージョンでも利用可能な内容となっています。著者はCADインストラクターの芳賀百合です。
本書は、機械設計の基礎知識やプロセスを初学者向けに楽しくわかりやすく解説しています。機械力学、材料力学、製図、加工法、メカトロニクスなどの広範な視点が必要とされる機械設計について学べます。著者は技術士として活躍する専門家たちです。
本書は、AutoCADを使用しながら建築製図の基本を学ぶための参考書です。戸建住宅を題材に、平面図・立面図・断面図の描き方を詳しく解説しています。AutoCAD初心者や建築CAD製図に興味がある人に適しており、練習用ファイルもダウンロード可能です。目次には、建築製図の概要やAutoCADの基本、各図面の作成方法が含まれています。著者は一級建築士の鳥谷部真です。
「軸受クランプ」の作成を例に解説。ゼロから作り上げる工程を手順に沿って実習し、CADの操作法を確実にマスターする。 Inventorによる3D CADのテキスト。冗長な解説は極力なくし、実習を通じて操作を学ぶ。「軸受クランプ」の作成を例に解説。一つのものをゼロから作り上げる工程を手順に沿って実習することで、達成感・満足感とともに、CADの操作法を確実にマスターできる。
本書は、機械工学の基礎を解説し、エネルギーを利用して動く物体(例:ロボット)の製造について学ぶ内容です。具体的には、材料、流体、熱、機構、制御、工作などの視点から、機械の設計や製造に関する知識を提供します。著者は東京工業大学附属科学技術高等学校の教諭であり、機械技術教育に情熱を注いでいます。
「DraftSight」の機械設計向け入門書で、無料でAutoCAD LTと同等の機能を持つCADソフトを使用して、機械製図の基礎知識や操作方法を学べます。具体的には、機械部品や要素の作図・編集を通じてDraftSightの使い方を解説しており、初心者でも理解しやすい内容です。JISの製図規格に対応し、インターネットから教材データをダウンロードする必要があります。著者はCAD講座の講師としても活動しています。
水力学演習の新装版で、流体力学や流体工学を数多くの問題を通じて学ぶための教科書です。内容は流体の物理的性質から始まり、流体静力学、運動量の法則、管路抵抗など多岐にわたります。著者は九州大学の名誉教授たちで、故人の著者も含まれています。
この書籍は、平成24年から29年に出題された457問の過去問を収録し、テキストと解説も含まれています。内容は、危険物に関する法令、基礎的な物理・化学、危険物の性質、火災予防、消火方法に関する章で構成されています。
この書籍は、材料選定に関する基礎知識を提供し、実務での対応力を高めることを目的としています。特に「品質」「コスト」「納期」に応じた材料特性の理解を重視し、熱処理などの技術的な内容も含まれています。著者は生産技術コンサルタントの西村仁氏で、豊富な実務経験を持っています。
この書籍は、円筒軸や多面体、板金プレス品、その他の部品の基本形状要素について解説しています。各章では、形状の設計方法や考え方に焦点を当てており、無駄のない美しい形状を追求する重要性が強調されています。著者は山田学氏で、兵庫県出身のラブノーツ代表取締役です。
この書籍は、検図に関する現状と課題を分析し、理想的な開発プロセスにおける検図の仕組みや詳細なプロセスを提案しています。具体的には、3D CADの活用法や自己検図の進め方についても触れています。著者の中山聡史は、自動車業界での豊富な経験を基に、設計改善や品質管理の支援を行っています。
この教科書は、機械システム構築に必要な機械要素の選定と組み合わせ方法を、豊富な図版や計算式、例題を用いて解説しています。ボールねじやリニアガイド、電動機などの最近の機械設計に対応し、実務に役立つ知識と応用力を養成します。第2版ではJIS規格の改訂やカム・リンク機構の項目増補、歯車強度計算の一般化が行われています。大学や企業の教育教材に最適です。
「機械製図」に関するよくある質問
Q. 「機械製図」の本を選ぶポイントは?
A. 「機械製図」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「機械製図」本は?
A. 当サイトのランキングでは『はじめて学ぶAutoCAD 2025 作図・操作ガイド 2024/2023/2022/LT 2021/2020/2019/2018/2017対応』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで117冊の中から厳選しています。
Q. 「機械製図」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「機械製図」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。











![『デザインの学校 これからはじめる AutoCADの本 [AutoCAD/AutoCAD LT 2020/2019/2018対応版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/5104VCr1GKL._SL500_.jpg)



![『AutoCADで3Dを使いこなすための97の方法[AutoCAD 2024対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ax7JEu5KL._SL500_.jpg)





















![『今すぐ使えるかんたん AutoCAD [改訂2版] (Imasugu Tsukaeru Kantan Series)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51b98Yrlv+L._SL500_.jpg)







![『だれでもできるAutoCAD LT[土木編] AutoCAD LT 2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009対応 (エクスナレッジムック)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51gFTuYBF4L._SL500_.jpg)










![『今すぐ使えるかんたん AutoCAD 完全ガイドブック 困った解決&便利技[2023/2022対応版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51KHflR-BKL._SL500_.jpg)





















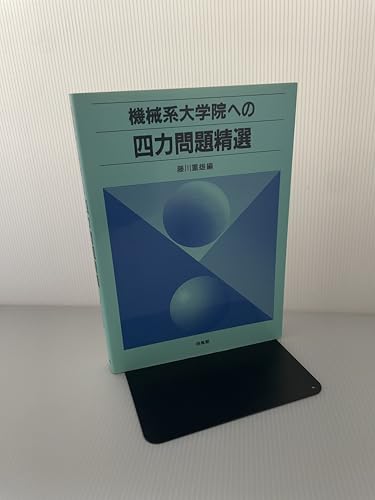


![『だれでもできるAutoCAD[土木編] AutoCAD&AutoCAD LT 2022/2021/2020/2019』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51QdUNvv9iL._SL500_.jpg)



![『やさしく学ぶ建築製図[完全版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51sY251buyL._SL500_.jpg)


![『AutoCADで学ぶ建築製図の基本[AutoCAD 2022対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/417oYW5kqFL._SL500_.jpg)








































