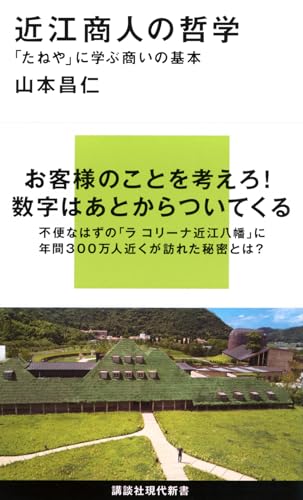【2025年】「東京裁判」のおすすめ 本 69選!人気ランキング
- 秘録東京裁判 (中公文庫 B 1-34 BIBLIO20世紀)
- 「東京裁判」を読む
- 東京裁判
- 漫画で知る「戦争と日本」ー壮絶! 特攻篇ー
- 東京裁判 フランス人判事の無罪論 (文春新書 892)
- 東京裁判 (下) (中公新書 248)
- 東京裁判却下未提出弁護側資料
- 日本の産業革命――日清・日露戦争から考える (講談社学術文庫)
- 「東京裁判」を読む
- 日本軍兵士―アジア・太平洋戦争の現実 (中公新書)
本書は東京裁判に関する冷静で実証的な研究を提供し、イデオロギーを排除した新たな視点から「文明の裁き」と「勝者の報復」の論争に終止符を打つことを目指しています。著者の日暮吉延は、東京裁判に関する新しい事実を一般に普及させるために執筆し、サントリー学芸賞を受賞しました。内容は東京裁判の成立背景、連合国の告発、日本の対応、判決の過程、戦犯の釈放に関する詳細を含んでいます。
この書籍は、明治維新から終戦までの日本と世界の出来事を、対外戦争を中心に戦況図とイラストで解説しています。開国以降の日本の歴史を年表と共に示し、特に日清戦争や日露戦争、さらに世界大戦について詳述しています。
著者は、ウクライナ戦争を背景に、歴史から学ぶ重要性を説き、日本の戦争の歴史を五十年にわたり研究してきた。近代日本が戦争に突き進んだ理由や戦争回避の可能性、明治・大正・昭和の戦争の違いを検証し、「戦争論」の見直しの必要性を提起。次代の日本のあり方についても提言する内容となっている。著者はノンフィクション作家で、数多くの取材を基にした研究を行っている。
大人気シリーズが完結。昭和11年の二・二六事件から昭和20年の玉音放送までの10年間を描き、日本軍部の暴走や対英米戦争の泥沼化を詳細に解説。中国の蒋介石が国際的な支援を得て抗日戦争を続ける中、日本は敗北を重ね、戦争の悲劇が深まる。著者は昭和史研究の第一人者で、戦争の意味を問い直す内容となっている。
東京裁判に関する概説書や学術論文は数多く刊行され、裁判論はすでに出尽くされたとの感がある。しかし、これまでの裁判論は主に政治・外交史を基調とし、法廷で適用された責任論や各被告人に対する判定の根拠を体系的に分析するものは数少ない。しかも従来の裁判論では、「日本無罪論」で知られるインド代表判事ラーダビノード・パルの個別反対意見や、オランダ代表判事B・V・A・レーリンクによる個別反対意見がもっぱら話題にされ、本来の東京判決である多数意見が軽視されてきた。その結果、東京判決そのものの実証研究は立ち遅れ、東京裁判を国際刑事裁判史のなかでどう評価するのかは、判決七五周年を迎える今でも未解決の研究課題である。このような状況をふまえ、東京裁判の事実認定がいかになされ、責任がどう問われたのかを実証的に解明し、東京裁判の功績と問題点を改めてあきらかにする。
この書籍は、明治以降の日本が経験した四つの対外戦争を通じて、指導者や一般市民がどのように国家の未来を考え、参戦を決断したのかを探る内容です。中高生向けの5日間の集中講義を通じて、戦争の背後にある論理や歴史的事実を考察します。著者は加藤陽子で、作品は小林秀雄賞を受賞しています。目次には日清戦争から太平洋戦争までの各章が含まれています。
この書籍は、日本が太平洋戦争に突入した理由を探るもので、為政者の戦争への論理や国民の支持の背景を解明します。著者の加藤陽子は、日清戦争以降の「戦争の論理」を分析し、軍備拡張や朝鮮半島の重要性、満州事変、日中・太平洋戦争への拡大など、歴史的な要因を詳述しています。近代日本の戦争に関する理解を深める画期的な研究です。
暴走の本質 軍備拡張競争の実態:建艦競争を中心に 近代日本における軍事力編成 近代日本の戦争を支えたソフト・システム・ハード 第二次世界大戦における日本の敗因 兵士たちの日中戦争 日本軍の航空特攻作戦の特徴 沖縄戦の軍事史的位置
ヒロシマの空 『きけわだつみのこえ』より レイテ戦記 私のひめゆり戦記 麦と兵隊 今夜、死ぬ 叫び声 指揮官たちの特攻 神聖喜劇 母と子でみる東京大空襲 断腸亭日乗 生ましめんかな 敗戦日記 はだしのゲンはピカドンを忘れない 私の中国捕虜体験 黒い雨 夏の花 沖縄よどこへ行く 回天特攻学徒隊員の記録 火垂るの墓 八月六日 暗い波濤 崖 七三一部隊で殺された人の遺族 夢がたり 戦争はおしまいになった 難民になる
欧洲大戦と日本のゆらぎ 三つの「戦争」 第二次世界大戦 南進と大東亜「解放」 朝鮮駐屯日本軍の実像 帝国在郷軍人会と政治 日本陸軍の中国共産党観 日本軍人の蔣介石観 戦前日本の危機管理 支那事変初期における近衛内閣の対応 日本人の日中戦争観 日中和平工作の挫折 汪兆銘のハノイ脱出をめぐって 桐工作をめぐって 対中和平工作 一九四二~四五年
「東京裁判」に関するよくある質問
Q. 「東京裁判」の本を選ぶポイントは?
A. 「東京裁判」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「東京裁判」本は?
A. 当サイトのランキングでは『秘録東京裁判 (中公文庫 B 1-34 BIBLIO20世紀)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで69冊の中から厳選しています。
Q. 「東京裁判」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「東京裁判」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。