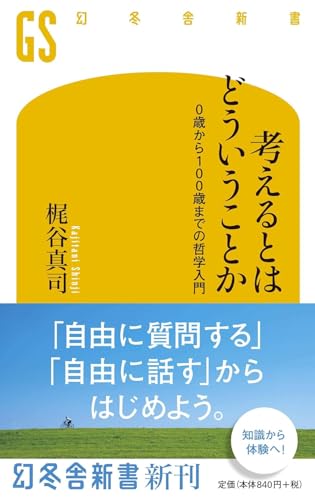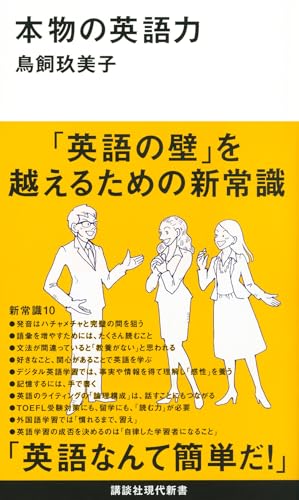【2025年】「人文学」のおすすめ 本 165選!人気ランキング
この作品は、親友を裏切って恋人を得た主人公が、その親友の自殺によって罪悪感に苦しみ、自らも死を選ぶという孤独な内面を描いています。物語は、学生の視点から主人公の魅力を描写した前半と、主人公の告白が対照的に展開される後半で構成されています。夏目漱石の後期三部作の集大成であり、「我執」のテーマが透明な文体で表現されています。
砂丘で昆虫採集中の男が砂穴の底に閉じ込められ、脱出を試みる。彼を引き留めようとする女と、男の逃亡を妨害する地域の人々が絡む中、人間存在の象徴を探求するサスペンスフルな長編小説。20数ヶ国語に翻訳された名作。
カミュの代表作『異邦人』は、母の死後に海水浴や女との関係を楽しむ主人公ムルソーが、友人を巡るトラブルで殺人を犯し、「太陽のせい」と動機を述べる物語です。彼は死刑判決を受けながらも幸福を感じ、処刑の日に見物人の憎悪を望むという、理性や人間性の不合理を探求しています。
「僕」が砂漠に不時着し、小さな星から地球に来た王子さまと出会う物語『星の王子さま』。この作品は60年以上経っても多くの人々の心をつかむ宝石のような物語で、新訳が優しい日本語で王子さまをよみがえらせている。著者はフランスの作家サン=テグジュペリで、航空パイロットとしての経験を活かし、数々の作品を残した。
読みやすくておもしろいなとおもいました。
子供向けの物語かと思いきや、大人が読んでも深く人生について考えさせられる本。大切なものは目に見えないんだというセリフが好き。
新緑の山あいの温泉で、島村は美しい娘・駒子と出会う。彼女に再会するため汽車に乗ると、同じ車両にいた葉子が気になる。葉子と駒子には隠されたつながりがあった。川端康成のこの作品は、日本的な「美」を描いた世界的名作で、ノーベル文学賞を受賞している。
三島由紀夫の長編小説『仮面の告白』は、女に魅力を感じない少年が、戦時中に級友の妹と出会い、幸福を感じるも、その瞬間に自らの逃避本能に気づく物語。少年の内面の葛藤と性的指向に関する告白が描かれ、著者自身のスキャンダラスな自伝的要素が含まれている。三島は1949年にこの作品で作家としての地位を確立し、その後も多くの名作を残した。
明治後期、部落出身の教員瀬川丑松は、父の戒めを破り解放運動家猪子蓮太郎の死に心を動かされ、社会問題に立ち向かう。結果、彼は社会から追放され、テキサスへ旅立つ。内面的な葛藤を描いたこの作品は、近代日本文学の傑作とされている。著者は島崎藤村で、自然主義文学の先駆者として多くの作品を発表した。
双子の星.よだかの星.カイロ団長.黄いろのトマト.ひのきとひなげし.シグナルとシグナレス.マリヴロンと少女.オツベルと象.猫の事務所.北守将軍と三人兄弟の医者.銀河鉄道の夜.セロ弾きのゴーシュ.饑餓陣営.ビジテリアン大祭. 年譜:p351~357
14歳からの「考える」のための教科書。「自分とは何か」「死」「家族」「恋愛と性」「メディアと書物」「人生」など30のテーマ。 今の学校教育に欠けている14歳からの「考える」の為の教科書。「言葉」「自分とは何か」「死」「家族」「社会」「理想と現実」「恋愛と性」「メディアと書物」「人生」等30のテーマ。 人には14歳以後、一度は考えておかなければならないことがある。 言葉、自分とは何か、死、心、他人、家族、社会、理想と現実、友情と愛情、恋愛と性、仕事と生活、本物と偽物、メディアと書物、人生、善悪、自由など、30のテーマを取り上げる。 Ⅰ 14歳からの哲学[A] 1 考える[1] 2 考える[2] 3 考える[3] 4 言葉[1] 5 言葉[2] 6 自分とは誰か 7 死をどう考えるか 8 体の見方 9 心はどこにある 10 他人とは何か Ⅱ 14歳からの哲学[B] 11 家族 12 社会 13 規則 14 理想と現実 15 友情と愛情 16 恋愛と性 17 仕事と生活 18 品格と名誉 19 本物と偽物 20 メディアと書物 Ⅲ 17歳からの哲学 21 宇宙と科学 22 歴史と人類 23 善悪[1] 24 善悪[2] 25 自由 26 宗教 27 人生の意味[1] 28 人生の意味[2] 29 存在の謎[1] 30 存在の謎[2]
この書籍は、母と姉弟の苦難を通じて犠牲の意味を考察する『山椒大夫』や、弟殺しの男と護送同心の会話から安楽死の問題を探る『高瀬舟』を含む全12編を収録しています。鴎外の思想や世界観を反映した作品群で、滞欧生活の経験を基にした『妄想』なども含まれています。
貧しい大学生ラスコーリニコフは、理論に基づいて高利貸の老婆を殺害し、その財産を利用しようとしますが、偶然妹も殺してしまいます。この予期しない出来事が彼に罪の意識を強く抱かせ、苦しむことになります。
本書は、井伏鱒二の短編集で、初期の代表作12編を収めています。内容は、老成と若さが交錯する豊かな詩精神を持ち、ユーモラスな『山椒魚』や抒情的な『屋根の上のサワン』などが含まれています。著者は多くの文学賞を受賞した広島出身の作家で、文学界において重要な存在です。
少年ハンスは自然児でありながら傷つきやすく、周囲の期待に応えようと勉強に励み神学校に入学。しかし、厳しい規則に苦しみ、反抗心から学校を辞めて見習い工として新たな道を模索する。これはヘッセの自伝的要素を含む代表作で、子どもの心と生活を描いている。
キャシー・Hは「提供者」と呼ばれる人々の介護をする優秀な介護人であり、彼女の回想を通じて、育った施設ヘールシャムの奇妙な日々や残酷な真実が明らかになる。著者はブッカー賞作家のカズオ・イシグロで、彼は日本とイギリスの文化を背景に育ち、数々の文学賞を受賞している。
内容は予めぼんやりと知っていたのだが想像よりもグロテスクで救いが全くなかった。それに加えこれはフィクションだと言いきれないような事が貧困国には起こってそうで読み進めるのが辛い部分があった。だが小説としてはとても素晴らしい出来でした。生きる事にしがみつく人間はここまで強欲に、そして提供されるクローンにここまで無慈悲にできるのかと人間の愚かさがこれほどまでに書かれていて、読み終わったあとは人間不信になる感覚でした。
『カラマーゾフの兄弟』は、物欲に満ちた父フョードル・カラマーゾフの血を引く三兄弟、放蕩者ドミートリイ、冷徹なイワン、敬虔なアリョーシャが織りなす愛憎劇を描いた名作です。物語は神と人間の根本問題を中心に展開されます。著者は19世紀ロシア文学の巨匠ドストエフスキーであり、彼の作品は時代の本質を鋭く捉えたものとして評価されています。翻訳者の原卓也は、ロシア文学の著名な翻訳家です。
古代の伝説が息づく伊勢湾の小島で、若者新治と少女初江が出会い、恋に落ちる物語。嵐の日に二人きりになり、彼らの関係が深まる様子が描かれ、三島由紀夫の文学が持つ美しさと青春の永遠性が表現されている。著者は三島由紀夫で、彼は多くの名作を残し、世界中で愛読されている。
『野菊の墓』は、15歳の政夫と2歳年上の従姉・民子の純真な恋を描いた物語で、世間の目により二人は引き離される。政夫は町の中学に通い、民子は他に嫁いで病死してしまう。作品は江戸川の田園を舞台にしており、恋の切なさを多くの読者に共感させる。著者は伊藤左千夫で、彼の他の作品として『守の家』や『浜菊』、『姪子』が収められている。
ウラジーミル・ナボコフの「ロリータ」は、中年男の少女への倒錯した恋を描いた作品で、恋愛小説、ミステリ、ロード・ノヴェルの要素を持つ文学的傑作です。多様な解釈が可能で、爆笑や涙を誘う内容が特徴の新訳版が登場しました。ナボコフはロシア生まれで、革命後は亡命生活を送り、アメリカで創作活動を行った著名な作家です。若島正は文学研究者で、受賞歴があります。
この書籍は、相手に伝わる文章を書くための方法と「文章を書く」ことの意義について解説しています。著者は、論理的ライティングは「異和感」から始まるとし、教育現場での経験を基に、思考と文章の相関関係を鍛える方法を提供。小論文執筆法を通じて「自分の言葉を持ってリアルに生きる」ための基本的な教養を伝授する内容です。目次では、論理的思考の始まりや社会問題への向き合い方、社会通念への懐疑、日常の中の論理について触れています。著者は大堀精一で、高校生向けの教育に長年従事しています。
この書籍は、明治以降の日本が経験した四つの対外戦争を通じて、指導者や一般市民がどのように国家の未来を考え、参戦を決断したのかを探る内容です。中高生向けの5日間の集中講義を通じて、戦争の背後にある論理や歴史的事実を考察します。著者は加藤陽子で、作品は小林秀雄賞を受賞しています。目次には日清戦争から太平洋戦争までの各章が含まれています。
「どうして勉強しなければいけないの?」「どうしていじめはなくならないの?」「生きている意味はあるの?」 学校の… 「どうして勉強しなければいけないの?」 「どうしていじめはなくならないの?」 「生きている意味はあるの?」 学校の先生や親がなかなか答えられない、子どもが抱えるリアルな悩みや疑問を、哲学者の言葉をヒントに解決。 哲学を通して子どもの考える力を育てる、必読の一冊。 古代ギリシャから近代、現代の有名な哲学者の解説も。 ■第1章 自分について考える Q 運動が苦手 Q 勉強ができない Q 自分の言葉で上手く話せない Q 綺麗になりたい Q 自分のいいところがわからない Q 「自分らしさ」って何? ■第2章 友達について考える Q 友達ができない Q 友達が他の子と仲よくしているとムカムカしてしまう Q 友達グループの中で仲間外れにする子がいる Q ケンカをした友達に「ごめんなさい」が言えない Q 人を好きになるってどういうこと? ■第3章 悪について考える Q どうしてルールを守らなくちゃいけないの? Q 人にやさしくしなきゃいけないのはなぜ? Q どうしていじめはなくならないの? Q 悪いことをしている人には注意した方がいい? ■第4章 生き方について考える Q どうして勉強しなければいけないの? Q 苦手なことはあきらめちゃダメ? Q 「本をたくさん読みなさい」って言われたけどなぜ? Q 自分の夢を反対される Q 生きている意味はあるの? Q 幸せって何? ■第5章 命について考える Q 心はどこにあるの? Q 花や木に命はある? Q 死ぬのが怖い Q 人は死んだあとどうなるの? Q 人はどうして人を殺すの? ■岩村先生の哲学講座 人間の祖先「ホモ・サピエンス」が生き残れたわけ 物事の原因はすべて「目に見えない」 「ふたつの時間」を生きる 愛は「心を受ける」こと
小川三四郎は熊本の高校を卒業し、東京の大学に入学する。そこで、自由奔放な女性里見美禰子と出会い、彼女に惹かれていく。青春の中での学問や友情、恋愛の不安や戸惑いが描かれ、三四郎の恋愛から失恋に至る過程が物語の中心となっている。この作品は、夏目漱石の三部作「それから」「門」の序曲となる。夏目漱石は1867年生まれの著名な日本の作家で、多くの傑作を残した。
チャーリイ・ゴードンは、32歳で幼児並みの知能を持つ男性。彼は大学の教授から知能を向上させる手術を提案され、白ネズミのアルジャーノンと競争しながら検査を受ける。手術後、彼は天才に変貌し、愛や孤独を通じて人間の心の真実を学ぶ。これは感動的な物語で、著者ダニエル・キイスの代表作として知られている。
号泣するという以外何をすればよいのかわからない
ドラマ版を見てから原作も気になり購入。もう涙が止まらなすぎて途中で手を止めないと読み進められないです。知的障害者のチャーリーにとって、知恵を得ることや真実を知る事は必ずしも幸せなのだろうかと考えさせられました。チャーリーが手術後に賢くなってから周りの人達は自分をただバカにしていた事や母親から虐待を受けていた事を気付いた時の心情が、、、言葉に表せないぐらい辛いのです。最終章の方でのチャーリーは自分もアルジャーノンと同じように知能が落ちてしまっていくと気付いた時の絶望感。それでも心から友達と言える、友達に出会えたことは彼の救いになったと思えました。
この書籍は、古代の錦織物の復原を成功させた二代龍村平蔵(光翔)とその後継者龍村光峯が、古代織物の美しさとその復原過程について語る内容です。目次には、錦とボロの関係、歴史的背景、復原の意義、伝統織物の保存に関する取り組みが含まれています。著者たちは、古代織物の技術を継承し、保存育成に努めています。
アイディアを軽やかに離陸させ、思考をのびのびと飛行させる方法を、広い視野とシャープな論理で知られる著者が、明快に提示する。 大学生協文庫年間ランキング2年連続1位! 2018年1月~2019年12月 (大学生協事業連合調べ) 歴代の東大生・京大生が根強く支持する異例のベスト&ロングセラー! 刊行から34年で124刷・253万部突破! 「もっと若い時に読んでいれば……」 そう思わずにはいられませんでした。 ――松本大介さん 自分の頭で考え、自力で飛翔するためのヒントが詰まった学術エッセイ。 アイディアが軽やかに離陸し、思考がのびのびと大空を駆けるには? 自らの体験に即し、独自の思考のエッセンスを明快に開陳する、恰好の入門書。 考えることの楽しさを満喫させてくれる一冊。 2008 年に東大(本郷書籍部)・京大生協の書籍販売ランキングで1 位を獲得して以来、12年間の間にともに7度の売上1 位を獲得。 「東大・京大で一番読まれた本」として知名度を高め、新たな読者を増やし続けています。 ■なぜ東大生が根強く支持するのか? 東大生の感想……外山滋比古講演会「思考の整理学を語る」より ・今の時代に必要なのは、情報を手に入れることよりも「捨てる」ことなのだ。 ・他分野との接触、混在が新しい思考法を生み出すという考えがとても新鮮に思えた。 ・大学やその先で求められている「学び」に対する姿勢が、少し分かった気がする。 ・知識に偏った勉強をしてきたからこそ、それじゃいけないんだ、と思いを新たにした。 ・考えがまとまらない時、くよくよするのがいちばんいけない。 ・メモをとり、整理する癖がつきました! ・根底にある理念は自ら学べ、という点だと感じた。 ・高校生の時は意味が良く分からなかったけれど、大学に入って文章を書くようになり、先生の仰っていたことの重要性が良く分かった。 ・今の自分を肯定して考えることの楽しさを教えてくれます。 ・時を経ても変わらない価値がある。 ・この本を読んでいないなんて、人生の半分を損している。
この書籍は、個性を大切にしながらも、集団の中での他人の視線や先輩への従属に悩む人々に向けたアドバイスを提供しています。著者は「世間」のルールや同調圧力について考察し、自己を大切にしつつ生きる方法を探ります。特に、他人の頼みを断ることや、仲間外れを恐れないことの重要性を強調しています。最終的に、より自分らしく生きるためのヒントを提示しています。
大学入学共通テストなどで揺れ動く国語教育・英語教育。ことばの教育はどうあるべきなのか、3人の専門家がリレー形式で思考する。 大学入学共通テストへの記述問題・民間試験導入などで揺れ動く国語教育・英語教育。ことばの教育はどうあるべきなのか、3人の専門家がリレー形式で思考する。 大学入学共通テストへの記述問題・民間試験導入などで揺れ動く国語教育・英語教育。ことばの教育はどうあるべきなのか、3人の専門家がリレー形式で思考する。
上手な話し方や相手を論破するテクニックのハウツーとはひと味違った、「人と人がわかり合うこと」の本質に迫る一冊 ソクラテスが様々な相手と語り合いながら思索を深める過程を書きとどめ、対話そのものの重要性を示したプラトンの名著『対話篇』。西洋哲学研究の第一人者である著者がその内容を踏まえ、現代社会のコミュニケーションに求められている「真の対話」のあり方を探ります。 そもそも「対話」とは何か? ふだんの日常会話、一方的な説得や意見の押し付けと混同されがちなその定義の見直からスタートし、15回のテーマに分けてわかりやすく解説。 「対話の成功=相手を思い通りにすることではない」、「目の前にいない相手と対話する難しさ」など、言葉を通じたやり取りのシチュエーションが多様化するなかでこそ意識したい心がまえを提案しています。 SNSにおける交流といった最新の話題も取り入れ、哲学に詳しくない方でも読みやすい点が特徴です。 上手な話し方や相手を論破するテクニックのハウツーとはひと味違った、「人と人がわかり合うこと」の本質に迫る一冊。 新型コロナ禍による様々な変化のなかで、コミュニケーションに悩む方にとくにおすすめです。 【目 次】 はじめに 目次 第一部・対話を知っていますか? ●第一回 対話という言葉から考えよう ●第二回 対話でないもの ●第三回 対話をすすめる技法 ●第四回 対話の強さと弱さ ●第五回 対話が目指すところ 第二部・危ない対話への勇気 ●第六回 言論嫌いという病 ●第七回 答えの得られない問い ●第八回 対話の衝撃を受けとめる ●第九回 言葉による誘惑 ●第十回 対話する勇気 第三部・対話が広がる世界 ●第十一回 対話の場の越境 ●第十二回 対話の相手の拡大 ●第十三回 不在者との対話 ●第十四回 自分自身との対話 ●第十五回 対話の実践 対話を知るために参考になる本 おわりに 【目 次】 はじめに 目次 第一部・対話を知っていますか? ●第一回 対話という言葉から考えよう ●第二回 対話でないもの ●第三回 対話をすすめる技法 ●第四回 対話の強さと弱さ ●第五回 対話が目指すところ 第二部・危ない対話への勇気 ●第六回 言論嫌いという病 ●第七回 答えの得られない問い ●第八回 対話の衝撃を受けとめる ●第九回 言葉による誘惑 ●第十回 対話する勇気 第三部・対話が広がる世界 ●第十一回 対話の場の越境 ●第十二回 対話の相手の拡大 ●第十三回 不在者との対話 ●第十四回 自分自身との対話 ●第十五回 対話の実践 対話を知るために参考になる本 おわりに
三島由紀夫の名作『金閣寺』は、吃音と醜い外貌に悩む学僧・溝口が、美の象徴である金閣に対する憧れと同時に、それを破壊せざるを得ない内面的葛藤を描いています。作品は現実の金閣放火事件を題材にし、三島文学の核心である「現象の否定とイデアの肯定」を探求しています。三島は1947年に作家としての道を歩み始め、1970年に自決するまでに多くの著作を残しました。『金閣寺』は国際的にも評価され、映画や舞台化もされています。
全体主義的な近未来を舞台に、真理省で歴史の改竄を行う党員ウィンストン・スミスが、恋人ジュリアとの出会いを通じて反政府活動に惹かれていく物語。ジョージ・オーウェルの名作が新訳で登場。
『斜陽』は、敗戦直後の没落貴族の家庭を背景に、恋と革命に生きる娘かず子、気品を保つ母、破滅に向かう弟直治の姿を描いた作品です。1947年に発表され、人気を博し「斜陽族」という言葉も生まれました。また、同時期の短篇『おさん』も収められています。
テネシー・ウィリアムズの名作「欲望という名の電車」は、ニューオリアンズのフレンチ・クォーターに降り立った主人公ブランチが、妹ステラのアパートで新しいアメリカの粗暴な生活に直面する物語です。1947年に初演され、ピューリッツァー賞を受賞したこの作品は、近代演劇の名作とされています。ウィリアムズは不幸な家庭環境を抱えつつ成功を収めましたが、私生活は孤独との葛藤に苦しみました。
日本企業の人事担当者が新卒採用で最も重視する「コミュニケーション能力」という概念について探求する内容です。調査によると、企業が求めるのは異文化理解を含むグローバルなコミュニケーション能力ですが、実際には上司の意図を察するなどの従来型の能力も求められており、若者は矛盾した要求に直面しています。著者はこの問題を解明し、コミュニケーションの本質を考察しています。
指針なき現代にこそ響く最強の古典!資本主義の本質を見抜き、日本実業界の礎となった渋沢栄一が、生涯を通じて貫いた経営哲学とは。 1番読みやすい現代語訳! 60万部突破!! いまこそ全ての日本人必読! 最強の古典 2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」主人公! 新1万円札の顔に決定! 指針なき現代においてわたしたちは「どう働き」「どう生きる」べきか? 迷ったとき、いつでも立ち返りたい原点がここにある!! 各界のトップ経営者も推薦! 岩瀬大輔氏 「あなたの仕事観を変える本。東洋の叡智がここにある! 」 佐々木常夫氏 「資本主義に対する彼の思想は、時代や国境を越えている」 新浪剛史氏 「“道徳に基づいた経営"という発想には学ぶべきことが多い」 資本主義の本質を見抜き、日本実業界の礎となった渋沢栄一。 「論語」とは道徳、「算盤」とは利益を追求する経済活動のことを指します。 『論語と算盤』は渋沢栄一の「利潤と道徳を調和させる」という経営哲学のエッセンスが詰まった一冊です。 明治期に資本主義の本質を見抜き、約480社もの会社設立・運営に関わった彼の言葉は、ビジネスに限らず、未来を生きる知恵に満ちています。 第1章:処世と信条 第2章:立志と学問 第3章:常識と習慣 第4章:仁義と富貴 第5章:理想と迷信 第6章:人格と修養 第7章:算盤と権利 第8章:実業と士道 第9章:教育と情誼 第10章:成敗と運命 なぜいま『論語と算盤』か(本書「はじめに」より抜粋) ここで現代に視点を移して、昨今の日本を考えてみると、その「働き方」や「経営に対する考え方」は、グローバル化の影響もあって実に多様化している。「金で買えないモノはない」「利益至上主義」から「企業の社会的責任を重視せよ」「持続可能性」までさまざまな価値観が錯綜し、マスコミから経営者、一般社員からアルバイトまでその軋轢の中で右往左往せざるを得ない状況がある。そんななかで、われわれ日本人が、「渋沢栄一」という原点に帰ることは、今、大きな意味があると筆者は信じている。この百年間、日本は少なくとも実業という面において世界に恥じない実績を上げ続けてきた。その基盤となった思想を知ることが、先の見えない時代に確かな指針を与えてくれるはずだからだ。 第1章:処世と信条 第2章:立志と学問 第3章:常識と習慣 第4章:仁義と富貴 第5章:理想と迷信 第6章:人格と修養 第7章:算盤と権利 第8章:実業と士道 第9章:教育と情誼 第10章:成敗と運命 十の格言 渋沢栄一小伝 『論語と算盤』注 参考図書
多くの経営者がバイブルとして挙げることの多い「論語と算盤」。明治維新後多くの企業を立ち上げて日本国を強くしてきた渋沢栄一の経営哲学が学べる。論語と算盤、すなわち今で言うとアートとサイエンス。この2つの両輪なくして経営は成り立たないしインパクトのある仕事はできない。常に渋沢栄一の経営哲学を頭に入れて日々過ごしていきたい。
子供の頃に親しまれた「大人国・小人国」の物語を、大人として再読すると、スウィフトの鋭い筆致が単なる諷刺を超えて人間そのものへの深い呪詛に至ることが明らかになる。
泉鏡花(1873-1939)は金沢出身の作家で、本名は鏡太郎。明治23年に上京し、尾崎紅葉に学ぶ。彼は「夜行巡査」や「外科室」で新進作家としての地位を確立し、その後「高野聖」や「婦系図」、「歌行燈」など浪漫的・神秘的な作品を発表。彼の文学は明治から昭和にかけて独自のスタイルを確立し、1973年には泉鏡花文学賞が創設された。
『浮雲』は、明治20年に発表された二葉亭四迷の処女作で、言文一致の新しい文章スタイルで当時の人々を驚かせました。物語は、秀才で世間知らずな青年官吏・内海文三の内面的な苦悩を描写し、知識階級を人間として描いた作品であり、日本近代小説の先駆けとされています。著者の二葉亭四迷は1864年生まれで、東京外国語学校で学び、後に作家として活動しました。
なんだか難しそうな哲学。しかし哲学することは特別なことではない。身近なテーマから、哲学するとはどんな行為なのかを解き明かす。 なんだか難しそうな哲学。中身は分からなくても、漠然と難しそうにみえる哲学。しかし、哲学することはなにも特別な行為ではない。哲学が扱うのはどれも実は身近な問題ばかりである。ニュースなどで見かける問題、人と話すときに話題にするようなこと、実はそこに哲学が隠れている。本書は、これを手がかりにさらに読者なりに考えを深めるための道具箱のようなものである。カントいわく、哲学は学べない。読者はこれをヒントに自分で考える。そこに哲学が存在する。 はじめに(戸田剛文) 第一部 身近なテーマから 第1章……いま芸術に何が期待されているのか(阿部将伸) はじめに 1 視線の向けかえ―古代 2 視線の落ち着き先の変容1―古代末から中世へ 3 視線の落ち着き先の変容2―近代 4 コミュニティ感覚 おわりに ❖おすすめ書籍 第2章……犬と暮らす(戸田剛文) はじめに 1 動物への道徳的配慮 2 具体的な問題 3 動物を食べることは正当化できるのか 4 幸福な社会 ❖おすすめ書籍 第3章……宗教原理主義が生じた背景とはどのようなものか(谷川嘉浩) はじめに 1 原理主義とはどのようなものか 2 近代化と、キリスト教原理主義 3 手のなかに収まらないものへ ❖おすすめ書籍 第4章……幸福の背後を語れるか(青山拓央) はじめに 1 幸福をめぐる三説 2 「私」の反事実的可能性 3 私的倫理と自由意志 4 『論考』と言語 5 『論考』と倫理 ❖おすすめ書籍 第二部 哲学の伝統 第5章……原因の探求(豊川祥隆) はじめに―「なぜ」という問いかけ 1 言葉の根―「アイティア」について 2 近代科学という営みと「目的」の瓦解 3 ドミノ倒し 4 現代の「原因」観―概念の多元主義にむけて 5 おわりに―人間の進歩と面白さ ❖おすすめ書籍 第6章……言葉と世界(佐野泰之) はじめに―言葉のない世界 1 言語論的転回 2 論理実証主義への批判 3 解釈学的転回 おわりに―私たちは言語の囚人なのか? ❖おすすめ書籍 第7章……知識と懐疑(松枝啓至) はじめに 1 古代懐疑主義 2 デカルトの「方法的懐疑」 3 「懐疑」について「懐疑」する―ウィトゲンシュタインの思索を手掛かりに ❖おすすめ書籍 第8章……存在を問う(中川萌子) はじめに 1 「存在とは何か」という問いの動機と必要性―ニーチェとハイデガーの時代診断 2 存在とは何か? 「存在とは何か?」と問うことはどのような営みか? 3 「存在とは何か」という問いの形式と歴史 4 「存在とは何か」と問うことの自由と責任―ハイデガーとヨナスの責任論 おわりに ❖おすすめ書籍 あとがき 索引(人名・事項)
「私を丸ごと受け入れてくれる人がきっといる」という幻想の中に真の親しさは得られない。人間関係を根本から見直す実用的社会学。 全国1000人以上の先生が選んだ、中高生にいま一番読んでほしい本 「キミに贈る本(キミ本)大賞」(読売中高生新聞主催)第1位! NHK「おはよう日本」 日本テレビ系列「世界一受けたい授業」(又吉直樹さん) TBS系列「林先生が驚く初耳学!」 朝日新聞「売れてる本」(武田砂鉄さん) 各メディアで紹介されて話題沸騰! ! 「みんな仲良く」という重圧に苦しんでいる人へ。 人付き合いのルールを知り少しの作法を身に付けるだけで、複雑な人間関係の中で必要以上に傷つかず、しなやかに生きられるようになる処方箋のような本! 友だちは何よりも大切。でも、なぜこんなに友だちとの関係で傷つき、悩むのだろう。人と人との距離感覚をみがいて、上手に“つながり"を築けるようになろう。 「みんな仲良く」という理念、「私を丸ごと受け入れてくれる人がきっといる」という幻想の中に真の親しさは得られない! 人間関係を根本から見直す、実用的社会学の新定番書。 これでもう、「みんな仲良く」のプレッシャーとはさようなら。 【反響の声、ぞくぞく! 】 まずは目次を見てほしい。 友だち、人との付き合い方のすべてが書かれています。 この本に書かれているのは、生きていくために大切なことのすべてです。 人間関係とは何か。どうすればいいか。 カンタンで深い答えがここにあります。 齋藤孝さん(明治大学教授) わたしは、人付き合いが苦手。 でも「他者と共存することはできる」とこの本は教えてくれました。 多くの人が独りでいたいし、皆といたい…… そんな矛盾の原因と対処法を教えてくれる本です。 壇蜜さん(タレント) 近いと大変で遠いとさびしい他人との「間合い」のとり方。 共感という幻想から自由になる方法。 刊行から10年の「現代の古典」には、生きる上で大切な「心の智慧」が詰まっている。 茂木健一郎さん(脳科学者) 私たちは世間という幻想の中に住んでいる。 中でも厄介な「友だち」について、これほど明快に解説した本は他にない。 読めば心が軽くなる。世界がスッキリ見えてくる。 小島慶子さん(エッセイスト) かつて同調圧力に服する共同体的な作法は、生存戦略と結びついたリアリズムであった。 だがシステムが生存戦略を用済みにした今、意外にも若者の同調圧力は強くなるばかり。作法を知らずに多様性が不安なのが背景だ。 本書は不安を超えるべく新たな作法を示す。 これを読めばあなたの人生は変わるはずだ。 宮台真司さん(社会学者) 『友だち幻想』は、ひとりを怖がり、だけど人と繋がっていることに息苦しさを感じている人=わたしに必要な一冊だった。 南沢奈央さん(女優)『サンデー毎日』2018年8月19-26日夏季合併号 お互いを縛る、窮屈な友だち関係になっていませんか? 自分たちの「関係」を見つめなおす視点を、菅野さんは鮮やかに提示してくれます。 西研さん(哲学者) 第1章 人は一人では生きられない? 第2章 幸せも苦しみも他者がもたらす 第3章 共同性の幻想―なぜ「友だち」のことで悩みは尽きないのか 第4章 「ルール関係」と「フィーリング共有関係」 第5章 熱心さゆえの教育幻想 第6章 家族との関係と、大人になること 第7章 「傷つきやすい私」と友だち幻想 第8章 言葉によって自分を作り変える
著者の梶井基次郎は、体調が優れないときに美しいものを求める気持ちを描き、14編の短編小説を収めた作品集を発表しました。表題作「檸檬」をはじめ、「城のある町にて」や「雪後」など、繊細な感受性が表現されています。彼は明治34年に生まれ、31歳で肺結核により亡くなるまで、詩的な作品を発表し続けました。
本書は身近な「感情」をテーマにした哲学の入門書です。感情や人間がどういうものか哲学がどういうものかわかる一冊となっています。 本書は身近な「感情」をテーマにした哲学の入門書です。大学でおこなわれた全15回の講義をまとめたものなので、哲学を知らなくても、感情や人間がどういうものか、哲学がどういうものかわかる一冊となっています。 感情と理性は対立する? ロボットは感情をもてる? 「感情」にまつわる疑問に答える、まったくの哲学初心者にむけて書かれた入門書 私たちの生活の中心にある感情。 私たちは日々うれしくなったり悲しくなったりして過ごしています。 誰もがもつこの「感情」とはいったい何なのでしょうか? 本書は身近な「感情」をテーマにした哲学の入門書です。大学でおこなわれた全15回の講義をまとめたものなので、哲学を知らなくても、感情や人間がどういうものか、哲学がどういうものかわかる一冊となっています。 「本書は、感情や哲学に興味をもった人が最初に読む本を目指して書かれたものです。なので、この本を読むために、感情についても、哲学についても、予備知識は一切必要ありません。 タイトルに「感情の哲学」と入っていますが、哲学だけでなく、心理学や脳神経科学、文化人類学、進化生物学など、さまざまな分野での感情研究も紹介します。つまり、できるだけ多くの観点から感情について考えてみたいと思います。そのため本書は、感情に興味をもつすべての人に向けて書かれています」 (「はじめに」より) はじめに 第1講 ガイダンス 1 日常のなかの感情 2 哲学は何をするのか 3 「感情」という言葉について 4 各講義の概要 第2講 感情の本質は何か 1 本質の見つけ方 2 本質の候補 3 思考の重要性 第3講 感情と身体 1 ジェームス=ランゲ説 2 根拠となる思考実験 3 身体説の検討 第4講 感情と思考 1 志向性 2 身体と思考の組み合わせ 3 どんな思考が必要なのか 4 「感情の本質」まとめ 第5講 感情と価値/基本的な感情 1 価値の客観性 2 正しい感情と誤った感情 3 基本感情 4 感情価 第6講 複雑な感情/感情と文化 1 感情の混合 2 高度な思考に基づく感情 3 文化の影響 第7講 無意識の感情/ロボットの感情 1 感覚と無意識 2 感情の役割 3 ロボットは感情をもてるか 4 意識のハード・プロブレム 第8講 他人の感情を見る 1 他我問題 2 「見る」とはどういうことか 3 表情は感情の表象か 4 表情は感情の部分 第9講 感情と気分/感情と痛み 1 感情と気分を分ける基準 2 なぜ憂うつになるのか 3 痛みの感情的側面 第10講 感情と理性は対立するか 1 感情は合理的でないのか 2 VMPFC損傷 3 二重過程理論 第11講 道徳哲学と感情の科学 1 道徳的判断 2 トロリー問題の二つのシナリオ 3 功利主義と義務論 4 道徳と二重過程 第12講 恐怖を求める矛盾した感情 1 負の感情のパラドックス 2 消去説 本当は怖がっていない 3 補償説 恐怖と喜びを同時に抱く 4 フィクションが関わる場合 第13講 感情とフィクション 1 フィクションのパラドックス 2 錯覚説 フィクションを現実と間違える 3 ごっこ説 怖がるフリをしている 4 思考説 思い浮かべて怖くなる 5 二つのパラドックスを合わせる 第14講 感情とユーモア 1 愉快な感情 2 笑いとコミュニケーション 3 ユーモアとは何か 4 不一致と、あと何か 第15講 全体のまとめ 1 感情をコントロールする 2 読書案内 あとがき 文献一覧
この書籍は、児童精神科医の著者が「反省以前の子ども」と呼ばれる、認知力が弱い子どもたちに焦点を当てています。特に「境界知能」の人々に注目し、彼らを社会生活に適応させるための実践的なメソッドを提供します。著者は非行少年との経験を通じて、教育システムや社会での支援の必要性を訴えています。目次には、子どもたちの特徴や教育方法についての章が含まれています。著者は立命館大学の教授であり、子どもたちの支援活動を行っています。
この文章は、ジェーン・オースティンの名作についての紹介です。作品は、経済的理由で好きではない人と結婚することの是非や、幸福な結婚を求める女性の悩みを描いています。エリザベスとダーシーの誤解から始まるラブロマンスは、心理描写が豊かでユーモラスであり、読後には幸福感をもたらします。新訳版には美しい19世紀の挿絵が収められています。オースティンは1775年に生まれ、1817年に亡くなった英国の女性作家で、鋭い人間観察が特徴です。
この書籍は、人工知能(AI)の進化が経済、社会、政治に与える影響を探求しています。著者は、AIが人間の頭脳に追いつく2030年までに多くの職業が失われる可能性があり、最大で人口の9割が失業する恐れがあると警告します。これに対処するため、著者はベーシックインカム(BI)の導入を提唱し、社会保障を一元化して全ての人に生活保障を提供する必要性を論じています。AIの未来とそれに伴う社会の変化について、経済学者が考察を行っています。
ネットが政治を動かす時代に、旧いままの民主主義をどう変えるか。分断と排除で動くヘタレリベラルと無法社会ニッポンを斬る挑戦状。 分断と排除で動くヘタレリベラルが変わるには? ネットが政治を動かす時代に、旧いままの民主主義をどう変える? 無法社会ニッポンに喝を入れる斬新な挑戦状。
著者チャールズ・ブコウスキーの短編集は、彼の酔っぱらった日常と性愛を描写しています。主人公は悲しみに溺れながらも、卑猥で下品な世界で生き、瞬間的な愛を求めます。作品は、町の美女や競馬、売春宿など多様なテーマを扱い、カルト作家としての彼の独特な視点を反映しています。ブコウスキーは多くの職業を経て、創作活動を続け、最終的には50冊以上の作品を残しました。
動物たちは飲んだくれの農場主ジョーンズを追い出し、「動物農場」を設立し、平等な社会を目指す。しかし、知力に優れたブタが権力を握り、特権を拡大していく過程で全体主義の問題が浮き彫りになる。これは権力構造への批判を寓話的に描いたオーウェルの風刺文学の名作である。
二十億光年の孤独 十八歳 六十二のソネット 62のソネット+36 愛について 絵本 あなたに 21 落首九十九 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎詩集 旅 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎詩集 うつむく青年 谷川俊太郎詩集 ことばあそびうた 空に小鳥がいなくなった日 夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった 定義 タラマイカ偽書残闕 谷川俊太郎詩集. 続 そのほかに コカコーラ・レッスン ことばあそびうた. また わらべうた わらべうた. 続 みみをすます 日々の地図 どきん 対詩 手紙 日本語のカタログ 詩めくり よしなしうた いちねんせい はだか メランコリーの川下り 魂のいちばんおいしいところ 女に 詩を贈ろうとすることは 子どもの肖像 世間知ラズ ふじさんとおひさま モーツァルトを聴く人 真っ白でいるよりも クレーの絵本 谷川俊太郎詩集 みんなやわらかい クレーの天使 minimal 夜のミッキー・マウス シャガールと木の葉 すき 私 子どもたちの遺言 トロムソコラージュ 詩の本
2015年にドイツで公開され、240万人を動員した映画の原作が日本で文庫化されました。このベストセラー小説では、ヒトラーが現代に蘇り、周囲の人々が彼を芸人だと誤解することで引き起こされる喜劇が描かれています。ドイツで250万部を売り上げ、42言語に翻訳された問題作です。著者はティムール・ヴェルメシュで、翻訳は森内薫が担当しています。
「考える」ためには何が重要か 多様性の時代の利他と利己 私はプロセスの途中にいる時間的存在 自分が自分であることの意味 民主主義とは何か わかりあえなさをつなぐということ
『藤十郎の恋』は、元禄期の名優坂田藤十郎の偽りの恋を描いた作品を含む、歴史物の短編小説集です。収録されている作品には、仇討ちを否定する『恩讐の彼方に』や『忠直卿行状記』などがあり、著者の菊池寛は封建性の打破を目指し、多様な題材と独自のテーマで知られています。菊池寛は1888年に生まれ、作家としての地位を確立し、文壇の大御所と呼ばれました。
十日前に結婚したアル中の笑子とホモの睦月は、セックスレスの奇妙な関係を持ちながらも、お互いを許し合い、愛し続ける。彼らの結婚を通じて、誠実さや友情、恋愛の本質が浮かび上がる。傷つきながらも愛を求める人々に贈る純度100%の恋愛小説。著者は江國香織。
この文章は、ミゲル・デ・セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』の内容を章ごとに紹介しています。物語は、主人公ドン・キホーテが騎士としての冒険を追求し、従者サンチョ・パンサとのユーモラスな対話や様々な冒険を通じて、幻想と現実の間で葛藤する様子を描いています。最終的には、ドン・キホーテの死に至るまでの旅が描かれています。
ミラン・クンデラの作品は、パリ亡命時代に発表された恋愛小説で、ドン・ファンの外科医トマーシュ、田舎娘テレザ、奔放な画家サビナの愛の悲劇を描いています。背景には「プラハの春」とその凋落があり、人生の軽さとその耐えがたさについて問いかけています。
小さな部屋.禅僧.閑山.紫大納言.露の答.桜の森の満開の下.土の中からの話.二流の人.家康.道鏡.夜長姫と耳男.梟雄.花咲ける石. 参考資料 和田博文編:p446 著者目録 関井光男編:p448~453
『注文の多い料理店』は、宮沢賢治の唯一の童話集で、全編と19編の地方色豊かな童話を収録しています。作品は、賢治が愛した岩手県の住人たちとの出会いを描いています。目次には、代表作「注文の多い料理店」や「雪渡り」などが含まれています。
「モービィ・ディック」は、巨大な白い鯨を巡る物語で、メルヴィルの最高傑作とされています。海洋冒険小説の枠を超えた独自のスタイルと象徴性を持ち、新訳として提供されています。内容は、様々な章で構成されており、鯨との遭遇や登場人物の背景が描かれています。
遺伝子操作によって新たな生物が生み出され、合成食品が主流となった近未来の世界で、巨大企業に支配された人々の中にエコロジカル宗教団体「神の庭師たち」が存在する。孤独な女性トビーと少女レンは新型ウイルスの襲来により地上が廃墟と化した中で生き残り、彼女たちの運命が描かれる。これは「マッドアダムの物語」三部作の第二作で、圧倒的な構想力と緊迫したストーリー展開が特徴の小説である。著者はカナダの作家マーガレット・アトウッド。
老漁師が84日間の不漁を経て、小舟で海に出ると、巨大カジキとの死闘が始まる。自然の厳しさに直面しながらも、屈しない人間の精神を描いた作品で、著者はノーベル文学賞を受賞した。
樋口一葉の短編小説集には、社会の底辺で苦しむ女性や思春期の恋愛を描いた作品が収められています。主な作品には『にごりえ』、遊女の姉を持つ美登利と僧侶になる信如の恋を描いた『たけくらべ』、その他の短編が含まれています。一葉は短い生涯の中で独自の文体を確立し、明治文壇で高く評価されました。
大江健三郎の長編小説は、頭部に異常を持って生まれた子どもを抱える親の恐怖と絶望を描いています。主人公は、火見子と快楽に溺れながらも、狂気の淵から再生の希望を見出そうと奮闘します。この作品は、現代人の運命を受け入れる過程を通じて、大江文学の新たな展開を示しています。
主人公ヤスミンは、黒い肌を持つ美しい女性で、マンハッタンの「人間の動物園」に住んでいます。彼女は本能に従い、五感の感覚を重視して幸福を追求しています。物語は、彼女と深い関係にある語り手の視点から描かれ、ヤスミンの「無垢」がテーマとなっています。この小説は泉鏡花賞を受賞しています。
共同パティオ 水泳チーム マジェスティ 階段の男 妹 その人 ロマンスだった 何も必要としない何か わたしはドアにキスをする ラム・キエンの男の子 2003年のメイク・ラブ 十の本当のこと 動き モン・プレジール あざ 子供にお話を聞かせる方法
大阪から上京したホステスの姉・巻子は、豊胸手術に執着し、言葉を発しない娘・緑子はノートに思いを綴る。三日間の夏を舞台に、身体と言葉の交錯を描いた感動的なドラマが展開される。これは芥川賞を受賞した作品である。著者は川上未映子で、多数の文学賞を受賞している。
行方不明の少年の事故死体を探すために旅に出た4人の少年の2日間を描いた短編「スタンド・バイ・ミー」は、少年期の友情と別れを感動的に表現している。著者の半自伝的作品であり、他に英国の奇譚クラブを描いた作品も収録されている。
井上ひさしの処女作では、四次元の大泥棒ブンが主人公となり、時間や空間を超えて奇抜な事件を引き起こします。彼の行動は権威や常識に挑戦し、ユーモラスな諷刺を生み出します。
「七王国の玉座」は、ローカス賞を受賞した大河ファンタジーの第1部で、改訂新版が登場しました。物語は、ウェスタロス大陸の七王国が冬を迎え、不安定な休戦状態にある中、ロバート王がエダード・スタークを“王の手”に任命したことで、各家の権力争いが激化する様子を描いています。著者はジョージ・R・R・マーティンで、彼はファンタジー作品「氷と炎の歌」シリーズで名を馳せています。
この書籍は、古代日本の神話や歴史を描いた「古事記」を現代語に完全翻訳したもので、特に読みやすさを重視しています。著者の竹田恒泰は明治天皇の玄孫で、解説を加えることで内容の理解を深める工夫がされています。巻末には神々や天皇の系図、主要語句の索引もあり、初心者でも読みやすいと好評です。シリーズ累計30万部を超えるベストセラーです。