【2025年】「教育」のおすすめ 本 167選!人気ランキング
- 0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす! (単行本)
- モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方 3歳 〜 12歳 の子ども対象
- モンテッソーリ教育で子どもの本当の力を引き出す! (知的生きかた文庫 ふ 31-1)
- モンテッソーリ教育は子を育てる、親を育てる お母さんの「敏感期」 (文春文庫 さ 46-1)
- 私たちは子どもに何ができるのか――非認知能力を育み、格差に挑む
- 子どもの才能を伸ばすモンテッソーリ教具100 (単行本)
- 授業の腕をあげる法則 (教育新書 1)
- 教育課程コアカリキュラムに対応した教育心理学
- 0~18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育: 子どもの可能性が広がる実践的子育てガイド
- 子供を動かす法則 (教育新書 41)
「モンテッソーリ教育」は、マリア・モンテッソーリによって創始された教育法で、特に0~3歳の子どもに焦点を当てています。この書籍では、親が子どもを自分で考え行動できるよう育てるための30の具体的な方法を紹介しています。内容は、妊娠中の準備から手作り教具、トイレトレーニング、2歳児の成長過程まで多岐にわたります。実例や写真が豊富で、家庭での実践が容易です。著者の藤崎達宏は、モンテッソーリ教育の専門家であり、全国でセミナーや講演を行っています。
この文章は、子どもの成長や潜在能力に焦点を当て、親が子どもの成長サイクルを理解し予習する重要性を強調しています。モンテッソーリ教育を通じて、子どもの自律や集中力を育てる方法を提案し、家庭で簡単に実践できることを紹介しています。これにより、子育てが楽しくなり、子どもの未来を輝かせることができると述べています。
この書籍は、モンテッソーリ教育の専門家である相良敦子が、子育てのポイントを「親育て」という観点から解説したものです。内容は、子どもの「敏感期」やお母さんの「敏感期」、自律と自立に関するキーワード、家庭での手づくり教材、子育ての重要な鉄則などが含まれています。育児書のロングセラーが文庫化された一冊です。
本書は、子どもの貧困が「非認知能力」の獲得機会を奪うことに焦点を当て、成功に必要な力(やり抜く力、好奇心、自制心など)を育む方法を最新の研究と事例を基に解説しています。著者ポール・タフは、特に貧困家庭の子どもにおける非認知能力の重要性を示し、具体的な育成方法を探求しています。教育者や親にとって、子どもの教育と貧困問題に関する貴重な示唆を提供する一冊です。
本書は、モンテッソーリ教育に基づく子どもの成長を促すための100の教具を紹介しています。特に0~6歳の「敏感期」における教具の重要性が強調されており、適切な教具が自律心や集中力、自己肯定感を育むとされています。著者はモンテッソーリ教育の専門家で、家庭で簡単に実践できる方法を提案しています。さらに、無料の素材ダウンロード特典も提供されています。
この書籍は、モンテッソーリ教育の理念と実践方法を紹介し、親が楽になり子どもが成長するための68のスキルを提供しています。内容は、モンテッソーリ教育の基本原則や家庭での実践、家族の生活の改善に焦点を当てています。著者は、モンテッソーリ教育の専門家であり、教育の重要性を強く感じている経験豊富な教育者たちです。
算数や国語の学力、粘り強さ、自己制御力、思いやり……、生まれた瞬間から最初の数年間に、親や保育者が子どもとどれだけ「話したか」ですべてが決まる。日本の子育て、保育が抱える課題とその解決策を、科学的な裏づけと著者自身の具体的な実践から示した書。 第1章 つながり:小児人工内耳外科医が社会科学者になったわけ 第2章 ハートとリズリー:保護者の話し言葉をめぐる先駆者 第3章 脳の可塑性:脳科学革命の波に乗る 第4章 保護者が話す言葉、そのパワー:言葉から始めて、人生全体の見通しへ 第5章 3つのT:脳が十分に発達するための基礎を用意する パート1:科学から実践へ パート2:「3つのT」の実際 第6章 社会に及ぼす影響:脳の可塑性の科学は私たちをどこへ導くのか 第7章 「3000万語」を伝え、広げていく:次のステップ エピローグ 岸に立つ傍観者であることをやめる 解説 子どもの言葉を育む環境づくり(高山静子) 訳者あとがき(掛札逸美)
本書は、子どもの才能を引き出すための方法をマンガ形式で紹介しています。特に、モンテッソーリ教育に基づき、子どもの「困った行動」を「輝く才能」として捉え、集中力や自立心を育むメソッドを提案。ハーバード大学の多重知能理論を取り入れた「9つの知能」を活用し、運動能力やコミュニケーション能力を伸ばすアクティビティも紹介しています。著者は乳幼児教育の専門家で、子どもの成長をサポートする具体的な方法を提供しています。
このテキストは、教育心理学に関する包括的な教材で、大学や短大の教職課程、教職を目指す学生、既に教職にある人の学び直しに適しています。2017年に改訂され、法律や指導要領の変化に対応し、演習問題を充実させています。内容は、教育心理学の基本から発達、学習メカニズム、授業の心理学、教育評価、知的能力、パーソナリティ、社会性、学級の心理学、不適応、特別支援教育に関する章で構成されています。付録には演習問題の解答や重要用語の解説も含まれています。
本書は、子どもが持つ「自ら育つ力」を理解し、その力を引き出すためのモンテッソーリ教育の実践方法を紹介します。0~6歳の子育てにおける親の悩みや疑問に対し、具体的な対応法を提案し、子どもを信じて育てる重要性を強調しています。著者はモンテッソーリ教師で、家庭での教育実践に役立つ情報を提供しています。
本書は、モンテッソーリ教育を通じて3歳から6歳の子どもに言語力、数字力、協調性、創造力を育む方法を紹介しています。著者は、子どもが自立し成長する力を引き出すための30の実践的なメソッドを提案し、特に自主性を重視しています。また、適切な教育法や子どもへの接し方についても触れています。著者はモンテッソーリ教育の専門家であり、全国で子育てセミナーを開催しています。
この本は、モンテッソーリ教育を通じて子どもの才能を伸ばす方法を紹介しています。著者の藤崎達宏先生が、家庭で簡単に実践できる具体策をマンガ形式で解説しており、子どもの成長における「敏感期」や適切な声がけの方法などが含まれています。親が子どもの成長を理解し、育児を楽にするための情報が豊富に提供されています。モンテッソーリ教育の基本や実践テクニックを学びながら、親子で楽しく育児に取り組むことができる内容です。
この書籍は、教師が子どもとの「ちょうどいい距離感」を築くための対話の技術を紹介しています。子どもの成長において教師の言葉が持つ影響を重視し、子どものニーズや保護者の期待を理解し、効果的にコミュニケーションを図る方法を提案しています。内容は、子どもの「欲しい」を感じ取る方法、ニーズを創出する技術、対話力の基本、教師自身の心構え、状況に応じた即興力について構成されています。著者は教育現場での経験を活かし、国内外での教育支援活動にも取り組んでいます。
本書は、子育て中の親が直面するイライラや困難を軽減するために、子どもに「おしごと」を与えることの重要性を説いています。モンテッソーリ教育に基づき、子どもの才能を伸ばすための具体的な方法や、親子の信頼関係を築くためのポイントが紹介されています。著者は、乳幼児教室を運営し、発達障害の子ども向けの支援も行っています。全体を通じて、子どもと一緒に成長し、幸せな子育てを楽しむためのヒントが提供されています。
モンテッソーリ流、自立した子が育つ<あそび>のレシピを紹介。国際モンテッソーリ協会0-6歳ディプロマ北川真理子氏監修。 モンテッソーリ流、自立した子が育つ<あそび>のレシピを紹介。SNSで注目を集める国際モンテッソーリ協会0-6歳ディプロマ北川真理子氏監修、その他人気インスタグラマー多数による製作あそびの提案。 時間やお金をかけなくても、 モンテッソーリ教育の考え方を取り入れた<あそび>で、 自立した子 が育つ――子どもの発達をうながす、おうちでできる<あそび>のレシピを紹介します。 ねんねの時期には、赤ちゃんが「見る対象」とできるような モビール を。1歳前後からは指先を鍛える ○○落としや ○○通し、 ハートバッグ など。自分でできた!を実感する、日常生活のあそびとして ごますり や マジックテープ、バックルとめ。分類や整理に興味がある時期には 実物合わせ や 色分け あそびを。文字や数に興味がある時期には 数字並べ や 時計の活動、 壁かけ五十音 など。いずれも家庭にあるものや、百円均一で揃えられるものを使ったあそびです。 ★★QRコードから 一部のあそびの型紙や台紙をダウンロードできます★★各あそびについて、「どの力が伸びるあそびか」「あそぶときのポイント」を国際モンテッソーリ協会0-6歳ディプロマ、保育園・幼稚園での現場経験もある北川真理子先生が解説します。製作あそびは、Instagramなどで知育あそびを発信している人気の方々が、わかりやすく紹介します。「自宅で、子どもとどうやってあそんだらよいか」「せっかくだから、子どもの発達をうながすあそびがしたい」「モンテッソーリ教育に興味があるけれど、何から始めたらいいかわからない」と感じているパパママに是非おすすめしたい1冊です! はじめに 本書の使い方 QRコード特典の使い方 序章 モンテッソーリ教育のきほん 1章 ねんねの時期のあそび 2章 指先を鍛えるあそび 3章 自分でできた!日常生活の練習 4章 分類・整理のあそび 5章 文字・数のあそび コソダチショップ おわにり クリエイター紹介 コラム 赤ちゃんの言語教育 ゆるっと「旅育」! 家事参加で無理なく子どもの力を伸ばす 自己表現の芽をつまないために
この本は、子育てにおける悩みや問題に対する具体的な対処法をモンテッソーリ式教育を通じて解説しています。特に1~3歳の子どもに向けた言葉かけや生活環境の整え方、遊び方を紹介し、家庭で実践できる工夫が詰まっています。著者は国際モンテッソーリ協会認定の教師で、子どもの個性や自立を育む方法を提案しています。日本語監修にはモンテッソーリ教育の専門家が関わっています。
本書は、教師1年目から効果的に働くための仕事術を紹介しています。学級づくりや日々の働き方を考えるための思考法や、仕事に追われないための3つのステップ(ビジョンの明確化、多様なアイデアの提示、実行の継続)を提案。内容は、仕事のデザイン、学級の1日・1年の計画、時間を生み出すタスクデザインなど多岐にわたります。著者は15年間の公立小学校教諭を経て、オルタナティブスクールで活動する青山雄太氏です。
サイバーエージェントの人事部門役員、曽山哲人による「抜擢メソッド」を紹介する書籍です。このメソッドは、若手社員が自発的に成長する環境を整える方法を解説しており、マネジャーやトレーナー向けに設計されています。内容は、若手が「やりたい」と言える空気の作り方、自走スイッチを入れる方法、成長サイクルの回し方などで構成され、実践的なワークシートも含まれています。
この書籍は、348種類の職業を紹介し、それぞれの仕事内容、魅力、勤務実態、なり方を詳述しています。人気職業から社会を支える職業まで幅広くカバーし、注目のトピックや先輩インタビューも含まれています。内容は13の業界に分かれており、小学校高学年から中学生向けに「好き」な分野から職業を探せるようになっています。著者は筑波大学の教授で、キャリア教育の専門家です。
この文章は、奈須正裕教授が著した教育に関する内容を紹介しています。テーマは「令和の日本型学校教育」で、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させる方法を探るものです。山形県天童市立天童中部小学校を実践校として、教師の理解と覚悟を基にした教育活動が展開され、子ども主体の授業の実現を目指しています。目次には、子どもの自立的学習や教師の専門性の再考などが含まれています。
著者は「全米最優秀女子高生」コンテストで優勝した娘を持つ日本人ママで、AI時代において重要な非認知能力を育てる教育の必要性を説いています。彼女の実践的ルール集では、心の強さやコミュニケーション能力、自己肯定感を育む方法が紹介されています。目次には、非認知能力の定義や、ルール作り、親子対話、遊びを通じた学び、自己受容、そして子どもの「好き」を見つけることが含まれています。著者はライフコーチとしても活動し、子育てやキャリアについて講演を行っています。
本書は、子どもが学び適応する過程を理解し、支援に必要な知識を提供する内容です。学びの意欲や仕組み、個別の支援方法、社会性の学びについて解説しており、教育現場で実践的に活用できる情報を提供しています。旧版の修正に加え、新しい項目も追加され、変化する教育環境に対応した改訂版です。著者は中澤潤氏で、千葉大学の名誉教授です。
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづけるスーパー名著!新卒の教師でもすぐに子供を動かせるようになる「法則」。 第1章 子供を動かす原理原則編(子供を動かす法則(群れとして動かす場合)-一つの法則と五つの補則 子供を動かす原則(組織として動かす場合)-三つの原則と九つの技能 新卒教師の教室は、なぜ混乱するか 「いじめ」の構造を、まず破壊せよ! 「プロの目」は、修業によって培われる 存在感が実感できてこそ子供は動く) 第2章 子供を動かす実践編(厳しく「教える」だけが動かす方法ではない 朝会に全校児童を集合させる 応援団の子供たちを動かす 指導方法を工夫して子供を動かす やるべきことを一人一人に示せ-卒業式よびかけの練習)
この本は、将来の夢が見つからない子どもたちに向けて、576種類の職業をマンガとイラストで紹介しています。主人公の12歳のユメオが宇宙人ワプリンと共に地球の仕事を見に行く冒険を通じて、さまざまな職業やその背後にある人々の思いを知ることができます。幅広い職種をカバーし、仕事の本質や未来についても考えるきっかけを提供。全漢字にふりがなが付いており、小学生から大人まで楽しめる内容です。将来に迷っている子どもたちに、新たな視点を与える一冊です。
「潜在連想」という視点から実証的に生徒のホンネに迫り,「偽装○○嫌い」の検出と救出を試みる。「教育の科学化」への挑戦。 日本の中学生の4割以上は「数学嫌い」であるというアンケート調査の結果は,本当に「科学的」であると言えるのか? 本書では,「潜在連想」という視点から実証的に生徒のホンネへと迫り,「偽装○○嫌い」の検出と救出を試みる。中学校教諭と教育心理学者による「教育の科学化」への挑戦。集団式簡易潜在連想テストの実施マニュアル付き。 ◆主な目次 はじめに 第1章 証拠に基づく教育の必要性 第2章 国際調査での日本の子どもたちの成績 第3章 アンケート調査の問題点 第4章 潜在連想構造を探る新しい検査法:こころのX線検査 第5章 学校教育現場で使える集団式潜在連想テストの開発 第6章 「偽装数学嫌い」生徒の検出 第7章 「偽装数学嫌い」生徒の救出 第8章 「こころのX線検査」のその他の活用例 第9章 教育の科学的研究の重要性:まとめに代えて 付 章 FUMIEテスト実施マニュアル おわりに はじめに 第1章 証拠に基づく教育の必要性 1.教育は間違った印象に左右されやすい 2.証拠に基づく教育 3.何が証拠なのか 1)調査結果は証拠にならない 2)因果関係の証拠はランダム化比較対照実験でしか得られない 3)ランダム化比較対照実験だというだけでは証拠不十分 4.この本で述べたいこと 第2章 国際調査での日本の子どもたちの成績 1.国際学力調査 2.PISA調査 1)「ゆとり教育」とPISAショック 2)幻だったPISAショック 3.TIMSS調査 1)TIMSS調査に現れた日本の子どもの特徴 2)「成績が良くて好き」から「成績が良いのに嫌い」になる 4.日本の子どもは嘘をついているのではないか 第3章 アンケート調査の問題点 1.学校で多用されるアンケート調査 2.アンケート調査の問題点:回答者が嘘をつく 1)嘘を見破る工夫 2)嘘をつかせない工夫 3)善意の嘘 3.アンケート調査の問題点:意識と無意識 1)フロイトの無意識とヘルムホルツの無意識 2)ロールシャッハテストの限界 4.国際学力調査のアンケート結果も正しいとは限らない 第4章 潜在連想構造を探る新しい検査法:こころのX線検査 1.潜在意識の科学的研究:プライミング効果 2.知識ネットワークモデルと潜在的認知プロセス 3.潜在的社会的態度測定のための潜在連想テストの開発 1)潜在的プロセスを反応時間で探る 2)反応時間の差に表れる潜在連想構造 4.潜在連想テストの活用の広がりと発展 1)プロジェクト・インプリシット 2)単一の測定対象のための潜在連想テスト 第5章 学校教育現場で使える集団式潜在連想テストの開発 1.学校では潜在連想テストは使えない 2.紙版の潜在連想テストというアイディア 3.集団式簡易潜在連想テスト「FUMIEテスト」の開発 1)キー押し反応の代わりに○×をつける 2)「速さ」を1分間の作業量で測る 3)ターゲット分類課題の廃止 4)評価語の選択と単語の提示順序の決定 5)作成されたFUMIEテストの信頼性と妥当性を測る 6)より良いものにするため改良を重ねる 第6章 「偽装数学嫌い」生徒の検出 1.学校での「研究」とは 2.FUMIEテストを用いた「偽装数学嫌い」生徒の検出 1)なぜ日本の中学生は数学を嫌うのか 2)中学生のホンネを探る 3.なぜ「数学嫌い」を偽装するのだろうか 第7章 「偽装数学嫌い」生徒の救出 1.やらなければ負けない 2.「偽装数学嫌い」生徒の戦略 1)数学と性差のステレオタイプとその真偽 2)不安と自信と自己暗示 3)間違った自己暗示の修正 3.「偽装を見破ること」の効果の科学的検証:ランダム化比較対照実験 1)「偽装数学嫌い」生徒の検出と2分割 2)「偽装数学嫌い」生徒の半分への潜在意識調査結果のフィードバック 3)効果の検証 4.この研究から得られた「証拠」 1)嘘の情報では効果が見られない 2)より確かな「証拠」とするために 第8章 「こころのX線検査」のその他の活用例 1.世界から取り残される日本の教育研究者たち 2.「こころのX線検査」の活用例 1)中学生の教科嫌いと潜在意識の乖離 2)中学生の集団登山前後での「登山」に対する潜在意識の変化 3)障害者に対する潜在的態度測定 4)外国人に対する潜在的態度測定 3.その他の「こころのX線検査」の活用の可能性 1)「学校」に対して否定的な潜在イメージを持つ生徒への予防対策 2)不登校児童生徒の「学校」に対する潜在イメージの変化 3)「ひらめき☆ときめきサイエンス」の効果の科学的検証 4)中学生の潜在的な価値観:中学生にとって一番「良いイメージのもの」 4.「こころのX線検査」という新しいツール 第9章 教育の科学的研究の重要性:まとめに代えて 1.教育の科学化 2.ランダム化も比較対照も科学の常識 1)比較対照条件の重要性 2)ランダム化が必要な人文社会科学系の実験 3.実験を120年以上前に導入した心理学 4.「教育の科学化」と実験教育学・教育心理学 5.教育心理学の停滞と復権 6.学校におけるランダム化比較対照実験の重要性の理解と協力 付 章 FUMIEテスト実施マニュアル おわりに 文献 索引
著者の小川大介氏は、中学受験のプロとして、多くの教え子を難関校に合格させてきた経験を基に、「本当に頭がいい子の育ち方」について語ります。彼は、子どもが親に見守られながら好奇心を育むことで、自ら学び成長することが重要だと強調します。本書では、子育てにおいて「否定しない」「与えすぎない」「あせらない」ことの重要性や、親が楽しむことが子どもに良い影響を与えることなど、実体験と心理学に基づく子育て法を紹介しています。
『幼稚園では遅すぎる』の続編である本書は、幼児教育に関する新しい子育て法を提案しています。著者は25年の研究を経て、母親の影響力や環境づくり、子どもの興味を引き出すことの重要性を強調しています。具体的には、母親が育児に専念することや、子ども同士の遊びを促すこと、興味を大切にすることが成長に繋がると述べています。
この書籍は、高学年から成長する子どもたちのための家庭環境や学習方法について解説しています。親が家庭でできる工夫を紹介し、子どもが成長するための環境作りや習慣、自由時間の重要性を強調しています。著者は花まる学習会の代表で、教育における実践的な知識が詰まっています。
ジョビィキッズは、芦田愛菜、鈴木梨央、寺田心などの子役タレントを育成する事務所で、子育てメソッドを紹介しています。本書では、子供のやる気、自信、素直さ、折れない心、個性を育てる方法を解説し、親とのコミュニケーションを通じて子育てをサポートするヒントが満載です。
本書は、ゼネラル・エレクトリック社(GE)の幹部研修プログラムでの学びを元に、「成長し続ける人」の共通点を探る内容です。著者はGEのクロトンビルでリーダーシップ研修を担当した田口力氏で、自己認識、伝達力、意思決定、学び続ける姿勢、変化への適応、自分の運命をコントロールすること、他者を導くことなど、成長に必要な要素を解説しています。
このテキストは、教育心理学の基本理論や知見を実践に活用する方法をわかりやすく解説した教材です。学校教育だけでなく、社会や家庭での教育活動にも応用可能です。最新版では「教職課程コアカリキュラム」に対応し、新たに「学級集団づくり」や「学習評価」の章、さらには「運動発達」についてのコラムが追加されています。著者は法政大学の藤田哲也教授です。
本書は、子育てに悩むママたちが抱える罪悪感に寄り添い、自己肯定感を高めるためのガイドです。著者は子育て専門カウンセラーの福田とも花で、母親が感じる「ごめんね」という思いを理解し、その背後にある心の癖や古傷に向き合うことを提案しています。自分を許し、ダメな自分でも大丈夫と認識することで、子どもとの関係も改善されると伝えています。各章では、罪悪感の原因や子どもとの関係の見直し、ハッピーママになるための方法が示されています。
生徒と教師が共に学習計画を立て、何をどう学ぶかを決めていく。人生や社会の課題解決を見据えた学び方の新たなスタンダード。 「あなたが教職を志した理由は何ですか?」 この問いかけは、本書が薦める「プロジェクト学習(Project Based Learning、以下PBL)」を学校で推進する役目を担う人物が、教師に投げかけたものです。教員は教壇に立つと、知識やスキルを伝達することに固執するあまり、つい生徒の学びをコントロールしてしまいがちです。PBLは、一つのプロジェクトを通して、自分の人生や社会の課題を解決するスキル、さらには社会のつくり手となるためのスキルを身につけるための、教師と生徒が共につくる学びの文化です。 本書では、PBLの具体的な進め方はもちろん、生徒一人ひとりをいかした学びを実現するための「質の高いPBL」について、数多くの詳細な実践例をもとに紹介しています。 さらに注目すべき点は、PBLが「教育の公平性を実現するためのツール」としての役割を果たすという信念に基づいていることです。そして、教育の公平性に関する信念は、PBLにかかわる多様な生徒同士の関係性だけでなく、教師と生徒との関係性においても貫かれています。 本書に登場する教師たちは、プロジェクトの設計段階から生徒や専門家の意見を積極的に取り入れます。計画段階では、生徒一人ひとりの違いをいかせるような豊富な足場(支援)が用意されています。さらに評価については、評価基準を生徒と一緒につくることもあります。このように、教室にいる教師と生徒が互いの公平性を保ちながら、プロジェクトを通してつくる文化がPBLの学びを最大限に引き出すのです。 PBLは教師と生徒という関係性を越えて、社会のつくり手として共に学ぶことの楽しさと大切さに気づかせてくれます。本書を通じて、教師としての自分が生徒とどんな学びの文化をつくりたいのか、そのためにできることは何かを考えさせられることでしょう。(協力者 井久保大介) 生徒と教師が共に学習計画を立て、何をどう学ぶかを決めていく。そして、社会のつくり手として共に学ぶことの楽しさと大切さに気づかせてくれます。人生や社会の課題解決を見据えた学び方の新たなスタンダード。
このテキストは、教職課程の「教育心理学」に関する内容を扱っており、文科省のコアカリキュラムに基づいて「発達」と「学習」に焦点を当てています。イラストや図表を多用し、初学者にも理解しやすく構成されており、各章には事例も含まれています。教職採用試験の対策にも適した内容で、教育心理学、発達理論、学習理論、記憶、動機づけ、教育評価、特別支援教育など幅広いテーマが網羅されています。著者は日本体育大学の教授陣です。
本書では、統計学があらゆる学問の中で最強である理由を解説し、現代社会におけるその重要性や影響力を最新の事例を通じて探求しています。著者は、統計学の基本概念や手法(サンプリング、誤差、因果関係、ランダム化など)を紹介し、統計学の魅力とパワフルさを伝えます。著者は東京大学出身の専門家で、データを活用した社会イノベーションに取り組んでいます。
学生の時にこの書籍を読んで統計学に興味を持った。統計学の魅力について分かりやすく学べる書籍。専門的な内容はそれほどないのでスラスラ読める。統計学ってどんなことができるの?なんでそんなにすごいの?ということを知りたい人がまず最初に読むべき本。
超一流の人材を輩出する世界中の「才能開発」機関を研究して解明した、自分を磨き、子どもや部下を成長させる52の秘訣。 第1章 はじめる-観察して、盗んで、バカになる(なりたい人を見つめる 1日に15分を使ってスキルを脳に刻み込む 遠慮なく盗む ほか) 第2章 スキルを伸ばす-スイートスポットを見つけて背伸びをする(スイートスポットを見つける 腕時計をはずす あらゆる動きを細分化する ほか) 第3章 上達を維持する-繰り返し、へこたれず、目標を秘密にする(繰り返しを大切にする 汗水たらして努力する 1時間の実戦のために5時間の練習をする ほか)
本書は、子どもが主体的に漢字を学ぶための新しい指導システムを提案しています。受け身の学習から脱却し、自立した学習者として成長できるようにすることが目的です。内容は、漢字指導の方法や効果的な学習活動のアイデアを紹介し、全員が漢字を定着させるためのシステムを解説しています。著者は教育者であり、数々の教育賞を受賞しています。
この書籍は、子どもの脳力を最大限に引き出すための0~3歳向けの育脳としつけに関する指南書です。親が日常生活で実践できる具体的な方法を示し、子どもが自分で考える力を育てるためのポイントを解説しています。内容は、規則正しい生活や安心感を与えること、遊びを通じた学び、親子のコミュニケーションの重要性などに焦点を当てています。著者は小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏で、専門用語を避けて分かりやすくまとめられています。
この書籍は、AIが苦手とする読解力を人間が身につける方法を提案しています。親、学校、個人ができる具体的な取り組みや、実際の授業例を紹介し、大人の読解力向上法も示しています。内容には「リーディングスキルテスト」やその分析、読解力を育むための教育方法が含まれています。著者は新井紀子で、AIと読解力に関する研究を行っています。
この書籍は、教育心理学の基礎知識と最新理論を子どもの理解と成長支援に焦点を当てて解説しています。学校での子どもの行動や教師の指導法を心理学的に考察し、理論と実践を結びつける内容です。各章の最後には実践的な視点からの留意点や課題が示されており、章末には演習問題も用意されています。著者は筑波大学名誉教授の櫻井茂男と福井県立大学教授の黒田祐二です。
本書は、将来性があり、長く続けられ、AIに取って代わられにくい仕事を100種厳選して紹介しています。内容は「ものづくり」「医療・福祉」「ホスピタリティ」「自然」「科学・テクノロジー」「新しい仕事」の6章に分かれ、各職業のリアルな声を取材しています。特に、AIによる影響や新型コロナ禍による働き方の変化に触れ、未来に残る職業や消える職業を特製マップで示しています。小学生から中学生向けで、親子で学べる内容となっています。
子どもたちの小さな日常に注目したEPISODEなど,学ぶ意欲を引き出し考えさせる工夫が豊富で理解を深めやすい入門書です 【QUESTION】や【EPISODE】を手がかりに,子どもたちの小さな日常から学びを深める入門書。章末には教師やSCなどがよくであう困難事例/指導場面/判断に迷う場面の【EPISODE】と検討課題が示され,理解確認とさらなる学びを促します。 序章 エピソードに学ぶ──困難な時代の子どもの学びと育ちの豊かさ Ⅰ部 子どもの育ち──発達を理解する 1章 思考の育ち──認知発達 2章 喜怒哀楽の育ち──情動発達 3章「わたし」の育ち──社会化と自己の発達 Ⅱ部 学校で育つ子ども──学びの過程を理解する 4章 学びの基礎──学習,記憶,メタ認知 5章 やる気がでるとき,でないとき──動機づけ 6章 教え方,学び方──学習指導 7章 学びの捉え方──教育評価 Ⅲ部 教室づくり,仲間づくり──学びあう場を支える 8章 仲間との学びあい──協同学習 9章 仲間との関係──適応,社会的学習,ソーシャルスキル 10章 学びと育ちを支える教室──教師─子ども関係,学級風土・学校文化 Ⅳ部 みんなのための学校──個に寄りそい,育ちあう 11章 子どもの困難の理解と支援──学校カウンセリング 12章 個のニーズに応じた学び──特別支援教育
探究! 教育心理学の世界 目次 まえがき 習得編 1 教育心理学とは 教育心理学の定義と課題 藤澤伸介 教育心理学の魅力と方法 無藤 隆 2 発達のメカニズム 教育と遺伝要因 安藤寿康 発達理論と発達段階 中澤 潤 発達研究法 飯高晶子 身体の発達と心への影響 松嵜くみ子 言語と認知の発達 内田伸子 社会性と情緒の発達 大久保智生 道徳性の発達 二宮克美 3 学習のメカニズム 学習とは何か 藤澤伸介 記憶のメカニズム 井上 毅 知識としての記憶 井上 毅 記憶と転移 寺尾 敦 習得のための学習法 藤澤伸介 探究力と創造性の獲得 楠見 孝 態度 犬塚美輪 4 学習を支える教育実践 教授学習の行動主義的基礎 小野浩一 目標・診断・評価 藤澤伸介 学習意欲 鹿毛雅治 授業づくり 鹿毛雅治 学習スタイルと教授スタイル 小林寛子 5 「ニーズ」と援助 学校教育とカウンセリング 伊藤亜矢子 しつけと学習の援助 鈴木雅之 学級風土と学級経営 伊藤亜矢子 6 特別支援教育 教師教育における特別支援 小沼 豊 障碍の理解─通常の学級における特別支援教育 小貫 悟 人権と特別支援教育 松田信夫 7 教育とICT 教育の情報化 田中俊也 情報機器活用の可能性と評価 田中俊也 ネット化浸透の負の側面 高比良美詠子 探究・活用編 1 教育 トピック1-1 教育理解の諸アプローチ 中澤 潤 トピック1-2 日本の学校教育と心理学 市川伸一 2 発達 トピック2-1 ピアジェ理論を考える 中澤 潤 トピック2-2 ギリシア神話と心理学 小川俊樹 トピック2-3 モンテッソーリ教育を考える 飯高晶子 トピック2-4 エリクソン理論を考える 山岸明子 トピック2-5 母語の獲得 大津由紀雄 トピック2-6 中高生の社会性 大久保智生 トピック2-7 知能について 安藤寿康 3 学習 トピック3-1 日本の学習者の実態 ─「高水準な義務教育の成果」の裏で 山森光陽 トピック3-2 ごまかし勉強 藤澤伸介 トピック3-3 学習観と学習法の選択 吉田寿夫 トピック3-4 学習習慣 藤澤伸介 トピック3-5 記憶と学習の意味 前野隆司 トピック3-6 自己調整学習 篠ヶ谷圭太 トピック3-7 予習の効果 篠ヶ谷圭太 トピック3-8 学習方略としての概念形成 藤澤伸介 トピック3-9 概念受容学習と概念発見学習 工藤与志文 トピック3-10 学習方略の活用 藤澤伸介 トピック3-11 ノートの活用 藤澤伸介 4 学習を支える教育実践 トピック4-1 ガニェの分類と学習指導要領 鈴木克明 トピック4-2 教師の成長 藤澤伸介 トピック4-3 学習指導要領と学校現場の乖離 藤澤伸介 トピック4-4 学力テストの実施法 藤澤伸介 トピック4-5 指導要録・通知表・内申書 鈴木雅之 トピック4-6 テストの統計的基礎 村井潤一郎 トピック4-7 指名と発問 藤澤伸介 トピック4-8 黒板の活用 藤澤伸介 トピック4-9 教授の基本原理 藤澤伸介 トピック4-10 集団思考と単独思考 釘原直樹 トピック4-11 教えて考えさせる授業 ─中学の数学を中心に 市川伸一 トピック4-12 習得の基礎としての「読解力」の指導 犬塚美輪 トピック4-13 母語獲得と外国語学習の違いから見えてくる 言語教育のあり方 大津由紀雄 トピック4-14 英語学習プロセスを探る ─中学生の英文主語把握 金谷 憲 トピック4-15 学習指導要領改訂と英語力経年変化 斉田智里 トピック4-16 理科教育における動機づけの可能性 飯高晶子 トピック4-17 社会科における誤概念の修正 進藤聡彦 トピック4-18 学級はどう変化していくか 伊藤亜矢子 トピック4-19 習熟度別少人数学習集団編制 山森光陽 トピック4-20 応用行動分析学の教室での活用 平澤紀子 トピック4-21 居眠り・私語・カンニング 釘原直樹 トピック4-22 学級崩壊 小林正幸 5 「ニーズ」と援助 トピック5-1 認知カウンセリング 藤澤伸介 トピック5-2 TET(教師生徒関係訓練法) ─望ましい教師と生徒関係 市川千秋 トピック5-3 予防的援助に一般意味論の活用を 藤澤伸介 トピック5-4 ブリーフカウンセリング ─解決焦点化アプローチ 市川千秋 トピック5-5 認知行動療法 神村栄一 トピック5-6 中1ギャップ 村栄一 トピック5-7 構成的エンカウンターグループ 野島一彦 トピック5-8 生理学的病態としての不登校理解 三池輝久 トピック5-9 モンスターペアレント 小野田正利 6 これからの教育を考える トピック6-1 日本の特別支援教育 山口豊一 トピック6-2 フィンランドの教育からの知見 福田誠治 トピック6-3 ニュージーランドの教育からの知見 植阪友理 トピック6-4 21世紀型教育 森 敏昭 あとがき 引用文献 索引 〔付録〕索引活用ガイド 著者一覧 装幀=藤澤伸介
よい教育とは何か?それはどのようにすれば実現できるのか?ゆとりか詰め込みかなど不毛な対立を廃し、真の意味での教育の意義を探る 「ゆとり」か「詰め込み」かなど、教育を巡る議論には様々な対立と齟齬が渦巻いています。こうした混乱を越え、どうすれば〈よい〉教育を作ることができるのか。〈よい〉教育のためにはどのような学校がいいのか? そのための教師の資質とは? 本書は義務教育を中心にどのような教育が本当に〈よい〉と言えるのか、それはどのようにすれば実現できるのかを原理的に解明し、その上で、その実現への筋道を具体的に示してゆきます。 「ゆとり」か「詰め込み」か、「平等」か「競争」かなど、教育を巡る議論ほどに対立と齟齬が起こっている問題はないと言っても過言ではありません。しかしそれらは、論者の個人的な感想や思い込みによる独りよがりである場合がほとんどです。みんなが善意と熱意を持って教育を論じるのだけれど、ある種、独りよがりな「思い入れ」や「思い込み」が先走ってしまい、不毛な対立が至るところで引き起こされてしまっている……それが教育を巡る言説の現実ではないでしょうか。しかし、この種の「対立」は冷静に考えてみれば錯覚であることが少なくありません。「ゆとり」か「詰め込み」かと二項対立で問われると、人はつい、どちらかの立場に与してしまいます。しかしそれは実は「問い方のマジック」に陥っているだけなのです。こういった偽の問題による不毛な対立を避けた、本当に意義のある教育を巡る議論が、いまこそ必要とされているのではないでしょうか。こうした混乱に終止符を打つためには教育、とりわけ公教育はそもそも何のために必要なのかをまず定義しなければなりません。著者の考えによるなら、それは一人一人の子供が近代社会のルールを身につけその中でより自由に生きられるようになることということになります。個々の子供の自由の感度こそが社会に対する信頼の土台となり、みんなでよりよい社会を作るという真の意味での市民参加型の民主主義社会の礎となるのです。では、どうすればそのような〈よい〉教育を作ることができるのでしょうか。著者の提案は様々ですが、その一つは、一方的に教師の授業を聞くという受け身の授業を改め、子供たちがある一つのテーマに関して自ら調べ、お互いに教え合う、授業の「プロジェクト化」です。日本ではあまりなじみのない方法ですが、すでにフィンランドやオランダなどでは成果を上げたメソッドです。競争よりも協力の方がそれぞれの子供の学力を上げることはすでに様々なデータで証明されています。〈よい〉教育をつくるためには学校の物理的な「構造」はどうなっているのがいいのか? 〈よい〉教育を行うための教師の資質とは何か? そしてその実現のための〈よい〉社会とは? 本書は、義務教育を中心に、どのような教育が本当に〈よい〉と言えるのか、それはどのようにすれば実現できるのかを原理的に解明し、その上でその実現への筋道を具体的に示してゆくものです。 序章 そのそも教育は何のため? 第一章 「よい」学びをつくる 第二章 学びの個別化 第三章 学びの共同化(共同的な学び) 第四章 学びのプロジェクト化(プロジェクト型の学び) 第五章 学校空間の再構築 第六章 教師の資質 第七章 教育からつくる社会
本書は、ビジネスにおける「提案の技術」をテーマに、論理思考やプレゼンテーション能力を実践的に学ぶためのガイドです。著者は、外資コンサルや商社での経験を基に、提案を成功に導くための基本的なスキルを整理しています。内容は、論理思考力、仮説検証力、会議設計力、資料作成力の4つの能力に焦点を当て、各章がストーリー、解説、まとめで構成されています。ビジネス現場での実践的なスキルを身につけることができる内容です。
ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。
この本は、子どもの可能性を引き出し、自主性や他人への思いやりを育むために親がどのように関わるべきかを、実例を交えて分かりやすく解説しています。幼児期の重要な学びや人格形成のプロセス、子どもの仕事の観察方法、日常生活を教育に活かす方法についても触れています。
この書籍は、ニューヨーク発の最新科学に基づいた愛と幸せに満ちた子育て法を紹介しています。内容は、子どもを幸せに育てるための方法や親子関係の改善、自己肯定感の向上、主体性を育むこと、多様性の尊重、親自身の幸せについて触れています。著者は松村亜里で、心理学と公衆衛生の専門家として、異文化子育て心理学の講座を提供しています。
この書籍は、モンテッソーリ子育てのアプローチを通じて、イヤイヤ期やイタズラに対処する方法を解説しています。著者は、子どもを信じて任せることの重要性を強調し、心の強い子どもを育てるための具体的なアドバイスを提供しています。内容は、子どもとの信頼関係の構築や、適切な環境の整備、過剰な干渉を避ける方法など、多岐にわたります。著者はモンテッソーリ教育の専門家であり、教育者の育成にも力を入れています。
この書籍は、小学生が知っておくべき約400種類の職業について、仕事内容、給与、なり方を詳しく解説しています。特に注目される職業や実際に働いている人へのインタビューも収録されており、「働くこと」のリアルな理解を促します。中学生になる前に将来の夢を見つける手助けをし、探求学習や進路決定にも役立つ内容です。著者は坂本真樹で、人工知能に関する専門知識を持つ大学副学長です。
アドラー心理学の第一人者が、数多くの実践例をあげながら、新しいクラスルーム・マネジメントのあり方、子どもの問題行動にどう対処するかなど、きわめて具体的、平易に説く。 第1章 学校はほんらい何をする所か 第2章 クラスはどのようにして病気にかかるか 第3章 クラスの病気はどのようにして悪化するのか 第4章 あなたはどんな教師か 第5章 どうすれば子どもたちは協力を学ぶか 第6章 どうすれば子どもたちは積極的になるか 第7章 どうすれば子どもたちは責任を学ぶか 第8章 クラスの中に民主的な秩序を建設する 第9章 子どもたちが相互に援助しあう環境を作る 第10章 子どもの問題にどう対応するか
不登校、引きこもり、摂食障害、等々、子育てをめぐる様々な悩みや 苦しみはなぜ生じるのか。その仕組みを心理学の概… 本書は、2010年9月に大隅書店から刊行された本と本文も装幀・造本もまったく同一のもので、2017年6月に版元名が大隅書店からさいはて社に変更されたことを受け、今回の増刷を機に、ISBNをあらためて発行するも… 不登校、引きこもり、摂食障害、等々…。子育てをめぐる様々な悩みや苦しみはなぜ生じるのか。その仕組みを心理学の概念で解き明かし、多数の事例を紹介しながら子どもとのコミュニケーションの望ましいあり方について具体的な方法を提案する。脳科学者/医師/臨床心理士/四児の父親/少年サッカーの指導者である著者による書き下ろし。 はじめに この本の目的と構成 Ⅰ 診察や面接で気がついたこと 1 親にできるのは自分が変わること 2 目に見えるものに偏りすぎていないか 3 勉強よりも大切なこと 4 先んずれば人を制す? 5 不登校は勇気ある行動である 6 子どもを信じて愛情を与える 7 まず好きになる 8 きちんとすることよりも好きになることを 9 子どもは導かないと成長しないのか Ⅱ 親子の関係 10親と子の別れ 11 子どもと親の距離――近すぎる親、遠すぎる親 12 近すぎる親の問題――子どもの出会う現実を加工する 13 遠すぎる親の問題――子どもの気持ちに無関心 14 現実を受け容れるということ 15 叱りすぎることの危険性 16 母親は子どもに去られるためにそこにいなければならない 17 空腹の自由、食欲の自由、排泄の自由 18 頼りないので手放さない 19 食べ物は毒? 20 優等生はなぜいじめられやすいのか 21 自分を守る心の仕組み――防衛機制について 22 自分の世界にこもることで自分を守る――引きこもりの防衛 23 不快をもたらす現実を受け容れない――否認の防衛 24 育児の不安、親の不安――置き換えの防衛 25 自分の思いを相手に映し出す――投影による防衛 26 子は親の鏡――だから親の昔を映すこともある 27 できたと思って喜ぶとすぐ逆戻り――打ち消しの防衛 28 なんでも思い通りになるという感覚――万能感による防衛 29 責められるより責める方が楽――攻撃者への同一化 30 親が子どもを守るということ Ⅲ 子どもとのコミュニケーション 31 先に進まない 32 小言を控える 33 指示しない 34 子どもに起きてくる変化 35 押しつけないことで伸びるものがある 36 子どもが失敗した時は愛情を与えるチャンス 37 おしゃれや化粧は自分を守る 38 衝動を制御する力はどう育つのか 39 家ではくつろがせてやる 40 子どものペースで 41 子どもは「嬉しい」や「悲しい」をどう学ぶのか 42 子どもをやる気にさせる 43 自分の意見を言える子どもはどうやれば育つのか 44 見守る 45 アイスクリーム療法 参考文献 おわりに
この書籍は教育心理学の基本を解説したロングセラーの第5版で、最新の統計データやいじめ問題、発達障害に関する記述が加わっています。内容は、記憶力、学び、やる気、評価方法、発達についての考察など多岐にわたり、教育や心理学に関心のある人々に向けてわかりやすくまとめられています。著者は鎌原雅彦と竹綱誠一郎で、共に教育学の博士号を持つ教授です。
先生や子どもたちがファシリテーターになると授業がとても楽しくなる。クラスが成長する「信頼ベース」の授業の進め方を紹介。 教師も子どももファシリテーターとなるクラスではお互いの信頼に支えられ授業をつくっていく。第1~第5までのステップに分け、小学校国語をはじめ、社会、理科、算数など著者のほか各地の授業事例を紹介しながら提案する。 先生や子どもたちがファシリテーターになると、教室に豊かな言語活動が育まれ、授業がとても楽しくなります。 子どもやクラスが成長する「信頼ベース」の授業の進め方を小学校国語、算数の授業事例などを用いて紹介します。 カラー口絵「信頼ベースの授業の進め方」 はじめに 取り扱い説明書 信頼ベースの授業 5つのステップ表 信頼ベースのクラスとは ●岩瀬直樹の授業 ①教科書に「拍手が起こる」国語 ②手を伸ばせば「物語」のある教室 ③学びの中核は対話 ④言語活動が加速するホワイトボード・ミーティング ⑤子どもたちがつくり始める学びのメインストリーム ⑥遊ぶように学び、学ぶように遊ぶ 基本的な準備物 ●信頼ベースの授業コンセプト ①信頼ベースの授業 5つのステップ 1.教室に豊かな言語活動の環境を育みます 2.信頼ベースの授業──3つの成長チャレンジと5つのステップ 3.子どもたちと先生は3つの成長にチャレンジします 4.6つの技術で学びの環境をつくります 5.特に会社活動で、子どもたちの表情が変わります ②プログラムデザイン「授業を進める6つのポイント」 1.一斉授業とファシリテーション型授業 2.学びのフレームと学びのサイクル 3.単元と授業のプログラムデザイン 4.ホワイトボード・ミーティングで「プログラムデザイン会議」 5.授業を進める6つのポイント ①学びのゴールと価値のインストラクションを共有 ②全体の流れ(見通し)と進め方、評価基準の共有 ③活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) ④観察とカンファランス、レクチャーの繰り返し ACT1 観察とカンファランスを練習しよう! ⑤学びの成果共有と価値のフィードバック ⑥振り返り ③授業でついやってしまう、よくある失敗 ACT2 シートントンキャンペーン ACT3 ハイタッチバリエーション ④信頼ベース × ○○の提案 信頼ベース × 協同学習……阿部隆幸さん ●言葉や態度を翻訳する「子ども理解」の技術を磨く ①「子ども理解」の技術を磨こう 1.心の体力が冷えると強く、激しくなる問題行動 2.不安な気持ちを翻訳して、安定的に受け止めます 3.愛情確認行動の対象は、特別の契約を結んだ相手です 4.承認欲求行動はクラスなど不特定多数が対象になります 5.状況が厳しいときほど、価値のフィードバックが大事です ②学級崩壊前後の取り組み方 1.学級崩壊前後の提案 2.担任がメンタルダウンしたときの介入方法の例 ③自分も友達も、授業で成長するクラス 1.何気ない毎日に、物語や成長が積み重なります 2.満たされた公平性と対等性の上に成り立つ多様性 3.学びの多様性が子どもたちの個性を引き出します 4.一緒に練習をしていきましょう! ACT4 教職員のためのファシリテーター度 10のチェックシート ACT5 ファシリテーターのかかわりスキル10か条 ●信頼ベースの授業 第1ステップ ①振り返りジャーナル ②絵本の対話型読み聞かせ ③会社活動 ④教室リフォームプロジェクト ⑤ミニホワイトボード ACT6 ○×クイズ ACT7 教室のあちこちで、ミニホワイトボードで対話 ミニホワイトボードの実践……石川晋さん ⑥プロジェクト・アドベンチャー プロジェクト・アドベンチャーの実践……甲斐崎博史さん ⑦クラス目標決定 ●信頼ベースの授業 第2ステップ ①オープン・クエスチョンの練習 ②ペアで聴きながらホワイトボードに書く 1.教室に多様な「承認し合う関係」を育みます 2.最初はミニホワイトボードからスタートして進化しよう! 3.ペアで聴きながら書く効果はスゴイ! 4.大事な約束「言いたくないことは、言わなくていい」 5.「聴きながら書く」に慣れてきたら、授業に活用します ③意見発表にチャレンジ「『今の自分』を話します」(小学4年国語/東京書籍) 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 2.全体の流れ(見通し)と進め方、評価基準の共有 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い)──振り返りまでの様子 ④わたしの構成要素 ⑤好きなおかしベスト5 ●信頼ベースの授業 第3ステップ ホワイトボード・ミーティング活用例 ①「学級新聞を作ろう」(小学4年国語/教育出版) 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 2.全体の流れ(見通し)と進め方、評価基準の共有 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) 4.観察とカンファランス、レクチャーの繰り返し 5.学びの成果共有と価値のフィードバック 6.振り返り ●信頼ベースの授業 第4ステップ~第5ステップ 1.「学びのサイクル」でいろんな教科が豊かになります 2.学びのフォーメーションと3つの成長チャレンジが連動します 3.カンファランスとレクチャーの充実が学び合いを促進します ①社会「江戸の文化と新しい学問」(小学6年/東京書籍) ②理科の進め方 ③算数の進め方 1.算数は積み重ねの教科です 2.チャレンジの環境設定をします 3.「構成的」から「非構成的」な学びのフォーメーションへ ④算数「小数のかけ算とわり算を考えよう」より(小学4年/東京書籍) ⑤算数「三角形のなかまを調べよう」(小学3年/東京書籍) 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 子どもたちとつくる価値のインストラクション……加藤健さん 2.めざそう!三角形マスター「三角形のなかまを調べよう」 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) ⑥算数「図形の角を調べよう」(図形の角)(小学5年/東京書籍)授業案の一例 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 2.単元の見通しと評価基準 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) 4.観察とカンファランス、レクチャーの繰り返し 5.学びの成果共有と価値のフィードバック 6.振り返り ⑦子どもたちが「自分の学び」をデザインする自主学習ノート 自主学習ノートの進め方……伊垣尚人さん ⑧第5ステップのクラスの様子 主な参考文献 おわりに
学習を成功へと導く授業とは? 熟練教師の実践知とメタ分析によるエビデンスを融合。教職専門性を支えるマインドフレームを示す。 学習を成功へと導く授業とは? 熟練教師の実践知とメタ分析によるエビデンスを融合。教師のコンピテンシーと両輪となって,教職専門性を支える「心的枠組み」を示す。メタ認知,協働学習など,現場のリアルな課題に応える。 学習を成功へと導く授業とは? そのために,教育者はどのように自身の指導と役割を考えればよいのか。熟練教師の実践知とメタ分析によるエビデンスを融合。教師のコンピテンシーと両輪となって,教職専門性を支える10の「心的枠組み」を示す。メタ認知,フィードバック,協働的な学びなど,現場のリアルな課題に応える。 [原書]John Hattie & Klaus Zierer (2018). 10 Mindframes for Visible Learning: Teaching for success. Routledge ■本書の主な目次 Chapter0.はじめに:行なったことの影響をいかに考えるかは,いかに行なうかを考えるよりも重要である Chapter1.私は生徒の学習に及ぼす影響の評価者である Chapter2.アセスメントは自身の影響と次のステップを知らせてくれるものである Chapter3.進歩させたいと考えていることや自身の影響について同僚や生徒と協働する Chapter4.私は変化をもたらすエージェントであり,すべての生徒が改善できると信じている Chapter5.私は「最善を尽くす」だけでなく,チャレンジに努める Chapter6.私は生徒にフィードバックを提供して理解できるように支援し,私に与えられたフィードバックを解釈して行動する Chapter7.私は一方向の説明と同じくらい対話を取り入れる Chapter8.何ができたら成功なのかを最初から生徒に明確に伝える Chapter9.間違えても他者から学んでも安心して学習できるように人間関係と信頼を築く Chapter10.学習と学習中の言葉に集中する Chapter11.可視化された学習のビジョン 邦訳版の刊行に寄せて Chapter0.はじめに:行なったことの影響をいかに考えるかは、いかに行なうかを考えるよりも重要である 1.50人の教師との1万5000時間 2.サイモン・シネックとゴールデンサークル 3.ハワード・ガードナーと3つのE 4.教育の専門知識:コンピテンシーとマインドフレーム 5.なぜこの本なのか 6.可視化された学習とは何か 7.本書はどのように構成されているのか 8.この本は誰を対象としているのか 9.謝 辞 Chapter1.私は生徒の学習に及ぼす影響の評価者である 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.教師は診断したり介入指導をしたり評価したりする必要がある 4.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter2.アセスメントは自身の影響と次のステップを知らせてくれるものである 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.課題(アサインメント)、テスト、クイズ式問題など:退屈な義務というだけではない? 4.ワークシートがなくなってもワークシートは不滅である:過剰なワークシートに対する批判 5.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter3.進歩させたいと考えていることや自身の影響について同僚や生徒と協働する 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 交流と協同の成果としての集合的知性 3.チーム・ティーチング:自明のように思われる要因の可能性と限界 4.何から始めればよいか チェックリスト /エクササイズ Chapter4.私は変化をもたらすエージェントであり、すべての生徒が改善できると信じている 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.問題解決型学習 4.学習者は動機づけられる必要がある 5.多様性を目的にした多様性に対抗する:エビデンスに基づいたさまざまな方法の多様性を求める 6.限界質量:変化を成功させるための条件 7.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter5.私は「最善を尽くす」だけでなく、チャレンジに努める 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.学習にとってのフローとその意義 4.学習目標のタキソノミー:可視化された学習と成功を収める授業に向けた重要な段階5.ゴルディロックスの原理 6.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter6.私は生徒にフィードバックを提供して理解できるように支援し、私に与えられたフィードバックを解釈して行動する 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.あなたの影響を知ること:成功する指導の鍵としてのフィードバック 4.フィードバックのレベルを接合する 5.初心者・上級者・専門家:達成レベルの役割 6.過去・現在・未来:フィードバックの3つの視点 7.包括的なフィードバックの呼びかけ:フィードバック・マトリクス 8.ギブ・アンド・テイク:フィードバックの対話構造について 9.仲間についてはどうか:学習者から学習者へのフィードバック 10.フィードバックを成功させるための必須条件:間違いの文化 11.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter7.私は一方向の説明と同じくらい対話を取り入れる 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.協同学習:仲間の力を活用する 4.確実な習得指導:協同学習を補完する 5.学級規模:重要ではあるが対話にはどうしてもというわけではない 6.何から始めればよいか 7.チェックリスト/エクササイズ Chapter8.何ができたら成功なのかを最初から生徒に明確に伝える 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.目標と成功の基準:双子のような目 4.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter9.間違えても他者から学んでも安心して学習できるように人間関係と信頼を築く 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.IKEA効果 4.「できない」でなく「まだできない」 5.笑顔を見せよう 6.カメレオン効果とルールや習慣化の力 7.一度でも嘘をついたら常に嘘をつくようになる:信頼は教師と生徒の健全な関係の中核である 8.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter10.学習と学習中の言葉に集中する 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.学習ファシリテーター、学習コーチ、学習カウンセラーなのか、そうではなくて教師である 4.バカなやつともっとバカなやつ効果 5.「見えないゴリラ」研究 6.認知負荷理論とその指導のための示唆 7.学習スタイル:実証的教育研究の神話 8.自己概念:成功する学習への鍵 9.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter11.可視化された学習のビジョン エピソード:テイラー・スウィフトと仲間たち、学習への情熱を引き出す方法 1.自然から学ぶ:ウェブモデル 2.可視化された教え方:授業計画を可視化する 3.将来の学校のビジョン 訳者代表あとがき 索引 文献 付録:指導要因と効果量ランキング
汐見稔幸先生は、子どもに関わるすべての人々を支援する存在であり、保育の質向上に悩む保育士や親に新たな視点を提供します。本書では、汐見先生の考えや言葉が集められ、新しい保育指針や要領の重要ポイントも解説されています。巻頭対談や保護者の悩みに対する回答も含まれ、子どもの幸せや成長に寄与するためのメッセージが伝えられています。著者は教育学の専門家で、保育の分野での豊富な経験を持っています。
この書籍は、算数授業のさまざまな要素を網羅しており、効果的な授業を行うための方法や工夫について解説しています。内容は、授業の準備や進行方法、子どもの思考を引き出すための課題提示、話し合いや発表の工夫、ノート指導や板書の重要性、教科書の扱い方、テストの意義、能動的な学習態度の育成など多岐にわたります。著者は新潟県出身の教育者で、算数教育において豊富な経験を持つ専門家です。
この書籍は、成功に必要な「やり抜く力」(グリット)について探求し、才能やIQではなく、情熱と粘り強さが成功を決定づける要素であると論じています。著者のアンジェラ・ダックワースは、やり抜く力を伸ばす方法を自己成長や他者への影響を通じて詳述し、子育てや教育、ビジネスにおける実践的なアドバイスを提供しています。成功者の共通点を明らかにし、誰でも一流になれるメソッドを提示する内容です。
本書は、個人情報保護法やGDPR、NISTフレームワークに対応するための企業向けの情報管理に関する総合専門書です。日本企業は、情報漏えいや国際的な情報管理リスクに直面しており、統一的な情報管理システムの構築が求められています。法的観点からの論点をベーカー&マッケンジー法律事務所が提示し、デロイトが実務的な解決策を提供しています。内容は、情報マネジメントの重要性や具体的な管理手法について詳述されています。
「道徳読み」=教科書の読み物教材を徹底活用した、どの教科書でも使える授業法。 準備物はありません。教科書と鉛筆、そして考える頭だけ。 「道徳読み」は次の5つのパートで構成されます。 1、普通に読む 2、道徳読み(道徳さがし・道徳みつけ)をする →子どもたちは、主体的に、真剣に、教材と向き合います。 3、みつけた道徳を発表する →子どもたちは、対話を通じて自分が気づかなかった道徳を獲得。 4、登場人物に通知表を付ける →子どもたちは、自分とは異なる考え方を学びます。 5、自分を省みる →子どもたちは、自分自身への深い学びを体験します。 この授業法を学べば、誰でも、主体的・対話的で深い学びのある道徳授業ができるようになります。 本書では「道徳読み」の基本から実践までを1冊に収録しました。実践パートでは、おなじみの教材を使った授業が、学習指導案から実際の授業のながれまで全学年分掲載されています。 Ⅰ 「道徳読み」の基本 1 道徳の基本的な考え方 ①道徳脳で教材を読む/②心は自分から/③第二の天性を豊かにする/④他人には優しく。自分には? 2 「道徳読み」の方法 ①普通に読む(通読)/②道徳さがし・道徳みつけ/③発表をする/④通知表を付ける/⑤省みる(自分の心に落とす) 3 評価(子どもに対する評価) ①「特別な教科 道徳」の評価/②「道徳読み」での評価 4 「道徳読み」の効果 ①子どもへの効果/②広がる目/③教師の教材分析力がつく Ⅱ 「道徳読み」の実際 1 学年別・授業実践 第一学年 「はしのうえのおおかみ」 第二学年 「七つぼし」 第三学年 「ヒキガエルとロバ」 第四学年 「ブラッドレーのせい求書」 第五学年 「手品師」 第六学年 「ブランコ乗りとピエロ」 2 「道徳読み」をより豊かにするために 発展例① 「道徳ってどんな勉強?」 発展例② 「読み物教材以外で『道徳読み』」 Ⅲ「道徳読み」に困ったらQ&A コラム●「道徳読み」と学級づくり ① 子どもを観る視点にする/② 5分間の小さな「道徳読み」/③「法治」と「徳治」
●1人1台端末時代に求められる「10X授業」を板書シリーズの実践をもとに提案! →小学校55事例 中学校20事例 ●Google の認定研修パートナーであるイーディーエル株式会社監修! 本書では、1人1台端末時代に求められる授業デザインの在り方を、Google Workspace for Educationの各種アプリを活用して解説しました。Google の認定研修パートナーであるイーディーエル株式会社が全体の構成案を練り上げ、教育現場の最前線でいち早くICT の利活用を実践され、成果をあげられている現役の先生方に執筆をお願いしました。現場からの智慧を集結して、本当に明日からすぐにでも授業でご活用いただけるよう考案したのが、「Google Workspace for Education 活用10 の型」と「Google ティーチャーズ・マップ(GTM)」です。「10X 授業10 の型」とは授業におけるICT 活用のコツをいち早くつかめるように、「場面(目的)」と「活用メリット」を組み合わせたパターンを、できる限りシンプルに解説したものです。この「型(パターン)」を理解することで、先生方ご自身でICT の特性を生かした授業をデザインできるようになります。この「10X 授業10 の型」に基づき、小学校1 年生から中学校3 年生までの全学年、全教科・領域を網羅し、「板書シリーズ」から具体的な事例を用いて、71 本のGTM を作成しました(板書シリーズ非該当教科はオリジナル実践)。ぜひこの豊富な10X 授業デザイン案を練習問題のように活用し、来週の授業をご自分でデザイン、実践してみてください。 はじめに 序章 いよいよ始まったGIGAスクール構想 〜教室が変わる!〜 1 GIGAスクール構想いよいよ始動。今、求められるものはビジョンと覚悟 2 ICT活用の基礎知識〈デジタル化〉とは 3 これだけは知っておきたい〈クラウド〉の恩恵とは 4 「10X 授業」とは4 Column1 Google 認定教育者のススメ 第1章 なぜ Google Workspace for Educationなら10 X授業を実現できるのか? 1 Google Workspace for Education とは? 2 授業を 10X するアプリの選び方とは? 3 Google のツールとマインドをかけ合わせると、授業が 10X する 4 10X 授業とComputational Thinking(計算論的思考) Column2 情報× 情操× デジタル・シティズンシップ 第 2 章 10X 授業を成功に導くICT 活用10 の型9 1 「10X 授業10 の型」とは何か 2 授業の魅力と成果を上げるための7 つの型 3 効率を上げる3 つの型 4 10X 授業10 の型とアプリ Column3 全児童39 名小規模校のICT への挑戦 第3章 「10X 授業10 の型」で創る授業デザインの基本 1 Goo?le ティーチャーズ・マップ(GTM)を活用して10X 授業を即実践! [実践例]小学校5年生 社会科「これからの食料生産とわたしたち 第1時 / 第2時 / 第4時2 / 第5時 Column4 職員室の雑談からICT は広まっていく 第4章 実践!「10X 授業10 の型」で創る授業デザイン 【小学校:板書シリーズ該当教科】 [国語]第1学年:しらせたいな、みせたいな [国語]第2学年:お手紙 [国語]第3学年:わたしたちの学校じまん [国語]第4学年:ごんぎつね [国語]第5学年:みんなが過ごしやすい町へ [国語]第6学年:メディアと人間社会/大切な人と深くつながるために/プログラミングで未来を創る [社会]第3学年:高松市のようすやよさが伝わる地図を完成させよう [社会]第4学年:各家庭ではどんなごみをどのように出しているのだろう [社会]第5学年:生産性を高めるために、どのような工夫があるのか調べよう0 [社会]第6学年:学習問題に対する自分の答えをまとめよう [算数]第1学年:ひきざんカードをならべよう [算数]第2学年:5×□のかけ算の答えは? [算数]第2学年:サイコロの形をつくろう [算数]第3学年:k(キロ)やm(ミリ)ってどんな意味かな? [算数]第4学年:正三角形のまわりの長さを求めよう [算数]第5学年:目指せ!プロの審判9.15mは何歩? [算数]第6学年:自分の考えをまとめよう [理科]第3学年:ゴムの伸ばし方を変えたときの車の進む距離の変わり方を比べる [理科]第4学年:半月や満月の働き方のきまりを見つける [理科]第5学年:さらに食塩やミョウバンを溶かす方法を発想する [理科]第6学年:持続可能な社会の構築に向けて人はどうすればよいか理解する [生活]第1学年:これまでの活動をまとめよう [生活]第1学年:夏の公園で遊ぼう [生活]第2学年:図書館で見付けたことを紹介しよう [生活]第2学年:生き物からの贈り物 [体育]第4学年:技の習得・習熟を目指そう [体育]第6学年:喫煙の害について考えよう [外国語活動]第3学年:クイズを作ってリハーサルをしよう [外国語]第6学年:行きたい国について話そう [道徳]第2学年:るっぺどうしたの [道徳]第4学年:絵葉書と切手 [道徳]第5学年:ブータンに日本の農業を 【小学校:板書シリーズ非該当教科】 [音楽]第2学年:どんな音がきこえるかな [音楽]第5学年:和音に合わせてせんりつをつくろう [図工]第3学年:「ちいさな自分」のお気に入り [図工]第6学年:わたしの感じる和 [図工]全学年 :身近な自然でアートしよう(夏休みオンライン宿題) [家庭]第5学年:どんな生活をしてるのかな [家庭]第6学年:まかせてね 今日の食事 [家庭]第6学年:上手に暮らそう [総合]第3学年:農作物を栽培しよう [総合]第4学年:福祉について調べよう [総合]第5学年:環境について考えよう [総合]第6学年:自分たちの住む地域をよくしよう [総合]3年以上:平和について考えよう(夏休みオンライン課題(配信)) [学級活動]第1学年:2学期の目標をきめよう [学校行事]第2学年:学習発表会 [学校行事]第3学年:秋の遠足を楽しもう [学級活動]第4学年:友達を大切にしよう [クラブ活動]第5学年:クラブを楽しもう [児童会活動]第6学年:委員会・食育集会を行おう 【中学校:板書シリーズ該当教科】 [理科]第1学年:振幅と振動数 [理科]第2学年:単体と化合物 [理科]第3学年:体細胞分裂の観察の考察 【中学校:板書シリーズ非該当教科】 [国語]第2学年:「走れメロス」の謎を探究する [社会]第1学年:ヨーロッパ州 〜国同士の統合による変化〜 [数学]第1学年:比例を利用しよう [音楽]第2学年:曲にふさわしい発声で歌おう [音楽]全学年 :楽器と唱歌によるパッチワーク [美術]第1学年:遠近感を出そう 〜線遠近法〜 [美術]第3学年:今を生きる私へ(自画像) [体育]第2学年:ダンス:創作ダンス [保健]第2学年:交通事故と危険予測の回避 [技術]第1学年:わたしのものづくり [技術]第3学年:植物工場を作ろう [家庭]第2学年:住まいの安全について考えよう [家庭]第3学年:消費者トラブルを解決する [外国語]第1学年:観光パンフレットを作ろう [道徳]第3学年:『二通の手紙』 [総合]第2学年:スマホ活用について考えよう [学級活動]第3学年:先輩に学ぼう 〜自分のライフプランを考えよう〜 Column5 日常的にICT を使うことの大切さ 第5章 アプリの基本機能と設定、操作方法 1 すべてに共通する操作と注意すべき点 Google アプリの3ステップを覚えよう 2 Google Classroom の基本操作 3 授業で使える便利な機能 000 Google Jamboard:[フレーム]に背景を設定するには? Google フォーム:自動採点のテストを作成するには? Google Meetでゲストティーチャーに取材するには? Google Keepの[メモ]を共同編集するには? Google ドライブ:最低限知っておくべき知識とは? 000 音声入力ってどうやるの? 000 安全かつ効率よく共有設定できるグループメールとは? 000 スライドのデザインを、AI にお任せするには? 000
「できる先生」の実践に隠された教える技術がわかる! 教え方にも「基礎・基本」がある! 「わかる」よりも「できる」が大切 面積の求め方をディスカッションしてはいけない?! 答えを写す子どものマインドセット 言えないものは覚えられない 子どもは教科書を読んでいない!? 理論と実践を結びつける「決定版」 どの教科にも応用できる「教え方」 絶対おさえておきたい教師の「鉄則」 これからのエビデンスベースドの教育の時代に、まずこの本はおさえておきたい!! 第1章 学習者検証の原則 「わかる」よりもまず「できる」が大切なわけ 第2章 成長マインドセットを育む やればできるを実現する 第3章 「算数」の読解力を底上げする 文章を読みとばすクセをなくす 第4章 アウトプットを意識する 反復練習で大切なこと 第5章 スモールステップで始める あれもこれもよくばらない 第6章 ワーキングメモリーを節約する ややこしくてわからないを防ぐ 第7章 視覚化してイメージをとらえる 読んでもわからないことは見てわかるようにする 第8章 学習方略を身につける 考える力が身につき、学び方がわかる 第9章 メタ認知をうながす 「わかっていない」ということがわかること 第10章 ピア・ラーニングを取り入れる 一斉授業か協同学習かを越えて
この書籍は、日常生活で直面する困難を描いた10人のストーリーを通じて、社会保障制度について学ぶことができる内容です。家族や健康、仕事などの問題に対処するための知識が、読者や大切な人を守る力になることを伝えています。著者は社会福祉士であり、社会保障制度の改善に取り組んでいます。
「いやだ」「やめて」というきもちをつたえることは、じぶんのこころとからだをまもるためのたいせつな第一歩です。 たっくんは、いとこのおねえちゃん、えっちゃんとゆうちゃんの家にあそびにきました。 たっくんは、えっちゃんとなかよくあそんでいたのだけど、ちょっといやなきもちになってきました。 でも、そ… たっくんは、いとこのおねえちゃん、えっちゃんとゆうちゃんの家にあそびにきました。 たっくんは、えっちゃんとなかよくあそんでいたのだけど、ちょっといやなきもちになってきました。 でも、そのことをうまくいえません。 4歳からの子どものための生と性の絵本「いのちのおはなし絵本」シリーズ。 ちいさな子どもの遊びの中での出来事です。主人公はいとこのお姉さんから、ふざけてほっぺたを触られます。いとこのお姉さんは、主人公をかわいいと思っての遊びの延長でしたが、主人公は嫌な思いをします。 そうした時に、きちんと「いやだ」と伝えることができ、また「いやだ」と言われた方も、自分が遊びの延長だと思っていても、相手にとって嫌なことはやってはいけないことなのだということを伝えます。 見返しなどでは、プライベートゾーンのことも紹介し、親しい人であっても触ったり、触られたりしてはいけないところがあることも伝えます。
算数や数学ができる子たちに共通する特徴とは?国際数学オリンピックのメダリストを多数育てた英才教室講師が明かす「数学センス」の磨き方。 第1章 「数感」とは何か(音感があるように「数感」がある 数学を面白いと感じる力 征服派と感動派 数の不思議を味わうには 理解する数学と解く数学 ほか) 第2章 数学の教育について 初級編(世間の誤解 自ら考え工夫する力をつける 数学を勉強するための一番よい動機づけとは 数学は怠け者の学問? しかし、計算力は大切だ ほか) 第3章 さまざまな能力の開発方法(記憶力 イメージ能力 発想力 推理力 構想力 ほか) 付録 数感を伸ばす練習問題10
「魔法のピットインカード」は、子育てコーチングを手軽に実践できる53枚のカードです。共働き家庭が増える中、短い時間でも子どもとの質の高いコミュニケーションを促進し、子どもの悩みを解決したり、自信を育てたりすることが可能です。アドラー心理学を基にしたこのカードは、親がうまく問いかけられなくても使えるため、親子の会話を楽しくし、心の充電やポジティブな作戦会議の場を提供します。著者は、親子コミュニケーションの改善に取り組むメンタルコーチの原潤一郎氏です。
『「やればできる!」の研究』は、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授による成功心理学の古典的名著で、マインドセットが成功と失敗を左右することを論じています。著者は、成長マインドセットと固定マインドセットの違いを探り、教育、ビジネス、スポーツ、人間関係におけるマインドセットの影響を解説。20年以上の研究を基に、マインドセットを柔軟にする方法や、成功するための思考法についても提案しています。
最近は色々な診断が流行っていますが、こちらも自分の強みを知る良いきっかけになりました。ストレングス・ファインダーの診断結果が具体的で、今後の仕事や生活に活かせそうです。自分を見つめ直したい人におすすめしたい本です。
自分の強み・弱みを知れるので一度やってみると面白いと思う。
本書は、青年が哲人に「アドラーを捨てるべきか」という苦悩を語るところから始まります。アドラー心理学の誤解を解く哲学問答を通じて、真の「自立」と「愛」、そして幸せになる方法について探求します。著者は岸見一郎と古賀史健で、アドラー心理学を基にした新たな視点を提供し、読者の生き方を変える力を持つ内容となっています。
東大・御三家に教え子を多数送り込むカリスマ講師が教えるわが子の理系的頭脳を育む極意。理系コンプレックスの親が陥りがちな失敗とは? 理系に強い子は面倒くさがり!?東大・御三家に教え子を多数送り込むカリスマ講師が教えるわが子の理系的頭脳を育む極意。理系コンプレックスの親が陥りがちな失敗とは?
本書「親業」は子育てにおいて親の関わりに焦点を当て、従来の子供中心のアプローチを見直します。親業には訓練が必要であり、権威主義に代わる方法やコミュニケーション技術、対立解決法などが具体的に紹介されています。親も人間であることを理解し、感情表現や能動的な聞き方を通じて子供との関係を深めることが重要とされています。
算数が苦手になるパターンを徹底的に分析し、その発端となる「4問」を特定(練習問題付き) 算数が苦手になるパターンを徹底的に分析し、 その発端となる「4問」を特定!(練習問題付き) 「親がバリバリの文系」でも、「算数、大好きな子」が育つ 算数は、小学校で学ぶ教科の中で、ただひとつ、 学習に必要な力(読解力・論理思考力・計算力・分析力・応用力……)を 「すべて」鍛えられる教科です。 だから、算数が得意になれば、国語も、理科も、社会も伸びる! シリコンバレーの上層階級が続々取り入れている、新!算数学習法
論理トレーニングは国語に行き着いた――好評『国語ゼミ』の内容はそのままに新原稿を収録。基礎の基礎から応用、質問や反論の力へ。 論理トレーニングは国語に行き着いた!――好評『国語ゼミ』が、内容はそのままに新たな原稿を加えパワーアップした。言葉の力をあなたの味方に変える実践の書。
この書籍は、算数授業を変えるための14の「しかけ」を紹介し、それぞれに5つの事例を提供しています。授業を通じて子どもたちの学びを深める方法を探る内容で、具体的な事例を通じて実践的なアイデアを提供します。著者は北海道教育大学附属札幌小学校の教諭、瀧ヶ平悠史氏です。
プラトン、フッサールの哲学は、互いの意見から共通了解をつくる「対話」の哲学であった。それを確かめ、現在に活かす方法を考える。 プラトン、フッサールの哲学は、互いの意見を確かめ、共通了解をつくりだす「対話」の哲学であった。そのことを丁寧に確かめ、現在の対話に活かす方法を考える。 プラトン、フッサールの哲学は、互いの意見を確かめ、共通了解をつくりだす「対話」の哲学であった。そのことを丁寧に確かめ、現在の対話に活かす方法を考える。
「教育」に関するよくある質問
Q. 「教育」の本を選ぶポイントは?
A. 「教育」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「教育」本は?
A. 当サイトのランキングでは『0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす! (単行本)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで167冊の中から厳選しています。
Q. 「教育」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「教育」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



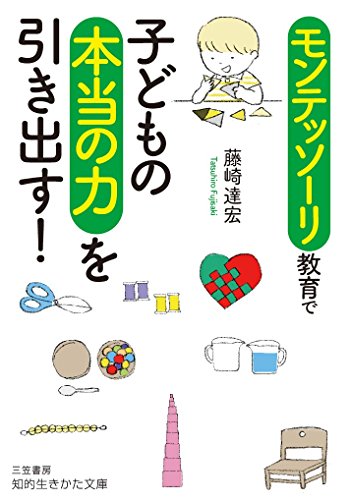































![『よくわかる教育心理学[第2版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/313YEZONG7L._SL500_.jpg)























![『絶対役立つ教育心理学[第2版]:実践の理論、理論を実践』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/31opcdhQBiL._SL500_.jpg)























































































































