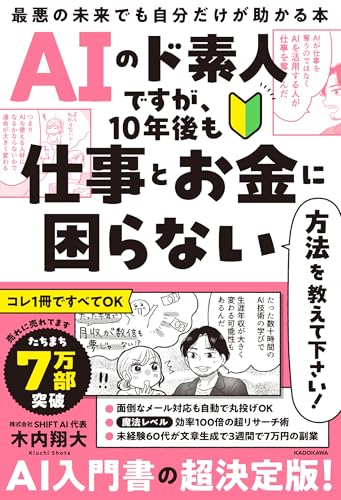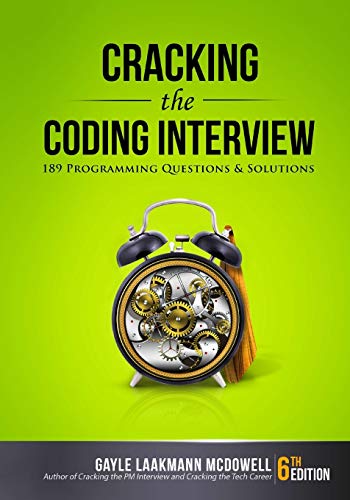【2025年】「システム開発」のおすすめ 本 174選!人気ランキング
- システム設計のセオリー --ユーザー要求を正しく実装へつなぐ
- リーダブルコード ―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック (Theory in practice)
- 1週間でシステム開発の基礎が学べる本 (1週間で基礎が学べるシリーズ)
- サーバ/インフラエンジニアの基本がこれ1冊でしっかり身につく本
- ちゃんと使える力を身につける Webとプログラミングのきほんのきほん
- この1冊ですべてわかる 新版 SEの基本
- Webを支える技術 -HTTP、URI、HTML、そしてREST (WEB+DB PRESSプラスシリーズ)
- 世界一わかりやすい IT業界のしくみとながれ
- 良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 ―保守しやすい 成長し続けるコードの書き方
- 絶対に挫折しない iPhoneアプリ開発「超」入門 第8版 【Xcode 11 & iOS 13】 完全対応 (Informatics & IDEA)
本書は、情報システムの設計手順を体系化し、ユーザーと開発チームをつなぐ方法を明示します。各工程の目的や作業内容を示しながら、データ、業務プロセス、画面UIの設計を「概要定義から詳細定義へ」「論理設計から物理設計へ」と進める手順を説明します。特定の開発手法に依存せず、実装技術や環境変化に左右されない原理原則を実践に即して解説しています。著者はシステム設計や業務改革に携わる専門家です。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
本書は、初心者向けのシステム開発解説書で、発注者と受注者の視点を両方考慮し、システム開発の全体像を理解するための基礎知識を提供します。関係者間の認識のズレを解消し、円滑な連携を促進することを目的としています。内容は、1週間でシステム開発の重要な局面や注意点を学べるよう構成されています。システム開発初心者にとって、役立つ一冊です。
本書は、サーバやインフラの運用・管理に必要な技術や知識を基礎から解説した教科書です。ネットワークやサーバの基本知識に加え、クラウド関連の知識やエンジニアとしての考え方、学習法、スキルアップ、業務知識、職業倫理も取り上げています。これからサーバ/インフラエンジニアを目指す人に適した内容となっています。目次には、エンジニアとしての生き方、ネットワーク、インターネット、サーバ、仮想化、ミドルウェア、Webサービス運用、セキュリティ、クラウド、法律・ライセンスの基礎知識が含まれています。著者は馬場俊彰氏で、豊富な実務経験を持つエンジニアです。
この書籍は、システムエンジニア(SE)として成功するために必要な知識とスキルをまとめた必読書です。テクニカルスキルやマネジメントスキル、コミュニケーション術、炎上プロジェクトへの対処法などが解説されており、特にIoTやAIの活用に焦点を当てています。著者は、SEの活動領域が広がる中で求められる発想力や戦略立案術、柔軟性についても触れています。全体を通じて、SEとしての心構えや人間力の重要性が強調されています。
本書は、Webサービスの実践的な設計に焦点を当てています。HTTPやURI、HTMLの仕様を歴史や設計思想とともに解説し、Webサービスにおける設計課題やベストプラクティスを紹介しています。目次は、Web概論、URI、HTTP、ハイパーメディアフォーマット、Webサービスの設計、付録から構成されています。
この本は、iOSプログラミング初心者向けの詳細な入門書であり、プログラミング経験がゼロでも理解できるように丁寧に解説されています。Swiftとアプリ開発の基本を習得できる内容で、Xcode 11やiOS 13.5、SwiftUIに対応しています。アプリ開発は副業にも最適で、リスクなく始められ、収益を上げる方法も紹介されています。著者はiPhoneアプリ開発の経験が豊富で、数々の成功作を持っています。
先を制してライバル企業に勝つためのポイントとは?決算を早期化して利益を稼ぎだすには?業務改革で会社をよみがえらせるには?最高のシステムをつくるための「亀のコウラ」とは?ベンチャーから中堅企業まで50社以上、業務設計・改善から会計監査さらにIPO支援まで20年近いコンサルティング実績を誇る「公認会計士兼システムコンサルタント」という異色の著者だからこそ書ける成功のノウハウが満載! 第1章 「稼げるシステム」と「稼げないシステム」の分かれ道はどこにあるのか? 第2章 先を制してライバル企業に勝つ"経営の視点" 第3章 決算を早期化して利益を稼ぎ出す"会計の視点" 第4章 業務改革で会社をよみがえらせる"業務の視点" 第5章 正しい知識で最高のシステムをつくる"システムの視点" 第6章 プロジェクトを成功に導き、会社を飛躍させよう
本書は、ソフトウェアアーキテクチャの重要性と、効果的なアーキテクチャを設計・構築・維持するためのスキルや知識を現代的視点から解説しています。内容は、アーキテクチャの基礎、アーキテクトの役割、アーキテクチャスタイル、チームとのコラボレーションに必要なソフトスキルなど多岐にわたり、実践的な例を交えて説明されています。著者は経験豊富なアーキテクトたちで、読者がソフトウェアアーキテクトとして成長するための道筋を示しています。
システム開発の上流工程の1つである、システム設計にスポットを当てた入門書です。システム設計を大きくアプリケーション設計とインフラ設計の2つに分類し、各分類における設計内容を軸に、実践のポイントや注意点などを紹介しました。関係者間で共通の認識を持って開発を進め、システムの品質を高められるようになるはずです。また、設計書の活用方法についても解説されているので、メンテナンスも効率的にできるようになるでしょう。 CHAPTER1 「システム設計」の位置付け Section 01 本書の前提とシステム「開発」の全体像 Section 02 「要件定義」とは Section 03 「設計」とは Section 04 「開発テスト」とは Section 05 「リリース」とは Section 06 「保守・運用」とは COLUMN どの工程にどれくらいリソース(工数)が必要なの? CHAPTER2 「システム設計」とは Section 07 本書における「システム設計」の整理方法 Section 08 設計書を作成する理由 Section 09 設計書の種類 Section 10 「全体設計」の概要 Section 11 「入出力設計」の概要 Section 12 「データベース設計」の概要 Section 13 「ロジック設計」の概要 Section 14 「ネットワーク設計」の概要 Section 15 「サーバ設計」の概要 COLUMN システム設計は広く、深い CHAPTER3 「システム設計」 に影響する考え Section 16 ソフトウェア設計モデル Section 17 フレームワーク Section 18 社外要因・社内要因 Section 19 オンプレミスとクラウド Section 20 仮想化技術 Section 21 ミドルウェア COLUMN ソフトウェアを作るのは勉強も必要だが、本来は楽しいもの CHAPTER4 全体設計 Section 22 全体設計の流れとポイント Section 23 システムアーキテクチャ設計 Section 24 信頼性・安全性設計(全体編) Section 25 環境設計(全体編) Section 26 性能設計(全体編) Section 27 セキュリティ設計(全体編) Section 28 運用方式設計(全体編) Section 29 外部接続方式設計(全体編) Section 30 標準化設計 Section 31 テスト方式設計(全体編) Section 32 移行方式設計(全体編) COLUMN こんなにも全体設計が必要なの? CHAPTER5 入出力設計 Section 33 設計書一覧 Section 34 画面系:画面一覧 Section 35 画面系:画面遷移図 Section 36 画面系:画面共通設計 Section 37 画面系:画面レイアウト Section 38 画面系:画面入力設計 Section 39 帳票系:帳票レイアウト Section 40 IF系:外部接続先一覧 Section 41 IF系:外部接続方式設計 Section 42 IF系:IFレイアウト Section 43 その他:送信メール設計 COLUMN 入出力設計は、システム知見に加えてコミュニケーション力が必要 CHAPTER6 データベース設計 Section 44 設計書一覧 Section 45 ボリューム一覧 Section 46 RDB:データベース設定 Section 47 RDB:ER図 Section 48 RDB:テーブルレイアウト Section 49 ファイル:ファイル設計 COLUMN データベース設計といえば、まずはRDBです CHAPTER7 ロジック設計 Section 50 設計書一覧 Section 51 ユースケース図 Section 52 アクティビティ図 Section 53 クラス図 Section 54 シーケンス図 Section 55 処理フロー図(フローチャート) Section 56 状態遷移設計 Section 57 バッチ全体設計 Section 58 処理設計(プログラム仕様書) COLUMN システム構築には「システムならではの考え方」や「業界特有の知識」が必要 CHAPTER8 ネットワーク設計 Section 59 設計書一覧 Section 60 ネットワーク全体構成図(物理構成) Section 61 ネットワーク全体構成図(論理構成) Section 62 ネットワーク提供サービス一覧 Section 63 通信要件一覧 Section 64 IPアドレス設計 Section 65 ネットワークサービス設計 Section 66 FW(ファイアーウォール)ルール設定方針書 Section 67 流量制御設計 COLUMN ネットワークの基礎はOSI参照モデルを知るのが早い CHAPTER9 サーバ設計 Section 68 設計書一覧 Section 69 サーバ仕様設計 Section 70 仮想化設計 Section 71 サーバプロダクト構成書 Section 72 サーバ稼働サービス一覧 Section 73 サーバ設定仕様書 Section 74 サーバ構築手順書(クラウド編) Section 75 サーバ運用設計 Section 76 障害対応手順書 COLUMN サーバ設計ができれば、たいていはなんとかなる CHAPTER10 設計書の活用 Section 77 設計書は開発のためだけではない Section 78 設計書は継続したメンテナンスが重要 Section 79 設計書は影響調査に使用する Section 80 設計書はシステムの品質を高めるために使用する Section 81 設計書は教育に使用する Section 82 設計書は移行の元ネタに使用する COLUMN 設計書は不要、という暴論
本書は、システムに詳しくない業務担当者向けに、企業のDX推進に必要なノウハウを解説した教科書です。システムを自ら作れなくても、他者に作ってもらうための技術や判断力が求められる時代において、具体的なプロセスや注意点を示します。内容は、システム構築の計画から実施までの各ステップを網羅しており、著者の実践的な経験に基づく事例も紹介されています。
本書は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)におけるノーコードおよびローコード開発手法の重要性を解説しています。エンジニア不足の中、誰でも簡単にアプリケーションを開発できるノーコードのメリット・デメリット、導入方法、活用事例、ツールの種類や学習方法を紹介。著者はノーコードコンサルタントで、社会課題解決にITを活用するプロジェクトに関わっています。ノーコードは、企業の変革を促進する手段として注目されています。
本書『新人エンジニア向け教科書』第3版は、システム開発の基礎知識をゼロから解説する入門書です。新人エンジニアや学生を対象に、ウォータフォール型とアジャイル型の開発手法の特徴や違いを学べる内容となっており、アジャイル型開発の解説が大幅に加筆されています。また、開発過程での文書作成手順や演習課題も用意されており、現役エンジニアや研修担当者にも役立つ一冊です。
本書は競技プログラミング(競プロ)に必要なアルゴリズムやデータ構造、考察テクニックを詳しく解説し、150問以上の演習問題を通じて知識を定着させることを目的としています。77個のテクニックを網羅し、320点以上の図で理解を助ける内容で、全問題は自動採点システムに対応しています。著者は国際情報オリンピックで金メダルを三度獲得した実績を持つ米田優峻氏です。
本書は、企業のIT担当者が必要とする基礎知識を解説しています。内容は、パソコンや周辺機器の調達、社内インフラの整備、情報セキュリティの強化、業務システムの導入、システム開発の外部委託に関する5章から構成されています。各章では、専門的な知識が求められるテーマを取り上げ、IT業務に携わる初心者向けに必要最低限の情報を提供しています。著者は、豊富な経験を持つエンジニアたちです。
『プリンシプル オブ プログラミング』は、プログラマーが3年目までに身につけるべき101の原理原則を紹介するガイドブックです。KISSやブルックスの法則など、古今東西の知恵を集約し、質の高いプログラミングを実現するための基本的な考え方や手法をわかりやすく解説しています。初心者から脱却したいプログラマーに最適な一冊です。著者は上田勲で、キヤノンITソリューションズでの豊富な経験を持っています。
コレ一冊読めばWeb技術の基本が分かる!新しいテクノロジーが登場しても基本となるWebの技術は非常に大事だし活きる!IT系の仕事に付く人はまずこの書籍を読んで基本を固めるべし!
本書は、駆け出しエンジニア向けに厳選されたIT用語をイラスト付きで解説しています。各用語は一言で説明され、関連する話題も取り上げることで理解を深めます。特に、入社1年目やIT業界未経験者でも分かりやすい内容となっており、専門書の副読本や資格対策としても適しています。目次には、トレンド用語、基本用語、システム開発用語、Web制作用語、セキュリティ用語、AI技術用語などが含まれています。知識を楽しく、効率的に身につけることができます。
SEの仕事の成否を分けるのは、コミュニケーションとマネジメントだった!業務システム開発の本質は「人」にあるということをいち早く見抜き、20年以上にわたって開発プロジェクトを次々に成功させてきた著者が、その成功の秘密を公開するSE必読の書。2006年の初版発行以来、増刷に増刷を重ね、No.1マニュアルとして全国のSEから絶賛されてきた『SEの教科書』が、続編『SEの教科書2』とあわせて改訂・完全版で登場。 第1部 成功するSEの考え方、仕事の進め方(SEの仕事は「人」が9割 失敗の原因はコミュニケーション不足 マネジメントが成否の鍵 コミュニケーション重視の会議術-準備編 コミュニケーション重視の会議術-実践編 プロジェクト初期段階の仕事術 成果物作成の仕事術 顧客業務分析の仕事術 設計・実装・テストの仕事術 プロジェクト運営の仕事術 業務システム開発は「伝言ゲーム」) 第2部 成功するSEのプロジェクト計画・運営術(名ばかりプロジェクトマネジメント 誤解がプロジェクトを破綻させる 上流工程はすべて計画活動 本当の計画、名ばかりの計画 ネットワーク図による計画作成術(アナログ式) ネットワーク図による計画作成術(デジタル式) ネットワーク図による計画の最適化 IT業界が日本を救う)
本書は、IT担当者や情報システム部門向けに、システム発注から導入に関するノウハウを提供します。著者は、システム導入の失敗はユーザー企業の力量不足が原因であると指摘し、経験が体系化されていないことが問題だと述べています。具体的には、ITプロジェクトの企画提案、要件定義、ユーザー受入テスト、教育、運用・保守に関するルールやノウハウを解説し、プロジェクトの主導権をユーザー企業が取り戻すための方法を示しています。著者はITコンサルタントとしての経験を活かし、実践的な知識を提供しています。
本書は、エンジニアでない人が「欲しいシステム」を手に入れるためのノウハウを提供する内容です。主人公がシステム開発の難しさを体験しながら、業務フロー、要件定義、プロジェクト計画などの重要事項を学ぶストーリー形式で進行します。新たにIT部署に配属された人やシステムに関わる全ての人に向けて、実務解説も含まれています。装丁画は注目の作家・今宵さんが手がけています。
本書は、HTML、CSS、JavaScriptを用いたフロントエンド開発の技術を包括的に学べる一冊です。Webサイト制作とWebアプリケーション開発の違いを理解し、エンジニアが共通して知っておくべき技術やスキルアップの方向性を示します。初心者から経験者まで幅広く役立つ内容で、開発現場のワークフローを疑似体験しながら、最新のフロントエンド技術を習得できることを目指しています。全6章で構成され、実践的な知識と技術の向上を促進します。
本書は、メタバースの可能性や影響を探るルポルタージュで、特にソーシャルVRに焦点を当てています。著者は仮想現実の住人として、メタバースが人間の文化やアイデンティティ、コミュニケーション、経済に与える影響を考察します。前半ではソーシャルVRサービスや関連技術を解説し、後半ではユーザーの経験や調査結果を基に、メタバースがもたらす変化を論じます。メタバースは新たな人間社会の形成を促進し、物理的制約から解放される可能性を示唆しています。
この書籍は、ITインフラの基礎知識を包括的に解説しており、サーバー、OS、ネットワーク、ストレージ、仮想化、クラウド、データセンター、セキュリティ、運用などの最新情報が含まれています。新入社員やインフラエンジニアを目指す人に推奨される入門書です。著者は富士通やLINEでの豊富な経験を持つ佐野裕氏です。
この書籍は、フロントエンド開発におけるさまざまな支援ツールの使い方と選択基準を解説しています。内容は、導入編でフロントエンドエンジニアに求められるスキルやツール群を説明し、実践編では開発環境やCI/CDのメリットを学び、応用編では解析やチーム開発について深く掘り下げます。著者は、Web開発やチーム効率の改善に取り組む経験豊富なエンジニアです。
本書は、Webアプリケーション開発におけるフロントエンドエンジニア向けに、テストの基本知識と実践手法を解説したものです。自動テストの重要性を強調し、具体的なテストコードの書き方や手法、ツールの使い分けを学べます。UIコンポーネントテストやビジュアルリグレッションテストなど、フロントエンド特有の課題に焦点を当て、サンプルアプリケーション(Next.js)を使ったハンズオン形式で進められます。テストを始めたいが方法がわからないエンジニアに最適な内容です。
この文章は、書籍の目次と著者情報を紹介しています。書籍は三部構成で、第一部ではアルゴリズムやプログラムの構造について、第二部ではパフォーマンスやアルゴリズムデザインのテクニックについて、第三部では具体的な問題解決の作品を扱っています。著者の小林健一郎は東京大学で物理学を学び、情報科学を専門とする教授です。
この文章は、エリック・エヴァンスの著書に関する目次と著者情報を紹介しています。目次は、ドメインモデルの機能、モデル駆動設計の要素、リファクタリングの深い洞察、戦略的設計の4部構成で、各部での主要なテーマが列挙されています。著者は、ビジネスとソフトウェア構築に関する専門家や技術コンサルタントであり、各自の経歴や専門分野も述べられています。
この書籍は、Webアプリ開発者向けに脆弱性の原因と対処法を解説したベストセラーの改訂版です。最新のOWASP Top 10 - 2017に対応し、HTML5やJavaScriptに関する新たな解説を追加しています。脆弱性診断の入門章も設けられ、実習環境はWindowsとMac両方に対応しています。著者はWebアプリケーションのセキュリティに関する専門家で、脆弱性診断やコンサルティングを行っています。
本書は、プログラムの洗練に必要な判断を学ぶためのケーススタディを提供しています。内容はクリーンコード、意味のある名前、関数、コメント、書式化、オブジェクトとデータ構造、エラー処理、境界、単体テスト、クラス、システム、創発、同時並行性、継続的改良、JUnitの内部、リファクタリング、経験則など多岐にわたります。プログラミングは動作するだけでは完結せず、質の向上が重要であることを強調しています。
この書籍は、システム保守における複雑なコードの分析手法や対処方法を解説しています。具体的には、コードの理解、テスト、リファクタリング、機能追加のためのテクニックを紹介。内容は、ソフトウェアの変更メカニズムや、変更作業における課題、依存関係の排除手法に分かれています。著者は、テスト駆動開発やオブジェクト指向設計に関する専門家たちです。
本書『リファクタリング』第2版は、ソフトウェアの内部構造を改善するためのガイドブックです。リファクタリングの概念や重要性、改善ポイントを実例を交えて解説しており、特にJavaScriptを用いた最新のコード例が豊富に含まれています。内容は約20年前の原稿を基にしつつも大幅に改訂され、リファクタリングの実践を促す内容となっています。著者は情報システムの専門家たちで構成されています。
Winner of the 2011 Jolt Excellence Award! Getting software released to users is often a painful, risky, and time-consuming process. This groundbreaking new book sets out the principles and technical practices that enable rapid, incremental delivery of high quality, valuable new functionality to users. Through automation of the build, deployment, and testing process, and improved collaboration between developers, testers, and operations, delivery teams can get changes released in a matter of hours- sometimes even minutes-no matter what the size of a project or the complexity of its code base. Jez Humble and David Farley begin by presenting the foundations of a rapid, reliable, low-risk delivery process. Next, they introduce the "deployment pipeline," an automated process for managing all changes, from check-in to release. Finally, they discuss the "ecosystem" needed to support continuous delivery, from infrastructure, data and configuration management to governance. The authors introduce state-of-the-art techniques, including automated infrastructure management and data migration, and the use of virtualization. For each, they review key issues, identify best practices, and demonstrate how to mitigate risks. Coverage includes * Automating all facets of building, integrating, testing, and deploying software * Implementing deployment pipelines at team and organizational levels * Improving collaboration between developers, testers, and operations * Developing features incrementally on large and distributed teams * Implementing an effective configuration management strategy * Automating acceptance testing, from analysis to implementation * Testing capacity and other non-functional requirements * Implementing continuous deployment and zero-downtime releases * Managing infrastructure, data, components and dependencies * Navigating risk management, compliance, and auditing Whether you're a developer, systems administrator, tester, or manager, this book will help your organization move from idea to release faster than ever-so you can deliver value to your business rapidly and reliably. Foreword by Martin Fowler Preface Acknowledgements About the Authors Part I Foundations 1 The Problem of Delivering Software 2 Configuration Management 3 Continuous Integration 4 Implementing a Testing Strategy Part II The Deployment Pipeline 5 Anatomy of the Deployment Pipeline 6 Build and deployment scripting 7 Commit Testing Stage 8 Automated Acceptance Testing 9 Testing Non-Functional Requirements 10 Deploying and Releasing Applications Part III The Delivery Ecosystem 11 Managing infrastructure and environments 12 Managing Data 13 Managing components and dependencies 14 Advanced version control 15 Managing Continuous Delivery Bibliography Index
この書籍は、プロジェクト管理手法「スクラム」の創始者であるジェフ・サザーランドが、効果的なチーム運営法を解説しています。スクラムは、ソフトウェア開発をはじめ、住宅リフォームや宇宙船の開発など多岐にわたる分野で革命を起こし、納期や予算の問題を解決する方法を提供します。著者は、最小限の時間と労力で最大の成果を出すための具体的な実践方法を伝授しています。
桜坂工兵は、厳しい就職活動を経てシステム開発会社に就職するが、教育係の室見立華は若くて働きすぎの厳しい指導者。工兵は彼女の指導の下で奮闘し、社長の無茶な受注により急遽仕事を任されることになる。システムエンジニアの厳しい現実をコミカルに描いたスラップスティック・ストーリー。著者は夏海公司。
本書は、ITエンジニアを目指す人に向けた必読のガイドです。IT業界の人材不足が続く中、異業種からの転職希望者も多く、自由な働き方やフリーランスの選択肢も魅力的です。著者は、ITエンジニアの職種やキャリアパス、雇用形態を理解し、自分に合った道を見つける重要性を説いています。また、就職・転職の準備やキャリアアップの具体例を通じて、次のステップへの進み方を指導します。成功するためのキャリアビジョンを構築する手助けをする内容です。
本書は、社会人が知っておくべきIT用語をイラスト付きで解説し、短時間で学べる内容になっています。各用語に関連する情報や使用例も掲載されており、理解を深めることができます。また、類似用語の違いも明確に説明されており、IT業界に不慣れな方でもわかりやすく学べる工夫がされています。目次は、ニュースやビジネス会話、Webサイト作成、セキュリティ用語など多岐にわたり、ITの全体像を把握する手助けをします。巻末には索引もあり、知りたい用語を簡単に探せます。著者は情報工学の専門家で、技術士としての資格を持っています。
本書は、ソフトウェア開発におけるリファクタリングやデザインパターンに関する知識を提供するもので、著者はエクストリームプログラミングの専門家であるジョシュア・ケリーエブスキー。各章ではリファクタリングの理由、手法、コードの臭い、パターンの活用法などが解説されており、実践的なカタログも含まれている。著者は多くの企業と協力しながら、ソフトウェア開発の指導に携わってきた。
開発チームをスムースに運営したいなら、プログラマ文化の深い理解が必要不可欠 あなたはプログラマーですか? プログラマーではないけれど、あなたの部下や同僚、あなたが関わっているプロジェクトにプログラマーが一人でもいれば、あなたは本書の読者です。 この本では、日頃あなたが不思議に思っていること、すなわち、 ●プロジェクトの計画と遂行の方法とソフトウェア開発プロセスが噛み合わない ●それによって生まれる衝突の回避 ・ソフトウェア開発プロジェクト管理の発展 ・開発手法のその利点と欠点の評価 ●プログラマーは何をどのようにやっているのか ●ソフトウェア開発プロセスや関連する用語、コードを書く以外にプログラマーが行っていること そして、 ●プログラマーの管理 ・プログラマーをどう採用するか ・一般的なプログラマーの心理学 ・開発者の心を占めているプレッシャーや優先度 ●プロジェクトの失敗にどう対処するか といったことに対して、著者自身が見聞し体験してきた、ソフトウェア開発にまつわる手酷い失敗や過ちをもとにした解決方法と指針を(ユーモアとともに)与えてくれます。 【重要な注】 そしてそれは、円滑にプロジェクトを進めるために必要な相互理解のステップであり、決定権の綱引きの方法ではありません。 もちろん、米国のソフトウェア開発事情と日本とでは、必ずしも全面的に同じではありませんが、日本の非プログラマー管理者たちにとっても、自身のプロジェクトを円滑に進めるためのヒントが詰まっている1冊といえます。 もちろん第一線で活躍しているプログラマーの皆さんにとっても得るものがたくさんあるはずです。 第1章 イントロダクション 1.1 読者は誰か 1.2 身に覚えがありますか? 1.3 この本は何か 1.4 この本は何ではないか 第2章 なぜソフトウェア開発は建築と似ていないのか 2.1 ソフトウェアプロジェクトの悲しい現実 2.2 固い数字 2.3 想像力の問題 2.4 見積りの問題 2.5 既知の問題 2.6 つまらないこと 2.7 未知のこと 2.8 ゲームするのを拒む 2.9 見積りは点ではなくグラフ 2.10 経験主義 2.11 算数の問題 2.12 ブルックスの法則 2.13 まとめ 第3章 アジャイル 3.1 アジャイルへの簡単な入門 3.2 SCRUM 3.3 他の方法論 3.4 アジャイルの利点 3.5 小さなスプリントと大きな決断 3.6 関係者の参加 3.7 チーム内のデザイナーと双方向の会話 3.8 同期 3.9 2歩進んで3歩戻る 3.10 統合 3.11 アジャイル対リーン 3.12 リーン開発の例 3.13 アジャイルかつリーン 3.14 アジャイルをいつ使うべきでないか 3.15 まとめ 第4章 彼らは一日中何をしているのか 4.1 何を作るか 4.2 ユーザー体験の詳細が重要 4.3 ユーザーストーリーは仕様ではない 4.4 Given-When-Thenシナリオ 4.5 引き渡し 4.6 コード 4.7 1と0 4.8 コンピューターの中身 4.9 ソフトウェア開発は抽象芸術 4.10 オブジェクト化 4.11 プログラミングとはモデル化である 4.12 完了 4.13 ソース管理 4.14 もう一組の目 4.15 配備 4.16 まとめ 第5章 緑の大きなチェックマーク 5.1 正攻法 5.2 すると言っていることをするか? 5.3 すると言っていないことをするか? 5.4 したと言ったことをするか? 5.5 失敗と折り合う 5.6 受け入れ 5.7 火のないところ 5.8 もう1つの方法 5.9 内部検査 5.10 テスト駆動 5.11 見えない品質 5.12 防止策 5.13 治療法 5.14 まとめ 第6章 ジャーゴンの謎を解く 6.1 インターネット 6.2 データ 6.3 セキュリティ 6.4 コーディング 6.5 まとめ 第7章 プログラマーを採用するには 7.1 プログラマーが本当に必要か 7.2 プログラマーをどうやって探すか 7.3 プログラマーの面接 7.4 プログラマーにイエスと言ってもらうには 7.5 まとめ 第8章 プログラマーの心を占めるもの 8.1 フォーラムという現象 8.2 ハイプサイクル 8.3 プログラマーの戦争 8.4 コードの美 8.5 まとめ 第9章 プログラマーを上機嫌に保つ 9.1 静かな部屋と強力なコンピューター 9.2 妙な時間 9.3 古いものと新しいもの 9.4 オープンソース 9.5 学び続けること 9.6 まとめ 第10章 すべてが悪くなるとき 10.1 メンバーが互いに反目しているとき 10.2 ひどくスケジュールから遅れているとき 10.3 できた製品が単に駄目だというとき 10.4 最後のまとめ
本書は、ダイレクトリクルーティングを活用したスカウト採用の手法を、プロの視点から解説した指南書です。中途・新卒採用担当者や経営者向けに、成功するためのテクニックやノウハウを紹介し、特にエンジニア採用に関する具体的なアドバイスも提供しています。著者は株式会社VOLLECTの代表で、500社以上のスカウト採用支援実績を持つ中島大志氏です。
この書籍は、経営において陥りやすい「同時代性の罠」として、「飛び道具トラップ」「激動期トラップ」「遠近歪曲トラップ」の3つを提唱しています。著者は、過去の経営判断を振り返り、現在の経営に活かす「逆・タイムマシン経営」の重要性を強調しています。具体的には、歴史を学ぶことで本質を見極め、戦略思考や経営センスを磨く方法論を提供しています。著者は一橋ビジネススクールの楠木建教授と社史研究家の杉浦泰氏です。
「シス管系女子」は、Linuxのコマンド操作を漫画で楽しく学べる書籍で、5万部を突破した人気シリーズの新エピソードを含んでいます。主人公の新人社員利奈と先輩社員大野のやり取りを通じて、シェルスクリプトやサーバー管理の基本が分かりやすく解説されており、実際の仕事で役立つ情報が満載です。各エピソードでは、リモート操作やファイル管理、コマンドの復帰など、具体的な操作方法が紹介されています。
著者小野壮彦は、100社以上のグローバルカンパニーで約5000人のエグゼクティブを評価してきたヘッドハンターであり、人物プロファイリングのノウハウを初公開します。彼の著書では、「人を見る目」を鍛えることができ、適切な人材選びが人生を変える重要性が説かれています。内容は「人を選ぶ意義」から始まり、人の本質を見抜くメソッドや、選ぶ際の注意点などを詳述しています。
本書は、Web系エンジニアになるための包括的なガイドです。IT業界の基盤が確立され、プログラミング教育が普及する中、特に需要が高まっているWeb系エンジニアの職業について、必要な知識やキャリアステップを解説しています。内容は、Web系企業の定義や職種、使用する技術、働き方、フリーランスへの道、キャリア形成の戦略など多岐にわたります。初学者や駆け出しエンジニアがWeb業界の全体像を理解し、必要なスキルを把握できる一冊です。著者は豊富な経験を持つエンジニアで、実体験に基づいた情報を提供しています。
ロジカルシンキングを使って、相手に納得してもらうことのできる報告や提案を組み立てるための手法を紹介。『ITエンジニアのロジカル・シンキング・テクニック』の内容を、多くのITエンジニアに導入した結果をフィードバックし、より分かりやすく、よりコンパクトにまとめたエッセンス。 第1章 構造化の基本(論理構造を作る 適切な根拠を与える ほか) 第2章 課題解決のための構造(原因探索型 目的展開型 ほか) 第3章 コンテキストの断裂(断裂の存在を知る ストーリーで断裂を越える ほか) 第4章 ドキュメントの構成(ドキュメントの3形態 起承転結より構造化 ほか)
本書は、プログラミングを独学で学ぶための効果的な学習方法を紹介しています。プログラミングに興味があるが何から始めればよいかわからない人や、学習がうまくいかないと感じている人に向けて、具体的な学習ステップや作品別の学習ルートを提案しています。著者は自身の経験をもとに、適切な学習法が成果に繋がることを強調し、プログラミングをスキルとして身につける手助けをすることを目的としています。
この書籍は、AWS(Amazon Web Services)に関する新しい入門書で、必要な知識を最短で身につけることを目的としています。多くの情報が溢れる中で、AWSエンジニアとして重要な情報を厳選し、基本的な考え方や構成、セキュリティなどを解説しています。著者はクラスメソッドのエンジニアたちで、実践的な知識を提供しています。AWSの全体像から具体的な構築方法、安全な利用法まで、幅広い内容がカバーされています。AWS初学者にとって必携の一冊です。
本書は新人SEやアプリケーションエンジニア向けのシステム方式設計入門書で、マンガと図解を使用して理解を助けています。ITアーキテクトとアプリケーションエンジニアの分業が進む中、方式設計の知識不足が問題を引き起こしているため、全てのSEがこの知識を持つことが重要とされています。内容は画面設計とDB性能に関するポイントを解説しており、具体的な事例を通じて学ぶことができます。
この本は、著名なIT企業でのシステム設計の面接対策を目的とした攻略本で、実務にも役立つ内容が含まれています。目次には、ユーザ数のスケールアップや各種システムの設計方法(レートリミッター、キーバリューストア、通知システムなど)が詳しく解説されています。著者のアレックス・シュウは、複雑なシステムの設計に情熱を持つ経験豊富なソフトウェアエンジニアです。
本書は、企業や組織におけるシステム開発のための設計書の作成と運用手順を解説しています。「組織でシステムを作る」をテーマに、クラウドやアジャイル開発などの現代の要素を取り入れた実践的なシステム構築法を紹介。元々はインプレスのWeb連載記事を基に書籍化され、大幅に加筆・修正されています。目次にはリスク管理やドキュメントの体系、データモデリングなどが含まれています。著者はシステムインテグレータの代表取締役社長、梅田弘之氏です。
この書籍は、中小企業向けにサイバーセキュリティ対策をわかりやすく解説したもので、知識がない人でも理解できる内容です。サイバー攻撃の手口や被害事例、具体的な対策(不正送金、情報漏えい、ネット詐欺、ウイルスなど)を紹介しており、マイナンバー制度への対応も含まれています。著者はサイバーセキュリティの専門家で、中小企業向けの啓蒙活動を行っています。
本書『JavaScript』は、最も広く使用されているプログラミング言語であるJavaScriptを包括的に解説したもので、第6版から大幅に加筆・更新されています。基本的な構文や機能、標準ライブラリ、クライアントサイドおよびサーバサイドのJavaScriptについて詳しく説明し、非同期プログラミングやクラスの定義方法、モジュールの使い方なども紹介しています。開発者にとって必携の一冊です。著者はJavaScriptの専門家であり、プログラミングの基礎から応用まで幅広くカバーしています。
ソフトウェアを起点にビジネスを考えなくてはいけない現代に重要なソフトウェアファーストの考え方をインストールできる書籍。DXが遅れている企業ではどうしても業務フローに合わせた非効率なソフトウェア開発が進んでいる。それよりも現代は既存のソフトウェアに業務フローをなるべく合わせて改善していくべき!
メタバースについて知りたいならまずこの書籍を手にとってみるべき。日本の新興メタバーススタートアップとして注目を浴びているクラスター創業者の加藤氏が語るメタバース。
この書籍は、SIer(システムインテグレーター)の役割や必要なスキル、IT業界のビジネスモデルの変化を解説しています。目次には、SIerの特徴、クラウド時代の変化、ユーザ企業が注目すべきポイント、ITエンジニアに求められる能力、クラウドサービス構築のステップ、実際のケーススタディが含まれています。著者は増田博道氏で、ITを活用して中小企業を支援する活動を行っています。
本書は、生成AI時代におけるMicrosoft Copilot for Microsoft 365の活用法を100のテクニックとして解説しています。生成AIの普及により、デスクワークは大きく変わるとされ、特にMicrosoftのアプリケーションでの活用が重要です。著者はアクセンチュアのデータ&AIグループで、Teams、Outlook、PowerPoint、Word、Excel、OneNote、Whiteboard、Power Automateなどの主要アプリにおける具体的なテクニックを紹介。生成AIを使いこなすための実用的なガイドとして位置づけられています。
本書『アジャイルサムライ』は、ソフトウェア開発におけるアジャイル手法を紹介しており、顧客に価値を提供するプロフェッショナルとしてのアプローチを解説しています。内容はアジャイルの基本、方向づけ、計画、プロジェクト運営、プログラミングに関する各部に分かれており、著者は実務経験豊かなアジャイルコーチたちです。
本書は、NoCode(ノーコード)によるアプリ開発について、基礎知識や主要ツール「Glide」「Adalo」「Bubble」の使い方を詳しく解説しています。各ツールの特徴や実際の活用例を紹介し、巻末にはNoCodeの未来についての座談会も収録されています。著者はNoCodeエバンジェリストであり、専門のオンラインサロンを運営しています。
本書では、プロジェクトマネジメントにおける問題の根源は「不確実性」にあると指摘されています。プロジェクトは常に新しい挑戦であり、成功するための固定された進め方は存在しません。そのため、各プロジェクトに応じた「固有のプロセス」を設計する必要があります。この考え方を「プロセスデザインアプローチ」と呼び、著者が具体的な方法を解説しています。内容は、プロジェクトの本質、不確実性の管理、プロジェクトの全体像、計画や進捗管理の方法、振り返りの重要性など、幅広いテーマを扱っています。著者は、実行品質を高めるためのコンサルタントであり、実践的なアプローチを提供しています。
この書籍は、フリーエンジニアとして成功するために必要なスキルや心構えを解説しています。著者は、ITエンジニア不足の現状を背景に、独立する際に重要な「技術以外の要素」を強調しています。具体的には、面接術、処世術、営業術、仕事術、勉強術など、実践的なアドバイスを提供しています。著者自身の経歴を通じて、フリーエンジニアとしてのキャリア形成に役立つ知識を伝えています。
この書籍は、Googleのソフトウェアエンジニアたちが超大規模ソフトウェアの開発と保守におけるベストプラクティスを、文化、プロセス、ツールの観点からまとめています。時間、変化、規模、成長、トレードオフ、コストという基本原理に基づき、持続可能なコードの方法論を解説。心理的安全性やダイバーシティなどの文化、コードレビューやテストのプロセス、継続的インテグレーションなどの自動化ツールについても触れています。経済学や心理学の視点を取り入れ、データ駆動の定量的・定性的な意思決定プロセスを説明しており、幅広い読者に役立つ知見を提供しています。
この書籍は、マンガを通じてデータベースの基礎知識を学ぶ内容です。目次には、データベースの基本概念、リレーショナルデータベースの解説、データベース設計、SQLの基本操作、運用方法、そしてデータベースの普及と活用についての章が含まれています。著者は高橋麻奈で、東京大学経済学部を卒業しています。
本書は、Web系エンジニアを含む全てのエンジニアに向けて、企業情報システムの設計に関する実践的なノウハウを提供する。16の視点から80の重要ポイントを解説し、データモデリングや業務設計、スコープ決定、ユーザーヒアリングなど、システム設計の本質を探求する内容。特に、顧客の要件やプロジェクト管理に関する具体的なアドバイスが盛り込まれており、エンタープライズシステムを成功に導くための知識が得られる。
本書は、急成長中の採用・人事業務代行会社の社長が、ベンチャー企業や中小企業向けに「本当にほしい人材」を集めるための実践的メソッドを解説しています。著者は350社以上の採用活動を支援し、自社も急成長を遂げた経験を基に、中途採用の戦略を紹介。具体的には、採用広報、スカウト文の作成、面接方法など、戦略的なアプローチが必要であると強調し、採用に悩む企業に有益な手法を提供しています。
本書は、株式会社セガのゲームプログラマが初心者向けに書いたプログラミング入門書です。一般的な入門書が提供しない根本的な考え方を学べる内容で、簡単なゲーム制作を通じてプログラム作成に必要な思考法を身につけることを目的としています。著者はプログラミング未経験者や基礎を再学習したい人々に向けて、具体的な手法を示しています。
本書は、デジタル化が進む世界の本質を解説し、日本企業がオンラインを活用する従来のアプローチを見直す必要性を訴えています。著者たちは、オフラインが存在しない「アフターデジタル」の時代を提唱し、すべてのビジネスがオンライン化される未来を描いています。内容は、デジタル化の現状、OMO型ビジネスの重要性、具体的な事例を通じた思考訓練、日本のビジネス変革に焦点を当てています。デジタル担当者だけでなく、未来を拓くすべてのビジネスパーソンに向けた一冊です。
デジタルが主体の時代に突入しどのように顧客行動が変わっていくかを中国の事例をふんだんにまじえながら教えてくれる良書。デジタル時代のマーケティングをおさえるためにぜひ読んでおきたい1冊
本書は、システム化企画や要件定義、基本設計などの上流工程に必要なスキルや心構えについて解説しています。単に実装スキルだけでなく、議論をリードし、関係者の合意を得る能力、全体を見通す視点が求められます。上流工程を初めて行う際の準備やスキルアップ方法についても具体的なアドバイスが提供されています。著者は、システム開発の専門家であり、若手エンジニアの育成に力を入れています。
本書は、現代社会におけるソフトウェアの重要性と、その不具合や不正行為がもたらす影響を踏まえ、ソフトウェア開発者やマネージャーに対して「規律、基準、倫理」の重要性を教え、堅牢で対障害性のあるソフトウェアの構築を促す内容です。目次には、テスト駆動開発や生産性、品質、倫理に関するテーマが含まれています。
本書は、リファラル採用の成功法則を提唱する鈴木貴史氏によるもので、企業が競争を避け、採用活動の効率を高める方法を紹介しています。著者は、日本でリファラル採用の概念を創出した起業家であり、企業が従来の手法に頼らず、社員を巻き込んだ採用戦略を実現することを目指しています。具体的には、企業ブランドへの共感を呼び起こし、採用コストを削減し、従業員のエンゲージメントを高めることが可能です。本書は、戦わない採用の実践方法や成功事例を通じて、企業の変革を促す内容となっています。
著者中島聡は、人気のiPadアプリ開発者であり、米国ベンチャー企業の経営者です。本書では、彼の人生観や若者へのメッセージを語り、世界で働くことの重要性や日本のエンジニアの現状、成功するための自己変革について述べています。目次には、エンジニアとしての成功やビル・ゲイツの面接試験に関する特別付録も含まれています。
この入門書は、初学者や非プログラマー向けにプログラムの動作原理を「実習」と「講義」を通じて解説しています。内容はプログラミングの基本、コンピュータやOSの役割、プログラミング言語の基礎、JavaScriptやC言語の学習、オブジェクト指向モデリングなど多岐にわたります。著者は河村進氏で、実業界や研究機関での豊富な開発経験を持つ専門家です。
本書は、コロナ禍によって加速した「アフターデジタル」社会の変革について論じています。日本企業はデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めていますが、その基盤が不十分な場合が多いと指摘。特に、中国のアリババやテンセントの成功事例を通じて、アフターデジタル社会における産業構造の変化や、ユーザー体験(UX)の重要性を強調しています。著者は、企業が新しい市場ルールを理解し、戦略を練る必要性を訴えています。
アフターデジタルが出版されてからコロナ禍に突入し、消費行動はデジタルに一気に偏った。そんな中続編として出版されたアフターデジタル2。前作と同じく非常に学びになるので1,2併せて読んでおきたい。
本書『アルゴリズムC 新版』は、2004年に刊行された名著の復刊で、世界的に評価されているアルゴリズムの教科書です。直感的な説明や豊富な図、具体的なコードが特徴で、研究者や学生に必携の一冊です。内容は基礎、データ構造、整列、探索の4部構成で、続刊『第5部グラフアルゴリズム』の刊行も決定しています。著者は電気通信大学の名誉教授らで構成されています。
この書籍は、Google Appsheet、Amazon Honeycode、Bubble、Thunkable、Clickといったノーコードツールを使ったアプリ開発方法を解説しており、実際にサンプルアプリを作成しながら学べる内容です。著者は、様々なプラットフォーム向けにプログラミング初心者向けの書籍を執筆している掌田津耶乃です。
『独習Python』は、プログラミング初学者向けのPython入門書で、著者は山田祥寛氏です。本書は、手を動かして学ぶスタイルを重視し、Pythonの基本から応用までを体系的に学べる内容となっています。解説、例題、理解度チェックの3ステップで、基礎知識がない人でも理解しやすい構成です。プログラミング初心者や再入門者におすすめの一冊です。目次には、Pythonの基本、演算子、制御構文、標準ライブラリ、ユーザー定義関数、オブジェクト指向構文などが含まれています。
Pythonをしっかり学びたい人向けの本格的な入門書です。基礎から応用まで幅広いトピックをカバーしており、実際に手を動かしながら理解を深められるよう工夫されています。独習スタイルに特化しているため、自分のペースで着実に学びたい人におすすめ。豊富なコード例や練習問題もあり、プログラミングの実力を着実に高めることができます。
この書籍は、実践的なGit/GitHubの使い方を学ぶための初心者向け入門書です。前半では基本的な操作を解説し、後半ではチーム開発のための知識を身につける内容となっています。コマンドライン操作が中心で、新しいGitコマンドやGitHubの機能、実務で役立つ慣習も紹介されています。著者はエンジニア経験を持つ専門家で、ワークショップ感覚で学べる構成になっています。
本書は、Dockerを初めて触る新人エンジニアや非エンジニア向けに、Dockerの仕組みと使い方を分かりやすく解説しています。初心者が理解できるようにイラストを多用し、単にコマンドを使えるようになるのではなく、Dockerの基本的な動作原理を理解することを重視しています。内容はDocker Desktopを中心に構成されており、他の環境へのインストール方法も紹介されています。Dockerを長く使うための基礎力を身につけたい方に適した一冊です。
Peter Seibel interviews 15 of the most interesting computer programmers alive today in Coders at Work, offering a companion volume to Apress's highly acclaimed best-seller Founders at Work by Jessica Livingston. As the words "at work" suggest, Peter Seibel focuses on how his interviewees tackle the day-to-day work of programming, while revealing much more, like how they became great programmers, how they recognize programming talent in others, and what kinds of problems they find most interesting. Hundreds of people have suggested names of programmers to interview on the Coders at Work web site: www.codersatwork.com. The complete list was 284 names. Having digested everyone's feedback, we selected 15 folks who've been kind enough to agree to be interviewed: * Frances Allen: Pioneer in optimizing compilers, first woman to win the Turing Award (2006) and first female IBM fellow * Joe Armstrong: Inventor of Erlang * Joshua Bloch: Author of the Java collections framework, now at Google * Bernie Cosell: One of the main software guys behind the original ARPANET IMPs and a master debugger * Douglas Crockford: JSON founder, JavaScript architect at Yahoo! * L. Peter Deutsch: Author of Ghostscript, implementer of Smalltalk-80 at Xerox PARC and Lisp 1.5 on PDP-1 * Brendan Eich: Inventor of JavaScript, CTO of the Mozilla Corporation * Brad Fitzpatrick: Writer of LiveJournal, OpenID, memcached, and Perlbal * Dan Ingalls: Smalltalk implementor and designer * Simon Peyton Jones: Coinventor of Haskell and lead designer of Glasgow Haskell Compiler * Donald Knuth: Author of The Art of Computer Programming and creator of TeX * Peter Norvig: Director of Research at Google and author of the standard text on AI * Guy Steele: Coinventor of Scheme and part of the Common Lisp Gang of Five, currently working on Fortress * Ken Thompson: Inventor of UNIX * Jamie Zawinski: Author of XEmacs and early Netscape/Mozilla hacker What you'll learnHow the best programmers in the world do their jobs! Who this book is for Programmers interested in the point of view of leaders in the field. Programmers looking for approaches that work for some of these outstanding programmers. Table of Contents * Jamie Zawinski * Brad Fitzpatrick * Douglas Crockford * Brendan Eich * Joshua Bloch * Joe Armstrong * Simon Peyton Jones * Peter Norvig * Guy Steele * Dan Ingalls * L Peter Deutsch * Ken Thompson * Fran Allen * Bernie Cosell * Donald Knuth
本書は、Webエンジニアを目指す人や2~3年目のエンジニア向けに、必要な知識やスキルを解説しています。最新の技術動向に基づき、開発環境の構築、データベース、バックエンド、フロントエンド、インフラ、セキュリティについて広範に紹介。著者は、豊富な実務経験を持つ専門家たちで構成されています。この本を通じて基礎を学び、将来的な技術の変化に対応できる力を養うことを目指しています。
「テストの教科書」は、初学者向けにソフトウェアテストの基礎から体系的に学べる内容の書籍です。丁寧な解説と平易な文章で、テストの基本的な考え方や5つのテスト技法を用いた欠陥の検出方法を紹介しています。目次には、ソフトウェアテストの基礎、さまざまなテスト技法、テストドキュメントとモニタリングが含まれています。著者は、ソフトウェアテストの専門家である石原一宏氏と田中英和氏です。
『これからはじめるプログラミング 基礎の基礎』の改訂第3版は、プログラミング入門者向けに書かれた定評ある書籍です。内容は現代の読者に合わせて見直され、プログラミング環境や言語もアップデートされています。目指すゴールは旧版と同じで、プログラミングの基本知識や実践的なステップを学ぶことができます。この本は、プログラミングを始める人にとっての「最初に読むべき入門書」とされています。
著者の久松剛が10年の経験を基に、ITエンジニアの採用とマネジメントに関する知見をまとめた教科書です。少子化とデジタルトランスフォーメーション(DX)の影響でITエンジニア不足が進む中、採用だけでなく、定着や活躍を支援する組織づくりが重要です。書籍では、採用市場の理解から選考、内定、定着支援、退職への備え、経験者以外の採用選択肢、DX実現に向けたエンジニアとの関係構築、未来予測までを包括的に解説しています。実践的な内容が特徴です。
本書は、Javaをゼロから学びたい人や他の言語からJavaに移行したい人向けに、プログラミングの基礎をわかりやすく解説しています。Javaは多くの業務システムで利用されており、エンジニアとしての需要も高い言語です。内容は、Javaの基本から高度なプログラミング、開発ツールの使い方、Webアプリケーションの開発まで幅広くカバーしています。実際にプログラムを組む体験を通じて、プログラミングの楽しさと難しさを学ぶことを目指しています。
本書は、JavaScriptの基礎から実践的な知識までを網羅しており、プログラミング初心者でも現場で役立つスキルを身につけられる内容です。目次には、導入編、基本編(変数、関数、オブジェクト指向など)、実践編(Webページ作成)、応用編(フレームワーク)などが含まれています。著者は技術書やゲーム開発に携わる柳井政和氏です。