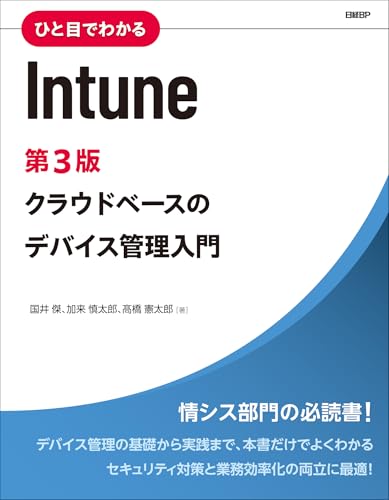【2025年】「アセンブラ」のおすすめ 本 96選!人気ランキング
- アセンブリ言語の教科書: Kenji’s homepage
- 独習アセンブラ
- はじめて読むマシン語
- リーダブルコード ―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック (Theory in practice)
- 独習アセンブラ 新版
- H8マイコン入門
- アセンブリ言語スタートブック
- マンガでわかるCPU
- 大熱血! アセンブラ入門
- 熱血!アセンブラ入門
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
高性能で人気の高いH8マイコンを平易に解説 H8は,日立製作所製の小型で高性能の組込型ワンチップマイコンである.このH8マイコンは,身の回りの家電機器をはじめ,携帯電話やカーナビなど,様々なところで使用されている.また,小型で高性能という利点を生かし,各種ロボコンの機体制御など,ホビーユースにおいても多く用いられている.本書は,H8マイコンの初心者を対象に,2進数の計算やマイコンのの基本概念から簡単なH8のアセンブラプログラムを解説.H8初心者のみならず,マイコン初心者でもH8マイコンが理解できるように執筆. 第1章 マイコン制御の基礎 1.1 コンピュータの基本構成 1 コンピュータ処理の流れ 2 ノイマン型コンピュータの基本構成 1.2 コンピュータの基本動作 1 命令実行の流れ 2 フォン・ノイマンのボルトネック 1.3 CPU 1 CPUの発達 2 マルチチップとシングルチップ 1.4 制御用のマイコン 1 マイコン制御とは 2 制御用マイコンの分類 1.5 マイコン制御の手順 1 実装までの流れ 2 必要な知識 第2章 H8マイコンとは 2.1 H8マイコンの種類 1 H8シリーズ 2 H8/300Hシリーズ 2.2 H8/3048F 1 H8/3048Fの概要 2 H8/3048Fボード 2.3 H8/3664F 1 H8/3664Fの概要 2.4 開発ツール 1 ソフトウェア 2 ハードウェア 第3章 マイコンでのデータ表現 3.1 2進数 1 2進数とは 2 2進数の計算 3 2進数と10進数 4 補数 5 負の数の表現 3.2 16進数 1 16進数とは 2 16進数と10進数 3 16進数と2進数 3.3 ディジタル回路 1 論理回路 2 算術演算と論理演算 3 マスク操作 4 シフト操作とローテイト操作 5 スイッチ信号 第4章 H8/3048Fマイコンの基礎 4.1 アーキテクチャ 1 アーキテクチャの概要 2 H8/3048Fの考え方 4.2 メモリ 1 メモリマップ 2 RAM 3 ROM 4.3 CPU 1 CPUの構成 2 汎用レジスタ(Ern) 3 コントロールレジスタ 4 スタックポインタ 5 命令セット 6 アドレッシング 7 処理状態 8 クロック信号 9 リセット 10 割込み 4.4 ポート 1 ポートの概要 2 ポートの使い方 3 ポートの出力許容電流 4.5 周辺機能 1 周辺機能の概要 2 DMAコントローラ(DMAC) 3 インデグレーテッドタイマユニット(ITU) 4 ウォッチドッグタイマ(WDT) 5 A-Dコンバータ 6 D-Aコンバータ 第5章 アセンブラ言語による実習 5.1 アセンブラ言語の基礎 1 アセンブラ言語とは 2 アセンブラ制御命令 3 プログラムの書き方 4 開発の手順 5.2 LEDの制御 1 LEDの点灯 2 スイッチ入力 3 LEDの点滅 4 インテグレーテッドタイマの使用 5.3 パルスモータの制御 1 パルスモータとは 2 パルスモータの回転制御 5.4 DCモータの制御 1 ドライバICによる回転方向制御 2 PWM機能による速度制御 5.5 A-D,D-Aコンバータの制御 1 A-Dコンバータ 2 D-Aコンバータ 5.6 割込み制御 1 IRQ端子を使った割込み 2 NMI端子を使った割込み 第6章 C言語による実習 6.1 Cコンパイラ 1 Cコンパイラの種類 2 プログラムの書き方 3 開発の手順 6.2 LEDの制御 1 LEDの点滅 2 スイッチ入力 3 インテグレーテッドタイマの使用 (1)H8命令セット一覧 (2)マイコンなどの入手先
この書籍は、熱心なエンジニア向けにセキュリティの専門家が執筆したもので、アセンブラの基礎から応用、発展的な内容まで幅広くカバーしています。目次には、基本操作、さまざまなCPUのアセンブラ、出力環境の構築、最適化、アセンブラの活用方法などが含まれています。著者の坂井弘亮は、組込みOSの開発やセミナーでの活動を行っている専門家です。
PICマイコンのC言語によるプログラミングの基礎を分かりやすく会解説。USB機能を持つPIC18F2550を使用。 PICマイコンのC言語によるプログラミングの基礎を分かりやすく解説。2進数や16進数などのデータ表現やC言語の基礎も掲載。USB機能を持つPIC18F2550を使って解説。簡単な回路でパソコンと接続できる。 第1章 マイコンとPIC-USBマイコン 1.1 マイコンとは 1.2 PIC-USBマイコン 1.3 C言語によるプログラムの開発 章末問題 第2章 データの表現 2.1 数体系 2.2 数値データ 2.3 論理演算 章末問題 第3章 C言語の基礎 3.1 C言語の概要 3.2 プログラムの基本構成 3.3 数値の表示と変数 3.4 演算子と関数 3.5 基本処理 章末問題 第4章 PIC-USBマイコンボード 4.1 PIC-USBマイコンボードの概要 4.2 PIC-USBマイコンボードの回路構成 4.3 PIC-USBマイコンボードを構成する部品 4.4 スルーホール 4.5 ファームウェア 章末問題 第5章 PIC-USBマイコン用プログラムの作成 5.1 プログラムの書式と記述例 5.2 基本操作 5.3 総合プログラム 章末問題 第6章 プログラム開発ツールの利用 6.1 開発に必要なソフトウェア 6.2 開発ツールのダウンロード方法 6.3 開発ツールのセットアップ 6.4 開発ツールの設定 6.5 開発ツールの使い方 6.6 シミュレータの使い方 章末問題 解答 付録 索引
本書は、なぜ多くの成功者がプログラミングの基本を学んでいるのか、その理由と効率的な学習方法を紹介しています。著名人たちも支持する「世界最良の学習メソッド」を用いて、小学生から大人まで誰でも楽しめる内容です。プログラミングの基礎知識は将来的に役立つスキルであり、初心者向けの学習サービスやプログラミング言語の選び方も解説しています。プログラミングを効率よく学びたい人や教育に興味がある人におすすめの一冊です。
この文章は、川合秀実著の書籍の目次を紹介しており、PCの仕組みやアセンブラ、C言語、画面表示、構造体、割り込み処理、マウス制御、メモリ管理など、プログラミングの基本から応用までの内容を網羅しています。
マイコンの動作原理や2進級の取扱いなどマイコン初学者でも理解できるように解説。 高性能で汎用性のあるワンチップマイコンのPICは,身の回りの制御用素子として多く使用されている。 本書は,マイコンの動作原理や2進数の取り扱いなど,マイコン初学者でも理解できるように解説。PICを取り扱う上でつまづきやすいアセンブラプログラムを,最もよく使用されているPIC 16F84に的を絞って解説。 第1章 マイコンとPIC16F84 1.1 マイコンとは 2. マイコンの構 3. マイコンの動作 4. マイコンの処理性能 1. マイコンとその利用 5. マイコンの分類 1.2 PIC16F84 1. PIC16F84の特徴 2. PIC16F84の基本構成 3. PIC16F84の構成要素 4. PICの使用例 1.3 プログラム開発 1. 準備 2. 開発手順 演習問題1 第2章 マイコンでのデータの扱い 2.1 2進数と16進数 1. 10進数,2進数,16進数 2. 10進数,2進数,16進数の変換 2.2 2進数の計算 1. 負の数の表現 2. 2進数の加算,減算 2.3 論理演算 1. 算術値と論理値 2. NOT,AND,OR,EX-OR 3. シフト・ローティト演算 演習問題 第3章 アセンブラ言語 3.1 命令の種類と命令の形式 1. 機械語とアセンブラ言語 2. 命令の種類 3. 命令の形式 3.2 機械語命令の働き 1. 転送命令 MOVF命令/MOVWF命令/MOVLW命令 2. 演算命令(算術演算命令) ADDWF命令/ADDLW命令/SUBWF命令/SUBLW命令/INCF命令/DECF命令 3. 演算命令(論理演算命令) COMF命令/ANDWF命令/ANDLW命令/IORWF命令/IORLW命令/ XORWF命令/XORLW命令 4. 演算命令(ローティト演算命令) RLF命令/RRF命令 5. 演算命令(その他の演算命令) CLRF命令/CLRW命令/BCF命令/BSF命令/SWAPF命令/CLRWDT命令 6. 分岐命令(条件分岐命令) INCFSZ命令/DECFSZ命令/BTFSC命令/BTFSS命令 7. 分岐命令(無条件分岐命令) GOTO命令 8. 分岐命令(サブルーチン命令) CALL命令/RETFIE命令/RETLW命令/RETURN命令 9. 制御命令 10. 機械語命令のまとめ 3.3 アセンブル例 1. 疑似命令 2. MPASMによるアセンブル例 演習問題 第4章 基本プログラムの作成 4.1 プログラムの書式と記述例 4.2 基本操作 1. データ転送 2. 条件分岐 3. 繰り返し 4. 数値計算 5. ビット操作 演習問題 第5章 応用プログラムの作成 5.1 副プログラム 1. サブルーチン 2. 割り込みサブルーチン 5.2 制御 1. 入出力ポートの設定 2. 入力処理 3. 出力処理 5.3 プログラム例 1. 論理回路の代用 2. 入力ノイズの除去 3. ライントレースカー 演習問題 6.マイクロマウスのプログラム 6.1 MPLABを使用したプログラム開発 1. MPLABのインストールと設定 2. アセンブル 3. シミュレータ 6.2 プログラムの書き込み 1. ライタの接続 2. プログラムの書きこみ 演習問題の解答 参考URL 索 引
『Cの絵本』は、C言語の初心者向け入門書としてリニューアルされ、プログラムの知識がなくても学び始められる内容になっています。新版ではポインタの解説が改善され、実践的な内容や最新の環境構築手順が追加されています。イラストを多用し、直感的に理解しやすい形式で提供されており、基礎からしっかり学べる一冊です。また、翔泳社の「絵本シリーズ」全体も改訂され、現代の技術に合わせた内容に刷新されています。
著者がトースターを原材料からゼロから作る挑戦を描いたドキュメンタリー。鉄鉱石や銅を採掘し、じゃがいものでんぷんからプラスチックを作る過程での苦労や発見をユーモラスに考察し、消費社会についても触れている。目次には解体、鉄、プラスチックなどの章があり、著者はデザイナーのトーマス・トウェイツ。
『教養としてのプログラミング講座』は、プログラミングの基礎から応用までを解説し、プログラマーの思考法を学べる一冊です。著者は国認定の「天才プログラマー」であり、プログラミングを「誰もが学ぶべき教養」と位置づけています。小中学校でのプログラミング必修化を受け、内容を増補して再刊行されました。目次には、プログラミングの基本、役立つテクニック、未来の展望などが含まれています。
IT系資格の登竜門となる,基本情報技術者をめざす方のためのやさしいオールインワンタイプの参考書&問題集です。最新の傾向を分析し,出題頻度の高い分野を中心に,イラストや豊富な図解・例え話を駆使して理解しやすく・記憶に残りやすいように説明し,「〇〇とくれば××」方式で重要ポイントを再確認。さらに関連の本試験問題をすぐ解くことで,知識が定着し応用力もつきます。 令和03年版ではシラバス7.1に対応し,紙面をリニューアルし大幅増ページ。試験攻略のためのアドバイスや,背景を理解するための参考など新コーナーを増やしました。また,全問題に正解率を掲載し,実力養成を後押しします。 収録問題数は,令和の過去問含めたっぷり273問。無駄なく効率よく短時間で合格レベルに到達することができる,受験者必携の1冊です。 ■第1章 コンピュータ構成要素 1-01 情報の表現 1-02 コンピュータの構成 1-03 CPU 1-04 CPUの動作原理 1-05 CPUの高速化技術 1-06 半導体メモリ 1-07 補助記憶装置 1-08 入出力装置 1-09 入出力インタフェース ■第2章 ソフトウェアとマルチメディア 2-01 ソフトウェア 2-02 ジョブ管理とタスク管理 2-03 記憶管理 2-04 ファイル管理 2-05 マルチメディア ■第3章 基礎理論 3-01 基数変換 3-02 補数と固定小数点数 3-03 浮動小数点 3-04 誤差 3-05 シフト演算 3-06 論理演算 3-07 半加算器と全加算器 3-08 計測と制御 3-09 オートマトン 3-10 AI 3-11 線形代数 3-12 確率・統計 ■第4章 アルゴリズムとプログラミング 4-01 アルゴリズム 4-02 配列 4-03 リスト 4-04 キューとスタック 4-05 木構造 4-06 データの整列 4-07 データの探索 4-08 計算量 4-09 プログラムの属性 4-10 プログラム言語とマークアップ言語 ■第5章 システム構成要素 5-01 システム構成 5-02 クライアントサーバシステム 5-03 RAIDと信頼性設計 5-04 システムの性能評価 5-05 システムの信頼性評価 ■第6章 データベース技術 6-01 データベース 6-02 データベース設計 6-03 データの正規化 6-04 トランザクション処理 6-05 データベースの障害回復 6-06 データ操作とSQL 6-07 SQL(並べ替え・グループ化) 6-08 SQL(副問合せ) 6-09 データベースの応用 ■第7章 ネットワーク技術 7-01 ネットワーク方式 7-02 OSI基本参照モデルとTCP/IP 7-03 ネットワーク接続機器 7-04 IPアドレス 7-05 IPアドレスのクラス 7-06 ネットワーク管理 ■第8章 情報セキュリティ 8-01 情報セキュリティと情報セキュリティ管理 8-02 脅威とマルウェア 8-03 サイバー攻撃 8-04 暗号技術 8-05 ネットワークセキュリティ ■第9章 システム開発技術 9-01 情報システム戦略とシステム企画 9-02 ソフトウェア開発 9-03 業務モデリング 9-04 ヒューマンインタフェース 9-05 モジュール分割 9-06 オブジェクト指向 9-07 テスト手法 ■第10章 マネジメント系 10-01 プロジェクトマネジメント 10-02 工程管理 10-03 ITサービスマネジメント 10-04 システム監査 ■第11章 ストラテジ系 11-01 ソリューションビジネスとシステム活用促進 11-02 経営組織と経営・マーケティング戦略 11-03 業績評価と経営管理システム 11-04 技術開発戦略 11-05 ビジネスインダストリ 11-06 品質管理手法 11-07 会計・財務 11-08 知的財産権とセキュリティ関連法規 11-09 労働・取引関連法規と標準化 11-10 オペレーションリサーチ
本書は、800円弱で入手可能なPicoおよびPico Wマイコンボードについて、仕様や製作例を幅広く解説しています。内容は、開発の基礎知識からプログラマブルI/O、USB機能、リアルタイムOS、人工知能の搭載、開発事例、Windowsでの利用、MicroPythonやC++による拡張モジュールの作成、Pico Wの活用事例まで多岐にわたります。
本書は、コンピューターの中核であるCPUの基本原理から設計例までを解説しており、アキバで手に入る部品を使った実際の製作も可能です。目次には、デジタル回路の基礎、リセットとクロック回路、ROMの作成、1ビットCPUの設計などが含まれています。著者は回路技術屋の渡波郁氏です。
本文オールカラー刷りならではの新学習機能をわんさか搭載! 午後試験にもしっかり対応! 本試験で狙われる論点を、新学習機能によって効率よくマスターすることができる基本テキストです。午後の出題範囲・配点の変更にもシッカリ対応。よりパワーアップしました。 気になる「CBT方式」対策法も掲載しています。 ★学習と試験対策の手引き 巻頭の「スタートアップ講座」で、学習の道筋から本試験の攻略法までをガイダンス。情報満載の目次でどこに何が載っているか、ひと目でわかる! 目的意識を持って学習を効率的に進めることができます。 ★インプットしやすい 午前試験対策と午後試験対策で解説方法を分けました。 →午前対策:側注つきレイアウト。実戦知識をすっきり解説。 →午後対策:一段組みレイアウト。“専用ページ”を設けしっかり解説。 ★イメージしやすい 見てすぐ理解につながるカラー図解と本試験に直結した色別の側注。 →図解は、考え方のプロセスを覚えやすいよう、彩色しています。 →知っていればよい知識は表組みにまとめました。 →側注でも、頻出論点を、重要度で色分けし、解説しています。 ★アウトプットもできる →章末問題(午前対策)と本文:午後対策頁で取り上げた午後問題を全文掲載。実践力を磨くことができます。 ★午前だけでなく午後試験にもしっかり対応 →午後試験では「各種プログラム言語または表計算」計5問から1問を選択して解答しなくてはなりませんが、類書も含め従来の基本テキストではほとんど解説がなく、基本書として不親切でした。そこで本書ではもっとも解答者が多い「表計算」対策の章を設けてあります。1冊で午前・午後両方の試験に対応しています。
『これからはじめるプログラミング 基礎の基礎』の改訂第3版は、プログラミング入門者向けに書かれた定評ある書籍です。内容は現代の読者に合わせて見直され、プログラミング環境や言語もアップデートされています。目指すゴールは旧版と同じで、プログラミングの基本知識や実践的なステップを学ぶことができます。この本は、プログラミングを始める人にとっての「最初に読むべき入門書」とされています。
本書は、セキュリティコンテストで出題されるCTF(Capture The Flag)の問題を通じて、セキュリティ技術を学ぶための実践的なガイドです。初心者向けに、問題解決のプロセスやアプローチをわかりやすく解説し、全14問の具体例を通じて知識を深めることができます。また、CTFの世界に興味を持ち、日々の学習や練習を促す内容となっています。
『デザインパターン』の23個のパターンをオブジェクト指向初心者向けに解説した書籍で、Javaのサンプルプログラムを掲載。新たに「デザインパターンQ&A」も追加されている。目次はデザインパターンの基本から、サブクラスの利用、インスタンス作成、構造管理など多岐にわたる。
基本情報技術者試験、午後問題を完全対策! 本書は、基本情報技術者試験のうち、「午後問題」に的を絞ったテーマ別頻出問題集です。 令和02年試験からの出題数/配点変更にともない、より重要となったテーマの問題数をアップ。 手厚く対策でき、合格へと着実に近づくことができます! ●本書の特徴 ・近年の出題傾向を踏まえて、よくでる問題を厳選収録 ・頻出問題をテーマ別に掲載。苦手な分野を集中対策できる ・設問ごとのていねいな解説で、解き方がしっかりわかる ・単なる解き方だけでなく、各設問の技術的な背景もわかりやすく解説 ・試験の時間配分を考慮した速読&解答テクニックも掲載 ■受験ガイダンス 「基本情報技術者」試験とは? 午後試験では何が出題される? 午後問題の速読テクニック アルゴリズム問題の解き方 例題を使い、アルゴリズム問題を解いてみよう! 合格したら、上位試験に挑戦! ■第1章 情報セキュリティ 01 VPNとVDIによるセキュリティ対策 02 利用者認証 03 攻撃と防御 04 パスワード管理 05 SSHを利用した通信 06 情報漏えい対策 07 ネットワークのセキュリティ対策 08 ログ管理 ■第2章 ハードウェア 01 論理回路 02 A/D変換と割込み 03 浮動小数点数 04 機械語命令 ■第3章 ソフトウェア 01 仮想記憶方式 02 タスク管理 03 コンパイラの機能 04 リスト構造 ■第4章 データベース 01 関係データベースの設計と運用 02 データベースのデータ抽出 03 派生表とビュー表 04 SQL-DDLと制約 05 データベースの運用 ■第5章 ネットワーク 01 セッション管理 02 ネットワークの障害対策 03 無線LANのデータ送信 04 イーサネットを介した通信 05 インターネットプロトコル ■第6章 ソフトウェア設計 01 WebAPI 02 マスタファイルの参照 03 コントロールブレイク処理 04 シーケンス図による設計 05 決定表による設計 ■第7章 マネジメント 01 プロジェクトの時間 プロジェクト管理手法 02 プロジェクトの資源 工数と要員数 03 プロジェクトのリスク リスクの特定と評価 04 プロジェクトの時間 進捗管理 ■第8章 ストラテジ 01 システム戦略 システムの統合 02 システム戦略 在庫量の削減 03 経営戦略・企業と法務 財務諸表の分析 04 経営戦略・企業と法務 業務改善の効果 ■第9章 アルゴリズム 01 文字列検索 02 文字列圧縮 03 意味解析処理 04 配列と文字列探索 05 最短経路の探索 06 配列と関数の処理 07 文字列の照合 08 整列アルゴリズム 09 グラフの最短距離
本書ではリンカとローダの役割を実践を通じて説明し、コア・ダンプの解析やリンカの自作などの実験を行います。目次には、リンカ・スクリプトの利用法や簡易ローダの作成、共有ライブラリの使い方などが含まれています。著者の坂井弘亮は、ネットワーク製品の開発に従事しながら、様々な技術に関する活動を行っています。
この入門書は、初学者や非プログラマー向けにプログラムの動作原理を「実習」と「講義」を通じて解説しています。内容はプログラミングの基本、コンピュータやOSの役割、プログラミング言語の基礎、JavaScriptやC言語の学習、オブジェクト指向モデリングなど多岐にわたります。著者は河村進氏で、実業界や研究機関での豊富な開発経験を持つ専門家です。
この書籍は、プログラミングとセキュリティの基礎を学ぶための改訂版で、64ビット対応です。目次には、デバッガの基本、関連ツールの使い方、プログラムの実行処理の追跡、実践的な処理変更、デバッガ自作、対策、問題、アセンブリ言語の基礎、64ビットアプリケーションの解析、情報セキュリティに関する内容が含まれています。
「C言語スタートブック」の改訂版で、C言語の基礎を学ぶための入門書です。サンプルプログラムや図を刷新し、プログラミングの問題解決を助ける「プログラミングアシスタント」や理解度確認のための「Let's challenge」などの新要素を追加しています。付属CD-ROMには穴埋めプログラムが収録されており、独学に最適です。著者は慶應義塾大学卒業後、大手電機メーカーでソフトウェア開発に従事し、現在は大学でプログラミング教育を行っています。
本書は、リバースエンジニアリングの基礎から応用までを詳しく解説しており、特にソフトウェアに焦点を当てています。内容は、アセンブラやC言語の文法、PEヘッダー、演算ルーチンのリバーシング、アンチリバースエンジニアリング技術、バイナリ作成の高度な手法など多岐にわたります。著者はリバースエンジニアリングやセキュリティに関する豊富な経験を持つ専門家たちです。
基本情報「午後」対策のベストセラーの改訂版! 【こんな方のための本です】 ・試験間際で焦っている人 ・学習時間をなかなか取れない人 ・直前対策・要点整理をしたい人 【本書のポイント】 ・「出る順」で「出るところだけ」掲載。短時間で得点力がグンと上がる。 ・合格するためにテーマを16に厳選。これだけやれば大丈夫! ・前提知識+解き方+過去問題を丁寧に解説。 ・新シラバスに完全対応。 ・今回の改訂により配点増となる「擬似言語」「情報セキュリティ」を手厚く解説。 【本書で「午後」試験を学習するとよい理由】 ・午後試験の合格率は午前試験に比べて低く、午後試験は合格・不合格の分かれ目になる。 →午前試験とは異なる「午後に特化した学習」が必要 ・午後試験の過去問は、午前試験と異なり再出題されることはほぼない。 →過去問だけの学習では非効率。 →過去問の「解き方」にこだわった学習をし、類題を解けるようにしている。 →新しく見える問題にも対応できる力がつく。 ・試験範囲が広く、どこまで学習するか迷う。 →非常に長い期間の過去問を分析し、「出るとこだけ」のテーマ・内容に厳選。 基本情報技術者試験とは 学習法 出る順 分野別傾向分析 本書の構成 長文問題の対策 トピックス|なぜ同じテーマを再出題? 出る順1位 SQL1 結合 内部結合 SELECT こう解く|結合条件式1 こう解く|結合条件式2 左外部結合 右外部結合 集合関数 COUNTとSUMの違い COUNTの種類 こう解く|集合関数の入れ子 日付 MAXを使った表現 GROU PBY こう解く|GROUP BY GROUP BYとDISTINCT GROUP BYと集計結果 HAVING GROUP BYとHAVING こう解く|HAVING こう解く|HAVINGとWHERE 練習問題 出る順2位 SQL2 副問合せ IN ANY =(副問合せ)と=IN(副問合せ) ビュー AND・OR ORDER BY ワイルドカード BETWEEN 練習問題 出る順3位 暗号と認証 公開鍵暗号方式 ハイブリッド暗号 ハッシュ関数 ディジタル署名 ディジタル署名と暗号化 公開鍵基盤 練習問題 出る順4位 文字列処理1 文字列処理 擬似言語 条件式 選択処理 繰返し処理 こう解く|トレース for 配列 関数 見落としがちな文法 こう解く|問題文・プログラム・表の対応付け 練習問題 出る順5位 文字列処理2 比較演算子 こう解く|条件の変換 こう解く|当てはめ法 こう解く|境界値検査 練習問題 出る順6位 文字列処理3 ありえない選択肢 こう解く|無限ループは不正解 こう解く|連続格納は不正解 練習問題 出る順7位 情報セキュリティ対策 ファイアウォール DMZ プロキシサーバ リバースプロキシ その他の情報セキュリティ製品 練習問題 出る順8位 データベース設計 データベース設計 列設計 正規化 こう解く|正規化と整合性 こう解く|正規化の決まり文句 練習問題1 練習問題2 出る順9位 ネットワークセキュリティ プロトコル 電子メールのプロトコル セキュアプロトコル その他のプロトコル 送信側の迷惑メール対策 受信側の迷惑メール対策 メールによる被害への対策 練習問題 出る順10位 スケジュール管理 プロジェクトマネジメント スケジュール管理 こう解く|こせきの式 練習問題1 練習問題2 出る順11位 サイバー攻撃 パスワードクラック パスワードクラックへの対策 スクリプト攻撃 スクリプト攻撃への対策 標的型攻撃 標的型攻撃への対策 その他のサイバー攻撃 練習問題 出る順12位 浮動小数点数 浮動小数点数 正規化 こう解く|仮数と指数を調整する こう解く|ビットに格納する こう解く|ビットから取り出す 練習問題 出る順13位 機械語命令1 機械語 基数変換 機械語命令の構造 図 命令語の形式 表 記号の説明 こう解く|ビット分割 表 実効アドレスの算出方法 こう解く|実効アドレスの算出 表 命令の仕様 こう解く|機械語命令のトレース 練習問題 出る順14位 機械語命令2 機械語命令を実行する手順 機械語命令の種類 練習問題 出る順15位 オブジェクト指向設計 オブジェクト指向 UML クラス図 集約 多重度 こう解く|クラス図の多重度 汎化 練習問題1 練習問題2 出る順16位 決定表 決定表 条件の省略 練習問題
本書は、C言語を学ぶための入門書で、基本事項の学習、具体例を通じた理解、問題解答による確認を組み合わせたステップアップ方式で構成されています。C言語を初めて学ぶ人や挫折した人、さらにスキルを向上させたい人に最適です。目次には、Cの基本、入出力、制御構造、配列、ポインタ、関数、演算子、構造体、データ型、プリプロセッサ、標準ライブラリ、ファイル処理が含まれています。
著者池澤あやかが、プログラミングを学ぶ方法を紹介する書籍を執筆。文系や女子でも楽しめるプログラミングの魅力や学習法、実践的な入り口を提案し、プログラミング的思考を身につける方法を解説している。彼女は女優としてのキャリアを持ちつつ、プログラマとしても注目されている。
「C言語入門書」の改訂版で、シリーズ累計120万部を突破したベストセラーです。著者の柴田望洋が、初心者から経験者まで幅広い読者に向けて、実際のサンプルプログラムと視覚的な図表を用いてC言語の基礎を丁寧に解説しています。内容は、演算、プログラムの流れ、配列、関数、ポインタなど多岐にわたります。
本書は、基本情報技術者試験の午後試験における「アルゴリズム分野」を、文系初学者やプログラム未経験者向けに対話形式で解説しています。アルゴリズムの基本から応用まで、身近な例を用いて理解を深める内容で、擬似言語問題の攻略法や過去問演習も含まれています。また、解説動画やまとめページも充実しており、スキマ時間での学習にも適しています。著者はわかりやすい解説で定評があるコンピュータ系ライターです。
この書籍は、機械語やアセンブリ言語の基礎から応用までを学ぶためのガイドです。リバースエンジニアリングやソフトウェアの脆弱性、プログラミング技術、セキュリティツールの活用法などを紹介し、コンピュータを自在に操る力を養います。著者は、リバースエンジニアリングやマルウェア解析の専門家で、セキュリティ技術の研究を行っています。
この本は、プログラミング教育の重要性を説き、子どもたちに論理的思考や創造力を育む方法を紹介しています。著者は、企業の成功にプログラミングが不可欠であることを強調し、親子で楽しく学ぶ方法やプログラミング教室の現状、基礎を理解させるためのアプローチを提供しています。著者は松林弘治で、技術と教育に関する豊富な経験を持つ専門家です。
本書は、Linuxカーネルのソースコードを理解するためのガイドブックであり、基礎から詳細な機能までを丁寧に解説しています。特に、Linux 2.6を対象に、メモリ管理やプロセススケジューリングの内容が大幅に改訂されています。著者たちは、Linuxやオペレーティングシステムに関する豊富な経験を持つ専門家です。
本書は、C言語入門者が中級者へステップアップするための解説書で、楽しいプログラム作りを通じてプログラム開発能力と応用力を身につけることを目的としています。具体的には、数当てゲームやタイピング練習など118編のサンプルプログラムを提供し、基礎知識を実践的に活用する方法を学びます。著者は福岡工業大学の准教授で、分かりやすいC言語教科書の執筆で評価されています。
この書籍は、現代人にとっての基礎教養としてプログラミングの入門を提供します。難しい数式は不要で、まずは紙と鉛筆を使って学ぶことが推奨されています。目次には、プログラムを身につけるコツ、プログラムの設計方法、コンピュータの機能、実際のプログラミング手法が含まれています。著者は山本貴光で、文筆家やゲーム作家として活動しています。
この書籍は、ハッカーの視点から攻撃手法を分析し、防御方法の本質を理解するためのセキュリティガイドの改訂版です。目次にはプログラミング、脆弱性攻撃、ネットワーク、シェルコード、攻撃と防御の共進化、暗号学などが含まれています。著者はセキュリティの専門家であり、ハッキングやプログラミングに関する豊富な経験を持っています。
著者ポール・グレアムは、成功したソフトウェアベンチャーの背景や、ものづくりのセンス、ビジネスの成功の秘訣を語ります。彼は、ハッカーとクリエイターの共通点や、革新的なアイデアの重要性を強調し、プログラミング言語やデザインの未来についても考察しています。全体を通じて、常識を超えた発想や行動が成功に繋がることを示唆しています。
現在成功している大人で、中学高校でnerd(日本語では「陰キャ」?)じゃなかったと言い切れる人は滅多にいない。実際に私が出会った優秀な方は昔は陰キャだったように思います。今陰キャだからといって、これからも暗い未来が待っているわけではありません。陰キャのときこそ、本質的なやるべきことをやり、それでいてただ耐えるたけでなく自ら行動することで未来を素晴らしいものにできることを教えてくれます。
この文章は、特定の書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は4つの部に分かれており、基本編、関数型プログラミング、言語オブジェクトに対する計算、パフォーマンスについて述べています。著者はそれぞれ異なる専門分野を持ち、教育機関や企業で活躍しています。
本書は、株式会社セガのゲームプログラマが初心者向けに書いたプログラミング入門書です。一般的な入門書が提供しない根本的な考え方を学べる内容で、簡単なゲーム制作を通じてプログラム作成に必要な思考法を身につけることを目的としています。著者はプログラミング未経験者や基礎を再学習したい人々に向けて、具体的な手法を示しています。
この文章は、特定の書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、道具の精神病理学や行為の心理学、知識の理解、デザインの重要性、ビジネスにおけるデザイン思考など、さまざまなテーマが含まれています。著者は、工学やデザイン、認知科学などの分野で専門性を持つ学者たちであり、それぞれの経歴や研究関心についても述べられています。
「スッキリわかる入門シリーズ」の進化改訂版C言語入門書が登場。クラウド学習環境「dokoC」を利用することで、初心者は手軽に学習を始められます。C言語は多くのプログラミング言語の基盤であり、OSや組み込み開発で広く使用されています。本書は、対話形式の解説や豊富な図解を取り入れ、難所を分かりやすく説明。コンピュータの原理にも触れ、初学者がスキルアップできる内容になっています。また、エラー解決の付録もあり、安心して学べます。C言語の基礎を学ぶことで、今後の技術理解にも役立つ一冊です。
『プログラムはなぜ動くのか』の改訂第3版は、プログラムの動作原理をわかりやすく解説し、基礎知識を身につけることを目的としています。内容は新しい製品やツールに更新され、初心者でも理解しやすいように加筆されています。特に、C言語と新たにPythonを用いた機械学習に関する章が追加されており、プログラミングの本質を探求することができます。全体を通して、プログラムの仕組みや環境について詳しく説明されています。
本書は、Cプログラミングを効率的に学ぶために必要な基礎知識を提供します。プログラミングは実際に手を動かして学ぶことが重要ですが、知識が不足していると効率が悪くなります。本書を読むことで、Cプログラミングの理解を深め、学習をスムーズに進める手助けとなるでしょう。目次には、プログラム作成やデータ表現、変数、関数などの基本的な概念が含まれています。著者は倉敷芸術科学大学の教授、村山公保氏です。
この書籍は、Webアプリ開発者向けに脆弱性の原因と対処法を解説したベストセラーの改訂版です。最新のOWASP Top 10 - 2017に対応し、HTML5やJavaScriptに関する新たな解説を追加しています。脆弱性診断の入門章も設けられ、実習環境はWindowsとMac両方に対応しています。著者はWebアプリケーションのセキュリティに関する専門家で、脆弱性診断やコンサルティングを行っています。
この文章は、C言語に関する書籍の目次と著者情報を提供しています。目次には、C言語の基礎からデータ構造やアルゴリズムまでの11章が含まれています。著者は情報工学や電子情報工学の専門家で、東京工科大学に関連する経歴を持つ教授陣です。各著者の学歴や職歴も詳述されています。
著者の庵野拓将は、科学に基づく筋トレ法を解説した本書で、トレーニング法、タンパク質摂取法、睡眠法などを紹介しています。スポーツ科学や医学の研究を基に、効率的かつ正しい筋トレ方法を提案し、健康リスクの回避やパフォーマンス向上を目指します。内容は「新常識」や「筋トレ方程式」、正しいトレーニング方法、タンパク質の摂取法、筋トレの続け方に関する章で構成されています。
この書籍は、累計10万部のベストセラーを改訂したもので、Webサイト制作とHTML・CSSの基本を学ぶ入門書です。架空のカフェ「KUZIRA CAFE」のサイトを作成しながら、最新のHTMLとCSSの技術を身につけることができます。PCとモバイル対応のサイト制作手順を図解で詳しく解説しており、初心者や再学習者に最適です。著者はUIデザイナーの狩野祐東です。
この本は、決算書を単なる数字の羅列ではなく、企業や業界の成長ストーリーとして読み解く方法を紹介しています。著者は、数字が読めないと感じる人々に向けて、実践的な決算分析の技術を提供し、ビジネスの理解を深めることを目的としています。内容は、ECビジネスやFinTech、広告、携帯キャリアなど、さまざまな業界の決算分析事例を通じて、企業の戦略や未来を予測する力を養うものです。読者は、決算を読む習慣を身につけることで、ビジネススキルを向上させることができるとされています。
本書は、初心者向けのプログラミング入門書で、シリーズ累計90万部を突破した改訂版です。Pythonを簡単に始められる「dokopy」という環境を提供し、学習中の疑問にしっかり答えることで理解を深めます。基礎を学びながら、専門分野への応用も可能です。第2版ではデザインが刷新され、実践的なゲーム開発の演習も追加され、コーディング力を鍛えることができます。プログラミングの楽しさを学び、新たな未来を切り開くことを目指します。
この書籍は、ディープラーニングをゼロから実装することで学ぶ入門書です。Python 3を用いて、基礎から誤差逆伝播法や畳み込みニューラルネットワークなどの実装を通じて理解を深めます。また、ハイパーパラメータの設定やBatch Normalization、Dropout、Adamなどの最新技術、さらには自動運転や画像生成などの応用例についても触れています。著者は斎藤康毅氏で、コンピュータビジョンや機械学習の研究開発に従事しています。
ディープラーニングの概要は分かっているし機械学習はある程度理解しているつもりだけど、ディープラーニングの中身はちゃんと理解できていない人にぜひ読んで欲しい書籍。ディープラーニングは一旦これ1冊読んでおけば問題なし。複雑で難しい印象だったディープラーニングがこれを読むだけで一気に身近なものになる。
この書籍は、クライアント/サーバの構築やソケットプログラミングに関する内容を扱っています。第1章から第4章では基本的な構築法を学び、第5章ではソケットの利用方法、第6章ではソケット操作の基本と注意点、第7章ではドメイン名からIPアドレスを取得する方法について解説しています。著者はネットワーキングの教育と研究に携わる専門家です。
この書籍は、JavaScriptを初めて学ぶ人や過去に挫折した人向けに、実践的なサンプルを通じて基礎力を身につけることを目的としています。楽しいサンプルを提供し、初学者がつまずくポイントを丁寧に解説することで、挫折を防ぐ内容になっています。第2版では新しいECMA Scriptの機能を取り入れ、情報を最新のものにアップデートしています。特にWeb業界に興味がある人やフロントエンドエンジニアを目指す人におすすめです。著者はUIデザイナーであり、実務経験を活かした内容が特徴です。
この書籍は、Javaを効果的に学ぶための人気入門書の改訂版であり、シリーズ累計90万部を突破しています。学習者が直面する「なぜ」「どうして」に応える解説が特徴で、特にオブジェクト指向の理解を深めるための具体的なアドバイスやイラストを用いた説明が提供されています。また、プログラミング環境の準備を手軽に行える「dokojava」サービスを利用することで、初心者でもスムーズに学習を進められます。基礎知識や実務に役立つポイントを幅広くカバーし、読みやすいデザインにリニューアルされています。著者は実務経験豊富なプロフェッショナルで、技術を活かした教育に力を入れています。
この本は、優れた組み込みソフトウェアを開発するための手法をサンプルコードと共に解説しています。前半では、制約のある組み込み環境でのテスト駆動開発の基礎を紹介し、後半ではオブジェクト指向のSOLID原則やリファクタリングをC言語に適用する方法を示します。また、レガシーコードへのテスト追加方法も詳しく解説しています。目次には、テスト駆動開発の基本や設計改善に関する内容が含まれています。
本書はRubyプログラミング言語の仕様や実践的な知識を解説した入門書で、豊富なサンプルコードと例題を通じて文法やプログラミングの流れを学べます。2017年に初版が発行され、2020年にはRuby 3.0の新機能に対応した改訂版が登場。初心者向けにわかりやすく説明されており、基礎からプロの技術まで幅広くカバーしています。著者は伊藤淳一氏で、プログラミング教育にも力を入れています。
この書籍は、初めてAndroidアプリを作成する人向けに、Android Studioの使い方やKotlinの基本を丁寧に解説しています。開発環境は最新のAndroid Studio 4.xに対応しており、さまざまなサンプルアプリを通じてアプリ開発の流れを楽しく学べる内容になっています。目次には、開発環境の準備から、具体的なアプリ作成の手順が詳述されています。著者はモバイルアプリのエンジニアで、IoT開発にも力を入れています。
この文章は、書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、ソフトウェアエンジニアリングやシステムデザインに関する様々なテーマが列挙されており、著者は滝沢徹、牧野祐子、富澤昇の3名で、それぞれの学歴と現在の職業が記載されています。
『オブジェクト指向でなぜつくるのか』の改訂第3版は、オブジェクト指向プログラミング(OOP)の基本と最新動向をわかりやすく解説しています。著者は、OOPの全体像、プログラミング言語の歴史、アジャイル開発手法などについて触れ、特に人気のある言語(Java、Python、Ruby、JavaScript)の情報も更新されています。読者は、OOPがソフトウェア開発においてどのように役立つかを学び、実践的な知識を得ることができます。
この文章は、書籍の目次と著者情報を紹介しています。書籍は三部構成で、第一部ではアルゴリズムやプログラムの構造について、第二部ではパフォーマンスやアルゴリズムデザインのテクニックについて、第三部では具体的な問題解決の作品を扱っています。著者の小林健一郎は東京大学で物理学を学び、情報科学を専門とする教授です。
本書は、プログラムの洗練に必要な判断を学ぶためのケーススタディを提供しています。内容はクリーンコード、意味のある名前、関数、コメント、書式化、オブジェクトとデータ構造、エラー処理、境界、単体テスト、クラス、システム、創発、同時並行性、継続的改良、JUnitの内部、リファクタリング、経験則など多岐にわたります。プログラミングは動作するだけでは完結せず、質の向上が重要であることを強調しています。
本書『Zero Bugs and Program Faster』は、高品質なコードを書くための具体的なレッスンを78の物語として提示しています。著者は、正確な仕様があればバグのないコードを書くことが可能だと主張し、ソフトウェア工学の広範な知見をカバーしています。内容は気軽に読めるコラム形式で、高い品質と生産性を目指す理由やエンジニアとしての心構えを扱っています。多様なプログラミング言語やドメインのソースコードを例に、バグを減らすための技術や習慣が解説されています。
「アセンブラ」に関するよくある質問
Q. 「アセンブラ」の本を選ぶポイントは?
A. 「アセンブラ」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「アセンブラ」本は?
A. 当サイトのランキングでは『アセンブリ言語の教科書: Kenji’s homepage』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで96冊の中から厳選しています。
Q. 「アセンブラ」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「アセンブラ」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。









































![『情報処理教科書 出るとこだけ! 基本情報技術者[午後]第2版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ru-o8S5iL._SL500_.jpg)
![『[試して理解]Linuxのしくみ ~実験と図解で学ぶOSとハードウェアの基礎知識』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51r+eNsY2fL._SL500_.jpg)





![『うかる! 基本情報技術者 [午後・アルゴリズム編] 2022年版 福嶋先生の集中ゼミ』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/518uVuO7yAL._SL500_.jpg)




















![『Cプログラミング入門以前 [第3版] (Compass Programming)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41l9vbvbLNL._SL500_.jpg)


















![『プロを目指す人のためのRuby入門[改訂2版] 言語仕様からテスト駆動開発・デバッグ技法まで (Software Design plus)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41LHdQuWVcL._SL500_.jpg)