【2025年】「ict教育」のおすすめ 本 57選!人気ランキング
- 逆引き版 ICT活用授業ハンドブック
- ICT主任になったら読む本 実務がうまくいく心構え&仕事術35
- [改訂第4版]基礎からわかる情報リテラシー
- 学校でつかいこなすICT (考えよう! 話しあおう! これからの情報モラル 4)
- 個別最適な学びを実現するICTの使い方
- よくわかる教育心理学[第2版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)
- 学びの質を高める! ICTで変える国語授業3 Google Workspace for Education編
- 基礎からのIT担当者リテラシー
- リーダブルコード ―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック (Theory in practice)
- 情報時代の学校をデザインする: 学習者中心の教育に変える6つのアイデア
この書籍は、GIGAスクール構想に基づき、1人1台端末の活用方法を101のアイデアで紹介しています。授業でのアプリ活用を「導入」「情報収集」「整理・分析」「意見交流・共有」「まとめ」「振り返り」「評価」の7つの場面に分類し、具体的なアプリの使用例を提供しています。また、学校生活や校務におけるアプリ活用のアイデアも掲載されています。著者は教育現場で活躍する専門家たちで構成されています。
本書は、特定のソフトの使い方に依存せず、基本的なスキルを学ぶことを目的としたマニュアルです。改訂第4版では、クラウドやオンライン会議に関する内容を追加し、Pythonによるデータサイエンスの基礎も学べるように改訂されています。著者は三重大学の名誉教授と講師です。
「機器のあつかい方」から「伝わるプレゼン」まで、まんがの例を通して解説。学校の授業で、上手にICTを活用できるようになろう。 「機器のあつかい方」から「伝わるプレゼン」まで、まんがの例を通して解説。学校の授業で、上手にICTを活用できるようになろう。 まんがや実例を通して、情報モラル・メディアリテラシーを考えるシリーズです。スマホやタブレットが身近になった今、子どもたちは情報技術に関して正しい理解と知識を持ち、そのうえで自分で考え判断する力・情報技術を活用する力を養うことが必要です。そのときに欠かせないのが情報モラルです。 この巻では、学校の授業でタブレットなどのICT機器を活用するために、5つのテーマについて知っておくべきことを解説します。 1 機器のあつかい方 2 クラスチャットでのトラブル 3 上手な写真の撮り方 4 伝わるプレゼンの方法 5 インターネットでの情報発信 また、特別編として、 ・インターネットでのトラブルについて相談できる窓口一覧 ・授業でつかえるICT用語辞典 を特集しています。 巻末では「情報学習の最前線」として、実際に行った小学校での授業のようすを紹介します。 1時間目 タブレット、こわしちゃった!/タブレットやノートパソコンをこわさないために 2時間目 授業中のチャットでトラブル?/チャットを気持ちよくつかうために 3時間目 上手に写真を撮りたい!/伝えたいことがわかりやすい写真を撮るために 4時間目 そのプレゼン、伝わる?/伝わるプレゼンにするために 5時間目 インターネットで発信する?/積極的に発信するために 放課後特集1 つらい気持ち……相談したい/いじめにあってしまったら……/相談は、自分の心や命を守る第一歩 放課後特集2 授業でつかえるICT用語辞典 情報学習の最前線 キャッシュレス決済を体験しよう
本書は、子どもが学び適応する過程を理解し、支援に必要な知識を提供する内容です。学びの意欲や仕組み、個別の支援方法、社会性の学びについて解説しており、教育現場で実践的に活用できる情報を提供しています。旧版の修正に加え、新しい項目も追加され、変化する教育環境に対応した改訂版です。著者は中澤潤氏で、千葉大学の名誉教授です。
本書は、企業のIT担当者が必要とする基礎知識を解説しています。内容は、パソコンや周辺機器の調達、社内インフラの整備、情報セキュリティの強化、業務システムの導入、システム開発の外部委託に関する5章から構成されています。各章では、専門的な知識が求められるテーマを取り上げ、IT業務に携わる初心者向けに必要最低限の情報を提供しています。著者は、豊富な経験を持つエンジニアたちです。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
教育現場での取組の中から教育のパラダイム転換を起こす原則や方法を紡ぎ出し,変化への反発や混乱,葛藤を乗り越える術を提案。 工業化から情報化への移行に合わせた教育の変化の必要性は,くり返し叫ばれてきた課題である。本書では,インストラクショナルデザインの第一人者である著者が,教育現場での取組の中からパラダイム転換を起こす原則や方法を紡ぎ出し,変化に対する混乱や葛藤を乗り越える術を提案。ピーター・センゲらの諸理論も付録に収録。 はじめに(日本語版への序) 謝辞 1 本質的な変化のために 少数のニーズに応えること すべてのニーズに応えること 時代遅れのビジネスニーズのために生徒たちが準備すること 情報時代の本質を探る 変わりゆく生徒の教育ニーズ この章の要約 2 情報時代の教育ビジョン コア・アイデア1:到達ベースのシステム コア・アイデア2:学習者中心の指導 コア・アイデア3:広がりのあるカリキュラム コア・アイデア4:新たな役割 コア・アイデア5:調和ある人格を育む学校文化 コア・アイデア6:組織構造とインセンティブ 構造的な変化 費用対効果 この章の要約 3 新しいパラダイムの具体例 ミネソタ・ニュー・カントリー・スクール(エデュビジョンズ) チュガッチ学区 モンテッソーリ教育のシステム その他の情報時代における学校システム この章の要約 4 どうやって変えていくのか? パラダイム転換を促す方略 パラダイム転換を引き起こす原則 残された課題 この章の要約 5 政府にできることは何か テクノロジ・ツール開発の支援 好事例を生み出す支援 パラダイム転換を促す力をつける パラダイム転換に関する知識をつける 連邦政府の戦略 さいごに この章の要約 付録A 情報時代のパラダイムへと進化している学校 付録B パラダイム転換に時間がかかった場合,どうなりますか? 付録C パラダイム転換へのツール集 センゲの氷山モデル センゲの「推論のはしご」 センゲのシステム思考に関する11の典型的パターン バナシーのシステムが持つ3つの側面 アコフの変化のための4つの方針 ライゲルースのカオス理論によるフラクタル ダフィーのパラダイム転換への3つの道のり 文献 索引 著者について 訳者あとがき 翻訳者からのメッセージ
テクノロジを活用した学習がもたらす「新たな力」と,学校教育とをどううまく統合していけばよいのか。先行する米国からの発信。 テクノロジを活用した学習がもたらす「新たな力」と,学校教育とをどう統合していけばよいのか。認知科学系の学習論を背景にした上で,教育を学校外に持ち出そうとするテクノロジの視座から,未来の学びのかたちを考える。 先行する米国からの発信。 学校教育改革,ICT活用,生涯学習など, 今後の日本の教育を再考するために! テクノロジを活用した学習がもたらす「新たな力」と,学校教育が担ってきた「欠かすことの出来ない貢献」とを,どううまく統合していけばよいのか。この避けられない課題に正面から切り込む。認知科学系の学習論を背景にした上で,教育を学校外に持ち出そうとするテクノロジという視座から,未来の学びのかたちを考える。 ◆訳者一覧 稲垣 忠 (東北学院大学教養学部) 序論,1章,10章 亀井美穂子(椙山女学園大学文化情報学部)2章,3章,10章 小川真理子(椙山女学園大学文化情報学部)2章,3章 林 向達 (徳島文理大学) 4章,8章,10章 金子大輔 (北星学園大学経済学部) 5章 益川弘如 (静岡大学大学院教育学研究科)6章,10章 藤谷 哲 (目白大学人間学部) 7章 深見俊崇 (島根大学教育学部) 9章,10章 1章 どのように教育は変わろうとしているのか 1 本書の構成 2章 テクノロジ推進派の意見 1 変化する世界 2 学習者を教育する能力の拡張 3 推進派の考える学校ビジョン 3章 テクノロジ懐疑派の意見 1 硬直化はなぜ起こるか? 2 なぜ教育改革は失敗するのか 3 学校におけるテクノロジ活用をはばむもの 4 まとめ:学校とテクノロジの矛盾 5 テクノロジ懐疑派の考える学校ビジョン 4章 アメリカにおける学校教育の発達 1 徒弟制から公教育制度へ 2 アメリカにおける公教育制度の確立 3 学校制度の進化 4 学校に対する要求はどのように変わったか 5 革命のサイクル 5章 新しい教育制度の芽ばえ 1 ホームスクーリング 2 職場での学習 3 遠隔教育 4 成人教育 5 ラーニングセンター 6 教育向けのテレビやビデオ 7 コンピュータを用いた学習用ソフト 8 技能資格 9 インターネットカフェ 10 生涯学び続けること 6章 教育における3つの時代の変化 1 責任:保護者から国家へ そして学習者自身や保護者へ 2 期待:社会的再生産から全員の成功へ そして個人の選択へ 3 内容:実用的スキルから学問的知識へ そして学び方の学習へ 4 方法:徒弟制から講義形式へ そして相互作用へ 5 評価:観察からペーパーテストへ そして状況に埋め込まれた評価へ 6 場所:家庭から学校へ そしてどんな場所でもへ 7 文化:大人文化から仲間文化へ そして年齢ミックス文化へ 8 関係性:個人的結びつきから権威者へ そしてコンピュータを介した相互作用へ 9 教育における重要な変化 7章 失われるもの,得られるもの 1 失われると思われること 2 得られると思われること 3 希望を実現しながら,危険を軽減する 8章 学校はどうすれば新たなテクノロジとつきあえるのか 1 パフォーマンスに基づく評価 2 新しいカリキュラム・デザイン 3 デジタル世界における公平さへの新しいアプローチ 9章 結局,何がいいたいのか? 1 子どもたちは,テクノロジから何を学んでいるか? 2 テクノロジは,子どもたちの「社会生活と学び」をどのように変えてきたのか? 3 私たちをどこに導こうとしているのか? 10章 テクノロジ世界のなかで教育を再考する 1 学ぶことの再考 2 モチベーションの再考 3 学ぶべきことの再考 4 キャリアの再考 5 学びと仕事の間での移行の再考 6 教育のリーダーシップの再考 7 教育における政府の役割の再考 8 私たちの将来ビジョン 座談会 テクノロジを日本の教育に生かすために
この書籍は、デジタル・リテラシーを向上させるための情報を提供するロングセラーの最新版です。ITの基本から最新トレンドまで幅広く解説し、特にデジタル化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性を強調しています。内容にはクラウドコンピューティング、AI、IoT、サイバーセキュリティなどのトピックが含まれ、ビジネスにおけるデジタル技術の活用法が示されています。また、特典として図版のPowerPointデータや専門用語解説のPDFが提供され、就活生や社会人に役立つ内容となっています。著者はネットコマース株式会社の代表で、IT業界における豊富な経験を持っています。
このテキストは、教育心理学の基本理論や知見を現場の実践に活用する方法をわかりやすく解説したもので、学校教育だけでなく社会や家庭での教育活動にも応用可能です。最新版では、「教職課程コアカリキュラム」に対応し、学級集団づくりや学習評価、運動発達に関する新しい章やコラムが追加されています。著者は法政大学の藤田哲也教授です。
この書籍では、日本の経済停滞とコロナ禍の影響を受け、「未来の教室」事業への期待とその成否が検証されます。また、労働の多くがロボットに代替される未来において、教育の役割が重要になる中、各国の政策対応や学びのイノベーションの推進についても論じられています。著者の佐藤学は、豊富なデータを基に学校改革の展望を示しています。
この書籍は教育心理学の基本を解説したロングセラーの第5版で、最新の統計データやいじめ問題、発達障害に関する記述が加わっています。内容は、記憶力、学び、やる気、評価方法、発達についての考察など多岐にわたり、教育や心理学に関心のある人々に向けてわかりやすくまとめられています。著者は鎌原雅彦と竹綱誠一郎で、共に教育学の博士号を持つ教授です。
話題の「まんがで知る教師の学び」に続く新シリーズスタート! 教育書の枠を超え、未来に向かって生きる全ての日本人が少なからず抱く問題意識をあらためて掘り起こし、投げかけます。 いまこの国で行われつつある「教育改革」が目指すものとは何か? 受験と部活動に明け暮れる中学校と時代に取り残される地域社会。 働き方も生き方も新たな局面を迎えたいま、学校と社会全体が向かうべき方向とは――。 教師(元小学校教頭)である著者が実感を込めて描くリアル・ストーリーです。 1分で読める! 水先案内的コラム「未来の社会を考えるビジネス書」では課題解決のための参考図書を紹介。 第1章 部活動と教育課程――教育課程とは何か 第2章 学習指導要領――社会に開かれた教育課程 第3章 新しい時代に求められる資質・能力――学習の基盤となる資質・能力 第4章 社会の変化――学び続ける力 第5章 学ぶ意義の明確化――なぜ学び、どういった力が身に付くのか 第6章 学習者の視点――教える側から学習する側へ 第7章 学習評価の充実――相互評価と自己評価 第8章 問題発見・解決能力――持続可能な社会づくりの担い手を育む
このテキストは、教職課程の「教育心理学」に関する内容を扱っており、文科省のコアカリキュラムに基づいて「発達」と「学習」に焦点を当てています。イラストや図表を多用し、初学者にも理解しやすく構成されており、各章には事例も含まれています。教職採用試験の対策にも適した内容で、教育心理学、発達理論、学習理論、記憶、動機づけ、教育評価、特別支援教育など幅広いテーマが網羅されています。著者は日本体育大学の教授陣です。
この書籍は、IT業界に関する基本的な知識を図解でわかりやすく解説し、関連するキーワードも紹介しています。内容は、業界の常識、業務の常識、最新の技術トレンドに分かれており、知識ゼロからでも理解できるように構成されています。また、Web連動で最新情報も提供されています。
この書籍は、教育心理学の基礎知識と最新理論を子どもの理解と成長支援に焦点を当てて解説しています。学校での子どもの行動や教師の指導法を心理学的に考察し、理論と実践を結びつける内容です。各章の最後には実践的な視点からの留意点や課題が示されており、章末には演習問題も用意されています。著者は筑波大学名誉教授の櫻井茂男と福井県立大学教授の黒田祐二です。
授業のつくり方をインストラクショナルデザインの考え方にならって詳説。アクティブラーニングやコアカリキュラム対応テキスト。 授業のつくり方をインストラクショナルデザインの考え方にならい詳説。学習指導案を実際に作成・実践・振り返りができる。アクティブラーニングや教職課程コアカリキュラムにも対応した高精度設計のテキスト。 授業のつくり方をインストラクショナルデザインの考え方にならって詳説。学習指導案を実際につくり,実践し,振り返りができるように各章を配列した。章末問題でポイントを再確認でき,巻末の付録は本書ウェブサイトからも入手可能。アクティブラーニングや教職課程コアカリキュラムにも対応した高精度設計のテキスト。 まえがき 本書の使い方 第1章 ガイダンス(1):これからの子どもたちに育みたい資質・能力 1.1 学校で子どもたちは何を学習するのか 1.2 「学力」の定義を探る 1.3 これからの世界を生きるために 1.4 家を建てるように 第2章 ガイダンス(2):教師に求められる授業力とは 2.1 教師に求められる資質・能力 2.2 授業を実践するために必要な知識 2.3 省察的実践家としての教師 2.4 教師として学び続けるために 第3章 設計の基礎(1):授業をつくるということ 3.1 授業ができるまで 3.2 授業の基本形 3.3 主体的・対話的で深い学びに向けて 第4章 設計の基礎(2):評価をデザインする 4.1 評価を行う意味 4.2 目標と評価と指導の関係 4.3 学習目標を5 種類に分けてとらえる 4.4 学習目標に応じた評価の方法 第5章 設計の基礎(3):学習環境をデザインする 5.1 「学習環境」とは何か 5.2 学びの空間をデザインする 5.3 チームで学びを支援する 5.4 学習環境を活用する授業づくり 第6章 実践の基礎(1):授業を支える指導技術(教師編) 6.1 教室の中の教師 6.2 教師の立ち振る舞い 6.3 発問・指示・説明 6.4 黒板・資料の提示 第7章 実践の基礎(2):学びを引き出す指導技術(児童・生徒編) 7.1 仲間と学び合う学級・一人ひとりが学ぶ学級 7.2 子どもとの関わり 7.3 学び合う集団をつくる 第8章 設計の実際(1):学習目標の設定 8.1 学習指導案の構成 8.2 授業前の子どもの姿を把握する 8.3 学習目標を明確にする 8.4 学習目標と資質・能力の関係 8.5 学習目標と学習課題 第9章 設計の実際(2):深い学びを導く教材研究 9.1 深い学びと浅い学び 9.2 教科書・教材の役割 9.3 課題分析の進め方 9.4 入口と出口をつなぐ 第10章 設計の実際(3):主体的・対話的な学習過程 10.1 単元をどのように組み立てるか 10.2 対話的な学習活動 10.3 主体的な学習活動 10.4 探究と主体的・対話的な学習アプローチ 第11章 設計の実際(4):学びが見える評価方法 11.1 学びの質を問う評価 11.2 何のためにいつ評価するのか 11.3 学習者による評価 11.4 学びの質を言語化する 11.5 長期的な取り組みを評価する 第12章 情報化への対応(1):授業の魅力・効果・効率を高めるICT 12.1 なぜICT を活用するのか 12.2 ICT を活用した指導方法 12.3 ICT が支援するコミュニケーション 12.4 思考を深めるICT の活用 第13章 情報化への対応(2):情報活用能力を育てる 13.1 技術の発達と社会の変化 13.2 情報活用能力をいつ育てるのか 13.3 情報活用能力の構成要素 13.4 探究する単元の設計と情報活用能力 13.5 情報モラルの指導 13.6 情報社会で学び続けるために 第14章 情報化への対応(3):これからの学習環境とテクノロジの役割 14.1 学びの道具としてのテクノロジ 14.2 授業と授業をつなぐ 14.3 一人ひとりの学びを支える 14.4 学校外の学びの変化 14.5 学校・教師の役割は何か 第15章 授業の実施:模擬授業・研究授業の実施と改善 15.1 模擬授業・研究授業を実施する 15.2 模擬授業・研究授業を記録・分析する 15.3 授業を振り返る 15.4 おわりに 付 録 「教育の方法と技術」シラバス例 学習指導案テンプレート 引用文献 索 引
この本は、著者の宮澤悠維が10年間の教師経験を基に学級経営のエッセンスをまとめたもので、150の基本的な心得を紹介しています。学級経営に悩む教師たちに向けて、心構え、原則、技法の三つの視点から実践的なアドバイスを提供し、何度でも読み返すことで学び直せる内容となっています。著者は、学級満足度を高めるためのノウハウを広めることを目指しています。
子どもたちの小さな日常に注目したEPISODEなど,学ぶ意欲を引き出し考えさせる工夫が豊富で理解を深めやすい入門書です 【QUESTION】や【EPISODE】を手がかりに,子どもたちの小さな日常から学びを深める入門書。章末には教師やSCなどがよくであう困難事例/指導場面/判断に迷う場面の【EPISODE】と検討課題が示され,理解確認とさらなる学びを促します。 序章 エピソードに学ぶ──困難な時代の子どもの学びと育ちの豊かさ Ⅰ部 子どもの育ち──発達を理解する 1章 思考の育ち──認知発達 2章 喜怒哀楽の育ち──情動発達 3章「わたし」の育ち──社会化と自己の発達 Ⅱ部 学校で育つ子ども──学びの過程を理解する 4章 学びの基礎──学習,記憶,メタ認知 5章 やる気がでるとき,でないとき──動機づけ 6章 教え方,学び方──学習指導 7章 学びの捉え方──教育評価 Ⅲ部 教室づくり,仲間づくり──学びあう場を支える 8章 仲間との学びあい──協同学習 9章 仲間との関係──適応,社会的学習,ソーシャルスキル 10章 学びと育ちを支える教室──教師─子ども関係,学級風土・学校文化 Ⅳ部 みんなのための学校──個に寄りそい,育ちあう 11章 子どもの困難の理解と支援──学校カウンセリング 12章 個のニーズに応じた学び──特別支援教育
教育改善を志向する実践者と研究者の協力関係の中で,実践と理論を架橋して行われるプロジェクト。成果の生かし方までガイドする。 インストラクショナルデザインとの相性もよく,学習科学の代表的研究法である「デザイン研究」。教育改善を志向する実践者と研究者の協力関係の中で,実践と理論を架橋して行われるプロジェクト。成果の生かし方までガイド。 インストラクショナルデザインとの相性もよく,学習科学の代表的研究法である「デザイン研究」。教育改善を志向する実践者と研究者の協力関係の中で,実践と理論を架橋して行われるプロジェクトである。現場での問題を実際に解決するだけでなく,実践-研究を共有する中で両者の「専門性の開発」まで見通す実施ガイド。 日本語版に寄せて 教育デザイン研究をやってみよう 謝辞 はじめに 第Ⅰ部 基 礎 第1章 教育デザイン研究について 教育デザイン研究への動機とその起源 教育デザイン研究の特徴 教育デザイン研究の主要なアウトプット 3つの方向性の豊富なバリエーション 教育デザイン研究と他の関連するジャンル 第2章 理論と実践への貢献:概念と事例 教育デザイン研究の理論的貢献 教育デザイン研究の実践的貢献 教育デザイン研究の例 第3章 教育デザイン研究の一般モデルを目指して インストラクショナルデザインからの教訓 カリキュラム開発からの教訓 既存のデザイン研究モデルからの教訓 デザイン研究のための一般モデル 第Ⅱ部 コアプロセス 第4章 分析と探索 主な活動とアウトプット 分析的視点と創造的視点 分析と探索への準備 分析 探索 このフェーズからの成果物 分析と探索の例と記録文書評価ツール 第5章 デザインと構築 主な活動とアウトプット 分析的視点と創造的視点 デザインと構築の準備を整える デザイン 構築 このフェーズからの成果物 デザインと構築の例と記録文書評価ツール 第6章 評価と省察 主な活動とアウトプット 分析的視点と創造的視点 評価と省察の準備を整える 評価 省察 このフェーズからの成果物 評価と省察の例と記録文書評価ツール 第7章 実装と普及 実装と普及への準備 実装 普及 実装と普及の決定要因 実装と普及の例と記録文書評価ツール 第Ⅲ部 次に向けて 第8章 教育デザイン研究の提案書を書く 研究提案書の目的と機能 最初に没入し,次に書く 研究の位置づけ 教育デザイン研究提案書作成のガイドライン 教育デザイン研究提案書の評価ツール 第9章 教育デザイン研究を報告する 教育デザイン研究の報告に共通する懸念 さまざまな立場の理解 執筆に向けての推奨事項 第10章 過去を振り返り,未来を見据える 本書のこれまでを振り返る 未来を見据えて:教育デザイン研究の未来 関連文献と資料 引用文献 人名索引 事項索引 監訳者あとがき
このテキストは、教育心理学に関する包括的な教材で、大学や短大の教職課程、教職を目指す学生、既に教職にある人の学び直しに適しています。2017年に改訂され、法律や指導要領の変化に対応し、演習問題を充実させています。内容は、教育心理学の基本から発達、学習メカニズム、授業の心理学、教育評価、知的能力、パーソナリティ、社会性、学級の心理学、不適応、特別支援教育に関する章で構成されています。付録には演習問題の解答や重要用語の解説も含まれています。
この書籍は、教育心理学の基礎理論とその実践への応用を学ぶためのテキストシリーズの第2巻です。簡潔な解説に加え、ディスカッション課題や演習課題、資料図版が豊富に掲載されており、学生が自ら考えることを促します。また、教員採用試験対策にも対応しています。著者は京都教育大学と関西外国語大学の教授で、心理学と人間科学の博士号を持っています。
AIが教育にもたらす影響を,カリキュラム設計と実際の利活用法の2点から解説。新学習指導要領がめざす方向性を深く理解できる。 AIが教育にもたらす影響を,カリキュラム設計と実際の利活用法の2点から解説する。新学習指導要領がめざす方向性を深く理解できる。OECDの教育に関する委員会の元議長で世界的なリーダーのファデル氏らによる提案。 人工知能の発展は教育にどのような影響をもたらすのか。第1部では生徒が「何を」学ぶべきかという視点から,「コア概念」の重要性を提案。第2部では「どのように」教えるのかという視点で教育AIの多様な活用例を紹介し,今後の可能性や倫理的問題も詳しく論じる。新学習指導要領がめざす方向性を理解するのにも最適。 【本書の主な目次】 ●第1部 生徒は何を学ぶべきか?:AIがカリキュラムに与える影響 1 教育の目的 2 基礎となる知識:生徒は何を学ぶ必要があるか? 3 コア概念の概要 4 必須のコンテンツの概要 5 意味づけとAIアルゴリズムの影響 6 コア概念 7 必須のコンテンツ 8 どのコンテンツを追加すべきか 9 どのコンテンツを削除すべきか 10 実際上の考慮事項 11 結論 ●第2部 どのように?:指導と学習にAIがもたらす可能性と影響 1 教育におけるAI 2 AIの背景 3 AIの技術と用語 4 AIは教育でどのように機能するか ― 教育におけるAIの活用 ― 5 知的学習支援システム 6 対話型学習支援システム 7 探索型学習環境 8 自動ライティング評価 9 他にどのようなAIEDがあるのか? 10 他にできることは何か? 11 教育におけるAI:暫定的なまとめ 目次 編訳者はしがき "Artificial Intelligence in Education(教育AIが変える21世紀の学び)"への賛辞 謝辞 はじめに―背景 第1部 生徒は何を学ぶべきか?:AIがカリキュラムに与える影響 1 教育の目的 2 基礎となる知識:生徒は何を学ぶ必要があるか? 3 コア概念の概要 4 必須のコンテンツの概要 5 意味づけとAIアルゴリズムの影響 5.1雇用可能性 5.2拡張知能 5.3教育への示唆と生徒が学ぶべきこと 5.4 意味の重要性 5.5 直観 5.6 有意義さ:知識を動員する 5.7 概念の道具箱をつくる 5.8 転移:学習した知識を新しい状況で使う 5.9 意味の領域 5.10 問題のある知識 5.11 最適化 6 コア概念 6.1 最も重要なことは何か? 6.2 「知っている」と「できる」 6.3 重要な知識枠組み 6.4 ツールとしての概念指標 6.5 構造のレベル 6.6 概念によるコンテンツの体系化 6.7 コンテンツの構造 7 必須のコンテンツ 7.1 何でも検索できるなら,なぜ何でも学ぶのか? 7.2 ダニング=クルーガー効果を避ける 7.3 日常生活で使うスピード,流暢さ,自動性 7.4 社会的に共有された背景知識 7.5 より複雑な概念に必要である 7.6 コア概念の基質となるコンテンツ 7.7 コンピテンシーの基質となる知識 7.8 現代的な知識 8 どのコンテンツを追加すべきか 8.1 テクノロジーとエンジニアリング 8.2 メディア 8.3 企業家精神とビジネス 8.4 個人ファイナンス 8.5 ウェルネス 8.6 社会科学 9 どのコンテンツを削除すべきか 9.1 学問分野によらない構造 9.2 カリキュラムの設計に学際的テーマを組み込む 9.3 学問分野の変化 10 実際上の考慮事項 10.1 意思決定 11 結論 第2部 どのように?:指導と学習にAIがもたらす可能性と影響 1 教育におけるAI 2 AIの背景 3 AIの技術と用語 3.1 アルゴリズム 3.2 機械学習 3.3 教師あり学習 3.4 教師なし学習 3.5 強化学習 3.6 人工ニューラルネットワーク 4 AIは教育でどのように機能するか 4.1 教育におけるAIの歴史 4.2 適応学習 4.3 コンピュータ支援教育 4.4 AIとCAI ― 教育におけるAIの活用 ― 5 知的学習支援システム 5.1 領域モデル 5.2 指導モデル 5.3 学習者モデル 5.4 典型的なITSのアーキテクチャ 5.5 ITSの効果を評価する 5.6 Mathia 5.7 Assistments 5.8 alta 5.9 さらなる例 6 対話型学習支援システム 6.1 CIRCSIM 6.2 Auto Tutor 6.3 Watson Tutor 7 探索型学習環境 7.1 Fractions Lab 7.2 Betty’s Brain 7.3 Crystal Island 7.4 ECHOES 7.5 まとめ 8 自動ライティング評価 8.1 PEG 8.2 Intelligent Essay Assessor 8.3 WriteToLearn 8.4 e-Rater 8.5 Revision Assistant 8.6 OpenEssayist 8.7 AIによる採点 9 他にどのようなAIEDがあるのか? 9.1 ITSプラス:ALT School,ALP,Lumilo 9.2 言語学習:BabbelとDuolingo 9.3 チャットボット:Ada とFreudbot 9.4拡張現実と仮想現実 9.5 学習ネットワーク編成器:Third Space Learning とSmart Learning Partner 10 他にできることは何か? 10.1 協働学習 10.2 生徒フォーラムのモニタリング 10.3 継続的な評価 10.4 AIによる学習コンパニオン 10.5 AIティーチングアシスタント 10.6 学習科学を発展させる研究ツールとしてのAIED 11 教育におけるAI:暫定的なまとめ 12 教育におけるAIの社会的影響 12.1 AIEDテクノロジーが教室に与える影響 12.2 AIEDの倫理 補足1 A1-1 トピックと概念のつながり A1-2 コンテンツの進化 A1-3 分野横断的なテーマ 補足2 A2-1 AIとは何か? A2-2 今日のAI A2-3 AIの技術 A2-4 AIの技術と専門用語 CCRについて 教育のスタンダードを再設計する 当センターの基本理念 「何を」にフォーカスする 当センターの業務 著者について 付論:人工知能と教育人材の養成 はじめに なぜ教育人材の育成なのか 教育人材育成のストラテジー 教育人材は「生身の人間」である必要があるのか 索引
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづける永遠の名著!技術があれば授業がうまくなり、子供たちは学校が好きになる。 第1章 授業の原則(趣意説明の原則 一時一事の原則 ほか) 第2章 教師の技量(子供に好かれる教師 子供が教わりたい教師 ほか) 第3章 授業の腕を上げる法則(根拠をもって実態をつかめ 教師の技量を向上させる常識的方法 ほか) 第4章 新しい教育文化の創造(「授業分析・授業解説」の力を付ける 教師の共通問題への挑戦 ほか)
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづけるスーパー名著!新卒の教師でもすぐに子供を動かせるようになる「法則」。 第1章 子供を動かす原理原則編(子供を動かす法則(群れとして動かす場合)-一つの法則と五つの補則 子供を動かす原則(組織として動かす場合)-三つの原則と九つの技能 新卒教師の教室は、なぜ混乱するか 「いじめ」の構造を、まず破壊せよ! 「プロの目」は、修業によって培われる 存在感が実感できてこそ子供は動く) 第2章 子供を動かす実践編(厳しく「教える」だけが動かす方法ではない 朝会に全校児童を集合させる 応援団の子供たちを動かす 指導方法を工夫して子供を動かす やるべきことを一人一人に示せ-卒業式よびかけの練習)
この文章は、心理学と教育に関する内容を15の章に分けて紹介しています。各章では、心理学の基本概念、発達段階、言語や社会性の発達、学習理論、動機づけ、記憶のメカニズム、問題解決、学校内の人間関係、教育評価、学校適応などについて解説しています。著者は杉村伸一郎と三宅英典で、いずれも大学教授です。
教育分野における公認心理師の活動のために 基礎から臨床まで心理学を基盤とした支援を学ぶ 教育・学校心理学の入門書 公認心理師は「チーム学校」の担い手として,子ども,教師,保護者と支え合いながら,スクールカウンセリング業務や学校・家庭・地域連携のキーパーソンとしての活動を通して,子どもの心の健康や学校生活の質を維持向上させることが期待される。教育分野で公認心理師として活動するための必須の知識を学ぶ1冊。 2022年の生徒指導提要の改訂を反映させた第3版です。 第1部 基礎編:教育・学校心理学の理論を学ぶ 第1章 教育・学校心理学の意義 石隈利紀 第2章 子どもの発達課題への取り組みの理解と援助 松本真理子 第3章 子どもの教育課題への取り組みの援助 増田健太郎 第4章 スクールカウンセリングの枠組み――何を援助するか 大河原美以 第5章 子どもの多様な援助者によるチーム援助 田村節子 第6章 3段階の心理教育的援助サービス――すべての子ども,苦戦している子ども,特別な援助ニーズを要する子ども 水野治久 第2部 実践編:子どもと学校を援助する 第7章 発達障害の理解と援助 小野純平 第8章 不登校の理解と援助 本間友巳 第9章 いじめの理解と援助 濱口佳和 第10章 非行の理解と非行をする子どもの援助 押切久遠 第11章 学校における危機対応 窪田由紀 第12章 学級づくりの援助――スクールカウンセラーの役割を中心に 伊藤亜矢子 第13章 学校づくりの援助 家近早苗 第14章 地域ネットワークづくりの援助 石川悦子 第15章 教育・学校心理学と公認心理師の実践 石隈利紀
対話によって人は学び,知識が構成される。学びの仕組みと具体的な教育方法を示し,ICTを活用した個別最適・協働的な学びを追求。 対話によって人は学び,知識が構成される。学びのメカニズムをふまえながら,いかに適切な教育方法を採用して授業設計するかについて解説。ICTを活用した個別最適な学び・協働的な学びへの道筋を探求する。 対話によって人は学び,知識が構成される。学びのメカニズムをふまえながら,いかに適切な教育方法を採用して授業設計するかについて解説。ICTを活用した個別最適な学び・協働的な学びへの道筋を探求する。教職課程コアカリキュラム「教育の方法及び技術」と「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に対応。 【主な目次】 ●第Ⅰ部 「学び」の諸原理 第1章 教育方法・技術論を学ぶ意義を考える [岩﨑千晶] 第2章 学びの形成における経験と知識の問題を考える [田中俊也] 第3章 学びの諸形態と学びの目標について考える [山田嘉徳] 第4章 動機づけと自己調整学習について考える [中谷素之] 第5章 批判的思考と学びの態度について考える [平山るみ] ●第Ⅱ部 さまざまな教育方法と技術 第6章 授業設計を考える [岩﨑千晶] 第7章 学習指導案の作成と学習指導の技術を考える [木村明憲] 第8章 インストラクショナルデザインを活用した指導案を作成する [根本淳子] 第9章 協働的な学びを考える [渡辺雄貴] 第10章 教育番組,映像コンテンツの活用を考える [宇治橋祐之] 第11章 タブレット端末の活用方法を考える [黒上晴夫] 第12章 デジタル教科書の活用を考える [中川一史] 第13章 遠隔・オンライン授業,教材作成を考える [今野貴之] 第14章 プログラミングを視座とする思考力の育成を考える [林 向達] 第15章 特別な支援を必要とする学習者へのICT活用を考える [植田詩織・岸磨貴子] 第16章 学習評価の原理・方法と技術を考える [山田剛史] 第17章 学習環境を考える [遠海友紀・久保田賢一] 第18章 授業研究を考える [小柳和喜雄] はじめに 第Ⅰ部 「学び」の諸原理 第1章 教育方法・技術論を学ぶ意義を考える [岩﨑千晶] 1 なぜ教育方法を学ぶ必要があるのか 2 社会の変容と求められる能力 3 学習指導要領とその改訂 4 個別最適な学び・協働的な学びの場づくり 第2章 学びの形成における経験と知識の問題を考える [田中俊也] 1 さまざまな経験と学び 2 経験の内的な変化:知の構成過程 3 知識の形成と学び 4 ICT活用と深い知識の獲得 第3章 学びの諸形態と学びの目標について考える [山田嘉徳] 1 学びの基本的構造 2 学びをとらえる社会・文化的視点 3 教育目標に向かう学びとその実現 第4章 動機づけと自己調整学習について考える [中谷素之] 1 学びと動機づけ 2 自分の学びを振り返る:メタ認知 3 自己調整学習:主体的学びの基本的原理 4 学習の共調整・社会的に共有された調整:学びの主体性を育む他者の役割 第5章 批判的思考と学びの態度について考える [平山るみ] 1 批判的思考 2 さまざまな思考のなかでの批判的思考 3 批判的思考と教育 4 メディアリテラシー 5 情報活用と情報モラル 第Ⅱ部 さまざまな教育方法と技術 第6章 授業設計を考える [岩﨑千晶] 1 授業設計 2 授業目標の設定 3 教育内容・方法のデザイン 4 評価方法のデザイン 第7章 学習指導案の作成と学習指導の技術を考える [木村明憲] 1 学習指導案とは 2 学校現場における学習指導の技術を高めるには 3 学習指導案と学習指導の技術 4 まとめ 第8章 インストラクショナルデザインを活用した指導案を作成する [根本淳子] 1 目標に向かった授業づくり 2 9教授事象を使ってデザインする 3 学習活動への動機づけ 4 よりよい授業をつくるための視点づくり 第9章 協働的な学びを考える [渡辺雄貴] 1 時代背景と学習指導要領での位置づけ 2 個別最適な学びと協働的な学び 3 協働学習の学術的・心理学的な位置づけと意味合い 4 協働学習の技法 5 協働学習の授業方略 6 ICTを活用した協働学習 第10章 教育番組,映像コンテンツの活用を考える [宇治橋祐之] 1 教育番組,映像コンテンツ活用の背景 2 教育番組,映像コンテンツの特性 3 教育番組,映像コンテンツを活用した授業設計 4 教育番組,映像コンテンツを活用した授業実践例や配慮すべき点 第11章 タブレット端末の活用方法を考える [黒上晴夫] 1 コンピュータ導入に関する小史 2 コンピュータの整備 3 1人1台端末の活用 4 まとめ 第12章 デジタル教科書の活用を考える [中川一史] 1 児童生徒1人1台端末時代への突入 2 デジタル教科書の学習効果 3 デジタル教科書の7つのアクセスのしやすさ 4 子ども主体の学びとデジタル教科書 5 デジタル教科書の課題 第13章 遠隔・オンライン授業,教材作成を考える [今野貴之] 1 遠隔・オンライン授業の形式と特徴 2 教材作成と留意点 3 個別最適な学びと協働的な学びとの関連 第14章 プログラミングを視座とする思考力の育成を考える [林 向達] 1 コンピュータとプログラミング 2 プログラミングを視座とする思考の育成 3 プログラミングの学習 4 学習指導要領とプログラミング 第15章 特別な支援を必要とする学習者へのICT活用を考える [植田詩織・岸磨貴子] 1 特別支援学校(肢体不自由)の実態とICT活用 2 特別支援学校(肢体不自由)におけるICT活用の事例 3 学習者に応じた道具の選択,活用,工夫 4 特別支援学校における個別最適化した学びの事例 5 特別支援教育における表現活動の広がりとICT 6 特別支援学校におけるICT活用を考える理論的枠組み 7 特別支援学校におけるICT活用と展望 第16章 学習評価の原理・方法と技術を考える [山田剛史] 1 学習評価の基本 2 学習評価の構成要素 3 学習評価の方法 4 ICTを活用した教学マネジメント 第17章 学習環境を考える [遠海友紀・久保田賢一] 1 学習環境とは 2 教室における学習環境 3 教室におけるICT整備 4 図書館,ラーニング・コモンズにおける学習環境 5 外部人材活用の背景 6 外部人材とは 7 ICT支援員との協働 8 大学や専門家との連携 9 チームとしての学校 第18章 授業研究を考える [小柳和喜雄] 1 授業研究とは 2 授業研究におけるICTの活用の意義 3 ICTを効果的に活用した学習指導に向けた授業研究 4 ICTを効果的に活用した公務の推進に向けての授業研究 あとがき 参考文献
堀江貴文は、逮捕や失敗を経験した後も希望を持ち続け、「働くこと」の意味を素直に語ります。本書では、仕事との出会いや選択、金銭的な価値観、自立の重要性、そして未来への希望について述べられています。著者は実業家であり、ライブドアの元CEOで、逮捕歴もある人物です。
ホリエモンの本は基本的にとりあえず行動しろよ!恐れるなよ!ということを言っているがこの本もご多分に漏れずそんな内容。ホリエモンの刑務所に居た時の話も語られ一旦全てを失った状態から這い上がってきたホリエモンの凄さに感銘を受けた。読めばモチベーションが上がるが行動しないと意味無し。
「ict教育」に関するよくある質問
Q. 「ict教育」の本を選ぶポイントは?
A. 「ict教育」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「ict教育」本は?
A. 当サイトのランキングでは『逆引き版 ICT活用授業ハンドブック』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで57冊の中から厳選しています。
Q. 「ict教育」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「ict教育」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



![『[改訂第4版]基礎からわかる情報リテラシー』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51rJHXpHVRL._SL500_.jpg)


![『よくわかる教育心理学[第2版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/313YEZONG7L._SL500_.jpg)






![『【図解】コレ1枚でわかる最新ITトレンド[増補改訂4版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/419tecJg5xL._SL500_.jpg)
![『絶対役立つ教育心理学[第2版]:実践の理論、理論を実践』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/31opcdhQBiL._SL500_.jpg)
















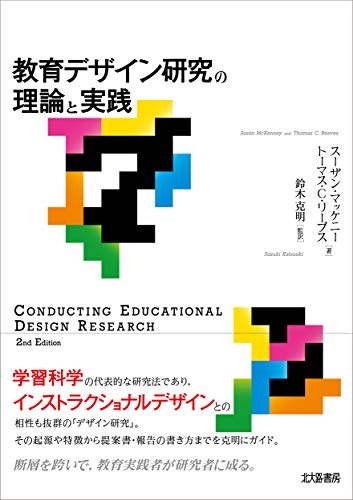













![『教育心理学のための統計学[心理学のための統計学4]: テストでココロをはかる (心理学のための統計学 4)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51otfb4JzwL._SL500_.jpg)























