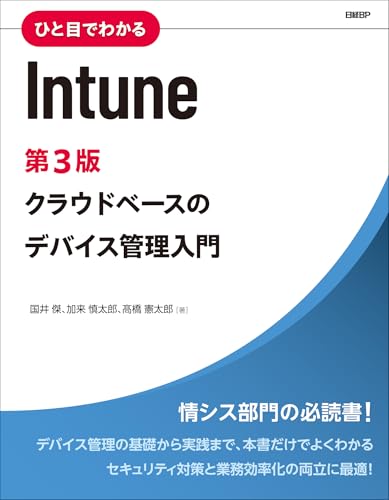【2025年】「ネットワーク」のおすすめ 本 165選!人気ランキング
- [改訂新版] 3分間ネットワーク基礎講座
- マスタリングTCP/IP―入門編―(第6版)
- ネットワークはなぜつながるのか 第2版 知っておきたいTCP/IP、LAN、光ファイバの基礎知識
- インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 第2版
- シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301
- 【改訂5版】図解でよくわかる ネットワークの重要用語解説
- 図解入門TCP/IP 仕組み・動作が見てわかる
- ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装
- インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク・デザインパターン 実務で使えるネットワーク構成の最適解27
- インフラエンジニアの教科書
この書籍は、TCP/IPの基礎を3分で理解できる内容で、ネットワークの基本知識、信号の伝送、IPアドレッシング、ルーティング、コネクションとポート番号について解説しています。著者の網野衛二は、コンピューター専門学校の講師であり、ネットワークに関する講座や連載を行っています。
本書『マスタリングTCP/IP 入門編 第6版』は、TCP/IPに関する解説書の最新版で、時代に即したトピックを追加し内容を刷新しています。豊富な図版や脚注を用いて、TCP/IPの基本をわかりやすく解説しており、ネットワークやインターネットプロトコルの理解を深めるための入門書として最適です。著者は複数の専門家で構成されています。
この書籍は、WebブラウザがURLを入力してからWebページが表示されるまでのプロセスを探る内容で、ネットワーク技術に関する基礎解説が大幅に加筆された改訂版です。目次にはブラウザ内部のメッセージ作成、TCP/IPプロトコル、LAN機器(ハブ、スイッチ、ルーター)、アクセス回線とプロバイダ、サーバー側のLAN、Webサーバーへの到達と応答データの戻りなどが含まれています。著者はネットワーク業界での経験を持つ戸根勤氏です。
この書籍は、ネットワーク構築に必要な基礎技術と設計ポイントを400以上の図を用いて解説したベストセラーの改訂版です。新たに高速化設計や最適化設計に関する内容が追加され、クラウドとオンプレミスの共存環境に対応しています。主な改訂点には、高速ネットワーク技術や仮想化設計手法、分かりやすい解説が含まれています。ネットワーク技術の基本から実務ノウハウまでを網羅した一冊です。著者はシステムエンジニアおよびネットワークコンサルタントとしての経験を持っています。
本書は2020年2月に改訂されたCCNA試験(試験番号200-301)に対応したテキストと問題集で、IT専門スクールの講師が執筆しています。基礎力を効率的に身につけることができ、理解度を確認するための問題や模擬試験が収録されています。独学での学習をサポートし、初めてCCNA試験に挑戦する人に最適です。合格に必要なポイントを網羅し、1冊で合格を目指せる内容となっています。
「図解でわかる ネットワークの重要用語解説」の改訂5版が発行され、フルカラーでイラストを用いてネットワーク用語を解説しています。初級エンジニアや学生、現場のSEやPMにも役立つ内容で、インターネット編が「基礎編」と「技術編」に分かれ、新たに「セキュリティ編」も追加されました。著者はコンピュータプログラマのきたみりゅうじです。
この書籍は、ディープラーニングをゼロから実装することで学ぶ入門書です。Python 3を用いて、基礎から誤差逆伝播法や畳み込みニューラルネットワークなどの実装を通じて理解を深めます。また、ハイパーパラメータの設定やBatch Normalization、Dropout、Adamなどの最新技術、さらには自動運転や画像生成などの応用例についても触れています。著者は斎藤康毅氏で、コンピュータビジョンや機械学習の研究開発に従事しています。
ディープラーニングの概要は分かっているし機械学習はある程度理解しているつもりだけど、ディープラーニングの中身はちゃんと理解できていない人にぜひ読んで欲しい書籍。ディープラーニングは一旦これ1冊読んでおけば問題なし。複雑で難しい印象だったディープラーニングがこれを読むだけで一気に身近なものになる。
『インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門』は、著者みやたひろしがネットワーク設計と運用管理に関するノウハウを解説する書籍です。27種類のネットワーク設計パターンを豊富な図解で紹介し、小規模から大規模までの鉄板構成を解説しています。実務理解を深めるだけでなく、RFPや提案書、設計書作成にも役立つ内容です。ネットワーク設計に関わるすべての人にとって必携の一冊です。
この書籍は、クラウド時代に対応したネットワークの入門書で、累計9万部を突破した第4版の改訂版です。スイッチ、ルータ、セキュリティ、無線LANなど、企業ネットワークの重要事項を図解と写真を用いてわかりやすく解説しています。初心者向けに、最新の情報やゼロトラストセキュリティの考え方も取り入れています。著者は30年の経験を持つネットワーク専門家です。
本書は、ゼロトラストネットワークの概念と実装方法について解説しています。従来の境界防御モデルが通用しなくなった現状を背景に、すべてのトラフィックを信頼せず検証するアプローチが強調されています。クラウドサービスやモバイルの普及により、セキュリティの境界が曖昧になったため、ゼロトラストが注目されています。具体的には、デバイスやユーザー、アプリケーション、トラフィックの信頼性を確立する方法が詳述されており、Googleの「BeyondCorp」を含むケーススタディも収録されています。著者は、ネットワークやセキュリティの専門家たちです。
「徹底攻略Cisco CCNA問題集」は、2020年改定の新試験「200-301 CCNA」に対応した問題集です。出題範囲が広がったため、問題を解くことで知識を自然に身につけられるよう構成されています。初心者向けに詳細な解説があり、模擬問題やスマホ問題集も提供されています。132問の模擬問題やIPアドレス計算問題も含まれ、合格を目指すための充実した内容です。
本書は、オープンソースのネットワーク解析ツール「Wireshark」を使ったパケット解析の入門書です。著者はWiresharkの日本語化担当者で、最新バージョン2.xに対応した操作方法や機能、便利なテクニックを解説しています。内容は、Wiresharkの概要、インストール・操作方法、パケットキャプチャ、ネットワークの仕組み、ダンプ解析、トラブルシューティングなど多岐にわたります。サンプルパケットもダウンロード可能で、初心者にもわかりやすく構成されています。
本書は、各種WAN技術の概要を紹介し、主流のMPLS-VPN、広域イーサネット、インターネットVPNのネットワーク構成や設定例を解説します。また、高可用性や運用監視、セキュリティに関する構成例も示しています。目次には、主要WANサービスの市場や技術、ケーススタディ、ハイブリッド型VPNやシスコ機器を用いた高度な活用法が含まれています。
この入門書は、パターン認識について基礎からわかりやすく解説しており、特にRを用いた実行例が含まれているため、実際の応用にも役立ちます。内容は識別規則や学習法、ベイズの識別規則、k最近傍法、サポートベクトルマシンなど多岐にわたり、最後には識別器の性能強化についても触れています。著者は筑波大学の名誉教授、平井有三氏です。
「はじめての」とついているが入門書ではなく結構難しい。ただ、機械学習の様々な手法が数式から学べるため中級者〜上級者には良いと思う。他の入門書で機械学習の概要を掴んだ後に読むべき本。
本書は、企業や個人のセキュリティ対策に役立つ知識を図解で提供する「使える教科書」です。基本的な考え方から具体的な技術、運用方法までを網羅しており、管理者や開発者にとっても有益です。目次には、ネットワーク攻撃やウイルス、暗号技術、法律など多岐にわたるテーマが含まれています。読者は興味のある項目を選んで学ぶことができ、実習項目もあり、自宅で体験することが可能です。セキュリティ対策を強化したい人に特におすすめです。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
この書籍は、CCNA合格に向けてネットワークの基礎を学ぶための入門書です。内容は、ネットワークの基本知識、各層の役割、IPアドレス、TCP、通信の流れ、ネットワーク設計、コンピュータ設定、シスコ機器の概要と設定方法に関するものです。著者の谷本篤民は、通信キャリアでの経験を持つインストラクターで、現場のニーズに応じた教育を提供しています。
この書籍は、機械学習とディープラーニングの基本を図解形式で解説しており、エンジニア1年生や関連企業への就職・転職を目指す人に最適です。内容は、人工知能の基礎、機械学習とディープラーニングのプロセス、アルゴリズム、システム開発環境に関する知識を包括的に学べる構成になっています。著者は、実践的な機械学習システムの実装をサポートする専門家です。
本書は、DNSの仕組みや運用ノウハウを包括的に解説する入門書です。内容は、ドメイン名のルール、リソースレコード、動作確認のためのコマンド、DNSSECの基礎知識などを含み、初心者でも理解しやすいように構成されています。基礎から実践、アドバンス編まで段階的に学ぶことで、DNSの正しい知識と運用方法を習得できます。
この書籍は、ネットワークエンジニアを目指す人や初心者向けに、最新のテクノロジーやトラブルシューティング手法をわかりやすく解説しています。内容は、ネットワークの基礎知識、ルーティングプロトコル、セキュリティ、無線LAN、データセンターなど多岐にわたり、ネットワーク設計・運用保守や自動化に関する情報も含まれています。各章では専門家がそれぞれの分野を詳しく説明しています。
『絵で見てわかるITインフラの仕組み』の新装版は、ITインフラの基盤技術を理解しやすく解説しています。著者の経験を基に、アーキテクチャ、ネットワーク、サーバーなどをマクロからミクロの視点で説明し、共通する原理を本質的に理解できるように工夫されています。図が豊富で、実務経験が浅い方でもイメージしやすく、インフラ担当者やアプリ開発者、DB管理者におすすめです。
ITエンジニアが知っておくべきネットワークプロトコルに関する知識を、イラストや図を豊富に使って分かりやすく解説 本書は、日経NETWORKに掲載したネットワークプロトコルに関連する主要な記事をまとめた1冊です。ネットワークプロトコルを網羅的かつ分かりやすく解説します。 文章を読むだけでは難解なネットワークプロトコルを、豊富なイラストや図を使って解説していることが特徴。「TCP/IPを学ぶ」編では、インターネットの通信で使われている主要プロトコルであるTCP/IPやその関連技術を豊富な図で解説します。「イーサネットを学ぶ」編では、有線通信の代表的なプロトコルのイーサネットやMACアドレス、ARPなどの基礎を初心者にも分かりやすいように説明します。「通信制御のプロトコルを学ぶ」編では、インターネットの通信に不可欠なDNSやIPアドレスなどを配布するDHCPなどを徹底図解。「データ送受信のプロトコルを学ぶ」編では、WebのプロトコルであるHTTPやデータ送受信のプロトコルFTPを豊富な図とイラストで解説します。HTTPの最新バージョンであるHTTP/3や安全性を高めたHTTPSについても詳述します。 ITエンジニアが知っておくべきネットワークプロトコルに関する知識を、イラストや図を豊富に使って分かりやすく解説します。 【第1部 TCP/IPを学ぶ】 第1章 マンガでわかるTCP/IP 第2章 ネットワーク技術解説 IPアドレスって何だろう? 第3章 図解で学ぶネットワークの基礎 IPアドレス 第4章 図解で学ぶネットワークの基礎 IP 第5章 ネットワーク技術解説 マルチキャストって何だろう? 第6章 ネットワーク技術解説 TCPって何がすごいの? 第7章 ネットワーク技術解説 TCPとUDPは何が違うの? 第8章 図解で学ぶネットワークの基礎 TCP 【第2部 イーサネットを学ぶ】 第1章 今こそ知りたいイーサネット 第2章 ネットワーク技術解説 イーサネットって何だろう? 第3章 図解で学ぶネットワークの基礎 イーサネットフレーム 第4章 図解で学ぶネットワークの基礎 MACアドレス 第5章 図解で学ぶネットワークの基礎 ARP 【第3部 通信制御のプロトコルを学ぶ】 第1章 安全DNSの極意 第2章 ネットワーク技術解説 DNSって何ですか? 第3章 図解で学ぶネットワークの基礎 DNS 第4章 まるわかりDHCP 第5章 ネットワーク技術解説 DHCPの役割とは? 第6章 図解で学ぶネットワークの基礎 DHCP 【第4部 データ送受信のプロトコルを学ぶ】 第1章 HTTP/3登場 第2章 ネットワーク技術解説 Webアクセスってどんなの? 第3章 ネットワーク技術解説 HTTPSってどんなの? 第4章 図解で学ぶネットワークの基礎 HTTP 第5章 ネットワーク技術解説 FTPって面白い? 第6章 図解で学ぶネットワークの基礎 FTP
本書は、CCNA/CCENT資格取得を目指す初心者向けのネットワーク技術解説書です。ネットワークの全体像と用語の理解を重視し、必要な基礎知識を効率的に習得できるように工夫されています。内容は、ネットワークの基本、TCP/IP、IPアドレッシング、Cisco機器の扱い方など多岐にわたり、試験対策に役立つ情報が網羅されています。著者はネットワーク技術の専門家で、実践的な知識を提供しています。
この書籍は、小規模ネットワークの設計と構築を自分で行うための入門書で、主に若手IT担当者やネットワーク管理者を対象にしています。フルカラー図解を用いてネットワーク構築の基本をわかりやすく解説し、シミュレーション形式で具体的な構築事例を示しています。内容はネットワークの進め方から高度化、運用管理まで幅広くカバーしています。著者はネットワーク技術の解説を行う専門家です。
本書は、ネットワーク技術と機器の役割を理解するための入門書で、LAN、WAN、TCP/IP、セキュリティなどの基礎知識を解説しています。新入社員や転職者向けにわかりやすく、見開き1トピック形式で構成されており、実習項目も含まれています。ネットワークの全体像や共通言語、Webサイトの仕組み、イーサネット、ルーティング、セキュリティ技術について学べます。
本書は、サーバやインフラの運用・管理に必要な技術や知識を基礎から解説した教科書です。ネットワークやサーバの基本知識に加え、クラウド関連の知識やエンジニアとしての考え方、学習法、スキルアップ、業務知識、職業倫理も取り上げています。これからサーバ/インフラエンジニアを目指す人に適した内容となっています。目次には、エンジニアとしての生き方、ネットワーク、インターネット、サーバ、仮想化、ミドルウェア、Webサービス運用、セキュリティ、クラウド、法律・ライセンスの基礎知識が含まれています。著者は馬場俊彰氏で、豊富な実務経験を持つエンジニアです。
この書籍は、数学の知識がなくても理解できる機械学習の入門書で、Pythonの機械学習ライブラリ「scikit-learn」を用いた実践的な解説が特徴です。著者はscikit-learnの開発に関わる専門家で、実践から理論へと学ぶスタイルを採用しています。特に「特徴量エンジニアリング」や「モデルの評価と改善」に焦点を当てており、従来の解説書にはない内容を提供しています。目次には教師あり学習、教師なし学習、データ処理などが含まれています。著者は機械学習の専門家で、産業界や学術界での経験があります。
この書籍は、CentOS 8に対応したLinuxサーバ構築の実用的なガイドです。内容は全面的に刷新され、実務に役立つ構成が特徴です。Cockpit、nginx、Redisなどの強化ポイントや認証サービスについても新章で詳しく解説しています。目次には、ネットワークサーバ構築の基礎、基本環境の構築、外部および内部サービスの導入、ネットワークサーバの管理、その他のサービスが含まれています。
本書は、ネットワーク入門書の改訂版で、スイッチ、ルータ、セキュリティ、IP電話、無線LANなど企業ネットワークの重要事項をわかりやすく解説しています。図解や写真を多く用いており、初心者向けに最新のネットワーク事情に対応した内容が盛り込まれています。著者はNECネッツエスアイの三上信男氏で、豊富な実務経験を持つ専門家です。
本書は、機械学習の有名なアルゴリズムをPythonを用いてゼロから実装することを目的としています。実用的なフレームワークを使用するのではなく、機械学習の仕組みを深く理解することで応用力や問題解決力を高めることを目指しています。内容は、Pythonの基本、機械学習に必要な数学、数値計算、そして具体的な機械学習アルゴリズムに関する解説を含んでおり、初心者や実務に携わるエンジニアに適しています。著者はシルバーエッグ・テクノロジーのチーフサイエンティストで、機械学習アルゴリズムの設計・実装に精通しています。
本書は、CCNA/CCENT資格取得を目指す人向けに、ネットワークの基礎知識を7コマの講義でわかりやすく解説しています。初心者でも楽しく学べるように、模擬問題や体験学習も充実。合格への第一歩を踏み出すためのサポートを提供します。著者は現役講師の林口裕志氏で、幅広いIT知識を持っています。
本書は、コンピューターの中核であるCPUの基本原理から設計例までを解説しており、アキバで手に入る部品を使った実際の製作も可能です。目次には、デジタル回路の基礎、リセットとクロック回路、ROMの作成、1ビットCPUの設計などが含まれています。著者は回路技術屋の渡波郁氏です。
最新IT技術やサービスを紹介すると共に大きく変化が始まった30年程前から、どのような紆余曲折を経て今の技術に至ったのか解説。 IT業界の進歩は早いものです。その中でも、インターネットが一般に浸透しはじめた1995年ごろを境に、IT技術やサービスが大きく進歩、そして変化しています。 本書では、「PCパーツ」「プログラミング言語」「人工知能」「ネットワーク」「ウイルス&セキュリティ」など、パソコンをとりまく最新のIT技術やサービスを紹介するとともに、大きく変化がはじまった30年ほど前から、どのような紆余曲折を経て、今の技術に至ったのかを解説します。 パソコンをとりまく最新のIT技術やサービスを紹介するとともに、大きく変化がはじまった30年ほど前から、どのような紆余曲折を経て、今の技術に至ったのかを解説します。 ■PCパーツ性能の移り変わり ・PCと自作パーツの進化 ・AMD新型プロセッサの性能と特徴 ・Intel第13世代Core iシリーズ ・高速シリアルインターフェイス「USB Type-C」 ・新世代拡張スロット「PCIe 5.0」 ■ネットワークの普及と完全ワイヤレス化 ・IT業界を激変させた「インターネット」 ・ゲーミングPCを完全ワイヤレスに ・驚異的な「Wi-Fi7」の世界 ■プログラミングとAI技術 ・プログラム言語とプログラム技法 ・AIの「夏」と「冬」 ・現在のAI事情 ・今すぐ使えるAI ・マルチパラダイムプログラミング言語 ■その他の技術 ・「ウイルス」と「セキュリティ」の変遷 ・生活に溶け込む「ロボット」と「センサ」 ・ドローンの歴史と未来
本書は、Linuxの基本的な仕組みや動作をフルカラーで解説したもので、プロセス管理、メモリ管理、ファイルシステム、仮想化、コンテナなどのテーマを含みます。豊富なグラフや図解を用いて、実験結果を視覚的に示し、難しい理論に踏み込まずに理解を助けます。また、ソースコードはC言語からGo言語とPythonに更新され、現代のLinuxの理解を深める内容となっています。著者はLinuxカーネルの開発に従事した経験を持つ専門家です。
3つのステップ学習で「合格」に導く総仕上げ問題集! 3ステップ学習で,着実に実力を伸ばせます。まずは知識量を確認!分野別Web確認テスト直近5期分の傾向と解法を,徹底的に理解しよう 本試験過去問題を詳細解説!本試験を想定したオリジナル「実力診断テスト」にチャレンジ最近の出題傾向を理解するための令和5年度春期試験の分析や,平成30年度秋期,令和元年度秋期,令和3年度春期,令和4年度春期,令和5年度春期の本試験問題とその詳細な解答・解説を提供しています。※平成30年度秋期,令和元年度秋期の本試験問題と解答・解説は,ダウンロードコンテンツです。◎試験対策の総仕上げに!◎正解だけでなく,間違い選択肢についても確認できる,詳細な解説! 試験制度解説編 第1部 分野別Web確認テスト 第2部 本試験問題 ・令和3年度春期試験 問題と解答・解説編 ・令和4年度春期試験 問題と解答・解説編 ・令和5年度春期試験 問題と解答・解説編 <出題分析> (1) 午前問題出題分析 (2) 午前の出題範囲 (3) 午後Ⅰ,午後Ⅱ問題 予想配点表 第3部 実力診断テスト
通信ネットワークの信頼性についての基礎理論から、目的に応じたネットワーク構造のモデル化、評価までを丁寧に解説。 ネットワークの高信頼化と経済性をどう両立するか? このバランスをとるのが信頼性設計である. 本書では,電話網を例にネットワーク設計法の概要を解説するとともに,一般的なネットワークの信頼性設計を行うための基礎的手法について解説.話題の中心は通信ネットワークであるが,通信以外の分野にも応用できるよう,モデル化する際の着眼点や発想および,信頼性設計全体の体系に重点を置いて説明した. また,web付録として信頼性解析プログラムを提供.これらを活用することで,様々なモデルを実際に計算し,各種理論の特性を体感することができる. 通信網,道路網,電力網など,様々なネットワークの設計・高信頼化を進めるうえで有用な一冊. 1 通信ネットワークの安全・信頼性 1.1 通信ネットワークの始まり 1.2 通信ネットワークの発展 1.3 通信ネットワークの品質と信頼性 1.4 高信頼化施策の体系と実際 1.5 トラヒック設計と信頼性設計の必要性 2 待ち行列および信頼性理論の基礎 2.1 待ち行列および信頼性理論の共通的手法 2.2 待ち行列 2.3 信頼性工学 3 ネットワークのモデル化と信頼性規定 3.1 果たすべき機能から見た電話ネットワークのモデル化 3.2 目標値として可能な信頼性測度 3.3 規模別信頼性目標の基礎理論 3.4 疎通率別信頼性目標の基礎理論 3.5 本章の方法論に関する考察 4 信頼性設計と解析 4.1 基本的評価方法と設計手順 4.2 具体的設計手順 4.3 潜在故障 4.4 故障許容時間 4.5 保全要因の考慮 4.6 ネットワークレベルの評価・設計 4.7 信頼性設計実施上の課題 5 解析プログラム編 5.1 確率の一般的手法に関するプログラム 5.2 信頼性規定の実用性検証に関するプログラム 5.3 詳細設計と解析に関連するプログラム
本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。
この文章は、ネットワーク技術に関する内容を扱った書籍の目次を示しています。主なトピックには、ネットワーク基礎、イーサネット、TCP/IP、ルーティング、VLAN、セキュリティ、IPv6の導入、シミュレーション問題などが含まれています。
◆合格直結の問題を豊富に掲載し、わかりやすく解説! ◆模擬試験問題付き(PDFファイルダウンロード形式) 本書は、工事担任者「第2級デジタル通信」試験対策の問題集です。 試験に合格するためには、できるだけ多くの問題に触れて、解く力を身に付ける必要があります。 1. 公表問題と予想問題で万全の対策 2022年11月に公表された「令和4年度第2回 工事担任者第2級デジタル通信試験問題」に1問ずつ丁寧な解説を付し、見開きページで簡潔にまとめました。さらに、予想問題を多数収録し、実力がしっかりと身に付く充実した解説を掲載しています。 このほか、随所に類題も掲載し、バランスの取れた受験学習を目指しています。 2. 公表問題を徹底分析 「基礎」、「技術・理論」、「法規」の各科目ごとに出題分析ページを設け、2022年11月公表問題を徹底分析しています。 これにより、合格を意識した具体的な受験対策と、無駄のない効率的な学習を実践することができます。 3. 試験直前で役に立つ「重点項目の総まとめ」 出題のポイントとなる重点項目を、各テーマごとに厳選し、短時間で学べる総まとめ形式で掲載しています。問題を解く前の予備学習や試験直前の総整理など、さまざまなシーンで知識の強化を図ることができます。 4. 総仕上げの模擬試験問題付き(PDFファイルダウンロード形式) 模擬試験1回分の問題および解説・解答(PDFファイル)をダウンロードしてご利用頂けます。本試験直前の実力判定にご活用ください。 ◆目次◆ 第1編 電気通信技術の基礎 1.電気回路 2.電子回路 3.論理回路 4.伝送理論 5.伝送技術 第2編 端末設備の接続のための技術及び理論 1.端末設備の技術(I) 2.ネットワークの技術(I) 3.端末設備の技術(II)、ネットワークの技術(II)、情報セキュリティの技術 4.接続工事の技術 第3編 端末設備の接続に関する法規 1.電気通信事業法 2.工担者規則、認定等規則、有線法、設備令、不正アクセス禁止法 3.端末設備等規則(I) 4.端末設備等規則(II) 第1編 電気通信技術の基礎 1.電気回路 2.電子回路 3.論理回路 4.伝送理論 5.伝送技術 第2編 端末設備の接続のための技術及び理論 1.端末設備の技術(I) 2.ネットワークの技術(I) 3.端末設備の技術(II)、ネットワークの技術(II)、情報セキュリティの技術 4.接続工事の技術 第3編 端末設備の接続に関する法規 1.電気通信事業法 2.工担者規則、認定等規則、有線法、設備令、不正アクセス禁止法 3.端末設備等規則(I) 4.端末設備等規則(II)
主人公アレックス・ロゴは、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナとの再会をきっかけに工場の再建に取り組む。彼は生産現場の常識を覆すジョナの助言を受け、仲間と共に努力するが、家庭を犠牲にしてしまい、妻ジュリーとの関係が危機に陥る。物語は、仕事と家庭の両立を巡る葛藤を描いている。
この本は、実務経験を積んだインフラエンジニアが次のステップに進むために必要な技術や知識をわかりやすく解説しています。日常のルーティンでは学べない原理やノウハウが豊富に含まれており、成長を目指す人に向けた続編です。目次には、プロトコル、OS、ネットワーク、データベース、セキュリティ攻撃など多岐にわたるテーマが含まれています。著者はLINE株式会社でインフラエンジニアとして活躍する佐野裕です。
本書は、GNS3というオープンソースのネットワークシミュレータを用いて、IPネットワークの基礎やスイッチング、VPNなどの技術を実際に構築・検証しながら学ぶための教材です。44の演習ラボを通じて、ネットワーク技術を体系的に習得でき、シスコの認定資格(CCENT/CCNA/CCNP)を目指す自習環境としても最適です。著者は、NTTでの豊富な経験を持つ関部然氏です。
本書は、業務レベルでのLinuxサーバ運用に必要な基本知識をまとめた教科書で、コマンドの実行例を多数掲載しています。学習者は実際にコマンドを実行しながら、Linuxの基礎を学ぶことができます。目次には、Linuxの導入からネットワーク管理、セキュリティ対策まで幅広いテーマが含まれています。著者は、LinuxやUNIXの専門家であり、長年の経験を持っています。
この資料には、模擬問題と徹底攻略スマホ問題集が含まれています。目次には、VLAN、STP、EtherChannel、レイヤ3冗長化、IPv4アクセスリスト、IPv6の実装、EIGRP、OSPF、WAN接続、インフラストラクチャサービス、運用、総仕上げ問題、シムレット、シミュレーション問題が含まれています。
この書籍は、データサイエンスにおける重要な統計学と機械学習の52の基本概念を簡潔に説明し、関連する数式やグラフ、RとPythonのコードを提供することで、深い理解を促進します。データの分類、分析、モデル化、予測のプロセスにおいて、必要な統計学の項目を明確にし、効率的に学べる内容です。改訂版ではPythonにも対応し、コードはGitHubからダウンロード可能です。著者はデータサイエンスの専門家であり、幅広い経験を持つ研究者たちです。
この文章は、パターン認識に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、識別関数、最尤推定法、ベイズ推定法、カーネル密度推定法など、さまざまな手法や理論が含まれています。著者の杉山将は、東京工業大学で学び、博士号を取得後、同大学院で助教授として活動しています。
本書は、モダンなモニタリングの必要性とその実践方法を解説する内容です。監視のベストプラクティスやデザインパターンを紹介し、フロントエンド、アプリケーション、サーバ、ネットワーク、セキュリティの各分野での監視基盤の設計と実装方法を示しています。また、日本語版には監視SaaSの導入や活用方法に関する付録も含まれています。著者は監視に関する専門家で、実務経験を持つエンジニアです。
本書『絵で見てわかるOS/ストレージ/ネットワーク』の新装版は、企業システムにおける重要なITインフラ技術を図を用いてわかりやすく解説しています。主にデータベース管理者や若手エンジニアを対象とし、データの入出力やハードディスク、メモリの役割を重点的に説明。新装版ではクラウドや仮想化に関する最新情報も追加されています。内容はOS、ストレージ、ネットワークの基礎から応用までをカバーし、実務に役立つノウハウが豊富に含まれています。
この書籍は、ブランチオフィスやモバイルワーカー向けの高セキュリティルーティングソリューションの設定に関する内容で、Ciscoルータの実装に必要なIPアドレッシングとルーティングの知識・スキルが求められます。目次には、EIGRP、OSPF、ルート再配布、BGP、IPv6、インターネット接続、ネットワーク管理に関する章が含まれています。
情報処理技術者試験のネットワークスペシャリスト試験用の合格教本の改訂版です。高度試験では午前I、午前II、午後I、午後IIの4つの試験が行われますが、本書は特にネットワークの専門知識が必要となる午前II以降の対策に焦点を当てた試験対策テキストです。手厚い解説と演習ソフト「DEKIDAS」による過去問演習で、難関試験の合格を目指します。 ■第Ⅰ部 知識のまとめ~午前Ⅱ、午後Ⅰ・午後Ⅱ問題対策 ・第1章 ネットワークの基礎知識 ・第2章 符号化と伝送 ・第3章 LANとWAN ・第4章 インターネットの技術 ・第5章 信頼性向上 ・第6章 セキュリティ ■第Ⅱ部 長文問題演習~午後Ⅰ・午後Ⅱ問題対策 ・午後Ⅰ問題の対策 ・午後Ⅱ問題の対策 ■読者特典 ・スマホでできる問題演習Webアプリ「DEKIDAS-WEB」 ・本書、第Ⅱ部の演習で利用できる午後問題の解答用紙PDF
本書は、新人エンジニアやクラウドに取り組むエンジニア向けに、Amazon Web Services、Google Cloud Platform、Microsoft Azureなどの主要クラウドサービスの全体像や、実際の企業事例を通じてクラウドの構築と運用のノウハウを学ぶためのガイドです。特集では、クラウドの現状と未来、主要プラットフォームの詳細、そして実践的な事例を紹介し、クラウドを効果的に活用するための知識を提供します。
『デザインパターン』の23個のパターンをオブジェクト指向初心者向けに解説した書籍で、Javaのサンプルプログラムを掲載。新たに「デザインパターンQ&A」も追加されている。目次はデザインパターンの基本から、サブクラスの利用、インスタンス作成、構造管理など多岐にわたる。
本書は「Infrastructure as Code」を定義し、現代のサーバーインフラ管理のパターンやプラクティスを体系的にまとめています。手動での構成管理をスクリプトで自動化するこの手法は、クラウドの進化により注目されています。内容は基礎からパターン、プラクティスに分かれ、特定のツールに依存せず、背景にある考え方を重視しています。著者は各分野での豊富な経験を持つ専門家です。
この書籍は、MySQLに関する包括的なガイドで、概要から開発時の問題、運用中のトラブルシューティング、堅牢な運用の実現方法、ソースコードのビルドに至るまでの内容を扱っています。著者は奥野幹也で、自由なソフトウェアの普及に取り組んでいます。
本書は、クラウドサービス「Amazon Web Services(AWS)」を利用してネットワークやサーバーの構築を学ぶためのガイドです。初心者やアプリ開発者に最適で、実機に触れることなくインフラ技術を習得できます。改訂4版では、AWSの最新UI、Amazon Linux 2023への対応、TLS/SSLやHTTP/2への配慮が追加されています。内容はシステム構築からネットワーク、サーバー、Webサーバーのインストール、通信の仕組みまで幅広くカバーしています。著者は技術者としての豊富な経験を持つ専門家たちです。
本書は、Raspberry Piを通じてコンピュータの仕組みやコンピュータサイエンスの基本を学ぶための教材です。著者たちはプロセッサ、メモリ、ストレージ、ネットワーク、オペレーティングシステムなどを歴史的背景と共に詳しく解説し、一部は実際にRaspberry Piを使って学ぶことも可能です。著者は、大学教授や企業の代表として、コンピュータシステムやネットワークの管理・運用に豊富な経験を持っています。
ITエンジニアの必須知識、ネットワークプロトコルの入門書 技術者ならこれだけは知っておくべき、プロトコルの入門書! ITエンジニアの必須知識の1つ、ネットワークプロトコル全般についての解説書です。 クラウド化が加速する現代においても、通信の仕組みとセットである ネットワークプロトコルの知識はITエンジニアにとって欠かせません。 本書では目に見えないネットワークの世界を理解するために、多くの図解イラストを 用いて解説しています。 全てのネットワークプロトコルを扱うことはできませんが、EthernetやIPv4、IPv6、 TCP/IP、HTTP、HTTPSといった基本はもちろん、SSHやSNMP、SSL/TLSなど、 技術者なら知っておくべきものに絞って解説しています。 著者はIT技術専門スクールで講師を務め、現役エンジニアとしても活躍している 川島拓郎さん。実際の講義の内容を意識しながら解説しています。 【こんな方達におススメすすめします】 駆け出しの ・ネットワークエンジニア ・セキュリティエンジニア ・クラウドエンジニア ・開発系エンジニア ・情報システム部門の担当者 【目次】 第1章 ネットワークのきほん 第2章 現代の通信に必須のプロトコルのきほん 第3章 通信の信頼性を支えるプロトコルのきほん 第4章 日常で使うインターネットを支えるプロトコルのきほん 第5章 ネットワークを支える技術のきほん 第6章 物理層に関係した技術のきほん 第7章 セキュリティ関連技術のきほん
本書は、Haskellのプログラミングを楽しく学べる入門書であり、原書「Learn You a Haskell for Great Good!」を基にしています。丁寧な解説と魅力的なイラストを通じて、型やモナドなどの難しい概念を自然に習得できるよう工夫されています。目次には、基本的な構文から入出力、モナドに至るまでのさまざまなトピックが含まれています。著者は計算機科学を学ぶ学生やプログラマ、研究者です。
ネットワーク技術の知識が,この1冊で深まります!! 内容をさらに充実させて第2版として刊行しました!! ◎複雑な内容を図を多く用いて説明し,分かりやすく,イメージしやすい構成 ◎学習者からよく出る疑問・質問をFAQで回答 ◎教科書としての側面を強化し,知識のインプットを手助け! ◎知識確認用に演習問題を掲載 ◎解答解説では,解き方のプロセスや誤答の選択肢も丁寧に解説 【こんな方におすすめ!】 ◆これから社会人になり,ITパーソンとして活躍しようと志している学生の方 ◆既にITパーソンとして実務を行いながら,ネットワーク技術全般を学習しようとする方 ◆ネットワークスペシャリスト試験におけるネットワーク分野の専門知識を効率的,かつ,しっかりと理解したい方 第1章 ネットワークの基礎知識 第2章 LANの方式 第3章 IP 第4章 TCPとUDP 第5章 DNSの仕組み 第6章 電子メールの仕組み 第7章 アプリケーションプロトコル 第8章 VoIP 第9章 ネットワーク機器 第10章 ネットワークセキュリティ
本書は、インターネット技術における情報セキュリティを体系的に学ぶための入門書であり、セキュリティ技術の基礎を広範にカバーしています。内容は、暗号技術、認証技術、セキュリティプロトコル、ホストおよびネットワークセキュリティ、Webセキュリティなど多岐にわたります。第2版では、技術の進歩とニーズの高まりを反映し、目次構成の見直しと大幅な加筆修正が行われています。著者は明治大学の齋藤孝道教授で、情報セキュリティ技術の専門家です。
ネットワーク技術に大きな変革をもたらすSDN(Software-Defined Networks)を学べる一冊。 ソフトウェア定義ネットワークの概念・設計・ユースケースを知る SDN(Software-Defined Networks:ソフトウェア定義ネットワーク)は、 ソフトウェアの力によって、従来のネットワークに対し高い柔軟性と拡張性を提供する技術です。 コントローラによる集中管理とデータプレーンのプログラマビリティを利用して、 従来のネットワークでは不可能だったさまざまなユースケースを実現できます。 また、オープンソースの実装も増えてきており、より身近なものになりつつあります。 本書は、SDNのコンセプト、基本アーキテクチャ、設計と実装のベストプラクティス、 さまざまな応用事例などについて包括的に解説した書籍です。 SDNの第一人者であるLarry Peterson氏・Bruce Davie氏らによって 「最先端のSDN」について説明された原著を、VMwareの進藤資訓氏らが翻訳。 第11章と付録では、日本語版オリジナルの書き下ろしとして、 国内でのSDNの活用事例も紹介しています。 ▼主な内容 ・オープンソースソフトウェアを例としたSDNのスタックの解説 ・SDNを支えるコンセプト、概念、設計理念 ・スケーラブルなクラウドのデザインがどのようにネットワークに適用できるか ・固定機能およびプログラマブルなスイッチに関する解説 ・スイッチをプログラム、制御するために使われるP4のためのツールチェーンの説明 ・SDNの各種ユースケースの紹介 ・社内、データセンター、アクセスにおけるネットワーク ・GitHubからダウンロード可能なハンズオン練習問題を含む SDN技術を学びたい(SDNの本質や実装を知りたい)エンジニア、 ネットワーク・クラウドの開発・構築に携わるエンジニアに一読いただきたい一冊です。 日本語版の刊行に寄せて――訳者まえがき 刊行に寄せて――原書序文 はじめに 第1章 SDNの概要と定義 1.1 市場の状況 1.2 技術的な状況 1.3 SDNの定義 第2章 ユースケース 2.1 ネットワークの仮想化 2.2 スイッチングファブリック 2.3 WANのトラフィックエンジニアリング 2.4 Software-Defined WAN 2.5 アクセスネットワーク 2.6 ネットワークテレメトリ 第3章 基本アーキテクチャ 3.1 ソフトウェアスタック 3.2 ベアメタルスイッチ 3.3 スイッチOS 3.4 ネットワークOS 3.5 リーフスパインファブリック 第4章 ベアメタルスイッチ 4.1 スイッチレベルの概略図 4.2 フォワーディングパイプライン 4.3 パイプラインの抽象化 4.4 P4プログラム 4.5 固定機能型パイプライン 4.6 比較 第5章 スイッチOS 5.1 シンスイッチOS 5.2 P4Runtime 5.3 gNMIとgNOI 5.4 SONiC 第6章 ネットワークOS 6.1 アーキテクチャ 6.2 ディストリビューテッドコア(分散型コア) 6.3 ノースバウンドインターフェース(NBI) 6.4 サウスバウンドインターフェース(SBI) 6.5 スケーラブルパフォーマンス 第7章 リーフスパインファブリック 7.1 機能セット 7.2 セグメントルーティング 7.3 ルーティングとマルチキャスト 7.4 カスタマイズされたフォワーディング 第8章 ネットワーク仮想化 8.1 課題 8.2 アーキテクチャ 8.3 構成要素 8.4 システム例 8.5 マイクロセグメンテーション 8.6 ネットワーク仮想化はSDNか? 第9章 アクセスネットワーク 9.1 背景 9.2 SD-PON 9.3 SD-RAN 9.4 SD-Fabricの役割 第10章 SDNの未来 10.1 ネットワークの検証とSDN 第11章 日本におけるSDN 11.1 日本におけるSDN――Rusmus Holtet Rusz&進藤資訓インタビュー 11.2 ユースケース 高精度ネットワークモニタリングシステム(HANMOC) 11.3 ユースケース モバイルパケットブローカー 付録A [補足]ネットワークファブリック A.1 コンピューティングリソースの変化 A.2 アプリケーションの変化 A.3 ネットワーク設計の変化 A.4 ネットワークファブリック A.5 リーフスパインファブリック A.6 ネットワークのディスアグリゲーション 付録B [活用例]SDNとNFV B.1 SDNとNFV B.2 SDNとNFVを実現するスライシング B.3 SDNとNFVの活用例 付録C ハンズオンプログラミング――演習問題 C.1 実行環境 C.2 演習問題
この書籍は、情報セキュリティ技術の知識を深めるための信頼できるリソースです。著者は教育経験が豊富で、技術分野ごとに分かりやすく解説しています。重要用語は色付きで示され、図解も用いられており、理解を助けます。また、知識確認のために138問の例題演習問題が掲載されています。内容は情報セキュリティの基礎から、暗号技術、Webシステムのセキュリティ、システムセキュリティに至るまで多岐にわたります。著者は長嶋仁で、研修講師や学習コンテンツ制作を手掛けています。
この書籍は、データベース設計やアプリケーション開発におけるアンチパターンを紹介し、失敗を避けるための改善策を提案しています。内容はデータベース論理設計、物理設計、クエリ、アプリケーション開発の4つのカテゴリに分かれており、複数の値を持つ属性や再帰的なツリー構造、小数値の丸め、SQLインジェクションなどの実践的な問題を扱っています。著者はソフトウェアエンジニアやデータモデリングの専門家で構成されています。
『Hadoop』の第3版が登場し、Hadoop 0.22系と2.x系の内容が大幅に加筆されています。新機能YARNやMapReduce 2について詳述し、旧バージョンの情報もカバーしています。日本語版の付録にはClouderaの小林大輔氏による「最新の高可用性HDFSの紹介」が含まれ、Hadoopの基礎から応用までを網羅した内容です。著者はHadoopの専門家であり、翻訳者たちも新技術の普及に努めています。
この文章は、書籍の目次と著者情報を紹介しています。書籍は三部構成で、第一部ではアルゴリズムやプログラムの構造について、第二部ではパフォーマンスやアルゴリズムデザインのテクニックについて、第三部では具体的な問題解決の作品を扱っています。著者の小林健一郎は東京大学で物理学を学び、情報科学を専門とする教授です。
本書は、Go言語の並行処理に関する包括的な手引書であり、設計哲学や言語機能、プログラミングテクニック、ベストプラクティス、内部構造を解説しています。Go言語のシンプルな仕様と強力な並行処理機能を活かし、サーバーサイドやコンテナツールなど多様な分野での活用を促進します。特に並行処理を学びたいプログラマにとって有用な内容です。著者はコンピュータ科学者であり、Goコミュニティへの貢献も行っています。
本書は、現代の分散システム設計におけるデータの扱いに焦点を当て、リレーショナルデータベースやNoSQL、ストリーム処理などのテクノロジーの特性を詳述しています。データ指向アプリケーションの設計に必要な基本概念を解説し、レプリケーションやトランザクション、バッチ処理などの分散データの管理手法についても触れています。ソフトウェアエンジニアやアーキテクトにとって必携の一冊です。
この文章は、第二版の内容紹介と目次を示しています。第二版では、計算モデルにおける時間の扱いに焦点を当て、状態を持つオブジェクトや並列プログラミング、関数型プログラミング、遅延評価、非決定性などの新しいテーマが強調されています。目次には、手続きやデータによる抽象の構築、オブジェクトと状態、超言語的抽象、レジスタ計算機に関する章が含まれています。
本書は、データサイエンスにおけるコンペティション、特にKaggleに焦点を当て、実践的なデータ分析手法やテクニックを紹介しています。分析コンペに参加することで得られるスキルは、実務でも役立つため、特徴量の作成やモデルの評価、チューニングなどの具体的な内容が含まれています。著者たちは、データサイエンスの専門家であり、実績を持つKaggleの競技者です。この本は、コンペに挑戦したい人や実務でのモデル精度向上を目指す人にとって有益な情報源となるでしょう。
データ分析コンペKaggleに挑戦するならこれをまず読んでおけば大丈夫!Kaggleに参加しないにしてもデータ分析の本質やテクニックがギュッと詰まっているので実務に活かせる。高度な内容も登場するが分かりやすく解説してくれるので初心者でも読みやすい。それでいてベテランの人も多くの学びがある書籍。著者はKaggleの最上位グランドマスターの方々であり説得力がある。過去のコンペの事例も取り上げてくれるのでそんなアプローチあったのかぁと学びが深い。文句なしの星5つ!
富とデータを独占する米巨大ITが、通信事業者の独擅場だった通信インフラも飲み込み始めた。その未来は、消費者にとって善か悪か NTTは日本の空洞化危機を防げるか 通信150年目の岐路 今や誰もがスマートフォンを持ち、インターネットを使う。ネットなしの生活など考えられないくらいだ。その隆盛を土台として支えてきた通信インフラが巨大IT企業や政治に揺さぶられている。 既に海底ケーブルはその多くがグーグルやアマゾンなどの巨大IT企業が敷設するようになった。これまでNTTなど通信事業者の牙城と思われてきた、電話のコアネットワークにもこれらの企業が進出しつつある。 一方で、ウクライナ戦争に端を発し、政治によるインターネットの分断も進む。5Gでも米中の分断が起こっている。これまでの開かれたネットの世界は夢幻になっていくのか。 こういった巨大ITや政治の力がネットを揺さぶる中で、日本はこれからどのようにしていくべきか。NTTは独自のIOWN構想でその存在感を示そうとする。 本書は、このような激変期を迎えた世界の通信に関する動きに、地政学という切り口でフォーカスを当てる。これらの動きから、来る2030年代の情報通信の世界を展望する。 富とデータを独占する米巨大ITが、通信事業者の独擅場だった通信インフラも飲み込み始めた。その未来は、消費者にとって善か悪か 序章 巨大IT企業が通信をのみ込む 第1章 海底の主役交代─ 巨大IT企業vs通信事業者 コラム 海底ケーブル世界有数の製造現場に潜入 第2章 クラウドの侵食─ 巨大IT企業vs通信機器大手 第3章 ネットの亀裂─民主主義国vs権威主義国 第4章 二つの5G─米国vs中国 第5章 「ゲームチェンジ」で挑む─ 巨大IT企業vs NTT 第6章 データを巡る闘い─ 巨大IT企業vs欧州 第7章 グローバルインターネットの終焉
本書は、CCNP Routing and Switching 300-101J ROUTE試験に対応した学習書で、現役エンジニアの講師が執筆しています。試験に出やすいポイントをわかりやすく解説し、模擬試験も2回分収録。実機がなくても学べる豊富な事例と出力例を提供しています。内容はネットワークの基本からルーティング、BGP、IPv6、VPNまで多岐にわたり、合格を目指すエンジニアにとって必携の一冊です。
この入門書は、ベイズ主義機械学習の基本原理を「モデルの構築→推論の導出」という手順で分かりやすく解説しています。内容は、機械学習とベイズ学習、基本的な確率分布、ベイズ推論による学習と予測、混合モデルと近似推論、応用モデルの構築と推論の5章から構成されています。著者は須山敦志と杉山将で、機械学習を身近に理解できるよう丁寧に記述されています。
2022年夏の事例を用いて最新の情報を提供。Wi-Fi、IoT、VPNなど、日々進化するネットワーク技術、その最新技術を解説 現在では、あらゆるものがネットワークにつながり、さまざまなデータをやり取りしています。 「高速化」「低遅延化」「複数接続化」が進む「Wi-Fi7」や、IoTによる家電の制御など、生活に密接に影響しはじめています。 本書では、「Wi-Fi」の意外な利用法や、第4世代「HD-PLC」、パスワードレス認証など、身近になったネットワーク技術を解説。 2022年春夏の事例を用いて、最新の情報を提供。Wi-Fi、IoT、VPNなど、日々進化するネットワーク技術、身近になったネットワーク技術の最新技術を解説。 ■ネットワーク技術 ・「インターフェイス」と「ネットワーク」 ・驚異的な「Wi-Fi7」 ・「Wi-Fi」の意外な利用法 ・「VPN」とブラウザ ・ネット回線速度とは ・“技適未取得”の外国製機器の実験的利用 ■IoT、ハードとネットワーク ・第4世代「HD-PLC」 ・「Ring Video Doorbell 4」を「IFTTT」経由で自作機器に接続 ・IoTネットワーク「Sigfox」 ■Webセキュリティ ・パスワードレス認証 ・「Webプロキシ」とは何か? ・犯罪に悪用される「AirTag」 ・デジタルサービス法
エンジニア必携!ヤマハネットワーク構築・運用の標準教科書 本書はネットワークの構築・運用に必要な技術や設定について学習される方を対象としています。また、ヤマハネットワーク技術者認定試験[YCNE(Yamaha Certified Network Engineer) Standard★★]に対応しています。 IPアドレス、サブネット、VLANなどの基礎を理解している前提として、ネットワークの構築と運用で必要となる技術や設定、およびセキュリティを中心に説明しています。 最初は、RIPやOSPF、VRRPなど構築に必須の技術、NTPやSNMPなど運用に必須の技術について説明します。そしてヤマハネットワーク機器でつくるネットワーク構成の例を示し、これらの技術を使った設計の検討内容や設定について、シミュレーション形式で説明します。LAN分割機能、マルチプルVLAN、QoS、L2MSなど構築と運用で利用する多くの機能と設定について、またネットワーク構築には"セキュリティ対策"も必須となるため、フィルタリングやVPN、認証といったセキュリティ関連の機能と設定についても説明していきます。 本書を読むことでヤマハネットワークの構築・運用に必要な技術や設定について理解が深まるとともに、YCNE Standard★★試験合格の近道となることを願っています。 1章 ネットワークを構築・運用する上での必須技術 1.1 通信の基本 1.2 ルーティング関連技術 1.3 RIPv1 1.4 RIPv2 1.5 OSPF 1.6 冗長化技術 1.7 ICMP関連技術 1.8 運用管理関連技術 1章のチェックポイント 2章 中規模ネットワークの構築 2.1 ネットワーク構成 2.2 初期設定 2.3 インターネット接続設定 2.4 VLANの設定 2.5 スパニングツリープロトコルの設定 2.6 OSPFの設定 2.7 VRRPの設定 2.8 拠点間接続VPNの設定 2.9 無線LANアクセスポイントの設定 2.10 ルーターやLANスイッチへのアクセス設定 2.11 設定の保存 2章のチェックポイント 3章 要件に合わせたネットワークの構築 3.1 ポート関連技術 3.2 ルーティング関連技術 3.3 インターネット接続関連技術 3.4 QoS 3.5 無線LAN関連技術 3章のチェックポイント 4章 ネットワーク運用管理 4.1 SNMPの設定 4.2 NTPの設定 4.3 Syslogの設定 4.4 ループ検出機能の設定 4.5 L2MS 4.6 LANマップ 4.7 無線LANの可視化 4.8 クラスター管理機能 4.9 YNOによるネットワーク統合管理 4章のチェックポイント 5章 セキュリティ 5.1 セキュリティの基本 5.2 入口対策 5.3 TLSを使った暗号化 5.4 VPNのセキュリティ技術 5.5 VPNの種類 5.6 ポート認証機能 5.7 ヤマハルーターのセキュリティ機能設定 5.8 ヤマハLANスイッチのセキュリティ機能設定 5.9 ヤマハ無線LANアクセスポイントのセキュリティ機能設定 5.10 UTM 5章のチェックポイント 参考情報 1 フレーム構造 参考情報 2 パケット構造 参考情報 3 TCPの構造 参考情報 4 UDPの構造
本書は、LPICのレベル1試験がVersion4.0から5.0にアップデートされたことに対応した学習書です。内容はLPI-incの認定テキストに基づき、101試験と102試験に対応しています。章ごとに練習問題や模擬試験を収録し、Linux実習環境も提供されています。LPIC試験の対策やLinux学習に役立つ一冊です。
「ネットワーク」に関するよくある質問
Q. 「ネットワーク」の本を選ぶポイントは?
A. 「ネットワーク」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「ネットワーク」本は?
A. 当サイトのランキングでは『[改訂新版] 3分間ネットワーク基礎講座』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで165冊の中から厳選しています。
Q. 「ネットワーク」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「ネットワーク」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『[改訂新版] 3分間ネットワーク基礎講座』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51oegv0Zi4L._SL500_.jpg)



![『シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ePkoEBL5L._SL500_.jpg)









![『(模擬問題、スマホ問題集付き)徹底攻略Cisco CCNA問題集[200-301 CCNA]対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/516N+slMSrL._SL500_.jpg)



』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/512hiIloWGL._SL500_.jpg)









![『[試して理解]Linuxのしくみ ~実験と図解で学ぶOSとハードウェアの基礎知識』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51r+eNsY2fL._SL500_.jpg)















![『ゼロトラストネットワーク[実践]入門』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH8GD2qQL._SL500_.jpg)













』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51--VB2W0WL._SL500_.jpg)



![『[試して理解]Linuxのしくみ ―実験と図解で学ぶOS、仮想マシン、コンテナの基礎知識【増補改訂版】』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51CKe00bsfL._SL500_.jpg)


![『(スマホ問題集付)徹底攻略 Cisco CCENT/CCNA Routing & Switching 教科書 ICND1 編[100-105J][200-125J]V3.0 対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51lFlJSle7L._SL500_.jpg)





![『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UB6ayAOaL._SL500_.jpg)

![『(スマホ問題集付)徹底攻略Cisco CCENT/CCNA Routing&Switching問題集 ICND1編[100-105J][200-125J]V3.0対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51mWPp--DoL._SL500_.jpg)











![『(スマホ問題集付)徹底攻略Cisco CCNA Routing & Switching教科書 ICND2編[200-105J][200-125J]V3.0対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Kvt7ga1OL._SL500_.jpg)


![『(スマホ問題集付)徹底攻略 Cisco CCNA Routing&Switching問題集ICND2編[200-105J][200-125J]V3.0対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ngzQD108L._SL500_.jpg)


![『徹底攻略Cisco CCNP Routing & Switching SWITCH教科書[300-115J]対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51gxE1GNQyL._SL500_.jpg)
![『徹底攻略 Cisco CCNP Routing & Switching SWITCH 問題集[300-115J]対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51HGxUcToKL._SL500_.jpg)




![『[左門式ネスペ塾]手を動かして理解する ネスペ「ワークブック」 (情報処理技術者試験)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y4DNhka5L._SL500_.jpg)



![『徹底攻略Cisco CCNP Routing & Switching ROUTE教科書[300-101J]対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51VfFXexRJL._SL500_.jpg)
![『TCP/IP&ネットワークコマンド入門 ──プロトコルとインターネット、基本の力[Linux/Windows/macOS対応] (Tech × Books plusシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41xJ48ROY4L._SL500_.jpg)

![『クラウドエンジニア養成読本[クラウドを武器にするための知識&実例満載! ] (Software Design plusシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/61fVpJ0Dd0L._SL500_.jpg)




![『徹底攻略Cisco CCNP Routing & Switching ROUTE問題集[300-101J]対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51BLkhXnL4L._SL500_.jpg)
![『エキスパートのためのMySQL[運用+管理]トラブルシューティングガイド』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41IlBoZCfcL._SL500_.jpg)



![『[第3版] Cisco LANスイッチ教科書』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51-AaxWKj0L._SL500_.jpg)


![『シスコ技術者認定教科書 CCNP Routing and Switching TSHOOT テキスト&問題集 [対応試験]300-135J』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51iKSLgsHcL._SL500_.jpg)
![『徹底攻略 Cisco CCNP Routing & Switching TSHOOT 問題集[300-135J]対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51X0ydLX9jL._SL500_.jpg)
![『Ciscoネットワーク構築教科書[設定編]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/513JJFEGUYL._SL500_.jpg)
























![『シスコ技術者認定教科書 CCNP Routing and Switching SWITCH テキスト&問題集 [対応試験]300-115J』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51kamjnNI-L._SL500_.jpg)





![『Raspberry Pi はじめてガイド―[Raspberry Pi 4完全対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51iYMy4OrQL._SL500_.jpg)








![『シスコ技術者認定教科書 CCNP Routing and Switching ROUTE テキスト&問題集[対応試験]300-101J』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51HXWLdSiXL._SL500_.jpg)



![『ヤマハルーター&スイッチによるネットワーク構築 標準教科書 [YCNE Standard★★対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41X5e3Rw0vL._SL500_.jpg)