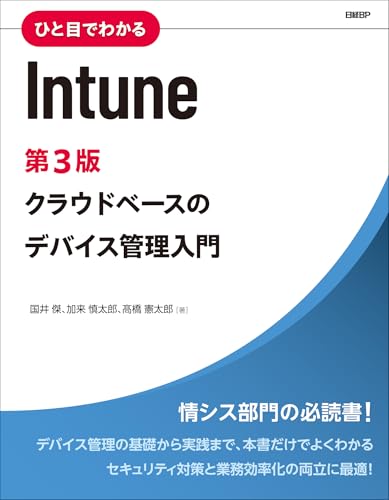【2025年】「システム設計」のおすすめ 本 162選!人気ランキング
- システム設計のセオリー --ユーザー要求を正しく実装へつなぐ
- はじめての設計をやり抜くための本 第2版 概念モデリングからアプリケーション、データベース、アーキテクチャ設計、アジャイル開発まで
- ソフトウェアアーキテクチャの基礎 ―エンジニアリングに基づく体系的アプローチ
- 1週間でシステム開発の基礎が学べる本 (1週間で基礎が学べるシリーズ)
- リーダブルコード ―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック (Theory in practice)
- 現場で役立つシステム設計の原則 ~変更を楽で安全にするオブジェクト指向の実践技法
- 良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門 ―保守しやすい 成長し続けるコードの書き方
- 図解即戦力 システム設計のセオリーと実践⽅法がこれ1冊でしっかりわかる教科書
- エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計 (IT Architects’Archive ソフトウェア開発の実践)
- この1冊ですべてわかる 新版 SEの基本
本書は、情報システムの設計手順を体系化し、ユーザーと開発チームをつなぐ方法を明示します。各工程の目的や作業内容を示しながら、データ、業務プロセス、画面UIの設計を「概要定義から詳細定義へ」「論理設計から物理設計へ」と進める手順を説明します。特定の開発手法に依存せず、実装技術や環境変化に左右されない原理原則を実践に即して解説しています。著者はシステム設計や業務改革に携わる専門家です。
本書は、システム開発における設計の基本知識を解説した14年ぶりのリニューアル版です。エンジニアが「はじめての設計」に挑戦する際の課題(アプリケーション設計、データベース設計、画面設計、外部システム接続、アーキテクチャ設計)を事例を交えて紹介し、実践的なノウハウを提供します。また、アジャイルやマイクロサービスに関する新しい情報も追加されています。若手エンジニアのステップアップやリーダーシップ向上を目指す一冊です。
本書は、ソフトウェアアーキテクチャの重要性と、効果的なアーキテクチャを設計・構築・維持するためのスキルや知識を現代的視点から解説しています。内容は、アーキテクチャの基礎、アーキテクトの役割、アーキテクチャスタイル、チームとのコラボレーションに必要なソフトスキルなど多岐にわたり、実践的な例を交えて説明されています。著者は経験豊富なアーキテクトたちで、読者がソフトウェアアーキテクトとして成長するための道筋を示しています。
本書は、初心者向けのシステム開発解説書で、発注者と受注者の視点を両方考慮し、システム開発の全体像を理解するための基礎知識を提供します。関係者間の認識のズレを解消し、円滑な連携を促進することを目的としています。内容は、1週間でシステム開発の重要な局面や注意点を学べるよう構成されています。システム開発初心者にとって、役立つ一冊です。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
システム開発の上流工程の1つである、システム設計にスポットを当てた入門書です。システム設計を大きくアプリケーション設計とインフラ設計の2つに分類し、各分類における設計内容を軸に、実践のポイントや注意点などを紹介しました。関係者間で共通の認識を持って開発を進め、システムの品質を高められるようになるはずです。また、設計書の活用方法についても解説されているので、メンテナンスも効率的にできるようになるでしょう。 CHAPTER1 「システム設計」の位置付け Section 01 本書の前提とシステム「開発」の全体像 Section 02 「要件定義」とは Section 03 「設計」とは Section 04 「開発テスト」とは Section 05 「リリース」とは Section 06 「保守・運用」とは COLUMN どの工程にどれくらいリソース(工数)が必要なの? CHAPTER2 「システム設計」とは Section 07 本書における「システム設計」の整理方法 Section 08 設計書を作成する理由 Section 09 設計書の種類 Section 10 「全体設計」の概要 Section 11 「入出力設計」の概要 Section 12 「データベース設計」の概要 Section 13 「ロジック設計」の概要 Section 14 「ネットワーク設計」の概要 Section 15 「サーバ設計」の概要 COLUMN システム設計は広く、深い CHAPTER3 「システム設計」 に影響する考え Section 16 ソフトウェア設計モデル Section 17 フレームワーク Section 18 社外要因・社内要因 Section 19 オンプレミスとクラウド Section 20 仮想化技術 Section 21 ミドルウェア COLUMN ソフトウェアを作るのは勉強も必要だが、本来は楽しいもの CHAPTER4 全体設計 Section 22 全体設計の流れとポイント Section 23 システムアーキテクチャ設計 Section 24 信頼性・安全性設計(全体編) Section 25 環境設計(全体編) Section 26 性能設計(全体編) Section 27 セキュリティ設計(全体編) Section 28 運用方式設計(全体編) Section 29 外部接続方式設計(全体編) Section 30 標準化設計 Section 31 テスト方式設計(全体編) Section 32 移行方式設計(全体編) COLUMN こんなにも全体設計が必要なの? CHAPTER5 入出力設計 Section 33 設計書一覧 Section 34 画面系:画面一覧 Section 35 画面系:画面遷移図 Section 36 画面系:画面共通設計 Section 37 画面系:画面レイアウト Section 38 画面系:画面入力設計 Section 39 帳票系:帳票レイアウト Section 40 IF系:外部接続先一覧 Section 41 IF系:外部接続方式設計 Section 42 IF系:IFレイアウト Section 43 その他:送信メール設計 COLUMN 入出力設計は、システム知見に加えてコミュニケーション力が必要 CHAPTER6 データベース設計 Section 44 設計書一覧 Section 45 ボリューム一覧 Section 46 RDB:データベース設定 Section 47 RDB:ER図 Section 48 RDB:テーブルレイアウト Section 49 ファイル:ファイル設計 COLUMN データベース設計といえば、まずはRDBです CHAPTER7 ロジック設計 Section 50 設計書一覧 Section 51 ユースケース図 Section 52 アクティビティ図 Section 53 クラス図 Section 54 シーケンス図 Section 55 処理フロー図(フローチャート) Section 56 状態遷移設計 Section 57 バッチ全体設計 Section 58 処理設計(プログラム仕様書) COLUMN システム構築には「システムならではの考え方」や「業界特有の知識」が必要 CHAPTER8 ネットワーク設計 Section 59 設計書一覧 Section 60 ネットワーク全体構成図(物理構成) Section 61 ネットワーク全体構成図(論理構成) Section 62 ネットワーク提供サービス一覧 Section 63 通信要件一覧 Section 64 IPアドレス設計 Section 65 ネットワークサービス設計 Section 66 FW(ファイアーウォール)ルール設定方針書 Section 67 流量制御設計 COLUMN ネットワークの基礎はOSI参照モデルを知るのが早い CHAPTER9 サーバ設計 Section 68 設計書一覧 Section 69 サーバ仕様設計 Section 70 仮想化設計 Section 71 サーバプロダクト構成書 Section 72 サーバ稼働サービス一覧 Section 73 サーバ設定仕様書 Section 74 サーバ構築手順書(クラウド編) Section 75 サーバ運用設計 Section 76 障害対応手順書 COLUMN サーバ設計ができれば、たいていはなんとかなる CHAPTER10 設計書の活用 Section 77 設計書は開発のためだけではない Section 78 設計書は継続したメンテナンスが重要 Section 79 設計書は影響調査に使用する Section 80 設計書はシステムの品質を高めるために使用する Section 81 設計書は教育に使用する Section 82 設計書は移行の元ネタに使用する COLUMN 設計書は不要、という暴論
この文章は、エリック・エヴァンスの著書に関する目次と著者情報を紹介しています。目次は、ドメインモデルの機能、モデル駆動設計の要素、リファクタリングの深い洞察、戦略的設計の4部構成で、各部での主要なテーマが列挙されています。著者は、ビジネスとソフトウェア構築に関する専門家や技術コンサルタントであり、各自の経歴や専門分野も述べられています。
この書籍は、システムエンジニア(SE)として成功するために必要な知識とスキルをまとめた必読書です。テクニカルスキルやマネジメントスキル、コミュニケーション術、炎上プロジェクトへの対処法などが解説されており、特にIoTやAIの活用に焦点を当てています。著者は、SEの活動領域が広がる中で求められる発想力や戦略立案術、柔軟性についても触れています。全体を通じて、SEとしての心構えや人間力の重要性が強調されています。
この本は、著名なIT企業でのシステム設計の面接対策を目的とした攻略本で、実務にも役立つ内容が含まれています。目次には、ユーザ数のスケールアップや各種システムの設計方法(レートリミッター、キーバリューストア、通知システムなど)が詳しく解説されています。著者のアレックス・シュウは、複雑なシステムの設計に情熱を持つ経験豊富なソフトウェアエンジニアです。
本書は、Webサービスの実践的な設計に焦点を当てています。HTTPやURI、HTMLの仕様を歴史や設計思想とともに解説し、Webサービスにおける設計課題やベストプラクティスを紹介しています。目次は、Web概論、URI、HTTP、ハイパーメディアフォーマット、Webサービスの設計、付録から構成されています。
本書『マスタリングTCP/IP 入門編 第6版』は、TCP/IPに関する解説書の最新版で、時代に即したトピックを追加し内容を刷新しています。豊富な図版や脚注を用いて、TCP/IPの基本をわかりやすく解説しており、ネットワークやインターネットプロトコルの理解を深めるための入門書として最適です。著者は複数の専門家で構成されています。
本書は、IT業界におけるシステム設計の重要性を解説し、特に「要件定義」の重要性を強調しています。システムを効果的に構築するための「UI・機能・データ」の三点セットを「クライアント・サーバ・DB」の三層構造に配置する方法を学びます。また、業務改善や最新技術の活用に向けたプロセス設計の重要性も取り上げ、具体的な手法や実務に役立つ知識を提供しています。システム設計の基礎から応用までを体系的に学べる内容です。
本書はテスト駆動開発(TDD)の実践方法を解説した日本語版で、原著者Kent Beckによる内容を和田卓人が翻訳しています。TDDは単なるテスト自動化ではなく、ユニットテストとリファクタリングを組み合わせた手法で、設計の進化を促進します。書籍は多国通貨オブジェクトやxUnitの例題を通じてTDDの原理とパターンを学ぶ構成になっています。
本書は、サーバやインフラの運用・管理に必要な技術や知識を基礎から解説した教科書です。ネットワークやサーバの基本知識に加え、クラウド関連の知識やエンジニアとしての考え方、学習法、スキルアップ、業務知識、職業倫理も取り上げています。これからサーバ/インフラエンジニアを目指す人に適した内容となっています。目次には、エンジニアとしての生き方、ネットワーク、インターネット、サーバ、仮想化、ミドルウェア、Webサービス運用、セキュリティ、クラウド、法律・ライセンスの基礎知識が含まれています。著者は馬場俊彰氏で、豊富な実務経験を持つエンジニアです。
本書は、システム化企画や要件定義、基本設計などの上流工程に必要なスキルや心構えについて解説しています。単に実装スキルだけでなく、議論をリードし、関係者の合意を得る能力、全体を見通す視点が求められます。上流工程を初めて行う際の準備やスキルアップ方法についても具体的なアドバイスが提供されています。著者は、システム開発の専門家であり、若手エンジニアの育成に力を入れています。
『デザインパターン』の23個のパターンをオブジェクト指向初心者向けに解説した書籍で、Javaのサンプルプログラムを掲載。新たに「デザインパターンQ&A」も追加されている。目次はデザインパターンの基本から、サブクラスの利用、インスタンス作成、構造管理など多岐にわたる。
『オブジェクト指向でなぜつくるのか』の改訂第3版は、オブジェクト指向プログラミング(OOP)の基本と最新動向をわかりやすく解説しています。著者は、OOPの全体像、プログラミング言語の歴史、アジャイル開発手法などについて触れ、特に人気のある言語(Java、Python、Ruby、JavaScript)の情報も更新されています。読者は、OOPがソフトウェア開発においてどのように役立つかを学び、実践的な知識を得ることができます。
本書は、ソフトウェアアーキテクチャの普遍的なルールについて解説しています。プログラムの構成要素の組み立て方に焦点を当て、プログラミングパラダイム、設計原則、コンポーネントの原則、アーキテクチャの詳細を紹介しています。目次にはイントロダクションから付録までの各部が含まれています。
本書は、システムに詳しくない業務担当者向けに、企業のDX推進に必要なノウハウを解説した教科書です。システムを自ら作れなくても、他者に作ってもらうための技術や判断力が求められる時代において、具体的なプロセスや注意点を示します。内容は、システム構築の計画から実施までの各ステップを網羅しており、著者の実践的な経験に基づく事例も紹介されています。
『プリンシプル オブ プログラミング』は、プログラマーが3年目までに身につけるべき101の原理原則を紹介するガイドブックです。KISSやブルックスの法則など、古今東西の知恵を集約し、質の高いプログラミングを実現するための基本的な考え方や手法をわかりやすく解説しています。初心者から脱却したいプログラマーに最適な一冊です。著者は上田勲で、キヤノンITソリューションズでの豊富な経験を持っています。
本書『アジャイルサムライ』は、ソフトウェア開発におけるアジャイル手法を紹介しており、顧客に価値を提供するプロフェッショナルとしてのアプローチを解説しています。内容はアジャイルの基本、方向づけ、計画、プロジェクト運営、プログラミングに関する各部に分かれており、著者は実務経験豊かなアジャイルコーチたちです。
本書『JavaScript』は、最も広く使用されているプログラミング言語であるJavaScriptを包括的に解説したもので、第6版から大幅に加筆・更新されています。基本的な構文や機能、標準ライブラリ、クライアントサイドおよびサーバサイドのJavaScriptについて詳しく説明し、非同期プログラミングやクラスの定義方法、モジュールの使い方なども紹介しています。開発者にとって必携の一冊です。著者はJavaScriptの専門家であり、プログラミングの基礎から応用まで幅広くカバーしています。
本書は、Web系エンジニアを含む全てのエンジニアに向けて、企業情報システムの設計に関する実践的なノウハウを提供する。16の視点から80の重要ポイントを解説し、データモデリングや業務設計、スコープ決定、ユーザーヒアリングなど、システム設計の本質を探求する内容。特に、顧客の要件やプロジェクト管理に関する具体的なアドバイスが盛り込まれており、エンタープライズシステムを成功に導くための知識が得られる。
本書は、マイクロサービスに関する包括的な解説書で、システム分割や設計、プロセス間通信、トランザクション、データベース、テスト、デプロイなど多岐にわたる側面を詳述しています。具体的なパターンとフードサービスのサンプルプロジェクトを通じて、実践的なノウハウを提供。著者はマイクロサービスの専門家であり、Javaを用いた豊富なサンプルで、成功するマイクロサービスの実装方法を解説しています。
この本は、iOSプログラミング初心者向けの詳細な入門書であり、プログラミング経験がゼロでも理解できるように丁寧に解説されています。Swiftとアプリ開発の基本を習得できる内容で、Xcode 11やiOS 13.5、SwiftUIに対応しています。アプリ開発は副業にも最適で、リスクなく始められ、収益を上げる方法も紹介されています。著者はiPhoneアプリ開発の経験が豊富で、数々の成功作を持っています。
本書は、企業や組織におけるシステム開発のための設計書の作成と運用手順を解説しています。「組織でシステムを作る」をテーマに、クラウドやアジャイル開発などの現代の要素を取り入れた実践的なシステム構築法を紹介。元々はインプレスのWeb連載記事を基に書籍化され、大幅に加筆・修正されています。目次にはリスク管理やドキュメントの体系、データモデリングなどが含まれています。著者はシステムインテグレータの代表取締役社長、梅田弘之氏です。
先を制してライバル企業に勝つためのポイントとは?決算を早期化して利益を稼ぎだすには?業務改革で会社をよみがえらせるには?最高のシステムをつくるための「亀のコウラ」とは?ベンチャーから中堅企業まで50社以上、業務設計・改善から会計監査さらにIPO支援まで20年近いコンサルティング実績を誇る「公認会計士兼システムコンサルタント」という異色の著者だからこそ書ける成功のノウハウが満載! 第1章 「稼げるシステム」と「稼げないシステム」の分かれ道はどこにあるのか? 第2章 先を制してライバル企業に勝つ"経営の視点" 第3章 決算を早期化して利益を稼ぎ出す"会計の視点" 第4章 業務改革で会社をよみがえらせる"業務の視点" 第5章 正しい知識で最高のシステムをつくる"システムの視点" 第6章 プロジェクトを成功に導き、会社を飛躍させよう
本書は、IT担当者や情報システム部門向けに、システム発注から導入に関するノウハウを提供します。著者は、システム導入の失敗はユーザー企業の力量不足が原因であると指摘し、経験が体系化されていないことが問題だと述べています。具体的には、ITプロジェクトの企画提案、要件定義、ユーザー受入テスト、教育、運用・保守に関するルールやノウハウを解説し、プロジェクトの主導権をユーザー企業が取り戻すための方法を示しています。著者はITコンサルタントとしての経験を活かし、実践的な知識を提供しています。
本書は、2014年に提唱された「マイクロサービス」について、中立的な立場からその仕組みや特徴、長所、短所、課題を詳しく解説しています。著者はThoughtworksでの実体験を基に、技術的側面だけでなく組織の生産性向上に関する知見も提供。信頼性や柔軟性に優れたシステム設計の指針となる内容です。目次は基礎、実装、人に分かれており、マイクロサービスの理解を深める構成になっています。
本書は、ソフトウェアアーキテクチャにおけるトレードオフ分析の重要性を解説し、状況に応じた選択を行うための実践的なアプローチを提供します。サービスの粒度やデータの所有権、コードの再利用、可用性などの課題に対して、モノリスからマイクロサービスへの移行例を通じて具体的な解決策を示します。著者たちは、現代のソフトウェア開発者にとって必携の知識を伝えることを目指しています。
本書は、インフラエンジニアに必要な知識やスキル、業務内容、労働環境、キャリアパスを詳しく解説しています。ITインフラの基礎から、インフラ設計・構築・運用の流れ、求人状況、働き方まで幅広くカバーしており、転職や就職を考える人にとって役立つ情報が満載です。豊富な図解を交え、インフラエンジニアの仕事を包括的に理解できる内容となっています。
本書は、メタバースの可能性や影響を探るルポルタージュで、特にソーシャルVRに焦点を当てています。著者は仮想現実の住人として、メタバースが人間の文化やアイデンティティ、コミュニケーション、経済に与える影響を考察します。前半ではソーシャルVRサービスや関連技術を解説し、後半ではユーザーの経験や調査結果を基に、メタバースがもたらす変化を論じます。メタバースは新たな人間社会の形成を促進し、物理的制約から解放される可能性を示唆しています。
本書では、統計学があらゆる学問の中で最強である理由を解説し、現代社会におけるその重要性や影響力を最新の事例を通じて探求しています。著者は、統計学の基本概念や手法(サンプリング、誤差、因果関係、ランダム化など)を紹介し、統計学の魅力とパワフルさを伝えます。著者は東京大学出身の専門家で、データを活用した社会イノベーションに取り組んでいます。
学生の時にこの書籍を読んで統計学に興味を持った。統計学の魅力について分かりやすく学べる書籍。専門的な内容はそれほどないのでスラスラ読める。統計学ってどんなことができるの?なんでそんなにすごいの?ということを知りたい人がまず最初に読むべき本。
『達人に学ぶSQL徹底指南書』の第2版は、SQLを扱うエンジニア必携の書で、10年ぶりの改訂を経て、最新のSQL機能や実践的なコーディング事例を多数紹介しています。ウィンドウ関数やCASE式、外部結合などの重要なトピックを詳しく解説し、標準SQLに基づいて多様なデータベースに対応しています。また、リレーショナルデータベースの歴史や原理についても触れています。SQLを深く理解したいエンジニアやプログラマにおすすめの一冊です。
本書は競技プログラミング(競プロ)に必要なアルゴリズムやデータ構造、考察テクニックを詳しく解説し、150問以上の演習問題を通じて知識を定着させることを目的としています。77個のテクニックを網羅し、320点以上の図で理解を助ける内容で、全問題は自動採点システムに対応しています。著者は国際情報オリンピックで金メダルを三度獲得した実績を持つ米田優峻氏です。
この書籍は、Webアプリ開発者向けに脆弱性の原因と対処法を解説したベストセラーの改訂版です。最新のOWASP Top 10 - 2017に対応し、HTML5やJavaScriptに関する新たな解説を追加しています。脆弱性診断の入門章も設けられ、実習環境はWindowsとMac両方に対応しています。著者はWebアプリケーションのセキュリティに関する専門家で、脆弱性診断やコンサルティングを行っています。
この書籍は、ネットワーク構築に必要な基礎技術と設計ポイントを400以上の図を用いて解説したベストセラーの改訂版です。新たに高速化設計や最適化設計に関する内容が追加され、クラウドとオンプレミスの共存環境に対応しています。主な改訂点には、高速ネットワーク技術や仮想化設計手法、分かりやすい解説が含まれています。ネットワーク技術の基本から実務ノウハウまでを網羅した一冊です。著者はシステムエンジニアおよびネットワークコンサルタントとしての経験を持っています。
この書籍は、データベース設計やアプリケーション開発におけるアンチパターンを紹介し、失敗を避けるための改善策を提案しています。内容はデータベース論理設計、物理設計、クエリ、アプリケーション開発の4つのカテゴリに分かれており、複数の値を持つ属性や再帰的なツリー構造、小数値の丸め、SQLインジェクションなどの実践的な問題を扱っています。著者はソフトウェアエンジニアやデータモデリングの専門家で構成されています。
『新版暗号技術入門』の改訂版は、2008年の刊行以来セキュリティ関連で人気を保ち続けている書籍です。暗号技術の基本を図解と易しい文章で解説し、対称暗号や公開鍵暗号、デジタル署名などを取り上げています。第3版では、現代の暗号技術に関する最新情報や、SHA-3、SSL/TLSへの攻撃、ビットコインとの関係などが加筆されています。全ての人にとって必読の内容で、暗号の歴史から応用技術まで幅広くカバーしています。
本書は、深層学習に関する改訂版のベストセラーで、トランスフォーマーやグラフニューラルネットワーク、生成モデルなどの手法を詳しく解説しています。著者は、理論的な証明がなくても納得できる説明を重視し、実用性を考慮した内容を提供。全12章で、基本構造から各種学習方法、データが少ない場合の対策まで幅広く網羅しています。著者は東北大学の教授であり、実務家との共同研究の経験も反映されています。
この書籍は、プロジェクト管理手法「スクラム」の創始者であるジェフ・サザーランドが、効果的なチーム運営法を解説しています。スクラムは、ソフトウェア開発をはじめ、住宅リフォームや宇宙船の開発など多岐にわたる分野で革命を起こし、納期や予算の問題を解決する方法を提供します。著者は、最小限の時間と労力で最大の成果を出すための具体的な実践方法を伝授しています。
本書は、JavaScriptの基礎から実践的な知識までを網羅しており、プログラミング初心者でも現場で役立つスキルを身につけられる内容です。目次には、導入編、基本編(変数、関数、オブジェクト指向など)、実践編(Webページ作成)、応用編(フレームワーク)などが含まれています。著者は技術書やゲーム開発に携わる柳井政和氏です。
『独習Python』は、プログラミング初学者向けのPython入門書で、著者は山田祥寛氏です。本書は、手を動かして学ぶスタイルを重視し、Pythonの基本から応用までを体系的に学べる内容となっています。解説、例題、理解度チェックの3ステップで、基礎知識がない人でも理解しやすい構成です。プログラミング初心者や再入門者におすすめの一冊です。目次には、Pythonの基本、演算子、制御構文、標準ライブラリ、ユーザー定義関数、オブジェクト指向構文などが含まれています。
Pythonをしっかり学びたい人向けの本格的な入門書です。基礎から応用まで幅広いトピックをカバーしており、実際に手を動かしながら理解を深められるよう工夫されています。独習スタイルに特化しているため、自分のペースで着実に学びたい人におすすめ。豊富なコード例や練習問題もあり、プログラミングの実力を着実に高めることができます。
本書は、日本の著名なITアーキテクトである著者が、30年の経験を基にエンタープライズアーキテクチャ(EA)の実践手法を解説しています。特に「EAの中心に全社データHUBを据える」という考え方が中心テーマで、ITマネジメント賞を受賞したアーキテクチャの全貌が紹介されています。内容は、問題の所在や課題、アーキテクチャの各要素、戦略・戦術ソリューションに分かれており、ユーザ企業やITベンダにとって貴重な知識となるでしょう。著者は協和発酵キリンでの豊富な経験を持ち、システム構築に貢献してきました。
本書は、システム開発における生成AIの活用方法を解説したもので、問題の明確化から実装、運用までの各ステップにおいてAIがどのように支援できるかを説明しています。著者の酒匂寛は、長年のソフトウェア開発経験を基に、AIを用いた効率的な問題解決手法を提案しています。目次には、課題探求や仕様策定、設計・実装、検証などの章が含まれています。
本書は、Webシステムの信頼性を確保する「サイトリライアビリティエンジニアリング(SRE)」について、個人がSREになる方法や組織がSREを導入・発展させるための指針を解説しています。著者は40年の経験を持つ専門家で、SREの基本概念や実践的なアドバイスを提供。SREに興味があるエンジニアや、導入を検討または実施している組織にとって有益な内容となっています。
本書は新人SEやアプリケーションエンジニア向けのシステム方式設計入門書で、マンガと図解を使用して理解を助けています。ITアーキテクトとアプリケーションエンジニアの分業が進む中、方式設計の知識不足が問題を引き起こしているため、全てのSEがこの知識を持つことが重要とされています。内容は画面設計とDB性能に関するポイントを解説しており、具体的な事例を通じて学ぶことができます。
この本は、プログラミング初心者向けに、PHPとMySQLを楽しく学べる方法を提供しています。秋葉原での速習コースを基に、挫折しやすいポイントを分析し、1日でWeb画面と簡単なデータベースを作成できる内容です。目次には心の準備、パソコン設定、プログラミング、データベースの各章があり、著者は豊富な経験を持つ谷藤賢一氏です。
本書は、プログラマー向けのソフトウェアアーキテクティング入門書で、ソフトウェアアーキテクチャの基礎やデザイン思考を解説しています。読者は、ステークホルダーのニーズ理解、技術選定、アーキテクチャ評価、チームのアーキテクト力向上などを学ぶことができます。実践的な設計手法を38のアクティビティとして紹介しており、より良いプログラマーや技術リーダーになるための必携の一冊です。
この書籍は、中小企業向けにサイバーセキュリティ対策をわかりやすく解説したもので、知識がない人でも理解できる内容です。サイバー攻撃の手口や被害事例、具体的な対策(不正送金、情報漏えい、ネット詐欺、ウイルスなど)を紹介しており、マイナンバー制度への対応も含まれています。著者はサイバーセキュリティの専門家で、中小企業向けの啓蒙活動を行っています。
この書籍は、上流工程の重要な局面である「基本設計」に焦点を当て、実用的なモデリングパターンや避けるべきアンチパターンを豊富な用例と共に解説しています。内容は、上流工程の困難、進め方、基本設計の概要、モデリングパターンの具体例などで構成されています。著者は新潟出身の渡辺幸三で、業務支援システムの設計・開発に従事しています。
この書籍は、大規模サービスの開発と運用に関する技術者向けの入門書です。内容は、OSや計算機の動作原理、DBの分散方法、実践的アルゴリズムの実装、大規模データ処理の検索エンジンの仕組み、インフラ設計など多岐にわたります。著者は、はてなの技術責任者である伊藤直也と、情報学博士の田中慎司です。
本書『新人エンジニア向け教科書』第3版は、システム開発の基礎知識をゼロから解説する入門書です。新人エンジニアや学生を対象に、ウォータフォール型とアジャイル型の開発手法の特徴や違いを学べる内容となっており、アジャイル型開発の解説が大幅に加筆されています。また、開発過程での文書作成手順や演習課題も用意されており、現役エンジニアや研修担当者にも役立つ一冊です。
この書籍は、アーキテクチャ設計における判断の重要性を強調し、クラウドやビッグデータ、アジャイル開発の時代におけるITアーキテクトの思考と行動を支える原則と手法を体系化しています。内容は、アーキテクチャの基本、プロセス、ビューポイントとパースペクティブのカタログ、そしてソフトウェアアーキテクトとしての実務に関する章で構成されています。著者はIT業界の専門家であり、アーキテクチャ設計に関する豊富な経験を持っています。
本書は、NoCode(ノーコード)によるアプリ開発について、基礎知識や主要ツール「Glide」「Adalo」「Bubble」の使い方を詳しく解説しています。各ツールの特徴や実際の活用例を紹介し、巻末にはNoCodeの未来についての座談会も収録されています。著者はNoCodeエバンジェリストであり、専門のオンラインサロンを運営しています。
本書は、IoT(Internet of Things)システムの構築に関する基礎知識と実践的ノウハウを解説しています。著者陣は多様な業界でのIoTシステム開発に携わっており、ゼロからの構築だけでなく、既存システムを基にした構築も取り上げています。IoTはハードウェアとソフトウェアの両面での設計が求められ、多岐にわたる知識が必要です。目次にはデバイス選定、通信方式、クラウドサービス、セキュリティ設計、事例紹介などが含まれています。著者にはソラコムの技術者やIoT専門家が名を連ねています。
本書では、プロジェクトマネジメントにおける問題の根源は「不確実性」にあると指摘されています。プロジェクトは常に新しい挑戦であり、成功するための固定された進め方は存在しません。そのため、各プロジェクトに応じた「固有のプロセス」を設計する必要があります。この考え方を「プロセスデザインアプローチ」と呼び、著者が具体的な方法を解説しています。内容は、プロジェクトの本質、不確実性の管理、プロジェクトの全体像、計画や進捗管理の方法、振り返りの重要性など、幅広いテーマを扱っています。著者は、実行品質を高めるためのコンサルタントであり、実践的なアプローチを提供しています。
この書籍は、計算機の性能を最大限に引き出すためのプログラミングテクニックを紹介しています。基本ツールの使い方から、GCCの拡張機能、セキュアプログラミング、OSのシステムコールやインラインアセンブラを用いた高度な技術までを解説。著名なハッカーたちが集まり、低レイヤのプログラミング技術の活用法と楽しみ方を示しています。目次には、イントロダクションやオブジェクトファイルのハック、GNUプログラミング、セキュアプログラミングなどが含まれています。
本書は、現代の分散システム設計におけるデータの扱いに焦点を当て、リレーショナルデータベースやNoSQL、ストリーム処理などのテクノロジーの特性を詳述しています。データ指向アプリケーションの設計に必要な基本概念を解説し、レプリケーションやトランザクション、バッチ処理などの分散データの管理手法についても触れています。ソフトウェアエンジニアやアーキテクトにとって必携の一冊です。
本書は、経営計画と整合した情報システムの構築方法を紹介し、経営効果を高める手段としての重要性を強調しています。目次では、経営計画の実現から情報システム要件の立案、全体推進計画の策定までの具体的なフェーズが示されています。著者の柴崎知己は、システム戦略やITマネジメントに関する豊富な経験を持つ専門家です。
本書『データマネジメント知識体系ガイド第二版 改定新版』は、データの価値を引き出すための知識を包括的に解説しています。データの品質が企業活動において重要であり、正確なデータが意思決定や業務の自動化、未来予測を可能にします。全17章から成り、データの設計、運用、セキュリティ、ガバナンスなど多岐にわたるテーマが扱われています。2011年の初版から改訂され、最新のトピックや事例が追加されており、経営者やIT担当者など、各役割に応じた実践的な知識が得られます。
本書は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)におけるノーコードおよびローコード開発手法の重要性を解説しています。エンジニア不足の中、誰でも簡単にアプリケーションを開発できるノーコードのメリット・デメリット、導入方法、活用事例、ツールの種類や学習方法を紹介。著者はノーコードコンサルタントで、社会課題解決にITを活用するプロジェクトに関わっています。ノーコードは、企業の変革を促進する手段として注目されています。
この書籍は、Google Appsheet、Amazon Honeycode、Bubble、Thunkable、Clickといったノーコードツールを使ったアプリ開発方法を解説しており、実際にサンプルアプリを作成しながら学べる内容です。著者は、様々なプラットフォーム向けにプログラミング初心者向けの書籍を執筆している掌田津耶乃です。
この書籍は、実践的なGit/GitHubの使い方を学ぶための初心者向け入門書です。前半では基本的な操作を解説し、後半ではチーム開発のための知識を身につける内容となっています。コマンドライン操作が中心で、新しいGitコマンドやGitHubの機能、実務で役立つ慣習も紹介されています。著者はエンジニア経験を持つ専門家で、ワークショップ感覚で学べる構成になっています。
『Effective Java』の改訂第3版は、Javaプログラマー必読の書で、Java 8の新機能(ラムダ、ストリームなど)を含む90項目を扱っています。デザインパターンやイデオムを示すコード例が豊富で、Javaの正しい理解とソフトウェア設計に役立ちます。著者はJavaの重要な機能の設計に関わった専門家であり、技術教育にも力を入れています。
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
この入門書は、初学者や非プログラマー向けにプログラムの動作原理を「実習」と「講義」を通じて解説しています。内容はプログラミングの基本、コンピュータやOSの役割、プログラミング言語の基礎、JavaScriptやC言語の学習、オブジェクト指向モデリングなど多岐にわたります。著者は河村進氏で、実業界や研究機関での豊富な開発経験を持つ専門家です。
『これからはじめるプログラミング 基礎の基礎』の改訂第3版は、プログラミング入門者向けに書かれた定評ある書籍です。内容は現代の読者に合わせて見直され、プログラミング環境や言語もアップデートされています。目指すゴールは旧版と同じで、プログラミングの基本知識や実践的なステップを学ぶことができます。この本は、プログラミングを始める人にとっての「最初に読むべき入門書」とされています。
本書は、データ活用に悩む企業向けに、データ基盤の構築やデータ分析組織の立ち上げに必要なノウハウを提供します。データを集めても活用できない理由や、データ基盤が機能しない原因を解説し、適切なデータ整備や組織の構築方法を提案。著者たちはデータ活用のプロフェッショナルであり、実践的な知識を惜しみなく披露します。データ基盤を効果的に機能させたい方にとって、必読の一冊です。
本書は、UNIXのユニークなコマンド組み合わせ技術を学ぶためのガイドで、初心者から上級者まで多様な内容を含んでいます。各章では、ファイルシステム、シェルの利用、プログラミング、文書作成など、UNIXの基本から応用までを網羅しています。著者は、UNIXの知られざる機能に驚かされ、自身の知識を深めることができたと述べています。付録にはエディタの要約や関連マニュアルも含まれています。
本書は、Dockerを初めて触る新人エンジニアや非エンジニア向けに、Dockerの仕組みと使い方を分かりやすく解説しています。初心者が理解できるようにイラストを多用し、単にコマンドを使えるようになるのではなく、Dockerの基本的な動作原理を理解することを重視しています。内容はDocker Desktopを中心に構成されており、他の環境へのインストール方法も紹介されています。Dockerを長く使うための基礎力を身につけたい方に適した一冊です。
お金の力を正しく知って、思い通りの人生を手に入れよう。変化の時代のサバイバルツールとして世界中で読まれるベスト&ロングセラー オリエンタルラジオ 中田敦彦さん「YouTube大学」で紹介、大絶賛! □最初に読むべき「お金」の基本図書 毎年多くの「お金」に関する本が出版され,書店に並び、そして消えていきます。 そんな状況の中で、「金持ち父さんシリーズ」は刊行から20年経った今でも変わらず多くの支持を得ています。 その第1作目である『金持ち父さん 貧乏父さん』は、時代が変わっても古びない原理原則を示す「お金」の基本図書。 「目からウロコの連続でした! 」という声が絶えず寄せられ、これまで数多の人々の「お金観」を変えてきました。 日本やアメリカのみならず、本書が刊行された2013年時点で51ヶ国語に翻訳され、109ヶ国で読まれています。 教えの書―金持ち父さんの六つの教え 金持ちはお金のためには働かない お金の流れの読み方を学ぶ 自分のビジネスを持つ 会社を作って節税する 金持ちはお金を作り出す お金のためでなく学ぶために働く 実践の書 まず五つの障害を乗り越えよう スタートを切るための十のステップ 具体的な行動を始めるためのヒント
初めて買ったのは、10年ほど前でした、1回読んであまり感じることがないと思ってましたが、ある動画で推奨されたので、再度購入して読んでみました。2回3回と読むことで、自分の中に様々な気づきがあり。これがススメの理由なのか?と思いましたが、私はお金を稼ぐことに意識しすぎていることがそもそもの間違いで、1日100円でも貯めることで、そんな僅かでも時間をかけることで大変な資産になりそれが、富を生み出してくれると云ったことだと思います
お金を稼ぐよりも増やし方が印象に残っています。 賢く稼ぎ、より賢く増やす。 収入は僅かだとしても、日々の積み重ねと時間が 資産を増やしていくと云ったことでした。 誰が読んでも自分のモノにし易い、 内容であると思います。
「テストの教科書」は、初学者向けにソフトウェアテストの基礎から体系的に学べる内容の書籍です。丁寧な解説と平易な文章で、テストの基本的な考え方や5つのテスト技法を用いた欠陥の検出方法を紹介しています。目次には、ソフトウェアテストの基礎、さまざまなテスト技法、テストドキュメントとモニタリングが含まれています。著者は、ソフトウェアテストの専門家である石原一宏氏と田中英和氏です。
本書は、Pythonを用いたバイナリ解析技法とハッキングツールの概念を解説しています。読者は独自デバッガの構築やバグ発見ツールの作成、オープンソースライブラリの活用法などを学べます。日本語版では補足情報やリバースエンジニアリングに役立つツールの解説も加えられています。著者はセキュリティ研究員のジャスティン・サイツと、コンピュータシステムの専門家である安藤慶一です。
本書は、RESTというWebアーキテクチャスタイルについて詳しく解説した初の本格的な書籍です。RESTfulアーキテクチャの概念や特徴、リソース指向アーキテクチャの基本ルールを説明し、実際のRESTfulサービスの例を挙げながら設計方法を紹介しています。また、RESTの制約を満たしていないサービスの再設計方法も取り上げています。著者はリチャードソン、ルビー、山本陽平の3名で、それぞれの経歴も紹介されています。
SEの仕事の成否を分けるのは、コミュニケーションとマネジメントだった!業務システム開発の本質は「人」にあるということをいち早く見抜き、20年以上にわたって開発プロジェクトを次々に成功させてきた著者が、その成功の秘密を公開するSE必読の書。2006年の初版発行以来、増刷に増刷を重ね、No.1マニュアルとして全国のSEから絶賛されてきた『SEの教科書』が、続編『SEの教科書2』とあわせて改訂・完全版で登場。 第1部 成功するSEの考え方、仕事の進め方(SEの仕事は「人」が9割 失敗の原因はコミュニケーション不足 マネジメントが成否の鍵 コミュニケーション重視の会議術-準備編 コミュニケーション重視の会議術-実践編 プロジェクト初期段階の仕事術 成果物作成の仕事術 顧客業務分析の仕事術 設計・実装・テストの仕事術 プロジェクト運営の仕事術 業務システム開発は「伝言ゲーム」) 第2部 成功するSEのプロジェクト計画・運営術(名ばかりプロジェクトマネジメント 誤解がプロジェクトを破綻させる 上流工程はすべて計画活動 本当の計画、名ばかりの計画 ネットワーク図による計画作成術(アナログ式) ネットワーク図による計画作成術(デジタル式) ネットワーク図による計画の最適化 IT業界が日本を救う)
本書は、企業のIT担当者が必要とする基礎知識を解説しています。内容は、パソコンや周辺機器の調達、社内インフラの整備、情報セキュリティの強化、業務システムの導入、システム開発の外部委託に関する5章から構成されています。各章では、専門的な知識が求められるテーマを取り上げ、IT業務に携わる初心者向けに必要最低限の情報を提供しています。著者は、豊富な経験を持つエンジニアたちです。
今では色んなところで引用される人生100年時代というパスワードのきっかけになった書籍。もう既に1つの会社に勤め上げるような旧来の生き方は崩壊している。将来に不安を抱いているビジネスパーソンはこの本を読んで時代の変化に置いていかれないような生き方を選択して欲しい。
「システム設計」に関するよくある質問
Q. 「システム設計」の本を選ぶポイントは?
A. 「システム設計」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「システム設計」本は?
A. 当サイトのランキングでは『システム設計のセオリー --ユーザー要求を正しく実装へつなぐ』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで162冊の中から厳選しています。
Q. 「システム設計」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「システム設計」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。





























![『マイクロサービスパターン[実践的システムデザインのためのコード解説] (impress top gear)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ChNGhBinL._SL500_.jpg)



![『情シス・IT担当者[必携] システム発注から導入までを成功させる90の鉄則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51YKHxkX4jL._SL500_.jpg)

























![『JavaScript[完全]入門』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51X+EGiSlYL._SL500_.jpg)
















![『[Web開発者のための]大規模サービス技術入門 ―データ構造、メモリ、OS、DB、サーバ/インフラ (WEB+DB PRESS plusシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZIHuv5uIL._SL500_.jpg)













![『[改訂第2版] [入門+実践]要求を仕様化する技術・表現する技術 -仕様が書けていますか?』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51hV6os4M5L._SL500_.jpg)

![『28日で即戦力! サーバ技術者養成講座[改訂3版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51XaEgH9xfL._SL500_.jpg)






































![『闘うプログラマー[新装版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51kV6tOSplL._SL500_.jpg)