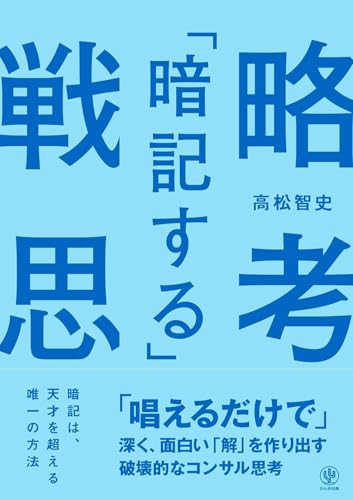【2025年】「コンサルティング」のおすすめ 本 179選!人気ランキング
- イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」
- コンサル一年目が学ぶこと 新人・就活生からベテラン社員まで一生役立つ究極のベーシックスキル30選
- 新版 考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則
- ロジカル・シンキング (Best solution)
- 外資系コンサルのスライド作成術―図解表現23のテクニック
- ロジカルシンキングを超える戦略思考 フェルミ推定の技術
- 地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」
- 新版 問題解決プロフェッショナル 思考と技術
- コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト 知らないと一生後悔する99のスキルと5の挑戦
- 図解即戦力 コンサルティング業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
本書は、外資系コンサルタントが身につけるべーシックスキル30個を紹介し、職業や業界を問わず役立つ普遍的なスキルを提供します。新人からベテランまでが使える内容で、15年後にも通用する能力を身につけることを目的としています。著者は自身の経験と元コンサルタントへの取材を基に、実践的な技術や思考法、デスクワーク術、プロフェッショナルマインドを解説しています。
バーバラ・ミントが著した本は、コミュニケーション力を向上させるための文章の書き方を紹介しています。内容は、書く技術、考える技術、問題解決の技術、表現の技術の4部構成で、特にピラミッド構造を活用した文書作成法に焦点を当てています。また、構造がない状況での問題解決や重要ポイントのまとめも含まれています。
本書は、体系的かつシンプルなロジカル・コミュニケーション技術を習得することを目的としています。著者たちは、訓練を通じて誰でもこの技術を身につけられると確信しています。内容は、伝えることの重要性や論理的思考の整理、構成技術に関する具体的な方法を提供しています。著者は共にマッキンゼーでの経験を持ち、コミュニケーション戦略やトレーニングに従事しています。
この書籍は、効果的なスライド作成やグラフ・チャートの描き方を解説しており、シンプルなスライドにするためのテクニックを紹介しています。内容は、スライドの基本構成、視覚化のためのグラフ・チャート作成方法、シンプルさを追求するためのヒント、そして練習問題を含んでいます。著者は、コンサルティング業界での経験を活かし、わかりやすいスライド作成を教えてきた専門家です。
フェルミ推定は、未知の数値を常識や知識に基づいて論理的に計算する戦略的思考を指し、単なる因数分解やコンサルティングツールではない。著者の高松智史は、この手法を用いてビジネスパーソンとしての能力を高める方法を解説しており、具体的な解法や実践的なトレーニング方法についても触れている。
本書では、企業やコンサルティング会社が求める「地頭のいい人」の重要性を説いています。インターネット依存が思考停止を招く中、真に価値を生む「考える力」が必要とされています。地頭力は「結論から」「全体から」「単純に」考える3つの思考力で構成され、これを鍛えるためのツールとして「フェルミ推定」が紹介されています。著者は、地頭力を向上させる方法やビジネスへの応用について解説し、読者に新たな思考の武器を提供することを目指しています。
学生時代にフェルミ推定の練習のために読んだ本。非常に分かりやすくロジカルシンキングについて学べるが練習問題などは豊富ではないので、練習用の書籍としては物足りないかもしれない。
この書籍は、戦略コンサルタントのスキルを学ぶための指南書で、問題解決の基本的な考え方をチャートを用いてわかりやすく説明しています。内容は、思考法(ゼロベース思考や仮説思考)、技術(MECEやロジックツリー)、プロセス(ソリューション・システム)、実践(具体的な活用方法)に分かれており、企業事例も新たに紹介されています。著者は齋藤嘉則で、経営コンサルタントとしての豊富な経験を持っています。
この本は、コンサルティングに必要な思考や技術が「才能」ではなく、実践的なスキルであることを強調しています。104のビジネススキルを紹介し、業界や職種に関わらず全てのビジネスパーソンに役立つ内容です。目次では、1年目から4年目までの成長過程を通じて、コンサルタントとしての心得やマネジメント技術の違いを示しています。
この書籍は、コンサルティング業界の全貌を解説しており、就活生や新卒、転職を考える社会人に向けておすすめです。業界の業務内容、必要な能力、働き方、キャリアパス、主要なコンサルファームについて詳細に説明しています。また、コンサルタントに求められるスキルや就職・転職の実態も紹介されており、業界の現状や将来の展望についても触れています。コンサルティング業界に興味がある人にとって、理解を深めるための有益な一冊です。
本書は、フェルミ推定を通じて問題解決の技術を習得する方法を解説しています。フェルミ推定を磨くことで、数字に強くなり、ロジカルな思考や戦略的思考を自然に身につけることができます。内容は、具体的な市場規模の推定事例やビジネスでの応用、さらには新たな問題解決の思考法についても触れています。著者は高松智史で、一橋大学卒業後、NTTデータやBCGでの経験を持ち、「考えるエンジン講座」を提供しています。
この本は、コンサルタントのマネージャーとして成功するための79の技術を紹介しています。マネージャーはクライアントや自分自身のために「お金」を生むことが重要で、3年にわたる成長過程を通じて、インテレクチャルリーダーシップやクライアントへの売り込み、部下への愛情をテーマにしています。著者は高松智史で、NTTデータやBCGでの経験を基に、思考の進化を促す内容を提供しています。
本書は、嘉永六年(1853年)以降の日本における攘夷と開国、勤王と佐幕の激しい政治闘争を描いた歴史小説で、特に長州藩の吉田松陰と高杉晋作を中心に、変革期の青春群像を描いています。著者は司馬遼太郎で、数々の文学賞を受賞した著名な作家です。
日本企業には戦略を実行できるリーダーが不足しており、36歳の変革リーダーが市場シェアを逆転させた実話を基に改革プロセスを描いたケースストーリーです。著者は三枝匡で、経営の実践や会社再建に豊富な経験を持っています。
本書は、21世紀の価値創造において、問題解決の専門家よりも「善」に基づいて価値を判断できる人が重要であると説いています。著者は、マッキンゼーとボストンコンサルティンググループの両方を知る数少ない存在であり、彼らの問題解決手法とその限界を分析し、新たな価値創造技術やビジネスの潮流を紹介します。具体的な事例を通じて、問題解決の新たなアプローチを提案しており、ビジネスパーソンにとって必携の一冊です。
本書は「論理的思考」をテーマに、思考の原則、論理の方法、分析のテクニックを体系的に解説しています。三部構成で、思考の基本から合理的な分析手法までを平易に実践的に紹介しています。著者は経営コンサルタントの波頭亮氏で、東京大学卒業後、マッキンゼーを経て独立し、戦略系コンサルティング会社を設立しました。
この本は、「暗記する」戦略思考を学ぶための実用的なガイドです。戦略思考とは、解答や意見を生成するための考え方であり、著者は特定のフレーズを覚えることでこの技術を身につけることができると提唱しています。内容は、実際のビジネスや人生のシナリオを通じて思考を切り替える方法や、戦略思考のマップを提示し、考える力を強化するための具体的な手法を紹介しています。著者は、NTTデータやBCGでの経験を基に、面白くインパクトのある思考を追求しています。
この本は、成果を上げるためには「正しい問い」を立てることが重要であると説いています。著者の内田和成は、問題解決力を向上させるための戦略思考や論点の絞り込み方法を解説しています。目次には、正しい問いの設定や論点の確認、ケーススタディを通じた思考の流れの理解、論点思考力を高めるための方法が含まれています。内田氏は早稲田大学ビジネススクール教授で、豊富なコンサルティング経験を持っています。
この書籍は、経営コンサルティングの歴史や影響力、特に日本における展開について詳述しています。経営コンサルタントの役割や実務、業界の課題と変革の必要性についても触れています。著者は、マッキンゼーでの経験を持つ並木裕太氏で、様々な産業でコンサルタントとして活躍しています。
この本は、1000以上のフェルミ推定問題を解いた東京大学の学生たちが、その解法を体系化したものです。フェルミ推定の基本パターンと解法ステップを学ぶことで、効果的な思考トレーニングが可能になります。目次には、フェルミ推定の基本体系、コア問題、練習問題が含まれています。
新進気鋭の経営学者、三宅秀道が企業事例や歴史的知識を基に、現代ビジネスの戦略を探る書籍。目次には、技術神話の打破、新しい文化の創造、問題解決のアプローチ、組織の課題、地域コミュニティとの連携などが含まれ、価値創造のための新たな視点が提案されている。著者は、製品開発や中小企業論の専門家で、多くの企業を研究している。
リバース・イノベーションは、途上国で生まれたイノベーションを先進国に逆流させる新しい概念で、その影響力とメカニズムを理論と企業事例を通じて解説しています。内容は二部構成で、第一部ではリバース・イノベーションの旅とマインドセットの転換について、第二部では具体的な挑戦者の事例を紹介しています。著者は戦略とイノベーションの専門家であり、ダートマス大学の教授たちです。
この書籍は、「ケース面接」を擬似体験できる内容で、現役コンサルタントの思考プロセスを模擬解答例から学ぶことができます。目次には、フェルミ推定系問題やビジネスケース系問題が含まれており、具体的な課題に対する解決策を考える力を養います。著者は大石哲之氏で、コンサルティング業界での豊富な経験を持つ専門家です。
この書籍は、顧客から学ぶことの重要性を強調し、「構築ー計測ー学習」というフィードバックループを通じて製品やサービスを育てるシリコンバレー発のマネジメント手法を紹介しています。内容はビジョン、舵取り、スピードアップの3部構成で、著者はスタートアップの経験を持つエリック・リース氏です。彼はビジネス戦略のアドバイスを提供し、さまざまな企業での講演活動も行っています。
スタートアップを立ち上げるために必要なリーンスタートアップという考え方を学ぶために読んだ。今の時代、スタートアップでも大企業でもどんな組織でもリーンスタートアップの考え方は重要で、小さいことをクイックに行い小さい成功をおさめてそこから雪だるま式に大きくしていくことが大事。小さい状態で失敗しても大きな痛手ではないので、とりあえず作ってみて検証する!ただ小さくはじめると小さくおさまってしまうという考え方も提唱している人がいて面白いと思った。イーロン・マスクなどはスペースXを起業する際に小さくなんか始めていない。出来るだけクイックに動いていたが最初から巨額の投資をしていた。イーロンはPaypalの売却益で巨額の富を得ていたからという人もいるが、それでも足りないくらいの額を突っ込んでいる。巨額の富を得ると、そこから小さく色んなところに投資してどれか当たればよいという考えてしまうケースが多い気がするが、本当に偉大なことを成し遂げたいのであれば小さく始めるという思考を取り払って大きく勝負に出ることも必要かもしれない。
この書籍は、仮説思考を用いることで作業効率を大幅に向上させる方法について解説しています。著者の内田和成は、BCGコンサルタントとしての経験を基に、仮説を立てることの重要性やその検証方法、思考力を高める方法を紹介しています。目次には、仮説思考の概念から始まり、実践的なステップが示されています。内田は東京大学卒で、経営戦略の専門家としての経歴を持っています。
本書は、システム化企画や要件定義、基本設計などの上流工程に必要なスキルや心構えについて解説しています。単に実装スキルだけでなく、議論をリードし、関係者の合意を得る能力、全体を見通す視点が求められます。上流工程を初めて行う際の準備やスキルアップ方法についても具体的なアドバイスが提供されています。著者は、システム開発の専門家であり、若手エンジニアの育成に力を入れています。
この本は、世界最高峰の経営コンサルティング会社で教えられている問題解決の考え方を、中高生向けに身近なストーリーとイラストを交えて解説しています。問題を小さく分けて考えることで解決策が見えてくることを学び、自ら考え行動する力を育む内容です。目次では、問題解決能力の習得、原因の見極め、目標設定と達成方法についての章が設けられています。著者は、経済を専攻した後にマッキンゼーでの経験を持つ渡辺健介氏です。
本書は、プロ経営者の思考と行動を学ぶための実話に基づくストーリーと戦略理論を融合させた作品です。新たに「戦略プロフェッショナルの要諦」と「経営者人材育成論」が加わり、目次には決意、行動、戦略などのテーマが含まれています。著者は、経営再建の専門家であり、ミスミグループ本社の代表取締役会長を務めています。
コンサルを目指している人やロジカルシンキングを身に着けたいビジネスパーソンに圧倒的におすすめな書籍。コンサルのフレームワークは抽象論ばかりで具体的な実務につなげるのが難しい場合が多いが、この書籍を読めば実務につなげるイメージが間違いなく湧く。ストーリー形式で話が進み、スラスラ読める。物語としても面白い。
この書籍は、大企業がイノベーションに失敗する理由や、成功を忘れがちな組織の課題を探求し、戦略的イノベーションを実現するための方法論を提供しています。著者たちは新しいビジネスモデルを模索し、組織変革を通じて爆発的な成長を促すための10のルールを提示しています。著者は、戦略とイノベーションの専門家であり、企業コンサルティングの経験も豊富です。
この書籍は、ボストン・コンサルティング・グループのノウハウを基に、勝てる戦略を生み出すための「イノベーション」を促進する発想法を解説しています。内容は、戦略に命を吹き込むインサイトの重要性、思考のスピードを上げる方法、三種類のレンズを用いた発想力の向上、インサイトを生み出すための頭の使い方、そしてチーム力を活かしたインサイト創出の方法について触れています。著者は御立尚資氏で、幅広い業界で事業戦略やイノベーションに関するプロジェクトを手掛けています。
本書は、経営環境の変化に対応して加筆・修正され、注目のビジネス・トピックスが増補されています。MBAコースで学ぶ経営理論とビジネス用語を体系的に網羅しており、内容は経営戦略、マーケティング、アカウンティング、ファイナンス、人・組織、IT、ゲーム理論・交渉術の7部構成です。
本書は、ビジネスにおける「提案の技術」をテーマに、論理思考やプレゼンテーション能力を実践的に学ぶためのガイドです。著者は、外資コンサルや商社での経験を基に、提案を成功に導くための基本的なスキルを整理しています。内容は、論理思考力、仮説検証力、会議設計力、資料作成力の4つの能力に焦点を当て、各章がストーリー、解説、まとめで構成されています。ビジネス現場での実践的なスキルを身につけることができる内容です。
ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。
ボストン・コンサルティンググループの戦略理論を紹介する本で、世界のトップ企業が採用する競争原理について解説しています。目次には、競争優位の視点、株主価値、顧客価値、バリューチェーン、事業構造、コスト優位、時間優位などのテーマが含まれています。著者は水越豊氏で、幅広い業界で戦略や組織に関するプロジェクトを手掛けている専門家です。
この書籍では、プロジェクト・マネジメントにおける人間行動の特性を考慮し、制約条件の理論(TOC)を応用したクリティカルチェーンの手法を提案しています。著者のゴールドラット博士は、パフォーマンスを大幅に改善するための新しいツールとソリューションを提示し、ビジネス小説としての形式を取っています。著者の背景には、TOCの創始者であるゴールドラット博士や、ビジネス教育に関わる三本木亮、プロジェクト管理の専門家である津曲公二がいます。
読みながら行動や考えを改められ、少しずつ自身に変化を感じられる素晴らしい書籍です!
誰もが知る名著なので一度は目を通しておくべきだが、内容は冗長で個人的にはあまりはまらなかった。重要度×緊急度のマトリクスの話が一番重要で、そこだけ理解しておけばいい気がする。緊急度は低いが重要度が高いタスクになるべく長期的な視点で取り組めるようになるべき。
ポスト会計時代の基本知識はコレだ。 第1章 会計とファイナンスはどう違う? 第2章 ファイナンス、基本のキ 第3章 明日の1万円より今日の1万円-お金の時間価値 第4章 会社の値段 第5章 投資の判断基準 第6章 お金の借り方・返し方
大学生が3カ月で100万円貯めるには、どうする?こんな突飛な質問から、試験、日常生活、ビジネスなど、あらゆる場面で一生使える最高の問題解決法とは-どんな問題も「3ジャンル、5ステップ」で解ける、東大発、新思考システム。 1 どんな問題もすらすら解ける!問題解決ケースの3ジャン・5ステップ(問題解決ケースの3ジャンル 問題解決ケースの5ステップ 実際の面接における5ステップ) 2 9パターンのコア問題で、問題を解く力を効率的に鍛える!(Privateケース:Project1、Project2、Project3 Pbulicケース:Project4、Project5、Project6 個人ケース:Project7、Project8、Project9)
この書籍は、戦国時代の重要な十二の戦闘を分析し、勝因や敗因を探る内容です。著者は桶狭間の戦いや大坂の戦いなどの歴史的事件を取り上げ、松浦静山の名言「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」の真偽を問います。また、戦場の誤算や勝負の微妙さから、ビジネスや人生に役立つ教訓を導き出す画期的な戦国合戦史です。
下村英雄氏が木村周氏の志を受け継いだ、キャリアコンサルタント必須のバイブルと行っても過言はないだろう。社会正義のキャリア支援も記述されており、今後、ディーセントワーク実現のため、キャリアコンサルタントには必読書である。
この書籍は、世界的な経営コンサルタント会社マッキンゼーのビジネス思考と仕事術を紹介しています。著者は、マッキンゼーがなぜ世界一であり続けるのかを探り、ビジネス問題の考え方、解決方法、プレゼンテーション技術、マッキンゼーでの生き残り方、そしてその伝統に関する知識を提供します。著者は元マッキンゼー社員のイーサン・M・ラジエルで、彼の経験をもとにした実践的なアドバイスが詰まっています。
この書籍は、コンサルティング業界を目指す人やその仕事に興味がある人に向けて、業界の基礎知識や各ファームの解説、プロジェクトの流れ、就職・転職のノウハウを提供しています。著者は人材紹介会社の代表であり、コンサルティング業界に特化したキャリアアドバイスを行っています。
本書は、コンテンツマーケティングを通じて潜在ユーザーをWebサイトに呼び込む方法を解説しています。内容は、コンテンツ制作やSEOの基本、オウンドメディアのライティング術、SEOを意識したWebサイト制作、リスティング広告の活用法など多岐にわたります。著者たちは、限られた予算や人手でも実践可能なノウハウを提供し、読者が自社のビジネスやユーザー理解を深め、効果的なコンテンツを作成できるようサポートします。
この書籍は、クリティカルチェーン法(CCPM)を中心にしたプロジェクトマネジメントの実践的な解説と事例を提供し、収益改善の手法をわかりやすく紹介しています。目次は、プロジェクトマネジメントの問題、TOC(制約条件理論)の基本、CCPMの適用方法、バッファマネジメント、組織の問題解決手法、そして導入事例を含んでいます。著者は、TOCやCCPMの専門家であり、企業へのコンサルティングやトレーニングを行っています。
本書は、著者が経営者として不振事業の再生に挑む軌跡とその戦略を初めて公開したものです。約50年間、現場での経験を通じて日本企業の再生手法を磨いてきた著者が、20代で経営者を志し、30代で初陣を迎えるまでの成功と失敗を描いています。経営者の仕事の難しさや、戦略と実行力の重要性を探求し、戦略プロフェッショナルを目指す人々に向けた内容となっています。シリーズ累計約100万部の名著が新たに改訂された決定版です。
全てのビジネスパーソンに読んで欲しい名著!戦略やロジカルシンキングを謳ったコンサル本は多いが、それを読んで学んでも結局実務に活かしづらい気がする。そんな中この書籍はストーリ形式でどうやってコンサルの考え方をビジネスに活かしていくか学べる良本。
本書は、常識と四則演算を用いてさまざまな現実的な問題を解決する「フェルミ推定」の良問76題を集めたドリルです。問題例には、100万人の集会に必要なトイレの数や、宇宙船の燃料量、人体の細胞数などが含まれています。フェルミ推定を学ぶことで、思考力を高め、誇張された主張を見抜く力も養える内容となっています。読後には、世界の見え方が変わる一冊です。
著者は、マッキンゼーの採用マネジャーとして12年間の経験をもとに、リーダーシップと採用基準について語る内容の書籍を執筆しました。目次では、誤解されがちな採用基準やリーダーシップの重要性、リーダーが果たすべき役割などが取り上げられています。著者はキャリア形成コンサルタントであり、リーダーシップ教育に関する啓蒙活動を行っています。
この本は、戦略コンサルティング会社の面接形式「ケース・インタビュー」を攻略するためのノウハウと最新のケース問題を提供しています。著者マーク・コゼンティーノは、30年以上にわたり多くの学生に指導しており、彼の著書は「MBAのバイブル」として高く評価されています。内容は面接プロセスやケース・インタビュー対策、思考法、実例集など多岐にわたります。
この書籍は、契約更新を続ける経営コンサルタントと単発のコンサルタントとの違いを探り、長期的な顧客関係を築くための秘訣を50の重要ポイントとして紹介しています。内容は、コンサルタントに求められるものやマインドセット、クライアントとの距離感、継続的な価値提供の方法など多岐にわたります。著者の林田康裕は、独立系コンサルタントとして中小企業や店舗ビジネスの支援を行っています。
本書は、ビジネスにおける論理的思考力を強化するための具体的な方法を示している。論理的思考の原理を理解した上で、3つのコアスキル「適切な言語化」「分ける・繋げる」「定量的な判断」をトレーニングすることが重要である。各スキルの習得方法や練習の仕方についても詳しく説明されている。著者は戦略系コンサルタントの波頭亮氏。
本書は、企業文化の変革とデジタル変革(DX)の成功に焦点を当て、マッキンゼーのノウハウを基に「Why」「What」「How」、そして読者自身が何をすべきかを解説します。日本企業はITシステムの導入を目的化しており、真のDXに成功している企業はわずかです。著者は、次世代リーダーに向けて、企業文化の変革が生き残りの鍵であることを強調し、具体的な戦略や人材育成、変革管理の重要性を論じています。
この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。
本書は、ヒアリングを通じて問題点や強みを抽出し、実効性のある提案を行うための「課題解決型ヒアリング」の手法を提唱しています。著者の寺嶋直史は、ヒアリング力を高めるための手順やルールを解説し、思考とヒアリングを同時に行うことで提案力を向上させる方法を示します。目次では、ヒアリングの問題点や課題解決思考の手順、実践的なルールが紹介されています。
本書は、ポーターの競争戦略論を基にした企業再発進に関する古典的な経営戦略論であり、初版から10年経過した今もその重要性が高まっている。増刷に際し、原注や参考文献を追加し、内容をさらに充実させている。目次には、競争戦略の分析技法や業界環境に応じた競争戦略、戦略的意思決定のタイプが含まれている。
著者・遠藤功氏の新著は、経営コンサルタントとしての30年の経験を集約した「仕事論」の集大成であり、ビジネスパーソンやコンサル志望者に向けた内容です。主なテーマは「究極の思考法」「人を動かす極意」「脳を活かすマインドと習慣」で、具体的な思考技術や人間関係の構築法、効率的な学び方が紹介されています。全体を通じて、一流のプロ人材になるための知識と実践的なスキルを磨くことが目的です。
顧客から、上司から、部下から「相談される」プロフェッショナルになるための教科書。聞く力、先見力、突破力などの極意を伝授する。 顧客から、上司から、部下から「相談される」プロになるための教科書。 戦略コンサルティングファームのトップがプロフェッショナルが身につけるべき「10の力」について伝授する。 聞く力:相談されることから仕事は始まる 先見力:常にクライアントの利益を第一に考える 献身力:正しい方向にクライアントを導けるか 突破力:自分の限界を超えるまで考えて考え抜く 巻き込み力:志とコミュニケーションで人を動かす 共創力:共にプロジェクトを創っていく 好奇心:常に新しいことを学び続ける 歴史観:歴史ぬきにブランドは語れない 忘れる力:ストレスは上手にコントロールする 恋愛力:個人と個人で惹かれ合う関係を築けるか 常に「最初に相談される人」であれ。 ロジカルであるだけでなくクリエイティブであれ。 ストレスは上手にコントロールせよ。 論理や分析に長けていることも大事だが、問題解決させすればクライアントから信頼されるわけではない。 大事な恋人との未来を考えるのと同じように、クライアントとの未来を考え、大きなビジョンを実現させるために解決すべき課題を見つけることができるか。 若手のコンサルタントはもちろんのこと、顧客や上司、部下という「クライアント」に助言をする立場のビジネスパーソンすべてが身につけるべき極意がここにある。 クライアントから信頼が得られれば、「コンペなし」で選ばれる関係になれる。 第1章 聞く力~相談されることから仕事は始まる ・コンサルタントとは何か ・聞く力のベースとなるのは語彙力 ・質問するには下調べが必要 第2章 献身力~常にクライアントの利益を第一に考える ・クライアントとは何か ・常に「最初に相談される人」であれ ・トップ同士をつなぐ 第3章 先見力~正しい方向にクライアントを導けるか ・なぜ先見力が必要なのか ・先見力を身につけるトレーニング ・失敗を予測する 第4章 突破力~自分の限界を超えるまで考えて考え抜く ・限界を超えたところに生まれるセレンディピティ ・1ヵ月で200本の企画を考える ・徹夜明けに出てきたアイデア 第5章 巻き込み力~志とコミュニケーション力で人を動かす ・紙に書いた言葉だけで人は動かない ・巻き込むためには、ドラマもつくる ・証券会社の経営者に学んだ巻き込み力 第6章 共創力~共にプロジェクトを創っていく ・共同作業、他流試合で化学反応を起こす ・ピラミッド・プリンシパルを上手に使う ・機械メーカーでの新規事業推進プロジェクト 第7章 好奇心~常に新しいことを学び続ける ・相手がどういう人か、好奇心を持つ ・銀座のママが教えてくれた好奇心の保ち方 ・学び方を学び続ける 第8章 歴史観~歴史ぬきにブランドは語れない ・日本の自動車メーカーは真のプレミアムブランドを構築できるか ・レースの歴史は自動車発展の歴史だった ・諸外国の歴史と、自国の歴史を知る 第9章 忘れる力~ストレスは上手にコントロールする ・眠れなくなるのは危険信号 ・眠ることで、どうでもいいことは忘れる ・うまくいかないときは「天の思し召し」と思う 第10章 恋愛力~個人と個人で惹かれ合う関係を築けるか ・自分を売り込まないほうが愛を育める ・お互いの距離の測り方 ・コンペなしで選ばれる関係になる Column コンサルティングの歴史を振り返り、未来を考える
この書籍は、日本人がロジカルな表現を苦手とする理由を探り、効果的なライティング技術を身につけるための方法を提供しています。序章では誤解を解き、各章で読み手の関心を引くためのOPQ分析、メッセージの整理、ロジックの展開、文書の構成を解説。終章では日常のメールを通じてこれらの技術を実践する方法を提案しています。著者の山崎康司は経営コンサルタントで、ビジネス思考やライティングに関する教育を行っています。
本書は、答えのない課題に対処するための思考技術を解説しています。著者は元戦略コンサルタントで、3000人以上に「考え方」を教えてきました。内容は、「答えのないゲーム」の戦い方、示唆の抽出、健全な議論のための思考技術、問題解決プロセスの体得、そして異なる思考スタイルの比較を含みます。この本を通じて、読者は考えることの楽しさを見出し、後悔のない選択ができるようになることを目指しています。
本書は、SDGs(持続可能な開発目標)を背景に、企業が直面する「産業革命」と「経営革命」に同時に対応する必要性を説いています。企業活動における社会価値と経済価値の重要性を強調し、経営モデルの革新や戦略の再構築を促します。内容は、SDGs時代の新たな経営モデルの潮流、企業のSDGsの理解、ステークホルダーの変化、そして新たな経営モデルへのシフトに向けた戦略に分かれています。企業はSDGsを「義務」ではなく「戦略」として捉え、成長を追求することが求められます。
本書は、プロジェクトマネジメント(PM)の基本スキルを習得するためのガイドです。著者は22年の経験を持つプロジェクトマネージャーで、一般的なビジネススキルとしてのPMの重要性を強調し、失敗の原因として基本知識の不足を指摘しています。新規事業やDXに関わるマネージャーやビジネスパーソンに向けて、業種や規模を問わず再現性のあるPMスキルを詳しく解説しています。目次には、プロジェクトの基本から契約、要件定義、デザイン、リリースまでの各ステップが含まれています。
事業構造改革、コーポレートガバナンス、場のマネジメントなど、最新のトピックスを交えて、躍動感に満ちた企業のメカニズムを解明する「生きた経営学」の決定版。大学生、ビジネスマン、MBA志望者、必読のスタンダードテキスト。 企業のマネジメントとは 第1部 環境のマネジメント(戦略とは何か 競争のための差別化 ほか) 第2部 組織のマネジメント(組織と個人、経営の働きかけ 組織構造 ほか) 第3部 矛盾と発展のマネジメント(矛盾、学習、心理的エネルギーのダイナミックス パラダイム転換のマネジメント ほか) 第4部 企業と経営者(企業という生き物、経営者の役割 コーポレートガバナンス)
本書は、アイデアが浮かばない、会議がまとまらない、意思決定に迷うといった悩みを解決するためのフレームワーク集です。70以上の手法が掲載されており、個人やチームで活用可能です。内容は問題発見、市場分析、課題解決、戦略立案、業務改善、組織マネジメント、情報共有に関するフレームワークを含み、使い方や活用のヒントも提供されています。すべてのフレームには記入例があり、PowerPointテンプレートとしても利用できます。
ビジネスフレームワークが図解で学べる。誰もが知っているビジネスでも実際にビジネスモデルは分からないことが多い。この書籍のビジネスフレームワークを一通り頭に叩き込んでおくことで色んなケースに応用が効く。
この書籍は、Excelの効果的な使い方を紹介し、作業効率を大幅に向上させるテクニックを提供しています。基本操作から便利な関数、データ分析、グラフ作成、印刷機能の活用まで幅広くカバーしており、誰でも簡単にマスターできる内容です。著者はExcel研修の専門家で、実践的なノウハウを通じて一生役立つスキルを身につけられることを強調しています。
この書籍は、マウスを使わずにパソコン作業の効率を上げるためのショートカットキーの活用法を紹介しています。年間120時間の時短が可能で、2週間でマスターできる内容です。著者の森新は、PCスキル向上による生産性向上を追求し、独自のノウハウを蓄積。大手企業でも採用されている方法を網羅しています。
本書は、仕事や趣味での新しい知識や技術の習得が人生を豊かにすることをテーマに、上達の違いを記憶心理学や学習心理学の観点から分析しています。上達の力学は「スキーマ」や「コード化」にあり、独自の練習法やスランプ対策を提案しています。著者は社会心理学者の岡本浩一で、努力が報われるための指南書として、本人や教育者、コーチに向けた内容となっています。目次は能力主義、記憶のしくみ、上達の方法論、スランプの対策などを含みます。
この本は、ESG(環境、社会、企業統治)の重要性を強調し、世界の投資の約30%がESGに向かっている現状を示しています。著者は、特に日本企業がこの流れに遅れていることを指摘し、不況期においてもESG思考が重要であると述べています。内容は、ESGが利益に与える影響や、ニュー資本主義の誕生、パリ協定やSDGsとの関連性について詳しく解説しています。ビジネスパーソンにとって必携の教科書とされています。
著者は、手本や解答がない現代において成功するための思考法を示し、戦略的思考の重要性を解説しています。内容は、戦略的思考の基礎や企業への応用、阻害要因、グループ形成、さらに戦略的経営計画の実践について詳細に述べています。
この書籍は、BBT大学の人気授業を基にしており、「もし自分が社長だったら?」という視点から、ニトリやAirbnb、コカ・コーラなどの企業の経営課題に取り組みながらビジネスモデルの作り方を学ぶ内容です。12のパターンを通じて「儲けの仕組み」を解説し、大前流の戦略的思考のプロセスが理解できます。著者は大前研一で、経営コンサルタントとしての豊富な経験を持っています。
著者は外資系コンサルタントとして12年間の経験を持つ元バンドマンで、初の著書を通じて「最速仕事術」を紹介しています。内容は、仕事のスピードや論点思考、説得力のある品質の重要性、会社の集合知の活用法など、幅広い業界で役立つ秘訣が盛り込まれています。特に、社会人1年目に知っておきたい実践的な知識が詰まった一冊です。
本書は、著者が提唱する32の思考法やキーワードを通じて、戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力などの基本概念とその活用法を解説しています。内容は、基本的な思考法、二項対立の考え方、コンサルタントのツール、AIとの比較、無知の知の重要性に分かれており、それぞれの章で「何か」「なぜか」「どう使うか」を明確にしています。著者はビジネスコンサルタントであり、思考力を高めるための実践的なアプローチを提供しています。
逆風こそ、変革の好機。事業を元気にする組織概念、人の心を動かす戦略…アメリカ流の後追いではない、独自の経営スタイルを編み出せ。 第1章 アメリカ流経営、九つの弱み 第2章 「日本的経営」も威張れたものではない 第3章 論理化する力・具体化する力 第4章 日本における「経営の原理」 第5章 「創って、作って、売る」サイクルの原理 第6章 人の心を動かす戦略 第7章 事業の再生、大組織の改革 第8章 抵抗勢力との闘い 第9章 失われてきた経営者育成の場 第10章 今、求められる経営者人材
この書籍は、情報の解像度を高める方法について解説しています。スタートアップの現場から得た知見を基に、解像度を上げるための視点や診断方法、行動の重要性、課題や解決策の深さ・広さ・構造・時間の観点からの考察を行っています。また、実験と検証を通じて未来の解像度を向上させる方法についても触れています。著者は東京大学の馬田隆明氏で、スタートアップ支援やアントレプレナーシップ教育に従事しています。
解像度についての解像度が上がる本。解像度には「深さ」「広さ」「構造」「時間」の4つの視点があり、「深さ」が足りていないことが圧倒的に多い。解像度を上げるためのリサーチ方法や顧客インタビューについて学べる。起業する上で重要なエッセンスが詰まっており起業家が読むべき一冊だと思う。
この書籍は、社会で騙されないための自己防衛の方法を解説した社会心理学の名著です。著者ロバート・B・チャルディーニは、影響力のメカニズムを8つの章に分けて説明し、具体的な戦略や心理的原理をユーモラスに描いています。新訳版では、マンガや事例が追加され、現代の広告戦略や社会問題についても触れられています。読者は、プロの手口を理解し、賢い消費者になるための知識を得ることができます。
人間関係の悩みが尽きない社会において、思考が動く考えられる本となっていました。 自分自身の行動を社会に当てはめ参考にしていけるので自分にとってポジティブな内容でした
ページ数が多く読み切るには根気がいるが、中身は目から鱗の内容ばかり。知っておくだけど対人関係が有利に働く法則などが多く学べる。
本書では、コダックやモトローラなどの企業幹部へのインタビューや成功したアドバイザーの研究を通じて、プロフェッショナルが持つべき特質を明らかにし、それを高める具体的な方法を示しています。特質には、無私・自立、共感力、深い知識、統合力、判断力、信念、誠実さが含まれ、価格ではなく付加価値で勝負できる真のプロフェッショナルになるための道筋が提示されています。著者はマーケティングの専門家シースと、経営アドバイザーのソーベル、コンサルタントの羽物です。
変革をリードする経営パワーを持つ人材が枯渇している。倒産寸前の会社に若き戦略型リーダーが舞い降りて、ついに成長企業に蘇らせる!実話に基づく迫真のケース。前著『戦略プロフェッショナル』より進んだ戦略手法の応用から抵抗勢力との闘い、リーダー育成法まで実践解説。 第1章 袋小路 第2章 白旗あがる 第3章 混沌の世界 第4章 零への回帰 第5章 成功への絞り 第6章 試練の谷 第7章 飛翔の時 第8章 最後の関門
この書籍は、会社の全体像を理解するためのガイドであり、経営や組織の仕組み、仕事内容、給与、人事評価、会社の数字について詳しく説明しています。著者の八巻優悦は、豊富な実務経験を持つ中小企業診断士であり、プロジェクトマネジメントの専門家でもあります。
本書は、ビジネスにおける問題解決の技術と実行方法を体系的に解説したテキストで、業種や立場を問わず活用できるスキルを提供します。問題解決の手順を明確にし、実践的な内容を重視。特に問題の特定能力を強調し、実例を交えた構成で理解を深めることを目指しています。全7章で、問題解決の手順を段階的に学び、結果の評価や定着化についても触れています。著者は経営コンサルタントとしての経験を活かし、実践的なビジネススキルを伝授します。
『経営戦略の基本』は、2008年の初版以来15年以上にわたり愛されてきたロングセラーの戦略入門書がリニューアルされたものです。この新版では、全社戦略と事業戦略を包括的に学べる内容が強化され、具体的な戦略策定から実行までを図解で解説しています。環境分析や事業領域設定、全社戦略の仕組みづくり、フレキシブルな戦略対応方法など、実務で役立つノウハウが豊富に盛り込まれています。また、最新のフレームワークや戦略ソリューションも追加され、現場で実際に使える知識が提供されています。著者は経営戦略の専門家であり、実務経験に基づいた内容が特徴です。
本書は、企業が10年後に生き残るための抜本的な変革を促す内容です。著者は「時間軸のトランスフォーメーション戦略」を提唱し、経営戦略の構想や実行のポイントを解説しています。成功事例としてリクルートHDやソニーグループなどを分析し、経営理論を活用した変革の成功法則を示しています。特に、長期的なポートフォリオマネジメントや市場創造戦略、カルチャーの変革など、5つの成功ポイントが強調されています。
SaaS系のプロダクトをどうやってスケールさせていくかの緻密な営業戦略が学べる。このスキームに沿ってほとんどのSaaS企業が営業組織を作っている。SaaS系を目指す経営者やSaaS系で働く会社員は全員読んでおいて損しない1冊。
現代ビジネス界に「戦略」を持ち込み、企業経営に革命をもたらした新しい知識人たちの苦闘の現代史。マッキンゼーやボストン・コンサルティング、ハーバード・ビジネス・スクールなどの攻防を描く。 解明すべき謎としての戦略 戦略を定義したブルース・ヘンダーソン 経験曲線の衝撃 マトリックスという武器 ビル・ベインが望んだこと マッキンゼーの目覚め マイケル・ポーター、奇想天外な世界に出会う 人間の重要性 生まれなかった新しいパラダイム 戦略を実現するための闘い〔ほか〕
本書『エッセンシャル思考』は、無駄を排除し、本当に重要なことに集中する方法論を提案しています。著者グレッグ・マキューンは、重要な選択を見極め、瑣末な事柄を捨て、システム化することで、より少なく、しかしより良く生きることを目指します。この考え方は、単なるタイムマネジメントやライフハックを超えたものであり、現代において求められる生き方の変革を促しています。
普段の仕事や生活で自分の時間がなくて常に何かに追われている感覚があるのであれば是非読んで欲しい!本質的でないことは全て捨てて自分のやりたいことにフォーカスしよう!一度きりの人生、悩んでいる時間は無駄。社会人になりたてで四苦八苦している人がいたら是非読んで欲しい。
本書は、現代におけるマインド・コントロールの危険性とその技術について解説するもので、カルトやテロ集団だけでなく、さまざまな組織や家庭においても利用されていることを指摘しています。著者は精神科医の岡田尊司氏で、彼は心の崩壊と戦う中で、マインド・コントロールの原理、騙されやすい人の特性、そしてその解決策について述べています。各章では、テロリズムや無意識の操作技術、行動心理学などが扱われ、現代社会における孤独や自己愛がもたらす影響が考察されています。
コンサルティング業界入門の定番書。外資から国内注目ファームまで網羅した決定版! 第1版刊行以来、6度目の改訂改版となる今回は企業情報ページを一新し、全面リニューアル。 ・仕事の基礎知識から実務、業界の行方まで網羅! ・注目ファーム30社超の特徴や強み、最新動向がすぐわかる! ・選考対策から独立後のキャリアまで充実の最新情報! ・各社の採用プロセス(新卒・中途)、育成方針など一覧掲載! ◆コンサルティングファームとは [コンサルティングとは何か? / どこで差別化するか〜コンサルティングファームの戦略とは / コンサルティングファームの機能とは何か / コンサルティング業界の現状と将来 / コンサルティングファームの経営 / パートナー制と株式公開 / 戦略系コンサルティングファームの将来〜戦略系は衰退産業か / コンサルティングとITの関係 / アウトソーシングとコンサルティングファーム] ◆コンサルタントという仕事 [コンサルタントの仕事の面白さ / コンサルタントの仕事の進め方 / コンサルタントのキャリアパス / プロジェクトはどのように進むか / コンサルタントのワークスタイル / コンサルタントの研修・育成 / コンサルタントの評価はどうなっている? / コンサルタントの将来] ◆主要ファームの特徴と戦略 [アーサー・D・リトル / アクセンチュア / アビームコンサルティング / A・T・カーニー / NTTデータ経営研究所 / クニエ / 経営共創基盤 / コーポレイトディレクション / シグマクシス / スカイライト コンサルティング / デリバリーコンサルティング / デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 / 電通コンサルティング / ドリームインキュベータ / 日本能率協会コンサルティング / 野村総合研究所 / 博報堂コンサルティング / PwCコンサルティング合同会社 / ビジネス・パートナーズ / 日立コンサルティング / 船井総合研究所 / プロレド・パートナーズ / フロンティア・マネジメント / ベイカレント・コンサルティング / べイン・アンド・カンパニー / ボストン コンサルティング グループ / マッキンゼー・アンド・カンパニー / 三菱総合研究所 / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング / リヴァンプ / リブ・コンサルティング / ローランド・ベルガ―] ◆コンサルティングファームに入るには [どうなっている? 新卒採用プロセス / 中途採用プロセスの実際 / 面接では何が評価されるのか / 新卒コンサルタントの価値とは? / コンサルティングファームが期待する人物像 / 必読! 選考突破に役立つおすすめ本] ◆主要ファームの採用プロセス・トレーニング・配属方法一覧 [アーサー・D・リトル / アクセンチュア / アビームコンサルティング / A・T・カーニー / NTTデータ経営研究所 / クニエ / 経営共創基盤 / コーポレイトディレクション / シグマクシス / スカイライト コンサルティング / デリバリーコンサルティング / デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 / 電通コンサルティング / ドリームインキュベータ / 日本能率協会コンサルティング / 野村総合研究所 / 博報堂コンサルティング / PwCコンサルティング合同会社 / PwCコンサルティング合同会社 Strategy& / ビジネス・パートナーズ / 日立コンサルティング / 船井総合研究所 / プロレド・パートナーズ / フロンティア・マネジメント / ベイカレント・コンサルティング / べイン・アンド・カンパニー / ボストン コンサルティング グループ / マッキンゼー・アンド・カンパニー / 三菱総合研究所 / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング / リヴァンプ / リブ・コンサルティング / ローランド・ベルガ―] ◆Special Talk コンサル“後”のキャリアを考える――コンサルティングファームで学べること、学べないこと [田野崎亮太さん(フェイスブックジャパン 執行役員)×若原強さん(コクヨ ワークスタイル研究所所長)×松村有晃さん(楽天 執行役員・顧客戦略統括部ディレクター)]
物流業の若手、新人、製造業・流通業の物流担当必読。輸配送、荷役、保管、流通加工、梱包・包装、情報管理-物流6大機能が図解ですっきりわかる! 1章 物流機能の基本 2章 調達・生産・販売物流の基本 3章 輸送業務の基本 4章 倉庫業務の基本 5章 物流情報システムの基本 6章 物流コストの基本 7章 ロジスティクス業務の基本 8章 次世代ソリューションの基本
この書籍は、情報過多の現代において効率的に学ぶ方法を提供します。著者は、日本一アウトプットする精神科医であり、脳科学に基づいた80のインプット術を紹介。内容は、質を重視したインプット法や記憶に残る読書法、効果的な聞き方、インターネット活用術など多岐にわたります。特に、限られた時間で良質な学びを得たい人や、学んだことを行動に移したい人に向けた実践的なアドバイスが満載です。著者は精神科医で、40万人以上に知識を伝えています。
本書は、未来シナリオを用いた未来洞察手法について、経営学やマーケティング学を基盤に、認知科学やデザイン学の視点を融合させた学際的なアプローチを提供する。内容は、未来を洞察する思考法、スキャニング手法、社会技術問題のシナリオ作成、シナリオ評価、アイデア生成の違い、ユーザー視点の導入によるアイデアの質向上、情報の多様性の影響、未来洞察による新商品開発とイノベーションなど多岐にわたる。著者は一橋大学の鷲田祐一教授で、マーケティングとイノベーション研究の専門家である。
この本は、企業再生や事業承継、現場改善などをテーマにした実践的なケーススタディを集め、生産性向上に焦点を当てて具体的に解説しています。各章では、異なる業種の具体的な事例を通じて、コンサルティングの基本や実行方法を紹介し、即実践可能な内容が盛り込まれています。
本書は、ITエンジニア向けの業務知識入門書の改訂版で、最新の社会情勢や法規に対応しています。システム開発にはITスキルだけでなく、業務知識も必要であり、全体像を把握しやすく解説されています。主要な6分野(会社経営、財務会計、人事管理、販売管理、生産管理、物流・在庫管理)について、情報システム構築に必要な知識を体系的にまとめています。
デジタルが主体の時代に突入しどのように顧客行動が変わっていくかを中国の事例をふんだんにまじえながら教えてくれる良書。デジタル時代のマーケティングをおさえるためにぜひ読んでおきたい1冊
日本人のライバルは中国、インドのトップ10%、これからは、リーグ戦を勝ち抜いた経営者の時代になる、仕事ができるかどうかのポイントは、ストレス耐性、一般解を求める経営者は、答えを先送りする、失敗がないのは、勝負してないことの証、プロフェッショナルは、人間の苦悩と対峙する仕事、ほか、ガチンコ勝負でプロフェッショナルをめざす、リーダーに必要なのは「ストレス耐性」と「胆力」だ。 第1章 カイシャ幕藩体制の崩壊(21世紀の日本人は、カイシャ幕藩体制では幸せにはなれない 下部構造が傷み始めたとき、上部構造はもっと傷んでいる ほか) 第2章 産業再生機構の修羅場で見えたもの(仕事ができるかどうかのポイントは、ストレス耐性 経営責任は、だれにもとれない ほか) 第3章 戦闘力を身につけろ(グレてストレス耐性を身につける 若さゆえにとれるリスクに身をゆだねろ ほか) 第4章 戦闘力はこう使え(経営の本質は「片手にそろばん、片手に論語」 リーダーに求められるのは、不断の自己否定 ほか)
戦略の基本ツール,論理の組み方,考え方を学ぶ大好評テキスト。インターネット時代の進展や社会の変化に合わせた最新版。プラットフォーマーを対象に加え,理論的フレームワークも更新,魅力的なケースも充実。学生・社会人に,経営戦略を学ぶにも最適の入門書。 序 章 イントロダクション──大きく,未来を,論理的に考える 第Ⅰ部 マーケティング戦略 第1章 マーケティング・ミックス──4つのP 第2章 ターゲット市場の選定──セグメンテーション 第3章 プロダクト・ライフサイクル──4つの段階とマーケティング・ミックス 第4章 市場地位別のマーケティング戦略──いかに他社と競争するか 第5章 インターネット時代のマーケティング戦略──ロングテールとプラットフォーマー 第Ⅱ部 より広い戦略的視点を求めて 第6章 業界の構造分析──6つの競争要因 第7章 全社戦略──PPMの考え方 第8章 事業とドメインの定義──戦略的思考の基本・出発点 終 章 戦略的思考に向かって──切り捨て,集中する
クロネコヤマトの社長が宅急便にカジを切って大成功した時のことが書いてある。周りからは反対されて黒字になるわけないと言われていた個人宅配を見事に軌道にのせた先見の明には脱帽。ネットワーク効果を見越して必ず黒字転換点があるはずと見込んでの一手。経営者がぜひ読むべきオススメの1冊。
「ブルー・オーシャン戦略」は、競争の激しい既存市場から脱却し、未開拓の市場を創出するための戦略を体系化した書籍です。著者は、世界で350万部以上が売れ、43カ国語に翻訳されたこのベストセラーを通じて、企業や非営利組織が新市場を開拓できる方法を示しています。内容は、戦略の策定と実行に関する具体的な手法やフレームワークを提供しており、幅広い組織に役立つものとなっています。著者は、国際的なビジネススクールの教授陣であり、戦略論や国際経営に精通しています。
MBAシリーズ第8弾!勝ち残るために「論理的思考力」を鍛える!論理展開、因果関係、構造的アプローチなど、実践的思考法を演習の繰り返しで習得。 クリティカル・シンキングを始める前に 第1部 論理を解き明かす(論理展開の基礎 因果関係を見極める) 第2部 構造を解き明かす(構造的アプローチ ケーススタディ)
本書は、マーケティングの入門書であり、12万部を超えるロングセラーの新装版です。顧客にとっての「価値」を出発点に、ターゲティング、差別化、4Pを通じてマーケティング理論を理解できる内容です。また、新人社員が廃業寸前のレストランを復活させるサブストーリーを通じて、実践的な活用法も学べます。著者はマーケティングの専門家で、さまざまな業界でのコンサルティング経験があります。
初学者向けのマーケティングの書籍として非常にオススメ。顧客が欲しいのはドリルではなくて穴。マーケティングにおいて重要な顧客の課題にフォーカスした考え方を学べる。マーケティングを学び始めたばかりの人はこの書籍をぜひ手にとって欲しい。
株主総会資料の電子提供、株主提案権の濫用的な行使の制限、取締役の報酬等の決定方針--。最新改正を踏まえてロングセラーを改訂。 2006年制定以来、改正が続けられている会社法。直近の2019年12月に成立した改正の主なポイントは、「株主総会に関する規律の見直し」と「取締役等に関する規律の見直し」の2つが柱です。 主な項目としては、①株主総会資料の電子提供、②株主提案権の濫用的な行使の制限、③取締役の報酬等の決定方針、④株式報酬等の手続、⑤D&O保険、会社補償、⑥業務執行の社外取締役への委任の要件・手続、⑦社外取締役設置義務化、⑧社債の管理、⑨株式交付(自社株式等を対価とするTOBなど)が盛り込まれています。 今回の改訂に当たっては、上記の改正の重要度の高いものをコンパクトに解説、ロングセラーテキストの最新版です。 第1章 企業活動と法 第2章 株式会社とは 第3章 株式会社の機関 第4章 株式の役割 第5章 会社の資金調達手段 第6章 損益の計算と分配 第7章 会社の組織変動
この本は、著者がBCGでの経験を通じて得た「行動を変える」技術「スウィッチ」を紹介しています。著者は、戦略やコンサルティングのセンスがなかったものの、「チャーム」を活かして先輩たちから多くのことを学びました。目次には、愛や想像力、チャーム、論点の重要性、示唆の見抜き方などが含まれており、行動や人生を今すぐ変える方法が提案されています。著者は一橋大学卒業後、NTTデータとBCGでの経験を活かし、考えるエンジン講座を設立しました。