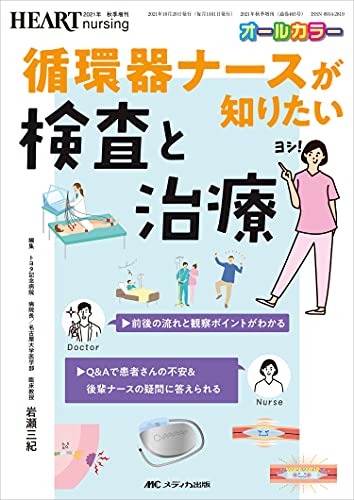【2025年】「教育担当」のおすすめ 本 149選!人気ランキング
- 企業内人材育成入門
- マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則
- 入社1年目の教科書
- 新しい教え方の教科書 Z世代の部下を持ったら読む本
- 若手育成の教科書 サイバーエージェント式 人が育つ「抜擢メソッド」
- 行動科学を使ってできる人が育つ! 教える技術
- 人事こそ最強の経営戦略
- 採用に強い会社は何をしているか ~52の事例から読み解く採用の原理原則
- 20代を無難に生きるな
- 人材マネジメント入門 日経文庫B76
本書は、人材育成に関する教育や学習の理論を心理学、教育学、経営学の観点から紹介し、企業全体の教育システムの重要性を説いています。著者たちは、個々の経験に基づく「私の教育論」が必ずしも他のケースに適用できないことを指摘し、効果的な研修や学習環境のデザイン、評価方法、キャリア開発などについての知見を提供します。最終的には、学びのメカニズムや動機づけの理論を通じて、より深い理解を促すことを目指しています。
本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。
この書籍は、仕事のやり方を変えるための50の指針を提供し、新人からベテランまで役立つ内容です。著者はライフネット生命保険の副社長であり、効率的な仕事の進め方やコミュニケーションの重要性を強調しています。具体的な指針として、遅刻をしない、迅速なメール返信、仕事の復習の重要性などが挙げられています。
入社1年目に限らず社会人として大事なエッセンスが詰まっている。1年目の若手はぜひこの本を読んで仕事に備えてほしい。この本に書いてあることをしっかり遂行できるか否かで社会人としてのパフォーマンスが大きく変わる。
これからの上司に求められるのはとにかくZ世代のパフォーマンスを高めることだ!これからの上司に必要なのは、Z世代を的確にマネジメントする能力――そう言っても過言ではないほど、すでに欠かすことのできない戦力になりつつあるZ世代。しかし、依然としてZ世代への関わり方に悩むマネジメント層は多い。そこで本書では、元中学・高校教師で、17,000名以上のZ世代社員への指導実績を誇る研修講師が、Z世代特有の価値観や彼らを動かすコツを解説。彼らの考えを理解し、パフォーマンスを高めることで、組織やチームを円滑に運営していきましょう。令和のマネジメント層の必読書――まさに「新しい教え方の教科書」です。 ■目次 第1章 平成の教え方はもう通用しない、Z世代のホンネと令和の教え方 第2章 教え育てることのスタートは、令和も良い関係をつくることから 第3章 これさえ知っていれば怖いものなし、令和式教え方のキホン 第4章 教えっぱなしはNG! 丁寧なフォローが今どき部下を動かす 第5章 一度教えるだけでは育たない、教え続けることの重要性とは 第6章 仕組みをつくり、人格を磨き続けて教え方のアップデートを
サイバーエージェントの人事部門役員、曽山哲人による「抜擢メソッド」を紹介する書籍です。このメソッドは、若手社員が自発的に成長する環境を整える方法を解説しており、マネジャーやトレーナー向けに設計されています。内容は、若手が「やりたい」と言える空気の作り方、自走スイッチを入れる方法、成長サイクルの回し方などで構成され、実践的なワークシートも含まれています。
この書籍は、グローバル人事の重要性とその実践方法について解説しています。具体的には、人の価値の測定や人材配置の戦略、グローバルリーダーの育成、組織の成長と変化、テクノロジーの影響などが取り上げられています。著者は人事戦略の専門家であり、過去には日本企業のグローバル人事に関する事例をまとめた著作もあります。
本書は、地方企業から有名企業、ベンチャーまでの成功事例を通じて、採用担当者が欲しい人材を惹きつける具体策を提供します。内容には、魅力的な求人コピーの作成法、SNSや人事ブログの活用、エージェントとの関係構築、リファラル採用の成功法、効果的な面接技術、候補者の本音を探る質問、内定辞退を防ぐための失敗例などが含まれています。多様な企業の事例を交えながら、採用担当者の悩みを解決するヒントが多数紹介されています。
この書籍は、20代における人生の基礎を築くための指南書であり、停滞するか成長するかの選択を促します。著者は、自分のスタイルを見つけること、周囲に流されず挑戦する姿勢、学びの重要性、人間関係の築き方を強調しています。特に「尖がれ」と「いい人を卒業する」ことが重要で、年上から学び、可愛がられる力を身につけることが推奨されています。最終的には、無難に生きるのではなく、挑戦することで成長と成功を得ることが強調されています。著者は人材育成の専門家で、多くの講演やセミナーを行っています。
本書は、ビジネス基本書「会社では教えてもらえない」シリーズの第5弾で、報告・連絡・相談(報連相)の重要性を解説しています。上司からの評価を得るためには、報連相を徹底することが不可欠であり、具体的なテクニックを紹介しています。内容は、報連相の基本から、効果的な報告方法、信頼を築く連絡、スムーズな相談方法、上司を動かすための報連相まで多岐にわたります。上司の評価に悩む人にとって、必読の一冊です。著者は経営コンサルタントの車塚元章氏です。
立教大学の中原淳教授による『人と組織の課題解決のための7つのステップ』は、人材開発と組織開発のプロセスを科学的かつ実践的に解説した入門書です。内容は、信頼構築、データ収集、フィードバック、実践、評価などのステップを通じて、企業の人事や教育担当者、コンサルタントが経営戦略に貢献する方法を探ります。著者は人材開発と組織開発の専門家であり、実務に役立つ知識を提供しています。
本書『エッセンシャル思考』は、無駄を排除し、本当に重要なことに集中する方法論を提案しています。著者グレッグ・マキューンは、重要な選択を見極め、瑣末な事柄を捨て、システム化することで、より少なく、しかしより良く生きることを目指します。この考え方は、単なるタイムマネジメントやライフハックを超えたものであり、現代において求められる生き方の変革を促しています。
普段の仕事や生活で自分の時間がなくて常に何かに追われている感覚があるのであれば是非読んで欲しい!本質的でないことは全て捨てて自分のやりたいことにフォーカスしよう!一度きりの人生、悩んでいる時間は無駄。社会人になりたてで四苦八苦している人がいたら是非読んで欲しい。
飛躍の法則
サイバーエージェント藤田さんの愛読書として名高いビジョナリー・カンパニー。偉大な会社を作る気概のある学生や経営者が読むべき書籍。1を読まずに2を読んでも問題ないが、2は偉大な企業を存続させることにフォーカスしていて1は偉大な企業を作ることにフォーカスしているのでまずは1から読むのがよいと思う。割と難解ではまらない人には全くはまらない書籍。
本書は、Googleの人事トップが採用、育成、評価の仕組みを初めて詳しく語るもので、企業がクリエイティブな働き方を実現するための原理を公開しています。著者はGoogleの人事システムを設計した責任者であり、同社の成功の秘訣や、優秀な人材の選び方、評価方法、チーム作りのノウハウを解説。古い働き方に悩むリーダーや若手に向けて、未来の働き方の指針を提供する内容です。
この書籍は、採用と人事が優れた企業は事業も強いと主張し、HR戦略に関する専門家8人の実践的な知見を提供しています。内容は、採用、育成、組織開発、HRテクノロジーに関する最新の理論と実務が含まれており、経営者や人事担当者にとって必読の一冊です。著者の北野唯我は、経営と人事の密接な関係を強調しています。
本書は、「スーパーボス」と呼ばれる優れたリーダーが有能な人材を育成する戦略を紹介しています。著者は多くの成功した経営者や指導者に取材し、彼らがどのように部下の能力を引き出し、創造性や業績を向上させるかを分析しました。スーパーボスは、部下に挑戦を与え、柔軟性を持ちながらも目的を貫く管理スタイルを持ち、部下同士の協力を促進します。また、元部下とのネットワークを築くことで、さらなる成功を収めることができます。リーダーやマネージャーにとって、スーパーボスになるための具体的な手法が示されています。
「最高の職場」をつくる6つの原則 シリコンバレーを魅了したネットフリックスの人材管理 CHROは経営者たれ アジャイル化する人事 ピープルアナリティクスで人事戦略が変わる 終身雇用を捨てよう 社員の成長につながる人事評価システムをつくる シニア世代を競争優位の源泉に変える コラボレーティブ・インテリジェンス 差別の心理学 人材は潜在能力で見極める
この書籍は、伝統的な「人事」のネガティブなイメージを払拭し、現在求められる「戦略性のマネジメント」について論じています。著者たちは、組織の力を引き出す方法やリーダーの育成、人事の役割について経営視点から詳述しています。人事の専門家が、企業の持続的な成長を支えるための実践的な知識を提供する内容となっています。
本書は、ポストコロナ時代における人材育成の方法を解説しており、自ら考え行動する人材を育てるための5つの原則を紹介しています。著者は、研修の効果を持続させるための理論を基に、具体的な事例を通じて人材育成の重要性や実践方法を示しています。特に、組織全体の活性化や社員の意義を考えさせることの重要性が強調されており、成功事例も多く紹介されています。著者は人材育成コンサルタントであり、年間100回以上の講義を行っています。
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)人材の育成方法とその重要性について解説しています。DX人材の役割や必要なスキル、育成手法、研修事例を具体的に示し、企業がDX人材をどのように発掘・育成できるかを詳述しています。経営者や人事担当者、管理職に向けて、実践的なノウハウを提供する内容となっています。著者はDXプロジェクトに関与する専門家であり、実績を基にした具体的な育成計画も紹介しています。
本書『人材マネジメント入門』は、人材マネジメントの基礎知識を体系的に解説した公式テキストです。10章にわたり、評価、報酬、採用、異動、人材開発などの重要なテーマを図解とともに紹介し、実際の企業の事例も挙げています。人事担当者や管理職向けに、知識の習得や試験を通じた証明を促進します。検定は年4回実施され、合格者には認定証が発行されます。著者は20年間の人事経験を持つ専門家です。
本書は、人材業界の過去100年を分析し、転職の価値観が変化した経緯や現状を探るとともに、今後の業界の未来を予測します。かつては終身雇用が一般的だったが、現在では転職がキャリア構築に不可欠な手段となっています。情報過多や信頼できるアドバイスを求める声が増えており、業界内ではAIや新たなビジネスモデルへの不安も広がっています。著者は、採用担当者や人材業界に興味を持つ人々に向けて、これからの変化にどう対応すべきかを考察しています。
公立高校野球部のマネージャーみなみは、ドラッカーの経営書『マネジメント』に出会い、野球部を強化するためにその教えを活用します。親友の夕紀や仲間たちと共に、甲子園を目指す青春物語が展開されます。この物語は、家庭や学校、企業など、あらゆる組織に役立つ内容です。著者は岩崎夏海で、放送作家やプロデューサーとしての経歴があります。
この書籍は、9つの学びのスタイル(経験、想像、内省、分析、思考、決定、行動、開始、バランス)を通じて、自分自身の学びのスタイルを理解し、長所と短所を把握する方法を紹介しています。これにより、人間関係やグループ活動に役立つヒントを得ることができます。また、経験から学ぶことで人生を変える可能性についても触れています。著者は経験学習の専門家であり、効率的なチーム作りや学習する組織の推進に取り組んでいます。
この本は、生成AI、特にChatGPTが教師の仕事や教育に与える影響を解説しています。具体的な活用法として、授業案の作成、アウトプットの準備、文書の校正など、多様な事例を紹介。基本的な使い方から応用編まで、誰でも実践できる内容が盛り込まれています。著者は京都府の公立小学校教諭で、教育の生産性改革を推進しています。
本書は、管理職向けのマネジメント書で、リモートワークにも適した「識学」という組織論を紹介しています。識学は、組織内の誤解や錯覚を解消する方法を明らかにし、4400社以上が導入しています。著者は安藤広大で、若手リーダーや中間管理職に向けた具体的なノウハウを提供し、リーダーの言動の重要性を強調しています。
組織のトップとしてのあるべき姿を説く書籍。この本に書いてある内容は自分の想像するリーダー像と違いすぎて驚いた。確かに組織を大きくして社会にインパクトを与えるためにはこの本の中で書かれているリーダーの仮面が必要なのかもしれないが、私はそんなことまでしてリーダーで居続けて何が楽しいのかなと思ってしまう。旧式の企業にはハマるがこれからの時代にはハマらない考え方な気がする。自分自身も会社を経営する身として参考にしつつもこの本の中で語られているリーダーとは違う姿を模索したい
この書籍は、学生や若手社会人が「会社」ではなく「ジョブ」で選ぶ新しい仕事図鑑です。NewsPicksが取材したプロフェッショナルの経験談や未来予測を通じて、22の職種の最新動向やリアルな情報を提供します。具体的には、各職種のスキルややりがい、将来性を紹介し、転職時のキャリアイメージを助ける内容になっています。また、JobPicksというWebサービスも紹介されており、様々な職業のキャリア情報を共有しています。自分に合った仕事を見つけるための一冊です。
この書籍は、上司が部下を効果的に育成するためのティーチング技術を紹介しています。「教える」とは何か、必要なスキルや実践方法について解説し、選択理論に基づく30のメソッドを提案しています。著者の佐藤英郎は、長年の研修経験を持ち、多くの企業で評価されています。内容は、部下を教える意味や上司の心得、実践方法、教える環境の整え方、コミュニケーション力の重要性について触れています。
著者は、マッキンゼーの採用マネジャーとして12年間の経験をもとに、リーダーシップと採用基準について語る内容の書籍を執筆しました。目次では、誤解されがちな採用基準やリーダーシップの重要性、リーダーが果たすべき役割などが取り上げられています。著者はキャリア形成コンサルタントであり、リーダーシップ教育に関する啓蒙活動を行っています。
この文章は、半世紀にわたって読み継がれてきた名著論文を収録した書籍の内容を紹介しています。目次には、モチベーションの定義や新しい理論、知識労働者の心理、MBOの失敗、ピグマリオン・マネジメント、モチベーショナル・リーダーの条件、理想の職場の作り方、Y理論の限界、本物のリーダーの特性などが含まれています。
著者の最新作は、次世代リーダーの育成に焦点を当て、一人ひとりの強みを活かしながら「フラットなチーム」を作る方法を具体的に紹介しています。リーダーが直面する悩みを解決するため、メンバーの「自分ごと化」を促し、主体的に話し合う会議の作り方や、チームでのゴール設定、組織を超えた交流の場の重要性について述べています。著者は、リーダーシップ開発に取り組む伊藤羊一氏です。
本書は、家庭や企業、コミュニティにおけるリーダーシップの課題に対処するための理論と実例を紹介し、実践的なエクササイズを通じてリーダーシップを身につける方法を探ります。著名な経営者の事例を解説し、具体的な知識を提供します。著者は金井寿宏で、経営学の専門家です。
この書籍は、新入社員や物覚えが悪い人を即戦力に育てる方法を紹介しています。良好な関係を築き、効果的に教え、自立を促す技術が解説されています。目次には、教える前の準備、教える目的、効果的な方法、心をつかむ技術、大人数への指導などが含まれています。著者はプレゼンテーションと教え方の専門家、田中省三氏で、教育現場での豊富な経験を持っています。
本書は、2025年に国難期を迎える中で、中小企業の廃業危機や社会保障の限界に対処するため、リーダーが若い人たちの潜在能力を引き出し育成する重要性を説いています。著者は「人的資本経営」の成功事例を通じて、リーダーが実践すべき101のセオリーを6章に分けて解説し、誰でも実践しやすい内容にしています。最終的には、企業の増収増益と従業員の幸福を目指すことが強調されています。
本書は、ゼネラル・エレクトリック社(GE)の幹部研修プログラムでの学びを元に、「成長し続ける人」の共通点を探る内容です。著者はGEのクロトンビルでリーダーシップ研修を担当した田口力氏で、自己認識、伝達力、意思決定、学び続ける姿勢、変化への適応、自分の運命をコントロールすること、他者を導くことなど、成長に必要な要素を解説しています。
この文章は、人事管理に関する基本知識を紹介する目次です。各章では、人事の基本、雇用管理、人材活用、育成、労働条件、報酬管理、福利厚生、安全衛生、社内コミュニケーション、そして現代の人事の課題について解説しています。
この書籍は、基本的な操作から応用まで、教育現場でのCanvaの活用法を3つのステップで解説しています。第1章では教師向けの使い方、第2章では子どもたちが使うためのステップ、第3章では授業での活用方法について具体的な事例が紹介されています。著者は青森県の公立小学校教諭で、プログラミング教育に関する専門家です。
本書は、子どもが主体的に漢字を学ぶための新しい指導システムを提案しています。受け身の学習から脱却し、自立した学習者として成長できるようにすることが目的です。内容は、漢字指導の方法や効果的な学習活動のアイデアを紹介し、全員が漢字を定着させるためのシステムを解説しています。著者は教育者であり、数々の教育賞を受賞しています。
社会人生活の基本となる「あいさつ」「身だしなみ」「言葉使い」などのビジネスマナーや、金融機関の職員に求められるコンプライアンス感覚をわかりやすく解説。雑誌風の見出しやコラム、図表やイラストを多用することで、わかりやすく解説している。金融業界への就職を控えた内定者や、金融業界への就職を希望する学生にとって最適な書。
この書籍は、部下育成に関する実践的な方法を提案しており、新人からベテランまで幅広く効果的な指導が可能な「ものさし」を紹介しています。著者たちは、年間15万人以上の受講者を持つ企業人の成長モデルを基に、適切な仕事の割り当てや公平な評価を通じて、部下の成長を促す方法を解説しています。目次には、部下育成のチャンスやステージ別の育成方法が含まれています。著者はリクルートマネジメントソリューションズの研究員であり、人材育成に関する豊富な経験を持っています。
著者は、3000人以上を指導した経験を持つ人気講師で、人に教える際の心構えや準備、反省の重要性を詳しく解説しています。内容は、効果的な教え方30のポイントを含み、講義の準備や話し方、集中を維持する方法などが紹介されています。
本書は、ビジネスにおける「提案の技術」をテーマに、論理思考やプレゼンテーション能力を実践的に学ぶためのガイドです。著者は、外資コンサルや商社での経験を基に、提案を成功に導くための基本的なスキルを整理しています。内容は、論理思考力、仮説検証力、会議設計力、資料作成力の4つの能力に焦点を当て、各章がストーリー、解説、まとめで構成されています。ビジネス現場での実践的なスキルを身につけることができる内容です。
ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。
本書『最高のコーチは教えない』は、相手のモチベーションを高め、能力を引き出すためのコーチング技術を紹介しています。著者の吉井理人は、教えるのではなく、質問を通じて自ら考えさせるアプローチを提唱。プロ野球選手のコーチング経験を基に、ビジネスシーンでも応用可能な方法を解説しています。読者からは、指導方法に悩む人々にとって有益であるとの声が寄せられています。
本書は、不安定で協働が苦手な教室に「つながり」を取り戻すための具体策を示した一冊です。子どもたちの内面を分析し、具体的なアクションやアクティビティをイラストでわかりやすく紹介しています。目次には、対等・安全な教室の基盤作りや、他者意識の醸成、関わりの量の増加など、様々な戦略が含まれています。著者の佐橋慶彦は、名古屋市の公立小学校で教育に従事し、学級経営や子ども目線のアプローチを研究しています。
この書籍は、算数授業のさまざまな要素を網羅しており、効果的な授業を行うための方法や工夫について解説しています。内容は、授業の準備や進行方法、子どもの思考を引き出すための課題提示、話し合いや発表の工夫、ノート指導や板書の重要性、教科書の扱い方、テストの意義、能動的な学習態度の育成など多岐にわたります。著者は新潟県出身の教育者で、算数教育において豊富な経験を持つ専門家です。
「ギブ&テイク」は、人間の行動を「与える人」「自分優先の人」「バランスを考える人」の3つのタイプに分類し、それぞれの特徴と可能性を分析する著作です。著者アダム・グラントは、与えることが成功につながる新しい常識を提唱し、成功するギバーの行動戦略や人脈の重要性を論じています。彼はペンシルベニア大学ウォートン校の最年少終身教授であり、組織心理学の専門家です。
著者はリクルートやライフネット生命、オープンハウスでの人事・採用責任者としての経験をもとに、人材マネジメントの重要性を説いています。書籍では、人事の役割や採用計画、面接の質向上、優秀な人材の確保などについての理論を解説しています。著者、曽和利光は人材研究所の代表であり、豊富な人事経験を持つ専門家です。
この書籍は、社員のモチベーションを高めるためには、まず「モチベーションを下げる要因」を取り除くことが重要であると説いています。著者は、疲弊する組織や高離職率の会社に共通する問題を分析し、改善策を心理的アプローチを基に解説しています。具体的には、上司の問題や組織の疲弊に関するパターンを示し、心理的安全性や自己効力感などの概念を通じて、金銭的報酬だけでなく「見えない報酬」の重要性を強調しています。著者は、経営コンサルタントとしての経験を活かし、効果的なマネジメント手法を提案しています。
これまでの経営学習論の研究成果を紹介・総括し,さらには独自の実証的な調査データを駆使して,組織経営における有効な人材能力形成施策を展望する定番書が,書き下ろしの新章「リーダーシップ開発」を加えて装いも新たにリニューアル刊行. 第1章 本書の概観 1.本書の目的 2.本書で用いるデータ 3.本書の構成 4.小括 第2章 経営学習論をめぐる社会的背景 1.「経営課題としての人材育成」をめぐる社会的背景 2.戦略的な「人材育成の再構築」へ 3.経営学習論の青写真 4.小括 第3章 組織社会化 1.組織社会化と学習 2.組織社会化プロセス 3.組織参入時の学習においてOJT指導員が果たす役割 4.小括 第4章 経験学習 1.経験と学習 2.経験学習研究の展開 3.経験学習の実態に迫る 4.小括 第5章 職場学習 1.職場学習の定義 2.職場学習の先行研究 3.職場学習への実証的アプローチ 4.小括 第6章 組織再社会化 1.2つの組織再社会化 2.中途採用者の組織再社会化 3.小括 第7章 越境学習 1.越境学習 2.越境学習の深層に存在する主要な社会的ニーズ 3.越境学習の実態に迫る 4.越境をめぐる社会的実験 5.小括 第8章 今後の研究課題――グローバル化に対応した人材育成の模索 1.グローバル化と人材開発 2.結語 補 章 リーダーシップ開発 1.リーダーシップ 2.「リーダーシップ開発」という概念 3.企業におけるリーダーシップ開発の実際 4.実証的研究 5.小括
この書籍は、7400人の調査結果と人材開発の理論を基に、現代の多様性の時代における女性の育成方法を探求しています。優秀な女性が職場で直面する問題に悩むマネジャーや人事担当者に向けて、女性が職場に求めるものや自信を得る瞬間、管理職への道、育児と仕事の両立についての洞察を提供します。著者は立教大学の中原淳教授で、企業における人材開発とリーダーシップの研究を行っています。
この書籍は、1500人以上の面接官を指導した著者が、企業の面接技法について解説しています。内容は、面接の問題点、成功する面接の秘訣、面接力を向上させる方法、質問力や見抜く力を高める実践例、悩み別の解決法、面接官が注意すべきポイントなどを含んでいます。著者はリクルートキャリアの面接コンサルタントで、心理学を学んだ経歴があります。
著者の酒井穣が、ベストセラー『はじめての課長の教科書』に続き、IT系ベンチャー企業フリービット株式会社での実務経験を基に人材育成プログラムの理論と実践を解説。プログラムの目的、対象、タイミング、設計、責任者、効果測定、具体例を含む内容が展開されている。
この書籍は、誰でも教え上手になれるノウハウを提供し、新卒や年上の部下、アルバイトなど多様な相手に対する指導法を伝授します。物語は旅館「塩の屋」の女将代理・温子が成長する過程を描き、彼女が人を見る目やアイデアを考える力を身につけていく様子が展開されます。著者はマンガ家のあべかよこと、企業内研修の専門家である関根雅泰です。
この書籍は、算数授業を変えるための14の「しかけ」を紹介し、それぞれに5つの事例を提供しています。授業を通じて子どもたちの学びを深める方法を探る内容で、具体的な事例を通じて実践的なアイデアを提供します。著者は北海道教育大学附属札幌小学校の教諭、瀧ヶ平悠史氏です。
本書は、個人情報保護法やGDPR、NISTフレームワークに対応するための企業向けの情報管理に関する総合専門書です。日本企業は、情報漏えいや国際的な情報管理リスクに直面しており、統一的な情報管理システムの構築が求められています。法的観点からの論点をベーカー&マッケンジー法律事務所が提示し、デロイトが実務的な解決策を提供しています。内容は、情報マネジメントの重要性や具体的な管理手法について詳述されています。
災害・危機発生時の職員の役割と行動 組織と法制度上の課題 被災自治体職員が抱える課題 災害時の応援自治体職員の課題と展望 危機管理における官民の連携 試案 大規模災害時における被災市町村への人的支援 「組織と人」に関する防災・復興法制の現状と課題 自治体職員の惨事ストレス 災害時のパニックと心理的ショック
本書は、採用活動における一般的な誤解やNG行動を指摘し、効果的な採用方法を提案しています。内容は「募集」「選抜」「フォロー」の3つのプロセスに沿って構成され、採用初心者にも理解しやすい形で説明されています。著者は、採用活動の進め方や求職者の集め方、応募者の選抜方法、内定辞退を避けるためのフォローなどを具体的に解説し、自社の採用課題を見つける手助けも行います。
このビジネス書は、多様性を取り入れた組織が成功する理由を探求し、致命的な失敗を未然に防ぎ生産性を高めるための組織改革の方法を提示しています。著者マシュー・サイドは、革新を促す要素やコミュニケーションの重要性について考察し、具体的な事例を通じて読者に考えさせる内容となっています。シリーズは好評を博し、さまざまなメディアで紹介されています。
今では色んなところで引用される人生100年時代というパスワードのきっかけになった書籍。もう既に1つの会社に勤め上げるような旧来の生き方は崩壊している。将来に不安を抱いているビジネスパーソンはこの本を読んで時代の変化に置いていかれないような生き方を選択して欲しい。
本書は、ビッグデータとAIを活用した「ピープルアナリティクス」が日本企業の人材マネジメントに与える影響を解説しています。内容は、ピープルアナリティクスの定義やその効果、データ活用の視点、人事システムの再構築、分析技術と実務、運用組織の構築、将来の展望に分かれています。また、実際の企業事例も紹介されており、データドリブン型の人事への変換を促進する内容となっています。著者は、HRテクノロジー分野の専門家であり、国内での普及活動にも力を入れています。
本書は、世界で最も賞賛される企業の人事担当者が、日本企業が欧米企業に比べて競争力を失った理由と、成功する人事施策の秘訣を解説しています。具体的には、優良企業の人材マネジメントや企業文化の構築に関する事例を通じて、活力ある企業風土の重要性を示しています。人事関係者や経営者にとって必読の内容です。著者は浅川港で、豊富な経歴を持つ専門家です。
カジュアル衣料品店「ナチュレル」で店長に抜擢された凛は、部下や後輩の指導に悩む中、ある男性と出会い「教える技術」を学ぶ。これを通じて、彼女自身や周囲の人々が変わり始め、店舗は地区ナンバーワンの売上を達成する。著者は行動科学の専門家で、ビジネスや教育の現場で活躍している石田淳。
本書は、世阿弥の「風姿花伝」に基づき、教師の授業実践と学びのあり方を探求します。著者の佐藤学氏は、授業技術を指南するのではなく、教師の「学びの思想」と「身体技法」を伝えることを目指しています。内容は、教師としての成長や創造的な授業技法、実践例を通じた教師の役割についての考察が含まれています。佐藤氏は教育界で高く評価されている専門家です。
本書は、外資系コンサルタントが身につけるべーシックスキル30個を紹介し、職業や業界を問わず役立つ普遍的なスキルを提供します。新人からベテランまでが使える内容で、15年後にも通用する能力を身につけることを目的としています。著者は自身の経験と元コンサルタントへの取材を基に、実践的な技術や思考法、デスクワーク術、プロフェッショナルマインドを解説しています。
道徳的価値って、そもそも何だろう? 文部科学省教科調査官(当時)として学習指導要領改訂に携わった著者が、道徳的価値について様々な観点から解説。道徳的価値への確かな理解がよりよい道徳授業を創る! 学習指導要領では特別の教科 道徳の教科目標として「道徳的価値の理解を基に・・(中略)・・道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」ことが示されました。では、道徳的価値とはそもそも何でしょう。 「自律」「自由」「責任」「個性の伸長」「社会正義」・・・など、大人でも説明が難しいような「道徳的価値」について、その見方・考え方を徹底解説。子どもたちの発達段階に合わせてどのような指導をしたらよいかが分かります。 ●著者について 赤堀 博行(帝京大学大学院教職研究科教授) 1960年東京都生まれ。都内公立小学校教諭、調布市教育委員会指導主事、東京都教育庁指導部義務教育心身障害教育指導課指導主事、同統括指導主事、東京都知事本局企画調整部企画調整課調整主査(治安対策担当)、東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事、東京都教育庁指導部主任指導主事(教育課程・教育経営担当)、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官を経て、現職。 教諭時代は、道徳の時間の授業実践、生徒指導に、指導主事時代は、道徳授業の地区公開講座の充実、教育課程関係資料の作成などに尽力する。この間、平成4年度文部省道徳教育推進状況調査研究協力者、平成6年度文部省小学校道徳教育推進指導資料作成協力者「うばわれた自由(ビデオ資料)」、平成14年度文部科学省道徳教育推進指導資料作成協力者「心のノートを生かした道徳教育の展開」平成15年度文部科学省生徒指導推進指導資料作成協力者「非行防止教育実践事例集」、平成20年度版『小学校学習指導要領解説 道徳編』の作成にかかわる。 第1章 学校の道徳教育における道徳的価値の考え方 1 道徳授業が目指すもの 2 道徳的価値の見方・考え方 3 道徳的価値と徳目 4 道徳の内容項目と道徳的価値 第2章 道徳の内容項目と道徳的価値 1 A主として自分自身に関すること ⑴善悪の判断、自律、自由と責任 ①正義 ➁自主自律 ➂自信 ④自由 ➄責任 ⑵正直、誠実 ①正直 ➁素直 ➂明朗 ④反省 ➄誠実 ⑶節度、節制 ①健康 ②安全 ③物持 ④節約 ➄整理整頓 ⑥自立 ⑦思慮 ⑧節度 ⑨節制 ⑷個性の伸長 ①個性伸長 ②向上心 ⑸希望と勇気、努力と強い意志 ①勤勉 ②努力 ③不撓不屈 ④希望 ➄勇気 ⑥克己 ⑹真理の探究 ①探究心 ②創意 ③進取 2 B主として人との関わりに関すること ⑴親切、思いやり ①親切 ②同情 ⑵感謝 ①尊敬 ②感謝 ③報恩 ⑶礼儀 ①礼儀 ②真心 ⑷友情、信頼 ①友情 ②協力 ③信頼 ④異性尊重 ⑸相互理解、寛容 ①相互理解 ②寛容 ③謙虚 3 C主として集団や社会との関わりに関すること ⑴規則の尊重 ①規則遵守 ②公共心 ③公徳心 ④権利 ➄義務 ⑵公正、公平、社会正義 ①公正 ②公平 ③社会正義 ⑶勤労、公共の精神 ①勤労 ②奉仕 ⑷家族愛、家庭生活の充実 ①家族愛 ・孝行 ・友愛 ⑸よりよい学校生活、集団生活の充実 ①愛校心 ⑹伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度 ①郷土愛 ②愛国心 ⑺国際理解、国際親善 ①国際理解 ②国際親善 ③人類愛 4 D主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること ⑴生命の尊さ ①生命尊重 ⑵自然愛護 ①動植物愛護 ②自然愛護 ③環境保全 ⑶感動、畏敬の念 ①畏敬 ②敬虔 ⑷よりよく生きる喜び ①高潔 おわりに 道徳科の特質を生かした授業を行うために
「道徳読み」=教科書の読み物教材を徹底活用した、どの教科書でも使える授業法。 準備物はありません。教科書と鉛筆、そして考える頭だけ。 「道徳読み」は次の5つのパートで構成されます。 1、普通に読む 2、道徳読み(道徳さがし・道徳みつけ)をする →子どもたちは、主体的に、真剣に、教材と向き合います。 3、みつけた道徳を発表する →子どもたちは、対話を通じて自分が気づかなかった道徳を獲得。 4、登場人物に通知表を付ける →子どもたちは、自分とは異なる考え方を学びます。 5、自分を省みる →子どもたちは、自分自身への深い学びを体験します。 この授業法を学べば、誰でも、主体的・対話的で深い学びのある道徳授業ができるようになります。 本書では「道徳読み」の基本から実践までを1冊に収録しました。実践パートでは、おなじみの教材を使った授業が、学習指導案から実際の授業のながれまで全学年分掲載されています。 Ⅰ 「道徳読み」の基本 1 道徳の基本的な考え方 ①道徳脳で教材を読む/②心は自分から/③第二の天性を豊かにする/④他人には優しく。自分には? 2 「道徳読み」の方法 ①普通に読む(通読)/②道徳さがし・道徳みつけ/③発表をする/④通知表を付ける/⑤省みる(自分の心に落とす) 3 評価(子どもに対する評価) ①「特別な教科 道徳」の評価/②「道徳読み」での評価 4 「道徳読み」の効果 ①子どもへの効果/②広がる目/③教師の教材分析力がつく Ⅱ 「道徳読み」の実際 1 学年別・授業実践 第一学年 「はしのうえのおおかみ」 第二学年 「七つぼし」 第三学年 「ヒキガエルとロバ」 第四学年 「ブラッドレーのせい求書」 第五学年 「手品師」 第六学年 「ブランコ乗りとピエロ」 2 「道徳読み」をより豊かにするために 発展例① 「道徳ってどんな勉強?」 発展例② 「読み物教材以外で『道徳読み』」 Ⅲ「道徳読み」に困ったらQ&A コラム●「道徳読み」と学級づくり ① 子どもを観る視点にする/② 5分間の小さな「道徳読み」/③「法治」と「徳治」
この書籍は、AI時代における人事戦略の新たな方向性を示すもので、著者バーナード・マーがデータを活用した人事の重要性を強調しています。内容は、データ・ドリブン人事戦略の概念から始まり、インテリジェントHRへの進化、採用、従業員エンゲージメント、パフォーマンスマネジメントなど多岐にわたるトピックを扱っています。翻訳は中原孝子が担当し、日本の人事プロフェッショナルの変革を促すことを目的としています。著者はビジネス界で広く認識されている専門家であり、さまざまな企業や政府機関に対して戦略アドバイザーとして活躍しています。
本書は、大人を教える際の効果的な方法について解説しています。著者の関根雅泰は、企業研修の専門家であり、大人に対する「正しい教え方」を提案しています。重要なポイントは「相手の立場に立つ」ことと「学習の手助けをする」ことです。内容は、命令的な教え方を避け、一方的な説明ではなく、相手が理解しやすい方法を重視しています。また、プライドの高い大人に対するアプローチや、教えられる側の重要性についても触れています。主に大人を指導する立場にある人に向けた内容です。
この1冊で、教師1年目を乗り切る! 本書では、 「仕事のやり方」「新年度・新学期の準備」「学級経営」「授業」 「子どもとのコミュニケーション」「保護者との関わり方」 という教師の基本的な仕事内容とそのコツを紹介しています。 1年目は特に覚えることも多く、慌ただしい毎日が続きますが、 きちんとコツをおさえていけば、学級崩壊もせず1年目を乗り切ることができます。 何年も初任者指導にあたってきた著者だからわかる、 初任者のよくある失敗例などもあわせて紹介しています! 序章 最初の1ヶ月で身につけたい仕事のきほん まずはマネて、マネて、仕事を覚える/50点でいい!提出物の締めきり/お先に失礼しますが言える教師になる 1章 必ずやっておきたい新年度・新学期の準備 忙しい始業式はまずこの5つをおさえる/ 子どもの居場所確保が教室設営の役割/初任の先生がよくつまづく失敗 2章 ここだけは押さえたい学級経営のコツ 返事・挨拶・後始末ができる子どもに/朝の会・終わりの会は10分以内で/給食当番で学級崩壊を防ぐ 3章 新任だからできる! 授業の指導 1時間の授業に単元の基本を入れる/話の聞き方を指導しよう/基本的な板書の技術/ノート指導/学習ルール 4章 クラスをまとめる子どもとのコミュニケーション ほめ方&叱り方をみにつけよう/子どもとの距離のとり方/5段階でトラブルを解決する/いじめを防ぐ方法 5章 新任教師だからできる保護者とのかかわり方 最初の授業参観が保護者との関係を決める/挫折しない学級通信の続け方/どの親もわが子が一番
この書籍は、ビジネススキルだけではなく、組織を効果的に動かすための「Deep Skill」の重要性を説いています。著者は4000人以上のビジネスマンを観察し、組織力学や人間心理を活用する方法を紹介。信頼資産の構築、戦略的な人間関係の形成、権力の動かし方、人間力の向上など、実践的な技術を解説しています。著者は企業の新規事業創出を支援するコンサルタントであり、組織内での成功には深いスキルが不可欠であると強調しています。
はなまるフードサービスは、首都圏で惣菜・弁当の製造販売店を展開し、急成長を遂げていますが、人材不足に悩まされていました。募集活動に真剣に取り組むことで、募集費を半減し、採用数を倍増させることに成功しました。本書では、著者の経営理念の変遷や「人の問題」を解決するための具体的な取り組みが紹介されています。企業の人材問題に悩む方々に向けた内容です。
本書は、日本企業が米軍のような「軍隊型組織」から脱却し、現場の自由な動きを促進するための新しい経営戦略を提案しています。著者は、米軍の「機動戦」から学び、PDCAサイクルを超えたOODAループやミッション・コマンド、クリティカル・インテリジェンスを活用して、柔軟で効果的な組織運営を実現する方法を解説しています。具体的な事例や理論を通じて、ビジネス環境での生き残りを目指す戦略を示しています。
本書は、企業が自社商品やブランドのファンをどのように作り出すかを探る内容です。セガ、キングジム、タカラトミー、タニタ、東急ハンズ、井村屋の6社の「中の人」にインタビューし、SNS運用の具体例を通じてファンづくりの秘訣を明らかにします。消費者とのつながりが重視される中、企業の「中の人」が重要な役割を果たすことが強調されています。また、さとなお氏との座談会を通じて、ファンベースの視点から企業が愛されるために必要な取り組みについても考察しています。
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の基本から実現プロセスまでを図解で分かりやすく解説しています。基礎知識、デジタル技術、成功事例、戦略、実践的なノウハウを網羅し、ビジネスパーソンが知りたいDXに関する情報を凝縮しています。著者はDXエバンジェリストの荒瀬光宏氏で、企業や自治体のDX研究に基づいた実践的な知識を提供しています。
企業が人手不足に直面する中、「できる人財」を育成する重要性が強調されています。著者の有本均氏は、マクドナルドの「ハンバーガー大学」やユニクロの教育責任者を務めた経験を活かし、教育と評価の仕組みを整えることで、どんな人でも成長できる環境を作る方法を提案しています。具体的には、店長教育やアルバイトのモチベーション向上に関するノウハウを紹介し、実際の企業事例を通じて実践的な内容を提供しています。この書籍は、外食・小売り・サービス業界の経営層や人事担当者、教育に悩むビジネスパーソンに向けられています。
本書は、組織開発の重要性とその歴史、哲学、手法の変遷を探求し、組織の健全さや効果性を高めるためのコミュニケーション活性化を目的としています。著者たちは、組織開発が単なる手法ではなく、計画的かつ協働的なプロセスであることを強調し、実践事例を通じてその具体的なアプローチを示します。また、組織開発と人材開発の相互関係についても論じています。全体を通じて、組織開発の未来に関する対談も行われています。
この書籍は、子どもとの信頼関係を築く方法や、学習支援、トラブル解決のアプローチを紹介しており、子どもに寄り添った関わり方を増やすことができる内容です。著者の佐橋慶彦は名古屋市立公立小学校で11年間教職に従事し、教育実践に関する研究と実践を行っています。
「教育担当」に関するよくある質問
Q. 「教育担当」の本を選ぶポイントは?
A. 「教育担当」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「教育担当」本は?
A. 当サイトのランキングでは『企業内人材育成入門』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで149冊の中から厳選しています。
Q. 「教育担当」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「教育担当」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。


![『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UB6ayAOaL._SL500_.jpg)