【2025年】「課長」のおすすめ 本 159選!人気ランキング
- HIGH OUTPUT MANAGEMENT(ハイアウトプット マネジメント) 人を育て、成果を最大にするマネジメント
- 人を動かす 文庫版
- マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則
- だから僕たちは、組織を変えていける —やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた【ビジネス書グランプリ2023「マネジメント部門賞」受賞!】
- ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則
- 1兆ドルコーチ シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教え
- [新装版]指導者の条件
- 地方にこもる若者たち 都会と田舎の間に出現した新しい社会 (朝日新書)
- 図解コーチングマネジメント
- 最高の結果を出すKPIマネジメント
インテル元CEOのアンディ・グローブによる経営書が待望の復刊。シリコンバレーの経営者や起業家に影響を与え続ける本書では、マネジャーが注力すべき仕事やタイムマネジメント、意思決定のポイント、効果的なミーティングの進め方など、実践的なアドバイスが満載。著名な経営者たちからも高く評価されており、マネジメントの基本原理を学ぶための重要な一冊となっている。
本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。
本書は、組織の変革を目指す人々に向けたガイドで、特に「関係性」を重視したアプローチを提案しています。近年の「デジタルシフト」「ソーシャルシフト」「ライフシフト」により、従来の管理主義が通用しなくなった中で、組織が抱える問題を解決する方法を示します。著者は、組織のメンバー一人ひとりが関係性、思考、行動を改善することで、全体を変えていけると主張しています。また、実践的なメソッドや成功事例を通じて、読者に希望を与える内容となっています。著者の講演も多くの企業から依頼されており、実績も評価されています。
飛躍の法則
サイバーエージェント藤田さんの愛読書として名高いビジョナリー・カンパニー。偉大な会社を作る気概のある学生や経営者が読むべき書籍。1を読まずに2を読んでも問題ないが、2は偉大な企業を存続させることにフォーカスしていて1は偉大な企業を作ることにフォーカスしているのでまずは1から読むのがよいと思う。割と難解ではまらない人には全くはまらない書籍。
本書は、シリコンバレーの伝説的リーダー、ビル・キャンベルの教えをまとめたもので、著者は彼に師事した人物です。キャンベルはジョブズと共にアップルを築き、グーグルやアマゾンを成功に導いたプロ経営者であり、彼の教えは「人がすべて」「信頼の重要性」「チーム重視」などの原則に基づいています。著者たちは、キャンベルの成功哲学を明らかにし、ビジネスにおける愛や成功の測り方についても触れています。
この文章は、松下幸之助の著作についての紹介です。内容は、自己受容や表現、怒りの感情、一視同仁の精神、命をかける覚悟、祈り、冷静さ、価値判断などのテーマを扱っています。松下幸之助は1894年に生まれ、松下電器を創立し、PHP研究所や松下政経塾を設立した実業家で、1989年に亡くなりました。
本書は、日本におけるコーチングの第一人者による、理論と実践を網羅した決定版のコーチング本です。組織の課題解決に向けて、なぜ行動が伴わないのか、戦略が徹底されないのかを探求し、コーチングがその突破口となることを示しています。内容は図解で分かりやすくまとめられ、組織のパフォーマンス向上や変革を目指すリーダーにとって必読の入門書です。
本書『最高の結果を出すKPIマネジメント』は、リクルートグループでのKPIマネジメントの実践ノウハウを紹介する一冊です。著者は11年間にわたりKPI講師を務めたプロフェッショナルで、ビジネスの数字を最大化するための具体的な手法や事例を提供しています。内容はKPIの基礎知識、実践のコツ、事例集、KPI作成のステップなど多岐にわたり、入門から実践レベルまで対応。特典として、著者による質疑応答集も付いています。
『おやすみ、ロジャー』は、たった10分で子どもを寝かしつけることができる絵本で、心理学的効果を活用した内容が特徴です。2016年に年間ベストセラー2位を獲得し、発行部数は100万部を超えました。著者は行動科学者のカール=ヨハン・エリーンで、子どもが寝たくない理由を考慮したリラックス効果のある読み方の指示が含まれています。世界的にベストセラーとなり、多くのメディアで特集が組まれました。シリーズ第2弾『おやすみ、エレン』も好評です。
この書籍は、ユニクロの柳井正が「最高の教科書」と称する内容を初公開し、経営の巨人ハロルド・ジェニーンの知恵を紹介しています。目次には、経営理論、リーダーシップ、企業家精神などが含まれ、ジェニーンの成功の秘訣や経営者としての条件について述べられています。ジェニーンはITの社長として14年半連続増益を達成し、多くの企業を買収・合併した実績を持つ人物です。
本書は、ビジョンの重要性をストーリー形式でわかりやすく解説し、ビジョンの創造と実践のプロセスを紹介しています。著者たちは、ビジョンが個人や組織の成功にどのように寄与するかを探求し、有意義な目的、明確な価値観、未来のイメージなど、ビジョンの要素を示しています。著者はリーダーシップや組織開発の専門家であり、実践的なアプローチを通じて、読者がビジョンを具体化し、実践できるよう支援します。
この書籍は、成功する人々がどのような行動を通じてリーダーシップやマネジメントを発揮するのか、またそれらの行動がどのような欲求に基づいているのかを探求しています。内容は、組織と個人の成功に必要な「たったひとつのこと」に焦点を当て、マネジャーとリーダーの違いや、成功を持続させるための重要な考え方について述べています。著者のマーカス・バッキンガムは、リーダーシップとマネジメントに関する専門家であり、翻訳者の加賀山卓朗がその著作を日本語に翻訳しています。
本書は、目標管理の本質に立ち返り、部下のやる気を引き出し業績を向上させるためのマネジメント手法を解説しています。著者は、単なるノルマ主義を超え、人や組織を大切にするアプローチを提唱。目次では、目標管理の嫌われる理由、チャレンジ目標の作成、リーダーの役割、振り返りミーティングの進め方などが取り上げられています。著者は教育コンサルタントとしての経験を活かし、実践的な内容を提供しています。
離職率ゼロを維持しながら業績全国1位のチームをつくりあげた、敏腕マネジャーの人材育成術を大公開! 離職率ゼロを維持しながら業績全国1位のチームをつくりあげたマネジャーが、自身の経験と産業カウンセラーとしての知見から編み出した、至高の人材育成術を大公開!ひとりも辞めない最強チームのつくり方を、余すところなくお伝えします!本書は、8年もの間1人も離職者を出さなかったマネジャーの人材育成術を、体系的にまとめたものです。具体的には、まず、人材育成の前提となるマネジメントの基礎を説明。次に、部下と上手くコミュニケーションをとるための基本的なスキル・マインドを紹介。そして、これらを踏まえて、「部下が辞めない1on1ミーティング」のやり方を、マネジャーと部下の対話例をまじえて、丁寧に解説しています。本書は、そこで終わらず、怒りをコントロールする方法や、部下が納得する人事評価の手法、マネジャーが備えるべきマインドセットなど、部下をもつ人であれば必ず知っておきたいことを、全て網羅しています。部下とのコミュニケーションに悩むマネジャー、待望の1冊です。 【目次】 第1章 1on1ミーティング成功の条件、「マネジメント」を固める 第2章 部下とのコミュニケーション技術は1on1ミーティングで磨かれる 第3章 1on1ミーティングを成功に導くために 第4章 1on1ミーティングで「怒りのコントロール」を学ぶ 第5章 1on1ミーテイングに人事評価を導入し、部下の最高のパフォーマンスを引き出す 第6章 1on1ミーテイングがあなたの「マネジャー哲学」を育む 第7章 部下タイプ別コミュニケーション術
本書は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が2015年に東京ディズニーランドを超える集客数を達成した理由を探る内容です。USJの成功は「マーケティング」を重視する企業文化に起因し、これにより新しいアイデアが次々と生まれ、事業成功率が30%から97%に向上しました。著者の森岡毅は、USJのマーケティング戦略やその本質、成功に向けたキャリア形成についても言及しています。
学生の頃に読んで衝撃を受けた森岡さんの書籍。マーケティング職について間もない人に是非読んで欲しい。徹底した消費者視点というマーケティングの本質が詰まっている。これを読んで消費者視点のマーケティングについて学んだ後は数学的マーケティングとして確率思考の戦略論も合わせて読んで欲しい。人生で読んだ中でトップ10に入る名著。
新入社員の小笠原は、営業部での半年間、売上ゼロのダメ営業マンだったが、スーパー営業マンの紙谷と出会い、彼から11の営業の「魔法」を学ぶ。小笠原は成長しトップ営業マンに昇進するが、最後の魔法を教わる前に紙谷が姿を消してしまう。物語は、彼の成長と営業の真髄を描いたサクセスストーリーである。
この本は、野菜を豊富に使った常備菜120品を紹介しています。内容は、時間が経っても美味しいおかずサラダ、寝かせることで味が増すサラダ、野菜をたっぷり使ったピクルスや漬け物、そしてサラダ用のソースやドレッシングの作り置きに分かれています。また、野菜や果物を使った甘い作り置きレシピも含まれています。
管理問題の発生と展開 管理の構造と発展 ヒトの管理をめぐる変遷 人的資源管理としての日本型雇用とその変容 企業内教育訓練・能力開発の課題 労働時間管理の変化と働く者のニーズ 賃金管理と処遇問題 多様な紛争解決システムと労働組合 日本型人的資源管理の行方
本書は、若いベンチャー企業や中小企業の新任管理職やリーダー候補生向けに、リーダーとしての成長や役割を伝える内容です。著者の経験に基づき、問題解決、コミュニケーション、部下育成、リーダーシップの磨き方、役立つ理論について解説しています。管理職育成に最適な一冊です。著者は人材育成に特化した企業の代表で、幅広い研修経験を持っています。
本書『人材マネジメント入門』は、人材マネジメントの基礎知識を体系的に解説した公式テキストです。10章にわたり、評価、報酬、採用、異動、人材開発などの重要なテーマを図解とともに紹介し、実際の企業の事例も挙げています。人事担当者や管理職向けに、知識の習得や試験を通じた証明を促進します。検定は年4回実施され、合格者には認定証が発行されます。著者は20年間の人事経験を持つ専門家です。
本書は、管理職向けのマネジメント書で、リモートワークにも適した「識学」という組織論を紹介しています。識学は、組織内の誤解や錯覚を解消する方法を明らかにし、4400社以上が導入しています。著者は安藤広大で、若手リーダーや中間管理職に向けた具体的なノウハウを提供し、リーダーの言動の重要性を強調しています。
組織のトップとしてのあるべき姿を説く書籍。この本に書いてある内容は自分の想像するリーダー像と違いすぎて驚いた。確かに組織を大きくして社会にインパクトを与えるためにはこの本の中で書かれているリーダーの仮面が必要なのかもしれないが、私はそんなことまでしてリーダーで居続けて何が楽しいのかなと思ってしまう。旧式の企業にはハマるがこれからの時代にはハマらない考え方な気がする。自分自身も会社を経営する身として参考にしつつもこの本の中で語られているリーダーとは違う姿を模索したい
この書籍は、リーダーシップに関する悩みを解決するための具体的な方法や考え方を提案しています。目次には、部下を覚醒させる任せ方や、信頼されるリーダーになる方法、一丸となったチーム作り、決断力を高める方法、孤独を感じた際の対処法などが含まれています。著者は伊庭正康で、リクルートグループでの豊富な経験を持ち、企業研修を提供する会社を設立しています。
災害・危機発生時の職員の役割と行動 組織と法制度上の課題 被災自治体職員が抱える課題 災害時の応援自治体職員の課題と展望 危機管理における官民の連携 試案 大規模災害時における被災市町村への人的支援 「組織と人」に関する防災・復興法制の現状と課題 自治体職員の惨事ストレス 災害時のパニックと心理的ショック
著者は60歳でライフネット生命保険を起業し、成功を収めた経験を基に部下マネジメントについて論じています。本書では、部下に仕事を任せる重要性や、効果的な指示の出し方、プレーイング・マネージャーにならないことの大切さなどを解説。読者が仕事を楽にし、チームの実力を向上させるための具体的な方法を提供しています。
本書は、リーダー向けの効果的な「話し方」を身につけるための実践的な方法を提供しています。著者の矢野香は、NHKでのキャスター経験を持つスピーチコンサルタントで、リーダーが注目を集め、高揚感を高め、信頼感を与え、基準を示し、人間の器を感じさせるための5つのポイントを解説しています。対象は若手リーダーや管理職、企業広報担当者などで、実践的なスピーチトレーニングを通じて人を動かすリーダーになる方法を学べる一冊です。
「バブル入社組」世代の苦悩を描いた物語で、東京中央銀行の半沢直樹が巨額損失を出した老舗ホテルの再建を任され、銀行内部の敵や金融庁との対決、出向先でのいじめに直面する。絶体絶命の状況で、彼らの逆転劇が描かれる。著者は池井戸潤。
本書では、強力なチームを作るための要素を探求しています。チームの文化はメンバーの個性ではなく、彼らの行動によって形成されると述べています。内容は、安全な環境の構築、弱さの共有、共通の目標の重要性に焦点を当てており、具体的な事例や実験を通じて、効果的なチームワークの方法を紹介しています。著者はダニエル・コイルで、ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家です。
この書籍は、交渉における成功は「駆け引き」ではなく、時間と労力を効果的に使うことにあると説いています。著者たちは、感情をコントロールし、相手の面子を立てながら自分の要求を通す方法を紹介し、どんな不利な状況でも逆転できる戦略を提案します。ハーバード大学の交渉学の専門家による研究に基づく内容です。
この本は、3業界、7企業、26チームにわたる1万2000件の日記調査と669人のマネジャーへの調査を基に、チームやメンバーの創造性と生産性を高めるためには「やりがいのある仕事が進捗するよう支援する」ことが重要であると示しています。しかし、マネジャーのわずか5%がこの「進捗の支援」の重要性を認識しているという驚くべき結果が得られました。著者は、ハーバード教授のテレサ・アマビールと心理学者スティーブン・クレイマーで、35年以上にわたる研究を通じてマネジメントの新常識を提案しています。
性格が優しいから、上手くリーダーシップがとれない。部下より年下だから、遠慮してしまう。部下と摩擦や軋轢を生みたくないから、厳しく指導しない。自分さえ我慢すれば、苦手な部下とも表面上はつくろえる-。そんな"悩める管理職"に必要なリーダーシップのカタチがある。それは「仕組み」と「見える化」のマネジメント。リーダーシップの優劣は性格や年齢に左右されない! オリエンテーション 性格の優しい上司・年上の部下をもつ上司のためのリーダーシップ・スキル開発9週間プログラム 第1週 リーダーシップは性格で決まらない!優しい性格の上司ほどマネジメントに優れている 第2週 人を使おうとするから苦しむ!年上の部下は「持ち上げて活かす」と割り切る 第3週 他部門を味方にする!「部門間連携」のマル秘テクニック 第4週 禍根を残さない叱り方・ケジメのつけさせ方-「性格の優しい上司」「年下の上司」でもできるストレスのない指導法 第5週 質問で部下を指導する!性格が優しい上司と年下上司に最適な「コーチング会話スキル」 第6週 もう迷わない!部下に任せる仕事と自らやる仕事の線引き 第7週 ルールを守る部下を育てる!記憶や意識に頼らない「仕組み」と「ルール」 第8週 モチベーションを高める!「傾聴型個人面談」で部下は必ず変わる 第9週 無理強いしなくても部下が自発的になる!コスト削減とヤル気アップを同時に実現するカイゼン活動ノウハウ 補10講 大手と中小の違いを知る!中小組織で求められるリーダーシップ
この書籍は、月に30分の1対1ミーティングを通じて、社員の自発的な行動や持続的なやる気を引き出し、離職を防ぐ方法を紹介しています。著者は、働きがいのある会社での実績を基に、対話の重要性や信頼構築、成長支援の具体的な手法を解説しています。1対1ミーティングの実践方法や質問例も提供されており、組織変革を促進するためのノウハウが詰まっています。著者は組織人事コンサルタントの世古詞一氏です。
この書籍は、マネジメントの成功には経験やセンスではなく、実行可能なフレームワークが必要であることを強調しています。著者は、数々の失敗から学び、小さなベンチャー企業を上場に導いたプロフェッショナルマネージャーであり、急成長を目指す組織のマネージャーや経営者に向けて具体的なノウハウを提供します。内容は、マネージャーの役割、現状把握、チーム戦略、強いチームの構築、推進システムの設計、初期成果の創出、継続的な改善、個人目標設定、ピープルマネジメント、コミュニケーション技術など多岐にわたります。
日本軍がなぜ戦争に負けてしまったのかを分析し、それを元に日本の組織における問題点を浮き彫りにしている書籍。責任の所在の曖昧さと、臨機応変に対応できない官僚主義が蔓延した日本組織は危機的状況において力を発揮できない。少々歴史の話は冗長だが一読する価値のある書籍。
広告代理店で働く主人公は、仕事に悩みを抱えている。そこにアドラー心理学を学んだ上司のドラさんが現れ、働く理由や仕事の楽しさを見つける手助けをする。物語は、主人公が自己肯定感を高め、他者との関係を築く過程を描いている。著者はアドラー派の心理カウンセラーで、企業での講演や研修を行っている。
この書籍は、AIやデジタルトランスフォーメーション(DX)時代において、管理職が生き残るための条件とシンプルな仕事術を紹介しています。管理職の役割は「チームの成果の最大化」であり、そのための6つのルールを解説しています。具体的には、迅速な意思決定、スピード感のある仕事、生産性向上、権限委譲、自律型人材の育成、最強チームの構築が挙げられています。また、外資系マネジャーが実践する36の具体的なルールも紹介されています。著者は人材活性ビジネスコーチの櫻田毅氏です。
『第3版 はじめての課長の教科書』は、中間管理職のスキルや心構えを解説した日本初の入門書で、2024年に新章を追加した改訂版が発売されます。15年間で20万部を超え、多くの企業や組織で活用されています。本書では、課長の役割や基本スキル、直面する問題、キャリア戦略に加え、高齢化社会への対応も取り上げています。課長は組織の重要なキーパーソンとして、特有のスキルが求められ、本書は新任マネジャーのバイブルとして広く支持されています。
著者ベン・ホロウィッツは、シリコンバレーの成功した投資家であり、彼の実体験を通じて得た教訓を語る本書では、会社の売却や起業、急成長といった困難な状況を乗り越えるための知恵と勇気を提供しています。目次には、直感を信じることや、事業継続に必要な要素、困難な問題を解決する法則がないことなどが含まれており、起業家に向けたアドバイスが展開されています。著者は、数々の成功した企業への投資経験を持ち、多くの読者に影響を与えています。
この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。
ジャック・ウェルチは、GEを時価総額世界No.1企業に成長させた「20世紀最高の経営者」として知られています。本書では、彼がビジネス成功のための具体的なノウハウを提供しており、人材採用や上司への対処法、キャリアの築き方など、幅広いテーマを扱っています。経営者から新入社員まで、あらゆる職位の人に役立つ実践的アドバイスが満載のビジネス指南書です。
この本は、決算書を単なる数字の羅列ではなく、企業や業界の成長ストーリーとして読み解く方法を紹介しています。著者は、数字が読めないと感じる人々に向けて、実践的な決算分析の技術を提供し、ビジネスの理解を深めることを目的としています。内容は、ECビジネスやFinTech、広告、携帯キャリアなど、さまざまな業界の決算分析事例を通じて、企業の戦略や未来を予測する力を養うものです。読者は、決算を読む習慣を身につけることで、ビジネススキルを向上させることができるとされています。
このビジネスストーリーは、気弱な課長がワインバーでの出会いをきっかけに、部下育成と組織マネジメントに自信を持つようになる過程を描いています。内容は、成人発達理論に基づき、異なる段階にいる部下との関わり方を示しながら、課長自身の成長を促す方法を探求しています。著者は人財開発コンサルタントの加藤洋平で、成人発達に関する専門知識を持っています。
ベンチャー企業が設立当初は順調に見えたが、2年後に業績不振で37歳のCEOが解任され、57歳の女性が新CEOに就任する。彼女はチームワークの重要性を理解し、会社の変革を実現する能力を持っている。著者は経営コンサルタントのパトリック・レンシオーニで、200ページにわたる物語を通じてそのプロセスとノウハウを紹介している。
本書は、人工知能、自動運転車、フィンテック、無人店舗などの先端技術がビジネスに与える影響を解説したもので、特にシリコンバレーと中国のテクノロジー企業を比較分析しています。著者は、これらの技術が既存産業をどのように変革しているかを示し、日本企業が競争に遅れないための戦略を提案しています。内容は、人工知能、次世代モビリティ、フィンテック、小売、ロボティクス、農業・食テックの6つの分野に分かれています。
この書籍は、ピーター・ドラッカーが自身の経験を基に、一流の仕事をするための方法や知的生産性を向上させる秘訣を紹介しています。内容は、世界の変化、働く意味の変化、自分自身のマネジメント、意思決定の基礎知識、自己実現への挑戦について触れています。
『知識創造企業』は、1995年に発表された経営学の重要な著作で、日本企業のイノベーションメカニズムを解明し、知識の重要性を示した。著者たちは、個々の暗黙知を組織の形式知に変換するプロセスを「知識創造理論」や「SECIモデル」として提唱し、世界中で影響を与えた。四半世紀ぶりに新装版として再登場し、知識創造の理論や実践的提言を含む内容が整理されている。著者は、野中郁次郎、竹内弘高、梅本勝博の三人で、各々が経営学やナレッジマネジメントの権威として知られている。
本書は、働き始めた若者たちが抱える「働き方のモヤモヤ」に答える新感覚ビジネス小説です。主人公サカモトが、伝説の人事部長石川さんとの出会いを通じてキャリアや働く意味を探求し、12の寓話を通じて「幸せ」と「仕事」に関する洞察を得ます。著者は荒木博行氏で、20代、30代に特におすすめの一冊です。
本書は、人気ブログ「凡人が、天才を殺すことがある理由。」を基にした物語で、著者の北野唯我が人間の才能やコミュニケーションの断絶について探求します。主人公の広報担当者が、謎の犬ケンとの出会いを通じて、天才、秀才、凡人の関係を考察し、才能を見出し伸ばす方法を模索します。書籍は自己啓発やビジネス書として高い評価を受け、多くのメディアで取り上げられています。
本書は、IT業界での技術系マネージャーを目指すエンジニアに向けて、マネジメントに必要なスキルやキャリアパスを解説しています。著者のカミール・フルニエは、テックリードからCTOに至る自身の経験を基に、メンタリング、プロジェクト管理、チーム管理、経営幹部の役割など、各ステージで求められる役割や考え方を具体的に紹介します。技術力の維持やチームの立て直しなど、管理職に伴うさまざまな課題への対処法も提案されており、マネジメントキャリアを志すエンジニアにとって必携の一冊です。
この書籍は、ビジネス書のベストセラー35冊をイラストで簡潔に紹介し、それぞれの要点をわかりやすく解説しています。内容は、個人の生き方やキャリア、人間の本質、企業や組織の戦略、社会の変化について考察しています。著者は荒木博行で、グロービス経営大学院の教授として活動しています。
『世界最高のチーム グーグル流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法』は、グーグルの「プロジェクト・アリストテレス」を基に、効果的なチームづくりの原則を解説しています。特に「心理的安全性」の重要性が強調され、チーム内の愚痴やもめごとを建設的な議論に変えることで生産性を向上させる方法が提案されています。また、多様性を活かした集合知や、良質なコミュニケーションの重要性も述べられています。著者は、実験主義や柔軟な思考を通じて、最少の人数で最大の成果を上げるための具体的なアプローチを示しています。
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
本書は、2022年の年間ベストセラー第4位に選ばれた『リーダーの仮面』の続編で、全プレーヤー向けの仕事術の「型」を体系化しています。著者の安藤広大は、全国4400社以上が導入した「識学」を基に、成長する人に共通する考え方を紹介。内容は、数字を意識した思考法や行動量、確率、変数、成功の捨て方などを探求し、数値化の限界についても触れています。
この書籍は、ビジネススキルだけではなく、組織を効果的に動かすための「Deep Skill」の重要性を説いています。著者は4000人以上のビジネスマンを観察し、組織力学や人間心理を活用する方法を紹介。信頼資産の構築、戦略的な人間関係の形成、権力の動かし方、人間力の向上など、実践的な技術を解説しています。著者は企業の新規事業創出を支援するコンサルタントであり、組織内での成功には深いスキルが不可欠であると強調しています。
この書籍は、出世や権力を握るための方法をスタンフォード大学の教授が解説したもので、ビジネスマンにとってのバイブルとして評価されています。内容は、コネや人脈の作り方、権力者らしい話し方、評判の上げ方、不遇の時期の乗り越え方など、成功に必要な資質や戦略がまとめられています。著者は組織行動学の専門家であり、数多くの著作を持つ実績があります。
『世界「倒産」図鑑』は、リーマン・ブラザーズやコダックなど、日米欧の25の企業の倒産事例を分析し、経営者の人間的な弱さや判断ミスが破綻に至る過程に与える影響を探る内容です。数字だけでは見えない教訓を提供し、企業がなぜ成功から転落したのかを理解する手助けをすることを目的としています。著者は荒木博行で、経営や人材育成に関する豊富な経験を持っています。
この本は、伝え方の技術が結果に与える影響を探り、効果的なコミュニケーションの方法を学ぶことができる内容です。著者の佐々木圭一は、伝えることが得意でなかった経験を経て、伝え方の技術を発見し、人生が変わったことを語ります。具体的には、相手の反応を変えるための技術や、感動を生む言葉の作り方について述べています。全体を通じて、強い言葉を生み出す力を身につけることがテーマです。
人に何かを伝える方法の勉強にはなるが伝え方が本当に9割なのかは疑問。〇〇が9割シリーズが流行っているので結局シーンによってどこに重点を置くかは変わる。読んで損はない。
この文章は、ロバート・K・グリーンリーフの著作に関する目次と著者情報を紹介しています。目次には、サーバント・リーダーシップに関連する様々な章があり、リーダーや組織、教育、教会などの文脈でのサーバントとしての役割が論じられています。グリーンリーフは、企業人としての経験を持ち、リーダーを「サーバント」として捉える考え方を提唱し、より良い社会の構築を目指しました。翻訳者は金井真弓で、金井壽宏は経営学の教授です。
著者・藤沢武夫は、本田宗一郎と共に本田技研を世界的企業に成長させ、社会的責任を重視した経営理念を実践した名経営者です。本書では、彼の半生や経営哲学を初めて明かし、様々な経営の教訓や心構えについて述べています。
この書籍は、コーチングのノウハウを集約し、人材開発から組織開発へと焦点を当てた改訂版です。内容は、コーチングの定義や必要な視点、基本原則、プロセス、スキルと実践例、組織への適用方法を含んでいます。著者は鈴木義幸氏で、コーチ・エイの代表取締役社長を務めています。
この書籍は、行動を60秒以内にほめることで、その行動を繰り返すようになるという心理学的なアプローチを紹介しています。著者の石田淳は、行動科学に基づくマネジメント手法を用いて、人材育成や問題解決を通じて企業の成長を促進しています。内容は行動分析の基本から、実践的なステップまで多岐にわたり、科学的なデータに基づく経営手法の可能性を探ります。
この文章は、チームマネジメントに関する書籍の目次を示しています。第1章ではチームマネジメントの基礎知識や関連用語、チームの類型について説明しています。第2章では、チーム力を高めるための技術やカンファレンス、ファシリテーション、コンフリクト・マネジメントについて取り上げています。第3章では、病院や施設におけるチームマネジメントの実践について、特に亜急性期や急性期のチーム機能に焦点を当てています。
この書籍は、コリン・パウエルが自身の経験を基にした「自戒13カ条」を通じて、リーダーシップや仕事の手順について語ったものです。内容は、目標達成や対人術、組織づくりに役立つ知識を提供し、ビジネスパーソン必読の一冊とされています。パウエルの実体験を交えながら、冷静さや楽観主義の重要性が強調されており、各界のキーパーソンからも推薦されています。
「人の用い方」は、経営者が直面する重要な課題であり、優れた商品や技術だけでは成功しないことを説いています。著者の井原隆一氏は、人材の求め方、育成、活用について具体的な指針を示し、経営者としての心構えや部下との関係の重要性を強調しています。目次には、経営者の魅力や信頼、戦略的思考、部下の理解など、多岐にわたるテーマが含まれています。井原氏は多くの企業再建を手掛けた実績を持つ経営者です。
この書籍は、幸福や喜び、楽しさといった現象を心理学や社会学、文化人類学などの視点から総合的に解明した作品です。目次には、幸福の再来や意識の分析、生活の質、フローの条件、身体や思考のフロー、仕事におけるフロー、孤独と人間関係、カオスへの対応、意味の構成が含まれています。
著者は、30,000冊のビジネス書を読破した経験を基に、読書が成功のための最も効果的な手段である理由を解説します。天才たちの思考を学ぶことで、未来を見通す力を得られると述べ、先人の知恵を借りることで凡人でもチャンスを掴むことができると強調しています。本書は、成功に向けたマインドやスキル、転職や起業、お金持ちになるための具体的な方法を紹介し、読者を成長の旅へと導きます。著者は、エリエス・ブック・コンサルティングの代表であり、メールマガジン「ビジネスブックマラソン」の編集長です。
大唐帝国の礎を築いた太宗が名臣たちと交わした政治問答集。編纂されて以来帝王学の古典として屹立する。本書では七十篇を精選・訳出 唐代、治世の問題を真正面から取り扱い、帝王学の指南書となった『貞観政要』。幾多の戦乱を乗り越え、太平の世を現出させた太宗(李世民)が名臣たちと交わした問答を史家・呉兢が編纂。爾来、中国のみならず日本においても為政者たちが折に触れて立ち返る古典の地位を得てきた。「指導者の条件」「人材の登用」「後継者の育成」など、およそ組織運営に関わる人間なら必ず迷い、悩むであろう問題に古人はどのように臨んできたのか。本書には汲めども尽きぬ教訓が今も満ち溢れている。本文庫は明代の通行本(戈直本)を底本とし、全篇より七十篇を精選・訳出。 第1章 治世の要諦 第2章 諌言の機微 第3章 人材の登用 第4章 後継者の育成 第5章 名君の条件 第6章 帝王の陥穽 第7章 学問の効用 第8章 刑罰の論理 第9章 用兵の限界 第10章 守成の心得
読みながら行動や考えを改められ、少しずつ自身に変化を感じられる素晴らしい書籍です!
誰もが知る名著なので一度は目を通しておくべきだが、内容は冗長で個人的にはあまりはまらなかった。重要度×緊急度のマトリクスの話が一番重要で、そこだけ理解しておけばいい気がする。緊急度は低いが重要度が高いタスクになるべく長期的な視点で取り組めるようになるべき。
本書は、マネジメントの本質を「管理」ではなく、仕事の成果を最大化するために関連する要素を「いい感じにする」ことと定義しています。具体的には、環境や人間関係、役割分担などを整えることが含まれます。視覚的な図解を用いて、手軽にマネジメントについて学び、会話や説明ができるようになることを目指しています。著者はマネジメントの専門家で、多くの企業でアドバイザーを務めています。
『孫子』は中国最古の兵書で、13篇から成り立っています。戦術と戦争の哲学が深く結びついており、戦争や人生の問題を広い視野で捉えています。この新訂版では、原文、読み下し文、現代語訳に加え、平易な注釈と重要語句索引が付されています。内容は、戦略、作戦、軍の動きなど多岐にわたります。
元リクルート社長の著者が、組織づくりに関するノウハウをまとめた書籍。29年間の経験を基に、事業成長や従業員満足を同時に実現する手法を紹介。「G-POPマネジメント」と名付けられたこのアプローチは、目標設定、事前準備、実行・改善、振り返りの4つの章から成り立っており、経営者や管理職向けに実践的な知識を提供します。
内向的で心配性な人々が優れたリーダーになる理由と、自己躍動するチームを作るための「静かなリーダーシップ」について解説した本です。著者は1000人以上の経営者から得た知見をもとに、リーダーシップの新しい考え方を提案しています。具体的には、人を動かすのではなく自ら動く環境を作ること、魅力的なビジョンを持つこと、物語を通じてビジョンを浸透させることなどが挙げられています。著者はシンクタンク・ソフィアバンクの代表で、多様な経歴を持つ藤沢久美氏です。
この書籍は、部下や同僚、上司との関係を良好に保つための38のコツを紹介しています。内容は「感情マネジメント」に焦点を当てており、自信のなさやイライラ、ハラハラといった感情を管理し、効果的なリーダーシップを発揮する方法を探ります。著者の折戸裕子は、リーダーシップ戦略コンサルタントとして多くの企業や団体で活動しており、その経験を基にした実践的なアドバイスが提供されています。
「課長」に関するよくある質問
Q. 「課長」の本を選ぶポイントは?
A. 「課長」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「課長」本は?
A. 当サイトのランキングでは『HIGH OUTPUT MANAGEMENT(ハイアウトプット マネジメント) 人を育て、成果を最大にするマネジメント』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで159冊の中から厳選しています。
Q. 「課長」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「課長」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



![『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UB6ayAOaL._SL500_.jpg)



![『[新装版]指導者の条件』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41taa2MLLQL._SL500_.jpg)































![『[オーディオブックCD] 「7つの習慣」実践ストーリー3 マネジメントを考える8のストーリー』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51+yvQqkSJL._SL500_.jpg)


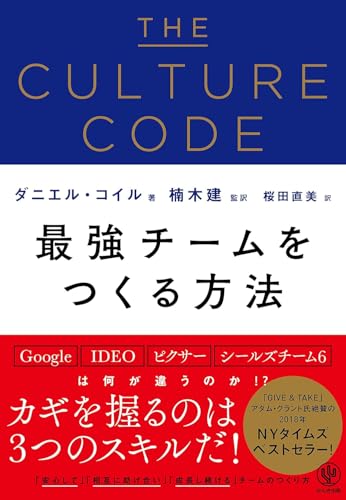







































![『経営者になるためのノート ([テキスト])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/21OIhMFu5cS._SL500_.jpg)


























![『ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ] やっかいな人のマネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー―EIシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51yw5J+NnOL._SL500_.jpg)





























































