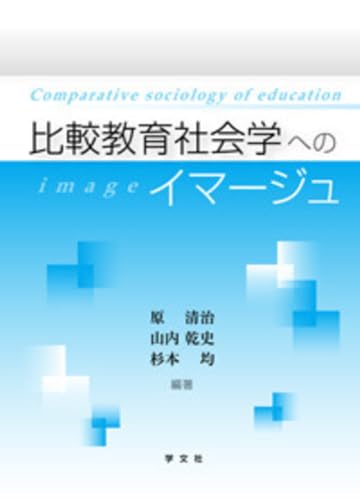【2025年】「教育学」のおすすめ 本 134選!人気ランキング
- 教育課程コアカリキュラムに対応した教育心理学
- よくわかる教育心理学[第2版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)
- 改訂版 たのしく学べる最新教育心理学: 教職に関わるすべての人に
- 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編
- 脳科学おばあちゃん久保田カヨ子先生の誕生から歩くまで 0~1才 脳を育むふれあい育児 (主婦の友生活シリーズ)
- 新しい視点からの教育社会学-人間形成論の視点から-
- 絵で読む教育学入門
- 教育心理学
- 発達障害の子が羽ばたくチカラ 気になる子どもの育ちかた
- 「自由」の危機 ――息苦しさの正体 (集英社新書)
本書は、子どもが学び適応する過程を理解し、支援に必要な知識を提供する内容です。学びの意欲や仕組み、個別の支援方法、社会性の学びについて解説しており、教育現場で実践的に活用できる情報を提供しています。旧版の修正に加え、新しい項目も追加され、変化する教育環境に対応した改訂版です。著者は中澤潤氏で、千葉大学の名誉教授です。
このテキストは、教育心理学に関する包括的な教材で、大学や短大の教職課程、教職を目指す学生、既に教職にある人の学び直しに適しています。2017年に改訂され、法律や指導要領の変化に対応し、演習問題を充実させています。内容は、教育心理学の基本から発達、学習メカニズム、授業の心理学、教育評価、知的能力、パーソナリティ、社会性、学級の心理学、不適応、特別支援教育に関する章で構成されています。付録には演習問題の解答や重要用語の解説も含まれています。
教職課程を学ぶ学生を対象にした教育社会学のテキスト。理論と実践を学ぶことができ、最新の教育社会学の知見も網羅している。 教職課程を学ぶ学生を対象にした教育社会学のテキスト。順に読み進めることで、教育社会学の理論と実践を学ぶことができ、現場の教師にあっては、最新の教育社会学の知見を学び、実践的な内容に触れることができるように構成している。 教職課程を学ぶ学生を対象にした教育社会学のテキスト。教育社会学の理論と実践を学ぶことができ、現場の教師にあっては、最新の教育社会学の知見を学び、実践的な内容に触れることができるように構成している。 特別寄稿 環境教育のための資料例 第1章 教育社会学へのアプローチ 第2章 教育社会学から見たカリキュラム 第3章 キャリア教育と教育機会 第4章 現代社会における高等教育 第5章 子どもの福祉と教育 第6章 多様化する家族のあり方 第7章 いじめ問題への対応 第8章 不登校児童生徒支援のあり方 第9章 子どもとメディア利用 第10章 特別支援教育 第11章 マイノリティとジェンダー 第12章 大学教育の今 第13章 これからの教育社会学ー人間形成としての「自己実現」を図るためにー
このテキストは、教職課程の「教育心理学」に関する内容を扱っており、文科省のコアカリキュラムに基づいて「発達」と「学習」に焦点を当てています。イラストや図表を多用し、初学者にも理解しやすく構成されており、各章には事例も含まれています。教職採用試験の対策にも適した内容で、教育心理学、発達理論、学習理論、記憶、動機づけ、教育評価、特別支援教育など幅広いテーマが網羅されています。著者は日本体育大学の教授陣です。
この文章は、奈須正裕教授が著した教育に関する内容を紹介しています。テーマは「令和の日本型学校教育」で、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させる方法を探るものです。山形県天童市立天童中部小学校を実践校として、教師の理解と覚悟を基にした教育活動が展開され、子ども主体の授業の実現を目指しています。目次には、子どもの自立的学習や教師の専門性の再考などが含まれています。
本書は、精神分析理論の基本を実感的に理解できるように改訂されたテキストであり、精神分析の歴史や構造、力動的観点、心の病理、発達論などを詳しく解説しています。著者の馬場禮子は、理論を実生活や臨床に結びつけながら、読者にわかりやすく伝えることを目指しています。講義形式を取り入れ、用語の解説を中心に基礎知識を提供し、精神分析が有機的に繋がる理論であることを強調しています。全体的に、初心者から中級者までが理解しやすい内容となっています。
「潜在連想」という視点から実証的に生徒のホンネに迫り,「偽装○○嫌い」の検出と救出を試みる。「教育の科学化」への挑戦。 日本の中学生の4割以上は「数学嫌い」であるというアンケート調査の結果は,本当に「科学的」であると言えるのか? 本書では,「潜在連想」という視点から実証的に生徒のホンネへと迫り,「偽装○○嫌い」の検出と救出を試みる。中学校教諭と教育心理学者による「教育の科学化」への挑戦。集団式簡易潜在連想テストの実施マニュアル付き。 ◆主な目次 はじめに 第1章 証拠に基づく教育の必要性 第2章 国際調査での日本の子どもたちの成績 第3章 アンケート調査の問題点 第4章 潜在連想構造を探る新しい検査法:こころのX線検査 第5章 学校教育現場で使える集団式潜在連想テストの開発 第6章 「偽装数学嫌い」生徒の検出 第7章 「偽装数学嫌い」生徒の救出 第8章 「こころのX線検査」のその他の活用例 第9章 教育の科学的研究の重要性:まとめに代えて 付 章 FUMIEテスト実施マニュアル おわりに はじめに 第1章 証拠に基づく教育の必要性 1.教育は間違った印象に左右されやすい 2.証拠に基づく教育 3.何が証拠なのか 1)調査結果は証拠にならない 2)因果関係の証拠はランダム化比較対照実験でしか得られない 3)ランダム化比較対照実験だというだけでは証拠不十分 4.この本で述べたいこと 第2章 国際調査での日本の子どもたちの成績 1.国際学力調査 2.PISA調査 1)「ゆとり教育」とPISAショック 2)幻だったPISAショック 3.TIMSS調査 1)TIMSS調査に現れた日本の子どもの特徴 2)「成績が良くて好き」から「成績が良いのに嫌い」になる 4.日本の子どもは嘘をついているのではないか 第3章 アンケート調査の問題点 1.学校で多用されるアンケート調査 2.アンケート調査の問題点:回答者が嘘をつく 1)嘘を見破る工夫 2)嘘をつかせない工夫 3)善意の嘘 3.アンケート調査の問題点:意識と無意識 1)フロイトの無意識とヘルムホルツの無意識 2)ロールシャッハテストの限界 4.国際学力調査のアンケート結果も正しいとは限らない 第4章 潜在連想構造を探る新しい検査法:こころのX線検査 1.潜在意識の科学的研究:プライミング効果 2.知識ネットワークモデルと潜在的認知プロセス 3.潜在的社会的態度測定のための潜在連想テストの開発 1)潜在的プロセスを反応時間で探る 2)反応時間の差に表れる潜在連想構造 4.潜在連想テストの活用の広がりと発展 1)プロジェクト・インプリシット 2)単一の測定対象のための潜在連想テスト 第5章 学校教育現場で使える集団式潜在連想テストの開発 1.学校では潜在連想テストは使えない 2.紙版の潜在連想テストというアイディア 3.集団式簡易潜在連想テスト「FUMIEテスト」の開発 1)キー押し反応の代わりに○×をつける 2)「速さ」を1分間の作業量で測る 3)ターゲット分類課題の廃止 4)評価語の選択と単語の提示順序の決定 5)作成されたFUMIEテストの信頼性と妥当性を測る 6)より良いものにするため改良を重ねる 第6章 「偽装数学嫌い」生徒の検出 1.学校での「研究」とは 2.FUMIEテストを用いた「偽装数学嫌い」生徒の検出 1)なぜ日本の中学生は数学を嫌うのか 2)中学生のホンネを探る 3.なぜ「数学嫌い」を偽装するのだろうか 第7章 「偽装数学嫌い」生徒の救出 1.やらなければ負けない 2.「偽装数学嫌い」生徒の戦略 1)数学と性差のステレオタイプとその真偽 2)不安と自信と自己暗示 3)間違った自己暗示の修正 3.「偽装を見破ること」の効果の科学的検証:ランダム化比較対照実験 1)「偽装数学嫌い」生徒の検出と2分割 2)「偽装数学嫌い」生徒の半分への潜在意識調査結果のフィードバック 3)効果の検証 4.この研究から得られた「証拠」 1)嘘の情報では効果が見られない 2)より確かな「証拠」とするために 第8章 「こころのX線検査」のその他の活用例 1.世界から取り残される日本の教育研究者たち 2.「こころのX線検査」の活用例 1)中学生の教科嫌いと潜在意識の乖離 2)中学生の集団登山前後での「登山」に対する潜在意識の変化 3)障害者に対する潜在的態度測定 4)外国人に対する潜在的態度測定 3.その他の「こころのX線検査」の活用の可能性 1)「学校」に対して否定的な潜在イメージを持つ生徒への予防対策 2)不登校児童生徒の「学校」に対する潜在イメージの変化 3)「ひらめき☆ときめきサイエンス」の効果の科学的検証 4)中学生の潜在的な価値観:中学生にとって一番「良いイメージのもの」 4.「こころのX線検査」という新しいツール 第9章 教育の科学的研究の重要性:まとめに代えて 1.教育の科学化 2.ランダム化も比較対照も科学の常識 1)比較対照条件の重要性 2)ランダム化が必要な人文社会科学系の実験 3.実験を120年以上前に導入した心理学 4.「教育の科学化」と実験教育学・教育心理学 5.教育心理学の停滞と復権 6.学校におけるランダム化比較対照実験の重要性の理解と協力 付 章 FUMIEテスト実施マニュアル おわりに 文献 索引
著者の小川大介氏は、中学受験のプロとして、多くの教え子を難関校に合格させてきた経験を基に、「本当に頭がいい子の育ち方」について語ります。彼は、子どもが親に見守られながら好奇心を育むことで、自ら学び成長することが重要だと強調します。本書では、子育てにおいて「否定しない」「与えすぎない」「あせらない」ことの重要性や、親が楽しむことが子どもに良い影響を与えることなど、実体験と心理学に基づく子育て法を紹介しています。
本書は、心理療法の基本と技術を学派を超えて解説した入門書です。著者は精神分析的立場から、面接の流れや重要な原則を平易に説明し、心理療法の実践における共通する要素を強調しています。特に、クライエントとの関係性や反発に対する基本的な対応の重要性を指摘し、成功するための基礎知識を提供しています。内容は、心理療法の開始から終結までの各段階や転移、抵抗、介入の技法など多岐にわたり、心理療法家としての熟練を目指す人にとって役立つ情報が詰まっています。
猿蟹合戦とは何か.国語入試問題必勝法.時代食堂の特別料理.靄の中の終章.ブガロンチョのルノアール風マルケロ酒煮.いわゆるひとつのトータル的な長嶋節.人間の風景
本書は、子育てに悩むママたちが抱える罪悪感に寄り添い、自己肯定感を高めるためのガイドです。著者は子育て専門カウンセラーの福田とも花で、母親が感じる「ごめんね」という思いを理解し、その背後にある心の癖や古傷に向き合うことを提案しています。自分を許し、ダメな自分でも大丈夫と認識することで、子どもとの関係も改善されると伝えています。各章では、罪悪感の原因や子どもとの関係の見直し、ハッピーママになるための方法が示されています。
秋月りすの4コマ漫画『OL進化論』を楽しみながら思考の技法を学ぶ。初心者のためのクリティカルシンキング超入門書。 「ものの見方・考え方」を、人気四コマまんが家・秋月りす氏のマンガ77編を楽しみながら身につけられる,画期的な本。心理学と論理学をベースに全くの一般人向けに書かれた「思考」の本。 秋月りすの4コマ漫画『OL進化論』を楽しみながら思考の技法を学ぶ。 初心者のためのクリティカルシンキング超入門書。 自分の周囲の人や種々の問題について,正確に理解し,自分の力で考え,適切な判断をしていくのがクリティカルな態度であり,その思考である。クリティカル思考は複雑化した現代社会に適応していく上でも必要となろう。本書では,ユーモアあふれる4コマ漫画を題材にわかりやすく楽しく身につけてもらうことをめざした。 はじめに 本書はこう読もう 序章 クリティカル思考とは ●「クリティカル」の意味 1.クリティカルに原因を推論する 2.クリティカルに何かを判断する 3.クリティカルに情報を選択する 4.クリティカルにいろいろ考える ●クリティカル思考の定義 1.クリティカル思考とは 2.事実と意見を分ける――クリティカル思考のための準備 3.議論を分析する――クリティカル思考のための第一歩 1章 推論の仕方は妥当か ●クリティカルに推論するとは? ●クリティカルに推論するやり方 1.あてはまらない例はないか? 2.一緒に変化するか? 3.四分割表で考える 4.四分割表「的に」考える 5.共通点と相違点に着目すれば 6.一致と差異に組織的に着目する 7.誰のせいかを考える 8.誰のせいかを「じっくり」考える ●因果関係を検討する上での留意点 1.一つの結果はいろいろな原因から生じる(1) 2.一つの結果はいろいろな原因から生じる(2) 3.一つの結果はいろいろな原因から生じる(3) 4.一つの結果はいろいろな原因から生じる(4) 5.一緒に変化したら因果関係と言える? 6.結果が原因で結果をひきおこす? 7.偶然という可能性も忘れずに 8.こうなることは初めから分かっていた? ●前後論法のもつ罠 1.変化したのは何のせい? 2.他にも出来事がなかった? 3.時間がたっただけじゃないの? 4.極端な状態はもとに戻る ●間違った議論のいろいろ 1.理由が理由になってるの? 2.あんなヤツに何が言えるんだ? 3.お前なんか簡単に倒せるよ 4.似てるからきっと同じだよ 5.そのままどんどん転がっていく? 6.シロじゃなければクロだ! 7.経験者は正しい? 2章 根拠としての「事実」は正しいか ●クリティカルに「事実」を検討するとは? ●事実検討の基本的スタンス 1.あなたの常識が一般の常識? 2.体験談そのものは事実だとしても…… 3.記憶とは事実とは限らない 4.情報の歪み方にはパターンがある 5.専門家の意見だから信じるの? 6.数字なら信用できる? ●スキーマによる事実の歪み 1.スキーマを通してものを見る 2.スキーマは情報をつなぎ,意味づけるための枠組み 3.スキーマによって同じ情報が違う意味にもなる 4.スキーマは未知・未確認の部分を埋める 5.スキーマは情報の取捨選択をガイドする 6.スキーマを見直すか,スキーマにこじつけるか ●偏った事実を「事実」とする過ち 1.一部分の事実から全体を推測する 2.偏ったサンプルが誤った結論をつくり出す 3.先入観に合う事実を見つけ出す 4.当たってないケースには注意が向きにくい 5.めだつ×めだつ=関連? 6.一面性の出来事に注意 7.欲しい情報だけを集め,欲しくない情報は無視するバイアス 8.反証となりうる情報も探せ ●「事実そういう人か」の検討 1.人を見るときのスキーマに気づこう 2.型にはまった固定観念 3.身近な人はさまざまだけど,遠い人は一くくり 4.そういうことをしたのはそういう人だから? 5.状況でもあり,個人でもある……かも 6.行為者と観察者の視点は違う 7.役割と個人は必ずしも同じではない 3章 クリティカルシンカーへの道 ●クリティカルシンカーの特性 1.クリティカルシンカーはものごとを疑う 2.クリティカルシンカーは思考の落とし穴を知っている 3.クリティカルシンカーは柔軟である 4.クリティカルシンカーは客観的である 5.クリティカルシンカーは単純化しない 6.クリティカルシンカーはあいまいさに耐える ●クリティカルに生活しよう 1.ものごとを他の面からもみるためには 2.ポジティブ思考に気をつけよう 3.後知恵から脱却するためには 4.要するにマインドフル 5.ちょっとクリシン――ちょっとクリティカルシンキング 6.あっからクリシン――「あっ」から始めるクリティカルシンキング 7.ユーモア精神で行こう!! おわりに──今日から始めるクリティカル思考 本書を読んだ人のための今後の読書案内 秋月りすから一言
本書では、統計学があらゆる学問の中で最強である理由を解説し、現代社会におけるその重要性や影響力を最新の事例を通じて探求しています。著者は、統計学の基本概念や手法(サンプリング、誤差、因果関係、ランダム化など)を紹介し、統計学の魅力とパワフルさを伝えます。著者は東京大学出身の専門家で、データを活用した社会イノベーションに取り組んでいます。
学生の時にこの書籍を読んで統計学に興味を持った。統計学の魅力について分かりやすく学べる書籍。専門的な内容はそれほどないのでスラスラ読める。統計学ってどんなことができるの?なんでそんなにすごいの?ということを知りたい人がまず最初に読むべき本。
この書籍は、実践に役立つカウンセリング理論33種類を厳選し、そのエッセンスをわかりやすく解説しています。全体の見取り図や主要理論の比較表を掲載し、クライアントの状況に応じた理論の使い分けや統合方法を示しています。下巻では、精神力動論、認知行動論、システム論などの最新のアプローチを解説し、カウンセリングにおける統合的アプローチについても触れています。著者は臨床心理士であり、教育学の専門家です。
この書籍は、子どもの脳力を最大限に引き出すための0~3歳向けの育脳としつけに関する指南書です。親が日常生活で実践できる具体的な方法を示し、子どもが自分で考える力を育てるためのポイントを解説しています。内容は、規則正しい生活や安心感を与えること、遊びを通じた学び、親子のコミュニケーションの重要性などに焦点を当てています。著者は小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏で、専門用語を避けて分かりやすくまとめられています。
探究! 教育心理学の世界 目次 まえがき 習得編 1 教育心理学とは 教育心理学の定義と課題 藤澤伸介 教育心理学の魅力と方法 無藤 隆 2 発達のメカニズム 教育と遺伝要因 安藤寿康 発達理論と発達段階 中澤 潤 発達研究法 飯高晶子 身体の発達と心への影響 松嵜くみ子 言語と認知の発達 内田伸子 社会性と情緒の発達 大久保智生 道徳性の発達 二宮克美 3 学習のメカニズム 学習とは何か 藤澤伸介 記憶のメカニズム 井上 毅 知識としての記憶 井上 毅 記憶と転移 寺尾 敦 習得のための学習法 藤澤伸介 探究力と創造性の獲得 楠見 孝 態度 犬塚美輪 4 学習を支える教育実践 教授学習の行動主義的基礎 小野浩一 目標・診断・評価 藤澤伸介 学習意欲 鹿毛雅治 授業づくり 鹿毛雅治 学習スタイルと教授スタイル 小林寛子 5 「ニーズ」と援助 学校教育とカウンセリング 伊藤亜矢子 しつけと学習の援助 鈴木雅之 学級風土と学級経営 伊藤亜矢子 6 特別支援教育 教師教育における特別支援 小沼 豊 障碍の理解─通常の学級における特別支援教育 小貫 悟 人権と特別支援教育 松田信夫 7 教育とICT 教育の情報化 田中俊也 情報機器活用の可能性と評価 田中俊也 ネット化浸透の負の側面 高比良美詠子 探究・活用編 1 教育 トピック1-1 教育理解の諸アプローチ 中澤 潤 トピック1-2 日本の学校教育と心理学 市川伸一 2 発達 トピック2-1 ピアジェ理論を考える 中澤 潤 トピック2-2 ギリシア神話と心理学 小川俊樹 トピック2-3 モンテッソーリ教育を考える 飯高晶子 トピック2-4 エリクソン理論を考える 山岸明子 トピック2-5 母語の獲得 大津由紀雄 トピック2-6 中高生の社会性 大久保智生 トピック2-7 知能について 安藤寿康 3 学習 トピック3-1 日本の学習者の実態 ─「高水準な義務教育の成果」の裏で 山森光陽 トピック3-2 ごまかし勉強 藤澤伸介 トピック3-3 学習観と学習法の選択 吉田寿夫 トピック3-4 学習習慣 藤澤伸介 トピック3-5 記憶と学習の意味 前野隆司 トピック3-6 自己調整学習 篠ヶ谷圭太 トピック3-7 予習の効果 篠ヶ谷圭太 トピック3-8 学習方略としての概念形成 藤澤伸介 トピック3-9 概念受容学習と概念発見学習 工藤与志文 トピック3-10 学習方略の活用 藤澤伸介 トピック3-11 ノートの活用 藤澤伸介 4 学習を支える教育実践 トピック4-1 ガニェの分類と学習指導要領 鈴木克明 トピック4-2 教師の成長 藤澤伸介 トピック4-3 学習指導要領と学校現場の乖離 藤澤伸介 トピック4-4 学力テストの実施法 藤澤伸介 トピック4-5 指導要録・通知表・内申書 鈴木雅之 トピック4-6 テストの統計的基礎 村井潤一郎 トピック4-7 指名と発問 藤澤伸介 トピック4-8 黒板の活用 藤澤伸介 トピック4-9 教授の基本原理 藤澤伸介 トピック4-10 集団思考と単独思考 釘原直樹 トピック4-11 教えて考えさせる授業 ─中学の数学を中心に 市川伸一 トピック4-12 習得の基礎としての「読解力」の指導 犬塚美輪 トピック4-13 母語獲得と外国語学習の違いから見えてくる 言語教育のあり方 大津由紀雄 トピック4-14 英語学習プロセスを探る ─中学生の英文主語把握 金谷 憲 トピック4-15 学習指導要領改訂と英語力経年変化 斉田智里 トピック4-16 理科教育における動機づけの可能性 飯高晶子 トピック4-17 社会科における誤概念の修正 進藤聡彦 トピック4-18 学級はどう変化していくか 伊藤亜矢子 トピック4-19 習熟度別少人数学習集団編制 山森光陽 トピック4-20 応用行動分析学の教室での活用 平澤紀子 トピック4-21 居眠り・私語・カンニング 釘原直樹 トピック4-22 学級崩壊 小林正幸 5 「ニーズ」と援助 トピック5-1 認知カウンセリング 藤澤伸介 トピック5-2 TET(教師生徒関係訓練法) ─望ましい教師と生徒関係 市川千秋 トピック5-3 予防的援助に一般意味論の活用を 藤澤伸介 トピック5-4 ブリーフカウンセリング ─解決焦点化アプローチ 市川千秋 トピック5-5 認知行動療法 神村栄一 トピック5-6 中1ギャップ 村栄一 トピック5-7 構成的エンカウンターグループ 野島一彦 トピック5-8 生理学的病態としての不登校理解 三池輝久 トピック5-9 モンスターペアレント 小野田正利 6 これからの教育を考える トピック6-1 日本の特別支援教育 山口豊一 トピック6-2 フィンランドの教育からの知見 福田誠治 トピック6-3 ニュージーランドの教育からの知見 植阪友理 トピック6-4 21世紀型教育 森 敏昭 あとがき 引用文献 索引 〔付録〕索引活用ガイド 著者一覧 装幀=藤澤伸介
ホッブズにおける信頼と「ホッブズ問題」 ヒュームとカントの信頼の思想 エスノメソドロジーにおける信頼概念 行動科学とその余波 政治学における信頼研究 社会心理学における信頼 ビジネスにおけるステークホルダー間の信頼関係 教育学における信頼 医療における信頼 機械・ロボットに対する信頼 障害者福祉における信頼 ヘイト・スピーチ 高等教育における授業設計と信頼 人工的な他者への信頼
新任の小谷先生が受け持つことになったのは、学校で一言もしゃべらない少年・鉄三。ハエ事件をきっかけに鉄三の気持ちを理解する小谷先生。さらに、変わった転校生・みな子が加わり、クラスメートたちは共に悩みながら「大切なもの」を見つけていく感動の物語。著者は灰谷健次郎で、彼は教師を経て作家として活躍しました。
カリキュラムや授業や学びについて、フィンランド教育など、最新の研究成果をわかりやすく提示。 カリキュラムや授業や学びについて、フィンランド教育など、最新の研究成果をわかりやすく提示。教育問題に対する思慮を深める基礎を提供する。 カリキュラムや授業や学びについて、フィンランド教育など、最新の研究成果をわかりやすく提示。教育問題に対する思慮を深める基礎を提供する。 まえがき 第一章 授業と学びの世界へ 第二章 変貌する教室 第三章 授業の様式 第四章 授業の歴史(1)欧米 第五章 授業の歴史(2)日本 第六章 学びの創造 第七章 協同的な学び 第八章 教室のジレンマ 第九章 授業のデザイン 第十章 授業の評価 第十一章 授業の研究(1)分析の方法 第十二章 授業の研究(2)言語と社会 第十三章 カリキュラムと単元の構成 第十四章 専門家としての教師 第十五章 改革の展望 参考文献
好評のテキスト,待望の改訂版。制度面の動向のみならず,子ども・教育をとりまく話題をふまえ刷新。新規Columnも追加。 初学者の目線で考えながら学べる,好評の教職対応テキスト,待望の改訂。 新学習指導要領/GIGAスクール/個別最適化/働き方改革/子どもの貧困/主権者教育など,教育や子どもをめぐる課題に応えて刷新。Columnも新規追加。 第1部 あなたの「教育観」をみつめてみよう──学びはじめる前に 第1章 よい教育ってどんな教育? 第2章 教育を社会の視点から考えてみよう 第2部 先人の知恵から学ぼう──試行錯誤の歴史 第3章 子どもという存在/人間という存在 第4章 教え方は試行錯誤されてきた──教育方法の歴史 第5章 教育を受ける権利 第6章 子どもの学びを支える仕組み 第3部 よりよい教育について考えよう──あなたなりの答えにたどり着くために 第7章 子どものための学校ってどんな学校? 第8章 学校では何を学ぶの? 第9章 よい先生ってどんな先生? 第10章 どんなふうに子どもに接すればよいのか? 第11章 子どもがよく学ぶためには? 第12章 学校を卒業したら学ばなくてもよいのか? 第13章 教育と学校の未来はどうなるの?
教育分野における公認心理師の活動のために 基礎から臨床まで心理学を基盤とした支援を学ぶ 教育・学校心理学の入門書 公認心理師は「チーム学校」の担い手として,子ども,教師,保護者と支え合いながら,スクールカウンセリング業務や学校・家庭・地域連携のキーパーソンとしての活動を通して,子どもの心の健康や学校生活の質を維持向上させることが期待される。教育分野で公認心理師として活動するための必須の知識を学ぶ1冊。 2022年の生徒指導提要の改訂を反映させた第3版です。 第1部 基礎編:教育・学校心理学の理論を学ぶ 第1章 教育・学校心理学の意義 石隈利紀 第2章 子どもの発達課題への取り組みの理解と援助 松本真理子 第3章 子どもの教育課題への取り組みの援助 増田健太郎 第4章 スクールカウンセリングの枠組み――何を援助するか 大河原美以 第5章 子どもの多様な援助者によるチーム援助 田村節子 第6章 3段階の心理教育的援助サービス――すべての子ども,苦戦している子ども,特別な援助ニーズを要する子ども 水野治久 第2部 実践編:子どもと学校を援助する 第7章 発達障害の理解と援助 小野純平 第8章 不登校の理解と援助 本間友巳 第9章 いじめの理解と援助 濱口佳和 第10章 非行の理解と非行をする子どもの援助 押切久遠 第11章 学校における危機対応 窪田由紀 第12章 学級づくりの援助――スクールカウンセラーの役割を中心に 伊藤亜矢子 第13章 学校づくりの援助 家近早苗 第14章 地域ネットワークづくりの援助 石川悦子 第15章 教育・学校心理学と公認心理師の実践 石隈利紀
学習を成功へと導く授業とは? 熟練教師の実践知とメタ分析によるエビデンスを融合。教職専門性を支えるマインドフレームを示す。 学習を成功へと導く授業とは? 熟練教師の実践知とメタ分析によるエビデンスを融合。教師のコンピテンシーと両輪となって,教職専門性を支える「心的枠組み」を示す。メタ認知,協働学習など,現場のリアルな課題に応える。 学習を成功へと導く授業とは? そのために,教育者はどのように自身の指導と役割を考えればよいのか。熟練教師の実践知とメタ分析によるエビデンスを融合。教師のコンピテンシーと両輪となって,教職専門性を支える10の「心的枠組み」を示す。メタ認知,フィードバック,協働的な学びなど,現場のリアルな課題に応える。 [原書]John Hattie & Klaus Zierer (2018). 10 Mindframes for Visible Learning: Teaching for success. Routledge ■本書の主な目次 Chapter0.はじめに:行なったことの影響をいかに考えるかは,いかに行なうかを考えるよりも重要である Chapter1.私は生徒の学習に及ぼす影響の評価者である Chapter2.アセスメントは自身の影響と次のステップを知らせてくれるものである Chapter3.進歩させたいと考えていることや自身の影響について同僚や生徒と協働する Chapter4.私は変化をもたらすエージェントであり,すべての生徒が改善できると信じている Chapter5.私は「最善を尽くす」だけでなく,チャレンジに努める Chapter6.私は生徒にフィードバックを提供して理解できるように支援し,私に与えられたフィードバックを解釈して行動する Chapter7.私は一方向の説明と同じくらい対話を取り入れる Chapter8.何ができたら成功なのかを最初から生徒に明確に伝える Chapter9.間違えても他者から学んでも安心して学習できるように人間関係と信頼を築く Chapter10.学習と学習中の言葉に集中する Chapter11.可視化された学習のビジョン 邦訳版の刊行に寄せて Chapter0.はじめに:行なったことの影響をいかに考えるかは、いかに行なうかを考えるよりも重要である 1.50人の教師との1万5000時間 2.サイモン・シネックとゴールデンサークル 3.ハワード・ガードナーと3つのE 4.教育の専門知識:コンピテンシーとマインドフレーム 5.なぜこの本なのか 6.可視化された学習とは何か 7.本書はどのように構成されているのか 8.この本は誰を対象としているのか 9.謝 辞 Chapter1.私は生徒の学習に及ぼす影響の評価者である 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.教師は診断したり介入指導をしたり評価したりする必要がある 4.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter2.アセスメントは自身の影響と次のステップを知らせてくれるものである 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.課題(アサインメント)、テスト、クイズ式問題など:退屈な義務というだけではない? 4.ワークシートがなくなってもワークシートは不滅である:過剰なワークシートに対する批判 5.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter3.進歩させたいと考えていることや自身の影響について同僚や生徒と協働する 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 交流と協同の成果としての集合的知性 3.チーム・ティーチング:自明のように思われる要因の可能性と限界 4.何から始めればよいか チェックリスト /エクササイズ Chapter4.私は変化をもたらすエージェントであり、すべての生徒が改善できると信じている 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.問題解決型学習 4.学習者は動機づけられる必要がある 5.多様性を目的にした多様性に対抗する:エビデンスに基づいたさまざまな方法の多様性を求める 6.限界質量:変化を成功させるための条件 7.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter5.私は「最善を尽くす」だけでなく、チャレンジに努める 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.学習にとってのフローとその意義 4.学習目標のタキソノミー:可視化された学習と成功を収める授業に向けた重要な段階5.ゴルディロックスの原理 6.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter6.私は生徒にフィードバックを提供して理解できるように支援し、私に与えられたフィードバックを解釈して行動する 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.あなたの影響を知ること:成功する指導の鍵としてのフィードバック 4.フィードバックのレベルを接合する 5.初心者・上級者・専門家:達成レベルの役割 6.過去・現在・未来:フィードバックの3つの視点 7.包括的なフィードバックの呼びかけ:フィードバック・マトリクス 8.ギブ・アンド・テイク:フィードバックの対話構造について 9.仲間についてはどうか:学習者から学習者へのフィードバック 10.フィードバックを成功させるための必須条件:間違いの文化 11.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter7.私は一方向の説明と同じくらい対話を取り入れる 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.協同学習:仲間の力を活用する 4.確実な習得指導:協同学習を補完する 5.学級規模:重要ではあるが対話にはどうしてもというわけではない 6.何から始めればよいか 7.チェックリスト/エクササイズ Chapter8.何ができたら成功なのかを最初から生徒に明確に伝える 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.目標と成功の基準:双子のような目 4.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter9.間違えても他者から学んでも安心して学習できるように人間関係と信頼を築く 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.IKEA効果 4.「できない」でなく「まだできない」 5.笑顔を見せよう 6.カメレオン効果とルールや習慣化の力 7.一度でも嘘をついたら常に嘘をつくようになる:信頼は教師と生徒の健全な関係の中核である 8.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter10.学習と学習中の言葉に集中する 自己省察のためのアンケート/エピソード 1.本章の概略 2.マインドフレームを支える要因は何か 3.学習ファシリテーター、学習コーチ、学習カウンセラーなのか、そうではなくて教師である 4.バカなやつともっとバカなやつ効果 5.「見えないゴリラ」研究 6.認知負荷理論とその指導のための示唆 7.学習スタイル:実証的教育研究の神話 8.自己概念:成功する学習への鍵 9.何から始めればよいか チェックリスト/エクササイズ Chapter11.可視化された学習のビジョン エピソード:テイラー・スウィフトと仲間たち、学習への情熱を引き出す方法 1.自然から学ぶ:ウェブモデル 2.可視化された教え方:授業計画を可視化する 3.将来の学校のビジョン 訳者代表あとがき 索引 文献 付録:指導要因と効果量ランキング
このテキストは、教育心理学の基本理論や知見を現場の実践に活用する方法をわかりやすく解説したもので、学校教育だけでなく社会や家庭での教育活動にも応用可能です。最新版では、「教職課程コアカリキュラム」に対応し、学級集団づくりや学習評価、運動発達に関する新しい章やコラムが追加されています。著者は法政大学の藤田哲也教授です。
『「やればできる!」の研究』は、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授による成功心理学の古典的名著で、マインドセットが成功と失敗を左右することを論じています。著者は、成長マインドセットと固定マインドセットの違いを探り、教育、ビジネス、スポーツ、人間関係におけるマインドセットの影響を解説。20年以上の研究を基に、マインドセットを柔軟にする方法や、成功するための思考法についても提案しています。
日本の教育改革の主な政策措置 初等中等学校の教育課程改革 ITリテラシーとプログラミング教育 高度な科学技術人材の育成をめざす教育 グローバル人材を育てるカリキュラム改革 児童生徒の学習評価と大学入試改革 大学の教育課程の改革動向 グローバル化時代における大学の国際化政策 第4次産業革命に対応する新型職業大学 教師教育をめぐる改革動向 日本の教育発展のこれからの課題
子どもたちの小さな日常に注目したEPISODEなど,学ぶ意欲を引き出し考えさせる工夫が豊富で理解を深めやすい入門書です 【QUESTION】や【EPISODE】を手がかりに,子どもたちの小さな日常から学びを深める入門書。章末には教師やSCなどがよくであう困難事例/指導場面/判断に迷う場面の【EPISODE】と検討課題が示され,理解確認とさらなる学びを促します。 序章 エピソードに学ぶ──困難な時代の子どもの学びと育ちの豊かさ Ⅰ部 子どもの育ち──発達を理解する 1章 思考の育ち──認知発達 2章 喜怒哀楽の育ち──情動発達 3章「わたし」の育ち──社会化と自己の発達 Ⅱ部 学校で育つ子ども──学びの過程を理解する 4章 学びの基礎──学習,記憶,メタ認知 5章 やる気がでるとき,でないとき──動機づけ 6章 教え方,学び方──学習指導 7章 学びの捉え方──教育評価 Ⅲ部 教室づくり,仲間づくり──学びあう場を支える 8章 仲間との学びあい──協同学習 9章 仲間との関係──適応,社会的学習,ソーシャルスキル 10章 学びと育ちを支える教室──教師─子ども関係,学級風土・学校文化 Ⅳ部 みんなのための学校──個に寄りそい,育ちあう 11章 子どもの困難の理解と支援──学校カウンセリング 12章 個のニーズに応じた学び──特別支援教育
累計2万7000部の好評書。令和の学校改革/協働的な学びと個別最適化/GIGAスクール等,近年の動向を変化をふまえ刷新 累計2万7000部の好評書の最新版。方法の歴史と理論を体系的に整理し,わかりやすくコンパクトに解説した入門テキスト。令和の日本型学校教育/協働的な学びと個別最適化/深い学びとICT活用/GIGAスクール構想等近年の文科省答申や社会的動向もふまえて刷新。 序 章 今なぜ,教育方法の学なのか 第Ⅰ部 教育方法の歴史と展望 第1章 西洋における教育思想と教育方法の歴史 第2章 日本における教育改革と教育方法の歴史 第3章 現代教育方法学の論点と課題 第Ⅱ部 教育の方法 第4章 子どもは何を学ぶか──教育目標・内容論 第5章 学習とは何か──学習論 第6章 学力をどう高めるか──学力論 第7章 授業をどうデザインするか 第8章 教育の道具・素材・環境を考える 第9章 何をどう評価するのか 第10章 教科外教育活動を構想する 第11章 どのような教師をめざすべきか
この文章は、精神分析の知識の対話的発展について語る書籍の下巻の紹介です。フロイト以後の精神分析の進展を、対象関係論、自我心理学、クライン、ビオン、ラカンなどの理論を通じて論じ、臨床への示唆を提供しています。著者は、精神分析が人間の行動や感情の背後にある意味を探る重要な学問であることを強調し、専門的な理解を深めるための対話的なプロセスを描写しています。著者の藤山直樹は、精神分析の実践と訓練を重視し、知識の発展が人々の心に変化をもたらす可能性を示しています。
本書は、青年が哲人に「アドラーを捨てるべきか」という苦悩を語るところから始まります。アドラー心理学の誤解を解く哲学問答を通じて、真の「自立」と「愛」、そして幸せになる方法について探求します。著者は岸見一郎と古賀史健で、アドラー心理学を基にした新たな視点を提供し、読者の生き方を変える力を持つ内容となっています。
プラトン、フッサールの哲学は、互いの意見から共通了解をつくる「対話」の哲学であった。それを確かめ、現在に活かす方法を考える。 プラトン、フッサールの哲学は、互いの意見を確かめ、共通了解をつくりだす「対話」の哲学であった。そのことを丁寧に確かめ、現在の対話に活かす方法を考える。 プラトン、フッサールの哲学は、互いの意見を確かめ、共通了解をつくりだす「対話」の哲学であった。そのことを丁寧に確かめ、現在の対話に活かす方法を考える。
ピア・ラーニングとは 必要な援助を求める 人と比べ合って学ぶ ピアとかかわる動機づけ 何をめざして学ぶか ピアとともに自ら学ぶ 「一人で読む」を超えて 子どもはピアに援助をどう求めるか 協同による問題解決過程 ピアを介した概念変化のプロセス メタ認知におけるピアの役割 協同による教育実践の創造 日本語教育におけるピア・ラーニング 発達に遅れや凸凹のある子どもの協同 豊かな学びあいに向けて
本書は、世阿弥の「風姿花伝」に基づき、教師の授業実践と学びのあり方を探求します。著者の佐藤学氏は、授業技術を指南するのではなく、教師の「学びの思想」と「身体技法」を伝えることを目指しています。内容は、教師としての成長や創造的な授業技法、実践例を通じた教師の役割についての考察が含まれています。佐藤氏は教育界で高く評価されている専門家です。
この入門書は、教育心理学の理論を実践に活かす視点から解説しており、各章末には現場での問題や課題を扱ったコラムが掲載されています。目次には、発達理論や学習理論、教育評価、カウンセリングなど多岐にわたるテーマが含まれています。著者は教育学の専門家で、臨床心理士や学校心理士としての経験も持っています。
シュタイナー学校の公的承認をめぐる一〇〇年の闘い 世界に広がるシュタイナー教育 シュタイナー学校とICT教育 シュタイナー学校の理科教育 シュタイナー学校の地理教育 シュタイナー学校にしみ渡る道徳教育 シュタイナー学校の教師として生きる シュタイナー幼児教育の道を歩み続けて 稲作文化に根ざしたシュタイナー幼児教育の実践 シュタイナー教育に学ぶ子育ての実践
学習と動機づけに関する心理学の視点から,教育実践における指導の方法や技術を包括的に捉える。自己調整学習をはじめ,自ら学ぶ意欲,協同学習の技法など,具体的な研究知見を,教育の現場とのつながりをもたせたわかりやすい表現で紹介。教職課程科目「教育方法・技術論」や「教育の方法と技術」等での使用を想定して編纂。 ◆主な目次 序章 児童生徒の学びを支える指導 第1章 学力の分類と指導 第2章 教育における目標 第3章 教室文化と学習規律 第4章 授業における教授方法 第5章 授業における指導の技術 第6章 学習意欲を促す指導 第7章 仲間との協同による学習 第8章 自律的な問題解決を促す指導 第9章 ICTを用いた指導方法 第10章 授業外の学習の指導 第11章 教師の専門性を高める「子どものつまずき」に応じた指導 第12章 障害のある児童生徒の理解と支援 第13章 教育における評価と学習 第14章 テストの作成と運用 終 章 自ら学び続ける教師を目指して ◆執筆者一覧(執筆順) 伊藤 崇達 編者 序章,第3章 中谷 素之 編者 序章,第6章 岡田 涼 編者 序章,第13章 深谷 達史 群馬大学大学院教育学研究科 第1章 進藤 聡彦 山梨大学大学院総合研究部 第2章 小林 寛子 東京未来大学モチベーション行動科学部 第4章 犬塚 美輪 大正大学人間学部 第5章 瀬尾美紀子 日本女子大学人間社会学部 第7章 梅本 貴豊 京都外国語大学総合企画室 第8章 髙橋麻衣子 日本学術振興会/東京大学先端科学技術研究センター 第9章 篠ヶ谷圭太 日本大学経済学部 第10章 植阪 友理 東京大学大学院教育学研究科 第11章 田爪 宏二 京都教育大学教育学部 第12章 鈴木 雅之 昭和女子大学人間社会学部 第14章 塚野 州一 編者 終章 序章 児童生徒の学びを支える指導 1.指導と学習 2.自己調整学習の視点 3.本書のねらいと構成 第1章 学力の分類と指導 1.学力観の変遷 2.学力とは 3.学力を育てる 第2章 教育における目標 1.教育目標の特徴 2.教育目標と授業の構成 3.教育目標と授業の実際 第3章 教室文化と学習規律 1.文化や風土としての教室 2.教室文化を支えるもの 3.自ら学ぶ学習規律の育成に向けて 第4章 授業における教授方法 1.発見学習 2.受容学習 3.その他の教授方法 第5章 授業における指導の技術 1.授業が「わかる」とはどういうことか 2.説明する技術 3.発問する技術 4.学び方を示す技術 第6章 学習意欲を促す指導 1.学習意欲とは 2.学習意欲を促す指導 3.21世紀型学力と動機づけ 第7章 仲間との協同による学習 1.仲間との協同による学習 2.協同による学習効果とその仕組み 3.協同による学習指導を考えるために 第8章 自律的な問題解決を促す指導 1.課題探究と問題解決 2.PBLとは何か 3.PBLの活用 第9章 ICTを用いた指導方法 1.教育場面におけるICTとは 2.知識の習得・理解の深化を促すICT 3.協調学習を支援するICT 4.学習者の能力を補償するICT 第10章 授業外の学習の指導 1.授業外学習の重要性 2.学習習慣の定着に向けて 3.予習の指導 4.復習の指導 5.授業外学習の指導のポイント 第11章 教師の専門性を高める「子どものつまずき」に応じた指導――個別学習指導(認知カウンセリング)から一斉授業まで―― 1.教師の専門性としての「子どものつまずき」をみとる力 2.個別学習を通じた学習上のつまずきへの対処――認知カウンセリング 3.学習上のつまずきを診断するテストとその活用 4.学習上のつまずきを一斉指導に生かす――「教えて考えさせる授業」 5.結びにかえて――ATIを越えた新たな個に応じた指導を目指して 第12章 障害のある児童生徒の理解と支援 1.心身の障害と教育 2.発達における障害の理解 3.学習場面における障害の理解と支援 4.対人関係における障害の理解と支援 5.障害のある児童生徒の理解と関わり方の姿勢 第13章 教育における評価と学習 1.教育評価とは 2.評価の基準 3.評価の主体 4.評価の時期 5.新しい評価をめぐって 第14章 テストの作成と運用 1.テストに期待される役割 2.テストによる学力の測定 3.テストの実施が学習者に与える影響 4.テストのフィードバック 5.テストに対する学習者の知識・認識とインフォームドアセスメント 終章 自ら学び続ける教師を目指して 1.これからの社会と求められる教師像 2.近年の学習心理学とメタ認知 3.メタ認知を活かした学習理論――自己調整学習 4.省察のもう1つの意義
本書は、普通の臨床家向けの精神分析的臨床の入門書であり、現代の多様な臨床スタイルに対応するためのものです。精神分析の特徴である「見立て」と「他者の心を理解する」アプローチを日常の臨床に活かす方法を解説しています。目次には、対象関係論や心の動き、面接方針の決定などが含まれています。著者は愛知教育大学の教授で、臨床精神分析学を専門としています。
この文章は、部活動に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、部活の成立、歴史、拡大、現状、政策、生徒と教師の安全、そして部活への生徒の向き合い方や未来のデザインについての章が列挙されています。著者の中澤篤史は教育学の博士で、現在は早稲田大学の准教授です。
この文章は、子どもの成長や潜在能力に焦点を当て、親が子どもの成長サイクルを理解し予習する重要性を強調しています。モンテッソーリ教育を通じて、子どもの自律や集中力を育てる方法を提案し、家庭で簡単に実践できることを紹介しています。これにより、子育てが楽しくなり、子どもの未来を輝かせることができると述べています。
この書籍は、生命の本質について分子生物学がどのように答えているかを探求し、歴史的な科学者たちの思考を紹介しながら、現代の生命観を明らかにします。著者の福岡伸一は、分子生物学の成果を平易に解説し、読者の視点を変える内容を提供しています。多くの著名人から高く評価され、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞しています。
私たちが何かを憶え,そして思い出すときに,どのようなことが起きているのだろうか。人間の記憶を支える7つの原理を丁寧に解説。 私たちが何かを憶え,そして思い出すときに,どのようなことが起きているのだろうか。人間の記憶を支える7つの原理を丁寧に解説。 謝辞 第1章 はじめに 1.1 記憶の原理 1.2 法則,原理,効果 1.3 原理とは何か 1.4 記憶の7原理 第2章 システム説と処理説 2.1 システム説と処理説 2.2 システム説 2.3 処理説 2.4 まとめ 第3章 手がかりがなければ始まらない 3.1 原理1:手がかりによる駆動 3.2 手がかりを使わない記憶 3.3 ワーキングメモリにおける手がかりの証拠 3.4 まとめ 第4章 符号化と検索の関係が大切 4.1 原理2:符号化-検索間の関係 4.2 手がかりの強さと符号化特定性 4.3 転移適切性処理は「処理が似ていること」ではない 4.4 原理2から示唆されること 4.5 まとめ 第5章 手がかりの負荷は軽い方が良い 5.1 原理3:手がかりの過負荷 5.2 原理の説明力 5.3 手がかりの過負荷への反論 5.4 まとめ 第6章 記憶は単なる再現ではない 6.1 原理4:再構成 6.2 記憶の再構成に関する古典的な研究 6.3 誤情報効果 6.4 意味記憶の再構成 6.5 リアリティ・モニタリング 6.6 DRMパラダイム 6.7 「同定できなくても再認ができる」 6.8 直接記憶における再構成 6.9 瞬時記憶における再構成 6.10 アイコニック・メモリにおける再構成 6.11 まとめ 第7章 混じりけなしでは測れない 7.1 原理5:混在 7.2 課題や処理が「純粋である」とはどういうことか 7.3 記憶課題によって記憶システムを分けられるのか 7.4 処理過程も純粋ではない 7.5 神経画像化における減算法の論理 7.6 まとめ 第8章 目立つものほど憶えられる 8.1 原理6:相対的な示差性 8.2 レストルフ効果 8.3 短期記憶とワーキングメモリにおける示差性 8.4 モデルを使った原理の証明 8.5 感覚記憶における示差性 8.6 意味記憶における示差性 8.7 潜在記憶における示差性 8.8 心理的な次元の妥当性 8.9 まとめ 第9章 決めうちされるほど憶えにくい 9.1 原理7:特定性 9.2 記憶の階層構造と表象のレベル 9.3 外的な助けと特定性 9.4 健忘症における特定性 9.5 固有名詞 9.6 まとめ 第10章 最後に,再び原理について 10.1 記憶の7つの原理 10.2 本書の原理と他の原理との関係 10.3 本書の原理と,記憶の法則との関連 10.4 原理となりそうな候補 10.5 本書の原理の評価 訳者あとがき 参考文献 索引 A. M. スープレナント(Aimee M. Surprenant) 1992年,Ph.D. 取得(エール大学)。インディアナ大学での研究により,アメリカ国立衛生研究所からNational Research Service Awardを獲得。現職はニューファンドランド・メモリアル大学心理学科教授。 I. ニース(Ian Neath) 1991年,Ph.D. 取得(エール大学)。現職はニューファンドランド・メモリアル大学心理学科教授。人間の記憶について多くの論文や著書を執筆し,現在はMemory & Cognition, Journal of Memory and Language, Psychological Science誌で編集委員を務める。 今井久登(いまい ひさと) 1962年生まれ。1995年,東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。博士(心理学)。東京大学助手,東京女子大学現代教養学部教授を経て,学習院大学文学部教授。著書に『新版 認知心理学』(有斐閣,2011),『心理学をつかむ』(有斐閣,2009)がある。
本書は、子どもの貧困が「非認知能力」の獲得機会を奪うことに焦点を当て、成功に必要な力(やり抜く力、好奇心、自制心など)を育む方法を最新の研究と事例を基に解説しています。著者ポール・タフは、特に貧困家庭の子どもにおける非認知能力の重要性を示し、具体的な育成方法を探求しています。教育者や親にとって、子どもの教育と貧困問題に関する貴重な示唆を提供する一冊です。
日中の歴史の共通認識に基づき教育支援を通じた未来の共同的創造を展望する。 序章 調査研究の基本的枠組み(課題としての歴史の共通認識と共通教育 日中の歴史認識と歴史教育における作用と反作用 ほか) 第1章 研究の対象と先行研究(戦争を認識するために-対象としての構造的暴力 対象としての雲南省〓西地区-日本から遙か遠く離れて ほか) 第2章 〓西地区における侵略戦争と抵抗(雲南における戦闘の特質 〓西地区におけるジェノサイド-暴走するタナトス ほか) 第3章 アイデンティティ形成における戦争認識の問題-歴史の共通認識と未来の共同的創造(国境を越えた元皇軍「慰安婦」支援 国境を越えた教育支援と未来の共同的創造)
この書籍は、科学的手法に基づいた子どものための最適な学習法を紹介しています。著者の竹内龍人氏は、心理学者としての経験を活かし、教育改革や最新の学習トピックに対応した実践的な勉強法を提案しています。内容は、脳の特性を活かす基本的なアイデア、効果的な学習テクニック、メンタル面でのアプローチに分かれており、すべての年齢層に役立つ方法が解説されています。
AIが教育にもたらす影響を,カリキュラム設計と実際の利活用法の2点から解説。新学習指導要領がめざす方向性を深く理解できる。 AIが教育にもたらす影響を,カリキュラム設計と実際の利活用法の2点から解説する。新学習指導要領がめざす方向性を深く理解できる。OECDの教育に関する委員会の元議長で世界的なリーダーのファデル氏らによる提案。 人工知能の発展は教育にどのような影響をもたらすのか。第1部では生徒が「何を」学ぶべきかという視点から,「コア概念」の重要性を提案。第2部では「どのように」教えるのかという視点で教育AIの多様な活用例を紹介し,今後の可能性や倫理的問題も詳しく論じる。新学習指導要領がめざす方向性を理解するのにも最適。 【本書の主な目次】 ●第1部 生徒は何を学ぶべきか?:AIがカリキュラムに与える影響 1 教育の目的 2 基礎となる知識:生徒は何を学ぶ必要があるか? 3 コア概念の概要 4 必須のコンテンツの概要 5 意味づけとAIアルゴリズムの影響 6 コア概念 7 必須のコンテンツ 8 どのコンテンツを追加すべきか 9 どのコンテンツを削除すべきか 10 実際上の考慮事項 11 結論 ●第2部 どのように?:指導と学習にAIがもたらす可能性と影響 1 教育におけるAI 2 AIの背景 3 AIの技術と用語 4 AIは教育でどのように機能するか ― 教育におけるAIの活用 ― 5 知的学習支援システム 6 対話型学習支援システム 7 探索型学習環境 8 自動ライティング評価 9 他にどのようなAIEDがあるのか? 10 他にできることは何か? 11 教育におけるAI:暫定的なまとめ 目次 編訳者はしがき "Artificial Intelligence in Education(教育AIが変える21世紀の学び)"への賛辞 謝辞 はじめに―背景 第1部 生徒は何を学ぶべきか?:AIがカリキュラムに与える影響 1 教育の目的 2 基礎となる知識:生徒は何を学ぶ必要があるか? 3 コア概念の概要 4 必須のコンテンツの概要 5 意味づけとAIアルゴリズムの影響 5.1雇用可能性 5.2拡張知能 5.3教育への示唆と生徒が学ぶべきこと 5.4 意味の重要性 5.5 直観 5.6 有意義さ:知識を動員する 5.7 概念の道具箱をつくる 5.8 転移:学習した知識を新しい状況で使う 5.9 意味の領域 5.10 問題のある知識 5.11 最適化 6 コア概念 6.1 最も重要なことは何か? 6.2 「知っている」と「できる」 6.3 重要な知識枠組み 6.4 ツールとしての概念指標 6.5 構造のレベル 6.6 概念によるコンテンツの体系化 6.7 コンテンツの構造 7 必須のコンテンツ 7.1 何でも検索できるなら,なぜ何でも学ぶのか? 7.2 ダニング=クルーガー効果を避ける 7.3 日常生活で使うスピード,流暢さ,自動性 7.4 社会的に共有された背景知識 7.5 より複雑な概念に必要である 7.6 コア概念の基質となるコンテンツ 7.7 コンピテンシーの基質となる知識 7.8 現代的な知識 8 どのコンテンツを追加すべきか 8.1 テクノロジーとエンジニアリング 8.2 メディア 8.3 企業家精神とビジネス 8.4 個人ファイナンス 8.5 ウェルネス 8.6 社会科学 9 どのコンテンツを削除すべきか 9.1 学問分野によらない構造 9.2 カリキュラムの設計に学際的テーマを組み込む 9.3 学問分野の変化 10 実際上の考慮事項 10.1 意思決定 11 結論 第2部 どのように?:指導と学習にAIがもたらす可能性と影響 1 教育におけるAI 2 AIの背景 3 AIの技術と用語 3.1 アルゴリズム 3.2 機械学習 3.3 教師あり学習 3.4 教師なし学習 3.5 強化学習 3.6 人工ニューラルネットワーク 4 AIは教育でどのように機能するか 4.1 教育におけるAIの歴史 4.2 適応学習 4.3 コンピュータ支援教育 4.4 AIとCAI ― 教育におけるAIの活用 ― 5 知的学習支援システム 5.1 領域モデル 5.2 指導モデル 5.3 学習者モデル 5.4 典型的なITSのアーキテクチャ 5.5 ITSの効果を評価する 5.6 Mathia 5.7 Assistments 5.8 alta 5.9 さらなる例 6 対話型学習支援システム 6.1 CIRCSIM 6.2 Auto Tutor 6.3 Watson Tutor 7 探索型学習環境 7.1 Fractions Lab 7.2 Betty’s Brain 7.3 Crystal Island 7.4 ECHOES 7.5 まとめ 8 自動ライティング評価 8.1 PEG 8.2 Intelligent Essay Assessor 8.3 WriteToLearn 8.4 e-Rater 8.5 Revision Assistant 8.6 OpenEssayist 8.7 AIによる採点 9 他にどのようなAIEDがあるのか? 9.1 ITSプラス:ALT School,ALP,Lumilo 9.2 言語学習:BabbelとDuolingo 9.3 チャットボット:Ada とFreudbot 9.4拡張現実と仮想現実 9.5 学習ネットワーク編成器:Third Space Learning とSmart Learning Partner 10 他にできることは何か? 10.1 協働学習 10.2 生徒フォーラムのモニタリング 10.3 継続的な評価 10.4 AIによる学習コンパニオン 10.5 AIティーチングアシスタント 10.6 学習科学を発展させる研究ツールとしてのAIED 11 教育におけるAI:暫定的なまとめ 12 教育におけるAIの社会的影響 12.1 AIEDテクノロジーが教室に与える影響 12.2 AIEDの倫理 補足1 A1-1 トピックと概念のつながり A1-2 コンテンツの進化 A1-3 分野横断的なテーマ 補足2 A2-1 AIとは何か? A2-2 今日のAI A2-3 AIの技術 A2-4 AIの技術と専門用語 CCRについて 教育のスタンダードを再設計する 当センターの基本理念 「何を」にフォーカスする 当センターの業務 著者について 付論:人工知能と教育人材の養成 はじめに なぜ教育人材の育成なのか 教育人材育成のストラテジー 教育人材は「生身の人間」である必要があるのか 索引
この書籍は、日本人に関する一般的な見解を検証し、文化的レッテルが国家や民族間の対立を激化させる危険性を警告しています。著者の高野陽太郎は、集団主義に関する通説やその成立過程、文化的ステレオタイプについて考察しています。
戦後69年企画 少年のまなざしで綴る激動の二年(1944~1945年) 日記の著者である藤田秀雄氏は、一九四四―四五年当時は、国民学校高等科から旧制中学一、二年生(一二歳から一四歳)の少年期でありました(その後、藤田氏は東京大学に入学、宮原誠一研究室の第一期生となり、卒業後は群馬県島村で社会教育に従事)。日記には、軍事教練、勤労奉仕、自習(先生の召集による)、東京大空襲、敗戦、進駐、買い出し、ストライキ、同盟休校、墨塗り教科書――など、当時のプロパガンダや見聞などをありのままに伝えられています。 当時を振り返り、藤田氏は「敗戦を迎えた時、あとは余命だと思った。この場合での余命とは、余分のいのちという意味である。そこで、あとは好きに生きればよいという、一種のすがすがしい気持になったのをおぼえている」と語ります。 編者の山田正行氏は、藤田日記には「少年の澄明な心理が、戦争という極限状況において人間性の深奥をかいま見せたと捉えられる」としています。また、山田氏は当時の時代状況を読者がより鮮明に理解するために、戦時標語・流行語・流行歌・年表などの詳細な資料を付しました。 はじめに 山田正行 一九四四年の日記 一九四五年の日記 資料 戦時標語・流行語・流行歌・年表 敗戦前後 少年の生活とおもい 藤田秀雄 藤田少年日記を読んで 娘たちに戦争と平和について語りたい 工藤優子 広義の社会教育がもつ原風景としての素朴さと危うさの弁証法 堂本雅也
この本は、いじめや孤独、自己肯定感の低さなどの悩みを抱える子供たちに向けて書かれています。著者は、子供たちの感情を理解し、表現することの重要性を伝え、学ぶことが生きる力になると励まします。また、助けを求めることの大切さや、そばにいることの意味についても触れています。著者は教育や心理学の専門家であり、子供たちを支える立場で活動しています。
この書籍は、幸福やウェルビーイングに関する科学的研究を探求し、親密な人間関係の構造や機能、対人魅力、コミュニケーションの重要性について論じています。特に、対人関係を通じて幸福を追求する方法や社会的スキルの役割に焦点を当て、価値の共有や共生を通じてより良い社会を築くことを提案しています。著者は大阪大学の教授、大坊郁夫です。
著者の塚越寛は「年輪経営」と呼ばれる経営手法を提唱し、社員の幸せを重視した企業戦略を実践しています。彼は人件費をコストではなく目的と位置付け、急成長を避け、決算は3年に1回で良いと考えています。48年間連続で増収増益を達成した実績を持ち、社員が幸せになる会社づくりや、経営者の教育者としての役割を強調しています。この書籍はその経営理念と実践を紹介しています。
混乱する教育の理念と価値観,繰り返される「改革」,変化する社会と子どもたち……,この現実をどのように言葉で語り,実践を切り拓くことができるか.「メディア」「格差」から,「人格」「学力」のとらえなおしまで,現代の教育学のキーワードを身につけるテキスト.現実を俯瞰し希望を語る教育理論の新しい見取り図. I メディア 1章 言語(今井)/2章 知識(田中)/3章 美(今井)/4章 カリキュラム(田中)/5章 メディア(今井) II 主 体 6章 身と心(今井)/7章 成長・発達(山名 淳)/8章 人格(田中)/9章 子ども(矢野智司)/10章 自律性(山名) III 関 係 11章 学ぶと考える(田中)/12章 教育評価(越智康詞)/13章 悪(矢野)/14章 教育(山名)/15章 関係性(矢野) IV システム 16章 学校(越智)/17章 教育政策(越智)/18章 公共性(小玉重夫)/19章 学力(小玉)/20章 教育学(田中)
この書籍では、日本の経済停滞とコロナ禍の影響を受け、「未来の教室」事業への期待とその成否が検証されます。また、労働の多くがロボットに代替される未来において、教育の役割が重要になる中、各国の政策対応や学びのイノベーションの推進についても論じられています。著者の佐藤学は、豊富なデータを基に学校改革の展望を示しています。
本書は、アランの「プロポ」から選ばれた幸福に関する93の哲学断章を収めたもので、ルーアンの新聞に連載されたことが始まりです。独特なスタイルで「哲学を文学に、文学を哲学に」変える試みが評価され、フランス散文の傑作とされています。日本でも早くから親しまれています。
本書は、教育に関する一般的な思い込みに科学的根拠を持って反論し、教育経済学の視点から「成功する教育・子育て」についての知見を提供します。内容は、ゲームの影響やご褒美の効果、非認知能力の重要性、少人数学級の効果、良い教師の条件など多岐にわたります。著者は、個人の経験よりもデータに基づく教育の重要性を強調し、教育関係者や親にとって必読の一冊とされています。
この文章は、社会心理学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は4つの部に分かれ、集団と組織、世論と集合現象、社会問題、文化と適応について論じています。著者は唐沢穣と村本由紀子で、それぞれ名古屋大学と横浜国立大学で教授を務めています。
葛藤に適切に対処し、円援に解決することは精神衛生上も社会適応上も重要な課題です。葛藤解決は円滑な社会生活を送るために必須のスキルなのです。本書は、社会的葛藤について長年研究を重ねてきた著者が、学術的根拠を示しながら葛藤解決を困難にする心理的障壁の正体を明らかにし、これを打ち破る方策を検討していきます。 1 社会的葛藤と紛争の社会心理学 2 社会的葛藤解決の心理的障壁-認知のバイアス 3 認知バイアスの背後にあるもの 4 社会的葛藤と感情 5 社会的葛藤解決の心理社会プロセス 6 社会的葛藤と人間関係 7 社会的葛藤解決における個人特性
この書籍は、教育や学習の本質を進化学、遺伝学、脳科学の観点から探求しています。著者は、学ぶことの目的は他人との成績を競うことではなく、個人にとっての意味を見出すことであると強調しています。学力の個人差には遺伝が50%影響するものの、教育はその遺伝的素質を活かすために存在し、他者との知識の共有を促進する役割を持っています。読者に対し、自身の学びを見つけることの重要性を伝えています。
このビジネス書は、多様性を取り入れた組織が成功する理由を探求し、致命的な失敗を未然に防ぎ生産性を高めるための組織改革の方法を提示しています。著者マシュー・サイドは、革新を促す要素やコミュニケーションの重要性について考察し、具体的な事例を通じて読者に考えさせる内容となっています。シリーズは好評を博し、さまざまなメディアで紹介されています。
この文章は、衝撃の超ベストセラーの20周年記念版について紹介しています。著者が序文で「本当は何を書いた本なのか?」という問いに答え、多くの読者を悩ませ楽しませてきた内容を示しています。目次には、音楽や論理学、数学、コンピュータシステム、脳と思考などのテーマが含まれています。
「適応」と「マイクロ-マクロ関係」をキーワードに,統合的な視点から「人間の社会性」を追究。 新しい研究知見を加えて刷新。 集団に組み込まれた個人を基礎に,「適応」と「マイクロ-マクロ関係」をキーワードとして,統合的な視点から「人間の社会性」を追究した,新しい社会心理学のテキスト。行動・実験経済学や社会神経科学等,10年間の研究知見を加えて,内容を刷新。 序 章 「人間の社会性」をどう捉えるか? 第1部 集団生活と適応 第1章 社会的影響過程 第2章 社会的交換 第3章 グループとしての協調行為 第4章 社会環境と適応行動 第2部 適応を支える認知 第5章 社会的認知のメカニズム 第6章 集団間認知とステレオタイプ 終 章 統合的な社会心理学に向けて
本書は、京都大学での「意思決定の授業」を基に、若い世代がカオスの時代を生き抜くために必要な意思決定の方法や決断力を学ぶための内容を提供しています。著者は、自分の人生を自分で考え、決める重要性を強調し、具体的な思考法や議論の意義、情報収集術などを通じて読者を導きます。人生の選択について考える手助けをすることを目的としています。
グローバル化する世界の学校を旅する 「半日制」の伝統をもつ学校-ドイツ 親と一緒に登校する学校-フランス 高い学力と平等性を誇る学校-フィンランド 教育の質を目指す学校教育-二部制から一部制の方向へ-メキシコ 貧困と陽気さが交差する学校-ブラジル 大国ロシアの発展を支える学校-ロシア 社会主義の学校からOECD教育モデルの学校へ-ポーランド 「世界の工場」から「世界の市場」へと変貌する学校-中国 ポスト・ドイモイと質重視の教育を模索する社会主義の学校-ベトナム〔ほか〕
この書籍は、教育心理学の基礎理論とその実践への応用を学ぶためのテキストシリーズの第2巻です。簡潔な解説に加え、ディスカッション課題や演習課題、資料図版が豊富に掲載されており、学生が自ら考えることを促します。また、教員採用試験対策にも対応しています。著者は京都教育大学と関西外国語大学の教授で、心理学と人間科学の博士号を持っています。
意見を異にする人々の社会が一つの選択を迫られたとき,どういう「きめ方」が望ましいか.本書は,投票のパラドックス,アロウの一般可能性定理などを楽しい具体例と簡単な図表で説き明かし,倫理社会の構築をめざす社会的決定理論を意欲的に提言する. はしがき 序章 「どうしたらいいと思う?」 I 投票による決定 II 民主的決定方式は存在するか III 個人の選好に対する社会的規制 IV 個人の自由と社会の決定 V ゲーム理論と社会道徳 VI 「公正な立場」からみた社会的決定の論理 VII 平等な社会と個人の倫理性 VIII 多様性の中に調和を
著者ブライアン・R・リトルによる最新刊は、パーソナリティとウェルビーイングの関係を科学的に解明した内容で、ハーバード大学で人気教授に選ばれた実績があります。書籍では、自分の性格を理解し、人生を主体的に生きる方法や、性格が幸福や寿命に与える影響について探求しています。各章では、性格の変化やクリエイティビティ、生活の質に関するテーマが取り上げられています。
「チーム学校」や,いじめ・不登校防止などの必須項目を解説しつつ,学校安全やキャリア教育といった近年の動向を踏まえた入門書。 「教職課程コアカリキュラム」を意識して主要な概念を解説。「チーム学校」や「学校安全」など、実践の場でも役立つ視点を取り入れる。図表や2頁単位の読み切り,キーワードの明示など初学者向けの工夫を施したテキスト。 「教職課程コアカリキュラム」に基づき,チーム学校やいじめ・不登校防止をはじめとする各領域の必須項目を解説。その上で,学校安全,ICT利用に関する問題への対応,キャリア教育の動向など実践の場でも役立つ視点を踏まえた内容を扱う。豊富な図表や見開き体裁,キーワードの強調など初学者向けの工夫を施した入門書。 はじめに 1章 学校適応援助 1.子どもの教育的ニーズと適応援助 2.学校適応と生徒指導 3.教育課程と生徒指導 4.学級・ホームルーム経営と子どもの学校適応 5.学校適応と課外活動 6.チーム学校 7.生徒指導にかかわる法律事項 8.生徒指導における体罰の問題 9.生徒指導の歴史 2章 問題行動の理解と対応 1.問題行動 2.生徒指導と教育相談の相違点 3.生徒指導の全校的な取り組み 4.学級経営 5.不登校の現状 6.不登校の早期発見・早期対応 7.不登校への対応 8.いじめ防止対策推進法 9.学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 10.いじめをどう捉えるか 11.いじめへの対応 12.いじめとその周辺 13.いじめ重大事態 14.いじめの事実確認と再発防止 15.非行の諸相 16.子どもの暴力行為 17.出席停止制度と停学・退学 3章 発達障害の理解と援助 1.特別支援教育とインクルーシブ教育システム 2.学級担任の役割 3.知能と子どもの実態を把握するアセスメント 4.認知特性と特性に応じた指導 5.自閉スペクトラム症,自閉症スペクトラム障害 6.限局性学習症,限局性学習障害 7.注意・欠如多動症,注意欠如・多動性障害 8.ユニバーサルデザインによる教育 9.学習への援助 10.適応への援助 11.学級への援助 12.就学前の時期の留意事項 13.小学校低学年での留意事項 14.小学校高学年での留意事項 15.中学校・高等学校での留意事項 4章 学校教育相談 1.学校教育相談の意義と目的 2.児童生徒理解 3.子どもと子どもを取り巻く環境のアセスメント 4.援助の進め方 5.スクールカウンセラー 6.スクールソーシャルワーカー 7.教育相談とスクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカーとの連携 8.性的マイノリティとされる児童生徒への配慮 9.自傷行為の理解と援助 10.心的外傷と回復 11.嗜癖の理解と対応 12.児童虐待の早期発見と対応 13.虐待を受けた子どもの理解と支援 5章 生徒指導における予防・開発的アプローチ 1.予防・開発的生徒指導 2.人とかかわる力の育成 3.心理教育プログラムの実際 4.自尊感情の育成 5.セルフコントロール力の育成 6.自殺予防教育 7.有害情報への対処 8.薬物乱用防止教育 6章 キャリア教育 1.キャリア教育とは 2.キャリア教育の理論:キャリア発達理論 3.キャリア教育の理論:職業選択理論 4.キャリア教育で育てる能力 5.キャリア教育の進め方 6.キャリア教育の方法:教育課程全体を通じた実践 7.キャリア教育の方法:職場体験 8.キャリア教育の評価 9.進路指導の実際 10.生涯キャリア発達の支援 7章 地域社会・保護者との連携 1.学校内外の連携 2.学校内の相談の構造 3.保健(母子保健,精神保健),医療との連携 4.福祉事務所との連携 5.児童相談所との連携 6.教育支援センターとの連携 7.警察との連携 8.保護者との連携・社会教育 8章 学校安全 1.学校における危機管理 2.交通安全と通学路の安全確保 3.福祉犯から児童生徒を守る 4.情報セキュリティ教育 5.学校内の事故防止又はスポーツ事故の防止 6.学校保健と生徒指導 7.食物アレルギーと給食指導 8.防災教育 引用・参考文献 索引
この書籍は教育心理学の基本を解説したロングセラーの第5版で、最新の統計データやいじめ問題、発達障害に関する記述が加わっています。内容は、記憶力、学び、やる気、評価方法、発達についての考察など多岐にわたり、教育や心理学に関心のある人々に向けてわかりやすくまとめられています。著者は鎌原雅彦と竹綱誠一郎で、共に教育学の博士号を持つ教授です。
「なぜ人権教育が必要?」「同和教育との関係は?」「学校で大事にすべきことは?」など、よくある25問にやさしく答えた入門書。さまざまな教育運動との関係、視点と方法、政策的動向や今後の課題などをまとめた大幅改訂新版 「なぜ人権教育が必要?」「同和教育との関係は?」「学校で大事にすべきことは?」など、よくある25問にやさしく答えた入門書。さまざまな教育運動との関係、視点と方法、政策的動向や今後の課題などをまとめた大幅改訂新版 はじめに 問1 人権教育とは何ですか? 問2 今の子どもや若者たちになぜ人権教育が必要なのでしょうか? 問3 人権と言われてもぴんときません。人権とはどのようなものでしょうか? 問4 なぜ「人間は平等だ」といえるのですか? 問5 「人権」があるなら、「猫の権利」や「メダカの権利」はどうでしょうか? 問6 人権のなかに矛盾や対立はないのですか? 問7 セルフエスティームやレジリエンスとはどんな意味でしょうか? 問8 「機会の平等」「結果の平等」とは何ですか? 問9 環境教育、持続可能な開発のための教育、シティズンシップ教育などと人権教育はどのようにかかわっているのですか? 問10 同和教育など、日本国内の反差別の教育と人権教育の関係は? 問11 多様性教育は人権教育とどう、かかわりますか。 問12 心の教育や道徳教育と人権教育の関係は? 問13 部落問題や在日韓国・朝鮮人問題などを学びましたが、なかなか身近に感じられません。 問14 人権ばかり学んでいては、責任感や義務感が育たないのではないですか? 問15 人権教育の手法にはどんなものがありますか? 問16 擬似体験やゲームで差別や人権の問題がわかるのでしょうか? 問17 参加型を活用した人権学習プログラムはどう組み立てればよいでしょうか? 問18 ファシリテーターは誰でもできるのでしょうか? 問19 学校ではまず何を大切にすべきでしょうか? 問20 人権総合学習とは何ですか? 問21 人権教育のために国際連合はどんなことをしてきましたか。 問22 「人権文化」とはどのような意味でしょうか? 問23 日本の人権教育に何か特徴がありますか? 問24 日本の政府や自治体は、どんなことをしているのでしょうか? 問25 日本でのこれからの課題はどんなことでしょうか? 参考図書の紹介
本書は、心理学者ヴィクトール・フランクルが強制収容所での体験を通じて「人間とは何か」を探求した作品です。人間は自己を定義し、悲惨な状況でも毅然とした態度を保つ存在であると述べています。1947年に初版が刊行され、以来600万部以上のロングセラーとなっており、今回新訳・新編集版として再登場しました。フランクルは、存在の意味を重視し、実存分析やロゴテラピーの理論を展開しました。
戦前から戦後にわたる宮原誠一の教育思想は、どのように展開されたのか。五十嵐顕によって継承・展開された「多面的重層的」思想構造と、その相互関連性を浮き彫りにする。「本書は、戦争責任の自覚を根底にすえた平和教育論の現代的継承という観点から書かれた、思想史研究の書でもある」 序章 研究の課題、方法、構成 第1章 宮原における思想と実践との連関構造—戦前の抵抗と戦後の展開 第2章 宮原社会教育学の思想的枠組み—人間発達と社会発展の総体的認識の学問としての社会教育学 第3章 戦時下の宮原の論理展開 第4章 体制変革の現実性と「軍部赤色革命論」—「陸軍国民教育」論に即して 第5章 五十嵐顕の平和教育の思想と実践—宮原から五十嵐への展開 第6章 地域社会教育実践における宮原と五十嵐の継承—平和憲法学習会と心に刻むアウシュヴィッツ・秋田展に即して 終章 意義と課題
教師になること/教師であることの現在 学校は、なぜこんなにも評価まみれなのか まじめな教師の罪と罰 新人教員の苦悩に対して教員養成には何ができるか 「若手教師」の成長を支えるもの 同僚に学びながら教師になっていく 中堅期からの飛躍 受験体制の中で自分の教育観にこだわる 教師バッシングはもうやめて 教師はどのようにして生徒の学びが〈みえる〉ようになっていくのか 制度としての「評価の圧力」の下での実践の創造 学校の「しんどさ」とどうつきあうか