【2025年】「精神分析」のおすすめ 本 173選!人気ランキング
- 精神分析入門(上) (新潮文庫)
- 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え
- 精神分析学入門 (中公文庫 フ 4-2)
- 集中講義・精神分析㊤─精神分析とは何か フロイトの仕事
- 図解ヒトのココロがわかるフロイトの話
- ユング心理学入門: 〈心理療法〉コレクション I (岩波現代文庫 学術 220 〈心理療法〉コレクション 1)
- 心のトリセツ「ユング心理学」がよくわかる本 (PHP文庫)
- フロイトの精神分析: 図解雑学 絵と文章でわかりやすい!
- 夢判断 上 (新潮文庫 フ 7-1)
- 生き延びるためのラカン (ちくま文庫 さ 29-3)
本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。
10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。
『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。
フロイトの『精神分析学入門』は、彼の精神分析学の体系と本質を詳述した代表作であり、人間理性の万能を否定し、性の力を強調することで近代の人間観に大きな変革をもたらした。内容は、しくじり行為、夢の解釈、ノイローゼの総論などを含む。フロイトは精神分析の創始者として、20世紀の思想に重要な影響を与えた。
この書籍は、精神分析を教養として学ぶための入門書です。内容はフロイトの人物像や無意識、夢の仕組み、心の発達、心を守る働き、治療法、精神分析の実用性、フロイトの真意など、多岐にわたります。著者は哲学・心理学の分野で活躍する山竹伸二です。
河合隼雄の処女作であるこの書籍は、日本初のユング心理学の入門書で、著者の心理学の出発点を示す重要なテーマが含まれています。文庫化に際し、ユング心理学を学ぶ経緯を記した序説と読書案内も収録されています。目次には、タイプ、コンプレックス、無意識、夢分析などが含まれています。河合隼雄は京都大学で教授を務め、ユング派分析家としても活躍しました。
著者はユング心理学が日本人に適していると主張し、心の病の原因や治療法、個性の理解に役立つユング心理学の概念を紹介しています。内容には夢分析、心のタイプ、元型、対人関係のヒントが含まれており、ユングのオカルトへの見解も探求されています。著者は長尾剛で、東京出身の作家です。
この本は、ユングの「分析心理学」をマンガ形式で解説し、彼の生涯と思想を簡潔に紹介しています。ユングは無意識の世界を探求し、夢や心理の理解に焦点を当てています。目次には、心理の発見、夢の解釈、無意識の共有、論理と非論理、自分らしい生き方のための夢判断などが含まれています。
本書は、あまり知られていないオーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーの心理学を通じて、幸福に生きるための指針を示しています。アドラーの生涯や彼の心理学の基本概念、育児や教育、対人関係、人生の意味についての考え方を解説し、読者に自立した人生を送るためのヒントを提供しています。
このテキストは、教育心理学に関する包括的な教材で、大学や短大の教職課程、教職を目指す学生、既に教職にある人の学び直しに適しています。2017年に改訂され、法律や指導要領の変化に対応し、演習問題を充実させています。内容は、教育心理学の基本から発達、学習メカニズム、授業の心理学、教育評価、知的能力、パーソナリティ、社会性、学級の心理学、不適応、特別支援教育に関する章で構成されています。付録には演習問題の解答や重要用語の解説も含まれています。
この書籍は、経営心理学と脳科学に基づいてリーダーが取るべき行動を解説しています。著者は公認会計士であり、心理学や脳科学を研究しながら企業の経営者を指導してきた経験をもとに、人の感情がビジネスに与える影響を探ります。内容は、感情のメカニズムや人間関係の重要性、組織や顧客との関係構築に焦点を当て、業績向上のための具体的な方法を提案しています。著者は心を扱うことの重要性を強調し、成功するためには人間の感情を理解することが不可欠であると述べています。
ヴィゴツキーの『芸術心理学』は、ソビエトの心理学や教育学に影響を与えた重要な著作であり、感情の昇華「カタルシス」について論じています。本書は、芸術の心理的側面を探求し、文学や心理学、教育学に対する示唆を提供します。内容は方法論、芸術の認識と手法、具体的な美的反応の分析、芸術心理学の4部構成となっています。著者は1896-1934年に活躍したヴィゴツキーで、訳者は東京大学名誉教授の柴田義松です。
本書は心理学の基礎から応用をやさしく解説し、科学的エビデンスを重視しています。実験や観察を通じて得られた知見をもとに、広告やマーケティングなど身近な場面での応用方法を紹介。実践的な心理学の知識を身につけることができます。著者は心理学者の植木理恵氏で、実証的研究を行い、数々の賞を受賞しています。
このFX解説本は、累計40万部を超える人気を誇るカリスマFXブロガー「羊飼い」と「ザイFX!」が共同で制作したもので、改訂第2版では最新データと億り人たちの成功事例を紹介しています。FXの基本から応用、ファンダメンタルズやテクニカル分析まで幅広くカバーし、個人投資家の体験談や勝ち方も詳述されています。FXを始めるための実践的なノウハウが満載の内容です。
本書は、臨床心理学の基礎から心理検査、カウンセリング、心理療法までを最新の研究に基づいて解説した入門書です。イラストや図表を多用し、心理学に興味のある人や心理職を目指す学生に最適です。内容は、心のつらさの軽減、心理的援助の基本、代表的な心理療法、心の問題の改善、臨床心理学の社会的役割に分かれています。著者はお茶の水女子大学の教授で、心理療法の研究に注力しています。
本書は、精神分析理論の基本を実感的に理解できるように改訂されたテキストであり、精神分析の歴史や構造、力動的観点、心の病理、発達論などを詳しく解説しています。著者の馬場禮子は、理論を実生活や臨床に結びつけながら、読者にわかりやすく伝えることを目指しています。講義形式を取り入れ、用語の解説を中心に基礎知識を提供し、精神分析が有機的に繋がる理論であることを強調しています。全体的に、初心者から中級者までが理解しやすい内容となっています。
本書は、フロイトとユングの心理学理論を基に、夢や性、暴力、環境破壊などの深層心理を探求する内容です。著者は、精神分析学の最新の学説にも触れつつ、20世紀初頭の学説が現代科学によって再評価されていることを示しています。著者は心理学の専門家であり、夢の心理学や自我論、死生学に関する研究を行っています。
この書籍は、韓国の人気グループ防弾少年団(BTS)のニューアルバムのコンセプトに基づいており、心理学者ユングの理論を探求する入門書です。ユングは心を未知の領域として探検し、その理論は人々を導く地図と見なされます。著者マレイ・スタインはユング派分析家で、ユングの著作を通じて理論の統一性を解説しています。目次には自我意識、コンプレックス、リビドー理論、集合的無意識などのテーマが含まれています。
この書籍は、ユング心理学の視点からグリム童話を分析し、人間の心の奥深くにあるものを探求しています。著者は、親子関係や男女の関係、自己の内面といったテーマを通じて、自己実現の方法を示しています。各章では、特定の童話を取り上げ、それに関連する心理的な概念や成長過程を解説しています。全体を通じて、読者が自分自身を理解し、成長するための指針を提供しています。
この書籍は、臨床心理学の基礎から心理アセスメント、心理療法、コミュニティ援助、心理臨床の現場、現代の心の問題に至るまでの内容を扱っています。著者の青木紀久代は、臨床心理士であり、発達臨床心理学と精神分析学を専門とし、大学や教育機関で心理臨床に従事しています。
本書は、心理療法の基本と技術を学派を超えて解説した入門書です。著者は精神分析的立場から、面接の流れや重要な原則を平易に説明し、心理療法の実践における共通する要素を強調しています。特に、クライエントとの関係性や反発に対する基本的な対応の重要性を指摘し、成功するための基礎知識を提供しています。内容は、心理療法の開始から終結までの各段階や転移、抵抗、介入の技法など多岐にわたり、心理療法家としての熟練を目指す人にとって役立つ情報が詰まっています。
現代思想における震源地であるラカン。その核心に実践臨床という入射角から迫る超入門の書。『疾風怒濤精神分析入門』増補改訂版。解説 向井雅明 現代思想における震源地であるラカン。その核心に実践臨床という入射角から迫る超入門の書。『疾風怒濤精神分析入門』増補改訂版。解説 向井雅明 千葉雅也氏推薦 「まず最初に読むべきラカン入門書です。」 二十世紀における思想的な震源地のひとつであるラカン。その理論は、思想としての側面と、実践臨床としての側面の二面性をもち、両者が渾然一体となっていることに難しさがある。本書は、著者みずからの精神分析の体験にもとづき、実践臨床の側面からラカンの本丸に迫る。ラカンの核心を読み解く超入門の書、『疾風怒濤精神分析入門』増補改訂版。 解説 向井雅明 第Ⅰ部 精神分析とはどのような営みか 第一章 それでも、精神分析が必要な人のために──精神分析は何のためにあるのか 第二章 自分を救えるのは自分しかいない──精神分析が目指すもの アンコール1 人はどのようにして精神分析家になるのか 第Ⅱ部 精神分析とはどのような理論か 第三章 国境を越えると世界が変わってしまうのはなぜか──想像界・象徴界・現実界について 第四章 私とはひとりの他者である──鏡像段階からシニフィアンへ アンコール2 手紙は必ず宛先に届く 第五章 〈父〉はなぜ死んでいなければならないのか──エディプス・コンプレクスと欲望 アンコール3 エディプス・コンプレクスは、今日? 第六章 不可能なものに賭ければよいと思ったら大間違いである──現実界について アンコール4 神経症・精神病・倒錯 終 章 すべてうまくはいかなくても──分析の終結について
本書は、FX初心者が勝てるようになるためのテクニックとメンタルを身につける入門書です。著者は本気でFXユーザーの成功を支援し、ダウ理論に基づいた勝ち方やリスク管理の重要性を強調しています。内容には、テクニカル分析、エントリータイミング、メンタルの鍛え方などが含まれ、実践的な練習チャートも提供されています。著者は経験豊富なトレーダーであり、FXを通じて資産を増やす方法を楽しく学べる内容になっています。
本書は「最新の学習心理学のもっとも簡明な教科書」の改訂版で、実際の講義から得た疑問や意見を反映し、近年の研究を追加しています。特に動物のエピソード記憶やメタ記憶に関する新たな章が設けられ、入門から応用まで幅広く活用できる内容になっています。目次には学習の基本概念から条件づけ、記憶に関する多様なテーマが含まれています。著者は千葉大学名誉教授の実森正子氏と関西学院大学教授の中島定彦氏です。
この書籍は、カウンセリングの基本と支援方法を学ぶための入門書で、カウンセラーを目指す人やカウンセリングを活用したい人に向けています。内容は、カウンセリングの定義や歴史、心の声の聴き方、青年期の自立支援、自分らしい生き方の探求など、具体的な事例を通じて構成されています。著者は臨床心理士の平木典子で、心理療法の専門家としての経験を活かしています。
理論と実践の双方向から「行動分析学」を体系的に解説。幅広い内容をコンパクトに収めた決定版。各種ツールも充実。 「行動分析学」を初めて学ぶ方に向けた概説テキスト。行動の分析を一つの軸に,基礎理論と臨床・日常場面への応用をリンクさせる一冊です。演習問題や事例紹介など,充実のツールで学びをサポート。医療福祉の現場に立つ方にもおすすめ。 第1章 心とは何か──行動分析学から接近する 第2章 観察法と実験法──行動を科学するために 第3章 生得性行動──経験によらない個体の行動とは 第4章 レスポンデント──環境の機能を変える方法を知る 第5章 オペラント──行動やその出現機会を作り出す方法を知る 第6章 強化随伴性──行動変容のための諸変数と規則 第7章 刺激性制御──はじめての環境に個体が出会うとき 第8章 反応遮断化理論と選択行動──強化と価値を考える 第9章 言語行動と文化随伴性──行動分析学から展望する
本書はFX初心者向けの入門書で、FXの基礎知識やテクニカル・ファンダメンタル分析、資金管理についてわかりやすく解説しています。会話形式やイラストを多用し、外国為替の仕組みやFXのメリット・デメリット、注文方法、経済指標の読み方などを詳しく紹介。特に、リスク管理を重視し、安定した利益を得るためのテクニックや資金管理の重要性についても触れています。著者は金融業界での経験を活かし、初心者がつまずきやすいポイントを丁寧に説明しています。
この書籍は、夢を通じて「本当の自分」を探求する内容で、フロイトの理論を基にした新しい翻訳と解説が特徴です。無気力や孤独感など現代の悩みを解明し、夢の分析を通じて希望や欲求を理解する手助けをします。著者は精神科医の大平健で、フロイトの理論を深く掘り下げ、夢の役割や心理学的な側面を探る内容が展開されています。
今に生きる古典理論から現代に必要な知識・方法までをコンパクトに解説。異なるアプローチを比較しながら学べる新時代の入門書。 そのセラピーが基づいている理論とは?その理論はどのような人間観をもっているのか?今に生きる古典理論から現代に必要な知識・方法までをわかりやすくコンパクトにまとめた。異なるアプローチを比較しながら学べるつくりで,それぞれの特長と限界がわかる。 序 章 臨床心理学と社会 第Ⅰ部 臨床心理学の理論 第1章 臨床心理学とは何か─歴史とその広がり 第2章 心理的問題の理解と方法─心理アセスメント 第3章 精神力動アプローチ①─学問の発展とそれを支えた研究者たち 第4章 精神力動アプローチ②─臨床の実際 第5章 ヒューマニスティックアプローチ①─学問の発展とそれを支えた研究者たち 第6章 ヒューマニスティックアプローチ②─臨床の実際 第7章 認知行動アプローチ①─学問の発展とそれを支えた研究者たち 第8章 認知行動アプローチ②─臨床の実際 第9章 統合的アプローチ 第Ⅱ部 臨床心理学の実際 第10章 セラピーを行う─アプローチの比較 第11章 臨床心理学の研究─効果研究の変遷と発展 第12章 臨床家の訓練と成長
この書籍は、実践に役立つカウンセリング理論33種類を厳選し、そのエッセンスをわかりやすく解説しています。全体の見取り図や主要理論の比較表を掲載し、クライアントの状況に応じた理論の使い分けや統合方法を示しています。下巻では、精神力動論、認知行動論、システム論などの最新のアプローチを解説し、カウンセリングにおける統合的アプローチについても触れています。著者は臨床心理士であり、教育学の専門家です。
著者の河合隼雄は、無意識の世界について探求し、行動の背後にある無意識の働きを解明します。彼は、夢や症例を通じて、異性のイメージや心のエネルギーの退行、マザー・コンプレックスの影響を分析します。目次には、無意識へのアプローチ、イメージの世界、無意識の深層、異性像、自己実現の過程が含まれています。河合はユング派の心理療法家として、臨床心理学を専門とし、京都大学で教授を務めました。
最近「認知バイアス」という言葉が注目を集めています。認知バイアスとは,私たちの誰もがもつ「思考の偏り」や,「考え方のクセ」のことです。私たちの毎日の行動は,無意識のうちに認知バイアスの影響を受けています。 たとえば,限定品と書かれると,それまで欲しくなかった商品もつい買いたくなってしまいませんか? これは「希少性バイアス」という認知バイアスの一種です。また,災害で危険がせまっているのに「まだ大丈夫」と思いこんでしまうのも,「正常性バイアス」というものです。私たちは,さまざまな心のクセによって,合理的でない判断や行動をしているのです。 本書では,さまざまな認知バイアスについて,生徒と先生の対話を通してやさしく解説します。認知バイアスについて知れば,思いこみや偏見のない判断ができ,日々の生活や人間関係の役に立つにちがいありません! 認知バイアスの世界をお楽しみください! 1時間目:誰の心にもひそむ考え方のクセ STEP1. 知覚と認識のバイアス 認知バイアスって何? 脳がつくりだす「見えている」世界 人は「目の前の変化」を見落とす A型の人が几帳面に見えるのはなぜ? 単純なのにまちがえる「2-4-6課題」 占いの結果は誰にでもあてはまる? 「成功から学ぶ」だけでは見落としがある STEP2. さまざまな問題につながる認知のゆがみ 悪いことがおきた人は「悪い人」なのか 自分の不幸は「社会のせい」ではない? 他人の失敗は実力のせい? 人は無意識に自分を正当化する 慣習や知識が「ちがう使い方」を見えなくする 2時間目:思わぬ危機をまねく思いこみや先入観 STEP1. 悪い状況なのに変えたくない心理 「まだそれほど危険じゃない」には要注意 ! 損切りできない「サンクコスト効果」 失敗を恐れ挑戦を避ける「現状維持バイアス」 聞き方次第で答えが変わる「フレーミング効果」 STEP2. 想像以上に変化しやすい私たちの記憶 「後出し」で記憶を修正する 記憶は言葉一つで,簡単に変わってしまう 後からつくられる「過誤記憶」の恐ろしさ 人は「中断されたこと」をより覚えている 3時間目:知っておきたい判断と行動のバイアス STEP1. 言葉や情報に影響される「判断」 「○○について考えるな」と言われると……? 「協力」より「競争」と考えるのはなぜか レアものや限定品がほしくなるワケ 具体的な数字を示されると,それが基準になる STEP2. 「好き」と思う意外な理由 ドキドキするのは「つり橋が揺れる」から? 「何度も見る」と好きになるのはなぜ? 誤った情報でも,くりかえし接すると……? STEP3. 思いこみやイメージで変わる「行動」 人は「イメージ」で評価しがち 確率が低いのに「もっともらしい」ほうを選ぶ理由 期待されると,成績はほんとうに上がる? 手間ひまかけると「同じモノ」でも価値が上がる 偽薬でも症状が改善する「プラセボ効果」 4時間目:無意識が影響する集団と人間関係 STEP1. 正しいと思っているのは自分だけ? 認識をゆがめる「固定概念」 他人は思ったより「あなた」に興味がない? あなたの気持ち,意外と見抜かれていないかも 自分だけは「偏向報道」の影響を受けていない? 思いだしやすいものが「実際に多い」とは限らない STEP2. 要注意! 対人関係が悪化する論法 相手が攻撃しているのは「わら人形」かもしれない 人格攻撃にも利用される「お前だって論法」 同じことをいっているだけなのに,なぜか説得される 白か黒かだけではない「二分法の誤謬」 STEP3. 「集団」が生みだすさまざまな心理 自分が属さない集団の人は,みな同じに見える 自国チームの勝利は実力,相手チームの勝利は運? 他者の行動に合わせたくなるのはなぜか 集団の意見に合わせてしまう理由 少数でも「一貫した人」には合わせることがある STEP4. 集団ならではの「便乗」と「無責任」 勝ち馬に乗って,自分も勝者になりたい ! 権威のある人には無条件にしたがってしまう!? 人がたくさんいると「傍観者」になる? 集団だと極端な結論がみちびかれやすい なぜ誰も望んでいない旅行に出かけたのか 5時間目:数字にまつわる思いこみや勘ちがい STEP1. 直感とことなる「確率」や「統計」 5回連続で黒が出たら,次は赤の確率が高い? 選択を変えたほうが確率が上がる!? 「精度99%の検査で陽性」のほんとうの意味とは ビールが売れると水難事故が増える? 「全体」と「部分」でことなる結論になる
本書は、フロイトとユングという精神分析学の巨人たちの思想と生涯を、日本の第一人者である二人の孫弟子が対談形式で語る記念碑的な作品です。彼らは人間存在の深層を探究し、今なお多大な影響を与えています。内容は、出会いや個々の人間性、心の構造、夢の分析、文化と社会に関するテーマに分かれており、深層心理学の理解を深めるためのヒントが提供されています。
ヒトは未完成な状態として生まれ「学習」に依って「人」となる。このようにヒトが人となるために必要な学習機能についてまとめる。育児や保育ならびに学校での教育実践(教育領域),適応的行動の形成や不適応行動の改善(臨床領域),学習機能に障害を持つ人々のサポート(障害領域)に資する基礎的研究や実践的研究を解説。 ◆◆◆おもな目次◆◆◆ 第1章 学習心理学へのいざない 第2章 学習の基礎研究:動物を使って学習の仕組みを探る 第3章 記憶のプロセスの研究:知識獲得のメカニズム 第4章 メタ認知:知識による行動の制御 第5章 学習意欲の研究とその応用 ◎現場の声1 学ぶ意欲をはぐくむ学級経営と授業 ◎現場の声2 定時制高校ではぐくむ学ぶ意欲 第6章 心理臨床と学習心理学 ◎現場の声3 病気の子どもと家族を支える ◎現場の声4 産業領域に活きる学習心理学の理解 第7章 学習指導と学習心理学 ◎現場の声5 授業はカレー。理論がルウで,実践知が具。煮込むほど美味しくなる ◎現場の声6 小学校5年生,勉強に悩みはじめる ◎現場の声7 小学校3年生,算数の考え方を説明し,次に生かす 第8章 一人ひとりの特性に応じた指導と学習心理学 ◎現場の声8 通級指導教室での子どもに応じた指導 ◎現場の声9 「学習に困難」がある子どもたちがおかれている現状 ◆◆◆シリーズ心理学と仕事 全20巻 ラインナップ紹介◆◆◆ 1感覚・知覚心理学/2神経・生理心理学/3認知心理学/4学習心理学/ 5発達心理学/6高齢者心理学/7教育・学校心理学/8臨床心理学/ 9知能・性格心理学/10社会心理学/11産業・組織心理学/12健康心理学/ 13スポーツ心理学/14福祉心理学/15障害者心理学/16司法・犯罪心理学/ 17環境心理学/18交通心理学/19音響・音楽心理学/20ICT・情報行動心理学 心理学を活かした仕事を目指す高校生・大学生・社会人,そして, 進路指導や心理学教育に携わる教育関係者に向けて,多彩な心理学ワールドを紹介。 実際に働く人々の「現場の声」も交えながら,シリーズ総勢 300名以上の執筆陣が, 心理学の今を伝える。 心理学って面白そう! どんな仕事で活かされている? 国家資格として「公認心理師」が定められ, 心理学と仕事とのつながりに関心が高まる中,シリーズ[全20巻]刊行! 監修のことば はじめに 第1章 学習心理学へのいざない 1節 学習心理学とは 2節 学習心理学の展望と本書の構成 第2章 学習の基礎研究:動物を使って学習の仕組みを探る 1節 はじめに 2節 学習を効率的に行う訓練法(1):古典的条件づけ 3節 学習を効率的に行う訓練法(2):オペラント条件づけ 4節 条件づけでは説明のできない動物の行動変化 5節 最後に 第3章 記憶のプロセスの研究:知識獲得のメカニズム 1節 知識獲得(学習)のメカニズム 2節 知識の構造と記憶の区分 3節 記憶の過程 第4章 メタ認知:知識による行動の制御 1節 知識による行動の制御のメカニズム 2節 メタ認知の仕組み 3節 メタ認知の指導 第5章 学習意欲の研究とその応用 1節 学習意欲のとらえ方 2節 学習意欲の測定法:学習理由と有能感ではかる 3節 自律的な学習意欲の育て方 ◎現場の声1 学ぶ意欲をはぐくむ学級経営と授業 ◎現場の声2 定時制高校ではぐくむ学ぶ意欲 第6章 心理臨床と学習心理学 1節 心理臨床の実際 2節 心理臨床に生かす「学習心理学」の理論 3節 学習心理学に基づく認知行動療法の技法 4節 心理臨床における「学習心理学」のさらなる応用 ◎現場の声3 病気の子どもと家族を支える ◎現場の声4 産業領域に活きる学習心理学の理解 第7章 学習指導と学習心理学 1節 長期記憶にするための学習方法 2節 学ぶ-振り返る-生かす 3節 アクティブ・ラーニング 4節 学習の評価 ◎現場の声5 授業はカレー。理論がルウで,実践知が具。煮込むほど美味しくなる ◎現場の声6 小学校5年生,勉強に悩みはじめる ◎現場の声7 小学校3年生,算数の考え方を説明し,次に生かす 第8章 一人ひとりの特性に応じた指導と学習心理学 1節 学習障害とは 2節 学習障害と社会参加 3節 学びを保障する特別支援教育 4節 特別支援教育と学習心理学 ◎現場の声8 通級指導教室での子どもに応じた指導 ◎現場の声9 「学習に困難」がある子どもたちがおかれている現状 付録 さらに勉強するための推薦図書 文献 人名索引 事項索引
この本は、より良い人間関係を築くために「聞く」ことの重要性を説いています。聞き上手になるための具体的なテクニックや心構えを紹介しており、相づちの打ち方やタイミング、自分の話を控えることなどがポイントとして挙げられています。
本書は、著者が臨床心理学の学問性や科学性について考察しつつ、実際に悩む人々に役立つことを重視した実践的な論考をまとめたものです。臨床心理学は医療、教育、社会福祉など多様な分野に広がりを見せており、「臨床」という概念も拡大しています。この変化は、理論と実践の乖離を生む「科学」の思考法にも影響を与えています。
「発達障害」の問題圏 発達障害における「生」と「死」の問い 学校×発達障害×精神分析 ベルギーのラカン派による施設での臨床について ラカン派精神分析における自閉症論 言語に棲まうものと知 とぎれとぎれに結びつく 可能的なものの技法
2023年9月、FRBの利上げにより円安ドル高が進行中で、FXを始める絶好の機会です。本書は、FX初心者向けに口座開設から取引方法、売買タイミングまでを解説。マンガ形式で、主人公がFXのリスクや仕組みを学びながら“億り人”を目指します。内容は2020年の『マンガでわかる 最強のFX入門』の改訂版です。著者は経済書籍やビジネス関連の執筆経験を持つ安恒理と、4コマ漫画を手がける吉村佳です。
老舗洋菓子チェーンのエリアマネジャーに抜擢された28歳の前島由香里は、思うようにいかず悩んでいる。そんな彼女の前にアドラー心理学の幽霊が現れ、成長を促すアドバイスを提供する。同期や部下との交流を通じて、由香里は自己理解を深め、様々な人間関係を学びながら成長していく。著者はアドラー心理学を基にしたカウンセリングを行う岩井俊憲。
本書は、ジークムント・フロイトが1915年に執筆した「メタサイコロジー序説」の一部で、現存する5篇の論文と草稿1篇を収録しています。フロイトは精神分析の理論を構築するために、欲動、抑圧、無意識、夢などの概念を再考察しましたが、残りの論文は公表されず、幻の書となりました。今回の新訳は、フロイトの理論の出発点を理解するための重要な資料として、初めて一冊にまとめられたものです。
男性における対象選択の特殊な類型について 性愛生活が多くの人によって貶められることについて 処女性のタブー ある女性の同性愛の事例の心的な成因について エディプス・コンプレックスの崩壊 解剖学的な性差の心的な帰結 「文化的な」性道徳と現代人の神経質症
この書籍は、行動心理学を通じて人間関係、仕事、恋愛、消費者行動などの悩みや疑問を解明する内容です。目次には、行動から本音や性格を読み取る方法、仕事に役立つ行動、恋愛における心の操り方、世の中の仕組みを理解するための行動分析が含まれています。著者は齊藤勇で、心理学の専門家です。
この文章は、精神分析の知識の対話的発展について語る書籍の下巻の紹介です。フロイト以後の精神分析の進展を、対象関係論、自我心理学、クライン、ビオン、ラカンなどの理論を通じて論じ、臨床への示唆を提供しています。著者は、精神分析が人間の行動や感情の背後にある意味を探る重要な学問であることを強調し、専門的な理解を深めるための対話的なプロセスを描写しています。著者の藤山直樹は、精神分析の実践と訓練を重視し、知識の発展が人々の心に変化をもたらす可能性を示しています。
本書は、初版から改訂された環境心理学の教科書で、重要な研究成果を追加しています。地球環境問題や少子高齢化、コミュニティの崩壊などの社会問題に興味がある人に適しています。内容は、環境の知覚や評価、環境デザイン、個人差、社会環境、住環境、教育・労働環境、自然環境、犯罪と環境に関するものです。
本書は、良好な人間関係を築くための心理術を紹介し、相手の本音を見抜く方法や操るテクニック、苦手な人との対処法など、200以上の即効性の高い心理テクニックを収録しています。目次には、相手のホンネを見抜く方法、操る技術、好印象を与える術、感情のコントロール法、心理法則の事典が含まれています。
この書籍は、カウンセリングの実践と具体的な進め方を包括的に解説しています。初回の受付から終結までの流れや、各段階での技法の使い方を詳述しており、初心者にも理解しやすい内容です。著者は教育学の専門家であり、カウンセリングの基本や技法について幅広く学ぶことができる実用的なガイドです。
この書籍は、心理学の実験や理論を基に、日常の悩みを解決する方法を提供します。著者の植木理恵は、恋愛や人間関係、ストレス管理などの問題に対して、実践的な心理術を解説しています。具体的には、忘れたい思い出の克服法や、人間関係を改善するテクニック、他者の心理を理解しコントロールする方法などが紹介されています。心理学を活用して、より良い日常生活を送るためのヒントが詰まった内容です。
本格派サブカルチャー批評集の第1弾は『新世紀エヴァンゲリオン』。「謎解き」から遠く離れて、あの熱狂はなんだったのかを考える。そのほかの論考に「アライグマのオヤジについて」「美少女コミック研究序論」「マンガ表現の解体学」など。 1 『エヴァ』の遺せしもの (1)アニメよアニメ!おまえは誰だ!?──テレビ・アニメの終焉と『新世紀エヴァンゲリオン』 霜月たかなか (2)アニメーション構造分析方法論序説──『新世紀エヴァンゲリオン』の構造分析を例題として 高田明典 (3)究極の“ゲッターアニメ”としての『新世紀エヴァンゲリオン』 山田たどん (4)サブカルチャーと「天使の羽」──『エヴァ』・ウルトラマン・宮崎アニメをめぐって 【対談】切通理作+松井不二夫 (5)〈人類補完計画〉あるいは、生きのびるということについて 岡真理 (6)『新世紀エヴァンゲリオン』のバランスシート アライ=ヒロユキ (7)こんなきたないきれいな日には──不条理という救い 遠藤徹 (8)ぼくたちの『エヴァ』体験──同人サークル座談会2 P.C.C.ILLUSTRATED THEATER──巨神兵の再起動 高橋信雅3 (1)アライグマのオヤジについて──『ぼのぼの』を読む 澤野雅樹 (2)『装甲騎兵ボトムズ』雑感 稲葉振一郎 (3)美少女コミック研究序論 糸山敏和 (4)季刊『諷刺画研究』がめざすもの 清水勲4 (1)保本登の寓意の彼岸 第0回『グロリア』 保本登 (2)マンガ表現の解体学 1 ……マンガの時間 竹内オサム (3)仮面ライダーがエントツの上に立った日──ある監督の回想録 その1:ヨーイ、スタート 奥中惇夫 (4)ときわたけしの幻獣標本箱 第一夜:河童 ときわたけし執筆者紹介
この書籍は、音楽が私たちの行動や心理に与える影響をユーモアを交えて解説しています。例えば、特定のBGMが購買意欲を高めたり、音楽が不眠症に効果的であること、IQ向上の可能性などが取り上げられています。著者は物理学者であり音楽家のジョン・パウエルで、音楽の好みや感情との関係、映画音楽の効果などについても考察しています。音楽が私たちの生活に与える豊かな影響を探求する内容です。
この書籍は、子どもの育ちに関する問題—自己肯定感の低下やコミュニケーション不全、親の育児ストレスからくる虐待や育児放棄—を家族関係や親子の心理の変化を通じて分析し、親と子どもが共に成長できる社会の在り方を考察しています。目次では、育児不安、先回り育児、家族の変化、子どもが育つ条件、生涯発達の視点について論じています。著者は教育学博士の柏木惠子で、発達心理学と家族心理学を専門としています。
この書籍は、マンガと図解を用いてFX(外国為替取引)の基本をわかりやすく解説する内容です。目次には、FXの魅力、利益の得方、取引の準備、実際の売買、分析力の向上、失敗回避の方法が含まれています。著者は横尾寧子で、テクニカルアナリストとしての経験を持ち、投資に関する情報を広く発信しています。
FXの上達には「値動きとローソク足のチャート分析」をマスターすることが重要であり、テクニカル指標だけに頼るのは逆効果です。ローソク足を正しく読み取ることで相場の流れを把握し、勝ち組に乗ることで利益を得ることができます。また、レンジ相場を利用したエントリーやエグジットの方法も解説されており、シンプルで効果的な技術が強調されています。著者はFXの専門家として、実践的な知識を提供しています。
この書籍は、交通心理学に関するさまざまな研究やテーマを扱っており、全10章で構成されています。内容は、ドライバーの応答特性、交通事故の心理学、運転適性、交通教育、発達心理学、カウンセリング、コーチング、リスク心理学、社会心理学など多岐にわたります。著者は、早稲田大学名誉教授の石田敏郎と実践女子大学教授の松浦常夫です。
本書は、スポーツ心理学の新しい枠組みを提案し、運動心理学、臨床スポーツ心理学、健康スポーツ心理学、アダプテッドスポーツ心理学、研究法の5部構成で、心と体のつながりや選手の心理的課題、障害者のスポーツに焦点を当てて解説しています。著者は荒木雅信で、豊富な経験を持つスポーツ心理学の専門家です。
本書は、普通の臨床家向けの精神分析的臨床の入門書であり、現代の多様な臨床スタイルに対応するためのものです。精神分析の特徴である「見立て」と「他者の心を理解する」アプローチを日常の臨床に活かす方法を解説しています。目次には、対象関係論や心の動き、面接方針の決定などが含まれています。著者は愛知教育大学の教授で、臨床精神分析学を専門としています。
本書は、理不尽な状況や人間関係の悩みに直面したときに役立つ55章から成り、心の声に耳を傾けながらトラブルに立ち向かうための秘策を提供します。目次には、心の理解やコミュニケーション、国際性の重要性など、多様なテーマが取り上げられています。
理解を促し楽しく学べる工夫が満載。基礎から応用まで心理学の世界の考え方・理論のエッセンスをコンパクトに解説。 誰もがもつ素朴な疑問から読み進められる構成で,WHITEBOARDやPOINTツール等,読んで・見て・考えながら学べる工夫が満載。基礎~応用まで広い心理学の世界を概観でき,それぞれの考え方・理論のエッセンスがつまったコンパクトな入門テキスト。 序 章 心は目に見えない─計量心理学 第1部 さまざまな心のとらえ方 第1章 目は心の一部である─知覚心理学 第2章 心は見えないが行動は見える ─学習心理学 第3章 ヒトの心の特徴 ─進化心理学 第4章 心は脳のどこにあるのか ─神経心理学 第5章 それぞれの人にそれぞれの心 ─個人差心理学 第2部 さまざまな心のメカニズム 第6章 心は機械で置き換えられるのか ─認知心理学 第7章 ヒトは白紙で生まれてくるのか ─発達心理学 第8章 感情はどのような役割を果たしているのか─感情心理学 第9章 いい人? 悪い人?─社会心理学 第3部 心の問題のとらえ方 第10章 なんだかいやな気持ち─ストレスと心の病気 第11章 発達の偏りと多様性─発達障害 第12章 心の問題へのアプローチ ─アセスメントと支援
この書籍は、動物に心があるかどうか、またその心が人間とどのように異なるかを探求する動物心理学について紹介しています。各章では、進化、歴史、感覚、知覚、本能、学習、記憶、コミュニケーション、思考、自己、社会、発達、個体差、人間と動物の関係などのテーマが扱われています。著者は中島定彦氏で、関西学院大学の教授として動物心理学の研究に貢献しています。
本書は、スポーツ愛好家や指導者、親向けにスポーツ心理学の基礎を解説したテキストです。心理的側面がパフォーマンスに与える影響を3つの視点(心理学の理解、スポーツ行動の理解、社会的要因との関係)から説明し、重要なトピックを取り上げています。内容は、心理学概説、不安やストレス、動機づけ、運動技術の学習、運動嫌いとバーンアウト、ジェンダー、ライフスキルなど多岐にわたります。著者は日本女子体育大学の教授で、スポーツ行動に関する研究を行っています。
「意志の力」に関するベストセラーが文庫化され、目標を持つ人々に向けた内容です。著者ケリー・マクゴニガルは、意志力を磨くことで人生が変わると説き、潜在能力を引き出す方法や自制心の重要性について解説しています。心理学や神経科学の知見を基に、健康や幸福を高める実践的な戦略を提供しています。翻訳は神崎朗子が担当。
本書は「生理心理学」をテーマに、脳と心の関係を探求する内容です。神経科学的手法を用いて、脳の活動や精神機能の生物学的基礎を解明し、細胞や分子レベルのメカニズムを理解します。また、精神機能に関する研究法や最新のアプローチについても触れています。目次には、脳の構造、知覚、記憶、学習、情動、心の病、睡眠、コミュニケーション、遺伝子と行動、意識、脳の発達などが含まれています。著者は心理学の専門家で、これまで多くの学術的な経歴を持っています。
本書は、メンタリストDaiGoが提唱する「片づけによって人生を最大化し、幸福を手に入れる」ためのメソッドを紹介しています。部屋をきれいにすることが目的ではなく、片づけの技法を通じて時間やお金、体力を最大化し、人生を思い通りに操る方法を学ぶことができます。目次には、片づけの基本原則や心理的メリット、捨てるための質問、毎日の片づけ習慣、理想の部屋の作り方、時間管理テクニック、8週間プログラムが含まれています。
相場の傾向が線を引くだけで先読みできる!上昇相場でも下降相場でも確実に儲かるチャート分析テクニック。デイトレ、スキャルピング、スイング、中・長期あらゆるトレードで効果絶大。 1 トレンドライン・トレードを始めよう 2 トレンドラインの引き方をマスターしよう 3 トレンドラインでトレードタイミングを見極める 4 トレンドライン・トレードの基礎力をつける20問 5 トレンドライン・トレードの勝率を上げる20問 6 トレンドラインでリスクを見極める10問
近年の犯罪心理学は、精神分析などの実証性に欠ける方法を排除し、科学的手法やビッグデータを用いたメタ分析を進めてきた。本書では、日本であまり紹介されてこなかった新しい犯罪心理学の成果をまとめ、著者の経験をもとに殺人や薬物犯罪などのメカニズムを解説する。目次には、犯罪の現状や犯罪者の評価・治療、エビデンスに基づく対策が含まれている。著者は犯罪心理学や認知行動療法の専門家である。
本書は、ビギナー向けのチャート分析テクニックを解説したもので、67の練習問題と詳細な解説が含まれています。内容は、チャートの基礎知識、パターンの理解、利益を確保するための基本原則、分析力を養う練習問題、売買の勘を磨く問題、移動平均線の理解に関する問題で構成されています。著者は、為替トレーダーの今井雅人氏で、行動心理学とテクニカル分析を駆使し、常勝トレーダーとして知られています。
この書籍は、非言語コミュニケーションの重要性を探求し、見た目や仕草、色、匂いなどの要素が人間関係や信頼にどのように影響するかを考察しています。著者は、心理学や社会学、マンガ、演劇など多様な知識を用い、特に女性の嘘を見破りにくい理由についても触れています。目次には、見た目の判断や仕草の法則、コミュニケーションの距離感などのテーマが含まれています。著者は竹内一郎で、さまざまな賞を受賞した経歴があります。
『使える行動分析学: じぶん実験のすすめ』は、日常生活や仕事における行動改善のヒントを、行動分析学の視点から提供する書籍です。自分自身の行動を分析し、実験的に改善する方法が具体例と共に紹介されており、実践的かつ身近な内容となっています。特に、行動変容を促すためのステップが分かりやすく解説されており、読者が日常生活にすぐに応用できる点が魅力です。科学的根拠に基づいたアプローチで、自己成長を目指す人に最適な一冊です。
この書籍は福祉心理学に関する内容を扱っており、乳幼児期から老年期までの各発達段階における心理的課題を探求しています。各部は、親性の形成や児童虐待、いじめ、不登校、発達障害、高学歴化社会、障害者へのヘイトクライム、老いの理解など、多岐にわたるテーマを含んでいます。最終的にはレジリエンスとウェルビーイングについてまとめられています。著者は中山哲志教授をはじめ、各分野の専門家たちです。
心と体の生涯発達への心理学的アプローチの方法から,乳幼児期の認知・自己・感情・言語・社会性・人間関係の発達の詳細,学童期〜高齢期の発達の概要,発達障害への対応まで,子どもにかかわるすべての人に必要な発達心理学の基礎が身に付くようガイドする.幼稚園教諭・保育士養成課程にも対応. はじめに(開) I 発達のとらえ方 1 発達心理学とは(齋藤) 2 遺伝と環境(佐々木掌子) 3 生涯発達の視点(齋藤) II 乳幼児期の発達をくわしく知る 4 胎児期・周産期(新屋裕太・今福理博) 5 感覚・運動の発達(伊村知子・白井 述・島谷康司) 6 愛着の発達(蒲谷槙介) 7 自己と感情の発達(森口佑介) 8 認知の発達(旦 直子) 9 言語の発達(小林哲生) 10 社会性・道徳性の発達(奥村優子・鹿子木康弘) 11 遊び・仲間関係(野嵜茉莉) III 発達を支える 12 学習の理論(後藤和宏) 13 障害と支援(浅田晃佑) 14 心と行動の問題および児童虐待(出野美那子) IV 学童期以降の発達を概観する 15 学童期〜青年期(林 創・松島公望) 16 成人期〜老年期(久保南海子) コラム1 女に育てたから女になるのか? コラム2 虐待の要因を探る サルの里子実験 コラム3 早産児の認知発達 コラム4 妊娠中の母親の食事と胎児の味覚的嗜好 コラム5 風船を持たせることによる乳幼児の歩行支援 コラム6 各愛着タイプのその後 コラム7 空想の友達 コラム8 赤ちゃんも計算ができる? コラム9 統語的手がかりを用いた動詞学習 コラム10 ヒトの視線のパワー コラム11 乳幼児の道徳性の発達 コラム12 きょうだい関係の役割 コラム13 生活習慣の獲得 コラム14 神経多様性 コラム15 遊びに現れる子どもの心 コラム16 子どもの嘘への対応 コラム17 日本人の宗教性とアイデンティティ コラム18 サルのサクセスフルエイジング? おばあちゃんザルの知恵 Introduction to Development Psychology Kazuo HIRAKI and Atsuko SAITO, Editors
心理学の定番入門書がそのままのコンパクトさで生まれ変わりました。「心理学の仕事」「研究法」「研究倫理」などのトピックが加わりいっそう社会に生きる心理学を感じられる内容に。ブックガイドも充実した心理学の必携書。公認心理師を目指す方にも。 序 章 心理学ってなんだ?──心理学の仕事とテーマ 第Ⅰ部 身近に感じる心理学 第1章 心理に関する支援を行う──臨床心理学 第2章 性格は変えられるか──性格と個人差の心理学 第Ⅱ部 心理学で日常生活を読み解く 第3章 身近な人や社会との関係──社会的行動の心理学 第4章 人が生まれてから死ぬまで──発達心理学 第5章 心を測る──心理学的アセスメント 第Ⅲ部 心理学のコアな原理 第6章 世界をどうとらえるか──知覚・認知・記憶の心理学 第7章 あなたはなぜそのように行動するのか──行動と学習の心理学 第Ⅳ部 心理学の歴史と方法 第8章 心はどう探究されてきたか──心理学の歴史 第9章 データから心を探る──心理学の研究法
読むとはこと。書くとはこと。認知心理学の知見を解きほぐして、文章と心の関係に迫る。 文章を読み書きする時,頭の中では何がおこっているのか。読む・書く時の心のしくみについて知り,どうやって読む・書く力をつけたらよいのかを考える。従来のハウツー本とは違い,読み書きの知識が自然に身につけられる。 読むとはこと。書くとはこと。 認知心理学の知見を解きほぐして、文章と心の関係に迫る。 題名をみて「国語の参考書か入試攻略本かな」と思う人がいるかもしれない。本書は,文章を読んだり書いたりする時に,頭の中で何がおこっているのか,読む・書く時の心のしくみについて知ってもらうための本である。この本を読むことで読む時書く時に,自分の心を見つめるまなざしが変わってくるはずだ。 序章 読者のみなさんに伝えたいこと 「読むこと」「書くこと」のしくみを理解し読み書きの楽しさを知ろう ・今からでも遅くない読解力と作文力アップ ・しくみをわかる ・心の中に辞書がある ・読むことは対面交通 ・この本の構成 1章 読むことはつなぐこと 1 文から文章へとつなぐ ・分けるとつなぐ ・読みは組み立て作業か? 2 文を読むためのルール ・知識が決め手 ・読んだことを活用する ・推測のルールみつけ ・ルールで学ぶ単語と漢字 3 文をつなぐ推論をしよう ・さまざまな橋渡し ・つなぐことのむずかしさ 4 埋め込まれた手がかりに注意しよう ・シグナルとしての接続詞 ・挿し絵や図のはたらき 5 文章構造の知識を使う ・予想を導く ・まとまりを与える 6 読むことのコツ ・読みの方略 ・要約の作り方 2章 理解を確かめる 1 自分の理解を評価する ・理解をチェック ・評価の観点 ・わかったつもりが邪魔をする 2 批判的読みをマスターする ・疑う者は救われる ・批判的読みを助けるモデル ・別の視点がないかを考えよう ・手がかりの言葉に目をつける ・多様な解釈にも正誤がある 3章 書くことは気づくこと 1 作文の過程とは ・書くという問題解決 ・書く過程を解剖する ・行ったり来たりの過程 2 プラニングのコツ ・プラニングのスタイル ・書き出しで悩まない ・道具の活用 ・具体的な表現選び 3 推敲は診断 ・推敲の達人 ・ズレを感じたら原因を診断しよう ・人にうまく頼る 終章 「読み方上手」「書き方上手」になろう ・この本を読み終えるにあたって ・「苦手よ,さらば」 ・3つの「変える」
この文章は、マズローの名著を紹介しており、人間の変化可能性や健全な人間のあり方を探求する重要性を強調しています。内容は、心理学的アプローチ、動機づけ理論、基本的欲求、自己実現、心理療法など多岐にわたります。全体的かつ力動的な視点から、人間の心理と健康について考察しています。
このテキストは、言語心理学の知見を基に「言語力を育てる」方法を心理学的観点から紹介する参考書です。内容は、言語力の定義や発達、教育現場や医療での育成方法、文章の読み書きに関する心理学的アプローチ、発達性読み書き障がいとその支援について構成されています。著者は福田由紀で、法政大学の教授です。
第一人者が実践してきたセルフケアをまとめて公開。『セルフケアの道具箱』と一緒に読みたい、みんなのカウンセリング副読本。 実はカウンセラーもこんな心の問題を抱えている!第一人者が実践してきた「自分で自分をケアする方法」をまとめて公開。『セルフケアの道具箱』と一緒に読みたい、みんなのカウンセリング副読本。ロングセラー『セルフケアの道具箱』の著者が、自ら実践しているセルフケアをまとめて大公開。カウンセラーを目指した経緯、さまざまな心理療法との出会いから、自らの不調・不安(多動、ギャンブル依存、喫煙癖、共依存の母親との関係etc…)に対して実践してきたコーピングまで、実体験に基づくセルフケアメソッドを惜しげもなく披露。『セルフケアの道具箱』と一緒に読みたい、みんなのカウンセリング副読本。イラスト・細川貂々。《スキーマ療法では、過去のトラウマや今抱えている生きづらさ、その人の人生そのものについて語り合うことが多く、そういうとき、「先生(伊藤)のトラウマや生きづらさや人生についても知りたい」と思うクライアントが少なくないようで、問われれば、率直にお伝えするようにしています。そのような私自身の自己開示によって、クライアントとの相互理解が進んだり、クライアント自身の自己理解が深まったりすることが少なくありません。読者が「まだ出会わぬクライアント」だとしたら、それらの方々に、私自身の実践や体験についてお伝えすることに、なにがしかの意味があるのではないか、と思うようになったのでした。》(「はじめに」より)【本書の内容より】●自動思考に対するマインドフルネスについての話……空に浮かぶ雲に自動思考をタイピング/シャボン玉かタンポポの綿毛をフーっと吹く/うんこのイメージ●マインドフルネスの普段使いについての話……食べる/触る/においを嗅ぐ/歩く/家事/●呼吸に親しみ、呼吸と仲良くすることについての話……待ち時間呼吸法/アロマ呼吸法/リフレッシュ呼吸法/●「思い直し」の技術である認知再構成法についての話……「自動思考」と「助ける思考」を対話させる/つらい感情を受容し、ひたすら優しい言葉をかけ続ける/イメージのなかで納得のいくストーリーを作る/●問題解決法という最強の対処法……翌朝の早起きが嫌で仕方がないときの問題解決/トイレ掃除をこまめにするための問題解決/難しい専門書を読み進めるための問題解決/痴漢撃退のための問題解決/母の入院先を見つけるときの問題解決/●衝動的かつアディクション的な特性でいろいろやばかった話……ゲーム/競馬とカジノ/万引きで捕まっちゃった!/●両親に巻き込まれ続けてきた話/●私が実践しているスキーマ療法……早期不適応的スキーマを手放す/チャイルドモードへのアクセスとケア/etc… 第1章 こうしてカウンセラーになりました 「どうしてカウンセラーになったのか」の話 その1 「どうしてカウンセラーになったのか」の話 その2 認知行動療法との出会いとその後についての話 その1 認知行動療法との出会いとその後についての話 その2 認知行動療法との出会いとその後についての話 その3 スキーマ療法との出会いとその後についての話 その1 スキーマ療法との出会いとその後についての話 その2 第2章 困ったときのマインドフルネス マインドフルネスとの出会いとその後についての話 自動思考とのつきあい方についての話 自動思考に対するマインドフルネスについての話 マインドフルネスの普段使いについての話 その1 マインドフルネスの普段使いについての話 その2 ネガティブな刺激に対するマインドフルネスについての話 呼吸に親しみ、呼吸と仲良くすることについての話 第3章 いまもこうして生きてます 「思い直し」の技術である認知再構成法についての話 問題解決法という最強の対処法についての話 エクスポージャー(曝露療法)をいろいろ試しちゃった話 試行錯誤しながら禁煙をなんとか続けているという話 衝動的かつアディクション的な特性があり、いろいろやばかった話 両親に巻き込まれ続けてきた話 私が実践しているスキーマ療法についての話
この書籍は、効果的な勉強法を探るためのガイドであり、心理学の視点から学習の問題点を分析しています。内容は以下の5章で構成されています。 1. **学習観の見直し**:勉強法の問題点や学習観を検討し、学問には王道がないことを示唆。 2. **記憶する**:英単語の学習法や記憶理論を紹介し、記憶のモデルを考察。 3. **理解する**:用語や図、文章の理解の仕方について解説し、知識と推論の重要性を強調。 4. **問題を解く**:問題解決の心構えや数学における暗記の誤解を解消し、広い意味での問題解決を考察。 5. **文章を書く**:小論文の書き方や文章作成のプロセスについて具体的なアドバイスを提供。 著者は東京大学の教授で、学習や理解に関する研究を行っています。全体を通じて、自己に合った効果的な学習法を見つけるための具体的なアドバイスが展開されています。
大学で心理学を学ぶということ 心理の仕事 社会人入学を考えているあなたへ 心理学って何だろう? 心理学者ってどんな人? 心理学は科学なの,哲学なの,医学なの? 心理学を学ぶとどうなるの? 心理学を学ぶにはどうしたらいいの Webで学ぶ心理学 本で学ぶ心理学:どんな本を読めばよいのだろう?
人間はどのように世界を認識しているか? 「情報」という共通言語のもとに研究を進める認知科学が明らかにしてきた,知性の意外なまでの脆さ・儚さと,それを補って余りある環境との相互作用を,記憶・思考を中心に身近なテーマからわかりやすく紹介. 【円城塔氏(作家)推薦の辞】 「この本を読むと,人間は自分で思っているよりも,いい加減なものだとわかる.いい加減な人が読むべきなのはもちろんだが,自分はしっかりしていると思っている人こそ,読むべきである.」 【長谷川寿一氏(東京大学教授)】 「知性とは何か? この問いに挑む認知科学は諸科学が交わるホットスポットだ. 東大駒場の名物講義を是非あなたにも.」 第1章 認知的に人を見る 認知科学とは 知的システム しくみ、はたらき、なりたち 学際科学としての認知科学 情報——分野をつなぐもの 生物学的シフト 認知科学を取り巻く常識? 第2章 認知科学のフレームワーク 表象と計算という考え方 さまざまな表象 知識の表象のしかた 認知プロセスにおける表象の役割 第3章 記憶のベーシックス 記憶の流れ 記憶と意図 一瞬だけの記憶——感覚記憶 人の記憶はRAMか——短期記憶とチャンク ワーキングメモリ——保持と処理のための記憶 知識のありか——長期記憶 情報を加工する——短期記憶から長期記憶へ 思い出しやすさ——符号化特定性原理 思い出していないのに思い出す——潜在記憶とプライミング まとめ 第4章 生み出す知性——表象とその生成 はかない知覚表象 言葉と表象 作り出される記憶 記憶の書き換え 仮想的な知識——アナロジー まとめ——表象とは何なのか 第5章 思考のベーシックス 新たな情報を生み出す——推論 目標を達成する——問題解決 選ぶ——意思決定 人間の思考のクセ まとめ 第6章 ゆらぎつつ進化する知性 四枚カード問題、アゲイン データに基づき考える 思考の発達におけるゆらぎ ひらめきはいつ訪れるのか まとめ——多様なリソースのゆらぎと思考の変化 第7章 知性の姿のこれから 表象の生成性 身体化されたプロセスとしての表象 世界への表象の投射 思考のゆらぎと冗長性 世界というリソース おわりに 引用文献 索引
この書籍は「社会心理学」をテーマに、個人と社会との関係をわかりやすく解説しています。協力や競争、攻撃、援助といった行動がどのように集団や組織に影響されるかを、図解やイラストを用いて紹介。具体的なテーマとして、社会現象、組織の心理、職場での心理、対人認知、社会のあり方などが取り上げられています。著者は東京大学の亀田達也教授で、心理学の実験結果も交えながら、日常生活における心理の働きを探求しています。
本書は、プライスアクション(値動き)の基本を解説し、必勝の売買ポイント「秘伝の18シグナル」を紹介しています。プライスアクションは、多くの投資家が注目するため当たりやすいとされ、著者はこの手法を用いて具体的なチャートパターンを示します。また、トレンド系指標「GMMA」との組み合わせによる実戦売買手法も解説されており、個人投資家が利益を上げるための確かな方法を提供しています。著者は経験豊富なトレーダーであり、投資家育成に注力しています。
この書籍は、元FBI捜査官のジョー・ナヴァロが、しぐさを通じて他人の感情や真意を読み取る方法を解説しています。言葉ではなくボディー・ランゲージに注目し、自信や不安を示すしぐさを見分けることで人間関係を円滑にするための知識を提供します。著者はFBIでの経験を基に、しぐさの意味やウソを見抜く技術について詳しく説明しています。
本書は、人と人とのコミュニケーションの難しさを解説し、ビジネスシーンで役立つ心理テクニックを紹介する古典的名著の文庫版です。内容は、相手の注意を引く方法やストレートに伝える技術、頑固な相手を説得する方法、感情の扱い方など、多岐にわたるコミュニケーションスキルを網羅しています。著者はアメリカの産業心理学者で、翻訳は小川敏子が担当しています。
この書籍は、社会で騙されないための自己防衛の方法を解説した社会心理学の名著です。著者ロバート・B・チャルディーニは、影響力のメカニズムを8つの章に分けて説明し、具体的な戦略や心理的原理をユーモラスに描いています。新訳版では、マンガや事例が追加され、現代の広告戦略や社会問題についても触れられています。読者は、プロの手口を理解し、賢い消費者になるための知識を得ることができます。
人間関係の悩みが尽きない社会において、思考が動く考えられる本となっていました。 自分自身の行動を社会に当てはめ参考にしていけるので自分にとってポジティブな内容でした
ページ数が多く読み切るには根気がいるが、中身は目から鱗の内容ばかり。知っておくだけど対人関係が有利に働く法則などが多く学べる。
本書は、カウンセリング技術を向上させたい人のための実践的な指南書です。著者は、関係構築や傾聴、問題解決における壁を乗り越える方法を提案しています。脳機能を「ウマの脳」「ワニの脳」「サルの脳」といったユニークな名称で解説し、クライエントの心の状態とカウンセラーの思い込みの違いを図版で示します。7つの課題をクリアすることで、カウンセリングプロセスを自然に習得できる構成になっています。各章では、関係構築や傾聴、脳科学、問題解決などの壁を具体的に解説し、実践的なアプローチを提供しています。
「トモダチ」は、人生を充実させるために必要なのは多くの友人ではなく「30人とのつながり」であると提唱する書籍です。著者メンタリストDaiGoは、人間関係の重要性や選び方について科学的視点から解説し、メンタルの作り方ややっかいな関係の処理方法を示します。特別付録として、幸福な人間関係を築くための8週間のワークも提供されています。
この文章は、音楽心理学に関する内容を紹介しており、音楽の知覚、認知、記憶、感情、社会心理学、音楽療法など、さまざまな側面を扱っています。また、著者の星野悦子は音楽と心理学の専門家で、現在上野学園大学で教授を務めています。
この入門書は、文系学生向けに心理学における統計の重要性と基本的手法を分かりやすく解説しています。内容は、統計の基礎から始まり、実践的な手法を学び、さらに深い理解へと進む3つのステップで構成されています。著者たちは心理学や神経科学の専門家であり、学生の視点を考慮した親切な学習ガイドです。
この書籍は、誕生から老年期に至るまでの人間の発達を、身体、感情、自己意識、人間関係、知能などの観点からビジュアルに解説しています。発達障害などの重要なテーマも取り上げており、すこやかな成長に必要な最新情報を提供しています。著者は、臨床心理士であり、教育や心理学の専門家としての経歴を持つ林洋一氏です。
この書籍は、消費者が思わず購入したくなる「売れる」インターフェイスデザインの心理的要素を解説しています。具体的には、「ストループ効果」や「ゲシュタルトの法則」などの心理学的概念を取り上げ、それらがマーケティングやデザインにどのように応用されるかを実践的に説明しています。著者の中村和正は、UXコンサルタントとして多くのプロジェクトに関わってきた経験を基に、心理学を考慮したユーザーインターフェイスやマーケティング手法を紹介しています。
この書籍は、現役の臨床心理士11人が自身の仕事について語り、心理のプロを目指す人々へのガイドとなる内容です。「公認心理師」という新しい国家資格も紹介されており、臨床心理士の役割や専門性、活躍の場について詳しく解説されています。また、臨床心理士になるための道筋や試験情報も提供されています。著者には、臨床心理士としての実績を持つ専門家が含まれています。
「精神分析」に関するよくある質問
Q. 「精神分析」の本を選ぶポイントは?
A. 「精神分析」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「精神分析」本は?
A. 当サイトのランキングでは『精神分析入門(上) (新潮文庫)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで173冊の中から厳選しています。
Q. 「精神分析」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「精神分析」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。































































































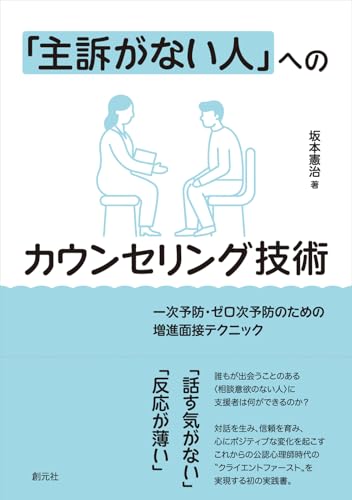

















![『イラストレート心理学入門 [第3版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41QQ2f0S-vL._SL500_.jpg)






![『よくわかる臨床心理学[改訂新版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41+q7jTug-L._SL500_.jpg)


























![『影響力の武器[第三版]: なぜ、人は動かされるのか』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Lm3fofgOL._SL500_.jpg)
























![『[買わせる]の心理学 消費者の心を動かすデザインの技法61』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51V0xquW8uL._SL500_.jpg)












