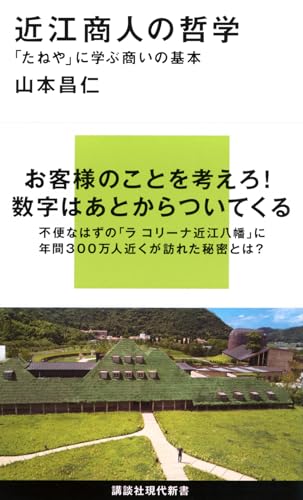【2026年】「日本古代史」のおすすめ 本 131選!人気ランキング
- 古代史講義 (ちくま新書)
- 金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】 原始・古代史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業)
- 早わかり日本史
- 「日本の伝統」の正体
- 飛鳥の都〈シリーズ 日本古代史 3〉 (岩波新書)
- 日本の歴史をよみなおす (全)
- 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
- 新 日本古代史
- はじめての日本古代史 (ちくまプリマー新書)
- ロマンで古代史は読み解けない: 科学者が結ぶ、地図と陰陽
古代史研究の最新成果と動向を一般読者にわかりやすく伝えるべく専門家15人の知を結集。平安時代までの全史が1冊でわかる入門書。 古代史研究の最新成果と動向を一般読者にわかりやすく伝えるべく 15人の専門家の知を結集。 列島史の全体像が1冊でつかめる最良の入門書。参考文献ガイドも充実。 1 邪馬台国から古墳の時代へ 吉松大志 2 倭の大王と地方豪族 須原祥二 3 蘇我氏とヤマト王権 鈴木正信 4 飛鳥・藤原の時代と東アジア 中村順昭 5 平城京の実像 馬場基 6 奈良時代の争乱 佐々田悠 7 地方官衙と地方豪族 佐藤信 8 遣唐使と天平文化 飯田剛彦 9 平安遷都と対蝦夷戦争 吉野武 10 平安京の成熟と都市王権の展開 仁藤智子 11 摂関政治の実像 榎本淳一 12 国風文化と唐物の世界 河内春人 13 受領と地方社会 三谷芳幸 14 平将門・藤原純友の乱の再検討 宮瀧交二 15 平泉と奥州藤原氏 大平聡
この書籍は、日本の歴史を図解でわかりやすく解説しており、さまざまな事件やエピソードを通じて楽しむことができます。内容は、縄文時代から弥生時代の日本文化の起源、律令国家の成立、大和政権、武士の時代、戦国時代を経て江戸幕府の成立、そして明治維新から太平洋戦争に至るまでの近代化の過程を扱っています。著者の河合敦は、難解な日本史を易しく解説することを目指しています。
この書籍は、日本の伝統がどのように形成され、私たちがそれをどのように受け入れてきたかを探る内容です。初詣や神前結婚式などの具体例を通じて、「伝統リテラシー」を身につけることを目的としています。目次には、季節や家庭における伝統、地域の特徴、神社仏閣や祭り、外国の影響などが取り上げられています。著者は藤井青銅で、作家や脚本家として活動しています。
著者の網野善彦は、日本中世の歴史を再評価し、農業中心社会のイメージや商工業者、芸能民の賤視について考察しています。文明史的大転換期における貨幣経済、階級差別、権力、信仰、女性の地位、多様な民族社会の実態を明らかにし、均質な日本社会像に疑問を呈しています。書籍は続編と共に文庫化され、歴史の多様な側面を平易に語ります。
この書籍は、日本の歴史を年号や年代を使わず、政権担当者を主役に据えて一つのストーリーとして解説しています。高校の日本史の知識を深めることができる内容で、目次には縄文時代から戦後までの各時代が含まれています。著者は福岡県立高校の教諭、山崎圭一です。
日本が誕生する瞬間を体感せよ! 「農耕のはじまり」から「武士の台頭」までを一気に駆け抜ける。すべての日本人必読の一冊。 日本が誕生する瞬間を体感せよ! 「農耕のはじまり」「律令国家の形成」から「院政の開始」「武士の台頭」までを一気に駆け抜ける。すべての日本人必読の一冊。 日本が誕生する瞬間を体感せよ! 「農耕のはじまり」「律令国家の形成」から「院政の開始」「武士の台頭」までを一気に駆け抜ける。すべての日本人必読の一冊。
妄想やスピリチュアルで古代史は分からない! 古代史にロマンを求めるあまり、思い込みや妄想で 都合良く解釈してもよいのだろうか? 愛知県岡崎市にある自然科学研究機構の研究者の二人が、 目に見える地図という“証拠”から何がわかるか 本書で挑戦してみた! 現存している建造物や地名などの 現存する動かしがたい「モノ」と、 時代を越えても変わることのない「ヒト」の心、 そして「科学」そのものの歴史、 という三つの軸で以下に取り上げる古代史に迫ります。 【取り上げる内容】 ○鏡の旅 ○陰陽寮 ○内宮と外宮 ○暦の歴史 ○暦の神ツクヨミ ○国津神と天津神 ○熊野大社の亀太夫神事 ○紀伊熊野の陰陽世界 ○修験道と忍者 ○諏訪大社 ○みすずかる信濃 ○上賀茂神社と下鴨神社 ○浄瑠璃姫の謎 ○北野廃寺と真福寺 ○岡崎最古の宮・菅生神社 ○岡崎の六並び 地図・図表多数掲載!
本書『歴史とは何か』は、E.H.カーによる歴史学の入門講義を基にしたもので、歴史の理解には現在と過去の対話が不可欠であると説いています。内容は「歴史家とその事実」や「社会と個人」などの重要テーマを扱い、カーの未完の第2版に向けた序文や自叙伝、解説が追加されています。新訳により、知的刺激とユーモアに満ちた名講義が再現されており、歴史学の古典として広く評価されています。
この書籍は縄文人の生活や文化についての詳細を紹介しています。内容は以下の4章に分かれています。 1. **縄文人のすがたと暮らし** - 縄文人の日常生活、服装、髪型など。 2. **縄文人の一生** - ライフステージや祭り、成人式について。 3. **縄文人と食** - 食料調達、食文化、旬に関する知識。 4. **縄文の祈り** - 祈りの形、ストーンサークルや土偶の役割。 著者は縄文時代の魅力を広める活動を行っている研究者たちです。
この書籍は、最新の発掘調査や科学的アプローチを用いて「日本」の誕生を探求する内容です。卑弥呼や倭の五王、空白の四世紀などのテーマを通じて、古代日本の歴史と東アジアの情勢を描写しています。各章では、邪馬台国や漢王朝の崩壊、卑弥呼の戦略や歴史的な断絶について詳しく分析し、視覚的な資料も豊富に提供されています。
シリーズ累計45万部突破!ベストセラー「嘘だらけシリーズ」の最新作は、日本の神話から平安時代までの嘘を暴く!\教科書に騙されている大嘘/◉最初の女性天皇は推古天皇◉魏志倭人伝は真実だ◉聖徳太子はいなかった◉大化の改新はなかった◉聖武天皇は偉人◉古代史の中心は藤原氏◉習字だけ上手な嵯峨天皇現代の皇位継承問題を考える上でも重要な古代史ですが、数多くの史料が残る近代史と比べ、古代史はほとんどありません。しかし、古代史は決してSFではないのです。都合がいいところだけを切り取り、皇位継承問題を混乱させては本末転倒です。本書が「天皇、皇室、皇位継承とは一体何か?」を考える礎となれば幸いです。【構成】序章 古代史を学ぶ基本スキーム第一章 これくらい知っておきたい日本神話第二章 伝説~神武天皇から守られてきた掟~第三章 掟となる先例を蓄積していく時代第四章 皇族が多すぎて争いが絶えなかった大和時代第五章 先例破りが横行した奈良時代終章 古代を終わらせた平安時代
この書籍は、日本の歴史を原始・古代から現代まで幅広く扱い、各時代の重要な出来事や人物を通じて日本の成り立ちや変遷を解説しています。著者はカリスマ講師として知られ、予備校での授業が大変人気です。内容は、古墳の役割や明治維新の成功要因、関東大震災の影響など、多様な視点から日本の歴史を考察しています。著者は東京大学卒業の歴史専門家で、講師経験が豊富です。
ゲノム解析などの最新のバイオサイエンスと天文学により、縄文、弥生、邪馬台国、日本書紀、万世一系など古代史の真実に迫る! 古代史は文献資料が限られるため、ゲノム解析などの最新のバイオサイエンス、ハイテクノロジーが活躍し、近年ではゲノム解析から縄文人や弥生人の非常に精巧な復顔像が作られ話題になるなど、理系に近い学問になってきていま… 最新のゲノム、AI解析により古代史研究に革命が起こる! 骨格や遺伝子を解析、縄文人、弥生人の容貌が明らかに! 韓国の遺跡で数多くの弥生人遺伝子を発見! 日本人が住んでいた! 邪馬台国は九州北部! 卑弥呼の正体も判明! 日本書紀と天皇家万世一系の謎を解く! 最新テクノロジーで常識(定説)が次々と覆る! 古代史は文献資料が限られるため、ゲノム解析などの最新バイオサイエンス、ハイテクノロジーが活躍し、近年ではその結果を参考に縄文人や弥生人の非常に精巧な復顔像が作られ話題になるなど、理系の学問に近づいています。 本書では、縄文、弥生、邪馬台国、日本書紀、万世一系などの古代史について、最新の研究結果を紹介し、従来の定説を検証します。 併せて、ゲノム解析にAIを活用した著者の英語論文を巻末に収録しました。 まえがき 序章 はじめに 大学での恩師の言葉 井沢元彦氏『逆説の日本史』の衝撃 巨大化するバイオサイエンスの影響 科学的論争の実情 古代史論争の難しさ 序章のまとめ 第一章 縄文人のサイエンス 3800年前の縄文人のDNA 朝鮮半島には縄文人が住んでいた 伽耶には弥生人が住んでいたのか 伽耶にはやっぱり弥生人が住んでいた なぜ朝鮮半島に縄文人が住んでいたのか 白村江敗戦後の朝鮮半島 2020年以降の研究 【コラム】日本人の血液型にA型が多い理由 第一章のまとめ 第二章 弥生人のサイエンス 弥生時代が500年早まった イネが運ばれたルートは 稲作の伝来は何回あったのか 中国の古代稲作との関係 【コラム】『交雑する人類』の感想 第二章のまとめ 第三章 邪馬台国のサイエンス 邪馬台国は北部九州にあった 卑弥呼は天照大神なのか 九州説の問題点 神武東征の出発地はどこか 現代に置き換えて考える 天の岩戸の日食はあったのか 卑弥呼が死亡した理由 日食は何回あったのか 【コラム】対馬海峡を往復した船 第三章のまとめ 第四章 日本書紀のサイエンス 日本書紀の謎の解読ことはじめ 奇想天外な仮説を思いつく 魏志倭人伝の記述を検討する 魏志倭人伝を隋書倭国伝と対比する 投馬国や邪馬台国にはどう行けばよいのか 邪馬台国の遺跡は発見できるのか 仮説の検証結果 日本書紀の編集方針の謎 日本書紀を読む場合の注意点 天武天皇の要望とは なぜ卑弥呼が登場しないのか 2倍年を使わざるをえない理由 倭王武の上表文の内容 神武東征はいつなのか 古事記も必要な理由 【コラム】なぜ朝貢をやめたのか 第四章のまとめ 終章 万世一系のサイエンス 万世一系は本当なのか 万世一系の定義を拡張する なぜ宇佐神宮を創建したのか 天皇の漢風諡号で「神」の意味は 男系の継承は何代までいいのか いわゆる「欠史八代」について 天壌無窮の神勅の重要性 【コラム】天皇家のY染色体のタイプは 終章のまとめ 補足説明 より詳しく知りたい人のために アイヌは日本の先住民族なのか 現代日本人は縄文人の直系の子孫なのか① 現代日本人は縄文人の直系の子孫なのか② 感染症の大流行による影響 数学的な手法の限界による影響 消去法による結論 あとがき 特別編 『邪馬台国は隠された』の感想と私の考察 主な参考文献 論文(プレプリント)紹介 金澤正由樹;0201;03;ゲノム解析などの最新のバイオサイエンスと天文学により、縄文、弥生、邪馬台国、日本書紀、万世一系など古代史の真実に迫る!;20221002
本書は、邪馬台国滅亡後の4世紀から古代天皇家が現れる5世紀までの「空白の古代史」と呼ばれる時代に焦点を当て、考古学的研究を基にその謎を解明します。文献資料が少ないこの時代について、ヤマト王権の成立、大王の系譜、地方王権の状況、庶民の生活など、さまざまな視点から議論を展開し、古代日本の成立に迫ります。著者は日本古代史の専門家であり、最新の研究成果を紹介しています。
本書は、日本の歴史を網羅し、教科書には載っていない意外なエピソードも紹介する楽しい日本史の決定版です。旧石器時代から平成までの各時代を分かりやすく解説し、現代人が人生をより良く生きるためのヒントを提供しています。著者は教育評論家の後藤武士氏で、全国で講演活動を行っています。
この書籍は、日本史を大人の教養として学ぶためのビジュアル重視の解説書です。重要なトピックが時代順に整理されており、古代から現代までの日本史の流れを把握できる内容となっています。各章では、日本の始まり、武士の支配、戦乱から平和、近代国家の形成、現代の課題などが取り上げられています。巻末には資料集も含まれています。
日本文化論に関する重要かつ基本的なキーワードと代表的な古典を,歴史的・相対的な視点からわかりやすく解説した書。 日本文化論に関する重要かつ基本的なキーワードと代表的な古典を,わかりやすく解説。「両立型」という概念を軸に,歴史的・相対的な視点から選び出された125のキーワードで,日本文化を読み解く。日本文化論を学ぶ学生,日本に関心をもつ留学生にお勧め。 総 論 第1章 日本文化のキーワード 第2章 古典を通して「日本」を読む 第3章 日本文化はどう論じられてきたか 第4章 日本文化論はイデオロギーか 第5章 外から見た「日本」 引用・参考文献一覧 事項索引 人名索引
日本考古学史上最大の謎の一つを解き明かす驚愕の最新研究。土偶とは「日本最古の神話」が刻み込まれた植物+貝の精霊像であった! 日本考古学史上最大の謎の一つがいま、解き明かされる。 土偶とは――「日本最古の神話」が刻み込まれた植物像であった! 「考古学×イコノロジー研究」から気鋭の研究者が 秘められた謎を読み解く、スリリングな最新研究書。 ・縄文時代に大量に作られた素焼きのフィギュア=「土偶」。 日本列島においては1万年以上前に出現し、2千年前に忽然とその姿を消した。 現代までに全国各地で2万点近くの土偶が発見されている。 ・一般的な土偶の正体として 「妊娠女性をかたどったもの」 「病気の身代わり」 「狩猟の成功を祈願する対象」 「宇宙人」…… などの説がこれまでに展開された。が、実はいずれも確証が得られていない。 ・本書では〈考古学の実証研究〉(データ)と 〈美術史学のイコノロジー研究〉(図像解釈学)によって ハート形土偶から縄文のビーナス、そして遮光器土偶まで 名だたる国内の「土偶の真実」を明らかにする。 そこには現代につながる縄文人たちの精神史が描かれていた。 日本、5000年の歴史。 現代人の心的ルーツを明らかにする人文書の新しい展開へ。 はじめに 序章:人類学の冒険 第1章:土偶プロファイリング1 ハート形土偶 第2章:土偶プロファイリング2 合掌土偶 第3章:土偶プロファイリング3 椎塚土偶 第4章:土偶プロファイリング4 みみずく土偶 第5章:土偶プロファイリング5 星形土偶 第6章:土偶プロファイリング6 縄文のビーナス 第7章:土偶プロファイリング7 結髪土偶 第8章:土偶プロファイリング8 刺突文土偶 第9章:土偶プロファイリング9 遮光器土偶 第10章:土偶の解読を終えて おわりに
この本は、日本の古代史を数万年前の人類の居住から794年の平安京遷都までを解説しており、関連する地図を用いています。内容は、縄文・弥生時代の日本人の起源、古墳時代の天皇家の形成、飛鳥時代の政治の変遷、奈良時代の仏教国家としての発展を章ごとに詳述しています。各章では、歴史的背景や重要な出来事、文化的側面について掘り下げています。
本書は、天武天皇崩御後の女性天皇たちによって守られた天武直系の皇統と、聖武天皇の治世を中心に古代日本の歴史を探求する。聖武天皇は、天災や疫病に苦しむ中で仏教に帰依し、平城京を仏都として発展させた。女性天皇の役割や王都の変遷、仏教の影響を詳細に描写し、平安遷都後の平城京の管理と寺院の活動についても考察する。全体を通じて、古代天皇の生涯と国家の実像を浮き彫りにする内容となっている。
この文章は、南北朝時代における異類異形の者たちや後醍醐天皇の特異な王権について探求する内容を紹介しています。著者は、社会や人間の潜在的な力を引き出しながら、異形の意味とその力を考察しています。目次では、異形の風景や力、後醍醐の王権に関するテーマが取り上げられています。
『日本書紀』を通じて、日本の理想の国像「よろこびあふれる楽しい国」を探求する歴史家・小名木善行氏が、古代から江戸幕末までの庶民の生活を描写。各時代における庶民の暮らしを、太古の海洋民族、奈良平安時代の教育文化、鎌倉から江戸時代の娯楽や商業、教育の発展などを通じて紹介し、歴史の主役である庶民の活力と文化を浮き彫りにする内容。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
この書籍は、日本の歴史を形成した著名な人物たちの「すごい」面と「やばい」面を紹介し、歴史の流れを理解しやすくしています。聖徳太子や織田信長など、様々な時代の人物のユニークなエピソードを通じて、日本史への興味を引き出します。著者は歴史学者や漫画家で構成されており、楽しみながら学べる内容になっています。
歴史学とはなにか,この根源的な問いに答えることを通じて,歴史学が時代とともに変貌しつつ果たしてきた役割と有効性を炙り出し,学問的な魅力を解き明かす.歴史学の目的や,客観的事実と主観的解釈を明確にし,そして歴史を構築する方法論を体系的に論じる書き下ろし. はしがき 序論——史学概論の目的 第1章 歴史学の目的 第1節 歴史学の目的の三区分 第2節 三様の歴史学の相違点と相互関係 第3節 歴史学の目的と効用 第2章 歴史学の対象とその認識 第1節 人類の過去の文化 第2節 事実についての予備的考察 第3節 事実の種類とそれぞれの性質 第4節 史料による事実の確認と復元 第5節 事実認識についての学界の論議 第6節 事実認識の可能性と限界 第3章 歴史学の境界 第1節 歴史学とその周辺 第2節 歴史学と隣接諸科学 第3節 歴史的世界における事実と真実 第4節 歴史学と文学 第4章 歴史認識の基本的性格 第1節 歴史学の主観性と客観性 第2節 歴史認識の蓋然性と歴史の趨勢 第3節 歴史における因果関係と因果的必然性 第4節 歴史における偶然性と自由意志 第5節 歴史における相互連関の円環構造 第6節 歴史学の社会的責任 結 論 ソフトな科学としての歴史学、およびその後
この書籍は、日本の歴史を神話から現代までの各時代に分けて解説しており、著者の渡部昇一が日本人特有の視点で歴史を捉えています。内容は、古代の神話、武士政権の成立、中世の動乱、近世の戦国時代から江戸幕府の興亡、近代の西洋列強との対峙、そして戦後の復興に至るまで、多様な時代の日本の姿を探求しています。著者は上智大学の名誉教授であり、国内外の大学で学びの経験があります。
本書は、旧石器・縄文・弥生時代から白村江の戦いまでの古代日本を新たな視点で俯瞰し、読者に古代史の再学習を促すものです。最新の研究成果を紹介し、特に以下の5つの観点に焦点を当てています。 1. **旧石器・縄文時代**: 日本史の始まりや縄文人の生活についての新常識。 2. **弥生時代**: 稲作の起源や弥生人の特性、地域ごとの文化の変化。 3. **日本神話**: 神話と歴史の関連性や出雲神話の重要性。 4. **ヤマト建国**: 初期ヤマト政権の発祥地や関係国の影響。 5. **渡来人**: 古代の朝鮮半島との関係や技術革新の影響。 特別コラムでは古代人の死生観についても触れています。
安本美典氏推薦!待望の続編が登場!渡来人はいなかった!DNAと最新ハイテクが明かす衝撃の事実! 安本美典氏推薦! 待望の続編!巻頭32ページカラー! 渡来人はいなかった! DNAと最新ハイテクが明かす衝撃の事実! 朝鮮半島古代人… 安本美典氏推薦! 待望の続編!巻頭32ページカラー! 渡来人はいなかった! DNAと最新ハイテクが明かす衝撃の事実! 朝鮮半島古代人は縄文人だった! 半島最古の土器は実は縄文土器! ソウル大教授の致命的なミスを発見! 邪馬台国の首都は九州に2つあった! 卑弥呼は2人いた! 大和朝廷は邪馬台国の正統な後継国家! 前著『古代史サイエンス』から2年が経過し、その間に数多くの研究成果が公開されています。そこで、内容を補完し、情報をアップデートするため、第2弾を世に送り出すことにしました。今回は、最新英語論文をフルに読み込み、神武東征、日本建国、卑弥呼、邪馬台国、巨大古墳、渡来人について、新たな視点から従来の定説を検証します。 併せて、ゲノム解析にAIを活用した著者の英語論文も収録しました。 まえがき 序章 はじめに 日本人はどこから来たのか 氷河時代とスンダランド 日本が他国と大きく違う理由 中国大陸のめまぐるしい変化 【まとめ】 第一章 縄文人と渡来人のサイエンス 朝鮮半島は7000年前まで無人だった 7300年前の鬼界カルデラ大噴火 古代人のゲノム解析にノーベル賞 朝鮮半島南部には縄文人が住んでいた 渡来人は存在したのか 朝鮮半島最古の隆起文土器 隆起文土器は縄文土器なのか ソウル大教授の致命的なミス 極めて不自然な二重構造説 韓国人のDNA 【まとめ】 【コラム】平和的でスピリチュアルな縄文人 第二章 弥生人と稲作伝来のサイエンス 日本人は平和的な民族なのか 平和的な縄文人と好戦的な弥生人 青谷上寺地遺跡から出土した人骨 高麗が編纂した『三国史記』 卑弥呼は2人いた? 水田稲作ことはじめ 日本最古の水田跡から出土した縄文土器 古代人DNAと水田稲作との関係 本当に渡来人が水田稲作を伝えたのか 【まとめ】 【ミニ知識】弥生人のDNA 第三章 邪馬台国と卑弥呼のサイエンス 邪馬台国が北部九州である理由 邪馬台国のイノベーション ゲーム感覚で邪馬台国の謎を解く 邪馬台国連合が成立した背景 弥生時代のセブン・イレブン 卑弥呼が倭国の女王になる 邪馬台国の海上ネットワーク 邪馬台国の覇権と東遷 伊勢神宮の謎 五丈原の戦いと親魏倭王の金印との関係 【まとめ】 【コラム】邪馬壹国は邪馬台国なのか 第四章 日本建国のサイエンス 古墳が語る神武東征の真実 イネのDNAによる検証 環濠集落の経済学 専守防衛の環濠は高コスト 吉野ヶ里遺跡に感じた大きな違和感 大和朝廷のイノベーション 和風諡号「ハツクニシラス」の意味 旭日の大和朝廷と落日の邪馬台国 大和朝廷と邪馬台国の逆転 古墳時代の開始 邪馬台国滅亡の謎 宇佐神宮の由緒 三韓征伐の謎 出雲大社が改名した理由 三種の神器の意味 朝鮮半島の「平和の遺伝子」 古代日本の「平和の遺伝子」 現代日本の「平和の遺伝子」 【まとめ】 【コラム】現在も生きている日本神話 第五章 巨大古墳建造のサイエンス 古墳時代の農業革命 古墳時代の「明治維新」 前方後円墳の形が示すこと 私の仮説のまとめ 鳥取県の古墳による仮説の検証 吉野ヶ里遺跡による仮説の検証 古墳の分布から考えること 【まとめ】 【コラム】朝鮮半島南部に前方後円墳がある理由 あとがき 補足説明 古代史研究の「学問の壁」 二重構造説は正しいのか ゲノム解析で見逃されていた事実 IBDセグメントの分析 朝鮮半島古代人のY染色体 弥生人のミトコンドリア 海洋リザーバー効果について 朝鮮半島最古で独自の土器の分布 データサイエンスの重要性 「パラダイム転換」が求められる 主な参考文献 英語論文紹介
好評既刊を全面改訂、A5判に。スポーツの価値とは何か。歴史をひもとき文化の豊かさ深さを知ることでスポーツがさらに面白くなる。 好評既刊を全面改訂、A5判に。スポーツの価値とは何か。歴史をひもとき文化の豊かさを知ることで見えてくる。様々な競技種目の誕生と変遷、欧米の歴史と日本での発展、世界平和とスポーツ、武道、パラリンピックなど。 2012年初版の好評既刊を全面改訂。現代におけるスポーツの価値とは? 総勢14名の気鋭の研究者が最新の知見をもって歴史をひもとき、文化としてのスポーツの豊かさ・深さを論じる。スポーツの起源、時代と社会の関わり、さまざまな競技種目の誕生と変遷、欧米のスポーツの歴史と日本への紹介・定着・発展、スポーツと世界平和、現代の社会とスポーツの課題、そして新たに、日本の武道、日本の学校教育とスポーツ、アダプテッド・スポーツとパラリンピックといった話題を加え、判型もハンディなA5判に変更。スポーツの歴史に対する興味・関心の高まりに応える充実の1冊。
日本史の教科書には載っていない面白い話や、歴史上の人物の別の側面、大事件の裏側などを集めた雑学本。異説や珍説を通じて、古代から近代までの日本史の魅力を紹介している。
女王卑弥呼の真実 邪馬台国はヤマトか 神功皇后 雄略天皇と親衛隊長 名湯を訪れた聖徳太子 大船団、北上す 熱き女帝、斉明天皇 奈良時代を建てた男 皇后の見えない糸 仲麻呂は逆賊か 「道鏡事件」の舞台裏 政治家・大伴家持の暗躍 若き日の空海 平安の悪女に花束を 海賊は国王を夢見たのか 後白河上皇と平清盛
本書は、日本の歴史に関する154の重要な論点を最新の研究動向に基づいて解説した学生や研究者向けのテキストです。各時代の概要を示す「総論」に続き、「議論の背景」「論点」「探究のポイント」の三部構成で、歴史研究の魅力を具体的に伝えます。著者は日本の各時代に特化した専門家たちで、歴史学の面白さを体感できる内容となっています。
〈前方後円墳〉への招待 前方後円墳とは何か 古墳と政治秩序 国の形成と戦い 歴史学から見た古墳時代 加耶の情勢変動と倭 前方後円墳が語る古代の日韓関係 いま〈古墳〉から何が見えるか
本書「90秒スタディ」は、オンライン予備校「スタディサプリ」で人気の社会科講師が執筆した日本史入門書です。特徴は、1項目を見開きで完結させ、重要度を3段階で色分けして効率的に学べることです。内容は、原始から現代までの日本史をタテ×ヨコのストーリーで理解しやすくまとめており、受験生や忙しい社会人に最適です。著者は伊藤賀一で、多くの科目を担当する講師です。
現代のヒーロー“光る君”として描かれた源氏物語の新たな解釈を通じて、平安時代の愛と葛藤を描いた長編小説。美貌と知性を持つ源氏が、許されぬ恋や苦しい恋を重ねる様子が描かれ、上巻には特定の巻が収められている。著者は田辺聖子で、受賞歴が豊富な作家。
環濠集落、銅鐸、三角縁神獣鏡、箸墓古墳…新進気鋭の研究者が重要なキーワードを体系的に解説した注目の書。 第一章 邪馬台国の年代 第二章 弥生型社会の確立と変質 第三章 地域間関係の変化と倭国乱 第四章 原邪馬台国勢力の形成 第五章 卑弥呼の宗教改革と青銅器管理 第六章 三角縁神獣鏡の系譜 第七章 邪馬台国から大和政権へ
歴史家の加来耕三氏は、25人の歴史的英雄の失敗を独自の視点で分析し、それらの失敗から現代に通じる教訓を引き出しています。具体的には、明智光秀や黒田官兵衛、徳川家康などの事例を通じて、リーダーシップや判断力の欠如、部下との関係、時代の変化への適応などの重要な要素を探求しています。本書は、失敗から学ぶことで「成功」「逆転」「復活」の法則を見出すことを目的としています。
人気YouTubeチャンネル「丸竹夷/ YouTube高校」が書籍化され、日本史を楽しく学べる内容になっています。視覚的な図解や動画リンクが豊富で、学生や大人が手軽に学び直すのに最適です。目次には旧石器時代から江戸時代までの各時代が含まれています。著者は教育に携わる経験を持ち、幅広い教育活動を行っています。
幕末から冷戦終結に至る130年余の日本の近代国家形成を,対外問題とそれへの権力の対応を中心に分析・考察する。 近代国家は,国民の上に巨大な力を及ぼす一方で,国民の支持なしには存在できない。また,内政と国際関係が密接に結び付く。幕末から冷戦終結に至る130年余の日本の近代を,中央レベルの政治権力を対象として分析・考察する。「植民地とその後」を加筆。 第1章 幕藩体制の政治的特質 第2章 西洋の衝撃への対応 第3章 明治国家の建設 第4章 政府批判の噴出 第5章 明治憲法体制の成立 第6章 議会政治の定着 第7章 日清・日露戦争 第8章 帝国の膨張 第9章 政党政治の発展 第10章 国際協調と政党内閣 第11章 軍部の台頭 第12章 帝国の崩壊 第13章 敗戦・占領・講和 第14章 自民党政治の発展 第15章 国際秩序の変容と冷戦の終焉 補 章 植民地とその後
『詳説日本史』に基づき、9年ぶりに全面改訂された日本通史のロングセラー。内容は原始・古代、中世、近世、近代・現代の4部構成で、日本の歴史を詳細に解説している。
1946(昭和21)年4月に発表された「堕落論」によって、坂口安吾(1906‐1955)は一躍時代の寵児となった。作家として生き抜く覚悟を決めた日から、安吾は内なるとの壮絶な戦いに明け暮れた。他者などではない。このこそが一切の基準だ。安吾の視線は、物事の本質にグサリと突き刺さる。 ピエロ伝道者 FARCEに就て ドストエフスキーとバルザック 意欲的創作文章の形式と方法 枯淡の風格を排す 文章の一形式 茶番に寄せて 文字と速力と文学 文学のふるさと 日本文化私観 青春論 咢堂小論 墜落論 墜落論(続墜落論) 武者ぶるい論 デカダン文学論 インチキ文学ボクメツ雑談 戯作者文学論 余はベンメイす 恋愛論 悪妻論 教祖の文学 不良少年とキリスト 百万人の文学
本書は、19世紀以降の西ヨーロッパ諸国の政治発展を比較政治の視点から概観し、共通性と多様性の要因を歴史的に探求する。目次には、国家形成や民主化の過程、ナショナリズム、大衆民主制の確立、戦争や経済危機の影響、現代のポピュリズムなどが含まれている。著者は、東京大学と千葉大学の教授で、ヨーロッパ政治史を専門とする。
教科書では結論しか触れられていない部分の「なぜ」と「つながり」に焦点を当てて、丁寧に解説。暗記不要で、学び直しにも最適! 教科書では結論しか触れられていない部分の「なぜ」と「つながり」に焦点を当てて、丁寧に解説。暗記不要で、学び直しにも最適! 「暗記が苦手」「教科書を読んでもよくわからない」「歴史をきちんと理解したい」という方におススメの歴史学習書です。中学校で習うレベルの歴史(じつは教養として必要十分な知識が詰まっている)を、他人に教えられるくらいに理解しながら学ぶことができます。 本書では、単に事実や用語を羅列するのではなく、教科書に書かれていないような、ちょっと深掘りした内容も盛り込むことによって、「なぜ」「どうして」という因果関係がしっかりわかるように解説していきます。 例えば、「なぜ平将門は乱を起こしたのか」「ソ連はなぜキューバにミサイルを設置したのか」など、教科書では結論しか触れられていない部分の「つながり」にも焦点を当てて、丁寧に説明しています。 本書で学習すれば、教科書でいまひとつよく理解できなかったところも、「なるほどそういうことだったのか!」と、これまで暗記するだけだった歴史のモヤモヤした部分が解消されていくでしょう。やさしい語り口で、歴史の影響や現在とのつながりについても触れられているので、歴史が苦手な方や中高生でも興味をもって読み進むことができる「かゆい所に手が届く」歴史学習書です。
古代国家成立に関与した渡来人の役割を論じる。2003年日本考古学協会滋賀大会シンポジウムでの発表をもとに書き下ろし、考古学と文献史学の立場から総合して捉えている。 古代国家成立に関与した渡来人の役割を様々な角度から論じた一冊。2003年に日本考古学協会滋賀大会でのシンポジウムの発表を元に書き下ろしたもので、考古学と文献史学の立場から総合して捉えている。 総論 ・古墳時代の畿内渡来人 花田 勝広 第1章 近畿の渡来人の受容 ・大和の渡来人 青柳 泰介 ・河内湖周辺の韓式系土器と渡来人 田中 清美 ・六・七世紀における近江の渡来文化 —大津北郊の横穴式石室・ 副葬品・建物を中心として— 吉水 眞彦 ・山城の渡来人 —秦氏の場合を中心に— 丸川 義広 ・播磨における大陸との交流 富山 直人 ・紀伊の渡来人 —横穴式石室からみた 渡来人の動向— 黒石 哲夫 第2章 渡来人と生産 ・渡来人と手工業生産の展開 —陶邑窯を中心として— 植野 浩三 ・吉備の渡来人と鉄生産 亀田 修一 ・近江の渡来人と鉄生産 藤居 朗 ・近江の渡来系氏族と古代寺院 小笠原好彦 第3章 史料からみた渡来人 ・古代史からみた渡来人 —令制前の渡来人をめぐって— 田中 史生 ・大和政権と渡来氏族の形成 大橋 信弥 付録 古代近江渡来人名集成 大橋 信弥
「日本古代史」に関するよくある質問
Q. 「日本古代史」の本を選ぶポイントは?
A. 「日本古代史」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「日本古代史」本は?
A. 当サイトのランキングでは『古代史講義 (ちくま新書)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで131冊の中から厳選しています。
Q. 「日本古代史」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「日本古代史」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。
















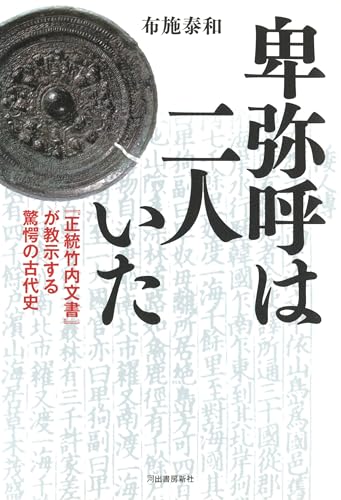






































































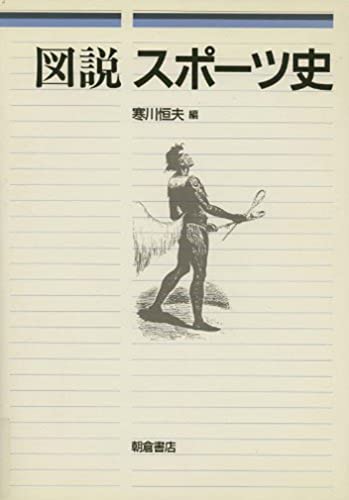









































![『「甘え」の構造 [増補普及版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51DUHuVS+NL._SL500_.jpg)