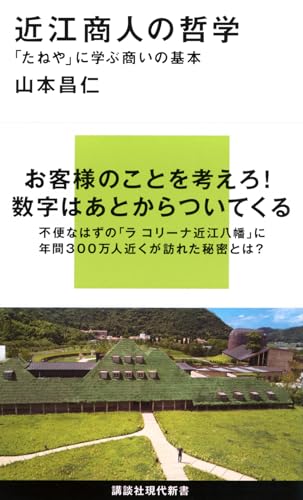【2026年】「軍事戦略」のおすすめ 本 140選!人気ランキング
- 現代の軍事戦略入門【増補新版】陸海空からPKO、サイバー、核、宇宙まで
- 帝国の参謀 アンドリュー・マーシャルと米国の軍事戦 略
- 軍事学入門
- 用兵思想史入門
- 失敗の本質: 日本軍の組織論的研究 (中公文庫 と 18-1)
- 増補新版-補給戦-ヴァレンシュタインからパットンまでのロジスティクスの歴史 (単行本)
- 孫子 (岩波文庫 青 207-1)
- 軍事戦略入門 (シリーズ戦争学入門)
- キューバ危機 - ミラー・イメージングの罠
- 戦略思想家事典
コリン・グレイをはじめ戦略研究の大御所がこぞって絶賛した話題の軍事戦略入門書がさらにグレードアップ! コリン・グレイをはじめ戦略研究の大御所がこぞって絶賛した話題の軍事戦略入門書がさらにグレードアップ! コリン・グレイをはじめ戦略研究の大御所がこぞって絶賛した話題の軍事戦略入門書がさらにグレードアップ! ●古典戦略から現代戦略までを軍事作戦の領域別にまとめた入門書 ●孫子、クラウゼヴィッツ、ジョミニ、マハン、コーベット、リデルハート、ローレンス、毛沢東、ドゥーエ、ミッチェルなどの「古典」的人物から、トフラー夫妻、オーエンス、シャリカシュヴィリ、セブロウスキー、クレピネヴィッチ、スケールズ、クレフェルト、リンド、ランベス、ハメスなどの現代の専門家まで幅広く取り上げ、“戦略”をコンパクトに紹介 ●PKO(平和維持)に関する章が新たに加わったほか、安全保障環境の変化をふまえ、第1版(邦訳2015年刊)の全章にわたって大幅に加筆修正。現代の軍事情勢を反映した充実した内容となっている。 part1 伝統的な戦略の次元 第1章 シーパワー 第2章 ランドパワー 第3章 エアパワー 第4章 核戦力と抑止 part2 戦略と非国家主体 第5章 非正規戦―反乱、対反乱作戦、新しい戦争、そしてハイブリッド戦 第6章 平和維持、安定化、人道的介入 part3 科学技術と戦略 第7章 統合理論と軍事トランスフォーメーション 第8章 サイバー戦争 第9章 スペースパワー
平和を追求するためには、戦争や軍事力の本質を理解する必要がある。軍事力は時代とともに進化し、戦争の形態も変化してきた。第二次世界大戦の大量破壊から湾岸戦争の精密攻撃へと移行し、軍事力は政治目的達成の重要な手段であり続けている。本書では、軍事力の理論、歴史、現代の様態、戦の形態、後方支援、科学技術との関係について探求している。
日本軍がなぜ戦争に負けてしまったのかを分析し、それを元に日本の組織における問題点を浮き彫りにしている書籍。責任の所在の曖昧さと、臨機応変に対応できない官僚主義が蔓延した日本組織は危機的状況において力を発揮できない。少々歴史の話は冗長だが一読する価値のある書籍。
本書は、16世紀以降の戦闘を「補給」の観点から分析し、補給が戦いの勝敗を決定する要因であることを明確に論じた名著の第二版。ナポレオン戦争や二度の世界大戦における補給計画や実施、戦闘への影響を具体的な数値と計算に基づいて解説している。著者はマーチン・ファン・クレフェルトで、石津朋之による翻訳と新たな解説が付されている。
『孫子』は中国最古の兵書で、13篇から成り立っています。戦術と戦争の哲学が深く結びついており、戦争や人生の問題を広い視野で捉えています。この新訂版では、原文、読み下し文、現代語訳に加え、平易な注釈と重要語句索引が付されています。内容は、戦略、作戦、軍の動きなど多岐にわたります。
この書籍では、軍事戦略の定義や成功の要因を探求し、歴史的事例を交えて分析しています。殲滅、撹乱、消耗、抑止、テロ、斬首、サイバー戦略など、さまざまな戦略を類型化し、その概念や背景を明らかにします。日本の安全保障や現代国際政治に関する洞察も提供されています。著者は米陸軍大学の教授と防衛省の研究員です。
本書は、古代から20世紀までの代表的な戦略思想家50人の生涯や業績を詳述した事典です。内容は、戦略研究の歴史、近代の思想家たち、日本の戦略思想に関する章で構成されています。著者は陸軍航空士官学校卒の前原透と、社会学専攻の片岡徹也です。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
この書籍は、軍事や戦争に関する基本的な概念とその背後にある思想を考察する内容で、古典的な軍事概念から現代の用語、戦略、指揮、そして日本や他国の軍事について詳述しています。著者は戦史・用兵思想史の研究家、片岡徹也氏です。
本書は、北朝鮮の核問題や米ロ間の緊張が続く中、地域や相手に応じた新しい核戦略が求められていることを論じています。かつては核廃絶が唱えられたものの、最近では核兵器の重要性が再認識されています。著者たちは、米中ロやNATO、インド・パキスタンの核戦略、サイバーセキュリティとの関連、日本の核抑止の課題について詳しく分析しています。核兵器の役割に関する議論は、賛否が分かれる重要なテーマです。
この書籍は、アメリカと中国の間で繰り広げられる技術を巡る戦略競争について、ワシントンからの最新リポートを基に考察しています。アメリカの技術への信念と、中国に対する不信感が背景にあり、海上戦闘、宇宙、AIの軍事応用、極超音速兵器などの分野での競争が激化しています。著者は、米国政治や安全保障に精通したテレビ朝日のワシントン支局長です。
歴史学、国際関係史の碩学が2018年BBCのラジオ講義「リース・レクチャー」をもとに書き下ろした2020年「ニューヨーク・… 歴史学、国際関係史の碩学が2018年BBCのラジオ講義「リース・レクチャー」をもとに書き下ろした2020年「ニューヨーク・タイムズベストブック10」入選の人文書、はやくも邦訳! 戦争を真正面からと… 歴史学、国際関係史の碩学が2018年BBCのラジオ講義「リース・レクチャー」をもとに書き下ろした2020年「ニューヨーク・タイムズベストブック10」入選の人文書、はやくも邦訳! 戦争を真正面からとらえ、世界中を古今東西、縦横無尽に駆け回り約400のテーマを簡潔、丁寧に論じた戦争全般についての基本図書。 「読みやすく説得力がある。マーガレット・マクミランの新たな傑作である」(ハーバード大学教授(ジョーゼフ・S・ナイ・ジュニア) 「重要な本であり戦争が社会のあらゆる面に入り込んでくる印象的な様を気づかせてくれる。読んで学ぶことが多い。」ジョージ・シュルツ(元米国国務長官) 〈目次〉 序 第1章 人間と社会と戦争 第2章 戦争の理由 第3章 方法と手段 第4章 近代の戦争 第5章 戦士をつくる 第6章 戦闘 第7章 一般市民 第8章 制御不能なもの(戦争)を制御するために 第9章 想像と記憶のなかの戦争 結び 〈目次〉 序 第1章 人間と社会と戦争 第2章 戦争の理由 第3章 方法と手段 第4章 近代の戦争 第5章 戦士をつくる 第6章 戦闘 第7章 一般市民 第8章 制御不能なもの(戦争)を制御するために 第9章 想像と記憶のなかの戦争 結び
著者クリストファー・コーカーは、人類の最大の課題である戦争と人間の関係を探求する新たな戦争論を提唱しています。進化論、文化、テクノロジー、地政学、平和、人道の6つのテーマを通じて、戦争が人間の本質的な営みであり文化に深く根付いている理由を論じています。多様な引用を用い、戦争の不可避性やその背景にある人間の心理を考察しています。
この書籍は、アメリカ、イギリス、イスラエルなどの特殊部隊が行った31の重要なミッションを紹介しています。内容は、ヴェトナム戦争からビンラディン襲撃まで幅広く、特に日本ではあまり知られていない2001年以降のアフガニスタン紛争の作戦についても詳述されています。著者はナイジェル・カウソーンで、翻訳は角敦子と友清仁が担当しています。
2009年10月3日、アフガニスタンの米軍戦闘前哨キーティングがタリバンの大規模な奇襲を受け、米兵たちは絶体絶命の危機に陥る。重火器による猛攻と包囲に直面し、友軍のアフガニスタン国軍は逃げ出し、米兵たちは次々に倒れる中、ロメシャ二等軍曹率いる生き残りの兵士たちは反撃の機会をうかがう。著者クリントン・ロメシャがこの苛烈な戦闘の詳細を語る記録。
本書は、弱者が強者に勝つための「ランチェスター戦略」を解説し、実践法を提供するものです。著者は、戦略コンサルタントの福永雅文氏で、50以上の事例を通じて、戦略の立案や実行のポイント、課題解決法を紹介します。内容は、弱者逆転の原理や市場占有率の重要性、戦略の奥義などを含み、特に中小企業経営者に向けた実用的なガイドとなっています。2005年のロングセラーを改訂した本書は、競争の激しいビジネス環境での勝利を目指す人々に必携の一冊です。
デジタル影響工作とはなにか デジタル影響工作のプレイブック 世界のメディアの変容 日本のニュース生態系と影響工作 デジタル影響工作に対する計算社会科学のアプローチ ロシアによるデジタル影響工作 権威主義国家によるデジタル影響工作と民主主義 各国のサイバー空間における活動と影響工作
本書は、マキアヴェリの「君主論」を現代の視点から再評価したもので、権謀術数やマキアヴェリズムの真髄を探ります。訳者の池田廉による詳細な解説や注釈、佐藤優による現代政治との対比が加えられ、さまざまな種類の君主国やその征服手段について論じています。マキアヴェリは、フィレンツェの政治思想家で、彼の作品は冷徹な観察に基づく政治の現実を描いています。
本書は、現代の集団安全保障の重要性を論じ、リアルな軍事論を提供します。内容は、軍事の歴史的変遷、各国の軍事動向(特に北朝鮮や中国、アメリカ、ロシア)、そして日本の安全保障政策と自衛隊の運用について詳述しています。著者の冨澤暉は、自衛隊の経験を持つ防衛専門家であり、現在は大学で安全保障や危機管理を教えています。
本書は、「孫子の兵法」を現代のビジネスマンの視点から実践的に学ぶためのガイドです。著者は、孫子の教えをビジネスシーンに応用し、価格競争や商談交渉、情報収集など具体的な事例を交えて解説しています。読者は、知識ゼロからでも理解しやすく、ビジネスや人生に役立つエッセンスを学ぶことができます。また、読者には「孫子の兵法」全文の無料PDFも提供されています。
本書は、著者である海軍の参謀がシーレーン確保の戦略を綴った貴重な体験記であり、現代日本の防衛においても重要な記録です。日本は資源を海外に依存しているため、海上交通線の問題は非常に重要です。著者は戦争中にさまざまな戦略や困難な状況を経験し、その詳細を各章にわたって述べています。著者、大井篤は海軍大佐として終戦まで海上護衛総司令部で活動し、戦後は戦史研究家や評論家としても知られています。
本書は、中国の軍事的膨張や北朝鮮の脅威、日米同盟への不満など、激動する国際情勢における日本の安全保障のあり方を論じています。著者たちは、政府、軍、国民の三者が協力して「国民安全保障国家」を構築する必要性を提言し、歴史的な視点から日本の政軍関係を検討しています。また、戦後の自衛隊の役割や国際比較も行い、現代の新たな危機に対する対応策を探ります。
この書籍は、Dデイ(6月6日)に行われたオーヴァーロード作戦からカーン攻略までの「史上最大の作戦」の詳細を描写した戦史ノンフィクションです。著者アントニー・ビーヴァーは、戦争の全貌を巧妙に語り、戦史の決定版として評価されています。目次には、作戦の決断や各ビーチでの戦闘、カーン占領の試みなどが含まれています。翻訳は平賀秀明が担当しています。
この書籍は、中世から第二次世界大戦までのヨーロッパの戦争を、戦術だけでなく社会、経済、技術の発展との関連性を考慮しながら概観したもので、2009年に改訂された日本初訳です。目次には、封建騎士、傭兵、商人、専門家、革命、民族、技術者の戦争に関する章が含まれています。著者は、戦争史の権威であるマイケル・ハワードをはじめ、戦後の日本で歴史を学んだ奥村房夫と奥村大作です。
本書は、アメリカのPR戦略がいかにして国際世論を形成し、セルビアの「民族浄化」報道を操作したかを描いています。著者の高木徹は、情報戦の実態を通じて「情報を制する国が勝つ」というテーマを探求し、講談社ノンフィクション賞と新潮ドキュメント賞を受賞した作品です。目次には、国務省の策謀や強制収容所など、歴史的な出来事が含まれています。
ベストセラーの「ランチェスター戦略『弱者逆転』の法則」の福永雅文先生が、初心者向けにランチェスター戦略をまとめ直しました。 ベストセラーの「ランチェスター戦略『弱者逆転』の法則」の福永雅文先生が、初心者向けにランチェスター戦略をまとめ直しました。
この書籍は、太平洋戦争中に若い潜水艦長として戦った海兵同期の物語を描いた海戦記です。著者は、潜水艦乗員たちの壮絶な戦いとその素顔を通じて、潜水艦の歴史を次世代に伝えることを目的としています。目次には、真珠湾攻撃からミッドウェー作戦、硫黄島や沖縄戦の詳細が含まれています。著者は海軍兵学校卒業後、潜水艦の艦長や参謀を歴任した経歴を持っています。
この書籍は、自衛隊の60年以上の歴史を振り返り、憲法9条や自衛隊法がどのように自衛隊の活動を制約してきたかを解説しています。著者は、安倍政権下での国防軍化の道を探りながら、中国やアメリカとの関係、国内の様々な敵についても言及。自衛隊の自主防衛を目指す必要性を訴えています。著者は航空自衛隊の元幹部で、政府見解に異を唱えたことで更迭された経歴を持つ田母神俊雄です。
内戦で萌芽し、独ソ戦を勝利に導き、冷戦時、アメリカと伍した、最強のソフト。現代用兵思想の要、「作戦術」とは何か? ソ連の軍事思想研究、独ソ戦研究の第一人者が解説する名著、待望の初訳。 作戦術(Operational Art)とは? ソ連は、第二次世界大戦前に、画期的な用兵概念である「作戦術(Operational Art)」を世界で初めて明確に定義し言語化することに成功。この作戦術は、独ソ戦においてソ連軍の勝利に貢献した。そしてアメリカ陸軍も、ベトナム戦争での敗北を機に、この「作戦術」の概念を自軍の軍事ドクトリンに導入。湾岸戦争で勝利を収める大きな原動力となった。 現在、世界の主要国の軍隊では、この「作戦術」という用兵概念はすでに常識となっている。 前書き(米陸軍参謀総長 カール・E・ヴオノ) 序文(サンドハースト王立陸軍士官学校 クリストファー・ドネリー) 著者による序文 第一章 ソ連の戦争研究 歴史と戦争/軍事ドクトリン/ミリタリー・サイエンス/ミリタリー・アート/軍事戦略/作戦術/戦術 第二章 作戦術の特質 作戦術の起源 作戦術の発展 縦深作戦の出現 戦争によるテスト 軍事における革命と作戦 作戦レベルの再現出と縦深作戦の再生 第三章 作戦の枠組み 任務(使命) 領域 行動 部隊 作戦戦略級大規模部隊-正面軍/作戦級大規模部隊-軍/作戦戦術級大規模部隊-軍団/作戦級中規模部隊/作戦戦術級中規模部隊/戦術級中規模部隊 結論 第四章 ソ連作戦術の形成期〔一九一七~一九四一年〕 導入 内戦とレーニン主義に基づく軍事ドクトリン〔一九一七~一九二一年〕 情況/ドクトリン/戦略/作戦/戦術 社会主義者の軍事ドクトリンの進化〔一九二一~一九二九年〕 情況/ドクトリン/戦力組成/戦略/作戦術/戦術 軍隊の技術的再建と縦深作戦の理論〔一九二九~一九三七年〕 情況/ドクトリン/戦略/作戦術/戦術/戦力組成 ソ連軍幹部の危機〔一九三七~一九四一年〕 情況/戦略/作戦術/戦術/戦争前夜 第五章 大祖国戦争と作戦術の成熟〔一九四一~一九四五年〕 陸軍の悲劇と再生〔一九四一~一九四二年〕 情況/戦力組成/ドクトリン/戦略/作戦術/戦術/結論 転換期の陸軍〔一九四三年〕 情況/戦力組成/戦略/作戦術/戦術/結論 戦勝〔一九四四~一九四五年〕 情況/戦力組成/ドクトリン/戦略/作戦術/戦術/結論 第六章 作戦術と軍事における革命 最後のスターリン時代〔一九四三~一九五三年〕 情況/ドクトリン/戦力組成/戦略/作戦術/戦術/結論 核の時代と軍における革命〔一九五三~一九六八年〕 情況/ドクトリン/戦力組成/戦略〔一九五三~一九六〇年〕/作戦術と戦術〔一九五三~一九六〇年〕/戦略〔一九六〇~一九六八年〕/作戦術〔一九六〇~一九六八年〕/戦術〔一九六〇~一九六八年〕/結論 第七章 軍事における革命の改善 背景 戦力組成 軍事ドクトリン 軍事戦略 作戦術-正面軍と軍による作戦 戦術-軍と師団の作戦 結論 第八章 将来に関する見通し 背景 軍事戦略 作戦術・戦術 戦力組成 結論 本書紹介 長く読まれるべき現代用兵思想の古典 田村尚也(軍事ライター) 解説 「作戦術」の系譜学――半世紀にわたる、軍事研究の成果 三浦一郎 訳者後書き 戦力組成表の出典に関する註 写真の出典に関する註 索引
この書籍は、ハイテク技術が戦争のスタイルを根本的に変えたことを探求しています。著者は、安全保障問題の専門家であり、軍、産業、政治の複雑な関係と新たな戦争が引き起こす課題を明らかにします。目次には、ロボット戦争の歴史や軍事における革命、無人戦争の進展などが含まれています。著者は、米ブルッキングズ研究所の上級研究員であり、戦争の無人化に関する影響を追究したことで著名です。
この本は、ビジネスや学習に役立つ基本的な情報を30~60分で得られる内容を提供しています。地理や歴史、経済に関するテーマを地図や図解を用いてわかりやすく解説し、大人の学び直しや子供の学習意欲を高めることを目的としています。具体的には、ロシアのウクライナ侵攻や米中対立、パレスチナ問題、中国の一帯一路構想など、国際情勢や経済の動きを地政学的に分析しています。著者は地理の予備校講師で、地理を通じて国際情勢の理解を深めることを提唱しています。
著者は太平洋戦争中に大本営情報参謀として米軍の作戦を的中させ、戦後は自衛隊情報室長を務めた経験を回顧。日本軍の敗戦は情報収集・解析の軽視に起因するとし、情報に疎い組織の構造的欠陥を指摘している。
『孫子』は2500年前に書かれた兵法書で、戦略やリーダーシップに関する名言がビジネスや生活にも応用できる知恵を提供します。書籍は、慎重さやリーダーの心構え、見極める力、現場での行動、必勝の策についての章があり、著者は歴史や神話に詳しい島崎晋です。コラムでは孫子に関する歴史的背景も紹介されています。
本書は「本質シリーズ」の最終巻で、歴史的な戦争における勝利のメカニズムを解明します。スターリン、チャーチル、ホー・チ・ミンの戦略を通じて、攻撃と防御、機動戦と消耗戦を柔軟に使い分ける「知略戦略」の重要性を説いています。具体的には、状況に応じた戦略の実践が勝利をもたらすことを示し、リーダーシップの本質に迫ります。内容は独ソ戦、イギリスの逆転、インドシナ戦争、イラク戦争に焦点を当てています。
『世界の駄っ作機』第1巻が18年ぶりに増補改訂版としてリニューアル登場。月刊『モデルグラフィックス』の人気連載をもとに、有名な駄作機を中心に新たなエピソードを加えた内容となっている。新しいイラストが描き下ろされ、美麗なカバーも特徴。著者は岡部ださくで、航空や艦艇に関する評論を行っている。
本書『サクッとわかるビジネス教養 地政学』は、急速にグローバル化が進む中でビジネスパーソンが世界情勢を理解するための地政学の重要性を解説しています。著者の奥山真司氏が、特別な図解を用いて地政学の基本概念や国際関係をわかりやすく説明し、最新の国際情勢に基づいた情報を提供しています。具体的には、パレスチナ・イスラエル戦争やロシアのウクライナ侵攻などのトピックを取り上げ、地政学的視点からの理解を深める内容となっています。初心者でも簡単に地政学を学べるよう工夫されており、会話や説明ができるレベルに達することを目指しています。
ポストINF時代の安全保障 ポストINF時代の抑止戦略 ポストINF時代の軍備管理 NATO「二重決定」とINF条約 ロシアにとってのINF問題 ポストINF時代の米国の国防戦略と戦力態勢 ポストINF時代の日本の課題 総括:ポストINFの世界はどうなるか?
この書籍は、日本の鉄道部隊が戦争期間中に果たした役割について詳述しています。シベリア出兵から大東亜戦争終結まで、鉄道部隊は人員や物資の輸送を支え、数々の危険に立ち向かいました。内容は、鉄道の歴史、装甲列車の整備、戦闘の実態などを写真やデータと共に解説しており、鉄道部隊の戦いの日々を明らかにしています。目次は、鉄道の始まりから大東亜戦争までの各時期に分かれており、それぞれの重要な出来事や装備の変遷を追っています。
本書は、湾岸戦争やボスニア紛争の経験を持つ元イギリス陸軍大将ルパート・スミスが、戦争、戦略、軍事力について考察した著作です。内容は、国家間戦争の歴史、冷戦時代の対立、人間戦争の現代的な傾向に分かれており、軍事力の新たな目的や未来の方向性を探ります。日本語訳が待望されており、著者は防衛に関する豊富な経験を持つ専門家です。
『孫子』は現代の国際関係や経営に応用可能な戦略書であり、2500年を経ても米軍やビジネススクールで研究され続けています。本書では『孫子』の不敗戦略や名言、学んだ偉人たちの事例、他の兵法書との比較を通じてその教えを解説しています。著者は守屋淳で、翻訳や書評を手掛ける専門家です。
本書は、第二次大戦前に編纂されたドイツ、フランス、ソ連、日本の陸軍教範を読み解き、各国の戦術を行軍、捜索、攻撃、防御の局面ごとに探求する内容です。戦術の基本となる教範を基に陸戦を研究し、理解を助ける図版や図表を40点以上収録しています。著者は軍事ライターの田村尚也です。
概観 プーチン大統領の戦略 戦局の展開と戦場における「相互作用」 ウクライナの戦争指導 バイデン政権とウクライナ侵略 NATOはロシアの侵攻にどう対応したか ウクライナ戦争に伴う経済制裁 ウクライナ危機で激変する国際エネルギー情勢 日本、中ロとの2正面対立の時代に ウクライナ戦争と核問題 ウクライナ戦争と中ロ関係、中台関係 ロシアのウクライナ軍事侵略と国際秩序
本書は、エア・パワー(空軍の航空機やドローンを含む航空戦力)の歴史、理論、現状を包括的に解説する入門書です。エア・パワーは国際関係や軍事戦略において重要な概念であり、過去から未来にかけての変遷や日本のエア・パワーの発展、理論家たちの思想、現代戦争における役割など、さまざまな視点から分析されています。著者は防衛研究の専門家であり、エア・パワーの重要性を強調しています。
世界最古の兵法書にして、最強のビジネス書をどこよりも分かりやすく全文“超”訳。『孫子』を読んで、明日に勝て! 世界最古の兵法書にして、最強のビジネス書をどこよりも分かりやすく全文“超”訳。『孫子』を読んで、明日に勝て!
「超限戦」に続く新しい中国の戦争概念がここにある。 序 文 肖天亮 はじめに 第1章 戦争形態の進化に関するいくつかの基本問題 戦争形態とは何か 主導的軍事技術(群) 戦争形態の交代のタイミング、条件、周期 戦争形態の進化の一般的過程 萌芽期 形成期 発展期 成熟期 衰亡期 歴史における戦争形態の進化 冷兵器戦争期 熱兵器戦争期 知的兵器戦争期 第2章 知能化ブーム 人工知能の台頭 人工知能とは何か 紆余曲折の中での成長 累積効果の形成 カギとなる技術のブレークスルー 情報技術革命の終焉 技術発展の S 字曲線モデル 情報技術が成熟期に入る 知能時代へ 知能の拡張 知能化態勢の急速的形成 知能がすべてを主導する 第3章 軍事分野における知能化革命 情報技術の苦境―戦場 精度の極限 インターネットで繋がる世界 即時破壊 新軍種の突然の出現―人工知能 軍事知能化革命の勃発 制高点をめぐる争奪戦 主戦兵器の交替 知能化の浸透 知能時代の戦争形態 知能化の潮流は止まらない 戦闘力形成パターンの転換 戦争形態の進化 第4章 新たな戦争 新たな理念 誰が私たちの敵か プラットフォーム中心 知能アルゴリズムがすべてを定義する 兵器装備の核心的な指標―自律性 データこそが力である 「死傷ゼロ」時代 第5章 戦力の転換 武器=基本戦闘ユニット 知能化兵器装備 航空知能化無人システム 水上/水中知能化無人システム 陸上陸上知能化無人システム 知能弾薬 全知能攻撃 「弾薬―プラットフォーム」の一体化 モジュール化 知能を中心とした軍事技術体系 万能戦士 計画者 意思決定者 生産者 誰が専門家なのか? 誰にでも有能なアシスタントが必要である ネットワークなくして勝利なし 第6章 ゲームのルールを変える 知能力の発揮を中心に据えて戦闘を行う 本質―全く新たな争い 核心となる作戦理念―敵の意志を直接挫く 多次元を統合した知能化作戦 従来の軍事行動の空間を超越する 一体化作戦 知能化作戦 基本的なモデル 主な行動パターン 遠隔暗殺・統制作戦 スワーム(群れ)作戦 第7章 軍隊を再構築する 「ピラミッド」の崩壊 伝統的な脅威から多次元的な脅威へ 中間層革命から基層革命へ 情報の横方向一体化から兵器操作の横方向一体化まで 軍種兵種の消滅 組織革命 「兵器庫式」特別混成編制 二種類の戦力 機能軍隊 知能型司令部 参謀の危機 ビッグデータセンター 三位一体指揮意思決定の核心 第8章 スマート後方支援 知能衝撃波 IoT は後方支援の全資源を可視化する 3Dプリンターは装備物資のサプライチェーンに衝撃を与える ビッグデータは伝統的な指揮意思決定支援モデルに挑戦する 目標:ちょうどよいところ 正確な後方支援 能動的な後方支援 積極的な後方支援 両端へ移動する保障実施の重点 前方自給式保障 直行配送式支援 遠隔知能化保障 ピーク値支援能力 後方支援力の転換 後方支援軍(部隊) 三レベル保障構造 モジュール化されたユニット 結 語 おわりに 解 題:安田 淳 解 説:情報通信技術・人工知能(AI)技術の発展および軍用AIの動向 木村 初夫 略 歴
「孫子の兵法」を小学生向けに超訳した本で、競争や人間関係、将来の悩みを解決するヒントが詰まっています。内容は勝つための戦略、夢をかなえる方法、困難への対処、そして一歩踏み出すためのアドバイスを含んでおり、オールカラー・総ルビで親子で楽しめる構成になっています。著者は教育学の専門家、齋藤孝氏です。
『戦争論』の日本語訳が、戦争研究の権威マイケル・ハワードによる解説付きで出版されました。19世紀の軍人カール・フォン・クラウゼヴィッツが著したこの名著は、なぜ今も読み継がれているのか、その本質を探ります。内容はクラウゼヴィッツの生涯、戦争の理論と実践、目的と手段、制限戦争と絶対戦争、彼の遺産について詳述されています。著者と監訳者の背景も紹介されています。
この書籍は、世界各国の軍隊で使用される500種の軍用小火器について詳しく解説した図鑑です。ピストル、ライフル、サブ・マシンガン、スナイパー・ライフル、マシンガン、ショットガン、グレネード・ランチャー、対物射撃銃などの基本データや開発経緯、メカニズム、特徴を紹介し、1100点以上のオリジナル写真や図版が収められています。著者は軍用兵器の取材に長年従事している床井雅美氏で、陸戦兵器の権威として知られています。
機甲戦のルーツとなった陸戦史を概観し、ドイツ・ソ連・イギリス・フランス・アメリカ・日本の機甲戦理論の形成を詳述する。さらに、現代の機甲戦までとりあげる。 機甲戦のルーツとなった陸戦史を概観し、ドイツ・ソ連・イギリス・フランス・アメリカ・日本の機甲戦理論の形成を詳述する。さらに、現代の機甲戦までとりあげる。 第1章 機甲戦前史及び序説 一 陸戦の発達と機動戦 二 機甲戦序説 第2章 機甲戦理論の形成と発展 一 ドイツ軍の電撃戦理論の形成と発展 二 赤軍の縦深戦略理論の形成と発展 三 英・仏・米陸軍の機甲戦理論の形成と発展 第3章 日本陸軍の機甲の発展 一 第一次大戦後の影響 二 日本陸軍の戦術教義と機械化 三 機械化部隊への発展と蹉跌 第4章 現代の戦争と機甲戦 一 現代の戦争とその概観 二 現代のドクトリンと機甲部隊運用 三 現代における機甲戦闘
第1章 プロローグ 第2章 統合運用の歴史とその必要性 第3章 統合運用の実績 弾道ミサイル対処 第4章 統合運用の実績 東日本大震災 第5章 統合運用の実績 海外 第6章 エピローグ
この文章は、日本のインテリジェンス・コミュニティの歴史とその改革について述べています。日本は日米同盟を深化させるのか、「自主防衛」を選択するのか、中国との協調関係を選ぶのかという選択肢が提示されています。冷戦後、日本の安全保障戦略家たちはインテリジェンス改革に取り組み、特定秘密保護法や国家安全保障会議の設立に至りました。著者は、日本のインテリジェンスの過去と未来を、収集、分析、伝達、保全、秘密工作、監視の6要素に焦点を当てて考察しています。
軍事戦略だけでなく、商船・商業港湾など「公共財としての海」をめぐる戦略まで幅広く取り上げた総合入門書 軍事戦略だけでなく、商船・商業港湾など「公共財としての海」をめぐる戦略まで幅広く取り上げた総合入門書 軍事戦略だけでなく、商船・商業港湾など「公共財としての海」をめぐる戦略まで幅広く取り上げた総合入門書 海洋戦略の双璧マハンとコーベットを中心に、ワイリー、リデルハート、ウェゲナー、ルトワック、ブース、ティルなどの戦略理論にまで言及 米海軍大学J.C.ワイリー海洋戦略講座教授ジェームズ・ホームズの A Brief Guide to Maritime Strategy, 2019 の完全日本語訳 ・シーパワーを測定する6つの決定要素とは? ・シーパワーの循環(作って、運んで、売る)を回し続ける方法(グローバルなサプライチェーンの問題とは?) ・シーパワーを支える商船と海軍、生産と市場 ・海軍の果たす警察的役割と外交的役割と軍事的役割 ・漁船・商船・海洋警察船舶を正面に出す「グレーゾーン戦略」を採る中国やロシアにどう対処するか ・日米同盟における「見捨てられ」と「巻き込まれ」問題―米国側は日本をどう見ているか 第1章 ❖ シーパワーの作り方 海とは何か?/シーパワーとは何か?/誰が正しい素質を有しているかを測定する:マハンの「シーパワーの要素」 第2章 ❖ 好循環を維持する方法 本国と海外の商業海港/本国と海外の軍港/軍港の候補者を評価する:君たちの地図を見よ/船舶:商船隊/艦艇:海軍/海に対する戦略的意志 第3章 ❖ 海軍はなにをするのか 戦略の不変性/外交的役割/警察的役割/グレーゾーンにおける警察的役割と軍事的役割の協力/軍事的役割/特別な例:「累積」作戦/トラブルメーカー戦略:分遣隊による戦争/新しくつくられた古いアイディア:接近拒否と領域拒否/マキャベリの警告:文化に気を配れ
本書では、習近平の独裁体制が強化される中、中国が戦略的に最悪の選択をしていると述べられています。著者のエドワード・ルトワックは、米中対立の時代における中国の実力を分析し、強硬な対外政策やコロナ対策に自信を深める習近平政権の動向を探ります。目次には、中国の戦略、米中対決、軍事テクノロジーの逆説などが含まれています。著者は米戦略国際問題研究所の上級顧問であり、戦略や歴史、経済に関する専門家です。
本書は、10代後半から20代向けに、2500年前の「孫子の兵法」を基にした「仕事えらび」の心構えを指南します。超売り手市場の中で、就職や転職、起業において幸福をつかむための戦略を提案し、自己理解や会社理解、タイミングの重要性、情報収集、戦略的思考を重視しています。著者は経営コンサルタントの長尾一洋氏で、孫子の知恵を現代経営に活かす活動を行っています。
CIAの前身が作成した「組織をうまくまわらなくさせる」ためのスパイマニュアル。「トイレットペーパーを補充するな」「鍵穴に木片を詰まらせよ」といった些細な悪戯から,「規則を隅々まで適用せよ」「重要な仕事をするときには会議を開け」まで,数々の戦術を指南。マネジメントの本質を逆説的に学べる,心理学の視点からの解説付き。津田大介氏推薦! ◆推薦のことば 日本の大企業や官僚制度が抱える問題の本質が 驚くほどわかる本書。 「あるある本」として笑いながら読んでいるうちに やがて楽しさは空恐ろしさへと変わる。 (ジャーナリスト/メディア・アクティビスト 津田大介) 解説 サボタージュ・マニュアル―――日本語版の発刊に寄せて 1 サボタージュ・マニュアルとは何か ■OSSとは何か ■OSSとサボタージュ・マニュアル ■サボタージュ・マニュアルとは何か ■なぜ、いまサボタージュ・マニュアルなのか 2 どのようにすれば、組織はうまくいかなくなるのか ■ホワイトカラーむけサボタージュ戦略 ■形式的な手順を過度に重視せよ ■マックス・ウェーバーの「官僚制」概念 ■ロバート・キング・マートンの「官僚制の逆機能」 ■ともかく文書で伝達せよ ■・・・そして文書を間違えよ ■会議を開き、議論して決定させよ ■なぜ集まると集団のパフォーマンスが低下してしまうのか ■集団は個人の能力を封じ込める ■スペースシャトル墜落の原因も「会議」 ■行動するな徹底的に議論せよ ■コミュニケーションを阻害せよ ■組織の危機自体がコミュニケーションの阻害を招く ■組織内にコンフリクトをつくり出せ ■集団維持機能をおろそかにする ■組織の注意を組織の外側に向けるな ■「黒い羊」効果を生じさせよ ■士気をくじけ! ■サボタージュ・マニュアルの現代的な意義 サボタージュ・マニュアル(暫定版) 1章 序文 2章 推定される効果 3章 サボタージュの促進 ▼1 個人的な動機 ▼2 破壊活動の推奨 ▼3 安全な方策 4章 道具、標的、タイミング ▼1 一般的条件 ▼2 武力攻勢前に ▼3 武力攻勢中に 5章 サボタージュに関する具体的提案 ▼1 建造物 ▼2 工業生産(製造) ▼3 生産(金属) ▼4 生産(鉱業と採鉱) ▼5 生産(農業) ▼6 交通(鉄道) ▼7 交通(自動車) ▼8 交通(水上交通) ▼9 コミュニケーション ▼10 電力 ▼11 組織や生産に対する一般的な妨害 ▼12 士気を下げ、混乱を引き起こすための一般的な工夫 あとがき
本書は、地政学を通じて国際情勢や戦争の歴史を体系的に学ぶことを目的としています。イスラエルとパレスチナの紛争やロシアのウクライナ侵攻、日本の米軍基地の意義など、様々な国際問題を地政学的視点から考察。具体的には、パックス・ブリタニカ、パックス・アメリカーナ、中国やロシアの影響、アジアにおける日本の地政学などを扱い、最新のビジネス教養を提供します。著者は一橋大学の教授で、国際関係学の専門家です。
この書籍は、孫子の教えを通じて競争や交渉、トラブル対処における戦略を学ぶ内容です。各章では、勝つための戦い方、武器の持ち方、戦わずして勝つ方法、状況の突破法、勢いの重要性、主導権の握り方、目標達成法、心の整理術などが紹介されています。著者の田口佳史は東洋思想研究者で、企業変革指導や講演を通じて多くの人々に影響を与えています。
大人気の歴史系YouTuber「いつかやる社長」が初の著書を出版。世界情勢を簡単に解説し、ウクライナや台湾、北朝鮮の問題を含む現代のニュースをわかりやすく説明。かわいい動物キャラを使って、地政学や国際情勢を学ぶことができる内容で、小中学生や新社会人に人気。地政学の基本や各国の考え方をイラスト付きで紹介し、学校では教わらない「世界のカラクリ」を理解できる入門書となっている。
「軍事戦略」に関するよくある質問
Q. 「軍事戦略」の本を選ぶポイントは?
A. 「軍事戦略」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「軍事戦略」本は?
A. 当サイトのランキングでは『現代の軍事戦略入門【増補新版】陸海空からPKO、サイバー、核、宇宙まで』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで140冊の中から厳選しています。
Q. 「軍事戦略」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「軍事戦略」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。