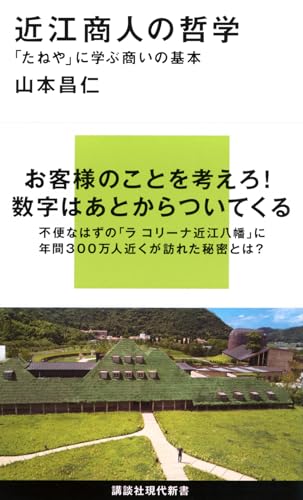【2026年】「経済史」のおすすめ 本 161選!人気ランキング
- 経済史 -- いまを知り,未来を生きるために
- 戦後日本経済史 (日経文庫)
- 海賊とよばれた男(上) (講談社文庫 ひ 43-7)
- 下町ロケット (小学館文庫)
- 決定版-HONZが選んだノンフィクション (単行本)
- アパレル興亡
- オレたちバブル入行組 (文春文庫)
- コア・テキスト経済史 (ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端 7)
- トヨトミの野望 (小学館文庫)
- 小説渋沢栄一 上 (幻冬舎文庫) (幻冬舎文庫 つ 2-12)
経済はなぜ成長するのか? いかに成長してきたのか? これらの問を入口に、人文社会科学の基本的概念を用いて俯瞰する歴史。 経済はなぜ成長するのか? 人類はいかにして生存してきたのか? 経済はいかに成長してきたのか? これらの問いを入口として,近代前から,分業,市場,貨幣といった経済学の用語のみならず,権力,文化,共同体等人文科学の基本的な概念も用いて俯瞰する歴史。 序章 経済史とは何か Ⅰ 導入──経済,社会,人間 1 経済成長と際限のない欲望/2 欲望充足の効率性と両義性 Ⅱ 前近代──欲望を制御する社会 3 総説:前近代と近現代/4 共同体と生産様式/5 前近代社会の持続可能性と停滞/6 前近代の市場,貨幣,資本 Ⅲ 近世──変容する社会と経済 7 総説:前近代から近代への移行/8 市場経済と資本主義/9 近世の市場と経済活動/10 近世の経済と国家/11 近世の経済規範/12 経済発展の型 Ⅳ 近代──欲望の充足を求める社会・経済 13 産業革命/14 資本主義の経済制度/15 国家と経済/16 自然と経済/17 家と経済/18 資本主義の世界体制 Ⅴ 現代──欲望の人為的維持 19 近代と現代/20 第一のグローバル経済と第一次大戦/21 第一次大戦後の経済/22 第二次世界大戦とその後の経済/23 第二のグローバル化の時代 終章 「現在」「未来」をどう生きるか
本書は、戦後日本経済の歴史を67のトピックスを通じて解説する入門書です。財閥解体や石油危機、消費税導入などの重要な出来事を追い、復興から成長、停滞までの軌跡を示しています。著者は日本経済新聞の記者で、現代経済の流れを理解するためのエピソードを中心に構成されています。また、「失われた20年」に関する補論も含まれており、初心者にも分かりやすい内容となっています。
本書は、1945年の敗戦後、日本で一人の男、国岡鐡造が石油会社「国岡商店」を立ち上げ、困難を乗り越え再起を図る物語です。彼は全てを失いながらも、従業員を守りつつ、石油を武器に新たな戦いに挑む姿を描いています。著者は百田尚樹で、作品は経済歴史小説として感動的な内容が特徴です。
直木賞受賞作『下町ロケット』が文庫化されました。主人公の佃航平は町工場・佃製作所を継ぎ、製品開発で成功を収めますが、大手メーカーから特許侵害で訴えられ、窮地に立たされます。国産ロケットを開発する帝国重工が佃製作所の特許技術に目を付け、特許を売れば救われるが、その技術には佃の夢が込められていました。男たちの矜恃が交錯する感動の物語です。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
大阪西支店の融資課長・半沢は、支店長の命令で無理に融資を承認した会社が倒産し、責任を押し付けられそうになる。四面楚歌の状況で債権回収に追われる半沢は、辛い中間管理職の現実を描いた痛快なエンターテインメント小説。著者は池井戸潤。
「池井戸潤」の半沢直樹シリーズ。大ヒットしたドラマの原作であり本も非常に面白い。物語としても面白いながら、普通に銀行ビジネスや大組織での立ち回りなど勉強になる部分も多い。
本書は、愛知県のトヨトミ自動車を舞台にした企業小説で、主人公の武田剛平が左遷から社長に昇りつめ、ハイブリッドカーの量産に挑む姿を描く。創業家出身の豊臣統一との確執や、自動車業界の経済戦争を通じて、フィクションと現実の境界が曖昧なストーリーが展開される。真偽のほどは不明だが、面白さは保証されている。
武蔵国の豪農の長男・栄一は、幼少期から商才を発揮し、幕末に尊王攘夷に目覚めて倒幕運動に参加。後に一橋慶喜に見出され幕臣となり、維新後は大蔵官僚として日本経済の基盤を築く政策に関与した。彼は「近代日本資本主義の父」と称される重要な人物の激動の人生を描いた作品。
この書籍は、消費増税やTPPなどの経済問題を歴史的視点から解説し、経済の仕組みを理解するための44の教養を提供しています。内容は、お金の成り立ちや国際通貨、貿易の自由化、金融の歴史、国家と財政に関する章で構成されており、経済の基本をストーリー形式で学ぶことができます。著者は茂木誠で、歴史を基に現代のニュースを考察する活動も行っています。
総合商社部長の山崎鉄郎は、出世街道を外れた後、泥酔の末に故郷の町長に就任。しかし、町の実情は非常に厳しく、私利を追求する町議会の影響や田舎特有の非常識に直面する。鉄郎は財政再建のため、老人向けテーマパークタウンの誘致を決断する。著者は楡周平で、1996年にベストセラー『Cの福音』でデビューした。
この作品は、メガバンクを舞台にした緊迫したエンターテインメントで、主人公の広報部長、寺田俊介が権力闘争や裏切りに巻き込まれながら、自らの出世を目指す物語です。経営難や人事抗争などの難題に直面し、掟破りの手段に手を染める彼の姿を描き、組織が人間から何を奪うのかを問いかけます。著者は元共同通信社の記者で、経済に関する豊富な知識を持つ小野一起です。
新部署「おもてなし課」に所属する若手職員・掛水が、地方振興のために地元出身の人気作家・吉門に観光特使を依頼する。しかし、吉門は次々と厳しい意見を寄せ、掛水は「お役所仕事」から脱却し、観光客を呼ぶ方法を模索する。彼の奮闘を描いた、地方と観光をテーマにしたエンターテインメント作品。著者は有川浩。
中堅ゼネコン・一松組の若手社員、富島平太が異動したのは大口公共事業を受注する“談合課”。地下鉄工事の受注が迫る中、彼は技術力で入札に挑むが、談合の壁に直面する。組織に従うか正義を貫くかを問う人間ドラマが展開される。著者は池井戸潤で、吉川英治文学新人賞を受賞した作品。
著者鈴木孝博が描く仕事ドラマでは、「自分」を変えずに「評価」を変えることの重要性が強調され、結果を求めすぎることによる罠について考察されています。鈴木は慶應義塾大学卒業後、様々な企業での経験を持ち、現在は発現マネジメントの代表取締役として若い経営者の育成にも力を入れています。
美しい女・麗子が香港のコンサルタント・工藤に五億円の送金を依頼し、脱税を企てる。しかし、四ヶ月後に彼女は五十億円と共に姿を消す。工藤は麗子と金の行方を追う。著者は金融に精通した橘玲。
新米特別国税徴収官ぐー子が、鬼上司の指導の下、カフェの二重帳簿疑惑や銀座クラブの問題に挑む姿を描いた税務署を舞台にしたエンタメ小説。税金に関わる人間の生活や欲望を学びながら、滞納者の取り立てに奮闘する様子が描かれている。著者は人気作家の高殿円。
若くして役員となった鹿子小穂は、父が招聘した大槻によって会社を追い出され、ヘッドハンティング会社に拾われる。新米ヘッドハンターとして、一流の経営者と接触しながら、仕事や経営、人情を学んでいく。著者の雫井脩介が新たな挑戦をしたビジネス小説で、緊迫感と感動が詰まった作品。
2009年以降、証券市場の民主化により、ニューヨーク証券取引所やNasdaq以外の取引所が増加し、ディーラーたちは売買価格が瞬時に変動する現象に悩まされる。二軍投資銀行のブラッド・カツヤマは、株を買うと価格が上がることに気づき、調査を開始。そこで、超高速取引業者「フラッシュ・ボーイズ」が投資家を出し抜いている実態を発見する。著者マイケル・ルイスによるこのノンフィクションは、ウォール街の詐欺と実情を描いており、映画化もされている。
老投資家とフリーターの青年が、預金量第三位の大都市銀行に復讐を挑む経済クライムサスペンス。二人の知恵を駆使した「秋のディール」が展開される。著者は石田衣良で、彼の作品は連続ドラマ化され話題となっている。
著者の川田修が伝説の営業マンと過ごした31日間の経験を通じて、営業テクニックだけでなく、仕事や人として大切なことを学んだ感動のストーリーを描いた本です。彼は外資系企業のトップセールスとして、営業目標を達成し続けており、現在は講演活動も行っています。
2018年、日産自動車の元経営者・塩路一郎が逮捕された。彼は労働組合の総帥として社長人事に影響を与え、経営を歪める一方で、私利私欲を追求していた。この実録小説は、大企業の腐敗の実態に迫る内容で、塩路がなぜ権力を持ち続けられたのかを探る。著者は高杉良で、経済界に関する豊富な取材を基に作品を発表している。
田中辰夫は、大手不動産会社でリストラを実施した後、自らも解雇され、失業者となる。一方、息子の雅人は就職先を辞め、ネットビジネスを目指す。父と子はそれぞれの困難に立ち向かいながら、新たな不動産サービスを模索し、再建を目指す物語。著者は江波戸哲夫。
本書は、14世紀から現代までのグローバルな視点から、アジアとヨーロッパの歴史的な関係や経済の変遷を描いています。内容は三部構成で、第一部ではアジアの時代とその交易、国際環境、植民地化を扱い、第二部では19世紀のヨーロッパの影響とアジアの近代化、経済の変化を探ります。第三部では20世紀の資本主義と社会主義の時代におけるアジアの経済状況を分析しています。著者は杉山伸也で、経済史の専門家です。
ベトナム研究の第一人者、日越大学(ハノイ)学長古田元夫氏によるベトナム入門書の決定版。一気に読めて「必要最小限」の知識が身… ベトナム研究の第一人者、日越大学(ハノイ)学長古田元夫氏によるベトナム入門書の決定版。一気に読めて「必要最小限」の知識が身につきます。 ❶ベトナムはどんな国か ベトナムの活力 言いたい放題だが「結論」の出る会議 ベトナムの宗教 多民族国家ベトナム 在外ベトナム人 ベトナム語の表記法 ベトナムの文化、日本の文化 【ベトナムの10人】 楊雲娥 ➋地域区分 概観 紅河デルタ地方 東北地方(越北地方) 西北地方 中部北方海岸平野地方 中部南方海岸平野地方 中部高原地方 南部東方地方 メコンデルタ地方 【ベトナムの10人】莫登庸 ❸主要都市 ハノイ ハイフォン ランソン ナムディン ヴィン フエ ダナン ホイアン バンメトート ホーチミン市 カントー 【ベトナムの10人】潘清簡 ❹歴史 先史からベトナム民主共和国独立まで ベトナム歴史像の変遷 三つの古代文化 李朝・陳朝 中華世界の南国へ チャンパ王国とそのベトナムとの関係 胡朝と明の支配 黎朝初期の大越 分裂の時代 西山朝から阮朝へ 越南、大南へ フランス植民地支配の形成 フランス植民地支配の意味 ベトナム民族運動の展開 ベトナム人のインドシナ再解釈 【ベトナムの10人】ファム・クイン ❺独立ベトナムの歩み ①戦争の時代 抗仏戦争(一九四五~五四年) 「ホー・チ・ミンの国」から「中国モデル」の受容へ ジュネーヴ会議 土地改革の展開 ゴ・ディン・ジエム政権と南ベトナム解放民族戦線 ジエム政権の崩壊と戦争のエスカレーション アメリカの戦争 革命勢力の総合戦略 貧しさを分かちあう社会主義 ソ連・中国の支援 テト攻勢 戦争の「ベトナム化」とカンボジア侵攻 七二年春季大攻勢と七三年パリ協定 サイゴン解放 統一ベトナムとカンボジア紛争、中越戦争、難民問題 【ベトナムの10人】 ヴォー・グエン・ザップ ❻独立ベトナムの歩み ②ドイモイの時代 「貧しさを分かちあう社会主義」の機能不全 集団農業における生産請負制 ドイモイ路線の提唱 東南アジアの「地域国家」ベトナム ASEANの中のベトナム 残存社会主義同盟からパートナー外交へ ドイモイ路線の展開 【ベトナムの10人】グエン・ティ・ビン ❼政治 ベトナムと中国 ホー・チ・ミン ベトナムの政治体制 【ベトナムの10人】レ・ズアン ❽経済と社会 経済の持続的高度成長 経済成長の担い手 外資と貿易の大きな役割 貧困削減と格差 中進国の罠 経済のグローバル化への積極的対応 都市と農村 【ベトナムの10人】ダン・ヴァン・グー ❾隣人との関係 北方・西方・南方 ベトナム版小中華帝国の試み フランス領インドシナ 「戦場の友」としての結合 ベトナム戦争後のカンボジア紛争 【ベトナムの10人】ヴー・ディン・ホエ ❿日本とベトナム 歴史の中の日越交流 近代日本とベトナム 一九四五年飢饉 南方特別留学生と新しいベトナム人 ベトナム戦争と日本 ベトナム民主共和国との国交樹立と日越関係の全面的発展の時代 今後の日越関係を展望して 【ベトナムの10人】ファン・フイ・レ あとがき インターネット出典写真一覧 参考文献 文献案内 索引
今日の世界を覆う 「資本主義的世界経済」 の出発点となった、16世紀ヨーロッパを中心とする近代世界システムの誕生の軌跡を鮮やかに描き出す。歴史および社会諸科学の記述を大きく塗り替えて、現代の古典となった記念碑的著作の第1巻。ウォーラーステインによる新たな序文を付した新版。 (全4巻) *岩波書店様から刊行された2巻本の 『近代世界システム』 (1981年岩波現代選書、2006年岩波モダンクラシックス、原著の第Ⅰ巻に対応) は、今回刊行する新版の第Ⅰ巻にまとめられます。 2011年版への序 序 章 社会変動の研究のために 第1章 近代への序曲 第2章 新たなヨーロッパ分業体制の確立 —— 1450年頃から1640年頃まで 第3章 絶対王政と国家機構の強化 第4章 セビーリャからアムステルダムへ —— 帝国の挫折 第5章 強力な中核諸国家 —— 階級形成と国際商業 第6章 「ヨーロッパ世界経済」 —— その周辺と外部世界 第7章 理論的総括 訳者あとがき
本書は、日本経済の平成から令和への変遷を解説し、コロナ危機や脱炭素革命、デジタル化などの現代の課題に焦点を当てています。著者は長年の経験を持つベテラン記者で、難しい理論を使わずにわかりやすく説明しています。経済に興味がない人でも理解できる内容で、学生やビジネスパーソンにおすすめです。目次には、平成の30年、デジタル革命、人口問題、金融政策、国際経済などが含まれています。
本書は、マクロ経済学の基本を身近に感じられるよう解説した入門書です。著者の塩路悦朗氏は、具体的な事例やニュースを交えて、GDPや財政政策、金融政策などの経済の仕組みをわかりやすく説明します。学生や公務員を含む幅広い読者を対象に、マクロ経済学が日常生活や仕事にどのように関連しているかを理解できる内容となっています。短時間で基礎知識を学ぶことができる構成です。
アセアンの主要加盟国として経済発展をけん引するなど確実に国際社会に存在意義を増しているベトナム。日本ともアジアの重要なパートナーという対等な関係にシフトしている注目のベトナムの魅力とその変貌ぶりを余すことなく伝える一冊。 I 「ベトナム」の成り立ち 第1章 「ベトナム」という名称――国号の変遷と「ベトナム(越南)」 第2章 ベトナム人の由来――建国神話と銅鼓、そしてベトナム考古学 第3章 北属南進の歴史――圧倒的な存在としての中国・フロンティアとしての中・南部 第4章 インドシナの時代――現代ベトナムが生まれたとき 第5章 ベトナム民族運動――勤王運動から独立まで 第6章 ベトナム戦争――二つのベトナム 第7章 ベトナムと周辺諸国との国境問題――混迷する中越間の国境問題 第8章 多民族国家――54の民族 第9章 越僑――海外在住ベトナム人との関係 第10章 ベトナム語と「クオックグー」――公用語としてのベトナム語 【コラム1】ベトナム人の名前 【コラム2】少数民族のベトナム語教育 II 大地と水、ムラとマチ 第11章 山と平野、水と土――二大デルタの自然と農業 第12章 北部平野集落の成り立ち――過密な人口を支える輪中地帯の形成 第13章 キムランとバッチャン――隣りあう窯業集落の対照性 第14章 新経済村から新農村へ――生存から生活への転換 第15章 盆地の生活と変化――ターイ族の暮らし、民族雑居 第16章 海とベトナム人――――海が苦手な北部の人、得意な中部の人 第17章 ハノイ――千年の古都と新しき郊外 第18章 サイゴン・ホーチミン市――クメールの街から華僑・華人の街、そしてベトナムの街へ 第19章 フエ、ホイアン、ミーソン――中部の世界遺産 第20章 生態系破壊――森林・マングローブの伐採・開発の現状と再生への試み 【コラム3】紅河デルタ地域の市場の風景 【コラム4】西北地方の町の市場 III 「公平・民主・文明的な社会」を目指して 第21章 階層――格差社会の現実 第22章 カィンハウ――Village in Vietnamが辿ってきた道のり 第23章 社会移動――新天地を目指して道は開けるか? 第24章 都市生活――低所得者には生活苦しい 第25章 家族――親子関係:母は強し 第26章 ジェンダー――規範と現実の狭間で揺れ動く:地殻変動が起きている!? 第27章 ライフスタイルの変化――格差とITがもたらしつつあるもの 第28章 福祉――多様な「生きること」を支える 第29章 教育――教育のドイモイは始まったか 第30章 汚職・腐敗――党・国家を蝕む社会の病 【コラム5】国際結婚――グローバル家族 【コラム6】おしん――農村から海外に輸出される労働力 IV グローバル化する文化と「民族文化」 第31章 「宗教」と「信仰」――公認されている宗教と非公認の宗教 第32章 ベトナムの民間信仰――聖母道 第33章 冠婚葬祭――「宴会〈アンコー〉」のさまざまなかたち 第34章 少数民族――チャム族の暮らし、越境する民族の文化 第35章 音楽・演劇――伝統芸能からV-popまで 第36章 文化遺産と美術品――遺産の保持と新たな創造 第37章 ベトナム美術の歴史――国立美術博物館の収蔵品を中心に 第38章 現代文学――戦争文学からポスト戦争文学 第39章 映像――プロパガンダからエンタメへ 第40章 ベトナムの食生活――熱と涼の調和 【コラム7】健康ブーム 【コラム8】ベトナムのモード・ファッション V ドイモイ下における政治の諸相 第41章 戦時体制からドイモイへ――ポスト冷戦期の社会主義志向路線 第42章 ベトナム共産党――その支配の「正統性」 第43章 国家機関――ベトナム的社会主義的法治国家 第44章 民主化運動と情報統制――インターネットを通じた市民社会の発展 第45章 軍隊と公安――その変容と本来の姿 第46章 大衆団体――現在の祖国戦線とその姿 第47章 行政改革――公務員の行動様式を変えられるか 第48章 地方行政機構――集権と分権のはざまで 第49章 安全保障――アメリカ・中国との関係 第50章 日本・ベトナム関係――過去の残像、未来への投影 【コラム9】ホー・チ・ミン――その光と影 【コラム10】カントー橋建設と日本のODA――日本の援助で始まる橋の建設 VI 「工業化・現代化」への道 第51章 ベトナム経済の現代史――ドイモイの25年 第52章 ベトナムの企業――多様な企業のダイナミックな成長 第53章 対外貿易――国際経済参入を成長のエンジンへ 第54章 工業化――2020年の工業国入りを目指して 第55章 農業――国際化、工業化のなかを生きる農民たち 第56章 ベトナムのインフラ事情――工業化に向けた最重要課題 第57章 労働市場――労働力不足の実態 第58章 証券市場――証券市場は国有企業の株式化を牽引するのか 第59章 海外直接投資――生産拠点のベトナム、消費市場のベトナム 第60章 小売・流通の発展――WTO加盟後の開放政策と実績、市場の特徴と課題 【コラム11】ベトナムで浸透し始めた日本食とビジネスチャンス 【コラム12】工業団地労働者の生活 年表 『現代ベトナムを知るための60章【第2版】』参考文献
新しい「東アジア経済論」を求めて 東アジアの経済成長 工業化政策と経済発展 経済格差と所得格差 国際的生産ネットワーク 東アジアにおける産業集積 国際金融環境と東アジア経済 東アジアの金融システム 経済発展の「北東アジアモデル」 東南アジア経済 東アジアの移行経済 東アジアの経済統合 東アジア経済を学ぶ
この文章は、ヴェトナムの歴史と文化、特に独立のための戦いと経済成長の背景を探る内容です。ヴェトナムは一億人の国としての発展を目指し、歴史的な人物たち(フンヴォンやホ・チ・ミン)を通じて国民性の強さを考察しています。目次には、中国支配、独立の過程、南進と国際関係、フランス植民地時代についての章が含まれています。
本書はマクロ経済学の基本を解説し、GDPや経済政策の影響についての疑問に答えます。経済の動きを理解することが求められる人々や、短期間で基礎知識を習得したい学生に向けた内容です。著者は中谷巌で、経済学の専門家です。
この書籍は、20世紀後半からのアジア地域の急速な経済成長が、従来の経済発展に関する議論に疑問を投げかけ、地域発展やアジアとヨーロッパの関係の見直しを促していることを背景に、グローバル経済史の重要な議論やテーマを紹介しています。内容は、経済の形成、一体化、深化、展開の4部構成で、15世紀から現在に至る経済の流れを学ぶことができます。著者は水島司と島田竜登で、それぞれインド史や東南アジア史を専門としています。
シリーズ累計48万部を超える経済学の入門書が10年ぶりに改訂され、経済の基礎をイラストや用語解説を交えてわかりやすく説明しています。内容は「お金とは何か」から始まり、需要と供給、ケインズ経済学、行動経済学など多岐にわたります。特に、円安や物価高の不安が増す現代において、経済学を学ぶことの重要性が強調されています。著者はジャーナリストの池上彰氏で、初めて経済学を学ぶ人や再学習を希望する人に最適な一冊です。
「機械をつくる機械」 の120年 ——。一国の技術水準を決定する工作機械工業で、現在わが国は世界の主導的立場にある。戦争をくぐり躍進はいかにして実現されたのか。「饗宴と飢餓」 の波に翻弄されつつ、後進性からの脱却のために費やされた努力の軌跡を丹念に追跡したライフワーク。 序 章 「機械をつくる機械」 の120年 第Ⅰ部 日本工作機械工業の形成 —— 戦前期 第1章 明治後期の工作機械工業 —— 重層的な市場・生産構造の形成 はじめに 1 明治後期の工作機械市場 2 明治後期の工作機械生産 おわりに 第2章 第1次世界大戦期の工作機械工業 —— 「饗宴」 と拡大 はじめに 1 工作機械市場の拡大 2 生産構造と工作機械生産者3類型の成立 おわりに 第3章 1920年代の工作機械工業 —— 「飢餓」 と縮小 はじめに 1 工作機械の需給構造 2 技術動向とメーカー・ユーザー間の交流 おわりに 第4章 1930年代の工作機械工業 —— 軍需・民需による拡大と市場・流通・生産構造の持続 はじめに 1 需要の急拡大と高度化 2 生産動向 おわりに 第5章 日本工作機械工業とアメリカ —— 戦前・戦中期 はじめに 1 アメリカ製工作機械の輸入 2 主要工作機械メーカーとアメリカ おわりに 補 論 アメリカ工作機械の輸入と商社 —— 1930~41年 第Ⅱ部 工作機械工業と経済統制 —— 戦時期 第6章 日中戦争期の工作機械工業 —— 戦時経済統制の展開と企業動向 はじめに 1 工作機械工業における戦時経済統制の展開過程 2 工作機械メーカーの動向 おわりに 第7章 太平洋戦争期の工作機械工業 —— 「飛躍」 の実態 はじめに 1 戦時生産の動向 : 計画と実績 2 戦時統制の展開 3 企業経営の諸側面 おわりに 第8章 「戦時型工作機械」 生産をめぐる諸問題 はじめに 1 戦時型工作機械構想の登場 2 戦時型工作機械の生産開始に向けた準備 3 戦時型工作機械生産の実態 おわりに 第Ⅲ部 戦前・戦時期の個別経営 第9章 唐津鉄工所 —— 自立的経営発展 はじめに 1 唐津鉄工所の経営発展 2 経営発展の諸条件 おわりに 第10章 大隈鉄工所 —— 下請管理の展開 はじめに 1 下請工場の構成と下請管理育成策の展開 2 戦時期における下請工場の動向 おわりに 第11章 碌々商店 —— 輸入商社からメーカーへ はじめに 1 碌々商店設立まで 2 碌々商店の設立と成長 3 自社工場の設立とその経営 4 戦間期の碌々商店と野田正一の業界活動 5 戦時下の碌々商店と野田正一 おわりに 第12章 津上製作所 —— 総合商社との関わりを中心に はじめに 1 創業期の津上製作所 2 三井物産の経営参加と津上製作所の拡大 おわりに —— 津上退助の辞任をめぐって 第Ⅳ部 工作機械工業の新展開 —— 戦後期 第13章 高度成長期の工作機械工業 —— 継承と変貌 はじめに 1 戦時期の遺産と戦後復興 2 高度成長期の業界動向と流通機構の変化 3 高度成長期における大手・中堅企業の経営と戦略 おわりに 第14章 NC化時代の到来と工作機械業界の構造変化 はじめに 1 1970年代後半から80年代の企業経営 2 1990年代・2000年代の新たな動き おわりに —— 工作機械工業の課題 終 章 日本工作機械工業の発展条件
最新の成果により、欧米・アジアなど世界各地域の発展過程をバランスよく解説した好評の入門書、大幅改訂による決定版。 欧米・アジアなど世界の発展プロセスをバランスよく解説、通史編とテーマ編の二部構成で学ぶ好評の経済史入門、大幅改訂による決定版。 世界の経済はどのような軌跡をたどってきたのか。グローバル・ヒストリーなど最新の成果をもとに、欧米・アジアや世界各地域の発展プロセスをバランスよく解説、通史編とテーマ編の二部構成で学ぶ好評の経済史入門、大幅改訂による決定版。 プロローグ なぜ経済史を学ぶのか I 通史編 第1章 東西文明の興隆 ——ローカル・ヒストリーの時代 1. 古代文明の農耕水準 2. 古代地域国家の経済制度 3. 民族移動と経済制度の変質 解説I-1 カール・ポランニーと経済人類学 第2章 東西世界の対決と交流 ——ローカル・ヒストリーからインターリージョナル・ヒストリーへ 1. 隋唐王朝の「世界帝国」化 2. イスラームの誕生と拡大 3. ゲルマン人国家とキリスト教社会 4. 東アジア・西アジア・ヨーロッパ諸勢力の対決と交流 解説I-2 マルク・ブロックと社会史 解説I-3 アジア交易圏論 第3章 東西世界の融合 ——インターリージョナル・ヒストリーの時代 1. 東の世界の商業発達 2. 西の世界の商業発達 3. アジア近世帝国の時代 4. ヨーロッパ近世王国の時代 解説I-4 フランクのアジアに対する眼差し 解説I-5 フェルナン・ブローデルと全体史 第4章 資本主義の生成と「近代」社会の登場 ——ナショナル・ヒストリーの勃興 1. 前近代の市場経済と近代の市場経済 2. 近代国家と資本主義の歴史的前提の東西比較 3. 封建制の崩壊と資本主義の生成 4. 産業革命と「近代」社会の登場 解説I-6 ドッブ-スウィージー論争とプロト工業化論 解説I-7 マックス・ウェーバーと大塚史学 第5章 資本主義による世界の再編成 ——ナショナル・ヒストリーからインターナショナル・ヒストリーへ 1. 海を基軸とした経済圏 2. ヨーロッパ・大西洋経済圏 3. 西アジア・インド洋経済圏 4. 東アジア・太平洋経済圏 5. 生産・流通面から見た近代資本主義 解説I-8 ロストウ/クズネッツの経済発展論 解説I-9 ガーシェンクロンとアジアの工業化 解説I-10 カール・マルクスと日本資本主義論争 第6章 資本主義世界経済体制の転回 ——インターナショナル・ヒストリーの時代 1. 19世紀末ヨーロッパ大不況とアジアの産業化 2. 世界経済の不均衡と帝国主義 3. 第一次世界大戦後の世界経済 4. 資本主義世界の恐慌とソ連経済の推移 解説I-11 古典的帝国主義論と自由貿易帝国主義論 解説I-12 社会主義計画経済システムの諸特徴 第7章 第二次世界大戦後の経済社会の展開 ——インターナショナル・ヒストリーからトランスナショナル・ヒストリーへ 1. 戦後経済体制の確立 2. 高度成長時代の展開と南北・南南格差の拡大 3. 低成長時代の到来と環境問題の表出 4. 21世紀への転換期の世界経済の実相 解説I-13 南北問題 解説I-14 ヨーロッパ統合 II テーマ編 第8章 市場経済の拡張とその限界 ——経済・経営活動の世界化 はじめに 1. ヒトの移動と経済圏の拡大 2. モノの移動と交易圏の拡大 3. カネの移動と世界化の限界 おわりに 解説II-1 ジェントルマン資本主義とアジアの資本主義 第9章 信用システムの生成と展開 ——経済活動と金融 はじめに 1. 信用貨幣の発展——貨幣取扱業者から銀行へ 2. 中央銀行の生成と金融政策の形成 3. 手形交換制度の生成——預金通貨と信用創造 4. 国際通貨制度の展開 おわりに——変動相場制下の金融肥大化 解説II-2 スーザン・ストレンジのカジノ資本主義論 第10章 市場の発達とその応用 ——経営活動の組織化 はじめに 1. 上下関係の強い経営組織 2. 比較的平等な経営組織 3. 経営組織間のネットワーク おわりに 解説II-3 チャンドラーとシュンペーター 第11章 市場の失敗とその克服 ——経済活動の秩序化 はじめに 1. 生産面での経済活動の制約 2. 流通面での経済活動の制約 3. 大量消費と現代社会の環境問題 おわりに 解説II-4 ノースとウィリアムソン 第12章 近現代市場経済の諸問題と国家介入 ——経済活動と国家 はじめに 1. 自由主義経済秩序と国家 2. 市場の調整(コーディネーション)と国家 おわりに——規制と規制緩和 解説II-5 ケインズとハイエク 第13章 福祉のコーディネーションと社会経済 ——経済活動と福祉社会 はじめに 1. 社会保障の諸領域と諸原則 2. 近代的経済社会の生成と社会福祉——自由主義的経済秩序観と社会福祉 おわりに——社会的共同性と福祉社会の展望 解説II-6 イギリス福祉史研究の諸潮流 解説II-7 アジア社会福祉研究の諸潮流 第14章 経済史認識の展開と現代 はじめに 1. 経済学の歴史への応用と経営史学の誕生 2. アナール派社会経済史から世界システム論へ 3. 現代の社会経済史学界の諸潮流 おわりに——21世紀に入ってからの論点 解説II-8 世界システム論からグローバル・ヒストリーへ 主要参考文献リスト あとがき 索 引 金井雄一/中西聡/福澤直樹編;0302;04;欧米・アジアなど世界の発展プロセスをバランスよく解説、通史編とテーマ編の二部構成で学ぶ好評の経済史入門、大幅改訂による決定版。;20200802
著者が駐ベトナム全権大使を務めた経験を基に、ベトナムの重要性を論じたリポート。中国の影響力が増す中、ベトナムは日本にとって信頼できる同盟国となり、両国の連携強化が求められている。著者は、ベトナムの対中リテラシーや経済力、歴史的背景についても触れ、ベトナムの繁栄が東アジア全体にとっても重要であると強調している。目次では両国の歴史や経済、ベトナムの改革努力について詳述されている。
本書は、資本収益率が所得の成長率を上回ることで生じる格差の問題を探求し、過去から未来に向けた洞察を提供します。主要な内容は、所得と資本の関係、格差の構造、そして21世紀における資本規制の必要性について論じています。著者はトマ・ピケティで、経済学の専門家です。
この書籍は、ミクロ経済学の基本を学べる内容で、身近な経済ニュースを通じて経済学の考え方を理解することができます。目次には、経済学の基本概念や市場の仕組み、労働市場、公共財、格差問題など多岐にわたるテーマが含まれており、経済についての理解を深める手助けをします。著者は経済学者のティモシー・テイラー、ジャーナリストの池上彰、翻訳家の高橋璃子です。
この書籍は、2020~2025年のベトナムビジネスのトレンドを予測し、激動するビジネス環境やノウハウを紹介しています。著者たちは、エースコックベトナムや東急グループなどのインタビューを通じて、経済の多様化や製造業、観光業、不動産業の動向を分析しています。さらに、スタートアップの視点から5年後のビジネス展望も探ります。著者は、ベトナムでの豊富な経験を持つプロフェッショナルたちです。
地球規模での交流や相互依存関係は、どのような世界から始まり、いかに拡がり深まってきたのか。長期的・広域的な視野で学ぶ。 地球規模での相互依存関係が拡がり深まった結果,異なる背景をもつ人々との交流や交渉の機会が増えてきた。こうしたヒト,カネ,モノ,情報の移動はどのような世界から始まり,いかに経済を推し進めてきたのか。そしてどこへ向かうのか。長期的・広域的な視野で学ぶ。 序 章 グローバル化の経済史 第Ⅰ部 前・近代の経済:グローバル化へのあゆみ 第1章 グローバル化以前の世界経済(~15世紀)/第2章 グローバル化の開始(16世紀)/第3章 危機の時代(17世紀)/第4章 近世経済の成立(18世紀) 第Ⅱ部 長い19世紀:グローバル経済の成立 第5章 工業化の開始と普及/第6章 ヒト・モノ・カネの移動の拡大と制度的枠組みの変化/第7章 植民地体制の変容とラテンアメリカ,アジアの工業化/第8章 工業化の新しい波と世界大戦 第Ⅲ部 停滞から再始動へ:グローバル化の新たな展開 第9章 世界大恐慌とグローバル化の停滞/第10章 再始動するグローバル化/第11章 グローバル化と開発/第12章 加速するグローバル化 終 章 グローバル化の行方
『花咲舞が黙ってない』は、東京第一銀行の調査役・相馬健が、問題を抱える支店で独りで臨店指導を行う中、上司を無視するスーパー女子行員・花咲舞とコンビを組む痛快オフィスミステリーです。彼らは様々なトラブルを解決し、腐敗した銀行を立て直す姿が描かれています。ドラマ化もされ、2024年4月に放送予定です。著者は池井戸潤。
高校3年生や大学新入生のための,経済学の導入書。経済問題,理論,歴史,学習法を通して,経済学を学ぶことの有用性を伝える。 経済学とはどんな学問なのか─高校3年生や大学新入生に向けて,一橋大学経済学部の教員が平易な言葉で語りかける。経済問題,理論,歴史,学習法を通して,経済学を学ぶ中で培われる思考法が,人生における困難を克服するための力となりうることを示す。 第1章 大きな社会問題,身近な経済問題 (経済成長/TPP/ギリシャ問題/貧困/財政赤字/大学の学生数/医療/廃棄物/イノベーション) 第2章 経済学的な発想とは? (効率・格差・衡平/ミクロ経済学/マクロ経済学/ゲーム理論/マーケットデザイン/為替レート/金融工学/公正・自由・競争/増税と国債) 第3章 歴史の中の経済社会 (経済史/上海経済/中国の経済成長/ドイツの電力システム/ 資源利用の歴史/貨幣の歴史) 第4章 プロフェッショナルにとっての経済学 (数学/統計学/経済学の古典:『国富論』『資本論』『自由論』/外国語:中国語・英語/ 政策のプロフェッショナルにとっての経済学)
この書籍は、14世紀のヴェネツィアで広まった複式簿記が、資本主義の発展にどのように寄与したかを探求しています。著者は、複式簿記が「富を測定したい」という人間の欲望を実現し、資本主義を促進したと論じています。目次には、会計の起源、ルカ・パチョーリの影響、産業革命、会計専門職の台頭などのテーマが含まれています。著者はジャーナリストのジェーン・グリーソン・ホワイトで、オーストラリアで数々の文学賞を受賞しています。
日本経済の課題を「自分ごと」として捉え,少子化対策や財政健全化,生産性向上等の解決策を読者自身が考えられる新しい入門書。 日本経済はなぜ衰退したのか? 物価や賃金はなぜ長期間低迷し続けたのか? 政府の巨額の借金をどうすべきか? 日本経済が抱える課題を「自分ごと」として捉えて,少子化対策や財政健全化,生産性向上などの解決策を読者自身が考えながら学べる新しい入門書。 第Ⅰ部 何が問題? 第1章 衰退途上国──親より良い生活はできない!? 第2章 安いニッポン──物価と金融政策 第3章 働き方が問題だ──労働市場 第4章 日本の借金は世界一!?──財政政策 第5章 格差拡大の真実──所得格差と貧困問題 第6章 国民生活は安心なのか?──社会保障 第7章 日本企業はどこへ?──国内投資と競争力 第8章 地球が直面する問題──気候変動とエネルギー問題 第Ⅱ部 解決できる? 第9章 誰もが希望を持てる日本へ──少子化対策 第10章 人々の可能性と活力を生かす社会へ──労働市場改革 第11章 将来にわたっての安心を──財政健全化 第12章 人々の可能性を引き出す──教育改革
この書籍は、数学が苦手でも経済学が理解できるよう、身近な例を用いてミクロ経済学やマクロ経済学の基本概念をわかりやすく紹介しています。内容は、経済学の考え方から、家計や企業、政府の目的、需要と供給、不完全競争市場、マクロ経済の短期と長期の分析など多岐にわたります。著者は経済ジャーナリストの木暮太一です。
本書は、GDPが倍増したベトナムの政治、経済、社会、文化を理解し、ビジネス進出方法や現地経営ノウハウをマンガと文章で解説しています。特に、成長著しいベトナムのビジネス環境に焦点を当て、親日国としての側面や歴史、経済の未来、現地で働く人々について詳述。著者はベトナムビジネスの専門家たちで、幅広い読者に向けた内容となっています。
この書籍は、経済学の入門書であり、現実経済や新たな経済学の動向を分かりやすく解説しています。内容はミクロ経済学とマクロ経済学に分かれ、需要と供給、消費者行動、市場の失敗、経済政策など幅広いテーマを扱っています。著者は東京大学の教授、伊藤元重氏です。
大原總一郎の波乱に満ちた人生を描いたノンフィクションノベル。彼は日本オリジナルの合成繊維「ビニロン」の事業化や国交回復前の中国へのプラント輸出を実現し、松下幸之助から「美しい経済人」と称賛される経営者であった。激動の昭和史を背景に、未来を見据えた彼の経営哲学と業績が描かれている。
幸福を経済学でひもとくと 就職活動の仕組みはどうなっている? スポーツは経済学で成り立つ!? ケータイ買うならどれにする? 貯金したって意味がない!? 恋愛に役立つ経済のテクニック 結婚という行動を経済学で解剖する! みんなの給料はどうやって決まる? 現代の格差社会はアメか?ムチか? 保険って結局トクですか? 子どもは嫌いじゃないけれど 経済学で賢い人生設計をする
この書籍は、脳科学や生物学、行動経済学など多角的な視点から「お金」の起源や歴史、社会的役割の変化、未来について探求しています。著者は、金融危機の中でお金に翻弄される理由や、貨幣のルーツが物々交換ではなく「債務」であるという新たな視点を提示し、宗教や芸術との関連性も考察しています。著者は金融業界の専門家であり、音楽プロデューサーとしても活躍しています。
2024年1月20日、JAXAは小型月面着陸実証機SLIMが月面に成功裏に着陸したと発表し、世界初のピンポイント着陸を実現したことが明らかになった。本書は、日本の宇宙開発の父である糸川英夫の生涯とイノベーションに焦点を当てた評伝であり、彼の影響を受けた事例として小惑星探査機「はやぶさ」の成功が紹介されている。内容は糸川の生い立ちから宇宙開発への道を辿り、彼の革新的なアイデアや業績を詳細に描いている。
家族、災害、健康、教育や娯楽、さらに森林やエネルギーなど、身近な生活環境を手がかりにして、経済社会の成り立ちをやさしく解説、消費や自然環境などの新たなテーマから、私たちの生活と経済の歴史の深いつながりを実感とともに学べる入門テキスト。 序 章 身近な生活から地域の環境を考えよう 第I部 地域社会と生活 第1章 家族・地域社会と経済活動 はじめに 1 家族と経済活動 2 「村」の役割 3 商店街とエスニック・グループ おわりに 解説1 無尽講と金融 第2章 災害と飢饉 はじめに 1 災害と飢饉 2 経済社会化と飢饉 3 江戸時代の災害・飢饉への対応 4 災害・飢饉への耐久性 おわりに 解説2 風評とデマ テーマI 社会史の方法 第II部 自然環境と生活 第3章 森林資源と土地所有 はじめに――地球環境問題と資源利用 1 森林資源利用の歴史 2 資源利用と土地所有 3 近現代日本の森林資源と過少利用問題 おわりに 解説3 温泉と開発 第4章 エネルギーと経済成長 はじめに――人新世の時代 1 石炭とイギリス産業革命 2 石炭・水力と日本の工業化 3 エネルギー革命と「東アジアの奇跡」 おわりに 解説4 日本の公害対策 テーマII 進歩と環境 第III部 近代化と生活 第5章 人口で測る経済力 はじめに――現代社会の人口と経済 1 人口に関する理論 2 日本の人口変遷 3 経済成長と人口 おわりに――人口の歴史は私たちに何を教えてくれるか 解説5 人口をめぐる思想と政策 第6章 健康と医薬 はじめに 1 健康と病い 2 生活と家計に見る健康と医薬 3 現代の健康と医薬 おわりに 解説6 感染症流行と経済発展 第7章 娯楽と消費 はじめに――「金」は天下の廻りもち 1 娯楽の産業化と消費社会 2 近代日本における娯楽の諸相 3 日記に見る人々の娯楽 おわりに――楽しみなしに人々は生きられるか 解説7 大衆消費社会論 テーマIII 共同体と近代 第IV部 社会環境と生活 第8章 教育と労働 はじめに――「学び」と「働き」の制度化 1 「学び」から「教育」へ 2 産業社会・労働の誕生と教育 3 子どもと女性から見た「教育」と「労働」 おわりに――戦後教育政策と新学歴社会の到来 解説8 集団就職 第9章 法と福祉 はじめに 1 慈善事業の時代 2 社会事業の時代 3 社会福祉の時代――第二次世界大戦後における生活をめぐる法整備 おわりに 解説9 育児と経済 第10章 帝国と植民地経済 はじめに――日本「帝国」史として考える 1 戦争と日本帝国の拡張 2 日本貿易の特徴 3 帝国内貿易の構造と植民地の生活 おわりに――「戦後/現代」と「帝国/植民地」 解説10A 植民地の近代をどう見るか 解説10B 経済競争と国際紛争 テーマIV システムという発想 終 章 競争と共存から未来を思い描こう 入門ガイド 文献史料と統計資料 参考文献 あとがき 索 引
本書は、竹中平蔵と佐藤雅彦が地球の経済をわかりやすく解説する新しい経済入門書です。内容は、貨幣や株、税金、アメリカ経済、アジア経済、投資と消費、起業、労働など多岐にわたり、競争と共存についても考察しています。著者はそれぞれ経済学とクリエイティブな分野での豊富な経験を持つ専門家です。
この本は、人類5000年の歴史を7時間で読み通すことができる新しい教科書です。著者の出口治明氏が、日本史、西洋史、文化史、経済史を一つにつなげて学べるように構成しており、流れをつかむことで教養を深めることができます。中高生から社会人まで、歴史の全体像を理解したい人に最適な入門書で、各章では紀元前から現代までの重要な歴史的出来事を網羅しています。
本書は、カリスマ経営者たちが著した書籍のエッセンスを解説し、ビジネスに活用するための視点を提供します。取り上げられているのは、稲盛和夫や柳井正など10名の経営者の代表作で、彼らの卓越した知見が満載です。読者が実際の経営判断に役立てられるよう、エクササイズも挿入されており、マネジメント層や若手ビジネスパーソンにとって必読の内容となっています。
桂木英一は、旧態依然とした日本の銀行を離れ、ウォール街の投資銀行で成長していく。彼は「伝説の男」竜神宗一と出会い、金融業界の変革期に直面する。1980年代の米国で、最先端の金融技術を駆使する中、複雑な取引や買収案件に挑むが、世界的な金融不安が彼を襲う。著者の黒木亮は、長年の金融業界の経験を持つ作家である。
本書は、ベトナム社会の不平等を「社会階層」という視点から分析し、各人の能力や努力に基づく上昇移動の可能性を考察します。社会階層は経済的、文化的、政治的な資本の分配を通じて不平等の構造を理解する枠組みです。近代化論では経済発展が社会の開放性を高め、不平等が解消されるとされますが、ベトナムでは政治的コネクションや家族背景が影響を及ぼす傾向が強いと指摘されています。著者は、データの制約を考慮しつつ、職業階層の形成過程を歴史や制度、経済的側面から多角的に検討し、ベトナムの社会の開放性と安定性を探求しています。
社内の権力闘争に翻弄されながらも、義を貫き再生を果たした一人の男の物語。定年後の人生をどう生きるかを考えさせる小説。 「部長職を解き調査役を命ずる」という辞令を受けた主人公。社内の権力闘争に巻き込まれ翻弄されながらも、「人間としてやるべきことは何か」を貫いた一人の男の再生の物語。定年後の人生をどう生きるかを考えさせる小説。 「部長職を解き調査役を命ずる」という四月一日付の辞令を受けた主人公は、その日から机の配置も変わり部下のいない社員、いわゆる窓際族になった。しかし社内の権力闘争から再び表舞台へ上がるが……。権力闘争に巻き込まれるも同僚への思い遣りの心を大切にし、「義を見て為ざるは勇無きなり」と義を貫く主人公の生き方は、聖書の言葉「日は昇り、日は沈みあえぎ戻り、また昇る」のごとく転変を繰り返す。本作品は、組織の掟と、義や情の間に揺れ動き翻弄されながらも、「人間としてやるべきことは何か」を貫いた一人の男の再生の物語だが、定年後の人生をどう生きるか──という、誰もが抱える後半生の大きなテーマに光を当てた物語でもある。 第一章 止まって見えた大時計の針 第二章 抜け切れない会社人間 第三章 君は何を報告したのだ 第四章 あなたは運のいい人だ 第五章 言われたとおりにやれ 第六章 社長が行方不明です 第七章 今度は君が社長だ 第八章 賽は投げられた 第九章 最初に見せたのは誰だ 第十章 常務が自殺 終 章 夢、遙か あとがき
この書籍は、経済学者アンガス・マディソンによる長期経済推計の集大成であり、世界経済の歴史と未来を探求しています。第1部では、西暦1年から2003年までの実質GDPデータに基づき、世界経済の発展を概観。第2部では、数量的経済分析の歴史と論争を紹介し、最後の第3部では、2030年の世界経済を予測しています。
銀行マン・鏑木健一が倒産寸前の書店に出向し、無知な女社長と敵対する店長たちとの関係を築きながら、情熱で社員たちの心を変えていくビジネス小説。決算書やマーケティングの基礎を学べる要素も含まれている。著者は中小企業の活性化に取り組むコンサルタントの小島俊一。
この書籍は、マクロ経済学をシンプルに学べる入門書であり、著者は「お笑いエコノミスト」としても知られるヨラム・バウマンです。内容は、失業やインフレーション、政府の役割、国際貿易、グローバルな経済問題など多岐にわたります。著者はワシントン大学で教鞭をとり、環境経済学を専門としています。
中堅メーカーでのパワハラ事件を発端に、会社の秘密が次々と明らかになるクライム・ノベル。エリート課長を訴えた部下と不可解な人事の背後に迫る主人公・原島が、親会社や取引先を巻き込んだ事態の真相を追います。会社や働くことの本質に迫る傑作。著者は池井戸潤。
この書籍は、ビジネスや経済に必要な知識を学ぶための解説書で、数学を分数から微分までやさしく説明しています。内容は、売上げの最大化に関する戦略やデータ分析の重要性、経済学の基本概念をグラフや数式を用いて解説しており、全ページにYouTube講義付きです。著者は経済学とファイナンスの専門家で、実務経験も豊富です。
この書籍は、ミクロ経済学の超入門書で、大学生に最も読まれた教科書の大幅改訂版です。内容は基礎的な概念から始まり、家計や企業の行動、市場制度、最適資源配分、不完全競争、不確実性、情報の不完全性、所得分配などを扱っています。著者の木暮太一は、経済学のわかりやすい書籍の執筆に注力しており、読者が理解しやすい内容を提供しています。
『経営戦略全史』シリーズの新装マンガ版が発売され、最新の経営トピックを加筆した合本版です。マンガ形式で経営戦略の進化を学べ、各章の後には解説が付いています。内容は、歴史的な経営戦略論と現代のイノベーション論に焦点を当て、経営学の復習やビジネスに対する指南書として役立ちます。著者は経営戦略コンサルタントから教育者に転身した三谷宏治氏で、約500ページにわたるストーリー形式で経営戦略の流れを描いています。
日本の実情を無視した経済政策ばかりで生活が苦しい。データを見れば賃上げの有効性は明らかだ。いま、日本経済を救える方法を示す。 日本の実情に合わない経済政策の乱発で生活は苦しいままだ。なぜ賃上げをすべきなのか、データを見れば一目瞭然。失政を振り返り、日本経済を救う手立てを示す。 アメリカの経済理論は、日本の実情に合っているのか? 「生産性」が上がっているのになぜ給料が上がらないのか! 日本の利益は、海外に流れている! 株高で誰が得する? 「生産性が上がらないから賃金は上げられない」 「少子化対策は無駄で、一人当たりの生産性があがれば良い」 実状を黙殺し、都合の良い政策を乱発した結果、日本の三十年間が失われてしまった。不景気に怯えた企業は、溜め込んだ資本を海外投資したものの、その利益は、外国人の株式取得を通じて海外流出し続けている。なぜその利益が家計に還元されてこなかったのか。一九九七年の金融危機以降、間違い続けてきた日本の経済政策を分析し、今こそ押すべきリセットボタンを提示する。 第1章 自分から植民地になった日本――1997年、転落の始まり 1 日本経済に何が起こったのか 2 経済データのレレレ構造 3 資金の行方――世界一の公的債務・対外純資産国 4 成長期のメインバンク好循環 5 今さら言えない――統計と理論の落とし穴 6 第1の失政は企業貯蓄増大を傍観したこと 第2章 バブル崩壊のツケはすべて家計に――2001年、小泉構造改革の熱狂 1 バブル崩壊から小泉構造改革へ 2 財政再建か上げ潮路線か? 成長率金利論争 3 自国通貨があれば政府支出は無限大に可能なのか 4 賃金抑制のトヨタショック 5 今さら言えない――成り立たない国際競争力低下論 6 今さら言えない――需要低下が生産性を下げた 7 第2の失政は家計消費そっちのけの構造改革 第3章 再度の流動性危機から異次元緩和へ――2008年のリーマン危機 1 金融危機はどう起こるか 2 巨大危機のあとの「借金返済」的余震 3 リフレ派はなぜ盛んになったのか 4 今さら言えない――商品券で理解する金融政策 5 第3の失政はものつくり国家への固執 第4章 ものつくり大国復活せず――2012年のアベノミクス、その失敗と「転進」 1 2012年のアベ復活と経済政策リベンジ 2 輸出促進隠密作戦の失敗 3 海外直接投資立国への「転進」 4 法人減税消費増税の隠密作戦 5 今さら言えない――品質調整停止による物価上昇 6 第4の失政は2倍2倍の異次元緩和開始 第5章 バズーカは国内に向けられた――2022年のインフレ再来 1 ウクライナ侵攻と予期せざるインフレ勃発 2 今さら言えない――賃金と物価に「好」循環はない 3 今さら言えない――金融政策モデルは日本経済の実情に合わない 4 第5の失政は輸入インフレを「好」循環と強弁したこと 第6章 新技術がもたらす格差拡大から貧困へ――迫り来る危機1 1 ネットがもたらした消費生活の変容 2 技術と組織の変容――アルゴリズムとスキャンダルの進化 3 職場の変容――仕事はなくなり、賃金は下がるのか 4 分断の構造――技術変容と格差拡大 5 政治行動の動揺――分断から独裁へ 6 第6の失政は技術変容軽視 第7章 世代間闘争必至の人口減少状況と社会保障――迫り来る危機2 1 今さら言えない――凄まじい出生数減少から世代間対立へ 2 財政はいいのか悪いのか――財政戒厳令の構造 3 家計貯蓄――恫喝より安心を 4 政府資産――なし崩しにするのではなく活用を 5 第7の失政は人口減少を傍観したこと 第8章 停滞と翼賛生成の組織論 1 長期停滞の基本的見方 2 一人綱引き経済政策 3 幻想は満たせない
この書籍は、ベトナムでの生活や仕事に必要な情報を提供するため、6章55のQ&A形式で構成されています。内容は基本情報、日本での準備、現地生活の基盤、ベトナム社会の理解、仕事を進めるヒント、直前チェック項目に分かれています。著者の古川悠紀は、ホーチミン在住のフリーランスライターで、ベトナムのライフスタイルやビジネスに関する幅広い記事を執筆しています。
19世紀半ばからの、資本主義経済社会の生成・発展過程に焦点を合わせ、経済構造の変化を中心に概説。論点を扱うコラムも充実。 19世紀半ばから百年余りの,日本における資本主義経済社会の生成・発展過程に焦点を合わせ,経済構造の変化を中心に概説。論点や学説を扱うコラム,用語解説欄,写真・資料,復習課題とその導き方も記され,理解を深めることができる。学んで考える経済史。 序 章 日本経済史入門 第1部 資本主義経済社会の形成 第1章 幕末開港の歴史的意義 第2章 明治維新と原始的蓄積 第3章 日本資本主義の確立 第2部 軍事大国への道 第4章 帝国主義的経済構造の形成 第5章 昭和恐慌と景気回復 第6章 戦時経済体制とその破綻 第3部 経済大国への道 第7章 戦後改革と経済復興 第8章 高成長経済の時代 第9章 安定成長への転換 終 章 最先進国日本の経験
本書は、著者が不振事業を再建するための戦略と実践を描いたもので、特に「2年で黒字化できなければ退任」という覚悟を持って取り組む姿勢が強調されています。内容は、業績回復のための組織改革やコンセプトの重要性、全体を貫くストーリー作り、社員の巻き込み方、実行の重要性などに分かれており、成功要因を探ります。著者は経営の専門家で、実際の事例をもとに企業再生の鍵を示しています。
本書は、さびれた商店街から「ユニクロ」を創り上げた柳井正の苦闘と成長を描いたノンフィクションです。青年の覚醒から始まり、東京進出やフリースブーム、海外展開の苦戦、ブラック企業批判を経て、ユニクロが情報製造小売業へと進化する過程をリアルに描写しています。著者は、柳井とその仲間たちの戦いを通じて、現代の企業や働く人々に希望を与える物語を提供しています。
生きたデータを用い現実の経済とマクロ経済学の関係を体系的に説明する。データのアップデート、近年の変化を盛り込んだ最新版。二… 生きたデータを用いて現実の経済とマクロ経済学の関係を体系的に説明する大好評テキスト。データのアップデートを行い,アベノミクスなど近年の動向を盛り込んだ最新版。二色刷で図表も見やすく,マクロ経済学,日本経済の学習に最新の情報で学ぶことができる。 第1章 GDPとは何だろうか?─一国の経済力の指標 第2章 消費と貯蓄はどのようにして決まるか?─消費と貯蓄の理論 第3章 設備投資と在庫投資─何のために投資するのか? 第4章 金融と株価─マクロ経済における金融の役割 第5章 貨幣の需要と供給─貨幣の役割と貨幣供給 第6章 乗数理論とIS─LM分析─総需要に注目した経済分析 第7章 経済政策はなぜ必要か?─経済政策の有効性 第8章 財政赤字と国債─政府支出拡大のマイナス面 第9章 インフレとデフレ─価格調整とそのコスト 第10章 失 業─マクロ経済における労働市場 第11章 経済成長理論─経済はなぜ成長するのか? 第12章 オープン・マクロ経済─為替レートと経常収支
重厚な考察に基づいて執筆された体系的テキスト。「小農社会」が形成・定着する徳川時代から現代までの400年を通史で学ぶ。 「既知」の内実を疑い,重厚な考察に基づいて執筆された体系的テキスト。「小農社会」が形成され,定着する徳川時代から,日本経済が大小の「連続と断絶」を内包しつつ現代に至る400年を通史で,人口減少という新たな領域に入りつつある未来を見据えて学ぶ。 プロローグ 日本の経済発展とその歴史的前提 第1章 「近世社会」の成立と展開(1600~1800年) 第2章 移行期の日本経済(1800~1885年) 第3章 「産業革命」と「在来的経済発展」(1885~1914年) 第4章 戦間期の日本経済(1914~1936年) 第5章 日本経済の連続と断絶(1937~1954年) 第6章 高度経済成長(1955~1972年) エピローグ 日本経済の課題
本書は、金融機関の役割やマーケットの仕組みをわかりやすく解説した入門書の最新版です。銀行、証券、保険などの金融界の全体像や、金利、為替、株価に関する基本的な知識を提供し、マイナス金利やデジタル通貨といった最近のトピックスも取り上げています。金融の勉強を始める人や金融機関への就職を考える人に適した内容です。目次はお金の動きから金融市場、当局の役割、国際金融の挑戦まで多岐にわたります。
池上信用金庫の小倉太郎は、取引先「松田かばん」の社長が急死した後、兄弟間の相続争いに巻き込まれる。社長の遺言では、会社の株は長男に譲られることになっており、次男は相続を放棄するよう言われていた。小倉は長男と対峙し、父の真意を探る。物語はこの表題作を含む六編から成る。著者は池井戸潤。
累計33万部のベストセラー『経営戦略全史』『ビジネスモデル全史』の新装マンガ版が発売され、最新のトピックを加えた合本版です。14世紀から21世紀までのビジネスモデルの変遷をマンガで楽しく学べ、各章の解説も充実しています。内容は、ビジネスモデルの定義から歴史的な変革、現代の挑戦まで多岐にわたり、70のビジネスモデルを紹介しています。著者は三谷宏治氏で、経営戦略コンサルタントとしての経験を活かし、幅広い読者に向けた内容となっています。
法務の最前線に立つ弁護士が経験を踏まえて解説する。企業法・投資法の最新状況や、労働法等の法改正を織り込んだ最新版。 企業の進出段階に応じてわかりやすく解説したベトナム法務解説書の決定版。企業法や投資法に関する近時の動向を織り込むとともに,労働法等に関連する法改正に対応。また,知的財産法や不動産法に関する解説もさらに充実させた最新版。 Ⅰ 総論 1 ベトナムの投資環境及び進出動向 2 法制度の特徴 Ⅱ 進出 1 進出方法比較など 2 外資規制 3 会社の新規設立 4 合弁 5 ベトナム企業とのM&A取引 6 不動産 7 インフラ開発 Ⅲ 現地での事業運営 1 企業法 2 契約法及び為替管理 3 資金調達・担保 4 輸出入規制 5 労働法 6 知的財産権 7 税務 Ⅳ コンプライアンス・危機管理・紛争対応 1 コンプライアンス 2 危機管理対応 3 紛争解決 Ⅴ 撤退 1 撤退に際して考えられる選択肢 2 持分または株式の譲渡 3 ベトナム現地法人の解散 4 外国法人の駐在員事務所又は支店の閉鎖 5 労務に関する留意点 6 倒産法制 7 その他の倒産・再生手続 Ⅵ 終わりに
この本は、貿易黒字が必ずしも「勝ち」ではないことを理解させる内容で、経済学の基礎を築くための貴重な一冊です。著者は現役高校教師の菅原晃氏で、GDPや貿易赤字、リカードの比較優位論などを解説しています。
中堅損保の秘書室次長、相沢靖夫は、会長の絵の個展を企画するが、贈られた一千万円の商品券を巡り口止め料を要求され、苦悩する。強面の経済記者の取材が加わり、職責を果たそうと奮闘する中間管理職の姿を描いた感動的な経済小説。著者は高杉良。
「経済史」に関するよくある質問
Q. 「経済史」の本を選ぶポイントは?
A. 「経済史」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「経済史」本は?
A. 当サイトのランキングでは『経済史 -- いまを知り,未来を生きるために』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで161冊の中から厳選しています。
Q. 「経済史」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「経済史」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



















































![『池上彰のやさしい経済学[令和新版] 1 しくみがわかる』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/512+OidTliL._SL500_.jpg)









![『池上彰のやさしい経済学[令和新版] 2 ニュースがわかる』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/514ImNpPysL._SL500_.jpg)
















![『入門経済学[第4版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41dClUCUpEL._SL500_.jpg)