【2025年】「ティール組織」のおすすめ 本 168選!人気ランキング
- ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現
- 自然経営 ダイヤモンドメディアが開拓した次世代ティール組織
- [イラスト解説]ティール組織――新しい働き方のスタイル
- マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則
- 実務でつかむ! ティール組織 "成果も人も大切にする"次世代型組織へのアプローチ
- 学習する組織――システム思考で未来を創造する
- 管理なしで組織を育てる
- リーダーシップとニューサイエンス
- 組織を芯からアジャイルにする
- 事業を創る人事 グローバル先進企業になるための人づくり
「ティール」は、従来の組織モデルを超えた新しいマネジメント手法を提案する本で、上下関係や売上目標がない組織のあり方を示しています。著者フレデリック・ラルーは、組織の進化を色で表現し、進化型組織の構造や文化を探求。多くの業界で変化が進んでおり、ポスト資本主義時代における新たな組織モデルとして注目されています。この本は、組織の変革や成果を追求するための実践的なガイドとして評価されています。
本書は、ダイヤモンドメディアの創業者・武井浩三氏と元ソニーの天外伺朗氏が、「ティール型組織」の実践について語る内容です。固定化されたヒエラルキーから脱却し、自然の摂理に基づいた「自然経営」を提唱。具体的な運営手法として、給与や財務の公開、役職の廃止、自律的な働き方を推奨しています。著者は自律した組織の構築方法や、権力の流動性についても解説し、次世代の組織運営のビジョンを示しています。
本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。
本書は、複雑系の科学を基にした新たな組織の在り方を探求し、混迷の時代に適応し続ける「進化しつづける組織」について論じています。著者のマーガレット・J・ウィートリーは、教育学博士であり、組織の健全性を取り戻すことに焦点を当てています。目次には、秩序の発見や自己組織化、カオスの意味などが含まれ、現代の科学的マネジメントに関する新しい視点を提供しています。翻訳は東出顕子が担当しています。
本書は、ソフトウェア開発におけるアジャイルのエッセンスを、「組織づくり・組織変革」に適用するための指南書です。ソフトウェア開発の現場で試行錯誤を繰り返しながら培われてきたアジャイルの本質的価値、すなわち「探索」と「適応」のためのすべを、DX推進部署や情報システム部門の方のみならず、非エンジニア/非IT系の職種の方にもわかりやすく解説しています。アジャイル推進・DX支援を日本のさまざまな企業で手掛けてきた著者による、〈組織アジャイル〉の実践知が詰まった一冊です。 イントロダクション 第1章 われわれが今いる場所はどこか 1-1 どうすれば組織を変えられるのか 1-2 組織が挑むDXの本質 1-3 組織の形態変化を阻むもの 組織の芯を捉え直す問い 第2章 日本の組織を縛り続けるもの 2-1 「最適化」という名の呪縛 2-2 目的を問い直す 2-3 アジャイルという福音 2-4 組織はアジャイル開発の夢を見るか 組織の芯を捉え直す問い 第3章 自分の手元からアジャイルにする 3-1 どこでアジャイルを始めるのか 3-2 組織アジャイルとは何か 3-3 組織アジャイルの段階的進化 組織の芯を捉え直す問い 第4章 組織とは「組織」によってできている 4-1 最適化組織 対 探索適応組織 4-2 四面最適化、時利あらず 4-3 “血があつい鉄道ならば走りぬけてゆく汽車はいつか心臓を通るだろう” 組織の芯を捉え直す問い 第5章 組織を芯からアジャイルにする 5-1 組織の中でアジャイルを延ばす 5-2 組織をアジャイルの回転に巻き込む 5-3 組織の芯はどこにあるのか 組織の芯を捉え直す問い 付録1 組織の芯からアジャイルを宿す26の作戦 付録2 組織アジャイル3つの段階の実践 参考文献 あとがき
ナシーム・ニコラス・タレブの著書では、「反脆弱性」という概念を通じて、不確実な世界での生き方を探求しています。経済や金融から人生、愛に至るまで、脆弱性と頑健性の考え方を用いて、私たちがどのように生きるべきかを解説しています。著者は、意思決定や不透明な世界での生存方法についての研究を行っており、リスク工学の教授としても知られています。
本書は、地方企業から有名企業、ベンチャーまでの成功事例を通じて、採用担当者が欲しい人材を惹きつける具体策を提供します。内容には、魅力的な求人コピーの作成法、SNSや人事ブログの活用、エージェントとの関係構築、リファラル採用の成功法、効果的な面接技術、候補者の本音を探る質問、内定辞退を防ぐための失敗例などが含まれています。多様な企業の事例を交えながら、採用担当者の悩みを解決するヒントが多数紹介されています。
この書籍は、伝統的な「人事」のネガティブなイメージを払拭し、現在求められる「戦略性のマネジメント」について論じています。著者たちは、組織の力を引き出す方法やリーダーの育成、人事の役割について経営視点から詳述しています。人事の専門家が、企業の持続的な成長を支えるための実践的な知識を提供する内容となっています。
この書籍は、採用と人事が優れた企業は事業も強いと主張し、HR戦略に関する専門家8人の実践的な知見を提供しています。内容は、採用、育成、組織開発、HRテクノロジーに関する最新の理論と実務が含まれており、経営者や人事担当者にとって必読の一冊です。著者の北野唯我は、経営と人事の密接な関係を強調しています。
本書は、組織開発の重要性とその歴史、哲学、手法の変遷を探求し、組織の健全さや効果性を高めるためのコミュニケーション活性化を目的としています。著者たちは、組織開発が単なる手法ではなく、計画的かつ協働的なプロセスであることを強調し、実践事例を通じてその具体的なアプローチを示します。また、組織開発と人材開発の相互関係についても論じています。全体を通じて、組織開発の未来に関する対談も行われています。
この書籍では、「選ばれる職場づくり」が経営課題であり、報酬や肩書きではなく、社員がありのままの自分でいられる環境が重要であると述べています。著者たちは「夢の組織」を実現するための原則を提案し、社員の強みを理解し、日常の仕事にやりがいを持たせる方法を探求しています。また、シンプルなルールと透明性を重視し、本物の組織を構築するための課題にも触れています。著者は組織行動学の専門家で、優良企業へのコンサルティング経験を持っています。
この書籍は、階層型組織からティール組織への移行における「自主経営(セルフ・マネジメント)」の実現方法を解説しています。著者たちは、マネジャーの役割を「ファシリテーター」に変え、ルールを「フレームワーク」にする必要性を強調。実践的なトピックとして、組織構造、コミュニケーション手法、対立への対処などを取り上げ、自主経営の実践知を提供しています。ティール組織の第一人者による翻訳とコラムも含まれています。
本書は、人材業界の過去100年を分析し、転職の価値観が変化した経緯や現状を探るとともに、今後の業界の未来を予測します。かつては終身雇用が一般的だったが、現在では転職がキャリア構築に不可欠な手段となっています。情報過多や信頼できるアドバイスを求める声が増えており、業界内ではAIや新たなビジネスモデルへの不安も広がっています。著者は、採用担当者や人材業界に興味を持つ人々に向けて、これからの変化にどう対応すべきかを考察しています。
ハーバード・ビジネス・スクールの名誉教授ジョン・P・コッターによる著書は、コロナ禍以降の変化する世界において、組織が進化する方法を探る内容です。人間の性質が変革やイノベーションに与える影響を考察し、成功する企業とそうでない企業の違いを解明します。脳科学の知見を取り入れ、リーダーシップや組織文化の変革、デジタル・トランスフォーメーションの成功法則などを提案し、ニューノーマルの時代を生き抜くための指針を示します。
本書は、効果的なリーダーシップを身につけ、組織に良い影響を与える方法を探る内容です。リーダーが自身を変容させ、組織を成長させるための具体的な実践方法を定量・定性の調査に基づいて解説しています。リーダーシップの拡大を通じて組織を発展させることを目指し、反応的なリーダーシップから創造的なリーダーシップへの変容を促進する方法も紹介されています。著者はリーダーシップ育成に豊富な経験を持つ井上奈緒氏です。
本書は、セムコ社のCEOリカルド・セムラーが提唱する新しい経営理念を紹介しており、従業員の自由を重視した結果、業績を大幅に向上させた事例を取り上げています。セムコ社は、辞職率が実質“ゼロ”という驚異的な成果を上げており、著者は日本の経営者やサラリーマンにその重要性を伝えています。目次は1週間の各曜日にちなんだ章立てになっており、経営の革新を日常的に考えることを促しています。
本書は、管理職向けのマネジメント書で、リモートワークにも適した「識学」という組織論を紹介しています。識学は、組織内の誤解や錯覚を解消する方法を明らかにし、4400社以上が導入しています。著者は安藤広大で、若手リーダーや中間管理職に向けた具体的なノウハウを提供し、リーダーの言動の重要性を強調しています。
組織のトップとしてのあるべき姿を説く書籍。この本に書いてある内容は自分の想像するリーダー像と違いすぎて驚いた。確かに組織を大きくして社会にインパクトを与えるためにはこの本の中で書かれているリーダーの仮面が必要なのかもしれないが、私はそんなことまでしてリーダーで居続けて何が楽しいのかなと思ってしまう。旧式の企業にはハマるがこれからの時代にはハマらない考え方な気がする。自分自身も会社を経営する身として参考にしつつもこの本の中で語られているリーダーとは違う姿を模索したい
この書籍は、グローバル人事の重要性とその実践方法について解説しています。具体的には、人の価値の測定や人材配置の戦略、グローバルリーダーの育成、組織の成長と変化、テクノロジーの影響などが取り上げられています。著者は人事戦略の専門家であり、過去には日本企業のグローバル人事に関する事例をまとめた著作もあります。
本書は、組織の変革を目指す人々に向けたガイドで、特に「関係性」を重視したアプローチを提案しています。近年の「デジタルシフト」「ソーシャルシフト」「ライフシフト」により、従来の管理主義が通用しなくなった中で、組織が抱える問題を解決する方法を示します。著者は、組織のメンバー一人ひとりが関係性、思考、行動を改善することで、全体を変えていけると主張しています。また、実践的なメソッドや成功事例を通じて、読者に希望を与える内容となっています。著者の講演も多くの企業から依頼されており、実績も評価されています。
著者はリクルートやライフネット生命、オープンハウスでの人事・採用責任者としての経験をもとに、人材マネジメントの重要性を説いています。書籍では、人事の役割や採用計画、面接の質向上、優秀な人材の確保などについての理論を解説しています。著者、曽和利光は人材研究所の代表であり、豊富な人事経験を持つ専門家です。
アジャイル型開発に主眼を置いた実務者のための実践ガイド。2022年11月発行『PMBOK®ガイド第7版』(日本語)にも対応。 建設、情報技術、医療から映画、音楽、ビデオゲームのプロジェクトの現場でも、プロジェクトマネジメントの実務は進化し続けています。従来の建設プロジェクトでは最初に企画のすべてを決める「ウォーターフォール型(予測型)開発」が主流でした。しかし、システム構築やソフトウェア開発に見られるように、高速でトライアンドエラーを繰り返しながらプロジェクトを完成に導く「アジャイル型(適応型)開発」のニーズが急増しています。 本書はその流れを受けて、プロジェクトマネジメントの全体像を俯瞰しながら、アジャイル型開発に主眼を置いた実務者のための実践ガイドです。2022年に発行となった『PMBOK®ガイド第7版』にも対応した内容です。 アジャイル型開発に主眼を置いた実務者のための実践ガイド。2022年11月発行『PMBOK®ガイド第7版』(日本語)にも対応。 第1部 価値を実現するプロジェクトマネジメント 第1章 リーダーシップ 第2章 プロジェクトとプロジェクトマネジメント 第3章 価値を生み出す開発アプローチ 第2部 プロジェクトの定義 第4章 プロジェクトの立上げ 第5章 コラボレーション 第6章 ルール 第3部 プロジェクトの計画 第7章 リスクマネジメント 第8章 WBS 第9章 計画 第10章 アジャイル 第11章 見積り 第12章 資源 第4部 プロジェクトの実行とコントロール 第13章 チーム 第14章 コミュニケーション 第15章 チェンジマネジメント 第16章 変更管理 第17章 進捗状況の測定 第5部 プロジェクトと企業戦略 第18章 企業戦略との連携 第19章 要求 第20章 品質と改善 PMBOKガイド®第6版と第7版の対応箇所
著者の最新作は、次世代リーダーの育成に焦点を当て、一人ひとりの強みを活かしながら「フラットなチーム」を作る方法を具体的に紹介しています。リーダーが直面する悩みを解決するため、メンバーの「自分ごと化」を促し、主体的に話し合う会議の作り方や、チームでのゴール設定、組織を超えた交流の場の重要性について述べています。著者は、リーダーシップ開発に取り組む伊藤羊一氏です。
はじめに 序論 プロジェクト手法の歴史 近代的プロジェクトの始まり ウォーターフォール型 変更要求 スパイラル型 アジャイルの誕生 第1章 アジャイル導入で変わるプロジェクトマネジメント 1.1 アジャイルの特徴とアジャイル・マニフェスト 1.2 アジャイル導入のメリット 1.3 アジャイル導入における課題 1.4 アジャイルを適用できる分野と適用しにくい分野 1.5 アジャイル導入の障壁と困難にする要素 1.6 アジャイル導入物語「第 1 話 振り返り」 第2章 プロジェクト手法の特徴と比較 2.1 ウォーターフォール(計画駆動開発) 2.2 スパイラル(反復型開発) 2.3 XP(エクストリーム・プログラミング) 2.4 FDD(フィーチャー駆動開発) 2.5 リーン(無駄の削減) 2.6 カンバン(ジャストインタイム;JIT:Just In Time) 2.7 DSDM(ダイナミック・システム開発) 2.8 スクラム(マネジメント・プロセス) 2.9 アジャイル導入物語「第 2 話 アジャイルって何?」 第3章 アジャイルを始めよう 3.1 アジャイルは革新である 3.2 変革実行のポイント 3.3 ビジネス・ケース作成 3.4 ビジネス・ケース作成手順 3.5 アジャイル手法を始めるポイント 3.6 アジャイル導入物語「第 3 話 研修」 第4章 大規模プロジェクトへの適用 4.1 規模に関する4つのテーマ 4.2 アジャイル導入物語「第 4 話 規模とチャンネル」 第5章 アジャイルに適した契約 5.1 日本のプロジェクト契約の現状 5.2 請負契約と準委任契約と派遣契約 5.3 契約のポイント 5.4 異文化圏との契約 5.5 アジャイル導入物語「第 5 話 アジャイルでの契約」 第6章 スクラム知識体系(SBOK)ガイドのフレームワーク 6.1 スクラムとは 6.2 6つのプリンシプル 6.3 経験を積み重ねるプロセス管理 6.4 自己組織化 6.5 協業 6.6 価値による優先順位付け 6.7 タイムボックス 6.8 反復開発(イテレーション) 第7章 5つの観点 7.1 組織 7.2 ビジネス正当性 7.3 品質 7.4 変更 7.5 リスク 第8章 5つのプロセス群(19 プロセス) 8.1 立上げ 8.2 計画と見積り 8.3 実行 8.4 レビューと振り返り 8.5 リリース 用語集 おわりに 索引 「アジャイルってなんだ?」 「どうやったらいいのかわからない」 PMBOKガイド監訳責任者がその疑問にお答えします! 欧米のソフトウェア開発プロジェクトでは当たり前となった「アジャイル」ですが、日本では名前だけが先行し、まだまだ事例が少ないのが実情です。 PMBOK監訳責任者でもある著者は、2年にわたりアジャイルに関する欧米、日本の事例を研究。 そこからアジャイルの具体的導入方法や日本における問題点を明確にし、本書にてプロジェクト成功のためのマネジメント手法として解説しています。 ・なぜアジャイルが生まれたのか、従来の「ウォーターフォール」からのプロジェクトの歴史も解説。 ・具体的な導入手順や失敗例からの教訓、アジャイルを進める事例を物語風に紹介。 ・PMBOKガイド翻訳の経験を活かし、アジャイルの独特な用語、表現も邦訳・解説。 さらにアジャイル手法のうち最新、かつ著者が最も優れていると考える「スクラム」の体系もわかりやすく解説しています。 これからアジャイル・プロジェクトにチャレンジしようという方におすすめです! IoTでも注目のソフトウェア開発手法!プロマネおよびプロジェクト構成員の入門書としてはもちろん、発注側の立場での情報も提供!
この文章は、リンダ・グラットンの著書の目次と著者情報を紹介しています。内容は、働き方の未来に関する予測や、未来を変える要因、現実の課題、理想的な未来の構築、働き方の変革についての考察を含んでいます。著者はロンドンビジネススクールの教授であり、経営組織論の権威として知られています。
本書『日本再興戦略』は、落合陽一による日本の未来を考察する作品です。AIやブロックチェーンの進化、少子高齢化などの影響を受け、日本が再興するための戦略を探ります。著者は改革ではなくアップデートを提唱し、過去の成功と失敗を検証することが重要だと述べています。目次は、欧米との比較、日本の特性、テクノロジーの影響、政治や教育の必要性、仕事の在り方など多岐にわたり、最終的には教育から再興が始まると結論づけています。
落合陽一氏が描く日本再興への道筋。少子高齢化が問題視されているが、もしかすると少子高齢化はAIの導入を早め、日本をAI大国にするためのきっかけになるかもしれない。そんな問題をそのまま問題と捉えるのではなく違った角度から見ることで可能性を見出す考え方に感銘を受けた。
本書は、個人や組織が変革を実現するための「免疫マップ」という手法を紹介しています。著者たちは、変化を望みながらも行動に移せない理由は「意志の弱さ」ではなく、変化と防御の間での葛藤にあると述べています。発達心理学と教育学の専門家が30年の研究を基に、変革のプロセスや成功事例を通じて、効果的な改革の方法を示しています。リーダーや組織メンバーに向けた実践的な手引きとなる一冊です。
ベンチャー企業が設立当初は順調に見えたが、2年後に業績不振で37歳のCEOが解任され、57歳の女性が新CEOに就任する。彼女はチームワークの重要性を理解し、会社の変革を実現する能力を持っている。著者は経営コンサルタントのパトリック・レンシオーニで、200ページにわたる物語を通じてそのプロセスとノウハウを紹介している。
『サピエンス全史』の著者が描く未来では、人類は不死と幸福、神性を追求し、ホモ・デウス(神のヒト)へと進化するが、その過程で格差が極端に広がることが示唆されています。
この本は、近現代の社会思想が性悪説に基づいていることを批判し、著者が世界各地で調査した結果、意外にも人間の本性は善であることを示しています。著者は、民主主義や資本主義の限界を考慮しながら、希望に満ちた人間観を提案し、社会設計や生き方についての示唆を提供する内容です。
元気な現場を創り出すヒントが満載 現在、日本企業の多くがオーバー・プランニング(過剰計画)、オーバー・アナリシス(過剰分析)、オーバー・コンプライアンス(過剰法令順守)の「三大疾病」に陥っています。米国流の分析的な経営手法に過剰適応した結果、自社の存在意義が見えなくなってしまったことに起因します。現場を知らない本社からの指示をこなすのに精一杯で、ミドル、現場がストレス過多でへばっている。これが日本企業の現状です。その一方で、現場が活性化し、社員一人ひとりが活き活きと仕事に向き合い、イノベーションや大きな成果を実現しているケースも少なからずあります。それらのケースに共通しているのは、企業と顧客、トップと部下、社員と社員との「出会い」の場があって、つながりが生まれ、そこでわき上がる「共感」が新しい価値を生む原動力となっていることです。 アメリカでもマイクロソフトのV字回復を達成し、時価総額世界1位へと導いたCEO、サティア・ナディラは「共感」を経営における最も重要な概念と位置づける「共感の経営」や「共感のリーダーシップ」を唱えている。 もう1つの共通点は、市場環境や自社の内部資源を分析し、市場における最適なポジショニングを見いだそうとする米国流の分析的戦略ではなく、自分たちはどうあるべきかという存在意義を問いながら、組織としてのビジョンを実現するため、その都度、最適最善の判断を行い、成功に至る「物語り戦略」を実践していることです。 物語り戦略は、絶えず変化する状況に対応、対処していくため、変動性や不確実性が高いなかでも、成果に至ることができます。そのため、海外の経営学においても、物語り戦略が注目されているのです。 共感経営を生み出すにはどんなマネジメントが求められるのか。物語り戦略を推進するための条件はどのようなものか。本書は、『Works』誌の連載「成功の本質」において、主に2015~19年にとりあげた30の題材のなかから、共感経営を実践し、物語り戦略により大きな成果を上げたケースを選りすぐり、それを可能にしたエッセンスを抽出します。 序章 共感と物語りが紡ぐ経営 第1章 価値を生む経営は「出会い」と「共感」から生まれる 第2章 イノベーションは「共感・本質直観・跳ぶ仮説」から生まれる 第3章 「知的機動戦」を勝ち抜く共感経営 第4章 不確実性の時代を「物語り戦略」で勝ち抜く 第5章 共感型リーダーに求められる「未来構想力」
この書籍は、現代人が抱える時間に関する悩みを解決するためのガイドです。ストーリー仕立てで、時間の使い方や投資の重要性、優先順位の付け方、トラブルに時間を奪われない方法などを解説しています。著者は麗澤大学の教授で、実践的なアドバイスを提供し、読者が自分の時間を有効に活用できるよう導きます。
プロジェクトの様々な局面で意思決定を迫られるプロジェクト・マネジャー。本書は世界中で活躍するプロジェクト・マネジャーによる97本のエッセイを収録した書籍です。ソフトウェア開発においてマネジャーに求められることは何か、人とチーム、さらにステークホルダーの管理、プロジェクトプロセスやプロジェクト要求、契約、国際化への対応と地理的に分散したチームの管理などについて、経験豊かなプロジェクト・マネジャーが自らの体験を踏まえて解説します。プロジェクト・マネジャーを勇気づけ、新たな気づきをもたらす一冊です。日本語版には、奥沢薫、神庭弘年、重木昭信、芝尾芳昭、冨永章、初田賢司、林衛による11本の書き下ろしを収録。 できるだけ早期にユーザーを巻き込む モグラたたき開発を避けよう ローカライゼーションのせいで締め切りに遅れる プロジェクト・オーナーは強力なプロジェクトサポーター 複雑よりもシンプルな方がいい 負債を支払う スキルでなく素質のある人を加えよう シンプルにいこう あなたは特別ではない スクロールから学んだこと〔ほか〕
この本は、日本一情報を発信する精神科医・樺沢紫苑が、脳科学に基づいた「アウトプット術」を紹介しています。読者が選ぶビジネス書グランプリ2025の特別賞を受賞し、シリーズ累計100万部を突破。内容は、伝え方、書き方、動き方に関する技術や方法論が含まれ、説明や雑談、プレゼンテーションなど多岐にわたるコミュニケーション能力を最大化することを目的としています。
アウトプットの重要性について語られて、具体的なアウトプット方法がたくさん学べる本。普通に過ごしているとどうしてもインプット過多になってしまうので、この本を読んでなるべくアウトプットする習慣を身につけていこう!
理由はわからないけど、最近社員のモチベーションが落ちている。そんな悩みを対話のチカラで解決する、組織開発の入門書。 本書は、近年注目が高まっている「組織開発」の入門書です。これまでの類書にはない、実践レベルにまで落とし込んだ一冊となります。監修・解説は、組織開発の第一人者であり、ベストセラー『入門 組織開発』(光文社)などの著者である中村和彦教授(南山大学)。著者3名は、 長年企業などで組織開発のプロフェッショナルとして定評があります。コロナ禍での業態変化や、在宅勤務の増加などに伴い、これまでにはないほど組織の在り方が変化した結果、より一層チームワークが重視されることとなりました。チームのモチベーションが下がっている、なんだか最近業績が落ちてきている、人がどんどん辞めていくなど、いまいち言語化できないチームや組織の悩みに向き合い、解決に近づけるのが組織開発です。本書は、そんな組織開発のはじめ方を、成功事例を踏まえてやさしく教える一冊です。中小企業、大企業、地域コミュニティなどの7つの事例を通して、バラバラになってしまった組織を生き返らせるために立ち上がった人々が、それぞれに抱えた悩みを解決するために起こしたアクションとそのポイントを紹介・解説します。この本を読めば、明日からチームの人たちと対話をしたくなるはず。組織開発はそこから始まります。
この書籍は、社員のモチベーションを高めるためには、まず「モチベーションを下げる要因」を取り除くことが重要であると説いています。著者は、疲弊する組織や高離職率の会社に共通する問題を分析し、改善策を心理的アプローチを基に解説しています。具体的には、上司の問題や組織の疲弊に関するパターンを示し、心理的安全性や自己効力感などの概念を通じて、金銭的報酬だけでなく「見えない報酬」の重要性を強調しています。著者は、経営コンサルタントとしての経験を活かし、効果的なマネジメント手法を提案しています。
本書は、長寿社会における新しい生き方や働き方を探る指南書です。著者は、教育、仕事、引退の従来のモデルが崩れつつある中で、個人がどのように戦略的に人生を設計すべきかを提案しています。重要なポイントとして、健康で長い人生を楽しむためには、見えない資産(スキルや人間関係など)の重要性や、柔軟な働き方、選択肢の多様化が挙げられます。また、結婚や労働市場の変化についても触れ、個人のアイデンティティや役割の調整が必要であることを強調しています。全体として、100歳時代を迎えるにあたっての新しいライフスタイルの指針が示されています。
今では色んなところで引用される人生100年時代というパスワードのきっかけになった書籍。もう既に1つの会社に勤め上げるような旧来の生き方は崩壊している。将来に不安を抱いているビジネスパーソンはこの本を読んで時代の変化に置いていかれないような生き方を選択して欲しい。
本書は、組織内の問題を「わかりあえないこと」から解決するためのアプローチを提案しています。著者は、対話を通じて新たな関係性を築くことが重要であるとし、組織の複雑な問題に対する実践的な手法を示しています。特に、ナラティヴ・アプローチを用いて、権力や対立を超えたコミュニケーションを促進する方法を解説。経営学者である著者のデビュー作であり、多くの読者から高い評価を受けています。
本書は、アイデアが浮かばない、会議がまとまらない、意思決定に迷うといった悩みを解決するためのフレームワーク集です。70以上の手法が掲載されており、個人やチームで活用可能です。内容は問題発見、市場分析、課題解決、戦略立案、業務改善、組織マネジメント、情報共有に関するフレームワークを含み、使い方や活用のヒントも提供されています。すべてのフレームには記入例があり、PowerPointテンプレートとしても利用できます。
ビジネスフレームワークが図解で学べる。誰もが知っているビジネスでも実際にビジネスモデルは分からないことが多い。この書籍のビジネスフレームワークを一通り頭に叩き込んでおくことで色んなケースに応用が効く。
この書籍は、月に30分の1対1ミーティングを通じて、社員の自発的な行動や持続的なやる気を引き出し、離職を防ぐ方法を紹介しています。著者は、働きがいのある会社での実績を基に、対話の重要性や信頼構築、成長支援の具体的な手法を解説しています。1対1ミーティングの実践方法や質問例も提供されており、組織変革を促進するためのノウハウが詰まっています。著者は組織人事コンサルタントの世古詞一氏です。
本書は、ダイレクトリクルーティングを活用したスカウト採用の手法を、プロの視点から解説した指南書です。中途・新卒採用担当者や経営者向けに、成功するためのテクニックやノウハウを紹介し、特にエンジニア採用に関する具体的なアドバイスも提供しています。著者は株式会社VOLLECTの代表で、500社以上のスカウト採用支援実績を持つ中島大志氏です。
著者の青野慶久は、サイボウズを「社員が辞めない変な会社」に変えるために奮闘し、多様性を重視した組織作りを進めました。彼は、各社員が自分らしく働ける環境を整えるために、柔軟な人事制度を導入。離職率を大幅に低下させ、クラウド化を進めるなど、会社の成長を実現しました。本書では、その取り組みの過程や成果について詳述されています。
災害・危機発生時の職員の役割と行動 組織と法制度上の課題 被災自治体職員が抱える課題 災害時の応援自治体職員の課題と展望 危機管理における官民の連携 試案 大規模災害時における被災市町村への人的支援 「組織と人」に関する防災・復興法制の現状と課題 自治体職員の惨事ストレス 災害時のパニックと心理的ショック
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドブックで、ビジネス部門や情報システム、現場の人々に向けて、仮説検証とアジャイル開発を基にした基本的な知識を提供します。DXの成功には、戦略と現場活動の一致が重要で、その体制や進め方を提案します。DXを進める4つの段階(業務のデジタル化、スキルのトランスフォーメーション、ビジネスのトランスフォーメーション、組織のトランスフォーメーション)を詳述し、関連するキーワードや具体的な構成も示しています。著者は、実践的な経験を持つ専門家です。
本書『組織が変わる』は、著者が職場の問題を解消するための新しい対話手法「2 on 2」を提案し、組織の慢性疾患に対する具体的な解決策を提供します。読者からは高評価を受けており、自分や相手の視点が変わることや、悩みを共有できるようになることが効能として挙げられています。著者は経営戦略や組織論の専門家で、カウンセリング手法を取り入れたアプローチを通じて、職場の活気を取り戻す方法を示しています。
このビジネス書は、多様性を取り入れた組織が成功する理由を探求し、致命的な失敗を未然に防ぎ生産性を高めるための組織改革の方法を提示しています。著者マシュー・サイドは、革新を促す要素やコミュニケーションの重要性について考察し、具体的な事例を通じて読者に考えさせる内容となっています。シリーズは好評を博し、さまざまなメディアで紹介されています。
本書は、ビッグデータとAIを活用した「ピープルアナリティクス」が日本企業の人材マネジメントに与える影響を解説しています。内容は、ピープルアナリティクスの定義やその効果、データ活用の視点、人事システムの再構築、分析技術と実務、運用組織の構築、将来の展望に分かれています。また、実際の企業事例も紹介されており、データドリブン型の人事への変換を促進する内容となっています。著者は、HRテクノロジー分野の専門家であり、国内での普及活動にも力を入れています。
本書は、急成長中の採用・人事業務代行会社の社長が、ベンチャー企業や中小企業向けに「本当にほしい人材」を集めるための実践的メソッドを解説しています。著者は350社以上の採用活動を支援し、自社も急成長を遂げた経験を基に、中途採用の戦略を紹介。具体的には、採用広報、スカウト文の作成、面接方法など、戦略的なアプローチが必要であると強調し、採用に悩む企業に有益な手法を提供しています。
ミンツバーグ教授による組織論の集大成が、半世紀の研究を基にアップデートされ、初めて邦訳された本書は、経営者や研究者に広く読まれてきた未訳の名著です。内容は組織の再検討やデザインの基本要素、さまざまな組織形態についての分析を含んでいます。著者は、組織管理やマネジャー育成に焦点を当てた経営学の巨匠です。
この書籍は、AI時代における人事戦略の新たな方向性を示すもので、著者バーナード・マーがデータを活用した人事の重要性を強調しています。内容は、データ・ドリブン人事戦略の概念から始まり、インテリジェントHRへの進化、採用、従業員エンゲージメント、パフォーマンスマネジメントなど多岐にわたるトピックを扱っています。翻訳は中原孝子が担当し、日本の人事プロフェッショナルの変革を促すことを目的としています。著者はビジネス界で広く認識されている専門家であり、さまざまな企業や政府機関に対して戦略アドバイザーとして活躍しています。
管理問題の発生と展開 管理の構造と発展 ヒトの管理をめぐる変遷 人的資源管理としての日本型雇用とその変容 企業内教育訓練・能力開発の課題 労働時間管理の変化と働く者のニーズ 賃金管理と処遇問題 多様な紛争解決システムと労働組合 日本型人的資源管理の行方
プロマネにとって本当に大事なことを教えてあげる!ヘタレな新米プロマネと凄腕女性メンターが倒産間近のシステム開発会社を救うストーリー。 第1章 人事管理システム(中規模)の開発(プロジェクトの各工程で、プロマネのやるべきことを把握する プロジェクトを黒字にする裏技を身につける クライアントからの予算の引き出し方と、決済の流れを理解する 業務に良いインパクトを与えるシステムを納品する クライアントに「決めさせる」テクニック) 第2章 顧客管理システム(大規模)の開発(要件が決まらない時は、視点を変えて情報を集める 爆弾を隠すユーザーたちを見つける 予算のバッファを把握して、引き際を明示する イレギュラー処理のシステム化の判断は、業務の理解から始まる) 第3章 倉庫管理システム(大規模)の開発(必要な情報を引き出すために駆け引きする ディープな情報は取捨選択して使う 自分の常識でプランを決めつけない 想定しないことが起きることを想定する)
本書は、現代社会におけるソフトウェアの重要性と、その不具合や不正行為がもたらす影響を踏まえ、ソフトウェア開発者やマネージャーに対して「規律、基準、倫理」の重要性を教え、堅牢で対障害性のあるソフトウェアの構築を促す内容です。目次には、テスト駆動開発や生産性、品質、倫理に関するテーマが含まれています。
この書籍は、ビジネススキルだけではなく、組織を効果的に動かすための「Deep Skill」の重要性を説いています。著者は4000人以上のビジネスマンを観察し、組織力学や人間心理を活用する方法を紹介。信頼資産の構築、戦略的な人間関係の形成、権力の動かし方、人間力の向上など、実践的な技術を解説しています。著者は企業の新規事業創出を支援するコンサルタントであり、組織内での成功には深いスキルが不可欠であると強調しています。
著者がエンジニアリングにおける課題解決のための思考整理法やメンタリング手法を解説する本です。コミュニケーションの不確実性、技術的負債、経営陣とエンジニア間の認識のずれを解消する方法について詳しく述べています。若手を育成し、成長する組織を設計・運営するための実践的なアプローチが紹介されています。著者は技術と経営の接続に関する豊富な経験を持つCTOです。
本書は、非暴力コミュニケーション(NVC)の手法を通じて、対話を促進し暴力や対立を排除する方法を紹介しています。評価や決めつけを避け、自分の感情や必要を理解し、それを相手に伝えることで、より豊かな人間関係を築くことができます。NVCは、観察、感情の認識、必要の明確化、具体的な要求の4つの要素に基づいており、世界中で多くの人に読まれています。また、ビジネスシーンでも注目され、紛争解決の方法が新たに追加されています。著者はマーシャル・ローゼンバーグ氏で、NVCの提唱者です。
本書は、日本企業が米軍のような「軍隊型組織」から脱却し、現場の自由な動きを促進するための新しい経営戦略を提案しています。著者は、米軍の「機動戦」から学び、PDCAサイクルを超えたOODAループやミッション・コマンド、クリティカル・インテリジェンスを活用して、柔軟で効果的な組織運営を実現する方法を解説しています。具体的な事例や理論を通じて、ビジネス環境での生き残りを目指す戦略を示しています。
本書は、Netflixの共同創業者リード・ヘイスティングスが、同社の成功の要因である「脱ルール」カルチャーを明らかにします。このカルチャーは、社員の意思決定を尊重し、不要な規則を排除することで、最高のパフォーマンスを引き出すことを目指しています。NetflixはDVD郵送レンタルから始まり、動画配信サービスやコンテンツ制作を通じて、190カ国で2億人の会員を獲得しました。著者は、企業文化の研究者エリン・メイヤーと共に、成功の秘密を探ります。
ネットフリックスの会社の制度について学べる。いかに素晴らしいタレントを集めているのか?優秀な人々にとって優秀な制度とはどんな制度なのか?について学べる。多くの企業がネットフリックスのようにふるまって上手くいくとは思えないが一つの制度設計の参考にはなる。
この書籍は、幸福や喜び、楽しさといった現象を心理学や社会学、文化人類学などの視点から総合的に解明した作品です。目次には、幸福の再来や意識の分析、生活の質、フローの条件、身体や思考のフロー、仕事におけるフロー、孤独と人間関係、カオスへの対応、意味の構成が含まれています。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
この書籍は、リーダーシップは特定の人に与えられるものではなく、日々の小さな行動を通じて信頼し合うチームを作れることを説いています。著者はNetscape、Apple、Slackでの経験を基に、リーダーに必要な振る舞いを30のエッセイで紹介し、具体的なマネジメントのテーマ(傾聴、信頼関係の構築、仕事の任せ方など)について解説しています。著者はシリコンバレーのエンジニアリングリーダーで、現在Appleに勤務しています。
本書『組織開発入門』は、組織開発の理論と実践を体系的に解説した公式テキストです。経営者やマネジャー、一般社員向けに、組織開発の基礎知識を100のポイントで図解し、わかりやすく学べる内容となっています。著者の坪谷邦生は20年以上の人事経験を持ち、実践的な視点から組織に「血を通わせる」ことを目指しています。検定試験もあり、知識の定着やキャリアアップを図ることが可能です。
本書は、ソフトウェアエンジニアが技術力を活かしてテクニカルリーダーシップを発揮し、エンジニアリング職でのキャリアを築くための指針を提供します。スタッフエンジニアになるために必要なスキルや具体的な行動、仕事を楽しむ方法についての疑問に答えることが目的です。内容は2部構成で、第1部ではスタッフエンジニアの役割を解説し、第2部では現役スタッフエンジニアのインタビューを通じて実像を紹介しています。特に日本語版では、日本人スタッフエンジニアのインタビューも追加されています。
本書は、企業が時代に適応するための能力を高める方法を提案しています。効率と柔軟性のジレンマを探求し、管理者に効率を少し落とすことで効果を大幅に向上させる方法を教えます。「ゆとり」の重要性を説明し、効率追求の中での適切な「ゆとり」の活用法を提案しています。目次は「ゆとり」「本当に速く仕事をするには」「変化と成長」「リスクとリスク管理」の4部構成です。著者はコンサルタントのトム・デマルコ氏で、国際的に生産性や企業文化に関する活動を行っています。
この文章は、書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、ソフトウェアエンジニアリングやシステムデザインに関する様々なテーマが列挙されており、著者は滝沢徹、牧野祐子、富澤昇の3名で、それぞれの学歴と現在の職業が記載されています。
本書『「学習する組織」入門』は、MIT発の組織開発メソッド「学習する組織」を紹介する入門書で、日本の第一人者が実践的に解説しています。変化に柔軟に対応し、持続的成長を実現するための「ダブル・ループ学習」や5つの「ディシプリン」を通じて、個人と組織の成長を促進します。各章には事例や演習が含まれ、実践上の課題にも触れながら、未来の組織とリーダーシップについても考察しています。著者は組織開発の専門家であり、広範な知見を基にした内容となっています。
本書では、企業が創造性を発揮し「0から1」を生み出すために、特別な才能がなくても可能なプロセスを探求しています。著者は「共観」という概念を提唱し、他者の視点を理解することで創造性を促進する方法を解説しています。特に「多元的視点取得」に焦点を当て、組織内での視点の多様性が創造的成果に寄与することを示しています。多様な人材を集めるだけではなく、視点の多様性が重要であるとし、実践的な工夫も提案しています。最終的に、組織としての創造性を追求するための指針を提供しています。
本書は、日本企業の組織開発に関する実践的な方法論を提示しています。著者の加藤雅則は、17年の経験を基に、経営トップから始め、各層の合意を生み出し、当事者主体で進めることの重要性を強調しています。業績は好調でも、組織の一体感や信頼度が低下している現状を踏まえ、効果的な組織変革を促すための対話や実践例を紹介しています。
本書は、リファラル採用の成功法則を提唱する鈴木貴史氏によるもので、企業が競争を避け、採用活動の効率を高める方法を紹介しています。著者は、日本でリファラル採用の概念を創出した起業家であり、企業が従来の手法に頼らず、社員を巻き込んだ採用戦略を実現することを目指しています。具体的には、企業ブランドへの共感を呼び起こし、採用コストを削減し、従業員のエンゲージメントを高めることが可能です。本書は、戦わない採用の実践方法や成功事例を通じて、企業の変革を促す内容となっています。
「シェアド・リーダーシップ」は、職場の全員が必要に応じてリーダーシップを発揮することを指し、モチベーションや業績を向上させる効果がある。この理論は、マネージャーだけでなく全メンバーがリーダーシップを発揮できることを前提にしており、その仕組みや効果、実現方法を最新の理論や研究を基に解説している。著者は立教大学の石川淳教授で、リーダーシップの重要性やシェアド・リーダーシップの特徴、効果、誤解、実践方法について詳述している。
この書籍は、心理学、脳科学、集団力学に基づいたリーダーシップの新しい教科書であり、人間関係の課題を克服するための知恵が詰まっています。著者は、妬みの管理、チームの温度差の解消、隠れた不満の活用、権力との賢い付き合い、信頼関係の修復など、具体的なリーダーシップの手法を提案しています。全てのリーダーにとって必読の内容です。著者は立命館大学の教授で、産業・組織心理学を専門としています。
この文章は、組織行動学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、組織行動学の基本、個人の行動、集団の行動、組織のシステムに関する4つの部に分かれており、それぞれのテーマを扱っています。著者はスティーブン・P・ロビンスと高木晴夫であり、ロビンスは組織行動学のベストセラー教科書作者で、国内外の大学で広く使用されています。高木は慶應義塾大学の教授で、経営学の専門家です。
日本軍がなぜ戦争に負けてしまったのかを分析し、それを元に日本の組織における問題点を浮き彫りにしている書籍。責任の所在の曖昧さと、臨機応変に対応できない官僚主義が蔓延した日本組織は危機的状況において力を発揮できない。少々歴史の話は冗長だが一読する価値のある書籍。
この文章は、ウィリアム・ブリッジズの著作に関する目次と著者情報を紹介しています。内容は、人生におけるトランジション(変化)の重要性を論じたもので、変化が必要な時期やその過程、そして新たな始まりについて触れています。著者のブリッジズは、トランジションに関するセミナーを開き、組織の変化を支援するコンサルタントとしても活躍しています。また、倉光修と小林哲郎のプロフィールも含まれており、両者は教育学と臨床心理学の専門家です。
この書籍は、チームの心理的安全性を高める方法について解説しています。著者の石井遼介は、心理的安全性がチームのパフォーマンス向上に寄与することを強調し、リーダーシップや行動分析、言葉の使い方が重要であると述べています。具体的には、心理的柔軟性を培う方法や、行動を変えるためのフレームワークを紹介しています。全体を通じて、健全な衝突がチーム力を引き上げることを示唆しています。
この書籍は、テレワークとジョブ型の時代において、自ら考え行動変容する人材を育成するための47の成長マネジメント技術を紹介しています。内容は、研修の効果や形態の変化、キャリア自律の重要性、社員の自律的な行動を促す具体策、そして上司と部下の関わり方に焦点を当てています。著者の永谷研一は行動科学の専門家であり、ITを活用した教育サービスの先駆者です。
この書籍は、成功する人々がどのような行動を通じてリーダーシップやマネジメントを発揮するのか、またそれらの行動がどのような欲求に基づいているのかを探求しています。内容は、組織と個人の成功に必要な「たったひとつのこと」に焦点を当て、マネジャーとリーダーの違いや、成功を持続させるための重要な考え方について述べています。著者のマーカス・バッキンガムは、リーダーシップとマネジメントに関する専門家であり、翻訳者の加賀山卓朗がその著作を日本語に翻訳しています。
本書では、ビジネスパーソンが「自分の弱さを隠す仕事」に多くのエネルギーを費やしている現状を指摘し、これを逆転させることで、より強い組織文化を築く方法を探ります。著者は「発達指向型組織(DDO)」を提唱し、メンバーが本来の自分でいることや弱点を認め合い、率直なフィードバックを行うことで成長を促す文化の重要性を説きます。成功事例として、ブリッジウォーター、デキュリオン、ネクスト・ジャンプの3社を挙げ、どのようにしてこのような組織文化を維持しつつ成果を上げているかを紹介します。最終的に、成長を促進するためには「痛み」を伴うフィードバックが必要であり、限界を克服することが現代のビジネス環境での成功につながると結論づけています。
本書は、ボランティア組織の運営や異世代交流の方法を解説しています。目次には、ボランティア組織の特質やメンバーの育成、リーダーシップに関するインタビュー、悩みの解決法などが含まれています。著者の長沼豊は、ボランティア学習や福祉教育を専門とし、多くの関連団体で役職を務めています。
本書は、2022年の年間ベストセラー第4位に選ばれた『リーダーの仮面』の続編で、全プレーヤー向けの仕事術の「型」を体系化しています。著者の安藤広大は、全国4400社以上が導入した「識学」を基に、成長する人に共通する考え方を紹介。内容は、数字を意識した思考法や行動量、確率、変数、成功の捨て方などを探求し、数値化の限界についても触れています。
立教大学の中原淳教授による『人と組織の課題解決のための7つのステップ』は、人材開発と組織開発のプロセスを科学的かつ実践的に解説した入門書です。内容は、信頼構築、データ収集、フィードバック、実践、評価などのステップを通じて、企業の人事や教育担当者、コンサルタントが経営戦略に貢献する方法を探ります。著者は人材開発と組織開発の専門家であり、実務に役立つ知識を提供しています。
日本語の「採用」と英語の「リクルートメント」の定義のちがいを手がかりに考察を展開。採用の戦略を多面的に分析した包括的研究。 日本語の「採用」と英語の「リクルートメント」の定義のちがいを手がかりに考察を展開。日本的雇用の特殊性を考慮した「採用のホィールモデル」を構築し、採用の戦略を多面的に分析した包括的研究。 人材の“Buy and Make”の新たな戦略モデル! 未曾有の人材獲得難を突破するには、新たな方法論が必要だ。分断された日本の外部労働市場と内部労働市場を「ホィール」によって結合し、繰り返しの中で採用力を高めていく。 新卒、中途、パート採用からアメリカ企業・フランス企業のタレント獲得までを網羅した総合研究。 ▼「新卒採用」への過度な偏重から脱却し、働き方改革やタレントマネジメントなど新たなパラダイム取り込んだ画期的な採用論。 ▼日本語の「採用」と英語の「リクルートメント」の定義のちがいを手がかりに考察を展開。日本的雇用の特殊性を考慮した「採用のホィールモデル」を構築し、採用の戦略を多面的に分析した包括的研究。 人口減少やデジタライゼ―ションにより、空前の「売り手市場」が発生し、いまや熾烈な人材獲得競争に勝ち抜くことが企業にとっての生命線となっている。今後、採用の戦略は、中途採用、パート採用、ときには海外でのタレント獲得も含めて立案しなければならない。その際、新卒や中途といった採用対象による分類から「攻めの採用」「守りの採用」という採用目的による分類へ、さらには外部労働市場の募集・選考プロセスに限った「小さな採用」論から、企業内部の雇用の仕組みも考慮した「大きな採用」論へと発想を切り替える必要があることを、本書では提示する。 第1章 二つの「戦略」 第2章 人材獲得競争の激化 第3章 日本企業の採用行動 第4章 採用のパターン 第5章 採用の成果 第6章 「採用のホィールモデル」の構築 第7章 「採用のホィールモデル」の検証 第8章 次世代リーダーの獲得――グローバルメーカーA社の変革事例 第9章 新卒・中途・有期雇用の採用はどう異なるのか 第10章 日本・フランス・アメリカ企業のタレント獲得 第11章 採用活動のフィードバックループ――日米企業の比較から 第12章 過去と未来 おわりに 参考文献 事項索引 人名索引
本書は、複数のプログラマが関わるプロジェクトの成功にはチームの協力が不可欠であることを強調し、著者がエンジニアとしての経験を基に「エンジニアが他人とうまくやる」ためのコツを紹介します。内容は「チーム文化の作り方」や「有害な人への対処法」など多岐にわたり、楽しい逸話を交えつつエンジニアの社会性を解説しています。
飛躍の法則
サイバーエージェント藤田さんの愛読書として名高いビジョナリー・カンパニー。偉大な会社を作る気概のある学生や経営者が読むべき書籍。1を読まずに2を読んでも問題ないが、2は偉大な企業を存続させることにフォーカスしていて1は偉大な企業を作ることにフォーカスしているのでまずは1から読むのがよいと思う。割と難解ではまらない人には全くはまらない書籍。
本書は、求人サービス「ビズリーチ」を手掛けるビジョナルの急成長の秘密を探るノンフィクションです。創業者南壮一郎氏は、楽天イーグルスでの経験から「問いを立てる力」を学び、それを活かしてビズリーチを12年で巨大スタートアップに成長させました。著名な経営者たちの教えや、挫折を乗り越えた実体験を通じて、読者は「問いの立て方」を理解し、挑戦したくなる内容になっています。
本書は、リーダーが組織内でのパワーを理解し、持続的な影響力を発揮するための洞察を提供します。人が動かされる理由や、成功するリーダーと脱線するリーダーの違い、組織の変革の可能性、パワーを手放せない理由などを探ります。内容は、パワーの理論、リーダーシップ理論、パワーの行使、パワーの委譲に分かれており、著者は経営大学院教授であり、コンサルタントとしての経験も持つ高岡明日香氏です。
本書は、有効で生産性の高い組織を作るための基本的な組織デザインの原則を解説しています。特に、仕事の分業や調整の方法に焦点を当て、組織の問題点を明らかにする手助けをします。目次には、組織形態、分業のタイプ、標準化、処理プロセス、ヒエラルキー、水平関係などのテーマが含まれています。著者は一橋大学の教授、沼上幹です。
本書は、デビッド・アレンの「GTD(Getting Things Done)」をアップグレードしたバイブルで、マルチタスクと情報過多の時代に必要な精神的スキルを身につける方法を提供します。GTDをマスターすることで、行動の明確化、集中力の向上、混乱の解消、リラックスが可能になります。内容は基本原則、ストレスフリーな環境での生産性向上、GTDの効果を体感することに焦点を当てています。著者は生産性の権威、デビッド・アレンと、プログラミング教育を手がける田口元です。
本書は「人的資本経営」について解説し、経営者や人事担当者が自社の人的資本の状態を把握し、適切に開示する方法を示しています。具体的には、理想の組織像を明確にし、調達、育成、活躍促進、維持、リスク低減の戦略を考えるための50の問いを提供。これにより、企業が健全な状態を保ちながら目的を達成するための具体的な取り組みを見つけられるように構成されています。
インテル元CEOのアンディ・グローブによる経営書が待望の復刊。シリコンバレーの経営者や起業家に影響を与え続ける本書では、マネジャーが注力すべき仕事やタイムマネジメント、意思決定のポイント、効果的なミーティングの進め方など、実践的なアドバイスが満載。著名な経営者たちからも高く評価されており、マネジメントの基本原理を学ぶための重要な一冊となっている。
アンカー・ジャパンのCEO、猿渡歩が初めて著したビジネス書が「ビジネスリーダー1万人が選ぶベストビジネス書TOPPOINT大賞2023上半期ベスト10」に選ばれました。彼は、創業9年目で売上300億円を達成した成功の秘訣を「1位思考」として紹介し、シンプルな6つの習慣を提唱しています。内容は「全体最適」「バリューを出す」「学ぶ」「因数分解」「1%にこだわる」「サボる」の習慣に分かれており、巻末には「面接を通過する10のコツ」も収録されています。
「ティール組織」に関するよくある質問
Q. 「ティール組織」の本を選ぶポイントは?
A. 「ティール組織」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「ティール組織」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで168冊の中から厳選しています。
Q. 「ティール組織」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「ティール組織」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



![『[イラスト解説]ティール組織――新しい働き方のスタイル』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51DS9KN-D7L._SL500_.jpg)
![『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UB6ayAOaL._SL500_.jpg)








![『反脆弱性[上]――不確実な世界を生き延びる唯一の考え方』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ll7SlzI1L._SL500_.jpg)
























































































![『ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ] やっかいな人のマネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー―EIシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51yw5J+NnOL._SL500_.jpg)





























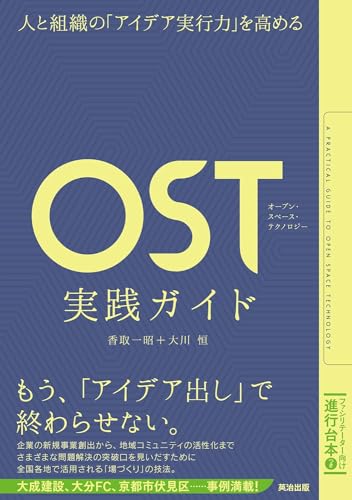













![『U理論[第二版]――過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41QQFrSRRpL._SL500_.jpg)



![『経営者になるためのノート ([テキスト])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/21OIhMFu5cS._SL500_.jpg)
















![『[新訳]HOLACRACY(ホラクラシー)――人と組織の創造性がめぐりだすチームデザイン』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/514xGi-yOcL._SL500_.jpg)












