【2025年】「組織論」のおすすめ 本 162選!人気ランキング
- 学習する組織――システム思考で未来を創造する
- はじめての経営組織論 (有斐閣ストゥディア)
- 他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論
- だから僕たちは、組織を変えていける —やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた【ビジネス書グランプリ2023「マネジメント部門賞」受賞!】
- 組織開発の探究 理論に学び、実践に活かす
- よくわかる組織論 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)
- ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現
- 恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす
- 人を動かす 文庫版
- 知識創造企業(新装版)
この書籍は、組織の定義や目的、コミュニケーションなどの基本的な概念から、組織の構造やプロセス、環境への適応までを学ぶための標準テキストです。著者は高尾義明教授で、組織が私たちの生活に与える影響を考察し、学術的な視点からその本質を探求します。目次は、組織の基本的な見方、構造とプロセス、変動する環境における組織の3部構成になっています。
本書は、組織内の問題を「わかりあえないこと」から解決するためのアプローチを提案しています。著者は、対話を通じて新たな関係性を築くことが重要であるとし、組織の複雑な問題に対する実践的な手法を示しています。特に、ナラティヴ・アプローチを用いて、権力や対立を超えたコミュニケーションを促進する方法を解説。経営学者である著者のデビュー作であり、多くの読者から高い評価を受けています。
本書は、組織の変革を目指す人々に向けたガイドで、特に「関係性」を重視したアプローチを提案しています。近年の「デジタルシフト」「ソーシャルシフト」「ライフシフト」により、従来の管理主義が通用しなくなった中で、組織が抱える問題を解決する方法を示します。著者は、組織のメンバー一人ひとりが関係性、思考、行動を改善することで、全体を変えていけると主張しています。また、実践的なメソッドや成功事例を通じて、読者に希望を与える内容となっています。著者の講演も多くの企業から依頼されており、実績も評価されています。
本書は、組織開発の重要性とその歴史、哲学、手法の変遷を探求し、組織の健全さや効果性を高めるためのコミュニケーション活性化を目的としています。著者たちは、組織開発が単なる手法ではなく、計画的かつ協働的なプロセスであることを強調し、実践事例を通じてその具体的なアプローチを示します。また、組織開発と人材開発の相互関係についても論じています。全体を通じて、組織開発の未来に関する対談も行われています。
この書籍は、組織論に関する包括的な内容を扱っており、以下の5つの部に分かれています。第1部では組織の基本とダイナミクス、第2部では個人のモチベーションやキャリア、ストレス、第3部では集団のダイナミクスやリーダーシップ、意思決定、第4部では組織デザイン、文化、戦略、第5部では組織変革や危機管理、人的資源管理について論じています。著者は愛知学院大学の田尾雅夫教授です。
「ティール」は、従来の組織モデルを超えた新しいマネジメント手法を提案する本で、上下関係や売上目標がない組織のあり方を示しています。著者フレデリック・ラルーは、組織の進化を色で表現し、進化型組織の構造や文化を探求。多くの業界で変化が進んでおり、ポスト資本主義時代における新たな組織モデルとして注目されています。この本は、組織の変革や成果を追求するための実践的なガイドとして評価されています。
著者エイミー・C・エドモンドソンの最新刊『チームが機能するとはどういうことか』では、Googleの研究で注目された「心理的安全性」の重要性が探求されています。著者は、ピクサー、フォルクスワーゲン、福島原発などの事例を通じて、対人関係の不安が組織に与える影響と、それを克服するための組織のあり方を描いています。書籍は心理的安全性の力、職場での実践、フィアレスな組織の構築に関する内容で構成されています。
『知識創造企業』は、1995年に発表された経営学の重要な著作で、日本企業のイノベーションメカニズムを解明し、知識の重要性を示した。著者たちは、個々の暗黙知を組織の形式知に変換するプロセスを「知識創造理論」や「SECIモデル」として提唱し、世界中で影響を与えた。四半世紀ぶりに新装版として再登場し、知識創造の理論や実践的提言を含む内容が整理されている。著者は、野中郁次郎、竹内弘高、梅本勝博の三人で、各々が経営学やナレッジマネジメントの権威として知られている。
立教大学の中原淳教授による『人と組織の課題解決のための7つのステップ』は、人材開発と組織開発のプロセスを科学的かつ実践的に解説した入門書です。内容は、信頼構築、データ収集、フィードバック、実践、評価などのステップを通じて、企業の人事や教育担当者、コンサルタントが経営戦略に貢献する方法を探ります。著者は人材開発と組織開発の専門家であり、実務に役立つ知識を提供しています。
本書は、マッキンゼーが20年間のケーススタディとハーバード・ビジネス・レビューの記事を基に、組織を効果的に率いるための10の法則を提唱しています。デジタル化やグローバリゼーションに対応するためのマネジメント手法を解説し、意思決定の質やスピードを向上させる方法、競争力のある組織文化の構築、優れた人材の育成と定着について具体的な実践法を紹介しています。リーダーやマネジャーにとって必携の一冊です。
現代社会の基本的要素となっている組織の行動・変化のメカニズムをダイナミックな視点から解明。好評の初版に最小限の改訂を行う。 現代社会の基本的要素としての組織を対象とし,その行動・変化のメカニズムをダイナミックな視点から解明する。従来の学説史中心・分析レベル順に構成されたテキストと異なり,組織と環境とのマクロレベルの関係性を重視。好評の初版に必要最小限の改訂を行う。 第Ⅰ部 組織論の基礎 第1章 なぜ組織理論を学ぶのか/第2章 組織の定義/第3章 組織均衡と組織論の枠組み 第Ⅱ部 環境に組み込まれた組織 第4章 組織の戦略的選択/第5章 組織への環境からのコントロール/第6章 組織目標と組織有効性 第Ⅲ部 組織構造のデザインと組織文化 第7章 組織構造と組織デザイン/第8章 組織デザインに影響を与える変数/第9章 組織文化 第Ⅳ部 組織内プロセス 第10章 モチべーション/第11章 マネジメント・コントロール/第12章 コンフリクト・マネジメント 第Ⅴ部 組織のダイナミクス 第13章 組織の長期適応と発展過程/第14章 組織学習と変革/第15章 組織の戦略的変革 第Ⅵ部 非営利組織 第16章 公的セクターの組織/第17章 ヒューマン・サービスの組織/第18章 ボランタリー組織/終 章 未来の組織と組織論の未来
本書『組織開発入門』は、組織開発の理論と実践を体系的に解説した公式テキストです。経営者やマネジャー、一般社員向けに、組織開発の基礎知識を100のポイントで図解し、わかりやすく学べる内容となっています。著者の坪谷邦生は20年以上の人事経験を持ち、実践的な視点から組織に「血を通わせる」ことを目指しています。検定試験もあり、知識の定着やキャリアアップを図ることが可能です。
インテル元CEOのアンディ・グローブによる経営書が待望の復刊。シリコンバレーの経営者や起業家に影響を与え続ける本書では、マネジャーが注力すべき仕事やタイムマネジメント、意思決定のポイント、効果的なミーティングの進め方など、実践的なアドバイスが満載。著名な経営者たちからも高く評価されており、マネジメントの基本原理を学ぶための重要な一冊となっている。
本書は、世界の主要な経営理論30を網羅した解説書で、ビジネスパーソンにとっての思考の軸を提供します。経営学の複雑なメカニズムを解明し、イノベーションや人材育成、M&Aなどに関する理論をわかりやすくまとめており、学生や研究者にも役立つ内容となっています。著者は早稲田大学の教授で、経営理論の重要性を強調しています。
本書では、強力なチームを作るための要素を探求しています。チームの文化はメンバーの個性ではなく、彼らの行動によって形成されると述べています。内容は、安全な環境の構築、弱さの共有、共通の目標の重要性に焦点を当てており、具体的な事例や実験を通じて、効果的なチームワークの方法を紹介しています。著者はダニエル・コイルで、ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家です。
管理問題の発生と展開 管理の構造と発展 ヒトの管理をめぐる変遷 人的資源管理としての日本型雇用とその変容 企業内教育訓練・能力開発の課題 労働時間管理の変化と働く者のニーズ 賃金管理と処遇問題 多様な紛争解決システムと労働組合 日本型人的資源管理の行方
人が組織においてさまざまな行動をとる,その理由とは。シチュエーションを想像し,我がこととして考えながら学べるテキスト。 やる気が出ないこともあれば,仕事に没頭することもある。もめごとが起きるかと思えば,1+1が3にも4にもなったりする。人が組織においてさまざまな行動をとる,その理由とは。実際のシチュエーションを想像し,我がこととして考えながら学べるテキスト。 序 章 組織行動論を「学ぶ」ということ 第1部 組織の中の個人 第1章 行動を駆動する力:ワーク・モチベーション 第2章 やりがいの設計:職務設計と内発的動機づけ 第3章 やる気を引き出す評価:公平理論と組織的公正 第4章 組織とのよき出会い:採用の意思決定 第5章 組織に馴染むプロセス:組織社会化 第6章 組織と個人の約束:心理的契約と離職モデル 第2部 集団と組織のマネジメント 第7章 マネジャーの仕事:モチベーション論とリーダーの行動 第8章 組織を動かすリーダー:変革型・カリスマ型リーダーシップ 第9章 集団の持つ力:グループ・ダイナミクス 第10章 もめごとを乗り越える:コンフリクトと交渉 第11章 貢献を引き出す関わり合い:文化とコミットメント 第12章 「私らしさ」と「我々らしさ」:組織アイデンティティ 終 章 組織行動論を「使う」ということ
本書は、防衛大学校で20年以上経営学を教えてきた著者が、ビジネス教養としての経営学を分かりやすく解説する入門書です。経営学の基本概念やセオリーを具体例を通して説明し、仕事や人生での選択に役立つ知識を提供します。内容は、費用対効果、意思決定、価格戦略、競争戦略、組織、リーダーシップなど多岐にわたり、実生活に応用できるマネジメントリテラシーを身につけることができます。著者は、経営学の重要性を学生に伝えることに注力しており、実生活の経験を基にしたアプローチが特徴です。
著者の青野慶久は、サイボウズを「社員が辞めない変な会社」に変えるために奮闘し、多様性を重視した組織作りを進めました。彼は、各社員が自分らしく働ける環境を整えるために、柔軟な人事制度を導入。離職率を大幅に低下させ、クラウド化を進めるなど、会社の成長を実現しました。本書では、その取り組みの過程や成果について詳述されています。
ミンツバーグ教授による組織論の集大成が、半世紀の研究を基にアップデートされ、初めて邦訳された本書は、経営者や研究者に広く読まれてきた未訳の名著です。内容は組織の再検討やデザインの基本要素、さまざまな組織形態についての分析を含んでいます。著者は、組織管理やマネジャー育成に焦点を当てた経営学の巨匠です。
本書は、Googleの人事トップが採用、育成、評価の仕組みを初めて詳しく語るもので、企業がクリエイティブな働き方を実現するための原理を公開しています。著者はGoogleの人事システムを設計した責任者であり、同社の成功の秘訣や、優秀な人材の選び方、評価方法、チーム作りのノウハウを解説。古い働き方に悩むリーダーや若手に向けて、未来の働き方の指針を提供する内容です。
飛躍の法則
サイバーエージェント藤田さんの愛読書として名高いビジョナリー・カンパニー。偉大な会社を作る気概のある学生や経営者が読むべき書籍。1を読まずに2を読んでも問題ないが、2は偉大な企業を存続させることにフォーカスしていて1は偉大な企業を作ることにフォーカスしているのでまずは1から読むのがよいと思う。割と難解ではまらない人には全くはまらない書籍。
ハーバード・ビジネス・スクールの名誉教授ジョン・P・コッターによる著書は、コロナ禍以降の変化する世界において、組織が進化する方法を探る内容です。人間の性質が変革やイノベーションに与える影響を考察し、成功する企業とそうでない企業の違いを解明します。脳科学の知見を取り入れ、リーダーシップや組織文化の変革、デジタル・トランスフォーメーションの成功法則などを提案し、ニューノーマルの時代を生き抜くための指針を示します。
本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。
日本軍がなぜ戦争に負けてしまったのかを分析し、それを元に日本の組織における問題点を浮き彫りにしている書籍。責任の所在の曖昧さと、臨機応変に対応できない官僚主義が蔓延した日本組織は危機的状況において力を発揮できない。少々歴史の話は冗長だが一読する価値のある書籍。
本書は、企業組織における問題の発生メカニズムや解決策、組織の違いについて体系的に解説したテキストです。第1部では組織の問題(ジレンマや信頼の形成など)を探求し、第2部では問題解決のための組織設計や関係性を論じ、第3部では意思決定プロセスや企業文化、リーダーシップの違いを明らかにします。著者は経営学の専門家たちで、事例分析や理論を通じて組織に関する深い洞察を提供しています。
本書『「学習する組織」入門』は、MIT発の組織開発メソッド「学習する組織」を紹介する入門書で、日本の第一人者が実践的に解説しています。変化に柔軟に対応し、持続的成長を実現するための「ダブル・ループ学習」や5つの「ディシプリン」を通じて、個人と組織の成長を促進します。各章には事例や演習が含まれ、実践上の課題にも触れながら、未来の組織とリーダーシップについても考察しています。著者は組織開発の専門家であり、広範な知見を基にした内容となっています。
本書は、日本企業の組織開発に関する実践的な方法論を提示しています。著者の加藤雅則は、17年の経験を基に、経営トップから始め、各層の合意を生み出し、当事者主体で進めることの重要性を強調しています。業績は好調でも、組織の一体感や信頼度が低下している現状を踏まえ、効果的な組織変革を促すための対話や実践例を紹介しています。
この文章は、組織行動学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、組織行動学の基本、個人の行動、集団の行動、組織のシステムに関する4つの部に分かれており、それぞれのテーマを扱っています。著者はスティーブン・P・ロビンスと高木晴夫であり、ロビンスは組織行動学のベストセラー教科書作者で、国内外の大学で広く使用されています。高木は慶應義塾大学の教授で、経営学の専門家です。
経営学のレリバンスを問いつつ,組織行動論の主立った理論・尺度を紹介する好評上級テキスト。3つの新章を増補し,さらに充実。 経営学のレリバンスを問いつつ,組織行動論の主立った理論・測定尺度を紹介する好評上級テキスト。リサーチ・プラクティス・ギャップを学説史的に掘り下げた第2章,実証主義とは何かを概説した第6章,実践家との共同研究の成功要因を探る第15章を増補。 第1部 組織行動論の立ち位置 第1章 組織行動研究の俯瞰⑴:現状把握のための横断的レビュー/第2章 組織行動研究の俯瞰⑵:学説史的レビュー/第3章 「知っている」ということについて/第4章 概念と理論/第5章 組織行動の測定/第6章 実証主義とは何か 第2部 組織行動論は何をどう測るか 第7章 リーダーシップ/第8章 組織の中の公正/第9章 欲求とモティベーション/第10章 人的資本,社会関係資本,心理的資本/第11章 組織と個人の心理的契約/第12章 組織コミットメント,ジョブ・エンベデッドネス/第13章 組織行動の成果 第3部 組織行動論の充実のために 第14章 2つの知のサイクルが共振する共同研究/第15章 共同研究が成功する条件/第16章 共同研究の鍵を握る共同イベント/第17章 組織行動研究のレリバンスを求めて
著者の勅使川原真衣が、職場での「傷つき」をテーマにした本を紹介しています。彼は、能力主義の限界に気づき、組織開発の新たな方向性を探る重要な作品を提案しています。内容は、職場での傷つきの実態やそのメカニズム、能力主義を超える方法、実践的なアプローチについて論じています。具体的な事例を通じて、個人や企業が職場環境を改善する方法を示唆しています。
本書は、効果的なリーダーシップを身につけ、組織に良い影響を与える方法を探る内容です。リーダーが自身を変容させ、組織を成長させるための具体的な実践方法を定量・定性の調査に基づいて解説しています。リーダーシップの拡大を通じて組織を発展させることを目指し、反応的なリーダーシップから創造的なリーダーシップへの変容を促進する方法も紹介されています。著者はリーダーシップ育成に豊富な経験を持つ井上奈緒氏です。
この書籍は、ビッグデータに活用できる統計的学習をRを用いて実践的に学ぶための内容で、初心者にも理解しやすく解説されています。主なトピックには、線形回帰、分類、リサンプリング法、モデル選択、木に基づく方法、サポートベクターマシン、教師なし学習などが含まれています。著者は南カリフォルニア大学と神戸大学で教鞭を執る専門家です。
この書籍は、9つの学びのスタイル(経験、想像、内省、分析、思考、決定、行動、開始、バランス)を通じて、自分自身の学びのスタイルを理解し、長所と短所を把握する方法を紹介しています。これにより、人間関係やグループ活動に役立つヒントを得ることができます。また、経験から学ぶことで人生を変える可能性についても触れています。著者は経験学習の専門家であり、効率的なチーム作りや学習する組織の推進に取り組んでいます。
この書籍は、チームの心理的安全性を高める方法について解説しています。著者の石井遼介は、心理的安全性がチームのパフォーマンス向上に寄与することを強調し、リーダーシップや行動分析、言葉の使い方が重要であると述べています。具体的には、心理的柔軟性を培う方法や、行動を変えるためのフレームワークを紹介しています。全体を通じて、健全な衝突がチーム力を引き上げることを示唆しています。
本書『ファクトフルネス』は、データに基づいた世界の見方を提案し、誤った思い込みから解放されることの重要性を説いています。著者ハンス・ロスリングは、教育、貧困、環境、エネルギー、人口問題などのテーマを通じて、正しい世界の理解を促進します。2020年には多くのビジネス書ランキングで1位を獲得し、100万部以上の売上を記録。ビル・ゲイツやオバマ元大統領も絶賛し、特に教育機関での普及が進んでいます。クイズ形式で誤解を解消し、ファクトフルネスを実践する方法も紹介されています。
自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。
本書は、リーダーシップ教育の専門家ジョン・P・コッターが、ハーバード・ビジネス・スクールや大手企業での講座を基に、リーダーシップの核心を解説しています。内容はリーダーシップとマネジメントの違いや企業変革の課題、権力と影響力の扱い方など多岐にわたり、最新の翻訳と2章の追加がなされています。著者はリーダーシップの実現を支援するコッター・インターナショナルの創設者であり、他の著者もリーダーシップや組織開発の専門家です。
著しい発展を遂げている分野である産業組織論の好評テキスト、待望の改訂版。ミクロ経済学の道具を産業分析にどう応用するのか。 著しい発展を遂げている分野である産業組織論の好評テキスト、待望の改訂版。ミクロ経済学の道具を産業分析にどう応用するのか。 著しい発展を遂げている分野である産業組織論の好評テキスト、待望の改訂版。ミクロ経済学の道具を産業分析にどう応用するのか。 第1章 産業分析の基本概念 1.コストとその決定要因 2.需要、競争そして経済厚生 3.市場構造、企業行動そして市場の成果 第2章 企業の機能と構造 1.企業とは 2.企業の利潤と企業資産 3.企業の利潤最大化行動 4.企業の範囲と規模の決定要因 補論 インセンティブ契約の理論 第3章 独占企業の行動とその経済的帰結 1.独占の生じる環境 2.独占企業の行動 3.独占の非効率性 4.価格差別 5.買い手独占 6.品質の選択 7.反独占政策 補論 独占企業による複数の品質の選択 第4章 垂直統合と垂直的制限 1.垂直統合の決定要因 2.垂直的制限 3.二重限界性と垂直的な外部性 補論 垂直的な取引における交渉力と不完備契約の投資への影響 第5章 競争の形態とその経済効果──価格競争と数量競争 1.数量競争:クールノー・ナッシュ均衡と戦略的代替性 2.2段階の数量競争:シュタッケルベルグ・モデルと部分ゲーム完全均衡 3.クレディブル・コミットメント 4.価格競争と戦略的補完性 5.市場集中度の指標と合併ガイドライン 補論1 水平的製品差別化モデル 補論2 市場集中度と利潤率の理論的関係 第6章 参入の経済効果 1.参入の経済効果 2.過剰な参入があるか 3.自然独占とコンテスタブルな市場 4.独占的競争と製品の多様性 補論 クールノー競争における参入の効果 第7章 カルテル、合併・買収及び事業提携 1.カルテルの種類と経済的影響 2.カルテルの限界 3.カルテルの維持可能性 ── トリガー戦略からの分析 4.カルテルの規制と事業提携 5.合併・買収の効率性 補論 アウトサイダーのカルテルへの影響 第8章 情報の非対称性と企業行動 1.品質についての情報の非対称性の影響:逆選択とモラルハザード 2.企業の戦略:シグナリング、ブランド名の確立及びスクリーニング 3.価格に関する情報の非対称性の影響:企業の市場支配力 4.広告と情報 5.企業の広告支出の決定要因 6.広告と経済厚生 7.政府の規制(情報開示、製造物責任、品質認定) 第9章 企業の戦略的行動 1.戦略的な行動とその類型 2.参入阻止とクレディブル・コミットメント 3.略奪価格 4.ライバルのコストを引き上げる戦略 5.企業の戦略的な行動と政府の対応 補論 排他的契約による参入阻止 第10章 技術進歩と研究開発競争 1.技術進歩と研究開発 2.技術の利用と研究開発へのインセンティブ 3.技術機会、研究開発と市場構造 4.研究開発と経済厚生 5.産業のライフサイクルとイノベーション 第11章 知的財産制度、共同研究開発とネットワーク外部性 1.知的財産制度と技術革新 2.技術のライセンス 3.共同研究開発 4.ネットワーク外部性と企業間競争 第12章 貿易と直接投資 1.国境と経済活動 2.貿易の原因と影響 3.貿易政策 4.直接投資の原因 5.直接投資の影響と政策 第13章 規制とその改革 1.自然独占規制の目的 2.自然独占の価格規制の理論 3.規制の実態と評価 4.規制の緩和と改革 補論 情報の非対称性の下での最適な価格規制
本書は「世界のフラット化」に対する先進国の人々、特に子供たちの教育や社会システムの必要性について論じている。具体的には、インドや中国との競争に勝ち抜くために必要な教育や企業の対応策を提案し、フラット化の真の可能性を探る。著者はトーマス・フリードマンで、彼の経験を基にした洞察が展開される。
著者はリクルートやライフネット生命、オープンハウスでの人事・採用責任者としての経験をもとに、人材マネジメントの重要性を説いています。書籍では、人事の役割や採用計画、面接の質向上、優秀な人材の確保などについての理論を解説しています。著者、曽和利光は人材研究所の代表であり、豊富な人事経験を持つ専門家です。
この文章は、半世紀にわたって読み継がれてきた名著論文を収録した書籍の内容を紹介しています。目次には、モチベーションの定義や新しい理論、知識労働者の心理、MBOの失敗、ピグマリオン・マネジメント、モチベーショナル・リーダーの条件、理想の職場の作り方、Y理論の限界、本物のリーダーの特性などが含まれています。
ベンチャー企業が設立当初は順調に見えたが、2年後に業績不振で37歳のCEOが解任され、57歳の女性が新CEOに就任する。彼女はチームワークの重要性を理解し、会社の変革を実現する能力を持っている。著者は経営コンサルタントのパトリック・レンシオーニで、200ページにわたる物語を通じてそのプロセスとノウハウを紹介している。
本書は、機械学習の発展を背景にした統計的学習に関する教科書「The Elements of Statistical Learning」の全訳です。機械学習は人工知能の一分野から発展し、統計学と密接に関連しています。内容は、教師あり学習の基礎からニューラルネットワークやサポートベクトルマシン、ブースティングなどの高度な手法まで幅広くカバーしており、情報技術を学ぶ大学生や研究者に最適です。著者は各分野の専門家で構成されています。
ポジティブ心理学は、心の病の治療ではなく、健康な人が「より幸せになる方法」を探求する分野です。マーティン・セリグマンが1998年に提唱し、現在は世界中で研究が進んでいます。本書では、ポジティブ心理学を日常生活に活かす方法を解説しており、目次には幸せの条件やストレスの役割、日本人向けのアプローチ、実践的なエクササイズ、社会への応用が含まれています。著者は慶應義塾大学の前野隆司教授で、幸福学など幅広い分野を研究しています。
この文章は、経済学者シュンペーターの「イノベーション」理論について紹介しています。シュンペーターは、単なるアイディアよりも既存の要素を組み合わせて新たな価値を生み出すことが重要だと説いており、スティーブ・ジョブズのiPhoneの成功がその例として挙げられています。シュンペーターの理論は、現代の経営者にとっても有用であり、変革は内から起こるべきであると強調しています。著者はシュンペーターの思想を学ぶことの重要性を訴えています。
本書では、チームビルディング研修の効果を紹介し、退職者が皆無になった企業や業績が向上した事例を通じて、職場の風土改善の方法を解説しています。具体的な研修手法やコミュニケーションのコツを学ぶことで、社員が働きやすく、楽しい職場環境を作ることが可能であると述べています。著者は、チーム力を高める専門家であり、実績として多くの企業で研修を行い、成功を収めています。
この書籍は、企業やビジネスマンにとって重要な「組織力」を高める方法について解説しています。内容は「遂行能力」と「戦略能力」を軸に、組織力の定義、発揮できない理由、効果的な組織の構築方法、リーダーシップについての章で構成されています。著者は、経営再生や組織改革に関わる専門家で、実践的な知見を提供しています。
2008年に発売した「ギスギスした人間関係をまーるくする心理学」で人間関係のTA(Transactional Analysis)を身近なものにした著者が、職場や家庭でどうTAを生かして組織のモヤモヤ、イライラをすっきりさせるかをたくさんの事例を入れながらわかりやすく紹介しております。 TA組織理論は人が集まってできるグループや組織といった集団に存在する問題の発見や、それらの解決・改善策を考えるための診断・分析ツールになります。組織の健康診断のチェックリスト、フレイムワークとして活用するための方法がこの本に詰まっています。 はじめに 1章 TA組織理論と組織診断 2章 組織の仕組みを分析・診断する「グループ・ストラクチャー」(Group Structure) 3章 組織の機能を分析・診断する「グループ・ダイナミックス」(Group Dynamics) 4章 TA組織理論の活用場面集 付録 TA心理学きほんのき あとがき 参考文献
本書は、渋沢栄一や三菱、三井、住友の起業家たちが逆境を乗り越えた事例を通じて、どん底でもチャンスがあることを伝えています。歴史は繰り返され、経営の原則は変わらないため、過去の成功者から学ぶ意義があります。著者は、胆力、危機管理力、先見力を持つ11人の経営者のエピソードを通じて、現代のビジネスに役立つ知恵を提供しています。読者は彼らの失敗や苦難から危機突破力を学び、ビジネスのヒントを得ることができるでしょう。
この書籍は、経営学の基礎と応用を解説し、SWOT分析や新規事業の成功見込みなどの重要な概念を紹介しています。マーケティング、事業創造、経営組織、組織行動、事業戦略、財務・会計、現代企業の各論点を扱い、ビジネススキルを向上させるための視点を提供します。著者は経営学者で、オンラインスクールを運営し、経営学の普及に努めています。
本書は、現代社会におけるソフトウェアの重要性と、その不具合や不正行為がもたらす影響を踏まえ、ソフトウェア開発者やマネージャーに対して「規律、基準、倫理」の重要性を教え、堅牢で対障害性のあるソフトウェアの構築を促す内容です。目次には、テスト駆動開発や生産性、品質、倫理に関するテーマが含まれています。
本書は、個人や組織が変革を実現するための「免疫マップ」という手法を紹介しています。著者たちは、変化を望みながらも行動に移せない理由は「意志の弱さ」ではなく、変化と防御の間での葛藤にあると述べています。発達心理学と教育学の専門家が30年の研究を基に、変革のプロセスや成功事例を通じて、効果的な改革の方法を示しています。リーダーや組織メンバーに向けた実践的な手引きとなる一冊です。
この書籍は、ドラッカーが提唱した「究極の質問」に基づく自己評価法を通じて、仕事と人生を変える方法を探求しています。著者フランシス・ヘッセルバインは、著名人の知見やミレニアル世代に向けた新しいコラムを加えた改訂版を提供しています。主要な内容は、ミッション、顧客、価値、成果、計画に関する5つの重要な質問を通じて組織の変革を促すものです。ドラッカーは経営思想家として多くのマネジメント概念を生み出し、影響を与えました。
この書籍は、一般的なマネジャーの日常に焦点を当て、偉大なリーダーの成功や失敗とは異なる、実務的なマネジメントの重要性を探求しています。著者ヘンリー・ミンツバーグは、マネジメントの本質や多様性、ジレンマ、効果的なマネジメントの方法について考察し、実践的な視点からマネジメント論を展開しています。
この書籍は、経営学の基本理論を具体的なトピックスや最新事例を通じて学ぶ初学者向けのテキストです。内容は企業経営や経営戦略、多角化戦略、国際化、組織マネジメントなど多岐にわたり、著者は経営学の専門家である加護野忠男と吉村典久です。
この書籍は、マネジメントの巨人ピーター・ドラッカーの名言を集めた愛蔵版で、仕事と人生を変えるヒントを提供します。著者のドラッカーは、ビジネス界での影響力を持つ思想家であり、数々のマネジメント理念を生み出しました。共著者には、ドラッカーの長年の友人であるジョゼフ・マチャレロと、ものつくり大学名誉教授の上田惇生がいます。
本書『経営12カ条』は、経営者が何を考え、どのように行動すべきかを示す稲盛和夫氏の経営哲学をまとめたものです。経営をシンプルな原理原則に基づいて理解し、実践することの重要性が強調されています。具体的には、事業の目的を明確にし、目標設定、強い願望、努力、経費管理、値決め、意志の強さ、創造性、誠実さ、ポジティブな心構えなど、12の基本的な条項が紹介されています。これらは京セラやKDDI、日本航空などでの実績を基にしており、経営の実践に役立つチェックリストや補講も収録されています。著者は稲盛和夫氏で、経営における原理原則を通じて、誰もが経営を成功させるための指針を提供しています。
本書は、人気マンガ『宇宙兄弟』を通じて自分の強みを理解し、他人の個性を把握する方法を解説しています。著者は「FFS理論」を用いて、登場人物の心理や行動を分析し、自己理解、他者理解、組織理解の観点から具体的な事例を挙げています。読者は、自分に似たキャラクターを知ることで、強みを活かし、効果的なチーム作りを学ぶことができます。
跡を絶たない談合・カルテル、M&A、廉価販売、下請支配、技術革新、グローバル化など、現実社会の問題を見据えつつ、日本の競争政策の今後を考えるために必要な基礎理論と実例を示す。法学部生、実務家にもわかりやすい「経済学用語解説」付き。 序論-競争はなぜ重要か 競争政策の生い立ちと仕組み 共謀と協調 コンテスタブル市場理論と参入阻止戦略 一般集中と独占的状態 合併・買収(M&A) 垂直的取引制限-再販を中心に 競争手段としての廉売 下請取引と優越的地位 技術革新と知的財産権 公益事業における競争 グローバル化する競争政策
本書は、地方企業から有名企業、ベンチャーまでの成功事例を通じて、採用担当者が欲しい人材を惹きつける具体策を提供します。内容には、魅力的な求人コピーの作成法、SNSや人事ブログの活用、エージェントとの関係構築、リファラル採用の成功法、効果的な面接技術、候補者の本音を探る質問、内定辞退を防ぐための失敗例などが含まれています。多様な企業の事例を交えながら、採用担当者の悩みを解決するヒントが多数紹介されています。
「ギブ&テイク」は、人間の行動を「与える人」「自分優先の人」「バランスを考える人」の3つのタイプに分類し、それぞれの特徴と可能性を分析する著作です。著者アダム・グラントは、与えることが成功につながる新しい常識を提唱し、成功するギバーの行動戦略や人脈の重要性を論じています。彼はペンシルベニア大学ウォートン校の最年少終身教授であり、組織心理学の専門家です。
日本文化論に関する重要かつ基本的なキーワードと代表的な古典を,歴史的・相対的な視点からわかりやすく解説した書。 日本文化論に関する重要かつ基本的なキーワードと代表的な古典を,わかりやすく解説。「両立型」という概念を軸に,歴史的・相対的な視点から選び出された125のキーワードで,日本文化を読み解く。日本文化論を学ぶ学生,日本に関心をもつ留学生にお勧め。 総 論 第1章 日本文化のキーワード 第2章 古典を通して「日本」を読む 第3章 日本文化はどう論じられてきたか 第4章 日本文化論はイデオロギーか 第5章 外から見た「日本」 引用・参考文献一覧 事項索引 人名索引
本書は、経営学部の学生が抱く「経営学の意義」への疑問を解消し、経営学の各分野(戦略、組織、会計、マーケティング)の相互関係を説明します。経営学の全体像や経済価値の追求、不確実性への対応についても触れ、学生や社会人の学び直しに役立つ内容となっています。著者は一橋大学の教授であり、経営学の専門家です。
主要トピックの理論と測定尺度を概観。経営学は実践の役に立つかを問い,実践家とともに理解を深め合える共同研究を模索する。 2020年現在の組織行動論領域において,学術的に確立された理論と測定尺度を概観。実際の経営現象を測定・研究する際,実践家とともに理解を深め合える協働を求め,経営学にとってのレリバンスとは何かを真摯に問う。研究者,ビジネスパーソン必読の書。 第1部 組織行動論の立ち位置 第1章 組織行動研究の俯瞰 第2章 「知っている」ということについて 第3章 概念と理論 第4章 組織行動の測定 第2部 組織行動論は何をどう測るか 第5章 リーダーシップ 第6章 組織の中の公正 第7章 欲求とモティベーション 第8章 人的資本,社会関係資本,心理的資本 第9章 組織と個人の心理的契約 第10章 組織コミットメント,ジョブ・エンベデッドネス 第11章 組織行動の成果 第3部 組織行動論の充実のために 第12章 2つの知のサイクルが共振する共同研究 第13章 組織行動研究のレリバンスを求めて
本書は、情報化時代における推薦システムの重要性とその実装方法について解説しています。推薦システムの概要、UI/UX、アルゴリズム、実システムへの組み込み、評価を網羅し、著者たちの実務経験をもとに成功事例や失敗事例を紹介します。実際の業務に役立つ内容を重視しており、推薦システムの導入を検討するウェブサービスに向けた入門書です。著者はそれぞれ推薦システムに関する研究や開発の経験を持っています。
この書籍は、「アンラーン」という概念を通じて、過去の学びや思い込みを手放し、新たな成長を促す技術を紹介しています。アンラーンは、学びの効率を高めるために必要なプロセスであり、特に変化に対応するために重要です。具体的には、固定化した思考を解きほぐし、日々の小さなアンラーンを習慣化する方法が提案されています。また、アンラーンを阻む壁を理解し、それを乗り越えるためのヒントも提供されています。最終的には、アンラーンを人生やキャリアの武器として活用することが強調されています。
リソース・ベースト・ビュー(経営資源に基づく戦略論)の第一人者J.バーニーの戦略論テキスト、待望の日本上陸。 第1章 戦略とは何か(戦略という概念の定義 戦略と企業ミッション ほか) 第2章 パフォーマンスとは何か(戦略の定義とパフォーマンスとの関係 パフォーマンス概念の定義 ほか) 第3章 脅威の分析(SCPモデル 脅威を分析する5つの競争要因モデル ほか) 第4章 機会の分析(業界構造と機会 戦略グループによる脅威と機会の分析 ほか) 第5章 企業の強みと弱み-リソース・ベースト・ビュー(企業の強み・弱みに関するこれまでの研究 組織の強みと弱みの分析 ほか)
この書籍は、「聞くこと」の重要性を強調し、他人の話をしっかりと聞くことで得られる新しい知識や友情の深まりについて述べています。著者は、会話を通じて孤独を感じず、信頼関係を築く方法を提案しています。また、相手の話を聞くことで自分自身の考えを広げることができるとし、聞くことが人生をより豊かにする鍵であるとしています。
本書は、ソフトウェアエンジニアが技術力を活かしてテクニカルリーダーシップを発揮し、エンジニアリング職でのキャリアを築くための指針を提供します。スタッフエンジニアになるために必要なスキルや具体的な行動、仕事を楽しむ方法についての疑問に答えることが目的です。内容は2部構成で、第1部ではスタッフエンジニアの役割を解説し、第2部では現役スタッフエンジニアのインタビューを通じて実像を紹介しています。特に日本語版では、日本人スタッフエンジニアのインタビューも追加されています。
産業・組織心理学の定番書が近年の動向を反映して改訂され、公認心理師科目にも対応。内容は採用、モチベーション、コミュニケーション、仕事の安全性、ストレス、キャリア発展、リーダーシップ、人事評価、消費者行動など多岐にわたる。最新トピックも加えられ、働き方改革に寄与する内容となっている。著者は九州大学や立命館大学の教授たち。
本書は、2022年の年間ベストセラー第4位に選ばれた『リーダーの仮面』の続編で、全プレーヤー向けの仕事術の「型」を体系化しています。著者の安藤広大は、全国4400社以上が導入した「識学」を基に、成長する人に共通する考え方を紹介。内容は、数字を意識した思考法や行動量、確率、変数、成功の捨て方などを探求し、数値化の限界についても触れています。
理由はわからないけど、最近社員のモチベーションが落ちている。そんな悩みを対話のチカラで解決する、組織開発の入門書。 本書は、近年注目が高まっている「組織開発」の入門書です。これまでの類書にはない、実践レベルにまで落とし込んだ一冊となります。監修・解説は、組織開発の第一人者であり、ベストセラー『入門 組織開発』(光文社)などの著者である中村和彦教授(南山大学)。著者3名は、 長年企業などで組織開発のプロフェッショナルとして定評があります。コロナ禍での業態変化や、在宅勤務の増加などに伴い、これまでにはないほど組織の在り方が変化した結果、より一層チームワークが重視されることとなりました。チームのモチベーションが下がっている、なんだか最近業績が落ちてきている、人がどんどん辞めていくなど、いまいち言語化できないチームや組織の悩みに向き合い、解決に近づけるのが組織開発です。本書は、そんな組織開発のはじめ方を、成功事例を踏まえてやさしく教える一冊です。中小企業、大企業、地域コミュニティなどの7つの事例を通して、バラバラになってしまった組織を生き返らせるために立ち上がった人々が、それぞれに抱えた悩みを解決するために起こしたアクションとそのポイントを紹介・解説します。この本を読めば、明日からチームの人たちと対話をしたくなるはず。組織開発はそこから始まります。
本書は、日本におけるコーチングの第一人者による、理論と実践を網羅した決定版のコーチング本です。組織の課題解決に向けて、なぜ行動が伴わないのか、戦略が徹底されないのかを探求し、コーチングがその突破口となることを示しています。内容は図解で分かりやすくまとめられ、組織のパフォーマンス向上や変革を目指すリーダーにとって必読の入門書です。
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドブックで、ビジネス部門や情報システム、現場の人々に向けて、仮説検証とアジャイル開発を基にした基本的な知識を提供します。DXの成功には、戦略と現場活動の一致が重要で、その体制や進め方を提案します。DXを進める4つの段階(業務のデジタル化、スキルのトランスフォーメーション、ビジネスのトランスフォーメーション、組織のトランスフォーメーション)を詳述し、関連するキーワードや具体的な構成も示しています。著者は、実践的な経験を持つ専門家です。
ダボス会議Young Global Leadersに選ばれたカリスマヘッドハンターが教える、「若くして活躍する人」に共通する「戦略的人脈作り」のノウハウ。 第1部 なぜ今、「人脈」なのか?-人脈の重要性再考と将来仮説(ハーバードで学んだ人脈の哲学と人脈スパイラル・モデル 人脈のパラダイム・シフトに伴う戦略的人脈構築の必要性) 第2部 人脈スパイラルと人脈レイヤー-抜擢される人の戦略的人脈構築モデル(自分にタグをつける コンテンツを作る 仲間を広げる 自分情報を流通させる チャンスを積極的に取りに行く) 第3部 人脈スパイラルの先には何があるのか?-戦略的人脈構築の本当の目的
本書は、現代の経営学が管理から自律へと変化する中で、事業創造と組織デザインの重要性を学ぶための入門書です。内容は、事業デザイン(イノベーション、ビジネスモデル、顧客ターゲティング、収益モデル、サプライチェーン、経営資源分析、財務理解など)と組織デザイン(採用、モチベーション、リーダーシップ、組織構造、チームマネジメント、知識創造など)の二部構成で、実践的な問題解決に役立つ知識を提供します。著者は、経営学の専門家たちです。
ジャック・ウェルチは、GEを時価総額世界No.1企業に成長させた「20世紀最高の経営者」として知られています。本書では、彼がビジネス成功のための具体的なノウハウを提供しており、人材採用や上司への対処法、キャリアの築き方など、幅広いテーマを扱っています。経営者から新入社員まで、あらゆる職位の人に役立つ実践的アドバイスが満載のビジネス指南書です。
本書では、企業が創造性を発揮し「0から1」を生み出すために、特別な才能がなくても可能なプロセスを探求しています。著者は「共観」という概念を提唱し、他者の視点を理解することで創造性を促進する方法を解説しています。特に「多元的視点取得」に焦点を当て、組織内での視点の多様性が創造的成果に寄与することを示しています。多様な人材を集めるだけではなく、視点の多様性が重要であるとし、実践的な工夫も提案しています。最終的に、組織としての創造性を追求するための指針を提供しています。
本書は、変化に適応する戦略の重要性を説いており、失敗から学ぶ試行錯誤型のアプローチが成功をもたらすと主張しています。具体的な実例として、イラク戦争の米軍、グラミン銀行、Googleの成長などが挙げられ、組織や個人が変革を遂げるための「アダプト」戦略が紹介されています。著者は、行動し、失敗し、適応することで不確実な世界を生き抜く方法を提案しています。
この書籍は「ザッソウ」という概念を提唱し、雑談と相談を組み合わせることで人間関係を強化し、心理的安全性を高める重要性を説いています。著者は、効率化だけを追求するのではなく、雑談を通じてチームビルディングを促進することが成果を上げる鍵であると主張しています。書籍は、ザッソウの効果や実践方法、職場環境の整え方について具体的に解説しており、リーダーの姿勢やコミュニケーション術も取り上げています。著者は株式会社ソニックガーデンの創業者であり、先進的な経営手法を実践しています。
本書『組織が変わる』は、著者が職場の問題を解消するための新しい対話手法「2 on 2」を提案し、組織の慢性疾患に対する具体的な解決策を提供します。読者からは高評価を受けており、自分や相手の視点が変わることや、悩みを共有できるようになることが効能として挙げられています。著者は経営戦略や組織論の専門家で、カウンセリング手法を取り入れたアプローチを通じて、職場の活気を取り戻す方法を示しています。
組織におけるアイデンティティのマネジメント 経営戦略論における知識の成長 非正社員の雇用形態の多様化と人材ポートフォリオ グローバル人材教育への貢献 次世代につなぐ法人〈コーポレート〉ガバナンス改革 日本の株式発行市場の現状 日本における「企業-社会関係」の課題 批判理論的方法論に基づく会計の学際的考察についての概説 監査制度の正統性の補修戦略における課題 簿記における縦割り教育 新製品の普及にみる消費者間ネットワークの影響 消費者ベースの「おもてなし」マーケティング戦略 不調和に基づいた広告におけるユーモア表現の方法
この書籍は、企業変革の成功と失敗の要因を探り、八段階の変革プロセスを提示しています。具体的には、危機意識の醸成、連帯の強化、ビジョンと戦略の策定などが含まれます。また、変革の意義や未来の企業像、リーダーシップと継続的学習についても論じています。著者は早稲田大学の教授で、経歴には多様な企業での経験があります。
この書籍は、わずか20年で時価総額1兆円に達した小さな業務スーパーの成功戦略を紹介している。著者は、零細企業でも競争に勝てる方法を探求し、緻密な戦略と実践を通じて、2店舗から「圧倒的な存在」へと成長した過程を描いている。目次には、独自のフォーマットや超高収益モデル、商品戦略、フランチャイズビジネスの秘密などが含まれており、企業規模に関係なく成功するための教訓がまとめられている。著者はビジネス分野を専門とする文筆家である。
本書は、星野佳路社長の経験を基にしたビジネスの教科書的アプローチを紹介しています。内容は以下の5部構成です。第1部では、古典的な本の重要性と徹底的な理解の必要性を説く。第2部では、独自の戦略で旅館やリゾートを再生する方法を示す。第3部では、マーケティングの基本を実行することで大きな変化をもたらすことを強調。第4部では、リーダーシップの重要性とビジョンの提示による社員の結束を述べる。第5部では、未経験者を育てることで成長を促す方法を解説しています。著者は中沢康彦で、経済学部卒業後、新聞社記者を経て現在は日経トップリーダーの副編集長です。
本書は、ダイレクトリクルーティングを活用したスカウト採用の手法を、プロの視点から解説した指南書です。中途・新卒採用担当者や経営者向けに、成功するためのテクニックやノウハウを紹介し、特にエンジニア採用に関する具体的なアドバイスも提供しています。著者は株式会社VOLLECTの代表で、500社以上のスカウト採用支援実績を持つ中島大志氏です。
本書は、IT界のカリスマ経営者であるジェイソン・フリードとデイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソンによるビジネスの心得を示すもので、失敗から学ばず、効率的に働くことや競争を意識することの重要性を説いています。内容は、会社の文化やプロモーション、人材採用など多岐にわたり、イラストも収録された完全版です。著者は「37signals」の創業者であり、成功したビジネスソフト「ベースキャンプ」を運営しています。
身近で魅力的なケースを用いて、楽しく経営学を学ぶ初版以来好評を博してきたテキスト。ケースを大幅に入れ替えた待望の第3版。 ケースと理論や概念の両方を楽しく学ぶ,初版以来好評を博してきたテキスト。従来の魅力はそのままに,メルカリ,サムスン,リクルート,アップル,良品計画ほか現代の若者に身近なケースを用いるなど,大幅な改訂を行った。はじめて経営学や企業にふれる人に。 序 章 この本の内容と利用の仕方 第Ⅰ部 企業とは何か 第1章 企業の誕生:メルカリの設立と成長/第2章 会社とは誰のものか:カゴメのファン株主拡大戦略 第Ⅱ部 企業のストラテジー 第3章 環境・組織・戦略:フォードとGM/第4章 競争戦略の基本型:日本マクドナルドとモスバーガー/第5章 事業のリストラクチャリングと組織改革:GEの企業革新/第6章 ビジネス・システムの革新とIoT:コマツのビジネス・システム/第7章 破壊的技術への対応と新規事業創造:富士フイルムの企業変貌/第8章 プラットフォーム・ビジネス:アップルのApp Store/第9章 グローバル戦略:サムスン電子の統合と適応のジレンマ 第Ⅲ部 企業のマネジメント 第10章 経営理念と組織文化:リクルート社の起業家精神と組織文化/第11章 人材のマネジメント:総合商社双日の人材マネジメント/第12章 日本的生産システム:トヨタ生産方式/第13章 成熟市場における商品開発:サントリーのハイボール・ストロングゼロの開発/第14章 環境変化のマーケティング活動の変革:良品計画における危機とその克服 第Ⅳ部 企業の社会性 第15章 ビジネスの倫理:JR西日本の新幹線台車亀裂トラブル/第16章 ソーシャル・ビジネス:アスヘノキボウによる協働のまちづくり 第Ⅴ部 学びのステップ 第17章 キーワードの理解からレポート作成・発表まで:T教授のオフィスアワー日誌
本書は、成長企業が「ヒト」に注力する時代において、組織人事コンサルタントが提唱する新しい組織論とリーダーの役割について述べています。リーダーが「ヒト」への投資を重視し、組織改革を進めるための7つの処方箋を提示しています。著者はリンクアンドモチベーションの麻野耕司氏で、組織の課題を解決するための具体的なアプローチを紹介しています。
「初心者に向けた分りやすさ」と「研究者に向けた詳細な分析」を両立、基本から応用まであらゆる理論を網羅した決定版。 第6章 垂直統合(垂直統合の定義 垂直統合の経済価値 ほか) 第7章 コスト・リーダーシップ(コスト・リーダーシップの定義 コスト・リーダーシップの経済価値 ほか) 第8章 製品差別化(製品差別化の定義 製品差別化の経済価値 ほか) 第9章 柔軟性(戦略の選択におけるリスクと不確実性の概念 柔軟性とオプションの定義 ほか) 第10章 暗黙的談合(協調問題 談合の定義 ほか)
「シェアド・リーダーシップ」は、職場の全員が必要に応じてリーダーシップを発揮することを指し、モチベーションや業績を向上させる効果がある。この理論は、マネージャーだけでなく全メンバーがリーダーシップを発揮できることを前提にしており、その仕組みや効果、実現方法を最新の理論や研究を基に解説している。著者は立教大学の石川淳教授で、リーダーシップの重要性やシェアド・リーダーシップの特徴、効果、誤解、実践方法について詳述している。
ユニクロは「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」という信念のもと、フリースやヒートテックなどのヒット商品を生み出し、グローバルに挑戦し続けています。しかし、その裏には大企業病の克服や後継者育成、海外展開、社内改革への不断の努力がありました。本書では、経営トップがその変革の過程を明かし、世界一を目指す組織作りの秘訣を探ります。著者はファーストリテイリングの柳井正氏で、彼の経歴やユニクロの成長の歴史も紹介されています。
この書籍は、市場環境と企業内部の視点を融合し、競争優位をコンピタンスの観点から解説しています。目次には、戦略的提携、多角化戦略、合併買収(M&A)、国際戦略などが含まれ、それぞれの経済価値や組織体制について詳述されています。著者は、経営戦略理論の権威であるジェイ・B・バーニーと、慶応義塾大学の岡田正大で、両者は戦略コンサルティングの経験も持っています。
この書籍は、競争戦略、業績評価システム、バランス・スコアカード、リスク・マネジメント、内部統制システムを統合し、戦略を利益に結びつける実践的な経営論を提案しています。内容は、戦略実行の基盤、業績評価システムの構築、利益目標と戦略達成のための方法論に分かれており、著者はハーバード・ビジネススクールのロバート・サイモンズと一橋大学の伊藤邦雄です。
本書は、組織論を「道具として使える知識」として位置づけ、チームや職場を効果的に活用し、目標を達成する方法を解説した教科書です。前提知識がなくても理解できる内容で、学生や社会人に向けて、組織の構造やリーダーシップ、意思決定などの基本概念を紹介しています。著者は神戸大学の鈴木竜太教授で、組織行動論の専門家です。
世界的大企業の元管理職が、オフィスを持たないベンチャーに転職──。驚きと戸惑いを越え「最強チーム」を作り上げるまでの奮闘記。 世界的企業の元管理職が、オフィスのないベンチャーで最強チームづくりに挑む。パソコン一台あれば世界中すべてが仕事場となり、いつでも好きな時間に働くことができる。夢の「リモートオフィス」は本当に機能するのか? 社員管理術は、コミュニケーション術は、信頼関係を作り上げるには、危機管理術は、プロジェクトが暗礁に乗り上げたら――その虚実を体験的に検証。「仕事の未来」を考える。
本書は、企業が直面する変革のジレンマや構造的無能化のメカニズムを解明し、改革を成功に導くための実践的なアドバイスを提供する一冊です。著者は、経営学者の宇田川元一氏で、企業の持続的発展に向けた課題を多様な事例や学術的知見を基に掘り下げています。経営層から現場リーダーまで、組織全体が自ら考え行動する力を回復する方法を探求しています。
この書籍は、心理的安全性が高い企業が増えていることを背景に、社員の幸福度を高め、効果的なチームを形成する方法について探求しています。著者の山藤賢と山田博は、「感じる経営」や「美しい経営」の概念を通じて、森から学ぶ経営のアプローチを提案しています。目次では、経営の本質や公正さ、喜びの経営などが扱われており、森のような組織づくりを目指す内容となっています。
この書籍は、成功する人々がどのような行動を通じてリーダーシップやマネジメントを発揮するのか、またそれらの行動がどのような欲求に基づいているのかを探求しています。内容は、組織と個人の成功に必要な「たったひとつのこと」に焦点を当て、マネジャーとリーダーの違いや、成功を持続させるための重要な考え方について述べています。著者のマーカス・バッキンガムは、リーダーシップとマネジメントに関する専門家であり、翻訳者の加賀山卓朗がその著作を日本語に翻訳しています。
シリーズ累計約100万部。多くのリーダーが学んだ不朽の名著が一新! ゼロから改革モデルを創造し、不振事業を再生する 危機の現場「死の谷」から独自の戦略を生み出した男。 その軌跡と「実戦」手法を初めて全公開する。 シリーズ累計約100万部、不朽の名著が一新! 独創的な戦略経営者は日本でいかに生まれたか? 経営者の仕事で最も難しいのは不振事業の再生である。約50年間、その難業に取り組み続けてきたのが著者だ。 常に現場で「戦略」と「論理に支えられた腕力」を磨き続け、日本企業の再生手法を編み出すことに尽くしてきた。しかし、その軌跡のすべては明らかにされていなかった。 シリーズ第1巻の本書では、まだ何ものでもない20代の若者が経営者を志して歩き始め、30代早々に「戦略経営者」の初陣に撃って出る。 そこで味わった成功と失敗を赤裸々に描いた唯一無二の経営戦略書+人生論である。 ――戦略プロフェッショナルを目指す、すべての人々に捧げる。 【目次】 プロローグ 第一章 経営者になりたい 第一節 自立の志 第二節 戦略コンサルタントへの挑戦 第二章 国際レベル人材を目指す 第一節 太陽がいっぱいの大学キャンパス 第二節 米国経営者の懐に入る 第三章 経営者への第一ステップ 第一節 人生の岐路に立つ 第二節 「全体俯瞰」で見る 第四章 決断と行動の時 第五章 飛躍への妙案 第六章 本陣を直撃せよ 第七章 戦いに勝つ 第八章 戦略経営者の初陣を終える エピローグ 世界の事業革新のメガトレンド 論考八~九 ※本書は、ダイヤモンド社より2013年6月に刊行された『戦略プロフェッショナル[増補改訂版]』を全面的にノンフィクションの書き下ろしに改め、さらに新章をはじめ大幅な加筆をした決定版です。 経営者の仕事で最も難しいのは不振事業の再生である。それに挑み続けた独創的な戦略経営者はいかに生まれたのか?危機の現場「死の谷」から新たな経営者像を確立した男がその軌跡と「実戦」手法を初めて全公開する。 プロローグ 第一章 経営者になりたい 第一節 自立の志 アマチュアからの旅立ち/出会い頭の衝突、運命的な出会い 三枝匡の経営ノート1 世界の事業革新のメガトレンド 論考一~三 第二節 戦略コンサルタントへの挑戦 戦略経営の黎明期/不意に来た転機/初めての米国、世界最高水準の頭脳たち/欧州出張と英語プレゼン/新たな葛藤を抱える etc. 第二章 国際レベル人材を目指す 第一節 太陽がいっぱいの大学キャンパス 結婚と妻の言葉/アベグレンに言い出せるのか/人生の恩/「戦略経営者」を目指すetc. 第二節 米国経営者の懐に入る トップダウンプロジェクト/米国南部の工場/母の死/米国企業は「意外に大ざっぱ」 三枝匡の経営ノート2 世界の事業革新のメガトレンド 論考四~七 第三章 経営者への第一ステップ 第一節 人生の岐路に立つ 日米合弁会社の経営不振/合弁会社は引退ローテーション人事/危険なポジション etc. 三枝匡の経営ノート3 競争戦略と内部組織の一元改革 第二節 「全体俯瞰」で見る パラシュート降下/社内の雰囲気をつかむ/トップへの昇進/米国側の勝手なご都合人事/プロテック事業部に乗り込む/プロテックの市場ポジション/ジュピターの技術優位 etc. 三枝匡の経営ノート4 事業の勝ち負け――ライフサイクルと事業の成長ルート 第四章 決断と行動の時 売れない理由の犯人捜し/「価格決定のロジック」を問う/営業体制の強み、弱み/競合相手の力を探る/アクションの時間軸を見定める etc. 三枝匡の経営ノート5 あなたの選択肢は何か 第五章 飛躍への妙案 しばしの沈黙/売れないはずがない/我々は何を売っているのか?/従来思考を壊す/考える集団へ/組織の葛藤 etc. 三枝匡の経営ノート6 戦略はシンプルか 第六章 本陣を直撃せよ 最後の一押し/攻撃目標はどこか/市場をセグメントする/セグメントの魅力度をつける/最終のセグメンテーション/行動進捗を追いかける/いよいよ戦闘開始 三枝匡の経営ノート7 絞りと集中 第七章 戦いに勝つ 勝ちどき/強敵の出現/マーケットシェアを逆転する/プロテック事業部の成長 etc. 第八章 戦略経営者の初陣を終える 全社改革への取り組み/米国親会社の新たな要求/合弁解消へのセットアップ/山は動いた/戦略系と人間系のバランス/ミッションの完了/挑戦は続く エピローグ 三枝匡の経営ノート8 世界の事業革新のメガトレンド 論考八~九
全てのビジネスパーソンに読んで欲しい名著!戦略やロジカルシンキングを謳ったコンサル本は多いが、それを読んで学んでも結局実務に活かしづらい気がする。そんな中この書籍はストーリ形式でどうやってコンサルの考え方をビジネスに活かしていくか学べる良本。
『世界最高のチーム グーグル流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法』は、グーグルの「プロジェクト・アリストテレス」を基に、効果的なチームづくりの原則を解説しています。特に「心理的安全性」の重要性が強調され、チーム内の愚痴やもめごとを建設的な議論に変えることで生産性を向上させる方法が提案されています。また、多様性を活かした集合知や、良質なコミュニケーションの重要性も述べられています。著者は、実験主義や柔軟な思考を通じて、最少の人数で最大の成果を上げるための具体的なアプローチを示しています。
インセンティブ制度の歴史 知識への投資 法律家以外の人のための知的財産法入門 知的財産権制度の設計 巨人の肩の上に立って:累積的発明の保護 ライセンス、ジョイントベンチャー、競争政策 権利の施行と訴訟 現代の発明における民間部門と公的部門の連携 研究開発と特許の価値 ネットワークとネットワーク効果 グローバル経済と技術革新 日本のイノベーションとインセンティブ
「組織論」に関するよくある質問
Q. 「組織論」の本を選ぶポイントは?
A. 「組織論」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「組織論」本は?
A. 当サイトのランキングでは『学習する組織――システム思考で未来を創造する』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで162冊の中から厳選しています。
Q. 「組織論」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「組織論」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



















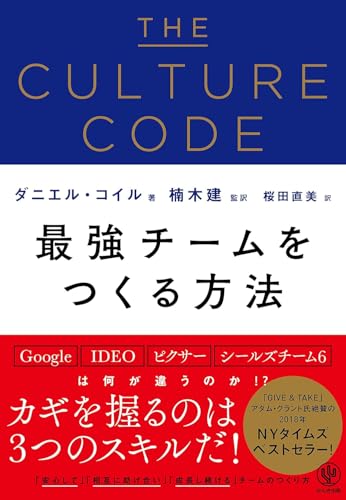






![『経営者になるためのノート ([テキスト])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/21OIhMFu5cS._SL500_.jpg)






![『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UB6ayAOaL._SL500_.jpg)






























![『[オーディオブックCD] 「7つの習慣」実践ストーリー3 マネジメントを考える8のストーリー』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51+yvQqkSJL._SL500_.jpg)










![『経営者に贈る5つの質問[第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41kbybZMXVL._SL500_.jpg)











































![『[オーディオブックCD] 倒産回避請負人が教える脱常識のしたたか社長論。 ()』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51I+ZJ+mPqL._SL500_.jpg)






















































