【2025年】「業務改善」のおすすめ 本 165選!人気ランキング
- 上流モデリングによる業務改善手法入門
- イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」
- 問題解決力を高める「推論」の技術
- リエンジニアリング革命: 企業を根本から変える業務革新
- 新版 考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則
- 儲かるメーカー 改善の急所〈101項〉
- 1枚のシートで業績アップ! 営業プロセス“見える化"マネジメント (DOBOOKS)
- マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則
- ビジネスフレームワーク図鑑 すぐ使える問題解決・アイデア発想ツール70
- 仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法
この文章は、業務モデリングと業務フローの活用に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。第1部では業務フローの書き方やUMLによる記述方法が解説され、第2部では業務フローを用いた問題解決や組織の改善について述べられています。著者は世古雅人と渡邊清香で、それぞれの経歴や専門分野が記載されています。世古は技術開発から経営に関心を持ち、渡邊はコンサルタントとして組織改善に取り組んでいます。
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
バーバラ・ミントが著した本は、コミュニケーション力を向上させるための文章の書き方を紹介しています。内容は、書く技術、考える技術、問題解決の技術、表現の技術の4部構成で、特にピラミッド構造を活用した文書作成法に焦点を当てています。また、構造がない状況での問題解決や重要ポイントのまとめも含まれています。
本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。
本書は、アイデアが浮かばない、会議がまとまらない、意思決定に迷うといった悩みを解決するためのフレームワーク集です。70以上の手法が掲載されており、個人やチームで活用可能です。内容は問題発見、市場分析、課題解決、戦略立案、業務改善、組織マネジメント、情報共有に関するフレームワークを含み、使い方や活用のヒントも提供されています。すべてのフレームには記入例があり、PowerPointテンプレートとしても利用できます。
ビジネスフレームワークが図解で学べる。誰もが知っているビジネスでも実際にビジネスモデルは分からないことが多い。この書籍のビジネスフレームワークを一通り頭に叩き込んでおくことで色んなケースに応用が効く。
この書籍は、仮説思考を用いることで作業効率を大幅に向上させる方法について解説しています。著者の内田和成は、BCGコンサルタントとしての経験を基に、仮説を立てることの重要性やその検証方法、思考力を高める方法を紹介しています。目次には、仮説思考の概念から始まり、実践的なステップが示されています。内田は東京大学卒で、経営戦略の専門家としての経歴を持っています。
この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。
本書は、2022年の年間ベストセラー第4位に選ばれた『リーダーの仮面』の続編で、全プレーヤー向けの仕事術の「型」を体系化しています。著者の安藤広大は、全国4400社以上が導入した「識学」を基に、成長する人に共通する考え方を紹介。内容は、数字を意識した思考法や行動量、確率、変数、成功の捨て方などを探求し、数値化の限界についても触れています。
本書は、組織の変革を目指す人々に向けたガイドで、特に「関係性」を重視したアプローチを提案しています。近年の「デジタルシフト」「ソーシャルシフト」「ライフシフト」により、従来の管理主義が通用しなくなった中で、組織が抱える問題を解決する方法を示します。著者は、組織のメンバー一人ひとりが関係性、思考、行動を改善することで、全体を変えていけると主張しています。また、実践的なメソッドや成功事例を通じて、読者に希望を与える内容となっています。著者の講演も多くの企業から依頼されており、実績も評価されています。
インテル元CEOのアンディ・グローブによる経営書が待望の復刊。シリコンバレーの経営者や起業家に影響を与え続ける本書では、マネジャーが注力すべき仕事やタイムマネジメント、意思決定のポイント、効果的なミーティングの進め方など、実践的なアドバイスが満載。著名な経営者たちからも高く評価されており、マネジメントの基本原理を学ぶための重要な一冊となっている。
新入社員の小笠原は、営業部での半年間、売上ゼロのダメ営業マンだったが、スーパー営業マンの紙谷と出会い、彼から11の営業の「魔法」を学ぶ。小笠原は成長しトップ営業マンに昇進するが、最後の魔法を教わる前に紙谷が姿を消してしまう。物語は、彼の成長と営業の真髄を描いたサクセスストーリーである。
この書籍は、コンサルティング業界の全貌を解説しており、就活生や新卒、転職を考える社会人に向けておすすめです。業界の業務内容、必要な能力、働き方、キャリアパス、主要なコンサルファームについて詳細に説明しています。また、コンサルタントに求められるスキルや就職・転職の実態も紹介されており、業界の現状や将来の展望についても触れています。コンサルティング業界に興味がある人にとって、理解を深めるための有益な一冊です。
本書は、管理職向けのマネジメント書で、リモートワークにも適した「識学」という組織論を紹介しています。識学は、組織内の誤解や錯覚を解消する方法を明らかにし、4400社以上が導入しています。著者は安藤広大で、若手リーダーや中間管理職に向けた具体的なノウハウを提供し、リーダーの言動の重要性を強調しています。
組織のトップとしてのあるべき姿を説く書籍。この本に書いてある内容は自分の想像するリーダー像と違いすぎて驚いた。確かに組織を大きくして社会にインパクトを与えるためにはこの本の中で書かれているリーダーの仮面が必要なのかもしれないが、私はそんなことまでしてリーダーで居続けて何が楽しいのかなと思ってしまう。旧式の企業にはハマるがこれからの時代にはハマらない考え方な気がする。自分自身も会社を経営する身として参考にしつつもこの本の中で語られているリーダーとは違う姿を模索したい
この文章は、製造業に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、製造業の業務内容や経営の特徴、ものづくり技術の習得、事業計画作成のポイント、高度な技術の必要性についての章で構成されています。著者は照井清一と八田信正で、それぞれ製造業の改善や中小企業支援に関する豊富な経験を持っています。
本書『はじめよう!プロセス設計』は、業務改革やITプロジェクトの効率を向上させるための「プロセス設計」の重要性を解説しています。日常の「モヤモヤ」を解消する鍵として、業務フローの見える化や仕組み化の方法をストーリー指向でわかりやすく紹介。システム開発においては、要件定義が成功の要であることを強調し、技術の選定やシステム設計のポイントについても触れています。幅広い読者に向けた実用的な内容で、業務の効率化を目指す人々に役立つ一冊です。
この書籍は、コールセンターの現状や構築に関する重要な要素を解説しています。第1章ではコールセンターの現状を、第2章では構築のための3つの柱を、第3章では運営フレームの構築を、第4章では人材の考え方を、第5章では結果の重要性を、第6章では組織視点での運用改善について述べています。著者の石原康子は、コールセンターやカスタマーオペレーションにおける豊富な経験を持ち、株式会社One's Valueを設立した実績があります。
本書は、経理部に配属された若手社会人や学生向けの経理入門書です。経理の仕事の本質や必要なスキル、キャリアの可能性を理解し、やりがいを感じられる内容となっています。ストーリー形式で進行し、主人公の「会計太郎」が公認会計士YouTuberの「くろい」に相談する形で、マンガや図解を交えながらわかりやすく解説しています。著者は豊富な実務経験を持つ公認会計士の白井敬祐氏で、経理の楽しさを伝えることを目指しています。
本書は、ビジネスに役立つ70の「フレームワーク」を紹介しています。フレームワークは、意思決定や問題解決、戦略立案などに使える共通の手法で、安定した品質で短時間に成果を出すことが特徴です。内容は、問題整理、組織・コミュニケーション、アイデア創出、計画作成、戦略策定、マーケティングなどの場面での具体的な使用方法を図解で解説しています。著者は福島正人と岩崎彰吾で、両者はコンサルタントとしての経験を持っています。
本書は、外資系コンサルタントが身につけるべーシックスキル30個を紹介し、職業や業界を問わず役立つ普遍的なスキルを提供します。新人からベテランまでが使える内容で、15年後にも通用する能力を身につけることを目的としています。著者は自身の経験と元コンサルタントへの取材を基に、実践的な技術や思考法、デスクワーク術、プロフェッショナルマインドを解説しています。
本書『RPAが楽しくなる!一番やさしいRPAガイドブック』は、働き方改革と関連するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)について、初心者向けにわかりやすく解説しています。具体的なRPAツールを用いて体験できるパートもあり、興味がある人や導入を考えている人に最適です。主要なRPAツールとしてWinActor、BizRobo、UiPath、RPA Expressを紹介し、実践的な知識を提供します。著者は企業向け研修を行うカワサキタカシ氏です。
この書籍は、製造業に関する重要な知識を提供し、顧客のニーズを把握する方法から商品企画、製造、顧客サービス、物流までのプロセスを解説しています。著者たちはそれぞれ異なる専門分野での豊富な経験を持ち、製造業の5つの機能についての理解を深めるための参考文献も掲載されています。
この書籍は、官公庁の大規模システム開発におけるカンバンシステムを用いたプロジェクト進行を、著者の実体験を基に描写しています。リーンソフトウェア開発の実践方法を具体的に解説し、プロジェクトの構成やチーム編成、デイリーミーティング、カンバンボードの活用などを紹介しています。著者は、開発とマネジメントの経験を持つコンサルタントであり、アジャイル開発の技術や戦略についても詳しく述べています。
この書籍は、日本経済の再生には生産性向上が不可欠であると主張し、生産性の概念を経済学的に再考察し、その向上策を詳細なデータを基に論じています。著者は、日本がバブル崩壊後に停滞を脱却できない理由を生産性の軽視に求め、アベノミクスの限界を指摘。市場の新陳代謝や企業の多角化、経営能力向上などの具体的な施策を提案し、日本経済の活力回復に向けた方策を示しています。
この本は、小さな会社の経理担当者向けに、経理業務の実務や迷いやすい点を「1日」「1ヶ月」「1年」の単位で解説しています。内容は、経理の基本テクニックや業務の流れ、現金管理、売上・仕入管理、月次決算、年次決算の重要性などを網羅しており、実践的な知識を提供します。
この書籍は、仕事の生産性を向上させるための「プロセス思考」に基づく7つのステップを紹介しています。内容は、個人の作業能力を最大限に引き出す方法や、業務改革による無駄の削減、ミスの減少、効果的な人材活用について解説しています。著者の土方雅之は、NECでの豊富な経験を活かし、業務改革の手法を提案しています。各章では、プロセス思考の概念や実践事例、持続的な生産性向上の重要性について触れています。
著者の最新作は、次世代リーダーの育成に焦点を当て、一人ひとりの強みを活かしながら「フラットなチーム」を作る方法を具体的に紹介しています。リーダーが直面する悩みを解決するため、メンバーの「自分ごと化」を促し、主体的に話し合う会議の作り方や、チームでのゴール設定、組織を超えた交流の場の重要性について述べています。著者は、リーダーシップ開発に取り組む伊藤羊一氏です。
この書籍は、累計30万部を超えるベストセラーの最新版で、最新のITやクラウド事情を反映して全面改稿されています。主な内容は、業務を効率化するための「仕組み」を紹介しており、具体的な手法として「Gmail式プロジェクト管理術」や「共同編集型会議」、「チェックシート」、「ミス撲滅委員会」などが挙げられています。仕組み化のメリットとして、時間の確保、ミスの削減、仕事の委任、効率的な成果の最大化、チームの成長が強調されています。特に、作業に追われている人や同じミスを繰り返す人に向けて、効率的な仕事術を提案しています。著者はファイナンシャルアカデミーの代表で、教育分野での経験を活かしてこの内容を展開しています。
この書籍は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の選定から導入・運用に至るまでの重要なポイントを解説しています。現場目線で、少しずつ始めて大きな成果を得るためのノウハウや活用事例、働き方改革のヒントが豊富に含まれています。目次には、RPAの全体像、導入計画、運用のポイント、成功事例などが含まれています。著者はディップ株式会社の進藤圭氏で、さまざまな事業企画に携わってきた経験があります。
この書籍は、プロジェクトの立ち上げ期に焦点を当て、「反常識のプロジェクト成功法」を解説しています。実際の企業事例やツール、当事者の声を交えて、視覚的に理解しやすく説明しています。内容は、変革の概要、現状調査・分析、将来のビジョンの構築、計画の価値を示すためのステップに分かれており、著者は両名ともコンサルタントとして多様な業界での改革に関与しています。
この書籍は、生産管理の基本から最新のトレンドや手法までを網羅し、生産性向上とコスト削減に必要な知識を図解でまとめています。目次には、生産管理の必要性、基礎知識、計画や統制、品質管理、資材管理、改善手法、代表的な手法が含まれています。著者は田島悟で、ブレークスルー株式会社の代表取締役社長であり、中小企業診断士としての経験を持っています。
著者は、マッキンゼーの採用マネジャーとして12年間の経験をもとに、リーダーシップと採用基準について語る内容の書籍を執筆しました。目次では、誤解されがちな採用基準やリーダーシップの重要性、リーダーが果たすべき役割などが取り上げられています。著者はキャリア形成コンサルタントであり、リーダーシップ教育に関する啓蒙活動を行っています。
本書は、戦略立案、マーケティング、問題解決、マネジメント、組織開発の5つの分野から77項目、200種類以上のフレームワークを図解で紹介したハンドブックです。著者はファシリテーションとビジネススキルの専門家で、フレームワークを活用することで思考を加速し、迅速な問題解決や意思決定を促進できることを目的としています。オールカラーで改訂され、実用的な内容が特徴です。
本書は、生成AI時代におけるMicrosoft Copilot for Microsoft 365の活用法を100のテクニックとして解説しています。生成AIの普及により、デスクワークは大きく変わるとされ、特にMicrosoftのアプリケーションでの活用が重要です。著者はアクセンチュアのデータ&AIグループで、Teams、Outlook、PowerPoint、Word、Excel、OneNote、Whiteboard、Power Automateなどの主要アプリにおける具体的なテクニックを紹介。生成AIを使いこなすための実用的なガイドとして位置づけられています。
本書は、企業の人手不足を解消する手段として注目されるRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)について、基本からわかりやすく解説しています。特に「ひとり情シス」が業務部門にRPAを効果的に導入する方法を説明し、経営視点を持つことの重要性を強調しています。対象読者は中堅中小企業の情報システム管理者や経営者などで、RPAの基本操作や導入のメリットを学ぶことができます。著者はRPA活用の専門家であり、実践的なアプローチを提案しています。
本書は、企業文化の変革とデジタル変革(DX)の成功に焦点を当て、マッキンゼーのノウハウを基に「Why」「What」「How」、そして読者自身が何をすべきかを解説します。日本企業はITシステムの導入を目的化しており、真のDXに成功している企業はわずかです。著者は、次世代リーダーに向けて、企業文化の変革が生き残りの鍵であることを強調し、具体的な戦略や人材育成、変革管理の重要性を論じています。
本書は、ビジネスパーソン向けに問題解決のための「フレームワーク」を解説したビジュアル版の書籍です。マーケティングや戦略プランニング、マネジメントに役立つ81のツールを紹介し、効率的に問題を解決する方法を提供します。大きな紙面で図解が直感的に理解できるようになっており、著者はグロービスの嶋田毅氏です。目次には、問題発見や解決、マーケティング、戦略策定、組織マネジメントに関するフレームワークが含まれています。
この書籍は、古い業務スタイルに固執する組織をどのように改善し、アップデートしていくかを探る内容です。著者の沢渡あまねと元山文菜は、300以上の企業や官公庁での経験を基に、現場の無力感や中間管理職の抵抗、提案が受け入れられない状況などの課題を分析し、効果的な変革の方法を提案します。業務改善やIT化の重要性を理解し、実行に移すための具体的なアプローチが示されています。
本書『戦略フレームワークの思考法』は、経営戦略を策定するためのフレームワークを全面的にリニューアルしたもので、論理と直感を活用しながら問題解決やアイデア創出を支援します。著者は経営コンサルタントの手塚貞治氏で、伝統的なフレームワークから新しいものまで幅広く紹介。特に「並列化」「階層化」「二次元化」「時系列化」「円環化」という5つの思考パターンに基づき、各フレームワークの使い方やメリット・デメリットを具体例を交えて解説しています。初心者でも理解しやすく、実践的なノウハウが得られる内容です。
本書は、日本におけるコーチングの第一人者による、理論と実践を網羅した決定版のコーチング本です。組織の課題解決に向けて、なぜ行動が伴わないのか、戦略が徹底されないのかを探求し、コーチングがその突破口となることを示しています。内容は図解で分かりやすくまとめられ、組織のパフォーマンス向上や変革を目指すリーダーにとって必読の入門書です。
この書籍は、社員のモチベーションを高めるためには、まず「モチベーションを下げる要因」を取り除くことが重要であると説いています。著者は、疲弊する組織や高離職率の会社に共通する問題を分析し、改善策を心理的アプローチを基に解説しています。具体的には、上司の問題や組織の疲弊に関するパターンを示し、心理的安全性や自己効力感などの概念を通じて、金銭的報酬だけでなく「見えない報酬」の重要性を強調しています。著者は、経営コンサルタントとしての経験を活かし、効果的なマネジメント手法を提案しています。
本書は、SDGs(持続可能な開発目標)を背景に、企業が直面する「産業革命」と「経営革命」に同時に対応する必要性を説いています。企業活動における社会価値と経済価値の重要性を強調し、経営モデルの革新や戦略の再構築を促します。内容は、SDGs時代の新たな経営モデルの潮流、企業のSDGsの理解、ステークホルダーの変化、そして新たな経営モデルへのシフトに向けた戦略に分かれています。企業はSDGsを「義務」ではなく「戦略」として捉え、成長を追求することが求められます。
主人公アレックス・ロゴは、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナとの再会をきっかけに工場の再建に取り組む。彼は生産現場の常識を覆すジョナの助言を受け、仲間と共に努力するが、家庭を犠牲にしてしまい、妻ジュリーとの関係が危機に陥る。物語は、仕事と家庭の両立を巡る葛藤を描いている。
著者は、ドイツと日本の生産性の違いを探求し、ドイツが日本より300時間少なく働きながら1.5倍の生産性を持つ理由を分析しています。主な要因として、「自立・独立の意識」「効率的なコミュニケーション」「明確な時間管理」「フラットな組織構造」「休暇の重視」が挙げられています。著者は、これらの要素を取り入れることで、日本のビジネスパーソンも生産性を向上させ、快適な働き方を実現できると提案しています。
この書籍は、ソフトウェアロボットによるデジタル業務改革の進展を探求し、特に「直下型RPA改革」による効果を強調しています。急増するRPA導入企業の現状や、成功するためのアプローチ、運用時のリスク管理、中小企業への浸透、AIとの連携による新たな展開、先進企業の事例、そして第4次産業革命における企業の成長戦略について解説しています。著者は、RPA導入の実績を持つコンサルタントであり、具体的な進め方を提案しています。
この本は、オフィス業務を効率化し、組織を活性化させる方法を解説しています。業務の見える化やコミュニケーションの見直しを通じて、改革と改善を進める手法を豊富なフォーマットと図解で紹介しています。目次には、業務改革の必要性から企画立案、実行、モニタリングまでのステップが含まれています。
本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。
10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。
『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。
本書は、魅力的な文章を書くために必要な表現やフレーズを100個紹介するカンニング本です。著者は25年間の記者・ライター経験を活かし、ビジネスやSNSなど幅広い場面で使える表現を提供。1日3分の練習で、書けない人から書ける人へと変身できる内容になっています。目次には基本フレーズ、知的に見える言葉、テーマ別便利フレーズ、呼応表現のルールが含まれ、実践的な文章術を学ぶことができます。
この書籍は、チームの心理的安全性を高める方法について解説しています。著者の石井遼介は、心理的安全性がチームのパフォーマンス向上に寄与することを強調し、リーダーシップや行動分析、言葉の使い方が重要であると述べています。具体的には、心理的柔軟性を培う方法や、行動を変えるためのフレームワークを紹介しています。全体を通じて、健全な衝突がチーム力を引き上げることを示唆しています。
災害・危機発生時の職員の役割と行動 組織と法制度上の課題 被災自治体職員が抱える課題 災害時の応援自治体職員の課題と展望 危機管理における官民の連携 試案 大規模災害時における被災市町村への人的支援 「組織と人」に関する防災・復興法制の現状と課題 自治体職員の惨事ストレス 災害時のパニックと心理的ショック
伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方に触れることのできる良書。
伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方にふれることができる。経営やビジネスの考え方というよりも哲学・道徳観点の話が多い書籍。なにかテクニック的なことを学ぶことはできないが人生を生き抜く上での指針になる。ぜひ読んで欲しい名著
リクルートの元新規事業開発室長が、5000の事業を支援した経験をもとに、新規事業成功のための具体的な方法論を紹介した書籍。重要なポイントとして、初期チームは2人が最適、リリース直後のマーケティングは避けるべき、顧客の声を重視することなどが挙げられている。また、新規事業開発は全ての職種にとって価値のあるスキルであり、失敗から成長できる機会を提供することが強調されている。著者は、社内起業家としての生き方や新規事業の立ち上げに関する知識を体系化している。
神奈川工場の長、新城吾郎は、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナと再会することで再建への意欲を取り戻す。ジョナの新しい考え方に基づき、工場の問題を科学的に解決しようと奮闘するが、家庭を犠牲にした結果、妻が失踪してしまう。物語は、全体最適のマネジメント理論であるTOCを基に、工場再建の過程を描いている。
工場の改善のお話で生産管理などに携わる人、経営者全てにオススメの1冊。漫画などでスラスラ読めて分かりやすい。それでいて重要なエッセンスはちゃんと詰まっている。何度も読み返したい1冊。
アクセンチュアが自社の「働き方改革」を進める過程を描いた『プロジェクト・プライド』の軌跡を紹介する書籍です。著者は日本法人の社長で、社員の意識改革や会社の風土改善を通じて生産性や従業員満足度を向上させる成功事例を明かしています。内容は、現状把握から改革のロードマップ、具体的な改革活動、そして次の成長ステージへの展望を含んでいます。
ホリエモンの行動力に驚く。結局本書で言っているのはグダグダ考えてないでとりあえず行動しろ!動けってこと。読むだけでモチベーションが上がるが、これを読んで満足してしまって何も行動しないのであれば元とも子もない。これを読んでしっかり行動に移すべき。
「MBA」でも「難関資格」でもない、ビジネスリーダーが本当にやるべき「頭と身体の鍛錬」。外資系戦略コンサルタントの第一人者がその独自の手法をすべて公開。 1 「感じる力」を高める(「現場センサー」を磨く 「主観力」で勝負する 「感じる力」を高める三つの勉強) 2 「考える力」を高める(思考を「見える化」する 「論理思考」の落とし穴 「箱」から飛び出る思考法) 3 「伝える力」を高める(「ストーリー」を「見える化」する 共感を生む表現を磨く 本を書くための六つの力)
このビジネス書は、多様性を取り入れた組織が成功する理由を探求し、致命的な失敗を未然に防ぎ生産性を高めるための組織改革の方法を提示しています。著者マシュー・サイドは、革新を促す要素やコミュニケーションの重要性について考察し、具体的な事例を通じて読者に考えさせる内容となっています。シリーズは好評を博し、さまざまなメディアで紹介されています。
この書籍は、ビジネススクールで学ぶ重要なスキルセットを「1フレーズ」で簡潔に理解できる内容です。10の主要スキルが3つのカテゴリー(土台スキル、実行スキル、成長スキル)に分かれ、ビジネスにおける生産性向上を目指します。著者はグロービスの教授であり、実務経験を持つ専門家です。
本書『福山式仕事術』は、若手ビジネスマン向けに、圧倒的な成長を遂げるための実践的な成功メソッド63を紹介しています。著者の福山敦士は、サイバーエージェントでの経験を基に、目標設定、目標管理、自分磨き、振り返り、アクション、コミュニケーションの6つの技術を体系的にまとめました。これにより、少しの視点の変化で優れた成果を得る方法を提供し、成長を目指す人々に役立つ内容となっています。
本書は、ソフトバンクのRPAプロジェクトチームが、効果的なRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入と運用方法を解説しています。RPA導入の成功には業務の流れや体制の明確化が必要であり、実際にプロジェクトを通じて得た経験を基に、課題解決のためのノウハウや資料を提供しています。特に「RPA自走集団」の形成に焦点を当て、導入時の悩みや推進体制の構築、AIとの連携についても触れています。巻末にはRPAツール選定フローチャートや各種ダウンロード資料が用意されています。
著者の森岡毅氏が提唱する最新刊「リーダーシップ論」は、リーダーシップは特別な能力ではなく、後天的に身につけられるスキルであることを強調しています。コロナ禍において、自分と他者を活かすためのリーダーシップの重要性を説き、具体的な獲得法や環境の整え方を示しています。また、著者自身の経験を交えながら、リーダーシップを育成するためのノウハウやコロナからの出口戦略についても言及しています。リーダーシップを学びたい人にとって、実践的な内容が詰まった一冊です。
この書籍は、戦略コンサルタントのスキルを学ぶための指南書で、問題解決の基本的な考え方をチャートを用いてわかりやすく説明しています。内容は、思考法(ゼロベース思考や仮説思考)、技術(MECEやロジックツリー)、プロセス(ソリューション・システム)、実践(具体的な活用方法)に分かれており、企業事例も新たに紹介されています。著者は齋藤嘉則で、経営コンサルタントとしての豊富な経験を持っています。
高齢化や後継者不足など、日本の農業を取り巻く課題を打開すべく最新のICT機器を駆使した次世代農業の最新情報が満載な1冊です。 就農者の高齢化や後継者不足など、日本の農業を取り巻く深刻な課題を打開すべく ICTや映像・画像技術を駆使した次世代農業のヒントと最新情報が満載な1冊です。 ハイパースペクトルカメラやドローン、衛星などを用いた映像・画像技術をはじめ 温度・湿度また土壌水分など環境データを収集・計測する各種センサ、クラウド技術などを駆使した スマート農業技術を多数紹介してます。 就農者の方々はもちろん、これから農業を学ぶ方々にとっても実用的な生産手引きとしてご活用いただけます。 【巻頭言】 「農業 ICT 革命」~日本の農業を魅力あるものにする ICT 利活用とは~ 日本農業情報システム協会/理事長 渡辺智之 【特別インタビュー】 “見える化"の先を目指して取り組むスマート農業 ―経験と勘に頼る農業からの脱却― 農林水産省/大臣官房研究調整官 安岡澄人 【環境モニタリングシステム】 ・農業ICTの新しい時代を切り拓く、先進の土壌水分センサ「WD-3」 株式会社A・R・P/マーケティンググループリーダー 福岡達也 ・水稲農家向けスマート水田サービス「paditch(パディッチ)」 株式会社笑農和/下村豪徳 ・廉価なワンボードマイコンを利用した圃場環境と 植物生育状態の計測と可視化 九州大学大学院 農学研究院 環境農学部門 准教授/岡安崇史 ほか ・あぐりクラウド農業生産におけるICTの利用 ~露地・施設園芸の栽培環境の見える化~ 株式会社ジョイ ・ ワールド・パシフィック/佐々木憲昭 ほか ・農業IT「みどりクラウド」による圃場環境の可視化 株式会社セラク/井田 明 ほか ・誰でもできる遠隔管理・監視システム 曽田園芸(島根県)/曽田寿博 ・継続可能な農業ICTを支える「ポジモ」の汎用・圃場ネットワーク 株式会社ネクステック ・農業 IoT e-kakashi PSソリューションズ株式会社/山口典男 ほか ・スペクトル技術による次世代農業の可能性 北海道衛星株式会社 ・衛星画像データと気象データを融合した営農支援情報サービス 有人宇宙システム株式会社 宇宙事業部 宇宙調査研究グループ/若森弘二 ほか 【特別インタビュー】 JA 北越後による「スマート農業」への取り組み JA 北越後 営農経済部 集荷販売課 稲作担当/川端麻里 JA 北越後 営農販売部 集荷販売課 お米センター長 兼 農産物販売営業/治田政明 【生産管理・記録システム】 ・農業分野における情報共有(農作業日誌 アルケファーム) 株式会社アルケミックス/代表取締役 森田吉公 ・ダウンロード数2万を超える農業スマホアプリ「畑らく日記」による 営農改善・実績データからの考察 株式会社イーエスケイ/片山健史 ・「千年農業」~アグリノートで実現する次世代の農業情報管理~ ウォーターセル株式会社/藤原拓真 ・映像を中心とした農業知識集約ソリューションの紹介 NECソリューションイノベータ株式会社/久寿居 大 ほか ・ICTデータを活用した次世代の農業経営(後継者・産地育成) テラスマイル株式会社/代表取締役 生駒祐一 ・営農支援アプリ「farmbox」と 契約取引支援サービス「MarketBox」 farmbox/堀 耕太 ・競争力のある農業経営をサポートするクラウド型営農システム 株式会社冨貴堂ユーザック/代表取締役社長 本田和行 ・農業法人としての IT 企業の挑戦 株式会社大和コンピューター/NB推進本部 本部長補佐 田代貴志(JAISA 会員) 【農業機械/ロボット/ドローン】 ・佐賀大学農学部・佐賀県農林水産部・オプティム、三者連携による 最新の IT 農業に対する取り組み 株式会社オプティム ・農業ロボットの最前線~トマト収穫ロボット開発秘話 スキューズ株式会社/市川裕則 ・GPS ガイダンスの最適な走行ラインを作成する「GPS-Line」 株式会社スマートリンク北海道/小林伸行 ・DJIと実現する精密農業 ―UAV技術を利用した持続可能な農業の進化 DJI JAPAN 株式会社 ・定置型イチゴ収穫ロボット (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センター 高度作業支援システム研究領域 高度施設型作業ユニット長/林 茂彦 【製品紹介】 ◎最先端近赤外線カメラ/株式会社アートレイ ◎農業日誌(栽培記録)のクラウドサービス/株式会社イーエスケイ ◎マルチスペクトルカメラ/株式会社ジェピコ ◎UAVとの相性抜群なHSC/株式会社システムズエンジニアリング ◎GPS-Line/株式会社スマートリンク北海道 ◎圃場の環境を見える化/住友精密工業株式会社 ◎色識別画像処理例/株式会社ケーアイテクノロジー ◎土壌水分センサ/SenSprout Inc. ◎分光イメージングカメラ/株式会社ブルービジョン ◎UECS-Piコントローラキット/株式会社ワビット
この書籍は、40代を迎えた人々に向けて、人生の後半をどう生きるかの選択肢を提供し、時間管理やキャリア、プライベートの重要性を強調しています。著者は、組織内でのスキルやマネジメント、効率的な学び方、人脈の重要性についても触れ、成功するための具体的な方法を提案しています。著者は大塚寿氏で、企業研修の専門家です。
この書籍は、Excelを活用して業務改善を図るための実践的なテクニックを紹介しています。著者は業務改善のプロで、具体的なサンプルを通じてExcelの機能を理解し、自分の業務にどう役立てるかを考える内容です。時短テクニックからマクロによる自動化まで、ビジネスパーソンに役立つスキルが詰め込まれています。サンプルファイルはダウンロード可能で、学習がスムーズに行える工夫もされています。著者はITストラテジストで、多くの業務改革プロジェクトをリードしてきた経験があります。
本書は、業務改善を目的としたプロジェクトマネジメントの入門書で、マンガ形式で基本をわかりやすく解説しています。PMBOKの「ステークホルダー」「コミュニケーション」「スコープ」「スケジュール」「資源」に重点を置き、実際の職場での問題点を楽しく学ぶことができます。著者はプロジェクト管理の専門家で、実践的な知識を提供しています。
管理問題の発生と展開 管理の構造と発展 ヒトの管理をめぐる変遷 人的資源管理としての日本型雇用とその変容 企業内教育訓練・能力開発の課題 労働時間管理の変化と働く者のニーズ 賃金管理と処遇問題 多様な紛争解決システムと労働組合 日本型人的資源管理の行方
第1部 IOTの全体俯瞰(産業用IoTとは何か IoTの市場構造とは) 第2部 垂直統合戦略(GEとボッシュに学ぶIoTの垂直統合戦略 垂直統合戦略のマーケットと日本における市場形成 プラットフォームを制する者が産業用IoTを制する) 第3部 水平横断戦略(コネクティビティはどうなるか クラウドとアナリティクスはどうなるか) 第4部 モノ重点戦略(IoTによって製造現場はどう変わるか) 第5部 IoTの中で日本・日本企業が生き残るための提言(企業は既存事業をIoT化するために何をすべきか 日本はどう対応すべきか)
この書籍は、ボストン・コンサルティング・グループのノウハウを基に、勝てる戦略を生み出すための「イノベーション」を促進する発想法を解説しています。内容は、戦略に命を吹き込むインサイトの重要性、思考のスピードを上げる方法、三種類のレンズを用いた発想力の向上、インサイトを生み出すための頭の使い方、そしてチーム力を活かしたインサイト創出の方法について触れています。著者は御立尚資氏で、幅広い業界で事業戦略やイノベーションに関するプロジェクトを手掛けています。
実務レベルでマーケティングについて深く学べる書籍。当たり障りのない抽象論でもなく、小手先のテクニックでもなく、マーケティングの本質がしっかり学べる。デジタルマーケティング職に配属された新卒はとりあえずこれを読んでおけば大丈夫といっても過言ではないくらい良い書籍。何度も読み直したい。
アンカー・ジャパンのCEO、猿渡歩が初めて著したビジネス書が「ビジネスリーダー1万人が選ぶベストビジネス書TOPPOINT大賞2023上半期ベスト10」に選ばれました。彼は、創業9年目で売上300億円を達成した成功の秘訣を「1位思考」として紹介し、シンプルな6つの習慣を提唱しています。内容は「全体最適」「バリューを出す」「学ぶ」「因数分解」「1%にこだわる」「サボる」の習慣に分かれており、巻末には「面接を通過する10のコツ」も収録されています。
本書は、UiPathを活用した業務自動化手法を紹介するもので、日常業務の自動化を目的としています。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)について基本的な知識を持つ非エンジニア向けに、具体的な自動化処理の方法を業務の種類ごとにまとめています。内容には、Webデータの出力やExcelデータの集計、メール送信の自動化などが含まれ、読者は実践的なテクニックを学ぶことができます。著者は業務の完全自動化を通じて、無駄なPC作業からの解放を目指しています。
この書籍は、ビジネススキルだけではなく、組織を効果的に動かすための「Deep Skill」の重要性を説いています。著者は4000人以上のビジネスマンを観察し、組織力学や人間心理を活用する方法を紹介。信頼資産の構築、戦略的な人間関係の形成、権力の動かし方、人間力の向上など、実践的な技術を解説しています。著者は企業の新規事業創出を支援するコンサルタントであり、組織内での成功には深いスキルが不可欠であると強調しています。
本書は、株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)の創業者南場智子が、会社の立ち上げから成長過程における失敗と奮闘を描いたものです。彼女は、チームが直面した困難を一つ一つ乗り越え、学びながら強さを築いていった様子を紹介しています。目次には、立ち上げ、生い立ち、資金調達、モバイルシフト、ソーシャルゲーム、退任、人と組織、そして未来についての章が含まれています。
本書は、日本IBMで初の女性取締役を務めた内永ゆか子が、働く女性に向けて職場で輝き続けるための35の秘訣を提供する内容です。各章では、キャリアや人間関係、仕事の成果、感情管理、女性の幸せ、長期的な働き方などについて具体的なアドバイスが述べられています。著者は女性の活躍を支援するNPO法人J-Winの理事長でもあります。
個人の地域密着型アウトドアショップがデジタルマーケティングで業績を飛躍的にアップさせていくストーリーに乗せて、DMの基礎を… 個人の地域密着型アウトドアショップがデジタルマーケティングで業績を飛躍的にアップさせていくストーリーに乗せて、DMの基礎を学ぶ
デジタルマーケティングとデータ分析について漫画で分かりやすく学べる。基本的な内容が網羅的に学べるのでデジタルマーケティング職についたばかりのビジネスパーソンや個人事業や中小企業でこれからデジタルに力を入れようとしている経営者にオススメ!
本書は、マネジメントの本質を「管理」ではなく、仕事の成果を最大化するために関連する要素を「いい感じにする」ことと定義しています。具体的には、環境や人間関係、役割分担などを整えることが含まれます。視覚的な図解を用いて、手軽にマネジメントについて学び、会話や説明ができるようになることを目指しています。著者はマネジメントの専門家で、多くの企業でアドバイザーを務めています。
この書籍は、請求書作成や経費精算、受注管理などの業務をロボットが自動化するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)について解説しています。内容は、UiPathの基本から応用、Excelやメール、Webサイトとの連携方法、さらには高度なテクニックまで幅広くカバーしています。著者はフリーライターの清水理史氏です。
本書は、21世紀の価値創造において、問題解決の専門家よりも「善」に基づいて価値を判断できる人が重要であると説いています。著者は、マッキンゼーとボストンコンサルティンググループの両方を知る数少ない存在であり、彼らの問題解決手法とその限界を分析し、新たな価値創造技術やビジネスの潮流を紹介します。具体的な事例を通じて、問題解決の新たなアプローチを提案しており、ビジネスパーソンにとって必携の一冊です。
稼ぐために働きたくない若手世代のための書籍。今の時代は基本的になんでも揃っていてそんなにお金がなくても十分幸せに生きていける。そんな時代に我々はどうやってモチベーションを高めていけばよいのか?そのヒントがこの書籍には書いてあります。
元リクルート社長の著者が、組織づくりに関するノウハウをまとめた書籍。29年間の経験を基に、事業成長や従業員満足を同時に実現する手法を紹介。「G-POPマネジメント」と名付けられたこのアプローチは、目標設定、事前準備、実行・改善、振り返りの4つの章から成り立っており、経営者や管理職向けに実践的な知識を提供します。
この書籍は、国際交渉の専門家である島田久仁彦が、交渉や調停のテクニックや哲学を紹介し、特に環境問題における成功事例を通じて日本の交渉力を強調しています。著者は、警戒を解き真意を引き出す方法や、国際会議での合意形成の手法を具体的な経験に基づいて語り、交渉における「戦わない」アプローチの重要性を説いています。
ある程度お金について教養のある人にとっては当たり前の内容なので読まなくてもいいが、お金について知らないことが多くて将来心配な人にとってはまず最初に読むといいかもしれない書籍。
本書は、体系的かつシンプルなロジカル・コミュニケーション技術を習得することを目的としています。著者たちは、訓練を通じて誰でもこの技術を身につけられると確信しています。内容は、伝えることの重要性や論理的思考の整理、構成技術に関する具体的な方法を提供しています。著者は共にマッキンゼーでの経験を持ち、コミュニケーション戦略やトレーニングに従事しています。
本書は、日本企業が米軍のような「軍隊型組織」から脱却し、現場の自由な動きを促進するための新しい経営戦略を提案しています。著者は、米軍の「機動戦」から学び、PDCAサイクルを超えたOODAループやミッション・コマンド、クリティカル・インテリジェンスを活用して、柔軟で効果的な組織運営を実現する方法を解説しています。具体的な事例や理論を通じて、ビジネス環境での生き残りを目指す戦略を示しています。
ある程度教養のある人にとっては目新しい内容は少ないが、お金に対して不安を持っている人は目を通しておくとよいと思う。資産形成の観点だけでなく生活における必要経費の出費をどれだけ抑えられるかについても学べる。
本書は、日本企業がIoT化を進める際の指針を提供しています。IoT導入における障壁やその解決策を探り、企業がどのようにIoTを活用できるかを示しています。内容は、IoTの市場構造や事例、構築の手順、セキュリティの問題、組織の壁を乗り越える方法、さらには日本型IoTビジネスモデルへの提言が含まれています。著者は、日立製作所での豊富な経験を持つ大野治氏です。
「業務改善」に関するよくある質問
Q. 「業務改善」の本を選ぶポイントは?
A. 「業務改善」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「業務改善」本は?
A. 当サイトのランキングでは『上流モデリングによる業務改善手法入門』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで165冊の中から厳選しています。
Q. 「業務改善」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「業務改善」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。








![『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UB6ayAOaL._SL500_.jpg)


















![『コールセンターの組織力と戦略的運営 [運営者と経営者が知っておきたい] ~運用を会話/数値/現象からみる‐SPT (R)(Service Positioning Tracking)~』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/416epUugqpL._SL500_.jpg)










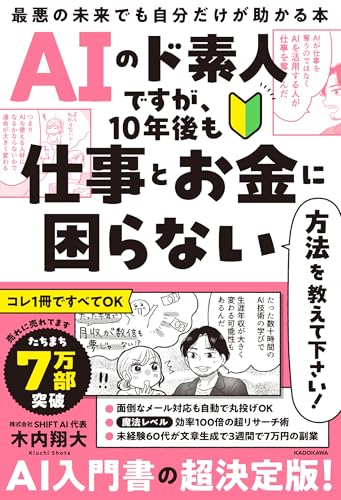






![『[オーディオブックCD] 「7つの習慣」実践ストーリー3 マネジメントを考える8のストーリー』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51+yvQqkSJL._SL500_.jpg)





![『ビジュアル ビジネス・フレームワーク[第2版] (日経文庫)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51MAXgtMdzL._SL500_.jpg)
























![『[カラー改訂版]営業の見える化』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51KVjDz5L0L._SL500_.jpg)


































































![『[カラー改訂版]頭がよくなる「図解思考」の技術』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51lgAYWk6sL._SL500_.jpg)



















![『経営者になるためのノート ([テキスト])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/21OIhMFu5cS._SL500_.jpg)
![『ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ] やっかいな人のマネジメント (ハーバード・ビジネス・レビュー―EIシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51yw5J+NnOL._SL500_.jpg)












