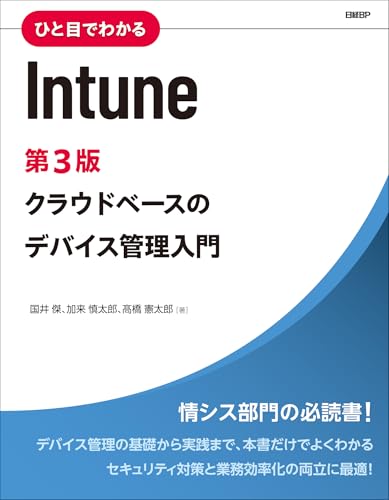【2025年】「iot」のおすすめ 本 156選!人気ランキング
- 図解即戦力 IoT開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書
- IoTシステムのプロジェクトがわかる本 企画・開発から運用・保守まで
- 図解即戦力 IoTのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書 IoT検定パワーユーザー対応版
- IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書
- 改訂新版 IoTエンジニア養成読本 (Software Design plusシリーズ)
- IoT開発スタートブック ── ESP32でクラウドにつなげる電子工作をはじめよう!
- 問題を解いて実力をチェック IoTの問題集
- 2時間でわかる 図解「IoT」ビジネス入門
- 未来IT図解 これからのDX デジタルトランスフォーメーション
- 知識ゼロからのIoT入門
この書籍は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性と実践方法について解説しています。DXの定義や背景、企業が取り組むべき領域、必要な内部変革、進め方、そして未来の社会やビジネスの変化について詳しく述べています。著者は、IT戦略やDXの専門家であり、企業内イノベーションリーダーの育成にも力を入れています。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
第1部 IOTの全体俯瞰(産業用IoTとは何か IoTの市場構造とは) 第2部 垂直統合戦略(GEとボッシュに学ぶIoTの垂直統合戦略 垂直統合戦略のマーケットと日本における市場形成 プラットフォームを制する者が産業用IoTを制する) 第3部 水平横断戦略(コネクティビティはどうなるか クラウドとアナリティクスはどうなるか) 第4部 モノ重点戦略(IoTによって製造現場はどう変わるか) 第5部 IoTの中で日本・日本企業が生き残るための提言(企業は既存事業をIoT化するために何をすべきか 日本はどう対応すべきか)
本書は、組込みエンジニアに必要な知識とスキルを幅広く解説し、ArduinoやRaspberry Piを用いた実践例も紹介しています。内容はハードウェア、ソフトウェア、組込みプログラム、リアルタイムOS、開発プロセス、IoTおよびAI時代の組込みソフトウェアに関する情報を含んでおり、特に新人エンジニアや組込みエンジニアを目指す人にとって必読の一冊です。著者は組込み技術者の育成に長年従事してきた専門家です。
この文章は、組込みソフトエンジニアリングに関する書籍の目次を示しており、プロローグではその重要性が述べられています。各章では、時間分割、機能分割、再利用、品質といった課題を克服する方法が探求されており、エピローグではエンジニアとしての成長がまとめられています。
本書は、経済産業省のガイドラインに基づき、IoT機器のセキュリティ検証を実践するための手法を解説しています。特に攻撃者の視点からの防御策の考案を重視し、実際のハッキング手法やコマンド、結果を示して理解を深める内容となっています。著者はIoTセキュリティの専門家であり、実践例を通じて安心安全な製品開発を促進することを目的としています。目次にはハードウェアハッキングやファジングテストなどの具体的なステップが含まれています。
この書籍は、IoT機器のハッキングとセキュリティ技術に関する内容で、WebカメラやWebサーバーの検証も含まれています。目次には、IoTの基礎、ハッキング環境の構築、セキュリティ診断基準、各種ハッキング手法(UART、SPI、JTAG)、およびペネトレーションテストが含まれています。著者は、IoTセキュリティに関心を持つ若い専門家たちです。
この本は、電子工作に関する疑問を解決し、基本を理解するためのガイドです。アナログやデジタル、ラジオ、ステレオなどに興味がある人に向けて、100項目を通じて楽しく学べる内容が紹介されています。著者の遠藤敏夫は、数学教師としての経験を活かし、特別支援教育にも取り組んできました。
この文章は、製造業に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、製造業の業務内容や経営の特徴、ものづくり技術の習得、事業計画作成のポイント、高度な技術の必要性についての章で構成されています。著者は照井清一と八田信正で、それぞれ製造業の改善や中小企業支援に関する豊富な経験を持っています。
『Cの絵本』は、C言語の初心者向け入門書としてリニューアルされ、プログラムの知識がなくても学び始められる内容になっています。新版ではポインタの解説が改善され、実践的な内容や最新の環境構築手順が追加されています。イラストを多用し、直感的に理解しやすい形式で提供されており、基礎からしっかり学べる一冊です。また、翔泳社の「絵本シリーズ」全体も改訂され、現代の技術に合わせた内容に刷新されています。
「図解でわかる ネットワークの重要用語解説」の改訂5版が発行され、フルカラーでイラストを用いてネットワーク用語を解説しています。初級エンジニアや学生、現場のSEやPMにも役立つ内容で、インターネット編が「基礎編」と「技術編」に分かれ、新たに「セキュリティ編」も追加されました。著者はコンピュータプログラマのきたみりゅうじです。
本書は、人工知能(AI)の最新の進展や活用方法、未解決の問題、潜在的な利益とリスク、科学的・哲学的な視点をわかりやすく解説したAI解説本です。著者は、AIの仕組みや実用性を深く掘り下げ、正確かつ明瞭な記述を提供しています。内容は、AIの歴史、機械学習、自然言語処理、倫理的問題など多岐にわたり、読者はAIの利点と脆弱性について理解を深めることができます。著者はコンピューター科学の専門家で、AIに関する豊富な知識を持っています。
本書は工作機械についての入門書で、日本のものづくりを支える「マザーマシン」としての役割を解説しています。工作機械の仕組み、種類、加工方法、最新の技術動向などを幅広く紹介しており、全7章で構成されています。著者は工学の専門家たちで、各自が豊富な経験を持っています。
この書籍は、製造業に関する重要な知識を提供し、顧客のニーズを把握する方法から商品企画、製造、顧客サービス、物流までのプロセスを解説しています。著者たちはそれぞれ異なる専門分野での豊富な経験を持ち、製造業の5つの機能についての理解を深めるための参考文献も掲載されています。
本書は、C言語を学ぶための入門書で、基本事項の学習、具体例を通じた理解、問題解答による確認を組み合わせたステップアップ方式で構成されています。C言語を初めて学ぶ人や挫折した人、さらにスキルを向上させたい人に最適です。目次には、Cの基本、入出力、制御構造、配列、ポインタ、関数、演算子、構造体、データ型、プリプロセッサ、標準ライブラリ、ファイル処理が含まれています。
本書は、ビジネス書グランプリや大賞を受賞した著者による現代の変化を分析し、AIとデータの発展がもたらす影響について論じています。読者は、社会の変化、企業の戦略、教育のあり方など多岐にわたる問いに対する答えを見つけることができます。著者は、建設的な未来の創造を目指し、ファクトベースでの現状分析を行い、ビジネス、教育、政策などの領域における具体的なアプローチを提案しています。
ビジネスパーソンにAIの書籍を1冊オススメするなら間違いなくこれを選ぶ。データサイエンティスト協会の理事も努めビジネス・アカデミックの両面からデータサイエンスにBETしている安宅さんが語るAIのあり方。我々日本人がこれからの時代において世界でプレゼンスを発揮するためにはどうすればよいかを教えてくれる書籍で非常に感銘を受けた。どんよりとした日本の停滞感に対して少しでも希望を見出すことのできる書籍。安宅さんの書籍はどれも素晴らしいが絶対にこれは読んで欲しい。
本書は、IoTプロジェクトを成功させるためのポイントを実体験に基づいて解説しています。著者の野々上氏は、スマートウオッチの開発を通じて得た知見をもとに、グランドデザイン、チーム編成、ハード/ソフト開発など多角的な視点からのアプローチを紹介。IoT市場の急成長に伴い、企業が直面する課題や成功のためのノウハウを提供しており、これからIoTに挑戦する人々に向けた指南書となっています。
本書は、AIの限界と人間の教育の問題を探る内容で、特に「東ロボくん」がMARCHクラスには合格したものの東大には入れなかった事例を通じて、AIが得意とすることと苦手とすることを考察しています。全国の読解力調査によると、多くの中高校生が教科書の文章を理解できておらず、将来的にAIに仕事を奪われる危険性が指摘されています。著者は、教育の改善が必要であるとし、最終章で専門家としての提言を行っています。
この書籍は、人工知能(AI)の進化が経済、社会、政治に与える影響を探求しています。著者は、AIが人間の頭脳に追いつく2030年までに多くの職業が失われる可能性があり、最大で人口の9割が失業する恐れがあると警告します。これに対処するため、著者はベーシックインカム(BI)の導入を提唱し、社会保障を一元化して全ての人に生活保障を提供する必要性を論じています。AIの未来とそれに伴う社会の変化について、経済学者が考察を行っています。
本書は、日常生活での「こういうものがあったらいいな」というアイデアを実現するための電子工作の入門書です。インターネットに接続できる電子工作を学び、様々なデバイスを作る楽しさを体験することを目的としています。目次には、Arduinoの使い方や電子部品の試し方、家電のネット化などが含まれています。著者は、インタラクションデザイナーの蔵下まさゆき氏です。
この書籍は、生産管理の基本から最新のトレンドや手法までを網羅し、生産性向上とコスト削減に必要な知識を図解でまとめています。目次には、生産管理の必要性、基礎知識、計画や統制、品質管理、資材管理、改善手法、代表的な手法が含まれています。著者は田島悟で、ブレークスルー株式会社の代表取締役社長であり、中小企業診断士としての経験を持っています。
この書籍は、WebブラウザがURLを入力してからWebページが表示されるまでのプロセスを探る内容で、ネットワーク技術に関する基礎解説が大幅に加筆された改訂版です。目次にはブラウザ内部のメッセージ作成、TCP/IPプロトコル、LAN機器(ハブ、スイッチ、ルーター)、アクセス回線とプロバイダ、サーバー側のLAN、Webサーバーへの到達と応答データの戻りなどが含まれています。著者はネットワーク業界での経験を持つ戸根勤氏です。
この書籍は、NC旋盤の基本的な機能や構造、使用技術について解説しています。NC旋盤は主に丸物の量産部品加工に特化しており、マシニングセンタとは異なり量産加工の現場で重要な役割を果たします。内容は、NC旋盤の概要、構造、NC制御の基礎知識、段取り、加工のポイントなどを分かりやすく説明しています。著者は、芝浦工業大学の准教授で、機械加工に関する豊富な知識と経験を持っています。
本書では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の本質を、デジタル技術と合理的なマネジメントの融合とし、GAFAの働き方を実践することが不可欠であると述べています。DXの成功は単にデジタルビジネスの導入ではなく、業務プロセスの最適化とコストパフォーマンスの向上にあると強調しています。一般企業は、デジタル技術を活用しつつ自身のアナログな強みを生かしてビジネスモデルを再構築する必要があり、そのための具体的な方法論がGAFAの働き方にあるとしています。著者は、DXを推進したい経営者や中間管理職に向けて実践的な知恵を提供しています。
本書は、ホワイトハッカーになるための知識とスキルを学ぶためのガイドです。サイバー攻撃を防ぐ専門家として、法令遵守と倫理観を持つホワイトハッカーの役割を解説し、成功するための再現性のあるアプローチを提案します。技術的な内容だけでなく、スキルアップやメンタル面にも触れ、読者がホワイトハッカーとして成長するための具体的な方法を提供します。最終的には、ホワイトハッカーになるための道筋を示すことを目的としています。
著者の種田元樹がC言語の基本から応用までを豊富なサンプルを交えて詳しく解説する書籍です。プリプロセッサやポインタ、配列などの重要なトピックもカバーし、ネットワークプログラミングやオープンソースの理解を深める内容が含まれています。gccとMakeを用いた実践的な開発手法が紹介されており、大規模開発にも対応可能です。
本書は、IoT(Internet of Things)システムの構築に関する基礎知識と実践的ノウハウを解説しています。著者陣は多様な業界でのIoTシステム開発に携わっており、ゼロからの構築だけでなく、既存システムを基にした構築も取り上げています。IoTはハードウェアとソフトウェアの両面での設計が求められ、多岐にわたる知識が必要です。目次にはデバイス選定、通信方式、クラウドサービス、セキュリティ設計、事例紹介などが含まれています。著者にはソラコムの技術者やIoT専門家が名を連ねています。
この書籍は、ハッカーが持つ知識やサーバー侵入の具体的な手順を初心者にも理解できるように解説しています。著者のIPUSIRONは、ハッカー育成講座を提供し、ハッキング技術を教える内容となっており、10年ぶりの最新作です。目次にはネットワークハッキングの理論と実践が含まれています。著者は福島県出身で、セキュリティアカデミーを運営し、数学と暗号理論を専攻していました。
この書籍は、レーザ加工に必要な基礎知識や段取り、実作業のポイントを体系的に解説した実務向けの入門書です。内容は、レーザ加工機の構造や仕組み、段取りの基礎知識、実際の加工作業における注意点などが含まれており、加工品質やコスト算出方法についても触れています。著者は三菱電機の技師で、学術的な背景も持っています。
センサとそのセンシング技術、関連半導体技術、そして技術における役割の変化と今後の期待などを紹介する。 センサとそのセンシング技術、関連半導体技術、そして技術における役割の変化と今後の期待などを紹介する。
この書籍は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を自社に導入したいが方法が分からない経営者や事業担当者に向けたガイドです。DXの本質や導入にあたる壁(何から始めるか、実現フェーズへの進行、リソース不足)を解説し、成功するDXの姿を示します。著者はAIビジネスデザイナーで、豊富な経験を持つ専門家です。
本書は、製造現場で必要な作業工具や取付具について、種類や原理、正しい使い方、便利な使い方のポイントを写真やイラストを用いて解説する実務向けの入門書です。内容は締緩工具、把握・切断工具、取付具・固定具、手仕上げ作業用工具の4章に分かれており、著者は芝浦工業大学の准教授で、ものづくりの専門家です。
本書『マスタリングTCP/IP 入門編 第6版』は、TCP/IPに関する解説書の最新版で、時代に即したトピックを追加し内容を刷新しています。豊富な図版や脚注を用いて、TCP/IPの基本をわかりやすく解説しており、ネットワークやインターネットプロトコルの理解を深めるための入門書として最適です。著者は複数の専門家で構成されています。
本書は、ビッグデータを収集・蓄積・活用する重要性を解説し、一般的なインターネット事業におけるビッグデータ分析システムの構築に必要な基本知識を図とともにわかりやすく紹介しています。目次には、ビッグデータ分析の全体像やシステムアーキテクチャ、機械学習の基礎などが含まれています。著者の渡部徹太郎は、データ工学の専門家であり、リクルートや日本AWSユーザー会での実績があります。
主人公アレックス・ロゴは、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナとの再会をきっかけに工場の再建に取り組む。彼は生産現場の常識を覆すジョナの助言を受け、仲間と共に努力するが、家庭を犠牲にしてしまい、妻ジュリーとの関係が危機に陥る。物語は、仕事と家庭の両立を巡る葛藤を描いている。
本書は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が失敗する理由と、成功するための新しいアプローチ「オーケストレーション」について詳述しています。従来のチェンジマネジメントを超え、組織内の多様なリソースを協働させるために必要な「8つの能力」とCDOやCTOの役割、具体的なアクションを提案します。変革のジレンマを乗り越え、デジタル能力を実装するための実践的な手引きとなる内容です。
本書は、モノづくり現場における「製造品質」「製造原価」「生産期間」を向上させるための治具設計に関する入門書です。治具は作業を楽にし、結果として品質向上、作業効率化、コスト削減を実現します。著者は生産技術コンサルタントの西村仁氏で、治具の導入目的や設計のコツなどを解説しています。
この書籍は、人工知能(AI)と人間の共存について考察し、知性の認識や人間の生き方を探る内容です。三部構成で、第一部ではAIの歴史やディープラーニングの進展を解説。第二部ではAIが世界の見方に与える影響を論じ、第三部ではAIと人間社会の関係や自由主義の課題について考察します。著者はそれぞれ異なる専門分野から、AIの進展がもたらす新しい時代の教養について議論します。
著者ポール・グレアムは、成功したソフトウェアベンチャーの背景や、ものづくりのセンス、ビジネスの成功の秘訣を語ります。彼は、ハッカーとクリエイターの共通点や、革新的なアイデアの重要性を強調し、プログラミング言語やデザインの未来についても考察しています。全体を通じて、常識を超えた発想や行動が成功に繋がることを示唆しています。
現在成功している大人で、中学高校でnerd(日本語では「陰キャ」?)じゃなかったと言い切れる人は滅多にいない。実際に私が出会った優秀な方は昔は陰キャだったように思います。今陰キャだからといって、これからも暗い未来が待っているわけではありません。陰キャのときこそ、本質的なやるべきことをやり、それでいてただ耐えるたけでなく自ら行動することで未来を素晴らしいものにできることを教えてくれます。
本書は、Webエンジニア向けの「IoT入門書」で、物理デバイス、ネットワーク、アプリケーションの有機的な結合に焦点を当てています。電気の基礎から始まり、JavaScriptとNode.js、Raspberry Piを使用して、読者が自分で回路を設計し、ハードウェアを操作できるようになることを目指しています。内容は、全体像の理解、セットアップ、電子回路の制御、センサーとサーバの連携、データの蓄積と活用、実生活への応用に分かれています。著者は、IoT関連の開発経験を持つ岩永義弘です。
この本は、日本企業が新興国の課題解決に取り組む新たな舞台である「ディープテック」に焦点を当てています。著者たちは、過去の技術を活用し、社会的インパクトを持つ解決策を提供することができると主張しています。具体的には、ディープテックの定義や歴史、海外の事例、日本の潜在能力について解説し、ビジネス開発や技術部門の専門家だけでなく、大学生や起業家にも役立つフレームワークを紹介しています。
神奈川工場の長、新城吾郎は、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナと再会することで再建への意欲を取り戻す。ジョナの新しい考え方に基づき、工場の問題を科学的に解決しようと奮闘するが、家庭を犠牲にした結果、妻が失踪してしまう。物語は、全体最適のマネジメント理論であるTOCを基に、工場再建の過程を描いている。
工場の改善のお話で生産管理などに携わる人、経営者全てにオススメの1冊。漫画などでスラスラ読めて分かりやすい。それでいて重要なエッセンスはちゃんと詰まっている。何度も読み返したい1冊。
この書籍は、エンドミル加工に関する基本知識や切削条件、実践的応用法を体系的に整理しています。著者は30年の経験を持つ工具メーカーの専門家で、独自の切削データやトラブル対策を提供。目次にはエンドミルの選定、材質、切削特性、トラブル予防など多岐にわたる内容が含まれ、加工実務を包括的に学ぶことができます。
この文章は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の事例と価値交換の仕組みについて述べています。具体的な企業例として、Netflix、Walmart、Sephora、Macy's、Freshippo、Nike、Tesla、Uber、Starbucksが挙げられ、それぞれの業界でのDXの影響や方向性が紹介されています。また、業界別にDXの事例を分析するセクションもあります。著者は金澤一央で、DX戦略の専門家として多くのプロジェクトを手掛けてきた経歴を持っています。
この文章は、オブジェクト指向ソフトウェア開発に関する書籍の目次を示しており、以下の内容を含んでいます: 1. オブジェクト指向開発の基本 2. 従来の設計の限界 3. デザインパターンの紹介 4. パターンを用いた思考方法 5. 新しい設計のパラダイム 6. パターンのその他の価値 7. ファクトリに関する章 8. まとめと今後の展望 全体として、オブジェクト指向に関する理論と実践を探求する内容です。
本書は、企業文化の変革とデジタル変革(DX)の成功に焦点を当て、マッキンゼーのノウハウを基に「Why」「What」「How」、そして読者自身が何をすべきかを解説します。日本企業はITシステムの導入を目的化しており、真のDXに成功している企業はわずかです。著者は、次世代リーダーに向けて、企業文化の変革が生き残りの鍵であることを強調し、具体的な戦略や人材育成、変革管理の重要性を論じています。
著者アンドレアス・ツェラーは、プログラムのデバッグに関する効率的な方法を提案する本書で、系統的かつ自動的なデバッグの重要性を説いています。具体的なテクニックやツールを紹介し、デバッグ作業の効率化と苦痛の軽減を目指しています。目次には、障害の発生、問題管理、再現、単純化、欠陥修正などが含まれています。著者はコンピュータサイエンスの教授であり、多くのプログラマにとって有益な一冊です。
バイオ・化学センシング、ウェアラブルデバイス、そして情報通信・サイバー関連まで、IoTを指向したセンシング技術についてまとめた1冊! 第1章 IoTのためのバイオ・化学センシング 1 揮発性化学情報(生体ガス・匂い成分)のためのバイオスニファ&探嗅カメラ 1.1 はじめに 1.2 酵素を利用したガス・匂い成分の高感度センシング 1.3 脂質代謝評価のための生化学式ガスセンサ「バイオスニファ」 1.3.1 酵素を用いたアセトンガス用バイオスニファ 1.3.2 呼気中アセトン計測による脂質代謝評価 1.4 呼気中エタノール用の可視化計測システム「探嗅カメラ」 1.4.1 エタノールガス用探嗅カメラ 1.4.2 呼気エタノールガスの可視化計測とアルコール代謝能の評価応用 1.5 おわりに 2 遺伝子センシング 2.1 はじめに 2.2 超高速PCR技術 2.3 IoTによる遠隔医療を志向した遺伝子センシングシステム 2.4 おわりに 3 食品機能センシング 3.1 はじめに 3.2 食品の機能性表示 3.3 食品機能センシング 3.3.1 抗酸化力測定 3.3.2 ORACによる抗酸化力測定 3.3.3 電気化学発光(ECL)による抗酸化力測定 3.4 食品機能のIoT利用 3.5 まとめ 4 微生物・ウイルスセンシング 4.1 はじめに 4.2 モバイル電気化学バイオセンサー 4.2.1 モバイル遺伝子センシング 4.3 モバイル型生菌数センサー 4.4 携帯電話カメラ機能を用いたモバイルバイオセンサーの開発 5 スポーツバイオセンシング 5.1 はじめに 5.2 無線通信機能を備えた携行型電気化学センサの開発 5.3 電気化学計測条件の検討 5.4 実試料の計測 5.5 まとめ 6 テロ対策化学生物剤センシング 6.1 はじめに 6.2 化学剤・生物剤センシング 6.3 捕集から検知までを可能にする自動検知装置の開発 6.4 おわりに 7 重金属汚染センシング 7.1 はじめに 7.2 6種類の重金属の同時測定 7.3 実サンプルを用いた測定 7.4 おわりに 8 ポリマー製フォトニック結晶を用いたポータブルバイオセンシング 8.1 はじめに 8.2 ナノ光学デバイスのバイオセンシングデバイスへの応用 8.2.1 ナノフォトニクス 8.2.2 ナノフォトニクスを用いたバイオセンシングデバイス開発の利点 8.3 ポリマーを基材としたバイオセンシングデバイスの開発 8.3.1 ナノインプリントリソグラフィーを基盤技術とした「プリンタブルフォトニクス」 8.3.2 フォトニック結晶 8.4 IoT応用を指向したフォトニック結晶バイオセンシングデバイス 8.4.1 ポリマー製フォトニック結晶を用いた酵素反応の検出 8.4.2 CMOSカメラを用いた酵素反応の検出 8.5 おわりに 9 ストレスセンシング 9.1 はじめに 9.2 ストレス学説とストレスマーカー計測の課題 9.3 ストレスセンシング用バイオ・化学センシングデバイス技術 9.4 ストレスセンシング用マイクロ流体デバイス技術 9.4.1 唾液NO代謝物分離アッセイ用マイクロ流体デバイスの開発 9.4.2 唾液NO代謝物分離アッセイの実唾液による実証研究 9.5 ストレスセンシング用マイクロバイオセンサー技術 9.5.1 ストレスセンシング用マイクロバイオセンサーの開発 9.6 ウエアラブルバイオセンサー技術 9.6.1 ストレスセンシング用ウエアラブルバイオセンサー 9.6.2 有機トランジスター型FETバイオセンサーの研究 9.6.3 有機トランジスター型FETストレスマーカーセンサーの基礎研究 9.7 終わりに 10 IoT/体外診断デバイスに向けた半導体バイオセンサの可能性 10.1 はじめに 10.2 半導体バイオセンサの原理 10.3 半導体/バイオインターフェイス構造の理解・設計・応用 10.4 診断医療における半導体バイオセンサの可能性 10.4.1 採血フリーグルコーストランジスタ 10.4.2 酵素活性イオンセンシングに向けた一方向固定酵素ゲートトランジスタの創製 10.4.3 アレルギー診断に向けた半導体原理に基づくバイオセンシング技術 10.4.4 Molecular charge contact法による生体分子計測 10.4.5 分子動力学シミュレーションによる半導体/バイオインターフェイス構造の解明 10.4.6 マルチバイオパラメータの同時計測技術 10.5 むすび 11 指輪型精神性発汗計測デバイス 11.1 はじめに 11.2 ストレス社会とストレスチェック制度 11.3 ストレスとは 11.4 ストレス計測 11.5 指輪型デバイス 11.6 指輪型発汗計 12 POCT型体外診断用機器の実用化 12.1 臨床検査用POCT機器 12.2 IoT機能搭載の臨床検査機器 12.3 ヘルスケア領域における検査機器のIoT機能 12.4 最後に 第2章 フレキシブルデバイス 1 フレキシブル温度センサ 1.1 はじめに 1.2 従来の温度センサ 1.3 ポリマーPTC 1.4 体温付近で反応するポリマーPTC 1.5 印刷可能なフレキシブルポリマーPTC 1.6 まとめ 2 有機FET型化学センサ 2.1 はじめに 2.2 有機トランジスタ型化学センサの構造と動作原理 2.3 オンサイト検出を指向した環境計測用センサデバイス 2.4 抗体および酵素を用いないアレルゲン検出法 2.5 有機FET型センサによる身体情報の可視化 2.6 おわりに 3 CMOS技術によるインプランタブル生体センサ 3.1 はじめに 3.2 CMOSチップ搭載インプランタブルセンサに求められる特徴 3.3 インプランタブルCMOSイメージセンサによるグルコースセンシング 3.4 CMOS搭載型フレキシブルバイオデバイスの実現 3.5 まとめと将来展望 4 柔軟なウェアラブルデバイスに向けた銀ナノワイヤ配線の開発 4.1 はじめに 4.2 ウェアラブルデバイス用材料に求められる機械的性質 4.3 ストレッチャブル配線の開発動向 4.4 銀ナノワイヤを用いたストレッチャブル配線技術 4.5 まとめ 5 電極表面処理技術と物性評価 5.1 はじめに 5.2 金属表面の性質 5.3 単分子膜形成 5.4 仕事関数 5.5 表面エネルギー 6 フレキシブルエナジーハーベスター 6.1 エナジーハーベスティングとは 6.2 環境エネルギーの種類と対応するエナジーハーベスターの特徴 6.3 光利用エナジーハーベスター 6.4 電波利用エナジーハーベスター 6.5 振動・圧力利用エナジーハーベスター 6.6 熱利用エナジーハーベスター 第3章 情報通信・サイバー関連 1 歩行映像解析によるバイオメトリック個人認証 1.1 はじめに 1.2 歩容認証の流れと特徴表現 1.2.1 歩容認証の流れ 1.2.2 モデルに基づく特徴表現 1.2.3 見えに基づく特徴表現 1.3 観測方向変化に頑健な手法 1.3.1 生成的アプローチ 1.3.2 識別的アプローチ 1.4 おわりに 2 センサデータに基づく情報システムの構築 2.1 センサデータに基づく音楽コンテンツ生成 2.2 共感空間:人の感情と行動を考慮するアンビエントシステム 2.3 音楽聴取者の生体信号データからのモチーフの発見とそれによる感情の特定 2.3.1 手法 2.3.2 結果 2.3.3 まとめ 3 ストレッチャブル電極を用いた生体計測システム 3.1 はじめに 3.2 ストレッチャブル電極を備えたワイヤレス脳波計測システム 3.2.1 ワイヤレス脳波計測センサシステム 3.2.2 ストレッチャブル電極シート 3.2.3 接触インピーダンス計測回路 3.3 実測結果 3.4 フロンタール脳波を用いたアルツハイマー診断 3.4.1 被験者 3.4.2 脳波計測 3.4.3 実測結果 3.5 まとめ 4 ウェアラブルセンサによるスポーツ支援 4.1 ウェアラブルセンサとスポーツ 4.2 ウェアラブルセンサを用いた深部体温推定 4.2.1 深部体温計測の現状 4.2.2 生体温熱モデル 4.2.3 Gaggeの2ノードモデルによる深部体温推定 4.2.4 モデルパラメータのキャリブレーション 4.3 今後の展望
この書籍は、日本企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進する際の課題を探ります。コロナ禍でDXの重要性が浮き彫りになった一方、日本企業は変革に苦手意識を持ち、過去の成功体験に固執しているため、DXが進まないと指摘しています。著者は、業務、組織、人、ITの「習慣病」を克服することがDX成功の鍵であると述べ、変革を遂げた6社の事例を通じて具体的なアプローチを解説します。
Pythonの基礎をしっかりと学べる構成になっていて、プログラミング初心者にも取り組みやすい内容。基本的な文法から実際に使えるスクリプトまで、ステップバイステップで解説されているため、無理なく進められます。増補改訂版として新たなトピックも追加されており、実践的なスキルを習得したい人にぴったりです。
Pythonを学びはじめる際に最初に読む本として最適。非常に分かりやすく基礎の基礎から学べる。
本書は、AI社会における職業の不安を解消し、文系の人がAIを活用してキャリアアップするための実践トレーニング本です。専門用語を最小限に抑え、多様な業種別事例を通じてAIとの共働きスキルを身につける方法を紹介しています。内容は、AI社会での職の保持、文系向けのAIキャリア、AIの基本理解、企画力の向上、業種別事例の紹介などを含んでおり、特に文系のAI人材が社会に与える影響に焦点を当てています。著者はAIビジネスの推進に取り組む専門家です。
本書は、デジタル化が進む世界の本質を解説し、日本企業がオンラインを活用する従来のアプローチを見直す必要性を訴えています。著者たちは、オフラインが存在しない「アフターデジタル」の時代を提唱し、すべてのビジネスがオンライン化される未来を描いています。内容は、デジタル化の現状、OMO型ビジネスの重要性、具体的な事例を通じた思考訓練、日本のビジネス変革に焦点を当てています。デジタル担当者だけでなく、未来を拓くすべてのビジネスパーソンに向けた一冊です。
デジタルが主体の時代に突入しどのように顧客行動が変わっていくかを中国の事例をふんだんにまじえながら教えてくれる良書。デジタル時代のマーケティングをおさえるためにぜひ読んでおきたい1冊
本書は、情報システムの設計手順を体系化し、ユーザーと開発チームをつなぐ方法を明示します。各工程の目的や作業内容を示しながら、データ、業務プロセス、画面UIの設計を「概要定義から詳細定義へ」「論理設計から物理設計へ」と進める手順を説明します。特定の開発手法に依存せず、実装技術や環境変化に左右されない原理原則を実践に即して解説しています。著者はシステム設計や業務改革に携わる専門家です。
本書は、機械学習アルゴリズムをオールカラーの図を用いてわかりやすく解説した入門書です。17種類のアルゴリズムを紹介し、各アルゴリズムの仕組みや使用方法、注意点を詳述しています。Pythonを用いたコードも掲載されており、実際に試しながら学ぶことができます。機械学習を学ぶ初心者や業務で利用している方にも役立つ内容となっています。
安藤裕美は人材紹介会社から独立し、プログラマーの転職を扱う企業「コードエージェント」を設立。しかし、取引先のプログラマーが企業データを暗号化して失踪し、7000万円の身代金を要求する事件が発生。安藤は出資者から紹介されたやる気のなさそうなプログラマー、鹿敷堂桂馬と共に極秘捜査を依頼される。情報社会を背景にしたブラックな社会派ミステリーが展開される。著者は柳井政和。
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性と実践方法について解説している。特に日本の少子高齢化に伴う人手や税金の不足を補うためにDXが不可欠であると述べ、正しい理解と実践が不足している現状を指摘。著者の坂村健が、DX推進のための成功の秘訣を明らかにする。目次には、DXの定義、道のり、オープンデータ、アジャイル手法、オープンの哲学、程度の問題の科学、社会におけるDXが含まれている。
本書は、日本企業がIoT化を進める際の指針を提供しています。IoT導入における障壁やその解決策を探り、企業がどのようにIoTを活用できるかを示しています。内容は、IoTの市場構造や事例、構築の手順、セキュリティの問題、組織の壁を乗り越える方法、さらには日本型IoTビジネスモデルへの提言が含まれています。著者は、日立製作所での豊富な経験を持つ大野治氏です。
日本の製造業は技術や品質に強みを持ちながらも、「モノづくり」に依存し、苦境に立たされています。著者は、企業が直面する5つの罠を指摘し、稼ぐ力を取り戻すための戦略を提案しています。具体的には、見える化、標準化、つなぐ化といった処方箋を通じて、企業の復活と再成長モデルを示しています。著者は経営共創基盤のCEOであり、様々な企業の経営改革に携わっています。
本書は、情報セキュリティ技術者向けの必携書で、Python 3に対応して改訂されています。サイバー攻撃手法をPythonを用いて解説し、通信プログラム、Proxy、Webアプリケーションへの攻撃、トロイの木馬の動作、フォレンジック手法、OSINTなどを扱い、攻撃者の手法と防御方法を学びます。日本語版には追加付録として「Slackボットによる命令の送受信」などが収録されています。著者はサイバーセキュリティの専門家やプロのプログラマーなど多様な経歴を持つ人々です。
自然言語処理編
ゼロから分かるディープラーニングシリーズはどれも非常に分かりやすい。こちらの自然言語処理編は前作を読みディープラーニングの基本を理解してより高度なアーキテクチャを学びたいと思った時にオススメ。レベルは少々上がっているがそれでも分かりやすく学べる。RNNやLSTMなどが学べる
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性とその実践方法について解説しています。著者はコロンビア大学の教授で、顧客、競争、データ、革新、価値の5つの要素(CC-DIV)を用いて、企業が新しいビジネスモデルを確立し、プロアクティブに自己変革を進める方法を示します。DXを戦略的な取り組みとして理解し、変化に適応するための具体的なフレームワークを提供しており、長期にわたり教科書としての価値があるとされています。
著者が5000本以上のダンプを解析した経験を基に、ダンプ解析のノウハウを解説する本。目次には、ダンプ解析の基礎知識やデバッガの設定、ダンプファイルの種類、実際の解析手法、条件分岐やケース別調査方法が含まれている。
初心者向けにプログラミングの基本を会話形式で楽しく学べる本です。プログラムの仕組みがイメージしやすく、キャラクターとのやり取りを通じて、複雑な概念もスムーズに理解できる内容になってます。プログラミングに全く触れたことがない人でも、無理なく始められる工夫がいっぱいで、Pythonの基礎を楽しみながら身につけたい人におすすめ。
この書籍は、強度設計に必要な材料力学の基礎や計算方法、実務での事例を丁寧に解説しており、機械設計の初心者から実務者まで役立つ内容を提供しています。目次には、強度設計の基本、材料力学、強度計算の方法、材料の基準強度、実務事例などが含まれています。著者の田口宏之は、豊富な設計経験を持ち、中小企業やスタートアップの支援も行っています。
「iot」に関するよくある質問
Q. 「iot」の本を選ぶポイントは?
A. 「iot」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「iot」本は?
A. 当サイトのランキングでは『図解即戦力 IoT開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで156冊の中から厳選しています。
Q. 「iot」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「iot」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。
















![『IoT電子工作 やりたいこと事典[Arduino、M5Stack、Raspberry Pi、Raspberry Pi Pico、PICマイコン対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41MHymjTx5L._SL500_.jpg)


![『リアルタイムOSから出発して 組込みソフトエンジニアを極める[改装版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41KnzD6hxiL._SL500_.jpg)
































![『(MCPC公式テキスト)IoT技術テキスト 基礎編 改訂3版 MCPC IoTシステム技術検定[基礎]対応』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Rlqsgr6AL._SL500_.jpg)




















































![『Pythonスタートブック [増補改訂版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51fE+EY9yuL._SL500_.jpg)

![『60分でわかる! IoTビジネス最前線[改訂2版] (60分でわかる! IT知識)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZEwE7c2BL._SL500_.jpg)



















![『[第3版]Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践 (impress top gear)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51j2a-lVLyL._SL500_.jpg)






![『ワイヤレスIoTプランナーテキスト[基礎編] 第3版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51IkmXqWq2L._SL500_.jpg)