【2025年】「社会保障」のおすすめ 本 161選!人気ランキング
- 15歳からの社会保障 人生のピンチに備えて知っておこう!
- いちばんわかる! トクする! 社会保険の教科書
- 社会保障制度指さしガイド (2024年度版)
- 誰も教えてくれないお金の話 (Sanctuary books)
- 社会保障ってなに? (きみが考える・世の中のしくみ)
- 図解でわかる社会保険 いちばん最初に読む本<改訂6版>
- 図解入門ビジネス 最新 生命保険の基本と仕組みがよーくわかる本[第3版]
- わかりやすい 社会保障制度 ~はじめて福祉に携わる人へ~
- ケースワークの原則[新訳改訂版]:援助関係を形成する技法
- わかりやすい社会保障制度 改訂版 ~はじめて福祉に携わる人へ~
この書籍は、日常生活で直面する困難を描いた10人のストーリーを通じて、社会保障制度について学ぶことができる内容です。家族や健康、仕事などの問題に対処するための知識が、読者や大切な人を守る力になることを伝えています。著者は社会福祉士であり、社会保障制度の改善に取り組んでいます。
この書籍は、主婦のうだひろえが「お金が貯まらない理由」を探る旅を描いています。内容は、節約の罠や家計簿の必要性、赤字の把握、先取り貯蓄、固定費削減など、お金に関する知識を深めるための実践的なアドバイスが満載です。著者は、ファイナンシャル教育の重要性を訴える泉正人で、日本最大級のマネースクールを運営しています。
本書は、社会保険に関する基礎知識を易しく解説した超入門書で、特に総務・労務や経理担当者に役立つ内容です。図解を用いて社会保険制度を分かりやすく説明しており、初心者でも理解しやすいように工夫されています。2011年の初版以来、改訂を重ね、最新の制度変更にも対応した「改訂6版」として新版化されています。医療や介護・福祉分野の現場や社会保険労務士を目指す人にも適しています。著者は、社会保険労務士としての経験を持つ専門家です。
この本は、ケースワークにおける援助関係を説明、定義、分析することを目的としています。目次は二部構成で、第一部では援助関係の本質や形成の原則について述べ、第二部では具体的な原則(個別化、感情表現、情緒的関与、受容など)を詳しく解説しています。著者は、ソーシャルワークや福祉学の専門家たちです。
<<援助職のための 超わかりやすい社会保障制度解説>> ①生活保護、②障害者福祉、③医療保険、④権利擁護、⑤年金、⑥子ども家庭福祉の 6つの社会保障制度について、その概要やサービス利用の流れ、活用事例を豊富なイラストと図表で わかりやすくまとめました。ケアマネジャーや相談援助職必携の1冊です。 ▶“オールカラー”でわかりやすい! 『社会保障制度活用ガイド』は、2022年版より、オールカラーに生まれ変わりました! 2021年版までも好評だった、手続きの流れなどに関する図表がさらに見やすくわかりやすくなりました。 既に2021年版を持っているという方も、要チェックです! ▶現場の実践に即した活用ポイントを紹介! 範囲が広く、必要な書類・手続きも複雑な社会保障制度。 「こんなとき、どんな制度が使えるの?」 「どこに相談すればいいの?」 「申請に必要な書類は?」 こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 本書では、フロー形式で求められる手続きや書類を整理。すぐに実践に活かせる内容が満載です。 ▶新たに「子ども家庭福祉」に関する情報を掲載! 生活困窮に陥っているひとり親家庭や、親に代わって祖父母が孫を養育しているケースなど、 家族のあり方は多様化しています。 相談援助職が押さえておきたい、事態の改善へとつながる社会資源に関する情報を網羅しました。 【主な目次】 早わかり! ケース別活用できる制度一覧 各制度の最新の動きをチェック! 第1章:生活保護 第2章:障害者福祉 第3章:医療保険 第4章:権利擁護 第5章:年金 第6章:子ども家庭福祉 早わかり! ケース別活用できる制度一覧 各制度の動きをチェック! 第1章:生活保護 第2章:障害者福祉 第3章:医療保険 第4章:権利擁護 第5章:年金 第6章:児童福祉
この書籍は、医療現場における患者と医者の意思決定プロセスを行動経済学の観点から分析しています。患者が治療方針を決められない理由や、医者が患者の不安を理解しきれない背景を探り、双方がより良い意思決定を行うための方法を提案しています。具体的には、がん治療や検診、遺族の後悔、高齢患者への支援など、多岐にわたるテーマを扱っています。著者は、医療者と患者がそれぞれのバイアスを理解し、合理的な選択ができるようになることを目指しています。
公立高校野球部のマネージャーみなみは、ドラッカーの経営書『マネジメント』に出会い、野球部を強化するためにその教えを活用します。親友の夕紀や仲間たちと共に、甲子園を目指す青春物語が展開されます。この物語は、家庭や学校、企業など、あらゆる組織に役立つ内容です。著者は岩崎夏海で、放送作家やプロデューサーとしての経歴があります。
この本は、40代を中心とした現役世代の「お金との向き合い方」を変える内容で、無駄遣いや詐欺に対する消費者意識、資産形成の重要性、納税者としての意識を強調しています。新型コロナウイルスによる経済への影響と、株価の上昇が常識に反する理由を解説し、経済ニュースを理解するための基礎知識を提供します。目次では、経済、投資、税金、お金の基本についての章があり、著者は池上彰で、わかりやすい解説が特徴です。
本書は、給与計算や病気、出産、失業、年金受給などに関連する社会保険・労働保険の制度や手続きを分かりやすく解説しています。内容は、社会保険・労働保険の全体像、労働保険や各種保険のしくみについての詳細が含まれており、最新の改正にも対応しています。著者は特定社会保険労務士の小島彰氏で、労務相談やIPO支援など幅広い業務を手掛けています。
この文章は、ソーシャル・ケース・ワークに関する目次を示しており、ソーシャル・ケース・ワークの定義、相互依存、個人差、意図的な行為の基礎、家庭や学校、職場、病院、裁判所との関係、ソーシャル・ワークの形態と相互関係、そしてケース・ワークと民主主義についての内容が含まれています。
この文章は、ロバート・キヨサキの著書の目次と著者情報を紹介しています。目次では、従業員と起業家の違いや、成功するための心構え、実社会での知恵、お金の重要性、ビジネスのリーダーシップについての章が列挙されています。著者のキヨサキは、ファイナンシャル教育の重要性を説き、従来の考え方に挑戦する姿勢を持つ起業家、教育者、投資家として知られています。翻訳者は白根美保子です。
信頼できる最新情報と,叙述のわかりやすさが好評のロングセラー・テキスト。基本的な考え方を通して制度の立体的理解へと導く。 信頼できる最新情報と,叙述のわかりやすさが好評のロングセラー・テキスト。「なぜ」「どうして」と考えていくうちに,制度の構造を立体的に理解できる。1つの制度の構造がつかめたら,比較して学ぶことにより社会保障の全体像が立体的に見えてくる決定版。 序 章 社会保障の見取り図 第1章 医療保険──病気やけがをしたら 第2章 生活保護と社会福祉制度──人らしい生活を保障する 第3章 介護保険──介護サービスを利用しやすく 第4章 年 金──老後の生活費は 第5章 雇用保険──失業したら 第6章 労働者災害補償保険──働く場でけがをしたら 第7章 社会保険と民間保険──2つの保険,その特徴は 第8章 社会保障の歴史と構造
この本は、社会保障に関心のある人々に向けて、複雑な社会保障制度をライフサイクルに沿って解説しています。内容には、手続き方法や問い合わせ先など、役立つ情報が豊富に含まれています。目次には妊娠・出産から高齢者、死亡に至るまでの各章が設けられています。
この本は、経済評論家・山崎元が金融に関する悩みを解決する内容で、マンガを通じてお金の知識を学べます。主なテーマは、他人を信じずに自分でお金を管理すること、年金や積立投資の重要性、新築マンションの購入を避けること、生命保険のリスク、ファイナンシャルプランナー(FP)への注意、銀行との付き合い方などです。読者は、資産運用の基本を理解し、賢いお金の使い方を学べる内容となっています。
日本の社会保障はなぜ使いにくいのか。複雑に分立した制度を整理し、その根底に渦巻く「働かざる者食うべからず」の精神を問う。 日本の社会保障はなぜこんなに使いにくいのか。複雑に分立した制度の歴史を辿り、日本社会の根底に渦巻く「働かざる者食うべからず」という倫理観を問いなおす。 病気やケガをしたとき、出産や育児、そして介護が必要になったときの生活を保障する社会保険。働けなくなったときや老後の生活を支える年金制度。毎月の給料から天引きされているものの、いざというとき自分がどの給付を受けられるのかわかりにくく、申請するのもどこか後ろめたい。日本の社会保障はなぜこんなにも使いづらいのか。複雑に分立した制度の歴史から、この国の根底に渦巻く「働かざる者食うべからず」の精神を問い、誰もが等しく保障される社会のしくみを考える。 はじめに 複雑で使いにくい社会保障/問題はどこにあるか/法律学というアプローチ/社会保障と法解釈/「勤労の義務」を問いなおす/人々の意識と法的権利/理想の社会保障に向けた共同作業 第一章 なぜ働き方によって社会保障が違うのか――労働者と自営業者 1 社会保障の全体像 老後四八八〇万円問題?/「労働」とは何か/「労働者」と「自営業者」/日本の社会保障の体系 2 公的年金における違い 公的年金の構造と老齢期の差/同業者同士での対応の限界 3 医療における違い 公的医療保険の構造/自営業者への対応 4 失業時・雇用継続対策における違い 雇用保険の適用関係による違い/求職者支援制度 5 労働災害における違い 労災保険という仕組み/労災保険の適用の有無による違い/労災保険への特別加入 第二章 なぜ働き方で分立しているのか――四つの社会保険 1 制度がつくられた時代 戦後日本の就業構造/農林業が中心だった時代 2 公的年金はなぜ分かれたか――国民年金と厚生年金 公的年金の歴史/労働者年金の設立と厚生年金への改組/国民年金の設立をめぐって/自営業者の所得を把握するのは難しい?/なぜ公的年金は分かれたか 3 公的医療保険はなぜ分かれたか――国民健康保険と健康保険 現在の公的医療保険/国民健康保険の制定・改正をめぐって/なぜ自営業には傷病手当金等がないか 4 雇用保険はなぜ自営業者には適用されないか 雇用保険とは何か/「自発的な」失業? 5 労災保険はなぜ自営業者には適用されないか 労災保険とは何か/特別加入とその例外性 6 社会保険はなぜ分かれたか 制度分立の理由/労働者中心の社会保障 第三章 なぜ使いにくいのか――社会保障と情報提供義務 1 社会保障と情報提供義務 申請しないと給付は受けられない?/情報提供義務をめぐる先駆的裁判例/その後の裁判例 2 行政以外の情報提供義務 民間主体と情報提供義務/行政の肩代わり? 3 他分野との比較 企業年金分野との違い/厚生年金基金と情報提供義務/確定給付年金と情報提供義務/社会保障法領域との比較 4 情報提供義務のどこが問題か 情報提供義務の意義/情報提供義務の限界 第四章 生活保護のうしろめたさ――社会保障と「勤労の義務」 1 生活保護を受給できるのは誰か 働かなくても生活保護を受けられる?/「稼働能力」とは何か 2 行政による「指導・指示」 受給中は「指導・指示」を受ける/働きながら生活保護を求めたXさんの事案/職業選択の自由?/裁判所の判断内容/「勤労の義務」と生存権 3 生活保護と不正受給 最低生活費はどう決まるか/不正受給は増えているのか/不正受給の事案/不正受給の背景にあるさまざまな事情/「働くこと」をめぐる規範意識 4 「勤労の義務」という精神 法の根本にある「勤労の義務」/「勤労の義務」という倫理観 中間のまとめ 「勤労の義務」という呪縛 「勤労の義務」と生活保護/「勤労の義務」と社会保障/「勤労」の中身?/時代状況の変化と「勤労」/「働かざる者食うべからず」という倫理観/倫理観が権利を阻害する/問題の根本はどこにあるか 第五章 「勤労の義務」の意味―日本国憲法制定時の議論を読む 1 なぜ「勤労の義務」を検討するか 「勤労の義務」規定と法的な効力/法解釈に唯一の正解はない 2 日本国憲法制定時の帝国議会の議論 帝国議会の推移と衆議院本会議での議論/衆議院帝国憲法改正委員会での議論 3 衆議院帝国憲法改正小委員会による勤労義務の挿入 小委員会の構成と生存権への言及/「勤労」か「労働」か/「勤労」とは何か/「法的義務」か「道徳的義務」か/道徳的義務としての見解の一致/文言の確定 4 勤労の義務の法的意義 イデオロギーを超えた合意/「勤労」と「義務」 第六章 働くことと社会保障を切り離す 1 変化する働き方 働き方と社会保障の関係を問いなおす/非正規労働者などの状況/変化する自営業者の就業実態/労働者という働き方の変容 2 社会保障をめぐる論争史 公的年金――民主党の年金一元化案/医療保険――コロナ禍による部分的な実現/雇用保険とその周辺をめぐる動向/労災保険における特別加入 3 働くことと社会保障を切り離す 依然として残る労働者中心主義/働き方の順位付けと法解釈問題/「働くこと」と社会保障を切り離す/技術的な問題 終章 新しい社会保障のために 1 現行制度とどうつなげるか 問題点のおさらい/現行制度をベースとした年金と医療の構想/現行制度をベースとした雇用保険の構想/現行制度をベースとした労災保険の構想/技術的な問題をどう乗り越えるか/複雑であっても利用しやすい社会保障/生存権の実現―「働かざる者食うべからず」を問いなおす 2 まったく新しい社会保障へ 社会保険を編みなおす/最低生活保障を編みなおす ブックガイド あとがき 参考文献
本書は、不安や恐怖を克服し、起業に必要な知識やスキルを身につけるためのガイドです。起業のアイデアからビジネスプラン、商品開発、価格設定、マーケティング、チーム作りまでを網羅しており、著者の今井孝が多くの起業家に成功のノウハウを伝えてきた経験を基にしています。
本書「日本社会のしくみ」は、現代日本が抱える様々な社会問題—女性や外国人への閉鎖性、転職の難しさ、長時間労働による低生産性など—の背景を探求しています。著者は、日本社会の慣習や雇用慣行がどのように形成されてきたのかを歴史的に検証し、改革が進まない理由を考察します。全体を通じて、雇用、教育、社会保障、政治などの側面から日本の社会の構造とその変化について分析しています。
この書籍は、人気の投資系YouTuber、高橋ダンの初著書であり、毎日2ページ読むことでお金に関する知識を身につけられる内容です。目次には、マインド、投資の基本、ポートフォリオ、短期投資、コモディティ、不動産、経済、習慣が含まれています。著者は東京出身で、アメリカで投資を学び、ウォール街での経験を経てヘッジファンドを共同設立した経歴を持っています。
この書籍は、相談面接技術に関する内容を扱っており、主に以下の三つの章で構成されています。第一章では、面接の環境や時間の使い方について説明し、第二章では面接技術の具体的な方法を紹介しています。第三章では、逐語的に相談面接技術を学ぶことに焦点を当て、実際の面接の進め方や援助関係の構築について述べています。著者は岩間伸之で、大阪市立大学の准教授であり、社会福祉学の専門家です。
この書籍は、女性が「好きなこと」や「得意なこと」を活かして起業するための実践的なガイドです。近年、自宅やシェアオフィスを利用して起業する女性が増えており、様々な業種で活動しています。本書では、事業プランの立て方、資金計画、開業準備、日々の運営方法など、起業に必要な知識やノウハウを提供し、トラブルを避けるためのアドバイスも含まれています。著者は女性の起業支援に特化した専門家で、実際の事例を交えながら、長期的に安定した事業運営を目指す方法を解説しています。
この書籍は、社会福祉事務所や自治体の相談業務に従事する人々が、相談者のニーズに応じた適切な社会サービスを紹介できるように、さまざまな社会保障制度をまとめた実務書です。2025年版では、診療や障害、介護報酬の改定に加え、最新の施策情報を提供し、未施行の改正内容も参考として掲載しています。主な目次には、高齢者、障害者、児童、生活保護など、幅広い福祉関連のテーマが含まれています。
この文章は、援助職者に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、援助職者の基本的な視点や援助関係、アセスメント、相談面接のプロセス、高齢者への援助、燃えつき防止策、介護の現実、ケアマネジメントについての章が並んでいます。著者の渡部律子は、社会福祉学や心理学の専門家で、日米での臨床経験と教育歴を持っています。
この書籍は、社会保障のあり方が日本の未来に与える影響について論じたもので、元厚労官僚の著者が社会保障制度の改革や維持の必要性を提起しています。内容は、社会保障の基礎、税改革の課題、年金や医療・介護の維持、少子化対策の家族支援、経済・財政の立て直し、そして民主主義のための社会保障についての考察が含まれています。著者は数々の政策を担当し、社会保障と税制の一体改革に関与した経験を持っています。
本書は、お金の仕組みを理解することで、働くことやお金から自由になる方法を解説しています。著者は、サラリーマンとしての限界を感じた経験をもとに、日本の税制や企業の実態、金融機関の影響を分析し、手取りを増やす秘訣やマインドセットの重要性を強調しています。また、労働者から資本家へと変わるためのステップや不労所得の重要性についても触れています。全体を通じて、読者にお金に対する新たな視点を提供する内容です。
この本は中小企業の経理・労務を支援する実務マニュアルで、基礎知識から定型業務、ケース別対応までを網羅しています。2025年の法改正にも対応し、オールカラーで見やすくなっています。初心者向けに給与計算や社会保険の基本を解説し、実務の流れや具体的な手続きも詳しく説明。特に、年金・健康保険、雇用保険、年末調整などの実務や、個別ケースに関する手順も豊富に掲載されています。
本書は、長寿社会における新しい生き方や働き方を探る指南書です。著者は、教育、仕事、引退の従来のモデルが崩れつつある中で、個人がどのように戦略的に人生を設計すべきかを提案しています。重要なポイントとして、健康で長い人生を楽しむためには、見えない資産(スキルや人間関係など)の重要性や、柔軟な働き方、選択肢の多様化が挙げられます。また、結婚や労働市場の変化についても触れ、個人のアイデンティティや役割の調整が必要であることを強調しています。全体として、100歳時代を迎えるにあたっての新しいライフスタイルの指針が示されています。
今では色んなところで引用される人生100年時代というパスワードのきっかけになった書籍。もう既に1つの会社に勤め上げるような旧来の生き方は崩壊している。将来に不安を抱いているビジネスパーソンはこの本を読んで時代の変化に置いていかれないような生き方を選択して欲しい。
著者・山口周は、現代の変化する世界において「正解を出す力」の価値が低下していると主張し、新たな生存戦略を提案しています。彼の著作では、思考法や働き方、キャリア、学び方における「ニュータイプ」の重要性が強調され、問題解決から課題設定へのシフトや、論理と直感の融合などのメガトレンドが紹介されています。
山口周さんの書籍はどれも素晴らしい。なんとなくふんわりと世の中に感じていることを言語化して理論的に積み上げて語ってくれる。この本ではオールドタイプとニュータイプの対比からニュータイプと呼ばれる現代を生き抜くためにどのような思考や行動を持つべきかという示唆を与えてくれる。課題を解決能力は既に誰もが持っている世の中では課題を発見し意味を見出し語れる能力が大事なのである。
本書は、日本の億万長者、本多静六が金銭と人生についての哲学を語った作品で、初めて文庫化されたものです。彼は貧農から東大教授となり、「月給4分の1天引き貯金」を元に巨万の富を築きました。晩年には全財産を寄付し、シンプルな生活を実践しました。目次には、貯金法、投資の鉄則、成功法などが含まれており、時代を超えた普遍的な真理を提供しています。
本多静六氏の書籍を読んで実践することでどんな人でもそれなりの富を築くことができるはず。誘惑に負けず愚直に貯めて投資をしよう。本多静六氏の書籍はどれも良作であり長年経っても決して色あせない重要なエッセンスが詰まっている。
この書籍は、ソーシャルメディアでの効果的な文章作成をテーマにしており、投稿が読まれない、仕事や人脈に繋がらない、書くネタが見つからないといった悩みを持つ人に向けて書かれています。著者はコピーライターの前田めぐるで、読みたくなる文章の書き方や信頼性のある文章の基本、情報の価値を高めるノウハウ、SNS疲れ対策などを詳しく解説しています。また、文章の質が人脈や仕事に影響を与えることを強調し、独自の視点を持った情報発信の重要性も述べられています。
「づんの家計簿」は、インスタグラムで人気を博した家計簿で、楽しく簡単にお金を管理できる方法を提供します。読者からは「楽しい」「きれい」との評価を受け、自然に貯金が増え、無駄に気づくことができると評判です。基本から応用までの書き方や、家計の把握方法を紹介し、主婦が成長する過程も楽しめる内容です。
生活保護、年金、医療、公衆衛生、介護保険、労災保険と雇用保険、子育て支援、財源としての消費税など、その最新事情から課題まで。 生活保護、年金、医療、公衆衛生、介護保険と高齢者福祉、労災保険と雇用保険、子育て支援、障害者福祉、財源としての消費税など、その最新事情から課題まで。 最新の法改正から判例、いま指摘される高額療養費などの課題まで。 社会保障の全体像をこの一冊で把握する 年金、介護、医療、労災、障害者福祉……現状と展望 私たちはいつ、病気で働けなくなったり、障害を負ったり、会社が倒産して仕事を失ったりするかわからない。個人の努力ではどうしようもない場面に遭遇した時にも健康で文化的な最低限度の生活が維持できるように憲法の生存権を保障する仕組みが社会保障だ。自分の力や家族や地域での支えあいではどうにもならないことが多いからこそ、この仕組みが必要である。では、法律と運用はどうなっているか。生活保護、年金、医療、公衆衛生、介護保険と高齢者福祉、労災保険と雇用保険、子育て支援、障害者福祉、社会保障財源としての消費税など、その仕組みと財政の最新事情から課題まで網羅する一冊。 序章 広がる貧困と生存危機 第一章 社会保障とは何か 1 社会保障の発展史 2 社会保障の定義と内容 ── 国民の生存権と国の義務 3 主要5制度 ── 公的扶助、社会保険、社会福祉、社会手当、公衆衛生 第二章 生活保護(公的扶助) 1 生活保護の現状と攻撃されるセーフティネット 2 どのような場合に、生活保護が受けられるのか ── 基本原則と仕組み 3 「健康で文化的な最低限度の生活」の水準とは? ── 保護の基準 4 8つの法定扶助 ── 生活保護の種類と方法 5 権利救済の仕組みと生活保護裁判のゆくえ 6 生活保護と生活困窮者対策の課題 第三章 年金 1 日本の年金制度の仕組みと特徴 2 給付 ── 老齢年金、障害年金、遺族年金 3 年金財政と年金積立金 4 年金改革の展開 5 年金改革の動向とゆくえ 6 安心できる年金制度の確立に向けて 第四章 医療 1 医療保険のあらましと公費負担医療 2 保険給付と診療報酬制度 3 医療保険財政と保険料 4 高齢者医療と特定健診・特定保健指導 5 病院再編・統合、病床規制 ── 医療提供体制のゆくえ 6 医療制度改革の動向と医療の課題 第五章 公衆衛生 1 重要性が再認識された社会保障としての公衆衛生 2 感染症法 3 予防接種法 4 地域保健法と母子保健法、母体保護法 5 精神保健福祉法 6 機能不全を招いた教訓と公衆衛生の課題 第六章 介護保険と高齢者福祉 1 介護保険のあらまし 2 介護保険財政と介護保険料 3 介護保険制度改革の展開 4 利用者からみた介護保険の問題点 ── 負担増と介護の再家族化 5 事業者・介護職からみた介護保険の問題点 ── 介護報酬減と深刻な人手不足 6 介護保険と高齢者福祉の課題 ── 介護保険から安心の介護保障へ 第七章 労災保険と雇用保険 1 労働保険の現状 2 労働保険と保険料 3 労災認定の仕組み 4 労災保険の給付と社会復帰促進等事業 5 雇用保険の給付と雇用保険事業 6 劣化する雇用と労働保険の課題 第八章 児童福祉・保育と子育て支援 1 児童福祉法 2 保育政策と少子化対策の展開 3 児童手当と児童扶養手当 4 児童虐待を防ぐには 5 保育の規制緩和がもたらしたもの ── 保育士不足と保育事故の増大 6 児童福祉・保育と子育て支援の課題 第九章 障害者福祉と障害児の療育 1 障害者福祉の改革史 2 障害者総合支援法 3 障害者福祉各法と障害者の雇用促進 4 障害児の療育 5 障害者・障害児への社会手当 6 障害者福祉と障害児の療育の課題 ── 重い家族負担の解消を! 第十章 社会保障の財政 ── 税制改革と社会保険改革の方向性 1 社会保障財政の特徴 2 歳出削減の最大ターゲットは社会保障費 3 消費税による財源確保の問題点 4 どんどん増える社会保険料負担の問題点 5 消費税はどこに消えた? 6 税制改革・社会保険改革の方向性 終章 社会保障はどこへ向かうのか 1 財源確保のための税制改革・社会保険改革の実現可能性 2 社会分断を煽る議論に抗して 3 政策転換の岐路
本書は、地域を基盤としたソーシャルワークの理論と実践について、著者の岩間伸之氏が解説しています。「行政」「専門機関」「地域住民」が協力して住民主体のソーシャルワークを展開するための指南書であり、地域の総合相談拠点の取り組みを紹介しています。目次には、本人主体のソーシャルワーク理論、地域を基盤としたソーシャルワークの全体像、総合相談の実践、ソーシャルワークにおける価値についての章が含まれています。著者は社会福祉の専門家であり、理論書として今後の社会福祉の方向性を示しています。
デザイン思考は「人々が抱える本当の問題」を解決するための考え方であり、共感やプロトタイプなどのプロセスを通じてユーザーを理解し、新しいアイデアを生み出します。本書は、著者がスタンフォード大学d.schoolで学んだ知識や実践経験を基に、デザイン思考を身に付けるための具体的なノウハウを提供しています。特に実践に重点を置いており、ビジネスパーソンや学生、マネジメントに関わる人々におすすめです。
戦後日本の社会保障の形成において社会保障制度審議会(1949?2001年)が果たした機能と役割を分析し、その有識者委員――近藤文二、末高信、大河内一男、隅谷三喜男――の理念が勧告・建議を通じて社会保障の発展に及ぼした影響を論じる。日本の社会保障のあり方に示唆を与える社会政策史。 はじめに 戦後日本社会保障の理念と政策過程 第Ⅰ部 社会保障制度審議会の軌跡 序 第1章 社会保障制度審議会の創設 第1節 設置の契機──ワンデル勧告(1948年)等の指摘 第2節 制度審設置法閣議決定案の作成──日米の交錯した思惑 第3節 法制上の主要論点 (1)制度審の性質 ①独立性の源泉──内閣総理大臣の所轄等 ②能動性と受動性──自らの建議と「あらかじめ」の諮問 ③役割の変遷の根源──所轄と権限の問題 (2)審議対象の範囲 ①法制定時の経緯──思惑が交錯したもう一つの論点 ②具体的な対象の内外──省庁との駆け引きと運用 (3)定めのない設置期限 (4)事務局の設置と幹事 ①事務局の設置──制度審の重要性の表れ ②幹事の扱い──後年の「実益」 第4節 国会議員の参画──社会保障への理解と支持 第5節 委員及び会長の選定──大内兵衛という牽引者 第2章 社会保障制度審議会が果たした役割の変遷 第1節 制度審の審議スタイル──不文律の確立と継続 第2節 制度審の果たしてきた機能と役割 (1)所与の機能──設置法が付与した権限 ①制度所管省庁から離れた立場からの提言等 ②例年の諮問への答申 (2)3期にわたり変遷した役割 (3)データで見る変遷の様子 ①勧告等の数 ②起草委員のシェアの変遷 ③国会での言及 ④小委員会制の変遷 (4)社会保障の成長・成熟と役割の変遷 ①第1期 社会保障の「推進役に回った」時代(創設~国民皆保険・皆年金) ②第2期 社会保障を「育成」する時代(総合調整~昭和の終期) ③第3期 社会保障を「護る」時代(平成前期) ④社会保障の性質と役割の変遷 (5)役割の変遷と政治構造の変質 ①自民党内における部会・族議員の台頭、及び与野党の構図の固定化 ②日本医師会等の一時の「不在」 (6)委員の属人性と役割の変遷──大内兵衛、近藤文二、今井一男 第3章 社会保障制度審議会の歴史の今日的意義 第1節 制度設計の妙と政争の具からの隔離 (1)制度設計に関わる点1──設置法と不文律の継続 (2)制度設計に関わる点2──第2条第2項を設けた意義(定期的な答申の重み) (3)政争の具からの隔離 第2節 制度審の廃止とその後の社会保障政策の展開 第3節 各論への貢献の分析 第II部 社会保障制度審議会委員における社会保障・社会政策の理念 序 第1章 日本における社会保障概念の確立──近藤文二による1950年勧告の起草 序 1950年勧告に向けた理論的格闘 第1節 社会保障概念を導いた論考の概観 第2節 近藤の概念と1950年勧告 (1)社会保障の範囲 ①近藤の系譜的整理と社会保障の範囲 ②1950年勧告と近藤の概念の関係 (2)社会保険中心主義 ①自主的責任の論理 ②社会保険の社会事業化の防止 第3節 時代状況の影響 (1)公衆衛生(特に結核)と貧困の関連 (2)社会主義との距離 (3)GHQの意向 第4節 近藤の論考の意義、及び今日的課題への示唆の追究 第2章 社会保険の本質及び接続領域 ──末高信の社会保障概念と社会保険制度調査会(1946年設立)を中心とした活動 序 末高の画期性と柔軟性 第1節 末高の社会保障概念の分析 (1)社会保険と社会保障の相違 (2)幅広い社会政策概念 (3)社会保険における保険事故の領域と限界 (4)社会保険とその接続領域──社会保障の萌芽 (5)ビバリッジ報告(1942年)と末高との近似性 (6)末高の社会保険概念の変転 第2節 終戦直後期の末高の活動 (1)社会保障研究会、社会保険制度調査会と社会保障制度要綱のまとめ(1947年1 月まで) 178 (2)社会保障制度要綱(1947年10月)への末高の評価 (3)ワンデル勧告(1948年)への末高の共感 (4)1950年勧告と末高──当初の批判,そして後の推進 (5)米国へのシンパシー 第3節 末高の論考と活動の評価 第3章 社会保障の基本理念としての生存権 ──1950-60 年代における近藤文二、末高信、平田冨太郎の論争 序 異なる生存権概念の捉え方 第1節 第1期(1950年前後)における論争 (1)生存権の具体化としての社会保障──末高の所論 (2)基本的人権としての生存権──平田の所論 (3)「生存権」を「生存権」として認めない資本制社会──近藤の批判 第2節 第2期(1960年前後以降)における論争 (1)国の努力義務としての生存権──近藤の提起 (2)生存権を援用した社会保障──末高の所論 (3)生存権を目的とする社会保障──平田の所論 第3節 末高、平田の妥当性 第4節 近藤の意図とその背景 (1)純粋経済学的な視点の貫徹 (2)社会保障充実のための負担の必要 第5節 負担の合理性の意義,権利論の展開という課題 第4章 「労働力の保全・培養」から「新しい社会政策」へ ──1970-80 年代における大河内一男の転回と社会保障制度審議会 序 「大河内理論」と社会保障制度審議会 第1節 「大河内理論」の転回 (1)基本的な考え方の提示 (2)社会政策と社会保障の連続 (3)ライフサイクル、非労働・消費生活、雇用関係以外の者 (4)「働く」を基本理念とした社会政策と社会保障、公的扶助、社会福祉の総合化 (5)資本主義社会での人間観の一貫性 第2節 大河内の転回の制度審への影響の検討 第3節 「総合社会政策」の今日的有効性 補 論 1995年勧告と隅谷三喜男──大河内からの継承と発展、及び射程の限界 序 理論的研究への注力 第1節 会長就任前の隅谷と社会保障(理論への関心) (1)1960年代の隅谷と社会保障 (2)社会保障の理論再訪(1980年の論考) 第2節 「広く国民」の社会保障 (1)「社会保障の新しい理論を求めて」(1989年及び1991年) (2)「広く国民」の社会保障 (3)隅谷の理論の評価──生存権を超える水準の必要 第3節 自立と社会連帯──大河内からの継承と発展 (1)大河内からの継承と発展 (2)理念や哲学の洞察──制度審の意義再訪 第4節 新たな時代への展開と射程の限界 (1)公的介護保険制度創設を提唱した意義 (2)射程の限界──社会保障と雇用政策 第5節 制度各論へのインパクト、隅谷の研究と信仰の関係という課題 おわりに 制度審の指向性と委員の理念が共存する場 あとがき
この書籍は、戦略デザイナーの佐宗邦威が「根拠のない妄想」を活用して、プレゼンや意思決定、アイデア創出を効果的に行う方法を紹介しています。著者は「妄想→知覚→組替→表現」の4段階サイクルを提案し、直感を現実に結びつけることで強いインパクトを生む技法を解説。妄想から価値あるアイデアを生み出すプロセスを通じて、停滞感を打破する思考法を探求しています。
保険会社が教えない本当の選び方 生命保険は「妻」を中心に、が正解! 日本で数少ない「保険評論家」として有名な著者がはじめて書き下ろす、保険見直しに潜む罠から損得、見直しのポイントまでわかりやすく教えてくれる本。 第1章 保険の見直しに潜む大きなカン違い 第2章 見直すなら「妻」を中心に、が正解! 第3章 20年後に後悔しない保険商品選び 第4章 担当者が言わない本当の保険の選び方 第5章 老後の不安に効く正しい保険選び 巻末付録 ちょっと聞きにくい保険のQ&A
この書籍は、ハッピーライフを実現するための基本や考え方を探求しています。第1章では実感を大切にした暮らしについて、第2章では「普通」とは何かを問い、第3章では衣食住の重要性を考察し、第4章では日々のポジティブな思考法を紹介しています。著者は大原扁理で、愛知県出身の彼は、高校卒業後に引きこもりを経験し、その後の旅を経て隠居生活を送っています。
この文章は、地域社会における多様な課題や支援体制についての内容を示しています。具体的には、地域共生社会の実現、福祉ガバナンス、多機関の協働、地域基盤のソーシャルワーク、災害時の支援体制、福祉計画の重要性とその運用、福祉行財政システムに関する章立てが紹介されています。
お金の力を正しく知って、思い通りの人生を手に入れよう。変化の時代のサバイバルツールとして世界中で読まれるベスト&ロングセラー オリエンタルラジオ 中田敦彦さん「YouTube大学」で紹介、大絶賛! □最初に読むべき「お金」の基本図書 毎年多くの「お金」に関する本が出版され,書店に並び、そして消えていきます。 そんな状況の中で、「金持ち父さんシリーズ」は刊行から20年経った今でも変わらず多くの支持を得ています。 その第1作目である『金持ち父さん 貧乏父さん』は、時代が変わっても古びない原理原則を示す「お金」の基本図書。 「目からウロコの連続でした! 」という声が絶えず寄せられ、これまで数多の人々の「お金観」を変えてきました。 日本やアメリカのみならず、本書が刊行された2013年時点で51ヶ国語に翻訳され、109ヶ国で読まれています。 教えの書―金持ち父さんの六つの教え 金持ちはお金のためには働かない お金の流れの読み方を学ぶ 自分のビジネスを持つ 会社を作って節税する 金持ちはお金を作り出す お金のためでなく学ぶために働く 実践の書 まず五つの障害を乗り越えよう スタートを切るための十のステップ 具体的な行動を始めるためのヒント
物語形式で、わかりやすくお金への知識が書いてありました。お金に関する本では、お金の使い方がずさんな人に対して攻撃的や嫌味な表現も見られますが、この本はそういったものがなく、気持ちよく読了できました。お金に関する入門書としてぜひ読んでほしいです。
『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』は、金銭教育の重要性と資産形成の基本をわかりやすく教えてくれる一冊です。著者が実際に経験した「金持ち父さん」と「貧乏父さん」の対比を通じて、働いて稼ぐだけでなく、投資やビジネスを通じた資産の増やし方を学べます。学校では教わらないお金に関する知識を、誰にでも理解しやすいエピソード形式で展開しており、特に経済的自立を目指す人にとって有益です。
この書籍は、Googleで「最速仕事術」を開発した著者たちが提案する、効率的な時間管理メソッドを紹介しています。テクノロジーに囲まれた現代において、重要なことに時間を使うための具体的な方法を提供します。内容は、実用的なノウハウや図解、名言が豊富で、すぐに役立つ情報が満載です。著者は、GoogleやYouTubeでの経験を持つデザイナーで、時間の使い方を再設計することに注力しています。
この文章は、ソーシャルワークに関する書籍の目次を示しており、以下の7つの章から構成されています。1章では総合的な支援の実践、2章では援助関係の形成、3章ではネットワークの形成、4章では社会資源の活用と調整、5章ではカンファレンス、6章では事例分析・検討・研究、7章では関連技法について述べられています。
本書は、IT界のカリスマ経営者であるジェイソン・フリードとデイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソンによるビジネスの心得を示すもので、失敗から学ばず、効率的に働くことや競争を意識することの重要性を説いています。内容は、会社の文化やプロモーション、人材採用など多岐にわたり、イラストも収録された完全版です。著者は「37signals」の創業者であり、成功したビジネスソフト「ベースキャンプ」を運営しています。
この書籍は、社会保険に関する届出や納付について分かりやすく解説した事務テキストです。内容には、健康保険・厚生年金の資格取得、標準報酬月額の決定方法、保険料の納付方法、労働保険の解説と届出様式の記載例が含まれています。具体的なトピックスとして、標準報酬月額の決定、保険料の計算、資格取得届、電子申請などが取り上げられています。
この書籍は「ヤングケアラー」、すなわち家族の介護を担う子どもたちに焦点を当て、その実態や支援の必要性を探求しています。著者は、高校生への調査を通じて、日本のヤングケアラーの状況を明らかにし、孤立や負担を抱える子どもたちの声を紹介しています。社会的背景として少子高齢化や家族主義が挙げられ、支援の重要性が強調されています。最終章では、地域や学校、福祉専門職による支援の具体策が提案されています。著者はヤングケアラー研究の第一人者であり、実践的な支援のあり方を模索しています。
この本は、マイナンバーに完全対応した社会保険と労働保険の手続きガイドで、届け出や手続きに関する基礎知識を提供します。働き方改革に基づいて内容が改訂され、実務に役立つ情報が豊富に盛り込まれています。目次が見やすく、必要書類のサンプルも多く掲載されており、初心者でも理解しやすい詳細な解説が特徴です。また、実用的なチェックシートも充実しています。著者は行政書士で、セミナー講師としても活動しています。
この書籍は、最年少上場を果たした25歳の若者が、お金や成功よりも幸せややりがいを重視するビジネスモデルを追求する姿を描いています。著者は、彼の起業の決意や上場までの道のり、そして人々を幸せにすることが自分自身のためにもなるという哲学について探求しています。著者の上阪徹は、経営や経済に関するフリーライターとして活動しています。
史上最年少25歳での上場を果たしたリブセンス創業者の村上氏がなぜ起業を志し、どうやってものすごいスピードで事業をスケールさせていったのかが語られた書籍。起業を志す人にぜひ読んで欲しい書籍になっています。村上氏は高校生の頃から起業を志していたそう。しかし、強烈に辛い過去や特別なバックグラウンドがあったわけではなく、きっかけは高校生の頃に人はなぜ生まれてきたのだろうという純粋な疑問を持ったことだったそうです。生まれてきたからには意味のあることをやろう!社会にインパクトを与えることをやろうと決め起業を志すことになるのです。この原体験は社名であるリブセンスにつながっています。リブセンスはそのままLive Senseで生きる意味なのです。彼は大学受験をせずに早稲田大学に入れる早稲田大学高等学院という高校に在籍していたため、高校の頃から起業に集中することができました。仲間を集めて大学1年生の時に起業を果たします。なんと大学1年生ながらビジネスコンテストに出て優勝し1年間のオフィス無料利用の権利を勝ち取るのです。さて、肝心のビジネスはというと、村上氏自体が高校生の頃にアルバイトを探した時に気付いた課題を元に立ち上げたサービス。アルバイトを探す人と求める人をマッチングするプラットフォーム。以前から同じようなプラットフォームはあったのですが、どれも広告を掲載するだけでお金を取るというモデルでした。しかし、そうなると1人も採用できなかったとしても広告費を払わなくてはいけないため、アルバイトを募集するお店側は人が欲しくてもなかなか費用が捻出できずプラットフォームに掲載できていない状況でした。そこで村上氏らが採用したのが、採用が成功した時にはじめて費用が発生する成果報酬型のモデルです。これにより多くの企業がプラットフォームに掲載してくれることになります。アルバイトを探す側は応募情報があればあるほど嬉しいので自ずと彼らのプラットフォームに集まるようになりました。さらに彼らは採用が決まった応募者に対して採用お祝い金という名のもとで数万円のお金を渡す制度を導入したのです。これにより応募者はよりたくさん集まることになりました。このシステムは応募者がより幸せになるビジネスにしたいという気持ちと、採用が成功したかどうかを確実にプラットフォーム側が把握するという目的がありました。彼らのビジネスモデルでは採用が成功してはじめて報酬が発生するので採用成功を把握することが大事なのです。その点応募者側に採用報告のメリットを与えておけば企業側に採用成功をごまかされることがないのです。このような従来のビジネスモデルをぶち壊す革新的なビジネスモデルで事業を大きくしてきた村上氏は資金調達することなく25歳にて見事上場を果たすのです。最年少上場というと華々しいキラキラした生活を想像するかもしれませんが、彼らは起業してからいくら会社が成長しても贅沢をせず、上場しても代表の村上氏は狭いアパートに住んでいたそうです。とにかく社会に価値あるもの届けて生きる意味を見出すために!こんな起業家が増えてくると日本も良くなるかもしれません。リブセンスが上場したのはもう10年以上前の話ですが、今読んでも学ぶことは多いです。ぜひ起業に興味のある方は読んでみて下さい!
20代のOL・ユイが投資を始め、投資と投機の違いや節約の重要性を学ぶコミック形式の書籍。月3万円の投資で将来の不安を解消する方法を、資産1500万円を超えた投資のプロから学ぶ内容。投資信託や変額保険、リバランスの重要性なども解説されており、若い世代に向けたお金の新常識を紹介している。著者はファイナンシャルプランナーの田中唯。
本書は、デジタル化が進む世界の本質を解説し、日本企業がオンラインを活用する従来のアプローチを見直す必要性を訴えています。著者たちは、オフラインが存在しない「アフターデジタル」の時代を提唱し、すべてのビジネスがオンライン化される未来を描いています。内容は、デジタル化の現状、OMO型ビジネスの重要性、具体的な事例を通じた思考訓練、日本のビジネス変革に焦点を当てています。デジタル担当者だけでなく、未来を拓くすべてのビジネスパーソンに向けた一冊です。
デジタルが主体の時代に突入しどのように顧客行動が変わっていくかを中国の事例をふんだんにまじえながら教えてくれる良書。デジタル時代のマーケティングをおさえるためにぜひ読んでおきたい1冊
本書では、資本主義の次の段階「お金2.0」について探求し、仮想通貨やフィンテック、シェアリングエコノミーなど新しい経済の形を解説しています。著者は、テクノロジーの進化が経済の仕組みを変え、価値主義へと移行する様子を論じ、私たちの生活や働き方の変化を示唆します。特に、従来の金融知識に依存しない新しいパラダイムの重要性を強調し、経済の民主化と内面的な価値の重要性を提唱しています。
お金の成り立ちからはじまり、昨今のブロックチェーン周りの話まで学べる。これからの時代の価値観をアップデートしてどう生きていくべきか考えていく指針になる良書。著者は天才起業家の佐藤航陽氏。メタップスを創業し現在は3DCGと宇宙を絡めた事業をやっている。最先端のテクノロジーに明るくて巨額の富を得てもなお自分の興味に駆動されて自分自身で手を動かしながら最新のテクノロジーを触っている姿は脱帽モノ。
本書は、起業に対する一般的な誤解を解き、誰でも一定の成果を得られる方法があると説いています。著者は、自身の経験を基に、サイバーエージェントやユニクロなどの成功企業が共通して用いる起業法を紹介。独立や起業を考えているが自分には無理だと思っている人に向けて、挑戦する価値があることを伝えています。
起業というとどうしてもリスクを背負って大きな挑戦をするイメージがあるが、そのイメージに疑問をなげかけるのが本書。キャッシュエンジンとは手堅い事業をまず作りそのキャッシュを元手に挑戦をしてスケールしていく経営手法。地味なイメージがあるがインターネットバブル期を代表するサイバーエージェントやライブドアも最初は広告代理店業や受託事業で手堅くキャッシュを稼いでそこから派手な挑戦をするに至っている。つまりこのキャッシュエンジン経営こそ起業を成功させ安定軌道に乗せるのに重要な手法なのだ。起業家必見の書籍。
連続起業家「家入一真氏」がどのような幼少期を過ごして起業にいたり、ここまでの成功をおさめたのかが記されている伝記。正直、この本を読むまでは家入氏は小さい頃から天才で周りを巻き込む起業家タイプであると思っていたが、全く逆で驚いた。起業家には強烈なコンプレックスが大事と言われるがそれをまさに体現している家入氏。周りと合わなくて孤独を感じていたり人生に不安を感じている若者こそこの本を読んで勇気を出して欲しい。その中から絶対家入氏のような起業家が生まれてくるはず。
労働・社会保険法規を表欄形式でまとめた実務マニュアルで、令和6年4月施行の裁量労働制やフリーランス新法、改正育介法に関する内容を含んでいます。構成は「労働法規の部」、「社会保険の部」、「関連法規の部」に分かれ、巻末には手続き一覧が付いています。最新の法令に対応し、労務相談にも役立つ内容となっています。
この書籍は、破産した大富豪と800万ドルの資産を築いた清掃員の対比を通じて、資産を築けない人の特徴やお金を手にし続けるためのマインドセットを紹介しています。著者は、経済的自由を得るための重要な考え方や投資の原則を解説し、読者の「お金の価値観」を変えることを目指しています。
この書籍はお金の縛りから解き放たれて人生を謳歌したい人のために書かれたもので、全世界でベストセラーになった名著です。あなたは、お金の本質的な価値はどこにあると思いますか?この本ではお金の価値は、贅沢な暮らしができることではなく、「自分の時間をコントロールし自由になれること」と定義されています。どうしても多くの人が、お金を手に入れると高級タワマンに引っ越したり高級外車を買ったりしてしまいますが、お金を無駄にそのようなものに使ってしまうと本質的な自由を手に入れることができません。実は、人の幸福度は自分で人生をコントールしている感覚から生まれると言います。いくらお金を手に入れていい暮らしを手に入れても、日々上司から言われた仕事に疲弊しながら汗水かいて働いていては本当の意味での幸福は手に入れることはできません。この本では2人の正反対の人生を送った男たちを対比しながら話を進めていきます。1人は高卒でガソリンスタンドや百貨店の清掃員として働きながらも日々堅実に投資し続けたことにより最終的に800万ドルもの資産を築いた男。かたや、ハーバード大学を卒業し外資金融の役員に若くして出世し資産家になったものの、2008年のリーマンショックの影響で多額の負債を抱えて破産に追い込まれた男。一見前者の男のほうが貧しい暮らしをしているように見えますが、最終的な結果は全く違います。彼は、いつでも仕事を辞められるほどの資産を築き、自分で人生をコントロールしている実感を得ていました。後者は虚栄心を満たしたいがために借金をして大豪邸をたてて破滅してしまいました。いくら高級取りで社会的ステータスが高くても、金銭的自由がなく仕事をしないといけない状態に追い込まれていると幸福感を得ることはできません。お金のために働くという状況を抜け出してこそ、自分で選び取ることのできる自由な人生が待っているのです。そのためには派手な浪費はせずにコツコツと堅実に投資するのが大事。そんな幸福な人生を掴み取るために必要なメソッドが学べるのがこの書籍。ぜひ興味のある方は読んでみて下さい。
この書籍は「社会心理学」をテーマに、個人と社会との関係をわかりやすく解説しています。協力や競争、攻撃、援助といった行動がどのように集団や組織に影響されるかを、図解やイラストを用いて紹介。具体的なテーマとして、社会現象、組織の心理、職場での心理、対人認知、社会のあり方などが取り上げられています。著者は東京大学の亀田達也教授で、心理学の実験結果も交えながら、日常生活における心理の働きを探求しています。
本書は、現代の精神医療の変化を反映した第2版で、特に「統合失調症」への病名変更などの重要な修正が加えられています。ケアの基本もさらに向上され、看護師だけでなく全ての医療者にとって有用な内容となっています。
本書は、ファイナンシャルアドバイザーの著者が「お金を増やす極意」をシンプルに解説したもので、特に投資を挫折しがちな人に向けています。投資の成功に必要なマインドや長期投資の重要性を説明し、具体的な実践方法も紹介しています。著者は多くの資産運用アドバイスを行っており、人生100年時代に適した賢い投資戦略を提案しています。
この本は、税金や社会保険について子どもたちの視点からわかりやすく解説しています。税金の必要性、使い道、種類、そして社会保険の役割についてマンガを交えながら説明し、少子高齢化問題にも触れています。各章には調べ学習のテーマが設けられ、学校の課題や自由研究にも役立つ内容です。著者は元国税専門官で、現在は芸人として活動しながら執筆や講演も行っています。
著者藤田晋は、高校生の頃に抱いた起業の夢を実現し、サイバーエージェントを設立。しかし、社長として直面したのはITバブルの崩壊や買収の危機、社内外からの厳しい圧力などの厳しい現実だった。このノンフィクションは、彼の孤独や絶望、そして成功を赤裸々に語り、夢を追う人々にとって必読の書である。
サイバーエージェント藤田氏の苦悩と成功を描いた自伝。将来起業を考えている学生や起業しながら色んな葛藤と戦っている人にはめちゃくちゃ刺さると思う。とにかくモチベーションが上がる。
この書籍は、6000以上の投資信託の中から「買うべき1本」を簡単に見つける方法を解説しています。内容は全面的にリニューアルされ、図解やイラストが増え、わかりやすさが向上しています。また、投資信託の選び方や管理をサポートするスマホアプリの活用法も紹介されています。著者は世界No.1の投信評価会社のトップであり、長期・分散・積立投資による資産形成の重要性を説いています。
『A Random Walk Down Wall Street』は、インデックスファンドへの投資が最も効果的であると主張する投資書で、1973年の初版以来150万部以上が売れています。著者は、アクティブファンドが市場平均を下回る理由をデータで示し、テクニカル分析やバブルについても言及しています。最新版では仮想通貨や「スマート・ベータ」などの新しい投資手法が追加され、初心者にも理解しやすい内容となっています。投資家にとって、インデックスファンドを保有することが最良の選択であると強調されています。
この本は、経済的リスクをゼロにしながら「好きなこと」をビジネスに変える方法を紹介しています。著者は、成功者たちのセミナーをプロデュースしてきた小山竜央氏で、90分で読了し、24時間以内にビジネスを立ち上げ、30日後に成功を目指す具体的なステップを提供しています。内容は、スモール起業の知識、ビジネスプランの構築、商品販売の技術、そして継続のためのアドバイスに分かれており、副業時代の必読書となっています。
本書は、全米で50万部以上のロングセラーを大幅改訂したもので、現代の投資家に向けた運用哲学のバイブルです。市場に勝つことが難しい今、インデックス・ファンドを活用することが最も効果的な投資方法とされています。内容は3部構成で、資産運用の基本、理論的な視点、個人投資家への具体的な助言が含まれています。著者は、投資の専門家としての経験を持つチャールズ・エリスと鹿毛雄二です。
本書は、ミレニアル世代に向けた「お金のバイブル」であり、仕事、結婚、子育て、奨学金、年金などに関する新しいお金の常識を解説しています。著者は、経済の変化や社会的な問題に対処するための具体的なアドバイスを提供し、貯蓄や投資の方法、保険の重要性などを等身大でわかりやすく説明しています。ミレニアル世代だけでなく、全世代に役立つ知識が満載の一冊です。
この書籍は、成功と失敗の背後にある見えざる法則を探求し、全国の経営者に成功法則を伝授してきたカリスマコンサルタント、神田昌典がそのエッセンスをまとめたものです。内容は、見せかけの成功物語や幸福と不幸の狭間、優しさの罠、成功の果てについての章で構成されています。著者は、経営コンサルタントとして多くの企業を支援し、貴重な情報を提供しています。
起業家・起業したい人全員に読んで欲しい起業家のためのバイブル。成功者の光の部分に焦点を当てた書籍は数しれずあるが、逆に闇の部分に焦点を当てているのがこの本。超有名マーケターの神田昌典氏が成功をおさめてから起きた様々な闇の部分について赤裸々に語られている。涙なしには読めないし、この本を読むことで自分にもあてはめて同じ轍を踏まないように意識することができる。
この文章は、著書の目次と著者情報を紹介しています。目次では、公理、リスク、強欲、希望、予測、パターン、機動力、直観、宗教、楽観と悲観、コンセンサス、執着、計画についてのテーマが挙げられています。著者は、投資家のマックス・ギュンター、経済学教授の林康史、そしてトーキョー・インベスター・ネットワーク代表の石川由美子です。各著者の経歴や専門分野も簡潔に述べられています。
この書籍は、身体障害認定に関する基準や要領、疑義解釈を障害種別ごとに整理し、診断書の記載例や解説を豊富に収録しています。医師や自治体関係者に向けて、平成30年7月からの視覚障害基準の見直しにも対応した内容となっています。目次には法令や通知、各障害に関する認定事務が含まれています。
トピック欄で問題を提起、基礎知識をわかりやすく解説。社会保障法を最新情報で実践的に学ぶ。最新の法改正に対応した充実の第19版 トピック欄で問題を提起、基礎知識をわかりやすく解説。社会保障法を最新情報で実践的に学ぶ。最新の法改正に対応した充実の第19版 ◆好評テキストが今年も最新アップデート!―初学者から各種試験用まで、幅広く利便の書◆ みぢかなトピックで問題を提起し、最新の基礎知識をわかりやすく解説。第19版では、雇用保険、生活保護の大幅改訂に加え、各章きめ細かく法改正・制度改正等をアップデート。コラムを随所に配し専門的な学習へと導く。英文による留学生のための補論も充実。初学者、ゼミ生、社会人、各種福祉系の資格試験学習に便利。最新の法改正に対応した、毎年改訂の2025年第19版。 『トピック社会保障法〔2025第19版〕』 本沢巳代子・新田秀樹 編 【目 次】 ・第19版 はしがき ◇オリエンテーション ◆1 医療保障 トピック 窓口でもらった診療明細書 1 医療保険の保険給付の種類と内容 医療保険の保険給付の種類 療養に関する給付と業務災害 療養に関する保険給付とその種類(健康保険制度を例に) その他の保険給付 2 保険診療の仕組み 医療機関の開設 保険医療機関の指定 保険診療の仕組み 診療報酬の支払い 3 医療保険の保険関係 医療保険制度の体系 医療保険の保険関係 4 医療保険の保険財源 トピック 国民医療費と医療保険料 医療保険の保険財源 保 険 料 STEPUP ◆2 介護保障 トピック 一人暮らしの祖母の介護 1 給付の手続きと内容 給付の手続き 保険給付の種類と内容 介護サービス提供機関 2 介護保険の保険関係と財源 トピック 介護保険の被保険者証はいつ貰えるの? 介護保険の保険者と被保険者 介護保険の財源と保険料負担 3 介護保険法と老人福祉法の関係 STEPUP ◆3 年金保険 トピック 若者と障害 1 障害年金給付 障害基礎年金 障害厚生年金 例 外 2 老齢年金給付 トピック 年金の保険料を払いたくない! 老齢基礎年金 老齢厚生年金(報酬比例部分) 年金生活者支援給付金 3 遺族年金給付 トピック 遺族年金って必要なの? 遺族基礎年金 遺族厚生年金 4 年金保険の併給調整 遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給 障害基礎年金と各厚生年金との併給調整 5 年金保険の保険関係 世代間扶養と3つのリスク 年金保険の保険者と被保険者 6 年金財源 年金財源と財政方式 免除と納付猶予 年金財源に関する問題点 STEPUP ◆4 労災補償 トピック アルバイトの過労死 1 労働災害―「補償」と「保障」 アルバイトと怪我 アルバイトと「労働者」 「補償」から「保障」へ 2 労災補償・労災保険給付 労災補償と安全衛生体制 労災保険給付 労災保険法の仕組み 業務上・外認定 3 通勤災害 トピック アルバイトと通勤災害 通勤災害の保護 通勤災害該当性 通勤災害と単身赴任・マルチジョブホルダー 4 労災民事訴訟―使用者の安全配慮義務 5 「補償」・「保障」再論 STEPUP ◆5 雇用保険 トピック 退職してはみたものの…… 1 就職や雇用継続を支える給付―失業等給付 求職者給付 就職促進給付 教育訓練給付 雇用継続給付 2 育児休業等にからむ給付―育児休業等給付 3 保険関係 トピック 雇用保険に入れない? 保 険 者 被保険者 適用除外 4 労働保険の適用関係と財源 適用関係 財 源 STEPUP ◆6 子ども支援 トピック 子どもが生まれたら 1 子育て支援と児童虐待への対応 子育て支援 児童虐待の発見 調査・判定 相談援助活動 親子分離 家庭再構築 自立支援 2 サービスの利用(種類や内容) トピック 同じ子育てなのに,利用するサービスが違う? 教育・保育施設 地域型保育事業等 3 サービスの利用関係 教育・保育の利用時間の認定 利用調整 利用可能な施設のあっせん,要請 利 用 料 STEPUP ◆7 家族支援 トピック 先立つものがない 1 子どもの貧困 2 子どもの貧困対策法 3 児童を育む場としての家庭の安定 児童手当 特別児童扶養手当・障害児福祉手当 4 ひとり親家庭の経済的な生活保障 経済的な生活基盤の維持 経済的支援 養育費の支払─私的扶養義務の履行確保 就労を通じた自立に向けた支援 生活支援・子育て支援 5 家族を対象とする諸施策 トピック 家族って何だろう 社会保障制度が前提としてきた家族像 制度横断的な性格 6 家族や児童の概念 家族の概念 児童の概念 STEPUP ◆8 障害者福祉 トピック 大学が提供する合理的配慮とは? 1 障害と障害者―個人モデルから社会モデルへ 国際機関における従来の定義 日本における定義 個人モデルから社会モデルへの障害(者)観の転換 障害者権利条約 障害者法制の見直し 差別禁止と合理的配慮 2 障害者法制の体系 トピック 重度障害者に対する介護サービスは十分か? 障害者基本法 障害者福祉法制 3 障害者総合支援法の概要 目的・基本理念・対象・市町村等の責務 自立支援給付 地域生活支援事業 STEPUP ◆9 社会福祉 トピック 会社によってサービス内容に違いがあるのだろうか? 1 社会福祉における登場人物とその役割 事 業 者 利 用 者 制度の調整役─国と地方公共団体 社会福祉の地域応援団─社協・共同募金・民生委員 2 福祉サービスの提供事業者 事業者の多様化 第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業 社会福祉法人 事業者の公共性 3 福祉サービスの従事者 職種と資格 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 ケア従事者の確保 4 福祉サービスの利用者 トピック 契約って難しそうだけど,わかるのかな? 利用者の選択を支える情報提供に関わる制度 判断能力が不十分な人に対する支援制度 220 契約締結 苦情解決手続 事業者規制と権利擁護 家族によるケア 家族の介護責任 STEPUP ◆10 生活保護 トピック リストラの果てに…… 1 保護の種類および内容 保護の種類および内容 世帯単位の原則 2 生活保護の目的と基本原理 生活保護の位置づけと目的 生存権保障の意義と生活保護 最低生活保障 無差別平等 3 保護の要件と申請・受給 トピック 福祉事務所で 保護受給のための手続き 申請保護の原則 保護の補足性 資産調査 収入認定 保護の実施機関・実施責任 不服申立て 家庭訪問と被保護者の権利義務 施設における保護 生活保護の費用負担 4 生活保護における「自立」 自立助長 就労による自立の促進 5 生活困窮者自立支援法 概要と法の理念 生活困窮者自立支援法に基づく事業と実施主体 STEPUP ◆11 社会保障 トピック 社会保障と社会保険 1 社会保障制度の成立と発展 先進諸国における社会保障制度の成立と発展 日本における戦後の社会保障制度の展開 2 社会保障の目的と機能 社会保障の目的 社会保障の機能と意義 3 社会保障の中心である社会保険の機能と意義 社会保険と民間保険 社会保険とそれ以外の社会保障給付 社会保険と公費負担 4 21世紀の社会保障制度改革 トピック 少子高齢社会と社会保障 経済財政諮問会議と社会保障制度改革 社会保障国民会議最終報告 民主党政権と社会保障改革 第2次安倍内閣と社会保障改革法 第3次安倍内閣と消費税率引上げ ニッポン一億総活躍プランと地域共生社会の実現 全世代型社会保障 STEPUP ◆補論 留学生の皆さんに知ってもらいたい日本の社会保障制度 Major social security programs to know for international students 1. Social Security for foreigners in Japan 2. National Health Insurance 3. Industrial Accident Compensation 4. National Pension system 5. Pregnancy and childbirth Medical examination and notification of pregnancy Unintended pregnancy- counseling, abortion and other options Maternal and Child Health Handbook (母子健康手帳/boshi-kenko-techo) Supports for health check-up and prenatal classes Lump sum payment for childbirth and childcare 6. Birth registration and the Status of Residence of the newborn child Birth notification in Japan Acquiring a Status of Residence (zairyu-shikaku) for the child in Japan Birth registration at Embassy or Consulate of the parent’s home country Childcare for pre-elementary school children 7. Social Security Agreements Elimination of dual coverage Totalization of coverage periods for Old-age Benefits ・事項索引 ・判例索引 ・参考文献
「社会保障」に関するよくある質問
Q. 「社会保障」の本を選ぶポイントは?
A. 「社会保障」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「社会保障」本は?
A. 当サイトのランキングでは『15歳からの社会保障 人生のピンチに備えて知っておこう!』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで161冊の中から厳選しています。
Q. 「社会保障」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「社会保障」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。







![『図解入門ビジネス 最新 生命保険の基本と仕組みがよーくわかる本[第3版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51gjTZNM+DL._SL500_.jpg)

![『ケースワークの原則[新訳改訂版]:援助関係を形成する技法』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41bu30JJazL._SL500_.jpg)














































![『援助を深める事例研究の方法[第2版]:対人援助のためのケースカンファレンス (MINERVA福祉ライブラリー32)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/512P9712WTL._SL500_.jpg)









![『ソーシャルワーク演習ワークブック[第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41lGU0bHTSL._SL500_.jpg)








![『図解入門ビギナーズ 最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本[第8版] (How-nual図解入門ビギナーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51bQc1xQDBS._SL500_.jpg)










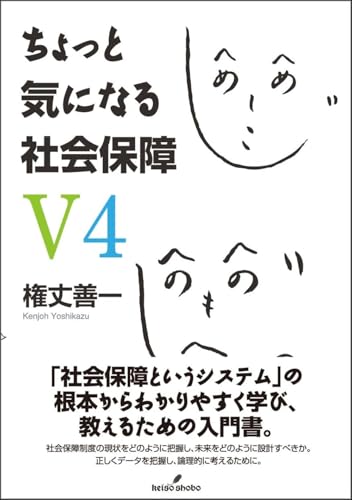
















![『ソーシャルワークの理論と方法[社会専門] (最新社会福祉士養成講座)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41HCKHUXAFL._SL500_.jpg)









































![『医療保険で損をしたくないならこの1冊[第4版]――正しい使い方・選び方がわかる!』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51g2DSiidRL._SL500_.jpg)


























