【2025年】「感性」のおすすめ 本 165選!人気ランキング
- 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え
- 感性のある人が習慣にしていること
- チーズはどこへ消えた?
- 春宵十話 随筆集/数学者が綴る人生1
- 「自己肯定感低めの人」のための本
- アタッチメントベビーマッサージ―感性豊かで幸せな子どもに育つ
- こどもと絵で話そう ミッフィーとフェルメールさん
- 茨木のり子詩集 (岩波文庫)
- いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか (ちくま学芸文庫 シ 8-3)
- 住吉の長屋/安藤忠雄 (ヘヴンリーハウス-20世紀名作住宅をめぐる旅 3)
本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。
10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。
『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。
この本は、心のクセやノイズを理解し、それを解消する方法を提供する内容です。著者は8000人の悩みを解決してきたカウンセラーで、自己納得感を高めることの重要性を説いています。読者は、自分の心のノイズを14タイプに分類し、日常生活でのノイズに気づく方法や、1分でできるエクササイズを通じて心を軽くする技術を学べます。メンタルノイズを手放すことで、より幸せな生活が送れるようになることを目指しています。
対話 見えない配達夫 鎮魂歌 茨木のり子詩集 人名詩集 自分の感受性くらい 寸志 茨木のり子 食卓に珈琲の匂い流れ 倚りかからず 茨木のり子集 言の葉. 3 歳月 『茨木のり子全詩集』所収「「スクラップブック」から」より 美しい言葉を求めて
本書は、おしゃれな配色アイデアを提供するユニークなカラーガイドで、15のテーマに基づく雰囲気を紹介しています。150以上の美しい写真と900以上の配色パレットを通じて、読者は感情を引き出す色選びを楽しむことができます。すべてのパレットはCMYK値やRGB値付きで、デザインやスタイリングに役立つ実用的なツールとして、色と感情の関係を理解する手助けをします。
本書は、リモート時代における「最高のチーム」を作るための新しいリーダーシップ論を提案しています。著者は、やる気やノルマに頼らず、人の認知メカニズムを活用して人を動かす方法を解説。リーダーは「行動」ではなく「認知」を変えることが重要で、チームのエフィカシー(自己効力感)を高めることが成功の鍵としています。具体的には、内面から人を動かす技術や、組織の目的をメンバーが自分ごと化する方法、心理的な抵抗を克服するための戦略を紹介しています。最終的には、チームが自然に進化するためのリーダーシップの原則を示しています。
この本は、ビジネスにおける「余白」の重要性を強調し、論理的思考やデータ分析だけではなく、直感や感性を育てる方法を提案しています。著者は、余白を創造することで思考の幅を広げ、効果的なコミュニケーションや人間関係の構築、スピーディな意思決定を促進できると述べています。各章では、余白の概念を仕事や人間関係、コミュニケーション、自身のメンタルに応用する方法が詳述されています。最終的には、余白のあり方を自分自身で決めることの重要性が強調されています。
この本は、共働き家庭や子どもが一人で留守番する家庭向けに、簡単で美味しい料理のレシピを提供する入門書です。子どもが自分で料理を楽しめるよう、少ない材料で安全に作れるレシピが多数紹介されています。内容は、すぐにできるメニュー、フライパンを使った料理、定番料理のアレンジが含まれ、料理初心者の大人にも役立ちます。著者は料理研究家の上田淳子で、育児経験を活かしたレシピが特徴です。
「認識」について,実験の醍醐味に触れながら,基礎的な内容から新しい知見までをカバーした,コンパクトで読みやすい入門書。 人間は世界をどのように認識しているのか。当たり前になしえている「認識」の背後にからみ合う複雑な営みを,1つ1つ解き明かしていく実証的・科学的手法の醍醐味を堪能してほしい。初版刊行後の新しい知見も盛り込んだ,コンパクトで読みやすい入門書。 第1章 認知心理学の誕生と変貌――情報工学から機能的生物学へ=道又 爾 第2章 知覚の基礎――環境とのファーストコンタクト=北〓崎充晃 第3章 高次の知覚――見ることから理解することへ=道又 爾 第4章 注 意――情報の選択と資源の集中=大久保街亜・道又 爾 第5章 表 象――こころの中身,その形式=大久保街亜 第6章 記 憶――過去・現在・未来の自己をつなぐ=今井久登 第7章 言 語――成長する心の辞書システム=山川恵子 第8章 問題解決と推論――普遍性と領域固有性の間で=黒沢 学
「小さな観葉植物を2、3個おく」「堂々とNOと言う」など、誰にでも簡単にできて恋愛からお金まで効果バツグンの魔法55を紹介。 累計著作105万部突破! 「教えていただいた通りに過ごしていたら、本当に願っていたことが次々叶い始めました!!」「この魔法を試してみたら、彼がプロポーズしてくれたのです!」「どうにもならないと思っていたことが、こんなにするすると叶ってしまうなんて」(以上、生徒さんの声) 本書では、全国各地から20~50代の女性たちが通い詰める大人気の学校「エーデルワイス」を主宰する著者が、夢や仕事から恋や結婚まで、あらゆる望みが自然と叶ってしまう55の魔法を大公開。 「小さな観葉植物を2、3個おく」「堂々とNOと言う」「とっておきの場所をつくる」「自分に「楽しい時間」をプレゼントする」「一番になることを目標にしない」など、誰にでも簡単にできてすごい方法をやさしく紹介します。 100人に一人しか受けられないほど超人気レッスン内容が、この1冊に!
本書では、弘法大師、石川啄木、ゴーゴリ、ニュートンの四人を通じて「創造性」の本質を探求しています。各章では、彼らの生涯や特徴、創造性に関する考察が展開され、天才の特質や社会的矛盾についても触れられています。著者はノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹と工学博士の市川亀久彌です。
満島ひかりと又吉直樹による回文を基にした掌編小説集『まさかさかさま』が書籍化されました。満島が創作した回文を元に、又吉が苦労して物語を執筆しました。この作品は、さまざまなテーマの短編が収められています。
仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版! 仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版! 超高収益を生む「キーエンス思考」をChatGPTで"完コピ"「付加価値」を圧倒的なスピードで創造できる――。仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版!「成果に最短距離で突き進む仕事術」を理解し、ChatGPT活用で遂行していく。日本屈指の高収益企業・キーエンスが成果を生む秘訣である「付加価値」をつくるためのプロセスを、ChatGPTで"完コピ"するための手法を詰め込みました。例えば、情報収集や分析はChatGPTに「仮説」を立てさせることで、新たな観点が生まれ、今手掛けている仕事をブラッシュアップできる。そして付加価値創造が実現し、成果が上がる――。全編を通して、日々の仕事で成果を上げることを念頭に置いたChatGPTのノウハウ本です。キーエンス出身で、自身も業務にChatGPTを有効活用。コンサルティング業務でも顧客にChatGPT活用を提案し、年10億円の利益改善などを実現している著者が徹底解説します。さて、ビジネスパーソンには、様々な立場の人がいます。本書は、どんな立場にあっても成果アップに直結させられる一冊です。例えば、こんなことが実現します。【一般社員のあなた】経験を積む時間を"チート"してみるみる成長【マネジャー(管理職)のあなた】部下が勝手に育ち、チームの業績もアップ【経営者のあなた】優秀な社員ばかりになり、組織の生産性が2倍に「サボっているわけではないのに、上司や同僚に評価されない」「なかなか部下が育たない」「自社、自部署の業績が上がらない」……。そんな悩めるビジネスパーソンにこそ読んで欲しい、AI時代に成果を上げるためのバイブルです。 第1章 キーエンス人~付加価値創造の考え方~ ●付加価値を生み続ける 「しごでき社員」の3大要素 ●「時間」と「お金」の約束は キーエンスでは誰一人軽視しない ●目的意識と目標意識があれば 自然と問題意識も生まれる ●情報に基づく知識こそ生命線。世界初を生む付加価値の秘密 ●成功プロセスを再現するため 十分な行動力が欠かせない 第2章 キーエンスに学ぶ プロの前提条件と必須条件 ●「しごでき社員」になるための 2つの前提を覚えておく ●成果を上げるために「必須」の 8つの原理原則を理解する ●他部署の人の働き方も お客さまのことも十分把握する ●「キーエンス思考」のプロセスは ChatGPT活用で実行できる 第3章 仕事を時短で楽に終える ChatGPT活用術(基本編) ●ChatGPTは何でもできる!? 適切に使うための基礎をおさらい ●危機感を煽りたくなるインパクト ~GPTとの衝撃的な出合い~ ●まだ危機感を持っていない人へ ~「しごでき」ではない人の末路~ ●一般常識をほぼ理解した"先生"に 分からないことはまず質問 ●「構成」や「セリフ」を考えさせて プレゼンの準備をすぐ終える 第4章 ロジカルに情報を整理する ChatGPT活用術(応用編) ●教育コンテンツ開発も計画立案も ChatGPTの生かし方は無限 ●欲しい内容に調整していける 質問と回答の連続こそ真骨頂 ●AIを使わない方が危険? ~火やSNSと理論は一緒~ 第5章 AI時代に仕事ができるとは、どういうことなのか? ●「同僚の彼」が評価される理由 ~目的に最短距離で突き進む~ ●AI時代に成果を上げる心構え ~「Why」の連鎖で目的を知る~ ●ChatGPTを活用して 超重要なビジネスモデルを知る ●ChatGPTにはまだ限界もある。AI時代に重宝される3つのスキル 第6章 PDCAを効率的に素早く回す ChatGPT無双術(前編) ●仕事の根幹「3大要素」を満たす 最重要プロンプトを徹底解説 ●経験を積む時間を"チート"して 最短時間で成果を上げる方法 ●情報収集や分析のヒントを ChatGPTから引き出す ●数値化しづらい情報も「明確化」。キーエンス流の分析手法も実現 ●目標が達成できなかったときは 問題の再設定を提案させる ●「付加価値をつくる仕事」で 迷う時間をできるだけ削る 第7章 アイデアや企画を無限に生む ChatGPT無双術(後編) ●ChatGPTをコーチ役にして 強みと課題を掘り下げていく ●AIにない「五感」を磨くべし。浮いた時間は感動体験に当てる ●「凡人」でも下克上できる。人×AIで天才化を目指せる 第8章 圧倒的な付加価値生産性が実現していく未来 ●すべてに"コパイロット"が付く 次の時代も目前に迫っている ●365コパイロット導入後は 結論が出る会議だけになる? ●日常の業務が激変する? "コパイロット"の未来は ●生活を見守り、アシスト? 日常生活も大きく変える ●高度にパーソナライズ化された 新たなサービスが次々生まれる 第9章 あなたが「しごでき社員」になる意義 ●付加価値をつくれる人は 仕事がどんどん好きになる ●「ハーズバークの理論」で知る 働きがいと働きやすさは別物
著者は、これからの時代に必要な「6つのプロフェッショナルスキル」を解説しています。これらのスキルは、マインドセット、思考力、アウトプット力、伝達力、コラボレーション力、知識・情報であり、正解のない問題に立ち向かうための意識や思考、複雑な問題へのアプローチ、タスクマネジメント、価値創造のコミュニケーション、組織のパフォーマンス向上、そして多様な情報の活用を重視しています。著者はKPMGコンサルティングのパートナーであり、豊富な経験を基に新たな学びの重要性を提案しています。
この書籍は、わかりやすく楽しい性教育を提供する実践編であり、男女の体の違いや命の成り立ち、防犯についての知識を小さな頃から学ぶ重要性を強調しています。自己肯定感を高め、性犯罪から身を守るためのアドバイスも含まれています。著者は性教育アドバイザーののじまなみで、家庭での楽しい性教育を広める活動を行っています。
本書は、ライフスタイルプロデューサーのWakoさんが「旅するように生きる」ことを提唱し、人生における感性を育むヒントを提供する内容です。Wakoさんは「感性」を「幸せを感じ取るセンサー」と定義し、心を豊かにすることと結びつけています。具体的には、日常生活での感性の育て方や、時間・場所・心のゆとりを確保する重要性を説いています。自分自身を喜ばせる方法を見つけることが感性の育成に繋がるとしています。
本文二色刷にカラー口絵付。豊富な図表,読書案内,練習問題,最新トピック紹介等により,高い学習効果を備えた決定版テキスト。 最新の研究知見を取り入れつつ,基本的な考え方,用語,概念の理解を目指し,豊富な図表と厚みのある解説を施した本格テキスト。第一線の研究者による最新トピック紹介,本文2色刷とカラー口絵,読書案内,練習問題などにより,高い学習効果を備えた決定版! 第Ⅰ部 認知心理学の基礎:感性・注意・記憶 第1章 認知心理学の歴史とテーマ/第2章 視覚認知/第3章 感性認知/第4章 注意/第5章 ワーキングメモリ/第6章 長期記憶/第7章 日常認知/第8章 カテゴリー化 第Ⅱ部 高次の認知心理学:言語・思考・感情 第9章 知識の表象と構造/第10章 言語理解/第11章 問題解決と推論/第12章 判断と意思決定/第13章 認知と感情 第Ⅲ部 認知心理学の展開:進化・社会・文化 第14章 認知進化と脳/第15章 認知発達/第16章 社会的認知/第17章 文化と認知/第18章 メディア情報と社会認識
本書は、アートを通じて「最先端の思考」と「感性の技術」を鍛える方法を探求し、シリコンバレーのCEOたちが実践するイノベーティブな発想の育成について解説しています。内容は、アート思考の本質やビジネスとの交差点、イノベーションを実現する発想法、アートと資本主義の関係、現代アートの鑑賞法など多岐にわたります。著者は秋元雄史で、アートの専門家として多くの美術館での活動を経て、現職に至っています。
この文章は、視覚、聴覚、時間知覚、意識、記憶、コミュニケーション、思考、デザイン、メタ認知、感情、動物の認知行動など、人間の認知に関するさまざまなテーマを扱った内容の目次を示しています。著者は仲真紀子で、北海道大学の教授です。
市川春子の最新作には、3つの短編が収録されています。『25時のバカンス』では、深海生物圏研究室の西乙女が弟の甲太郎と再会し、貝に侵食された自らの姿を見せます。『パンドラにて』は、土星の衛星にある女学院の不良学生ナナと新入生の交流を描き、『月の葬式』では天才高校生が雪深い地域で一人の男と共同生活を始める様子が描かれています。
いま人類が直面する、最大の危機 二つの資本主義が世界を覆う 世界中の人をドーナツの中に入れる 倫理と経済、どちらが先か? 資本主義を再構築する 社会契約をつくり直す 資本主義は『脱物質化』する 生命の網のなかの資本主義
箱を祀る霊能者と箱詰めにされた少女たちを巡る事件が、美少女転落事件とバラバラ殺人を結びつける。探偵・榎木津、文士・関口、刑事・木場が事件に関与し、京極堂の元へ向かう。果たして憑物は落とせるのか?日本推理作家協会賞受賞のミステリー作品、妖怪シリーズ第2弾。
本書は、プロのグラフィックデザイナーが教える配色のコツを紹介し、イラストやインテリア、ネイルアートなど多様なシーンで活用できる配色アイデアを提供します。内容はスタイル、国、季節ごとに分かれており、具体的な色の組み合わせや実例サンプルが豊富に掲載されています。色に迷った際のインスピレーションを得るための一冊です。
相互に影響しながらも独自の特徴を持つ知覚と感性を実験心理学の立場から総合的に考察する。多感覚統合,感性の脳内基盤,知覚と感性の発達,芸術,言語,身体知といった多彩なテーマを取り上げつつ,心理物理学的測定法や感性評価などそれらに迫るための方法論も詳しく説明し,この研究領域の全体像を浮き彫りにする。 まえがき 第1部 基礎と理論 第1章 感性認知―アイステーシスの実証科学として― 1節 はじめに 2節 アイステーシス 3節 アイステーシスとしての知覚特性 4節 「感性」の定義と背景 5節 感性の位置づけ 6節 アイステーシスへの接近――知覚と感性をともに考える研究テーマ 7節 おわりに 文献 第2章 多感覚統合と感性 1節 はじめに 2節 共感覚 3節 多感覚情報の時空間統合 4節 日常経験する事象における多感覚統合 5節 触覚と身体の感性 6節 五感による食経験 7節 五感と感情へのアプローチ 8節 嗅覚とマルチモダリティ 9節 まとめ 文献 第3章 感性の基本次元と脳内基盤 1節 はじめに 2節 SD法からわかる感性特性 3節 感性次元の感覚関連性 4節 感性次元と脳活動の対応関係 5節 おわりに 文献 第4章 知覚と感性の発達 1節 はじめに 2節 色の知覚の発達 3節 形の知覚の発達 4節 動きによって促進される感性――形と空間の知覚 5節 おわりに 文献 第5章 感性研究の方法論 1節 はじめに 2節 感性の測定 3節 さまざまな測定方法 4節 SD法に基づく印象形成過程の検討 5節 感性心理学研究の展開 文献 第2部 展開と実践 第6章 絵画と仮想 1節 はじめに 2節 絵画時間の仮想 3節 画家の時間と鑑賞者の空間 4節 仮想の反転 文献 第7章 感性言語―擬音語・擬態語と脳― 1節 はじめに 2節 感覚尺度としての擬音語・擬態語 3節 感覚・知覚と擬音語・擬態語 4節 五感と共感覚 5節 感性語 6節 擬音語・擬態語の脳内表現――fMRIによる実験 7節 擬音・擬態語の構造と機能 8節 まとめ 文献 第8章 音響感性情報としての「間」 1節 はじめに 2節 「間」の感性 3節 「間」を科学する――音楽・朗読の「間」 4節 意図の表現と理解に関わる「間」 5節 会話の「間」 6節 コミュニケーションの基盤としての「間」 7節 音響情報の感性 文献 第9章 身体知―習熟と伝承― 1節 はじめに 2節 身体知を身につける 3節 身体知を学習する 4節 「場」から学習する 5節 まとめ 文献 第10章 好みの形成―単純接触効果と広告― 1節 はじめに 2節 単純接触効果の分類 3節 単純接触効果の理論 4節 単純接触効果と広告効果 5節 まとめ 文献 第11章 情報のデザイン 1節 はじめに 2節 情報のデザイン 3節 情報デザインの事例 4節 おわりに 文献
本書は、アートを通じて柔軟な思考を育むための12のドリルを提供しています。大人や子供が楽しめる内容で、アートの面白さや美学の深さを体感しながら、正解のない状況に対処するヒントを得られます。著者はアート思考のキュレーターであり、様々な分野での経験を活かして、想像力を刺激する内容を展開しています。
本書は、幸せの感じ方には個人差があるものの、共通の傾向が存在することを学術的に探求し、地域に適した政策を提案しています。世界と国内の大規模調査を基に、幸福度の決定要因や地域別の比較を行い、特にお金、人とのつながり、働き方、住環境などが幸福度に与える影響を分析しています。著者は南山大学や九州大学の准教授や教授で、持続可能性や新国富指標の研究に関与しています。
本書は、人生の成功に導く「偉大なる秘密」を紹介しています。この「秘密」は、プラトンやシェイクスピアなどの偉人たちが知っていたもので、健康、富、人間関係など人生のあらゆる面に影響を与えるとされています。著者は、この知識を通じて多くの人々に喜びをもたらすことを目的としており、実際にこの「秘密」を活用して成功を収めた人々の体験談も紹介されています。読者は、自身の内に秘めた力を理解し、夢の人生を歩み始めることができるとされています。
本書は、特別な存在になることを夢見ていたが、現在は中途半端な大人として生きる私たちへの慰めと応援を提供する内容です。正解が不明な時代に、自分を認め愛する方法を探るための「to do list」が複数紹介されており、自分を大切にし、不安を克服し、共に生きることを促しています。著者はイラストレーターのキムスヒョンで、翻訳者は吉川南です。
本書は、歴史上の著名なアーティストや現役のクリエイターたちが自らデザインした家250軒を紹介しています。これらの家は生活空間であり、アート作品でもあり、インスピレーションの源となる場所です。収録されているアーティストには、画家、建築家、ファッションデザイナー、作家、音楽家など多岐にわたり、彼らの自宅に込められたストーリーや知られざる一面を探ります。
本書は、鈴川葵という女子社員が「考える力」を高めながら成長していく物語です。会議術や資料作りを学び、コンサルタントの父から教わった「思考の循環サイクル」を実践することで、会議や資料の質を向上させる過程を描いています。ビジネスパーソンが「考えること」をどう実践すべきかを探り、考え方の原理を理解する手助けをします。シリーズ第3弾で、過去のテーマから「中身」の質の向上に焦点を当てています。読者は主人公の成長を通じて、自らの考え方を見直すことができる内容となっています。
著者の植松努は、小さな町工場から自家製ロケットを打ち上げ、宇宙開発の常識を覆す活動を行っています。彼のTEDxスピーチは150万人に感動を与え、“どんな夢も実現させる方法”を提唱しています。本書では、夢を実現するための5つのステップ「思い描く」「思い込む」「思いやる」「思い切る」「思い続ける」が紹介されています。植松は、社会システムの改善を目指す「ARCプロジェクト」も進めています。
『ええところ』は、小学1年生のあいちゃんが自分に自信を持てず、「ええところがない」と悩む物語です。親友のともちゃんとの対話を通じて、思いやりや自己肯定感を育む内容で、著者は元小学校教諭のくすのきしげのりです。絵はニューヨークで活動するイラストレーターのふるしょうようこが手掛けています。この絵本は、子どもが自信を失ったときに読みたい一冊です。
この書籍は、イノベーション都市の高卒者が旧来型製造業都市の大卒者よりも高い収入を得ている現象を探求し、新しい仕事の創出場所や「ものづくり」だけでは経済が成長しない理由を論じています。目次には、都市の浮沈、イノベーションの影響、給料の決定要因、移住の影響、地域再生の条件などが含まれています。著者はエンリコ・モレッティで、労働経済学や都市経済学の専門家です。
からだを温める。深く呼吸する。自分と打ち合わせをする。体や心をたいせつにするワークで、自分の気持ちに気づいて心地よく変わる。 からだを温める。深く呼吸する。自分と打ち合わせをする。自分の年表を作る。体や心をたいせつにするワークで、自分の気持ちに気づいて心地よく変わる。 からだを温める。深く呼吸する。自分と打ち合わせをする。自分の年表を作る。体や心をたいせつにするワークで、自分の気持ちに気づいて心地よく変わる。
現代の社会的認知研究をベースに 社会的場面での認知の問題,認知と感情の関係性を検討。 現代の社会的認知研究をベースに,社会的場面における認知の問題,認知と相互に影響し合う感情の問題を検討する。適応的行動を生み出すメカニズム,自動的過程と意識的過程の役割,感情情報処理と認知情報処理との関係性などの視点を軸に,現実の幅広い現象を取り上げながら社会的認知の本質に多面的に迫る。 ◆執筆者一覧(執筆順) 森 津太子 放送大学教養学部 第1章 尾崎由佳 東海大学チャレンジセンター 第2章 榊 美知子 University of Southern California 第3章 藤島喜嗣 昭和女子大学大学院生活機構研究科 第4章 田中知恵 明治学院大学心理学部 第5章 村田光二 編者 第6章 工藤恵理子 東京女子大学現代教養学部 第7章 北村英哉 東洋大学社会学部 第8章 唐沢かおり 東京大学大学院人文社会系研究科 第9章 遠藤由美 関西大学社会学部 第10章 唐沢 穣 名古屋大学大学院環境学研究科 第11章 沼崎 誠 首都大学東京大学院人文科学研究科 第12章 『現代の認知心理学』刊行にあたって まえがき 第1部 基礎と理論 第1章 社会的認知過程のモデル 1節 はじめに 2節 社会的認知とは 3節 社会的認知過程モデルにおける人間観の変遷 4節 古典的モデルと社会的認知過程モデル――印象形成の二過程モデル 5節 現代の社会的認知過程モデル 文献 第2章 社会的判断と行動の自動性 1節 はじめに 2節 自動性現象とそのメカニズム 3節 自動的過程の機能 4節 自動性と意識 文献 第3章 自己知識とそのはたらき 1節 はじめに 2節 自己知識の構造と機能――抽象度による分類 3節 自己知識の構造と機能――知識の内容による分類 4節 自己知識の限界 5節 おわりに 文献 第4章 自尊感情と自己関連動機に基づく推論の歪み 1節 はじめに 2節 自尊感情 3節 自己関連動機に基づく推論の歪み 4節 おわりに――今後の展望 文献 第5章 感情とその制御 1節 はじめに 2節 感情の役割 3節 感情制御 4節 感情価と感情制御 5節 おわりに 文献 第6章 感情予測 1節 はじめに 2節 感情予測の正確さと誤り 3節 感情予測のインパクトバイアス 4節 感情予測が果たす役割 文献 第2部 展開と実践 第7章 他者の心的状態の推論のメカニズム 1節 はじめに 2節 自分の心的状態の利用 3節 他者の心的状態の推論の特別なケース――行為者によるメタ推論 4節 他者の心的状態の推論に用いられる(自分の心的状態以外の)道具 5節 他者の心的状態の推論における自己の主観的経験の特別視・例外視 6節 正確さをめざした場合の帰結 文献 第8章 認知と感情のダイナミズム 1節 はじめに 2節 認知・感情システムと適応 3節 感情と認知――感情の認知への影響 4節 認知的感情理論 5節 感情とコミュニケーション 6節 おわりに 文献 第9章 援助場面での社会的認知過程 1節 はじめに 2節 傍観者効果と援助行動研究 3節 援助を動機づける認知――原因帰属 4節 援助を受ける側の心的過程と援助をめぐる相互作用 5節 おわりに 文献 第10章 関係性と適応 1節 はじめに 2節 社会的動物としての人間 3節 関係性認知――こころのなかの他者像・関係像 4節 関係性の脅威・阻害――関係の糸が結べない時 5節 実在人物以外との関係 6節 親密二者関係のダイナミズム 7節 まとめと将来の課題 文献 第11章 認知の社会的共有とコミュニケーション 1節 はじめに 2節 社会的認知の共有過程 3節 集団表象の共有 4節 社会的認知と言語表現 5節 認知と言語の文化的基盤 6節 おわりに 文献 第12章 ステレオタイプと社会システムの維持 1節 はじめに 2節 ステレオタイプの機能 3節 社会システムとステレオタイプの内容 4節 システム正当化 5節 展望――ステレオタイプと社会 文献 人名索引 事項索引
著者は、建築士からアート研究者、大企業での新規事業立ち上げを経て起業家となり、様々な経験を通じて「アート・シンキング」の重要性を説く。本書では、複雑な時代においてビジネスや人生にアート的思考が求められる理由を探り、独自の視点で新しい発想を生む方法論を提示。アートの価値、身体的思考、制約を超える視点、イノベーションの源泉など、さまざまなテーマを通じて、閉塞感を打破するための思考術を提供する。
著者・阿佐田哲也(色川武大)は、人生には優等生的な道だけでなく、困難な部分を大切に育てることも重要だと説く。彼は自身の経験を通じて、愚かで不格好な人間が生きるための技術や考え方を静かに語る。目次には、人生の様々な側面に関する章が並び、著者の独自の視点が反映されている。
囚われの心で 勇者の帰還 晩鐘 白い花 光の雨 遺影画家 天国にいちばん近い村 さかのぼる民 饒舌な傭兵 英雄 「殻」の中の住人 さらば、相棒 グレオ爺さんの話 七十五年目の蝉時雨 母、帰る 殺戮将軍の悲劇 挽歌の島 嘘つきの少女 コトばあさんのパン 命の順位 天のつぶて 忘れないでね 弱き者からの手紙 待ち人、来りて はずれくじ 道しるべ 老兵士の遺言 語り部サミィ ハンナの旅立ち 壁の向こうに 永遠の孤独
認知心理学の核をなすような形で発展してきた記憶研究の到達点を概観し,今後の方向性を展望する。ワーキングメモリ,長期記憶,意識,記憶の脳内メカニズム,記憶の生涯発達などの重要テーマを網羅する一方で,今後さらなる解明が期待される日常場面や臨床場面における記憶のはたらきについて詳細に論じる。 『現代の認知心理学』刊行にあたって まえがき 第1部 基礎と理論 第1章 記憶研究の歴史と現状 1節 はじめに 2節 科学的研究のはじまり 3節 認知心理学の誕生と発展 4節 今日の研究状況 文献 第2章 ワーキングメモリ 1節 はじめに 2節 ワーキングメモリの成立 3節 ワーキングメモリの個人差 4節 ワーキングメモリの脳内機構 5節 ワーキングメモリの個人差とその脳内機構 文献 第3章 長期記憶Ⅰ―エピソード記憶と展望記憶― 1節 はじめに 2節 エピソード記憶 3節 展望記憶 文献 第4章 長期記憶Ⅱ―知識としての記憶― 1節 はじめに 2節 知識の記憶研究の概観 3節 知識の記憶に関する最近の研究動向 4節 おわりに 文献 第5章 記憶と意識 1節 はじめに 2節 潜在記憶 3節 想起意識と処理の二重性 4節 記憶の再体験と想起意識 5節 まとめ 文献 第6章 記憶の脳内メカニズム 1節 はじめに 2節 シナプス可塑性 3節 記憶に関わる脳領域 4節 まとめ 文献 第7章 記憶の数理モデル 1節 はじめに 2節 時系列規則の記憶――潜在学習 3節 エピソード記憶 4節 意味的知識の記憶 5節 記憶の再生と再認のモデル 参考 ニューロン特性と学習アルゴリズム 文献 第2部 展開と実践 第8章 自己と記憶 1節 はじめに 2節 実験室的な記憶・学習課題と自己 3節 自伝的記憶 4節 自己・他者・私たちと記憶 5節 研究を展開するうえでの留意点 文献 第9章 日常記憶 1節 はじめに 2節 実験室的研究と日常記憶研究 3節 日常記憶研究をめぐるトピックス 4節 日常記憶研究の課題と今後の方向性 文献 第10章 記憶の変容 1節 はじめに 2節 出来事の記憶は言葉で変わる 3節 記憶は他者からの情報で変わる――記憶への社会的影響 4節 まとめ 文献 第11章 記憶の生涯発達 1節 はじめに 2節 記憶の生涯発達に関する研究動向と視点 3節 年齢区分別に見た記憶機能の特徴 4節 今後の研究課題 文献 第12章 臨床と記憶 1節 はじめに 2節 臨床的問題における記憶を論じる前提 3節 トラウマの記憶 4節 強迫性障害(確認症状)と記憶 5節 統合失調症と記憶 6節 解離性同一性障害と記憶 7節 うつ病と自伝的記憶の抽象性 8節 記憶の制御と臨床的問題 9節 治療過程における記憶の問題 10節 まとめ――各障害の特徴が記憶にも現れる 文献
「バビロンいちの大金持ち」を漫画化したこの本は、100年読み継がれるお金の知識をわかりやすく紹介しています。お金儲けのテクニックではなく、資産を増やし充実した人生を送る方法を教えます。現代人に向けた普遍的な知恵が描かれ、子どもから大人まで幅広い読者に支持されています。漫画形式により、楽しくスムーズに読み進められ、感動的なストーリーが展開されます。
漫画で分かりやすく読めるお金にまつわる話。現代にも通用するお金に関する根本的な考え方が学べる。将来のお金に不安がある人は、まずこの書籍から読んでみると良いと思う。
ある空港で出会った男と老人の会話からなす、仕事への向き合い方を勉強できる話。細かいTips というより、新しいアイディアや挑戦を仕事の中で生み出す姿勢を学べる。発明者の実例が話に盛り込まれていてワクワクするし、会話ベースで簡単に読める。何事も試したくなる本。試しに読んでみては!
仕事に対する価値観をガラッと変えてくれる書籍。1つの目標を設定したらブレずに突き進むのが吉だと思われていることが多いが、この本では目標は常に変化して良いとしてる。もちろんブレブレなのはよくないが、環境の変化によって臨機応変に目標を変えるのは問題ないしむしろ変えるべき。とにかく色んなことを試して行動してそこから自分の好きなことや目標を見つけていこうと思える書籍。モチベーションが上がる。
注意が認知機能において果たす基礎的な役割から,高齢化やヒューマンエラーとの関係,産業・医療領域における研究まで幅広く紹介。 注意が認知機能において果たす役割から, 産業・医療領域における研究まで幅広く紹介。 「注意」は,記憶や意思決定といった認知機能とは違い,人間の認知機能全体を明らかにする可能性を秘めた研究領域と言える。本書は,「注意」が果たす基礎的な役割から,脳科学やワーキングメモリ,高齢化やヒューマンエラーとの関係,さらには,産業・医療領域における応用研究まで幅広く紹介。注意研究の現在を一望する。 『現代の認知心理学』刊行にあたって まえがき 第1部 基礎と理論 第1章 注意の理論とその歴史(岩崎祥一) 1節 はじめに 2節 注意の古典的研究 3節 初期選択説と後期選択説 4節 近代的注意研究 5節 注意制御の仕組み 6節 まとめ 文献 第2章 注意と脳科学(熊田孝恒) 1節 はじめに 2節 注意の神経科学的基盤 3節 ヒトの注意機能の脳機能イメージング 4節 実践研究への展開 5節 最後に 文献 第3章 注意とワーキングメモリ(齊藤 智) 1節 はじめに 2節 ワーキングメモリの概念と測定 3節 日常的な逸脱現象とワーキングメモリ 4節 注意課題の成績とワーキングメモリ機能の関係 5節 注意制御におけるワーキングメモリの役割 6節 まとめと今後の課題 文献 第4章 注意と行動・眼球運動(木村貴彦・三浦利章) 1節 はじめに 2節 実験室実験からの諸知見 3節 行動的実験からの諸知見 4節 まとめ 文献 第5章 注意と発達(板倉昭二) 1節 はじめに 2節 注意と乳児の認知――視覚的注意の4つの機能 3節 物理的注意 4節 社会的注意 5節 注意と実行機能の発達 6節 今後の展望 文献 第2部 展開と実践 第6章 注意・制御と高齢化(原田悦子・須藤 智) 1節 はじめに 2節 注意の実験的研究に見る高齢化の効果 3節 認知的高齢化に関するモデル 4節 日常的文脈での活動に見られる注意・制御・高齢化 5節 まとめ――注意の高齢化研究に必要な要件 文献 第7章 注意・安全とメンタルワークロード(芳賀 繁) 1節 はじめに 2節 メンタルワークロードとは何か 3節 メンタルワークロードの評価指標 4節 メンタルワークロードと注意の関係 5節 メンタルワークロードと技術開発 文献 第8章 注意とヒューマンエラー―交通安全と注意問題を中心として―(篠原一光) 1節 はじめに 2節 ヒューマンエラーに関連する注意概念 3節 焦点的注意とヒューマンエラー 4節 分割注意とヒューマンエラー 5節 エラー分類と注意の関係 6節 まとめ 文献 第9章 産業安全におけるヒューマンエラーと違反(臼井伸之介) 1節 はじめに 2節 労働場面での事故の統計的現状 3節 ヒューマンエラーの発生メカニズム 4節 違反とリスクテイキング 5節 これからの安全に求められるもの 文献 第10章 医療安全と認知(松尾太加志) 1節 はじめに 2節 専門的リスクによる事故 3節 作業リスクによる事故 4節 患者自身による事故とリスク認知 5節 事故防止 文献 第11章 複雑な人間-機械系における状況認識と安全・注意(高橋 誠) 1節 はじめに 2節 自動化システムにおける認知機能の役割 3節 状況認識の定義とモデル 4節 状況認識アプローチの重要性 5節 状況認識概念の有効性と課題 文献 追補 注意の神経心理学(熊田孝恒) 人名索引 事項索引
一般知能や情動,進化,遺伝,脳内機構といった 基礎的テーマを軸に研究の現在を一望。 教育や医療,産業など現実の多様な場面でその知見が求められている認知の個人差研究の現在を一望する。一般知能や情動的知性,認知の個人差にかかわる進化的・遺伝的基盤や脳内機構といった基礎的テーマを手厚く論じながら,社会的認知能力,認知のエイジングなどの応用的テーマ,認知の個人差の測定法まで幅広く取り上げる。 ◆執筆者一覧(執筆順) 箱田裕司 編者 第1章 小松佐穂子 徳山大学福祉情報学部 第1章 第2章翻訳 Gerald Matthews University of Cincinnati 第2章 菱谷晋介 北海道大学名誉教授 第3章 平石 界 慶應義塾大学文学部 第4章 安藤寿康 慶應義塾大学文学部 第5章 八田武志 関西福祉科学大学健康福祉学部 第6章 大橋智樹 宮城学院女子大学学芸学部 第7章 若林明雄 千葉大学文学部 第8章 権藤恭之 大阪大学大学院人間科学研究科 第9章 石岡良子 東京都健康長寿医療センター研究所 第9章 中村知靖 九州大学大学院人間環境学研究院 第10章 光藤崇子 Ecole de psychologie Universite Laval 第10章 『現代の認知心理学』刊行にあたって まえがき 第1部 基礎と理論 第1章 認知の個人差の理論 1節 はじめに 2節 メンタルスピードの個人差と知能――IT 論争 3節 情動の個人差の理論――IQとEQ 4節 認知スタイルと大域情報処理・局所情報処理 5節 まとめと展望 文献 第2章 情動的知性と知能 1節 はじめに 2節 情動的知性の背景 3節 情動的知性の定義および概念 4節 情動的知性の評価 5節 情動的知性の理論と研究 6節 おわりに 文献 第3章 イメージ能力の個人差 1節 はじめに 2節 なぜ個人差か 3節 個人差の測定 4節 理論・モデルに基づいた個人差の測定 5節 最後に 文献 第4章 認知の個人差の進化心理学的意味 1節 はじめに 2節 進化的人間行動研究――進化心理学と人間行動生態学 3節 自然淘汰理論 4節 個人差への進化的視点 5節 実証研究の解釈――一般認知能力の個人差 6節 最後に 文献 第5章 認知の個人差と遺伝 1節 はじめに 2節 遺伝学の基礎――メンデル遺伝学と分子遺伝学 3節 行動遺伝学の理論と方法 4節 認知能力の遺伝と環境 5節 最後に 文献 第6章 認知の個人差の脳内機構 1節 はじめに 2節 認知の性差の特徴とその範囲 3節 認知の性差の規模と特性 4節 認知の性差をもたらすもの――性ホルモン 5節 性ホルモン――閉経の影響と月経周期の影響からの検証 6節 認知の個人差の分散と規模 7節 認知の個人差をもたらす脳内機構――神経心理学的説明 8節 おわりに 文献 第2部 発展と実践 第7章 視覚認知特性の個人差測定に基づく事故予防 1節 はじめに 2節 適性とは何か 3節 産業における適性検査の実践事例 4節 適性検査の要素 5節 事故予防のための個人差測定の展望 文献 第8章 社会的認知能力の個人差 ―自閉症スペクトラムから認知スタイル・モデルへ― 1節 はじめに 2節 心の理論と自閉性障害 3節 自閉症傾向の個人差から認知的傾向の個人差へ 4節 E-S理論と認知スタイル 5節 認知的特徴の個人差を生み出す神経生理学的基盤 6節 結論 文献 第9章 高齢者の生活環境,ライフスタイルと認知機能 1節 はじめに 2節 認知のエイジングとライフスタイル研究 3節 環境やライフスタイルが認知機能に影響するメカニズム 4節 認知機能維持のための介入研究 5節 今後の研究の方向性 6節 最後に 文献 第10章 項目反応理論から見た認知の個人差 1節 はじめに 2節 項目反応理論 3節 認知心理学における項目反応理論の応用例 4節 まとめと展望 文献 人名索引 事項索引
お金ってなんだろう? 2ちゃんねる、ニコニコ動画、など…、月5万円極貧生活から年収二億円まで経験… これからぼくたちはお金とどうつきあえばよいのか 2ちゃんねる、ニコニコ動画など…、月5万円極貧生活から年収二億円まで経験した ひろゆきがおくる、最強のお金哲学の極意! ! 「お金ってなんだろう」「お金がないと幸せになれないの」 「お金や経済はこれからどう変わっていくのか」など お金の正体やお金のしくみ、経済とお金、ネットとお金、通貨 お金はどう稼いでどう使うのが正しいのか、などなど。 お金とのつきあい方がわかります!
モデルに基づくアプローチを重点的に取り上げ, 基礎研究と応用研究の最新動向を解説! 概念モデルや計算モデルなどのモデルに基づくアプローチを重点的に取り上げ,思考と言語に関する認知心理学の基礎研究・応用研究の最新動向を解説する。推論,問題解決,概念などの基本的テーマから,意思決定と行動経済学,批判的思考と高次リテラシー,比喩理解と身体化認知などの発展的テーマまで,研究の最前線へ誘う。 ◆執筆者一覧(執筆順) 服部雅史 立命館大学文学部 第1章 鈴木宏昭 青山学院大学教育人間科学部 第2章 坂本康昭 Stevens Institute of Technology 第3章 都築誉史 立教大学現代心理学部 第4章 山岸侯彦 東京工業大学大学院社会理工学研究科 第5章 楠見 孝 編者 第6章 岡田 猛 東京大学大学院教育学研究科 第7章 横地早和子 東京未来大学こども心理学部 第7章 小島隆次 滋賀医科大学医学部 第8章 岸 学 東京学芸大学教育学部 第9章 平 知宏 大阪市立大学・大学教育研究センター 第10章 米田英嗣 京都大学白眉センター 第11章 『現代の認知心理学』刊行にあたって まえがき 第1部 基礎と理論 第1章 演繹推論と帰納推論 1節 はじめに 2節 規則とシンボル操作 3節 スキーマ,モジュール,認識論的効用 4節 確率的アプローチ 5節 カテゴリ帰納 6節 因果帰納 7節 まとめ 文献 第2章 問題解決 1節 はじめに 2節 問題解決の定義 3節 ヒューリスティクスによる問題解決 4節 スキーマによる問題解決 5節 類推による問題解決 6節 身体,外的資源と問題解決 7節 創造的問題解決 8節 まとめと今後の課題 文献 第3章 概念とカテゴリ化 1節 はじめに 2節 カテゴリ化学習と概念の獲得 3節 規則ベースの理論 4節 類似性ベースの理論 5節 まとめ 文献 第4章 言語と思考に関するコネクショニストモデル 1節 はじめに 2節 コネクショニストモデルの概要 3節 言語理解のモデル 4節 思考のモデル 5節 まとめと今後の展望 文献 第2部 展開と実践 第5章 意思決定と行動経済学 1節 はじめに 2節 行動経済学と心理学 3節 意思決定心理学の分類 4節 確率判断の非合理性 5節 処方的決定理論 6節 近年の動向 7節 おわりに――初学者の誤解 文献 第6章 批判的思考と高次リテラシー 1節 はじめに 2節 批判的思考の定義 3節 批判的思考のプロセス 4節 高次リテラシーと批判的思考 5節 批判的思考の教育と測定 6節 まとめ 文献 第7章 科学と芸術における創造 1節 はじめに 2節 創造性の心理学的研究の流れ 3節 科学と芸術の創造をとらえる枠組み 4節 科学における創造 5節 美術における創造 6節 結論 文献 第8章 空間表現理解と実践的応用 1節 はじめに 2節 空間表現理解研究における基本事項 3節 空間表現の分類 4節 空間表現理解に関わる幾何的・視覚的要因 5節 対象に関する知識や状況がもたらす空間表現理解への影響 6節 空間表現理解研究の実践的応用のためのモデル 7節 空間表現理解に関わるさまざまな問題点と今後の展望 文献 第9章 説明文・マニュアルの理解と表現 1節 はじめに 2節 宣言的説明文の理解と表現 3節 手続き的説明文・マニュアルの理解と表現 4節 非連続型テキストを含む説明文(文書)の理解 5節 おわりに――これからの展開と応用 文献 第10章 比喩理解と身体化認知 1節 はじめに 2節 比喩理解の過程 3節 比喩の理解の効果 4節 概念の比喩性と身体化認知 5節 まとめ 文献 第11章 物語理解と社会認知神経科学 1節 はじめに 2節 近年の物語理解研究 3節 社会認知神経科学の一分野としての物語研究 4節 今後の課題 5節 おわりに 文献 人名索引 事項索引
生涯にわたる発達において,ワーキングメモリはどのような役割を果たすのか。 成功(専門知識の獲得)や失敗(嗜癖行動,不適切な意思決定)との関係を明らかにし, 日常生活に与える影響を示す。トレーニングの利点も言及。 ワーキングメモリ――情報の意識的な処理――は,知性における最も重要なものの一つとしてますます認識されてきている。・・・ 本書では,一流の心理学者たちがワーキングメモリに関する最新の研究をレビューし,ワーキングメモリが人の発達や生涯においてどのような役割をしているかについて考察している。豊かなワーキングメモリがどのように成功(学術的に,そして専門知識の獲得に)と関係し,乏しいワーキングメモリが失敗(嗜癖行動や不適切な意思決定)と関係しているのかが明らかにされているのである。寄稿論文はまた,ワーキングメモリが私たちの認知的な進化においてどのような役割を果たしているか,そして日常生活の諸事,例えば何を食べ,どのくらい眠るかといったことがワーキングメモリの機能にどのように影響するかといったことを示している。最後に,ワーキングメモリトレーニングの利点に関するエビデンスについて探求している。(「認知心理学のフロンティア・シリーズ」紹介文より引用) ◇目次 第I部 ワーキングメモリ:新しい知性 第1章 ワーキングメモリ:序論 第2章 ワーキングメモリと知能:展望 第3章 ワーキングメモリの進化 第II部 生涯にわたるワーキングメモリ 第4章 発達におけるワーキングメモリ 第5章 ワーキングメモリの階層モデルと健康な高齢者のその変化 第III部 ワーキングメモリと専門知識 第6章 熟達者のワーキングメモリ:伝統的なワーキングメモリ概念との質的な相違 第7章 ワーキングメモリ容量と音楽の技能 第IV部 ワーキングメモリと身体 第8章 ワーキングメモリと食習慣 第9章 断眠とパフォーマンス:ワーキングメモリの役割 第10章 ワーキングメモリと嗜癖行動 第V部 ワーキングメモリと意思決定 第11章 ワーキングメモリと不安:個人差と発達の相互作用を探る 第12章 情動と認知的制御の統合 第13章 ワーキングメモリと瞑想 第VI部 ワーキングメモリの将来:トレーニング 第14章 ワーキングメモリをトレーニングする 第15章 ワーキングメモリトレーニング:神経イメージングからの洞察 第Ⅰ部 ワーキングメモリ:新しい知性 第1章 ワーキングメモリ:序論 第2章 ワーキングメモリと知能:展望 第3章 ワーキングメモリの進化 第Ⅱ部 生涯にわたるワーキングメモリ 第4章 発達におけるワーキングメモリ 第5章 ワーキングメモリの階層モデルと健康な高齢者のその変化 第Ⅲ部 ワーキングメモリと専門知識 第6章 熟達者のワーキングメモリ:伝統的なワーキングメモリ概念との質的な相違 第7章 ワーキングメモリ容量と音楽の技能 第Ⅳ部 ワーキングメモリと身体 第8章 ワーキングメモリと食習慣 第9章 断眠とパフォーマンス:ワーキングメモリの役割 第10章 ワーキングメモリと嗜癖行動 第Ⅴ部 ワーキングメモリと意思決定 第11章 ワーキングメモリと不安:個人差と発達の相互作用を探る 第12章 情動と認知的制御の統合 第13章 ワーキングメモリと瞑想 第Ⅵ部 ワーキングメモリの将来:トレーニング 第14章 ワーキングメモリをトレーニングする 第15章 ワーキングメモリトレーニング:神経イメージングからの洞察
今では色んなところで引用される人生100年時代というパスワードのきっかけになった書籍。もう既に1つの会社に勤め上げるような旧来の生き方は崩壊している。将来に不安を抱いているビジネスパーソンはこの本を読んで時代の変化に置いていかれないような生き方を選択して欲しい。
福岡伸一が「動的平衡」をキーワードに、西田幾多郎の難解な哲学に挑む書籍が新書化されました。福岡は生命とは何かをわかりやすく解説し、西田哲学と科学の融合を探求します。池田善昭との対話を通じて、読者は哲学と生命科学の深い理解に導かれる内容となっています。オリジナル版はベストセラーとなり、哲学の面白さを再発見させる一冊です。
西野亮廣氏の書籍はどれも素晴らしい。自己啓発書でありがちなモチベーションが上がって終わりみたいなことがなく、具体的な事例をもとに自分の打ち手の引き出しを増やすことができる。
読みながら行動や考えを改められ、少しずつ自身に変化を感じられる素晴らしい書籍です!
誰もが知る名著なので一度は目を通しておくべきだが、内容は冗長で個人的にはあまりはまらなかった。重要度×緊急度のマトリクスの話が一番重要で、そこだけ理解しておけばいい気がする。緊急度は低いが重要度が高いタスクになるべく長期的な視点で取り組めるようになるべき。
『茶の本』の全訳と『東洋の理想』の抄訳を収録したこの書籍は、岡倉天心の思想や生涯を紹介しています。茶道の精神を通じて日本文化の独自性や自然との調和を探求し、天心のエピソードや証言を交えた伝記が添えられています。内容は茶の文化や流派、道教と禅、茶室、芸術鑑賞、花の重要性、茶人の影響など多岐にわたります。読みやすい訳文と解説により、天心の思想や人間性を理解する入門書となっています。
このビジネス書は、多様性を取り入れた組織が成功する理由を探求し、致命的な失敗を未然に防ぎ生産性を高めるための組織改革の方法を提示しています。著者マシュー・サイドは、革新を促す要素やコミュニケーションの重要性について考察し、具体的な事例を通じて読者に考えさせる内容となっています。シリーズは好評を博し、さまざまなメディアで紹介されています。
この本は、仏教の教えを通じて感性を磨くことで、虚しい人生から脱却し、幸せを実現する方法を提案しています。著者は、感性が人生の質を左右することを強調し、苦しい時の考え方や人間関係の改善、老いと死についての捉え方など、感性を豊かにする技術を紹介しています。全体を通じて、心を整える練習を通じて「ありのまま」に生きることができる方法を探求しています。
注意,学習,記憶という認知プロセスと感情を含む動機づけのプロセスとの関係について,最新の研究状況を俯瞰し,解説する。 動機づけと認知の相互依存性に関心をもつ研究者必携のハンドブック。 心理学と神経科学の融合分野の現在を一望する。 動機づけが認知を,あるいは,認知が動機づけを支えるメカニズムは,どのようになっているのだろうか? また,その際の相互作用は? 注意,学習,記憶という認知プロセスと感情を含む動機づけのプロセスとの関係について最新の研究状況を俯瞰し,認知心理学と神経科学との融合分野として,今後の研究のあり方も含め解説する。 ◆主な目次 第1章 動機づけと認知コントロール:序論 ●第I部 認知処理と目標指向的行動に及ぼす報酬の影響 第2章 視覚情報処理における動機づけの役割 第3章 注意に対する報酬の影響:動機づけを超えて 第4章 刺激と報酬の連合についての試行内効果 第5章 認知コントロールへの動機づけの影響:報酬処理の役割 第6章 認知コントロールに及ぼす報酬の効果の構造解析 第7章 目標指向的行動の観念運動メカニズム ●第II部 認知的自己調整の感情の源泉と動機づけの源泉 第8章 目標は行動をどのようにコントロールするのか:行為-結果と報酬情報の役割 第9章 感情,動機づけ,認知範囲 第10章 嫌悪信号としての葛藤:感情調整役割におけるコントロール適応の動機づけ 第11章 活力と疲労:感情の多様性はいかにして効果的な自己コントロールの基盤になるか 第12章 努力を要するコントロールにおける老廃物処理問題 ●第III部 認知的動機づけにおける年齢に関連した変化 第13章 十代の脳:誘惑抵抗における「発育停止」 第14章 適応的な神経認知的表象の生涯発達:認知と動機づけの互恵的相互作用 第15章 健常加齢における動機づけ-学習の3要因理論に向けて 第16章 認知的関与,動機づけ,および行動におけるコストの加齢変化の関係 第17章 動機づけの加齢変化:成人期と高齢期にわたる動機づけの加齢変化は情動経験に影響するのか 日本語版『動機づけと認知コントロール』の読者のみなさんへ 推薦文 第1章 動機づけと認知コントロール:序論 1節 動機づけと認知コントロール 2節 広範な視点 3節 本書の必要性 4節 重要な研究テーマと本書の構成 1.認知処理と目標指向的行動に及ぼす報酬の影響 2.認知的自己調整の感情の源泉と動機づけの源泉 3.認知的動機づけにおける年齢に関連した変化 5節 要約と結論 第I部 認知処理と目標指向的行動に及ぼす報酬の影響 第2章 視覚情報処理における動機づけの役割 1節 はじめに 2節 視覚処理への動機づけの初期の影響と後期の影響 3節 課題関連刺激に対する注意選択の動機づけによる促進 4節 過去の報酬による視覚的注意の調節 1.注意選択への動機づけの短期的な影響 2.注意選択への動機づけの持続的な影響 3.注意選択への持続的な動機づけの影響の神経基盤 5節 動機づけと注意の関係 6節 動機づけの関連性についての情報は視覚領域にどのように到達するのか 7節 結論と展望 第3章 注意に対する報酬の影響:動機づけを超えて 1節 外的報酬が注意を調節するという証拠 2節 価値駆動型注意:目標と価値が葛藤している場合 3節 報酬に基づく動機づけと価値駆動型注意の分離 1.価値駆動型注意がない場合の報酬に基づく動機づけ 2.報酬に基づく動機づけがない場合の価値駆動型注意 4節 報酬が注意にバイアスをかけるというさらなる証拠 5節 価値駆動型注意:動機づけられた認知の意義 第4章 刺激と報酬の連合についての試行内効果 1節 はじめに 2節 手がかりのない試行内報酬操作 3節 反応性コントロールの寄与の可能性とボトムアップ型のプロセス 4節 結論と展望 第5章 認知コントロールへの動機づけの影響:報酬処理の役割 1節 はじめに 2節 人間の脳における報酬処理 3節 認知コントロールへの報酬の影響 4節 動機づけ要因としての報酬 5節 ストレス:動機づけ要因か抑制要因か 6節 ストレス暴露は認知プロセスと報酬回路を調節する 7節 抑うつと神経報酬システムの調節障害 8節 おわりに:報酬処理の認知コントロール 第6章 認知コントロールに及ぼす報酬の効果の構造解析 1節 はじめに 2節 報酬の構造解析 3節 認知コントロールの構造解析 4節 認知コントロールに対する報酬の効果の構造解析 1.認知コントロールに及ぼす報酬の快楽効果:探索 2.認知コントロールに及ぼす報酬の学習効果:活用 3.認知コントロールに及ぼす報酬の動機づけ効果:予期 5節 いくつかの決定要因 1.報酬信号:報酬の顕著性と刺激の持続時間 2.報酬スケジュール:手がかりの存在と遂行随伴性 6節 今後の研究のための指針 7節 結論 第7章 目標指向的行動の観念運動メカニズム 1節 目標指向的行動 2節 観念運動理論 1.刺激-行為結果の転移 2.刺激-行為結果の適合性 3節 行為と習慣の神経生物学 4節 動機づけと誘因学習 5節 動機づけコントロールの実行 6節 結論 第II部 認知的自己調整の感情の源泉と動機づけの源泉 第8章 目標は行動をどのようにコントロールするのか:行為-結果と報酬情報の役割 1節 はじめに 2節 認知コントロールの方向づけ開始点としての行為-結果表象 3節 認知コントロールの活性開始点としての報酬信号 4節 行為における結果と報酬の情報 5節 研究意義と将来の方向性 第9章 感情,動機づけ,認知範囲 1節 はじめに 1.定義 2節 動機づけと認知との相互作用(行動面からの検討) 1.時間知覚 2.注意 3.記憶 4.カテゴリー化 5.課題遂行 3節 認知範囲に及ぼす動機づけ強度の影響の神経相関 1.非対称的な前頭皮質の活動 2.事象関連電位 3.ベータ波の抑制 4節 結論 第10章 嫌悪信号としての葛藤:感情調整役割におけるコントロール適応の動機づけ 1節 認知コントロールのトップダウン型の調整とボトムアップ型の調整 2節 なぜ反応葛藤はコントロール適応を引き起こすのか 3節 動機づけ理論における葛藤の役割 4節 葛藤の動機づけの影響 5節 反応葛藤の嫌悪的性質 6節 嫌悪的葛藤とは何か 7節 嫌悪信号は系列的処理調整を引き起こすのか 8節 葛藤によって引き起こされた感情的逆調整 9節 葛藤信号の意識経験 1.断片的研究知見の統合 第11章 活力と疲労:感情の多様性はいかにして効果的な自己コントロールの基盤になるか 1節 情動エピソードとしての自己コントロール 1.エラーと葛藤はネガティブ感情傾向をもつ 2.遂行モニタリング 3.感情処理,前帯状皮質,および遂行モニタリング 2節 情動エピソードとしての自己コントロール:コントロールの調整 1.警報信号としての感情 2.ネガティブ感情と自己コントロールの(明らかな)限界 3節 討論 1.感情の現象学,コントロールの主観的価値,および自己調整 2.葛藤に対する神経感情的反応の役割 4節 結語と将来の方向性 第12章 努力を要するコントロールにおける老廃物処理問題 1節 認知コントロールによって産出される毒性老廃物とは何か 2節 認知コントロールに関するどのような神経系が老廃物を生み出すのか 3節 認知コントロールは老廃物の蓄積をどのように加速するのか 1.青斑核,細胞代謝,そして学習 2.前帯状皮質,青斑核,そして神経活動の同期性 4節 未解決の部分 5節 結論 第III部 認知的動機づけにおける年齢に関連した変化 第13章 十代の脳:誘惑抵抗における「発育停止」 1節 はじめに 2節 青年期とは何か 3節 青年期の神経生物学的モデル 4節 認知コントロールの発達 5節 動機づけプロセスの発達 6節 認知プロセスと動機づけプロセスの相互作用 7節 青年の利益のために脳と行動の変化をどのように利用するか 8節 結論 第14章 適応的な神経認知的表象の生涯発達:認知と動機づけの互恵的相互作用 1節 はじめに 2節 前頭-線条体-海馬システムのドーパミン調節を介した認知-動機づけの互恵的相互作用 3節 ドーパミン調節の成熟と老化 4節 遂行モニタリングメカニズムの生涯発達 1.フィードバック関連処理の心理生理学的指標における年齢差 5節 注意と記憶の動機づけ調整の生涯発達 1.記憶の報酬調節における生涯にわたる差異 2.注意の報酬調節における生涯にわたる差異 6節 習慣的・方略的な目標指向的学習と意思決定の生涯発達 1.習慣的プロセスと目標指向的プロセス 2.モデルフリー学習と意思決定における生涯発達的差異 3.モデルベース学習と意思決定における生涯発達的差異 4.習慣的・方略的な目標指向的学習と意思決定の相互作用の生涯発達 7節 展望と結語 第15章 健常加齢における動機づけ-学習の3要因理論に向けて 1節 はじめに 2節 本章の構成 3節 動機づけとは何か,どのように定義されるか? 4節 動機づけの全体的側面と局所的側面 5節 分離可能な学習システムと課題指向的動機づけ 1.意思決定 6節 意思決定における動機づけ-学習インターフェイスに関する実証的検証 7節 健常加齢における動機づけ-学習インターフェイス 1.健常加齢における学習システムと課題指向的動機づけ 8節 実証研究1:健常加齢における課題指向的動機づけと意思決定 9節 実証研究2:健常加齢における全体的回避動機づけ(圧力)と状態に基づく意思決定 10節 総合考察 11節 今後の方向性 12節 結論 第16章 認知的関与,動機づけ,および行動におけるコストの加齢変化の関係 1節 高齢期における認知資源の選択的関与 1.加齢と認知的関与のコスト 2.認知的関与における選択性効果 3.加齢,コスト,動機づけ,および関与の関係 2節 結論と含意 1.日常生活における能力と課題遂行との関係 2.高齢期における認知的健康 3.関与閾への影響 第17章 動機づけの加齢変化:成人期と高齢期にわたる動機づけの加齢変化は情動経験に影響するのか 1節 加齢における動機づけの変化に関する社会情動的視点 2節 私たちの研究室でのポジティブ性効果の実証的検証:視覚的注意の場合 3節 調整方略の年齢差は基盤となる動機づけの変化を反映する 4節 認知プロセスと感情の結果を結びつけるための理論的枠組み 5節 社会情動的加齢に関する補足的な動機づけ以外の説明 6節 結語 文献 邦訳文献 索引 訳者あとがき
この書籍は、経営者である稲盛和夫が自身の成功の基盤となる人生哲学を語ったもので、刊行10年目にして100万部を突破したロングセラーです。内容は、夢の描き方や実現方法、人間として大切なことについて述べており、トップアスリートたちも推薦しています。目次には、思いを実現させる法則、原理原則の重要性、心の磨き方、利他の精神、宇宙との調和などが含まれています。著者は京セラとKDDIの創業者であり、経営者育成にも力を入れています。
伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方に触れることのできる良書。
伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方にふれることができる。経営やビジネスの考え方というよりも哲学・道徳観点の話が多い書籍。なにかテクニック的なことを学ぶことはできないが人生を生き抜く上での指針になる。ぜひ読んで欲しい名著
判断や意思決定過程と理論における歴史的基礎,認知的一貫性と非一貫性,神経経済学と神経生物学など6つの分野に焦点を当て詳説。 判断や意思決定過程とその理論探求は,経済的な影響のみならず,人の幸福と関連する重要課題として学際的な広がりを見せている。本書ではその歴史的基礎,認知的一貫性と非一貫性,ヒューリスティクスとバイアス,神経経済学と神経生物学,発達段階における差異と個人差,意思決定の改善の6つの分野に焦点を当て詳説する。 【主な目次】 序章 ●第I部 歴史的基盤 第1章 熟達者による意思決定:5人のキーとなる心理学者の影響 ●第II部 認知的一貫性と非一貫性 第2章 認知的一貫性:認知的・動機づけ的観点 第3章 感情予想に関する矛盾をはらんだ乖離についてのファジートレース理論による説明 ●第III部 ヒューリスティクスとバイアス 第4章 ファジートレース理論における直観,干渉,抑制,そして個人差の問題 第5章 意思決定前にみられる情報の歪曲 第6章 精密性効果:精密な数値表現が日常的判断にどのような影響を及ぼすか ●第IV部 神経経済学と神経生物学 第7章 フレーミング効果の行動的・神経科学的分析による意思決定過程の検討 第8章 “熱い”認知と二重システム:導入・批判・展望 第9章 慈善的寄付の基盤となる神経経済学と二重過程モデル ●第V部 発達と個人差 第10章 発達におけるリスク志向性:決定方略,感情,制御の変化 第11章 意思決定能力の生涯発達 ●第VI部 よりよい決定のために 第12章 リスクのある意思決定の予測因子:フィッシング攻撃の実例に基づく,判断と意思決定の向上 第13章 シミュレーション結果の経験による判断と意思決定の改善 序章 第Ⅰ部 歴史的基盤 第1章 熟達者による意思決定:5人のキーとなる心理学者の影響 1節 James McKeen Cattell 2節 Wilhelm Wundt 3節 Edward Titchener 4節 Edwin G. Boring 5節 一般化された普通の成人の心 6節 計量心理分析を用いた伝統的な意思決定研究 7節 線形モデルを用いた伝統的な意思決定研究 8節 情報の利用に関する仮説 9節 ヒューリスティクスとバイアスによる伝統的な意思決定研究 10節 Wilhelm Wundt とWard Edwards 第Ⅱ部 認知的一貫性と非一貫性 第2章 認知的一貫性:認知的・動機づけ的観点 1節 認知的一貫性に関する諸理論 1.認知的一貫性の潮流/2.自己理論の潮流/3.意味管理の潮流/4.個人差の潮流 2節 統合的枠組み 1.既存の枠組み/2.枠組みを拡張する 3節 実験結果 4節 結論 第3章 感情予想に関する矛盾をはらんだ乖離についてのファジートレース理論による説明 1節 ファジートレース理論 2節 主旨と発達,熟達化 3節 リスクの知覚とリスクテイキング 4節 少数の特性から高い正確性を得る 5節 ファジートレース理論と感情の記憶 6節 幸福度と主観的ウェルビーイングのアセスメント 7節 主旨に基づいた感情価の判断 8節 逐語的詳細に基づいた正確な判断 9節 主旨情報に基づく全般的予測 10節 結論 第Ⅲ部 ヒューリスティクスとバイアス 第4章 ファジートレース理論における直観,干渉,抑制,そして個人差の問題 1節 判断,意思決定における干渉 1.干渉の処理 2節 主旨に基づいた意思決定 3節 個人差と抑制 4節 衝動性と直観:異なる概念 5節 認知的能力の高さがよい判断・意思決定につながらない場合 6節 結論 第5章 意思決定前にみられる情報の歪曲 1節 経験的証拠 2節 情報の歪曲は測定方法によるアーティファクトなのか 3節 情報の歪曲は取り除くことができるのか 4節 情報の歪曲を示さない人は存在するのだろうか 5節 情報の歪曲は何によって引き起こされるのか 6節 インプリケーション 1.初頭効果による解釈 7節 情報の歪曲の合理性とベイズ推定 8節 ヘッドスタートの影響 9節 出現した選好に対する関与 10節 判断と意思決定の研究パラダイム 11節 エピローグ 1.情報の歪曲に関する研究の歴史/2.実験パラダイム間の対立 第6章 精密性効果:精密な数値表現が日常的判断にどのような影響を及ぼすか 1節 不一致帰属仮説 2節 計算容易性効果 1.不一致帰属の役割/2.素朴理論の役割 3節 精密性効果 1.不一致帰属の役割/2.素朴理論の役割 4節 精密性と信用可能性 1.文脈的手がかりの役割 5節 精密性と希少性 1.文脈的手がかりの役割 6節 精密性と信頼区間 7節 残された課題 1.神経科学の役割 8節 結論 第Ⅳ部 神経経済学と神経生物学 第7章 フレーミング効果の行動的・神経科学的分析による意思決定過程の検討 1節 序論 1.課題 2節 フレーミングタスク 3節 個人差について 4節 二重過程理論 5節 情動過程とフレーミング効果 6節 フレーミング効果とそれ以外の効果における脳代謝レベルでの効果 7節 意思決定の新しい理論を検証するための新しい方法 8節 特殊な集団におけるフレーミング効果 9節 生涯にわたる意思決定 10節 高齢の意思決定者におけるフレーミングと課題に関連した違い 11節 まとめ,結論と将来の研究 第8章 “熱い”認知と二重システム:導入・批判・展望 1節 温度隠喩 2節 “熱”から自律神経反応と誘因顕著性へ 3節 二重過程と二重システムモデル 4節 展望:さらに優れた疑問の問いかけ 5節 R3:熟考の再処理と強化モデル 第9章 慈善的寄付の基盤となる神経経済学と二重過程モデル 1節 二重過程の枠組み 2節 慈善的寄付における,情動と認知の役割について 3節 命の評価における行動的な偏見 4節 心理物理的な無感覚 5節 規模の感受性の鈍麻 6節 同定可能性 7節 疑似無効力とプロポーション優越性 8節 慈善的寄付の神経経済学的視点 9節 まとめ 第Ⅴ部 発達と個人差 第10章 発達におけるリスク志向性:決定方略,感情,制御の変化 1節 決定方略 1.統合的な方略とヒューリスティック/2.統合的な決定方略とヒューリスティックの発達プロセス/3.意思決定の神経科学 2節 感情と制御:二重過程モデルによる説明 1.文脈/2.個人差/3.感情と制御:よい意思決定を学習する 3節 結論 第11章 意思決定能力の生涯発達 1節 意思決定能力の定義 1.規範的理論:人はどのように意思決定を行うべきか?/2.記述的研究:人はどのようなときに規範的な基準に反する意思決定を行うのか? 2節 意思決定能力の生涯発達 1.青年期と成人期の意思決定能力に関する比較/2.高齢者と若い成人の意思決定能力についての比較 3節 意思決定能力の総合的な尺度の開発とその妥当性の検討 1.個人差を反映した妥当性のある意思決定能力の尺度の必要性/2.個人差を反映した意思決定能力の尺度の開発と妥当性の検討/3.意思決定能力の要因と結果を考察する枠組み 4節 今後の展望 第Ⅵ部 よりよい決定のために 第12章 リスクのある意思決定の予測因子:フィッシング攻撃の実例に基づく,判断と意思決定の向上 1節 実証的に支持される知見 2節 考察 第13章 シミュレーション結果の経験による判断と意思決定の改善 1節 人の認知処理の長所と短所 2節 判断課題の構造 3節 人と課題とのマッチング:その含意 4節 シミュレーションの経験の検討:研究プログラムの概要 1.確率判断課題/2.投資/3.競争的行動 5節 考察 文献 人名索引 事項索引 監訳者あとがき
実証的知見を踏まえつつ, 教育的介入を意図した実践的研究の紹介に力点を置く。 言語力や推論能力,動機づけなど学習にかかわる主要な認知活動とその発達に関する基礎理論,実証的知見を踏まえつつ,学校での教科の学習を中心に教育的介入を意図した実践的研究の紹介に力点を置く。メタ認知や学習観の形成,文章理解,数学的問題解決,科学的概念の獲得など,具体的な教育実践に多大な示唆を与える。 ◆執筆者一覧(執筆順) 秋田喜代美 東京大学大学院教育学研究科 第1章 針生悦子 東京大学大学院教育学研究科 第2章 藤村宣之 東京大学大学院教育学研究科 第3章 山 祐嗣 大阪市立大学大学院文学研究科 第4章 村山 航 University of Munich 第5章 遠藤利彦 東京大学大学院教育学研究科 第6章 植阪友理 東京大学教育学研究科学校教育高度化センター 第7章 犬塚美輪 大正大学人間学部 第8章 瀬尾美紀子 日本女子大学人間社会学部 第9章 湯澤正通 広島大学大学院教育学研究科 第10章 今井むつみ 慶應義塾大学環境情報学部 第11章 佐治伸郎 日本学術振興会/慶應義塾大学 第11章 市川伸一 編者 第12章 『現代の認知心理学』刊行にあたって まえがき 第1部 基礎と理論 第1章 認知心理学は学習・教育の実践と研究に何をもたらしたか 1節 はじめに 2節 学習観の転換と理解過程や知識への注目 3節 社会文化的なコミュニティへの参加による学びあう過程の解明 4節 まとめにかえて 文献 第2章 言語力の発達 1節 はじめに 2節 話しことばの発達 3節 書きことばへの移行 文献 第3章 数量概念の獲得過程 1節 はじめに 2節 数量概念獲得の現状 3節 手続き的知識とスキルの発達 4節 概念的理解の発達 5節 数量概念獲得の微視的プロセス 6節 数量概念獲得の促進可能性 7節 数量概念獲得に関わる社会的要因 文献 第4章 推論能力の発達 1節 はじめに 2節 演繹推論の発達 3節 帰納推論の発達 4節 領域固有性対領域普遍性 5節 まとめ 文献 第5章 認知と動機づけ 1節 はじめに 2節 動機論 3節 認知論 4節 動機づけ研究における認知論とは 5節 認知と動機づけに関する研究――認知論を超えて 6節 おわりに 文献 第6章 感情と情意理解の発達 1節 はじめに 2節 認知的評価の視座から見る感情の発達 3節 情意理解の礎としての社会的感性 4節 視線と表情の理解が拓く発達的可能性 5節 「心の理論」と情意理解の深化 6節 結びとして 文献 第2部 展開と実践 第7章 メタ認知・学習観・学習方略 1節 はじめに 2節 メタ認知・学習観・学習方略とは 3節 メタ認知・学習観・学習方略を支援する試み 4節 結びにかえて――今後の課題 文献 第8章 文章の理解と産出 1節 はじめに 2節 文章の理解 3節 文章の産出 4節 文章理解と産出の教育に関する新しい課題 5節 まとめ 文献 第9章 数学的問題解決とその教育 1節 はじめに 2節 数学的問題解決の認知過程 3節 数学的問題解決を説明する要因 4節 数学的問題解決の学習と指導――認知心理学から教育実践への提案 5節 おわりに――今後の課題 文献 第10章 科学的概念の発達と教育 1節 はじめに 2節 3タイプの科学のイメージ 3節 論理的推論としての科学的思考・概念の発達 4節 理論の変化としての科学的概念の発達 5節 科学的概念の発達と適用を支える文脈 文献 第11章 外国語学習研究への認知心理学の貢献―語意と語彙の学習の本質をめぐって― 1節 はじめに 2節 語彙学習の重要性 3節 言語のカテゴリーと認識の関係――色名の多様性を例に 4節 語と語の関係を理解することの重要性 5節 基本的な動作の名前のつけかたの違い 6節 学習者は複雑な意味領域の意味地図をどのように学習するのか 7節 本章のまとめと結論 文献 第12章 認知心理学は教育実践にどう関わるか 1節 はじめに 2節 認知心理学が提供する人間観・学習観 3節 児童・生徒の現実に関わる 4節 教育関係者との関わり 5節 認知心理学の転換期――状況論,PDP,そして認知神経科学 6節 認知心理学を生かした授業と評価 7節 認知心理学のどこをどう教育に生かすのか 文献 人名索引 事項索引
『文明論之概略』は、福澤諭吉が維新直後の日本における文明の理想と自国の独立の重要性を論じた著作です。彼は当時の日本の状況を冷静に分析し、文明の本質や智徳について考察しています。この作品は、巧みな例示とリズミカルな文体で知られ、近代日本の重要な文献として現代語で再評価されています。著者の福澤は啓蒙思想家であり、慶應義塾の創設者でもあります。
人に何かを伝える方法の勉強にはなるが伝え方が本当に9割なのかは疑問。〇〇が9割シリーズが流行っているので結局シーンによってどこに重点を置くかは変わる。読んで損はない。
自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。
ホリエモンの行動力に驚く。結局本書で言っているのはグダグダ考えてないでとりあえず行動しろ!動けってこと。読むだけでモチベーションが上がるが、これを読んで満足してしまって何も行動しないのであれば元とも子もない。これを読んでしっかり行動に移すべき。
この絵本「あなたが今日、ここにいる」は、新しい世界に踏み出す子どもたちへの贈り物として、彼らの存在がどれほど素晴らしいかを伝える内容です。入園・入学の際に最適で、感動的なメッセージが多く寄せられています。著者は玉置永吉とえがしらみちこで、絵本としての評価も高く、各種賞を受賞しています。
「感性」に関するよくある質問
Q. 「感性」の本を選ぶポイントは?
A. 「感性」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「感性」本は?
A. 当サイトのランキングでは『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで165冊の中から厳選しています。
Q. 「感性」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「感性」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。


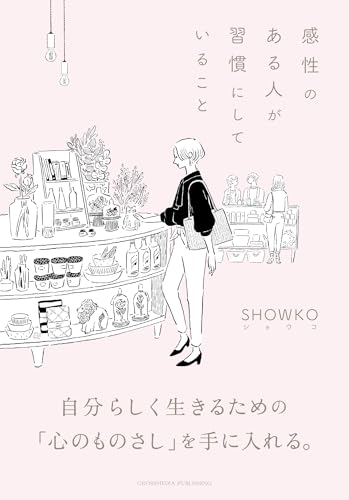






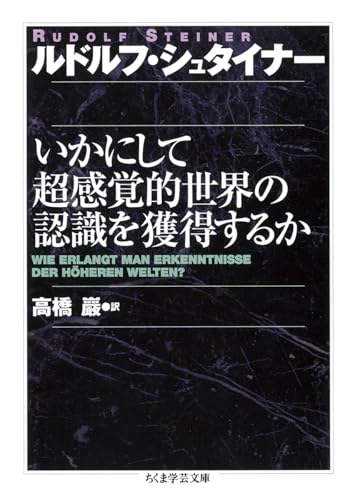






















![『配色アイデア手帖 めくって見つける新しいデザインの本[完全保存版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41YDOPwkFtL._SL500_.jpg)























































































![『シールアートブック 世界の名画 ([バラエティ])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51uMTaq5m5L._SL500_.jpg)
























































