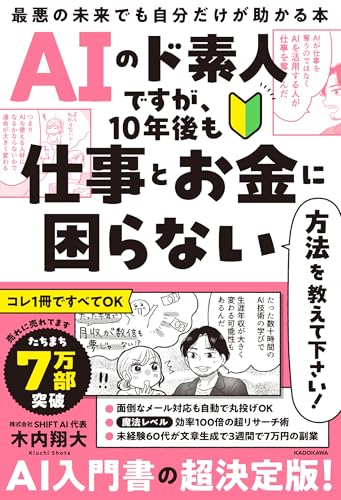【2025年】「脳の仕組み」のおすすめ 本 146選!人気ランキング
- メカ屋のための脳科学入門-脳をリバースエンジニアリングする-
- つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線 (ブルーバックス 1994)
- 進化しすぎた脳―中高生と語る「大脳生理学」の最前線 (ブルーバックス)
- 単純な脳、複雑な「私」 (ブルーバックス 1830)
- 面白くて眠れなくなる脳科学
- 小説みたいに楽しく読める脳科学講義
- ビジュアル図解 脳のしくみがわかる本 気になる「からだ・感情・行動」とのつながり (「わかる!」本)
- 世界最先端の研究が教える すごい脳科学
- もっと! : 愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学
- カラー図解 脳の教科書 はじめての「脳科学」入門 (ブルーバックス)
この書籍は、脳科学をエンジニアリングの視点から探求する内容で、以下の5つの編から構成されています。第1編では脳の構造と機能を紹介し、第2編では神経細胞の特性と情報処理メカニズムを解説。第3編では運動の制御機構について、第4編では知覚の形成と脳の学習メカニズムを探ります。最後に第5編では脳と芸術の関係を考察し、好みや芸術の法則性について論じています。著者は東京大学の高橋宏知で、神経工学と聴覚生理学の専門家です。
この書籍は、脳の働きについての最新研究を紹介し、記憶や感情、認知のメカニズムを探求しています。具体的には、グリア細胞やニューロン、空間記憶、感情の神経回路など、脳内のさまざまな「つながり」を解明する9つの章から構成されています。脳の機能や病気の治療法、親子の絆に関する研究も含まれており、心を生み出す脳の理解を深める内容となっています。
著者池谷裕二の新著は、最先端の脳科学に基づき「心」の生成メカニズムを探求する連続講義の内容をまとめたものです。私たちの心に対する理解が最新の研究によって変わっていく様子を描き、著者自身が特に愛着を持つ作品としています。各章では、脳の理解、心の視点、自由の創造、ノイズからの生命生成などがテーマとなっています。
この本は、脳の不思議や可能性について探求する内容で、右脳と左脳の役割、脳の細胞の重要性、自己認識のメカニズムなどを解説しています。目次では、脳の歴史や脳科学と心理学の関係、夢のメカニズムなど多様なテーマが取り上げられています。著者は毛内拡で、脳科学の専門家として研究を行っています。
本書は脳の基本的な構造や機能をイラストと図解でわかりやすく解説した入門書です。脳の役割、感情や記憶、体との連携、五感のメカニズム、体の調整機能、老化に伴う病気について触れています。監修者の加藤俊徳氏は、脳を理解することが人生を知ることにつながると述べ、脳の成長と変化が個人の経験に影響を与えることを強調しています。読者に脳への関心を深めてもらうことを目的としています。
この書籍は、最新の脳科学を基に人間の心と行動を科学的に検証し、行動の背後にある理由を解明します。脳の機能や記憶力向上、メンタルの鍛え方、恋愛やダイエットの方法、認知機能の維持、天才と普通の人の脳の違いなど、実生活に役立つ情報が豊富に含まれています。全5章で脳と心の関係、感覚の不思議、意外な研究結果、恐怖に関する研究、倫理的問題の処理などを紹介し、脳科学への興味を引き立てる内容となっています。著者は玉川大学脳科学研究所の教授、坂上雅道氏です。
この本は、ドーパミンが私たちの欲求、創造性、成功に与える影響を探求しています。ドーパミンは「快楽物質」ではなく、「欲求ドーパミン」と「制御ドーパミン」の2つの回路を通じて期待や達成感を生み出します。著者は、恋愛、依存症、創造性、政治、社会の進歩など、多様なテーマを通じてドーパミンの役割を解説し、未来志向のドーパミンと現在志向のバランスが脳の潜在能力を引き出す鍵であると述べています。著者はダニエル・Z・リーバーマンとマイケル・E・ロングです。
この書籍は、脳の構造や機能について豊富なカラー図版を用いてわかりやすく解説しています。脳の進化、神経細胞やグリア細胞の役割、記憶の形成と蓄積、意識や思考のメカニズムなど、脳に関する多様な謎を最新の研究を交えて紹介しています。医学生や医療関係者だけでなく、脳に興味があるすべての人にとって必読の一冊です。著者は、脳の高次機能や進化に関する研究を行っている京都大学名誉教授の三上章允です。
NHKスペシャル『立花隆 臨死体験』出演の天才脳科学者、初の翻訳! 脳は意識を生み出すが、コンピューターは意識を生み出さない。では両者の違いはどこにあるのか。クリストフ・コッホが「意識に関して唯一、真に有望な基礎理論」と評した、意識の謎を解明するトノーニの「統合情報理論」を紹介。わくわくするようなエピソード満載でわかりやすく語られる脳科学の最先端、待望の翻訳! 【本書が挑む脳科学最前線の驚異の事例】 ・脳幹に傷を負い植物状態に見えるロックトイン症候群患者(映画「潜水服は蝶の夢を見るか」の主人公)。彼らの意識の有無はどう診断すればいいのか? ・麻酔薬を投与するとなぜ意識が失われるのか? 麻酔時に意識が醒めてしまうとどうなるのか(1000人に1人はそうなる) ・右脳と左脳をつなぐ脳梁を切断する(スプリットブレイン。てんかん治療で行われることがある)と、1つの脳のなかに意識が2つ生まれる!?
この文章は、脳の構造や機能、記憶、学習、意識、倫理に関する内容を扱った書籍の目次を紹介しています。手法編では脳の観察方法、記憶・学習編では海馬の役割、意識編では情動や無意識の意思決定、倫理編では社会的価値について触れています。また、著者の高橋宏知は神経工学と聴覚生理学の専門家で、東京大学で講師を務めています。
自分探し」は、これでおしまい! 「やりたいことがわからない人」に贈る科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」。 「私は、何がしたいんだろう?」「自分の人生、このままでいいのだろうか?」一度でも、こんなことを考えたことはありませんか?人と比べて、「何者でもない自分」に絶望したとき先が見えなくて、「将来が不安」なとき就職、転職、結婚、第2の人生……「人生の岐路」に立たされたとき今の仕事に「やりがい」を感じられないときなかなか結果が出なくて「焦っている」ときそんなとき、向いている仕事、自分の強み、進むべき道を考えて、自分で、自分がわからなくなる――。こうした「自分探し」は、今日でもうおしまい!本書は、200以上の論文と7つのワークで、科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」を解説します。ワーク1 「ライフワークの原石」を見つけようワーク2 「ライフワークの原石」を採点してみようワーク3 7つの質問で「自分の個性」を可視化するワーク4 自分の才能がわかる「診断シート」ワーク5 自分に「向いている仕事」を探すワーク6 「3つのバランス」を確認しようワーク7 「メメント・モリ」で人生の優先順位を明らかにこの1冊で、これまでのモヤモヤがパっと晴れる「やりたいこと探し」の決定版。
このビジュアル図鑑は、脳の構造や機能、最新の研究成果をわかりやすく解説しており、入門書や参考書に最適です。内容は脳の成り立ち、機能、感覚、コミュニケーション、記憶、意識、未来の脳、関連疾患について構成されています。著者は九州大学の専門家たちです。
この書籍は、最新の科学に基づいて脳細胞の増やし方を解説しています。目次には、運動や学習、ストレス、不安、うつ、注意欠陥障害、依存症、ホルモンの変化、加齢、そして脳を鍛える方法が含まれています。著者はハーバード大学の医学博士ジョン・レイティで、精神医学の専門家として多くの研究を行っています。彼はまた、定期的な有酸素運動の重要性を広める活動でも知られています。
本書は、Googleの独自研修プログラム「サーチ・インサイド・ユアセルフ(SIY)」を通じて、楽しく創造的に働くためのマインドフルネスの実践方法を紹介しています。著者のチャディー・メンは、自己認識力や創造性を高める技法をユーモアを交えてわかりやすく説明し、ビジネスパーソンや入門者にとっての実践バイブルとしています。SIYは他の企業や大学でも採用されており、情動的知能を育むことが強調されています。
本書は、大人が効果的に学び直すための方法を紹介しています。加齢による脳の記憶力低下は誤解であり、大人の脳は学生時代よりも優れた状態にあると説明されています。脳科学に基づいた勉強法や記憶力向上のテクニックを提案し、30代から60代以降までの大人が脳力を高めるための具体的な方法を提供します。著者は脳内科医の加藤俊徳で、脳の成長段階やトレーニングについての専門家です。
本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。
10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。
『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。
この書籍は、1900年にM・プランクが「量子」という概念を考案したことから始まり、量子力学の発展と、それに伴う物理学の変革を描いたノンフィクションです。アインシュタインとボーアの論争を中心に、ハイゼンベルク、ド・ブロイ、シュレーディンガーなどの物理学者の人間ドラマも交えながら、物理学の100年の歴史を追います。著者はマンジット・クマールで、翻訳は青木薫が担当しています。
この本は、親が一貫した姿勢を持つことの重要性を説き、子育ての悩みを解決するための具体的な方法を提供します。著者の奥田健次は、数万件の育児問題を解決してきた専門家であり、子どもとの接し方やルール作り、効果的な叱り方など、実践的なアドバイスを通じて「親子ともによく育つ」方法を提案しています。内容は、いじめやスマホの使い方、不登校のリスクなど現代の課題にも対応しています。
本書は、社会認知神経科学の専門家であるマシュー・リーバーマンが、人間の脳に備わる「つながる」「心を読む」「調和する」という三つの力が人類の発展の鍵であることを探求しています。脳の働きや社会的な関係性、感情の理解、そして日常生活での実践方法について述べられており、より良い生活を送るためのヒントが提供されています。目次は進化と社会性、つながる脳、心を読む脳、調和する脳、実践編の五部構成になっています。
本書は、心理学の基本概念を生徒と先生の対話形式でわかりやすく解説する入門書です。心の働きが日常の行動や判断にどのように影響するかを科学的に理解することを目指しています。目次には性格、社会心理学、感情、記憶、臨床心理学などが含まれています。著者は東京大学の教授で、臨床心理学を専門としています。
1848年、米国での事故により、現場監督P・ゲージの性格が変わった。この事例を通じて、著者アントニオ・ダマシオは、合理的な意思決定が身体状態と結びついた情動や感情の影響を受けることを示す「ソマティック・マーカー仮説」を提唱。彼は心身二元論を批判し、心、脳、身体の関係を探求する。新訳文庫版で、著者の経歴も紹介されている。
本書は、脳研究の第一人者・池谷裕二氏が、最新の研究成果を基に脳と心の関係について探求する内容です。心や意識の起源、臨死体験、脳の病気、さらには脳の若返りに関する研究など、多様なテーマを扱っています。視覚的に理解しやすい画像や3Dイラストも豊富で、脳の新しい理解を提供します。著者は東京大学の教授で、脳の可塑性を研究しています。
この書籍は、生命の本質について分子生物学がどのように答えているかを探求し、歴史的な科学者たちの思考を紹介しながら、現代の生命観を明らかにします。著者の福岡伸一は、分子生物学の成果を平易に解説し、読者の視点を変える内容を提供しています。多くの著名人から高く評価され、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞しています。
著者である京大総長の山極寿一は、スマホ時代に生きる若者たちの不安を取り上げ、200万年の人類の歴史とゴリラ研究の視点から「未知の時代」における人間らしさや生物としての自覚を考察します。講演会での高校生の声を通じて、自然やテクノロジーとの共生を模索し、未来の社会のあり方を探る内容です。目次には、スマホ依存の不安や言葉の意味、人間らしさの探求などが含まれています。
この本は、スタンフォード大学の脳神経外科医が「引き寄せの法則」とその科学的根拠を解説し、富と幸運を引き寄せるための6つの具体的なステップを提供しています。内容は、集中力の回復、真の願望の明確化、ネガティブな自己イメージの排除、無意識への意図の埋め込み、目的の追求、期待を手放すことに焦点を当てています。著者は、自己実現を促進するための脳の働きとその活用法を紹介し、科学と個人の経験を結びつけています。
本書は、生成AI時代におけるMicrosoft Copilot for Microsoft 365の活用法を100のテクニックとして解説しています。生成AIの普及により、デスクワークは大きく変わるとされ、特にMicrosoftのアプリケーションでの活用が重要です。著者はアクセンチュアのデータ&AIグループで、Teams、Outlook、PowerPoint、Word、Excel、OneNote、Whiteboard、Power Automateなどの主要アプリにおける具体的なテクニックを紹介。生成AIを使いこなすための実用的なガイドとして位置づけられています。
本書は、脳の基本的な仕組みや高次機能の成長方法について解説しています。前半では脳の各部位の機能やメカニズムを平易に説明し、後半では脳のネットワーク化を基にした活用法を紹介しています。著者の加藤俊徳氏は「脳番地」という概念を提唱し、脳の8つの部位の特性を理解することが重要であると述べています。大人でも脳を成長させる方法があり、年齢に関係なく能力を伸ばすことが可能です。
本書は、著者が出会った奇妙な症状を持つ患者たちを通じて、脳の不思議な働きや仕組みについて考察する内容です。切断された手足を感じるスポーツ選手や、自分の体の一部を他人だと主張する患者などの実例を挙げ、脳の機能や意識、自己の本質に迫ります。著者は、左脳と右脳の異なる役割についての仮説や、意識に関する「ハードプロブレム」など、現代の神経科学の最前線をわかりやすく解説しています。名著が文庫化され、脳の世界の魅力を伝えています。
本書は、脳と人工知能(AI)の融合がもたらす未来の可能性について探求しています。著者は、脳に知識をダウンロードしたり、思考を直接伝えたり、AIによる健康管理が可能になるなど、科学者たちが真剣に研究している近未来のシナリオを提示しています。松尾豊氏が絶賛するこの本は、科学技術の進展に対する私たちの考え方や備えについても問いかけており、未来の社会を考える人々にとって必読の一冊です。
本書『火星の人類学者』では、脳神経科医オリヴァー・サックスが、全色盲の画家やトゥレット症候群の外科医、自閉症の動物学者など、さまざまな脳の病を持つ患者たちの独特な人生を描き出しています。彼はこれらの障害を単なる病とせず、彼らのアイデンティティや創造力の源と捉え、人間の存在の可能性を探求する感動的な医学エッセイです。著者は多くの医学エッセイを執筆し、全米でベストセラーとなっています。
この入門書は、文系学生向けに心理学における統計の重要性と基本的手法を分かりやすく解説しています。内容は、統計の基礎から始まり、実践的な手法を学び、さらに深い理解へと進む3つのステップで構成されています。著者たちは心理学や神経科学の専門家であり、学生の視点を考慮した親切な学習ガイドです。
藤子不二雄Aの漫画『笑ゥせぇるすまん』の主人公、喪黒福造が人々を巧妙に陥れる様子を描きつつ、彼の“騙しと誘惑の手口”を脳科学の視点から考察する内容です。人間の心のスキマを解明し、騙されやすいメカニズムや心理的テクニックを分析しています。巻末には藤子不二雄Aとの対談も収録されています。著者は脳科学者の中野信子です。
この書籍は、860億個のニューロンが脳内でどのように繋がり、コミュニケーションを行っているかを探求しています。ニューロンの繋がりは、ケガや病気、成長過程の異常によって変化し、これが自閉スペクトラム症やうつ病、統合失調症などの精神疾患に繋がる可能性があります。著者は神経科学の専門家であり、脳の混乱が思考や感情、行動に与える影響を研究し、治療法の可能性を模索しています。内容は脳障害や精神疾患に関する章で構成されており、脳と心の関係を明らかにすることを目指しています。
この文章は、重力の不思議な性質とその宇宙における重要性について述べています。重力は生命や星の形成に不可欠で、その研究はニュートンやアインシュタインの理論を経て現在の第三の黄金期を迎えています。内容は、特殊相対論や一般相対論、ブラックホール、量子力学、超弦理論など多岐にわたり、重力の謎を解明する冒険が描かれています。著者は大栗博司で、素粒子論や超弦理論の専門家です。
この本は、心理学の全体像を俯瞰できる入門書で、各分野を豊富なカラーイラストと写真を用いて解説しています。基礎から学べるステップアップ形式で構成されており、初学者に最適です。目次には心理学の歴史や学習、知覚、認知、社会、人格、臨床、発達、神経心理学などが含まれています。著者は心理学と工学的アプローチを融合させた研究を行う専門家です。
この書籍は、脳の構造と機能、神経系のメカニズム、高次機能、病気の原因と治療法を詳細に解説しています。精密なイラストと豊富な情報が特徴です。著者は、解剖学と生理学の専門家であり、各々の研究背景を持っています。
神経科学の基礎知識 科学者は自説をどのくらい信じているのか 双子は離れて育っても性格が似る 複雑な脳は単純な規則で組み上げられる 脳を育てるのは脳自身 子どもの脳と大人の脳の違いは 日々生まれ変わる10代の脳 生涯続く脳地図の陣取り合戦 道具で伸び縮みする身体 薬物依存は治らないのか 脳は変化に目を向ける 脳vsコンピューター 神経伝達物質はいくつあるのか 眼は見るべきものを見る 視覚は超能力 味覚にはふたつの役割がある 触覚は多くの情報の組み合わせ 痛みはどこで生じるか 脳は時間を正しく歪める 見えてきた脳内信号の全体像 実験動物は選択と比較が大切 「反射」が脳に運動を教える リハビリゲームで脳卒中から完全回復を 意識的行動も大部分は習慣 声を聞き分ける脳 動物も「心の理論」を持つか 助け合いは動物の本能 恋愛は生存本能から進化した 性的指向は生物学的に決まる 脳は仮説を立てる科学者 セクシュアルな広告が有効なわけ 美人はなぜ美しいのか 本能を学習させる脳の罠 脳は過大評価されている ドーパミン意思決定に近づくAI コンピューターは脳になれない 「心」を持つマシンは必ず作れる
この書籍は、YouTubeの人気動画「科学的根拠に基づく最高の勉強法」を基に、効率的な勉強法を科学的に解説しています。著者は医者としての経験を通じて、従来の学習法(再読、ノート写し、ハイライトなど)が効果的でないことを指摘し、アウトプットの重要性を強調しています。具体的な勉強法として、アクティブリコールや分散学習、記憶術などを紹介し、心身や環境を整える方法についても触れています。著者は、誰でも実践できる効果的な学習法を提供することを目指しています。
この書籍は、最新の脳科学に基づいた「頭のいい子」の育て方を提案する育児書です。著者は、育児における重要な6つの視点を示し、偏食や外遊び、読み聞かせ、デジタルメディアの利用についての具体的なアドバイスを提供します。特に、睡眠、食事、運動、遊び、読書、メディアのサイクルを通じて、子どもの脳の発達を促す方法を解説しています。育児と仕事を両立したい親に向けた実践的な内容が特徴です。
本書は、意識の謎に迫る研究者たちの最新のレポートをまとめたもので、脳の物質的な反応から意識がどのように生まれるのかを探求しています。クオリアやニューロンの知見を基に、実験成果を通じて人間の意識の理解を深め、人工意識の可能性についても考察します。著者は脳科学の専門家であり、意識研究の最前線を描き出しています。
8年ぶりの改訂版で、約30%の内容が更新された「脳科学」に関する教科書です。全9パート、64章からなり、新たに「ブレイン・マシン・インターフェース」など3章が追加されました。神経系のメカニズムや疾患について詳述し、情報工学に関する項目も強化されています。最新の研究データを各章で紹介し、読みやすい日本語訳と907点のフルカラー図版が特徴です。初学者から専門家、AIエンジニアまで幅広い読者に向けた内容で、手頃な価格で提供されています。
本書は脳の科学に関する基礎知識や最新の研究成果を紹介しています。脳の構造や機能、記憶のメカニズム、うつ病やアルツハイマー病などの心の病、発達障害の特性について詳しく解説しています。また、天才の脳の特性や創造性、記憶力の驚異的な能力についても触れています。脳研究の最前線や最新技術を活用したアプローチも紹介され、脳の理解を深めるための内容が盛り込まれています。
脳科学者のジル・ボルト・テイラーは、37歳で脳卒中に襲われ、脳の機能が著しく損傷しました。8年間のリハビリを経て復活し、脳に関する新たな発見や気づきを得た彼女の経験を描いた感動的なメモワールです。著者はハーバード大学で脳神経科学を研究し、精神疾患の啓発活動にも取り組んでいます。
この書籍は、ストーリーを通じて心理テクニックを学ぶことができる内容です。目次には、日常生活や友人、対人関係、仕事、ビジネス、恋愛、自分を変える方法など、様々な心理学の応用が紹介されています。著者は精神科医のゆうきゆうで、心理学に関する多くの活動を行っています。
あなたが正しいと思うことが間違っている理由30。自分で自分が怖くなる!自分を知って謙虚になれる、最新の「認知バイアス」練習問 あなたが正しいと思うことが間違っている理由30。自分で自分が怖くなる!自分を知って謙虚になれる、最新の「認知バイアス」練習問題。 本書は、いわゆる認知バイアスと呼ばれる脳のクセを、ドリル風に解説したものです。 私が本を書くときに気をつけていることは、一般の方が読んでも、脳科学や心理学の専門家が読んでも、納得できるレベルに近づけることにあります。今回も気軽な体裁をとってはいますが、細部にまで徹底的な試行錯誤を重ね、最終形に落ち着くまでに実に5年以上を要しました。 さらに、単なる解説本にしたくないという想いから、イラストや装丁を広く一般募集しました。予想を超える多数の応募をいただき、その中から私の構想にピッタリな提案をくださった服部公太郎さんにお願いしました。結果、紙媒体の本として、飾って楽しい、資料としても役立つ、前例のない「絵本」に仕上がったと自負しています。 認知バイアスにはたくさんの項目があります。本書では古典例から最新例まで慎重に30個選定しました。残念ながら取り上げられなかったものについては、代表的な183項目を巻末にリストしています。すべて科学的に実証されたものです。 胸に手を当てながら、素直にこのリストを眺めると、図星を指される項目も多く、自戒に胸が疼きます。でも、落ち込む必要も、恥ずかしがる必要もありません。なぜなら、それらはすべて脳の仕様ですから。人はみな偏屈です。脳のクセを知れば知るほど、自分に対しても他人に対しても優しくなれます。それがこの本の狙いです。(「おわりに」より)
この入門書は、日常生活で「怒り」に悩む人々に向けて、怒りの感情を理解し、上手にコントロールする方法「アンガーマネジメント」をわかりやすく解説しています。著者の安藤俊介は、日本にこの技術を普及させた第一人者で、実践的な手法を通じて読者が自分の感情をプラスに活かす手助けをします。目次では、怒りの仕組みや感情の抑え方、記録による「見える化」などが紹介されています。
コミュニケーション最強の武器となる笑顔は、“楽しい”を表すのではなく、笑顔を作ると楽しくなるという逆因果。脳は身体行動に感情を後づけしているのだ。姿勢を正せば自信が持てるのもその一例。背筋を伸ばして書いた内容のほうが、背中を丸めて書いたものよりも確信度が高いという─。とても人間的な脳の本性の「クセ」を理解し、快適に生きるため、気鋭の脳研究者が解説する最新知見!
この書籍は、神経科学者フリストンが提唱した「能動的推論」と「自由エネルギー原理」に基づき、脳の知覚、認知、運動、思考、意識などの機能を統一的に説明する理論を解説した初の入門書です。内容は、脳の推論機能や注意、運動制御、意思決定、感情、好奇心、精神障害との関連、認知発達など多岐にわたります。著者は認知神経科学と計算論的神経科学の専門家です。
この書籍は、私たちの行動が「自分の意識」によって制御されているのではなく、脳が自動的に動いていることを解明しています。著者のデイヴィッド・イーグルマンは、意識が脳の活動を傍観しているだけであり、行動の責任について考える必要があると指摘しています。内容は、脳と心の関係や行動のメカニズムについての最新の脳科学を紹介しており、意識の働きについての理解を深めることを目的としています。
本書は「自分史上最高の脳」になるための最新メソッドをまとめたもので、科学的に証明された脳に良い習慣を網羅しています。内容は、運動、食事、睡眠、腸内細菌、社会性、性欲、学習、幸福など多岐にわたり、環境や生活習慣が知力に与える影響を強調しています。著者は脳の健康に関する専門家で、習慣を変えることで脳も変わると述べています。
この書籍は、ワーキングメモリが成功や幸福に与える影響について解説しており、IQに関係なく実績が異なる理由を探ります。ワーキングメモリを強化することで、仕事の効率や記憶力、スポーツのパフォーマンスが向上し、ダイエットやメンタルヘルスの改善にもつながると述べています。著者は、ワーキングメモリの発達と衰え、トレーニング方法、食生活、習慣について具体的な提案を行っています。著者はワーキングメモリ研究の専門家であり、教育分野での応用も重視しています。
この書籍は、神経科学者デイヴィッド・イーグルマンが、視覚や聴覚、身体の一部を失った際に脳内で何が起こるのかを探求し、脳の可塑性を活かして新たな感覚を創出する可能性について論じています。著者は脳を常に自己改造する装置と捉え、科学技術を用いて感覚の代行や新しい感覚の発展について考察します。
この書籍は、人間の行動を進化論の観点から解明する入門書であり、自然淘汰、性による繁殖、性淘汰、心の適応反応、心の病、脳の進化、知能の進化などのテーマを扱っています。著者は進化心理学や科学史の専門家であり、進化論に基づく人間の行動理解を深める内容となっています。
この書籍は、第37回講談社科学出版賞を受賞した作品で、脳の機能に関する新たな視点を提供しています。従来の常識ではニューロンが脳の働きを担っているとされていましたが、著者は「すきま」と呼ばれる脳内の細胞外スペースに注目し、そこに流れる脳脊髄液やグリア細胞が心や知性の源である可能性を示唆しています。内容は、脳の掃除機能や認知症との関係、情報伝達の新しいメカニズム、知性の進化など多岐にわたります。著者は脳科学の新しいアプローチを提唱し、脳を健康に保つ方法についても考察しています。
この本は、三日坊主になりがちな人々に向けて、脳の特性を活かしてやる気を引き出す方法を解説しています。特に「淡蒼球」という脳の部分を活性化させるための4つのスイッチ(身体を動かす、いつもと違うことをする、ごほうびを与える、なりきる)を紹介し、続ける技術ややる気の秘密を探ります。著者はイラストレーターの上大岡トメと脳研究者の池谷裕二です。
ホラー映画を見るとき、私たちの脳・心・身体で何が起こっているのか? モンスター、暴力、トラウマ、音……さまざまな切り口から、脳科学や心理学で〈恐怖〉のしくみを解き明かす もっと眠れなくなること必至の、ホラー映画×科学の世界! 私たちはなぜ、ホラー映画という〝悪夢の燃料〟を求めるのか? 私たちの脳や身体はホラー映画の何に恐怖を感じ、どのように反応するのか? 本書では、科学コミュニケーターとして活動する著者が多彩なホラー映画を例に、人が恐怖を感じ、脅威に対処するメカニズムを紹介。脳科学・心理学・神経科学・生物学の知見から、〈恐怖〉のさまざまな側面を明らかにする。 登場する映画は、『サイコ』『エクソシスト』など古典的名作から、『ヘレディタリー/継承』『アス』『クワイエット・プレイス』など現代のヒット作まで約300本。サイコ、SF、スラッシャー、スプラッター、クリーチャー、オカルトなどのサブジャンルを縦横無尽に扱いながら、ホラー映画の歴史もおさらい。いかに映画における〈恐怖〉が作り出されてきたのか、そして私たち観客はいかにそれを受け取るのかに迫る。 各章には、ひとつの作品を掘り下げるコラムと、映画の製作者や研究者へのインタビューも収録。尽きることのないホラーの魅力を存分に楽しめること間違いなし。 [本書に登場する映画] 『スクリーム』『サイコ』『ハロウィン』『エルム街の悪夢』『13日の金曜日』『ジョーズ』『エクソシスト』『サスペリア』『暗闇にベルが鳴る』『羊たちの沈黙』『悪魔のいけにえ』『エイリアン』『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』『ヘレディタリー/継承』『シャイニング』『アス』『ソウ』『リング』『仄暗い水の底から』『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』『チャイルド・プレイ』『ムカデ人間』……など300作品以上! [本書に登場する用語やトピック] 脅威/闘争・逃走反応/PTSD/ジャンプスケア/嫌悪感/ミラーニューロン/捕食・被食関係/不気味の谷/仮面/クモ恐怖/不協和音/周波数/叫び/恐怖記憶/認知発達理論/侵入思考/スポイラー/ホラー映画と犯罪の関係/脱感作/馴化/レーティング/妊娠ホラー/拷問/マンデラ効果/血や眼球にまつわる恐怖/ホラー好きは遺伝するか/刺激追求度/カタルシス説……ほか 最高のホラー映画とは、階段を歩いたり明かりを消したりするのが不安になるような映画だ。指のあいだから覗くようにスクリーンを見て、その晩は眠れなくなるような映画だ。 はじめに 第1章 恐怖を感じると、脳はこうなる 第2章 ホラー映画の歴史 第3章 モンスターの作り方 第4章 耳からの恐怖 第5章 恐怖が付きまとう理由 第6章 暴力的メディアと暴力行為 第7章 血、ゴア、ボディホラー 第8章 ホラーの変わらぬ魅力 あとがき 謝辞 訳者あとがき 参考文献 索引 プロフィール
内面のドラマともいうべき、無意識的な心の変遷過程をたどる。ユング思想の全体を浮かびあがらせる絶好の入門書。 集合的無意識の概念を紹介し、個性化過程の考えを打ちだし、ユング心理学の基礎を築き上げた初期代表作。内面のドラマともいうべき、無意識的な心の変遷過程を個々の例を挙げながら分りやすく説くという点で、ユング思想の全体像を浮かびあがらせる入門書。 第一部 意識におよぼす無意識の諸作用 第一章 個人的無意識と集合的無意識 第二章 無意識の同化作用のおこす後続現象 第三章 集合的心の一部としてのペルソナ 第四章 集合的心からの個性解放の試み A ペルソナの退行的復元 B 集合的心との同一化 第二部 個性化 第一章 無意識の機能 第二章 アニマとアニムス 第三章 自我と無意識の諸形象とを区別する技術 第四章 マナ=人格 訳者解説 無意識とユング
本書は、脳内の細胞の約80%を占める「グリア細胞」の重要性を探るもので、従来はニューロンの単なるサポートと見なされていたが、最近の研究によってニューロンの活動を感知し制御できることが明らかになった。著者は、従来の「ニューロン中心主義」に疑問を呈し、グリア細胞の役割が脳科学における理解を大きく変える可能性を示唆している。内容は、グリアの基本的な役割から健康や病気における影響、思考や記憶における機能まで多岐にわたる。
◆第1巻の特徴◆ 鮮度の高い事例や普遍的なハウツーを盛り込みながら,どの研究法にも共通する基盤的知識を解説。研究倫理も手厚く扱う。実証に基づく科学としての心理学が「なるほど!」と理解できて,もっと研究したくなる入門書。 第1部では,心理学研究に着手する技能や技術を身につけるにあたって,最低限知っておきたい知識を解説。第2部では,心理学研究に必要な技能や技術についてのハウツーを述べる。効果量や検定力分析,ベイズ統計学の基本的考え方などについても鮮度高く解説。 第3部では,研究を「公表する」にあたって研究者が心がけるべき倫理について手厚く解説。仮説の後づけ(HARKing), p値ハッキング(p-hacking)など問題のある研究実践(QRPs)への警鐘をならし,モラル違反を抑止する策について述べる。 ◆第1巻 主なもくじ◆ 序章 心理学とは何か ―第1部 心理学を「研究する」ということ― 第1章 心理学のなりたち:心理学史 第2章 研究の準備:心理学研究の基礎知識 第3章 研究の準備:先行研究の探し方 ―第2部 心を「測定する」ということ― 第4章 研究の基礎:研究法概説 第5章 研究の基礎:人間を対象とする測定における諸問題 第6章 データの中身を知る:記述統計 第7章 データから対象を見通す:推測統計 ―第3部 研究を「公表する」ということ― 第8章 研究倫理:研究者として「なすべきこと」 第9章 研究倫理:研究者として「やってはいけないこと」 第10章 研究倫理:モラル違反を抑止するシステム 第11章 研究成果の公表:心理学論文の書き方 終章 よりよい心理学研究のために ◆◆◆『心理学ベーシック』全5巻-シリーズ監修 三浦 麻子-◆◆◆ 心のはたらきを科学的に見つめるまなざしを養い,「自らの手で研究すること」に力点をおいたシリーズ 第1巻 なるほど! 心理学研究法 三浦麻子 著 第2巻 なるほど! 心理学実験法 佐藤暢哉・小川洋和 著 第3巻 なるほど! 心理学調査法 大竹恵子 編著 第4巻 なるほど! 心理学観察法 佐藤 寛 編著 第5巻 なるほど! 心理学面接法 米山直樹・佐藤 寛 編著 ◆「心理学ベーシック」シリーズ刊行にあたって(一部抜粋)◆ 「心理学を学ぶこと」をめぐる状況は,2015年に国家資格「公認心理師」の制度化が決まったことによって大きな岐路に立った。-略- しかしわれわれは,心理職としての現場での実践を有為なものとするためには,何よりもまず,心理学諸領域の基礎的な知見や理論を学び,それらをふまえて自らテーマを設定して研究を計画し,収集したデータを分析・考察するという一連の科学的実証手続きを遂行するためのスキルとテクニックを習得することが必要だという強い確信をもっている。 「心理学ベーシック」シリーズ刊行にあたって はしがき 序章 心理学とは何か 1節 心理学の定義 2節 心理学を研究することの難しさ 3節 心理学を研究することの面白さ ―第1部 心理学を「研究する」ということ― 第1章 心理学のなりたち:心理学史 1節 心理学と哲学 2節 心理学と医学 3節 心理学と生物学 4節 近代心理学の創始とその発展 5節 第二次大戦後の心理学 6節 日本の心理学 第2章 研究の準備:心理学研究の基礎知識 1節 概念的定義と操作的定義 2節 信頼性と妥当性 3節 相関と因果 4節 さまざまな変数 第3章 研究の準備:先行研究の探し方 1節 リサーチ・クエスチョン 2節 巨人の肩の上に立つということ 3節 先行研究レビューの意義 4節 先行研究の収集法:概論 5節 心理学の研究論文に触れる 6節 心理学の研究テーマを知る 7節 さあ,歩きはじめよう ―第2部 心を「測定する」ということ― 第4章 研究の基礎:研究法概説 1節 実験法 2節 調査法 3節 観察法 4節 面接法 第5章 研究の基礎:人間を対象とする測定における諸問題 1節 参加者効果 2節 実験者効果 3節 努力の最小限化 4節 生態学的妥当性との両立 第6章 データの中身を知る:記述統計 1節 数値データの利点 2節 尺度 3節 記述統計 第7章 データから対象を見通す:推測統計 1節 推測統計とは 2節 標本抽出に伴う結果の変動 3節 統計的仮説検定 4節 統計的仮説検定における2種類の誤り 5節 効果量と検定力分析 6節 ベイズ統計学の基本的考え方 ―第3部 研究を「公表する」ということ― 第8章 研究倫理:研究者として「なすべきこと」 1節 エシックスの基本的な考え方 2節 最小限のコストやリスク 3節 説明責任 4節 個人情報・データの保護 5節 成文化されたエシックス 6節 倫理審査 第9章 研究倫理:研究者として「やってはいけないこと」 1節 モラルとしての研究倫理 2節 研究者が陥るかもしれない「地獄」 3節 仮説の後づけ(HARKing) 4節 p値ハッキング(p-hacking) 5節 蔓延するQRPs 第10章 研究倫理:モラル違反を抑止するシステム 1節 研究結果の再現可能性 2節 心理学界で起こった問題 3節 システムの整備 4節 心理学研究の「パラダイムシフト」 第11章 研究成果の公表:心理学論文の書き方 1節 論文のアウトライン 2節 論文の文章表現 3節 図表 4節 全体的なチェック [付録] 心理科学実験実習 レポート作成 チェックリスト 終章 よりよい心理学研究のために 1節 「研究」するということ 2節 よい研究とは何か 3節 心理学研究への船出 引用文献/索 引
この書籍は、脳に知能が生じる理由を探求し、大脳新皮質の「皮質コラム」に着目した「1000の脳」理論を解説しています。著者ジェフ・ホーキンスは、脳と人工知能の理解に革命をもたらす新しい視点を提供し、ビジネスや研究における知的挑戦を描いています。内容は脳の新しい理解、機械の知能、人間の知能に関する考察を含みます。ホーキンスは神経科学者であり、AI研究の先駆者として知られています。
この書籍は、脳と記憶に関する対談を通じて、記憶を司る「海馬」の重要性や脳の発展について探求しています。著者の池谷裕二は、脳が老化によって衰えるのではなく、30歳を過ぎてからも成長する可能性を示唆しています。糸井重里との対話を交え、脳科学の知識を深めつつ、読者に生きる力を与える内容となっています。各章では、脳の機能や記憶に影響を与える薬、天才を育む環境についても触れています。
本書は、脳を理解し使いこなすことで、自己成長や幸せを得る方法を紹介しています。最新の脳科学に基づき、従来の誤解(例:右脳・左脳の概念)を払拭し、脳の構造や機能を理解することでポジティブな思考や生活習慣の改善を促します。著者の増田勝利は、脳科学や心理学を応用し、成功に導くメソッドや幸せを呼び寄せる方法を提供。また、ビジネス効率を高めるための戦術も解説しています。全体を通じて、脳との正しい付き合い方を学ぶことができる一冊です。
この書籍は、楽観主義と悲観主義の脳の活動パターンの違いを探求し、人格形成のメカニズムを心理学、分子遺伝学、神経科学の視点から解明します。著名な楽観主義者たちを例に、彼らが逆境を克服する際の思考方法を考察しています。著者は心理学者・神経科学者のエレーヌ・フォックスで、オックスフォード大学で感情神経科学センターを率いています。
この文章は、音楽心理学に関する内容を紹介しており、音楽の知覚、認知、記憶、感情、社会心理学、音楽療法など、さまざまな側面を扱っています。また、著者の星野悦子は音楽と心理学の専門家で、現在上野学園大学で教授を務めています。
自分の言葉で心理学を思考し、心を観察し、今そこにある問題を考える。簡潔な文章と多彩なイラストでヒトの心の不可解に迫る入門書 簡潔な文章と多彩なイラストで一読である程度理解できる「簡潔性」、知識の詰め込みではなく考える材料になる「思考促進性」、現代人が抱える悩みや課題にこたえる「現在性」に留意したたいへん読みやすい一冊。入門書に最適。 読むだけである程度理解できる「簡潔性」、知識の詰め込みではなく考える材料になる「思考促進性」、現代人が抱える悩みや課題にこたえる「現在性」に留意したたいへん読みやすい一冊。教科書としてだけではなく一般書としても読み応え十分。一読すれば、いまそこにある心の問題が見えてくる。 はじめに 心理学を学ぶ喜びと意義 1章 荒川歩 心理学とは:心理学に何を期待するのか? コラム1 フェヒナーの精神物理学と感覚の尺度化 2章 三星宗雄・荒川歩 知覚:人の目はカメラとどう違うのか? コラム2 騒色公害の系譜とその解決 3章 三星宗雄・荒川歩 知覚の障害:私たちに見える世界は共通か? コラム3 ユニバーサルデザインとカラーユニバーサルデザイン 4章 浅井千絵 記憶と学習:人はどのように学ぶのか? コラム4 感情と色彩 5章 浅井千絵 認知:人はどのように世界を理解するのか? コラム5 絵画・デザイン制作の認知科学 6章 荒川歩 感情:感情は何のためにあるのか? コラム6 無意識 7章 荒川歩 自己:私はどこにあるのか? コラム7 アイデンティティ拡散と回復 8章 荒川歩・河野直子 発達:それぞれの年代において人はどんな課題とむきあうか? コラム8 子どもの絵の発達 コラム9 氏か育ちか、氏も育ちも 9章 遠藤架児 発達の障害:障害なのか? 個性なのか? コラム10 サヴァン症候群 10章 桂 瑠以 性格と社会的認知:何が人の性格や態度を決めるのか? コラム11 心理(性格)検査って何? 11章 桂 瑠以 人間関係 : 人と人とは、どう関わるか? コラム12 コミュニケーションメディアの使い分け 12章 桂 瑠以 社会的影響と集団:集団はどのような影響を及ぼすか? コラム13 商品開発と心理学 コラム14 広告と心理学 13章 河野直子・荒川歩 心と脳:心はどのような脳内メカニズムに支えられているか? コラム15 心とからだ コラム16 アフォーダンス 14章 河野直子・尾崎紀夫 病理:精神疾患とどう付き合っていくか? コラム17 病跡学:作品や人物を精神病理で理解する コラム18 芸術療法:アートと心理学のもう1つの関係 引用文献 索引
本書は、神経科学の進歩により脳の記憶のメカニズムが明らかになり、記憶力を高める方法を科学的に探求する内容です。著者は「夢の薬」を研究し、LTPやシナプス可塑性などの最新理論を解説しながら、具体的な記憶力向上法を紹介しています。著者は記憶を未来の自分へのメッセージと捉え、巧妙な記憶の仕組みを読者に伝えています。目次には脳の構造や記憶の可塑性、記憶力を鍛える方法、未来の脳科学についての章が含まれています。
「経済からのアプローチ」、「知覚からのアプローチ」「感情・直観からのアプローチ」といった章を新たに立て、構成を大幅に刷新。 「経済からのアプローチ」、「知覚からのアプローチ」「感情・直観からのアプローチ」といった章を新たに立て、構成を大幅に刷新。心理学の知識がなくても読みやすく、幅広い読者におすすめできる1冊。教科書にも最適。 意思決定研究の基礎はこれで学べる! 行動経済学を生み、医療や科学技術のリスコミにも欠かせないリスクと意思決定の基礎知識が満載! 好評入門書の第3版! ▼学界で好評を得た「行動的意思決定」の入門書を10年ぶりに改版! 「意思決定とリスク」に関わる概念・理論についての心理学的知見の蓄積と最新の動向をいち早く紹介した入門書の第3版。行動経済学やリスクコミュニケーションが注目される今、「経済からのアプローチ」をはじめ、「知覚からのアプローチ」「感情・直観からのアプローチ」といった章を新たに立て、構成を大幅に刷新。心理学の知識がなくても読みやすく、幅広い読者におすすめできる1冊。教科書にも最適。 はじめに 改訂版によせて 第3版刊行にあたって 第Ⅰ章 意思決定、不確実性と心理学 Ⅰ―1 意思決定とは Ⅰ―2 ギャンブルと不確実性 Ⅰ―3 事故・災害、環境問題のリスク Ⅰ―4 医療意思決定、その他領域での展開 Ⅰ―5 集団での行動、意思決定と生産性 Ⅰ―6 リスクと不確実性、曖昧性 Ⅰ―7 曖昧さは嫌われる? 第Ⅱ章 認知からのアプローチ Ⅱ―1 不確実性下での意思決定と期待効用 Ⅱ―2 経済学における意思決定(1)効用逓減と期待効用理論 Ⅱ―3 経済学における意思決定(2)期待効用理論の侵犯 Ⅱ―4 代表性ヒューリスティック(1) Ⅱ―5 代表性ヒューリスティック(2)基準比率の無視 Ⅱ―6 利用可能性ヒューリスティック Ⅱ―7 係留と調整ヒューリスティック Ⅱ―8 感情ヒューリスティック、適応的ヒューリスティック Ⅱ―9 枠組み効果 Ⅱ―10 プロスペクト理論 Ⅱ―11 意思決定の二重過程モデル Ⅱ―12 ヒューリスティックス&バイアス研究への批判 Ⅱ―13 その他の認知的意思決定理論 第Ⅲ章 知覚からのアプローチ Ⅲ―1 ランダムネスの知覚と生成 Ⅲ―2 共変関係の知覚 Ⅲ―3 錯誤相関 Ⅲ―4 原因帰属理論 Ⅲ―5 制御幻想 Ⅲ―6 抑うつのリアリズム Ⅲ―7 自信過剰 第Ⅳ章 感情・直観からのアプローチ Ⅳ―1 感情が判断や意思決定に与える影響 Ⅳ―2 ストレスと意思決定 Ⅳ―3 決定後の心理:認知的不協和の低減 Ⅳ―4 単純接触効果 Ⅳ―5 選択と理由 Ⅳ―6 後悔 Ⅳ―7 予測と経験 第Ⅴ章 行動からのアプローチ Ⅴ―1 動物の選択行動 Ⅴ―2 迷信行動とギャンブル行動 Ⅴ―3 動物行動研究から見た遅延割引 Ⅴ―4 自己制御(セルフコントロール)と衝動性 Ⅴ―5 ヒトの価値割引研究への展開 Ⅴ―6 選択行動研究とマッチングの法則 Ⅴ―7 行動生態学 第Ⅵ章 社会からのアプローチ Ⅵ―1 集団の影響 Ⅵ―2 集団の問題解決 Ⅵ―3 集団の意思決定と合議(1) Ⅵ―4 集団の意思決定と合議(2) Ⅵ―5 集団の意思決定と合議(3)集合知 Ⅵ―6 リスク心理研究(1) Ⅵ―7 リスク心理研究(2)リスクコミュニケーション Ⅵ―8 科学情報のコミュニケーション Ⅵ―9 リスクリテラシー 第Ⅶ章 経済からのアプローチ Ⅶ―1 行動経済学(1)需要供給分析 Ⅶ―2 行動経済学(2)無差別曲線分析 Ⅶ―3 心の会計とサンクコスト効果 Ⅶ―4 保有効果と現状維持バイアス Ⅶ―5 行動ファイナンス Ⅶ―6 神経経済学 引用文献一覧 索 引 BOX 目次 ( )内は執筆者 1 Blue seven 現象(坂上) 2 選択肢は多いほどよいか?(山田) 3 平均への回帰(増田) 4 様々な合理性の見解(広田) 5 マーフィーの法則を科学する(増田) 6 好物は後で? 上昇選好(井垣) 7 終わり良ければすべてよし? ピーク・エンドの法則(井垣) 8 競合分割効果(広田) 9 時間と意思決定(広田) 10 飛行爆弾は狙って打ち込まれたか?(増田) 11 読みやすい名前は好かれる?(森) 12 最高を求めると不幸になる?(森) 13 誠意のコスト(森) 14 自己制御の技術(坂上) 15 動物も不公平を嫌う?(石井) 16 ただ乗り問題と共有地の悲劇 社会的ジレンマ(広田) 17 1円はどこへ消えた?(広田) 18 「直観」が全てを知っている?! 現実場面での意思決定(三田地) 19 デフォルト(山田) 20 貨幣錯覚(井垣) 21 ソマティックマーカー仮説(石井)
この書籍は、脳科学と身体運動学の観点から音楽の演奏における脳と身体の関係を探求しています。目次には、超絶技巧の実現、音の動きへの変換、音楽家の聴覚、楽譜の理解と記憶、ピアニストの障害と省エネ技術、運動技能、感動的な演奏についての章が含まれています。著者は音楽演奏科学者の古屋晋一で、医学博士の学位を持ち、国内外で講演活動を行っています。
コロナ禍に始めたキャンプで焚き火の魅力にとりつかれた脳科学者が、前代未聞の学内焚き火実験を開始!脳科学で焚き火に迫る。 焚き火をすると人はどうなる? 炎の「 1/f ゆらぎ」と「癒やし」は本当に関係あるの? コロナ禍に始めたキャンプで焚き火の魅力にとりつかれた脳科学者が、 前代未聞の学内焚き… 焚き火の魅力にとりつかれた脳科学者が、焚き火にあたりながら自分の脳波を測定する前代未聞の実験をキャンパス内で実施した。じつはこれまで、焚き火の効果は、実験で直接確かめられていなかった! 本書には、コアな焚き火好きをはじめ、脳科学に興味のある高校生や大学生、脳科学研究に取り組んでいる大学院生や研究者、新規プロジェクトを立ち上げたい方、広く教養を求めている方々に向けて、実験結果だけでなく、脳科学についても幅広く書かれている。 キャンプブームが落ち着いた今、焚き火に思いを馳せながら脳科学をじっくり学ぶための絶好の一冊。 はじめに 第1章 焚き火の魅力 私は脳機能*(スター)学者 焚き火の魅力とは? 癒やしだけでない焚き火の効果 焚き火と写真で悦に入る さらに焚き火と写真で悦に入る 脳をめぐる世間の誤解 焚き火中の脳活動はどうなっているのか? 第2章 焚き火と脳科学のソロ実験 コロナ禍で教育・研究活動に疲れた私 焚き火の脳科学研究プロジェクトに着火 1年をかけて大学を説得①——前編 1年をかけて大学を説得②——中編 1年をかけて大学を説得③——後編 焚き火実験の準備、予備実験と本実験 実験の概要とやり方をわかりやすく説明する 物理、心理、脳波測定の項目とは? 第3章 焚き火の脳科学実験の結果と考察 物理測定の結果を発表! 心理測定の結果を発表! 脳波測定の結果を発表! 世界初! 焚き火と心理・脳波との因果関係を深掘りする 確率推論でわかった焚き火と心理の因果関係 脳波に焚火と心理がどう影響したのか? 焚き火実験の総まとめ 焚き火の効果と1/fゆらぎ 第4章 焚き火と脳のメカニズムを考える ヒトの感覚とは何か? 感覚に関する実験の問題点①——データ取得編 感覚に関する実験の問題点②——データ解析編 感覚に関する実験の問題点③——データ検討編 なぜ焚き火で気分が上がるのか? 刺激を受けないと脳は働かない ヒトの感覚の凄さ、脳の感覚野の巧みさ その味、本当? ヒトの感覚の序列 第5章 脳科学の研究成果は社会で活かせるか そもそも脳科学研究は社会の役に立つのか? 焚き火の炎と脳波は暗号にも応用できる 「オカモトモデル」で見つけた視覚の特性 世界初! 冷暖房の風が脳活動に及ぼす影響を解明 柑橘系の匂いを嗅ぐとオレンジ色が覚えにくくなる 3日間の脳波トレで長期記憶の向上に成功 脳科学の共同研究とキビシイお金の事情 岡本剛研究室、共同研究、絶賛募集中 第6章 脳の大問題を解決する 2045年問題、AIとヒトの脳 宇宙のような脳のナゾを解く ヒトの可能性を追究するフィールド脳科学 脳科学の限界を突破するニューロフィードバック技術 天才脳は作れるか? 死なない脳はできるか? 私の研究はノーベル賞を狙えるのか? おわりに 参考文献
論文の読み方入門書。『心理学論文の書き方』の姉妹篇。論文読破に必要となる概説的な知識や論文の形式・ルールをやさしく解説。 「書く」のためには,まずは「読む」ことから!『心理学論文の書き方』の姉妹篇。論文を読むことは学問という知的な世界を旅することである。論文読破に必要となる概説的な知識や形式・ルールをやさしい筆致でコンパクトにまとめた,論文ビギナー必携の入門書。 プロローグ 論文を読もうとする人に Step1 論文を読む前に 第1章 なぜ論文を読むのか 第2章 論文の作法を知る 第3章 読む前に大切なこと Step2 論文を読む 第4章 論文の構造をつかむ 第5章 いろいろな読み方を試してみる 第6章 読むときに役立つこと 第7章 図表を読む 第8章 統計の結果を読む 第9章 読んだ後にすべきこと 第10章 英語論文を読む 第11章 論文を探すコツ エピローグ 論文の読み方を極める
『雑食動物のジレンマ』『人間は料理する』で知られるジャーナリストが 自ら幻覚剤を体験し、タブーに挑む! 今どんな幻覚剤の研究がおこなわれているのか。 幻覚剤は脳にどんな影響を与えるのか。 そして、医療や人類の精神に、幻覚剤はいかに寄与しうるのか。 「不安障害」「依存症」「うつ病」「末期ガン」などへの医学的利用の可能性と、“変性する意識”の内的過程を探る画期的ノンフィクション。 ニューヨークタイムズ紙「今年の10冊」選出(2018年)、ガーディアン紙、絶賛! 一部の精神科医や心理学者が過去の幻覚剤研究の存在に気づき、発掘を始めたのは最近のことだ。 彼らは現代の基準で再実験をおこなって、その精神疾患治療薬としての可能性に驚愕し、(中略)幻覚剤が脳にどう働くのか調べはじめた。 ——幻覚剤ルネッサンスである。(宮﨑真紀) 第一章 ルネッサンス 第二章 博物学——キノコに酔う 第三章 歴史——幻覚剤研究の第一波 第四章 旅行記——地下に潜ってみる 第五章 神経科学——幻覚剤の影響下にある脳 第六章 トリップ治療——幻覚剤を使ったセラピー
これまでの心理学は、とかく人間の欠けているところ、できない部分に注目してそれを克服することに着目しがちでしたが、これからは人間のポジティブな側面にもっと注目し、人間の本来もつ強さを引き出すことによって個人や社会を支えるような学問を目指すべきだ、とする考え方が生まれています。本書は、スポーツ心理学、健康心理学に、新たに確立してきたポジティブ心理学をあわせて、積極的な人生追求のためのこころのサイエンスの最前線を紹介する入門書です。 目次 ●もくじ はじめに 第1部 スポーツ心理学 中込四郎 1‐1 スポーツ心理学 スポーツと心理学が出会う 1‐2 タレント発掘 早期トレーニングの功と罪 1‐3 青年期とスポーツ スポーツで「自己」を体験する 1‐4 アスリートのパーソナリティ スポーツによってパーソナリティをつくる 1‐5 こころの強化 スポーツメンタルトレーニングの今 1‐6 ピークパフォーマンス 実力発揮につながる心理的世界を知る 1‐7 積極的思考 弱気から強気に変える 1‐8 イメージトレーニング イメージをうまく活用する 1‐9 スポーツ・モニタリング・トレーニング こころと体の動きを知る 1‐10 ソーシャルサポート まわりの人的資源を活用する 1‐11 スランプ いくらやっても上達しない 1‐12 アスリートの燃え尽き 努力する割には報われない 1‐13 心因性動作失調 こころが動きを縛る 1‐14 スポーツセラピー スポーツでこころを癒やす 1‐15 運動の継続 運動の継続を妨げるもの 第2部 健康心理学 石崎一記 2‐1 健 康 心身ともにその人らしくいること 2‐2 健康心理学 健康をこころと体の結びつきの面から科学する 2‐3 健康の査定 健康ってはかれるの? 2‐4 生涯発達 一生変化し続けるもの 2‐5 QOL 人生の質、生活の質 2‐6 生きがい 生きる意味が感じられること 2‐7 ストレス ストレスって本当に悪いもの? 2‐8 ストレス・コーピング ストレスとの上手な付き合い方 2‐9 感 情 人を心底から動かすもの 2‐10 グループと自然の癒やし効果 人や自然と関わることで健康づくり 第3部 ポジティブ心理学 外山美樹 3‐1 ポジティブ心理学とは 人間のもつ「強さ」から考える 3‐2 学習性無力感 説明スタイルの違いから謎を解く 3‐3 楽観主義 自分の将来を楽観的に考える 3‐4 悲観主義ネガティブ思考のポジティブなパワー 3‐5 フロー経験 夢中になる 3‐6 目 標 自分の未来を導く 3‐7 自尊感情 揺れ動く自己 3‐8 認知的複雑性 物事を多面的に見る能力 3‐9 ネガティブ感情とポジティブ感情 感情の凹凸 3‐10 笑 い 人は幸福だから笑うのではない 3‐11 気晴らし 気晴らしにもコツがいる 3‐12 自己開示 こころをオープンにすると健康になる? 3‐13 アサーション 自己表現によってよりよい人間関係を築く 3‐14 ハーディネス ストレスに強い性格とは 3‐15 認知療法 考え方の癖を見ぬく 人名索引 事項索引 文 献
この書籍は、アルツハイマー病研究の現状を批判的に見直し、特にアミロイドに偏った治療アプローチが無駄な時間を費やしてきたことを指摘します。著者は、アカデミズム、製薬業界、政府の関与による研究の迷走を明らかにし、過去数十年の認識を根本から問い直す重要な告発を行っています。内容は、アルツハイマー病の歴史、治療法の探求、研究モデルの問題点、今後の研究戦略の多様化に焦点を当てています。
この書籍は、うつ病や自閉スペクトラム症、ADHD、PTSD、統合失調症、双極性障害などの精神疾患のメカニズムと治療法について、最新の研究成果を基に解説しています。精神疾患は脳の変化から生じることが多く、遺伝や環境要因が影響を与えます。各章では、シナプスやゲノム、脳回路、慢性ストレス、動く遺伝因子、治療法などが詳しく探求され、精神疾患を「治る病」にするための道筋が示されています。著者たちは、脳科学や新たな治療アプローチを通じて、精神疾患の理解を深め、支援方法を模索しています。
「認識」について,実験の醍醐味に触れながら,基礎的な内容から新しい知見までをカバーした,コンパクトで読みやすい入門書。 人間は世界をどのように認識しているのか。当たり前になしえている「認識」の背後にからみ合う複雑な営みを,1つ1つ解き明かしていく実証的・科学的手法の醍醐味を堪能してほしい。初版刊行後の新しい知見も盛り込んだ,コンパクトで読みやすい入門書。 第1章 認知心理学の誕生と変貌――情報工学から機能的生物学へ=道又 爾 第2章 知覚の基礎――環境とのファーストコンタクト=北〓崎充晃 第3章 高次の知覚――見ることから理解することへ=道又 爾 第4章 注 意――情報の選択と資源の集中=大久保街亜・道又 爾 第5章 表 象――こころの中身,その形式=大久保街亜 第6章 記 憶――過去・現在・未来の自己をつなぐ=今井久登 第7章 言 語――成長する心の辞書システム=山川恵子 第8章 問題解決と推論――普遍性と領域固有性の間で=黒沢 学
本書は、日本の未来に対する警告を発し、1990年代末に書かれたもので、2050年を見据えた内容です。著者は、日本の精神性や金融、産業、教育の構造的問題を指摘し、没落の危機を予見しています。唯一の解決策として「東北アジア共同体」構想を提案し、その実現に向けた障害についても論じています。著者は森嶋通夫で、経済学の専門家として多くの業績を残しました。
河合隼雄の処女作であるこの書籍は、日本初のユング心理学の入門書で、著者の心理学の出発点を示す重要なテーマが含まれています。文庫化に際し、ユング心理学を学ぶ経緯を記した序説と読書案内も収録されています。目次には、タイプ、コンプレックス、無意識、夢分析などが含まれています。河合隼雄は京都大学で教授を務め、ユング派分析家としても活躍しました。
この書籍は、最新の実証研究に基づき、効率的な学習法について解説しています。一般的に信じられている学習方法が実は非効率であることを示し、記憶と学習の科学的知見を提供します。特に、テストの重要性、練習の組み合わせ、学習の難しさの受け入れ、能力の伸ばし方、学びの定着方法などについて詳述しています。ビジネスパーソンや教育者、学生に向けたアドバイスも含まれており、実践的な学びを促進する内容です。著者は心理学者で、学習と記憶の専門家たちです。
この書籍は、発達・教育・学習に関する教育心理学の基礎を分かりやすく解説し、カウンセリングや特別支援教育に関連する具体例を紹介しています。第4版では最新の情報とデータが盛り込まれた入門書です。目次は教育心理学の総論と心理教育的援助に関する内容で構成されています。著者は法政大学の教授や非常勤講師、臨床心理士などの専門家です。
この書籍は、精神疾患の治療を超え「幸せ」を追求するポジティブ心理学について解説しています。著者は、ポジティブ心理学が人生の価値観を問い、哲学的知見を融合した学問であると述べ、様々な実験を通じて幸福を促進する方法を学術的に検証しています。内容は、幸福の科学的解明、美徳や人格的強みの再発見、個人から社会へのポジティブ心理学の発展に分かれ、具体的な事例を交えつつ、ポジティブな心の状態を育む方法を提案しています。著者は政治学者であり、ポジティブ心理学の可能性を豊富な事例をもとに解説しています。
この書籍は「引き寄せの法則」が科学的に実在することを探求し、脳科学、エピジェネティクス、量子物理学などの研究を通じて、思考が物質に与える影響を実証しています。各章では、脳の働き、エネルギーの物質化、感情の環境への影響、DNAの制御、思考の共鳴、シンクロニシティのメカニズム、そして思考を超える意識について解説し、実践的なエクササイズも提供しています。著者はエネルギー心理学を研究する専門家たちです。
思い通りに体を動かす、アートを作り出す、人の気持ちがわかるなど、AI時代の「真の頭の良さ」を考える。カギは「脳の持久力」! カギは「脳の持久力」にあった! 思い通りに体を動かす、アートを作り出す、感じる、人の気持ちがわかるなど、AI時代に求められる「真の頭の良さ」を考える。 カギは「脳の持久力」にあった! 思い通りに体を動かす、アートを作り出す、感じる、人の気持ちがわかるなど、AI時代に求められる「真の頭の良さ」を考える。 藤井聡太と大谷翔平には、ある重要な共通点があった それは、「脳の持久力」! 能力を発揮し続けられる人と続けられない人の違いを脳科学が解明する === 「頭がいい」とは、IQや記憶力だけでなく、感覚や運動能力、アートと創造性、他者の気持ちがわかる能力なども含まれる。どんな仕組みで良くなるのかを脳科学の観点から解説する。このような能力を発揮し続けるための力を「脳の持久力」と名付け、そこに深く関係する脳細胞、アストロサイトの働きを紹介し、人間の脳とAIの比較、今求められる知性について著者の考えをまとめる。 【目次より】 ・IQは本当に頭の良さの指標なのか ・脳はできるだけ「省エネ」であろうとしている ・若い時の知力と、歳を取ってからの知力 ・忘却は、記憶と同じく重要なもの ・「身体を動かす」脳のしくみ ・アートの原動力はかわいいと思うこと? ・わかり合うには、どうしたらいいのか ・アストロサイトは、頭の良さに関係する ・AIと脳は、どう違うのか 第1章 「頭がいい」ってどういうこと? 第2章 注意しなければ知覚できない 第3章 脳の働きがいいとは、どういうことか 第4章 記憶という不思議な仕組み 第5章 思い通りに体を動かす 第6章 感受性と創造性 第7章 人の気持ちがわかる 第8章 脳の持久力を担うアストロサイト 最終章 AI時代に求められる真の”頭の良さ”
「脳の仕組み」に関するよくある質問
Q. 「脳の仕組み」の本を選ぶポイントは?
A. 「脳の仕組み」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「脳の仕組み」本は?
A. 当サイトのランキングでは『メカ屋のための脳科学入門-脳をリバースエンジニアリングする-』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで146冊の中から厳選しています。
Q. 「脳の仕組み」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「脳の仕組み」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。