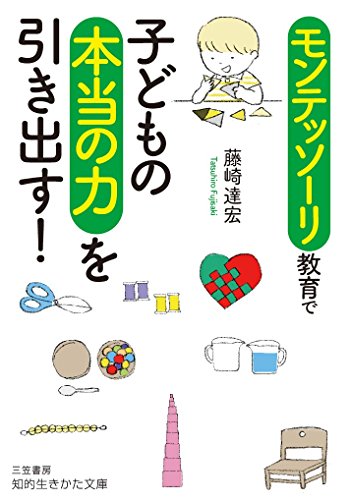【2025年】「子供の発達」のおすすめ 本 142選!人気ランキング
- 発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ (健康ライブラリースペシャル)
- 0歳~6歳 子どもの発達と保育の本 第2版 (Gakken保育Books)
- 子どもに伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ!
- はじめてママ&パパの育児―0~3才赤ちゃんとの暮らし 気がかりがスッキリ! (実用No.1シリーズ)
- 完全カラー図解 よくわかる発達心理学
- 子育てベスト100──「最先端の新常識×子どもに一番大事なこと」が1冊で全部丸わかり
- 子どもはみんな問題児。
- ベーシック発達心理学
- 子どもの発達障害 子育てで大切なこと、やってはいけないこと (SB新書)
- 子どもが育つ魔法の言葉 (PHP文庫)
この本は、0~6歳の子どもの発達を8つの段階に分けて解説し、保育実践をイラストや写真を用いて紹介しています。発達の特徴を生理的機能や運動、言語、社会性の観点から詳述し、発達を促す保育のポイントや環境づくりのアイディアも提供しています。著者は河原紀子で、発達心理学の専門家です。
保育士てぃ先生の初の育児アドバイス本は、忙しい親向けに子育ての悩みを解決するための「斬新かつ効果的な伝え方」を状況別にまとめています。内容は、子どもの特性を理解し、適切にコミュニケーションを取ることの重要性を強調。目次には、子どもとの日常的な困りごとに対処するための具体的な方法が135項目収められています。著者は男性保育士で、全国で講演活動や保育内容のアドバイスを行っています。
この書籍は、育児に関する疑問や悩みを解決するために現役ママ編集者チームがまとめたもので、赤ちゃんの成長に関する情報を月齢別に提供しています。内容は、赤ちゃんの発育や生活、母乳・ミルク、離乳食、生活リズム、予防接種、事故対策、病気のケアなど多岐にわたります。オールカラーでわかりやすく、先輩ママの体験談も含まれ、育児を楽しむためのヒントが満載です。著者は国立成育医療研究センターの理事長で、専門家による監修がなされています。
本書は発達心理学の基礎知識を、胎児期から老年期までの発達段階を通じてわかりやすく解説しています。イラストや図版を多く用い、育児や教育に関わる人々に必要な情報を提供。著者は発達心理学の専門家で、教育実践にも取り組んでいます。
この書籍は、現代の子育てに必要な新しいアプローチを提案しています。家庭学習や遊び、習い事、コミュニケーション能力、自己肯定感、創造力など、教育学や心理学、脳科学に基づく421の具体策を紹介。著者の加藤紀子は教育分野での豊富な経験を持ち、子どもに必要な力を育む方法を網羅しています。
著者中川李枝子が贈る子育てバイブルでは、焦らず悩まず子どもらしさを大切にすることが強調されている。保母としての経験を基に、子どもに関する45のメッセージが収められ、子育ての基本や本の読み方、良いお母さんの姿について語られている。著者は名作絵本「ぐりとぐら」の生みの親であり、子育てに役立つ知恵を提供している。
心と体の生涯発達への心理学的アプローチの方法から,乳幼児期の認知・自己・感情・言語・社会性・人間関係の発達の詳細,学童期〜高齢期の発達の概要,発達障害への対応まで,子どもにかかわるすべての人に必要な発達心理学の基礎が身に付くようガイドする.幼稚園教諭・保育士養成課程にも対応. はじめに(開) I 発達のとらえ方 1 発達心理学とは(齋藤) 2 遺伝と環境(佐々木掌子) 3 生涯発達の視点(齋藤) II 乳幼児期の発達をくわしく知る 4 胎児期・周産期(新屋裕太・今福理博) 5 感覚・運動の発達(伊村知子・白井 述・島谷康司) 6 愛着の発達(蒲谷槙介) 7 自己と感情の発達(森口佑介) 8 認知の発達(旦 直子) 9 言語の発達(小林哲生) 10 社会性・道徳性の発達(奥村優子・鹿子木康弘) 11 遊び・仲間関係(野嵜茉莉) III 発達を支える 12 学習の理論(後藤和宏) 13 障害と支援(浅田晃佑) 14 心と行動の問題および児童虐待(出野美那子) IV 学童期以降の発達を概観する 15 学童期〜青年期(林 創・松島公望) 16 成人期〜老年期(久保南海子) コラム1 女に育てたから女になるのか? コラム2 虐待の要因を探る サルの里子実験 コラム3 早産児の認知発達 コラム4 妊娠中の母親の食事と胎児の味覚的嗜好 コラム5 風船を持たせることによる乳幼児の歩行支援 コラム6 各愛着タイプのその後 コラム7 空想の友達 コラム8 赤ちゃんも計算ができる? コラム9 統語的手がかりを用いた動詞学習 コラム10 ヒトの視線のパワー コラム11 乳幼児の道徳性の発達 コラム12 きょうだい関係の役割 コラム13 生活習慣の獲得 コラム14 神経多様性 コラム15 遊びに現れる子どもの心 コラム16 子どもの嘘への対応 コラム17 日本人の宗教性とアイデンティティ コラム18 サルのサクセスフルエイジング? おばあちゃんザルの知恵 Introduction to Development Psychology Kazuo HIRAKI and Atsuko SAITO, Editors
本書は、発達障害の子どもたちの育て方について解説したもので、臨床経験30年以上の児童精神科医が著者です。子どもたちの成長のペースはそれぞれ異なり、定型発達に合わせる必要はないと強調しています。育て方のポイントは「多数派に合わせない」「平均値に合わせない」「友達に合わせない」の3つで、幼児期から思春期までの具体的なアドバイスが提供されています。目次には、発達障害の理解や子どもへの接し方、生活スキル、育て方の重要性についての章が含まれています。
この書籍は、世界22カ国で愛読され、日本で120万部以上のベストセラーとなった子育てに関する指南書です。子育ての重要なポイントや親としてのあり方についてのヒントが提供されています。具体的な内容としては、子どもがどのように育つかに影響を与える親の言動や接し方が示されており、励ましや愛情が子どもの成長に与えるポジティブな影響が強調されています。著者は教育者のドロシー・ロー・ノルトと精神科医のレイチャル・ハリスで、翻訳は石井千春が担当しています。
この文章は、子どもの成長段階を示す目次であり、入園面接から始まり、首がすわる時期から歩行の完成、自我の発展、自制心の育成に至るまでの各段階が記載されています。著者は京都大学の准教授、田中真介です。
この書籍は、発達心理学のトピックを乳児期から老年期までの各段階に分けて解説しています。図解を豊富に用い、発達障害や依存症、性の多様性など、現代の関心が高いテーマにも触れています。学生や教育関係者、保護者など、幅広い読者に向けた内容です。著者は心理学の専門家で、様々な教育機関で教鞭をとっています。
本書は、0~5歳児の発達を理解し、保育者がどのように支援できるかを学ぶための生活習慣に関するガイドです。食事、排せつ、睡眠、着脱、清潔、生活力向上の6章を通じて、子どもの生活習慣を深く理解します。
特別支援教育の専門家が、2000人以上の支援経験をもとに、子どもとの効果的な接し方やアセスメント方法をまとめた一冊。イライラやパニックなどの問題に対処するための具体的なスキルを100紹介。内容は、発達障害の子どもが感じることから、支援の原則、効果的なほめ方や教え方、行動の予防法、パニックや暴力への対応法まで多岐にわたる。著者は小学校教諭で、全国で講演や研修を行っている。
本書は1歳児クラス向けの指導計画を解説し、年案、月案、週案、日案、保育日誌、食育計画、防災・安全計画などの書き方を豊富な文例と共に紹介しています。新保育指針に対応し、CD-ROMにはすべての計画が収録されています。著者は千葉経済大学の教授で、教育現場の経験を持つ専門家です。
子どもの発達と教育について、エビデンスに基づく最新の知見に加え、理論的にもピアジェの認知発達,ボウルビィの愛着の発達を基本に、現代の神経構成主義への系譜を豊富な図版・資料とともに丁寧に概説。発達心理学を学ぶ学生や保護者をはじめ、心理・教育・保育・保健の専門家にとっても有用な一冊。 原著まえがきより 日本語版への序 第1章 枠組みと方法 1.1 発達心理学における重要な疑問 1.2 心理学的データの収集と分析 1.3 まとめ 第2章 理論と方法 2.1 初期の見方 2.2 ジョン・ロック 2.3 ジャン‐ジャック・ルソー 2.4 ジャン・ピアジェの構成主義 2.5 レフ・ヴィゴツキーの社会・文化理論 2.6 ジョン・ボウルビィの愛着理論 2.7 コネクショニズム 2.8 ダイナミックシステムズ 2.9 神経構成主義 2.10 まとめ 第3章 乳幼児期への導入 3.1 胎児期の発達 3.2 新生児 3.3 座位,立つこと,歩行 3.4 手のコントロールの発達 3.5 聴覚,嗅覚,味覚,視覚 3.6 まとめ 第4章 乳児期の認知発達 4.1 カテゴリー化の発達 4.2 対象の処理 4.3 数量の理解 4.4 コア認識 4.5 まとめ 第5章 初期の言語発達 5.1 話しことばの知覚の発達 5.2 喃語の発達 5.3 初期言語発達における社会的文脈 5.4 初期の語彙:単語の理解 5.5 語を話すことの学習 5.6 まとめ 第6章 乳児期における社会的,情動的発達 6.1 他者への気づき 6.2 他者の模倣 6.3 微笑みと社会的認識 6.4 愛着の発達 6.5 自己概念の発達 6.6 感情への反応 6.7 まとめ 第7章 就学前期への導入 7.1 脳の発達 7.2 運動発達 7.3 描画 7.4 まとめ 第8章 就学前期の認知発達 8.1 ピアジェの前操作的推理の理論 8.2 ピアジェの前操作的思考のテストへの批判 8.3 問題解決 8.4 類推による推理 8.5 見かけ,想像と現実 8.6 社会的認知と心の理論 8.7 まとめ 第9章 就学前期における言語発達 9.1 言語発達の理論的説明 9.2 初期の語結合 9.3 文法の始まり 9.4 早期の文法理解の実験的研究 9.5 特異的言語発達障害(SLI) 9.6 言語障害と言語的不利 9.7 まとめ 第10章 就学前期の社会性と情動の発達 10.1 友情と交友関係 10.2 社会的問題解決 10.3 性役割の発達 10.4 自己の理解 10.5 遊び,想像,ふり 10.6 信頼の発達 10.7 まとめ 第11章 児童中期への導入 11.1 運動技能 11.2 脳の発達 11.3 発達障害 11.4 まとめ 第12章 児童中期の認知発達 12.1 推理 12.2 問題解決 12.3 ワーキングメモリ 12.4 数的処理の学習 12.5 まとめ 第13章 読み書き能力(リテラシー) 13.1 読むことの学習 13.2 書くことの学習 13.3 読み書きの学習の障害 13.4 まとめ 第14章 児童中期の社会性と感情性の発達 14.1 仲間との交流 14.2 道徳性の発達 14.3 感情性の発達 14.4 性役割の発達 14.5 まとめ 第15章 青年期への導入 15.1 青年期の矛盾 15.2 青年期の脳の発達 15.3 青年期の思春期成熟変化 15.4 青年期についての比較文化的展望 15.5 まとめ 第16章 青年期の認知発達 16.1 ピアジェの形式的操作的推理の理論 16.2 ピアジェの理論への批判 16.3 実行機能の発達 16.4 まとめ 第17章 青年期の社会的,情動的発達 17.1 道徳的推理 17.2 人間関係 17.3 青年期の友人関係の性差 17.4 争いと攻撃的行動 17.5 家族の中での性的役割 17.6 まとめ 文献 索引 訳者あとがき 著者・訳者紹介
この本は、子育てに関する悩みを解決するための実用的なガイドです。内容は、接し方やコミュニケーション、家庭や外出時の工夫、学校生活や学習支援に関するアドバイスが含まれています。著者の大場美鈴は、発達障害を持つ子どもを育てる経験を活かし、育児に役立つ情報を発信しています。
この書籍は、出産や育児に関する疑問や不安を解消するためのリストを提供し、ママ・パパ・家族が子育てを楽に楽しめるようサポートします。内容は産前産後の準備、日常のお世話、子どもの成長に合わせた必要事項、年中行事の準備、育児に必要な物、育児での検討事項、病気やケガの対処法に分かれています。医療や子どもの発達については専門家が監修しています。
この書籍は、薬を使わない自然流の子育てを提唱する著者、真弓定夫によるもので、子どもを「自然の一部」として育てる方法を探求しています。内容は、現代の子どもたちの健康問題や食生活の見直し、生活習慣の改善、病気の自然治癒法、そして大人ができる子育ての基本について述べています。著者は経験豊富な小児科医であり、子どもの心を尊重した育て方を重視しています。
この文章は、児童精神科医が乳幼児期の育児の重要性について語った内容を紹介しています。乳幼児期が人格形成の基盤を作る時期であり、育児における社会の変化や人との関わり、信頼関係の構築、自立へのステップ、しつけや思いやりの育成、友達との学び合いなど、さまざまな側面が取り上げられています。また、保育士や親へのメッセージも含まれています。
生まれてから老いていくまで,生涯にわたる心の発達を解説する。豊富な図版でわかりやすいコンパクトな入門書。 私たちはいかにして生まれ,育ち,そして老いていくのか。子どもが認知能力を獲得する過程から,自己を確立し未来へと世代を継承していくに至るまで,生涯にわたる成熟の流れをわかりやすく解説する。コンパクトで読みやすい入門書。 第Ⅰ部 発達を支えるもの 第1章 発達の可塑性:生涯発達心理学とは 第2章 認知発達の基盤1:胎児と0歳児 第3章 認知発達の基盤2:表象の獲得 第Ⅱ部 生涯にわたる発達 第4章 他者との関係性のはじまり:基礎と展開 第5章 子どもの自己発達:自己のはじまりと表現 第6章 認知能力の生涯発達 第7章 関係性の発達:人間関係の広がりと深まり 第8章 大人の自己発達:自己を未来へつなぐ 第9章 成熟と英知:人生を上手に生きること
この書籍は、子育てに関する重要なポイントをまとめたもので、幼児や小学生を持つ親に向けた内容です。「AERA with Kids」の元編集長が、子育ての基本や新しい教育観を23のキーワードで紹介しています。具体的には、自己決定力や自己肯定感を育む方法、親が身につけるべき習慣、勉強や受験に関する誤解、金融教育の重要性などが取り上げられています。子育てのエッセンスを学び、実践するためのガイドとして役立つ一冊です。
この書籍は、離乳食の基本から2歳までの幼児食の進め方をサポートする内容で、食材別の調理方法や300品の簡単レシピをオールカラーで紹介しています。目次には、離乳食の基本ルール、進め方、栄養バランス、調理法、時期別の献立レシピ、食材別のレシピが含まれています。
この書籍は、新米ママ・パパ向けに、子どもがかかりやすい病気や症状、ホームケアの方法、予防接種、事故予防、救急ケアなどの情報をオールカラーで提供しています。育児誌「Baby-mo」特別編集で、実際の体験談や写真も豊富に掲載されており、育児に役立つ事典として、子どもの健康や成長に関する知識を網羅しています。
この文章は、育児に役立つ「スゴワザ」を紹介する書籍の目次と著者情報をまとめています。書籍は三つの章に分かれ、日常生活を楽にするテクニック、幼稚園や小学校受験に役立つ学習法、子どもとの良好な関係を築く方法が紹介されています。著者の祖川泰治は、幼児教育センターの園長として約30年間、約400人の園児を指導してきた経歴を持っています。
本書は、0歳の赤ちゃんと親が楽しむための遊びを紹介しています。赤ちゃんの発達段階に応じた遊びを提案し、親がリラックスして楽しむことが重要だと強調しています。伝統的な手遊びや、日常の合間に気軽にできる遊びが豊富に掲載されており、親子でお気に入りの遊びを見つける手助けをします。著者は教育学の専門家で、育児に役立つ知識を提供しています。
本書は、子育てに悩む親に向けて「叱らなくていい子育て」の方法を提案しています。子どもが叱られる行動をとる理由を解明し、すぐに実践できるヒントを提供。親と子が共に幸せになるための具体策を紹介し、子どもを受け入れることの重要性を強調しています。著者は保育士としての経験を持つ須賀義一氏です。
この書籍は、誕生から老年期に至るまでの人間の発達を、身体、感情、自己意識、人間関係、知能などの観点からビジュアルに解説しています。発達障害などの重要なテーマも取り上げており、すこやかな成長に必要な最新情報を提供しています。著者は、臨床心理士であり、教育や心理学の専門家としての経歴を持つ林洋一氏です。
本書は、発達障害児が通常学級での学びを保障されるための支援方法や好事例を、ライフステージごとに紹介しています。家庭、学校、福祉などの関係機関が連携するために必要な法律や制度の変遷もわかりやすく解説しており、特に教育関係者にとって必読の内容です。著者は特別支援教育の専門家で、実践的な指導・支援の方法や制度についても詳述しています。
子どもが生まれたときに購入して以来、わたしの心のお守りです!チェック表があり、病院なのか救急車を呼ぶレベルなのか、お家で様子を見るのか判断できます。キティちゃんがかわいいので家においておいてもゴツくないところも気に入っています!
この本は、「ていねいな保育」に焦点を当て、0・1・2歳児クラスの実践例を28項目紹介しています。内容は「基本」「生活」「遊び」「支える活動」の4章に分かれ、約20の保育園やこども園を取材しています。160ページのフルカラーで、400点以上の写真を使用し、専門用語の解説やコラムも含まれています。保育者や保護者にとって、保育の理解を深めるための参考書となることを目指しています。
この本は、親が一貫した姿勢を持つことの重要性を説き、子育ての悩みを解決するための具体的な方法を提供します。著者の奥田健次は、数万件の育児問題を解決してきた専門家であり、子どもとの接し方やルール作り、効果的な叱り方など、実践的なアドバイスを通じて「親子ともによく育つ」方法を提案しています。内容は、いじめやスマホの使い方、不登校のリスクなど現代の課題にも対応しています。
この書籍は、親子で一緒に食べられる栄養満点の204レシピを紹介しています。冷凍保存が可能で、毎日作る必要がなく、作り分けや味変も不要です。幼児食の基本や冷凍作り置きの方法、年齢別の食材や栄養の目安、よくある悩みへのQ&Aなど、必要な情報が豊富に含まれています。著者は管理栄養士の中村美穂氏と冷凍生活アドバイザーの西川剛史氏です。
この書籍は、子どもの行動や言葉に隠された意味を理解することで新たな視点を得ることを提案しています。内容は、発達心理学に基づき、胎児期から高齢期までの各発達段階について詳しく解説しています。著者は心理学博士で、発達心理学を専門とする目白大学の教授です。
『子どもの気持ちがわかるシリーズ』の第2弾で、6歳から11歳の子どもの行動や感情に関する育児書です。子どもの脳の発達を理解し、よくある問題(集中力の欠如、怒りっぽさなど)に対する具体的な対応法を、イラストと共に紹介します。最新の神経生物学に基づき、子どもの行動の裏にある動機を分析し、親がどのように接すれば良いかを提案しています。著者は心理療法士のイザベル・フィリオザと教育者のアヌーク・デュボワです。
脳研究者の池谷裕二氏が、娘の4歳までの成長を脳の発達と機能の観点から分析し、子育てのコツを紹介する書籍です。専門的な知見を基にした「脳科学の育児術」は、親にとって新たな発見をもたらします。内容は、1歳から4歳までの子どもの脳の成長段階を詳しく解説しています。著者は東京大学の教授で、神経科学と薬理学を専門としています。
この書籍は「臨床発達心理士」資格取得を目指す人向けのガイドで、学習内容や資格取得者の活動、過去問の一部を紹介しています。内容は、臨床発達心理学の基礎、資格取得のための条件、実習や試験の方法、資格取得後の研修や倫理、社会的貢献、実践の場など多岐にわたります。公認心理士との関連や、資格更新についても触れています。
著者が発達障害を持つ娘との育児を通じて学んだ「療育」の考え方を描いたマンガです。福田萌さんや鳥居みゆきさんが推薦しており、母親としての葛藤や成長を描写。0歳からの療育園探しや日々のエピソードを通じて共感を呼び、多くのフォロワーを獲得した内容が盛り込まれています。Instagramでは読めない新たなエピソードも含まれています。
猿蟹合戦とは何か.国語入試問題必勝法.時代食堂の特別料理.靄の中の終章.ブガロンチョのルノアール風マルケロ酒煮.いわゆるひとつのトータル的な長嶋節.人間の風景
『幼稚園では遅すぎる』の続編である本書は、幼児教育に関する新しい子育て法を提案しています。著者は25年の研究を経て、母親の影響力や環境づくり、子どもの興味を引き出すことの重要性を強調しています。具体的には、母親が育児に専念することや、子ども同士の遊びを促すこと、興味を大切にすることが成長に繋がると述べています。
本書は、忙しい親向けの子ども向け作りおきレシピ集です。1歳半から5歳児に必要な栄養を考慮したおかずを集めており、40分で3日分の食事を作ることができます。食べる際は温めるだけで簡単に提供でき、子どもが喜ぶ人気料理が含まれています。さらに、役立つコラムもあり、食事の時間を楽しくする工夫が紹介されています。著者は管理栄養士で、乳幼児の食育に豊富な経験を持っています。
本書は、非認知能力(意欲、粘り強さ、自己抑制、社会性、自尊心など)を育む方法について解説しています。乳幼児期にこれらの能力を育てることで、将来の幸福や成功につながるとされています。内容は二部構成で、第1部では非認知能力の定義や育成の重要性を説明し、第2部では具体的な遊びのレシピを通じて実践的な方法を紹介しています。著者は乳幼児教育の専門家で、子育て支援に関する豊富な経験を持っています。
この入門書は、発達障害に関する基本知識や支援方法、関連する福祉サービスを視覚的に解説しています。発達支援の専門職や保育者、教員など、発達障害のある人と関わるすべての人に向けて書かれています。内容は、発達障害の定義、症状、支援の視点、ライフステージに応じた制度、家族との関係、具体的な支援事例などを網羅しています。著者は広瀬由紀准教授です。
本書は、発達障害を持つ子どもとの関わり方を保育・療育の専門家が指南するガイドブックです。家庭や教育現場で役立つ52の具体的な方法を紹介しています。内容は、子どもとの基本的な関わり方、子どもの気持ちを理解する重要性、困難な状況への対応策、子どものタイプに応じたアプローチなどに分かれています。著者は保育園を運営する中村敏也氏で、地域に根ざした福祉事業を展開しています。
算数や国語の学力、粘り強さ、自己制御力、思いやり……、生まれた瞬間から最初の数年間に、親や保育者が子どもとどれだけ「話したか」ですべてが決まる。日本の子育て、保育が抱える課題とその解決策を、科学的な裏づけと著者自身の具体的な実践から示した書。 第1章 つながり:小児人工内耳外科医が社会科学者になったわけ 第2章 ハートとリズリー:保護者の話し言葉をめぐる先駆者 第3章 脳の可塑性:脳科学革命の波に乗る 第4章 保護者が話す言葉、そのパワー:言葉から始めて、人生全体の見通しへ 第5章 3つのT:脳が十分に発達するための基礎を用意する パート1:科学から実践へ パート2:「3つのT」の実際 第6章 社会に及ぼす影響:脳の可塑性の科学は私たちをどこへ導くのか 第7章 「3000万語」を伝え、広げていく:次のステップ エピローグ 岸に立つ傍観者であることをやめる 解説 子どもの言葉を育む環境づくり(高山静子) 訳者あとがき(掛札逸美)
秋月りすの4コマ漫画『OL進化論』を楽しみながら思考の技法を学ぶ。初心者のためのクリティカルシンキング超入門書。 「ものの見方・考え方」を、人気四コマまんが家・秋月りす氏のマンガ77編を楽しみながら身につけられる,画期的な本。心理学と論理学をベースに全くの一般人向けに書かれた「思考」の本。 秋月りすの4コマ漫画『OL進化論』を楽しみながら思考の技法を学ぶ。 初心者のためのクリティカルシンキング超入門書。 自分の周囲の人や種々の問題について,正確に理解し,自分の力で考え,適切な判断をしていくのがクリティカルな態度であり,その思考である。クリティカル思考は複雑化した現代社会に適応していく上でも必要となろう。本書では,ユーモアあふれる4コマ漫画を題材にわかりやすく楽しく身につけてもらうことをめざした。 はじめに 本書はこう読もう 序章 クリティカル思考とは ●「クリティカル」の意味 1.クリティカルに原因を推論する 2.クリティカルに何かを判断する 3.クリティカルに情報を選択する 4.クリティカルにいろいろ考える ●クリティカル思考の定義 1.クリティカル思考とは 2.事実と意見を分ける――クリティカル思考のための準備 3.議論を分析する――クリティカル思考のための第一歩 1章 推論の仕方は妥当か ●クリティカルに推論するとは? ●クリティカルに推論するやり方 1.あてはまらない例はないか? 2.一緒に変化するか? 3.四分割表で考える 4.四分割表「的に」考える 5.共通点と相違点に着目すれば 6.一致と差異に組織的に着目する 7.誰のせいかを考える 8.誰のせいかを「じっくり」考える ●因果関係を検討する上での留意点 1.一つの結果はいろいろな原因から生じる(1) 2.一つの結果はいろいろな原因から生じる(2) 3.一つの結果はいろいろな原因から生じる(3) 4.一つの結果はいろいろな原因から生じる(4) 5.一緒に変化したら因果関係と言える? 6.結果が原因で結果をひきおこす? 7.偶然という可能性も忘れずに 8.こうなることは初めから分かっていた? ●前後論法のもつ罠 1.変化したのは何のせい? 2.他にも出来事がなかった? 3.時間がたっただけじゃないの? 4.極端な状態はもとに戻る ●間違った議論のいろいろ 1.理由が理由になってるの? 2.あんなヤツに何が言えるんだ? 3.お前なんか簡単に倒せるよ 4.似てるからきっと同じだよ 5.そのままどんどん転がっていく? 6.シロじゃなければクロだ! 7.経験者は正しい? 2章 根拠としての「事実」は正しいか ●クリティカルに「事実」を検討するとは? ●事実検討の基本的スタンス 1.あなたの常識が一般の常識? 2.体験談そのものは事実だとしても…… 3.記憶とは事実とは限らない 4.情報の歪み方にはパターンがある 5.専門家の意見だから信じるの? 6.数字なら信用できる? ●スキーマによる事実の歪み 1.スキーマを通してものを見る 2.スキーマは情報をつなぎ,意味づけるための枠組み 3.スキーマによって同じ情報が違う意味にもなる 4.スキーマは未知・未確認の部分を埋める 5.スキーマは情報の取捨選択をガイドする 6.スキーマを見直すか,スキーマにこじつけるか ●偏った事実を「事実」とする過ち 1.一部分の事実から全体を推測する 2.偏ったサンプルが誤った結論をつくり出す 3.先入観に合う事実を見つけ出す 4.当たってないケースには注意が向きにくい 5.めだつ×めだつ=関連? 6.一面性の出来事に注意 7.欲しい情報だけを集め,欲しくない情報は無視するバイアス 8.反証となりうる情報も探せ ●「事実そういう人か」の検討 1.人を見るときのスキーマに気づこう 2.型にはまった固定観念 3.身近な人はさまざまだけど,遠い人は一くくり 4.そういうことをしたのはそういう人だから? 5.状況でもあり,個人でもある……かも 6.行為者と観察者の視点は違う 7.役割と個人は必ずしも同じではない 3章 クリティカルシンカーへの道 ●クリティカルシンカーの特性 1.クリティカルシンカーはものごとを疑う 2.クリティカルシンカーは思考の落とし穴を知っている 3.クリティカルシンカーは柔軟である 4.クリティカルシンカーは客観的である 5.クリティカルシンカーは単純化しない 6.クリティカルシンカーはあいまいさに耐える ●クリティカルに生活しよう 1.ものごとを他の面からもみるためには 2.ポジティブ思考に気をつけよう 3.後知恵から脱却するためには 4.要するにマインドフル 5.ちょっとクリシン――ちょっとクリティカルシンキング 6.あっからクリシン――「あっ」から始めるクリティカルシンキング 7.ユーモア精神で行こう!! おわりに──今日から始めるクリティカル思考 本書を読んだ人のための今後の読書案内 秋月りすから一言
この書籍は「発達心理学」を50のキーワードを通じて学ぶ内容で、研究方法や理論、生涯にわたる発達過程を扱っています。初版から内容が刷新され、発達心理学に興味のある人々にとって学びやすい一冊です。著者は各大学で教育学を専門とする教授たちです。
好評書、待望の改訂!注目のトピック(出生前検査、エピジェネティクス等)を加え、変化の激しい青年・成人期の章は全面改訂。 累計2万5000部の好評テキスト。10年ぶりの大改訂。社会状況の変化をふまえ,青年・成人期および発達のつまずきを扱う9~13章は全面改訂。新規トピックやコラムも追加。QUESTIONツールが読者に問いかけ理解を深めます【公認心理師カリキュラムにも対応】 序 章 ヒトとして生まれ,人として生きる 第1章 発達するとはどういうことか 第2章 生命の芽生えから誕生まで 第3章 見て・さわって・感じる──赤ちゃんがとらえる世界 第4章 他者との関係性を築く──コミュニケーションと人間関係の発達 第5章 「いま」「ここ」をこえて──言語と遊びの発達 第6章 自分を知り,自分らしさを築く──関わりの中で育まれる自己 第7章 関わりあって育つ──仲間の中での育ち 第8章 思考の深まり──学校での学び 第9章 子どもからの卒業 第10章 大人になるために 第11章 関わりの中で成熟する 第12章 人生を振りかえる 第13章 発達は十人十色──発達におけるつまずきをどう理解し支えあうか
本書は、発達障害(ASD、ADHD、アスペルガー症候群)について、日本の専門家が正しい知識と豊富な事例を基に解説する作品です。近年、ドラマや小説で発達障害を持つキャラクターが増え、その影響で「自分は発達障害かもしれない」と感じる人が増加しています。著者は、発達障害の特性、問題点、社会の受け入れ方について詳しく説明し、誤解や偏見を解消する手助けをします。新年度に向けて、多様な人々との出会いが増える中で必読の一冊です。
本書は「保育ドキュメンテーション」として、写真つきエピソード記録の作成方法や実例を紹介しています。ナビゲーターはカメラを持ったネコの「シャロク」で、具体的な作り方や注意点、振り返りの方法を写真とイラストを使って分かりやすく解説。初心者向けの基本型から、毎日作成している方向けの応用型まで多様な例を提供し、手書きやパソコンでの作成方法も含まれています。保育者や保護者が子どもの魅力を再発見し、楽しく共有するための内容です。
この書籍は、0~5歳児向けのおたより作りに役立つ文例とイラストを豊富に提供しています。文例361点、イラスト2392点が収録されており、カラー・モノクロのテンプレートも含まれています。行事や食育、健康に関する内容が盛り込まれ、読みやすく伝わりやすいおたより作成のコツも紹介されています。著者は保育士・幼稚園教諭の永井裕美です。
新任の小谷先生が受け持つことになったのは、学校で一言もしゃべらない少年・鉄三。ハエ事件をきっかけに鉄三の気持ちを理解する小谷先生。さらに、変わった転校生・みな子が加わり、クラスメートたちは共に悩みながら「大切なもの」を見つけていく感動の物語。著者は灰谷健次郎で、彼は教師を経て作家として活躍しました。
「モンテッソーリ教育」は、マリア・モンテッソーリによって創始された教育法で、特に0~3歳の子どもに焦点を当てています。この書籍では、親が子どもを自分で考え行動できるよう育てるための30の具体的な方法を紹介しています。内容は、妊娠中の準備から手作り教具、トイレトレーニング、2歳児の成長過程まで多岐にわたります。実例や写真が豊富で、家庭での実践が容易です。著者の藤崎達宏は、モンテッソーリ教育の専門家であり、全国でセミナーや講演を行っています。
この書籍は、発達障害の子どもが学校環境で直面する課題と、その解決策について述べています。著者は、発達障害の子どもに世間の基準を無理に合わせるべきではないとしつつ、学校の集団活動やルールとの折り合いをどうつけるかを探求しています。目次では、親と教師の役割、発達障害の理解、学力と教育のあり方、特別支援教育の選び方、そして未来の学校教育についての考察が展開されています。著者は信州大学の教授で、発達障害に関する豊富な経験と研究を持つ専門家です。
このテキストは、公認心理師カリキュラムに基づいた発達心理学の学習教材で、視覚的にわかりやすく、実践的な内容が特徴です。重要語句解説や個別学習をサポートする工夫が施されており、授業から試験、実務に至るまで活用可能です。内容は、発達心理学の基礎から出生前後の発達、青年期以降の発達、非定型発達までを網羅しており、発達の生物学的基礎、感覚や運動、アタッチメント、認知、社会性、感情、遊び、言葉の発達など多岐にわたります。著者は教育学の専門家で、臨床的意義を重視しています。
この文章は、子どもの成長や潜在能力に焦点を当て、親が子どもの成長サイクルを理解し予習する重要性を強調しています。モンテッソーリ教育を通じて、子どもの自律や集中力を育てる方法を提案し、家庭で簡単に実践できることを紹介しています。これにより、子育てが楽しくなり、子どもの未来を輝かせることができると述べています。
プーさんのしかけミニえほん!いないいないばあ遊びをしよう。くり返し遊んでも飽きない!最後のページにはお子さんの顔が…! ページをめくって、プーさんのなかまたちと”いないいないばあ”遊びをしましょう。 最後のページにミラーシートが貼られていますので、お子さんの顔を鏡に映してお楽しみいただけます。 バッグにすっぽり入るコンパクトサイズ。丈夫なボードブックで、おでかけのおともにぴったり! くり返しお楽しみいただけます。 お母さんのための「遊びかたのヒント」つき 115×115mm 厚紙 鏡つき しかけ <内容> ・はちみつ壺の向こうにいるのは……、プーさん! ・ハロウィーンかぼちゃの向こうにいるのは……、ティガー! ・ふうせんの向こうにいるのは……、ピグレット! ・窓の向こうに見えるのは、きらきら輝くお月さま……と思ったら、お子さんのにこにこ笑顔が!
「なんで!?」がわかれば子育てがラクになる!・こだわりが強い・融通がきかない・友達づくりが苦手 臨床経験30年以上の医師が指南!●20ケースのマンガにあわせて具体的なサポート例を紹介・臨機応変な対人関係が苦手・自分の関心、ペースが最優先そんな自閉スペクトラム症の子の「あるある」をマンガ紹介→「どうして?」と思ったら解説を読んで解決! ■プロローグ:「自閉スペクトラム症」の子どものフシギ ・発達障害の中でもASD(自閉スペクトラム症)中心に事例を紹介 ・こだわりが強い、臨機応変な対応が苦手、友達づくりが苦手 ・ASDのコミュニケーションは理解されづらく、 「普通だったらわかるでしょ」がわからない ■20ケースのマンガにあわせて具体的なサポート例を紹介 ※幼児期から小学生まで Case1 何にでも手を出して、勝手に遊んでしまう Case2 特定の子と一緒になると、いつもケンカになる Case3 自分からは話しかけるのに、人の話は聞かない Case4 いたずらして注意されると、むしろ調子に乗る Case5 学校での生活に、いつまでたっても慣れない Case6 園に行くとき、いつも同じ道を通りたがる Case7 外出先の病院などで、ちゃんと挨拶しない Case8 タンスに登って飛び降りるので、危ない Case9 着替えや食事などの生活ルーチンが身につかない Case10 ささいなことで、かんしゃくを起こす Case11 偏食があって、なかなか変わらない Case12 真冬でも、半袖・半ズボンを着ている Case13 学校で教室移動中に、廊下を走り出す Case14 褒められたのに、先生の腕をかんでしまった Case15 大人に注意されると、腰砕けな答えを返す Case16 文章の細かいところを気にしすぎる Case17 質問されると、すぐに「わからない」と言う Case18 話し方が変わっていて、同級生と打ち解けない Case19 自分の意見を言わず、まわりに合わせてしまう Case20 元気に学校に行っていたのに「突然不登校」に ■エピローグ
『「やればできる!」の研究』は、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授による成功心理学の古典的名著で、マインドセットが成功と失敗を左右することを論じています。著者は、成長マインドセットと固定マインドセットの違いを探り、教育、ビジネス、スポーツ、人間関係におけるマインドセットの影響を解説。20年以上の研究を基に、マインドセットを柔軟にする方法や、成功するための思考法についても提案しています。
汐見稔幸先生は、子どもに関わるすべての人々を支援する存在であり、保育の質向上に悩む保育士や親に新たな視点を提供します。本書では、汐見先生の考えや言葉が集められ、新しい保育指針や要領の重要ポイントも解説されています。巻頭対談や保護者の悩みに対する回答も含まれ、子どもの幸せや成長に寄与するためのメッセージが伝えられています。著者は教育学の専門家で、保育の分野での豊富な経験を持っています。
乳幼児から成人期までの成長を追いながら、娘が幸せになるために必要なパパの心得やコミュニケーションの取り方などをアドバイス。 幼い頃は、無邪気に駆け寄ってきたのに、成長とともに離れてしまう娘の心。時には「大嫌い!」「キモイ」などと言われてしまう切ない存在のパパ。本書は、幼児期から思春期、成人期までの娘の精神的成長を、発達心理学をベースに読み解き、年代別に接し方、かかわり方をアドバイス。いつまでも好印象のパパであり続けるため、そして何よりも娘の幸せを願うパパのための、娘の“取扱説明書”です。 【女の子のパパ必読! 娘の気持ちがわかる本】 パパにとって娘は目に入れても痛くないほどかわいい存在。幼い頃は「パパ!パパ!」と無邪気に抱きついてきた娘なのに、自我が芽生え、成長するとともに、突如としてやってくる「パパ嫌い!」。わが娘とはいえ異性であるため、自分の成長過程を振り返っても、なぜ口もきいてくれないのか、不機嫌な態度ばかりをとるのか、父親はまるで理解することができず、娘との距離は開いていくばかり。 本書は、幼児期から思春期、成人期までの娘の精神的成長を、発達心理学をベースに理解しながら、それぞれの時期において、父親はどのように接し、何をどう努力すればいいのかを解説。上手な叱り方やほめ方、言っていいことやNGワードなども盛り込み、今どき女子のアンケート結果も交えて女の子の不思議を読み解きます。 いつまでも「パパ好き!」と言ってもらえる好印象のパパであり続けるため、そして何よりも娘の幸せを願うパパのための、娘の“取扱説明書”です。 【本書の主な内容構成】 第1章 幼児期(2~6歳) イヤイヤ天使との会話を楽しもう/休日はパパの存在感を高めるチャンス/娘が本当に欲しいモノが分かりますか? パパ塾 ぶきっちょパパもそのまま使える娘へのほめ言葉/気を付けたい 娘の心にしこりを残す言葉がけ 第2章 小学校前半(7~9歳) 一緒にお風呂の卒業記念日はいつ?/叱り上手・ほめ上手になるテクニック/さわやかな自己主張のお手本はパパ パパ塾 イザというときに効果てきめん!上手な叱り方とほめ方 第3章 小学校後半(10~12歳) スマホ問題はパパ主導で解決しよう/娘にとってパパは最後の防波堤/娘が意見を言ってきたら、まず認めよう パパ塾 傾聴のコツ 第4章 中学生(13~15歳) パパなんて大嫌い!に傷付かないで/たまには娘の前で本音を語ろう パパ塾 中学生の娘に言ってはいけないNGワード 第5章 高校生(16歳~18歳) きみが一番と娘に伝え続けよう/娘の人生の先輩になろう 第6章 大学生~社会人 「めげない力」を育むヒントを知ろう/娘を真の大人にするために父親がすべきこと パパ塾 娘のエゴ・レジリエンス力を鍛えよう
本書は発達心理学の基本をストーリーまんが形式で解説した入門書です。乳児期から青年期までの登場人物の成長を通じて、218の重要キーワードをわかりやすく紹介しています。従来のテキストの難しさを解消し、教育や福祉、医療に関心のある人々に最適です。楽しく学べる内容で、試験前の復習にも役立ちます。著者は法政大学の教授で、専門は発達心理学です。
子どもが自分の気持ちや他人の気持ちに気づき、感情を調節し、他人とうまくかかわっていくためのワークブック。家庭や保育園・幼稚園、学校などで、親や先生と一緒に楽しく学べるよう、工夫をこらしたワークを満載。対象は幼児から小学校中学年程度まで。 まえがき 感情について知ろう! 1 感情とは 2 感情についての知識 3 最近の子どもたち 4 考えること、行動すること 5 感情の調節 6 感情の発達 7 感情のリテラシーの発達 8 感情の表出の発達 9 感情を育てる 10 感情を育てる方法 11 感情のカリキュラムの説明 感情を育てよう! 対象年齢:幼児から小学校低学年 01 いま、どんな気持ち? 02 友だちはどんな気持ちかな? 03 がまんするって? 04 わたしとあなたの思いは違う 05 気持ちと言葉のマッチング 06 友だちの表情を読み取る 07 負けてくやしいとき、どうする? 08 友だちを励ましてみよう! 09 気持ちを色であらわしてみよう! 10 うれしいときの顔は? 11 気持ちを巻き戻してみる 12 うまくかかわる言葉を探そう 対象年齢:小学校低学年から中学年 13 ポジティブな気持ちって? 14 大事なお友だちについて考える 15 ああ、迷っちゃう! 16 怒りのコントロール日記 17 どっちにしようか迷ったとき 18 困ったときに何をしてあげる? 19 立ち止まって考える 20 「ごめんね」の気持ちを伝える 21 こんなときどうする?ゲーム 22 物語から感情を学ぶ 23 気持ちにぴったりの言葉 24 気持ちを知ったうえでかかわる 25 心と身体はつながっている 26 友だちの言葉に耳をすます 27 怒りのレベルはどれくらい? 28 「協力」できるかな? 29 「おこりんぼうさん」になるとき 30 ノンバーバルから気持ちに気づく 31 感情コントロールスキル 32 そっと教えちゃうノート 33 入り混じった感情に気づく 34 共感力を育てる 35 状況をポジティブにとらえる 36 相手の気持ちになってかかわる 対象年齢:幼児から小学校低学年 37 「代わりばんこ」できるかな?
生涯にわたる心の発達をこの1冊に。学びのスイッチを入れるツール等,読ませ・考えさせる工夫が満載の新しいタイプの入門書。 心の発達には何が影響するのか。あなたのこれまでを振り返りつつ,将来に思いをはせつつ,心の発達メカニズムとその多様性にふれてみよう。QUESTIONツールや親しみやすいレイアウト等読ませる工夫が満載。考える愉しみを味わいながら理解が深まる入門書です。 序 章 ヒトとして生まれ,人として生きる 第1章 発達するとはどういうことか 第2章 生命の芽生えから誕生まで 第3章 見て・さわって・感じる――赤ちゃんがとらえる世界 第4章 他者との関係性を築く――コミュニケーションと人間関係の発達 第5章 「いま」「ここ」をこえて――言語と遊びの発達 第6章 自分を知り,自分らしさを築く――関わりの中で育まれる自己 第7章 関わりあって育つ――仲間の中での育ち 第8章 思考の深まり――学校での学び 第9章 子どもからの卒業 第10章 大人になるために 第11章 関わりの中で成熟する 第12章 人生を振りかえる 第13章 発達は十人十色――発達におけるつまずきをどう理解し支えるか
プーさんのしかけミニえほん!穴の向こうにいるのはだ~れだ?楽ししかけで、くり返し遊んでも飽きない!持ち運びに便利なミニサイズ くまのプーさんの穴あきしかけ絵本。 「むこうにいるのはだれかな?なにかな?」 ページをめくるたび、わくわくどきどき。自分の指を入れて、象さんのお鼻遊びもできちゃいます。 楽しいしかけでくり返し遊べて、好奇心や想像力を育てます。 手のひらサイズで、小さなおこさまにもめくりやすく、バッグにすっぽり入るコンパクトサイズ。 丈夫なボードブックで、おでかけのおともにぴったり! お母さんのための「遊びかたのヒント」つき 115×115mm 本文16ページ 丈夫なボードブック しかけつき
今日は雨降り。それでもぞうくんはごきげん。かばくんと一緒にお池の中を散歩します。ところがお池はだんだん深くなり……。 今日は雨降り。それでもぞうくんはごきげん。かばくんを散歩に誘うと、お池の中ならいいよ、と言われ、2匹は池の中を歩き出します。ところがお池はだんだん深くなって、泳げないぞうくんは困ってしまいます。するとかばくんがぞうくんを背中に乗せてくれたのですが、進んでいくとまたまたお池は深くなって……。ご存じ『ぞうくんのさんぽ』の36年ぶりの続編です。簡潔な文章と抑えた表現の絵が、子どもたちの想像力をふくらませます。 今日は雨降り。それでもぞうくんはごきげん。かばくんと一緒に池の中を散歩します。ところが池はだんだん深くなり……。『ぞうくんのさんぽ』の36年ぶりの続編です。
この書籍は、妊娠から出産、産後までのママと赤ちゃんの身体の変化や、安産のための食事・運動、妊娠・出産にかかるお金に関する情報を提供します。また、妊娠中の病気やトラブルへの対処法や、新生児のお世話、産後のケアについても詳しく解説されています。さらに、パパができるサポートのアドバイスも28項目紹介されています。著者は周産期医学や生殖免疫学の専門家です。
本書は、幅広い発達障害特性を理解し支援するための包括的アセスメントのアプローチを解説しています。アセスメントの重要性や実施方法、フォーマル・インフォーマルな手法の活用、データ分析のポイント、具体的な支援事例を紹介し、支援職にとって必読の内容となっています。著者は発達障害に関する研究と支援の専門家であり、実践的な情報を提供しています。
この書籍は、誕生会や卒園式などで使える155曲の保育向けの歌を収録しており、弾きやすい指番号付きでオシャレな「プチデコ」コード編曲が特徴です。内容は、園生活の歌、季節・行事の歌、定番の人気歌に分かれており、劇あそび用のBGMや効果音も含まれています。
本書では、排せつ、食事、睡眠、着脱、清潔の5つの習慣について、イラストを用いて指導のポイントを分かりやすく紹介しています。著者は谷田貝公昭で、子どもの生活技術に関する研究を行っています。目次には各習慣に加え、保護者向けの情報や資料も含まれています。
ピア・ラーニングとは 必要な援助を求める 人と比べ合って学ぶ ピアとかかわる動機づけ 何をめざして学ぶか ピアとともに自ら学ぶ 「一人で読む」を超えて 子どもはピアに援助をどう求めるか 協同による問題解決過程 ピアを介した概念変化のプロセス メタ認知におけるピアの役割 協同による教育実践の創造 日本語教育におけるピア・ラーニング 発達に遅れや凸凹のある子どもの協同 豊かな学びあいに向けて
この本は、イヤイヤ期における子どもの様々な「イヤイヤ」に対処するための具体的な方法を、ユーモアあふれるイラストとともに紹介しています。内容は、寝かしつけや食事、着替え、おトイレ、歯磨き、お風呂、家庭内でのイヤイヤなど、シーン別に100の対処法が解説されています。著者はイヤイヤ期専門の保育士で、育児コラムも手掛けています。
この書籍では、最先端の脳科学に基づき、子どもの脳の成長に関する重要なポイントを解説しています。特に6歳までの発達が重要であり、早寝・早起き、コミュニケーション能力の向上、遊びや栄養、しつけの方法が脳の成長に与える影響について述べています。各章では、脳を育てるための具体的なアプローチが紹介されています。
「子供の発達」に関するよくある質問
Q. 「子供の発達」の本を選ぶポイントは?
A. 「子供の発達」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「子供の発達」本は?
A. 当サイトのランキングでは『発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ (健康ライブラリースペシャル)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで142冊の中から厳選しています。
Q. 「子供の発達」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「子供の発達」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。




















![『発達心理学[第2版]:周りの世界とかかわりながら人はいかに育つか (いちばんはじめに読む心理学の本 3)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UsUc81FuL._SL500_.jpg)
![『よくわかる発達心理学[第2版] (やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41NZcG4nvVL._SL500_.jpg)











































![『臨床発達心理士 わかりやすい資格案内[第4版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41eO3qshJYL._SL500_.jpg)