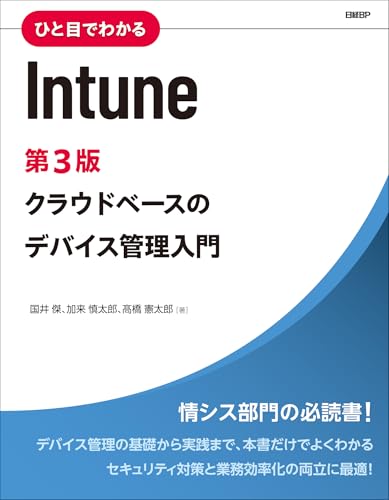【2025年】「フレームワーク」のおすすめ 本 157選!人気ランキング
- ビジネスフレームワーク図鑑 すぐ使える問題解決・アイデア発想ツール70
- 仕事のアイデア出し&問題解決にサクっと役立つ! ビジネスフレームワーク見るだけノート
- ひらめきとアイデアがあふれ出す ビジネスフレームワーク実践ブック
- ドリルを売るには穴を売れ
- 弱者でも勝てるモノの売り方 お金をかけずに売上を上げるマーケティング入門
- 60分でわかる! ビジネスフレームワーク
- 知的生産力が劇的に高まる最強フレームワーク100
- マッキンゼーで叩き込まれた 超速フレームワーク ――仕事のスピードと質を上げる最強ツール (単行本)
- 図解でわかるビジネスフレームワーク いちばん最初に読む本
- 事例で学ぶ BtoBマーケティングの戦略と実践
本書は、アイデアが浮かばない、会議がまとまらない、意思決定に迷うといった悩みを解決するためのフレームワーク集です。70以上の手法が掲載されており、個人やチームで活用可能です。内容は問題発見、市場分析、課題解決、戦略立案、業務改善、組織マネジメント、情報共有に関するフレームワークを含み、使い方や活用のヒントも提供されています。すべてのフレームには記入例があり、PowerPointテンプレートとしても利用できます。
ビジネスフレームワークが図解で学べる。誰もが知っているビジネスでも実際にビジネスモデルは分からないことが多い。この書籍のビジネスフレームワークを一通り頭に叩き込んでおくことで色んなケースに応用が効く。
本書は、ビジネスパーソン向けに問題解決のための「フレームワーク」を解説したビジュアル版の書籍です。マーケティングや戦略プランニング、マネジメントに役立つ81のツールを紹介し、効率的に問題を解決する方法を提供します。大きな紙面で図解が直感的に理解できるようになっており、著者はグロービスの嶋田毅氏です。目次には、問題発見や解決、マーケティング、戦略策定、組織マネジメントに関するフレームワークが含まれています。
本書は、マーケティングの入門書であり、12万部を超えるロングセラーの新装版です。顧客にとっての「価値」を出発点に、ターゲティング、差別化、4Pを通じてマーケティング理論を理解できる内容です。また、新人社員が廃業寸前のレストランを復活させるサブストーリーを通じて、実践的な活用法も学べます。著者はマーケティングの専門家で、さまざまな業界でのコンサルティング経験があります。
初学者向けのマーケティングの書籍として非常にオススメ。顧客が欲しいのはドリルではなくて穴。マーケティングにおいて重要な顧客の課題にフォーカスした考え方を学べる。マーケティングを学び始めたばかりの人はこの書籍をぜひ手にとって欲しい。
本書は、元星野リゾートの著者によるマーケティング入門書で、主に次の2点が特徴です。まず、マーケティングは誰でも理解できるシンプルなものであり、専門用語を避けて実践的な内容を紹介しています。次に、資金が限られた「弱者」でも実践可能なマーケティング手法を提案し、喫茶店「ワーグナー」の新米店長エミがV字回復を果たすストーリーを通じて学びます。幅広い読者に役立つ内容で、SNSを活用した売上向上の方法も紹介されています。著者の上杉惠理子は、マーケティング戦略コンサルタントとして活動しています。
本書は、ビジネスにおける問題解決や戦略思考、データ分析などに役立つフレームワークを紹介しています。忙しいビジネスマンが収入を増やすために必要な知識やスキルを身につけるための内容で、具体的なフレームワークやアイデア発想法、データの魅力的な伝え方などが収録されています。著者は新規事業プロデューサーの永田豊志氏で、幅広いビジネス経験を持つ専門家です。
本書は、マッキンゼーで培った「超速フレームワーク仕事術」を紹介しており、効率的な問題解決や生産性向上に役立つ20のフレームワークを厳選しています。これらのフレームワークを活用することで、分析や意思決定の精度が向上し、論理的なコミュニケーションが可能になります。著者の大嶋祥誉は、実用性の高いフレームワークを通じて思考力や行動力を磨くことを提案しています。
本書は、ビジネスに役立つ70の「フレームワーク」を紹介しています。フレームワークは、意思決定や問題解決、戦略立案などに使える共通の手法で、安定した品質で短時間に成果を出すことが特徴です。内容は、問題整理、組織・コミュニケーション、アイデア創出、計画作成、戦略策定、マーケティングなどの場面での具体的な使用方法を図解で解説しています。著者は福島正人と岩崎彰吾で、両者はコンサルタントとしての経験を持っています。
BtoB業界では、従来の顧客獲得手法からWebを活用したインバウンドマーケティングへと大きな変革が進んでいます。しかし、ノウハウが不足している企業が試行錯誤しても成功が難しいのが現状です。本書は、BtoBマーケティングの専門家である栗原代表が、実際の企業例を交えながら効果的なマーケティング手法を解説しています。内容は初心者にも理解しやすく、戦略設計やコンテンツマーケティングの実践方法も網羅されています。
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
本書は、現代の営業スタイルが変化していることを強調し、顧客が営業に接触する前に商談プロセスの多くが進んでいる現実に対応する必要性を訴えています。著者は、SaaSビジネスの成長を支えた経験を元に、「科学的アプローチ」に基づく新しいレベニューモデルを提案し、マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサクセスのプロセスを紹介します。さらに、SFAやMAの運用方法の変化や、組織の成長を促すための戦略を具体的に解説し、実践的な「プレイブック」としての役割を果たしています。
SaaS系のプロダクトをどうやってスケールさせていくかの緻密な営業戦略が学べる。このスキームに沿ってほとんどのSaaS企業が営業組織を作っている。SaaS系を目指す経営者やSaaS系で働く会社員は全員読んでおいて損しない1冊。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
マーケティング部に異動した真二は、熱血上司と強力なライバル商品に直面しながら成長していくビジネスストーリー。各章では経営理念、環境分析、マーケティング・ミックス、製品ライフサイクル、目標市場設定、デジタル・マーケティングなど、実践的な手法が紹介され、専門用語も理解しやすく解説されている。著者はマーケティングの専門家、五味一成。
本書は、ビジネスにおける問題解決の技術と実行方法を体系的に解説したテキストで、業種や立場を問わず活用できるスキルを提供します。問題解決の手順を明確にし、実践的な内容を重視。特に問題の特定能力を強調し、実例を交えた構成で理解を深めることを目指しています。全7章で、問題解決の手順を段階的に学び、結果の評価や定着化についても触れています。著者は経営コンサルタントとしての経験を活かし、実践的なビジネススキルを伝授します。
新人商品プランナーの宮前久美が、日本企業が抱える「高品質・多機能なのに低収益」という課題に挑む。顧客中心主義の本質を探り、過当競争の中での差別化やマーケティング戦略を解説。具体的な事例を通じて、顧客のニーズに応えるだけでなく、自社の独自価値を提供する重要性を示す。全10章で、マーケティング理論や成功事例を紹介し、日本企業の成長戦略を考察する内容。
本書は、「自然に売れる仕組み」を構築するための原理原則と実践法を紹介しています。著者の理央周氏は、ターゲット設定、商品開発、コミュニケーション戦略を整理することで、解決すべき課題を明確にする重要性を強調しています。マーケティングのフレームワークや実例を通じて、読者に実践的なヒントを提供し、中小企業やスタートアップの経営者に役立つ内容となっています。
本書は、戦略立案、マーケティング、問題解決、マネジメント、組織開発の5つの分野から77項目、200種類以上のフレームワークを図解で紹介したハンドブックです。著者はファシリテーションとビジネススキルの専門家で、フレームワークを活用することで思考を加速し、迅速な問題解決や意思決定を促進できることを目的としています。オールカラーで改訂され、実用的な内容が特徴です。
このマーケティング入門書は、全60点のインフォグラフィックスを用いて、初心者から中堅マーケターまで最新の理論と実践を学べる内容です。全20テーマを5分で学習でき、博報堂のトップマーケター21人が寄稿しています。内容は「基礎編」と「デジタルナレッジ応用編」に分かれ、マーケティングの基本概念やデータ活用、顧客アプローチなどが網羅されています。
この書籍は、経営戦略や現状分析、戦略策定の失敗要因を探り、効果的な戦略を機能させるためのスキルを身につける実践問題集です。著者の牧田幸裕は経営大学院准教授で、主に製造業の経営企画や営業部門の変革に携わっています。内容は、経営戦略の機能不全や現状分析の重要性、中期経営計画の実行に必要な要素について詳しく解説しています。
この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。
本書『戦略フレームワークの思考法』は、経営戦略を策定するためのフレームワークを全面的にリニューアルしたもので、論理と直感を活用しながら問題解決やアイデア創出を支援します。著者は経営コンサルタントの手塚貞治氏で、伝統的なフレームワークから新しいものまで幅広く紹介。特に「並列化」「階層化」「二次元化」「時系列化」「円環化」という5つの思考パターンに基づき、各フレームワークの使い方やメリット・デメリットを具体例を交えて解説しています。初心者でも理解しやすく、実践的なノウハウが得られる内容です。
本書は、全米で「マーケティング・バイブル」と称されるジェイ・エイブラハムのベストセラーの新訳版で、経営者向けに具体的なマーケティング戦略を提供しています。著者は1万人以上の経営者を指導した実績があり、ビジネスの本質やインターネット活用法を含む重要な内容が復活翻訳されています。全体で17章から成り、収入増加や成功を手に入れるための具体的な方法を解説しており、実践すれば売上アップが期待できるとしています。
この書籍は、イノベーションの成功において顧客データや市場分析よりも“顧客の片づけたいジョブ”が重要であることを強調しています。著者たちは、顧客がモノを購入するメカニズムを解明し、予測可能で優れたイノベーションの創出方法を提案しています。内容はジョブ理論の概要からその可能性、組織におけるジョブの位置づけまで幅広く扱っています。著者は経営学者のクレイトン・クリステンセンをはじめとする専門家たちです。
マーケターなら絶対に外してはいけないのがこのジョブ理論。ニーズやインサイトという言葉を聞いたことをある人が多いと思うが、まずフォーカスすべきなのは顧客が本当に解決したいジョブ。マクドナルドに通う人が解決したいジョブは小腹を満たすことなのか?それともジャンキーなハイカロリー食事で日々の仕事の鬱憤を晴らしたいのか?同じ商品を消費していたとしても人やシーンによってジョブは違う。本当に顧客が解決したいジョブを顧客観察から見出し、そこにぶっ刺さる商品やサービスを提供するのがマーケターの仕事。それを学べるジョブ理論はマーケターのバイブルです。
この書籍は、デジタルネイティブであるZ世代の消費行動や働き方、理想とする生活について詳しく分析しています。コロナ禍を経験した彼らがどのように商品を購入し、ブランドとの関わりを持つのか、効果的なマーケティング手法や求人活動についても言及しています。著者は世代研究の専門家であり、Z世代の特性を理解し、企業がどのように彼らを顧客や社員として引き付けるかを探求しています。
この文章は、組織行動学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、組織行動学の基本、個人の行動、集団の行動、組織のシステムに関する4つの部に分かれており、それぞれのテーマを扱っています。著者はスティーブン・P・ロビンスと高木晴夫であり、ロビンスは組織行動学のベストセラー教科書作者で、国内外の大学で広く使用されています。高木は慶應義塾大学の教授で、経営学の専門家です。
本書は、外資系コンサルタントが身につけるべーシックスキル30個を紹介し、職業や業界を問わず役立つ普遍的なスキルを提供します。新人からベテランまでが使える内容で、15年後にも通用する能力を身につけることを目的としています。著者は自身の経験と元コンサルタントへの取材を基に、実践的な技術や思考法、デスクワーク術、プロフェッショナルマインドを解説しています。
本書は、グロービスMBAホルダーが提唱する「資産になる読書法」を紹介しています。著者は、読書をただの費用として終わらせず、スキルやお金に変える方法を教えています。内容は、選書術や要点を素早くつかむ整理法、著者の資産本コレクションなどから構成されています。読書を通じて一生モノの知的資産を築くための具体的な手法を学べる一冊です。
本書は新規事業の立ち上げを任された人向けに、アイデア発想から市場調査、ビジネスモデル構築、事業計画書作成、プレゼン、計画の見直しまでの最速手順を解説しています。90日間で事業計画書を完成させるための具体的な方法を提供し、特典として「マスター事業計画書」と「新結合カード」がダウンロード可能です。著者は新規事業の支援を多数行っている専門家です。
この本は、世界最高峰の経営コンサルティング会社で教えられている問題解決の考え方を、中高生向けに身近なストーリーとイラストを交えて解説しています。問題を小さく分けて考えることで解決策が見えてくることを学び、自ら考え行動する力を育む内容です。目次では、問題解決能力の習得、原因の見極め、目標設定と達成方法についての章が設けられています。著者は、経済を専攻した後にマッキンゼーでの経験を持つ渡辺健介氏です。
本書は、組織開発の重要性とその歴史、哲学、手法の変遷を探求し、組織の健全さや効果性を高めるためのコミュニケーション活性化を目的としています。著者たちは、組織開発が単なる手法ではなく、計画的かつ協働的なプロセスであることを強調し、実践事例を通じてその具体的なアプローチを示します。また、組織開発と人材開発の相互関係についても論じています。全体を通じて、組織開発の未来に関する対談も行われています。
本書は、リーダーシップ教育の専門家ジョン・P・コッターが、ハーバード・ビジネス・スクールや大手企業での講座を基に、リーダーシップの核心を解説しています。内容はリーダーシップとマネジメントの違いや企業変革の課題、権力と影響力の扱い方など多岐にわたり、最新の翻訳と2章の追加がなされています。著者はリーダーシップの実現を支援するコッター・インターナショナルの創設者であり、他の著者もリーダーシップや組織開発の専門家です。
本書は、PythonとDjangoの超入門書の改訂版で、Djangoのバージョン3に対応しています。CPythonとVC Codeを使用した環境で、Webアプリやサービスを作りたい初心者向けに構成されており、手順に従ってサンプルを作成しながら学べます。目次にはDjangoの基本から本格アプリケーション作成までが含まれ、巻末には初心者向けのPython入門も収録されています。著者はプログラミング初心者向けの書籍を多数執筆している掌田津耶乃氏です。
「改訂新版 超図解!新規事業立ち上げ入門」は、新規事業を立ち上げるためのフレームワークやテクノロジーを最新のものにアップデートし、知識ゼロの担当者向けに書かれた実用書です。7つのステップを通じて、アイデア創出から実行までの重要ポイントを網羅し、デザインシンキングやフェルミ推定、具体的なケーススタディも紹介しています。著者は中小企業診断士であり、多くの事業立ち上げの経験を持つ木下雄介氏です。
本書は、企業の新規事業を成功させるための手引きであり、特に「人との関係性」を重視しています。著者は「リレーショナルスタートアップ」というアプローチを提唱し、思い込みを打破し現実世界と接触する方法を示します。具体的な新規事業立ち上げのステップやアクションをまとめたマニュアルも収録されています。著者は新規事業支援の専門家で、長年の経験を基にした知見が詰まった一冊です。新規事業に行き詰まった際の参考にすることができます。
本書は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が2015年に東京ディズニーランドを超える集客数を達成した理由を探る内容です。USJの成功は「マーケティング」を重視する企業文化に起因し、これにより新しいアイデアが次々と生まれ、事業成功率が30%から97%に向上しました。著者の森岡毅は、USJのマーケティング戦略やその本質、成功に向けたキャリア形成についても言及しています。
学生の頃に読んで衝撃を受けた森岡さんの書籍。マーケティング職について間もない人に是非読んで欲しい。徹底した消費者視点というマーケティングの本質が詰まっている。これを読んで消費者視点のマーケティングについて学んだ後は数学的マーケティングとして確率思考の戦略論も合わせて読んで欲しい。人生で読んだ中でトップ10に入る名著。
本書は、Django3.2(LTS)を使用したWebアプリ開発手法を解説する書籍です。Djangoの基本的な設計・作成方法、フォーム作成、認証処理、データベース連携、クラウドとの連携、セキュリティについて一通り学べます。対象はPythonの基礎知識を持つフルスタックエンジニアで、Djangoは多くの機能を標準装備しており、開発が容易です。著者は大高隆氏で、フリーのソフトウェアエンジニアとして活動しています。
この書籍は、ドラッカーが提唱した「究極の質問」に基づく自己評価法を通じて、仕事と人生を変える方法を探求しています。著者フランシス・ヘッセルバインは、著名人の知見やミレニアル世代に向けた新しいコラムを加えた改訂版を提供しています。主要な内容は、ミッション、顧客、価値、成果、計画に関する5つの重要な質問を通じて組織の変革を促すものです。ドラッカーは経営思想家として多くのマネジメント概念を生み出し、影響を与えました。
本書は、チームの課題解決において「問い」のデザインが重要であることを説いています。良いアイデアや一体感が生まれない原因は、解決すべき課題が適切に設定されていないことにあります。著者は、企業や教育現場での複雑な問題を解決するための思考法やスキルを体系化し、創造的な対話を促進する方法を紹介します。ワークショップのデザインやファシリテーション技法を通じて、チームのポテンシャルを引き出し、イノベーションを促すことを目指しています。
この書籍は、シリーズ累計100万部を突破したJava入門書の改訂版で、最新のJava 11に対応しています。文法の基礎からオブジェクト指向までを丁寧に解説し、サンプルプログラムを通じて理解を深めることができます。初心者でも無理なく学べる内容で、プログラミングに挑戦したい人に最適です。著者は東京大学卒の高橋麻奈です。
この書籍は、顧客のニーズを把握し、売れる仕組みを構築するためのマーケティング戦略を解説しています。内容は、マーケティングの基礎から市場分析、自社と競合の比較、製品、価格、流通、プロモーション戦略に至るまで多岐にわたります。著者は漫画家の弘兼憲史と経営コンサルタントの前田信弘で、両者はそれぞれの専門知識を活かしてビジネス教育や執筆活動を行っています。
この書籍は、効果的なスライド作成やグラフ・チャートの描き方を解説しており、シンプルなスライドにするためのテクニックを紹介しています。内容は、スライドの基本構成、視覚化のためのグラフ・チャート作成方法、シンプルさを追求するためのヒント、そして練習問題を含んでいます。著者は、コンサルティング業界での経験を活かし、わかりやすいスライド作成を教えてきた専門家です。
この本は、アイデア創出からニーズ発見、分析・検証、企画、プレゼン、改善までの一生使えるスキルを、基本、図解、事例を交えて丁寧に解説しています。各章では具体的な手法やフレームワークが紹介されており、さまざまなビジネスシーンで活用可能です。
本書では、著者の西口一希氏が「顧客起点マーケティング」の重要性を説き、特に一人の顧客(N1)の分析を通じて効果的なマーケティングアイデアを導き出す方法を紹介しています。著者はP&Gやロート製薬、スマートニュースでの成功経験を基に、顧客ピラミッドや9セグマップといったフレームワークを用いて、ターゲット顧客の可視化や競合分析を行う手法を解説します。具体的には、未購買顧客を顧客化し、ロイヤル顧客に育てるための戦略や、デジタル時代における顧客分析の重要性についても触れています。
期待度が高かっただけあって、それほど学びがなく残念だった。顧客一人にフォーカスしたN1分析は確かにデータ分析の初期シーンでよく使うので考え方としては分かるが、そこからマーケティングに転化していくイメージがあまり湧かなかった。
本書では、成功するビジネスモデルを55種類に分類し、システマチックにビジネスモデルを構築する方法を紹介しています。スイス・ザンクトガレン大学のガスマン教授の研究に基づき、企業文化に適した革新手法が解説されています。具体的な事例として、ネスレ社が複数のビジネスモデルを組み合わせて成功を収めたことが挙げられています。内容は、ビジネスモデルの基本概念や変革管理、55の勝ちパターンの詳細に分かれています。企業はこれらの知識を活用して自社のビジネスモデル革新に挑戦することが期待されています。
この書籍は、仮説思考を用いることで作業効率を大幅に向上させる方法について解説しています。著者の内田和成は、BCGコンサルタントとしての経験を基に、仮説を立てることの重要性やその検証方法、思考力を高める方法を紹介しています。目次には、仮説思考の概念から始まり、実践的なステップが示されています。内田は東京大学卒で、経営戦略の専門家としての経歴を持っています。
明快なフレームワークに基づいた的確な解説により、定評を得てきた入門テキストを新版化。電子商取引の発展、コロナ禍の影響などを… 明快なフレームワークに基づいた的確な解説により,定評を得た入門テキストを新版化。マーケティング戦略の立案に必要な知識と手順を説き明かす。電子商取引の発展,コロナ禍の影響など,最新動向も取り入れ,事例やコラムを更新した,新しい時代のスタンダード。 序 章 マーケティングへの招待 第1部 環境分析 第1章 競争環境 第2章 市場環境 第3章 流通環境 第2部 マーケティング戦略形成 第4章 市場機会の探索と評価 第5章 需要多様性への対応 第6章 価値提供と競争優位 第7章 新製品開発戦略 第8章 製品ライフサイクルとマーケティング戦略 第3部 マーケティング・ミックスの策定 第9章 製品政策 第10章 価格政策 第11章 プロモーション政策 第12章 流通チャネル政策 さらなる学習のための文献ガイド 参考文献一覧
本書は、著者が提唱する32の思考法やキーワードを通じて、戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力などの基本概念とその活用法を解説しています。内容は、基本的な思考法、二項対立の考え方、コンサルタントのツール、AIとの比較、無知の知の重要性に分かれており、それぞれの章で「何か」「なぜか」「どう使うか」を明確にしています。著者はビジネスコンサルタントであり、思考力を高めるための実践的なアプローチを提供しています。
本書は、少人数で効率的にBtoBマーケティングを行うための基礎知識と施策を解説した入門書です。初心者でも理解しやすいように図版を多用し、オンラインを活用したリードの掘り起こしや育成の手法を紹介しています。著者は実務経験豊富で、具体的な事例を交えながら実践的なマーケティング手法を伝授します。BtoB企業が売上を伸ばし、部門間の業務をスムーズにするための知識が得られます。
本書『「学習する組織」入門』は、MIT発の組織開発メソッド「学習する組織」を紹介する入門書で、日本の第一人者が実践的に解説しています。変化に柔軟に対応し、持続的成長を実現するための「ダブル・ループ学習」や5つの「ディシプリン」を通じて、個人と組織の成長を促進します。各章には事例や演習が含まれ、実践上の課題にも触れながら、未来の組織とリーダーシップについても考察しています。著者は組織開発の専門家であり、広範な知見を基にした内容となっています。
この書籍は、戦略分析の基本フレームワーク(3C、5つの力、バリューチェーンなど)を理解し、ミドルリーダーの行動を通じてその実用性を探る内容です。戦略のパターン(差別化、コストリーダーシップ、集中戦略)や重要な戦略キーワード(イノベーションのジレンマ、プロダクトライフサイクル、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントなど)についても解説されています。著者はグロービス経営大学院の教授で、戦略や思考に関する教育を行っています。
この書籍は、経営学者やコンサルタントがビジネスシーンで活用する50のフレームワークを100の図表で解説しています。クリティカルシンキング、戦略立案、マーケティングなどの思考ツールを直感的に理解できる内容で、説得力ある主張を支える方法が紹介されています。著者はグロービスの経営大学院教授で、経営戦略やマーケティングの専門家です。
この書籍は、現代のビジネスパーソンに必須のマーケティングスキルを、主要な9つのフレームワークとケーススタディを通じて学ぶ内容です。各章ではニーズの把握から始まり、環境分析、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、製品戦略、価格戦略、流通戦略、コミュニケーション戦略に至るまで、マーケティングの基本的な流れと実践法を解説しています。著者の金森努は、30年以上のマーケティング経験を持つコンサルタントで、顧客視点の重要性を強調しています。
この書籍は、戦略コンサルタントのスキルを学ぶための指南書で、問題解決の基本的な考え方をチャートを用いてわかりやすく説明しています。内容は、思考法(ゼロベース思考や仮説思考)、技術(MECEやロジックツリー)、プロセス(ソリューション・システム)、実践(具体的な活用方法)に分かれており、企業事例も新たに紹介されています。著者は齋藤嘉則で、経営コンサルタントとしての豊富な経験を持っています。
本書は、日本企業の組織開発に関する実践的な方法論を提示しています。著者の加藤雅則は、17年の経験を基に、経営トップから始め、各層の合意を生み出し、当事者主体で進めることの重要性を強調しています。業績は好調でも、組織の一体感や信頼度が低下している現状を踏まえ、効果的な組織変革を促すための対話や実践例を紹介しています。
この書籍は、ビジネスにおけるフレームワークを学び、理解から実践、カスタマイズまでのスキルを向上させることを目的としています。目次には、基本的なフレームワークや問題発見、課題分析、評価・解決の手法が含まれており、業務改善に役立つ内容が整理されています。著者は外資系コンサルタントで、システム運用改善やファシリテーションに精通しています。
本書は、新規事業やDXにおける成功の鍵である「プロダクトマーケットフィット(PMF)」について解説しています。多くの新規事業が市場に適した製品を提供できず失敗する中、PMFを達成するための具体的な方法や、14社の事例を通じた実践的なノウハウを紹介しています。新規事業の責任者やプロダクトマネージャーにとって必読の一冊です。
本書は、売れない製品が生まれる理由を分析し、成功確率を高めるためのマーケティング理論を体系化したものです。著者は豊富な事例を基に、マーケティングの失敗パターンや理論(U&E、イノベータ理論、プロダクトライフサイクル理論など)を紹介し、実践的なノウハウを提供しています。著者は森行生で、長年のコンサルティング経験を持つ専門家です。
本書は「論理的思考」をテーマに、思考の原則、論理の方法、分析のテクニックを体系的に解説しています。三部構成で、思考の基本から合理的な分析手法までを平易に実践的に紹介しています。著者は経営コンサルタントの波頭亮氏で、東京大学卒業後、マッキンゼーを経て独立し、戦略系コンサルティング会社を設立しました。
主人公まりもは、仕事の失敗や失恋から癒しを求めて帰省するが、実家の饅頭屋「たまや」は倒産の危機にあり、結婚話も持ち上がる。そこで、マーケティングの妖精ロジーとエモーが現れ、彼女と共に「たまや」を救おうと奮闘する。物語は、マーケティングの基本を楽しく学びながら、顧客を呼び戻す方法を探る内容。著者はマーケティングの専門家で、実績を持つ安田貴志。
数学的にマーケティングを学ぶのであれば絶対にこれ。というかこれくらいしか数学的観点でここまで詳しくマーケティングについて学べる書籍はない。森岡さんがどうやってUSJを立て直したのかが数学的な観点から学べる。「USJを変えたたった1つのこと」と合わせて読むことでマーケティングのいろはが身につくはず。
本書は、ビジネスパーソン必見のマーケティング理論を50冊にまとめ、企業事例を交えて解説しています。著者は元IBMのマーケティングマネジャーで、古典的な理論から最新のトレンドまで幅広くカバー。理論の理解を深めるだけでなく、実践的な活用方法も提供しており、忙しいビジネスパーソンに最適な内容となっています。
この書籍は、データを活用した新規事業の立ち上げにおける課題と成功のためのノウハウを解説しています。データそのものは価値がなく、陳腐化や模倣のリスクがあるため、効果的なビジネスモデルが必要です。著者たちは、データビジネスのアイデア創出から事業化、収益化までの思考法を段階的に説明し、主要9業界の分析や未来予測も提供しています。データビジネスの成功率を高めるための具体的な方法が満載です。
田所雅之氏の最新刊は、日本に不足している起業家を支える「起業参謀」の重要性を強調し、参謀人材を育成するための体系的な知識やフレームワークを提供する初の書です。内容は、起業参謀の価値、思考法、プロセス、そして「5つの眼」と呼ばれるフレームワークを通じて、起業家と参謀に必要なマインドやスキルを解説しています。著者は、豊富な経験を持つ経営コンサルタントであり、スタートアップ支援に力を入れています。
本書は、デジタル化が進む世界の本質を解説し、日本企業がオンラインを活用する従来のアプローチを見直す必要性を訴えています。著者たちは、オフラインが存在しない「アフターデジタル」の時代を提唱し、すべてのビジネスがオンライン化される未来を描いています。内容は、デジタル化の現状、OMO型ビジネスの重要性、具体的な事例を通じた思考訓練、日本のビジネス変革に焦点を当てています。デジタル担当者だけでなく、未来を拓くすべてのビジネスパーソンに向けた一冊です。
デジタルが主体の時代に突入しどのように顧客行動が変わっていくかを中国の事例をふんだんにまじえながら教えてくれる良書。デジタル時代のマーケティングをおさえるためにぜひ読んでおきたい1冊
本書は、未顧客(買わない人)を理解し、マーケティング戦略を通じて市場を拡大するための教科書です。著者は、未顧客へのアプローチが重要であることを強調し、海外の研究に基づく理論や実践的な手法を紹介しています。内容は、未顧客理解の重要性、無関心を動かす技術、マーケティング戦略、利用機会の創出、ブランド再解釈のケーススタディなどを含み、ビジネスパーソンにとって必携の一冊です。
この書籍は、Webマーケティングからデジタルマーケティングへの入門書で、ネット活用の基本を解説しています。目次には、ページビューの重要性や顧客理解、トラブル対応などが含まれています。著者はデジタルコンテンツ制作会社の創業者であり、複数の企業でマーケティングに携わった経験を持つ村上佳代と、漫画家の星井博文です。
ロジカルシンキングを法律を整理して理解するツールとして解説。新たに、事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法も加わる! ロジカルシンキングを法律を整理して理解するツールとして解説。新たに、事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法も加わる! 序章 なぜ法律をロジカルシンキングの視点からみるのか ──法律学におけるロジカルシンキング 第1章 論理的思考方法と説明方法――ロジカルシンキング総論 1 ロジカルシンキングの意味 2 狭義のロジカルシンキング 3 ロジカルプレゼンテーション 4 まとめ 第2章 論理的思考と図表作成の方法――狭義のロジカルシンキング 1 狭義のロジカルシンキングの思考方法 2 狭義のロジカルシンキングの図表作成手法 第3章 法律学におけるロジカルシンキング――MECE・法的三段論法・リーガルマ インド 1 法律学におけるMECEのフレームワークとなる基礎概念・用語 2 法律学におけるロジカルシンキング・プレゼンテーションの基本――法的三段論法 3 法律学全体をカバーする基本理念――リーガルマインド 4 法律学におけるロジカルシンキングの重要性 第4章 民法・私法の基本原則と民法典の体系――民法の全体構造 1 民法の基本原理──民法の三大原則とその変容 2 信義誠実の原則(信義則)と権利濫用禁止の原則 3 民法典の構造──パンデクテン構造 4 民法におけるMECEのフレームワーク 5 民法におけるMECEを用いたフレームワークのまとめ 第5章 時系列に基づく民法の体系──民法各論 1 はじめに――民法における成立要件から対抗要件 2 契約の成立要件 3 契約の有効要件 4 契約の効果帰属要件 5 契約の効力発生要件 6 対抗要件 7 まとめ COLUMN① 教科書の読み方 第6章 法律の構造と条文の読み方――条文の形式的な意味 1 法令・条文の形式的意味の理解の必要性 2 条文の形式的意味の理解のために必要な知識 3 条文の形式的意味の確定から実質的意味・適用範囲の確定へ 第7章 条文解釈の方法──規範の実質的内容の検討 1 法解釈と条文解釈の意義 2 法的三段論法と条文解釈 3 法律要件と法律効果 4 条文解釈の身近な具体例 5 条文解釈の一般理論 COLUMN② 民法の歴史と民法を作った人々 第8章 法的文章の作成方法──ロジカルプレゼンテーション 1 ロジカルプレゼンテーション総論 2 ロジカルプレゼンテーションの内容に関する必要条件 3 ロジカルプレゼンテーションの方法に関する必要条件 第9章 ロジカルシンキングに基づく答案作成──事例の図式化と答案構成の手法 1 事例を図式化する方法 2 答案構成の方法 COLUMN③ 答案作成に関するポイント あとがき――法律学習のポイント 事項索引
「顧客獲得実践会」は、10年以上前に2万人以上が参加し、3000億円以上の売上増を達成した伝説的な集団です。この書籍は、彼らの成功事例を基にしたマーケティングの原則をまとめたもので、感情マーケティングや売上アップの方法などが紹介されています。著者は経営コンサルタントの神田昌典氏で、彼は顧客獲得実践会を創設し、現在は「次世代ビジネス実践会」を運営しています。
この書籍は、情報の解像度を高める方法について解説しています。スタートアップの現場から得た知見を基に、解像度を上げるための視点や診断方法、行動の重要性、課題や解決策の深さ・広さ・構造・時間の観点からの考察を行っています。また、実験と検証を通じて未来の解像度を向上させる方法についても触れています。著者は東京大学の馬田隆明氏で、スタートアップ支援やアントレプレナーシップ教育に従事しています。
解像度についての解像度が上がる本。解像度には「深さ」「広さ」「構造」「時間」の4つの視点があり、「深さ」が足りていないことが圧倒的に多い。解像度を上げるためのリサーチ方法や顧客インタビューについて学べる。起業する上で重要なエッセンスが詰まっており起業家が読むべき一冊だと思う。
本書は、企業が10年後に生き残るための抜本的な変革を促す内容です。著者は「時間軸のトランスフォーメーション戦略」を提唱し、経営戦略の構想や実行のポイントを解説しています。成功事例としてリクルートHDやソニーグループなどを分析し、経営理論を活用した変革の成功法則を示しています。特に、長期的なポートフォリオマネジメントや市場創造戦略、カルチャーの変革など、5つの成功ポイントが強調されています。
本書は、デジタル時代におけるマーケティングの基本を解説し、企業の「売りたい気持ち」を消費者の「買いたい気持ち」に変える方法を提案します。新規顧客と継続顧客の育成、デジタルコミュニケーションの重要性を強調し、顧客の状態に応じたアプローチを紹介。著者は、実践的なデジタルマーケティングのメソッドを10項目にまとめ、売上成長のための基本的な考え方を提供します。
本書は、業務システムやアプリ開発における成功の鍵である「要件定義」の重要性を解説しています。要件定義は、ユーザーと開発者の合意を形成し、UIや機能、データを明確にするプロセスですが、しばしば軽視され、プロジェクトが迷走することがあります。豊富な図解を用いて、要件定義の知識をわかりやすく提供し、さらに「プロセス設計」や「システム設計」についても触れ、業務改善や最新技術の活用に向けた具体的な手法を示しています。読者は、システム設計を自信を持って進めるための理解を深めることができるでしょう。
本書は、現代のマーケティング・リサーチの基礎を解説した入門書で、ビッグデータや質的データの活用方法を紹介しています。実務に役立つ内容が豊富で、正しい顧客理解やマーケティング施策の立案・評価に焦点を当てています。各章ではリサーチの進め方やデザイン、質的・量的調査の方法と分析、今後の展望について詳しく解説されています。著者は、慶應義塾大学と早稲田大学の教授で、それぞれ学術的な背景を持っています。
本書は、ビジネスで役立つ20のフレームワークを紹介し、問題解決のスキルを向上させるための実用的なガイドです。コンサルタントの経験を基にしたフレームワークは、思考法やマーケティング、組織運営など多岐にわたり、日常の仕事や就職活動、恋愛にも応用可能です。特に、初心者でも理解しやすい事例を交えながら解説されており、フレームワークを使うことで仕事の効率が向上することを目指しています。巻末には練習問題とワークシートも付いています。
この書籍は、デジタルマーケティングにおける「定石」を整理し、成果を上げるための施策パターンを詳しく解説しています。内容は、デジタルの特性や限界、各フェーズにおける定石の理解、そしてそれをビジネスモデルに適用する実践方法に分かれています。著者は、デジタルマーケティングの専門家であり、AIを活用した分析ツールの開発にも携わっています。
ロジカルな「らくがき」による"全脳思考""見える化"が可能にした、ロジカルシンキング最短・最速習得術。 序章 ロジカルシンキングは、「これだけ!」で大丈夫-誰でも、カンタンに、最短最速で、ロジカルシンキングが身につく! 第1章 ピラミッド1「削る」-ロジカルシンキングを知る 第2章 ピラミッド2「足す」-一流のプロの思考を借りる 第3章 ピラミッド3「強化する」-頭が良くなる「らくがき」、マインドマップを知る 第4章 ピラミッド4 ロジカルな「らくがき」-4Stepsの概説‐ピラミッドの全体像(システム)を確認する 第5章 Step1「見わたす」-「ソリューション・ボックス」を準備する 第6章 Step2「見える化」-「ソリューション・ボックス」に思考の断片を洗い出す 第7章 Step3「構造化」-「ソリューション・ツリー」で思考のパズルを完成させる 第8章 Step4「物語」-「ストーリー・ピラミッド」で「ひとつの物語」に結晶化する 終章 ラストシーン-明日から使う「4Steps」
本書は、ダイレクト・マーケティングの専門家ダン・ケネディが、効果的なマーケティング戦略を伝授する内容です。具体的なテクニックや原則を解説し、「究極のマーケティングプラン作成シート」が付属しています。目次には、メッセージの組み立て方、ターゲット選定、口コミ促進、短期間での売上増加方法などが含まれています。著者は多くの企業とコンサルタント契約を結び、幅広い分野で活躍しています。
本書は、ユーザーを知るためのインタビュー技術を学ぶ実践テキストで、初心者から経験者まで幅広い読者を対象としています。内容はインタビューの基本知識、計画、準備、実施、考察の各フェーズに分かれており、特にオンラインインタビューにも対応しています。実践的なノウハウやサンプルテンプレートも提供されており、読者がインタビューをより効果的に行うための支援をしています。改訂版であり、最新の状況に合わせて内容が更新されています。
この本は、セールスやマーケティングにおける顧客心理の重要性を30の法則で解説しています。著者は、テレビ通販での成功経験を基に、心理的トリガーを用いて営業成績を向上させる方法を示しています。具体的なエピソードを通じて、複雑な心理を理解しやすく伝え、読者が実践できる内容となっています。メンタリストDaiGo氏や世界一のセールスマン、ジョー・ジラード氏も推薦しており、実践的な知識を得るために読む価値がある一冊です。
人気ウェブ連載「ノヤン先生」が書籍化され、実践的かつアカデミックな内容をわかりやすく解説しています。目次には、マーケティングの巨匠、フレームワーク、顧客評価、チャネルとツール、組織とキャリア、学び方などが含まれています。著者はプロフェッショナルマーケターの庭山一郎で、シンフォニーマーケティング株式会社を設立し、顧客管理サービスを提供しています。
本書では、43社の先駆的なマーケティング戦略を分析し、価格競争に巻き込まれないための「6つの戦略スキーム」を紹介。著者は、マーケティング戦略の立案や環境分析、セグメンテーション、ブランド戦略、サービス差別化、イノベーションに関する視点を提供し、実践的な思考プロセスを解説しています。著者は、マーケティング戦略の専門家であり、多くの企業のコンサルティングを行っています。
本書は、新規事業のアイデアを見つけ、社内承認を得るためのメソッドを紹介しています。著者は元リクルートのマネジャーで、具体的なステップとして、事業検討の準備、テーマ設定、ビジネスチャンスの発見、事業企画の立案、承認取得のプロセスを解説しています。著者の石川明は新規事業インキュベータとしての経験を持ち、多くの事業案に関与してきました。
本書は、未来シナリオを用いた未来洞察手法について、経営学やマーケティング学を基盤に、認知科学やデザイン学の視点を融合させた学際的なアプローチを提供する。内容は、未来を洞察する思考法、スキャニング手法、社会技術問題のシナリオ作成、シナリオ評価、アイデア生成の違い、ユーザー視点の導入によるアイデアの質向上、情報の多様性の影響、未来洞察による新商品開発とイノベーションなど多岐にわたる。著者は一橋大学の鷲田祐一教授で、マーケティングとイノベーション研究の専門家である。
この書籍は、8つの身近なストーリーを通じてマーケティングの基礎を学ぶ内容です。各章では、腕時計のCM、ベンツの広告、北海道でのマンゴー栽培、赤字のプリン屋、セブンイレブンの立地、女性の財布、きゃりーぱみゅぱみゅの成功、古本屋の利益などを例に、バリュープロポジションや商品戦略、価格戦略などのマーケティング理論を解説しています。著者は、マーケティング戦略アドバイザーの永井孝尚氏で、専門用語を使わずにわかりやすくマーケティングの本質を伝えることを目指しています。
本書は、データに基づくマーケティングの重要性を説く教科書で、アマゾンのような企業が実践している手法を紹介しています。著者は15の指標を通じて、データを活用した効果的な意思決定の方法を解説し、マーケティングの成果を向上させるための具体的なアプローチを提案しています。経営者やマーケティング幹部にとって必読の内容です。著者は、ノースウェスタン大学の教授やコンサルタントとしての豊富な経験を持つ専門家たちです。
ジェフ・ベゾスが全社員にまず読ませる書籍ということで読んでみたが、内容はありきたりのものでそれほど目新しさがなかった。とりあえず適切なKPIを設定してそれをトラッキングできるようにせよ!ということ。
人を説得するためには論理的な思考法とレトリックが不可欠。本書にしたがって頭のトレーニングをつめば、論理的感覚が自然に身につく。あなたの日本語に磨きをかける確かな方法がここにある。 1 推論のトレーニング-論理学から(論理的に考えるための基本 論理学と日常言語の落差 推論の実際) 2 論証のトレーニング-レトリックから(立論と反論 レトリック的推論) 3 論証と反論(論証の型 準論理的論証 事実的論証) 4 誤謬推理と詭弁
多くの一流企業で行なっている研修の内容がベースになっています。対話形式になっているので、本物の研修を受けているような臨床感を味わいながら、どんどん読み進めることができます。 1 なぜ理論的に考える必要があるのか?(ビジネスを「変える」ために論理思考力が必要になる ビジネスを「変える」にはより良いアイデアが不可欠 ほか) 2 論理思考は「言葉」である(論理には「言葉」が欠かせない 言葉とは境界線である ほか) 3 論理思考は「引き出す」である(ビジネスは「しまった」の思い思わせ合い アイデアを引き出すのはむずかしい ほか) 4 論理思考は「広げる」である(ゼロベース思考はむずかしい 広く考えるための論理思考とは ほか) 5 論理思考を実践してみよう(直感より多くのアイデアが出せればOK ツリーの3つの種類を知る)
ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。
このムックは、デジタルマーケティングの最新動向を41のキーワードやケーススタディ、トレンド分析を通じて解説する内容です。第9弾となる今年の版では、脱クッキー対策やカスタマーサクセスなどのトレンド、メタバースやNFTなどの基本・先端技術キーワード、企業ケーススタディ、米国の最新事情、人気パッケージ比較調査、データとランキングが含まれています。また、電通デジタルの川上社長やスターバックスの森井CMOへのインタビューも掲載されており、マーケティングに関心のあるビジネスパーソンや学生に役立つ内容となっています。
「フレームワーク」に関するよくある質問
Q. 「フレームワーク」の本を選ぶポイントは?
A. 「フレームワーク」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「フレームワーク」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ビジネスフレームワーク図鑑 すぐ使える問題解決・アイデア発想ツール70』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで157冊の中から厳選しています。
Q. 「フレームワーク」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「フレームワーク」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



















![『ビジュアル ビジネス・フレームワーク[第2版] (日経文庫)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51MAXgtMdzL._SL500_.jpg)



























![『社内新規事業コンパス――イノベーションを起こすための[リレーショナルスタートアップ]の技法』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51v2SzQgCEL._SL500_.jpg)




![『経営者に贈る5つの質問[第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41kbybZMXVL._SL500_.jpg)



![『Djangoのツボとコツがゼッタイにわかる本[第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51pR8iDijvL._SL500_.jpg)










































![『グロービスMBA集中講義 [実況]ロジカルシンキング教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51kjOsY1MmS._SL500_.jpg)










































![『[ポケットMBA]ロジカル・シンキング 互いに理解し、成果につなげる! (PHPビジネス新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51fR1higP5L._SL500_.jpg)






![『[練習問題アプリ付き]問題解決のためのロジカルシンキング』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51o5xV8-Q6L._SL500_.jpg)

 (スッキリわかるシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51UtDR4w6KL._SL500_.jpg)