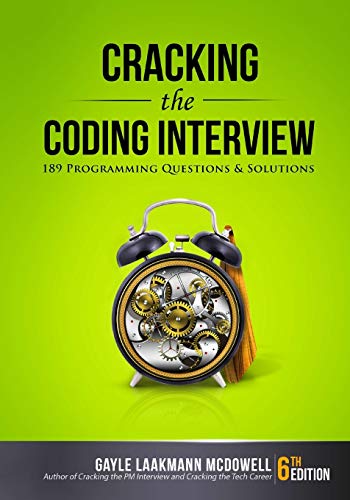【2025年】「コンピュータサイエンス」のおすすめ 本 129選!人気ランキング
- みんなのコンピュータサイエンス
- 決定版 コンピュータサイエンス図鑑
- 教養としてのコンピューターサイエンス講義 第2版 今こそ知っておくべき「デジタル世界」の基礎知識
- リーダブルコード ―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック (Theory in practice)
- コンピュータシステムの理論と実装 ―モダンなコンピュータの作り方
- コンピュータはなぜ動くのか 第2版 知っておきたいハードウエア&ソフトウエアの基礎知識
- コンピュータサイエンス入門[第2版]: コンピュータ・ウェブ・社会 (Computer Science Library 1)
- 確かな力が身につくJavaScript「超」入門 第2版
- 解いて論理的思考力を身につける はじめてのコンピュータサイエンス (くもんこれからの学び)
- スッキリわかるJava入門 第3版 (スッキリわかる入門シリーズ)
本書は、現代社会におけるコンピュータの重要性を踏まえ、コンピュータサイエンスの基礎知識を8つのジャンル(基礎、効率、戦略、データ、アルゴリズム、データベース、コンピュータ、プログラミング)に絞って解説します。エンジニアや学生が効率よく全体像を把握し、問題解決能力を向上させるための内容が盛り込まれています。コンピュータサイエンスを学ぶ際の入門書として適しており、理論と実践の橋渡しを強化します。
この書籍は、コンピュータ科学の基本を幅広くカバーしており、ハードウェア、プログラミング、ネットワーク、ソーシャルメディア、デジタル時代の課題について解説しています。著者たちは教育者や研究者であり、コンピュータ科学教育やプログラミングに関する専門知識を持っています。内容はコンピュータサイエンスの概要から始まり、具体的な技術や倫理的な問題に至るまで多岐にわたります。
本書は、デジタル時代に必要な基礎知識を身につけるためのガイドで、プリンストン大学の講義を基にしています。第2版では「データ」を新たに加え、4部構成となり、プログラミング言語としてPythonも紹介されています。著者は伝説的な計算機科学者ブライアン・カーニハン氏で、一般向けに分かりやすく説明されています。コンピューター、ソフトウェア、インターネット、データの仕組みを理解することで、デジタル社会をより良く生きるための知識を提供します。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
『コンピュータはなぜ動くのか』の改訂第2版は、コンピュータの基本知識を包括的に解説する書籍です。ハードウェア、ソフトウェア、データベース、ネットワーク、セキュリティについて、入門者からベテランエンジニアまで幅広い読者に向けて内容が更新されています。具体的には、プログラムはPython、データベースはMySQL、暗号化は公開鍵方式に変更されています。全12章で構成され、コンピュータの仕組みやプログラミング、データベース、ネットワークの理解を深めることができます。
この入門書は、コンピュータに関する基礎知識を身につけるためのもので、内容がアップデートされ、章末問題に解答例が追加されています。取り扱うテーマには、コンピュータの歴史、情報システム、2進数、マイクロプロセッサ、オペレーティングシステム、プログラミング、データベース、ビッグデータ、機械学習、インターネット、ウェブ、情報倫理とセキュリティが含まれます。著者は増永良文で、情報処理学会やデータベース学会の重要な役職を歴任してきました。
この書籍は、JavaScriptを初めて学ぶ人や過去に挫折した人向けに、実践的なサンプルを通じて基礎力を身につけることを目的としています。楽しいサンプルを提供し、初学者がつまずくポイントを丁寧に解説することで、挫折を防ぐ内容になっています。第2版では新しいECMA Scriptの機能を取り入れ、情報を最新のものにアップデートしています。特にWeb業界に興味がある人やフロントエンドエンジニアを目指す人におすすめです。著者はUIデザイナーであり、実務経験を活かした内容が特徴です。
本書は、コンピュータサイエンスの基礎を楽しく学ぶための入門書です。論理演算や情報セキュリティなど、コンピュータの動作を理解することを目的としており、高校での情報科目や大学入試での出題が増加している背景があります。問題を解くことで論理的思考力や読解力を養い、専門知識がなくても楽しめる内容になっています。対象は小学校高学年から大人までで、コンピュータを効果的に使うための考え方を学ぶことができます。
本書は日本初のデータサイエンス学部(滋賀大学)が、身近な事例を通じてデータ分析をわかりやすく解説した一冊です。データ分析が社会や企業で必要とされる中、初心者でも理解できる内容で、情報1・情報2を学ぶ学生にも最適です。具体的な事例を通じて、手軽なデータ分析から本格的な分析手法までを紹介し、豊富な図表で視覚的に理解を助けます。また、企業や行政のデータ分析導入事例も掲載されています。
このプログラミング本は、全世界で700万部以上売れた決定版で、初心者から経験者まで幅広く学べる内容が特徴です。著名人からの推薦も多く、プログラミングを楽しく学べるよう工夫されたイラストや手書きノート式のデザインが魅力です。内容は、プログラミングの歴史や基礎から始まり、ScratchやPythonを用いたプログラミング、データ分析、アルゴリズムなど多岐にわたります。この一冊で一生使えるスキルが身につくことを目指しています。
本書は、数学の基礎を理解し単位を取得するための講義と問題演習を提供します。内容は高校の復習から始まり、1変数および2変数の微分・積分、極限、ε-δ論法まで幅広くカバーしています。著者の石井俊全は数学教育に豊富な経験を持ち、様々な分野の数学を教えています。問題はPDF形式で配布され、繰り返し解くことで理解を深めることができます。
本書は、米国の大学で広く使用されているコンピュータ科学の教科書で、コンピュータ科学を抽象化ツールの階層構造として統一的に説明しています。内容はデータストレージ、データ操作、オペレーティングシステム、ネットワーク、アルゴリズム、プログラミング言語、ソフトウェア工学など多岐にわたり、全12章から構成されています。再刊行にあたり誤植が修正されています。
この書籍は、プログラミングの理解を深めるために、視覚的な疑似体験やPythonを用いた実践的なプログラム作成を通じて学ぶ内容です。目次には、プログラミングの基本概念、流れ、共通の真髄、疑似体験、Pythonによるプログラミング、スキルアップのための知識、学ぶべき言語選び、今後の学習方法が含まれています。著者は、元デンソーのソフトウェア開発者である立山秀利氏です。
この書籍は、コンピュータの基本を理解するための入門書であり、坂村健教授が解説しています。コンピュータ技術の進化を背景に、「情報とは何か」「コンピュータとは何か」を学ぶ重要性を説いています。目次には、情報理論やプログラミング、オペレーティングシステム、インターネットの信頼性など、コンピュータに関するさまざまなテーマが含まれています。
『プログラムはなぜ動くのか』の改訂第3版は、プログラムの動作原理をわかりやすく解説し、基礎知識を身につけることを目的としています。内容は新しい製品やツールに更新され、初心者でも理解しやすいように加筆されています。特に、C言語と新たにPythonを用いた機械学習に関する章が追加されており、プログラミングの本質を探求することができます。全体を通して、プログラムの仕組みや環境について詳しく説明されています。
この書籍は、領域特化アーキテクチャについての新しい章を追加し、具体的な実用DSA(Google Tensor Processing Unit、Google Pixel Visual Core、Intel Nirvana Neural Network Processor、Microsoft Catapult)を解説しています。また、ウェアハウススケールコンピューティングに関する章も最新の情報で更新されています。著者には、スタンフォード大学名誉学長のジョン・L・ヘネシーと、Googleのデイビッド・A・パターソンが含まれています。
この文章は、トーマス・J・ワトソン・ジュニアの自伝に関する内容で、彼の経歴やIBMでの役割、反骨精神について述べています。ワトソン・ジュニアは、父の影響を受けながらも独自の道を歩み、戦争を経て自信を持ってIBMに戻り、最終的にはCEOに就任し、社会に貢献しました。また、彼の成長過程や経営哲学が紹介されています。著者はピーター・ピーターで、翻訳は高見浩が担当しています。
この書籍は、プログラムを作成する人向けに、基本的なアルゴリズムとデータ構造を解説しています。高速で実用的なアルゴリズムを中心に、動作原理や注意点、計算時間を詳細に説明し、図や具体的なプログラムを豊富に掲載しています。プログラム例は主にPascalで示され、一部はCやCommon Lispでも提供されています。目次には、アルゴリズムの計算量、探索、整列、グラフ、文字列アルゴリズム、難しい問題などが含まれています。
この本は、プログラミング教育の重要性を説き、子どもたちに論理的思考や創造力を育む方法を紹介しています。著者は、企業の成功にプログラミングが不可欠であることを強調し、親子で楽しく学ぶ方法やプログラミング教室の現状、基礎を理解させるためのアプローチを提供しています。著者は松林弘治で、技術と教育に関する豊富な経験を持つ専門家です。
この文章は、コンピュータ関連のさまざまな重要なアイデアや技術についての章立てを紹介しています。内容は、検索エンジンのインデクシングやページランク、公開鍵暗号法、誤り訂正符号、パターン認識、データ圧縮、データベース、一貫性、デジタル署名、決定不能性など多岐にわたります。著者はコンピュータ・サイエンスの教授であり、翻訳者も多くの書籍を手掛けています。
この書籍は、現代人にとっての基礎教養としてプログラミングの入門を提供します。難しい数式は不要で、まずは紙と鉛筆を使って学ぶことが推奨されています。目次には、プログラムを身につけるコツ、プログラムの設計方法、コンピュータの機能、実際のプログラミング手法が含まれています。著者は山本貴光で、文筆家やゲーム作家として活動しています。
この書籍は、Webサイト制作の決定版としてリニューアルされ、HTMLとCSSの基本から最新技術までを体系的に学べる内容です。著者Manaは、Webデザインの専門家であり、初心者向けに手を動かしながら学べるテクニックを提供しています。モバイルファーストやアニメーションなどのトレンドも取り入れ、5年間の最新情報が追加されています。本書は、Webサイト制作を始めたい人や美しいデザインを学びたい人に最適です。
本書は、Linuxの基本的な仕組みや動作をフルカラーで解説したもので、プロセス管理、メモリ管理、ファイルシステム、仮想化、コンテナなどのテーマを含みます。豊富なグラフや図解を用いて、実験結果を視覚的に示し、難しい理論に踏み込まずに理解を助けます。また、ソースコードはC言語からGo言語とPythonに更新され、現代のLinuxの理解を深める内容となっています。著者はLinuxカーネルの開発に従事した経験を持つ専門家です。
データゼネラルの新機種ハードウェア・ファームウェア開発に密着したノンフィクション。著者はトレイシー・キダーで、彼は『超マシン誕生』でピューリッツァー賞を受賞。目次には、開発プロセスやチーム作り、展示会などのエピソードが含まれている。
この文章は、物理学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には静力学、運動の法則、保存則、振動、相対運動と座標変換、万有引力が含まれています。著者は前野昌弘で、神戸大学卒業後、大阪大学で博士号を取得し、琉球大学で教員を務めています。
この入門書は、オペレーティングシステムの基本概念を平易に解説しています。内容は、I/Oデバイス、プロセスとスレッド、スケジューリング、相互排除と同期、メモリ管理、ファイルシステム、ネットワーク、セキュリティ、そしてWindowsオペレーティングシステムのケーススタディにわたります。著者は、河野健二で、情報科学の専門家です。
橋元淳一郎先生による『電磁気学』は、大学生向けの試験対策本で、物理の理解において「イメージ」を重視した解説が特徴です。著者は受験物理の人気講師で、厳選された問題に挑戦することで試験対策も万全にできます。内容は、電磁気学の基本からマクスウェルの方程式まで幅広くカバーしており、理解を深めるための数学の手引きも付いています。
「小学生のための数学入門、大人のための再入門」の書。 「小学生のための数学入門、大人のための再入門」の書。復刊に際し、三部構成の一冊に、全イラスト・事例を時代に合わせてリメイクした。自然数の無限から素数へ、整数からベクトルへ、そして虚数へと進む。とくに電卓による分数の学習は圧巻。本書は2014年12月に東海大学出版部より発行された同名書籍(最終版:2018年7月第5刷)を弊社において引き継ぎ出版するものです。 第一部:自然数を追え,無限を掴まえろ 第二部:ベクトルをまわせ,ドミノを倒せ! 第三部:二階建ての数「分数」の世界 索引
この書籍は、累計10万部のベストセラーを改訂したもので、Webサイト制作とHTML・CSSの基本を学ぶ入門書です。架空のカフェ「KUZIRA CAFE」のサイトを作成しながら、最新のHTMLとCSSの技術を身につけることができます。PCとモバイル対応のサイト制作手順を図解で詳しく解説しており、初心者や再学習者に最適です。著者はUIデザイナーの狩野祐東です。
この書籍は、ネットワーク技術に関する基本的な知識を提供するもので、IPアドレッシング、ルーティング(RIP、OSPF、EIGRP、BGP)、スイッチング技術(VLAN、STP)について解説しています。著者の網野衛二は、コンピューター系専門学校の講師であり、ネットワークに関する講座や連載も行っています。
この書籍は、リナックスの創始者リーナス・トーバルズが自身の経験を通じてリナックス哲学を語る内容です。目次はオタクの誕生、オペレーティング・システムの誕生、舞踏会の王といった三部構成で、彼のプログラミングの始まりや人生の転機、アメリカでの経験などが描かれています。著者にはトーバルズの他、デイビッド・ダイアモンド、風見潤、中島洋が含まれています。リナックスはオープンソースの考え方に基づき、世界のサーバーOSの25%のシェアを持っています。
この書籍は、量子力学を学ぶための入門書であり、古典力学では説明できない現象について解説しています。内容は、光や物質の波動性と粒子性、シュレーディンガー方程式、波動関数、物理量の期待値、演算子など多岐にわたります。著者は琉球大学の准教授、前野昌弘氏です。
この書籍は、初心者向けのJavaScriptプログラミング入門書で、コードには「ふりがな」が付いており、挫折しにくい内容です。目次には、基本的な文法や関数、Webページへの組み込み、サーバーとの通信についての章が含まれています。著者は及川卓也で、IT企業での経験を持ち、企業や社会の変革を支援する会社を設立しています。
本書は、月刊誌『子供の科学』の新シリーズ「子供の科学★ミライサイエンス」の第1弾で、テーマは「コンピューター・サイエンス」です。コンピューターやインターネットが日常生活に浸透する中、子供たちがその仕組みや使い方を理解することの重要性を伝えます。内容は、コンピューターの基本、思考プロセス、接続の仕組み、リスク、進化について解説され、視覚的なイメージ図を用いてわかりやすく構成されています。監修は慶應義塾大学の村井純教授です。
本書は、アルゴリズム設計の技法を中心に、学生やコンピュータ技術者が効果的なアルゴリズムを設計するための実用的なマニュアルです。技術系企業の採用面接準備にも役立ちます。内容は「技法」と「リソース」の二部構成で、上巻ではハッシングやランダム化アルゴリズムなど多様なトピックを扱っています。数学的解析は強調せず、インフォーマルな議論に留め、詳細は参考文献に委ねています。著者はスティーブン・スキーナと平田富夫です。
この文章は、トランジスタや増幅回路に関する内容を扱った書籍の目次を紹介しています。目次は、トランジスタの動作と特性、増幅回路の基本構造、トランジスタ基本回路、帰還回路と発振回路、差動増幅回路と演算増幅器の各章で構成されています。また、著者は工学博士の藤井信生で、東京工業大学の名誉教授です。
この文章は、ケイティ・ハフナーとマシュー・ライアンによる著書の目次と著者情報を紹介しています。目次には、即断即決や大聖堂の建設、大学、プログラム、ハッキング、電子メール、ロケットに関する章が含まれています。著者は科学技術に関する記事を執筆しており、ハフナーは複数の著書を持ち、ライアンはカリフォルニア大学バークレイ校の副学長補佐を務めています。
本書は、Javaプログラミングの入門書で、開発環境のインストールから基本的なプログラミング技術までをわかりやすく解説しています。初めての人に最適で、変数、配列、条件分岐、ループ、クラスの基礎などを学べます。著者はテクニカルライターの齊藤新三とフリーライターの山田祥寛です。
本書は、コンピュータに関わる全ての人を対象にした線形代数の参考書であり、専門的な知識を持たない読者にも理解しやすく線形代数の本質を伝えることを目的としています。内容は、ベクトルや行列から始まり、逆行列、固有値、コンピュータでの計算方法などを網羅しており、数学的な考え方を促進します。著者は東京大学出身の平岡和幸と堀玄です。
本書は、Pythonを用いたデータサイエンスのための実用的なリファレンスの改訂版です。IPython、Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを活用し、データ操作、可視化、行列計算、時系列解析、統計分析、機械学習などの幅広いトピックをカバーしています。各トピックには基本知識や便利なコマンドが紹介されており、データ処理を行う人にとって必携の一冊です。著者はデータ駆動研究を支えるツールの開発に従事しているジェイク・ヴァンダープラス氏です。
本書は、ディジタル電子回路の基本を学ぶための入門書であり、理工系の学生や社会人にとって必須の内容です。基本論理ゲート、ブール代数、論理回路、フリップフロップ、順序回路、A/D変換などを取り上げ、ディジタル電子回路の理解を深めることを目的としています。目次には、ディジタル回路の概念から、論理回路の構成、記憶、信号変換まで幅広いトピックが含まれています。
本書『Introduction to Algorithms』第4版の翻訳書は、アルゴリズムの標準的教科書であり、安定結婚問題や機械学習などの新章を含む。全35章と付録から成り、学部や大学院の講義用、技術者の手引書、辞典として利用可能。著者は複数の専門家で構成されている。
著者ポール・グレアムは、成功したソフトウェアベンチャーの背景や、ものづくりのセンス、ビジネスの成功の秘訣を語ります。彼は、ハッカーとクリエイターの共通点や、革新的なアイデアの重要性を強調し、プログラミング言語やデザインの未来についても考察しています。全体を通じて、常識を超えた発想や行動が成功に繋がることを示唆しています。
現在成功している大人で、中学高校でnerd(日本語では「陰キャ」?)じゃなかったと言い切れる人は滅多にいない。実際に私が出会った優秀な方は昔は陰キャだったように思います。今陰キャだからといって、これからも暗い未来が待っているわけではありません。陰キャのときこそ、本質的なやるべきことをやり、それでいてただ耐えるたけでなく自ら行動することで未来を素晴らしいものにできることを教えてくれます。
本書は、最新のオープンソースプロセッサ「RISC-V」の設計思想や命令セットについて、コンピュータアーキテクチャの権威であるデイビッド・パターソン教授が詳細に解説しています。RISC-Vは、無償で公開され、誰でも改良や再配布が可能な命令セットを持ち、幅広い適用範囲を誇ります。著者は、RISC-Vの開発に関与した専門家であり、技術的な完成度も高いです。RISC-V基金が設立され、GoogleやNVIDIAなどの企業が参加していることから、その期待の高さが伺えます。内容は、基本的な命令から拡張機能まで多岐にわたります。
本書は、初心者向けのJavaプログラミング入門書で、最新の開発環境に対応しています。文法や基本知識を丁寧に解説し、条件分岐や繰り返し、クラス・メソッドの使い方を学べます。各章には簡潔なサンプルプログラムと練習問題があり、理解を深める構成です。Javaを初めて学ぶ人や基礎を再確認したい人に最適です。著者は筑波大学の教授で、豊富な教育経験があります。
『新・明解C++言語入門編』は、著者柴田望洋によるC++の基礎を分かりやすく解説した入門書です。307のサンプルプログラムと245の図表を用いて、プログラミングの基本を丁寧に学べます。初めてプログラミングを学ぶ人や他の書籍で挫折した人に最適な一冊です。著者は工学博士で、教育界での実績も豊富です。
この本は、教師が学生に論理学の魅力を伝えることを目的としており、二部構成になっています。第1部では日常の言葉を用いて論理学の基本的な概念を紹介し、第2部では記号を使った記号論理学を展開します。実用的な内容も含まれており、論理的思考を身につけたい人に役立つ一冊です。初心者向けに配慮された構成で、問題と解説を交えながら進むため、理解しやすくなっています。著者は哲学を専門とする野矢茂樹です。
この文章は、Chad Fowlerによる書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は市場の選択、製品への投資、実行、マーケティング、研鑽の重要性についての章で構成されています。著者は著名なソフトウェア開発者であり、Ruby言語の専門家として知られています。彼は多くの企業での経験を持ち、ソフトウェア関連の書籍も執筆しています。
本書は、C++17に対応した完全書き下ろしの教科書で、9年ぶりにリニューアルされました。システム開発者やゲームプログラマー向けに、C++の基本から標準ライブラリまでを詳細に解説しています。全13章で構成され、具体的なサンプルプログラムや練習問題を通じて学習を深められる内容となっています。著者はBoostコミッターの高橋航平氏です。
この書籍は、ディープラーニングをゼロから実装することで学ぶ入門書です。Python 3を用いて、基礎から誤差逆伝播法や畳み込みニューラルネットワークなどの実装を通じて理解を深めます。また、ハイパーパラメータの設定やBatch Normalization、Dropout、Adamなどの最新技術、さらには自動運転や画像生成などの応用例についても触れています。著者は斎藤康毅氏で、コンピュータビジョンや機械学習の研究開発に従事しています。
ディープラーニングの概要は分かっているし機械学習はある程度理解しているつもりだけど、ディープラーニングの中身はちゃんと理解できていない人にぜひ読んで欲しい書籍。ディープラーニングは一旦これ1冊読んでおけば問題なし。複雑で難しい印象だったディープラーニングがこれを読むだけで一気に身近なものになる。
この書籍はC++プログラミングに関する内容を扱っており、以下の章で構成されています:C++の基礎、コンストラクタやデストラクタ、リソース管理、デザインと宣言、実装、オブジェクト指向設計、テンプレート、メモリ管理のカスタマイズ、その他のトピック。著者は小林健一郎氏で、東京大学で理学博士号を取得後、研究員や教授としての経歴を持っています。
この書籍は、Webの発明者であるティム・バーナーズ=リーが今後のWebの行方について語る内容です。目次には、探索、つながり、プロトコル、プライバシー、マシンとの関係など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者は、Webの基礎技術やシステムを開発した人物であり、現在もWebの発展に貢献しています。また、共著者の高橋徹もインターネットの研究や普及に関与してきた専門家です。
本書『Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software 2nd Edition』は、ITエンジニア必読の名著が21年ぶりに改訂されたもので、コンピュータの複雑な仕組みを身近な題材を通じて解説します。著者チャールズ・ペゾルドは、点字やモールス符号、プログラミング言語などを用いて、コンピュータの本質を探ります。新版ではCPUの仕組みも詳しく説明され、全体で100ページ以上のボリュームアップが図られています。読者は、コンピュータの内部動作を深く理解する旅に誘われます。
本書は、基本情報技術者試験の科目Bに特化したアルゴリズムと擬似言語のトレーニング本の改訂版です。16問のアルゴリズム問題を中心に、過去問やオリジナル問題を多数収録し、実践的なトレーニングを提供します。内容は、変数やデータ構造、擬似言語プログラミング、基本例題、応用例題、サンプル問題に分かれており、特にアルゴリズムに自信のない受験者におすすめです。著者はIT企業での経験を持つ教育者です。
本書は、コンピュータサイエンスにおける重要な論理体系である様相論理K、CTL、様相ミュー計算、PDLについて、その数学的基礎を明確かつ厳密に解説しています。また、プログラム検証に関連するホーア論理についても詳述し、証明体系の完全性や計算可能性、ゲーム意味論の妥当性に関する証明も含まれています。全体を通じて、論理の基礎を徹底的に学ぶことができる内容となっています。著者は東京工業大学の准教授、鹿島亮氏です。
この文章は、インターネットの歴史と進化に関する書籍の目次を示しています。内容は、JUNETや商用インターネットの初期、インターネットブームの影響、個人サイトやウェブログの登場などを扱っています。また、パソコン通信の重要性にも触れられています。
この書籍は、MATLABに関する内容を扱っており、以下の章で構成されています:MATLABの機能、行列の基礎、データの流れ管理、大規模プログラム作成のための関数、グラフィックス、ファイル操作、ユーザインターフェイスの設計。著者は上坂吉則で、名古屋工業大学を卒業後、複数の大学で教授を務め、工学博士の学位を持っています。
『プリンシプル オブ プログラミング』は、プログラマーが3年目までに身につけるべき101の原理原則を紹介するガイドブックです。KISSやブルックスの法則など、古今東西の知恵を集約し、質の高いプログラミングを実現するための基本的な考え方や手法をわかりやすく解説しています。初心者から脱却したいプログラマーに最適な一冊です。著者は上田勲で、キヤノンITソリューションズでの豊富な経験を持っています。
本書は、Linuxプログラミングの入門書であり、Linuxの仕組みを理解し、プログラムを作成するための基礎を学ぶことを目的としています。内容は、Linuxの基本概念から始まり、システムコールやライブラリ関数を用いた具体的なコマンドの作成、さらにはネットワークプログラミングに至るまで幅広くカバーしています。著者は、読者がLinuxの世界を理解し、プログラミング技術を習得できるよう導いています。
この書籍は、インターネットの原点と未来を探求し、新時代の共通基盤の本質を明らかにします。内容は二部構成で、第1部ではインターネットの理念や仕組み、運用方法について解説し、第2部ではTCP/IPの発明者からの課題としてインターネットの再発明について考察しています。著者の村井純は、日本のインターネットの発展に寄与した重要な人物であり、数々の業績を持つ教授です。
本書はプログラマー向けにコンピュータの基本的な仕組みを解説するもので、アセンブリ言語やCPUの内部動作、メモリ、入出力装置、ネットワーク、グラフィックス、OSの機能、データの内部表現、抽象化・仮想化について詳しく説明しています。著者はコンピュータ関連の豊富な著作を持つ専門家で、プログラミングの理解を深めるための重要な情報を提供しています。
本書はデータサイエンスの基礎知識を図解で解説しており、初心者にも理解しやすい内容です。データの種類、統計学、AIの基本、セキュリティ問題など幅広くカバーし、情報社会におけるデータ活用の課題も取り上げています。データ分析に関心がある人や業務で関わる人におすすめです。目次には、データサイエンスを支える技術やデータ処理方法、統計学、AIの手法などが含まれています。著者は技術士で、ビジネス数学とITを融合したスキルアップ支援を行っています。
プログラミングの世界で、数学の定理や公式に相当するものがアルゴリズムです。本書では,πの計算や文字列の検索、迷路の解法などのプログラムをC言語で作成して基本的アルゴリズムを習得していきます。 第1章 ウォーミング・アップ 第2章 数値計算 第3章 ソートとサーチ 第4章 再帰 第5章 データ構造 第6章 木(tree) 第7章 グラフ(graph) 第8章 グラフィックス 第9章 パズル・ゲーム
『新版暗号技術入門』の改訂版は、2008年の刊行以来セキュリティ関連で人気を保ち続けている書籍です。暗号技術の基本を図解と易しい文章で解説し、対称暗号や公開鍵暗号、デジタル署名などを取り上げています。第3版では、現代の暗号技術に関する最新情報や、SHA-3、SSL/TLSへの攻撃、ビットコインとの関係などが加筆されています。全ての人にとって必読の内容で、暗号の歴史から応用技術まで幅広くカバーしています。
本書は、コンピュータの基本原理やプログラム、通信の基礎を概観し、現代社会における情報セキュリティや情報倫理、データ駆動型意思決定の実践例についても学べる教科書の改訂版です。著者陣は各大学の名誉教授や准教授で構成されています。
本書は、マイクロソフト、アップル、グーグルでのエンジニア経験を持つ著者による、トップIT企業のプログラミング面接対策本です。米国で人気の「Cracking the Coding Interview」の日本語版で、実際の面接問題を通じてアルゴリズムやコンピュータサイエンスの基礎を学ぶことができます。問題数が増え、解説が充実しており、読みやすさも向上しています。著者の親切な解説が特徴です。
この文章は、書籍の目次と著者情報を紹介しています。書籍は三部構成で、第一部ではアルゴリズムやプログラムの構造について、第二部ではパフォーマンスやアルゴリズムデザインのテクニックについて、第三部では具体的な問題解決の作品を扱っています。著者の小林健一郎は東京大学で物理学を学び、情報科学を専門とする教授です。
本書は「計算とは何か?」という疑問から始まり、プログラミング、アルゴリズム、シミュレーション、データマイニング、情報セキュリティなどを通じてコンピュータサイエンスの全体像を探ります。計算を通じて世界を理解する楽しさを伝え、情報通信技術の未来について考察します。著者は東京工業大学の教授で、計算理論を専門としています。
この書籍はプログラミング言語についての包括的な解説を提供しており、序論から始まり、プログラミング言語の特徴、構文、命令型およびオブジェクト指向プログラミング言語、意味論、具体的な言語としてC言語とJava言語に関する章が含まれています。著者は大山口通夫と五味弘で、それぞれ工学の博士号を持ち、大学での教育や研究に従事しています。