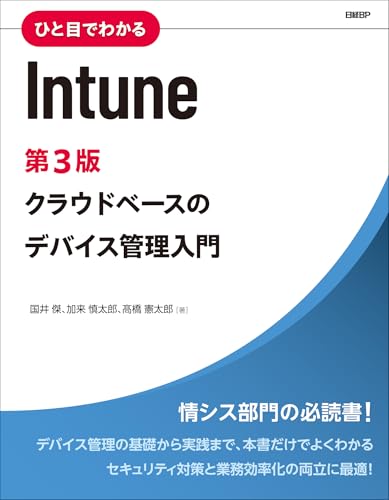【2025年】「強化学習」のおすすめ 本 179選!人気ランキング
- Pythonではじめる機械学習 ―scikit-learnで学ぶ特徴量エンジニアリングと機械学習の基礎
- Pythonによる深層強化学習入門 ChainerとOpenAI Gymではじめる強化学習
- 機械学習のエッセンス -実装しながら学ぶPython,数学,アルゴリズム- (Machine Learning)
- 現場で使える!Python深層強化学習入門 強化学習と深層学習による探索と制御 (AI & TECHNOLOGY)
- ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装
- ゼロから作るDeep Learning ❷ ―自然言語処理編
- 見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み 機械学習図鑑
- 機械学習スタートアップシリーズ Pythonで学ぶ強化学習 [改訂第2版] 入門から実践まで
- パターン認識と機械学習 上
- Kaggleで勝つデータ分析の技術
この書籍は、数学の知識がなくても理解できる機械学習の入門書で、Pythonの機械学習ライブラリ「scikit-learn」を用いた実践的な解説が特徴です。著者はscikit-learnの開発に関わる専門家で、実践から理論へと学ぶスタイルを採用しています。特に「特徴量エンジニアリング」や「モデルの評価と改善」に焦点を当てており、従来の解説書にはない内容を提供しています。目次には教師あり学習、教師なし学習、データ処理などが含まれています。著者は機械学習の専門家で、産業界や学術界での経験があります。
本書は、機械学習の有名なアルゴリズムをPythonを用いてゼロから実装することを目的としています。実用的なフレームワークを使用するのではなく、機械学習の仕組みを深く理解することで応用力や問題解決力を高めることを目指しています。内容は、Pythonの基本、機械学習に必要な数学、数値計算、そして具体的な機械学習アルゴリズムに関する解説を含んでおり、初心者や実務に携わるエンジニアに適しています。著者はシルバーエッグ・テクノロジーのチーフサイエンティストで、機械学習アルゴリズムの設計・実装に精通しています。
本書は、深層強化学習の開発手法に焦点を当てた一冊で、AIサービスやロボティクス分野での応用が期待されています。著者陣は第一線の専門家で、基礎編では強化学習と深層学習の基本概念やアルゴリズムを解説し、実装例として倒立振子制御を紹介。応用編では、連続動作制御、組合せ最適化、系列データ生成の具体的なアプローチを実装と共に説明しています。読者は深層強化学習の技術を学び、実際の開発に役立てることができます。対象は理工系の学生やエンジニアです。
この書籍は、ディープラーニングをゼロから実装することで学ぶ入門書です。Python 3を用いて、基礎から誤差逆伝播法や畳み込みニューラルネットワークなどの実装を通じて理解を深めます。また、ハイパーパラメータの設定やBatch Normalization、Dropout、Adamなどの最新技術、さらには自動運転や画像生成などの応用例についても触れています。著者は斎藤康毅氏で、コンピュータビジョンや機械学習の研究開発に従事しています。
ディープラーニングの概要は分かっているし機械学習はある程度理解しているつもりだけど、ディープラーニングの中身はちゃんと理解できていない人にぜひ読んで欲しい書籍。ディープラーニングは一旦これ1冊読んでおけば問題なし。複雑で難しい印象だったディープラーニングがこれを読むだけで一気に身近なものになる。
『ゼロから作るDeep Learning』の続編である本書は、自然言語処理や時系列データ処理に焦点を当て、ディープラーニングの技術を実装レベルで学ぶことができます。具体的には、word2vec、RNN、LSTM、GRU、seq2seq、Attentionなどの最新技術を取り上げ、分かりやすく解説しています。著者は、人工知能の研究開発に従事する斎藤康毅氏です。
ゼロから分かるディープラーニングシリーズはどれも非常に分かりやすい。こちらの自然言語処理編は前作を読みディープラーニングの基本を理解してより高度なアーキテクチャを学びたいと思った時にオススメ。レベルは少々上がっているがそれでも分かりやすく学べる。RNNやLSTMなどが学べる
本書は、機械学習アルゴリズムをオールカラーの図を用いてわかりやすく解説した入門書です。17種類のアルゴリズムを紹介し、各アルゴリズムの仕組みや使用方法、注意点を詳述しています。Pythonを用いたコードも掲載されており、実際に試しながら学ぶことができます。機械学習を学ぶ初心者や業務で利用している方にも役立つ内容となっています。
この入門書の改訂版は、Pythonを用いた強化学習の実装方法をゼロから丁寧に解説しており、読者の要望に応じてPolicy GradientやA2Cの部分を見直しています。コードが公開されているため、実践が容易です。また、強化学習の弱点やその克服方法についても詳しく紹介しています。内容は、強化学習の基本概念から解法、ニューラルネットワークの適用、弱点とその対策、活用領域に至るまで多岐にわたります。
強化学習の①理論②実装③応用が三拍子揃ってってバランスよく書かれた良書です。強化学習は理論部分の難易度が高く、最初に読む本を間違える(理論をちゃんと勉強してから実装や応用に進もうとする)と挫折してしまうリスクが高い分野ですが、本書を最初に読んでおけば間違いありません。書籍内で示されているサンプルコードも品質が高く、実務でもそのままプロダクション環境で使えるレベルです(※適用先ドメイン固有の例外処理などは追加実装する前提)。
本書は、データサイエンスにおけるコンペティション、特にKaggleに焦点を当て、実践的なデータ分析手法やテクニックを紹介しています。分析コンペに参加することで得られるスキルは、実務でも役立つため、特徴量の作成やモデルの評価、チューニングなどの具体的な内容が含まれています。著者たちは、データサイエンスの専門家であり、実績を持つKaggleの競技者です。この本は、コンペに挑戦したい人や実務でのモデル精度向上を目指す人にとって有益な情報源となるでしょう。
データ分析コンペKaggleに挑戦するならこれをまず読んでおけば大丈夫!Kaggleに参加しないにしてもデータ分析の本質やテクニックがギュッと詰まっているので実務に活かせる。高度な内容も登場するが分かりやすく解説してくれるので初心者でも読みやすい。それでいてベテランの人も多くの学びがある書籍。著者はKaggleの最上位グランドマスターの方々であり説得力がある。過去のコンペの事例も取り上げてくれるのでそんなアプローチあったのかぁと学びが深い。文句なしの星5つ!
この書籍は、機械学習とディープラーニングの基本を図解形式で解説しており、エンジニア1年生や関連企業への就職・転職を目指す人に最適です。内容は、人工知能の基礎、機械学習とディープラーニングのプロセス、アルゴリズム、システム開発環境に関する知識を包括的に学べる構成になっています。著者は、実践的な機械学習システムの実装をサポートする専門家です。
本書は、プログラミング言語Python 3.6の入門書で、538本のサンプルコードと154本のPythonファイルを通じて基礎から機械学習まで学べる内容です。3つのパートに分かれており、Part 1ではPythonの環境設定、Part 2では基本的な構文やデータ構造、Part 3では科学計算や機械学習の応用を解説しています。初心者から実践者まで、確実なスキルアップを目指すことができます。著者はコンピュータ専門誌への寄稿や教材開発を行っている大重美幸氏です。
本書は人気シリーズの第3弾で、オリジナルのディープラーニングフレームワーク「DeZero」をゼロから作成する内容です。最小限のコードでモダンな機能を実現し、全60ステップでフレームワークを完成させます。これにより、PyTorchやTensorFlowなどの知識を深めることができます。著者は人工知能の研究開発に従事する斎藤康毅氏です。
この書籍は、人工知能(AI)の全体像を理解し、5年後の活用イメージを掴むための内容です。3部構成で、第一部ではAIの基礎知識、第二部では機械学習のアルゴリズム、第三部ではビジネスにおけるAIの活用法を学びます。著者の梅田弘之は、システムインテグレータの代表であり、AIを活用した新しいプロダクトやサービスの開発に取り組んでいます。
本書は、強化学習の原理を「平均」という視点からわかりやすく解説する入門書です。初歩的な数学を用いて、価値、探索、マルコフ決定過程などの基本概念を紹介し、初学者でも理解しやすい内容となっています。また、PythonとMATLABのコード例を通じて、理論と実践を結びつけ、深層強化学習の基本やコツを自然に学べるよう工夫されています。著者は理学博士で、研究と教育の経験を持つ専門家です。
本書は、2018年に発行された機械学習に関する書籍の全面改訂版で、不確実性の高い機械学習プロジェクトを「仕事で使う」という視点から整理しています。新たに「ML Ops」や「機械学習モデルの検証」などの章が追加され、読者が直面する問題解決に役立つ内容となっています。著者は機械学習分野の専門家で、実践的な知識を提供しています。
機械学習の手法やテクニックにフォーカスした書籍ではなくて、機械学習を仕事に取り入れるためにはどうすればよいのか?どういうところに注意しなくてはいけないのかがまとめられた書籍。実務で機械学習を利用している人利用する可能性のある人は絶対に読むべき書籍。そもそも本当に機械学習を使う必要があるのかということをしっかり考える、機械学習ありきのプロジェクトは必ず失敗する。
著者松尾豊は、日本の人工知能研究の第一人者として、最新技術「ディープラーニング」の進展とその影響を探求し、知能や人間の本質について問い直します。本書では、人工知能の歴史やブームを振り返りながら、技術の進化が人類にもたらす可能性と危機について論じています。
「Unity ML-Agents」は、2017年に登場し、2020年に正式版がリリースされたツールで、C#を使用してゲームAIを開発できることが特徴です。本書は、機械学習の基礎から学習環境の構築、さまざまな学習方法をステップ・バイ・ステップで解説しており、実際のゲーム開発に役立つサンプルも紹介しています。ゲームAIを学びたい初心者に向けた内容で、基礎から実践まで網羅しています。著者は人工知能の研究開発に携わる技術書著者です。
この書籍は、人工知能を用いて「ソニック」や「レトロゲーム」、さらには「マインクラフト」や「株トレード」といったゲームを攻略する方法を解説しています。特に「OpenAI Gym」という強化学習ツールキットを利用し、さまざまなゲーム環境でAIを構築する手法が詳述されています。著者は、強化学習アルゴリズムの実装や、ゲーム攻略のための具体的な手順を示し、最終的には多様な学習環境の概要も紹介します。
この書籍は、強化学習に必要な数理を広くカバーし、詳細な解説を提供しています。内容は、強化学習の基本概念やマルコフ決定過程、プランニング手法、探索と活用のトレードオフ、モデルフリー型およびモデルベース型の強化学習、関数近似技術、部分観測マルコフ決定過程(POMDP)、そして最近のトピックである深層強化学習について説明しています。付録や参考文献も充実しており、じっくりと学ぶことができる構成です。
文科と理科両方の学生のために,統計的なものの考え方の基礎をやさしく解説するとともに,統計学の体系的な知識を与えるように,編集・執筆された.豊富な実際例を用いつつ,図表を多くとり入れ,視覚的にもわかりやすく親しみながら学べるよう配慮した. 第1章 統計学の基礎(中井検裕,縄田和満,松原 望) 第2章 1次元のデータ(中井検裕) 第3章 2次元のデータ(中井研裕,松原 望) 第4章 確率(縄田和満,松原 望) 第5章 確率変数(松原 望) 第6章 確率分布(松原 望) 第7章 多次元の確率分布(松原 望) 第8章 大数の法則と中心極限定理(中井検裕) 第9章 標本分布(縄田和満) 第10章 正規分布からの標本(縄田和満) 第11章 推定(縄田和満) 第12章 仮説検定(縄田和満,松原 望) 第13章 回帰分析(縄田和満) 統計数値表 練習問題の解答
この書籍は、Pythonの主要な機械学習ライブラリ(scikit-learn、Keras、TensorFlow)を用いて、幅広い機械学習の手法を解説した改訂版です。新たに大規模言語モデルや生成AIのトピックを追加し、実践的な問題解決に焦点を当てています。サンプルコードはノートブック形式で提供され、読者は実際に手を動かしながら学ぶことができます。著者は機械学習の専門家で、実務経験を持つメンバーで構成されています。
本書は、機械学習を実践的に学ぶための教材で、scikit-learn、TensorFlow、Kerasを用いて、基礎から応用までの手法を体系的に解説しています。内容には、データ処理、モデル学習、深層学習、強化学習、コンピュータビジョン、自然言語処理などが含まれ、サンプルコードはすべてGitHubで公開され、Jupyter Notebookで試すことができます。第2版では新たに畳み込みニューラルネットワークやGANによる画像生成の説明も追加されています。機械学習を学びたいエンジニアにとって必携の一冊です。
本書は、ディープラーニングの理解に必要な数学を高校1年生レベルからやさしく解説し、最短コースで学べる内容です。微分、ベクトル、行列、確率などの必要最低限の数学を特製のマップで整理し、実際に動かせるコードをJupyter Notebook形式で提供します。内容は機械学習入門から始まり、理論編、実践編、発展編に分かれており、ディープラーニングの動作原理を深く理解できることを目指しています。
本書『Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2, 3rd Edition』は、機械学習の理論とPythonによる実践を解説するベストセラーの第3版です。分類、回帰、深層学習、強化学習など幅広いトピックをカバーし、最新のPythonライブラリに対応しています。特に、敵対的生成ネットワークと強化学習の新章を追加し、従来の内容を刷新しました。機械学習の理解を深めるための実用的な一冊です。
この入門書は、パターン認識について基礎からわかりやすく解説しており、特にRを用いた実行例が含まれているため、実際の応用にも役立ちます。内容は識別規則や学習法、ベイズの識別規則、k最近傍法、サポートベクトルマシンなど多岐にわたり、最後には識別器の性能強化についても触れています。著者は筑波大学の名誉教授、平井有三氏です。
「はじめての」とついているが入門書ではなく結構難しい。ただ、機械学習の様々な手法が数式から学べるため中級者〜上級者には良いと思う。他の入門書で機械学習の概要を掴んだ後に読むべき本。
本書は、深層学習に関する改訂版のベストセラーで、トランスフォーマーやグラフニューラルネットワーク、生成モデルなどの手法を詳しく解説しています。著者は、理論的な証明がなくても納得できる説明を重視し、実用性を考慮した内容を提供。全12章で、基本構造から各種学習方法、データが少ない場合の対策まで幅広く網羅しています。著者は東北大学の教授であり、実務家との共同研究の経験も反映されています。
本書は、Scratchを使ったゲームを通じて強化学習を学ぶ入門書です。強化学習の基本概念を中学レベルの数学で説明し、3つのオリジナルゲームを使って段階的に理解を深めます。著者はAIの専門家で、実践的な内容が特徴です。
本書は、数学が苦手な方でも機械学習を楽しく学べる入門書です。プログラマのアヤノと友達のミオの会話を通じて、機械学習の基本や実践方法を説明します。内容は、機械学習の重要性、回帰や分類の手法、モデルの評価、Pythonでの実装まで幅広くカバーし、数式も分かりやすく解説しています。特に、数式が苦手な方に配慮した内容になっています。著者はLINE Fukuokaのデータエンジニアで、実務経験を基にした知識を提供しています。
本書は、戦略ゲームAIの仕組みや意思決定プロセスを解説したバイブルで、ゲーム開発者やAIエンジニアに向けて書かれています。ストラテジー&シミュレーションゲームの技術を国内外の事例を交えて詳しく説明し、基本概念からアルゴリズムまでをビジュアルを用いて解説しています。著者はゲームAIの専門家で、教育機関での経験も豊富です。読者は戦略ゲームAIの理解を深めることができます。
本書は、強化学習の基礎、発展、応用を多角的に解説した一冊です。強化学習は、データが不足している状況でも最適化を図る技術であり、人工知能やロボット制御、金融工学など多くの分野での応用が期待されています。内容は、基礎的理論から発展的手法、工学的応用、知能モデルとしての強化学習に至るまで幅広くカバーされています。初心者から研究者まで、強化学習の理解を深めるための内容が充実しています。
この入門書は、ベイズ主義機械学習の基本原理を「モデルの構築→推論の導出」という手順で分かりやすく解説しています。内容は、機械学習とベイズ学習、基本的な確率分布、ベイズ推論による学習と予測、混合モデルと近似推論、応用モデルの構築と推論の5章から構成されています。著者は須山敦志と杉山将で、機械学習を身近に理解できるよう丁寧に記述されています。
『ファイナルファンタジー15』における人工知能(AI)技術とその応用について解説した書籍です。基礎編ではゲームAIの基礎知識やシステムについて、コンテンツ編では仲間やモンスターなどのAIについて、未来編では会話AIや今後の技術について触れています。また、プログラマー、デザイナー、制作チームリーダーとの対談も収録されており、ゲームAIの進化やキャラクターデザインの重要性について議論されています。
本書は、日本ディープラーニング協会の「ディープラーニングG検定ジェネラリスト」試験に向けたテキストと問題集で、合格に必要な知識と対策を提供します。数式を控え、わかりやすい説明で構成されており、ビジネスでのディープラーニング活用を目指す人を対象としています。内容は、AIの歴史、数学的基礎、機械学習の基礎と実装、ディープラーニングの基本と研究分野、産業展開、制度政策など多岐にわたります。著者はAIの専門家であり、実践的な学習が可能です。
ヨシュア・ベンジオ スチュアート・J・ラッセル ジェフリー・ヒントン ニック・ボストロム ヤン・ルカン フェイフェイ・リー デミス・ハサビス アンドリュー・エン ラナ・エル・カリウビ レイ・カーツワイル ダニエラ・ルス ジェイムズ・マニカ ゲアリー・マーカス バーバラ・J・グロース ジュディア・パール ジェフリー・ディーン ダフニー・コラー デイヴィッド・フェルッチ ロドニー・ブルックス シンシア・ブリジール ジョシュア・テネンバウム オーレン・エツィオーニ ブライアン・ジョンソン
本書は、ディープラーニングを一から学びたい人向けに、数学的表現を避けて実践的なコードを用いて基本概念を解説します。著者はKerasの開発者で、TensorFlowをバックエンドに使用。内容は、ディープラーニングの基礎から始まり、コンピュータビジョンや自然言語処理の応用例まで幅広くカバー。最終的には、ディープラーニングの適用可能性や限界を理解できるようになります。
本書は、機械学習におけるグラフの重要性を基礎から解説し、グラフニューラルネットワークの理論と応用を深く掘り下げたテキストです。内容は、グラフの定義やニューラルネットワークの基礎、グラフニューラルネットワークの定式化、様々なタスクへの応用、高速化手法、スペクトルグラフ理論、過平滑化現象の対策、表現能力など多岐にわたります。著者は佐藤竜馬氏で、研究者としての専門知識を活かし、理論に基づいた実践的な内容を提供しています。
本書は、Human-in-the-Loop機械学習を活用して高品質な学習データを効率的に作成し、機械学習モデルの品質向上とコスト削減を図る方法を解説しています。特に、能動学習を用いたアノテーションプロセスの改善に重点を置き、実践的なテクニックやアノテーション管理手法を提供しています。データサイエンティストや機械学習エンジニアにとって、効果的なAIシステム開発に寄与する内容となっています。
本書はディープラーニング、ニューラルネットワークについての予備知識がなくても学習を進められるようゼロから丁寧に、理論とその実装について解説します。 実装にはPythonのディープラーニング向けのライブラリ、TensorFlow (1.0) およびKeras (2.0) を用います。 「ディープラーニングについて何となくわかってはいるけれど、もう少し理解を深めたい」「画像認識だけでなく、時系列データを分析するためのモデルについても学びたい」という方にとって、学びの役に立つのではないかと思います。 単純パーセプトロンにはじまり、多層パーセプトロン、ディープニューラルネットワーク、リカレントニューラルネットワークなど多くの手法について学びます。扱うデータの種類ごとに考えるべき課題も異なり、それに合わせてネットワークも様々な形に変化させ学習を進めます。 ディープラーニングは1つひとつのテクニックの積み重ねであり、その根底にあるのは「人間の脳をどう数式やアルゴリズムで表現できるか」です。本書で学んできた土台となる理論さえきちんと理解していれば、今後どのようなディープラーニングの手法が出てこようとも、すぐに理解し使いこなせるようになるでしょう。そして、自身で新たなモデルを考え出すこともできるはずです。 [本書の構成] 1章では、ニューラルネットワークの理論を学習するうえで必要となる数学の知識について簡単におさらいし、続く2章では、実装に向けてのPython開発環境のセットアップ、およびPythonライブラリの簡単な使い方を扱います。 3章からは、いよいよニューラルネットワークの学習に入っていきます。3章ではその基本形について学び、4章ではディープニューラルネットワーク、いわゆるディープラーニングについて学びます。通常のニューラルネットワークと何が違うのか、どのようなテクニックが用いられているのかを実装を交えて理解します。 5、6章では、時系列データを扱うためのモデルであるリカレントニューラルネットワークについて詳しく学んでいきます。5章では、リカレントニューラルネットワークの基本形を簡単なデータ例を用いて理論・実装について学び、6章ではその応用例について扱います。
本書は、Googleの機械学習ライブラリTensorFlowを用いて、Pythonの基礎を学んだ人向けにJupyter Notebookでの活用法を解説する入門書です。シンプルな二値分類から画像認識、自然言語処理の時系列データ分析まで、理論を交えながら体系的に学べます。TensorFlow 2.0に対応し、Kerasが統合されたことでプログラミングが簡素化されています。内容は、TensorFlowの基本、開発環境の構築、例題を通じた学習、ディープラーニングの実装などを含みます。
本書は、ディープラーニングの実用化に向けた最新の動向と事例を紹介するもので、国内35社の具体例を通じてその活用方法や課題を解説しています。東京大学の松尾豊氏による技術的発展のロードマップを基に、業務効率化や新規事業創出に役立つ情報を提供。各章では、単純作業の自動化から異常検知、ロボットや自動運転技術、さらには創作業務への応用まで幅広くカバーしています。また、ビジネス活用に関するQ&Aも含まれ、企業の導入に役立つ内容となっています。
本書は、ディープラーニングの父であるヤン・ルカン氏が、AIとディープラーニングの過去、現在、未来について詳細に綴った作品です。特に、研究者たちの交流や思考過程が赤裸々に描かれ、AI革命の影響や課題についても考察されています。一般読者向けに平易な言葉で説明しつつ、専門的な内容も含まれているため、幅広い読者層に対応しています。ルカン氏の経験を通じて、ディープラーニングの重要性とその社会的インパクトが強調されています。
この本は、初心者向けにUnityを使った2Dゲームの作り方を解説しています。カエルのキャラクターが登場し、Unityのインストールから基本的なゲーム制作までをサポートします。2Dゲームに焦点を当てる理由は、基本を学びやすくするためで、後に3Dゲーム制作にも役立ちます。サンプル画像やスクリプトを用いて、自分で考えてゲームを作ることを重視しています。内容はUnityの基本から始まり、スクリプトの解説やゲームの要素を組み合わせる方法を学ぶ構成です。著者は長年のゲーム制作経験を持つ森巧尚氏です。
本書は初心者向けの機械学習入門書で、シリーズ累計90万部を突破しています。読者が楽しく反復練習を通じてスキルを身に付けられるように構成されており、表データの分析が独力で行える力を養います。数式やライブラリの使い方を単純に列挙するのではなく、データ分析のストーリーに沿って必要な手法を紹介します。また、初心者が直面しがちなエラーとその解決策をまとめた「エラー解決・虎の巻」も付属しています。第2版では最新のpandasに対応し、新付録として「Polars入門」が追加されています。全体的に読みやすさと使い勝手が向上しています。
この本は、2020年度から始まった小学校のプログラミング教育に対応し、プログラミングを初めて学ぶ子どもとその親のために作られています。専門の教科ではないため、現場の先生の裁量に任されていますが、ゲームを通じてプログラミングの基礎を学べる内容になっています。具体的には、Scratchを使った様々なゲームの制作を通じて、プログラミングの考え方や作り方を丁寧に解説しています。対象は小学3年生以上です。
この書籍は、AIが人類にもたらす影響について探求し、脅威と福音の両面を考察しています。著者は、AIの自律的な動きや自動化の進展を解説し、AI教育の重要性や未来の共存の可能性についても論じています。内容は、自律世界の到来やAIの役割、そして人間との関係性に焦点を当てています。著者は、技術とビジネスの専門家であり、AIの進化がもたらす社会の変革に関する洞察を提供しています。
この書籍は、TensorFlowを使って深層強化学習を実践する方法を解説しています。アルファ碁や自動運転などの応用例を挙げ、Python、TensorFlow、OpenAI gym、PyBulletを用いて、深層学習と強化学習の基本原理から実装、実環境での応用までを詳述しています。著者は、牧野浩二と西崎博光で、それぞれの専門的な背景を持っています。
本書は、生成AIの技術、法的課題、そして市場への影響を解説するもので、東京大学の松尾・岩澤研究室の協力を得ています。第1章ではAIの安全性と規制についての対談、第2章では生成AIの技術動向、第3章ではその市場への影響、第4章ではAI規制と関連法について述べています。2025年に向けたAIの進化が期待される中、生成AIの現状と展望を包括的に理解できる内容です。特典としてPDF版ダウンロード権も付いています。
本書は、日本ディープラーニング協会が監修し、ディープラーニングをビジネスに活用するための実践的な知識と事例を紹介しています。特に「ディープラーニングビジネス活用アワード」の受賞プロジェクト6件を詳細にケーススタディとして取り上げています。事例には、キユーピーのAI食品原料検査装置や楽天の自動翻訳プロジェクトなどが含まれ、効果を4つのカテゴリ(商品開発、消費者対応、働き方改革、社会課題解決)に分けて説明しています。また、松尾豊理事長による「ディープラーニング技術年表」も収録されており、技術的なアドバイスが提供されています。
本書は、機械学習に必要な数学の基本概念を最小限の前提知識から解説し、線形回帰、主成分分析、混合ガウスモデル、サポートベクターマシンの四つの手法を導出します。多くの図や例を用い、演習問題も用意されており、初学者が機械学習と数学の基礎を理解するための助けとなります。機械学習の普及に伴い、数学的な理解が求められる中、本書はそのギャップを埋める役割を果たします。
本書『機械学習の数理100問』は、機械学習を実践的に学ぶための演習形式の教材です。100の問題を解くことで、数式やPythonプログラムを理解し、自分のスキルを向上させることを目的としています。各章には解説と問題があり、問題から始めても解説を参照することで理解を深められます。大阪大学の講義や公開講座でも使用されており、高評価を得ています。統計的機械学習の著名な書籍に準拠した中間的な内容で、機械学習の知識やデータサイエンスに必要なスキルを身につけるのに適した一冊です。著者は大阪大学の教授で、データ科学や機械学習に関する研究を行っています。
本書は、機械学習の解釈性とその重要性に焦点を当て、特にブラックボックスモデルの理解を助ける手法を紹介しています。著者は、解釈性を高めるための4つの手法(PFI、PD、ICE、SHAP)を説明し、実務での適用方法や注意点を解説します。具体的には、線形回帰モデルを通じて解釈性を理解し、機械学習モデルの振る舞いを説明できるようになることを目指します。また、実データ分析を通じて手法を実装することが可能です。著者は、機械学習プロジェクトに従事する経験を持つ専門家です。
この本は、人工知能がプログラマや既存の科学を超えて進化し、人間の知性からも独立しつつある様子をわかりやすく語っています。内容は、将棋や囲碁における機械学習や強化学習の進展、倫理的な観点からの議論を含んでおり、著者は将棋プログラム「ポナンザ」の開発者である山本一成氏です。
この書籍は、Scratchプログラミングを学びたい子ども向けの改訂版で、最新のScratch 3.0に対応しています。小学校の教科に関連したプログラムを作成しながら、創造力や論理的思考力を育むことを目的としています。著者は教育の専門家で、実践的な作例やノウハウが豊富に盛り込まれており、特にmicro:bitとの連携についても説明しています。未経験者でも楽しめる内容で、保護者や教師が子どもと一緒にプログラミングを学ぶのに適しています。
この本は、初心者向けに「ボルツマン機械学習」を中心に機械学習を解説し、最終的には深層学習の実装まで導く内容です。イラストを用いてわかりやすく説明し、機械学習の専門用語や概念を解きほぐしています。章立ては、基礎から応用にかけて構成されており、著者は東北大学の准教授である大関真之氏です。
本書は、Pythonを用いた機械学習の入門書で、実際に手を動かしながら機械学習モデルの構築やWebサービスへの導入を学ぶことを目的としています。読者は、開発環境の整備からデータ収集、ユーザ反応の仕組み作り、推薦システムの構築まで、幅広いトピックを通じて機械学習を活用したサービス開発の基礎を習得できます。また、理論や詳細な実装に焦点を当てず、実践的なカリキュラムが組まれています。サンプルコードもダウンロード可能です。
この書籍は、ディープラーニングの理論的基礎と応用技術を詳しく解説しています。著者は、機械学習の基礎を扱った前著『はじめてのパターン認識』の著者であり、ディープラーニングが近年の技術として広く利用されるようになった背景や成功要因を探ります。内容は、誤差逆伝搬法や自動微分、最適化技法、さまざまなネットワーク構造(CNN、VAE、GAN、RNN、Self-AttentionとTransformer)についても網羅しています。機械学習分野の急速な進化に対応するための深い理解を促す一冊です。
この書籍は、AIを活用した様々な応用例を紹介しており、機械学習やディープラーニングの基礎、画像・動画処理、自然言語処理、業務効率化の方法などを学ぶことができます。また、マスク着用の判定など新しい生活様式に対応したサンプルも収録されています。著者はプログラミングや機械学習に関する多くの書籍を執筆しているクジラ飛行机氏をはじめ、専門家たちです。
この書籍は、データ分析における「分析モデル」をテーマにしたもので、回帰分析や深層学習、強化学習などの実践的な分析手法を網羅的に解説しています。著者は、データ分析者がモデルの本質を理解し、データを最大限に活用できるようにすることを目的としています。内容は定型データから非定型データの扱い、強化学習、データから知見を得る方法まで多岐にわたり、各章で具体的な手法や技術が詳しく説明されています。著者は東京大学の博士号を持つデータサイエンティストで、データ分析の啓蒙活動にも従事しています。
本書は、Unity 6に対応した初心者向けのゲーム制作入門書です。簡単な2Dゲームから始め、徐々に難易度を上げながら学ぶ構成になっています。プログラミング経験がない人でも安心して学べるようにC#の基礎知識が解説されており、ゲームを面白くするためのテクニックやレベルデザインの方法も紹介されています。著者は、ゲーム開発の経験を持つ北村愛実さんです。
本書は、AI社会における職業の不安を解消し、文系の人がAIを活用してキャリアアップするための実践トレーニング本です。専門用語を最小限に抑え、多様な業種別事例を通じてAIとの共働きスキルを身につける方法を紹介しています。内容は、AI社会での職の保持、文系向けのAIキャリア、AIの基本理解、企画力の向上、業種別事例の紹介などを含んでおり、特に文系のAI人材が社会に与える影響に焦点を当てています。著者はAIビジネスの推進に取り組む専門家です。
本書は、小学校低学年向けのドリル形式のScratch入門書で、5つのプロジェクトを通じてプログラミングの基礎を学べます。手を動かしながら直感的に学ぶことに重点を置き、図や手順を多用した構成で飽きずに進められます。Scratch3.0に対応しており、親子での学習や独習、指導者向けの教材としても利用可能です。著者は現役のシステムエンジニアとデザイナーです。
AIのベースの一つである機械学習とは、コンピュータに大量のデータや経験を与えることによって、事象のパターン・ルールを発見し、予測などまでをも実現する技術である。機械学習の基礎から筆者らの最先端の研究までを初めての人にもわかりやすく解説する一冊。 はじめに 1 機械学習とは何か――人工知能(AI)の基礎知識 1.1 人間の学習能力をコンピュータで再現する「機械学習」 1.2 AI研究、これまでとこれから 1.3 人工知能の/による/のための研究 2 人工知能と社会 2.1 研究者とともに、学生とともに、エンジニアとともに 2.2 さまざまな分野におけるAI技術の応用 2.3 AIと社会の関係 3 機械学習の基礎 3.1 AIの学習モデルと学習法 3.2 3種類の機械学習 3.3 教師付き学習とは 3.4 教師なし学習とは 3.5 強化学習とは 3.6 機械学習の原理:「学習する」とは 3.7 なぜ教師付き学習で予測が当たるのか? 3.8 直線で分離できない問題への対応 4 高度化する教師付き学習 4.1 誤りを含む教師情報への対応 4.2 弱い教師情報の活用 4.3 限られた情報からロバストに:信頼できる機械学習に向けて 4.4 理研AIPに見る汎用基盤研究の現在地 5 今後の展望 5.1 モデルと学習法と、ある種の制約 5.2 機械学習の新技術:生成AI 5.3 AIと人間の未来
本書は、統計学の基礎から応用までを扱った内容で、基礎編ではR言語を用いた記述統計や統計的仮説検定について解説し、応用編ではベクトルや行列、データフレーム、外れ値の影響などを取り上げています。著者は、教育心理学を専門とする学者たちで、各自が教育機関での実績を持っています。
本書は、日本ディープラーニング協会が実施する「ディープラーニングG検定」の法律・倫理分野に特化したテキストで、AI関連の法律や倫理を平易に解説しています。演習問題には過去の検定問題が含まれており、AI開発者やビジネスでAIを活用する人々に役立つ内容です。目次は導入、AIに関する法律と契約、AI倫理とガバナンスの3章から構成され、各法律や倫理の重要事項が詳述されています。
本書は、物理学と深層学習の関係を探る入門書で、物理学者の視点から原理から応用まで詳しく解説しています。機械学習が物理学に、またその逆も有用であることを示し、物理学的な観点からディープラーニングの原理や応用を体系的に学ぶことができます。目次は、機械学習の一般論から始まり、ニューラルネットワークの基礎や教師なし学習、さらには物理学への具体的な応用についても触れています。著者は理化学研究所の研究者であり、物理学と機械学習の交差点に関する最新の知見を提供しています。
本書は、ビジネスユーザー向けに機械学習の基本をExcelを通じて理解するための入門書です。第1部では機械学習の全体像やビジネス活用事例を紹介し、第2部では具体的なアルゴリズム(線形回帰、ロジスティック回帰、クラスタリングなど)をExcelで実現する方法を解説します。数式を避けながら、アルゴリズムのメリットやビジネスへの応用可能性を理解できる内容となっています。
本書は、ビジネス書グランプリや大賞を受賞した著者による現代の変化を分析し、AIとデータの発展がもたらす影響について論じています。読者は、社会の変化、企業の戦略、教育のあり方など多岐にわたる問いに対する答えを見つけることができます。著者は、建設的な未来の創造を目指し、ファクトベースでの現状分析を行い、ビジネス、教育、政策などの領域における具体的なアプローチを提案しています。
ビジネスパーソンにAIの書籍を1冊オススメするなら間違いなくこれを選ぶ。データサイエンティスト協会の理事も努めビジネス・アカデミックの両面からデータサイエンスにBETしている安宅さんが語るAIのあり方。我々日本人がこれからの時代において世界でプレゼンスを発揮するためにはどうすればよいかを教えてくれる書籍で非常に感銘を受けた。どんよりとした日本の停滞感に対して少しでも希望を見出すことのできる書籍。安宅さんの書籍はどれも素晴らしいが絶対にこれは読んで欲しい。
本書は、機械学習をビジネスに活用するためのAIエンジニア向けの入門書です。Pythonとscikit-learnを使用し、各手法のアルゴリズムを実装しながら学ぶ内容になっています。機械学習の概要や教師あり・教師なし学習の手法、モデル評価の方法を解説し、実践的なプログラミングを通じて理解を深めることを目的としています。著者は機械学習の研究開発に従事する専門家です。
本書『G検定 公式テキスト 第3版』は、ディープラーニングの基礎知識を学ぶための試験対策書で、新シラバスに完全準拠しています。日本ディープラーニング協会の監修のもと、章末問題や解説が一新され、初心者にも適しています。G検定は、ディープラーニングの知識と事業活用能力を評価する試験で、オンラインで年6回実施されます。対象読者は、G検定受験者やディープラーニングの活用を考える人々です。著者は中部大学の教授で、AI分野での実績があります。
本書は、野村総合研究所のアナリティクス研修を基にした増補改訂版で、ビジネス現場でのデータ分析や統計解析、機械学習の実践を重視しています。内容は、統計的モデリングの基本、要因分析と予測の違い、モデル作成の手順、結果解釈の注意点などを含み、RとPythonを使った実務体験が可能です。データサイエンスに関心がある方に向けた最短学習コースです。
「彼が京大に入る確率は80%」などというように,「確率」は日常の用語としても広く使われる.しかし,そもそも確率とは何か? 厳密な公理的確率論が確立しているがために,かえってこれまでの教科書では,確率とは何か,をきちんと語っていない.日常の「確率」概念を根底から問い直すところから,読者を数学の世界に誘う.
本書は、金融、流通、製造、インフラなど8業界36業種におけるAI導入事例を解説し、活用分野や親和性について鳥瞰図で示しています。豊富な実例を通じてビジネスアイデアの創出を促し、実装やトライアルのノウハウも提供。各業種ごとに具体的な解説があり、AIの実用性や将来可能性を探る手助けとなります。購入者特典として鳥瞰図のダウンロードも可能です。著者はAIとデータ分析の専門家で、実績豊富です。
本書は、ファインチューニングの基本から実践までを具体的なPythonコードを通じて解説しています。画像識別や自然言語処理、生成AIモデル、強化学習におけるファインチューニングの手法を「レシピ」として整理し、実務での活用を目指すエンジニアや学生に向けた内容です。各章では基礎知識や手順を詳しく説明し、読者が自身の課題に合わせて実践できるようにしています。ファインチューニングを始めたい方や実践のコツを学びたい方におすすめの書籍です。
本書は、人気のプログラミング入門書「はじめてのプログラミング」をScratch 3.0に対応させ新装改訂したもので、漫画と解説を組み合わせてゲーム制作を学ぶ内容になっています。付録にはプログラミングスキルをさらに発展させるための情報や人工知能のコーナーも含まれています。著者はプログラミング教育に関わる専門家たちで構成されています。
改訂3版のG検定受験者必携問題集が登場しました。最新のシラバスや出題形式に基づき全編が書き下ろされ、解説はわかりやすく、収録問題も増加。巻末には模擬試験「総仕上げ問題」があり、試験直前の実力診断をサポートします。目次には人工知能の基礎から法律、倫理に関する内容が含まれています。
この書籍は、人工知能(AI)と人間の共存について考察し、知性の認識や人間の生き方を探る内容です。三部構成で、第一部ではAIの歴史やディープラーニングの進展を解説。第二部ではAIが世界の見方に与える影響を論じ、第三部ではAIと人間社会の関係や自由主義の課題について考察します。著者はそれぞれ異なる専門分野から、AIの進展がもたらす新しい時代の教養について議論します。
この本は、プログラミング初心者向けの入門書で、カラフルなイラストと丁寧な解説を通じて、プログラミングの基本やゲームの作り方を学ぶことができます。特に「スクラッチ」と「Python」の2つのプログラミング言語を扱い、7つのプロジェクトを通じて実践的なスキルを身につけることを目指します。また、コンピューターの仕組みや現実世界でのプログラミングの応用についても触れています。すべての漢字にはふりがなが付いており、子どもでも理解しやすい内容です。
本書は、機械学習の基礎から実践的な活用法までを解説した一冊で、管理職や技術者に向けて書かれています。内容は、機械学習の概念や手法、タスク、企業での活用方法、具体的な適用事例、実運用に耐えうるモデルの構築、モデルの説明性について詳しく述べられています。著者は、機械学習エンジニアとしての経験を活かし、理論と実践を結びつける橋渡しをしています。
本書は人気シリーズの第4弾で、強化学習をテーマにしています。外部ライブラリに頼らず、基本的な技術やアイデアをゼロから実装しながら学ぶスタイルを採用しています。理論と実践の両面から、強化学習の構成要素を丁寧に解説し、数式だけでなくコードを通じて理解を深めることができます。目次にはバンディット問題やマルコフ決定過程、ベルマン方程式などが含まれています。著者は人工知能の研究開発に従事する斎藤康毅氏です。
強化学習のイメージを掴むのに最適な本です。難しい理論や細かい実装テクニックなどは端折って、"強化学習って何をしているの?"を誤魔化すことなく0から説明しています。取り扱っているトピックの範囲は狭いですが、強化学習の基礎的なトピックに対して深く堅い普遍的な理解が得られます。 著者は他分野でもゼロつくシリーズとして高品質な書籍を量産していますが、こんなに広い分野に対して正しい解釈と体系を構築できることに畏怖の念を抱いてしまいます。
本書は、人工知能(AI)を学びたい初心者向けの入門書であり、特にエンジニアでない中高生や文系の大学生、ビジネスパーソンに向けて分かりやすくAIの基礎知識とビジネス活用法を解説しています。著者は人気講師で、初心者にも理解しやすい内容に配慮しています。書籍は3部構成で、基礎編ではAIの基本を、ビジネス編では業界別の活用事例と注意点、技術編ではAIの仕組みと最新技術を紹介しています。これにより、AIの本質や活用方法についての理解を深めることができます。
本書は、ディープ・ラーニングの基礎とそのプログラム化についてステップ・バイ・ステップで解説し、ラズベリー・パイでの実装方法も紹介しています。また、データサイエンスの技術を用いて製造現場の課題を解決するためのデータ分析やプログラミング技術に重点を置き、実践的なサンプルプログラムを提供しています。目次には、ディープ・ラーニングの紹介から、ラズパイでの体験、プログラミング練習、主要アルゴリズムの体感、自動運転や対戦AIの深層強化学習までが含まれています。
この書籍は、人工知能プログラミングに必要な数学を基礎から優しく学べる参考書です。著者は「10秒で始める人工知能プログラミング学習サービス」の代表者で、数学に苦手意識がある人でも理解できる内容になっています。基本的な数学から微分、線形代数、確率・統計を学び、実践編では住宅価格の推定や自然言語処理、手書き数字認識などの具体的な例を通じて理解を深めます。対象読者は、AIアルゴリズムを学びたいが数学に不安がある人々です。
この書籍は、導出システム、MLの操作的意味論、及び型システムについての内容を三部構成で解説しています。第1部では自然数の基本演算や証明方法を紹介し、第2部ではMLの評価や関数、リストの扱いについて説明しています。第3部では型システムの基本概念や型推論を扱っています。著者は五十嵐淳で、東京大学及び京都大学での教育・研究経験があります。
この書籍は、UnityとC#の基本を学ぶための入門書で、初心者向けに「究極のやさしさ」を目指しています。コードには「ふりがな」が付いており、「読み下し文」での解説もあります。内容は、UnityとC#の基礎、条件分岐、繰り返し文、ゲームオブジェクトの操作、ゲーム制作の要素を学ぶ構成になっています。著者はゲーム開発の経験が豊富な安原祐二氏です。
この書籍は、スクラッチを使ってアクションゲームやレーシングゲームなど8種類のゲームを作る方法を学べる解説書です。カラフルなイラストと図解で、楽しみながらプログラミングを学べ、カスタマイズも自由自在。作成したゲームは仲間と遊んだり、オンラインで公開することができます。内容は、コンピューターゲームの基礎から始まり、具体的なゲーム作りの手順やプログラミングの技術まで幅広くカバーしています。全ての漢字にはふりがなが付いています。
本書は、Pythonを用いて強化学習と転移学習の基礎から応用までを学べる内容です。強化学習の理論やシミュレーションを丁寧に解説し、簡単なプログラミング経験があれば理解できるようになっています。また、転移学習を組み合わせた転移強化学習についても詳しく説明し、学習の効率化や実装上の注意点も網羅しています。著者は東京工芸大学の准教授で、関連ソースコードは出版社のウェブサイトで公開されています。
この書籍は、ガウス過程に関する日本初の入門書であり、ベイズ的回帰モデルの柔軟性を解説しています。内容は線形回帰から始まり、ガウス過程の原理や教師なし学習、実応用に関する最新の話題も取り上げています。各章では、ガウス過程の基本概念、計算法、適用例などが詳しく説明されています。著者は統計や情報科学の専門家です。
本書は、音声認識システムにおける音源分離技術を解説したもので、特に中級者以上を対象としています。音源分離は、複数の音が混ざった中から特定の音を抽出する技術であり、基礎からPythonを用いた実装まで詳しく説明しています。目次には音声処理の基礎や数学的知識、古典的および現代的な音源分離方法、残響除去法などが含まれています。著者の戸上真人は音声処理の専門家で、AI研究に従事しています。
初心者向けにプログラミングの基本を会話形式で楽しく学べる本です。プログラムの仕組みがイメージしやすく、キャラクターとのやり取りを通じて、複雑な概念もスムーズに理解できる内容になってます。プログラミングに全く触れたことがない人でも、無理なく始められる工夫がいっぱいで、Pythonの基礎を楽しみながら身につけたい人におすすめ。
この書籍は、R言語を用いたデータ解析の入門書で、進化し続けるRの機能を活用する方法を紹介しています。初版以来、多くのRユーザーに支持されてきたロングセラーで、第2版では深層学習やネットワーク分析など新たな内容が追加されています。データマイニングの基礎から始まり、主成分分析やクラスター分析、ニューラルネットワークなど多岐にわたる分析手法を学ぶことができます。著者は金明哲で、統計科学の専門家です。
この本は、Pythonを使用した機械学習における216の問題とその解決策を提供します。データの基本的な取り扱いから、特徴量抽出、次元削減、様々なモデル(線形回帰、決定木、ランダムフォレスト、SVM、ニューラルネットワークなど)まで広範囲にカバーしています。改訂版では最新のフレームワークに対応し、PyTorchを用いたニューラルネットワークの情報が増加しています。実践的な問題解決に役立つ内容です。
この書籍は、TensorFlowを用いて深層学習モデルを構築する方法を解説しています。ニューラルネットワークの基礎から、CNNやRNN、転移学習を利用したキャプション生成までをカバーし、データ整形からモデル構築までのプロセスをステップ・バイ・ステップで示しています。著者は新村拓也氏で、機械学習やデータマイニングの専門家です。
『独習Python』は、プログラミング初学者向けのPython入門書で、著者は山田祥寛氏です。本書は、手を動かして学ぶスタイルを重視し、Pythonの基本から応用までを体系的に学べる内容となっています。解説、例題、理解度チェックの3ステップで、基礎知識がない人でも理解しやすい構成です。プログラミング初心者や再入門者におすすめの一冊です。目次には、Pythonの基本、演算子、制御構文、標準ライブラリ、ユーザー定義関数、オブジェクト指向構文などが含まれています。
Pythonをしっかり学びたい人向けの本格的な入門書です。基礎から応用まで幅広いトピックをカバーしており、実際に手を動かしながら理解を深められるよう工夫されています。独習スタイルに特化しているため、自分のペースで着実に学びたい人におすすめ。豊富なコード例や練習問題もあり、プログラミングの実力を着実に高めることができます。
このビジネス書は、機械学習やディープラーニングの基本概念からビジネスチャンスまでを図解でわかりやすく解説し、法律的なリスクについても弁護士が詳しく説明しています。内容は、人工知能と共創するビジネスの未来、自動運転技術、ドローンビジネス、画像認識、マッチングビジネス、フィンテックなど幅広いテーマをカバーしています。著者は法律とビジネスの専門家で、企業の戦略立案やM&Aに関する豊富な経験を持っています。
この書籍は、記号論理の入門書として知られる旧著の新装版で、安東祐希による補足が加えられています。内容は、命題の表現法、演繹、真理値、トートロジー、命題の同値、ド・モルガンの法則、さまざまな同値式に関する章で構成されており、論理記号やその使用法について詳しく解説しています。また、補遺や付録も含まれており、論理体系の理解を深めるための参考資料が提供されています。著者は前原昭二で、数学の教育に長年携わってきました。
本書は、機械学習や深層学習の予備知識がない読者を対象に、理論を明快に解説する入門書です。内容は、機械学習と深層学習の基本、ニューラルネットの仕組み、勾配降下法、誤差逆伝播法、自己符号化器、畳み込みニューラルネット、再帰型ニューラルネット、ボルツマンマシン、深層強化学習など多岐にわたります。著者は、理論的な基礎を重視し、学びやすい形式で解説しています。
『Python実践 機械学習システム 100本ノック 第2版』は、データ分析プロジェクトの成果を上げるための実践的なテクニックを提供する書籍です。内容はデータの加工・可視化、機械学習モデルの構築、分析レポート作成などを含み、ビジネス現場で即戦力となるスキルを習得できます。新たに生成AIの活用ノックが追加され、読者は最新技術を学びながら実践的な課題に挑戦できます。著者は業界での豊富な経験を持ち、データ分析やAIシステム開発に関する専門知識を活かしています。
「強化学習」に関するよくある質問
Q. 「強化学習」の本を選ぶポイントは?
A. 「強化学習」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「強化学習」本は?
A. 当サイトのランキングでは『Pythonではじめる機械学習 ―scikit-learnで学ぶ特徴量エンジニアリングと機械学習の基礎』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで179冊の中から厳選しています。
Q. 「強化学習」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「強化学習」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。








![『機械学習スタートアップシリーズ Pythonで学ぶ強化学習 [改訂第2版] 入門から実践まで』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/5124MXduAyL._SL500_.jpg)























![『[第3版]Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践 (impress top gear)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51j2a-lVLyL._SL500_.jpg)





































































![『(コードDL可能)Pythonライブラリによる因果推論・因果探索[概念と実践] 因果機械学習の鍵を解く (impress top gear)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51GvWpfSciL._SL500_.jpg)
![『RとPythonで学ぶ[実践的]データサイエンス&機械学習【増補改訂版】』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51zfxaceWyL._SL500_.jpg)