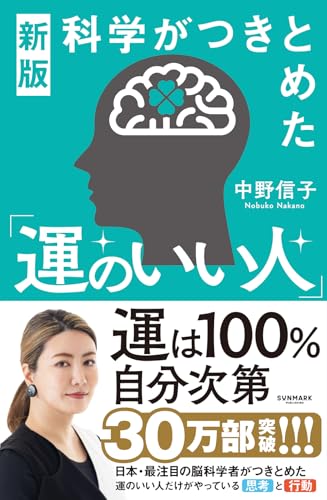【2025年】「脳科学」のおすすめ 本 149選!人気ランキング
- メカ屋のための脳科学入門-脳をリバースエンジニアリングする-
- 進化しすぎた脳―中高生と語る「大脳生理学」の最前線 (ブルーバックス)
- 脳を鍛えるには運動しかない! 最新科学でわかった脳細胞の増やし方
- つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線 (ブルーバックス 1994)
- カラー図解 脳の教科書 はじめての「脳科学」入門 (ブルーバックス)
- 量子革命: アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突 (新潮文庫)
- 「人間とは何か」はすべて脳が教えてくれる: 思考、記憶、知能、パーソナリティの謎に迫る最新の脳科学
- 面白くて眠れなくなる脳科学
- 小説みたいに楽しく読める脳科学講義
- 意識はいつ生まれるのか――脳の謎に挑む統合情報理論
この書籍は、脳科学をエンジニアリングの視点から探求する内容で、以下の5つの編から構成されています。第1編では脳の構造と機能を紹介し、第2編では神経細胞の特性と情報処理メカニズムを解説。第3編では運動の制御機構について、第4編では知覚の形成と脳の学習メカニズムを探ります。最後に第5編では脳と芸術の関係を考察し、好みや芸術の法則性について論じています。著者は東京大学の高橋宏知で、神経工学と聴覚生理学の専門家です。
この書籍は、最新の科学に基づいて脳細胞の増やし方を解説しています。目次には、運動や学習、ストレス、不安、うつ、注意欠陥障害、依存症、ホルモンの変化、加齢、そして脳を鍛える方法が含まれています。著者はハーバード大学の医学博士ジョン・レイティで、精神医学の専門家として多くの研究を行っています。彼はまた、定期的な有酸素運動の重要性を広める活動でも知られています。
この書籍は、脳の働きについての最新研究を紹介し、記憶や感情、認知のメカニズムを探求しています。具体的には、グリア細胞やニューロン、空間記憶、感情の神経回路など、脳内のさまざまな「つながり」を解明する9つの章から構成されています。脳の機能や病気の治療法、親子の絆に関する研究も含まれており、心を生み出す脳の理解を深める内容となっています。
この書籍は、脳の構造や機能について豊富なカラー図版を用いてわかりやすく解説しています。脳の進化、神経細胞やグリア細胞の役割、記憶の形成と蓄積、意識や思考のメカニズムなど、脳に関する多様な謎を最新の研究を交えて紹介しています。医学生や医療関係者だけでなく、脳に興味があるすべての人にとって必読の一冊です。著者は、脳の高次機能や進化に関する研究を行っている京都大学名誉教授の三上章允です。
この書籍は、1900年にM・プランクが「量子」という概念を考案したことから始まり、量子力学の発展と、それに伴う物理学の変革を描いたノンフィクションです。アインシュタインとボーアの論争を中心に、ハイゼンベルク、ド・ブロイ、シュレーディンガーなどの物理学者の人間ドラマも交えながら、物理学の100年の歴史を追います。著者はマンジット・クマールで、翻訳は青木薫が担当しています。
この本は、脳の不思議や可能性について探求する内容で、右脳と左脳の役割、脳の細胞の重要性、自己認識のメカニズムなどを解説しています。目次では、脳の歴史や脳科学と心理学の関係、夢のメカニズムなど多様なテーマが取り上げられています。著者は毛内拡で、脳科学の専門家として研究を行っています。
NHKスペシャル『立花隆 臨死体験』出演の天才脳科学者、初の翻訳! 脳は意識を生み出すが、コンピューターは意識を生み出さない。では両者の違いはどこにあるのか。クリストフ・コッホが「意識に関して唯一、真に有望な基礎理論」と評した、意識の謎を解明するトノーニの「統合情報理論」を紹介。わくわくするようなエピソード満載でわかりやすく語られる脳科学の最先端、待望の翻訳! 【本書が挑む脳科学最前線の驚異の事例】 ・脳幹に傷を負い植物状態に見えるロックトイン症候群患者(映画「潜水服は蝶の夢を見るか」の主人公)。彼らの意識の有無はどう診断すればいいのか? ・麻酔薬を投与するとなぜ意識が失われるのか? 麻酔時に意識が醒めてしまうとどうなるのか(1000人に1人はそうなる) ・右脳と左脳をつなぐ脳梁を切断する(スプリットブレイン。てんかん治療で行われることがある)と、1つの脳のなかに意識が2つ生まれる!?
著者池谷裕二の新著は、最先端の脳科学に基づき「心」の生成メカニズムを探求する連続講義の内容をまとめたものです。私たちの心に対する理解が最新の研究によって変わっていく様子を描き、著者自身が特に愛着を持つ作品としています。各章では、脳の理解、心の視点、自由の創造、ノイズからの生命生成などがテーマとなっています。
この書籍は、最新の脳科学を基に人間の心と行動を科学的に検証し、行動の背後にある理由を解明します。脳の機能や記憶力向上、メンタルの鍛え方、恋愛やダイエットの方法、認知機能の維持、天才と普通の人の脳の違いなど、実生活に役立つ情報が豊富に含まれています。全5章で脳と心の関係、感覚の不思議、意外な研究結果、恐怖に関する研究、倫理的問題の処理などを紹介し、脳科学への興味を引き立てる内容となっています。著者は玉川大学脳科学研究所の教授、坂上雅道氏です。
この文章は、脳の構造や機能、記憶、学習、意識、倫理に関する内容を扱った書籍の目次を紹介しています。手法編では脳の観察方法、記憶・学習編では海馬の役割、意識編では情動や無意識の意思決定、倫理編では社会的価値について触れています。また、著者の高橋宏知は神経工学と聴覚生理学の専門家で、東京大学で講師を務めています。
このビジュアル図鑑は、脳の構造や機能、最新の研究成果をわかりやすく解説しており、入門書や参考書に最適です。内容は脳の成り立ち、機能、感覚、コミュニケーション、記憶、意識、未来の脳、関連疾患について構成されています。著者は九州大学の専門家たちです。
本書は、意識の謎に迫る研究者たちの最新のレポートをまとめたもので、脳の物質的な反応から意識がどのように生まれるのかを探求しています。クオリアやニューロンの知見を基に、実験成果を通じて人間の意識の理解を深め、人工意識の可能性についても考察します。著者は脳科学の専門家であり、意識研究の最前線を描き出しています。
この書籍は、認知脳科学に関する内容を扱っており、脳の構造や機能、視覚や他の感覚、運動、感情、記憶、学習、エグゼクティブ機能、社会性認知について詳述しています。著者は嶋田総太郎で、慶應義塾大学で工学の博士号を取得し、東京大学や明治大学で研究・教育に従事してきた専門家です。
1848年、米国での事故により、現場監督P・ゲージの性格が変わった。この事例を通じて、著者アントニオ・ダマシオは、合理的な意思決定が身体状態と結びついた情動や感情の影響を受けることを示す「ソマティック・マーカー仮説」を提唱。彼は心身二元論を批判し、心、脳、身体の関係を探求する。新訳文庫版で、著者の経歴も紹介されている。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
本書は脳の基本的な構造や機能をイラストと図解でわかりやすく解説した入門書です。脳の役割、感情や記憶、体との連携、五感のメカニズム、体の調整機能、老化に伴う病気について触れています。監修者の加藤俊徳氏は、脳を理解することが人生を知ることにつながると述べ、脳の成長と変化が個人の経験に影響を与えることを強調しています。読者に脳への関心を深めてもらうことを目的としています。
この書籍は、生命の本質について分子生物学がどのように答えているかを探求し、歴史的な科学者たちの思考を紹介しながら、現代の生命観を明らかにします。著者の福岡伸一は、分子生物学の成果を平易に解説し、読者の視点を変える内容を提供しています。多くの著名人から高く評価され、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞しています。
この書籍は、楽観主義と悲観主義の脳の活動パターンの違いを探求し、人格形成のメカニズムを心理学、分子遺伝学、神経科学の視点から解明します。著名な楽観主義者たちを例に、彼らが逆境を克服する際の思考方法を考察しています。著者は心理学者・神経科学者のエレーヌ・フォックスで、オックスフォード大学で感情神経科学センターを率いています。
この文章は、重力の不思議な性質とその宇宙における重要性について述べています。重力は生命や星の形成に不可欠で、その研究はニュートンやアインシュタインの理論を経て現在の第三の黄金期を迎えています。内容は、特殊相対論や一般相対論、ブラックホール、量子力学、超弦理論など多岐にわたり、重力の謎を解明する冒険が描かれています。著者は大栗博司で、素粒子論や超弦理論の専門家です。
この書籍は、男性脳と女性脳の違いを理解し、それを活用することでコミュニケーションやビジネスの結果を向上させる方法を紹介しています。著者のメンタリストDaiGoは、脳の特性に基づく「伝え方」や「見せ方」を変えることで、交渉や営業、評価、面接などでの成功を目指します。内容は、脳の違いを利用したマインドセットや具体的な行動ポイント、異性脳を身につけるためのワークを含んでいます。
この書籍は、私たちの行動が「自分の意識」によって制御されているのではなく、脳が自動的に動いていることを解明しています。著者のデイヴィッド・イーグルマンは、意識が脳の活動を傍観しているだけであり、行動の責任について考える必要があると指摘しています。内容は、脳と心の関係や行動のメカニズムについての最新の脳科学を紹介しており、意識の働きについての理解を深めることを目的としています。
この本は、ドーパミンが私たちの欲求、創造性、成功に与える影響を探求しています。ドーパミンは「快楽物質」ではなく、「欲求ドーパミン」と「制御ドーパミン」の2つの回路を通じて期待や達成感を生み出します。著者は、恋愛、依存症、創造性、政治、社会の進歩など、多様なテーマを通じてドーパミンの役割を解説し、未来志向のドーパミンと現在志向のバランスが脳の潜在能力を引き出す鍵であると述べています。著者はダニエル・Z・リーバーマンとマイケル・E・ロングです。
自分探し」は、これでおしまい! 「やりたいことがわからない人」に贈る科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」。 「私は、何がしたいんだろう?」「自分の人生、このままでいいのだろうか?」一度でも、こんなことを考えたことはありませんか?人と比べて、「何者でもない自分」に絶望したとき先が見えなくて、「将来が不安」なとき就職、転職、結婚、第2の人生……「人生の岐路」に立たされたとき今の仕事に「やりがい」を感じられないときなかなか結果が出なくて「焦っている」ときそんなとき、向いている仕事、自分の強み、進むべき道を考えて、自分で、自分がわからなくなる――。こうした「自分探し」は、今日でもうおしまい!本書は、200以上の論文と7つのワークで、科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」を解説します。ワーク1 「ライフワークの原石」を見つけようワーク2 「ライフワークの原石」を採点してみようワーク3 7つの質問で「自分の個性」を可視化するワーク4 自分の才能がわかる「診断シート」ワーク5 自分に「向いている仕事」を探すワーク6 「3つのバランス」を確認しようワーク7 「メメント・モリ」で人生の優先順位を明らかにこの1冊で、これまでのモヤモヤがパっと晴れる「やりたいこと探し」の決定版。
脳科学者・中野信子の初めての児童書は、子どもたちが「イヤな気持ち」にどう向き合い、エネルギーに変えるかを脳科学の視点から解説しています。人間関係や将来への不安、承認欲求などの悩みを抱える思春期の子どもたちに、自分の力で感情を処理する方法をアドバイスします。内容は、脳の機能や「イヤな気持ち」を成長の糧とする重要性についてのメッセージを含んでいます。
『頭がよくなる!寝るまえ1分おんどく366日』に続く、1歳から始められるファースト音読ブックが登場。子どもの脳を左右同時に鍛え、言葉や文字への興味を引き出し、伝える力を育成。親子での音読が良い眠りを促し、学びを定着させる。内容は昔話や名作、詩、ことわざなど多岐に渡り、楽しいイラストで理解を深める工夫がされている。著者は脳科学者の加藤俊徳。
人間はどのように世界を認識しているか? 「情報」という共通言語のもとに研究を進める認知科学が明らかにしてきた,知性の意外なまでの脆さ・儚さと,それを補って余りある環境との相互作用を,記憶・思考を中心に身近なテーマからわかりやすく紹介. 【円城塔氏(作家)推薦の辞】 「この本を読むと,人間は自分で思っているよりも,いい加減なものだとわかる.いい加減な人が読むべきなのはもちろんだが,自分はしっかりしていると思っている人こそ,読むべきである.」 【長谷川寿一氏(東京大学教授)】 「知性とは何か? この問いに挑む認知科学は諸科学が交わるホットスポットだ. 東大駒場の名物講義を是非あなたにも.」 第1章 認知的に人を見る 認知科学とは 知的システム しくみ、はたらき、なりたち 学際科学としての認知科学 情報——分野をつなぐもの 生物学的シフト 認知科学を取り巻く常識? 第2章 認知科学のフレームワーク 表象と計算という考え方 さまざまな表象 知識の表象のしかた 認知プロセスにおける表象の役割 第3章 記憶のベーシックス 記憶の流れ 記憶と意図 一瞬だけの記憶——感覚記憶 人の記憶はRAMか——短期記憶とチャンク ワーキングメモリ——保持と処理のための記憶 知識のありか——長期記憶 情報を加工する——短期記憶から長期記憶へ 思い出しやすさ——符号化特定性原理 思い出していないのに思い出す——潜在記憶とプライミング まとめ 第4章 生み出す知性——表象とその生成 はかない知覚表象 言葉と表象 作り出される記憶 記憶の書き換え 仮想的な知識——アナロジー まとめ——表象とは何なのか 第5章 思考のベーシックス 新たな情報を生み出す——推論 目標を達成する——問題解決 選ぶ——意思決定 人間の思考のクセ まとめ 第6章 ゆらぎつつ進化する知性 四枚カード問題、アゲイン データに基づき考える 思考の発達におけるゆらぎ ひらめきはいつ訪れるのか まとめ——多様なリソースのゆらぎと思考の変化 第7章 知性の姿のこれから 表象の生成性 身体化されたプロセスとしての表象 世界への表象の投射 思考のゆらぎと冗長性 世界というリソース おわりに 引用文献 索引
この書籍は、脳の8つのエリアを活性化させる66のトレーニングメニューを紹介しています。内容は、思考、感情、運動、聴覚、視覚、伝達、理解、記憶に関する脳のトレーニングに分かれています。著者は加藤俊徳医師で、脳機能に関する研究を行ってきた専門家です。
本書は、Googleの独自研修プログラム「サーチ・インサイド・ユアセルフ(SIY)」を通じて、楽しく創造的に働くためのマインドフルネスの実践方法を紹介しています。著者のチャディー・メンは、自己認識力や創造性を高める技法をユーモアを交えてわかりやすく説明し、ビジネスパーソンや入門者にとっての実践バイブルとしています。SIYは他の企業や大学でも採用されており、情動的知能を育むことが強調されています。
本書は、運の良さは生まれつきではなく、考え方や行動パターンによって変わることを示し、「運のいい人」になるための習慣を紹介しています。著者である脳科学者・中野信子は、運の良さを高めるための思考法や行動を解説し、具体的な方法を提案しています。内容は、自己中心的な思考、ポジティブな自己イメージ、他者との共生、個人の幸せに基づく目標設定、そして祈りの重要性に分かれています。
この本は、親が一貫した姿勢を持つことの重要性を説き、子育ての悩みを解決するための具体的な方法を提供します。著者の奥田健次は、数万件の育児問題を解決してきた専門家であり、子どもとの接し方やルール作り、効果的な叱り方など、実践的なアドバイスを通じて「親子ともによく育つ」方法を提案しています。内容は、いじめやスマホの使い方、不登校のリスクなど現代の課題にも対応しています。
本書は、社会認知神経科学の専門家であるマシュー・リーバーマンが、人間の脳に備わる「つながる」「心を読む」「調和する」という三つの力が人類の発展の鍵であることを探求しています。脳の働きや社会的な関係性、感情の理解、そして日常生活での実践方法について述べられており、より良い生活を送るためのヒントが提供されています。目次は進化と社会性、つながる脳、心を読む脳、調和する脳、実践編の五部構成になっています。
本書は、神経科学の進歩により脳の記憶のメカニズムが明らかになり、記憶力を高める方法を科学的に探求する内容です。著者は「夢の薬」を研究し、LTPやシナプス可塑性などの最新理論を解説しながら、具体的な記憶力向上法を紹介しています。著者は記憶を未来の自分へのメッセージと捉え、巧妙な記憶の仕組みを読者に伝えています。目次には脳の構造や記憶の可塑性、記憶力を鍛える方法、未来の脳科学についての章が含まれています。
この本は、寝る前に1分間音読を行うことで子どもの「読む力」を育て、脳の発達を促すことを目的としています。音読は視覚、聴覚、理解を結びつけ、集中力や理解力を高める工夫がされています。内容は名作や古典、詩など多岐にわたり、1日1ページの構成で集中しやすく、質の良い睡眠を通じて記憶の整理を助けます。著者は脳科学者の加藤俊徳氏で、脳の成長を促すメソッドを提唱しています。
本書は、脳科学者の中野信子が「世界で通用する頭のいい人」が実践している31の方法を紹介しています。これらの方法は、空気を読まないことや適度なストレスを与えること、嫌いな仕事を他人に振ることなど、脳科学的に理にかなったテクニックです。内容は、頭のいい人の特徴や心がけ、スケジュールの立て方、自己分析、自己改良の方法について具体的に解説されており、誰でも実践できるコツが満載です。
本書は、脳研究の第一人者・池谷裕二氏が、最新の研究成果を基に脳と心の関係について探求する内容です。心や意識の起源、臨死体験、脳の病気、さらには脳の若返りに関する研究など、多様なテーマを扱っています。視覚的に理解しやすい画像や3Dイラストも豊富で、脳の新しい理解を提供します。著者は東京大学の教授で、脳の可塑性を研究しています。
本書は、大人が効果的に学び直すための方法を紹介しています。加齢による脳の記憶力低下は誤解であり、大人の脳は学生時代よりも優れた状態にあると説明されています。脳科学に基づいた勉強法や記憶力向上のテクニックを提案し、30代から60代以降までの大人が脳力を高めるための具体的な方法を提供します。著者は脳内科医の加藤俊徳で、脳の成長段階やトレーニングについての専門家です。
この本は、スタンフォード大学の脳神経外科医が「引き寄せの法則」とその科学的根拠を解説し、富と幸運を引き寄せるための6つの具体的なステップを提供しています。内容は、集中力の回復、真の願望の明確化、ネガティブな自己イメージの排除、無意識への意図の埋め込み、目的の追求、期待を手放すことに焦点を当てています。著者は、自己実現を促進するための脳の働きとその活用法を紹介し、科学と個人の経験を結びつけています。
この書籍は、子どもの脳力を最大限に引き出すための0~3歳向けの育脳としつけに関する指南書です。親が日常生活で実践できる具体的な方法を示し、子どもが自分で考える力を育てるためのポイントを解説しています。内容は、規則正しい生活や安心感を与えること、遊びを通じた学び、親子のコミュニケーションの重要性などに焦点を当てています。著者は小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏で、専門用語を避けて分かりやすくまとめられています。
本書は、脳の基本的な仕組みや高次機能の成長方法について解説しています。前半では脳の各部位の機能やメカニズムを平易に説明し、後半では脳のネットワーク化を基にした活用法を紹介しています。著者の加藤俊徳氏は「脳番地」という概念を提唱し、脳の8つの部位の特性を理解することが重要であると述べています。大人でも脳を成長させる方法があり、年齢に関係なく能力を伸ばすことが可能です。
人類は、なぜ「さみしい」という感情を持つのか?あなたの知らないあなたの心を脳科学の視点で解き明かす! さみしさは心の弱さではない。生き延びるための本能-。人類は、なぜ「さみしい」という感情を持つのか?あなたの知らないあなたの心を脳科学が解き明かす!「ひとりでいるのがつらい」「誰といても満たされない」集団をつくり、社会生活を営むわたしたち人類のなかで、さみしい・孤独だと一度たりとも感じたことがない人は、おそらくいないのではないでしょうか。集団をつくる生物は、孤立すればより危険が増すため、さみしさを感じる機能をデフォルトで備えているはずだからです。さみしさは人類が生き延びるための本能であり、心の弱さではありません。それなのになぜ、私たちは、「さみしいのは、よくないことだ」「ひとりぼっちは、みじめだ」などと考えてしまうのでしょうか。そこには、さみしさという感情を捉える際に起こりがちな、さまざまな思い込みや刷り込み、偏見が隠れています。本書では、脳科学的、生物学的な視点から、なぜ、さみしいという感情が生じるのかという問いに焦点をあてていきます。また、なぜ、さみしいという感情をネガティブなものと捉えてしまうのか、その科学的要因、社会的要因からも考察していきます。すべての感情には、意味があるはずです。であれば、さみしいという感情が生じたときにも、無理に抑え付けたり、なかったことにしたりするのではなく、「そこにはどんな意味があるのか」を考え、理解していくほうが、この感情をスムーズに扱えるのではないでしょうか。さみしさの扱い方に慣れ、その生じる仕組みを理解することで、さみしさを必要以上におそれることなく、振り回されることもなく、上手に付き合いながら、長い人生をより豊かに、穏やかな気持ちで過ごしていくことができるようになるはずです。 ○第1章 なぜ、人はさみしくなるのか …さみしさは「人間が生き延びるため」の仕組み …さみしさの本質を知る意味 など ○第2章 わたしたちがさみしさを不快に感じる理由 …「さみしいのは、よくないことだ」という思い込みが苦しみを強める …なぜ「ソロ活」は流行し、「ぼっち」は忌み嫌われるのか など ○第3章 脳や心の発達とさみしさの関係 …わたしたちの脳や心は石器時代から変わっていない …思春期に孤独感が強くなる理由 など ○第4章 さみしさがもたらす危険性 …心の弱みに付け込む悪意ある人たち …「激しい怒り」に内在する強いさみしさ など ○第5章 さみしさとうまく付き合っていくために …趣味でつながる新しい共同体の在り方 …さみしいときに持つべき思考の〝置き換え″ など
本書は、著者が出会った奇妙な症状を持つ患者たちを通じて、脳の不思議な働きや仕組みについて考察する内容です。切断された手足を感じるスポーツ選手や、自分の体の一部を他人だと主張する患者などの実例を挙げ、脳の機能や意識、自己の本質に迫ります。著者は、左脳と右脳の異なる役割についての仮説や、意識に関する「ハードプロブレム」など、現代の神経科学の最前線をわかりやすく解説しています。名著が文庫化され、脳の世界の魅力を伝えています。
「脳活ドリル」の最新刊は、1日1ページ、100日間で楽しみながら脳を鍛える内容です。熟語問題やダジャレ、間違い探し、クロスワードなど多様な問題が収録されており、脳の若返りを目指します。
この書籍は、860億個のニューロンが脳内でどのように繋がり、コミュニケーションを行っているかを探求しています。ニューロンの繋がりは、ケガや病気、成長過程の異常によって変化し、これが自閉スペクトラム症やうつ病、統合失調症などの精神疾患に繋がる可能性があります。著者は神経科学の専門家であり、脳の混乱が思考や感情、行動に与える影響を研究し、治療法の可能性を模索しています。内容は脳障害や精神疾患に関する章で構成されており、脳と心の関係を明らかにすることを目指しています。
◆「認知科学のススメ」シリーズの刊行にあたって 人間や動物は、どのように外界の情報を処理し、適切に反応しているのでしょうか?認知科学は、このような関心から。動物も含めた人間の知能や、人工知能システムなどの知的システムの性質や処理メカニズムを理解しようとする学問です。人間や動物のさまざまな現象にかかわるため、認知科学は、心理学、進化学、情報科学(とくに人工知能)、ロボティクス、言語学、文化人類学、神経科学・脳科学、身体運動科学、哲学などの幅広い分野の研究者が集まって作られました。そのため認知科学は、これらの諸分野を横断する学際的な学問分野となっていて、数学、物理、歴史などの伝統的な分野と比べて、体系化することは容易ではありません。そのためもあってか、私たち自身について知るための基本的な学問であるにもかかわらず、これまで中学校や高校の教育の中で教えられることはありませんでした。しかし学問の存在を知らなければ、その道へ進もうと志す人もなかなか現れません。 第1巻では、認知科学の基本や多彩な取り組み全体をクイズやコラムを交えて紹介します。 はじめての認知科学 目次 まえがき 序章 ヒトはどんなふうにものを考えるか? パズルで試す「ヒトの考え方」 直感と論理の差がある 確率的なものをどう捉えるか? 常識的ってなんだろう? 序章の読書案内 1 章 出発点 こころを問うひとびと こころの研究を「科学」にする 条件反射から行動主義心理学へ こころの中の「認知地図」 こころの中にあるもの 表象という「なにか」 情報科学がもたらしたもの Box アラン・チューリング /ジョン・フォン・ノイマン ノーバート・ウィーナー /クロード・シャノン Column こころを持った機械への夢とチューリング・テスト 双子の学問の誕生 情報科学からこころを追うと……定理証明プログラム モデルという理解の仕方 問題を解く「こころ」とコンピュータ・プログラム 境界を越えて Column 日本に認知科学がやってきたとき 1章の読書案内 2 章 こころをわかるために章 ――記号,表象,計算,意味,理解 こころの働きを情報処理になぞらえる 大きな枠組で理解する 情動を伝える2つのルート 形式的に扱う=計算論的扱い 計算主義・記号主義とレイヤー ことばのないネコ,知性と言語 ヒトのこころとことば 文を作る能力は生得的か? ヒトに固有な言語活動 ことばを獲得するとき ことばの意味がわかる,とは 記号接地問題 使いやすいヒューリスティックな思考 Column もう1 つの計算主義 ニューラルネットワーク 2章の読書案内 3 章 こころと身体と言語 表情も身体だ 身体を動かしたほうがクリエイティブ 身体とミラーニューロン Box 「共感」と「心の理論」――他者に共鳴する能力 Column 神経科学のあゆみ 問題解決に役立つ心内シミュレーション 記号だけに頼れない? 身体とアフォーダンス 身体と触れ合う世界 ことばを持つ「意味」とヒトの能力 Column 身体を持ったロボットは知性を持つのか 3 章の読書案内 4 章 動物らしさvs. ヒトらしさ あなどれない動物の認知システム イルカの「音」の世界 オオカミからイヌへ キツネの家畜化からわかるもの 動物とヒトはどう違うのか 数字の短期記憶実験 推移的推論はできるか 対称性についての奇妙な結果 ヒトの認知システムの基本を探る 推論の基本 ヒトの知性をがっちり支える道具=アブダクション 発達とは学び続けること Column 脳をのぞく――画像撮影装置の発展 4 章の読書案内 間奏曲 認知科学対話 I 根っこから外れる節操の無さ 役に立つか 人とモノの間で II がんばれ東ロボくん! 会話プログラムと川柳 文脈と忘却 III どんな状況にも対応できるヒトのこころ ボトムからもトップからも考えるヒト 情動を超えて 生き残る仕事はなにか見極めるために 5 章 認知科学のここまで,そしてこれから 認知科学は何をやってきたのか 1995 年から2012 年の日本の認知科学 認知科学は社会とつながる 情報社会を認知科学すると これからの問題は Column 認知科学を学ぶには あとがき 文献一覧 索引 装幀=荒川伸生 イラスト=大橋慶子
本書は、脳と人工知能(AI)の融合がもたらす未来の可能性について探求しています。著者は、脳に知識をダウンロードしたり、思考を直接伝えたり、AIによる健康管理が可能になるなど、科学者たちが真剣に研究している近未来のシナリオを提示しています。松尾豊氏が絶賛するこの本は、科学技術の進展に対する私たちの考え方や備えについても問いかけており、未来の社会を考える人々にとって必読の一冊です。
本書『火星の人類学者』では、脳神経科医オリヴァー・サックスが、全色盲の画家やトゥレット症候群の外科医、自閉症の動物学者など、さまざまな脳の病を持つ患者たちの独特な人生を描き出しています。彼はこれらの障害を単なる病とせず、彼らのアイデンティティや創造力の源と捉え、人間の存在の可能性を探求する感動的な医学エッセイです。著者は多くの医学エッセイを執筆し、全米でベストセラーとなっています。
本書は脳に関する最新研究と科学的データを用い、日々の習慣が脳に与える影響を分析。継続的に生活改善に取り組む方法を伝授する。 本書ではわかりやすい数々の事例に加え、最新研究と豊富な科学的データで、習慣が脳に与える影響を徹底的に分析。上手に、かつ継続的に生活改善に取り組むためのモチベーションとその方法を伝授する。 老齢になっても明晰な頭を維持できる魔法の薬などない――脳の健康に関する第一人者である著者は、教育、食生活、運動、人間関係、そして睡眠という基本的な5つの生活習慣を健全なものにさえすれば、加齢とともに失われていく脳の能力は甦ると主張する。本書ではわかりやすい数々の事例に加え、最新研究と豊富な科学的データで、習慣が脳に与える影響を徹底的に分析。上手に、かつ継続的に生活改善に取り組むためのモチベーションとその方法を伝授する。
著者ジョン・メディナの本書は、「100年人生」を楽しく過ごすための脳に良い生き方を提案しています。脳の適応力や加齢による修復能力を強調し、社交や運動、マインドフルネス、十分な睡眠、引退しないことなど、脳の健康を保つための具体的な10のルールを紹介しています。友人を作り、ストレスを減らし、楽観的な態度を持つことが脳に良い影響を与えるとされています。
この書籍は、最新の脳科学に基づいた「頭のいい子」の育て方を提案する育児書です。著者は、育児における重要な6つの視点を示し、偏食や外遊び、読み聞かせ、デジタルメディアの利用についての具体的なアドバイスを提供します。特に、睡眠、食事、運動、遊び、読書、メディアのサイクルを通じて、子どもの脳の発達を促す方法を解説しています。育児と仕事を両立したい親に向けた実践的な内容が特徴です。
この書籍は、神経科学者フリストンが提唱した「能動的推論」と「自由エネルギー原理」に基づき、脳の知覚、認知、運動、思考、意識などの機能を統一的に説明する理論を解説した初の入門書です。内容は、脳の推論機能や注意、運動制御、意思決定、感情、好奇心、精神障害との関連、認知発達など多岐にわたります。著者は認知神経科学と計算論的神経科学の専門家です。
本書は脳の科学に関する基礎知識や最新の研究成果を紹介しています。脳の構造や機能、記憶のメカニズム、うつ病やアルツハイマー病などの心の病、発達障害の特性について詳しく解説しています。また、天才の脳の特性や創造性、記憶力の驚異的な能力についても触れています。脳研究の最前線や最新技術を活用したアプローチも紹介され、脳の理解を深めるための内容が盛り込まれています。
本書『時間は存在しない』では、天才物理学者カルロ・ロヴェッリが「時間の本質」を探求し、時間が常に同じように流れるわけではなく、過去から未来へ直線的に進むものではないという考えを展開します。彼は、物理学的に時間が存在しないと主張しつつ、私たちが時間を感じる理由を哲学や脳科学の視点から考察します。全体は三部構成で、時間の崩壊、時間のない世界、時間の源について論じています。イタリアで18万部を売り上げ、35か国での翻訳が予定されている話題作です。
「意志の力」に関するベストセラーが文庫化され、目標を持つ人々に向けた内容です。著者ケリー・マクゴニガルは、意志力を磨くことで人生が変わると説き、潜在能力を引き出す方法や自制心の重要性について解説しています。心理学や神経科学の知見を基に、健康や幸福を高める実践的な戦略を提供しています。翻訳は神崎朗子が担当。
藤子不二雄Aの漫画『笑ゥせぇるすまん』の主人公、喪黒福造が人々を巧妙に陥れる様子を描きつつ、彼の“騙しと誘惑の手口”を脳科学の視点から考察する内容です。人間の心のスキマを解明し、騙されやすいメカニズムや心理的テクニックを分析しています。巻末には藤子不二雄Aとの対談も収録されています。著者は脳科学者の中野信子です。
この書籍は、神経科学者デイヴィッド・イーグルマンが、視覚や聴覚、身体の一部を失った際に脳内で何が起こるのかを探求し、脳の可塑性を活かして新たな感覚を創出する可能性について論じています。著者は脳を常に自己改造する装置と捉え、科学技術を用いて感覚の代行や新しい感覚の発展について考察します。
洗剤選びから政治的立場の決定まで、人の選択には無自覚に方向性を決める「癖」がある。選択結果を誘導する認知的環境や選択肢の設計はいかなるものか。誘導技術は善用できないのか。人の情報処理の仕組みを解明し、さらなる考察へと誘う入門書。 選択と誘導の認知科学 目次 まえがき 1章 物理的環境と選択の関係を考える ――選択に働きかける 1 街中の看板と貼り紙によるメッセージ ファストフード店での滞在時間を決めるもの 電車のシートへの座り方 公園のベンチは誰が使うのか 街中の花壇の役目 なぜ看板や貼り紙がうまくいかないのか Box 心理的リアクタンス なぜ物理的環境がうまくいくのか 看板・貼り紙vs.物理的環境 まとめ――認知的環境と選択 Box 対応バイアス 2章 デフォルトの効果――選択に働きかける 2 「選択」に働きかける デフォルト① 「質問」でのの有無は何を生むか 「オプトイン」と「オプトアウト」 デフォルト② 受診手続きと受診率 デフォルト③ 自動車保険を選ぶ デフォルト④ エネルギーを選ぶ デフォルト⑤ 臓器を提供するかしないか デフォルト⑥ お金を運用する なぜデフォルトの選択肢は選択されやすいのか 不幸になりたい人などいない 「選択アーキテクチャ」という考え方 原因と対処 自動システムと熟慮システム 興味や関心を刺激する働きかけと比較する ミシュランのグルメガイドブックの起源は? フォルクスワーゲンの「ファン・セオリー」 興味や関心を刺激する働きかけとの違い まとめ 3章 選択肢を分割する効果――選択に働きかける 3 オバマ政権は支持されていたか 分割の効果① 自動車が動かない原因を考える 分割の効果② デート相手を選ぶ 分割の効果③ ホテルを選ぶ 分割の効果④ ワインを選ぶ 分割の効果⑤ 防衛政策を判断する 選択肢の操作で世論は変わるか まとめ 4章 よい働きかけとはどういうものか ――選択に働きかける 4 選択アーキテクチャにはさまざまな問題がある 「する」と「しない」は同じか 「する」が満足に与える効果 「する」と「しない」から行為者の意図を読み取る 「する」は心理的な関与を高める デフォルトは規範を変える 選択と自律 一般人の反応 まとめ 5章 「理由」は選択を正しくあらわしているか ――選択を説明する 1 選択とそのための理由 経路実験――どうやって「経路」を選ぶか ストッキング実験――置く位置か品 「理由」はあてにならない 条件づけ――良いものと一緒にされると好きになる 単純接触効果――見るほどに好きになる サブリミナル効果――見えない刺激の力 働きかけに抵抗する人もいる 洗剤実験――選択の根拠は効能か反復か まとめ 6章 「差別していない」は本音か言い訳か ――選択を説明する 2 「オートコンプリートの真実」 「母親 無職」と「父親 無職」に続くのは? 性別役割分担意識 ドクター・スミス課題 性別役割分担意識とステレオタイプ 職業と性差別 客観性の幻想 差別と曖昧さ まとめ 7章 無理に理由を考えるとどうなるか ――選択を説明する 3 絵画実験――「2つの絵画について答えてください」 好かれも嫌われもする作品 好悪の理由を分析するのは難しい 難しくても,無理に理由を分析すると何が起こるか 「不自然な理由」が作り出される 目隠しテストで芸能人を格付けチェック テイスティング方法と評価の関係は? 「ペプシ・パラドクス」現象 「ペプシ・パラドクス」を考え直す ペプシ・コーラとコカ・コーラの味の「違い」とは 「ペプシ・パラドクス実験」もう一度 「ペプシ・パラドクス実験」のまとめ まとめ――「もっともらしい理由」を作って決める判断とは あとがき 文献一覧 索引 装幀=荒川伸生 イラスト=大橋慶子
この書籍は、脳の構造と機能、神経系のメカニズム、高次機能、病気の原因と治療法を詳細に解説しています。精密なイラストと豊富な情報が特徴です。著者は、解剖学と生理学の専門家であり、各々の研究背景を持っています。
この事典は、認知科学の全分野を網羅し、哲学、心理学、神経科学、計算論的知能、言語学、文化・認知・進化の6つの主要分野から厳選された470項目を収録しています。各項目は第一級の研究者によって執筆されています。
この本では、科学的な研究に基づいた「テキトー子育て」の方法を紹介しています。親が子どもに過度に期待することがストレスの原因となり、逆に子どもの成長を妨げることがあると指摘。具体的には、挨拶や部屋の片づけ、食べ物の好き嫌いなどにこだわらず、子どもの自立を促すことが大切だと述べています。「テキトー」とは、必要以上にこだわらず、リラックスした育児を意味し、これにより親も子どもも楽になるというメッセージが伝えられています。
本書は「自分史上最高の脳」になるための最新メソッドをまとめたもので、科学的に証明された脳に良い習慣を網羅しています。内容は、運動、食事、睡眠、腸内細菌、社会性、性欲、学習、幸福など多岐にわたり、環境や生活習慣が知力に与える影響を強調しています。著者は脳の健康に関する専門家で、習慣を変えることで脳も変わると述べています。
神経科学の基礎知識 科学者は自説をどのくらい信じているのか 双子は離れて育っても性格が似る 複雑な脳は単純な規則で組み上げられる 脳を育てるのは脳自身 子どもの脳と大人の脳の違いは 日々生まれ変わる10代の脳 生涯続く脳地図の陣取り合戦 道具で伸び縮みする身体 薬物依存は治らないのか 脳は変化に目を向ける 脳vsコンピューター 神経伝達物質はいくつあるのか 眼は見るべきものを見る 視覚は超能力 味覚にはふたつの役割がある 触覚は多くの情報の組み合わせ 痛みはどこで生じるか 脳は時間を正しく歪める 見えてきた脳内信号の全体像 実験動物は選択と比較が大切 「反射」が脳に運動を教える リハビリゲームで脳卒中から完全回復を 意識的行動も大部分は習慣 声を聞き分ける脳 動物も「心の理論」を持つか 助け合いは動物の本能 恋愛は生存本能から進化した 性的指向は生物学的に決まる 脳は仮説を立てる科学者 セクシュアルな広告が有効なわけ 美人はなぜ美しいのか 本能を学習させる脳の罠 脳は過大評価されている ドーパミン意思決定に近づくAI コンピューターは脳になれない 「心」を持つマシンは必ず作れる
この書籍は、著者が脳の高次機能障害の臨床医としての経験を基に、人間の「理解」のメカニズムを明らかにする試みです。「わかる」という感覚が生じる瞬間や脳内での変化について探求し、理解を深めるために必要な要素を考察しています。目次は「わかる」ための素材や手がかり、記憶の役割などを含んでおり、より深い理解を追求する内容です。著者は神経内科の専門家で、記憶障害や認知障害に関する研究を行っています。
本書は、脳内の細胞の約80%を占める「グリア細胞」の重要性を探るもので、従来はニューロンの単なるサポートと見なされていたが、最近の研究によってニューロンの活動を感知し制御できることが明らかになった。著者は、従来の「ニューロン中心主義」に疑問を呈し、グリア細胞の役割が脳科学における理解を大きく変える可能性を示唆している。内容は、グリアの基本的な役割から健康や病気における影響、思考や記憶における機能まで多岐にわたる。
この書籍は、YouTubeの人気動画「科学的根拠に基づく最高の勉強法」を基に、効率的な勉強法を科学的に解説しています。著者は医者としての経験を通じて、従来の学習法(再読、ノート写し、ハイライトなど)が効果的でないことを指摘し、アウトプットの重要性を強調しています。具体的な勉強法として、アクティブリコールや分散学習、記憶術などを紹介し、心身や環境を整える方法についても触れています。著者は、誰でも実践できる効果的な学習法を提供することを目指しています。
この書籍は、最新の科学に基づいて新米ママパパ向けに子育てに関する正しい情報を提供します。妊娠期から子どもの脳の発達、夫婦関係の影響、子どもの気質、感情の育成、道徳心の育て方まで幅広く解説しています。特に、科学的根拠をもとに「子どもの脳に良いこと悪いこと」を明らかにし、効果的な子育て方法を提案しています。
この書籍は、脳に知能が生じる理由を探求し、大脳新皮質の「皮質コラム」に着目した「1000の脳」理論を解説しています。著者ジェフ・ホーキンスは、脳と人工知能の理解に革命をもたらす新しい視点を提供し、ビジネスや研究における知的挑戦を描いています。内容は脳の新しい理解、機械の知能、人間の知能に関する考察を含みます。ホーキンスは神経科学者であり、AI研究の先駆者として知られています。
この本は、認知症の専門医である長谷川和夫が自身の認知症体験を通じて、認知症の実態や予防策、医療の役割を伝える内容です。長谷川は「長谷川式スケール」の開発者であり、認知症の歴史や社会における理解の必要性についても触れています。著者は、認知症に関する知識を広め、日本人に伝えたいメッセージを込めた「認知症の生き字引」としてこの書をまとめました。
この書籍では、日本が直面する困難な状況の中で、人間の脳が持つ「挑戦」の能力が重要であることが論じられています。脳は柔軟なシステムであり、試練に直面した時に新たな力を発揮します。著者は、日常生活における「挑戦」の普遍性や、人間が困難を乗り越えて自分を確立するための方法について様々な事例を交えて考察しています。著者は脳科学者の茂木健一郎で、彼の専門知識を基にした内容が展開されています。
『雑食動物のジレンマ』『人間は料理する』で知られるジャーナリストが 自ら幻覚剤を体験し、タブーに挑む! 今どんな幻覚剤の研究がおこなわれているのか。 幻覚剤は脳にどんな影響を与えるのか。 そして、医療や人類の精神に、幻覚剤はいかに寄与しうるのか。 「不安障害」「依存症」「うつ病」「末期ガン」などへの医学的利用の可能性と、“変性する意識”の内的過程を探る画期的ノンフィクション。 ニューヨークタイムズ紙「今年の10冊」選出(2018年)、ガーディアン紙、絶賛! 一部の精神科医や心理学者が過去の幻覚剤研究の存在に気づき、発掘を始めたのは最近のことだ。 彼らは現代の基準で再実験をおこなって、その精神疾患治療薬としての可能性に驚愕し、(中略)幻覚剤が脳にどう働くのか調べはじめた。 ——幻覚剤ルネッサンスである。(宮﨑真紀) 第一章 ルネッサンス 第二章 博物学——キノコに酔う 第三章 歴史——幻覚剤研究の第一波 第四章 旅行記——地下に潜ってみる 第五章 神経科学——幻覚剤の影響下にある脳 第六章 トリップ治療——幻覚剤を使ったセラピー
この書籍は、幼少期の脳教育が社会的成功に重要であることを説き、脳内格差を解消するために、読み書き算盤や音楽を通じて「成功脳」を育てる方法を紹介しています。内容は脳の本質や臨界期、多重知能の育成、人間性知能(HQ)の育て方に焦点を当て、乳児期から幼児期にかけてのHQ育成法や日常生活での訓練方法について詳述しています。著者は脳科学の専門家であり、多くの著書を持っています。
私たちは悲しいからから泣くのか? 泣くから悲しいのか? 脳科学の根源的なテーマ「情動」と「こころ」の謎に第一人者が迫る! 人は悲しいから泣くのか? それとも泣くから悲しいのか? これは脳科学では昔から論争が続いている根源的なテーマです。実は動物やヒトの行動は「理性」よりもはるかに強く「情動」によって支配されています。情動がなければ、私たちは意思決定さえままなりません。そしてヒトはさらに、情動より複雑で厄介な「こころ」を身につけました。それはいかにして生まれるのか? 私たちを支配するものの「正体」に第一人者が迫ります! 人は悲しいから泣くのか? 泣くから悲しいのか? 世界的トップランナーが解き明かす「こころ」の正体! 私たちは、自分の行動は自分が考えて決めていると思っている。 己を動かすものは、己の「理性」のみであると信じている。 だが、残念ながらそれは錯覚にすぎない。 行動は理性よりもはるかに、「喜び」「怒り」「悲しみ」「恐怖」などの 「情動」に強く支配されているのだ。 情動とは、生き残る確率を高めるために脳にプログラミングされた、 下等動物からヒトにまで共通する必須の機能なのである。 ところがヒトは、情動よりもさらに複雑な行動決定のメカニズムを獲得した。 それが「こころ」である。 ヒトにはなぜ、このように不可思議で厄介なしくみが備わったのだろうか。 「こころ」はいかにして生まれ、私たちに何をしているのだろうか。 脳神経科学の第一人者が「こころ」の生成プロセスと作動原理を解き明かし、 私たちを支配しているものの「正体」に迫る! 第1章 脳の情報処理システム 第2章 「こころ」と情動 第3章 情動をあやつり、表現する脳 第4章 情動を見る・測る 第5章 海馬と扁桃体 第6章 おそるべき報酬系 第7章 「こころ」を動かす物質とホルモン 終 章 「こころ」とは何か 著者略歴 1964年東京生まれ。筑波大学大学院医学研究科修了。医師、医学博士。日本学術振興会特別研究員、筑波大学基礎医学系講師、テキサス大学ハワード・ヒューズ医学研究所研究員、筑波大学大学院准教授、金沢大学医薬保健研究域教授を経て、現在、筑波大学医学医療系および国際統合睡眠医科学研究機構教授。1998年、覚醒を制御する神経ペプチド「オレキシン」を発見。平成12年度つくば奨励賞、第14回安藤百福賞大賞、第65回中日文化賞、平成25年度文部科学大臣表彰科学技術賞、第2回塩野賞受賞。著書に『睡眠の科学・改訂新版』『食欲の科学』(いずれもブルーバックス)、『「眠り」をめぐるミステリー』(NHK出版新書)など。 第1章 脳の情報処理システム 第2章 「こころ」と情動 第3章 情動をあやつり、表現する脳 第4章 情動を見る・測る 第5章 海馬と扁桃体 第6章 おそるべき報酬系 第7章 「こころ」を動かす物質とホルモン 終 章 「こころ」とは何か
この書籍では、最新の科学研究に基づき、従来の学習方法や勉強習慣が誤っていることが示されています。著者であるニューヨークタイムズのサイエンスレポーターが、効率的な学習法や記憶法を解説し、脳を最大限に活用するためのテクニックを紹介しています。内容は、脳の学習メカニズム、記憶力や解決力を高める方法、無意識の活用など多岐にわたります。勉強法を見直すことで、大学受験や資格試験、仕事の学習に役立つ一冊です。
8年ぶりの改訂版で、約30%の内容が更新された「脳科学」に関する教科書です。全9パート、64章からなり、新たに「ブレイン・マシン・インターフェース」など3章が追加されました。神経系のメカニズムや疾患について詳述し、情報工学に関する項目も強化されています。最新の研究データを各章で紹介し、読みやすい日本語訳と907点のフルカラー図版が特徴です。初学者から専門家、AIエンジニアまで幅広い読者に向けた内容で、手頃な価格で提供されています。
この書籍は、アルツハイマー病研究の現状を批判的に見直し、特にアミロイドに偏った治療アプローチが無駄な時間を費やしてきたことを指摘します。著者は、アカデミズム、製薬業界、政府の関与による研究の迷走を明らかにし、過去数十年の認識を根本から問い直す重要な告発を行っています。内容は、アルツハイマー病の歴史、治療法の探求、研究モデルの問題点、今後の研究戦略の多様化に焦点を当てています。
「脳科学」に関するよくある質問
Q. 「脳科学」の本を選ぶポイントは?
A. 「脳科学」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「脳科学」本は?
A. 当サイトのランキングでは『メカ屋のための脳科学入門-脳をリバースエンジニアリングする-』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで149冊の中から厳選しています。
Q. 「脳科学」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「脳科学」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。