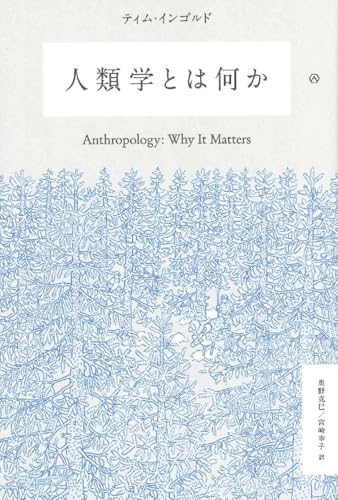【2025年】「文化人類学」のおすすめ 本 126選!人気ランキング
- 自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門(未来のわたしにタネをまこう7)
- これからの時代を生き抜くための 文化人類学入門
- 発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ (角川文庫)
- 人類学のコモンセンス: 文化人類学入門
- ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと
- 現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践 (ワードマップ)
- フィールドワークへの挑戦―“実践”人類学入門
- 文化人類学 [カレッジ版] 第4版
- よくわかる文化人類学[第2版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)
- 生のものと火を通したもの (神話論理 1)
ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」とのフィールドワークから見えてきたこと。豊かさ、自由、幸せとは何かを根っこから問い直す、刺激に満ちた人類学エッセイ! 「奥野さんは長期間、継続的にプナン人と交流してきた。そこで知り得たプナン人の人生哲学や世界観は奥野さんに多くの刺激と気づきをもたらした。この書を読み、生産、消費、効率至上主義の世界で疲弊した私は驚嘆し、覚醒し、生きることを根本から考えなおす契機を貰った。」 ――関野吉晴氏(グレートジャーニー)
◆街へ出る前に、フィールドへ行く前に◆ フィールドワーク、エスノグラフィー(民族誌)について、手紙の書き方、ノートの取り方から機器の扱い方まで、手取り足取り解説した本は多くあります。J・クリフォードらの『文化を書く』以来、文化を誰が、どこから、どう書くのか、という政治性が指摘されていますが、本書はそのような問題意識を組み入れながら、ポジショナリティ、自己再帰性、表象の政治、当事者研究などの基本概念を詳述し、介護、障害、ボランティアなどの新しい対象分野を取り上げ、さらにはフィールドに出たときに調査者が出会う初歩的な問題についても、体験をとおした適切なアドバイスをしています。これからのフィールドワークに必携の「思想的」ガイドブックといえましょう。 ワードマップ 現代エスノグラフィー─目次 はじめに 「新しい」アプローチ一覧 第一部 現代エスノグラフィーの展開 エスノグラフィー現場を内側から経験し記述する 『文化を書く』エスノグラフィー批判の衝撃 自己再帰性他者へのまなざし、自己へのまなざし ポジショナリティ誰が、どこから、どう見るのか ■コラム 厚い記述 表象の政治語る、語られる、語りなおす ポスト構造主義とポストモダニズム「知識」の断片性・不完全性・文脈依存性 第二部 エスノグラフィーの「新しい」アプローチ アクティヴ・インタヴュー質問者と回答者が協働する フェミニスト・エスノグラフィー「女」が「女」を調査する ネイティヴ・エスノグラフィー「内部者」の視点から調査する 当事者研究「自分自身でともに」見いだす アクション・リサーチ協働を通して現場を変革する チーム・エスノグラフィー他者とともに調査することで自らを知る ■コラム チームでの実践を振り返る ライフストーリー個人の生の全体性に接近する オートエスノグラフィー調査者が自己を調査する オーディエンス・エスノグラフィーメディアの利用を観察する マルチサイテッド・エスノグラフィーグローバルとローカルを繋ぐ 第三部 応用研究 アイデンティティ「なる」「する」様態に迫る ジェンダー・セクシュアリティ男/女の線びきを問いなおす 人種・エスニシティ越境する人々の意味世界を理解する 学校教師と生徒のまなざしを明らかにし、変えていく 医療・看護病いとケアの経験を記述する 障害経験される世界に接近する 生/ライフ「生き方」を主題化し表現する 社会運動・ボランティア「参与」しながら観察する メディア・大衆文化メディアが受容される文脈をさぐる 第四部 フィールドで出会う問題 調査の説明と同意 フィールドに入るときに 権力 フィールドのただなかで 親密性 フィールドのただなかで 守秘義務と匿名性 フィールドを後にするときに 利益 フィールドで得たもののゆくえ ■フィールドからの声 話してもらえる私になる 『ギャルとギャル男の文化人類学』の現場から お嬢様がお嬢様を調査するジレンマ 恋愛感情にまつわることからは逃れられない おわりに ブックガイド 事項索 人名・書名索引 装幀―加藤光太郎
この書籍は、人間と文化の関係を探求し、身体観や死生観、宗教、世界観などを通じて人間理解を深めることを目的としています。文化人類学の新たな視点を提供し、いのちについて再考するためのスタンダードなテキストです。目次には、文化の基本的な概念や質的研究、個人と家族、通過儀礼、宗教、健康などが含まれています。
ほぼ地産地消が実践されていた昭和30年代の暮らしと食について、滋賀県内8地域を調査、食材の調達、加工、保存などのようすを記… ほぼ地産地消が実践されていた昭和30年代の暮らしと食について、奥永源寺や朽木の山村、湖に面した半農半漁の村など、滋賀県内8地域を調査。多様な湖魚・山菜・果実・獣肉の調達、野菜類の栽培・加工・保存のようすを記録。 いまこそ環境共生型の伝統的な暮らしと食のスタイルから学ぶべきことは多い。──食品スーパーはなく、ほぼ地産地消が実践されていた昭和30年代の暮らしと食に焦点をあて、奥永源寺や朽木の山村、琵琶湖や内湖に面した半農半漁の村など、滋賀県内8地域で聞き取り調査。多様な湖魚・山菜・果実・獣肉などの調達、穀類・野菜類の栽培・加工・保存のようすを記録。 はじめに 第1章 「滋賀の暮らしと食」その背景と特徴を探る 第2章 湖北の暮らしと食 第3章 奥永源寺の暮らしと食 第4章 安土の暮らしと食 第5章 野洲の暮らしと食 第6章 甲賀の暮らしと食──小佐治集落を中心に 第7章 伊香立の暮らしと食──生津集落の調査を中心に 第8章 志賀の暮らしと食 第9章 朽木針畑の暮らしと食 あとがき
介護・福祉・教育等ヒューマンサービスの現場のみならず、マーケティング分野でも必須の調査手法をきめ細かく紹介した基本図書。 人々が生きる現場をどう内側から理解し深めていくか。医療・介護・福祉・教育等、ヒューマンサービスの現場のみならず、マーケティング分野でも必須の調査手法をきめ細かく紹介し、実践に役立つ方法論を提示。長らく最適な入門書として幅広く支持されてきた名著。 エスノグラフィーをはじめよう 改訂版まえがき プロセス・マップ 1 エスノグラフィーとは 2 実例から学ぶ 3 エスノグラフィーのプロセス 4 現場を選ぶ 5 マナー・倫理・安全 6 現場に入る 7 概念力をきたえる 8 研究計画を立てる 9 現場調査(フィールドワーク)をする 10 分析する 11 発表する 12 社会へとひらく 実例 ミニエスノグラフィー 付録 索引 参照文献
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
ビデオ・エスノグラフィーという手法の意義=概観= 〈社会モデルの洗練〉という社会学の理論的課題 〈器用仕事の発見〉という社会学の理論的課題 インフォームド・コンセントのビデオ・エスノグラフィー 医学教育のビデオ・エスノグラフィー リーガル・コミュニケーションのビデオ・エスノグラフィー 在宅療養のビデオ・エスノグラフィー 音楽療法のビデオ・エスノグラフィー ビデオ・エスノグラフィーの基盤と未来
この入門書は、文化人類学の主要テーマをわかりやすく解説し、学問の面白さと奥深さを伝えています。最新版では近年の研究動向に基づく新しいテーマも追加されており、異文化を通じて自文化を見つめ直す視点を提供しています。内容は基本テーマと新たなテーマに分かれており、著者は筑波大学名誉教授の綾部恒雄とノートルダム清心女子大学の桑山敬己です。
この書籍は、塩麹、醤油麹、酒粕、甘酒を使った90点のレシピを紹介しています。発酵調味料を活用することで、料理が簡単に美味しくなり、腸の健康にも寄与します。忙しい人に最適な、手軽でヘルシーな料理法が提案されています。目次には、肉や魚の漬け方、野菜を使った主菜、家族向けの定番メニュー、作り置き、スピード副菜、ご飯やスープ、簡単スイーツが含まれています。
いま世界の人類学者が考えていること かつて思想界をリードした文化人類学は、一九九〇年代のクリフォード=マーカス『文化を書く』での民族誌の記述をめぐる批判以降、低迷してきましたが、今また新たな胎動期を迎えました。本書は批判に鍛え直されて生まれ変わった新しい人類学を紹介します。グローバル化する現代において、人類学の古典的対象(未開社会、呪術、儀礼など)は消え失せましたが、「開発」「災害」「リスク」「コモンズ」「アソシエーション」「差別」「病気」「景観」「超越論」などの現代的なキーワードを手がかりに、「21世紀の人類学」のパラダイムを提示し、魅力的で生産的な民族誌の具体例を示します。いま考えうる最も充実した「現代文化人類学入門」です。 21世紀の文化人類学 目次 はじめに 序章 「人類学的」とはどういうことか (前川啓治) 超越的・超越論的 「文化」の客体化 コラム 「超越的」と「超越論的」の変遷 超越論的展開 過去から未来へ生成する人類学 コラム クック船長の死 Ⅰ部 自然・存在・イメージの生成 1章 人格と社会性 (深川宏樹) 人間の概念 変容可能性 構造と機能 人間社会の自然科学 身体とサブスタンス 生殖=再生産の「事実」からの解放 社会性 切断=拡張する思考 コラム マリリン・ストラザーンとの対話――研究現場での「部分的つながり」 2章 アクターネットワーク理論以降の人類学 (浜田明範) アクターネットワーク理論 科学と政治が絡まり合いながら変化する世界を探る 存在論的 具体的なものを通して反・自文化中心主義を深める ポストプルーラル 二つ以上のものが互いに別個に存在していると言えないこと 疾病/病い 文化の複数性からポストプルーラルな自然へ 生物学的市民 生物学的なステータスが駆動する政治 3章 「歴史」と「自然」の間で――現代の人類学理論への一軌跡 (里見龍樹) 歴史人類学 「文化」を問い直す カーゴ・カルト 〈新しいもの〉をとらえる コラム 想起されるマーシナ・ルール 景観 「歴史」と「自然」の間で 「自然/文化」をめぐる人類学 南アメリカにおける展開 「人間」を超える人類学 可能性の探究 Ⅱ部 実践―生成する世界へ 4章 公共性 (木村周平) 「表象の危機」その後 『文化を書く』からの展開 公共性 関与・介入・貢献 災害 脆弱性とレジリエンス リスク 未来の予測可能性をめぐって エスノグラフィ 知の創造と活用 5章 運動と当事者性――どのように反差別運動に参加するのか (根本達) アイデンティティ・ポリティクス 不確実な世界における暴力的な対立 被差別者と人類学 差別に抗する、差別から逃れる 生活世界の声 動態的で輻輳的なそれぞれ 寛容の論理 等質でないものの繫がり 生成変化の政治学 当事者性を拡張する Ⅲ部 社会科学と交差する人類学 6章 持続可能性と社会の構築――ハイブリッドな現実の社会過程の多元的な分析の必要性 (三浦敦) 合理的個人 合理的には見えない個人の行動を、合理的に説明する 家族制生産とグローバル経済 なぜ資本主義経済において小規模家族制生産は維持され続けるのか 多元的法状況における所有 「ものを所有する」ということは、自明なことではない コモンズ 自然環境を守ること、それはわれわれの生活を守ること 開発 大資本の手先か住民の味方かという、不毛な二元論を超えて アソシエーションと社会的連帯経済 連帯はどのように可能なのか、連帯は人々を救えるのか コラム 十九世紀のフランス農村と文化人類学の前史 終章 過去・現在・未来 (箭内匡) 文化人類学の現在と過去 人類学は今、どこにいるのか 「外」 人類学的思考を貫く本質的要素とは何か 不可量部分 人類学者がフィールドで出会うものとは? イメージ フィールドの現実を新たな目で捉えなおす 時間 未来の人類学に向かって思考の軸をずらしてみる あとがき 引用文献 事項索引 人名索引 装幀――加藤光太郎
「貧富の差」のない共同体や、学校へ行かず「習う」という概念もない社会が存在する。常識をひっくり返した時、問題の根本が見える。 世界には、「貧富の差」のない共同体や、学校に行かずそもそも「教わる」という概念もない社会が存在する。常識をひっくり返して考えた時、問題の根本が見える。 世界には、「貧富の差」のない共同体や、学校に行かずそもそも「教わる」という概念もない社会が存在する。常識を常識をひっくり返して「そもそも」を問う思考法には、問題を定義し直し、より本質的な議論に導く力があります。学校教育や貧富の格差、心の病など、身近で大きな社会・環境危機に人類学で立ち向かう一冊。 【本書で扱う一例】 ヘヤー・インディアンは「教わる」という概念を持たない ⇒学校ってなぜ行くの?そもそも学ぶって何? プナンは獲物もお金もみんなでシェアして貧富の差がない ⇒格差や権力はそもそもなぜ生まれるの? ひっくり返して考えた時、問題の根本が見える。 序章 人類学でひっくり返すとはどういうことか? 1「精神の危機」によって生まれた人類学 2『ひっくり返す人類学』とは何か? 3本書が目指す「処方箋」としての人類学 第1章 学校や教育とはそもそも何なのか 1私の「お稽古ごと」時代 2ピアノ教室の未知の世界 3学校教育とは何か 4「師弟関係」がないヘヤー・インディアン 5ヘヤーにとって「覚える」とは? 6ボルネオ島の狩猟民プナンにとっての「学び」 7プナンにとって「学校」とは何か? 8学校には行かなければならないの? 9「知識」とともに「知恵」を重んじる 第2章 貧富の格差や権力とはそもそも何なのか 1世界と日本における貧富の格差 2貧富の格差のないプナン社会 3貧富の格差が生じないような仕組み 4権力とは何か 5気前のいいビッグマン、不穏なビッグマン 6権力を生じさせないための工夫 第3章 心の病や死とはそもそも何なのか 1働きすぎやうつ病をめぐる私たちの日常 2うつ病や心の病のない社会 3カリスの唇のあやまち 4それは心の病ではない 5日本における「この世」からの別離 6葬儀の変化、死の消滅 7人が死ぬと残された家族の名前が変わる 8日本の戒名とプナンのデス・ネーム 9死者を「忘れる」 第4章 自然や人間とはそもそも何なのか 1自然と人為という枠組み 2人間から分け隔てられる動物 3自然と人間の二元論に抗する思考 4トリと動物と人間の三者間関係 5動物は思考し、森も思考する 6山や川もまた人間 おわりに
他者と“ともに”学ぶこと—— 他者と向き合い、ともに生きるとは、どういうことか。 人類学は、未来を切り拓くことができるのか。 現代思想、アートをはじめ、ジャンルを超えた影響と挑発をあたえつづけるティム・インゴルド。 世界の知をリードする巨人が語る、人類学と人類の未来。 世界が直面する未曾有の危機にどう立ち向かうべきか。 インゴルドの思想の核心にして最良の人類学入門。 第1章 他者を真剣に受け取ること 第2章 類似と差異 第3章 ある分断された学 第4章 社会的なるものを再考する 第5章 未来に向けた人類学 解説 原注 読書案内
文化人類学への誘い、ふたたび ファーストコンタクト再演 媒介としての文化 村のなかのテント 見晴らしのよい場所 民族誌のメイキングとリメイキング 未完のフィールドワーク 私の野蛮人 民族誌を再演する 文化への焦点化 首狩の理解から自己の解放へ いま、フィールドで何が起きているか
旧来の人類学のイメージを塗り替え、世界的に注目されるインゴルドの代表作待望の邦訳!〈線〉から開かれる知的興奮にみちた人類学。 マリノフスキーからレヴィ=ストロースへという未開の地の探索という人類学のイメージを塗り替え、世界的な注目を集める人類学者インゴルドの代表作。文字の記述から道路まで、〈線〉という切口から、新鮮な開かれる知的興奮。 人類学とは、人間がこの世界で生きてゆくことの条件や可能性を問う学問である! マリノフスキーからレヴィ=ストロースへと連なる、未開の地を探索する旧来の人類学のイメージを塗り替え、世界的な注目を集める人類学者インゴルドの代表作、待望の邦訳! 文字の記述、音楽の棋譜、道路の往来、織物、樹形図、人生… 人間世界に遍在する〈線〉という意外な着眼から、まったく新鮮な世界が開ける。知的興奮に満ちた驚きの人類学! 管啓次郎解説・工藤晋訳(原著LINES a brief history, Routledge, 2007) 日本語版への序文 謝辞 序論 第1章 言語・音楽・表記法 第2章 軌跡・糸・表面 第3章 上に向かう・横断する・沿って進む 第4章 系譜的ライン 第5章 線描・記述・カリグラフィー 第6章 直線になったライン 人類学の詩的想像力 訳者あとがき 工藤晋 さわやかな人類学へ 解説に代えて 管啓次郎 文献一覧
1世紀にわたる人類学の成果を総括し、人類学が今後いかなる道を歩むべきかを提示する。いま人類学は可能なのか、可能とするならばなにができるのか──著者の40年にわたるフィールドワークと透徹した思索の精華ともいうべきゴドリエ入門書。 序章 人類学はなんの役に立つのか 第1章 贈るモノ、売るモノ、売っても贈ってもダメでとっておいて継承しなくてはならないモノ 第2章 家族や親族に基礎をおく社会など存在したことがない 第3章 子どもをつくるには男と女のほかに必要なものがある 第4章 人間の〈性/セクシュアリテ〉は根本的に非社会的である 第5章 個人はいかにして社会的主体となるのか 第6章 複数の人間集団はどのようにして社会を構成するのか 結論 社会科学をたたえる 訳者あとがき 文献
「場面を描く、生活を書く」『タイミングの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2024第2位)の著者、最新刊。体感する入門書。 「場面を描く、生活を書く」『タイミングの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2024第2位)の著者、最新刊。エスノグラフィの息遣いを体感する入門書。 生活を書く、それがエスノグラフィの特徴です。そして、もっとも良質なエスノグラフィの成果は、 苦しみとともに生きる人びとが直面している世界を表し出すところに宿るものです。もともと人類学で発展したこの手法は、シカゴ学派を拠点に、 社会学の分野でも広がっていきました。本書では、5つのキーワードに沿って、そのおもしろさを解説していきます。予備知識はいりません。ぜひ、その魅力を体感してください。 【担当編集のおすすめポイント】 ・実例に裏打ちされた思考のプロセスが「話し書き」されたものを読むことで、エスノグラフィとは何かを体感することができます。 ・INAさんによる20点の挿画が、イメージを広げるためのジャンプ台となってくれます。 ・調査の仕方から本の読み方、コラムにある卒論紹介まで、具体的で、かゆいところに手が届いています。 ・豊富な読書案内が、次に読むべき本を教えてくれます。 ・小説、日記、エッセイなど、ものを書くこと一般に関心があるひとにも応用できる内容です。 はじめに エスノグラフィとは/本書の著者について/エスノグラフィの核心/本書のスタイル/あるひとつの入門書 第1章 エスノグラフィを体感する 通夜と賭けトランプ/センス・オブ・ワンダー/海の少年/場面と主題/二重写しに見る/フィールド調査の十戒/フィールドの人びととの関係のあり方/調査の進め方/社会学的に観察する/フィールド調査のねらい/本章のまとめ コラム1 サイクリストの独自世界 第2章 フィールドに学ぶ 経験科学/フィールド科学/雪かきの現場から/モノグラフ/可量と不可量/不可量を書く/ボクサーの減量の事例/人びとの経験に迫る/身体でわかる/フィールドへのエントリー/漁民から見る/人びとの対峙する世界/本章のまとめ コラム2 ペットによる社会的影響とその効果 第3章 生活を書く シカゴ学派/生活を見る眼/アフリカの毒/同時代の人びとへ/地続きの人類学/生活実践へ/日常生活批判/差別の日常/「いま―ここ」の注視/「人びとの方法」への着目/遠近法的アプローチ/まひるのほし/本章のまとめ コラム3 遊びとしての公的空間での眠り 第4章 時間に参与する 生活論/生活を読み取る/生活環境主義/「森林保護」による生活破壊/時間へ/ボクサーの「典型的な一日」/時間的単位を知る/周期性とリズム/時間をめぐる困難/生が「生活」になるとき/共に活動すること/私の失敗談/本章のまとめ コラム4 手話サークルから見るろうコミュニティとコロナウイルス 第5章 対比的に読む 図書館の歩き方/探索することの魅力/「赤青」の色鉛筆/読みの体感/エスノグラフィを読む/裏舞台だけを読まない/着眼点の移植/対比的に発見する/データをつくる/本章のまとめ コラム5 リスクから見るサブカルチャー 第6章 事例を通して説明する フィリピンとの出会い/繰り返し通うこと/対比という方法/事例を通した説明/論理の解明へ/羅生門的手法/客観性から客観化へ/ミクロ・マクロ問題/バンコクのバイクタクシー/エスノグラフィとルポルタージュ/本章のまとめ コラム6 部活動におけるケガの社会学 おわりに――次の一歩へ 学ぶこと/受苦を生きる/楽しみと苦しみ あとがき――読書案内をかねて 参考文献 索引
この書籍は、人類が暴力を根絶し平和に向かう可能性を探るもので、先史時代から現代までの歴史を通じて神経生物学や脳科学の知見を用いて人間の本性を分析しています。著者スティーブン・ピンカーは、文明化や人道主義革命を通じて平和化のプロセスを論じ、希望に満ちた未来のビジョンを提示しています。ニューヨークタイムズ・ベストセラーに選ばれています。
本書は、文化人類学を学ぶ学生を対象に、基礎知識を深め、新たな研究動向を紹介することを目的としています。内容は2部構成で、第1部では姉妹書の内容を詳細に更新し、第2部では最新の理論やテーマを取り上げています。著者は学界の代表的な研究者たちで、真剣に学びたい学生のために執筆されています。
人を動かすのはモノである。だからこそ、いわゆる物質文化研究ではない、真に【モノを主人公にした】人間中心主義を 越えた人類社会論を構 築するのだ。熟練の逆説/ものの介入/記号的なものの物質性/アフォーダンス等々——音や会話といった事象をも対象に斬新な方法・ 視点と溌剌とした議論で、新しい人類学を拓く秀作。 プロローグ(口絵写真):ものをして語らせよ 序章:なぜ「もの」の人類学なのか? [床呂郁哉・河合香吏] 第Ⅰ部 「もの」の生成・消滅・持続 1章 かたち・言葉・物質性の間 —陝北の剪紙が現れるとき [丹羽朋子] Key Words:陝北の剪紙,「もの」の現れ,感性的経験,記号的なものの物質性,反復と創造 2章 潜むもの,退くもの,表立つもの —会話におけるものと身体の関わり [菅原和孝] Key Words:対面相互行為,ものの介入,アフォーダンス,資源,直示 第Ⅱ部 「もの」と環境のネクサス 3章 「もの」の御し難さ —養殖真珠をめぐる新たな「ひと/もの」論 [床呂郁哉] Key Words:真珠,熟練の逆説,自然(環境)の御し難さ,「もの」との対話 4章 土器文化の「生態」分析 —粘土から「もの」へ [印東道子] Key Words:土器技術,技術変化,生態環境,技術適応,知識の身体化 エッセイⅠ 現れる「もの」 1 名前がかたちを得る場: ものと経験を動員するジャワバティックの伝統文様 [佐藤純子] 2 カシュタが人を動かす:ウズベク刺繍がもつ「もの」の力 [今堀恵美] 3 ものと人の関係性の「遊び」: バナナと人間は依存しあっているか? [小松かおり] 第Ⅲ部 「もの」と身体のダイナミクス 5章 土器つくりを知っている —エチオピアの女性土器職人の「手」と技法の継承 [金子守恵] Key Words:エチオピア,土器,女性職人,身体技法,技法を獲得する過程 6章 男性身体と野生の技法 —強精剤をめぐる自然・もの・身体 [田中雅一] Key Words:漢方,生命主義,広告,セックス,ゲテモノ エッセイⅡ 妖(怪)しい「もの」 1 パゴダと仏像のフェティシズム [土佐桂子] 2 身体から吸い出される「もの」: ラダックのシャーマニズム儀礼より [宮坂 清] 第Ⅳ部 「もの」のエージェンシー 7章 仮面が芸能を育む —バリ島のトペン舞踊劇に注目して [吉田ゆか子] Key Words:仮面,物性,芸能,もの中心の記述,ものらしくないもの 8章 「生きる」楽器 —スリンの音の変化をめぐって [伏木香織] Key Words:インドネシア,バリ・ガムラン,楽器,音の変化,音の「もの」性 9章 ものが見せる・ものに魅せられる —インドの占い師がもたらす偶然という「運命」 [岩谷彩子] Key Words:占い,偶然性,インデックス,ナイカン,チョーディ エッセイⅢ 揺らぐ「もの」 1 グローバル化するアボリジニ絵画,ローカル化する「芸術」 [窪田幸子] 2 太平洋諸島移民アーティストの身体と芸術のかたち [山本真鳥] 3 ほんものであり続けること: 「紅型」と「琉球びんがた」のあいだ [村松彰子] 第Ⅴ部 新たな「もの」論へ 10章 道具使用行動の起源と人類進化 [山越 言] Key Words:チンパンジー,アフリカ,霊長類,二足歩行,採食技術 11章 霊長類世界における「モノ」とその社会性の誕生 [黒田末寿] Key Words:霊長類,手,スガリ,モノの社会化,平等原則 12章 身体と環境のインターフェイスとしての家畜 —ケニア中北部・サンブルの認識世界 [湖中真哉] Key Words:インターフェイス,身体の拡張,アフォーダンス,擬家畜化,隠喩的思考 13章 チャムスの蝉時雨 —音・環境・身体 [河合香吏] Key Words:牧畜民チャムス,単独行動による放牧,音環境,ひとりであること,音の「もの」性 エピローグ:意志なき石のエージェント性 —「もの」語りをめざして [内堀基光] あとがき
鍛冶屋と鎚の対話、神が宿るとされる石等、世界各地の多様な「もの」と人間の関係を分析し、「ひと」と「もの」の境界に迫る。 「ひと」と「もの」の境界は何か。それは極めて不明瞭で流動的で、両者はときに一体となる。鍛冶屋と鎚の対話、将棋ソフトと人間の棋士の相互作用等、多様な事例をもとに編み上げた、人間中心主義を超える斬新な人類社会論。 日々スマホを使ってチャットをし,乗り物を使って移動し,パソコンを開いて思考する私たち.これらの「もの」は非人間の「もの」なのか,「ひと」の一部なのか,それとも私たち自身がじつは「もの」なのか? 鍛冶屋と鎚の対話,将棋ソフトと人間の棋士の相互作用,ひとが「ひとでなし」化されたホロコースト等、世界各地の多様な事例をもとに「もの」と「ひと」の混淆した関係を暴く,斬新な人類社会論. 序 章 新たな「もの」の人類学のための序章 —脱人間中心主義の可能性と課題 [床呂郁哉・河合香吏] 1 「もの」からの出発 2 「もの」をめぐる逆説的状況 3 関連諸分野における「もの」への回帰 4 人類学における「もの」研究の系譜 5 新たな「もの」概念へ 6 本書の扱う問題群—脱人間中心主義的な人類学へ向かって 7 本書の構成と各章の概要 8 結びに代えて—脱人間中心主義的人類学の可能性と課題 第Ⅰ部 ひとともののエンタングルメント 第1章 ものが生まれ出ずる制作の現場 —鉄と道具と私の共同作業 [黒田末寿] KEY WORDS:農鍛冶,手仕事,道具の循環,共成長,制作の対話モデル,ものの主体化,未完の思想 1 鍛冶見習い 2 技術者松浦清さん 3 鍛冶の基本作業 4 鉄を打つ感覚 5 ものが私を呼んでいる 6 制作者・道具・使用者の共なる成長 7 ものが生まれ出ずる文化 8 ものが生まれ出ずる文化の広がりと制作の両義性 9 成長する制作物,未完の思想 第2章 「もの」が創発するとき —真珠養殖の現場における「もの」,環境,人間の複雑系的なエンタングルメント [床呂郁哉] KEY WORDS:真珠養殖,流体的なテクノロジー,エンタングルメント,創発 1 「ひと」と「もの」のエンタングルメントの人類学へ 2 真珠とは何か 3 真珠養殖の民族誌—近代的真珠養殖技術の概要 4 流体的なテクノロジーと「もの」・環境・人間のエンタングルメント 5 「もの」の創発と複雑系—設計主義を越えて 6 結語—新たなマテリアリティ研究へ向けて 第3章 存在論的相対化 —現代将棋における機械と人間 [久保明教] KEY WORDS:将棋,コンピュータ,存在論的転回,比較,可塑性 1 怖がらないコンピュータ 2 それはいかなる転回か 3 比較の可塑性 4 相対化の実定性 Column 1 人工物を食べる—遺伝子組み換えバナナの開発 [小松かおり] EYWORDS:遺伝子組み換え,ゲノム編集,バナナ 第Ⅱ部 もののひと化 第4章 絡まりあう生命の森の新参者 —ボルネオ島の熱帯雨林とプナン [奥野克巳] KEY WORDS:諸自己の生態学,意思疎通,狩猟民プナン,複数種の絡まりあい,マルチスピーシーズ人類学 1 諸自己の生態学にみられる意思疎通 2 エクアドル・アヴィラの森のハキリアリをめぐる複数種の絡まりあい 3 ボルネオ島の熱帯雨林の生態学 4 ブラガの森の一斉開花・一斉結実期における複数種の絡まりあい 5 森の新参者たちの過去,現在,未来 第5章 サヴァンナの存在論 —東アフリカ遊牧社会における避難の物質文化 [湖中真哉] KEY WORDS:存在論的比較,国内避難民,遊牧,レジリアンス,最低限のもののセット 1 東アフリカ遊牧社会における存在論 2 紛争と国内避難民 3 遊牧民の国内避難民の物質文化悉皆調査 4 避難の物質文化—民族集団B,C,D の比較分析 5 最低限のもののセット 6 サヴァンナの存在論へ向けて 第6章 石について —非人工物にして非生き物をどう語るか [内堀基光] KEY WORDS:自然物,人工物,岩田慶治,五来重,アニミズム 1 「ひと」の手にならない「もの」 2 「ひと」の痕とその連鎖 3 「もの」に「ひと」を見る—岩田アニミズム 4 「もの」に「ひと」を見る—石の宗教 5 より「即物的」に Column 2 観察するサル,観察される人間 —非人間であるとはどのようなことか [伊藤詞子] KEY WORDS:人間と非人間,フマニタスとアントロポス,自己と他者,区別と関係 第Ⅲ部 ひとのもの化 第7章 「もの人間」のエスノグラフィ —ラスタからダッワ実践者へ [西井凉子] KEY WORDS:もの人間,ラスタ,ダッワ,髪,声,水 1 「もの人間」という事態 2 ファイサーンとポーンの住むパーイという町 3 ラスタの世界 4 ラスタからダッワへの移行 5 ダッワ実践者になる 6 結論にかえて—もの人間,生成する出来事 第8章 中国黄土高原に潜勢する〈人ならぬ—もの〉の力 [丹羽朋子] KEY WORDS:中国黄土高原,儀礼行為,イメージ=力,変異する出来事としての「もの」, 陰陽の境界域,剪紙が描く生の力線 1 〈人ならぬ—もの〉とはなにか 2 黄土高原の〈天地〉に生動する非人格的な力の捉え方 3 徴候的な力に触れる—災いへの対処儀礼 4 鬼への変化と孝子への変身—陝北の葬送儀礼 5 生生不息の剪紙—老女たちが描く生々流転する世界 6 まとめに代えて 第9章 〈ひとでなし〉と〈ものでなし〉の世界を生きる —回教徒とフェティシストをめぐって [田中雅一] KEY WORDS:アウシュヴィッツ,ホロコースト,フェティシズム,商品カタログ,ゾンビ 1 人とものとの否定的な関係 2 アウシュヴィッツの回教徒〈ひとでなし〉の出現 3 複製技術とフェティシズム—〈ものでなし〉の出現 4 ゾンビ・回教徒・フェティシスト Column 3 音となったコトバ—インドネシア,ワヤン・ポテヒの出場詩 [伏木香織] KEY WORDS:音,言葉,文字,ワヤン,ポテヒ,布袋戯,su liam pek,suluk,インドネシア,東ジャワ 第Ⅳ部 新たなもの概念 第10章 数からものを考える —『無限の感知』を参照しつつ [春日直樹] KEY WORDS:数,無限,神話,支払い,リズム 1 なぜ数をもちだすのか 2 パプアニューギニア,イクワィエ人の数え方 3 数の構造とイクワィエ人の再生産 4 神と人間,男と女 5 1,2,1,2,……の反復と無限 6 数とものの結びつき 7 「項目と数」によるアナロジー 8 リズムを含めて考える 9 ものを数で考えること 第11章 五感によって把握される「もの」 —知覚と環境をめぐる人類学的方法試論 [河合香吏] KEY WORDS:環境,五感,生態的参与観察,経験の共有,共感 1 「身の回り世界」と知覚 2 背景—「音」のもの性についての試論 3 五感をめぐる二つの視点—五感の統合性と五感の共鳴 4 知覚を扱う方法論—生態的参与観察 5 「五感」に基づく知覚世界とその社会的共同性(五感の共鳴)の普遍性に向けて 6 結びにかえて Column 4 使い終えた授業ノートをめぐって—ゴミとして識別されていく過程を人—「もの」関係としてとらえる試み [金子守恵] KEY WORDS:授業ノート,ゴミ,人—「もの」関係 第Ⅴ部 ものの人類学を超えて —動物研究と哲学からの視線 第12章 「人間」と「もの」のはざまで —「動物」から人類学への視点 [中村美知夫] KEY WORDS:動物の視点,存在論的転回,非人間,「自然」と「文化」,「普遍」と「特殊」 1 動物は「もの」を超える? 2 動物から人類学を見る 3 人間と非人間のはざまで—サル学者の「捻れ」た立場 4 「転回」と人類学 5 「非人間」について 6 動物の主体性なるもの 7 「自然」と「文化」 8 人類学者という「われわれ」? 9 人類学のゆくえ 第13章 〈もの自体〉を巡る哲学と人類学 [檜垣立哉] KEY WORDS:思弁的実在論,もの自体,メイヤスー,大森荘蔵 1 〈「もの自体」の形而上学〉 2 思弁的実在論ともの 3 祖先以前的な「もの」 4 類似の問い—大森荘蔵 5 非相関主義の射程 6 課題の総覧 索引 執筆者紹介
「日本では何もできない」。夫の国である日本に移住したものの、日本語が自在に操れず、孤立していた子育て中の外国人女性のことばである。出自国と日本との経済格差により弱い立場に置かれることも多く、社会で活躍するチャンスも奪われ、人的ネットワークも築けない。そのような結婚移住女性たちのコミュニケーションの力を、いかに育てればよいのか。日本語教師である著者が立ち上げた、結婚移住女性と日本人女性が交流する親子参加型サークルでの実践研究をもとに、地域日本語教育の在り方を考える。コミュニケーションの力が育つ過程で〈ことばの学び〉がどのように促されるのか、エスノグラフィーを通して浮かび上がらせる。 【目次】 第1章 本研究の目的と研究課題 第2章 先行研究と理論 第3章 研究方法 第4章 【エスノグラフィーⅠ】自分なりのリテラシーを生成・活性化するナルモンさん 第5章 【エスノグラフィーⅡ(1)】コミュニティへの周辺参加から十全参加に向かうリンさん 第6章 【エスノグラフィーⅡ(2)】メンタルヘルスの問題を抱え、「対話」を求めるレイラさん 第7章 【エスノグラフィーⅡ(3)】親密圏の中で人的ネットワークを構築するアンさん 第8章 結婚移住女性にとっての〈ことばの学び〉 第9章 日本人にとっての〈ことばの学び〉 ──再考・子育て中の女性にとっての地域日本語教育 第10章 生活者のLife を支える〈ことばの学び〉を促すための地域日本語教育
生身の身体を伴った,生活する人間を,同じく,生活する人間が理解するとはどういうことか? フィールドワークの「原点」へ。 生身の身体を伴った,生活する人間を,同じく,生活する人間が理解するとはどういうことか? 地域社会を這いずり回る4人の研究者が,乳幼児期の食(共食の体験),青年期の労働(沖縄のヤンキー),成人期の政治行動(市町村合併),老年期の社会関係(孤独・孤立)をとおして考える。フィールドワークの「原点」へ。 ■主な目次 第1章 乳幼児期の食をとおして考える〈生活-文脈〉理解――〈生活-文脈〉とは何かについて 【宮内 洋】 第2章 青年期の労働をとおして考える〈生活-文脈〉理解――沖縄のヤンキーのフィールドワークから 【打越正行】 第3章 成人期の政治行動をとおして考える〈生活-文脈〉理解――市町村合併の事例から 【新藤 慶】 第4章 老年期の孤独・孤立をとおして考える〈生活-文脈〉理解――高齢者の「文脈」なき「生活」理解を超えて 【松宮 朝】 終 章 〈生活-文脈〉理解の視点から永山則夫の「転職」を再考する 【宮内 洋】 まえがき 第1章 乳幼児期の食をとおして考える〈生活-文脈〉理解――〈生活-文脈〉とは何かについて 1.はじめに:ヒトの発達における環境について「狼に育てられた子」から考える 2.食をとおしてみる人間の発達 3.〈生活― 文脈〉とは何か 4.まとめにかえて:なぜいま〈生活― 文脈〉理解が必要となるのか 第2章 青年期の労働をとおして考える〈生活-文脈〉理解――沖縄のヤンキーのフィールドワークから 1.『ヤンキーと地元』で書いたこと 2.戦い方から現実に迫る 3.沖縄の建設業を生きる 4.沖縄のヤンキーの〈生活― 文脈〉理解:長きにわたって奪いつづける関係をもとに 【第2章 補論】 脇の甘いフィールドワーカーがフィールドに巻き込まれた軌跡 1.パシリ気質の父親 2.脇の甘いフィールドワーカー 3.〈生活― 文脈〉理解と、観察者の変化 4.時間をかけて馴染ませる 第3章 成人期の政治行動をとおして考える〈生活-文脈〉理解――市町村合併の事例から 1.はじめに:市町村合併論議と住民の〈生活-文脈〉 2.住民の生活圏と「村の精神」という文脈:鈴木榮太郎の議論 3.農民の日常生活と「生活組織」という文脈:有賀喜左衛門の議論 4.群馬県旧富士見村における市町村合併問題 5.群馬県旧榛名町における市町村合併問題 6.政治グループにみる地域社会における政治行動と〈生活―文脈〉理解 第4章 老年期の孤独・孤立をとおして考える〈生活-文脈〉理解――高齢者の「文脈」なき「生活」理解を超えて 1.はじめに:鎌をめぐる出来事から 2.高齢者の「孤独」・「孤立」をめぐって 3.「文脈」なき「生活モデル」? 4.高齢者の〈生活― 文脈〉理解から 5.さらなる〈生活― 文脈〉理解に基づく福祉実践へ 6.おわりに:「文脈」をふまえた「生活」理解 終 章 〈生活-文脈〉理解の視点から永山則夫の「転職」を再考する 1.はじめに:永山則夫と二冊の本 2.永山則夫の転職 3.永山則夫と虐待 4.トラウマによる〈逃走〉の可能性 5.おわりに:見る人自身の〈生活― 文脈〉 あとがき
「東京ばな奈」は、なぜ東京土産の定番になれたのか?調査点数1073点、身近な謎に丹念な調査で挑む画期的研究。 「東京ばな奈」は、なぜ東京土産の定番になれたのか?そして、なぜ菓子土産は日本中にあふれかえるようになったのか?調査点数1073点、身近な謎に丹念な調査で挑む画期的研究。 「東京ばな奈」は、なぜ東京土産の定番になれたのか? そして、なぜ菓子土産は日本中にあふれかえるようになったのか? 調査点数1073点、身近な謎に丹念な調査で挑む画期的研究。 日本人は旅行に行くと必ず菓子の土産を買って周囲に配る。しかし実はこれは、案外最近定着した振る舞いにすぎない。1970年~80年代を境に、土産はモノから食べ物中心へと劇的に変化した。なぜこれほどまで全国に似たような菓子土産があふれるようになったのか、そもそもなぜ土産を購入するのか。本書ではその問いをきっかけとして、日本における土産の歴史と現在を詳細な資料調査と、文化人類学の手法によって解き明かす。そこから見えてきたのは、交通網の発展に伴った大量生産、大量消費の時代から、国策も背景とした地元でしか作れない本物性へのこだわりへの転換だった。菓子土産についての初めての学術的研究が誕生。 ◎目次 まえがき 第1章 問題の所在と本論の目的 第1節 旅と土産品 第2節 本論文における用語・資料について コラム1 自宅で買える菓子土産─ 移動する非日常と移動しない日常 第2章 「新しいタイプの菓子土産」の登場 第1節 菓子土産の歴史(第1世代 1950年代に誕生) 第2節 菓子土産の歴史(第2世代 1960~70年代に誕生) 第3節 「新しいタイプの菓子土産」――「白い恋人」と「萩の月」の登場(第3世代 1970年代後半に誕生) 第4節 「新しいタイプの菓子土産」の後継 第5節 菓子土産の増加とその背景――菓子製造機械の進化とノウハウの蓄積 コラム2 レゴランド・ジャパンと菓子土産 第3章 地域づくりから生まれる「特産品菓子土産」 第1節 「特産品菓子土産」が生まれた経緯 第2節 地域の特産品を活かした「特産品菓子土産」の現状 第3節 発見・発掘される新たな地域性 コラム3 大手菓子メーカーの地域限定商品─ ご当地物の菓子土産 第4章 より本物らしさが求められる菓子土産 第1節 「新しいタイプの菓子土産」と「特産品菓子土産」における地域性の比較 第2節 「新しいタイプの菓子土産」と「特産品菓子土産」における「菓子土産」が成立する前提条件の比較 第3節 聖/俗をめぐる構造分析における菓子土産 第4節 菓子土産と真正性 コラム4 どちらがより本物らしい菓子土産?――北海道産小豆使用 vs 地域産小豆使用 終章 日本人の旅行と菓子土産 第1節 菓子土産の地域性、真正性 第2節 菓子土産を追い求めて コラム5 菓子土産を販売する土産品売り場の増加 あとがき 参照文献 まえがき 第1章 問題の所在と本論の目的 第1節 旅と土産品 第2節 本論文における用語・資料について コラム1 自宅で買える菓子土産─ 移動する非日常と移動しない日常 第2章 「新しいタイプの菓子土産」の登場 第1節 菓子土産の歴史(第1世代 1950年代に誕生) 第2節 菓子土産の歴史(第2世代 1960~70年代に誕生) 第3節 「新しいタイプの菓子土産」――「白い恋人」と「萩の月」の登場(第3世代 1970年代後半に誕生) 第4節 「新しいタイプの菓子土産」の後継 第5節 菓子土産の増加とその背景――菓子製造機械の進化とノウハウの蓄積 コラム2 レゴランド・ジャパンと菓子土産 第3章 地域づくりから生まれる「特産品菓子土産」 第1節 「特産品菓子土産」が生まれた経緯 第2節 地域の特産品を活かした「特産品菓子土産」の現状 第3節 発見・発掘される新たな地域性 コラム3 大手菓子メーカーの地域限定商品─ ご当地物の菓子土産 第4章 より本物らしさが求められる菓子土産 第1節 「新しいタイプの菓子土産」と「特産品菓子土産」における地域性の比較 第2節 「新しいタイプの菓子土産」と「特産品菓子土産」における「菓子土産」が成立する前提条件の比較 第3節 聖/俗をめぐる構造分析における菓子土産 第4節 菓子土産と真正性 コラム4 どちらがより本物らしい菓子土産?――北海道産小豆使用 vs 地域産小豆使用 終章 日本人の旅行と菓子土産 第1節 菓子土産の地域性、真正性 第2節 菓子土産を追い求めて コラム5 菓子土産を販売する土産品売り場の増加 あとがき 参照文献
ヤンキーは何を考え、どのようにして大人になるのか――。高校で〈ヤンチャな子ら〉と3年間をともに過ごし、高校を中退/卒業してからも継続して話を聞いて、集団の内部の亀裂や、地域・学校・家族との軋轢、社会関係を駆使して生き抜く実際の姿を照らす。 序 章 〈ヤンチャな子ら〉のエスノグラフィーに向けて 1 巷にあふれる「ヤンキー語り」と調査の不在 2 〈ヤンチャな子ら〉を調査・研究する意義 3 本書の目的と独自性 4 調査の概要 5 本書の構成 第1章 ヤンキーはどのように語られてきたのか 1 若者文化としてのヤンキー 2 生徒文化としてのヤンキー 3 階層文化としてのヤンキー 4 これまでのヤンキー研究の課題 5 分析の方針 第2章 〈ヤンチャな子ら〉の学校経験――教師との関係に着目して 1 〈ヤンチャな子ら〉と教師の対立? 2 学校文化の三つのレベル 3 家庭の文化と学校文化の葛藤 4 〈ヤンチャな子ら〉と教師の相互交渉 5 教師への肯定的評価と学校からの離脱 6 〈ヤンチャな子ら〉と「現場の教授学」 第3章 〈ヤンチャな子ら〉とは誰か――〈インキャラ〉という言葉に着目して 1 集団の曖昧さ 2 類型論的アプローチを超えて 3 〈インキャラ〉という解釈枠組み 4 文脈のなかの〈インキャラ〉 5 〈インキャラ〉という解釈枠組みのゆらぎ? 6 集団の内部の階層性 第4章 「貧困家族であること」のリアリティ 1 「子ども・若者の貧困」研究における本章の位置づけ 2 「記述の実践としての家族」という視点 3 記述の実践としての「貧困家族」 4 アイデンティティとしての家族経験 第5章 学校から労働市場へ 1 〈ヤンチャな子ら〉の仕事への移行経路 2 〈ヤンチャな子ら〉の移行経験――六人の語りから 3 移行経路と社会的ネットワーク 終 章 〈ヤンチャな子ら〉の移行過程からみえてきたこと 1 〈ヤンチャな子ら〉集団内部にある「社会的亀裂」 2 重層的な力学のなかにヤンキーを位置づけた意義 3 「ヤンキー」と括られる人々の内部に目を向けることの重要性 4 アンダークラスとしてカテゴリー化することの危険性 5 〈貧困の文化〉か、〈社会的孤立〉か 6 社会関係の編み直しに向けて 巻末資料 参考文献 初出一覧 あとがき
当たり前の日常が、視点を変えると全く別の世界になる―。 気鋭の人類学者による、世界の見方を変える「手引き」書。 西日本新聞で2020~2022年に連載した「人類学者のレンズ」、朝日新聞で2018年に連載した「松村圭一郎のフィールド手帳」を加筆・修正、再編集して書籍化。 「うしろめたさの人類学」などで知られる筆者は、コロナ禍やオリンピック、地震、水害、戦争などの社会、時事問題が噴出する「現在」に立脚しつつ、人類学の先行研究、原点であるエチオピアの人類学調査、古里の熊本での思い出をたどっていく。 人類学者のさまざまな眼を通じて、「危機」の時代を読み解き、揺れる「今」を生きるヒントを考える。 レヴィ=ストロース、ルース・ベネディクト、デヴィッド・グレーバー、ティム・インゴルド、岩田慶治、猪瀬浩平、磯野真穂など、国内外の人類学者の論考が登場。人類学という学問と現実をつないでいく試み。 西日本新聞連載時と同様に福岡出身の写真家、喜多村みかとコラボ。ポートレートでありながら、抽象性を合わせ持つ喜多村の写真は、文章の余白や解釈の幅を広げる。
民俗研究映像「盆行事とその地域差」 葬儀は誰がするのか、してきたのか? 祖霊とみたまの歴史と民俗 葬法と衛生観念 自動車社会化と沖縄の祖先祭祀 列島の民俗文化と比較研究 討論
この書籍は、陰陽師の歴史と役割を探求し、彼らが日本社会に与えた影響を考察しています。陰陽道は古代中国の思想から生まれ、日本に導入され、国家の科学技術機関として機能しました。著名な陰陽師、特に安倍晴明の業績や他の陰陽師たちの活動を紹介し、平安時代の黄金期から明治時代の廃止までの歴史を辿ります。現代でも利用できる陰陽道の実践的な知識も提供されており、陰陽師の存在が今もなお重要であることを示唆しています。
文化人類学者とともに「働くこと」のポジティブな未来を探究する人気ポッドキャスト「働くことの人類学」、 待望の【活字版】!! 文化人類学者とともに「働くこと」のポジティブな未来を探究する人気ポッドキャスト「働くことの人類学」、 待望の【活字版】!! 文化人類学者が、それぞれのフィールドで体験した 知られざる場所の知られざる人びとの「働き方」。 それは、わたしたちが知っている「働き方」となんて違っているのだろう。 逆に、わたしたちはなんて不自由な「働き方」をしているのだろう。 狩猟採集民、牧畜民、貝の貨幣を使う人びと、 アフリカの貿易商、世界を流浪する民族、そしてロボット........が教えてくれる、 目からウロコな「仕事」論。 わたしたちの偏狭な〈仕事観・経済観・人生観〉を 鮮やかに裏切り、軽やかに解きほぐす、笑いと勇気の対話集。 ゲスト:柴崎友香/深田淳太郎/丸山淳子/佐川徹/小川さやか/中川理 /久保明教 ◼️巻頭対談 ありえたかもしれない世界について 柴崎友香 + 松村圭一郎 【第1部|働くことの人類学】 貝殻の貨幣〈タブ〉の謎 深田淳太郎 ひとつのことをするやつら 丸山淳子 胃にあるものをすべて 佐川徹 ずる賢さは価値である 小川さやか 逃げろ、自由であるために 中川理 小アジのムニエルとの遭遇 久保明教 【第2部|働くこと・生きること】 2020年11月「働くことの人類学」の特別編として開催されたイベント「働くことの人類学:タウンホールミーティング」。 オンラインで4名の人類学者をつなぎ、参加者xの質問を交えながら「働くこと」の深層へと迫った白熱のトークセッション。デザインシンキングからベーシックインカムまで、いま話題のトピックも満載のユニークな「働き方談義」を完全収録。 深田淳太郎×丸山淳子×小川さやか×中川理 ホスト=松村圭一郎 進行=山下正太郎・若林恵 【論考】 戦後日本の「働く」をつくった25のバズワード 【働くことの図書目録】 仕事と自由をもっと考えるためのブックガイド 松村圭一郎/深田淳太郎/丸山淳子/佐川徹/小川さやか/中川理/久保明教/コクヨ野外学習センター 【あとがき】 これは「発信」ではない 山下正太郎
エドワード・バーネット・タイラー ヴィルヘルム・シュミット フランツ・ボアズ マルセル・モース ブロニスロウ・K・マリノフスキー アルフレッド・R・ラドクリフ=ブラウン ルース・フルトン・ベネディクト マーガレット・ミード クライド・クラックホーン レスリー・ホワイト ジュリアン・H・スチュワード ロイ・A・ラパポート リチャード・リー ハロルド・コリヤー・コンクリン マーシャル・D・サーリンズ エリック・ウルフ ヴィクター・W・ターナー デイヴィッド・M・シュナイダー クリフォード・ギアツ フレドリック・バルト ベネディクト・アンダーソン E・E・エヴァンズ=プリチャード ロドニー・ニーダム エドマンド・R・リーチ メアリー・ダグラス クロード・レヴィ=ストロース モーリス・ゴドリエ ピエール・ブルデュー ダン・スペルベル ロジャー・キージング ジェイムズ・クリフォード ジーン・レイヴ ウィリアム・バリー ジュディス・バトラー アーサー・クラインマン マーガレット・ロック ロバート・チェンバース アルジュン・アパドゥライ マリリン・ストラザーン アルフレッド・ジェル ティム・インゴールド フィリップ・デスコラ ブルーノ・ラトゥール エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ アネマリー・モル
文化人類学における「人格」. ヴァヌアツ・アネイチュム島. 一八四八. 村落の誕生. 持続と断絶. 恥辱と歴史認識. 譲渡できないものを贈与する. 名の示すもの. 人格の手前にあるもの. 死と状況的人格. 共在する人格 文化人類学における「人格」 ヴァヌアツ・アネイチュム島 一八四八 村落の誕生 持続と断絶 恥辱と歴史認識 譲渡できないものを贈与する 名の示すもの 人格の手前にあるもの 死と状況的人格 共在する人格
浅草の初夏を熱狂の渦に巻き込む三社祭。その花形である三基の本社神輿を担いでるのは誰なのか。神輿の棒を激しい争奪戦で勝ち取ってきた有名神輿会に飛び込んだ著者が、祭りの狂騒と闘争をリアルに描き出すエスノグラフィー。 下町・浅草の初夏を熱狂の渦に巻き込む三社祭。 その花形である三基の本社神輿を担いでるのは誰なのか? 神輿の棒を激しい争奪戦で勝ち取ってきた有名神輿会に飛び込んだ著者が、祭りの狂騒と闘争をリアルに描き出すエスノグラフィー。 序章 神輿渡御を闘争として分析する 第一章 民俗学の(複数の)新しい方向性の提示を目指して 一 民俗学的研究の三つの方針 二 「非公式」的祭礼研究宣言 第二章 神輿渡御をどう理解するのか──本書の分析視角 一 東京圏の神輿渡御の社会的背景 二 祭礼研究の地図──分析視角の批判的考察 三 闘争からみる浅草の神輿渡御 四 浅草地域と三社祭 第三章 モノの観点からみる東京圏の神輿渡御 一 神輿とは何か 二 神輿渡御とは何か 三 「江戸前」の美学と標準化した祭礼運営の手法 四 本書は神輿渡御をどのように理解するか 第四章 江戸・東京の祭礼史 一 前史──天下祭における形式性と周辺祭礼における乱痴気騒ぎの時代 二 第一期──町神輿の登場と町会による権威的配分の時代 三 第二期──町会と神輿会との闘争の時代 四 第三期──権威的配分の再成立と社会─祭礼関係の時代 五 町神輿は何をもたらしたか──京都市域の神輿渡御と比較して 第五章 神輿会のエスノグラフィー 一 神輿会の概要 二 A神輿会の概要 三 祭礼の場におけるA神輿会 四 A神輿会内部における人間関係 五 A神輿会の男性性と女性会員 六 A神輿会と他の神輿会の関係 七 神輿会と伝統・宗教 八 A神輿会の社会階層 九 神輿会にとって神輿担ぎとは何か 第六章 町会・青年部による祭礼運営のエスノグラフィー 一 町会の概要 二 B睦会による祭礼運営 三 祭礼運営における論点 四 町会・青年部にとって神輿渡御とは何か 第七章 神輿渡御における地域的共同性はいかにして達成されるか 一 神輿渡御における〈資源配分をめぐる闘争〉 二 「棒振り」と資源の権威的配分 三 〈右肩の会〉と〈左肩の会〉 四 神輿渡御の三者関係 五 地域的共同性の再成立と地域の再統合 第八章 「江戸前」の美学の創造・拡大・定着 一 神輿渡御における「美学」をめぐる闘争 二 「江戸前」以前の美学 三 「江戸前」の美学の創造・拡大・定着 四 「江戸前」スタイルの意味するもの 第九章 神輿を担ぐことの文化政治 一 神輿渡御における神聖化戦略をめぐる闘争 二 三社祭における神聖化戦略をめぐる闘争 三 神輿パレードにおける神聖化戦略をめぐる闘争 四 〈イベントから「伝統」へ〉 結章 まとめと展望 一 本書の要約 二 本書の目的はどこまで達成されたか 三 残された課題 補論 コロナ禍の三社祭を歩く 文献一覧 あとがき 初出一覧 索引
柳田國男の生い立ちと学問的背景 柳田國男旧蔵考古資料とは? 柳田國男はどんな考古資料を収集したのか 柳田考古遺物の採集地はどこか? 1 明治後期における柳田國男の旅行先 柳田考古遺物の採集地はどこか? 2 樺太紀行の旅程 柳田考古遺物の採集地はどこか? 3 南樺太の領有と当時の人類学者たちの動向 柳田考古遺物の採集地はどこか? 4 「樺太紀行」以後のサハリン島における考古学の展開 お雇い外国人の活躍と一八八〇年代の「日本人種論」 日本人研究者による人種論の始まり 柳田國男の考古遺物収集と山人論の形成 古代史学者喜田貞吉の日本民族論と柳田國男との関係 鳥居龍蔵の固有日本人論 形質人類学者による日本人種論 柳田國男はなぜ考古学を批判し、考古学と決別したのか 自然科学と文学 柳田國男と南方熊楠との交流 山人論から稲作民俗論へ 文学との決別が柳田民俗学を生んだのか 民俗学の誕生と考古学への意識 まとめ
東アジア各地域におけるレコード史が、日本と関わりを持ちながら展開してきた点に言及し、普及した背景等をSPレコードを軸に探求。 東アジア各地域におけるレコード史が、日本と関わりを持ちながら展開してきた点に言及し、レコードが東アジアに普及した背景や、日本が音楽の伝承に与えた影響などを、音盤(SPレコード)を軸に様々な角度から探求した。 19世紀に誕生した蓄音機は、20世紀に入りアジアでも急速に普及した。西洋のクラシック音楽の輸入盤ばかりでなく、日本、中国、台湾、朝鮮でもさまざまな録音が行われ、多くの音盤(SPレコード)が発売された。本書では、東アジア各地域におけるレコード史が、日本と関わりを持ちながら展開してきた点に言及し、レコードが東アジアに普及した背景や、複雑な構造の中で日本が音楽の伝承に与えた影響などが論じられている。当時、欧米の外資系を含む日本のレコード会社は、東アジア各地に積極的に進出し、録音、販売を行った。こうした東アジアのレコード産業の歴史は、グローバリゼーションのひとつの例と見ることができる。さらに、台湾と朝鮮半島のレコード産業の発展は中国とは異なり、日本の植民地支配の影響も大きかった。日本のレコード産業と植民地の歴史には、グローバリゼーションや資本主義、植民地主義が複雑に交錯している。また本書が音盤(レコード)を扱いながらも、書名に「音楽」ではなく「声」を用いているのは、当時のこれらのレコードの内容が音楽にとどまらず、歌はもちろんのこと、演説や映画説明、戯劇など、多様な声の表現にわたっていたものだからだ。東アジアの歴史を、音盤を通して様々な角度から探求した一冊。 総説 蓄えられた声を百年後に聴く──私たちはなぜこの百年のレコード史を追っているのか(劉 麟玉) 第1部 東アジアのレコード産業――声の近代 第1章 日本の円筒録音時代――声の再生、模倣、保存(細川 周平) 第2章 日本統治時代における台湾レコード産業と「台湾盤」の市場メカニズム(黃 裕元/訳:岡野〔葉〕翔太) 第3章 台湾テイストを作り出す――日本蓄音器商会の台湾レコード制作の戦略を探る(王 櫻芬/訳:長嶺 亮子) 第4章 「新譜発売決定通知書」を通してみる台湾コロムビアレコード会社と日本蓄音器商会の間の「対話」──戦争期のレコード発売状況の調査を兼ねて(一九三〇〜一九四〇年代)(劉 麟玉) 第5章 写音的近代と植民地朝鮮、一八九六~一九四五(山内 文登) 第2部 東アジアのレコード音楽の諸相――声の平行と交錯 第6章 草津節――お座敷からレコードへ、そして外地へ(福岡 正太) 第7章 戦前・戦中台湾のコロムビアレコードの音から――歌仔戯(ゴアヒ)と新興劇の音楽の繋がりをさぐる(長嶺 亮子) 第8章 清朝末期から中華民国期の崑曲SPレコード──吹込者と録音内容にたどる近代伝統劇界の変遷(尾高 暁子) 第9章 義太夫節・パンソリ・蘇州弾詞の歴史的音源に聴く演奏様式の変容(垣内 幸夫)
本書は、レヴィ=ストロースの構造主義を中心に、彼の影響力や思想の核心を探る内容です。哲学を放棄しブラジルへ向かった背景、彼の主要著作『親族の基本構造』『野生の思考』『神話論理』を通じて、未開社会の親族構造や神話研究の豊かな可能性を解明します。また、構造主義の誤解を解き、ポストコロニアル論への応用を目指す新たな入門書です。
身近な経験とつながるさまざまな制度や出来事を人類学はどのように見るのか,最新の成果をわかりやすく伝える入門テキスト。 私たちの身近な経験とつながる制度や出来事を人類学はどのように見るのか,最新の成果をわかりやすく伝える入門テキスト。文化と社会の多様性がわかるさまざまなテーマを通じて世界の見方を学び,世界を変えていく手がかりを得るための1冊。 序 論 第Ⅰ部 傷つきやすいものとしての人間 第1章 貧困(森田良成) 第2章 自然災害(金谷美和) 第3章 うつ(北中淳子) 第4章 感染症(浜田明範) 第5章 性愛(深海菊絵) 第Ⅱ部 文化批判としての人類学 第6章 アート(兼松芽永) 第7章 人間と動物(奥野克巳) 第8章 食と農(竹沢尚一郎) 第9章 自分(春日直樹) 第10章 政治(松田素二) 第Ⅲ部 人類学が構想する未来 第11章 自由(中川 理) 第12章 分配と価値(西 真如) 第13章 SNS(久保明教) 第14章 エスノグラフィ(小川さやか)
ベナンの妖術師 ヒマラヤの雪男イエティ どうして「呪われた」と思ってしまうの? かもしれない、かもしれない…… ヴァヌアツで魔女に取り憑かれる 中央オーストラリアの人喰いマムー 幼児の死、呪詛と猫殺しと夢見 鬼のいる世界 映像によって怪異な他者と世界を共有する方法
急性期の現場で連携するため看護師たちは何を見聞し、考え、お互い報告しているのか。「チーム医療の大切さ」といった理念の主張に留まらず、個々の看護を協働によって円滑に成し遂げる方法論を見出し、病棟の時間と空間の編成を描きだす記録集。
この書籍は、日本における文化人類学の重要性を探求し、同じ景色を見ても異なる視点が存在することを強調しています。著者たちは、日本をフィールドとして多様なテーマ(家族、老い、信仰、性、移民など)を通じて、文化や社会の理解を深めることを提案しています。読者に対して、「あたりまえ」を疑うことで自己の世界を広げることを促しています。
本書は、「秘密のケンミンSHOW」の元リサーチャーが全国の注目店を紹介し、地元に根ざした飲食店の成功法則を探ります。取り上げるのは、福田パンや551 HORAI、ばんどう太郎など、地域限定の魅力を持つ7つの店舗で、各店のユニークな特徴やビジネスモデルを通じて、逆境をチャンスに変えるための黄金ルールを解説しています。著者は、ライターであり、テレビ番組のリサーチャーとしての経験を活かし、地域の飲食文化を掘り下げています。
グローバル・ネットワークが地球を覆い尽くす「人新世」時代においてその網の目からこぼれ落ちる他者の営みに人類の可能性を見出す。 近代のプロジェクトが推し進めてきたグローバル・ネットワークが、地球全体を覆い尽くす「人新世」時代と呼ばれる今日。近代化の網の目からこぼれ落ちる、過剰なる他者たちの営みから、人類の想像力の可能性を見出す。 近代化の網の目からこぼれ落ちる、過剰なる他者たちの営みから、いかに人類の想像力の可能性を見出すか――。 総勢12名の人類学者が対話・インタビュー形式で「人新世」時代を語る、最新の研究動向に迫る論集。 近代のプロジェクトが推し進めてきたグローバル・ネットワークは、地球全体を覆い尽くすまでに拡大した今日。それは、もはや地球の存在そのものが危ぶまれる、「人新世」時代へと突入したと呼ばれるようになった。 このような21世紀初頭の時代において、人類のさまざまな文化のあり方をつぶさに研究してきた文化人類学もまた、大きな岐路に立たされている。文化人類学という学問が、80億人に達した人類について、その過去と現在を問い、その未来の限界と可能性を探究するという壮大な規模の問題を扱う実践である以上、その担い手である人類学者の立場も関心も見解も多様にならざるをえないだろう。 本書は、こうした豊かな多様性を孕みつつ共通の感性でゆるやかにつながれた文化人類学という学問の実情をできる限りそのままに提示する試みた、文化人類学者たち自身による文化人類学という学的実践の実験的な民族誌である。 対話の形式で紡がれる本書は、現在進行中の文化人類学の実践の目的、対象、方法、意義などの一端が、地域・フィールドを異にする文化人類学者たち自身によってさまざまに語られると同時に、問答を応酬しながら相互に触発し合うことで、新たなパースペクティヴの予感を宿しながら未来の可能性を孕む種子や胚を懐胎してゆく姿を提示していく。 はじめに 序 章 「人新世」時代の文化人類学の挑戦(大村敬一) 第Ⅰ部 グローバル・ネットワークの外部からの挑戦 第1章 多重に生きる ―― カナダ・イヌイトの挑戦(大村敬一) 第2章 先住民運動の挑戦 ―― 新たな政治制度を目指して(深山直子) 第3章 アナーキズム社会の挑戦 ―― マダガスカルのヴェズの戦術の可能性(飯田卓) 第Ⅱ部 変質しゆくグローバル・ネットワーク 第4章 科学技術と気候変動の人類学――近代の「自然/人間」の二元論の再考(森田敦郎) 第5章 グローバル・エコノミーの隙間からの挑戦(中川 理) 第6章 プラネタリーヘルスの挑戦 ――「人新世」時代の医療と公衆衛生(モハーチ ゲルゲイ) 第Ⅲ部 変質しゆく人類 ―― 非人間との出会い 第7章 災害の人類学 ―― 近代を凌駕する他者の力に向き合う(木村周平) 第8章 人類の可変性 ―― 非人間とのもつれ合いのなかで(モハーチ ゲルゲイ/久保明教) 第Ⅳ部 人類の創造力の可能性 第9章 芸術 ―― 「仮構作用」の創造力(中谷和人) 第10章 日常に潜む「生きる力」 ―― 人類社会の根っこにある宗教(土井清美) 第11章 進化史のなかの人類 ―― 人類の創造性と可変性の進化史的基盤(入來篤史/河合香吏) 終 章 人類と地球の未来―― 多様性の苗床になる(大村敬一)
児童養護施設の社会学へ 調査概要 日常生活のエスノグラフィーと実践としての「施設」 施設内の仲間集団の影響と〈友人〉形成と実践 コミュニケーションとして生じる子ども間の身体的暴力と実践 子ども間での「差」と保護者との実践 施設内のルールによる養育環境形成のジレンマと子どもの社会化実践 施設において垣間見られる「家庭」実践 結論
社会的背景 理論的背景 オートエスノグラフィーの構成 〈研究1〉教員志望学生のキャリア選択過程 〈研究2〉大学教員による日常的なキャリア支援 〈研究3〉成長の瞬間を生み出す「よいキャリア支援」の意味感覚 総合考察
文化人類学の中から100のキーワードを厳選し,見開き2頁で解説する。各項目のヴァージョン・アップを図り,改訂した。 文化人類学という幅広い学問分野の中から,100の基本的なキーワードを厳選し,見開き2頁で解説する。初版刊行後10年間の社会の変動と学問の進展を反映させるため,各項目のヴァージョン・アップをはかると同時に,必要に応じて新しい項目に入れ替えた。 改訂版によせて この本を手にした人へ 執筆者紹介と執筆分担 第1章 文化人類学の技法とディスクール 第2章 人間の多様性 第3章 文化のダイナミズム 第4章 社会のコンプレクシティ 第5章 現代のエスノグラフィー 参照文献一覧 事項索引 人名索引
人類の誕生と進化の歴史、日本列島に渡来したホモ・サピエンスの活動などをわかりやすく解説する。 これまでの科学的学説を紹介し、現在定説化しているものを基本にしながら、人類学、遺伝学(分子人類学)の流れを整理。人類の誕生と進化の歴史、日本列島に渡来したホモ・サピエンスの活動などをわかりやすく解説する。 ヒトはどこから来たのか――。 これまでの科学的学説を紹介し、現在定説化しているものを基本にしながら、人類学、遺伝学(分子人類学)の流れを整理。人類の誕生と進化の歴史、日本列島に渡来したホモ・サピエンスの活動などをわかりやすく解説する。 はじめに 第一部 人類の起源 第一章 霊長類の誕生とダーウィンの挑戦 ●第一節 ビッグバンから地球と人類の誕生まで ●第二節 ダーウィンの『種の起源』と進化論 ●第三節 人類のアフリカ起源説と多地域進化説 ●第四節 DNAと分子人類学の発展 第二章 人類の進化 ●第一節 チンパンジーとの分岐と猿人の出現 ●第二節 ホモ属の出現と原人、旧人 ●第三節 ネアンデルタール人とデニソワ人 ●第四節 アフリカでのホモ・サピエンス 第三章 出アフリカから世界への拡散 ●第一節 ホモ・サピエンスの「出アフリカ」 ●第二節 ユーラシア大陸への展開 ●第三節 ホモ・サピエンスのオセアニアへの拡散 ●第四節 最後の大陸・南北アメリカへ 第四章 古代農業革命と歴史時代への移行 ●第一節 古代の農業革命 ●第二節 農業革命と戦争・ゲノムの変化 ●第三節 歴史時代のさまざまな変革と限界 ●第四節 人類と言語について 第五章 今後の人類の課題 ●第一節 自然現象と関連した課題 ●第二節 植民地主義と核兵器の廃絶 ●第三節 「人新世」の提起 第二部 日本人の起源 第一章 日本の後期旧石器時代 ●旧石器時代の地理的、歴史的特徴 第二章 縄文時代の一万二〇〇〇年 ●第一節 分子人類学からの視点 ●第二節 縄文の名称と特徴、一万二〇〇〇年の長さ ●第三節 縄文人の衣食住確保と食生活 ●第四節 縄文時代の主要な道具 ●第五節 三内丸山遺跡、上野原遺跡などの事例 第三章 弥生時代の水田稲作と金属器など ●第一節 弥生時代の定義とDNAの変化 ●第二節 階級社会の成立と戦争、金属器の普及 ●第三節 琉球列島集団、北海道集団の成立と弥生時代 ●第四節 崎谷満氏の「縄文主義」と「長江文化神話」批判 第四章 古墳時代から飛鳥時代へ ●第一節、古墳時代の王権確立と人口増加 ●第二節 飛鳥時代の変化 第五章 日本の歴史時代を縦断する ●第一節 歴史時代の日本の「革命」 ●第二節 日本史の時代区分について ●第三節 日本が直面した危機的事件 第六章 日本語の起源について ●第一節 日本語の起源についての代表的な説 ●第二節 縄文語の探求と太平洋沿岸言語圏 ●第三節 日本語の起源に関するさまざまな説 ●第四節 最近の国際研究チームの発表 ●第五節 日本語のルーツに関する今後の課題 第七章 日本人起源論の系譜 ●第一節 明治初頭の外国人の「日本人起源論」 ●第二節 大学アカデミーと日本人起源説 ●第三節 分子人類学者らの「二重構造説」批判 第八章 今後の課題 おわりに 参考文献 ■第一部コラム 宇宙~人類略史年表/チャールズ・ダーウィンの年譜/DNAのコンタミネーション/主な遺跡の発見年表/人類進化の系統表/ネアンデルタール人関連略史/虫歯の人類史/ヒトとチンパンジーの成長期間/英国のビルトダウン人事件/シルクロードと東西交流 ■第二部コラム 沖縄で発見された主な旧石器時代遺跡/日本の五大火山爆発/アイヌ人と和人の戦いと近年の法的措置/太安万侶の墓
質的研究のためのエスノグラフィーと観察 目次 編者から(ウヴェ・フリック) 「SAGE質的研究キット」の紹介 質的研究とは何か 質的研究をどのように行うか 「SAGE質的研究キット」が扱う範囲 本書について(ウヴェ・フリック) はじめに 1章イントロダクション─エスノグラフィーと参与観察 エスノグラフィーを用いた研究小史 社会文化理論とエスノグラフィー エスノグラフィー─基本原理 定 義 方法としてのエスノグラフィー 産物としてのエスノグラフィー スタイルと文脈としての参与観察 2章エスノグラフィーの有効性─エスノグラフィーの方法によって、 どのようなトピックを効果的かつ効率よく研究できるのか エスノグラフィーの方法─その一般的有効性 エスノグラフィーによる研究の実例 エスノグラフィーの方法─研究上の特有の課題 エスノグラフィーの方法─研究の場面 3章フィールドサイトの選定 自己目録作りから始める フィールドサイトを選ぶ ラポール 4章フィールドでのデータ収集 「事実」と「現実」 メモ:応用的エスノグラフィーについて 3つの主要な技法の領域 観 察 インタビュー 文書研究 5章観察について 観察の定義 観察研究のタイプ 観察研究の課題 観察研究のプロセス 妥当性の問題 観察者のバイアス 公共の場所での観察 倫理と観察研究 6章エスノグラフィー・データの分析 パターン データ分析のプロセス メモ:エスノグラフィー・データの分析における コンピューターの使用について 7章エスノグラフィー・データの表現方略 伝統的な学術的形式でのエスノグラフィー・データの表現 文書形式でのエスノグラフィー・データの他の表現方法 文書を超えて 8章倫理的配慮 研究に関係する倫理的配慮のレベル 制度的機構 研究倫理の個人的次元 結 論 9章21世紀のエスノグラフィー 変化しつつある研究文脈─テクノロジー 変化しつつある研究文脈─グローバリゼーション 変化しつつある研究文脈─バーチャルな世界 訳者あとがき 用語解説 文 献 人名索引 事項索引 装幀=新曜社デザイン室
広大なネット社会を見極める方法 協力者の生活の「現場」に参加・観察し記述する。これが人類学の代表的な参与観察研究法です。しかし、デジタル機器やインターネットに媒介される現代のコミュニケーションは現場に参与・観察できず、研究法は変革を求められています。そこで著者が提唱するのが、定性・定量の両面から迫り、多時的・多所的なデータ、干渉型・非干渉型の組合せという複数の意味をもつハイブリッド・エスノグラフィーです。本書ではその可能性が、机上の理論ではなく、日米デジタルネイティブの比較調査、モバイル機器利用から見るデジタルデバイド調査、日本最大のニュースサイトのコメントというビッグデータを用いたオンラインエスノグラフィーなどの着実な知見をもたらす実践で明らかになります。今後のネットワークコミュニケーション研究の道標となる分析としても、ビジネス界でニーズの高まる研究法、エスノグラフィーの大胆な革新としても読むことができる著者の集大成です。 ハイブリッド・エスノグラフィー 目次 はじめに Ⅰ ネットワークコミュニケーション/エスノグラフィー/ハイブリッド・エスノグラフィー 第1章 ネットワークコミュニケーション研究 1―1 「ネットワークコミュニケーション」 1―2 本書が対象とする「ネットワークコミュニケーション研究」 1―3 技術の社会的形成―――本書における技術と社会との関係の捉え方 第2章 ネットワークコミュニケーションの特性 2―1 5つの軸 2―2 関与者数 2―3 クローン増殖性と記憶・再生・複製・伝播様式 2―4 時間軸・空間軸における離散性・隣接性 2―5 「物理的存在」(オフラインの存在)/「論理的存在」(オンラインの存在)と社会的手掛かり 2―6 秩序形成への欲求とメディアイデオロギーの形成 第3章 NC研究におけるエスノグラフィーアプローチの展開 3―1 エスノグラフィー・質的研究への高まる関心 3―2 人類学におけるNC研究 3―3 サイバーエスノグラフィー研究 第4章 「ヴァーチュアル・エスノグラフィー」と「デジタル人類学」のあいだ 4―1 「エスノグラフィー」の危機 4―2 「ヴァーチュアル・エスノグラフィー」 4―3 「ヴァーチュアル・エスノグラフィー」と「デジタル人類学」のあいだ 52 4―4 エスノグラフィー革新の必要性 第5章 デジタル世界における対称性の拡張知識産出様式としてのエスノグラフィー革新の方向性 5―1 デジタルメソッド 5―2 知識産出様式における〈対称性(シンメトリー)〉の拡張 5―3 デジタル空間における「定量/定性」の対称性と「フィールド」概念の変容 5―3―1 デジタル空間における「定量/定性」の対称性 5―3―2 SNA・ネットワーク科学とエスノグラフィーとの接合「定性/定量」対称性方法論として 5―3―3 「干渉型参与観察」特権化の瓦解 5―4 「ビジネス/学術」の対称性 5―4―1 CUDOSからPLACE 5―4―2 ネットワークに埋め込まれる人々の活動とIT企業 5―4―3 「ビジネスエスノグラフィー」と「デジタル人類学」 第6章 ハイブリッド・エスノグラフィーの方法論的基礎 6―1 リサーチプロセスから規定する「エスノグラフィー」 6―2 「アブダクション(仮説生成的推論)」―――エスノグラフィーの中核的力 6―3 「ヒューリスティクス(発見法)」―――HEの中核的力 第7章 ハイブリッド・エスノグラフィーの具体的遂行と課題 7―1 エスノグラフィー調査の具体的遂行過程 7―2 つながりとしての「フィールド」とサイバーエスノグラフィー・アプローチ3類型 7―2―1 つながりとしての「フィールド」 7―2―2 焦点となる〈つながり〉からみたサイバーエスノグラフィー・アプローチ3類型 7―2―3 論理的存在/物理的存在の分離がもたらす方法論的課題 7―3 調査倫理 7―3―1 ケアの原則(principle of care) 7―3―2 調査研究許諾の確認と説明研究機関およびvenue毎の必要性 7―3―3 関係形成のダイナミズム 7―4 フィールドワークにおけるデータ収集法 7―4―1 観察、インタビュー、保存記録 7―4―2 インタビューの多元性 7―5 質的/量的をいかに組み合わせるかHEにおけるMMの具体的展開法 7―6 HEが展開される空間 7―6―1 NC研究の多層性・多元性 7―6―2 NC研究の重層的空間 Ⅱ ハイブリッド・エスノグラフィーの実践 第8章 VAP(Virtual Anthropology Project)ソーシャルメディア利用の日米デジタルネイティブ比較 8―1 VAP(Virtual Anthropology Project)とデジタルネイティブ研究 8―1―1 VAP(Virtual Anthropology Project) 8―1―2 「デジタルネイティブ」論と「デジタルネイティブ」概念の脆弱性 8―1―3 日本社会において「デジタルネイティブ」研究の持つ意味 8―2 HEとしてのVAPリサーチデザイン―――3つの観点 8―3 デジタル現在(digital present)―――観察・アーカイブ・インタビューの融合 8―3―1 デジタル現在(digital present)――HEにおける「民族誌的現在」の革新 8―3―2 VAPにおけるデジタル現在(digital present) 8―4 TML(Translational Multi―Level)デザイン ―――インフォーマント集団をより大きな社会文化集団に定位する方法 8―4―1 アンケート調査との並行・継起デザイン 8―4―2 VAP―Iでの実践 8―4―3 TML(Translational Multi―level)デザイン ――定性調査の弱点克服とウェブ調査のバイアス 8―5 VAP―V(北米調査)―――社会文化間比較に拡張したTMLデザイン 8―5―1 VAP―Vのリサーチデザイン 8―5―2 国際比較、異文化間比較研究 8―5―3 VAP―Vにおける日米ウェブ調査モニター・インフォーマントの偏り 8―6 TMLデザインによる日米比較 8―6―1 インターネット利用全般 8―6―2 ケータイメール・SMS利用の規範意識、気遣い 8―6―3 ブログ・BBS・SNS情報発信・交流・自己開示 8―7 SNS利用と社会的ネットワーク空間の構造 8―7―1 日本社会におけるSNSの普及せめぎ合う3つの「つながり原理」 8―7―2 「世間」の支配力 8―7―3 対人関係空間の構造 8―7―4 SNSの考古学 第9章 ワイヤレス・デバイドユビキタス社会の到来と新たな情報格差 9―0 本章の位置づけ 9―1 データ通信カードと「モバイルデバイド」本章の主題 9―2 デジタルデバイド研究 9―3 データ通信カードの普及 9―4 グループインタビューによる定性的調査 9―5 ウェブアンケートによる定量的調査 9―6 「魚の目」の重要性 第10章 ネット世論の構造 10―0 本研究の問題意識と主題 10―1 日本社会における「ネット世論」の形成回路とYahoo!ニュースの位相 10―1―1 ニュース産出流通回路の変革 10―1―2 「ネット世論」=「拡散」「炎上」の図式を越える必要 10―2 本研究データの概要 10―3 投稿者識別IDクラスタリング 10―4 投稿者ID―IPアドレス、親コメント―子コメントとの関係 10―5 非マイノリティポリティクス「ヤフコメ」に通底する社会心理 10―5―1 PRSに現れるネット世論の関心 10―5―2 投稿者マジョリティに現れるネット世論の関心 10―5―3 非マイノリティポリティクスと道徳基盤理論 10―6 ポスト・リベラルの社会デザイン おわりに 参考文献 索引 装幀 荒川伸生
文化概念の再考を迫る名著、待望の邦訳。著者インタヴューと解説「批判人類学の系譜」(太田好信)を収録。 純粋なものが、狂ってゆく 第1部 言説(民族誌的権威について 民族誌における権力と対話-マルセル・グリオールのイニシエーション ほか) 第2部 転置(民族誌的シュルレアリスムについて 転置の詩学-ヴィクトル・セガレン ほか) 第3部 収集(部族的なものと近代的なものの歴史 芸術と文化の収集について) 第4部 歴史(『オリエンタリズム』について マシュピーにおけるアイデンティティ)
新宿二丁目に生起する人びとの関係を、生活世界として描きだす。セクシュアリティ研究、都市論、歴史学の領域を交差させた先駆的研究 新宿二丁目に生起する人びとの関係を、ていねいで鋭い観察により、生活世界として描きだす。セクシュアリティ研究、都市論、歴史学の領域を交差させたパイオニア的研究! 新宿二丁目に生起する人びとの関係を、ていねいで鋭い観察により、生活世界として描きだす。 セクシュアリティ研究、都市論、歴史学の領域を交差させたパイオニア的研究! はじめに 序章■文化人類学と新宿二丁目と 1●どのように書くか、なぜ書くか 2●フィールドをめぐって 3●ゲイバーとは 4●文化人類学とゲイ研究 5●本書の構成について 【I.新宿二丁目の民族誌】 第1章■変化する二丁目 1●レインボー祭りの開催 2●祭りの分析 3●二丁目とゲイ・コミュニティ 4●組織化としての新宿2丁目振興会 小結●象徴化されつづける二丁目 第2章■盛り場における社会的結合 1●盛り場と都市 2●多層構造と「コモン」 3●利用者が接合される「なじみ」 小結●二丁目にみる盛り場の構造 第3章■ゲイバーの民族誌 1●商売と「相互扶助」のあいだで 2●ゲイバーで働く、ゲイバーに通う 3●ゲイメンズバーにおける社会的結合 小結●共同性と演出性が並存する空間として 【II.新宿の歴史とゲイの歴史】 第4章■新宿の編成 1●新宿の変遷 2●新宿の場所性 3●空間の物理的編成 小結●新宿を動かしてきたもの 第5章■ゲイをめぐる社会状況の変化 1●ゲイをとりまく現状 2●沈黙から顕在化への歴史 3●コミュニティ感の醸成 4●概念枠組みの変化と多面性/多層性 小結●沈黙の歴史からコミュニティ意識へ 【III.セクシュアリティとコミュニティ】 第6章■セクシュアリティ再考 1●新宿二丁目とセクシュアリティ 2●パートナーシップとコミュニティ 3●ゲイメンズバーから考えるセクシュアリティ 小結●新たな視点からのセクシュアリティ論 結章■<コミュニティ化>する新宿二丁目 1●社会的空間としての二丁目 2●ゲイの抵抗的実践 3●「コモンズ」と<コミュニティ化> 4●そして、新宿二丁目のいま あとがき 引用文献/文献レビュー
息を「吹く」しぐさと「吸う」しぐさ 指を「隠す」しぐさ 指を「弾く」しぐさ 股のぞきと狐の窓 「後ろ向き」の想像力 虫の動きを封じるしぐさ 祟りと摂食行為 エンガチョと斜十字 ハナヒからクサメへ クシャミの由来譚 一声と二声の俗信 片道と往復の俗信 「同時に同じ」現象をめぐる感覚と論理 しぐさと呪い
音楽にはヒト、モノ、空間を結びつける力がある。この動態とプロセスを、人類学者や作曲家らが協力して描く、新たな音楽の民族誌。 世界各所で音楽や芸能に向き合ってきた人類学者、音楽教育の実践者や作曲家らが、「音が生み出される場」の豊かな描出を通じて、「音楽の力とは何なのか」という問いに言葉を与えようと模索する、新たな音楽の民族誌。 「音楽」は、一つの楽曲を意味する言葉にとどまらないだろう。 「音楽」には、作品そのものに本来備わる特質・構造・意味/メッセージだけでなく、それがあらゆるアクター(表現者・オーディエンス・空間や環境・音楽プレイヤーや音響機材・人間の身体/心情や音をめぐるコンテクストなど)をつなぎ合わせ、一つの塊のように統合させようとする力があるからだ。 本書では、このようにさまざまなものを編み込んでいく音楽の力(=サウンド・アッサンブラージュ)を包括的に表現し、「音楽」の持つ意味を大きく拡張していく。 世界各所で音楽や芸能に向き合ってきた人類学者、音楽教育の実践者や作曲家らが、「音が生み出される場」の豊かな描出を通じて、「音楽の力とは何か」という問いに言葉を与えようと模索する、新たな音楽の民族誌。 〈序章〉「音楽の力」を取り戻すための試論 小西公大 第1部 つながる(媒介) 〈第一章〉音が編み込む力 —インド・タール沙漠の芸能世界が教えてくれたこと 小西公大 〈第二章〉「見せる場」から「音楽とともにいる場」へ —ウガンダの学校と盛り場で 大門碧 〈第三章〉音を継ぎ合わせる「視線」 —インドの歌舞踊ラーワニーの舞台実践から 飯田玲子 第2部 うみだす(創造) 〈第四章〉醸される島の音の力 —三宅の声と太鼓が生み出すアッサンブラージュ 小林史子 〈第五章〉つながりを手繰り寄せる/選り分ける —社会的存在としてのチベタン・ポップ 山本達也 〈第六章〉調を外れて響き合うトーンチャイム —サウンド・アッサンブラージュの授業風景 石上則子 第3部 つたえる(継承) 〈第七章〉制度と情動をめぐる相剋 —東北タイのモーラム芸能にみる暴力・性・死 平田晶子 〈第八章〉一切をつむぎ、交感するアッサンブラージュの力 —高知におけるガムランプロジェクトの実践を通して 宮内康乃 〈第九章〉媒介、愛着、継承 —ソロモン諸島アレアレにおける在来楽器アウをめぐって 佐本英規 〈補論〉 仮想空間で音楽になること 小西公大 おわりに
アイヌの養母に育てられた開拓農民の子が大切に覚えてきた、言葉、暮らし。明治末から昭和の時代をアイヌの人々と生き抜いてきた軌跡。解説 本田優子 アイヌの養母に育てられた開拓農民の子が大切に覚えてきた、言葉、暮らし。明治末から昭和の時代をアイヌの人々と生き抜いてきた軌跡。解説 本田優子 == 「トキさん」は1906年、十勝の入植者の子どもとして生まれ、口減らしのため、生後すぐにアイヌの家族へ養女として引き取られた。和人として生まれたが、アイヌの娘として育った彼女が、大切に覚えてきたアイヌの言葉、暮らし。明治末から大正・昭和の戦前戦後を、鋭い感覚と強い自立心でアイヌの人々と共に生き抜いてきた女性の人生を描く優れた聞き書き。 == 開拓農家に生まれ、アイヌの養母 に育てられ、暮らしと結びついた アイヌの言葉の記憶を大切に、 激動の時代を生きた女性の人生。
世界を変えるための「最古の科学」が「儀式」だった! 火渡りの祭礼から卒業式まで、儀式の秘密と活用のヒントを探究する空前の書。 世界を変えるための「最古の科学」が「儀式」だった――。 生活や価値観が猛スピードで変化する現代。昔からある「儀式」は単調で、退屈で、無意味にみえる。でも、ほんとうに? 認知人類学者の著者は熱した炭の上を歩く人々の心拍数を測り、インドの祭りでホルモンの増減を測定。フィールドに実験室を持ち込んで、これまで検証されてこなかった謎めいた儀式の深層を、認知科学の手法で徹底的に調査する。ハレとケの場、両方にあふれる「儀式」の秘密と活用のヒントを探究する空前の書。 ジョセフ・ヘンリック(人類学者、ハーバード大教授) 「ギリシャの火渡りからアマゾンの恐ろしい祭礼まで、認知人類学者の著者は、リズム、ダンス、音楽、苦痛、犠牲などから成る、一見すると無意味で反復的で因果関係が不明瞭な〈儀式〉を、人類がどのように、なぜ行うのかを探求する。民族学的なデティール、個人のナラティヴ、認知科学の成果が盛り込まれた本書は、QOLや健康状態の改善、地域社会の構築のために、古代からの知恵であり最新の科学でもある〈儀式〉をどのように活用できるかを教えてくれる」 第1章 儀式のパラドックス 第2章 儀式と種 第3章 秩序 第4章 接着剤 第5章 沸騰 第6章 強力接着剤 第7章 犠牲 第8章 幸福 第9章 儀式の力の活用
何気なく「そういうものだ」と思っている習俗習慣は、先祖たちの暮らしの蓄積が生んだものだった。われわれの深層心理から、日本の歴史を読みとく。 何気なく「そういうものだ」と思っている習俗習慣は、先祖たちの暮らしの蓄積が生んだものだった。われわれの深層心理から、日本の歴史を読みとく。 === ふとした時に表れる日本人独特の感覚。自分の湯呑みを他人に使われてしまった時の気まずさなどはその一例といえるだろう。高取によればこの感覚は、自己の範囲を所有するモノや所属する集団にまで広げて認識していた近代以前の名残だという。また祖先としての神、他所から来る神という二種の神観念があるのも、定住だけでなく漂泊もまた少なくなかった前近代の暮らしに由来するという。本書はそうしたわれわれの感覚や習慣を形作ってきたさまざまな事例を挙げ、近代的な自我と無意識下の前近代が交錯する日本人の精神構造を明らかにする。民俗学の傑作にして恰好の入門書。 解説 阿満利麿 ===
Among histories Indigenous articulations Varieties of indigenous experience Ishi's story Hau'ofa's hope Looking several ways Second life : the return of the masks Epilogue
優しい狐と幻の椿 浮き上がる人 魂との遭遇 森へ消えた飛行兵 ミミズ素麵と小さな人 峠に立つ男 死のサイン 入りたかった温泉 見つけてください-栗駒山 不吉な笑い声 何が光を見せるのか? 山で出会うモノ 子狐 穴から出てくる人 ワープする爺 消えないテレビ 騒ぐ木々 白神山地近辺 謎の血痕 消えた馬頭観音 寂しがりやの魂 火の玉を探す人たち 本州最北端の魂 甘党の狐 狐の警告 撃ってはいけない熊 丑三つの少女 ついてきた男 案内する火の玉 跳び出す婆 "羆撃ち"久保俊治さんの体験 座敷わらしと山の神 追いつけない鈴音 片品村の出来事 引き寄せられるバイク 案内される人 唐辛子を持っていく訳 見つけてください-上野村 切ってはいけない木と山中の太鼓 狐狸の宴 おにぎり婆 月はどっちに出ている バスに乗りたかったのは 首括りの木 山音 狐火いろいろ 五十年目の神隠し 謎のスキーヤー 一緒に来たのは ささやく男 叫ぶ女 赤い部屋 夜の訪問者 大蛇の森 野焼きと火の玉 動かすと死ぬ 尼さんの忠告 一向一揆の里 火の玉ラッシュアワー ツチノコの里 追いかけてくるモノ 犬と百人一首 不思議な相談 山から出られない人 行者の戦い ノックは三回 消えるテレビマン 奥山の女性 最後の昼飯 神域の巨樹 帰りたかったのは 狸話 魂虫 家に帰れない訳
感染症と闘い、時には共存していくために生み出された「疱瘡絵」や「はしか絵」などの「疫病芸術」を時代別・テーマ別に紹介。 疱瘡やはしかなど、様々な感染症に見舞われてきた日本。 病原体の存在が知られていなかった時代には、感染症はもののけや怨霊、悪鬼など、目に見えない存在によってもたらされるもと信じられていた。 そんな中で人々は、神仏や有名な武将、予言獣などのイメージに病除けの願いを託し、上手な対処法を探ってきた。 社寺が授ける護符から「疱瘡絵」や「はしか絵」、郷土玩具など民間信仰による素朴なお守りなど……。 病と闘い、時に共存していくために生み出されたそうした表現を著者は“疫病芸術”と呼び、「私たちの生活をある側面では豊かにもしてきたのではなかったろうか」と語る。 そんな“疫病芸術”50点以上を、時代・テーマ別にカラー図版満載のビジュアルで 一挙に紹介。 日本人がこれまでどのように感染症を受けとめてきたかの軌跡を知ることで、新型コロナ禍の今を生きる参考にしてもらう。 【目 次】 はじめに 1章 疫神の誕生 コラム・祇園信仰と蘇民将来 2章 近世のまじない絵 コラム・疫病除けの郷土玩具 3章 予言する妖怪たち コラム・疫病鎮めの祭と社 4章 明治の流行病 参考文献 はじめに 1章 疫神の誕生 コラム・祇園信仰と蘇民将来 2章 近世のまじない絵 コラム・疫病除けの郷土玩具 3章 予言する妖怪たち コラム・疫病鎮めの祭と社 4章 明治の流行病 参考文献
異文化接触に伴う緊張のなかでも、衝突をかわし、差別を避けながら、ともに生きていく人類の知恵とは。狩猟、婚姻、紛争などの人類学の基本的なテーマを、日本で編まれた民族誌を基礎に丁寧に解説。 序論:民族と世界 はじめに 1.文化人類学の歴史 2.文化とは 3.世界の変容、文化人類学の変貌 第1章 バリ島民:伝統舞踊と社会変化 はじめに 1.バリ島の概況 2.歴史 3.バリ・ヒンドゥー文化 (1)インドとバリのヒンドゥー文化(2)民俗方位(3)悪魔払いの儀礼(4)稲の精霊信仰 4.観光人類学 おわりに 第2章 ナバホ族:ネイティブ・アメリカンの歴史と宗教 はじめに 1.ネイティブ・アメリカンの移住と分布 2.ナバホ族の歴史 3.ナバホ族の世界観 4.伝統医療とアルコール依存症 おわりに 第3章 アラスカ・エスキモーの社会 はじめに 1.エスキモーの地域文化 2.環境の対比と双分社会 (1)夏の居住形態(2)冬の居住形態 3.社会 (1)家族(2)霊魂観 4.捕鯨エスキモーの事例 おわりに 第4章 アフリカ・ナイル上流のヌエル族:牧畜・血族・内戦 はじめに 2.ヌエル族の概況 (1)エヴァンズ=プリチャード(2)ヌエル・ランド 3.ヌエル族の社会 (1)政治体系(2)リネージの分節 4.婚姻 (1)年齢組と成人男性(2)インセスト・タブーと花嫁代償(3)生物学的父≠法的父の婚姻形態 5.スーダン内戦 おわりに 第5章 中央アフリカ:ピグミーの狩猟 はじめに 1.アフリカの概況 (1)自然(2)アフリカの狩猟民 2.ピグミーの歴史 (1)民族名称(2)歴史 3.ピグミーの社会 (1)バンド(2)社会組織(3)宗教と病気 4.狩猟 (1)伝統狩猟(2)ネット・ハンティング(3)農耕民との共生 5.独立後の混乱と内乱による環境破壊 おわりに 第6章 イスラム世界:モロッコ・フェズの社会生活と聖信仰 はじめに 1.民衆イスラム 2.イスラム教の教義 (1)コーランの教え(2)本質(3)信仰 3.聖者信仰 (1)聖者(2)聖者の霊力(3)現世利益と「取りなし」理論 4.モロッコの古代都市フェズ (1)モロッコの概況(2)フェズの概況(3)家庭生活 5.聖者祭り (1)ムーセム(Musem)(2)日程(3)場所·祭祀空間(4)祭りの参加者(5)部族対立の調停 6.「聖者」の役割 おわりに 第7章 トロブリアンド諸島の母系社会とクラ交易 はじめに 1.マリノフスキー 2.メラネシアの概況 3.クラ交易 (1)クラ交易の概説(2)クラ交易の社会的機能(3)クラ研究の展開 4.社会と母系制 (1)性肯定社会(2)結婚の意義(3)母系制(4)タブー(5)性と夢 おわりに おわりに
「文化人類学」に関するよくある質問
Q. 「文化人類学」の本を選ぶポイントは?
A. 「文化人類学」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「文化人類学」本は?
A. 当サイトのランキングでは『自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門(未来のわたしにタネをまこう7)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで126冊の中から厳選しています。
Q. 「文化人類学」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「文化人類学」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。








![『文化人類学 [カレッジ版] 第4版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41bSQKMHGfL._SL500_.jpg)
![『よくわかる文化人類学[第2版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41CxcuifolL._SL500_.jpg)









![『よくわかる文化人類学[第3版] (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/31cRI8Tm1HL._SL500_.jpg)