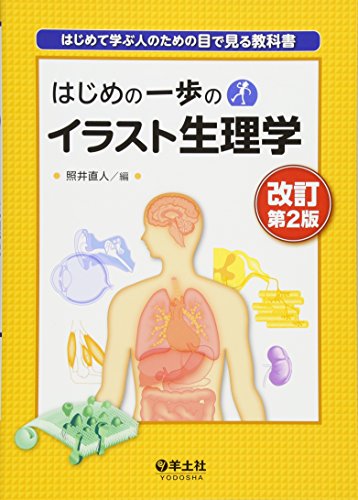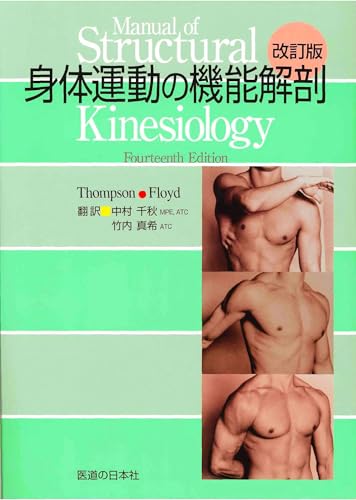【2026年】「生理学」のおすすめ 本 145選!人気ランキング
- のほほん解剖生理学
- 標準生理学 第9版 (Standard Textbook)
- ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説
- ガイトン生理学 原著第13版
- コスタンゾ明解生理学 原著第6版 電子書籍付(日本語・英語)
- 解剖生理学 超速! ゴロ勉
- イラスト解剖学 第10版
- 乳酸サイエンス: エネルギー代謝と運動生理学 (体育・スポーツ・健康科学テキストブックシリーズ)
- なんでやねん! 根拠がわかる解剖学・生理学 要点50
- イラストでまなぶ生理学[Web講義動画付] 第4版
この書籍は、200点以上の精密なイラストと豊富な解説を通じて人体の構造を詳しく理解できる内容です。目次は、総論、頭部・頚部、胸部、腹部・背部、上肢・下肢の5章から構成されています。著者は、坂井建雄(順天堂大学教授)と橋本尚詞(東京慈恵会医科大学教授)で、両者とも解剖学や細胞生物学に関する豊富な研究背景を持っています。
ガイトン生理学テキストの第13版が8年ぶりに改訂され、日本語・英語版の電子書籍が付属しています。この版は生物学や生理学の基本から始まり、神経系、心臓、循環、呼吸、消化器系、内分泌学、スポーツ生理学など多岐にわたる内容を網羅しています。
本書は、解剖生理学を学ぶ医療従事者向けに、人気のゴロ合わせをまとめた書籍です。SNSでの支持を受け、イラストやミニドリルを用いて効率的に知識を習得できる内容になっています。特典として、声優によるゴロ音声も付いており、通勤中などに耳から学ぶことができます。
この書籍は、医療職を目指す学生向けに解剖学・生理学を効率的に学ぶ方法を提案しています。著者は、用語の丸暗記を避け、関連性を理解することが重要だと強調し、関西弁の先生がそのコツを教えます。内容は、解剖生理学の基本から各器官系に関する知識を網羅しています。著者は、医療分野での豊富な経験を持つ専門家です。
看護学生・看護職のみならず、その他の医療系学生にも評判の高い生理学の入門書。たくさんのイラストを掲載しているため、気軽に楽しくまなべる。また、本文は重要度を3段階で示し、キーワードを色文字にして強調していることで学習の手助けとなる。第4版では押さえておきたい重要なポイントを著者みずからが解説した動画を収載。生理学の基本的事項を網羅的かつわかりやすく解説した、必携の1冊!
プロメテウス解剖学アトラスが改訂され、解剖学総論と運動器系の内容がさらにわかりやすくなりました。美しいイラストと的確な解説文を維持しつつ、図版の配置や文の推敲が行われ、医療職全般から支持されています。進化を続ける最高峰の解剖学アトラスです。
この書籍は、骨格筋に関する知識を体系的にまとめたもので、第二版では新しい知見を盛り込み全面改訂されています。内容は、骨格筋の構造や機能、神経系による運動調節、エネルギー代謝、ホルモン分泌、筋の肥大と萎縮、運動と心肺機能、認知機能、生活習慣病との関連など多岐にわたります。著者は、筑波大学の名誉教授である勝田茂氏と、筑波大学の教授である征矢英昭氏です。
本書は、ヨガのポーズが上手くいかない理由や身体の痛みの原因を解剖学的視点から解説します。「太陽礼拝」を中心に、全てのアーサナに共通する身体の使い方や怪我を防ぐための基礎知識を提供しています。著者は理学療法士であり、ヨガインストラクターとしての経験を活かして、安全で効果的なアーサナの指導を行っています。
本書は、ヨガのポーズを取る際の身体の解剖学的な理解を深めるためのガイドです。骨、関節、筋肉の基本的な構造を解説し、ポーズを図解しています。また、図解を塗り絵として楽しむことで、各部の位置や機能を覚えやすくなります。ヨガを学ぶ人々にとって、人体の仕組みを理解する手助けとなる一冊です。さらに、巻末には携帯用カードも収録されています。
この書籍は、臓器別に編集された全10巻の内容を一冊にまとめた改訂版で、解剖学と生理学をわかりやすく学べる教科書です。シリーズは累計23万部を超え、最新の知見を反映しつつ、図解を中心にしたビジュアルな構成で、重要事項をコンパクトにまとめています。読者にはスマートフォンやタブレットで閲覧できる電子書籍も提供され、各臓器の構造と機能の関連を順を追って学べるようになっています。
この書籍は、運動生理学の基礎から応用までを網羅した日本語版の教科書で、健康や競技力向上に役立つ知識を提供しています。豊富なカラー図やコラムを通じて、運動生理学の重要性を学ぶことができ、関連する分野の知識も深められます。著者は運動生理学の専門家で、教育者としても高い評価を受けています。この教科書は、運動やスポーツに関わる教員、学生、医療従事者、トレーナーにとっての必携書です。
この書籍は、子ども向けの140cmの人体ポスターで、頭蓋骨や肋骨などをめくって見ることができる仕掛けが多数あります。壁にかけて常に観察でき、20ページの詳細な解説が付いており、人体の仕組みをリアルに学べます。目次には細胞、心臓、呼吸、消化、免疫などのテーマが含まれています。著者は順天堂大学の坂井建雄教授で、解剖学の専門家です。
この教科書は、生理学と解剖学を統合的に学ぶための効率的な教材で、要点整理と明確な図表を用いて長期記憶を促進します。国試練習問題で目標が明確になり、医療職に役立つ情報が凝縮されています。内容は人体の基本的な構造と機能から始まり、各器官系(心臓、循環系、呼吸器系など)の詳細、さらに環境生理学や皮膚、口腔の構造と機能まで幅広くカバーしています。
この文章は、神経や生理学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には神経系、内分泌、消化、循環などの生理学的なテーマが含まれています。著者の二宮治明は鳥取大学の教授で、神経内科の臨床経験を持ち、ニーマン・ピック病C型の研究を行っています。
医療系学生向けの生理学教科書が5年ぶりに大改訂され、人体機能全般を体系的に扱っています。特に「感覚系」と「腎機能」の章が整理・再構成され、最新の知見や新図を盛り込むことで「わかりやすさ」が向上しました。主要な内容には細胞、神経系、運動系、内分泌、消化などが含まれています。著者は順天堂大学名誉教授の大地陸男です。
この書籍は、筋肉や体の仕組みをわかりやすく学ぶことで、理想の体を手に入れる方法を紹介しています。内容は、体の基本的な構造や筋肉のイラスト図鑑、不調をケアするためのボディメンテナンスに分かれており、著者は理学療法士の有川譲二氏です。彼は解剖学を楽しく身近に学べるように、体験を通じた教育を提供しています。
この教材は、165項目の講義動画を用いて解剖学と生理学を学ぶためのもので、7日間にわたって計画的に学習できる構成になっています。内容は循環器、呼吸器、中枢・末梢神経系、運動器、消化器、泌尿器・生殖器、感覚器と多岐にわたり、医療系国家試験の基礎固めにも適しています。著者は町田志樹氏で、解剖学教育の専門家です。
この文章は、スポーツに関連するさまざまな生理学的要素を解説する内容を紹介しています。具体的には、骨格筋・神経、エネルギー供給、呼吸、循環、代謝、内分泌、脳機能、遺伝子、栄養、体組成、発育発達、体温調節、コンディショニング、高所・低酸素トレーニング、身体不活動など、スポーツにおける多角的な視点を取り上げています。著者は冨樫健二で、運動生理学やスポーツ医学を専門とする三重大学の教授です。
本書は、ストレングス&コンディショニングに関する最新の科学的知見を基に、トレーニング、リカバリー、身体情報の活用について解説しています。筋力、スピード、持久力の科学的基礎とトレーニングメソッドを紹介し、リカバリー方法や最適な戦略についても触れています。トレーニングコーチやパーソナルトレーナーにとって必読の内容です。
この書籍は、現代人の不眠やストレス、疲労、うつ病の原因を解決するための健康法を提唱しています。著者の有田博士は、幸せホルモンであるセロトニンが太陽光によって生成されることを強調し、現代人がセロトニン不足に陥っている理由を説明します。太陽光との関係を古代から考察し、セロトニンの重要性とその活用法を紹介しています。目次には、自然と生命の営み、セロトニン神経の機能、オキシトシンとメラトニンの役割などが含まれています。
「コアアトラス」の最新版は、臨床情報をまとめた臨床BOXの拡充やレイアウトの改善を行い、さらなる読みやすさを追求した意欲的な改訂版です。定番の解剖学アトラスとして、今後も選ばれる一冊です。
著者池谷裕二の新著は、最先端の脳科学に基づき「心」の生成メカニズムを探求する連続講義の内容をまとめたものです。私たちの心に対する理解が最新の研究によって変わっていく様子を描き、著者自身が特に愛着を持つ作品としています。各章では、脳の理解、心の視点、自由の創造、ノイズからの生命生成などがテーマとなっています。
最新のランニング・トレーニング本が登場し、体力向上やレースでの結果を目指すプログラムを提供しています。800mからマラソン、トライアスロンまで幅広い種目に対応し、効率的なトレーニングを提唱。VDOTによるペース設定や新たな練習メニューも追加され、応用しやすい内容に改訂されています。著者は長年の経験を持つジャック・ダニエルズで、彼の指導のもと多くの選手が成功を収めています。
動き回ることのできない植物。どのようにして地球上で繁栄してきたのか。植物の体の中で起こっている「生きる仕組み」を解説する。 動物のように動き回ることのできない植物。しかし、地球上に多種多様な植物が繁栄していることからわかるように、彼らは環境の変化にうまく対応し、進化してきたのです。植物たちは、まわりの環境をどのように感じとり、どのようなメカニズムをもって生きているのでしょうか。本書は、意外と知らない光合成や、生長や代謝にかかせない植物ホルモンのはたらきなど、植物の体の中で起こっている「生きる仕組み」を紹介します。
この書籍は、セロトニン、オキシトシン、メラトニンの3つの脳内物質を増やすことで「疲れない脳」を作る方法を紹介しています。著者は脳生理学者の有田秀穂で、朝5分の日光浴から始める手軽な実践法を提案。脳疲労の原因やストレスへの対処法、快眠の重要性、さらにはカラオケやダンスなどの活動が脳に良い影響を与えることを解説しています。最終的には「前頭前野」の活性化が人生を好転させるとしています。
『ネッター解剖学アトラス』第7版は、イラストの美しさと解剖学的正確さで定評があり、学生や医師の意見を反映して内容をアップデートしました。新たに図表や体表解剖・血管神経系を俯瞰する章を追加し、各章末には臨床に役立つ知識をまとめています。また、電子版が付属し、より学習しやすい内容となっています。
本書は、脳研究の第一人者・池谷裕二氏が、最新の研究成果を基に脳と心の関係について探求する内容です。心や意識の起源、臨死体験、脳の病気、さらには脳の若返りに関する研究など、多様なテーマを扱っています。視覚的に理解しやすい画像や3Dイラストも豊富で、脳の新しい理解を提供します。著者は東京大学の教授で、脳の可塑性を研究しています。
この書籍は、シンプルな文章と自由なイラストを用いて解剖生理を学ぶための最適な教材です。初学者から国家試験、臨床まで幅広く対応しており、水・電解質の調節についての理解を深めることができます。目次には腎臓の解剖や機能、検査、関連疾患についての章が含まれています。
アーサー・リディアードによるマラソンのトレーニング理論「リディアード・トレーニング法」は、年齢やレベルを問わず効果を発揮します。著者はリディアードに25年間師事し、トレーニングの基本や具体的な手順を解説。内容は生理学に基づき、初心者からトップアスリートまでが実践できる方法を提供しています。全体は概要、具体的手順、補足とまとめに分かれており、長期的な発達やトレーニングの重要性についても触れています。
本書は、現役ナースが解剖生理学を1000点以上のイラストを用いてわかりやすく解説した入門書です。解剖学の基本から臨床で役立つ知識まで幅広く網羅しており、楽しく学べる内容になっています。看護学生や医療従事者におすすめで、基礎医学を学ぶ際に役立つ情報や豆知識も豊富に含まれています。著者は看護師でイラストレーターの角野ふち、監修には医学部教授や助教が関わっています。
この書籍は、機能解剖学の専門家が運動時の人体の使い方を解説したもので、アスリートやトレーナーに必須の内容を提供しています。続編となる本書では、筋肉の特性、キネティックチェーン、体幹や上肢の動き、ストレッチングやテーピングについて詳しく説明しています。著者は筑波大学の准教授で、最新のスポーツ科学の知見を取り入れています。
この書籍は、骨格筋に焦点を当て、筋肉名、起始・停止、支配神経、主な働きを解説し、オールCGによる筋肉図を掲載しています。筋名は和名と英語名で表記され、さまざまな角度からの図が含まれています。内容は、上肢から頭部までの各部位の筋肉を扱い、巻末には略語集や和英・英和INDEXも付いています。著者は筋生理学の専門家で、教育や解剖学の講義に従事しています。
本書は、脳と人工知能(AI)の融合がもたらす未来の可能性について探求しています。著者は、脳に知識をダウンロードしたり、思考を直接伝えたり、AIによる健康管理が可能になるなど、科学者たちが真剣に研究している近未来のシナリオを提示しています。松尾豊氏が絶賛するこの本は、科学技術の進展に対する私たちの考え方や備えについても問いかけており、未来の社会を考える人々にとって必読の一冊です。
この書籍は、解剖生理を楽しく学べる内容で、レクチャー形式の文章と豊富なイラストが特徴です。章末には国試対策があり、主要疾患もわかりやすく解説されています。初学者から臨床実践者まで幅広く対応しており、消化管に関する詳細な情報が提供されています。
この文章は、運動生理学に関する書籍の目次を示しており、基礎編では運動生理学の基本知識(筋、換気、ガス交換、循環など)を扱い、臨床編では疾病の病態や運動制限の原因、運動が健康に及ぼす影響について説明しています。
この文章は、スポーツ・バイオメカニクスに関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、スポーツ・バイオメカニクスの定義、バイオメカニクスの基礎(筋肉の役割、エネルギー供給、運動の調整機構、体の構造と運動、力学の法則)と実際の運動(立つ、歩く、走る、高く跳ぶ、遠くへ跳ぶなど)に分かれています。著者は金子公宥と藤原敏行で、それぞれの経歴が簡潔に述べられています。
Unit I: Introduction to physiology: the cell and general physiology -- Unit II: Membrane physiology, nerve, and muscle -- Unit III: The heart -- Unit IV: The circulation -- Unit V: The body fluids and kidneys -- Unit VI: Blood cells, immunity, and blood coagulation -- Unit VII: Respiration -- Unit VIII: Aviation, space, and deep-sea diving physiology -- Unit IX: The nervous system: A. General principles and sensory physiology -- Unit X: The nervous system: B. The special senses -- Unit XI: The nervous system: C. Motor and integrative neurophysiology -- Unit XII: Gastrointestinal physiology -- Unit XIII: Metabolism and temperature regulation -- Unit XIV: Endocrinology and reproduction -- Unit XV: Sports physiology
NHKスペシャル『立花隆 臨死体験』出演の天才脳科学者、初の翻訳! 脳は意識を生み出すが、コンピューターは意識を生み出さない。では両者の違いはどこにあるのか。クリストフ・コッホが「意識に関して唯一、真に有望な基礎理論」と評した、意識の謎を解明するトノーニの「統合情報理論」を紹介。わくわくするようなエピソード満載でわかりやすく語られる脳科学の最先端、待望の翻訳! 【本書が挑む脳科学最前線の驚異の事例】 ・脳幹に傷を負い植物状態に見えるロックトイン症候群患者(映画「潜水服は蝶の夢を見るか」の主人公)。彼らの意識の有無はどう診断すればいいのか? ・麻酔薬を投与するとなぜ意識が失われるのか? 麻酔時に意識が醒めてしまうとどうなるのか(1000人に1人はそうなる) ・右脳と左脳をつなぐ脳梁を切断する(スプリットブレイン。てんかん治療で行われることがある)と、1つの脳のなかに意識が2つ生まれる!?
「標準生理学」改訂第10版は、40年の支持を受けて、読みやすさと使いやすさを向上させた生理学教科書です。誌面デザインをリニューアルし、構成マップをビジュアル化。製本方法も改善され、学習しやすくなりました。内容は読者モニターの意見を反映し、基礎的な解説を充実させつつ、生理学研究の魅力を紹介。医師国家試験対策や日常学習をサポートし、巻末には臨床問題に関する付録もあります。生涯学習のパートナーとして最適な一冊です。
この書籍は、疲労の定義や測定方法、スポーツや運動中の疲労の原因(エネルギーの枯渇や脱水など)、疲労に影響を与える要因、そして今後の研究の方向性についてまとめています。著者は運動生理学の専門家であり、運動パフォーマンスやメンタルヘルスに関する研究を行っています。
この文章は、テーパリングに関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、テーパリングの定義やメカニズム、実践的なガイドラインが示されています。著者の河森直紀は、スポーツ科学の専門家であり、国際的な大会に向けたトレーニング指導の経験を持つフリーランスのS&Cコーチです。
本書は、解剖学の複雑さを解消するために、教育の第一人者が整理した新しい教科書です。明快な本文、美しいイラスト、豊富なコラムを通じて、解剖学の知識をわかりやすく楽しく学べるように工夫されています。
この書籍は、レクチャー形式の文章と楽しいイラストを用いて解剖生理をわかりやすく解説しています。各章の末尾には国試対策問題があり、臨床の理解を深めることができます。また、主要疾患についても簡潔に説明されています。
本書は、意識の謎に迫る研究者たちの最新のレポートをまとめたもので、脳の物質的な反応から意識がどのように生まれるのかを探求しています。クオリアやニューロンの知見を基に、実験成果を通じて人間の意識の理解を深め、人工意識の可能性についても考察します。著者は脳科学の専門家であり、意識研究の最前線を描き出しています。
本書は、持久系スポーツにおける耐久力の限界について探求し、心と体のどちらがその決定要因であるかを考察します。著者アレックス・ハッチンソンは、著名なアスリートたちの物語を交え、科学的知見を基に人間の耐久力や痛み、筋肉、エネルギーなどの要素を解明します。また、エリウド・キプチョゲのマラソンサブ2挑戦に関する裏話も紹介されており、すべての持久系アスリートに向けた耐久力向上のヒントが詰まっています。限界は幻想であり、柔軟であることが強調されています。
本書は、ストレングスコーチMark Rippetoeの著書の日本語版で、バーベルを用いた5種のストレングストレーニング(スクワット、プレス、デッドリフト、ベンチプレス、パワークリーン)の効果的な方法を解説しています。初心者から経験者まで役立つ内容で、トレーニングの原点に戻ることができ、シンプルなプログラミングも提案されています。また、補助種目やアクセサリーエクササイズについての情報も含まれています。
この文章は、脳の構造や機能、記憶、学習、意識、倫理に関する内容を扱った書籍の目次を紹介しています。手法編では脳の観察方法、記憶・学習編では海馬の役割、意識編では情動や無意識の意思決定、倫理編では社会的価値について触れています。また、著者の高橋宏知は神経工学と聴覚生理学の専門家で、東京大学で講師を務めています。
この書籍は、解剖学や生理学、主要な疾患について、レクチャー形式の文章と視覚的に楽しめるイラストで分かりやすく解説しています。医療従事者や初学者向けで、血算や骨髄検査、白血病や輸血についても学べる内容です。
本書は、韓国の漫画家ソク・ジョンヒョンが9年かけて執筆した美術解剖学の集大成で、人体の自然な動きを描くための技法が紹介されています。内容は生物の形、身体の基礎、頭部、胴体、腕と手、脚と足、全身に分かれており、解剖学的な視点から人の動きを丁寧に解説しています。また、1コマ漫画を交えた楽しい読み進め方が工夫されています。著者は多彩な経歴を持ち、国内外で人体描写の特別講義を行っています。
この書籍は、神経科学者フリストンが提唱した「能動的推論」と「自由エネルギー原理」に基づき、脳の知覚、認知、運動、思考、意識などの機能を統一的に説明する理論を解説した初の入門書です。内容は、脳の推論機能や注意、運動制御、意思決定、感情、好奇心、精神障害との関連、認知発達など多岐にわたります。著者は認知神経科学と計算論的神経科学の専門家です。
この書籍は、脳科学をエンジニアリングの視点から探求する内容で、以下の5つの編から構成されています。第1編では脳の構造と機能を紹介し、第2編では神経細胞の特性と情報処理メカニズムを解説。第3編では運動の制御機構について、第4編では知覚の形成と脳の学習メカニズムを探ります。最後に第5編では脳と芸術の関係を考察し、好みや芸術の法則性について論じています。著者は東京大学の高橋宏知で、神経工学と聴覚生理学の専門家です。
この書籍は、脳に知能が生じる理由を探求し、大脳新皮質の「皮質コラム」に着目した「1000の脳」理論を解説しています。著者ジェフ・ホーキンスは、脳と人工知能の理解に革命をもたらす新しい視点を提供し、ビジネスや研究における知的挑戦を描いています。内容は脳の新しい理解、機械の知能、人間の知能に関する考察を含みます。ホーキンスは神経科学者であり、AI研究の先駆者として知られています。
本書は、筋力トレーニングに必要な部位や筋肉を目的に応じて強化するための情報を提供するもので、正確なカラーイラストで示されています。スポーツコーチや体育教師、筋力トレーニングを目指す全ての人にとって役立つ内容です。目次には上腕、肩部、胸部、背部、脚部、臀部、腹部が含まれています。著者は筋肉やスポーツ医学に関する専門知識を持つプロフェッショナルです。
『雑食動物のジレンマ』『人間は料理する』で知られるジャーナリストが 自ら幻覚剤を体験し、タブーに挑む! 今どんな幻覚剤の研究がおこなわれているのか。 幻覚剤は脳にどんな影響を与えるのか。 そして、医療や人類の精神に、幻覚剤はいかに寄与しうるのか。 「不安障害」「依存症」「うつ病」「末期ガン」などへの医学的利用の可能性と、“変性する意識”の内的過程を探る画期的ノンフィクション。 ニューヨークタイムズ紙「今年の10冊」選出(2018年)、ガーディアン紙、絶賛! 一部の精神科医や心理学者が過去の幻覚剤研究の存在に気づき、発掘を始めたのは最近のことだ。 彼らは現代の基準で再実験をおこなって、その精神疾患治療薬としての可能性に驚愕し、(中略)幻覚剤が脳にどう働くのか調べはじめた。 ——幻覚剤ルネッサンスである。(宮﨑真紀) 第一章 ルネッサンス 第二章 博物学——キノコに酔う 第三章 歴史——幻覚剤研究の第一波 第四章 旅行記——地下に潜ってみる 第五章 神経科学——幻覚剤の影響下にある脳 第六章 トリップ治療——幻覚剤を使ったセラピー
この書籍は、トレーニングと健康に関する最新のサイエンスを解説し、身体を変え、パフォーマンスを向上させ、人生を楽しむ方法を提供します。内容は筋肉の性質や運動の仕組み、トレーニング方法について理論と実践に分かれて詳しく説明されています。著者は東京大学の教授で、運動生理学やトレーニング科学の専門家です。
この書籍は、アルツハイマー病研究の現状を批判的に見直し、特にアミロイドに偏った治療アプローチが無駄な時間を費やしてきたことを指摘します。著者は、アカデミズム、製薬業界、政府の関与による研究の迷走を明らかにし、過去数十年の認識を根本から問い直す重要な告発を行っています。内容は、アルツハイマー病の歴史、治療法の探求、研究モデルの問題点、今後の研究戦略の多様化に焦点を当てています。
本書は、人の身体を自動車に例え、筋肉をエンジンとし、パワーと効率を中心テーマとして扱っています。パワーはエンジンの馬力、効率は燃費に相当し、身体の機能を理解するためにはこれらを無視できません。内容は、人体エンジンの構造、筋肉の特性、パワーの発育とトレーニング、効率の定義と評価法などが含まれ、身体活動や能力の理解に役立つことを目指しています。
この書籍は、神経科学者デイヴィッド・イーグルマンが、視覚や聴覚、身体の一部を失った際に脳内で何が起こるのかを探求し、脳の可塑性を活かして新たな感覚を創出する可能性について論じています。著者は脳を常に自己改造する装置と捉え、科学技術を用いて感覚の代行や新しい感覚の発展について考察します。
本書では、一般的に信じられている通説(例:健診で健康になる、テレビが学力を下げる、偏差値の高い大学が収入を上げる)が経済学の研究によって否定される理由を解説しています。著者は「因果推論」の手法を用い、数式なしでわかりやすく説明することで、根拠のない通説にだまされない力を養うことを目指しています。各章では、様々な因果関係を証明する方法(ランダム化比較試験、自然実験、差の差分析など)を紹介しています。
スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるための食事摂取法とは? 運動と食事をどのように組み合わせれば,健康の維持増進につながるのか? 本書はその基礎となる理論を紹介しながら,細胞・分子レベルで解説.「なるほど」と納得できる役立つ内容が満載. はじめに 序 章 スポーツ栄養学とは? 第1章 身体組成と体脂肪・脂肪細胞の種類 第2章 エネルギー消費量と摂取量 第3章 糖質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その1) 第4章 たんぱく質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その2) 第5章 脂質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その3) 第6章 運動中の水分摂取法とスポーツドリンクの効果 第7章 パフォーマンス・健康とサプリメント