【2025年】「ガンジー」のおすすめ 本 52選!人気ランキング
- ガンディー 平和を紡ぐ人 (岩波新書)
- ガンジーの実像 (文庫クセジュ 858)
- ガンジ-自伝 (中公文庫 B 1-43 BIBLIO20世紀)
- スクワットの深さは人間性の深さ 戦略思考とやり抜く力を鍛える最強のトレーニング
- ガンジ- (世界の伝記 コミック版 15)
- 韓国発 刺しゅう図案集 レトロかわいい刺しゅう
- 鷗外・ドイツ青春日記
- ガンディー 強く生きる言葉
- ガンジー: インドを独立にみちびき、非暴力によってせかいを変えた人 (伝記世界を変えた人々 9)
- ガンジーセーター 編み方とパターン 詳細解説
本書は、インド独立運動の精神的指導者マハトマ・ガンジーの生涯を描いた自伝的著作の英語版全訳である。ガンジーは真実と非暴力を信奉し、インド古来の思想を再生させた。彼の著作には『自叙伝』と『南アフリカにおける非服従運動』があり、これらが再編集されて一冊にまとめられた。ガンジーは南アフリカでの差別に抗議し、帰国後は民族解放運動を指導し、1948年に暗殺された。著者の蝋山芳郎は、インド特派員としてガンジーの時代を生きたジャーナリストである。
本書は、ストレングスコーチMark Rippetoeの著書の日本語版で、バーベルを用いた5種のストレングストレーニング(スクワット、プレス、デッドリフト、ベンチプレス、パワークリーン)の効果的な方法を解説しています。初心者から経験者まで役立つ内容で、トレーニングの原点に戻ることができ、シンプルなプログラミングも提案されています。また、補助種目やアクセサリーエクササイズについての情報も含まれています。
本書は、象の頭を持つガネーシャや青い女神カーリーなどの神々を紹介し、インドの宗教の発展や主要な経典、詩、神話をわかりやすく解説しています。豊富な図版や写真を通じて、ヒンドゥー教の世界とインド神話の歴史を探求します。目次には、ヒンドゥー神話の宇宙論、主要な神々、二大叙事詩「ラーマーヤナ」と「マハーバーラタ」、プラーナ、著名な人物についての章があります。著者は歴史や神話に関する多くの著作を持つマーティン・J・ドハティ氏で、翻訳は井上廣美氏が担当しています。
インド独立の父、ガンディーの言葉をちりばめながら、特にその内的世界=精神世界の軌跡をたどる異色作。写真多数。 ガンディーの強靭な精神世界を支えていたのは、自ら「精神の参考書」と呼んだ『バガヴァット・ギーター』であった。ガディーの言葉をちりばめながら、彼の内的世界の軌跡をたどる。写真多数。 「非暴力と不服従」でインドを独立に導いたマハトマ・ガンディー。彼の強靭な精神世界を支えていたのは、自ら 「精神の参考書」と呼んだ『バガヴァット・ギーター』であった。ガンディーの言葉をちりばめながら、彼の内的 世界の軌跡をたどる。写真70点。ガンディーの内面=精神世界にスポットをあてた異色作。 イーシュワランのガンディー像――マイケル・N・ナグラー(カリフォルニア大学バークレー校名誉教授) ガンディーのインドに育って――当時と今 塩の行進/アシュラムでのガンディー/非暴力/ガンディーのメッセージ 第一章 変容の時代――幼年期、ロンドン留学、南アフリカ恥ずかしがり屋の少年/イギリスでの「実験」/ヨハネスブルグで得た成功 /奉仕する喜び/妻の忍耐/自分自身を変える/深い内省を経て 第二章 愛の道――南アフリカとインドにおける非暴力 マリッツバーグ駅での一夜/市民的不服従/憎しみには愛を/非暴力への確信/行動する愛/「神の子」とともに/悪に協力しない/ ネルーの一家/塩のサティアグラハ/怒りのエネルギーを非暴力の力へ/イギリス再訪/非暴力に応じたパシュトゥーン人/愛を広げる /非暴力への試練 第三章 母なるギーター――霊性の源『バガヴァッド・ギーター』 執着せず最善を尽くす/真実との一致/自己をゼロにする/マントラ/至高の境地 第四章 ひとりの人間として――生活すべてにわたる非暴力 人はどうあるべきか/愛は要求しない/セヴァグラム・アシュラム/瞑想から始まる一日/美しい人柄/夕食そして祈り/「わたしの人 生が、わたしのメッセージです」 非暴力はいかに作用するか――ティモシー・フリンダーズ(教育者、文筆家) サティアグラハ――魂の力/アヒンサー/サティアグラハの挑戦/現代におけるサティアグラハ ガンディーの時代――年譜と解説 地図/参考文献 索引
ガンジーにとって、真理とは神であり、神を実現するのが非暴力であり、愛だった。インド的伝統に深く根ざしながらも、世界のさまざまな宗教や哲学からインスピレーションを受け、真理を実現しようとしたガンジー。多くの人々を魅了するその思想と行動を、多元的な文化の存在意味を論究する間文化論哲学の視点から紐解く。 第1章 諸文化の間のガンジーの人生 第2章 文化多元的亜大陸としてのインド 第3章 ガンジーの直観 第4章 ガンジーの実践化綱領 第5章 間文化論的比較におけるガンジー
古代インドのヴェーダ文献・神話を中心に、ことばの持つ無限の力を探究する。呪文・呪術の源泉に迫る、シリーズ神話叢書、第2弾! 【ことばは、世界を創造するとともに、神をも滅ぼす】 ことばの本来の力が発揮される「呪文」とは何か。 なぜ「真の名前」は秘されるのか。 古代インドのヴェーダ文献・神話を中心に、 ことばの持つ無限の力を探究する。 呪文・呪術の源泉に迫る、シリーズ神話叢書、第2弾! 呪文を唱えて火を操り、敵の部族や悪魔を倒す話。 呪術師たちを引き連れて呪文を唱えることで、神が洞窟の壁を打ち砕く話。 名前をくれ、名前をくれと懇願してくる神の話。 ことばを間違えて取り返しのつかない失敗をした魔神の話。 世界を理解するための知識が集積された「ヴェーダ文献」。 神々への賛歌を集めた『リグ・ヴェーダ』とヴェーダ祭儀書文献に おける「ことばと呪力」にまつわる物語を読み解く。 【目次】 序章 ことばの呪術と古代インドの言語文化 1:呪術について 2:高められたことば 3:古代インドの言語文化 第1章 ヴェーダ神話集その一――内容通りの事柄を引き起こすことば 1:導入 2:部族長ヴァーマデーヴァの火の呪文 3:首席祭官ヴリシャ・ジャーナの悪魔祓いの歌 4:首席祭官ウシャナス・カーヴィヤと戦神インドラの二重奏 第2章 ヴェーダ神話集その二――打ちのめし破壊することば 1:導入 2:戦神インドラの魔女殺しの歌 3:戦神インドラの歌と呪術師たちの合唱 4:魔神アスラたちの失言 第3章 ヴェーダ神話集その三――運命を引きよせる名前 1:導入 2:火神アグニの名づけ要求 3:造形神トヴァシュトリの発音間違い 4:国王ダルバの改名儀礼 終章 ことばと共に生きるということ 【目次】 序章 ことばの呪術と古代インドの言語文化 1:呪術について 2:高められたことば 3:古代インドの言語文化 第1章 ヴェーダ神話集その一――内容通りの事柄を引き起こすことば 1:導入 2:部族長ヴァーマデーヴァの火の呪文 3:首席祭官ヴリシャ・ジャーナの悪魔祓いの歌 4:首席祭官ウシャナス・カーヴィヤと戦神インドラの二重奏 第2章 ヴェーダ神話集その二――打ちのめし破壊することば 1:導入 2:戦神インドラの魔女殺しの歌 3:戦神インドラの歌と呪術師たちの合唱 4:魔神アスラたちの失言 第3章 ヴェーダ神話集その三――運命を引きよせる名前 1:導入 2:火神アグニの名づけ要求 3:造形神トヴァシュトリの発音間違い 4:国王ダルバの改名儀礼 終章 ことばと共に生きるということ
『マハーバーラタ』は、古代インドの叙事詩で、全18巻・約10万詩節から成り、神話や哲学が織り交ぜられた物語です。この入門書では、物語の主筋と挿話を4章に分けて解説し、登場人物や神話の読み解き、他地域との比較などのコラムも掲載しています。附録には系図や人物一覧もあり、深く楽しむための内容が充実しています。著者は沖田瑞穂氏で、インド神話を専門としています。
『マハーバーラタ』を再話し、挿絵付きで読みやすくまとめた本。インドの神話や文化を解説するコラムもあり、英語圏で15万部以上の売上を誇る入門書。著者は神話研究者のデーヴァダッタ・パトナーヤクで、他にインド神話や比較神話を専門とする研究者たちが関与している。全体像を把握できる内容で、物語はプロローグから始まり、様々なテーマに沿って構成されている。
数百年間イギリスの植民地支配下にあったインドで宗教歌謡が生活に息づき、人々が自国の音楽に関心を寄せ続ける背景は何か。現地調査をもとに音楽界や芸能と社会の関係を考察した民族音楽的研究と南アジア地域研究の成果を貴重な写真・図版とともに提示する。 凡例 はじめに――賛歌の「価値」を南インドの文脈で捉え直す 第1部 南インドの「賛歌の伝統」概説 第1章 ナーマ・シッダーンタ――神の御名の教え 1 思想的側面 2 「賛歌を歌う者」バーガヴァタル 3 「賛歌の体系」(バジャナ・パッダティ) 4 様々な賛歌の実践機会 5 音楽的側面 第2部 インドの楽聖の系譜――「賛歌の伝統」のレパートリーを中心に 第2章 バクティ運動期――十二世紀―十七世紀 1 バクティ運動と賛歌群の形成 2 ベンガル地方の詩聖ジャヤデーヴァ 3 ターッラパーカ詩人アンナマーチャーリヤ 4 マハーラーシュトラ地方の宗教詩人 第3章 タンジャーヴール・マラーター時代――一六七四―一八五五年 1 タンジャーヴール・マラーター時代概説 2 ナーマ・シッダーンタ派の「賛歌のグル」 3 楽聖ナーラーヤナ・ティールタ 4 楽聖ティヤーガラージャ 5 サットグルスワーミ 6 そのほかの楽聖の賛歌と「賛歌のグル」をめぐる議論 第3部 近現代南インドの音楽界と賛歌 第4章 イギリス統治期――十九世紀中期―二十世紀中期 1 非バラモン階層の台頭と「ドラヴィダ民族運動」 2 イギリス統治期での音楽界の変化 3 イギリス統治期マドラスでの賛歌の実践 4 タミル・ナショナリズムと音楽界 第5章 独立インド時代――独立以降―一九八〇年代 1 「インド伝統文化」へのまなざし 2 バーガヴァタルの集団化 3 プドゥコーッタイ・ゴーパーラクリシュナ・バーガヴァタル 4 ハリダース・ギリ 5 クリシュナプレーミ・スワーミ 第6章 一九九〇年代以降の変化 1 「文化資源化」する賛歌 2 マラーティー・キールタンの包摂 おわりに 参考文献一覧 あとがき 事項索引 人名索引
この書籍は、古代インド文明の全貌を描いたもので、インダス文明やグプタ文化、仏教の興隆と衰退を扱っています。著者の中村元は、先住民やアーリヤ人の侵入、バラモン教の確立、都市の発展、原始仏教の成立、マウリヤ王朝の成立、異民族の侵入、大乗仏教、グプタ王朝の集権化など、様々な歴史的側面を詳細に解説しています。苛酷な環境と多様な文化の融合が生み出した古代インドの人々の姿を鮮やかに描写しています。
本書は、清掃カーストを取り上げ、それに着目しつつ、「ヒンドゥー教の宿命として従属的状況を受け入れる」不可触民像を再検討する。 本書は、不可触民のなかでも、都市の清掃カーストを事例に取り上げ、カーストの流動性に着目しつつ、これまでの研究が提示してきた「ヒンドゥー教の宿命として従属的状況を受け入れる」不可触民像に再検討を迫るものである。 ▼差別と困難に抗う新たな「不可触民」像 大都市デリーを舞台に、清掃カースト(バールミーキ)の人びとの声と運動からカーストの変容と現代的特質に迫る。 「自由・平等・民主主義」が憲法上保障された独立後のインドにおいて、カーストや不可触民差別というインド社会を特徴づけてきた問題はどのように変容しているのか? 不可触民とされてきた人びとをとりまく福祉政策の現状と課題、さらに、かれらにたいする減ることのない暴力・差別行為に抗する組織的活動や地位向上運動から、カーストの現代的特質を論じる。 デリーの清掃カースト・コミュニティにておこなってきたフィールドワークをもとにした意欲作。 第1章 カースト、不可触民差別は過去のものか? 1 社会的現実としてのカースト 2 清掃カーストに関する研究の成果と課題 (1) カーストとは何か (2) カースト研究の三つのアプローチ (3) 不可触民(ダリト)研究 (4) 清掃カースト研究 3 カースト、不可触民問題の現代的特質と本研究の視座 4 本書の構成 第2章 デリーの横顔 1 デリーの概観 (1) デリーの地理的特徴 (2) デリーの指定カースト 2 「バールミーキ」の名のもとに結集するデリーの清掃カースト 3 外国人女性の参与観察者 第3章 清掃カーストとされる人びと 1 不可触民の起源 2 「不可触民」から「指定カースト」への制度化 3 指定カーストの地域的広がり 4 不可触民のなかの清掃カースト (1) 清掃カーストの起源 (2) 清掃カーストの名称と代表的なカースト (3) 清掃カーストの「伝統的」職種 5 発展から取り残される清掃カースト ―― デリーの国勢調査にみる指定カーストの内的格差 (1) 教育 (2) 「伝統的」職種とのつながり ―― 清掃と皮なめしの比較 第4章 カースト制批判と不可触民解放をめぐる思想と政策 ―― ガーンディー、ガーンディー主義者による清掃カースト問題の「解 決」 1 不可触民解放の思想と運動の展開 (1) ヒンドゥー教内部の改革運動 (2) 脱ヒンドゥー教的価値観を志向する運動 2 カースト制批判と不可触民解放をめぐるガーンディーとアンベード カルの対立 3 ガーンディー主義者による清掃カーストの問題「解決」 ―― NGO スラブの活動 (1) インドの開発NGOとガーンディー主義 (2) 清掃カーストの福祉政策にみる政府とNGOスラブの「共生」 (3) スラブの活動分析 4 福祉政策における清掃カーストの「解放」の問題 (1) SC政策の時代的特徴 ―― 独立以降から1990年代の経済自由化 導入まで (2) 清掃カーストを対象とする政策の概要 (3) 清掃カーストを対象とする政策の進展状況とその問題 (4) 福祉政策における清掃カーストの「解放」に関する批判的考察 第5章 バールミーキ住民の社会経済的状況 1 デリーに住む ―― 物価高騰と住宅不足 2 調査地区(コロニー)の概況 3 バールミーキ住民の基本情報 (1) 宗教 (2) 教育 (3) 世帯規模 (4) カースト内婚 (5)移住歴 4 清掃労働の非正規化と「女性化」 第6章 清掃カースト出身者の内なる葛藤と抵抗のかたち 1 ダリト性(dalitness)への接近 2 働く ―― 清掃労働への恥じらい 3 学ぶ ―― 出自を知る、留保制度を足がかりにして 4 ロール・モデル意識の生成 5 結ばれる ―― 高学歴バールミーキのカップル 6 祈る ―― ヴァールミーキ詩聖崇拝にみる共属意識のゆらぎ (1) バールミーキ・アイデンティティの展開 (2) ガーンディー、大財閥ビルラーとデリーのヴァールミーキ詩聖寺 院 (3) 寺院の「歴史」認識 (4) 詩聖崇拝をめぐるカースト内の対立 第7章 清掃カーストの組織化と運動 ―― 清掃労働者組合から公益訴訟へ(1960年代―2010年代) 1 はじめに ―― 「エリート」の登場と拡散するダリト運動 2 運動体としてのカースト団体 3 清掃カーストの組織化とその変遷 (1) 清掃労働者の結集(1960年代) (2) カリスマ的指導者の登場による会議派と蜜月期、アンベードカル 生誕百年祭(1970年代―90年代初頭) (3) 清掃労働者会議の分裂、運動の多様化(1990年代半ば―2010年 代) 4 運動としての訴訟の始まり ―― 社会正義の実現手段として注目さ れる公益訴訟 (1) 人権侵害を告発する事例 (2) 指定カースト留保政策の改正を求める事例 5 おわりに ―― 突破口としての司法の可能性と課題 第8章 バールミーキの困難と挑戦のゆくえ 1 各章の論点とその成果のまとめ 2 本研究の含意と残された課題 おわりに 参考文献 図表・写真一覧 索 引
「ガンジー」に関するよくある質問
Q. 「ガンジー」の本を選ぶポイントは?
A. 「ガンジー」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「ガンジー」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ガンディー 平和を紡ぐ人 (岩波新書)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで52冊の中から厳選しています。
Q. 「ガンジー」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「ガンジー」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。















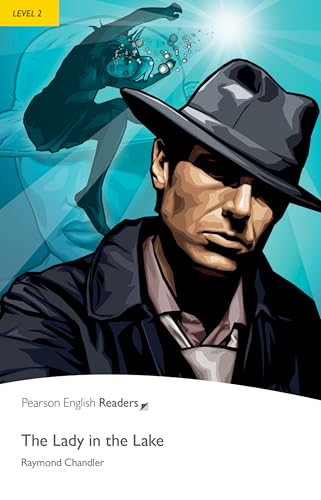





![『[ヴィジュアル版]インド神話物語百科』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51SHIT9s7QL._SL500_.jpg)










































