【2025年】「機能解剖学」のおすすめ 本 185選!人気ランキング
- 身体運動の機能解剖
- ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説
- プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系 第3版
- のほほん解剖生理学
- プロメテウス解剖学 コア アトラス 第3版
- グレイ解剖学 原著第4版 電子書籍付(日本語・英語)
- 世界一ゆる~いイラスト解剖学 からだと筋肉のしくみ
- 標準解剖学 (Standard Textbook)
- カラー図解 人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版【電子書籍つき】
- プロメテウス解剖学アトラス コンパクト版 第2版
この書籍は、200点以上の精密なイラストと豊富な解説を通じて人体の構造を詳しく理解できる内容です。目次は、総論、頭部・頚部、胸部、腹部・背部、上肢・下肢の5章から構成されています。著者は、坂井建雄(順天堂大学教授)と橋本尚詞(東京慈恵会医科大学教授)で、両者とも解剖学や細胞生物学に関する豊富な研究背景を持っています。
プロメテウス解剖学アトラスが改訂され、解剖学総論と運動器系の内容がさらにわかりやすくなりました。美しいイラストと的確な解説文を維持しつつ、図版の配置や文の推敲が行われ、医療職全般から支持されています。進化を続ける最高峰の解剖学アトラスです。
この書籍は、筋肉や体の仕組みをわかりやすく学ぶことで、理想の体を手に入れる方法を紹介しています。内容は、体の基本的な構造や筋肉のイラスト図鑑、不調をケアするためのボディメンテナンスに分かれており、著者は理学療法士の有川譲二氏です。彼は解剖学を楽しく身近に学べるように、体験を通じた教育を提供しています。
本書は、解剖学の複雑さを解消するために、教育の第一人者が整理した新しい教科書です。明快な本文、美しいイラスト、豊富なコラムを通じて、解剖学の知識をわかりやすく楽しく学べるように工夫されています。
460枚の解剖学習カードがポケットサイズの単行本として再登場し、筋の起始・停止・神経支配・作用に関する情報が追加されました。美しい解剖図に加え、オリジナルの索引や臨床的コメント、Q&Aも含まれており、持ち運びに便利で解剖用語の学習に役立ちます。
『ネッター解剖学アトラス』第7版は、イラストの美しさと解剖学的正確さで定評があり、学生や医師の意見を反映して内容をアップデートしました。新たに図表や体表解剖・血管神経系を俯瞰する章を追加し、各章末には臨床に役立つ知識をまとめています。また、電子版が付属し、より学習しやすい内容となっています。
本書は、ヨガのポーズが上手くいかない理由や身体の痛みの原因を解剖学的視点から解説します。「太陽礼拝」を中心に、全てのアーサナに共通する身体の使い方や怪我を防ぐための基礎知識を提供しています。著者は理学療法士であり、ヨガインストラクターとしての経験を活かして、安全で効果的なアーサナの指導を行っています。
本書は、ストレングスコーチMark Rippetoeの著書の日本語版で、バーベルを用いた5種のストレングストレーニング(スクワット、プレス、デッドリフト、ベンチプレス、パワークリーン)の効果的な方法を解説しています。初心者から経験者まで役立つ内容で、トレーニングの原点に戻ることができ、シンプルなプログラミングも提案されています。また、補助種目やアクセサリーエクササイズについての情報も含まれています。
「コアアトラス」の最新版は、臨床情報をまとめた臨床BOXの拡充やレイアウトの改善を行い、さらなる読みやすさを追求した意欲的な改訂版です。定番の解剖学アトラスとして、今後も選ばれる一冊です。
本書は、人気フィットネスYouTuberによるシリーズ第2弾で、運動を楽しく習慣化する方法を解説しています。5分でできる7つの部位別エクササイズや、全身痩せを促す4習慣プログラムが含まれ、QRコードでYouTube動画と連動しています。心と体の健康を促進し、運動不足やダイエットに効果的です。内容は、心を強くする体作りやマインドセットの重要性、1週間で変化を実感できるエクササイズについて詳しく説明されています。
体表から観察し体内を予測することで人体の内部が見えているかのように治療を進めることが可能になり患者のケアの改善に貢献できる 800枚以上のカラー写真に、3次元的に優れたグラフィックを体表へ描き、まるで骨や筋肉、血管等の内部が見えているかのように再現されている本書は、臨床家が「全身」の筋骨格系の体表解剖学的アプローチを開発する一助に… 正確な実施に特化した教科書といえる本書は、触診による位置確認の方法をわかりやすく伝える。 構造と機能の解剖学に欠かせない知識を補ってくれる。 臨床家が「全身」の筋骨格系の体表解剖学的アプローチを開発する一助になり、さまざまな領域における構造のパターン、類似性、差異を特定できるようになる。 基礎科学、臨床的な知識、実践的なスキルなどを理解し、徒手療法の専門家として成長、発展するためのサポートとなる臨床家が蔵書すべき一冊。 ◎多くの知識やスキルに加え、長期にわたって解剖学と徒手療法にかかわったなかで得られた提案やヒント、知識を数多く取り入れている。 ◎理学療法、オステオパシー、徒手療法分野の学生や臨床家が患者をよりよくケアできるようにする。医学生や医師の役に立つことができる。 ◎800枚以上のカラー写真に、3次元的に優れたグラフィックを正確に体表へ描き、まるで骨や筋肉、血管等の内部が見えているかのように再現されている。 ◎人体解剖学の理解をより深め、知識を得ることができる。 1 基本原理 臨床家が体表解剖学を必要とする理由 本書の体表解剖学で理解できること 体表解剖学の活用範囲 関節や脊椎分節の評価の構成要素 特殊な評価や治療テクニックを行う前の定位 腱や滑液包などの局所治療の基礎 臨床的な関連性 触診の特徴 体表解剖学を活用するとき 前提条件 解剖学/局所解剖学の背景 プロセスとしての正確な触診 経験 触診テクニックと抵抗 手順の中心面 触診でかける圧 触診テクニック 骨縁の触診 骨の隆起の触診 筋腹の触診 筋の縁の触診 腱の触診 靭帯の触診 関節包の触診 滑液包の触診 末梢神経の触診 血管(動脈)の触診 触診の補助 導く構造 ラインをつなぐ 触診の確認に役立つ手法 構造に印をつける 練習用の最初のポジション(練習用SP) 練習問題 2 肩甲帯 肩領域の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 全体の定位─後面 局所の触診─後面 局所の触診─側面 全体の定位─前面 局所の触診─前内側 局所の触診─前外側 練習問題 3 肘関節 肘関節の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 全体の定位─前面 局所の触診─前面 局所の触診─内側 局所の触診─外側 全体の定位─上腕後面 練習問題 4 手 手の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 全体の定位─背面 背面の軟部組織の局所の触診 手根骨背面の局所の触診 全体の定位─掌側 手掌の軟部組織の局所の触診 手根骨手掌面の局所の触診 練習問題 5 股関節と鼡径部 股関節と鼡径部の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 局所の触診─外側 局所の触診─背面 局所の触診─前面 練習問題 6 膝関節 膝関節の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 体温上昇の触診 浮腫の触診 局所の触診─前面 局所の触診─内側 前内側の軟部組織の局所の触診 局所の触診─外側 局所の触診─後面 練習問題 7 足 足の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 足の内側縁の局所の触診 足の外側縁の局所の触診 足背部の局所の触診 脚の遠位後面の局所の触診 練習問題 8 軟部組織 軟部組織の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 触診プロセスのまとめ 最初のポジション 難しい最初のポジション 触診テクニック 評価と治療のヒント 治療例 練習問題 9 骨盤後面 骨盤領域の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 触診プロセスのまとめ 骨を簡易的に定位する触診テクニック 筋を簡易的に定位する触診テクニック 局所の触診テクニック 定位のための投影 骨盤─大転子領域の局所の触診 評価と治療のヒント 練習問題 10 腰椎 腰椎の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 触診プロセスのまとめ 最初のポジション 難しい最初のポジション 触診テクニック 評価と治療のヒント 練習問題 11 胸椎と胸郭 胸部の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 触診プロセスのまとめ 最初のポジション 難しい最初のポジション 後面の触診テクニック 前面の触診テクニック 練習問題 12 頸椎 頸椎の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 触診プロセスのまとめ 最初のポジション 難しい最初のポジション 後面の触診テクニック 外側の触診テクニック 前面の触診テクニック 練習問題 13 頭部と顎 はじめに 顎関節の重要性と機能 この領域の治療でよく使う方法 必要とされる解剖学と生体力学の基礎知識 頭蓋骨の解剖学 頭蓋骨の触診 顎・顎関節 顎関節の触診 顎の筋の触診診察 練習問題 参考文献 索引
この書籍は、臨床例を通じて神経解剖学を学ぶ新しいスタンダードを提供しており、100以上の厳選された症例や大きな解剖イラスト、豊富な神経放射線画像を含んでいます。内容は神経解剖学の基礎から高次脳機能まで多岐にわたり、動画による神経学的検査法も紹介されています。著者は神経科学の専門家で、脳ネットワークの研究に取り組んでいます。
この神経解剖学テキストは、臨床との関連を重視し、豊富なイラストを用いて解説されています。内容は「運動系」、「感覚系」、「大脳皮質と辺縁系」、「内臓系」などの機能別に章分けされ、症候と病変部位の理解を深めることができます。コラム「臨床との関連」も挿入されており、学生から臨床家まで幅広く活用できる内容です。著者は群馬大学と京都大学の教授陣です。
本書『食事×筋トレで理想のカラダをつくれる本』は、著者岡田隆がボディビルの経験と研究を基に、食事をボディメイクに活かす方法を解説しています。食事の重要性を強調し、栄養素の役割や摂取方法について詳しく説明。特に筋肥大や除脂肪に焦点を当て、130以上の栄養素を紹介しています。また、消化・吸収のメカニズムや5大栄養素の関係も掘り下げ、実践的な食事管理の知識を提供しています。
本書は、ピラティスの基本を紹介し、体幹筋肉を効果的に鍛える方法を解説しています。特に、効率的なボディメイクを実現するために重要な骨格の知識や特有の動きを学ぶことが強調されています。4つの基本ポーズをマスターすることで、全身をバランスよく鍛え、理想の体を手に入れることができるとされています。また、プラスワントレーニングや日常的な疑問へのQ&Aも含まれ、ピラティスを日常生活に取り入れる方法が提案されています。著者は運動指導者の森拓郎氏で、ボディメイクに関する豊富な経験を持っています。
名著『グレイ解剖学』の改訂版で、解剖学アトラスとして新たに「女性の鼠径管」が追加され、イラストに加えて写真やX線・CT画像も掲載。各章末には振り返り用の表や概略図があり、すべての図はPCやモバイル端末で閲覧可能。内容は人体の各部位に関する詳細な解剖学情報を網羅しており、1858年から続く世界標準の解剖学テキストです。著者は秋田恵一氏。
アプリ版『動画でマスター! 機能解剖学的触診技術』は、書籍の内容に加え、105本の動画を収録し、QRコードからストリーミング視聴可能です。複数カメラで撮影されたエキスパートの手技により、立体的な動きが理解しやすく、学習に役立つ内容となっています。
この書籍は、日常動作やスポーツ動作における筋肉と関節の働きを詳しく解説し、目的に応じた関節動作の強化や適切な筋トレ種目を紹介しています。著者は筋肉研究の権威であり、バイオメカニクスに基づいたトレーニング方法を学ぶことができる内容です。目次には各関節の動きと鍛え方が含まれています。
インストラクター歴20年日本ピラティス界の第一人者・千葉絵美先生、待望の最新刊!!姿勢や所作が良くなり、体のゆがみが原因の不調が改善!お腹ぺたんこ&全身引き締めダイエット効果があるピラティス☆本書には、初心者~中級者向けの7つのLESSONを収録すべての動きを動画で確認できるので絵美先生のプライベートレッスンを受けている感覚でご自分のペースで楽しくレッスンできます♪
『ネッター解剖学アトラス』第6版は、美しいイラストと正確な解剖学情報で評価されている。新たに図が追加され、各章末には主要な筋の起始・停止をまとめた表が掲載され、より深い知識が得られる。また、学習サイトStudent Consultも引き続き利用可能。医療従事者や学生に支持される解剖学の決定版である。著者は慶應義塾大学の相磯貞和。
アプリ版『動画でマスター! 機能解剖学的触診技術』は、書籍の内容に加え、127本の動画(合計122分)を追加し、QRコードからストリーミング視聴が可能。複数カメラで撮影されたエキスパートの手技により、立体的な動きが理解しやすく、学習に役立つ内容となっています。
この書籍は、機能解剖学の専門家が運動時の人体の使い方を解説したもので、アスリートやトレーナーに必須の内容を提供しています。続編となる本書では、筋肉の特性、キネティックチェーン、体幹や上肢の動き、ストレッチングやテーピングについて詳しく説明しています。著者は筑波大学の准教授で、最新のスポーツ科学の知見を取り入れています。
この書籍は、骨格筋に焦点を当て、筋肉名、起始・停止、支配神経、主な働きを解説し、オールCGによる筋肉図を掲載しています。筋名は和名と英語名で表記され、さまざまな角度からの図が含まれています。内容は、上肢から頭部までの各部位の筋肉を扱い、巻末には略語集や和英・英和INDEXも付いています。著者は筋生理学の専門家で、教育や解剖学の講義に従事しています。
自分と対話しながら体を大切に使ってご機嫌な毎日を。55本の動画と連動し、本文とあわせてよりわかりやすくなっています。 みなさんの代わりは他にいません。自分と対話しながらカラダを大切に使ってご機嫌な毎日を。 (本書より) 55本の動画と連動し、本文とあわせてよりわかりやすくなっています。 はじめに、目次、この本の使い方 1章 呼吸を楽にするゆるピラ 呼吸のお話、呼吸ってどういうこと?、スタンディング・ロールダウン、マーメイド、キャットストレッチ、ヒップロールズ/コラム 胸郭と呼吸 2章 体をゆるめて整える夜のゆるピラ ローリング・ライク・ア・ボール ①②、シェルストレッチ、気持ちを前向きにするリラックス法、ポールで腕&脚のワーク ①② /コラム ピラティスと呼吸 3章 快適な一日をすごす朝のゆるピラ おしりフリフリ、猫のように伸びるストレッチ、肩回し(ぐるぐる回し編、合掌編、合掌編・起きやすいまちがい、棒編)、背骨の柔軟性を保つ運動、肩甲骨を動かそう、足首と足ゆびのエクササイズ、マーメイドからのバリエーション ①②/コラム ピラティスとは ① 4章 肩こり・腰痛・疲れを楽にする症状別ゆるピラ 肩甲骨の6つの動き、おしり歩き、ロールオーバーprep(準備編)、平泳ぎとバタフライ(床上編)、スレッドニードル、ブック・オープニング、猫背を改善するエクササイズ、四十肩・五十肩予防 肩関節の組織化 ①②、肩関節・股関節の分離運動、骨盤の位置をつかむエクササイズ、転倒予防① 中殿筋強化のエクササイズ、転倒予防② パジャマウォークとボールエクササイズ、バンドで脚とおなかの運動/コラム ピラティスとは ② 5章 イスに座ってできるゆるピラ バンドやポールを使うゆるピラ クイズ どうやってイスから立ち上がってる?、イスに座って平泳ぎとバタフライ、イスに座ってマーメイド、イスに座ってわきを伸ばすエクササイズ、バンドで体側ストレッチ、バンドでわき・胸・肩・肩甲骨の運動、ヒップロールズ・ウィズ・ポール、ロールオーバー(チャレンジ編)、お風呂掃除でエクササイズ/コラム ピラティスの効果 6章 産前のマタニティゆるピラ 股関節・肩関節と背骨の運動、股関節とわきを伸ばす、マタニティゆるピラ、骨盤と背骨を動かす、下半身(ひざ下)のむくみ解消、胸を開くエクササイズ 「ゆるピラ」に関する主な骨格図・筋肉図・ニュートラルとインプリント・胸部とコア/おわりに
「ほぐピラ」は、筋膜や筋肉をほぐしながらピラティスの動きで体を鍛える新しいエクササイズです。著者の星野由香氏が考案し、モデルや女優たちに人気があります。この書籍では、全エクササイズを写真とQRコード付きの実演動画で解説。10分でできる「リラックスコース」と「脂肪燃焼コース」も紹介されています。手持ちのローラーやタオルを使って簡単に始められる内容です。
この文章は、スポーツ・バイオメカニクスに関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、スポーツ・バイオメカニクスの定義、バイオメカニクスの基礎(筋肉の役割、エネルギー供給、運動の調整機構、体の構造と運動、力学の法則)と実際の運動(立つ、歩く、走る、高く跳ぶ、遠くへ跳ぶなど)に分かれています。著者は金子公宥と藤原敏行で、それぞれの経歴が簡潔に述べられています。
この教科書は、生理学と解剖学を統合的に学ぶための効率的な教材で、要点整理と明確な図表を用いて長期記憶を促進します。国試練習問題で目標が明確になり、医療職に役立つ情報が凝縮されています。内容は人体の基本的な構造と機能から始まり、各器官系(心臓、循環系、呼吸器系など)の詳細、さらに環境生理学や皮膚、口腔の構造と機能まで幅広くカバーしています。
本書は、ヨガのポーズを取る際の身体の解剖学的な理解を深めるためのガイドです。骨、関節、筋肉の基本的な構造を解説し、ポーズを図解しています。また、図解を塗り絵として楽しむことで、各部の位置や機能を覚えやすくなります。ヨガを学ぶ人々にとって、人体の仕組みを理解する手助けとなる一冊です。さらに、巻末には携帯用カードも収録されています。
この書籍は、子ども向けの140cmの人体ポスターで、頭蓋骨や肋骨などをめくって見ることができる仕掛けが多数あります。壁にかけて常に観察でき、20ページの詳細な解説が付いており、人体の仕組みをリアルに学べます。目次には細胞、心臓、呼吸、消化、免疫などのテーマが含まれています。著者は順天堂大学の坂井建雄教授で、解剖学の専門家です。
この書籍では、姿勢や体幹、呼吸を整えることで、更年期世代の様々な不調(腰痛、尿漏れ、猫背、頭痛、不眠など)を解消する「大人ピラティス」のプログラムを紹介しています。著者はバルセロナ在住のトレーナーで、初心者向けの基本レッスンやお悩み別のエクササイズを動画付きで提供。体の不調は姿勢や動作の歪みが原因であり、少しのメンテナンスで改善できることを実感できる内容です。
本書は運動器障害に関する運動・動作分析の基盤を提供する名著の完訳版で、900以上のカラーイラストや表を用いて理論をわかりやすく解説しています。著者のP.D.アンドリュー氏が監訳を行い、最新の研究を反映して内容が改訂され、特に股関節に関する記述が充実しています。また、新章として「走行の身体運動学」が追加され、各章末には関連動画のQRコードも掲載されています。リハビリテーション実践に役立つ内容となっています。
8年ぶりの改訂版で、約30%の内容が更新された「脳科学」に関する教科書です。全9パート、64章からなり、新たに「ブレイン・マシン・インターフェース」など3章が追加されました。神経系のメカニズムや疾患について詳述し、情報工学に関する項目も強化されています。最新の研究データを各章で紹介し、読みやすい日本語訳と907点のフルカラー図版が特徴です。初学者から専門家、AIエンジニアまで幅広い読者に向けた内容で、手頃な価格で提供されています。
この文章は、医学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、細胞や各種組織、器官系(循環器系、呼吸器系、消化管など)に関する項目が列挙されており、著者は河田光博教授と小路武彦教授です。
本書は、筋力トレーニングに必要な部位や筋肉を目的に応じて強化するための情報を提供するもので、正確なカラーイラストで示されています。スポーツコーチや体育教師、筋力トレーニングを目指す全ての人にとって役立つ内容です。目次には上腕、肩部、胸部、背部、脚部、臀部、腹部が含まれています。著者は筋肉やスポーツ医学に関する専門知識を持つプロフェッショナルです。
この書籍は、インナーマッスルを鍛えるピラティスの基礎から上級者向けのエクササイズまでを網羅した決定版です。内容は、ピラティスの基本知識、呼吸法、プレピラティス、クラシカルピラティス、目的別プログラム(初心者向け、姿勢改善、腰痛予防など)を含み、エクササイズの目的や手順を豊富な写真と共に解説しています。著者はトレーニングスタジオの代表で、ピラティスの専門家です。
この書籍は神経解剖学を短期間で学べる内容で、明瞭な図を多数収載しています。神経学との関連がわかりやすく、目次には神経系の細胞や各部位の解説が含まれています。著者は水野昇と野村嶬で、共に京都大学での豊富な経歴を持つ専門家です。
この書籍は、ピラティス初心者向けに自宅で行えるエクササイズプログラムを紹介しています。内容は、ピラティスの基本(姿勢や呼吸)、正しい姿勢を保つためのプログラム、スムーズな動きを促進するプログラム、シェイプアップやボディメイク、強く美しい体を作るプログラム、そして疲れを取るストレッチに分かれています。著者は、ピラティスの専門家であり、心身の総合的な指導を行っています。
実際の解剖標本を基にした独特のイラストが特徴の解剖学図譜の改訂版。独自の剖出アングルを維持しつつ、現代的なデザインに統一。初学者や臨床、学術の場で必携の一冊。
『Science of Strength Training』の日本版は、筋力トレーニングの科学的解説とハイクオリティなCGビジュアルを提供します。部位ごとの代表的なトレーニングを紹介し、正しい姿勢や筋肉の動きが理解しやすくなっています。怪我の予防やトレーニングプログラムの組み方についても詳しく解説されており、スポーツ指導者やトレーニングに真剣に取り組む人々にとって必携の一冊です。監修は東京大学名誉教授の石井直方氏です。
この書籍は、医療職を目指す学生向けに解剖学・生理学を効率的に学ぶ方法を提案しています。著者は、用語の丸暗記を避け、関連性を理解することが重要だと強調し、関西弁の先生がそのコツを教えます。内容は、解剖生理学の基本から各器官系に関する知識を網羅しています。著者は、医療分野での豊富な経験を持つ専門家です。
この解剖学の入門書は、看護学生や医学生、コメディカルに評判が高く、イラストがフルカラー化されて理解しやすくなっています。本文は重要度に応じて活字の大きさが異なり、基本的な解剖学の事項を網羅的に解説しています。必携の一冊です。
ピラーティスの基礎となる原理と手順を、豊富なカラー写真で紹介。実用ガイドとして、基本原則も十分に理解できる最適な入門書。 ピラーティスは、アライメント(並べる、整列、比較などの意味)の動きを体に覚えこませるメソッドとして、体を中心から整え、インナーマッスルを意識したスラリとした引き締まった体を手に入れることができます。 柔軟性と体幹の強さを向上させるための包括的なピラーティスの入門書 ピラーティスの基本概念とは、体の中心を軸とし、左右対称に骨や筋肉を自然なアライメント(整列)にし、人間本来の健康でしなやかな体をつくることです。実践することによって、背中の痛みを解消させ、しつこい関節の悩みに作用し、職業による体への負担やトラブルにも効果的で、体のあらゆる骨と筋肉が本来あるべき場所へ整うことで、スラリとした引き締まった体を手に入れることができます。さらに自律神経のバランスを整え、人生への活力を最大限に引き出してくれる理想のエクササイズです。 『実践ピラーティス』は、一般的な情報だけでなく、身体への意識を深め、強さ、トーン、姿勢を改善するのに役立つ、的確で集中力のあるエクササイズシステムが含まれています。ストレッチ、リラクゼーション、ビジュアライゼーション、呼吸法などのアドバイスに加え、ジョーゼフ・ピラーティスのエクササイズ・メソッドの歴史や、ピラーティス・プログラムの基本原則も十分に理解できる最適な入門書です。 ピラーティスの基礎となる原理と手順を、豊富なカラー写真で紹介しています。無理や負荷のない、バランスの取れたエクササイズにより、初心者へもおすすめの実用ガイドとして、あなたを手厚くサポートします。 約350枚もの写真やイラストを掲載し、ビジュアルからの情報を入れることで、高い集中力を手に入れ、動き方のポイントや次の動作が瞬時にわかり、無理なく進めることができます。 本書の使い方 はじめに 第1 章:ピラーティスシステム ジョーゼフ・ピラーティス─その人となりと功績 原理 骨格について 筋肉のガードル こんな人がピラーティスでよい効果を得られます ピラーティスとその他の療法 第2 章:ピラーティスを始める前に エクササイズを行う前に ボディー・チェック 服装、道具、スペース 第3 章:心と身体の再教育 アライメント 骨盤底 心を引き締める 呼吸 休憩とリラクゼーション パーソナル・プログラム 第4 章:基本的なエクササイズ 首の筋肉をほぐす 肩の緊張をとりのぞく 内腿を独立して動かす 下背部の筋肉を働かせる 背骨の回旋 骨盤と足を独立して動かす 骨盤の動きを自由に 腹筋を鍛える 身体の前面を鍛える 安定した体幹から、足を伸ばす 内腿を伸ばすエクササイズ 太腿の前面をほぐす 背骨を伸びやかに 基本の立ち位置 背骨の感覚 グラウンドワーク 足全体のバランス セルフ・チェック 第5 章:より高度なエクササイズ 呼吸法の上達 背骨のコントロール力を高める 骨盤の安定 楽な座り方 股関節の回旋 さらにお腹を鍛える ハンドレッド 斜筋を働かせる ダイアゴナル・ストレッチ ジャベリン 立った姿勢で腕を鍛える バランスと筋力 ストレスのない座り方 腿の内側と外側を働かせる 胸の緊張をほぐす まとめ ウエイトを使ったエクササイズ インテグレーション 用語解説 国内の関連情報 海外の関連情報 索引
本書は、解剖生理学を学ぶ医療従事者向けに、人気のゴロ合わせをまとめた書籍です。SNSでの支持を受け、イラストやミニドリルを用いて効率的に知識を習得できる内容になっています。特典として、声優によるゴロ音声も付いており、通勤中などに耳から学ぶことができます。
この書籍は、骨格筋に関する知識を体系的にまとめたもので、第二版では新しい知見を盛り込み全面改訂されています。内容は、骨格筋の構造や機能、神経系による運動調節、エネルギー代謝、ホルモン分泌、筋の肥大と萎縮、運動と心肺機能、認知機能、生活習慣病との関連など多岐にわたります。著者は、筑波大学の名誉教授である勝田茂氏と、筑波大学の教授である征矢英昭氏です。
詳細な解説と、解剖学的イラスト付きの46種類のエクササイズによって、特定の筋肉のストレッチ、強化、精密なコーディネーション… フィットネスクラブやアスリートのトレーニング・プログラム、医療施設などの新しい舞台に浸透しているピラーティスは、初学者にも、理学療法士など人体解剖学に広範な知識のある人にもたいへん役立つエクササイズである。 『ピラーティス アナトミィ 第2版』は、詳細な解説とステップごとの説明、見事な解剖学的イラスト付きの46種類のエクササイズによって、特定の筋肉のストレッチ、強化、精密なコーディネーションを探究できるようになっている。 本書は、どの筋肉が作用しているか、呼吸・アライメント・動きが根本的にどうつながっているか確認しながら、体を引き締め、コアを安定させ、バランスを改善し、柔軟性を高めるエクササイズに取り組むことができるよう設計されている。 各エクササイズの「エクササイズのパーソナライズ」セクションを活用すれば、自分の目的やレベルに合わせて調整し、ワークアウトをカスタマイズできるようになっている。 モディフィケーションによって難易度を下げれば誰にでもこなしやすいエクササイズになり、バリエーションやプログレッションを選択すればエクササイズに高度な要素が加味される。そうして難易度を上げていくことは、ピラーティス上級者への階段を一歩一歩上がっていくことにもなる。 また、呼吸・集中・自己認識のテクニックにも触れ、心身ともに鍛える独特のエクササイズを体験できるようになっている。 ピラーティスの美と恩恵を探求しはじめたばかりの人にとっても、何年もピラーティスを続けてきた人にとっても、本書はほかに類を見ない情報源であると確信できる。 『ピラーティスアナトミィ 第1 版』は2011 年の刊行後、世界中で読まれ、たくさんの言語に翻訳された。 第2版の本文は約80ページ増え、46種類のエクササイズには、難易度を下げる方法(モディフィケーション)、難易度を上げる方法(プログレッションとバリエーション)を含む「エクササイズのパーソナライズ」という項目が追加され、適用範囲が広がり、自分のレベルや目的に合わせて変化をつけられるように改良された。本書は、初版より9年の時を経て、おおいなる進化を遂げ、私たちを更なる深みへと到達させてくれる。 はじめに 第1章 ピラーティスの6つの原則 第2章 脊柱、コア、ボディ・アライメント 第3章 筋肉、動きの分析、マットワークを始める前に 第4章 マット・セッションの基本 第5章 動きと安定のための腹筋ワーク 第6章 柔軟な脊柱のための精密なアーティキュレーション 第7章 機能的な脊柱のためのブリッジング 第8章 効果的なコアのための体側のエクササイズ 第9章 強い背中のための伸展エクササイズ 第10章 ピラーティス・プログラムのカスタマイズ エクササイズ一覧 参考文献 著者・監訳者略歴 Earn Continuing Education Credits/Units
この書籍は、トレーニングと健康に関する最新のサイエンスを解説し、身体を変え、パフォーマンスを向上させ、人生を楽しむ方法を提供します。内容は筋肉の性質や運動の仕組み、トレーニング方法について理論と実践に分かれて詳しく説明されています。著者は東京大学の教授で、運動生理学やトレーニング科学の専門家です。
本書は、韓国の漫画家ソク・ジョンヒョンが9年かけて執筆した美術解剖学の集大成で、人体の自然な動きを描くための技法が紹介されています。内容は生物の形、身体の基礎、頭部、胴体、腕と手、脚と足、全身に分かれており、解剖学的な視点から人の動きを丁寧に解説しています。また、1コマ漫画を交えた楽しい読み進め方が工夫されています。著者は多彩な経歴を持ち、国内外で人体描写の特別講義を行っています。
この書籍は、運動系、内臓系、脈管系、神経系、感覚器の各部の名称と意味を、360点のカラー図版を用いて視覚的に理解できる内容です。目次には各系の構造や機能に関する詳細が含まれています。
トリガーポイント療法と筋肉連鎖を簡潔にまとめた教本。日常の臨床の場ですぐに使える完全な参考書! 痛みを訴える患者に効果的な療法トリガーポイントを見つけ出し、刺激を与え、リリースする! 筋肉連鎖のさまざまなコンセプトを紹介。 歪みの発生を分析、評価。 それぞれのコンセプトがオステオパシーの手技療法を日常行う上でどのぐらい有用か、その答えは本書にある。 よく見落とされる、痛みの原因となっている筋肉組織。多くある、筋肉組織とトリガーポイントの存在が原因の運動器の痛み。たくさんの写真を掲載して解剖学的な概要を説明、トリガーポイントとその痛みの領域の正確な位置が簡単にわかる。 はじめに vi 第Ⅰ部 筋肉連鎖 1 序 論 2筋筋膜連鎖モデル 3生理学 4頭蓋仙骨モデル 5ジョン・マーチン・リトルジョンのバイオメカニクス・モデル脊柱の力学 6姿勢筋、相性筋とクロスシンドロームに関連する姿勢パターン、ウラジミール・ヤンダの筋筋膜治療法への貢献 7ジンク・パターン 8筋筋膜の連鎖1つのモデル 9平衡状態 10診 断 11療 法 第Ⅱ部 トリガーポイントとその治療 12定 義 13トリガーポイントの分類 14トリガーポイントの病態生理学 15診 断 16トリガーポイント療法 17トリガーポイントを保持する因子 18促通された分節 19トリガーポイント 20参考文献 索引
スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるための食事摂取法とは? 運動と食事をどのように組み合わせれば,健康の維持増進につながるのか? 本書はその基礎となる理論を紹介しながら,細胞・分子レベルで解説.「なるほど」と納得できる役立つ内容が満載. はじめに 序 章 スポーツ栄養学とは? 第1章 身体組成と体脂肪・脂肪細胞の種類 第2章 エネルギー消費量と摂取量 第3章 糖質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その1) 第4章 たんぱく質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その2) 第5章 脂質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その3) 第6章 運動中の水分摂取法とスポーツドリンクの効果 第7章 パフォーマンス・健康とサプリメント
本書は、精神医学の基礎知識をわかりやすく解説した入門書で、研修医や看護師向けに精神疾患の患者への初期対応を説明しています。著者の森皆ねじ子は、イラストを用いて精神科治療が必要な患者を適切に見つけ、専門家に繋げるための知識を提供します。内容は、心の病の概念や各種精神疾患(統合失調症、躁うつ病、うつ病、神経症、人格障害、子どもの精神障害、依存症)についての解説が含まれています。
本書は、ピラティスの創始者ジョセフ・H・ピラティスの著作『YOUR HEALTH』と『Return to Life』を合本したもので、ピラティス・メソッド(コントロロジー)の理論と実践を深く理解するための内容が紹介されています。初の日本語版として、70年の歴史を持つ名著を通じて、ピラティスを学ぶ人々に向けた重要な一冊です。著者ジョセフ・H・ピラティスの背景や、ピラティスを広めた経緯も触れられています。
「機能解剖学」に関するよくある質問
Q. 「機能解剖学」の本を選ぶポイントは?
A. 「機能解剖学」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「機能解剖学」本は?
A. 当サイトのランキングでは『身体運動の機能解剖』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで185冊の中から厳選しています。
Q. 「機能解剖学」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「機能解剖学」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

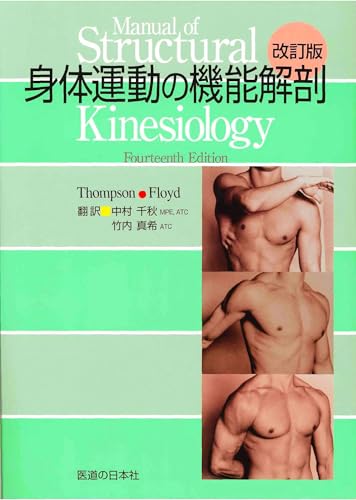









』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41XVDoaUybL._SL500_.jpg)













































































































![『改訂版 生物 [教番:生物/310]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/515TXX09f2S._SL500_.jpg)


![『第一学習社 高等学校 改訂 生物 [生物311]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41WAERNzOUL._SL500_.jpg)










![『新・徒手筋力検査法 原著第10版[Web動画付]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ytgZDSMDL._SL500_.jpg)





























































