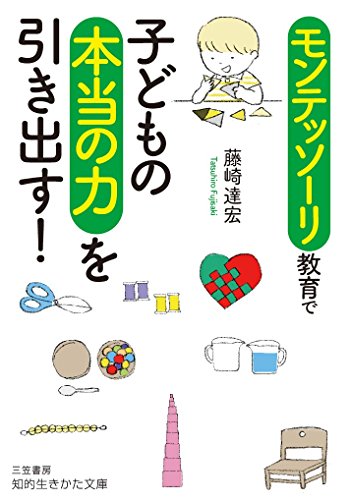【2025年】「幼児教育」のおすすめ 本 160選!人気ランキング
- モンテッソーリ教育で子どもの本当の力を引き出す! (知的生きかた文庫 ふ 31-1)
- 0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす! (単行本)
- モンテッソーリ教育は子を育てる、親を育てる お母さんの「敏感期」 (文春文庫 さ 46-1)
- 非認知能力を育てる あそびのレシピ 0歳~5歳児のあと伸びする力を高める (こころライブラリー)
- 子どもの才能を伸ばすモンテッソーリ教具100 (単行本)
- モンテッソーリの幼児教育 ママ,ひとりでするのを手伝ってね!
- 子どもが育つ魔法の言葉 (PHP文庫)
- 3000万語の格差――赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ
- 私たちは子どもに何ができるのか――非認知能力を育み、格差に挑む
- 0~18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育: 子どもの可能性が広がる実践的子育てガイド
この文章は、子どもの成長や潜在能力に焦点を当て、親が子どもの成長サイクルを理解し予習する重要性を強調しています。モンテッソーリ教育を通じて、子どもの自律や集中力を育てる方法を提案し、家庭で簡単に実践できることを紹介しています。これにより、子育てが楽しくなり、子どもの未来を輝かせることができると述べています。
「モンテッソーリ教育」は、マリア・モンテッソーリによって創始された教育法で、特に0~3歳の子どもに焦点を当てています。この書籍では、親が子どもを自分で考え行動できるよう育てるための30の具体的な方法を紹介しています。内容は、妊娠中の準備から手作り教具、トイレトレーニング、2歳児の成長過程まで多岐にわたります。実例や写真が豊富で、家庭での実践が容易です。著者の藤崎達宏は、モンテッソーリ教育の専門家であり、全国でセミナーや講演を行っています。
この書籍は、モンテッソーリ教育の専門家である相良敦子が、子育てのポイントを「親育て」という観点から解説したものです。内容は、子どもの「敏感期」やお母さんの「敏感期」、自律と自立に関するキーワード、家庭での手づくり教材、子育ての重要な鉄則などが含まれています。育児書のロングセラーが文庫化された一冊です。
本書は、非認知能力(意欲、粘り強さ、自己抑制、社会性、自尊心など)を育む方法について解説しています。乳幼児期にこれらの能力を育てることで、将来の幸福や成功につながるとされています。内容は二部構成で、第1部では非認知能力の定義や育成の重要性を説明し、第2部では具体的な遊びのレシピを通じて実践的な方法を紹介しています。著者は乳幼児教育の専門家で、子育て支援に関する豊富な経験を持っています。
本書は、モンテッソーリ教育に基づく子どもの成長を促すための100の教具を紹介しています。特に0~6歳の「敏感期」における教具の重要性が強調されており、適切な教具が自律心や集中力、自己肯定感を育むとされています。著者はモンテッソーリ教育の専門家で、家庭で簡単に実践できる方法を提案しています。さらに、無料の素材ダウンロード特典も提供されています。
この本は、子どもの可能性を引き出し、自主性や他人への思いやりを育むために親がどのように関わるべきかを、実例を交えて分かりやすく解説しています。幼児期の重要な学びや人格形成のプロセス、子どもの仕事の観察方法、日常生活を教育に活かす方法についても触れています。
この書籍は、世界22カ国で愛読され、日本で120万部以上のベストセラーとなった子育てに関する指南書です。子育ての重要なポイントや親としてのあり方についてのヒントが提供されています。具体的な内容としては、子どもがどのように育つかに影響を与える親の言動や接し方が示されており、励ましや愛情が子どもの成長に与えるポジティブな影響が強調されています。著者は教育者のドロシー・ロー・ノルトと精神科医のレイチャル・ハリスで、翻訳は石井千春が担当しています。
算数や国語の学力、粘り強さ、自己制御力、思いやり……、生まれた瞬間から最初の数年間に、親や保育者が子どもとどれだけ「話したか」ですべてが決まる。日本の子育て、保育が抱える課題とその解決策を、科学的な裏づけと著者自身の具体的な実践から示した書。 第1章 つながり:小児人工内耳外科医が社会科学者になったわけ 第2章 ハートとリズリー:保護者の話し言葉をめぐる先駆者 第3章 脳の可塑性:脳科学革命の波に乗る 第4章 保護者が話す言葉、そのパワー:言葉から始めて、人生全体の見通しへ 第5章 3つのT:脳が十分に発達するための基礎を用意する パート1:科学から実践へ パート2:「3つのT」の実際 第6章 社会に及ぼす影響:脳の可塑性の科学は私たちをどこへ導くのか 第7章 「3000万語」を伝え、広げていく:次のステップ エピローグ 岸に立つ傍観者であることをやめる 解説 子どもの言葉を育む環境づくり(高山静子) 訳者あとがき(掛札逸美)
本書は、子どもの貧困が「非認知能力」の獲得機会を奪うことに焦点を当て、成功に必要な力(やり抜く力、好奇心、自制心など)を育む方法を最新の研究と事例を基に解説しています。著者ポール・タフは、特に貧困家庭の子どもにおける非認知能力の重要性を示し、具体的な育成方法を探求しています。教育者や親にとって、子どもの教育と貧困問題に関する貴重な示唆を提供する一冊です。
この書籍は、モンテッソーリ教育の理念と実践方法を紹介し、親が楽になり子どもが成長するための68のスキルを提供しています。内容は、モンテッソーリ教育の基本原則や家庭での実践、家族の生活の改善に焦点を当てています。著者は、モンテッソーリ教育の専門家であり、教育の重要性を強く感じている経験豊富な教育者たちです。
本書は、モンテッソーリ教育を通じて3歳から6歳の子どもに言語力、数字力、協調性、創造力を育む方法を紹介しています。著者は、子どもが自立し成長する力を引き出すための30の実践的なメソッドを提案し、特に自主性を重視しています。また、適切な教育法や子どもへの接し方についても触れています。著者はモンテッソーリ教育の専門家であり、全国で子育てセミナーを開催しています。
この本は、子育てにおける悩みや問題に対する具体的な対処法をモンテッソーリ式教育を通じて解説しています。特に1~3歳の子どもに向けた言葉かけや生活環境の整え方、遊び方を紹介し、家庭で実践できる工夫が詰まっています。著者は国際モンテッソーリ協会認定の教師で、子どもの個性や自立を育む方法を提案しています。日本語監修にはモンテッソーリ教育の専門家が関わっています。
著者は「全米最優秀女子高生」コンテストで優勝した娘を持つ日本人ママで、AI時代において重要な非認知能力を育てる教育の必要性を説いています。彼女の実践的ルール集では、心の強さやコミュニケーション能力、自己肯定感を育む方法が紹介されています。目次には、非認知能力の定義や、ルール作り、親子対話、遊びを通じた学び、自己受容、そして子どもの「好き」を見つけることが含まれています。著者はライフコーチとしても活動し、子育てやキャリアについて講演を行っています。
この書籍は、モンテッソーリ教育の理念に基づき、子どもの「イヤイヤ期」を「敏感期」と捉え、子育てを楽にする方法を提案しています。内容は、子どもの自立や成長を促す環境作り、学びのサイクルについて解説しており、著者は日本のモンテッソーリ教育の第一人者である相良敦子と、モンテッソーリ教師のあべようこです。マンガ化されており、視覚的にも理解しやすい形式で提供されています。
本書は、教育に関する一般的な思い込みに科学的根拠を持って反論し、教育経済学の視点から「成功する教育・子育て」についての知見を提供します。内容は、ゲームの影響やご褒美の効果、非認知能力の重要性、少人数学級の効果、良い教師の条件など多岐にわたります。著者は、個人の経験よりもデータに基づく教育の重要性を強調し、教育関係者や親にとって必読の一冊とされています。
この書籍では、ノーベル経済学賞受賞者ジェームズ・J・ヘックマンが提唱した「非認知能力」について解説しています。非認知能力とは、コミュニケーションや共感、忍耐力など、テストでは測りにくいが将来の成功に重要な能力を指します。著者は、子どもや大人がこの能力をどう育むか、またその重要性が増している理由を理論と実例を交えて説明しています。具体的には、実践的な育成方法や大人たちの取り組みも紹介されています。著者は岡山大学の准教授で、教育方法学を専門とし、幅広い世代の非認知能力向上に努めています。
子どもが生まれたときに購入して以来、わたしの心のお守りです!チェック表があり、病院なのか救急車を呼ぶレベルなのか、お家で様子を見るのか判断できます。キティちゃんがかわいいので家においておいてもゴツくないところも気に入っています!
本書は、将棋の藤井聡太七段やジェフ・ベゾスが受けたことで知られるモンテッソーリ教育のポイントをマンガを通じて紹介しています。モンテッソーリ教育は、子どもの成長に必要なことを観察し、適切なタイミングで手助けを行うことで自立した思いやりのある人間を育てることを目指します。ストーリーを通じて、家庭で簡単に実践できる方法を提案し、子育ての悩みに応える内容となっています。著者は田中昌子氏で、モンテッソーリ教育の専門家です。
著者中川李枝子が贈る子育てバイブルでは、焦らず悩まず子どもらしさを大切にすることが強調されている。保母としての経験を基に、子どもに関する45のメッセージが収められ、子育ての基本や本の読み方、良いお母さんの姿について語られている。著者は名作絵本「ぐりとぐら」の生みの親であり、子育てに役立つ知恵を提供している。
この本は、モンテッソーリ教育を通じて子どもの才能を伸ばす方法を紹介しています。著者の藤崎達宏先生が、家庭で簡単に実践できる具体策をマンガ形式で解説しており、子どもの成長における「敏感期」や適切な声がけの方法などが含まれています。親が子どもの成長を理解し、育児を楽にするための情報が豊富に提供されています。モンテッソーリ教育の基本や実践テクニックを学びながら、親子で楽しく育児に取り組むことができる内容です。
本書は、子育て中の親が直面するイライラや困難を軽減するために、子どもに「おしごと」を与えることの重要性を説いています。モンテッソーリ教育に基づき、子どもの才能を伸ばすための具体的な方法や、親子の信頼関係を築くためのポイントが紹介されています。著者は、乳幼児教室を運営し、発達障害の子ども向けの支援も行っています。全体を通じて、子どもと一緒に成長し、幸せな子育てを楽しむためのヒントが提供されています。
モンテッソーリ流、自立した子が育つ<あそび>のレシピを紹介。国際モンテッソーリ協会0-6歳ディプロマ北川真理子氏監修。 モンテッソーリ流、自立した子が育つ<あそび>のレシピを紹介。SNSで注目を集める国際モンテッソーリ協会0-6歳ディプロマ北川真理子氏監修、その他人気インスタグラマー多数による製作あそびの提案。 時間やお金をかけなくても、 モンテッソーリ教育の考え方を取り入れた<あそび>で、 自立した子 が育つ――子どもの発達をうながす、おうちでできる<あそび>のレシピを紹介します。 ねんねの時期には、赤ちゃんが「見る対象」とできるような モビール を。1歳前後からは指先を鍛える ○○落としや ○○通し、 ハートバッグ など。自分でできた!を実感する、日常生活のあそびとして ごますり や マジックテープ、バックルとめ。分類や整理に興味がある時期には 実物合わせ や 色分け あそびを。文字や数に興味がある時期には 数字並べ や 時計の活動、 壁かけ五十音 など。いずれも家庭にあるものや、百円均一で揃えられるものを使ったあそびです。 ★★QRコードから 一部のあそびの型紙や台紙をダウンロードできます★★各あそびについて、「どの力が伸びるあそびか」「あそぶときのポイント」を国際モンテッソーリ協会0-6歳ディプロマ、保育園・幼稚園での現場経験もある北川真理子先生が解説します。製作あそびは、Instagramなどで知育あそびを発信している人気の方々が、わかりやすく紹介します。「自宅で、子どもとどうやってあそんだらよいか」「せっかくだから、子どもの発達をうながすあそびがしたい」「モンテッソーリ教育に興味があるけれど、何から始めたらいいかわからない」と感じているパパママに是非おすすめしたい1冊です! はじめに 本書の使い方 QRコード特典の使い方 序章 モンテッソーリ教育のきほん 1章 ねんねの時期のあそび 2章 指先を鍛えるあそび 3章 自分でできた!日常生活の練習 4章 分類・整理のあそび 5章 文字・数のあそび コソダチショップ おわにり クリエイター紹介 コラム 赤ちゃんの言語教育 ゆるっと「旅育」! 家事参加で無理なく子どもの力を伸ばす 自己表現の芽をつまないために
この本は、「ていねいな保育」に焦点を当て、0・1・2歳児クラスの実践例を28項目紹介しています。内容は「基本」「生活」「遊び」「支える活動」の4章に分かれ、約20の保育園やこども園を取材しています。160ページのフルカラーで、400点以上の写真を使用し、専門用語の解説やコラムも含まれています。保育者や保護者にとって、保育の理解を深めるための参考書となることを目指しています。
本書『定本 育児の百科』は、育児に関する不安を抱える人々に勇気を与える内容で、著者の医師としての経験と最新の医学知識を基に編纂されています。全3巻構成で、上巻は生後5カ月まで、中巻は5カ月から1歳6カ月まで、下巻は1歳6カ月以降を対象に、育児の基本や子どもの主体性を尊重する重要性を解説しています。1967年の初版以来、改訂を重ね、多くの支持を受けてきた育児の指南書です。
著者の小川大介氏は、中学受験のプロとして、多くの教え子を難関校に合格させてきた経験を基に、「本当に頭がいい子の育ち方」について語ります。彼は、子どもが親に見守られながら好奇心を育むことで、自ら学び成長することが重要だと強調します。本書では、子育てにおいて「否定しない」「与えすぎない」「あせらない」ことの重要性や、親が楽しむことが子どもに良い影響を与えることなど、実体験と心理学に基づく子育て法を紹介しています。
『幼稚園では遅すぎる』の続編である本書は、幼児教育に関する新しい子育て法を提案しています。著者は25年の研究を経て、母親の影響力や環境づくり、子どもの興味を引き出すことの重要性を強調しています。具体的には、母親が育児に専念することや、子ども同士の遊びを促すこと、興味を大切にすることが成長に繋がると述べています。
この書籍は、高学年から成長する子どもたちのための家庭環境や学習方法について解説しています。親が家庭でできる工夫を紹介し、子どもが成長するための環境作りや習慣、自由時間の重要性を強調しています。著者は花まる学習会の代表で、教育における実践的な知識が詰まっています。
本書は、子育てに悩むママたちが抱える罪悪感に寄り添い、自己肯定感を高めるためのガイドです。著者は子育て専門カウンセラーの福田とも花で、母親が感じる「ごめんね」という思いを理解し、その背後にある心の癖や古傷に向き合うことを提案しています。自分を許し、ダメな自分でも大丈夫と認識することで、子どもとの関係も改善されると伝えています。各章では、罪悪感の原因や子どもとの関係の見直し、ハッピーママになるための方法が示されています。
この書籍は、子どもの脳力を最大限に引き出すための0~3歳向けの育脳としつけに関する指南書です。親が日常生活で実践できる具体的な方法を示し、子どもが自分で考える力を育てるためのポイントを解説しています。内容は、規則正しい生活や安心感を与えること、遊びを通じた学び、親子のコミュニケーションの重要性などに焦点を当てています。著者は小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏で、専門用語を避けて分かりやすくまとめられています。
この書籍は、教育者でジャーナリストの羽仁もと子が、母としての経験を基に生活教育について綴った案内書です。内容は育児や家庭教育の基礎、親子の愛、教育の重要性など多岐にわたります。
この書籍は、AIが苦手とする読解力を人間が身につける方法を提案しています。親、学校、個人ができる具体的な取り組みや、実際の授業例を紹介し、大人の読解力向上法も示しています。内容には「リーディングスキルテスト」やその分析、読解力を育むための教育方法が含まれています。著者は新井紀子で、AIと読解力に関する研究を行っています。
本書は、子どもの才能を引き出すための方法をマンガ形式で紹介しています。特に、モンテッソーリ教育に基づき、子どもの「困った行動」を「輝く才能」として捉え、集中力や自立心を育むメソッドを提案。ハーバード大学の多重知能理論を取り入れた「9つの知能」を活用し、運動能力やコミュニケーション能力を伸ばすアクティビティも紹介しています。著者は乳幼児教育の専門家で、子どもの成長をサポートする具体的な方法を提供しています。
この本は、初めての赤ちゃんとの楽しい生活のための知恵や方法を紹介しています。小児科医の著者は、赤ちゃんの個性に応じた柔軟な対応の重要性を強調し、親を安心させる内容です。和田誠さんのかわいいイラストや詩も楽しめます。目次には、授乳や夜泣き、寝かしつけなど、子育てに関する様々なトピックが含まれています。著者は小児科医の毛利子来で、子育ての重要性を広める活動を行っています。
本書は「保育ドキュメンテーション」として、写真つきエピソード記録の作成方法や実例を紹介しています。ナビゲーターはカメラを持ったネコの「シャロク」で、具体的な作り方や注意点、振り返りの方法を写真とイラストを使って分かりやすく解説。初心者向けの基本型から、毎日作成している方向けの応用型まで多様な例を提供し、手書きやパソコンでの作成方法も含まれています。保育者や保護者が子どもの魅力を再発見し、楽しく共有するための内容です。
この書籍は、モンテッソーリ子育てのアプローチを通じて、イヤイヤ期やイタズラに対処する方法を解説しています。著者は、子どもを信じて任せることの重要性を強調し、心の強い子どもを育てるための具体的なアドバイスを提供しています。内容は、子どもとの信頼関係の構築や、適切な環境の整備、過剰な干渉を避ける方法など、多岐にわたります。著者はモンテッソーリ教育の専門家であり、教育者の育成にも力を入れています。
『今すぐ始められる! 0歳からのモンテッソーリ教育』の第二弾が発売され、子どもの才能を引き出す「あそび方」と適切な「ほめ方・叱り方」を詳述しています。82のあそびをジャンル別に紹介し、42のシチュエーションに基づく具体的な言葉の例も提供。Q&Aコーナーやおすすめの音楽・絵本も含まれ、伊藤美佳先生の監修で読みやすい内容になっています。子どもが楽しみながら成長する手助けをします。
汐見稔幸先生は、子どもに関わるすべての人々を支援する存在であり、保育の質向上に悩む保育士や親に新たな視点を提供します。本書では、汐見先生の考えや言葉が集められ、新しい保育指針や要領の重要ポイントも解説されています。巻頭対談や保護者の悩みに対する回答も含まれ、子どもの幸せや成長に寄与するためのメッセージが伝えられています。著者は教育学の専門家で、保育の分野での豊富な経験を持っています。
現代の社会において成功した人生を歩むためには、バランスのとれた認知的スキルと社会情動的スキルが鍵となる。本書は、人生の成功に結びつく社会情動的スキル(あるいは非認知的スキル)を特定し、そうしたスキルを育成するための方策を整理する。 まえがき 序文 謝辞 頭字語・略語 要旨 第1章 今日の世界における教育とスキルの役割 本報告書の目的 今日の社会経済的概観 今日の課題に対処するための教育とスキルの役割 結論 第2章 学習環境、スキル、社会進歩:概念上のフレームワーク はじめに 社会進歩 スキル 学習環境 結論 第3章 人生の成功を助けるスキル はじめに スキルがもたらす、より広範な恩恵 結論 第4章 スキル形成を促進する学習環境 社会情動的な発達の過程 社会情動的発達を促進する学習環境 結論 第5章 社会情動的スキルを強化する政策、実践、評価 はじめに 各国の教育目標 ナショナル・カリキュラム 学校の課外活動 評価 地方や学校レベルでの取り組み 結論 付録5A 社会情動的スキルの育成に向けた取り組み:教育制度の目標とスキルフレームワーク(国・地域別) オーストラリア オーストリア ベルギー(フランドル地域) ベルギー(フランス語地域) カナダ(オンタリオ州) チリ チェコ デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ(ノルトライン=ヴェストファーレン州) ギリシャ ハンガリー アイスランド アイルランド イスラエル イタリア 日本 韓国 ルクセンブルク メキシコ オランダ ニュージーランド ノルウェー ポーランド ポルトガル スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス(チューリッヒ州) トルコ 英国(イングランド) 米国(カリフォルニア州) ブラジル ロシア 第6章 社会情動的スキルを育む方法 政策メッセージ 本報告書の主な結果 「何が効果的か」と「実際に何が起こっているのか」のギャップ 今後に向けて 結論 あとがき コラム・図表一覧 ――第1章 今日の世界における教育とスキルの役割 コラム1.1 OECDの学習の社会的成果(SOL)プロジェクト コラム1.2 ウェルビーイングと社会進歩に関するOECDの活動 図1.1 多くのOECD諸国で若者の失業率が最も高い 図1.2 5人に1人の子どもが過体重である 図1.3 10人に1人の少年が学校でいじめられている 図1.4 投票率は低下している 図1.5 高い水準のリテラシーは肯定的な社会的成果の確率を高める ――第2章 学習環境、スキル、社会進歩:概念上のフレームワーク コラム2.1 ビッグ・ファイブ コラム2.2 パーソナリティ特性の主観的な指標:ビッグ・ファイブ尺度 図2.1 学習環境、スキル、社会進歩の関係 図2.2 個人のウェルビーイングと社会進歩のフレームワーク 図2.3 認知的スキルと社会情動的スキルのフレームワーク 図2.4 課題に対するパフォーマンスにおける動機づけ、努力、スキルの関係 図2.5 生涯にわたるスキルの発達 図2.6 認知的スキルと社会情動的スキルの動的相互作用 図2.7 学習環境のフレームワーク 表2.1 スキルを強化するための直接的投資、環境的要因、政策手段(例) ――第3章 人生の成功を助けるスキル コラム3.1 スキルの効果とスキル形成の因果過程についてのOECD縦断的分析 図3.1 認知的スキルは高等教育進学に大きく影響する 図3.2 認知的スキルは高等教育修了に大きく影響する 図3.3 認知的スキルは所得と失業に大きく影響する 図3.4 社会情動的スキルは肥満に大きく影響する 図3.5 社会情動的スキルは抑うつに大きく影響する 図3.6 社会情動的スキルは問題行動に大きく影響する 図3.7 社会情動的スキルはいじめに大きく影響する 図3.8 社会情動的スキルは被害者になるかどうかに大きく影響する 図3.9 社会情動的スキルは生活満足度に大きく影響する 図3.10 社会情動的スキルは健康に関する生活習慣因子を改善する 図3.11 社会情動的スキルの10段階ランクが高い人ほど大学進学の利益が大きい 図3.12 認知的スキルが抑うつの可能性を減少させる影響は、自尊感情の高い人のほうが大きい 表3.1 介入プログラムの多くは、目標を達成し、他者と協働し、感情をコントロールするといった子どもの能力を高めている 表3.2 生涯の成功を推進する社会情動的スキルとは、個人が目標を達成し、他者と協働し、感情をコントロールする能力を高めるスキルである 表3.3 認知的スキルと社会情動的スキルは子どもの人生の成功に貢献する 98 ――第4章 スキル形成を促進する学習環境 コラム4.1 社会情動的スキル向上のために計画されたプログラム:米国の事例 図4.1 スキルがスキルを生み出す 図4.2 今スキルを向上させることが、将来さらに多くのスキルを発達させる(韓国) 図4.3 社会情動的スキルは、社会情動的スキルだけでなく認知的スキルの蓄積も促進する(韓国) 図4.4 高いレベルの社会情動的スキルを身につけた子どもほど、新たな学習への投資からより多くの利益を得て、社会情動的スキルと同様に認知的スキルをさらに発達させる(韓国) 図4.5 現在のスキルへの投資が将来のスキル投資の利益を増加させる(韓国) 表4.1 高いレベルの社会情動的スキルを身につけている子どもほど、認知的スキルおよび社会情動的スキルにおいてより多くの新たな投資を受ける(韓国) 表4.2 社会情動的スキルの向上:有望な介入プログラム(抜粋) ――第5章 社会情動的スキルを強化する政策、実践、評価 コラム5.1 社会情動的スキルの育成に特化した教科:各国の事例 コラム5.2 社会情動的スキルを育成するためにカリキュラムを広げるアプローチ:各国の事例 コラム5.3 社会情動的スキルを育成する校内の課外活動:各国の事例 コラム5.4 学校が社会情動的スキルを評価するツール:各国の事例 コラム5.5 社会情動的スキルの評価を含む国家調査 コラム5.6 社会情動的スキルに関する教育活動を地方や地域が主導する実践:各国の事例 コラム5.7 課外活動を通して社会情動的スキルを育成するために、学校と地域社会の連携を進める取り組み:各国の事例 図5.1 ボランティアや奉仕活動の実施状況 表5.1 各国の教育システムの目標に含まれる社会情動的スキルの種類 表5.2 ナショナル・カリキュラムのフレームワークに含まれる社会情動的スキルの種類 表5.3 初等学校・前期中等学校で社会情動的スキルの育成を取り扱う教科 表5.4 社会情動的スキルの評価に対する各国のアプローチ ――第6章 社会情動的スキルを育む方法 コラム6.1 OECDによる都市部でのスキル発達に関する国際的縦断研究
この書籍は、成功に必要な「やり抜く力」(グリット)について探求し、才能やIQではなく、情熱と粘り強さが成功を決定づける要素であると論じています。著者のアンジェラ・ダックワースは、やり抜く力を伸ばす方法を自己成長や他者への影響を通じて詳述し、子育てや教育、ビジネスにおける実践的なアドバイスを提供しています。成功者の共通点を明らかにし、誰でも一流になれるメソッドを提示する内容です。
本書では、排せつ、食事、睡眠、着脱、清潔の5つの習慣について、イラストを用いて指導のポイントを分かりやすく紹介しています。著者は谷田貝公昭で、子どもの生活技術に関する研究を行っています。目次には各習慣に加え、保護者向けの情報や資料も含まれています。
『「やればできる!」の研究』は、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授による成功心理学の古典的名著で、マインドセットが成功と失敗を左右することを論じています。著者は、成長マインドセットと固定マインドセットの違いを探り、教育、ビジネス、スポーツ、人間関係におけるマインドセットの影響を解説。20年以上の研究を基に、マインドセットを柔軟にする方法や、成功するための思考法についても提案しています。
この本は、子どもの集中力や友人とのコミュニケーションに悩む親向けに、家庭での対応を変えることで子どもが成長できる方法を紹介しています。特に、モンテッソーリ教育とマインドフルネスを組み合わせることで、社会情動的スキル(自己認識や自己制御など)を育むことが重要とされています。具体的なアクティビティや声かけの方法を通じて、親子での関係を深め、ストレスや感情管理にも役立つ内容です。子育てに関するQ&Aも含まれています。
この書籍では、最先端の脳科学に基づき、子どもの脳の成長に関する重要なポイントを解説しています。特に6歳までの発達が重要であり、早寝・早起き、コミュニケーション能力の向上、遊びや栄養、しつけの方法が脳の成長に与える影響について述べています。各章では、脳を育てるための具体的なアプローチが紹介されています。
この書籍は、中学受験の成功には早期学習よりも親の適切な働きかけが重要であると説いています。著者は、子どもの成長を促すために幼少期からの準備が必要であり、遊びと勉強を融合させることが効果的だと主張しています。具体的な学習法や親の関わり方、環境作りのポイントを示し、勉強嫌いを防ぐためのアプローチを提案しています。難関校に合格した子どもたちの実例も紹介され、タイプ別の勉強法が掲載されています。
本書は、子どもを自立した個人に育てるための親の役割と子育て法を紹介しています。過剰な世話が依存心を強める中、親は子どもに考える力や「生きる力」を身につけさせるべきだと述べています。コーチングの技術を応用し、子どもが自分で考え、答えを出せるようにする方法を解説しています。著者は人材開発コンサルタントの菅原裕子で、子どもが自分らしく生きることを支援するプログラムを展開しています。
本書は、子どもが持つ「自ら育つ力」を理解し、その力を引き出すためのモンテッソーリ教育の実践方法を紹介します。0~6歳の子育てにおける親の悩みや疑問に対し、具体的な対応法を提案し、子どもを信じて育てる重要性を強調しています。著者はモンテッソーリ教師で、家庭での教育実践に役立つ情報を提供しています。
本書は、0~5歳児の発達を理解し、保育者がどのように支援できるかを学ぶための生活習慣に関するガイドです。食事、排せつ、睡眠、着脱、清潔、生活力向上の6章を通じて、子どもの生活習慣を深く理解します。
小児科専門医の著者が、母親としての経験や医学論文を基に、子育てに関する疑問や不安にQ&A形式で答える本です。内容は、頭の形やワクチン接種、食事、日常生活に関するトピックを含み、参考文献も掲載されています。著者の描いた4コマ漫画やイラストも豊富で、楽しく読める内容です。
… ー医者になりたいという夢がかなった! ー東大に主席合格! ー算数オリンピックで金メダル! 最強の実績を持つ講師陣が教える 我が子の能力を最大限に引… ー医者になりたいという夢がかなった! ー東大に主席合格! ー算数オリンピックで金メダル! 最強の実績を持つ講師陣が教える 我が子の能力を最大限に引き出す教育法 4人全員の子どもを東大理Ⅲに合格させた あのベストセラー著者・佐藤亮子ママも推薦!! 『子どもの夢を叶える子育てをしましょう!』 ~本書の主な内容~ ◆知育玩具を選ぶときに知っておくべきこと◆習い事を決めるときに知っておくべきこと ◆自己肯定感を持たせるために知っておくべきこと◆子どもを叱る時に知っておくべきこと など ◆1.知育玩具を選ぶときに知っておくべきこと 知育玩具で想像力を豊かにする ① ●子どもの頭を良くするおもちゃや知育玩具 おもちゃや知育玩具は、子供が小さい頃の教育としてとても大事なものです。賢い子に育てるためのおもちゃや知育玩具はどのようなものか? どのように選び、子供に与えていけば良いか? ・知育玩具で想像力を豊かにする ・粘土や積み木使って、指、手足を使わせる ・大量に与えるのがポイント 部屋の3分の1を玩具で埋め尽くす ・算数の土台もできる ・課題を与えて、何かを作らせる ・身の回りのすべてが知育玩具 身近な日常品も有効 鍋、おたま、石ころ ・脳を鍛えるチャンスはいつもある ・プレッシャーをかけない。一緒に遊ぶことが大切 ◆2.習い事を決めるときに知っておくべきこと ●習い事に取り組ませる際の工夫と注意点 ② 難関校に合格した子や、医者になった人たちというのは、子供の頃に習い事をしていた人が多い。では、いつ頃から、どのような習い事をすれば良いのか?親はどのように取り組んでいけばいいのか? ・なぜ習い事に取り組ませるのか? ・最初から適性を決めない。まずはやらせてみて選ぶ ・習い事はゴールを決める ・フェードアウトするのでなく目標達成させる ・中学受験を見据えて ・将来に向けて、体力と集中力がつくもの ・両方の手を使わせる ・子どもは褒めることで伸びる ◆3.自己肯定感を持たせるために知っておくべきこと ●子どもが自分の能力を信じるために親がすべきこと 子どもをほめる際の工夫と注意点 経過、過程に対してほめる 子どもが目標を持ち、その目標を達成するための行動をしていくためには、子ども自身が自分の能力を心から信じていく必要があります。そのためにも、子どもの一番近くにいる親は、子どもに対してどのような働きかけをすると良いのか? 親に褒められることは、子どもの成長にとって大きな影響を与える。そのため、子どものマインド面を培うためには、親が褒めることはとても重要。では、子どもを褒める際には、どのような工夫をすればいいのか? ■自己肯定感を身につけさせる ・できるだけ多くの成功体験をさせる ・マイナス思考の言葉を使わない ・できない理由を探すのではなく、どうしたらできるか ・プロセスをしっかり見てあげる ■ほめるときの工夫 ・幼児期は何でもほめる ・頑張った事実をほめまくる ・わかりやすくほめる ・感謝の気持ちを伝える ・抱きしめてほめる ・親のリアクションも大事 ◆4.子どもを叱る時に知っておくべきこと ●賢い子に育てるために親が意識すべき言葉使い 子どもを伸ばす親の上手な叱り方 子どもは親の言葉をよく聞いている。そのため、親の言葉は子どもの成長に大きく影響を与える。親は子ども対して、どのような言葉を選んで口にすべきなのか? 子育ての中で、子どもに対して「叱る」ときは必ず出てきます。子どもの自己肯定感を保ちながら、効果的に叱るためにはどうすればいいか? どのような時に叱ればいいのか? ■親が意識するべき言葉使い ・親の愛情を常に伝える 言葉と態度で伝える ■子どものしかり方 ・叱るときには子どもの状態を客観的に見る ■良い教材や問題集 ・両親が一番の教師 ・子どもは親を真似して育つ ・体験が一番の教材 五感で感じさせる ◆5.自主性を身につけさせるために知っておくべきこと ■自分から勉強する子どもに育てるための親の働きかけ ・自分から進んで何かをする子どもにするために ・自分で人生を切り開く大人にするために ・受験を勝ち抜くには、自分で勉強することが必須 ・勉強は楽しいと実感させるには? ・親も勉強に対して取り組んでいる姿を見せる ■自分から夢を抱く子どもにするために ・子どもが自ら「医者になりたい」と思うために ・子どもの野心を育てる ・医者の仕事を分解する ・医者になるための底力をつけさせる ・親の知識も大事 ■自主的に勉強させるには ・親に自信がないと子どもはついてこない ・なぜ勉強するのかを親子で考えてみる ・知識を身につけるだけでは説得できない ・知識を使うことの大切さ ・知識がないと思考に繋がらない ・社会に出た時の予行演習 ■好きなことをさせる ・親が望むこととのギャップ ・興味を持たせたらとことん深める ・焦らなくても大丈夫 勉強とセットで好きなことをさせる ◆6.子どもが挫折しそうになった時に 知っておくべきこと 中学受験までは、子供の学習計画を立てるのは親の仕事。子どもの学習計画を立てる上で、注意すべき点や工夫する点はどのようなことがあるのか? 共感・過去の成功体験・親が動揺しない)→過去の達成感があれば、挫折しても大丈夫。 何か問題にぶち当たった時、子どもはまだまだ経験が浅いため、心が折れて挫折してしまうことがある。挫折を防ぐためには、そばで親が励ましてあげることが必要。親は子どもをどのように励ましてあげればいいのか? ■学習計画の大切さ ・子どものモチベーションにフォーカスした計画の立て方 ・※糖尿病患者の例 ・達成感を積みかさねる 子どもは達成感がないと継続できない ・スケジュールは少ない量から組み立てる ・先取学習で自信をつけさせる ・ウオーミングアップをするとハードルが下がる ■子どもが挫折しそうになった時の対処方法 ・難しい目標にぶつかった時の対処法 ・共感して励ます ・過去の成功体験を呼び戻して自信を回復させる ・目標は先にあることを認知させる ・決して動揺しない ◆7.成長段階で知っておくべきこと 幼稚園までと小学校までの子育ての違い 小学校と中学校以降の子育ての違い 子どもの成長に合わせて、親の接し方も変わってくる。幼稚園までの子育てと、小学校からの子育てにはどのような違いがあるのか? 中学校以降の子育てにはどのような違いがあるのか? 親はどのようなことを意識すべきなのか? ■成長段階での子育て 子育てのステージ ・成長段階ごとに変えていくこと ・幼稚園では社会性を身につける 協調性、自主性、忍耐 ・自信を持たせる ・小学校以降は社会に出るための規律 ・原因と結果を意識させる 自分自身で考査する能力 ・中学 親が手を引くことを明確にする ・子どもの異性問題 ◆8.賢く育てるために知っておくべきこと ●子どもを賢く育てるための日常生活での意識 「子どもに考えさせる」,「想像させる」、「創造させる」、「表現させる」。 「オープンクエスチョン」 子どもの頭を良くするためには、一時的に何かをするするのではなく、普段から継続的に意識すべきことがあると思います。 賢い子どもに育てるためには、常日頃からどんなポイントを意識すればいいのか? ■子どもが賢くなる日常生活での意識 ・考えさせる、想像させる、創造させる、表現させる ・アウトプットさせることで自分で考え、成長につながる ・アウトプットの手段 ・会話が大切 質問は脳を働かせる ◆あとがき ■子どもの学習環境 ・勉強する雰囲気作りが一番大切 ・親が一緒にいて見守る環境 ・勉強は楽しいと親自身が思う ・親が見本になって一緒に勉強する環境
子どもが自分の気持ちや他人の気持ちに気づき、感情を調節し、他人とうまくかかわっていくためのワークブック。家庭や保育園・幼稚園、学校などで、親や先生と一緒に楽しく学べるよう、工夫をこらしたワークを満載。対象は幼児から小学校中学年程度まで。 まえがき 感情について知ろう! 1 感情とは 2 感情についての知識 3 最近の子どもたち 4 考えること、行動すること 5 感情の調節 6 感情の発達 7 感情のリテラシーの発達 8 感情の表出の発達 9 感情を育てる 10 感情を育てる方法 11 感情のカリキュラムの説明 感情を育てよう! 対象年齢:幼児から小学校低学年 01 いま、どんな気持ち? 02 友だちはどんな気持ちかな? 03 がまんするって? 04 わたしとあなたの思いは違う 05 気持ちと言葉のマッチング 06 友だちの表情を読み取る 07 負けてくやしいとき、どうする? 08 友だちを励ましてみよう! 09 気持ちを色であらわしてみよう! 10 うれしいときの顔は? 11 気持ちを巻き戻してみる 12 うまくかかわる言葉を探そう 対象年齢:小学校低学年から中学年 13 ポジティブな気持ちって? 14 大事なお友だちについて考える 15 ああ、迷っちゃう! 16 怒りのコントロール日記 17 どっちにしようか迷ったとき 18 困ったときに何をしてあげる? 19 立ち止まって考える 20 「ごめんね」の気持ちを伝える 21 こんなときどうする?ゲーム 22 物語から感情を学ぶ 23 気持ちにぴったりの言葉 24 気持ちを知ったうえでかかわる 25 心と身体はつながっている 26 友だちの言葉に耳をすます 27 怒りのレベルはどれくらい? 28 「協力」できるかな? 29 「おこりんぼうさん」になるとき 30 ノンバーバルから気持ちに気づく 31 感情コントロールスキル 32 そっと教えちゃうノート 33 入り混じった感情に気づく 34 共感力を育てる 35 状況をポジティブにとらえる 36 相手の気持ちになってかかわる 対象年齢:幼児から小学校低学年 37 「代わりばんこ」できるかな?
この書籍は、幼児向けの運動遊びに関するガイドで、全身運動やボール、マット、跳び箱、なわ跳び、鉄棒など、さまざまな運動あそびを紹介しています。各運動には、イラスト、ねらい、指導方法、注意点が詳述されており、0~5歳児向けに分かれています。著者は幼児運動学の専門家で、運動が子どもの発育に与える影響を研究しています。
この文章は、子どもの成長段階を示す目次であり、入園面接から始まり、首がすわる時期から歩行の完成、自我の発展、自制心の育成に至るまでの各段階が記載されています。著者は京都大学の准教授、田中真介です。
児童精神科医・佐々木正美氏による「子どもへのまなざし」シリーズは、乳幼児期の育児の重要性を強調し、育児に関わる人々に向けた心構えを伝える内容です。シリーズは3冊からなり、初巻では乳幼児期が人間関係の基礎を築く時期であることを解説。続編では読者の質問に答え、少年犯罪の背景やADHDの理解について触れています。最終巻では、現代社会の問題(虐待、ひきこもり、発達障害)に対する接し方を考察し、育児だけでなく人生の指針ともなる内容です。
本書は1歳児クラス向けの指導計画を解説し、年案、月案、週案、日案、保育日誌、食育計画、防災・安全計画などの書き方を豊富な文例と共に紹介しています。新保育指針に対応し、CD-ROMにはすべての計画が収録されています。著者は千葉経済大学の教授で、教育現場の経験を持つ専門家です。
「モンテッソーリ・ファーム」主宰の著者が教育内容とエッセンスを伝授、初の小学生向けモンテッソーリ本。蛸山めがねのマンガ入り。 小学生のためのモンテッソーリ教室「モンテッソーリ・ファーム」主宰の著者が、教育内容と家庭での見守り方を伝授した初の小学生向けモンテッソーリ本。マンガ家・蛸山めがねのマンガ入り。
児童精神科医の佐々木正美が、乳幼児の育児に関するアドバイスを提供する書籍。臨床経験を基に、悩む親を励ます内容が詰まっており、見出し付きで読みやすい構成。母性や父性、子どもの成長に必要な要素、遊びと勉強の関係など、多岐にわたるテーマを扱っている。持ち運びしやすいソフトカバーで、同シリーズの他の本と合わせて読むことが推奨されている。
『12歳までに「勉強ぐせ」をつける お母さんの習慣』の続編である本書は、子どもが自発的に勉強するために必要な「正しい自信」を育む方法を提案しています。著者は子育てと教育の経験を活かし、親自身の自信が子どもに影響を与えることを強調。家庭での環境作りや子どもの可能性を引き出す方法、親の自信の育て方などを解説しています。モンテッソーリ教育を取り入れたオリジナルメソッドも紹介されています。
本書は、0歳児クラス向けの指導計画(年案、月案、個人案など)や保育日誌、食育、防災・安全計画の書き方を解説し、豊富な文例を収録しています。新保育指針に対応しており、CD-ROMにはすぐに使える計画が含まれています。著者は千葉経済大学の教授、横山洋子氏です。
この書籍は、赤ちゃんとママのための睡眠改善方法を紹介しています。内容は、赤ちゃんの夜泣きの原因や、簡単な3ステップでの眠りの改善法、快適な安眠スケジュール、寝かしつけの方法、「おっぱい」と眠りの関係、夜泣きのメッセージについて解説しています。著者は夜泣き専門保育士の清水悦子と医学博士の神山潤で、赤ちゃんの睡眠に関する研究やサポート活動を行っています。
この本は、モンテッソーリ教育に基づいた紙遊びを家庭で楽しむ方法を紹介しており、子どもの自立心を育むことを目的としています。内容には、切り紙やカード作り、紙を編むなどの活動が含まれています。著者はモンテッソーリ教育の専門家であり、実践的な教育経験を持っています。
この文章は、東京都足立区の保育園での0.1.2歳児保育の質向上に関する取り組みを紹介しています。保育所保育指針の改定を受けて、5年前から始まった乳児保育の見直し実践の過程や、当初の課題を含めた内容が述べられています。具体的には、生活や遊び、環境における「当たり前」を再考することをテーマに、保育の質向上に向けた具体例が挙げられています。著者は伊瀬玲奈氏で、保育の研究に取り組んでいます。
「幼児教育」に関するよくある質問
Q. 「幼児教育」の本を選ぶポイントは?
A. 「幼児教育」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「幼児教育」本は?
A. 当サイトのランキングでは『モンテッソーリ教育で子どもの本当の力を引き出す! (知的生きかた文庫 ふ 31-1)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで160冊の中から厳選しています。
Q. 「幼児教育」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「幼児教育」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。