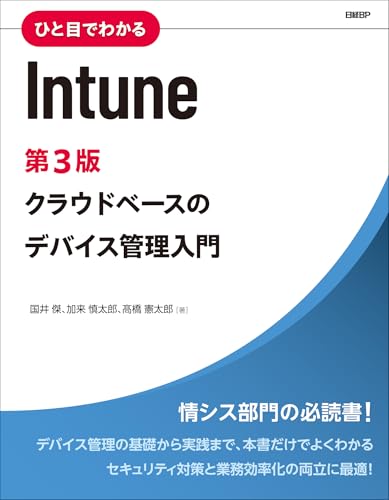【2025年】「web」のおすすめ 本 166選!人気ランキング
- ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版]
- 1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座
- なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。〉
- Photoshop しっかり入門 増補改訂版 【CC完全対応】[Mac & Windows対応]
- スラスラわかるHTML&CSSのきほん 第2版
- Webデザイン良質見本帳[第2版] 目的別に探せて、すぐに使えるアイデア集
- 確かな力が身につくJavaScript「超」入門 第2版
- 沈黙のWebマーケティング —Webマーケッター ボーンの逆襲—アップデート・エディション
- いちばんよくわかるWebデザインの基本きちんと入門 レイアウト/配色/写真/タイポグラフィ/最新テクニック (Design&IDEA)
- Illustrator しっかり入門 増補改訂 第2版 【CC完全対応】[Mac & Windows 対応]
本書は、デザイナーでない人向けのデザイン基本書で、デザインの「4つの基本原則」(近接、整列、反復、コントラスト)を解説しています。プロでなくても、魅力的なデザインやプレゼン資料を作りたい人に最適で、具体的な作例とともに原則を適用する方法を紹介しています。また、日本語版では日本語を使ったデザインの適用方法も解説されています。18年間のロングセラーで、待望の第4版です。
デザインの基本原則をシンプルかつ実践的に解説する一冊です。デザインの経験がない人でもすぐに活用できる具体的なアドバイスが豊富に含まれており、特にレイアウトやフォントの使い方については実用的な例が満載です。デザイン初心者がプロのようなレイアウトを作り出すためのヒントが詰まっており、初心者から中級者まで幅広い層に役立つ内容です。
この本は「デザイン=楽しい」をテーマに、デザイナーの思考プロセスを豊富なビジュアルで解説します。内容は、編集とデザインの関係、デザイナーの必須ツール、デザインの基本要素(文字、言葉、色、写真、グラフ)などを扱っています。著者は株式会社コンセントのアートディレクター・デザイナーの筒井美希氏です。
デザイン全く分からない自分でもわかりやすく、デザインについて知るきっかけになりました!
デザインの基本的な考え方を視覚的にわかりやすく解説する一冊です。専門的な知識がなくても楽しめる内容で、初心者にも理解しやすく、具体的なデザイン例を豊富に掲載しています。デザインの意図や効果を実際の作品で確認できるため、デザインの背景にある理論を自然に学ぶことができます。視覚的に訴える構成が魅力で、デザイナー以外の読者にもおすすめです。
本書は、429点の厳選された良質なWebサイトを集めた見本集であり、全面的に改訂されています。デザインの基礎知識や印象、配色、業種別、レイアウト、素材、トレンドなどを解説しており、具体的なデザインパーツの分析も行っています。アイデアが浮かばない時や制作に困った際に役立つ内容で、デザイン制作に活用できる実例を提供しています。
この書籍は、JavaScriptを初めて学ぶ人や過去に挫折した人向けに、実践的なサンプルを通じて基礎力を身につけることを目的としています。楽しいサンプルを提供し、初学者がつまずくポイントを丁寧に解説することで、挫折を防ぐ内容になっています。第2版では新しいECMA Scriptの機能を取り入れ、情報を最新のものにアップデートしています。特にWeb業界に興味がある人やフロントエンドエンジニアを目指す人におすすめです。著者はUIデザイナーであり、実務経験を活かした内容が特徴です。
この書籍は、Webマーケティングの基本を理解できる内容で、人気のWebコンテンツにオリジナルの解説を加えています。目次には、SEO、Webデザイン、ライティング、SWOT分析、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディア運用など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者はWebライダーの松尾茂起と、イラストレーターの上野高史です。
Webマーケティングといえばこの書籍。ストーリ形式でWebマーケティングについて学べるのでサクサク読めてそれでいてWebマーケティングのエッセンスがギュッと詰まっている。それもそのはず超有名マーケターのWebライダー松尾氏が著者。Webマーケティングを学びはじめた初学者はまず手にとって欲しい書籍。ちなみにWebマーケティングの中でもかなりSEO・オウンドメディア運営にフォーカスしているので広告などについて学びたい人には向かない。
この書籍は、Webデザインを学びたい初心者向けの入門ガイドで、レイアウト、配色、写真、タイポグラフィ、HTML5、CSS3、インタラクション、マーケティングなどの基礎知識を網羅しています。実例を交えながら、プロ仕様のWebデザインを作成するためのテクニックを解説しており、一生使えるスキルを身につけることができます。著者はWebデザインやマーケティングの専門家です。
本書は、PCおよびモバイルサイトのデザインとHTML・CSSコーディングを同時に学べる入門書です。架空のカフェサイトを作成しながら、基本的なHTML要素とCSSの構造を理解し、5つのレイアウトパターンやレスポンシブデザインの技術を習得します。チュートリアル形式で、実践的なテクニックを体験しながら学べる内容となっており、特典としてレスポンシブデザインやポートフォリオ作成の参考資料も付いています。著者は、ウェブ制作の専門家であり、多様なプロジェクトに関与しています。
このガイドブックは、フロントエンドエンジニアやWeb制作に関わる人々のために、HTML5とCSS3の最新仕様とその実用的な使い方をまとめたものです。内容は、基本設定からボックスモデル、フレキシブルボックスレイアウト、グリッドレイアウト、主要ブラウザの対応状況まで幅広くカバーしており、制作現場で必携の一冊となっています。
この書籍は、Webサイト制作の決定版としてリニューアルされ、HTMLとCSSの基本から最新技術までを体系的に学べる内容です。著者Manaは、Webデザインの専門家であり、初心者向けに手を動かしながら学べるテクニックを提供しています。モバイルファーストやアニメーションなどのトレンドも取り入れ、5年間の最新情報が追加されています。本書は、Webサイト制作を始めたい人や美しいデザインを学びたい人に最適です。
この本は、デザインにおける「余白」の重要性を解説し、カフェ、ビジネス、和もの、化粧品、季節もの、ラグジュアリーなど多様なデザインのレイアウト例を紹介しています。デザインの基礎を学ぶための実用的なガイドです。
余白がもたらすデザインの効果を深く掘り下げた一冊です。余白の取り方一つでデザインの印象が大きく変わることを、多彩な事例を通して解説しています。視覚的なバランスや、情報の整理の仕方に焦点を当てており、シンプルで洗練されたデザインを目指す人にとって必携のガイドブックです。余白の重要性を理解することで、よりプロフェッショナルなデザインが可能になります。
本書は、Webサイト制作を学ぶ初心者向けの入門書で、HTML/CSSとWebデザインの基本を手を動かしながら楽しく学べる内容です。4種類のサイトを制作しながら、FlexboxやCSSグリッド、レスポンシブデザイン、CSSアニメーションを習得できます。また、学習の進め方や重要なポイントも紹介されており、知識ゼロからでも自分で学びを深められるようになります。特典として、サンプルデザインデータや公開方法のPDF、役立つサイト集、初学者用のチートシートが付いています。著者はWeb制作の専門家で、実践的な知識を提供しています。
HTML初心者です。勉強してみようかなと思って手に取ったのがこの本です。文章だけだと難しい内容ですが、QRコードで動画解説のあるところなど実際にPC画面が動くところを見ることができるので読みやすいです。
本書は、Adobe XDを使用してWebデザインとUIのプロトタイピングを学ぶためのガイドです。ワイヤーフレーム制作からデザインカンプ、インタラクティブなプロトタイプの作成、コーディングに必要なデザインスペックの共有まで、実践的なスキルを身につけることができます。初心者や経験が浅いデザイナー、グラフィックデザインからWebデザインに転向したい人に最適な内容です。全10章で構成され、具体的な制作手順が示されています。
この書籍は、ウェブサイト制作者を目指す人のための入門書で、HTMLとCSSの基本からサイト制作、公開・管理方法までを15のレッスンで解説しています。各レッスンは実習ファイルを用いて、手を動かしながら学ぶ形式で構成されており、著者陣は専門学校の講師です。最新エディタ「Visual Studio Code」に対応した改訂版で、基礎力を身につけることができる内容となっています。
この書籍は、Webマーケティングからデジタルマーケティングへの入門書で、ネット活用の基本を解説しています。目次には、ページビューの重要性や顧客理解、トラブル対応などが含まれています。著者はデジタルコンテンツ制作会社の創業者であり、複数の企業でマーケティングに携わった経験を持つ村上佳代と、漫画家の星井博文です。
本書は、タイポグラフィにおけるレタースペーシング(文字間調整)を論理的に解説したもので、デザイナー向けの実用書です。感覚的に扱われがちなレタースペーシングを、基礎知識から具体的な事例までを通じて学びます。内容は、レタースペーシングの基本、和文・欧文・和欧混植の具体的な調整方法、実例の分析、練習問題などで構成されています。デザインの質を左右する重要な要素を理解し、実践的なスキルを身につけるための一冊です。
「これからはじめるPhotoshopの本」2022年最新版は、Photoshopを学びたい初心者向けのガイドです。基本操作や写真の補正、加工、合成、ポストカード作成など、幅広い内容が含まれており、付属の練習ファイルを使って楽しく学べます。著者はデザインと教育に関わる専門家で、短時間で基本をマスターできる構成になっています。
コレ一冊読めばWeb技術の基本が分かる!新しいテクノロジーが登場しても基本となるWebの技術は非常に大事だし活きる!IT系の仕事に付く人はまずこの書籍を読んで基本を固めるべし!
この本は、Webページデザインを「ボックスを並べること」と捉え、ボックスのレイアウト手法を詳しく解説しています。ブログ・ニュース系サイトとビジネス系サイトの実例を用いて、パーツの組み立て方やスマートフォン対応のテクニックを紹介しています。目次には、段組みやサイト作成の準備、各種ページの具体例が含まれています。
この書籍は、最新のWebサイト制作技術を学べる内容で、手描きやグラデーション、JavaScriptライブラリを使ったアニメーションなど、自由な表現方法を紹介しています。目次には、レスポンシブデザインや装飾、フォーム作成、動画の使い方など、さまざまなWebサイトの制作方法が含まれています。著者は、グラフィックデザイナーとしての経験を持ち、現在はWeb制作のインストラクターとして活動しています。
この本は、Photoshopの基本を楽しく独学できる内容で、特に初心者向けに設計されています。著者は人気の教育系YouTuberで、基本的な機能「レイヤー」「フィルター」「ツール」を理解することで、Photoshopを効果的に使いこなせるようになることを目指しています。実践編では、写真の補正やデザインの際に役立つテクニックも紹介されており、学び直しにも適しています。全体を通じて、楽しく学べる工夫が施されています。
本書は、デザインの基本原則と新しい考え方を学ぶことで、一生使えるプロの技術を身につけることができる内容です。レイアウトの基本ルールとトレンドを組み合わせることで、優れたデザインを作成できるようになります。対象読者は、レイアウトを学び始める人や本気で学びたいデザイナーです。目次には、レイアウトの影響、基本ルール、応用テクニック、実際のデザイン作成方法が含まれています。著者は、デザインや編集に関する豊富な経験を持つ専門家です。
この本は、HTMLとCSSの主要なタグやプロパティに焦点を当てたリファレンスガイドです。最新のブラウザやHTML Living Standardに対応し、目的別に整理されているため、簡単に引きやすく、持ち運びに便利なポケットサイズです。内容は、HTMLの基本、HTMLリファレンス、スタイルシートの基本、CSSプロパティリファレンスなどが含まれ、Webサイト制作や運営に役立つ情報が凝縮されています。著者はフリーランスのHTMLコーダーとライターです。
この書籍は、プロ志向のHTMLを学ぶための包括的なガイドです。ウェブデザイン制作に役立つ知識を深め、基本的なウェブサイトの仕組みから、アクセシビリティやユーザビリティを考慮したコーディング技術までを学べます。現役講師による会話形式の解説で、初心者でも挫折しにくく、ゼロから自力でHTMLを書く力を身につけることができます。内容は、HTMLの基本構造、テキストマークアップ、リンクやコンテンツの埋め込み、表とフォームの作成、ページ構造の整理、より良いページ作りなど多岐にわたります。著者はウェブデザイナーの柴田宏仙氏で、実践的な学習が可能です。
本書は、HTMLやCSSの基本を学びながら、4つのレイアウトパターンとレスポンシブデザインを実践的に習得できる独習書です。ライブ感のあるチュートリアル形式で、実際のWeb制作現場で役立つテクニックを紹介し、サンプルサイトを作成することで学びを深めます。著者は、Web制作やデザインに関する豊富な経験を持つ服部雄樹氏です。サンプルデータのダウンロードサービスも提供されています。
この書籍「ULSSAS(ウルサス)」は、SNSマーケティングの基本を解説し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)とULSSASという概念を活用して、商品やサービスの購入につなげる方法を紹介しています。著者の飯高悠太は、SNS時代における情報伝播の流れを示し、実際に効果的なマーケティング手法を提案します。内容はSNS活用とコンテンツマーケティングの2部構成で、具体的な戦略や考え方が述べられています。
本書は、HTMLの基礎知識を持つ初心者や中級者を対象に、HTMLを深く学ぶための内容を提供しています。シンタックスとセマンティックスの理解を重視し、静的なウェブページから動的なウェブアプリケーションまでの設計能力を高めることを目指しています。また、HTML仕様を理解するための前提知識や、アクセシビリティやセキュリティに関する情報も含まれています。内容は、基本概念、マークアップルール、主要要素、属性とWAI-ARIAに分かれており、実践的な知識を得ることができます。
この配色本は、3色の組み合わせに特化しており、配色が苦手な人でも簡単におしゃれなデザインができるアイデアを提供しています。全ての配色例にはデザイン作例と色の面積比が示されており、バランスの良い配分も理解できます。ファッションやイラスト、チラシなど幅広いシーンで活用できる配色が紹介されており、自然体やカラフル、エレガントなどのカテゴリーに分かれています。
この本は、フォントの使い分けやデザインの重要性を解説しており、魅力的な文字デザインがどのように効果を生むかを示しています。内容は、カフェやビジネス、カジュアルなど、さまざまなデザインスタイルに焦点を当てています。フォントを選ぶことがデザインの武器になることを伝えています。
フォントの魅力とその活用方法を中心に紹介するデザイン本です。フォント選びの重要性や、それが与える印象の違いを丁寧に解説しており、デザインにおいてフォントがいかに大切な役割を果たすかが実例を通して理解できます。多様なフォントの選び方や使い方を知ることで、デザインの幅を広げたい人にとって非常に有用な参考書です。
この本は、知識ゼロからでも理解できるように、jQueryの基本から実務で役立つテクニックまでを丁寧に解説しています。著者はトップクリエイターで、わかりにくいポイントを押さえた内容で、確かな基礎力と実践力を身につけることができます。目次には、jQueryの基礎知識、簡単な入門、基本的な書き方、必修テクニック、ギャラリーページの作成、さまざまな表現方法などが含まれています。
本書は、Web開発におけるCSSの設計方法について解説しています。特に、BEMやSMACSSといった設計手法や、デザイナーとの連携方法、Sassなどのツールを用いたビルドプロセスに焦点を当てています。実務に入る人や現場で悩む人に向けて、破綻しないCSSを組むための思考法を育てる内容となっています。著者はWeb制作の専門家で、実践的な知識を提供しています。
本書は、Webサイトの売り上げを向上させるための「マイクロコピー」の重要性を解説した日本唯一の入門書です。たった2文字の変更で売り上げが1.5倍になることもある具体例を挙げ、ボタンやフォーム、エラーメッセージなどの細部の文言改善方法を豊富な事例と共に紹介しています。第2版では最新の事例が追加され、即効性が高められています。著者はデジタルマーケターの山本琢磨氏で、多数の企業に対して成功事例を基にしたコンサルティングを行っています。
本書は、Webサービスの実践的な設計に焦点を当てています。HTTPやURI、HTMLの仕様を歴史や設計思想とともに解説し、Webサービスにおける設計課題やベストプラクティスを紹介しています。目次は、Web概論、URI、HTTP、ハイパーメディアフォーマット、Webサービスの設計、付録から構成されています。
本書は、MFI(モバイルファーストインデックス)時代におけるSEOの知識と技術を網羅したガイドです。SEO施策の背景、考え方、実装方法を解説し、マーケティング担当者やエンジニアに役立つ内容となっています。構成は、SEOの基本から始まり、マイナス評価の回避、サイト構造、Googlebotの制御、セマンティックマークアップ、サイトの高速化、モバイル対応、コンテンツSEO、リンクビルディング、モニタリング・保守まで多岐にわたります。著者はSEOやデータ解析に精通した専門家で、実践的な施策を具体的に紹介しています。
『レイアウト、基本の「き」』は内容を見直し、20ページ以上増補して新たに出版された書籍です。目次にはレイアウトの視覚的要素や全体構成、書体、写真・イラスト、チャート・地図・表・グラフ、色の選び方が含まれています。著者の佐藤直樹は、アートディレクターやデザイン会社の設立者としての経歴を持ち、教育機関での講師も務めています。
この書籍は、文章が書けない理由と、書くための実践的なメソッドを紹介しています。著者はニュースメディアで新人教育を担当しており、書ける人が自然に行っている基本を誰でも学べるように伝授します。企画書や報告書、ブログなどに役立つ内容で、特に言いたいことが伝えられない、書き始めが分からない、書き終えられない人におすすめです。ポイントとしては、事前に計画を立てることや構成の工夫、読み返しの重要性などが挙げられています。
本書は、HTML、CSS、JavaScriptを用いたフロントエンド開発の技術を包括的に学べる一冊です。Webサイト制作とWebアプリケーション開発の違いを理解し、エンジニアが共通して知っておくべき技術やスキルアップの方向性を示します。初心者から経験者まで幅広く役立つ内容で、開発現場のワークフローを疑似体験しながら、最新のフロントエンド技術を習得できることを目指しています。全6章で構成され、実践的な知識と技術の向上を促進します。
本書は、オープンソースのテキストエディタVisual Studio Code(VSCode)を初心者から中級者向けに解説したガイドです。Webクリエイターやプログラマー、日常業務でVSCodeを利用したい人々に向けて、基本操作からカスタマイズ、効率的な使い方、さらにGitの利用方法までを丁寧に説明しています。WindowsとMacに対応しており、ユーザーがVSCodeをより便利に活用できるようサポートします。
この書籍は、デジタルマーケティングにおける「定石」を整理し、成果を上げるための施策パターンを詳しく解説しています。内容は、デジタルの特性や限界、各フェーズにおける定石の理解、そしてそれをビジネスモデルに適用する実践方法に分かれています。著者は、デジタルマーケティングの専門家であり、AIを活用した分析ツールの開発にも携わっています。
本書は、著者が発信してきたWeb制作のTipsをまとめたもので、HTMLやCSSの基礎を学んだ人を対象に、デザインを実装するための具体的な方法を解説しています。70種類のデザインパターンを紹介し、コーディングの最適化や短縮化の方法も学べます。各章では、背景やテキスト装飾、レイアウト、ボタンデザインなどのテーマに沿った情報が提供され、サンプルコードが特典として配布されるため、すぐに実装可能です。
Figmaは、デザインプロセスを効率化し、チームがデジタルプロダクトを迅速に提供できるデザインコラボレーションツールです。2012年にサンフランシスコで誕生し、シンプルな操作性と共同編集機能が特徴です。本書では、Figmaの基本操作からチームでのペアデザインの実践まで、ポートフォリオサイト、コーポレートサイト、ECサイト、レシピアプリの4つの作例を通じて学べる内容となっています。日本語化にも対応しており、初心者でも安心して利用できます。著者は株式会社neccoのクリエイティブチームで、デザインやウェブ制作に豊富な経験を持つ専門家たちです。
本書は、商品やサービスを「売る」ための文章術を解説したロングセラーのセールスライティングの指南書です。1985年の初版以来、豊富な事例を基にしたコピーの書き方やテクニックが紹介されており、約10年ぶりの改訂版ではデジタルマーケティングに関する内容も追加されています。対象読者はコピーライターやマーケティング担当者などで、広告の原則から最新のデジタル手法まで幅広くカバーしています。著者はロバート・W・ブライで、40年以上のキャリアを持つ経験豊富なコピーライターです。
本書は、2万回のA/Bテストから厳選した実例を基に、ユーザーに支持されるUIデザインを解説する内容です。実際のテスト結果をもとに、成功したデザインと失敗したデザインを比較し、ユーザーのニーズを明らかにします。具体的な事例が35件掲載されており、A/Bテストの概要を知りたい読者にも適しています。著者の鬼石真裕は、様々な企業での経験を持つ専門家です。
この書籍は、実践的なGit/GitHubの使い方を学ぶための初心者向け入門書です。前半では基本的な操作を解説し、後半ではチーム開発のための知識を身につける内容となっています。コマンドライン操作が中心で、新しいGitコマンドやGitHubの機能、実務で役立つ慣習も紹介されています。著者はエンジニア経験を持つ専門家で、ワークショップ感覚で学べる構成になっています。
この文章は、特定の書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、道具の精神病理学や行為の心理学、知識の理解、デザインの重要性、ビジネスにおけるデザイン思考など、さまざまなテーマが含まれています。著者は、工学やデザイン、認知科学などの分野で専門性を持つ学者たちであり、それぞれの経歴や研究関心についても述べられています。
この書籍は、レイアウトデザインの基本とルールを網羅した初心者向けのガイドです。版面率やグリッド、ジャンプ率などの重要な概念を解説し、豊富な実例やイラストを通じて理解を深められます。内容は基本理論から具体的な実例まで幅広くカバーしています。
本書は、外資系コンサルタントが身につけるべーシックスキル30個を紹介し、職業や業界を問わず役立つ普遍的なスキルを提供します。新人からベテランまでが使える内容で、15年後にも通用する能力を身につけることを目的としています。著者は自身の経験と元コンサルタントへの取材を基に、実践的な技術や思考法、デスクワーク術、プロフェッショナルマインドを解説しています。
本書は「5W1Hマネジメント」と題し、When、Who、Where、What、Why、Howの視点から人とチームを効果的に動かす18の技術を紹介しています。単に質問を投げかけるのではなく、的確な問いを通じて部下の思考を促し、VUCA時代の複雑な問題に対応するためのマネジメントツールとしての活用法を提案しています。著者はビジネスコンサルタントの渡邉光太郎氏で、豊富な経験を基にした実践的な内容が特徴です。
この書籍は、就職テスト対策の定番であり、特にSPIテストの主要3方式(テストセンター、ペーパーテスト、Webテスティング)に対応しています。過去の出題傾向を踏まえた問題が収録されており、初心者でも理解しやすい講義形式の解説が特徴です。また、問題と解説が見開きで配置されているため、電子書籍版でも使いやすい設計になっています。内容は非言語、言語、性格検査の完全攻略を含み、就職活動をサポートするための情報が豊富に提供されています。
超有名なブロガー2人が運営するブログサロンの内容を元にWebライティングについて分かりやすくまとめてくれている書籍。これ1冊読んでおけばWebライティングに関しては全く問題ないと思う!手元においておきたい1冊。
沈黙のWebマーケティングに続いて2作目となる本書。1作目を読んでハマった方はぜひこちらの2作目も読んでみて欲しい。ストーリ形式で分かりやすくSEOライティングについて学べる
この書籍は、デザインセンスを身につけたい人のための実用書で、センスがない人でも簡単に理解できるように構成されています。ビジネスや日常生活に役立つデザインの法則やルールを紹介し、レイアウト、配色、フォントなどの基本セオリーをビジュアルでわかりやすく解説しています。著者は株式会社日本デザインの代表、大坪拓摩です。
本書は、Web系エンジニアになるための包括的なガイドです。IT業界の基盤が確立され、プログラミング教育が普及する中、特に需要が高まっているWeb系エンジニアの職業について、必要な知識やキャリアステップを解説しています。内容は、Web系企業の定義や職種、使用する技術、働き方、フリーランスへの道、キャリア形成の戦略など多岐にわたります。初学者や駆け出しエンジニアがWeb業界の全体像を理解し、必要なスキルを把握できる一冊です。著者は豊富な経験を持つエンジニアで、実体験に基づいた情報を提供しています。
Webデザインの作業フェーズ・業務シーンごとに、 「Adobe Photoshop」と「Adobe Illustrator」の 便利な使いこなし方やノウハウを解説する本です。 Webにまつわるビジュアルをより魅力的なものにするために、 あるいはWeb制作を効率的に行うために必要となるテクニックを 目的に沿って作例を用いながら解説します。 Webデザイン初心者、Webデザインに活動範囲を 広げたいと考えているグラフィックデザイナーはもちろん、 簡単な素材の制作や写真加工を行う必要があるプログラマーや コーダーにとっても有益な内容です。 Adobe Creative Cloud 2020/2019対応。 ※教材データはインターネットからダウンロードする必要があります。 【CONTENTS】 ●CHAPTER 1 Webデザイン+Photoshop+Illustratorの基礎知識 印刷物のデザインとは違ったセオリーやルールなど、 Webデザインの基礎知識について解説! ●CHAPTER 2 ワイヤーフレーム制作で使えるテクニック Webページに要素をどう配置するのかを表した大枠(ラフレイアウト)である 「ワイヤーフレーム」制作の際に役立つテクニックについて解説! ●CHAPTER 3 画像処理に使えるテクニック 印刷物のデザイン時にも活用できる基本的な画像の補正や加工から、 Webの機能を盛り込んだ表現まで幅広く解説! ●CHAPTER 4 パーツ制作で使えるテクニック アイコンやロゴ、囲み罫、背景パターン、バナーといった Webページを構成するパーツを効率よく制作する方法を解説! ●CHAPTER 5 カンプ制作で使えるテクニック 補正や加工を施した画像や、作成したパーツを組み合わせて デザインカンプとして仕上げる際に必要なテクニックを解説! ●CHAPTER 6 コーディン向けに使えるテクニック 編集・作成した画像、パーツ、デザインカンプなどをWebページに適した形式や、 コーディングに適した状態で書き出す際のテクニックについて解説!
本書は、SPIのパソコン受検版であるテストセンターに特化した対策本です。2024年から実施企業が増加し、2022年10月からは自宅受検も可能になりました。テストセンター、ペーパーテスト、Webテスティングでは出題範囲が異なるため、特にテストセンター対策を重点的に行います。内容は受検の流れや効果的な対策、最新の問題傾向を含み、見開きで問題と解答を掲載することで使いやすさを追求しています。2027年度版として更新された情報を基に作成されており、幅広い受検者に対応しています。
本書は、レガシーコードの問題を解決するための9つのプラクティスを紹介し、初めから質の高いコードを作る方法を解説しています。レガシーコードはバグが多く、管理が難しいため、事前に適切な開発手法を取り入れることが重要です。具体的には、目的を明確にし、開発を小さなバッチで進めること、継続的な統合、チームの協力などが提案されています。信頼性と拡張性の高いソフトウェアを目指す開発者やマネージャにとって必携の一冊です。
本書は、プロジェクトマネジメントを実践する人向けに、84のテーマを通じて基本的な知識、技術、思考を解説しています。直感的に理解できるように、見開きで解説と図・イラストを掲載。ガントチャートなどの基本ツールも実例を交えて紹介し、実践しやすさを重視しています。また、リーダーシップなどの「人間力」についても触れ、プロジェクト成功に必要な知識と技術を学べる内容です。企業が求める「プロジェクトマネジメントができる人財」になるためのスキル向上を目指します。著者は日本プロジェクトソリューションズ株式会社の代表で、プロジェクトマネジメント教育に携わっています。
本書は、Pythonを使用したデータ収集技術「スクレイピング」の入門書であり、待望の第2版が登場しました。著者はヤギ博士とフタバちゃんと共に、ファイルのダウンロード、HTML解析、データの読み書き、APIを利用したデータ収集、データの可視化方法を解説します。Python 3.12に対応し、各種ライブラリやオープンデータのアップデートが含まれています。初心者向けに対話形式で基礎知識を学べる内容で、実践的なサンプルも用意されています。対象はデータ収集や分析に興味がある初心者です。
この書籍は、Webサイトで成果を上げるための文章の書き方をストーリー形式で学ぶ実用入門書であり、特にSEOに強いライティングに焦点を当てています。目次には、SEOライティングの基本や独自の強み(USP)の活用、リライトや推敲の重要性、オウンドメディアの活用法などが含まれています。著者はWebマーケティングの専門家であり、音楽活動も行っています。また、イラストレーターも参加しており、視覚的な要素も重視されています。
沈黙のWebマーケティングに続いて2作目となる本書。1作目を読んでハマった方はぜひこちらの2作目も読んでみて欲しい。ストーリ形式で分かりやすくSEOライティングについて学べる
この書籍は、WebサービスのUI/UXデザインに必要な基本要素(文字、色、写真、装飾、配置)を解説しており、デザインのロジックを理解することでデザインへの恐怖を和らげることを目的としています。目次には、ITシステムのデザインの重要性、デザイン思考のプロセス、タイポグラフィ、情報整理、ビジュアル表現、レイアウト、色彩の基本と調和、実践的なコツなどが含まれています。著者の伊藤博臣は、広告やUI/UXデザインの専門家であり、クライアントの売上向上に貢献しています。
この書籍は、Webデザインの基本ノウハウを紹介しており、初心者向けに進化し続けるWebデザインの技術を解説しています。目次には、Webデザインの基礎、制作ツール、サイトのプランニング、CSSによるレイアウト、魅力的なページ作成のためのテクニックなどが含まれています。著者はアートディレクターでありWebデザイナーの加藤才智氏です。
ロゴ&マークのつくり方。 : 大黒大悟/梅原真/木下謙一/青木克憲/秋山具義/山野英之/山﨑晴太郎/小杉幸一/木住野彰悟/川上恵莉子/水野学/村上要×佐藤可士和ほか
本書は、初心者向けの全面改訂版Webデザイン入門書で、HTMLやCSSの基本から最新のレスポンシブデザインまでを学べる内容です。30のレッスンで「講義」と「実習」を通じてスキルを身につけ、サンプルソースをWebからダウンロード可能。特典PDFも提供され、Web制作を始める人に最適な一冊です。著者はフリーランスのWeb制作専門家であり、初心者向けセミナーの講師も務めています。
著者による日本で最も売れているJavaScriptの本が、7年ぶりに大幅改訂され、ECMAScript 2022に対応した内容で200ページ増となりました。基本文法から応用トピックまで幅広く解説し、特にオブジェクトの扱いやオブジェクト指向構文に重点を置いています。JavaやC言語などの他のプログラミング言語の経験がある方や、JavaScriptを学びたい方におすすめです。目次には、基本的な書き方、演算子、制御構文、組み込みオブジェクト、関数、オブジェクト指向、DOM操作などが含まれています。
この書籍は、Webライター初心者向けの入門書で、文章作成の基本やノウハウをプロが伝授します。文章がうまく書けない、読まれないと悩む人々に向け、実践的なテクニックや例文、練習問題を提供。目次にはライティングのチェックポイントやキャッチコピー、メール活用術などが含まれ、成果を上げるための方法を学ぶことができます。著者はコンテンツマーケティングの専門家で、豊富な経験を持つライターたちです。
この書籍は、Webデザイナー向けにPhotoshopやIllustratorを用いたデータ作成や納品時の指示方法についての正しい手法をまとめたルールブックです。内容はWebデザインの基本ルール、デザインデータの問題点、わかりやすい納品データの作成法、PhotoshopとIllustratorの効果的な使い方に分かれています。
この書籍は、日本インダストリアルデザイナー協会(JIDA)によって編纂されたプロダクトデザインの基礎知識をまとめたもので、デザイン思考が生活や仕事に与える影響を探ります。内容はプロダクトデザインの背景、社会との関係、ビジネスとの関連、デザインプロセス、ユーザ調査、コンセプト作成、視覚化手法、デザイン評価、マーケティング、技術とデザインに関する章で構成されており、プロダクトデザイン検定2級の公式テキストとしても利用されます。
この本は、ホームページ作成の基礎を学ぶためのガイドで、HTMLの書き方、画像の扱い、サーバーでの公開、検索エンジンへの登録方法を詳しく解説しています。目次には、準備、作成、公開、デザイン、無料ツールの利用、HTMLとCSSのリファレンスが含まれています。
本書は、レスポンシブWebデザインに対応した最新のHTML・CSSの書き方を解説するガイドです。スマートフォン時代に必要な考え方と実践的なテクニックを豊富なサンプルコードを通じて学べる内容となっています。対象読者は、Web制作を学びたい初心者や最新の技術を知りたい経験者、フレックスボックスによるレイアウトに興味がある方です。内容は、Webサイトの仕組みからHTML・CSSの基礎、テキストやリンク、ボックス、テーブル、フォーム、ページレイアウト、レスポンシブデザインまで多岐にわたります。著者はUIデザイナーの狩野祐東氏です。
本書は、デザイナーやアートディレクター向けにタイポグラフィの基礎知識を解説しています。具体例を交えながら、文字を美しく見せるためのテクニックや、9つの基本レイアウトパターン、10種類の演出スタイルを紹介。目次には、タイポグラフィの素材、基本テクニック、レイアウトスタンダード、書体の選び方、文字の作り方が含まれています。
初心者向けデザインシリーズ「デザインの学校」から、最新版「これからはじめる Illustratorの本」がリニューアルされました。この本は、作例を通じて短期間でIllustratorの基本操作を習得できる内容で、プロも利用する機能をわかりやすく学べます。目次には、イラスト、ロゴ、名刺、地図、ポストカード、SNSのヘッダー画像の作成方法が含まれており、楽しく学べる入門書です。
本書は、Webエンジニアを目指す人や2~3年目のエンジニア向けに、必要な知識やスキルを解説しています。最新の技術動向に基づき、開発環境の構築、データベース、バックエンド、フロントエンド、インフラ、セキュリティについて広範に紹介。著者は、豊富な実務経験を持つ専門家たちで構成されています。この本を通じて基礎を学び、将来的な技術の変化に対応できる力を養うことを目指しています。
あらゆるネットビジネスの手順・手配方法の手引書 Webサイト制作から運用に伴う各種手続きまで、これ1冊で心配ご無用!Webサイトでのビジネスを展開したい事業担当者に向けた、作業や手続き、フロー、アウトソーシングの発注の仕方など、Webサイト制作および運用にまつわる全てのタスクを完全図式化して網羅する「制作・運用のバイブル」です。Web制作・運用における作業段階を時系列で並べ、見開き単位でアイコンや図解で解説、読んで考えさせるのではなく、実際の作業に必要なポイントをほぼ見るだけで把握できます。コロナ禍による「新常態」をきっかけに、Webサイトを介したビジネスは業種問わず必須になりました。リアルでの商売だけでは切実な問題が発生しており、Webサイト構築での新しい商売を生み出さなければならない状況です。しかし、いざ「Webサイトを立ち上げよう!」「Webを使ったビジネスを始めよう!」と思っても、何から手をつけていいか、実際にプロジェクトが進行していても本当にこれでやり残しはないか、問題ないか心配になる方は多いはず。●Webサイトの作り方・運用の仕方をイチから「すぐに」「一通り」把握したい!●多様化するユーザーのタッチポイントや動向にスピーディに対応した施策を次々と打ち出していきたい!●セキュリティやコンプライアンスなど、Webサイト制作の周辺も落ち度なく進めたい!そんな方にオススメです。
本書は、Webサイト制作のプロセスを体系的に紹介し、デザイナーがワイヤーフレームからデザインカンプに至るまでの試行錯誤を解説しています。クライアントへのヒアリングやデザイン調整の過程を通じて、デザイナーの意図や考え方を明らかにし、より良いWebサイトを作るためのチェックポイントも提供しています。著者は株式会社BISCOMの代表で、Webデザインに関する豊富な経験を持っています。
この書籍は、デザイン初心者でも理解できる「売れる」WEBデザインのルールを紹介しています。顧客心理を基にしたデザイン思考と実践法を学び、魅力的なサイト作りを通じて売上を向上させる方法を解説しています。著者は、実績のあるWEBデザイナーで、成功したネットショップの運営経験を持つ野口哲平氏です。
本書は、スマートフォン対応のWebサイト制作に特化したHTMLとCSSの入門書です。実際のWeb制作トレンドを反映し、ステップ・バイ・ステップで基本文法や役割を学べる構成になっています。内容は、Webサイトの準備から始まり、HTMLやCSSの基本、ページの作成、PC対応、最終的な公開までを網羅しています。初心者やスキルアップを目指す人に最適な一冊です。著者はWebエンジニアやデザイナーとしての豊富な経験を持っています。
著者の東香名子が、Webライティングの法則を解説し、1万PVから650万PVに成長させた経験をもとに、効果的な文章作成法を紹介する書籍です。内容は、ターゲット設定やヒットタイトル作成、記事のクオリティ向上、ネタの増やし方など多岐にわたり、巻末には読者のクリック率を向上させるためのキーワードリストも収録されています。
本書は、52歳でリストラされた著者が売れっ子ライターに転身した経験を基に、ライターを目指す人々に向けた入門書です。ライティングの副業から本執筆まで、50のポイントを通じて、どんな逆境にも負けない「自分」を武器にする働き方を提案します。人生100年時代をしなやかに生き抜くための心構えや秘訣が紹介されています。
本書は、全米で「マーケティング・バイブル」と称されるジェイ・エイブラハムのベストセラーの新訳版で、経営者向けに具体的なマーケティング戦略を提供しています。著者は1万人以上の経営者を指導した実績があり、ビジネスの本質やインターネット活用法を含む重要な内容が復活翻訳されています。全体で17章から成り、収入増加や成功を手に入れるための具体的な方法を解説しており、実践すれば売上アップが期待できるとしています。
この書籍は、JavaScriptを用いたWeb開発のためのレシピ集で、基本的な文法からプロ向けのテクニックまで幅広くカバーしています。内容は目的別に整理されており、初心者から中級者まで利用でき、ECMAScript 2018に準拠しています。著者は池田泰延と鹿野壮で、両者はWeb制作やアプリ開発に関する豊富な経験を持っています。
本書は、SPIの自宅受検版であるWebテスト「WEBテスティング」に特化した対策本です。テストセンターやペーパーテストとは異なる特徴を持つため、専用の対策が必要です。内容には、CUBIC、TAP、TALといった各種テストの特徴と対策方法が詳述されており、最新の問題や模擬テストも掲載されています。また、解答・解説が見開きで完結する形式のため、電子書籍版でも使いやすい設計になっています。さらに、実施企業の情報や裏技も紹介されています。
この書籍は、上司のいないデザイナー向けに、オンライン上司・ニシグチが新米デザイナーの作品を赤ペン添削し、クライアントの意図を理解するためのアドバイスやデザイン改善ポイントを解説します。上司と部下の会話形式で、選ばれるデザインのコツを学べる内容です。著者はフリーランスのアートディレクター・西口明典で、幅広いクリエイティブを手掛けています。
本書は、CSS設計のさまざまな手法を紹介し、プロジェクトに応じた最適解を導き出すための考え方や実践ポイントを明確化しています。ボタンやラベル、カード、テーブルなどのウェブモジュールを実例コードと共に取り上げ、代表的な設計手法である「BEM」と著者の「PRECSS」を対比的に解説しています。駆け出しのウェブ開発者やフロントエンドエンジニアにとって、CSSの理解を深めるための実践的なガイドとなる一冊です。
この書籍は、マンガを通じてデータベースの基礎知識を学ぶ内容です。目次には、データベースの基本概念、リレーショナルデータベースの解説、データベース設計、SQLの基本操作、運用方法、そしてデータベースの普及と活用についての章が含まれています。著者は高橋麻奈で、東京大学経済学部を卒業しています。
本書は、Webライティングに関する実践的なテクニックや知識を提供するガイドです。特に、読者の心を動かし行動を促す方法に焦点を当てています。内容は、Web特有の執筆法、構成、SEO対策、取材方法など多岐にわたり、すぐに実践できるポイントが多数紹介されています。対象は、フリーや企業のライター、広報担当者、ブログ運営者など、Web記事の効果を高めたい人々です。著者は、豊富な経験を持つライターで、BtoB企業向けのメディア支援を行っています。
デザイン書のベストセラーシリーズ第4弾が登場。内容は、効果的な配色の重要性に焦点を当てており、色の選び方がデザインの印象を大きく左右することを解説しています。具体的には、9つのカラーカテゴリー(POP、NUANCE、COOL、GIRLY、AGE、EVENT、SALES、BUSINESS、LUXURY)と7つの配色技法を紹介し、感覚ではなく知識に基づいた配色のコツを提供しています。
この書籍は、企業が効果的なWeb集客を実現するための「パノラマ・デジマ6原則」を紹介し、デジタル・マーケティングの全体像を初心者から中級者向けに解説しています。著者の森和吉は、音楽雑誌や不動産投資におけるデジタルマーケティングの経験を持ち、実践的な知識を提供しています。目次には、デジタルマーケティングの重要性や、売上を倍増させるための原則が含まれています。
初心者向けデザインシリーズ「デザインの学校」の2020年最新版が登場しました。作例を通じて短期間でIllustratorの基本操作を習得できる内容で、一流講師陣による信頼性の高い情報が提供されています。主な章は、イラスト、ロゴ、名刺、地図、ポストカード、ブログのタイトル画像を作成する方法を学ぶ構成になっています。大きな文字と画面で読みやすく、実践的な内容が特徴です。
本書は、Adobe IllustratorのCS6からCC2018までの基本操作を効率的に学べる教材です。ダウンロード可能なイラストを使いながら実践的に学習でき、各章には理解度を確認する課題も含まれています。バージョンによって機能が異なるため、最新のIllustratorを使用することが推奨されています。初心者がIllustratorの楽しさを感じられるよう、学習のハードルを下げることを目指しています。著者は広田正康で、デザイン書籍の制作を手掛けています。
「web」に関するよくある質問
Q. 「web」の本を選ぶポイントは?
A. 「web」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「web」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版]』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで166冊の中から厳選しています。
Q. 「web」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「web」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51HKaOqL-RL._SL500_.jpg)


![『Photoshop しっかり入門 増補改訂版 【CC完全対応】[Mac & Windows対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51QUag2UBxL._SL500_.jpg)

![『Webデザイン良質見本帳[第2版] 目的別に探せて、すぐに使えるアイデア集』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/514iV1akJwL._SL500_.jpg)



![『Illustrator しっかり入門 増補改訂 第2版 【CC完全対応】[Mac & Windows 対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41Wgf80ZiuL._SL500_.jpg)
![『いちばんよくわかるWebデザインの基本きちんと入門[第2版] レイアウト/配色/写真/タイポグラフィ/最新テクニック』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51+Ek5YIXaL._SL500_.jpg)
![『HTML&CSSとWebデザインが1冊できちんと身につく本[増補改訂版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51vDxB6MrSL._SL500_.jpg)

![『【Amazon.co.jp限定】1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版] (特典:「Webデザイナーのポートフォリオの作り方入門講座」データ配信)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51skMJ-OVcL._SL500_.jpg)



![『デザイン入門教室[特別講義] 確かな力を身に付けられる ~学び、考え、作る授業~ (Design&IDEA)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41YXUWBgsAL._SL500_.jpg)


![『世界一わかりやすいHTML&CSSコーディングとサイト制作の教科書[改訂2版] (世界一わかりやすい教科書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41DhABLJdKL._SL500_.jpg)



![『デザインの学校 これからはじめる Photoshopの本 [2022年最新版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51KRScvohkL._SL500_.jpg)











![『HTML&CSSポケットリファレンス [改訂3版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51B+O-9xO8L._SL500_.jpg)










![『Webコピーライティングの新常識 ザ・マイクロコピー[第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51CCbzhuPdL._SL500_.jpg)
![『[改訂版]WordPress 仕事の現場でサッと使える! デザイン教科書[WordPress 5.x対応版] (Webデザイナー養成講座)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51WVmmR+DRL._SL500_.jpg)

![『配色アイデア手帖 めくって見つける新しいデザインの本[完全保存版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41YDOPwkFtL._SL500_.jpg)










![『セールスライティング・ハンドブック 増補改訂版[新訳] 広告・DMからWebコンテンツまで、「売れる」コピーのすべて』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51eH2M6cgkS._SL500_.jpg)














![『デザインの学校 これからはじめる HTML & CSSの本 [Windows 10 & macOS対応版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/511iJWNit0L._SL500_.jpg)
![『WebデザインのためのPhotoshop+Illustratorテクニック[2020/2019対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/511eCFX2rHL._SL500_.jpg)








![『Web制作の現場で使うjQueryデザイン入門[改訂新版] (Web Professional Books)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51SB3qDuV9L._SL500_.jpg)

![『Figma for UIデザイン[日本語版対応] アプリ開発のためのデザイン、プロトタイプ、ハンドオフ』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51rmgfGSO8L._SL500_.jpg)





















![『タイポグラフィの基本ルール -プロに学ぶ、一生枯れない永久不滅テクニック-[デザインラボ]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51WV+W1nY5L._SL500_.jpg)

![『ゼロから学ぶ はじめてのWordPress [バージョン6.x対応]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51FIZvkZEzL._SL500_.jpg)


![『デザインの学校 これからはじめる Illustratorの本 [2022年最新版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51yu0OvARzL._SL500_.jpg)

![『世界一わかりやすい Illustrator 操作とデザインの教科書 [改訂3版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41ai8G9QqwL._SL500_.jpg)













![『デザインの学校 これからはじめるPhotoshopの本 [2020年最新版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/511N0mXrKHL._SL500_.jpg)





![『やさしい配色の教科書[改訂版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51IVjwlnB5L._SL500_.jpg)















![『デザインの学校 これからはじめる Illustrator & Photoshopの本 [2019年最新版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51h9B6tFj1L._SL500_.jpg)





![『デザインの学校 これからはじめる Illustratorの本 [2020年最新版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ag-c2dWXL._SL500_.jpg)