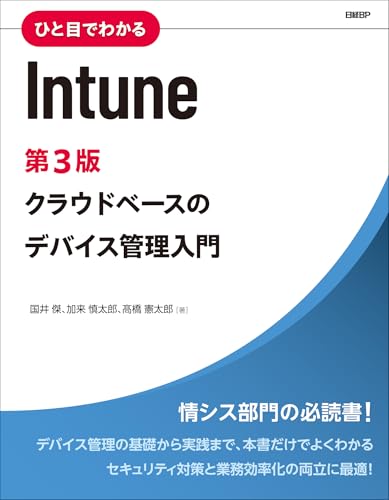【2025年】「デジタル」のおすすめ 本 86選!人気ランキング
- DX経営図鑑
- (購入特典PDF版ダウンロード)いちばんやさしいDXの教本 人気講師が教えるビジネスを変革する攻めのIT戦略
- DX(デジタルトランスフォーメーション)経営戦略
- DX実行戦略 デジタルで稼ぐ組織をつくる
- イラスト&図解でわかるDX(デジタルトランスフォーメーション);デジタル技術で爆発的に成長する産業、破壊される産業
- はじめてでもよくわかる! デジタルマーケティング集中講義
- 呪術廻戦 28 (ジャンプコミックス)
- ジ・アート・オブ・めめめのくらげ
- とことん解説! キャラクターの描き方入門教室 CLIP STUDIO PAINT PROではじめるデジタルイラストの基本
- 神時間力
この文章は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の事例と価値交換の仕組みについて述べています。具体的な企業例として、Netflix、Walmart、Sephora、Macy's、Freshippo、Nike、Tesla、Uber、Starbucksが挙げられ、それぞれの業界でのDXの影響や方向性が紹介されています。また、業界別にDXの事例を分析するセクションもあります。著者は金澤一央で、DX戦略の専門家として多くのプロジェクトを手掛けてきた経歴を持っています。
本書は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が失敗する理由と、成功するための新しいアプローチ「オーケストレーション」について詳述しています。従来のチェンジマネジメントを超え、組織内の多様なリソースを協働させるために必要な「8つの能力」とCDOやCTOの役割、具体的なアクションを提案します。変革のジレンマを乗り越え、デジタル能力を実装するための実践的な手引きとなる内容です。
こんな産業が破壊される!経産省がガイドライン化するほど国も危機感を抱くDX!DXトップコンサルタントが徹底解説する入門書 DXへの取り組みの活発化の波において躓く日本企業…どんな産業が破壊されるのか?どんな産業が発展するのか?経産省がガイドライン化するほど国も危機感を抱くDX!DXトップコンサルタントが徹底解説するDX入門書! DXトップコンサルタントが徹底解説する入門書! ● DXとは? ● なぜ、経産省がガイドラインを出すほど、 国も危機感を抱いているのか? ● DXへの取り組みが活発化しているものの、 つまずく日本企業が多いのはなぜなのか? ● AirbnbやUBER、アマゾン、Google によってどんな産業が破壊されているのか? ● どんな産業が破壊されるのか? ――原子力発電、火力発電、教育産業、スマホ関連…… ● どんな産業が発展するのか? ――長寿・美容産業、都市農業・細胞農業、宇宙産業…… ● デジタル進化が、さらにどのような変化をもたらすのか? 一般ビジネスパースンから、DX推進担当者、個人投資家まで必見! 第1章 なぜ、DXが必要なのか 第2章 デジタル技術が生み出したビジネスモデル 第3章 今後、注目すべき基盤テクノロジー 第4章 こんな産業が破壊される 第5章 こんな産業が発展する 第6章 変化の本質 第7章 個人のキャリアの考え方
この書籍は、現代人が抱える時間に関する悩みを解決するためのガイドです。ストーリー仕立てで、時間の使い方や投資の重要性、優先順位の付け方、トラブルに時間を奪われない方法などを解説しています。著者は麗澤大学の教授で、実践的なアドバイスを提供し、読者が自分の時間を有効に活用できるよう導きます。
この書籍は、キャラクターを描く際に必要な知識を部位ごとに整理し、事典形式で解説しています。内容は、デッサンの基本、人体の構造、アタリの描き方、描画のコツやデジタルテクニックなどを含み、顔、胴体、手、足について詳しく説明しています。著者はフリーランスのイラストレーターで、イラストの技術を教えるライブ配信も行っています。画力向上を目指すための実用的なガイドです。
本書は、システムに詳しくない業務担当者向けに、企業のDX推進に必要なノウハウを解説した教科書です。システムを自ら作れなくても、他者に作ってもらうための技術や判断力が求められる時代において、具体的なプロセスや注意点を示します。内容は、システム構築の計画から実施までの各ステップを網羅しており、著者の実践的な経験に基づく事例も紹介されています。
この本は、SNSで「映える」イラストを描くためのノウハウをプロ100人の意見をもとにQ&A形式で解説しています。内容は、基本的なテクニックや人気イラストレーターのこだわりを紹介し、キャラ作画、構図、ライティングなどが含まれています。購入特典として、メイキングデータや動画も提供され、イラスト制作の理解を深めることができます。
この書籍は、アマゾンや食べログ、メルカリなどの具体的な企業ケースを通じてデジタル・マーケティングの基本概念や理論を解説する入門テキストです。内容は、デジタル社会におけるマーケティング、消費者行動、ビジネスモデル、戦略、マネジメントに分かれており、具体的な企業の事例を用いて実践的なツールやインフラも紹介しています。著者は法政大学と学習院大学の教授で、それぞれの分野での受賞歴があります。
本書は、彩色に関する基礎知識とテクニックをイラストで解説し、特に光と色の重要性に焦点を当てています。色塗りに悩む人や表現を広げたい人に向けて、質感表現やデジタル技術の活用法、作画の流れを紹介しています。内容は、デジタルペインティングから基本ルール、光と色、質感表現、補正、メイキングまで多岐にわたります。
本書は、デジタル時代におけるマーケティングの基本を解説し、企業の「売りたい気持ち」を消費者の「買いたい気持ち」に変える方法を提案します。新規顧客と継続顧客の育成、デジタルコミュニケーションの重要性を強調し、顧客の状態に応じたアプローチを紹介。著者は、実践的なデジタルマーケティングのメソッドを10項目にまとめ、売上成長のための基本的な考え方を提供します。
この本は、光と色の理解を深め、デジタル彩色の技術を向上させるためのガイドです。読者が「色を塗ると同じになってしまう」や「迫力が出ない」という悩みを解消するために、光の性質や色の変化、陰影の表現方法を詳しく解説しています。内容は、光と色の基礎、ライティング、材質、色の調整、彩色技法、キャラクターや背景の彩色メイキングに分かれており、魅力的なイラストを描くための知識やコツが詰まっています。
この書籍は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を自社に導入したいが方法が分からない経営者や事業担当者に向けたガイドです。DXの本質や導入にあたる壁(何から始めるか、実現フェーズへの進行、リソース不足)を解説し、成功するDXの姿を示します。著者はAIビジネスデザイナーで、豊富な経験を持つ専門家です。
村上隆は、作品が高額で取引される日本人アーティストであり、他のアーティストとは異なり、世界基準の戦略を立てて成功を収めています。彼はアートとビジネスの関係を熱意と冷静な分析で語り、作品のブランド化やプレゼンテーション、才能を引き出す方法について解説しています。本書では、芸術における起業や開国の重要性、価値を生み出す訓練についても触れています。村上は「スーパーフラット」というコンセプトで現代美術の巨匠として世界的に活躍しています。
本書は、11人のプロ絵師がCLIPSTUDIO PAINT PROを使った多様なキャラ塗りテクニックを解説する事典です。アニメ塗り、ブラシ塗り、水彩塗りなどの基本技法から、和風塗りやアナログ風塗りといった個性的なスタイル、さらに配色やエフェクトのテクニックまで幅広く紹介し、読者の画力向上と独自の塗りスタイル探求をサポートします。
本書は、デジタルマーケティングにおける重要な「考え方」と「感覚」を解説しています。著者の板澤一樹氏は、データ分析を基にした改善プロセスの重要性を強調し、計数感覚やファクト志向、リスク管理などの要素を紹介。デジタルマーケターとしてのスタンスや顧客調査、KPI設計、AIの活用法など、実践的な知識をまとめた一冊です。
イラストレーター村カルキ氏による本書は、7つのテーマカラーを用いた美麗イラストを通じて、キャラクターや背景の描き方を解説します。厚塗りや水彩塗りなどの基本技法を初心者向けにわかりやすく紹介し、色使いやテクスチャの効果的な活用法も学べます。背景や小物、動物の描写に悩む方に最適な指南書です。
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性とその実践方法について解説しています。著者はコロンビア大学の教授で、顧客、競争、データ、革新、価値の5つの要素(CC-DIV)を用いて、企業が新しいビジネスモデルを確立し、プロアクティブに自己変革を進める方法を示します。DXを戦略的な取り組みとして理解し、変化に適応するための具体的なフレームワークを提供しており、長期にわたり教科書としての価値があるとされています。
この書籍は、Webマーケティングの基本を理解できる内容で、人気のWebコンテンツにオリジナルの解説を加えています。目次には、SEO、Webデザイン、ライティング、SWOT分析、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディア運用など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者はWebライダーの松尾茂起と、イラストレーターの上野高史です。
Webマーケティングといえばこの書籍。ストーリ形式でWebマーケティングについて学べるのでサクサク読めてそれでいてWebマーケティングのエッセンスがギュッと詰まっている。それもそのはず超有名マーケターのWebライダー松尾氏が著者。Webマーケティングを学びはじめた初学者はまず手にとって欲しい書籍。ちなみにWebマーケティングの中でもかなりSEO・オウンドメディア運営にフォーカスしているので広告などについて学びたい人には向かない。
本書は、プロ絵師の技術を徹底解説したイラストメイキング本で、シリーズ累計10万部を突破しています。具体的なレイヤー設定やブラシの使い方、配色のRGB値などを詳細に記載し、プロの塗りを再現することで技術を学べます。10名のプロ絵師による多様な塗り方(アニメ塗り、ブラシ塗り、水彩塗りなど)を紹介し、パーツごとの解説もあり、実践しやすい内容です。さらに、購入者限定のダウンロード特典として、レイヤー別完成イラストや練習用線画、カスタムブラシデータ、カラーセットが提供されます。
ソフトウェアを起点にビジネスを考えなくてはいけない現代に重要なソフトウェアファーストの考え方をインストールできる書籍。DXが遅れている企業ではどうしても業務フローに合わせた非効率なソフトウェア開発が進んでいる。それよりも現代は既存のソフトウェアに業務フローをなるべく合わせて改善していくべき!
この書籍は、Webマーケティングからデジタルマーケティングへの入門書で、ネット活用の基本を解説しています。目次には、ページビューの重要性や顧客理解、トラブル対応などが含まれています。著者はデジタルコンテンツ制作会社の創業者であり、複数の企業でマーケティングに携わった経験を持つ村上佳代と、漫画家の星井博文です。
本書は、Unityを用いたゲームエフェクト制作の手法を解説する書籍です。Shader GraphやShurikenを使用してシェーダーやエフェクトを作成する過程を詳述し、さらにHoudiniなどのDCCツールを使ったリソース制作方法も紹介しています。内容は基礎から応用まで幅広く、エフェクト制作に必要な知識を深めることができます。著者はゲームエフェクト制作の専門家であり、実践的な内容が盛り込まれています。
本書は、プロダクションデザインの巨匠ハンス・バッハーが、映像制作におけるストーリーを効果的に伝えるためのビジュアルデザインの原則を解説します。具体的には、「ライン」「シェイプ」「明度」「色」「光」「カメラ」などの基本要素を分析し、観察力を高める方法を紹介。シンプルな原則を用いて、視覚的にストーリーを表現する技術を学ぶことができます。著者はアニメーション映画のレジェンドであり、教育活動や講演も行っています。
本書は、韓国の漫画家ソク・ジョンヒョンが9年かけて執筆した美術解剖学の集大成で、人体の自然な動きを描くための技法が紹介されています。内容は生物の形、身体の基礎、頭部、胴体、腕と手、脚と足、全身に分かれており、解剖学的な視点から人の動きを丁寧に解説しています。また、1コマ漫画を交えた楽しい読み進め方が工夫されています。著者は多彩な経歴を持ち、国内外で人体描写の特別講義を行っています。
イラストレーター神慶による厚塗り技法の解説書。神慶の描き方や考え方を詳細に学べる内容で、ラフから仕上げまでの工程やキャラクターデザイン、肌や目の表現、ファッションアイテムの描き方などを紹介。特典として神慶特製ブラシや着彩動画、レイヤー付きCLIPデータ、花の線画素材が付属。全体を通して光と影を活かした美しい絵作りのノウハウが得られる。
本書は、デジタル・ディスラプションがあらゆる業界に及ぼす影響と、既存企業がその変化にどう対応すべきかを探る。著者たちは、デジタル技術が新たな価値提案を可能にし、既存ビジネスモデルを破壊する力を解明。企業がディスラプターとして成功するための実践的な戦略や組織能力についても詳述している。具体的には、4つの対応戦略や3つの組織能力を通じて、競争力を高める方法を提案している。
おなか絵師mignonが、肌の塗り方やマスク塗りの基本を詳しく解説する書籍です。内容には、Photoshopを用いた技術や肌のデフォルメ方法、キャラクターの描き方、服装や背景のテクニックが含まれています。また、ダウンロード特典として塗り方の解説動画、ブラシ、PSDデータ、肌のパレットデータ、汗のレイヤースタイルが提供されます。美麗なイラスト表現を確認できる印刷にも配慮されています。
本書は、変化するSEO環境に対応した手法を解説しており、Web担当者が状況に応じて「基礎知識」「手軽な対策」「本気の対策」「ハイレベル対策/トラブル対応」の4つのカテゴリから必要な情報を簡潔に得られるようにまとめられています。特に、スマートフォンの普及に伴うユーザー行動の変化にも焦点を当て、実践的なテクニックを提供しています。著者は岡崎良徳氏で、実務経験に基づいた内容となっています。
本書は、美少女イラストにおけるリアルな肌の描き方と塗り方を解説しています。デフォルメされた顔とリアルな体の表現を融合させ、女性らしい魅力を引き立てる技術を重視しています。人体の骨格や筋肉を理解し、必要な部分を省略することが重要です。内容は肌の基本から始まり、頭部、上半身、下半身の各パーツごとの塗り方を詳述。デジタルを基準にしていますが、アナログでも応用可能です。著者はフリーのイラストレーターたちです。
この書籍は、Webサイトで成果を上げるための文章の書き方をストーリー形式で学ぶ実用入門書であり、特にSEOに強いライティングに焦点を当てています。目次には、SEOライティングの基本や独自の強み(USP)の活用、リライトや推敲の重要性、オウンドメディアの活用法などが含まれています。著者はWebマーケティングの専門家であり、音楽活動も行っています。また、イラストレーターも参加しており、視覚的な要素も重視されています。
沈黙のWebマーケティングに続いて2作目となる本書。1作目を読んでハマった方はぜひこちらの2作目も読んでみて欲しい。ストーリ形式で分かりやすくSEOライティングについて学べる
本書は、若手エリートの間で人気の「FIRE」(経済的自立と早期退職を目指すライフスタイル)について、第一人者のクリスティー・シェンとブライス・リャンがその全貌を解説しています。30代で経済的自立を達成するための技術や戦略を網羅し、早期リタイアのメリットやデメリット、実践的なアドバイスを提供しています。著者は、FIREムーブメントに関する情報を発信するサイト「MILLENNIAL REVOLUTION」を運営しています。
この本は、SNSを効果的に活用して収益を上げる方法を紹介しています。著者は3度の起業に成功し、3000人以上を指導したコンサルタントで、ブランディングや自分の強みを活かすことが重要だと説いています。具体的には、女性らしさやファンの獲得、集客倍増のテクニックを解説し、「自分らしさ×SNS=お金」の仕組みを教えます。SNSの活用法が分からない人に向けて、失敗しないビジネスの仕組みを提供しています。
本書は、企業が直面する「変革を担う人材がいない」という課題に対し、リーダー育成とビジネス変革を同時に進める「育つ変革プロジェクト」を提案しています。著者は具体的な事例を交え、プロジェクトの立ち上げや推進方法、人材育成のノウハウを詳細に解説。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業に向けた実践的な内容となっており、組織全体での学びの拡大も強調されています。
本書は、トヨタ自動車の成功の要因としての「社内コミュニケーション術」に焦点を当てています。著者はトヨタでの経験を基に、無駄を省く会議術や本質思考、教育方法、人間関係の構築、配慮の重要性などを分析し、トヨタが大企業病に侵されずに成長し続ける理由を探ります。日本のビジネスパーソンにとって必読の内容です。
著者の平井孝志は、図を使って考えることが思考を深める理由を解説し、誰でも実践できるメソッドを体系化した書籍を提供しています。内容は、図を用いる基礎的な考え方から、具体的な図の型(ピラミッド、田の字、矢バネ、ループ)を使った実践方法までを含み、図で考えることで仕事や人生がより良くなることを示しています。著者は、MBAやPh.D.を持ち、外資系コンサルタントや大学教授としての豊富な経験を有しています。
この書籍は、人気講義「インスタグラムマーケティング基礎講座」を元に、SNS時代における情報のシェアとトレンドの形成について分析しています。著者は、スマホの普及やビジュアルコミュニケーションの重要性、新たなトレンド(「消える」「盛る」「ライブ」)などを取り上げ、SNSの活用事例も紹介。情報との出会いが「ググる」から「#タグる」へと変化した現状を探ります。著者は電通の研究員で、メディア環境やオーディエンスインサイトを分析しています。
この本は、CLIP STUDIO PAINT PRO/EXの初心者から上級者まで、すべてのユーザーに役立つガイドです。基本的な操作から効率を向上させる便利なテクニックまで、QA形式で網羅されています。iPad版の操作にも対応し、最新の機能に基づいて内容が増量されています。目次には基本設定、レイヤー管理、描画、色塗り、作業効率向上などが含まれ、幅広いスキルを学ぶことができます。著者は平井太朗氏で、講師活動も行っています。
この書籍は、日本企業がデジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進する際の課題を探ります。コロナ禍でDXの重要性が浮き彫りになった一方、日本企業は変革に苦手意識を持ち、過去の成功体験に固執しているため、DXが進まないと指摘しています。著者は、業務、組織、人、ITの「習慣病」を克服することがDX成功の鍵であると述べ、変革を遂げた6社の事例を通じて具体的なアプローチを解説します。
本書は、SNSでコンテンツが話題にならないマーケティング担当者向けに、シェアされるコンテンツの作り方をQ&A形式で解説しています。シェアの動機や事例、写真やテキスト作成のポイント、カテゴリ別のコンテンツアイデアなど、実践的な情報が豊富に含まれています。著者はWebデザインや新規事業開発の経験を持つ清水将之氏です。
本書は、デジタル化が進む世界の本質を解説し、日本企業がオンラインを活用する従来のアプローチを見直す必要性を訴えています。著者たちは、オフラインが存在しない「アフターデジタル」の時代を提唱し、すべてのビジネスがオンライン化される未来を描いています。内容は、デジタル化の現状、OMO型ビジネスの重要性、具体的な事例を通じた思考訓練、日本のビジネス変革に焦点を当てています。デジタル担当者だけでなく、未来を拓くすべてのビジネスパーソンに向けた一冊です。
デジタルが主体の時代に突入しどのように顧客行動が変わっていくかを中国の事例をふんだんにまじえながら教えてくれる良書。デジタル時代のマーケティングをおさえるためにぜひ読んでおきたい1冊
本書は、5人のクリエイターによる美少女イラストの制作過程を紹介するメイキング集です。各イラストは特定のテーマに基づいて描かれ、技術や個々のこだわり、質感表現について詳しく解説されています。クリエイターの試行錯誤の様子も盛り込まれており、実践的なテクニックを学ぶことができます。イラストのPSDデータもダウンロード可能で、魅力的な絵を描きたい人におすすめの一冊です。
この書籍は、初めてSNSを運用する人向けに、予算をかけずに効果的なソーシャルメディアマーケティングの方法を解説しています。内容は、SNSマーケティングの基本から、各プラットフォーム(Facebook、Twitter、Instagramなど)の活用法、マーケティングの分析と改善、成功事例まで多岐にわたります。著者はIT企業での経験を持つ清水将之氏です。
本書は、コロナ禍によって加速した「アフターデジタル」社会の変革について論じています。日本企業はデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めていますが、その基盤が不十分な場合が多いと指摘。特に、中国のアリババやテンセントの成功事例を通じて、アフターデジタル社会における産業構造の変化や、ユーザー体験(UX)の重要性を強調しています。著者は、企業が新しい市場ルールを理解し、戦略を練る必要性を訴えています。
アフターデジタルが出版されてからコロナ禍に突入し、消費行動はデジタルに一気に偏った。そんな中続編として出版されたアフターデジタル2。前作と同じく非常に学びになるので1,2併せて読んでおきたい。
本書は、Instagram運用における成功のためのノウハウを提供するもので、特にデータ分析に基づいた正しい運用方法が重要であると強調しています。著者は、Instagramのプロ集団「SAKIYOMI」での経験をもとに、フォロワーを増やし、売上を向上させるための36のステップを解説しています。内容は、プロフィールの作成からフォロワーをファンにする方法、保存されやすい投稿の作成、ユーザーの誘導方法まで多岐にわたります。誰でも再現可能な施策が紹介されており、Instagramの仕組みを理解することが成功の鍵であると述べています。
本書は、現役ゲームクリエイターが提供するゲームUIデザインの実践ノウハウをまとめたもので、ターゲットやジャンルによるデザインの違いや、体系化が難しいワークフローに対する解決策を示しています。内容は、コンセプト策定からプロトタイプ作成、デザイン手法、実装時のコツまで、各工程に沿った実践的なテクニックを紹介しており、ゲームUIデザイナーや関連職のプランナー、エンジニアを対象としています。著者はバンダイナムコオンラインのプロデューサー、太田垣沙也子氏です。
この書籍は、YouTube、Twitter、Instagram、TikTokなどのSNSを活用したマーケティングやプロモーションのノウハウをまとめたもので、アカウント運用からフォロワーの集客方法までを分かりやすく解説しています。著者はSNSプロモーションの専門家であり、実践的な知識を提供する内容となっています。各SNSの活用方法を章ごとに詳述し、SNSマーケティングの決定版として位置付けられています。
この書籍は、リスティング広告の基礎から応用までを解説したもので、特に最近の機械学習や自動化のトレンドに対応しています。講師陣が経験に基づき、予算設定やキーワード選定、入札の考え方を丁寧に説明し、実践的な解決力を養います。また、自動化による広告効果の向上方法も紹介されています。初心者にとって、ネット広告を学ぶための最適な一冊です。
本書は、紙媒体からウェブ媒体までの多様な広告の特徴や制作方法、運用施策を基礎から解説しています。初心者向けに分かりやすく構成され、最新のデジタル広告知識や実例を100点以上掲載。広告の目的や効果測定、改善方法についても詳しく説明しており、広告に関する知識をアップデートしたい人や効果的な施策を学びたい人におすすめです。著者は広告業界のプロフェッショナルで、実践的な視点から広告戦略を提案しています。
本書は、Googleアナリティクスのデータ活用を実践的に解説した入門書で、集客や広告、EC売上などの目的別にデータの取り方や分析方法を学べる。著者はデジタルマーケティングの専門家で、セミナー感覚で読み進められる内容となっている。目次にはデータ活用の流れやレポート作成術などが含まれている。
「デジタル」に関するよくある質問
Q. 「デジタル」の本を選ぶポイントは?
A. 「デジタル」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「デジタル」本は?
A. 当サイトのランキングでは『DX経営図鑑』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで86冊の中から厳選しています。
Q. 「デジタル」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「デジタル」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

















































![『いちばんやさしい新しいSEOの教本 第2版 人気講師が教える検索に強いサイトの作り方[MFI対応] (「いちばんやさしい教本」シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/519qHZi-znL._SL500_.jpg)


















![『CLIP STUDIO PAINTの「良ワザ」事典 第3版 [PRO/EX対応] (デジタルイラスト描き方事典シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/5185iO15AjL._SL500_.jpg)



![『AfterEffects for アニメーション BEGINNER [CC対応 改訂版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51uyCGqD1CL._SL500_.jpg)











![『いちばんやさしい[新版]リスティング広告の教本 ⼈気講師が教える⾃動化で利益を⽣むネット広告 (「いちばんやさしい教本」シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51x8MXHDSoL._SL500_.jpg)