【2025年】「マキャベリ」のおすすめ 本 74選!人気ランキング
- 今度こそ読み通せる名著 マキャベリの「君主論」 (名著シリーズ第3弾)
- 君主論
- 君主論 - 新版 (中公文庫 マ 2-4)
- 読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊
- キッシンジャー 1923-1968 理想主義者 1
- 貞観政要 (ちくま学芸文庫)
- イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」
- すらすら読める新訳 君主論
- 社長のためのマキアヴェリ入門 (中公文庫 か 56-7)
- 自民党: 政権党の38年 (中公文庫 き 34-1)
本書は、マキアヴェリの「君主論」を現代の視点から再評価したもので、権謀術数やマキアヴェリズムの真髄を探ります。訳者の池田廉による詳細な解説や注釈、佐藤優による現代政治との対比が加えられ、さまざまな種類の君主国やその征服手段について論じています。マキアヴェリは、フィレンツェの政治思想家で、彼の作品は冷徹な観察に基づく政治の現実を描いています。
本書は、人類の歴史と知識を活用した「最強のブックガイド」であり、ビジネスリーダーに求められる読書の重要性を説いています。内容は二部構成で、第1部では人類の知の進化を探求し、第2部では歴史に残る200冊の書籍を紹介しています。著者の堀内勉は、豊富な経験をもとに選書し、読書が人生の選択や危機において「光明」となることを強調しています。
大唐帝国の礎を築いた太宗が名臣たちと交わした政治問答集。編纂されて以来帝王学の古典として屹立する。本書では七十篇を精選・訳出 唐代、治世の問題を真正面から取り扱い、帝王学の指南書となった『貞観政要』。幾多の戦乱を乗り越え、太平の世を現出させた太宗(李世民)が名臣たちと交わした問答を史家・呉兢が編纂。爾来、中国のみならず日本においても為政者たちが折に触れて立ち返る古典の地位を得てきた。「指導者の条件」「人材の登用」「後継者の育成」など、およそ組織運営に関わる人間なら必ず迷い、悩むであろう問題に古人はどのように臨んできたのか。本書には汲めども尽きぬ教訓が今も満ち溢れている。本文庫は明代の通行本(戈直本)を底本とし、全篇より七十篇を精選・訳出。 第1章 治世の要諦 第2章 諌言の機微 第3章 人材の登用 第4章 後継者の育成 第5章 名君の条件 第6章 帝王の陥穽 第7章 学問の効用 第8章 刑罰の論理 第9章 用兵の限界 第10章 守成の心得
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。
この書籍は、日本政治の裏側と表側を深く理解するための重要な一冊であり、特に小沢一郎氏の政治活動に焦点を当てています。著者は、小沢氏の政権交代に対する理解や、彼が直面した敗北からの立ち直りを通じて、日本政治の課題を浮き彫りにしています。内容は、小沢氏への独占インタビューを基に、民主党政権や自民党の権力構造、政治改革の必要性などを探求し、今後の日本政治に向けた道標を示しています。政治に関心のある人々にとって必読の書です。
本書は、明石市長を務めた泉房穂氏が、日本の政治を変えるために闘った経験を記録したものです。彼は、10歳で「優しい社会」を実現する決意をし、47歳で市長に就任。議会やマスコミ、利権に囲まれながらも、市民の支持を得て新たな政治闘争を宣言します。内容は、彼の市長選挙の勝利、政治家引退の真相、行政の問題点、そして「誰一人見捨てない社会」を目指す姿勢について語られています。
本書は、著者が「銀座のユダヤ人」として知られる藤田田による、ユダヤ商法の「定石」を紹介した経営ノウハウの復刊版です。1972年に初版が刊行され、240刷、82万7000部を売り上げた伝説的なベストセラーです。「定石」は金持ちになるための原理原則であり、これを守ることで誰でも金儲けが可能とされています。若者やビジネスマンにとって必読の内容で、ユダヤ商法の背景や実践例が解説されています。
この書籍は、コリン・パウエルが自身の経験を基にした「自戒13カ条」を通じて、リーダーシップや仕事の手順について語ったものです。内容は、目標達成や対人術、組織づくりに役立つ知識を提供し、ビジネスパーソン必読の一冊とされています。パウエルの実体験を交えながら、冷静さや楽観主義の重要性が強調されており、各界のキーパーソンからも推薦されています。
泉房穂市長の著書は、障害を持つ弟への「復讐」として市長になった経緯や、明石市での革新的な政策、コロナ禍の中での自治体の役割、そして日本の政治への希望を伝えています。著者は明石市民としての視点から、社会を変える方法をまとめており、特に子どもや高齢者、障害者福祉に力を入れた施策が市の好循環を生んでいることを強調しています。
いま政治学では何が問題なのか。政治史・政治理論・国際政治・福祉・行政学など12のテーマで初学者を導く政治学への道案内。 いま政治学では何が問題になっているのか。政治史・政治理論・国際政治・福祉・行政学・地方自治などの専門研究者が12のテーマで初学者を導く政治学への道案内。
本書は、政治の基本概念や仕組みを分かりやすく解説した入門書です。政治の成り立ちや日常生活との関連を理解し、合意形成の重要性を学ぶことができます。著者は、政治が難解ではなく、私たちの生活に直結していることを示し、子供にも教えたくなる内容を提供しています。
この書籍は、日本の戦後史における対米隷属の歴史を探るもので、著者は元外交官の孫崎享。日本の政治家たち(石橋湛山、岸信介、田中角栄、小沢一郎など)が、アメリカとの関係でどのように葬られてきたのかを分析している。著者は、対米交渉や基地問題を通じて、日本の国家のあり方を問い直し、戦後の真実を明らかにしようとしている。各章では、安保闘争の真相や対米自主派の政治家たちの運命、日米関係の不平等性について詳述されている。
マックス・ヴェーバーの講演記録で、政治の本質や政治家に求められる資質と倫理について語られています。彼は、困難な状況でも「それにもかかわらず!」と言える自信を持つ人が政治に向いていると主張しています。
本書は、ジャーナリストの池上彰が中学生を対象に行った特別授業を基に、政治の重要性や選挙の意義について解説します。生徒たちの鋭い質問に答える形で、政治が私たちの生活にどのように関わっているのかを説明し、選挙に行くことの重要性や国の借金の実態についても触れています。授業を通じて生徒たちは政治を身近な問題として捉え、未来に向けての意識を高めることができました。全体を通じて、政治の基本的な知識をわかりやすく伝える内容になっています。
この書籍は、戦争の危機がなぜ続くのかという問いに対し、国際政治の現実を分析する入門書です。著者は、軍縮、経済交流、国際機構などを具体的に検討し、国家利益やイデオロギーの絡み合いを踏まえた議論を展開しています。国際関係を単純化せず、現実的な視点から平和の実現を探求しています。著者は高坂正堯で、国際政治学の専門家です。
本書は、政治に関する基本的な疑問に結論から直接答える新しい形式の入門書です。解散や総辞職の時期、アメリカの大統領選の違い、ロビー活動、小選挙区と比例代表の違い、政党交付金、パレスチナの紛争、ロシアのウクライナ侵攻など、今さら聞けない知識を簡潔に解説しています。忙しい現代人向けにハンディサイズで、スキマ時間に学べる内容となっており、政治をフラットに理解したい人に最適です。著者は公民科教育の専門家で、長年教育に携わっています。
本書は、日本国憲法の枠組みの中で展開された戦後日本政治を分析している。自民党と社会党のイデオロギー対立が1960年の安保改定問題でピークに達した後、自民党は経済成長に専念し、一党支配を強化した。80年代末からは「改革」が焦点となり、民主党政権を経た後、第二次安倍政権以降は再び与党と野党が防衛問題を巡って対立している。著者は憲法をめぐる対立に注目し、戦後日本政治の変遷と現在の状況を考察している。
本書は、ジャーナリスト池上彰が「経済」と「政治」の基本をわかりやすく解説したもので、ニュースを正しく理解するためのポイントを紹介しています。内容は、経済に関するしくみやルール、金融や投資の基礎、世界と日本の経済の動向を含む「経済」と、国会や総理大臣の役割、政治用語、選挙、憲法の争点に関する「政治」の情報をカバーしています。イラストを用いて、誰でも理解できるようにまとめられています。
本書は、国際情勢の理解を深めるための必読書であり、特に米中関係やウクライナ戦争、パレスチナ問題などの背景にある各国の歴史と論理を解説しています。著者はテレビ東京の記者・キャスターで、客観的な視点から現代の安全保障問題を分析。日本が直面する課題についても考察し、ビジネスパーソンにとっても重要な教養となる内容です。
身近な問題とイラストを入れて,政治学のおもしろさをわかりやすく説明した好評テキスト。新たな話題を盛り込み第3版化した。 身近な問題を切り口に,イラストを交えて,政治学のおもしろさをわかりやすく説明したテキストの第3版。改訂に際し,平明な説明を維持しつつ,小泉政権以降の現実政治の動きも取り入れ,新たな話題も数多く盛り込んだ。初版以来,読んでいて楽しいと大好評。 まえがき パートⅠ 政治と経済 第1章 組織された集団 第2章 官と民の関係 第3章 大企業と政治 パートⅡ 政治と社会 第4章 選挙と政治 第5章 地方分権 第6章 マスメディアと政治 パートⅢ 政治のしくみ 第7章 国 会 第8章 内閣と総理大臣 第9章 官 僚 パートⅣ 政治と世界 第10章 冷戦の終わりからテロとの戦いへ 第11章 経済交渉 第12章 国境を越える政治
本書は、世界の政治や選挙制度についての一般教養と知的雑学を紹介しています。各国のユニークな政治体制や選挙の仕組みを解説し、特に日本と関わりの深い国々を取り上げています。知識を深めることで、ニュースをより理解し楽しむ手助けとなる内容です。著者は弁護士で元法政大学教授の串田誠一氏です。
この書籍は、投票に対する理解不足や面倒さから投票を避けている人々に向けて、納得できる一票を投じるための手引きを提供します。選挙の基本や候補者の選び方、投票率向上のための活動について解説しており、特に18歳の学生やその親、教師にとって必読の内容です。著者の松田馨は選挙プランナーであり、選挙に関する豊富な経験を持っています。
この本は、政治を理解し考えるための必読書50冊を紹介しています。近代史や著名な思想家の考え、時代背景を分析し、重要なアイデアを提示しています。各著作の解説には著者のプロフィールや引用も含まれています。著者はトム・バトラー=ボードンで、自己啓発書の専門家です。
新総理・石破茂の最新刊が緊急出版され、戦後保守の可能性と彼の政治ビジョンを探る内容となっています。石破は「納得と共感の政治」を掲げ、国民の信頼を失った理由や保守リベラルの原点を考察。著書では自身の来歴や政策スタンス、近現代史の再学習、信頼回復の方法についても述べています。全国民必読の一冊とされ、石破の人生と政治哲学が展開されています。
この本は、日本の政治の仕組みや政治家の役割、国会や内閣の機能について解説しています。政治が私たちの生活に与える影響や、政治を理解するための視点を提供し、読者が政治にどう関わるべきかを考える手助けをします。各章では、政治の目的、メディアとの関係、議会制民主主義、現代の民主政治の課題などが取り上げられています。著者は北海道大学の教授、山口二郎氏です。
この本は、早稲田大学の政治入門講義を基にしており、読者を「政治的存在」にすることを目的としています。内容は、価値や人権、教育、労働、階級、結婚、生命、秩序、刑罰、象徴、政府、国民、恐怖などのテーマを扱っています。著者は大田比路で、現在は個人投資家として活動しながら早稲田大学の非常勤講師も務めています。
「歴史」「理論」「アクター」「イシュー」という4つの章から,バランスよく国際政治学を学べると好評の入門テキストの第3版。 「歴史」「理論」「アクター」「イシュー」という4つの章からバランスよく国際政治学を学べると好評の入門テキストの第3版。新版刊行後の国際政治の動きをふまえて各unitをアップデートし,新たに「ポスト冷戦」「米中関係」のunitを追加している。 unit0 国際政治学を学ぶ 第1章 国際政治のあゆみ unit1 主権国家の誕生/unit2 ナショナリズムと帝国主義の時代/unit3 第一次世界大戦/unit4 第二次世界大戦/unit5 冷戦/unit6 ポスト冷戦 第2章 国際政治の見方 unit7 パワーと国益/unit8 対立と協調/unit9 支配と従属/unit10 規範と制度/unit11 安全保障/unit12 国際政治経済/unit13 国際政治における文化 第3章 国際政治のしくみ unit14 政治体制/unit15 対外政策決定過程/unit16 外交交渉/unit17 国連・国際機関の役割/unit18 地域主義/unit19 脱国家的主体 第4章 国際政治の課題 unit20 核/unit21 新しい戦争/unit22 国連PKO,平和構築,多国籍軍/unit23 人権と民主主義/unit24 グローバリゼーション/unit25 開発援助/unit26 地球環境問題/unit27 科学技術とエネルギー/unit28 米中関係 unit29 さらに国際政治学を学ぶために
この書籍は、自民党議員の政治資金パーティーや裏金問題について、著者が長年の告発を通じてその本質を明らかにし、政治改革の必要性を訴える内容です。著者は、政治家の収入源や政治資金規正法の抜け道、90年代の政治改革が金権政治を助長した経緯を解説し、市民が政治資金の透明性を確保する方法を示します。最終的には、真の政治改革には収入源の見直しや選挙制度の改革が不可欠であると提言しています。
この書籍は、政治の基本的な仕組みや選挙、国会、内閣、憲法、裁判所、地方自治について詳しく解説しており、政治に対する理解を深めるための決定版です。著者の池上彰は、わかりやすい解説で知られるジャーナリストであり、読者が投票や政治参加を考える際の指針となる内容が盛り込まれています。
本書は、政経受験のためのロングセラーシリーズの改訂版で、過去の入試問題を分析した受験対策が特徴です。左ページに「板書ポイント」、右ページに「爽快講義」を配置し、授業の臨場感を提供します。出題頻度を★で示し、共通テストや私大などの試験対策に役立つ情報を提供。また、グラフや統計の読み取りや最新の時事問題にも対応しています。
このテキストは、政治思想を時代順に解説し、主要な思想家や重要なキーワードを紹介する内容です。特に「主権」「ナショナリズム」などの基本概念や、近年の「保守・リベラル」「ポピュリズム」「公共性」なども取り上げています。また、日本の政治思想についても触れ、現代に繋がる思想の流れを示しています。著者は成蹊大学、立命館大学、明治大学の教授陣です。
「蔭山の共通テスト政治・経済」の改訂版は、代々木ゼミナールの蔭山克秀先生による人気の参考書で、共通テストに対応しています。旧版の内容を加筆修正し、さらにわかりやすくなっています。講義調の文章で政治・経済の知識を身につけやすく、練習問題も収録。オールカラーで視覚的にも読みやすく、受験生にとって効果的な学習ツールです。2025年1月からの新課程に向けての対策が可能です。
角川まんが学習シリーズの『のびーるシリーズ』に新たに社会が登場し、ジェイクとシェリーが地球外生命体ふえーる君と共に日本の政治を学びます。内容は日本国憲法や選挙、国会、内閣、裁判所、地方自治、経済、国際社会など多岐にわたり、カードバトル形式で進行します。楽しみながら政治知識を身につけられる構成で、中学受験や公民の先取り学習にも役立つ解説ページやクイズが充実しています。
『派閥と多党化時代 政治の密室 増補新版』は、元読売新聞政治部長の渡辺恒雄が、日本政治の派閥や権力の実態を深く掘り下げた書籍です。著者は政界の内幕を詳細に描写し、派閥のメカニズムや政界と財界の癒着を明らかにしています。現代政治に関する解説も収録されており、政治の変遷を理解するための重要な資料とされています。多くのメディアで取り上げられ、政治の現状を知るための必読書とされています。
この用語集は、全6点の「政治・経済」教科書から約3500語を収録し、各用語に解説を付けて理解を促進します。用語の重要度は教科書の掲載数に基づいて1~6の頻度数で示され、頻度5以上の用語は赤色で強調されています。配列は工夫されており、どの教科書でも利用可能です。巻末には索引もあり、授業の予習・復習や大学受験に役立つ必携の一冊です。
自民党衆院議員が妻の参院選出馬に際し、地元議員に現金を配布する前代未聞の買収事件が発覚した。この事件では、100人に2871万円が配られ、広島の地元紙が「政治とカネ」の問題を追及する中で、自民党の巨額「裏金」問題に繋がる。著者は事件の経緯や政権中枢の問題を掘り下げた調査報道を展開している。
著者ベン・アンセルは、35歳でオックスフォード大学の正教授に就任した注目の政治学者であり、本書では分断と格差の起源と解決策を探求しています。彼は、私たちが直面する政治の失望や近視眼的選択の「罠」を乗り越え、持続可能な民主主義や社会福祉の実現に向けた方法を提示します。各章では、民主主義、平等、連帯、セキュリティ、繁栄についての課題とそれらの「罠」を解説し、具体的な解決策を提案しています。この書籍は、彼の初の一般読者向けの作品です。
ロールズの思想的「変遷」と哲学の方法 思想史家としてのジョン・ロールズ パネルディスカッション リバタリアニズムは特定の道徳理論からよりも、ある種の価値観から出ている リバタリアニズムの可能性 パネルディスカッション 利己主義の道徳理論は存在するのか 道徳理論としての利己主義と合致の問題 パネルディスカッション リベラリズムはどのように理解可能か 「自由」の語られ方 パネルディスカッション はじめに-政治思想における過去の受容と継承 一七世紀から一九世紀の日本政治思想における過去の受容と継承 政治思想における過去の受容と継承 「書き手」とは何か パネルディスカッション 「的確な位置づけ」と「熟議民主主義的な視座」 規範的民主主義擁護論から熟議民主主義論を再考する パネルディスカッション
本書は,憲法に現れる国民主権,基本的人権,平和主義といった理念から,近代を中心に政治思想史を語り直していく試みである。 本書は,現在の日本政治・社会をかたちづくる日本国憲法の条文を手がかりに,その根底にある西洋政治思想の歴史をひもといてく画期的テキスト。新版化に際しては,憲法に関する判例を取り上げ,政治思想史の観点から解説する「ケース」を新たに設けた。 プロローグ 第1回 クルーソーと「近代」の物語──政治思想史の課題と方法 第Ⅰ部 内戦の時代(16・17世紀) 第2回 政教分離──アウグスティヌスとマキアヴェリ 第3回 思想・良心の自由/信教の自由──宗教戦争とモンテーニュ 第4回 主権/代表──ホッブズと近代国家の作り方 第5回 基本的人権/議会──ジョン・ロックと近代立憲主義の成立 第Ⅱ部 イングランドの世紀(18世紀) 第6回 権力分立──政治体制論の伝統とモンテスキュー 第7回 結社/二院制──アメリカ独立革命とフェデラリスト 第8回 経済的自由/財産権──スコットランド啓蒙思想とスミス 第Ⅲ部 フランス革命の時代(18世紀) 第9回 生存権/憲法改正──ジャン=ジャック・ルソーと人民主権 第10回 政党/代議制──エドマンド・バークとフランス革命 第11回 自衛権/公務員──カントとリアルな平和論 第Ⅳ部 〈民主化〉の時代(19世紀) 第12回 地方自治/陪審制──トクヴィルと政治参加 第13回 平等/参政権──ミルとフェミニズムの誕生 第14回 天皇制/議院内閣制──バジョットの英国国制論と「行政権」 エピローグ 第15回 労働社会の「人間らしさ」?──ヨーロッパの世紀末と政治思想史の役割
紛争や悲劇は避けることができないのか。どうして日本の政治家の大半は男性なのか。そもそも政治はなぜ必要なのか。東大1、2年生たちの好奇心に応えながら、法学部の政治学系スタッフがそれぞれの研究について熱く語った珠玉の講義。東大で政治を学び、東大から政治を考えよう。 はじめに 第1講 日本の有権者と政治家――序論にかえて(谷口将紀) 第2講 政治とは、国際政治とは――戦争と平和の問題を中心に(遠藤乾) 第3講 「冷戦の終わり方」を問い直す――ドイツ統一をめぐる国際政治史研究を題材に(板橋拓己) 第4講 「利益誘導」の条件――日仏の政治史を比較すると何が見えるか?(中山洋平) 第5講 現代アメリカの政治――「分断」の由来と大統領の挑戦(梅川健) 第6講 「中国化」の中国政治――習近平のアイデンティティ政治を読み解く(平野聡) 第7講 自由をめぐる政治思想(川出良枝) 第8講 「公共」と政治学のあいだ――日本政治思想史の視角から(苅部直) 第9講 戦前の政党内閣期が示唆すること(五百旗頭薫) 第10講 現代日本の官僚制と自治制――行政研究の焦点(金井利之) 第11講 ジェンダーと政治(前田健太郎) 第12講 憲法をめぐる政治学(境家史郎) 第13講 租税政策をめぐる福祉国家の政治――比較の中の日本(加藤淳子)
本書は、哲学が現実にどのように至るかを探求し、「人間ならざるもの」とは自然や神々を指し、それに浸透した人間が非政治的存在として捉えられることを論じています。新しい政治的関与の形は、人間ならざる者の実存主義によって哲学的に根拠づけられ、その真意が明らかにされるとしています。目次では、戦後の京都学派の影響や新しい実在論、反政治の政治学などが取り上げられています。著者は哲学を専門とする浅沼光樹氏です。
本書は、情動に注目することでプラットフォーム資本主義や権力の支配からの解放の可能性を探るカルチュラル・スタディーズを扱っています。内容は、現代の不確実性の時代における情動の役割、神経政治学から情動論への移行、加速主義とコミュニケーションテクノロジーの関係、メディアを通じたリアリティの構築、戦時期の海のイデオロギーとアニメにおける情動政治、さらにプラットフォームとオブジェクト指向存在論に関する考察から成り立っています。著者は川村覚文で、批判理論やメディア文化論を専門とする准教授です。
本書『楽しい政治』は、過去と現在の政治的なつながりを探る内容で、映像作品を通じてそのプロセスを明らかにします。第I部では『ウォッチメン』や『トイ・ストーリー』などの作品から、歴史の影響を考察。第II部では「Qアノン」や「カエルのペペ」などの現代の出来事を通じて、政治の存在を示します。巻末にはキーワード事典もあり、政治の「過去」と「今」を楽しく理解するためのガイドブックです。著者はアメリカ文化研究の専門家、小森真樹です。
この文章は、高市早苗氏の著書の目次と著者情報を紹介しています。目次は、安倍晋三元総理の遺志を継ぐことをテーマに、経済安全保障、健康・医療、宇宙政策、サイバーセキュリティ、国家防衛、中国への対応など、さまざまな政策に関する章で構成されています。著者情報では、高市氏の経歴や役職が詳述されており、衆議院議員や自由民主党の要職を歴任していることが強調されています。
この書籍は、政治評論家の乾正人が、自民党総裁選を通じて「善人政治家」や「悪党政治家」の実態を論じ、現代日本の政治状況を批評する内容です。著者は、クリーンさだけを求める政治家ではなく、時には「悪党」と呼ばれるような有能な政治家が必要だと主張し、失われた30年の原因を善人たちに求めています。また、具体的な政治家の名前を挙げながら、彼らの特徴や問題点を分析し、政治の現実を鋭く切り取っています。
本書は、古典から現代の名著まで81篇を厳選し、35名の専門家によるわかりやすい紹介を提供しています。目的は、名著の代わりではなく、読者が政治学に興味を持つきっかけを作ることです。政治思想史の必読書や現代政治の基本図書、国際政治に関する重要書籍など、幅広い分野をカバーし、政治学の世界への入門を促します。
本書『良い政府の政治経済学』は、民主主義における政府や政治家の行動を理論的に分析する中級テキストで、特に「良い政府」とは何かを探求します。政治経済学の視点から、選挙を通じて国民が望む政策を実現するための理論モデルを提供し、政府の失敗や政治的説明責任についても詳述しています。著者はこの分野の専門家であり、経済学を用いた政治の解剖を通じて、民主主義を機能させるための基盤を探ります。全体を通じて、理想的な政府の特徴や、政治家とその行動に関する多角的な視点が示されています。
本書『宗教と政治の戦後史』は、統一教会、日本会議、創価学会の3大団体がどのように政界に近づき、日本社会を変えてきたかを探る研究です。著者は、安倍元首相の銃撃事件を契機に宗教と政治の関係を再考し、信教の自由や政教分離の問題、各団体の歴史や影響力を分析しています。著者は宗教社会学の専門家であり、政治と宗教の癒着についての問いを投げかけています。
「マキャベリ」に関するよくある質問
Q. 「マキャベリ」の本を選ぶポイントは?
A. 「マキャベリ」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「マキャベリ」本は?
A. 当サイトのランキングでは『今度こそ読み通せる名著 マキャベリの「君主論」 (名著シリーズ第3弾)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで74冊の中から厳選しています。
Q. 「マキャベリ」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「マキャベリ」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。











![『マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41UB6ayAOaL._SL500_.jpg)



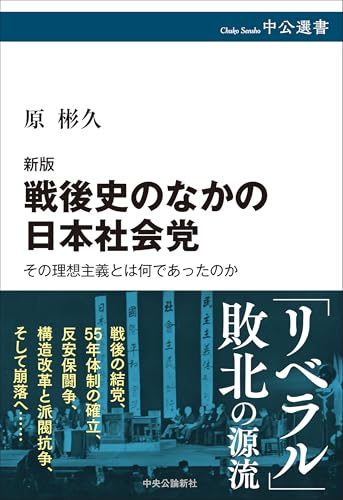



























![『イラスト図解 社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる[新訂版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51JhbJzgihL._SL500_.jpg)










































