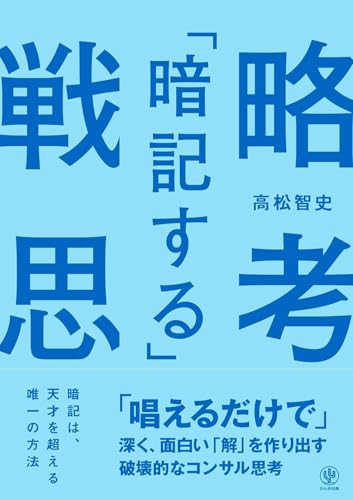【2025年】「思考」のおすすめ 本 182選!人気ランキング
- 世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく
- 新版 考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則
- ロジカル・シンキング (Best solution)
- 3分でわかるロジカル・シンキングの基本
- 改訂3版 グロービスMBAクリティカル・シンキング
- イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」
- 知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ (講談社+アルファ文庫 G 74-1)
- 仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法
- 問題解決のためのロジカルシンキング
- 入門 考える技術・書く技術――日本人のロジカルシンキング実践法
この本は、世界最高峰の経営コンサルティング会社で教えられている問題解決の考え方を、中高生向けに身近なストーリーとイラストを交えて解説しています。問題を小さく分けて考えることで解決策が見えてくることを学び、自ら考え行動する力を育む内容です。目次では、問題解決能力の習得、原因の見極め、目標設定と達成方法についての章が設けられています。著者は、経済を専攻した後にマッキンゼーでの経験を持つ渡辺健介氏です。
バーバラ・ミントが著した本は、コミュニケーション力を向上させるための文章の書き方を紹介しています。内容は、書く技術、考える技術、問題解決の技術、表現の技術の4部構成で、特にピラミッド構造を活用した文書作成法に焦点を当てています。また、構造がない状況での問題解決や重要ポイントのまとめも含まれています。
本書は、体系的かつシンプルなロジカル・コミュニケーション技術を習得することを目的としています。著者たちは、訓練を通じて誰でもこの技術を身につけられると確信しています。内容は、伝えることの重要性や論理的思考の整理、構成技術に関する具体的な方法を提供しています。著者は共にマッキンゼーでの経験を持ち、コミュニケーション戦略やトレーニングに従事しています。
この文章は、大石哲之による論理的思考に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、論理的に考える、伝える、鍛える、実践するためのコツが4つの章に分かれて示されています。著者は株式会社ティンバーラインパートナーズの代表であり、コンサルタントを目指す人々を支援する活動も行っています。
この書籍は、ビジネスに必要な論理的思考力を豊富な演習と事例を通じて学ぶことを目的としています。斬新な発想や機会の発見、効果的なコミュニケーション、集団意思決定、説得・交渉・コーチングのスキル向上を促し、成功をつかむための手助けをします。内容は論理の構造化や思考の基本姿勢、現状分析、因果関係、仮説検証などを含む構成になっています。
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
この書籍は、仮説思考を用いることで作業効率を大幅に向上させる方法について解説しています。著者の内田和成は、BCGコンサルタントとしての経験を基に、仮説を立てることの重要性やその検証方法、思考力を高める方法を紹介しています。目次には、仮説思考の概念から始まり、実践的なステップが示されています。内田は東京大学卒で、経営戦略の専門家としての経歴を持っています。
本書は、ビジネスパーソンに必須の「ロジカルシンキング」を実践的に学ぶためのガイドです。読者が内容を忘れないよう、関連する50問の練習問題を提供する無料アプリ「問題解決ナビ」を付属しています。具体的なビジネスシーンでの活用法を解説し、基礎から応用までのスキルを身につけることを目指しています。著者は、ロジカルシンキングの専門家であり、実践的な事例を交えながら解説しています。全5章で構成され、思考法や問題解決のツール、伝達技術、トレーニング方法が紹介されています。
この書籍は、日本人がロジカルな表現を苦手とする理由を探り、効果的なライティング技術を身につけるための方法を提供しています。序章では誤解を解き、各章で読み手の関心を引くためのOPQ分析、メッセージの整理、ロジックの展開、文書の構成を解説。終章では日常のメールを通じてこれらの技術を実践する方法を提案しています。著者の山崎康司は経営コンサルタントで、ビジネス思考やライティングに関する教育を行っています。
本書は、鈴川葵という女子社員が「考える力」を高めながら成長していく物語です。会議術や資料作りを学び、コンサルタントの父から教わった「思考の循環サイクル」を実践することで、会議や資料の質を向上させる過程を描いています。ビジネスパーソンが「考えること」をどう実践すべきかを探り、考え方の原理を理解する手助けをします。シリーズ第3弾で、過去のテーマから「中身」の質の向上に焦点を当てています。読者は主人公の成長を通じて、自らの考え方を見直すことができる内容となっています。
この本は、アイデアを手に入れる方法についての究極の発想術を紹介しています。60分で読める内容でありながら、一生役立つ知識を提供します。目次には、経験や心の訓練、既存要素の組み合わせなど、アイデア創出に関するさまざまな考察が含まれています。
『5分で論理的思考力ドリル』は、論理的思考力を楽しく手軽に身につけるためのドリルです。全35問の問題が収録されており、家庭や学校、ビジネスシーンで脳を活性化させます。対象年齢は10歳から大人までで、問題はシンプルながら奥深く、思考力を鍛えるのに最適です。装丁はデザイン界の巨匠、寄藤文平氏が手掛けており、知的で温かみのあるデザインが特徴です。
この書籍は、ロジカルシンキングを実生活やビジネスで効果的に活用するためのトレーニングブックです。読者が「なんとなくわかった」状態から「自信を持って考え、伝えることができる」ようにレベルアップすることを目的としています。内容は、主張の展開、因果関係の明確化、情報整理、合理的推論、問題解決、コミュニケーション、分析フレームワークの活用など多岐にわたります。著者は日沖健で、経営戦略のコンサルタントとしての経験を持っています。
フェルミ推定は、未知の数値を常識や知識に基づいて論理的に計算する戦略的思考を指し、単なる因数分解やコンサルティングツールではない。著者の高松智史は、この手法を用いてビジネスパーソンとしての能力を高める方法を解説しており、具体的な解法や実践的なトレーニング方法についても触れている。
この書籍は、日経文庫ビジュアル版の改訂版で、現代の不透明な時代における思考法を提供します。著者は、ロジカル・シンキングを基に、幅広いシナリオを考慮し、問題解決のための「正しい答えの導き方」を示しています。内容は、論理的思考の基本から問題解決、コミュニケーション技術、訓練法まで多岐にわたり、特に若手ビジネスパーソンや就活生に役立つ内容となっています。
本書では、プログラミングとロジカルシンキングの類似性を探求し、プログラミングを通じてロジカルシンキングを習得する方法を提案しています。プログラミングは最適な手順を作成し、意図した通りにシステムを動かすこと、ロジカルシンキングは目的達成のために筋道を考え計画的に実行することに共通点があります。著者は、明確で誤解のない表現がロジカルシンキングの核であり、これを身につけることで日常のコミュニケーションも改善できると述べています。内容は共通点の紹介やプログラミング思考、ロジックツリーの使い方、コミュニケーション技術などを含んでいます。
本書では、現代人が抱える「将来の不安」「お金への欲望」「死への恐怖」といった悩みを、哲学者たちの視点から解決に導く内容が紹介されています。アリストテレスやアンリ・ベルクソン、マックス・ウェーバーの考えを通じて、平易な言葉で哲学を学びながら悩みを解消することができる一冊です。
『ルビィのぼうけん(原題:Hello Ruby)』は、フィンランドのプログラマーリンダ・リウカスによる絵本で、親子で楽しみながらプログラミング的思考を学ぶことを目的としています。物語では、好奇心旺盛な女の子ルビィが父親からの手紙を手がかりに宝石を探す冒険を通じて、問題を小さく分解したりパターンを見つけたりする考え方を学びます。絵本は4~11歳の子ども向けに工夫されており、プログラミングの基礎を楽しく触れる入り口となることを目指しています。
本書は、グロービスMBAホルダーが提唱する「資産になる読書法」を紹介しています。著者は、読書をただの費用として終わらせず、スキルやお金に変える方法を教えています。内容は、選書術や要点を素早くつかむ整理法、著者の資産本コレクションなどから構成されています。読書を通じて一生モノの知的資産を築くための具体的な手法を学べる一冊です。
この本は、コンサルタントのマネージャーとして成功するための79の技術を紹介しています。マネージャーはクライアントや自分自身のために「お金」を生むことが重要で、3年にわたる成長過程を通じて、インテレクチャルリーダーシップやクライアントへの売り込み、部下への愛情をテーマにしています。著者は高松智史で、NTTデータやBCGでの経験を基に、思考の進化を促す内容を提供しています。
この本は、ビジネスにおける「余白」の重要性を強調し、論理的思考やデータ分析だけではなく、直感や感性を育てる方法を提案しています。著者は、余白を創造することで思考の幅を広げ、効果的なコミュニケーションや人間関係の構築、スピーディな意思決定を促進できると述べています。各章では、余白の概念を仕事や人間関係、コミュニケーション、自身のメンタルに応用する方法が詳述されています。最終的には、余白のあり方を自分自身で決めることの重要性が強調されています。
この書籍は、デザイン思考をビジネスに応用する方法を解説したもので、著者はイリノイ工科大学で学んだ第一人者です。デザイン思考は、答えのない時代における創造的な問題解決手法として注目されており、GoogleやP&G、IBMでも活用されています。内容は、思考法、マインドセット、プロセス、ツール、キャリア、経営戦略、幸福など多岐にわたり、ビジネスパーソンがデザイン思考を実践するためのノウハウが詰まっています。著者は、戦略デザインファーム「BIOTOPE」の代表で、さまざまな企業のイノベーションを支援しています。
本書は、効率的な読書法や本の選び方、活用法を体系的に解説したもので、著者「ぶっくま」さんのオリジナルメソッドを紹介しています。読書を通じて人生や仕事を向上させたいが方法が分からない人に向けて、具体的な手法や習慣化のポイントを図解付きで提供。内容は、選書の重要性、効率的な読み方、アウトプットの方法、読書習慣の確立など多岐にわたり、誰でも実践可能な内容となっています。
この本は、まさに「本の使い方」を教えてくれる究極のガイドです!これまで私は、何となく興味のある本を手に取り、漫然と読んでいましたが、この本を読んでからは、自分が本に何を求めているのか、どう活用すれば良いのかがクリアになりました。特に、図解が豊富で、「ひと目でわかる」作りになっているので、文章だけでは掴みにくいコツやテクニックが直感的に理解できます。「目的別に読む方法」や「読んだ本を記憶に定着させるテクニック」など、実生活ですぐに試したくなるヒントが満載で、読書の楽しさと効率が倍増しました。本好きはもちろん、これから読書を始めたい人にもぜひおすすめです!
この本は、コンサルティングに必要な思考や技術が「才能」ではなく、実践的なスキルであることを強調しています。104のビジネススキルを紹介し、業界や職種に関わらず全てのビジネスパーソンに役立つ内容です。目次では、1年目から4年目までの成長過程を通じて、コンサルタントとしての心得やマネジメント技術の違いを示しています。
この本は、情報を整理・分析し、図を使って考える技術を提供します。内容は「図解思考」の理論や、自分の考えを図でまとめる方法、効果を高めるフレームワークの活用法、実践例などを含んでいます。著者は知的生産研究家の永田豊志氏です。
時間に対する新たな視点が生まれる。人生の限られた時間をどう使うかについて考えさせられる一冊でした。時間を有効に使うだけでなく、無駄に見える時間も大切にする視点が新鮮で、日々の選択を見直すきっかけになりました。
限りある人生をいかに充実したものにするかについて学べる良書。仕事に追われていて時間がないビジネスパーソンに是非読んで欲しい。
本書では、メタ思考を実践するための「Why型思考」と「アナロジー思考」という二つの具体的な思考法を紹介し、それぞれのトレーニング問題を提供しています。問題を解くことで思考力を高めることを目指しており、著者はビジネスコンサルタントの細谷功氏です。
この書籍は、成功の鍵はIQやEQではなく、ポジティブ才能(PQ)であると説いています。著者は、幸せであることが成功に繋がると主張し、ポジティブな成長を促進する方法を紹介しています。目次には、ポジティブな現実の選択、成功へのメンタルマップ作成、力を引き出す場所の特定、ネガティブな要素の排除、ポジティブな視点の広め方などが含まれています。著者はポジティブ心理学の専門家であり、世界中で講演を行っています。
この書籍は、働く女性のキャリア戦略について、実例やデータ、理論を交えて解説しています。著者は、成功した女性たちの共通点を明らかにし、働く女性が直面する課題や新たな時代の到来について考察しています。具体的なアドバイスやチェックリストも含まれており、キャリアのオーナーシップを持つことや自分らしい未来を築くためのヒントを提供しています。全体として、女性のキャリア形成を支援する内容となっています。
著者が経済学の重要性を感じ、経済学を学ぶ必要性を伝えるために本書を執筆しました。テレビや新聞で経済に関する情報が常に流れている中、真の教養を得るためには経済学の思考枠組みを理解することが重要です。著者は東京大学での20年以上の教育経験を基に、ミクロ経済学とマクロ経済学のエッセンスを20項目にまとめ、1日30分で学べる内容にしています。主要なトピックには消費者行動、企業行動、市場機能、財政・金融政策、経済成長などが含まれています。
仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版! 仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版! 超高収益を生む「キーエンス思考」をChatGPTで"完コピ"「付加価値」を圧倒的なスピードで創造できる――。仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版!「成果に最短距離で突き進む仕事術」を理解し、ChatGPT活用で遂行していく。日本屈指の高収益企業・キーエンスが成果を生む秘訣である「付加価値」をつくるためのプロセスを、ChatGPTで"完コピ"するための手法を詰め込みました。例えば、情報収集や分析はChatGPTに「仮説」を立てさせることで、新たな観点が生まれ、今手掛けている仕事をブラッシュアップできる。そして付加価値創造が実現し、成果が上がる――。全編を通して、日々の仕事で成果を上げることを念頭に置いたChatGPTのノウハウ本です。キーエンス出身で、自身も業務にChatGPTを有効活用。コンサルティング業務でも顧客にChatGPT活用を提案し、年10億円の利益改善などを実現している著者が徹底解説します。さて、ビジネスパーソンには、様々な立場の人がいます。本書は、どんな立場にあっても成果アップに直結させられる一冊です。例えば、こんなことが実現します。【一般社員のあなた】経験を積む時間を"チート"してみるみる成長【マネジャー(管理職)のあなた】部下が勝手に育ち、チームの業績もアップ【経営者のあなた】優秀な社員ばかりになり、組織の生産性が2倍に「サボっているわけではないのに、上司や同僚に評価されない」「なかなか部下が育たない」「自社、自部署の業績が上がらない」……。そんな悩めるビジネスパーソンにこそ読んで欲しい、AI時代に成果を上げるためのバイブルです。 第1章 キーエンス人~付加価値創造の考え方~ ●付加価値を生み続ける 「しごでき社員」の3大要素 ●「時間」と「お金」の約束は キーエンスでは誰一人軽視しない ●目的意識と目標意識があれば 自然と問題意識も生まれる ●情報に基づく知識こそ生命線。世界初を生む付加価値の秘密 ●成功プロセスを再現するため 十分な行動力が欠かせない 第2章 キーエンスに学ぶ プロの前提条件と必須条件 ●「しごでき社員」になるための 2つの前提を覚えておく ●成果を上げるために「必須」の 8つの原理原則を理解する ●他部署の人の働き方も お客さまのことも十分把握する ●「キーエンス思考」のプロセスは ChatGPT活用で実行できる 第3章 仕事を時短で楽に終える ChatGPT活用術(基本編) ●ChatGPTは何でもできる!? 適切に使うための基礎をおさらい ●危機感を煽りたくなるインパクト ~GPTとの衝撃的な出合い~ ●まだ危機感を持っていない人へ ~「しごでき」ではない人の末路~ ●一般常識をほぼ理解した"先生"に 分からないことはまず質問 ●「構成」や「セリフ」を考えさせて プレゼンの準備をすぐ終える 第4章 ロジカルに情報を整理する ChatGPT活用術(応用編) ●教育コンテンツ開発も計画立案も ChatGPTの生かし方は無限 ●欲しい内容に調整していける 質問と回答の連続こそ真骨頂 ●AIを使わない方が危険? ~火やSNSと理論は一緒~ 第5章 AI時代に仕事ができるとは、どういうことなのか? ●「同僚の彼」が評価される理由 ~目的に最短距離で突き進む~ ●AI時代に成果を上げる心構え ~「Why」の連鎖で目的を知る~ ●ChatGPTを活用して 超重要なビジネスモデルを知る ●ChatGPTにはまだ限界もある。AI時代に重宝される3つのスキル 第6章 PDCAを効率的に素早く回す ChatGPT無双術(前編) ●仕事の根幹「3大要素」を満たす 最重要プロンプトを徹底解説 ●経験を積む時間を"チート"して 最短時間で成果を上げる方法 ●情報収集や分析のヒントを ChatGPTから引き出す ●数値化しづらい情報も「明確化」。キーエンス流の分析手法も実現 ●目標が達成できなかったときは 問題の再設定を提案させる ●「付加価値をつくる仕事」で 迷う時間をできるだけ削る 第7章 アイデアや企画を無限に生む ChatGPT無双術(後編) ●ChatGPTをコーチ役にして 強みと課題を掘り下げていく ●AIにない「五感」を磨くべし。浮いた時間は感動体験に当てる ●「凡人」でも下克上できる。人×AIで天才化を目指せる 第8章 圧倒的な付加価値生産性が実現していく未来 ●すべてに"コパイロット"が付く 次の時代も目前に迫っている ●365コパイロット導入後は 結論が出る会議だけになる? ●日常の業務が激変する? "コパイロット"の未来は ●生活を見守り、アシスト? 日常生活も大きく変える ●高度にパーソナライズ化された 新たなサービスが次々生まれる 第9章 あなたが「しごでき社員」になる意義 ●付加価値をつくれる人は 仕事がどんどん好きになる ●「ハーズバークの理論」で知る 働きがいと働きやすさは別物
本書は、スタンフォード大学の睡眠研究の権威である著者が、質の高い睡眠を得る方法を解説したものです。単に「良く眠る」ことではなく、体温と脳を操作することで睡眠の質を向上させ、日中のパフォーマンスを最大化することが重要とされています。具体的な戦略や最新の研究データを基に、理想的な睡眠法や覚醒法について詳述しています。
この書籍は、著者が偏差値35から東京大学に合格した経験をもとに、誰でも「東大生の頭の良さ」を再現できる「5つの思考技術」を紹介しています。これらの技術は、日常生活で身につけられるもので、記憶力、要約力、説明力、ひらめき力、問題解決力を高める方法を具体的に解説しています。著者は、特別な才能ではなく、日常からの思考習慣が重要だと強調しています。
本書は、経営者やマネジャーを目指す若者に必要なクリティカルシンキングを紹介しています。この思考法は、組織の判断や問題解決において重要であり、コンサルティングや金融、IT業界の採用試験、公務員試験でも頻出です。内容は「資料解釈」「文章理解」「論理構造把握」「判断推理」「論証」の5章からなり、実践的なスキルを身につけるためのトレーニングを提供します。著者は日沖健で、経営戦略のコンサルタントとして活動しています。
本書は、アイデアが浮かばない、会議がまとまらない、意思決定に迷うといった悩みを解決するためのフレームワーク集です。70以上の手法が掲載されており、個人やチームで活用可能です。内容は問題発見、市場分析、課題解決、戦略立案、業務改善、組織マネジメント、情報共有に関するフレームワークを含み、使い方や活用のヒントも提供されています。すべてのフレームには記入例があり、PowerPointテンプレートとしても利用できます。
ビジネスフレームワークが図解で学べる。誰もが知っているビジネスでも実際にビジネスモデルは分からないことが多い。この書籍のビジネスフレームワークを一通り頭に叩き込んでおくことで色んなケースに応用が効く。
著者は、これからの時代に必要な「6つのプロフェッショナルスキル」を解説しています。これらのスキルは、マインドセット、思考力、アウトプット力、伝達力、コラボレーション力、知識・情報であり、正解のない問題に立ち向かうための意識や思考、複雑な問題へのアプローチ、タスクマネジメント、価値創造のコミュニケーション、組織のパフォーマンス向上、そして多様な情報の活用を重視しています。著者はKPMGコンサルティングのパートナーであり、豊富な経験を基に新たな学びの重要性を提案しています。
この書籍は、考える力を養うための3つのツールを紹介しており、子どもからCEOまで幅広く活用できる内容です。目次には、思考を整理する「ブランチ」、問題解決を助ける「クラウド」、目標を明確にする「アンビシャス・ターゲットツリー」が含まれています。著者は、TOC(制約理論)の専門家岸良裕司と絵本作家のきしらまゆこです。
本書は、企業が直面する複雑な課題を解決するための思考法を提案しています。フレームワークやネット検索に依存せず、アップルやグーグルなどの成功事例を通じて、独自の解決策を見つける方法を示します。著者の高野研一氏は、キャリアアップや非連続な変化への対応に必要な「超仮説」を立てる力を強調し、実践を重視しています。
デザイン思考は「人々が抱える本当の問題」を解決するための考え方であり、共感やプロトタイプなどのプロセスを通じてユーザーを理解し、新しいアイデアを生み出します。本書は、著者がスタンフォード大学d.schoolで学んだ知識や実践経験を基に、デザイン思考を身に付けるための具体的なノウハウを提供しています。特に実践に重点を置いており、ビジネスパーソンや学生、マネジメントに関わる人々におすすめです。
ロジカルシンキング(論理思考)を身につければ、あなたの仕事力は驚くほど上がる! コンサルタントのスゴ技をわかりやすく解説! ◎ロジカルシンキング(論理思考)こそ、最強の武器! ・「話す・書く」ときの説得力が段違い! ・仕事の進捗管理がうまくいく! ・仮説を立てて検証する力がつく! ・アイデアがどんどん湧いてくる! ロジカルシンキングを活用すれば あなたの仕事の「質」と「スピード」が 格段に上がる! コンサルタントが 仕事で実際に使っているスゴ技を わかりやすく解説!
「人を動かす」は、そのシンプルでありながら効果的なアプローチから、その名の通り、他者を「動かす」ためにはどうするか毎日悩んでばかりいる私のような人間にとって、まさに必読であると思いました。この本は、他人との関係を深め、相手の心を動かしたいと考えるすべての人に強くおすすめします。カーネギーの提案する原則を実生活で実践することで、人間関係の改善はもちろん、より良いコミュニケーションが生まれてくると確信しました。
確かに名著なので目を通しておくべきだが、思ったより冗長な内容になっているので全てを吸収するのではなくて必要なものだけピックアップするのが良い。
本書は、ビジネスにおける問題解決の技術と実行方法を体系的に解説したテキストで、業種や立場を問わず活用できるスキルを提供します。問題解決の手順を明確にし、実践的な内容を重視。特に問題の特定能力を強調し、実例を交えた構成で理解を深めることを目指しています。全7章で、問題解決の手順を段階的に学び、結果の評価や定着化についても触れています。著者は経営コンサルタントとしての経験を活かし、実践的なビジネススキルを伝授します。
本書は、パスカルの「人間は考える葦である」という言葉を基に、思考実験を通じて論理的思考を養う内容です。マンガで様々な哲学的問題(トロッコ問題や親殺しのパラドックスなど)を紹介し、その後に考え方を解説します。章は「善と平等」「アイデンティティと本質」「矛盾と逆説」「損得と期待値」「プログラムと近未来」に分かれており、思考の幅を広げることを目的としています。著者は哲学対話のファシリテーターとして活動している田代怜奈です。
神奈川工場の長、新城吾郎は、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナと再会することで再建への意欲を取り戻す。ジョナの新しい考え方に基づき、工場の問題を科学的に解決しようと奮闘するが、家庭を犠牲にした結果、妻が失踪してしまう。物語は、全体最適のマネジメント理論であるTOCを基に、工場再建の過程を描いている。
工場の改善のお話で生産管理などに携わる人、経営者全てにオススメの1冊。漫画などでスラスラ読めて分かりやすい。それでいて重要なエッセンスはちゃんと詰まっている。何度も読み返したい1冊。
本書は、ドネラ・H・メドウズの「システム思考」を解説し、複雑な問題を大局的に捉える技術を提供します。株価の暴落や資源枯渇などの現象の背後にある構造や人間の思い込みを理解することで、真の解決策を見出す方法を学ぶことができます。メドウズは「成長の限界」などの著作で知られ、システム思考を通じて経済、環境、社会の課題に取り組みました。
本書は、家庭で子どもの思考力、判断力、表現力を育むための具体的なアクティビティを年齢別に提供する内容です。著者はクリティカル・シンキングの重要性を強調し、情報を分析し、疑問を持つ力を育てる方法を解説しています。特に、グローバル社会で必要な思考力を身につけるための実践的なアプローチが紹介されており、親や教師にとって役立つ内容となっています。
主人公アレックス・ロゴは、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナとの再会をきっかけに工場の再建に取り組む。彼は生産現場の常識を覆すジョナの助言を受け、仲間と共に努力するが、家庭を犠牲にしてしまい、妻ジュリーとの関係が危機に陥る。物語は、仕事と家庭の両立を巡る葛藤を描いている。
この本は、「暗記する」戦略思考を学ぶための実用的なガイドです。戦略思考とは、解答や意見を生成するための考え方であり、著者は特定のフレーズを覚えることでこの技術を身につけることができると提唱しています。内容は、実際のビジネスや人生のシナリオを通じて思考を切り替える方法や、戦略思考のマップを提示し、考える力を強化するための具体的な手法を紹介しています。著者は、NTTデータやBCGでの経験を基に、面白くインパクトのある思考を追求しています。
この書籍は、60歳までに貯金するのではなく、60歳から毎月10万円を稼げる自分を目指すための戦略を提案しています。内容は、不安の分析、働き方の見直し、報酬を上げる方法、稼ぐ力の向上、賢い貯金法、お金の使い方、自分への投資の重要性について述べています。著者の有川真由美は多様な職業経験を持ち、働く女性のアドバイザーとして活動しています。
「頑張っても報われない」のは考え方から間違っている ・「売上を上げたい」「なんとかしたい」… 漠然とした考え・目標を達成するために、30代で会社を十数億で売却し、その後100億の売上を達成した著者の思考法 会社では「売上をあげろ」「●●をなんとかして」というミッションも出てくるものですが、目の前の解決策に飛びついていないでしょうか? 著者によると、そうした解決策の多くが「間違っている」だけでなく、目の前の目標をより困難にするだけではなく、長期的に見ても解決にはつながっていないことも多いようです。「頑張る」だけの繰り返しでは、いつか疲れてしまいます。 そうしたときに著者がやってるのは、ただ「分解」していくだけ。 大学にも行かなかった著者が実践する誰でも簡単に結果を出せる「思考法」を紹介します。 ・仕事だけでなく、自分の漠然とした目標も叶え方がわかる また、個人でも、「ふわっとして何が言いたいのかわからない」と言われたり、「こんなことがしたい」と思いつつも、明確な言葉にできず、方法もわからない、ということは多くあります。最近では解像度を上げてとか言われるようにもなりました。こんな時にも「分解」は使えます。仕事にも、自身の人生やキャリアにも役立つ考え方です。 ・ロジカルシンキングの本を読んでもいまいちわからない人のための、超実践的で結果の出る解説! 本書のベースにあるのは、「ロジカルシンキング」ですが、実際に現場で使いこなすとなると難しい面もあります。本書では、事例や、フローチャート、図版、分解例などを入れながら誰にでも使いやすい内容にしています。 第1章 「分解思考」とは何か 第2章 1枚のシートで「分解思考」を使ってみる【仕事編】 第3章 1枚のシートの「分解思考」で個人の理想を実現する【個人のキャリア編】 第4章 仕事で使える様々な分解 ■「課題・目標」を分解する ■「購入数」を分解する ■「期間」を分解する ■「タスク」を分解する ■「売り方」を分解する ■悲観と楽観に分解する 第5章 解像度を上げて、飛躍するアイデアを出すために
この本は、効果的なプレゼンテーションのための具体的なテクニックを図解で解説しています。内容が整理されていないと、いくら見栄えの良い資料を作っても意味がないことを強調し、プレゼン技術を向上させる方法を紹介。ビジネスコミュニケーションの重要性を示し、プレゼン能力が価値を高めることを提案しています。目次には、プレゼンの問題点や図解思考、アイデア創出のテクニックなどが含まれています。
本書は、ビジネスパーソン向けに問題解決のための「フレームワーク」を解説したビジュアル版の書籍です。マーケティングや戦略プランニング、マネジメントに役立つ81のツールを紹介し、効率的に問題を解決する方法を提供します。大きな紙面で図解が直感的に理解できるようになっており、著者はグロービスの嶋田毅氏です。目次には、問題発見や解決、マーケティング、戦略策定、組織マネジメントに関するフレームワークが含まれています。
本書は、メンタリストDaiGoが自身の成功体験を基に、効率的な勉強法を初公開する内容です。彼は慶應義塾大学で人工知能を研究し、メンタリズムを日本に広めた後、ビジネスや学術の分野で活躍。累計300万部のベストセラーを持つ著者として、入学試験や資格試験に役立つ勉強法を提案します。内容は、やってはいけない勉強法や、効果的な学習テクニック、地頭を良くするためのトレーニングなど、多岐にわたります。
本書は、答えのない課題に対処するための思考技術を解説しています。著者は元戦略コンサルタントで、3000人以上に「考え方」を教えてきました。内容は、「答えのないゲーム」の戦い方、示唆の抽出、健全な議論のための思考技術、問題解決プロセスの体得、そして異なる思考スタイルの比較を含みます。この本を通じて、読者は考えることの楽しさを見出し、後悔のない選択ができるようになることを目指しています。
〈入門編/実践篇〉クリティカルシンキングの理解・体得への王道。思い込みや常識を超える思考の技術を身につける。 現代をよりよく生きるために「よい思考」が必要。大切なのは、よく考えようとする「態度」である。頭の良し悪しでは決まらない。「ものの考え方」自体を系統的に解き明かし、実用的な思考力を身につけるための方法を解説。 「ものの考え方」自体を学ぶ機会がこれまでにあっただろうか。本書は,現代をよりよく生きるために必要な「ものの考え方」,すなわち「クリティカルシンキング」を系統的に学習するためのテキスト。提示された「原則」や,豊富な練習問題を通じ,自ら考えようとする態度や習慣を身につけるためのガイドとして最適である。 1章 クリティカルな思考とは何か、いかに学べばよいのか 1 はじめに 2 クリティカルな思考とは何か? 3 クリティカルな思考を伸ばすための実用的アプローチ 4 本書の構成 5 本書の使い方 2章 ものごとの原因について考える 1 はじめに 2 原因推測ということばを整理しておこう 3 原因の選択 4 因果関係を決定する規準 5 原因─結果について結論をくだす際の落とし穴 6 真の因果関係を決定するための方略 3章 他人の行動を説明する 1 はじめに 2 内的原因か外的原因かの判断──立方体モデル 3 原因の重要性の推論 4 原因を決める際の落とし穴 5 原因帰属を改善する 4章 自分自身を省察する 1 はじめに 2 自己奉仕バイアス 3 自己欺瞞の有用性 4 帰属の正確さを高める 5 認知的不協和 6 他者への印象づけ 7 自分自身について合理的に考える 5章 信念を分析する 1 はじめに 2 信じる? それとも疑う? オカルト信念の強固さ 3 自分自身で体験することの強烈さ 4 確率判断を支える二つのヒューリスティクス 5 偶然と確率を正しく理解する 6 間違った信念は強められてしまう クリティカルシンキングのための原則 【考えてみよう】の解説 推薦図書 事項索引 引用文献
多くの一流企業で行なっている研修の内容がベースになっています。対話形式になっているので、本物の研修を受けているような臨床感を味わいながら、どんどん読み進めることができます。 1 なぜ理論的に考える必要があるのか?(ビジネスを「変える」ために論理思考力が必要になる ビジネスを「変える」にはより良いアイデアが不可欠 ほか) 2 論理思考は「言葉」である(論理には「言葉」が欠かせない 言葉とは境界線である ほか) 3 論理思考は「引き出す」である(ビジネスは「しまった」の思い思わせ合い アイデアを引き出すのはむずかしい ほか) 4 論理思考は「広げる」である(ゼロベース思考はむずかしい 広く考えるための論理思考とは ほか) 5 論理思考を実践してみよう(直感より多くのアイデアが出せればOK ツリーの3つの種類を知る)
西野亮廣のビジネス書。西野亮廣氏はアンチから批判されることも多いが、やっていることは至極真っ当でビジネスの才能が圧倒的、目指している世界観も共感する。そんな西野亮廣氏は元々芸人ということもあり伝える能力がずば抜けていて、書籍の中でも西野亮廣氏の取り組んできたことを抽象化して言語化して読み手に伝えてくれる。ビジネスパーソンは一読の価値あり!
「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる。練習問題多数収録の実用的入門書。 「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる能力である。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる能力である。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 構造図で明晰な思考へ! 正しい推論/正しくない推論を見分けるための「思考力」は生まれ持ったセンスでは決まらない。推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につく能力なのだ。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 === 第1章 「推論」としての「考える」こと 1・1 「推論」の基礎を知る 「論理的に考える」とは/推論の確実さ/理由表示語と結論表示語/「認識根拠」と「存在根拠」 1・2 「推論」の理解をもう一歩進める 推論と条件文/少し複雑な推論/理由からの推論と、仮定からの推論 第2章 推論の構造 2・1 推論の基本構造 構造図/文と主張/基本理由、中間結論、最終結論 2・2 構造把握のレベルアップ 複雑な推論の構造図/2種類の推論の混在/推論の主張化 2・3 推論の周辺 暗黙の前提/コメント 第3章 いくつかの気を付けるべきポイント 3・1 必要条件と十分条件 3・2 因果関係と相関関係 3・3 「割合」を考える 3・4 多義性 3・5 否定詞「……ない」の使い方 第4章 推論を評価する 4・1 存在根拠を与える推論の評価 4・2 認識根拠を与える推論の評価 練習問題解答・解説
ビジネスの現場で注目される「デザイン思考」。日本でその黎明期から実践と指導を重ねてきた第一人者がその成果をこの1冊に集約。 デザインはデザイナーのものだけじゃない。 製品、システム、サービス、組織を革新する「デザイン思考」。 日本企業でも注目されるこの世界標準の問題解決手法を、 デザイン思考の黎明期から、企業・教育現場で、試行錯誤と実践を重ねてきた伊豆裕一・静岡文化芸術大学教授が、その成果をあますところなく1冊に集約し、基礎から説き起こす。 付随する実践CARDs(無料アプリ&ダウンロード)とインストラクションweb動画付きで平易に解説。 知識ゼロからすいすいわかる。 企業セミナーやワークショップでも使える本。
『進化思考』は、生物の進化のプロセス(変異と適応)を基にした創造性を引き出す思考法を紹介する書籍です。道具の発明を通じて私たちの願いを具現化し、偶発的なアイデアを自然選択で洗練させることで、イノベーションを生み出すことができます。本書では、50の進化ワークを通じて、変異や適応の手法を実践しながら創造性を高めることが目指されています。生物の進化に学び、創造性を体系的に理解するための内容が盛り込まれています。
楽しく頭を使って、「ロジカル脳」へ。すぐに役立つ、ずっと活かせる!さまざまな角度から論理的に考えられる。広く深く考えて原因や対策を見つけられる。相手を尊重しながら納得のいく説明ができる。 第1章 ロジカルシンキングってどういうこと? 第2章 頭をやわらかくしよう 第3章 いろいろな角度から考えよう 第4章 理由をロジカルに考えよう 第5章 ロジックツリーで広く深く考えよう 第6章 「なるほど!」と思ってもらおう
本書『ファクトフルネス』は、データに基づいた世界の見方を提案し、誤った思い込みから解放されることの重要性を説いています。著者ハンス・ロスリングは、教育、貧困、環境、エネルギー、人口問題などのテーマを通じて、正しい世界の理解を促進します。2020年には多くのビジネス書ランキングで1位を獲得し、100万部以上の売上を記録。ビル・ゲイツやオバマ元大統領も絶賛し、特に教育機関での普及が進んでいます。クイズ形式で誤解を解消し、ファクトフルネスを実践する方法も紹介されています。
自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。
この書籍は、ビジネスにおけるフレームワークを学び、理解から実践、カスタマイズまでのスキルを向上させることを目的としています。目次には、基本的なフレームワークや問題発見、課題分析、評価・解決の手法が含まれており、業務改善に役立つ内容が整理されています。著者は外資系コンサルタントで、システム運用改善やファシリテーションに精通しています。
この書籍は、クリエイティビティを高めることで独自の成果を生み出すための「右脳型」問題解決力を楽しく学ぶ方法を紹介しています。内容は、ペインポイントの理解、アイデアの発展と絞り込み、実際の形にしてテストするプロセスに分かれており、特に失敗から学ぶ重要性を強調しています。著者は渡辺健介で、デルタスタジオの代表取締役社長です。
この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。
本書は、ビジネスにおける「提案の技術」をテーマに、論理思考やプレゼンテーション能力を実践的に学ぶためのガイドです。著者は、外資コンサルや商社での経験を基に、提案を成功に導くための基本的なスキルを整理しています。内容は、論理思考力、仮説検証力、会議設計力、資料作成力の4つの能力に焦点を当て、各章がストーリー、解説、まとめで構成されています。ビジネス現場での実践的なスキルを身につけることができる内容です。
ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。
ロジカルシンキングを法律を整理して理解するツールとして解説。新たに、事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法も加わる! ロジカルシンキングを法律を整理して理解するツールとして解説。新たに、事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法も加わる! 序章 なぜ法律をロジカルシンキングの視点からみるのか ──法律学におけるロジカルシンキング 第1章 論理的思考方法と説明方法――ロジカルシンキング総論 1 ロジカルシンキングの意味 2 狭義のロジカルシンキング 3 ロジカルプレゼンテーション 4 まとめ 第2章 論理的思考と図表作成の方法――狭義のロジカルシンキング 1 狭義のロジカルシンキングの思考方法 2 狭義のロジカルシンキングの図表作成手法 第3章 法律学におけるロジカルシンキング――MECE・法的三段論法・リーガルマ インド 1 法律学におけるMECEのフレームワークとなる基礎概念・用語 2 法律学におけるロジカルシンキング・プレゼンテーションの基本――法的三段論法 3 法律学全体をカバーする基本理念――リーガルマインド 4 法律学におけるロジカルシンキングの重要性 第4章 民法・私法の基本原則と民法典の体系――民法の全体構造 1 民法の基本原理──民法の三大原則とその変容 2 信義誠実の原則(信義則)と権利濫用禁止の原則 3 民法典の構造──パンデクテン構造 4 民法におけるMECEのフレームワーク 5 民法におけるMECEを用いたフレームワークのまとめ 第5章 時系列に基づく民法の体系──民法各論 1 はじめに――民法における成立要件から対抗要件 2 契約の成立要件 3 契約の有効要件 4 契約の効果帰属要件 5 契約の効力発生要件 6 対抗要件 7 まとめ COLUMN① 教科書の読み方 第6章 法律の構造と条文の読み方――条文の形式的な意味 1 法令・条文の形式的意味の理解の必要性 2 条文の形式的意味の理解のために必要な知識 3 条文の形式的意味の確定から実質的意味・適用範囲の確定へ 第7章 条文解釈の方法──規範の実質的内容の検討 1 法解釈と条文解釈の意義 2 法的三段論法と条文解釈 3 法律要件と法律効果 4 条文解釈の身近な具体例 5 条文解釈の一般理論 COLUMN② 民法の歴史と民法を作った人々 第8章 法的文章の作成方法──ロジカルプレゼンテーション 1 ロジカルプレゼンテーション総論 2 ロジカルプレゼンテーションの内容に関する必要条件 3 ロジカルプレゼンテーションの方法に関する必要条件 第9章 ロジカルシンキングに基づく答案作成──事例の図式化と答案構成の手法 1 事例を図式化する方法 2 答案構成の方法 COLUMN③ 答案作成に関するポイント あとがき――法律学習のポイント 事項索引
本書は在庫管理に関する考え方と技術を解説し、古典理論から最新の研究成果まで実務経験に基づいた実践的な内容を提供しています。目次には在庫の現状、適正在庫の考え方、求め方、活用方法、具体的な進め方、最新理論が含まれています。著者は経営・技術コンサルタントの勝呂隆男氏です。
本書では、知識が過去の集大成であるのに対し、思考力は新しいアイデアを生み出すための能力であり、特に変化の激しい時代に重要であると述べています。目次には、思考力の重要性、問題解決の手法、論理と直感の関係、フレームワーク思考、日常トレーニングなどが含まれています。また、2015年の『ロジカルシンキングを鍛える』を改訂した内容です。
本書は、フェルミ推定を通じて問題解決の技術を習得する方法を解説しています。フェルミ推定を磨くことで、数字に強くなり、ロジカルな思考や戦略的思考を自然に身につけることができます。内容は、具体的な市場規模の推定事例やビジネスでの応用、さらには新たな問題解決の思考法についても触れています。著者は高松智史で、一橋大学卒業後、NTTデータやBCGでの経験を持ち、「考えるエンジン講座」を提供しています。
ロジカルな「らくがき」による"全脳思考""見える化"が可能にした、ロジカルシンキング最短・最速習得術。 序章 ロジカルシンキングは、「これだけ!」で大丈夫-誰でも、カンタンに、最短最速で、ロジカルシンキングが身につく! 第1章 ピラミッド1「削る」-ロジカルシンキングを知る 第2章 ピラミッド2「足す」-一流のプロの思考を借りる 第3章 ピラミッド3「強化する」-頭が良くなる「らくがき」、マインドマップを知る 第4章 ピラミッド4 ロジカルな「らくがき」-4Stepsの概説‐ピラミッドの全体像(システム)を確認する 第5章 Step1「見わたす」-「ソリューション・ボックス」を準備する 第6章 Step2「見える化」-「ソリューション・ボックス」に思考の断片を洗い出す 第7章 Step3「構造化」-「ソリューション・ツリー」で思考のパズルを完成させる 第8章 Step4「物語」-「ストーリー・ピラミッド」で「ひとつの物語」に結晶化する 終章 ラストシーン-明日から使う「4Steps」
本書は「ロジックツリー」と「PAC思考」を通じて、問題解決や論理的思考を強化する方法を解説しています。ロジックツリーを活用することで、視点力や論理力を高め、マネジメントや創造性を向上させることができます。また、PAC思考は前提、仮定、結論の関係を評価し、論理の整合性をチェックするフレームワークで、実生活やビジネスシーンでの応用方法を具体的な事例を交えて紹介しています。著者は外資系コンサルタントで、ビジネス思考のフレームワークを提唱し、研修や講義を行っています。
ホリエモンの行動力に驚く。結局本書で言っているのはグダグダ考えてないでとりあえず行動しろ!動けってこと。読むだけでモチベーションが上がるが、これを読んで満足してしまって何も行動しないのであれば元とも子もない。これを読んでしっかり行動に移すべき。
本書は、雑談に苦手意識を持つ人々に向けて、効果的な雑談力を身につけるための具体的なコツを紹介しています。雑談は友人との会話やビジネスの正式な会話とは異なる「第3の会話」であり、多くの人が失敗する原因を解説。著者は、コミュニケーションの達人が教える7つのルールや場面別のアドバイスを通じて、雑談をスムーズに行う方法を提供しています。具体的なNG例とOK例を示しながら、明日から使える実践的なテクニックを学べる内容です。
戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力・・・・・・。32のキーワードの「何?」「なぜ?」「どう使う?」がすっきりわかる。 シリーズ累計25万部のロングセラー『地頭力を鍛える』著者が説く 戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力、無知の知、メタ認知・・・・・・ 32のキーワードの基本と使い方、 【WHAT:何?】【WHY:なぜ?】【HOW:どう使う?】 がすっきりわかる。 【主要目次】 Chapter1 基本の思考法を押さえる 戦略的思考:いかに並ばずに人気のラーメンを食べるか? ロジカルシンキング:誰が見ても話がつながっているか? 仮説思考:プロジェクトは「最終報告」から考える フレームワーク:良くも悪くも「型にはめる」 具体と抽象:思考とは「具体→抽象→具体」の往復運動 「なぜ?」:なぜ「Why?」だけが特別なのか? アナロジー思考:アイデアは遠くから借りてくる Chapter2 二項対立で考える 二項対立:二者択一はデジタル的、二項対立はアナログ的 因果と相関:雨が降れば傘が売れるが、傘が売れても雨が降るわけではない 演繹と帰納:「そう決まっているから?」「多くがそうだから?」 発散と収束:「落としどころありき」の思考停止はいけない 論理と直観:「論理」で守り、「直観」で攻める 論理と感情:できるビジネスパーソンは「使い分け」がうまい 川上と川下:「自ら考える力」は使いどころを見極める Chapter3 コンサルタントのツール箱 ファクトベース:「みんな言ってる」って、誰がいつ言ったのか? MECE:マッキンゼー流の十八番 ロジックツリー:「形から入る」ことで論理が身に付く 2×2マトリックス:コンサルタントが好きな4象限マッピング フェルミ推定:なぜコンサル、外資系金融の面接試験の定番なのか? Chapter4 AI(人工知能)vs.地頭力 地頭力:結論から、全体から、単純に考える 問題発見と問題解決:なぜ優等生は問題発見ができないのか? AI(人工知能):何ができて、何ができないのか? ビジネスモデル:「何を売っているか」ではなく「収益の上げ方」のパターン 多様性:思考回路の転換と「ニワトリと卵」の関係 未来予測:アマゾンは書店の代替ではない、と気づいたか? Chapter5 「無知の知」からすべては始まる 無知の知:自分を賢いと思ったらゲームオーバー 知的好奇心:地頭力のベース、考えることの原動力となる 能動性:「育てる」ではなく「育つ」 常識の打破:「常識に従う」ことで思考停止に陥ってはいけない 「疑う」こと:「信じてはいけない」(この本に書いてあることも) 認知バイアス:人間の目は曇っている メタ認知:気づくためには上から自分を見る Chapter1 基本の思考法を押さえる 戦略的思考:いかに並ばずに人気のラーメンを食べるか? ロジカルシンキング:誰が見ても話がつながっているか? 仮説思考:プロジェクトは「最終報告」から考える フレームワーク:良くも悪くも「型にはめる」 具体と抽象:思考とは「具体→抽象→具体」の往復運動 「なぜ?」:なぜ「Why?」だけが特別なのか? アナロジー思考:アイデアは遠くから借りてくる Chapter2 二項対立で考える 二項対立:二者択一はデジタル的、二項対立はアナログ的 因果と相関:雨が降れば傘が売れるが、傘が売れても雨が降るわけではない 演繹と帰納:「そう決まっているから?」「多くがそうだから?」 発散と収束:「落としどころありき」の思考停止に陥ってはいけない 論理と直観:「論理」で守り、「直観」で攻める 論理と感情:できるビジネスパーソンは「使い分け」がうまい 川上と川下:「自ら考える力」は使いどころを見極める Chapter3 コンサルタントのツール箱 ファクトベース:「みんな言ってる」って、誰がいつ言ったのか? MECE:マッキンゼー流の十八番 ロジックツリー:「形から入る」ことで論理が身に付く 2×2マトリックス:コンサルタントが好きな4象限マッピング フェルミ推定:なぜコンサル、外資系金融の面接試験の定番なのか? Chapter4 AI(人工知能)vs. 地頭力 地頭力:結論から、全体から、単純に考える 問題発見と問題解決:なぜ優等生は問題発見ができないのか? AI(人工知能):何ができて、何ができないのか? ビジネスモデル:「何を売っているか」ではなく「収益の上げ方」のパターン 多様性:思考回路の転換と「ニワトリと卵」の関係 未来予測:アマゾンは書店の代替ではない、と気づいたか? Chapter5 「無知の知」からすべては始まる 無知の知:自分を賢いと思ったらゲームオーバー 知的好奇心:地頭力のベース、考えることの原動力となる 能動性:「育てる」ではなく「育つ」 常識の打破:「常識に従う」ことで思考停止に陥ってはいけない 「疑う」こと:「信じてはいけない」(この本に書いてあることも) 認知バイアス:人間の目は曇っている メタ認知:気づくためには上から自分を見る
この書籍は、メンタリストDaiGoが提唱する思考法を紹介しており、仕事や人間関係、メンタル面での成長を促す内容です。目次には、クリティカル・シンキングのメリットや「ソクラテス式問答法」、正しい思考を養うトレーニング、他人を操作するための思考法などが含まれています。著者は慶應義塾大学卒のメンタリストで、心理学をテーマにした著書が多数あります。
本書では、統計学があらゆる学問の中で最強である理由を解説し、現代社会におけるその重要性や影響力を最新の事例を通じて探求しています。著者は、統計学の基本概念や手法(サンプリング、誤差、因果関係、ランダム化など)を紹介し、統計学の魅力とパワフルさを伝えます。著者は東京大学出身の専門家で、データを活用した社会イノベーションに取り組んでいます。
学生の時にこの書籍を読んで統計学に興味を持った。統計学の魅力について分かりやすく学べる書籍。専門的な内容はそれほどないのでスラスラ読める。統計学ってどんなことができるの?なんでそんなにすごいの?ということを知りたい人がまず最初に読むべき本。
人を説得するためには論理的な思考法とレトリックが不可欠。本書にしたがって頭のトレーニングをつめば、論理的感覚が自然に身につく。あなたの日本語に磨きをかける確かな方法がここにある。 1 推論のトレーニング-論理学から(論理的に考えるための基本 論理学と日常言語の落差 推論の実際) 2 論証のトレーニング-レトリックから(立論と反論 レトリック的推論) 3 論証と反論(論証の型 準論理的論証 事実的論証) 4 誤謬推理と詭弁
この本は、デザイン思考の基礎から実践方法までを包括的に解説しており、IDEOの創設者やイノベーションの専門家による論文が収められています。具体的な方法論を通じて、社員の創造力を引き出す手法や、顧客ニーズの理解、失敗から学ぶ経営などが紹介されています。各章では、デザイン思考の活用法や実践事例が示されており、リーダーシップやイノベーションの推進に役立つ内容が満載です。
本書は「論理的思考」をテーマに、思考の原則、論理の方法、分析のテクニックを体系的に解説しています。三部構成で、思考の基本から合理的な分析手法までを平易に実践的に紹介しています。著者は経営コンサルタントの波頭亮氏で、東京大学卒業後、マッキンゼーを経て独立し、戦略系コンサルティング会社を設立しました。
この本は、著者がBCGでの経験を通じて得た「行動を変える」技術「スウィッチ」を紹介しています。著者は、戦略やコンサルティングのセンスがなかったものの、「チャーム」を活かして先輩たちから多くのことを学びました。目次には、愛や想像力、チャーム、論点の重要性、示唆の見抜き方などが含まれており、行動や人生を今すぐ変える方法が提案されています。著者は一橋大学卒業後、NTTデータとBCGでの経験を活かし、考えるエンジン講座を設立しました。
学生の頃読んで衝撃を受けた書籍。退屈な日々で何か自分を変えたいと思っている若者には是非読んで本書の課題をぜひ実行して欲しい。読むだけでモチベーションを上げて終わってしまってはだめ。
この書籍は、一流のプロフェッショナル365人からの知恵を集めた仕事のバイブルであり、仕事力と人間力を高める内容です。各月ごとに異なるテーマで、著名人の考えや座右の銘が紹介されています。著者は藤尾秀昭で、月刊誌『致知』の編集長を務めています。
著者ネイト・シルバーは、米大統領選でオバマの勝利を的中させたデータアナリストで、情報の中から真実を見つけ出す統計分析理論や予測技法を紹介します。本書では、予測の成功と失敗、経済や気象予測の課題、テロリズムの統計学など多岐にわたるテーマを扱っています。シルバーは政治予測ブログを運営し、様々な分野での統計的見解を提供しています。
この本は、伝え方の技術が結果に与える影響を探り、効果的なコミュニケーションの方法を学ぶことができる内容です。著者の佐々木圭一は、伝えることが得意でなかった経験を経て、伝え方の技術を発見し、人生が変わったことを語ります。具体的には、相手の反応を変えるための技術や、感動を生む言葉の作り方について述べています。全体を通じて、強い言葉を生み出す力を身につけることがテーマです。
人に何かを伝える方法の勉強にはなるが伝え方が本当に9割なのかは疑問。〇〇が9割シリーズが流行っているので結局シーンによってどこに重点を置くかは変わる。読んで損はない。
本書は、ダメ社員の桃子が「A4メモ書き」を使って論理的思考を身につけ、ビジネススキルを向上させる方法を紹介しています。内容は、ロジカル・シンキングの基礎や、思考を整理するフレームワーク、問題解決のための「ゼロ秒思考」など、多岐にわたります。著者の赤羽雄二は、マッキンゼーでの豊富な経験を活かし、実践的な思考法を提供しています。
『5分で論理的思考力ドリル』は、論理的思考力を楽しく手軽に身につけるためのドリルです。教育改革により、考える力が求められる現代において、子どもから大人まで幅広い年齢層に対応しています。全35問のシンプルで奥深い問題が収録されており、家庭や学校、職場で脳を活性化させることができます。装丁はデザイン界の巨匠、寄藤文平氏が手がけ、知的で遊び心のあるデザインが特徴です。問題を解くことで、思考力を鍛えることができます。
若手エンジニアのために、機械設計の基礎なる図形センスを鍛える演習本。 「を理解形状できない」「三次元的な空間をイメージできない」若手エンジニアのために、機械設計の基礎とな る図形センスを鍛える演習本。指定された空間に収まるように配置する演習を何度も繰り返し、形状認識力と空 間認識力を鍛え、幾何学のロジカルシンキングが身につく。
〈入門編/実践篇〉とをキーワードに、適切な根拠に基いた論理的で、偏りのない思考へ導く。 信じるにたるとするものを見極め,自分の進むべき方向を決断し,問題を解決する生産的思考がクリティカル思考だ。メタ認知とマインドフルな態度を軸に学習,問題解決,議論の際の<クリシン>思考を身につける本。 好評の<入門篇>に続く<実践編>。たんに懐疑や批判のための思考ではなく,信じるにたるとするものを見極め,自分の進むべき方向を決断し,問題を解決する生産的な思考がクリティカル思考である。メタ認知とマインドフルな態度を支柱に,学習,問題解決,意志決定,議論の際の<クリシン>思考を身につける本。 6章 自分は何を知っているかを知る 1 はじめに 2 メタ認知 3 何を学ぶべきかについて考える 4 なぜ「わかったつもり」になってしまうのか 5 十分勉強したかどうかを知る 7章 問題を解決する 1 はじめに 2 「問題」とは何か 3 効果的な問題解決へのアプローチ 8章 意思決定をする 1 はじめに 2 システマティックな意思決定モデル 3 意思決定が間違っていたことがわかったとき 9章 良い議論と悪い議論 1 はじめに 2 「議論」の定義 3 二つの議論の形式を概観する 4 演繹的議論を評価する規準 5 帰納的議論を評価する規準 6 誤った論法 10章 エピローグ 1 省察的思考としてのクリティカル思考 2 アクティブな思考としてのクリティカル思考 3 問題解決の中でのクリティカル思考 クリティカルシンキングのための原則 【考えてみよう】の解説 推薦図書 事項索引 引用文献
「思考」に関するよくある質問
Q. 「思考」の本を選ぶポイントは?
A. 「思考」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「思考」本は?
A. 当サイトのランキングでは『世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで182冊の中から厳選しています。
Q. 「思考」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「思考」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。





































![『[ポケットMBA]ロジカル・シンキング 互いに理解し、成果につなげる! (PHPビジネス新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51fR1higP5L._SL500_.jpg)

![『グロービスMBA集中講義 [実況]ロジカルシンキング教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51kjOsY1MmS._SL500_.jpg)





![『[カラー改訂版]頭がよくなる「図解思考」の技術』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41fr0hgCtLL._SL500_.jpg)