【2025年】「アーユルヴェーダ」のおすすめ 本 86選!人気ランキング
- ア-ユルヴェ-ダ: 日常と季節の過ごし方
- アーユルヴェーダ食事法 理論とレシピ──食事で変わる心と体
- これ1冊できちんとわかるアーユルヴェーダ
- 新版 インドの生命科学 アーユルヴェーダ
- 本当の自分を取りもどすアーユル-ヴェーダ 新装版
- 黄金のアーユルヴェーダ・セルフマッサージ 1日10分 伝統のデトックス法で奇跡の美肌
- ア-ユルヴェ-ダ実践BOOK: 古代インドの叡智で健康&幸せ生活!今日から始めるヨ-ガ、食事、マッサ-ジ (地球丸からだブックス)
- アーユルヴェーダ入門
- ア-ユルヴェ-ダのハ-ブ医学: 東西融合の薬草治療学
- パーフェクト・ヘルス
インド伝承医学、アーユルヴェーダ食事法の決定版! すべての不調を整える食事法を詳しく解説。アーユルヴェーダ・レシピも満載。 インド伝承医学、アーユルヴェーダ食事法の決定版。きれいも若さも食事がつくる!すべての不調を整える食事法を詳しく解説。アーユルヴェーダ・レシピも満載。体質チェックから自分に合う食べ方まで、これ一冊ですべて分かる! ●ブッダも治療を受けている! アーユルヴェーダとは、少なくとも2500年以上の歴史をもち、 チベット医学や古代ギリシア医学等にも大きな影響を与えたとされるインド伝統医学のことです。 ●食べるアーユルヴェーダ アーユルヴェーダでは健康を保つうえでも、治療をするときでも、 食事のコントロールが成否の鍵を握っています。本書は、この食事法にスポットライトをあてました。 ●アーユルヴェーダを基礎から正しく これ一冊で、食事法だけでなくアーユルヴェーダを基礎から正しく、しかも、わかりやすく学べます。 さらに、自分の体質に合った食材・食べ方がわかるので、不調が続く方や病気の方はもちろん、 若く美しく健康でいたい方にもぴったりです! ●まず、美味しい! そして、体にやさしい。 インド・スパイス料理研究家、香取薫の絶品アーユルヴェーダ・レシピを多数掲載しました! スパイス使いのコツもしっかりマスターできて、編集部もハマる美味しさ!! ぜひ味わってみてください。 理論からレシピまで、読み応えのある本になりました。 ぜひ、アーユルヴェーダで本物の健康を手に入れてください。 はじめに 心も体も食べ物でできている ●1 アーユルヴェーダとはなにか? 幸せになるための「生命科学」……アーユルヴェーダの目的 ブッダの医学……アーユルヴェーダの歴史 みんな違ってみんないい……すべての個性を尊重する体質論 [コラム]正倉院に残るアーユルヴェーダ ●2 自分の体の特徴を知ろう───ドーシャでとらえる私たちの体 (1)自然を支配する3つのドーシャ ▼ヴァータ・ドーシャ……風に象徴される生命エネルギー:風+空 ヴァータと五大元素 ヴァータは動かす力 ヴァータの性質(乾燥性、軽性、冷性、粗性、微細性、変動性) 体の中のヴァータの働きと症状 ヴァータを増やすもの──冷えと乾燥と動きすぎ ヴァータを減らすもの──オイルマッサージ [コラム]インドの産後ケアにみるヴァータの対処法 ▼ピッタ・ドーシャ……火に象徴される生命エネルギー:火(+水) ピッタと五大元素 ピッタは変換する力 ピッタの性質(少し油性、鋭性、温性、軽性、生臭さ、流動性、液体性) 体の中のピッタの働きと症状 ピッタを増やすもの──熱と怒り ピッタを減らすもの──ギーと芳香 ▼カパ・ドーシャ……水に象徴される生命エネルギー:水+土 カパと五大元素 カパは抱きしめる力 カパの性質(油性、冷性、 性、緩慢性、滑性、粘着性、停滞性) 体の中のカパの働きと症状/カパを増やすもの──運動不足と甘い物 カパを減らすもの──運動、蜂蜜、ドライマッサージ (2)ドーシャの足し算・引き算のコツ ご飯の炊き方とドーシャのバランス ドーシャの減らし方 ドーシャを増やしてバランスをとってはいけない (3)生まれつき変わらない体質「プラクリティ」 (4)自分の体質を知る───セルフ・チェックシート [コラム]蜂蜜の威力──甘いのに痩せる! 加熱すると毒に? ●3 消化のしくみを知ろう───正しい食べ方とはなにか? (1)神話に隠された不老不死の秘訣……オージャス (2)食事から作られる毒素……万病のもとアーマ (3)消化力とはお腹の中の焚き火……アグニ (4)親玉アグニと13種類のアグニの関係……消化と代謝 (5)癌も肌トラブルも消化力から (6)消化のしくみ……アグニとドーシャ (7)アーマ(未消化による毒素)の排毒法 [コラム]食事の前後にすること [コラム]白湯の効用 ●4 なにを食べればよいのか?───避けるべき食べ物を知る (1)消化に重すぎるものを避ける……重性と軽性の見わけ方 (2)体組織の質を落とすものを避ける……干物や乾物を常食しない (3)心を汚す食べ物を避ける……心の3つの性質を知る (4)食べあわせの悪いものを避ける (5)ドーシャを激しく乱すものを避ける (6)味がもつ性質(効力)を知る 古典書によるスパイスの効果と使い方一覧 [コラム]1000通りの使い方がある万能薬「ギー」 ●5 インド・スパイス料理研究家 香取薫のアーユルヴェーダレシピ ▼スパイス ヒーング 唐辛子 チャートマサラ カレーリーフ マスタードシード コリアンダー ターメリック クミン 生姜 ミント ブラックペッパー アジョワンシード フェヌグリークシード カルダモン タマリンド ベイリーフ、テージパッタ ▼その他の食材 ウラド豆 ムーング豆 イヌホオズキ チウラ スージ粉 ココナッツファイン ココナッツミルク ▼主食 キチュリー 炒ってから炊く白米 炒ってから煮る粥 チウラ プットゥー ウプマ ミント粥 タピオカキチュリー ソフトチャパーティー ホットサンド ギーを塗ったトースト フレンチトースト ギーの作り方 ▼おかず カリフラワーのサブジ じゃがいものしっとりサブジ キャベツを使って基本のポリヤル ニガウリで作るココナッツポリヤル 人参のトーレン イヌホオズキのパリヤ ビーツメラクピラティー ほうれん草のクートゥー 芽もやしのクスンブリ 芽もやしの作り方 大根で作るムーリーキリ 冬瓜オーレン ムーング豆のダール カブカレーカシミール風 梅干しを使うジャパニーズアミラー ▼スープ トマトスープ レモン味の豆カレー・ムーングダルラッサム ビーツで作るルビースープ キャベツのポタージュ 玄米とごぼうのポタージュ 大根と人参のポタージュ コリアンダー好きにはたまらないタンブリ ▼薬味ペーストなど トマトチャトニー 絶品!!ズッキーニチャトニー ビーツチャトニー 和製ポディー ▼シンプル野菜料理 茹で野菜 茹で汁アレンジ アレンジつけだれ ▼シンプル和食 鶏がら野菜スープ 鯛のあらスープ シンプルなキャベツうどん ▼ドリンク バターミルク クミン茶 焦がしクミン茶 アジョワン茶 コリアンダー茶 トゥルシー茶 ミント茶 ブラーフミー茶 ●6 食べ方のルール───10か条 (1)食事時間を決める (2)消化される分だけ適量を食べる (3)温かいもの・作りたてのものを食べる (4)食べる速度は速すぎず遅すぎず (5)怒りながら食べない (6)心をこめて調理されたものを食べる (7)好きなものを食べる……満足感が大切 (8)慣れたもの、自分の体質・年齢・症状・仕事量・土地柄などにあったものを食べる (9)食べあわせの悪いもの、複雑すぎる調理法のものを避ける (10)6つの味と少し油性があるものを食べる ▼補足 季節の変化にあわせて食べる……旬のものを選ぶ ●7 古典書にみる食品の性質 肉・卵・魚類 乳製品 穀物 調味料 野菜類 果物類 スパイス類 ●8 体調が悪いときのキッチンファーマシー───症状別対処法 キッチンファーマシー(台所薬局)の使い方 軽い風邪や体調不良のとき 頭痛 下痢 便秘 咳 発熱 貧血──秘伝のドライフルーツ・ミルクドリンク アトピー性皮膚炎 リューマチ性関節炎 生理痛・更年期障害──花も薬にかえられる〈薔薇の花のグルカンド〉 あとがき お店紹介 出典リスト
現代人向けアーユルヴェーダ実践書の決定版。健康な生活を最大限楽しむための体質別日常生活の過ごし方を具体的に手引きする。 現代に生きる人々の健康と幸せのために、古代インドの医療体系、アーユルヴェーダをわかりやすく解説した実践書。体質別に、日課、仕事、食事、睡眠、余暇、運動、感情など、日々をどう過ごすかを詳しく手引きする。 現代に生きる人々の健康と幸せのために、古代インドの医療体系、アーユルヴェーダをわかりやすく解説した実践書。アーユルヴェーダの概念と基礎、病気と体質との関係などを取り上げるとともに、アーユルヴェーダ式診断で体質を確かめて、体質別に、日課、仕事、食事、睡眠、余暇、運動、感情など、日々をどう過ごすかを詳しく手引きする。ライフスタイルを変えることで、人生を変え、健康な精神とからだを手に入れることを目指す。本書により、自分が何者であり、また、どうすれば健康でいられるか、なぜ病気になるのか、健康な生活を最大限楽しむには生活をどう変えればよいのかを知ることができる。 初刷と2刷は表紙が異なります。内容は同一です。 自己認識と自己発見 アーユルヴェーダは生命の科学である 第1部 アーユルヴェーダを理解するために 1 アーユルヴェーダの起源 あらわれの哲学/大元素/基本的性質 2 3つの生命エネルギー VPK の性質/ VPK の基本的性質一覧/共有する性質と対立する性質/ VPKとあなたの体質/体質の特徴/ドーシャと心/ VPK の通常のはたらき/体質の査定 第2部 健康なからだと病気 3 健康なからだ ヴァータ、ピッタ、カパの座/アグニ/消化作用/消化の3段階/ 6つの味の作用/ 7つの組織/通路 4 病気の進行 ドーシャのアンバランス/ VPKを乱す要因/ナチュラルな衝動の抑制/病気の進行の初期段階/弱点/病気の進行の後期段階/ドーシャが組織に入る徴候/代謝の乱れ/負の感情/病気/病気の診断 第3部 健康の維持 5 毎日の活動 日課/仕事場でのVPK /余暇の楽しみ方/休暇/運動/簡単な連続運動/仕事、レジャー、運動の査定/朝の日課/朝の日課に取り入れると良い習慣/色の効果/朝の査定/帰宅/性交/オイリング/友達とするオイリング/睡眠と夢/便秘/トリパラー 6 食べものと食事 食べものリスト/食べものの本来の性質/食べものの性質を変える/食べものの取りあわせ/食べものの量/生育地の重要性/四季/ 1日のなかのVPK の時間/食事についての一般的ルール/食生活を変える/どのドーシャを減らす食事にするか?/食べもののプロフィール/スパイスとハーブ/ハーブとスパイスの飲みもの/キッチェリ/野菜を食べる 7 心と感情 感情を理解する/人生の行事と変化/抑圧された感情とからだ/さまざまな関係/個人の独自性/意識と瞑想 8 生活を変える アドバイスを求めて 索引 188
南インドカレーは、野菜が豊富で油が控えめなため、心身に良い影響を与えると紹介されています。このカレーは動脈硬化や高血圧、痛風の予防、アトピー対策、便秘解消、ストレス軽減、ダイエットにも効果的です。著者の渡辺玲は、インド料理の専門家であり、医食同源の知恵とレシピを通じて、体に良い食事を提案しています。
本書は、人気フィットネスYouTuberによるシリーズ第2弾で、運動を楽しく習慣化する方法を解説しています。5分でできる7つの部位別エクササイズや、全身痩せを促す4習慣プログラムが含まれ、QRコードでYouTube動画と連動しています。心と体の健康を促進し、運動不足やダイエットに効果的です。内容は、心を強くする体作りやマインドセットの重要性、1週間で変化を実感できるエクササイズについて詳しく説明されています。
アーユルヴェーダの基礎概念や健康増進法、日常生活、食事、アンチエイジングの代表的ハーブなどを、日本で活躍するインド人専門医… アーユルヴェーダの古典『チャラカサンヒター』を参照し、その基礎概念や健康増進法、食事、アンチエイジングの代表的ハーブなどを、日本で活躍するインド人専門医が解説する。五千年にわたり進化を続けるインド伝統医学入門。 5000年にわたり進化を続けてきたインド伝統医学=アーユルヴェーダ。 その古典籍である『チャラカサンヒター』をひもとき、アーユルヴェー ダの基礎概念や健康増進法、食事、アンチエイジングの代表的なハーブ などを、日本で活躍するインド人専門医が解説する。 序 章 なぜアーユルヴェーダか 第一章 アーユルヴェーダの紹介 一、アーユルヴェーダについて /二、アーユルヴェーダの部門/ 三、アーユルヴェーダの目的/四、アーユルヴェーダの治療 第二章 日常生活 一、日々の生活が一生の壮健を決める/二、起 床/三、朝の排泄 と洗顔/四、歯磨きと舌の清掃/五、目の健康増進/六、鼻の健康 増進/七、のどの健康増進/八、オイルマッサージ/九、運動/ 一〇、入浴 第三章 季節の過ごし方 一、春の養生法/二、夏の養生法/三、秋の養生法/四、冬の養生法 第四章 精神衛生 第五章 体 質 第六章 食 事 一、量について/二、材料の質について/三、調理について/四、 土地について/五、時間について/六、味と健康について/七、食 べ合わせ/八、食物と精神 第七章 基礎概念 一、生命の機能、ドーシャは三種類/二、三つのドーシャがすべて の原因/三、ドーシャ総論/四、ドーシャおよび属性の関係/五、 ドーシャと季節/六、ダートゥおよび構成要素/七、老廃物(マラ) /八、アグニとアーマ(消化力と未消化物)/九、スロータス(経路) 第八章 アンチエイジングのための三大薬草―アーマラキー、シャター ワリー、ブラフミー 1.「アーマラキー」―全身の強壮剤/2.「シャターワリー」―女性 にうれしい強壮剤/ 3.「ブラフミー」―脳の強壮剤
本書は、ピラティスの基本を紹介し、体幹筋肉を効果的に鍛える方法を解説しています。特に、効率的なボディメイクを実現するために重要な骨格の知識や特有の動きを学ぶことが強調されています。4つの基本ポーズをマスターすることで、全身をバランスよく鍛え、理想の体を手に入れることができるとされています。また、プラスワントレーニングや日常的な疑問へのQ&Aも含まれ、ピラティスを日常生活に取り入れる方法が提案されています。著者は運動指導者の森拓郎氏で、ボディメイクに関する豊富な経験を持っています。
インストラクター歴20年日本ピラティス界の第一人者・千葉絵美先生、待望の最新刊!!姿勢や所作が良くなり、体のゆがみが原因の不調が改善!お腹ぺたんこ&全身引き締めダイエット効果があるピラティス☆本書には、初心者~中級者向けの7つのLESSONを収録すべての動きを動画で確認できるので絵美先生のプライベートレッスンを受けている感覚でご自分のペースで楽しくレッスンできます♪
自分と対話しながら体を大切に使ってご機嫌な毎日を。55本の動画と連動し、本文とあわせてよりわかりやすくなっています。 みなさんの代わりは他にいません。自分と対話しながらカラダを大切に使ってご機嫌な毎日を。 (本書より) 55本の動画と連動し、本文とあわせてよりわかりやすくなっています。 はじめに、目次、この本の使い方 1章 呼吸を楽にするゆるピラ 呼吸のお話、呼吸ってどういうこと?、スタンディング・ロールダウン、マーメイド、キャットストレッチ、ヒップロールズ/コラム 胸郭と呼吸 2章 体をゆるめて整える夜のゆるピラ ローリング・ライク・ア・ボール ①②、シェルストレッチ、気持ちを前向きにするリラックス法、ポールで腕&脚のワーク ①② /コラム ピラティスと呼吸 3章 快適な一日をすごす朝のゆるピラ おしりフリフリ、猫のように伸びるストレッチ、肩回し(ぐるぐる回し編、合掌編、合掌編・起きやすいまちがい、棒編)、背骨の柔軟性を保つ運動、肩甲骨を動かそう、足首と足ゆびのエクササイズ、マーメイドからのバリエーション ①②/コラム ピラティスとは ① 4章 肩こり・腰痛・疲れを楽にする症状別ゆるピラ 肩甲骨の6つの動き、おしり歩き、ロールオーバーprep(準備編)、平泳ぎとバタフライ(床上編)、スレッドニードル、ブック・オープニング、猫背を改善するエクササイズ、四十肩・五十肩予防 肩関節の組織化 ①②、肩関節・股関節の分離運動、骨盤の位置をつかむエクササイズ、転倒予防① 中殿筋強化のエクササイズ、転倒予防② パジャマウォークとボールエクササイズ、バンドで脚とおなかの運動/コラム ピラティスとは ② 5章 イスに座ってできるゆるピラ バンドやポールを使うゆるピラ クイズ どうやってイスから立ち上がってる?、イスに座って平泳ぎとバタフライ、イスに座ってマーメイド、イスに座ってわきを伸ばすエクササイズ、バンドで体側ストレッチ、バンドでわき・胸・肩・肩甲骨の運動、ヒップロールズ・ウィズ・ポール、ロールオーバー(チャレンジ編)、お風呂掃除でエクササイズ/コラム ピラティスの効果 6章 産前のマタニティゆるピラ 股関節・肩関節と背骨の運動、股関節とわきを伸ばす、マタニティゆるピラ、骨盤と背骨を動かす、下半身(ひざ下)のむくみ解消、胸を開くエクササイズ 「ゆるピラ」に関する主な骨格図・筋肉図・ニュートラルとインプリント・胸部とコア/おわりに
「ほぐピラ」は、筋膜や筋肉をほぐしながらピラティスの動きで体を鍛える新しいエクササイズです。著者の星野由香氏が考案し、モデルや女優たちに人気があります。この書籍では、全エクササイズを写真とQRコード付きの実演動画で解説。10分でできる「リラックスコース」と「脂肪燃焼コース」も紹介されています。手持ちのローラーやタオルを使って簡単に始められる内容です。
生命とは、絶え間ない流れの中にある動的なものである。読んだら世界がちがってみえる。哲学する分子生物学者が問う「命の不思議」。今まで体験したことのないサイエンス・ストーリー。 プロローグ 生命現象とは何か 第1章 脳にかけられた「バイアス」-人はなぜ「錯誤」するか 第2章 汝とは「汝の食べた物」である-「消化」とは情報の解体 第3章 ダイエットの科学-分子生物学が示す「太らない食べ方」 第4章 その食品を食べますか?-部分しか見ない者たちの危険 第5章 生命は時計仕掛けか?-ES細胞の不思議 第6章 ヒトと病原体の戦い-イタチごっこは終わらない 第7章 ミトコンドリア・ミステリー-母系だけで継承されるエネルギー産出の源 第8章 生命は分子の「淀み」-シェーンハイマーは何を示唆したか
本書は、微生物が人体や土壌において果たす重要な役割を探求し、肥満やアレルギー、農業の豊かさとの関連を示しています。著者は、微生物研究を通じて食や医療、私たち自身の理解を深めることを提唱し、土壌と人体の微生物相の協力関係を強調しています。著者は地質学者のデイビッド・モントゴメリーと生物学者のアン・ビクレーで、二人はシアトルに在住しています。
この書籍では、姿勢や体幹、呼吸を整えることで、更年期世代の様々な不調(腰痛、尿漏れ、猫背、頭痛、不眠など)を解消する「大人ピラティス」のプログラムを紹介しています。著者はバルセロナ在住のトレーナーで、初心者向けの基本レッスンやお悩み別のエクササイズを動画付きで提供。体の不調は姿勢や動作の歪みが原因であり、少しのメンテナンスで改善できることを実感できる内容です。
本書『ファクトフルネス』は、データに基づいた世界の見方を提案し、誤った思い込みから解放されることの重要性を説いています。著者ハンス・ロスリングは、教育、貧困、環境、エネルギー、人口問題などのテーマを通じて、正しい世界の理解を促進します。2020年には多くのビジネス書ランキングで1位を獲得し、100万部以上の売上を記録。ビル・ゲイツやオバマ元大統領も絶賛し、特に教育機関での普及が進んでいます。クイズ形式で誤解を解消し、ファクトフルネスを実践する方法も紹介されています。
自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。
この書籍は、インナーマッスルを鍛えるピラティスの基礎から上級者向けのエクササイズまでを網羅した決定版です。内容は、ピラティスの基本知識、呼吸法、プレピラティス、クラシカルピラティス、目的別プログラム(初心者向け、姿勢改善、腰痛予防など)を含み、エクササイズの目的や手順を豊富な写真と共に解説しています。著者はトレーニングスタジオの代表で、ピラティスの専門家です。
この書籍は、ピラティス初心者向けに自宅で行えるエクササイズプログラムを紹介しています。内容は、ピラティスの基本(姿勢や呼吸)、正しい姿勢を保つためのプログラム、スムーズな動きを促進するプログラム、シェイプアップやボディメイク、強く美しい体を作るプログラム、そして疲れを取るストレッチに分かれています。著者は、ピラティスの専門家であり、心身の総合的な指導を行っています。
マルマとは、アーユルヴェーダ独特の体のエネルギー・ポイントで、鍼灸療法のツボに似ています。このマルマを操ることで、プラーナつまり生命エネルギーを、健康、幸福、そして自己変革へと導くことができます。マルマはヨーガのチャクラとナーディにつながっていて、心身両方のバランスをとるのに用いられます。 マルマ療法は、ヨーガおよびアーユルヴェーダ治療の重要なツールの1つです。どちらかの体系を十二分に活用したければ、マルマの知識とその扱い方を覚える必要があります。 『アーユルヴェーダとマルマ療法』は、欧米人のドクターが加わり、現代に生きる人々にも、よく解るように著されたマルマ療法の本です。107の主要マルマの位置、特性、そして用法を明確に示し、マッサージ、アロマ、ハーブ、ヨーガなど、さまざまな方法でマルマをどう扱えばよいか、詳しく説明しています 監訳者のことば上馬塲和夫 はしがきアトレヤ・スミス 第1部マルマ概論 ヨーガとアーユルヴェーダのエネルギー・ポイント 第1章マルマヨーガとアーユルヴェーダのエネルギー・ポイント アーユルヴェーダ医学とマルマ療法/マルマとヨーガ体系/マルマとヴェーダ科学/マルマ、タントラ、シッダ医学/マルマの歴史的背景/マルマと武術 第2章アーユルヴェーダ治療の体系とマルマ療法 3つのドーシャ/ヴァータ・ドーシャ 動きや推進の原動力/ピッタ・ドーシャ 消化や発熱の原動力/カパ・ドーシャ 結合と凝集の原動力/マルマとアーユルヴェーダの体質/マルマ療法とアーユルヴェーダの体質/7つの組織(ダートゥ)/老廃物(マラ)/導管経(スロータス)/消化力(アグニ) 第3章マルマの特性と分類 第4章マルマとヨーガ行法 マルマ、チャクラ、ナーディ/マルマと7つのチャクラ/マルマと14本のナーディ/眉間につながる特別なナーディ/腕と脚の2本のナーディ/マルマとアーサナ行法/マルマとプラティヤーハーラとプラーナーヤーマ/18のヨーガのマルマ領域とそれに対応するマルマ/マルマ瞑想/マルマとマントラ/重要なビージャ(種子)マントラとマルマの用法/マントラの使い方/5元素のマントラ/マルマと色彩や宝石の療法/マルマと宝石療法/水晶の用法/一次宝石/聖なる石とヤントラ 第5章マルマ療法の手法(1)マッサージ・アロマ療法・プラーナ療法 1マルマ・マッサージとオイル・マッサージ 2アロマ療法 3マルダナ(指圧) 4プラーナ療法、エネルギー療法 第6章マルマ療法の手法(2)ハーブ療法 1ハーブパスタ剤を使ったマルマ療法 2マルマのハーブ治療 第2部マルマとその療法 第7章マルマ図とマルマ療法の概要 マルマ療法の概要 マルマとドーシャ マルマ療法・マルマ処方の方法 第8章腕と手のマルマ 11のマルマ領域と22のポイント 手のクシプラ・マルマ/手のタラフリダヤ・マルマ/手のクルッチャ・マルマ/手のクルチャシラ・マルマ/マニバンダ・マルマ/腕のインドラヴァスティ・マルマ/クルパラ・マルマ/腕のアーニ・マルマ/バーヴィ(腕のウルヴィ)・マルマ/腕のローヒタークシャ・マルマ/カクシャダラー・マルマ 第9章脚と足のマルマ 11の領域と22のポイント 足のクシプラ・マルマ/足のタラフリダヤ・マルマ/足のクルッチャ・マルマ/足のクルチャシラ・マルマ/グルパ・マルマ/脚のインドラヴァスティ・マルマ/ジャーヌ・マルマ/脚のアーニ・マルマ/脚のウルヴィ・マルマ/脚のローヒタークシャ・マルマ/ヴィタパ・マルマ 第10章腹と胸のマルマ 8の領域と12のポイント グダ・マルマ/ヴァスティ・マルマ/ナービ・マルマ/フリダヤ・マルマ/スタナムーラ・マルマ/スタナローヒタ・マルマ/アパラーパ・マルマ/アパスタンバ・マルマ 第11章背中と腰のマルマ 7の領域と14のポイント カティカタルナン・マルマ/ククンダラ・マルマ/ニタンバ・マルマ/パルシュヴァサンディ・マルマ/ブリハティー・マルマ/アンサパラカ・マルマ/アンサ・マルマ 第12章頭と首のマルマ 14の領域と37のポイント ニーラ・マルマ/マニヤ・マルマ/シラー・マートリカ・マルマ/パナ・マルマ/アーパンガ・マルマ/ヴィドゥラ・マルマ/クリカティカ・マルマ/シャンカ・マルマ/ウトゥクシェーパ・マルマ/アヴァルタ・マルマ/シュリンガタカ・マルマ/スタパニ・マルマ/シーマンタ・マルマ/アディパティ・マルマ 第3部追加資料および補遺 補遺1マルマ療法における器具の使用?瀉血・鍼・アグニカルマ・クシャーラカルマ 補遺2マルマ鍼灸(アーユルヴェーダ式鍼灸治療) 補遺3アーユルヴェーダと中国医学の類似理論?上馬塲和夫 執筆 補遺4マルマの名称と分類 補遺5サンスクリット語のアーユルヴェーダ用語 補遺6アーユルヴェーダのハーブとオイル 補遺7関連情報
ピラーティスの基礎となる原理と手順を、豊富なカラー写真で紹介。実用ガイドとして、基本原則も十分に理解できる最適な入門書。 ピラーティスは、アライメント(並べる、整列、比較などの意味)の動きを体に覚えこませるメソッドとして、体を中心から整え、インナーマッスルを意識したスラリとした引き締まった体を手に入れることができます。 柔軟性と体幹の強さを向上させるための包括的なピラーティスの入門書 ピラーティスの基本概念とは、体の中心を軸とし、左右対称に骨や筋肉を自然なアライメント(整列)にし、人間本来の健康でしなやかな体をつくることです。実践することによって、背中の痛みを解消させ、しつこい関節の悩みに作用し、職業による体への負担やトラブルにも効果的で、体のあらゆる骨と筋肉が本来あるべき場所へ整うことで、スラリとした引き締まった体を手に入れることができます。さらに自律神経のバランスを整え、人生への活力を最大限に引き出してくれる理想のエクササイズです。 『実践ピラーティス』は、一般的な情報だけでなく、身体への意識を深め、強さ、トーン、姿勢を改善するのに役立つ、的確で集中力のあるエクササイズシステムが含まれています。ストレッチ、リラクゼーション、ビジュアライゼーション、呼吸法などのアドバイスに加え、ジョーゼフ・ピラーティスのエクササイズ・メソッドの歴史や、ピラーティス・プログラムの基本原則も十分に理解できる最適な入門書です。 ピラーティスの基礎となる原理と手順を、豊富なカラー写真で紹介しています。無理や負荷のない、バランスの取れたエクササイズにより、初心者へもおすすめの実用ガイドとして、あなたを手厚くサポートします。 約350枚もの写真やイラストを掲載し、ビジュアルからの情報を入れることで、高い集中力を手に入れ、動き方のポイントや次の動作が瞬時にわかり、無理なく進めることができます。 本書の使い方 はじめに 第1 章:ピラーティスシステム ジョーゼフ・ピラーティス─その人となりと功績 原理 骨格について 筋肉のガードル こんな人がピラーティスでよい効果を得られます ピラーティスとその他の療法 第2 章:ピラーティスを始める前に エクササイズを行う前に ボディー・チェック 服装、道具、スペース 第3 章:心と身体の再教育 アライメント 骨盤底 心を引き締める 呼吸 休憩とリラクゼーション パーソナル・プログラム 第4 章:基本的なエクササイズ 首の筋肉をほぐす 肩の緊張をとりのぞく 内腿を独立して動かす 下背部の筋肉を働かせる 背骨の回旋 骨盤と足を独立して動かす 骨盤の動きを自由に 腹筋を鍛える 身体の前面を鍛える 安定した体幹から、足を伸ばす 内腿を伸ばすエクササイズ 太腿の前面をほぐす 背骨を伸びやかに 基本の立ち位置 背骨の感覚 グラウンドワーク 足全体のバランス セルフ・チェック 第5 章:より高度なエクササイズ 呼吸法の上達 背骨のコントロール力を高める 骨盤の安定 楽な座り方 股関節の回旋 さらにお腹を鍛える ハンドレッド 斜筋を働かせる ダイアゴナル・ストレッチ ジャベリン 立った姿勢で腕を鍛える バランスと筋力 ストレスのない座り方 腿の内側と外側を働かせる 胸の緊張をほぐす まとめ ウエイトを使ったエクササイズ インテグレーション 用語解説 国内の関連情報 海外の関連情報 索引
詳細な解説と、解剖学的イラスト付きの46種類のエクササイズによって、特定の筋肉のストレッチ、強化、精密なコーディネーション… フィットネスクラブやアスリートのトレーニング・プログラム、医療施設などの新しい舞台に浸透しているピラーティスは、初学者にも、理学療法士など人体解剖学に広範な知識のある人にもたいへん役立つエクササイズである。 『ピラーティス アナトミィ 第2版』は、詳細な解説とステップごとの説明、見事な解剖学的イラスト付きの46種類のエクササイズによって、特定の筋肉のストレッチ、強化、精密なコーディネーションを探究できるようになっている。 本書は、どの筋肉が作用しているか、呼吸・アライメント・動きが根本的にどうつながっているか確認しながら、体を引き締め、コアを安定させ、バランスを改善し、柔軟性を高めるエクササイズに取り組むことができるよう設計されている。 各エクササイズの「エクササイズのパーソナライズ」セクションを活用すれば、自分の目的やレベルに合わせて調整し、ワークアウトをカスタマイズできるようになっている。 モディフィケーションによって難易度を下げれば誰にでもこなしやすいエクササイズになり、バリエーションやプログレッションを選択すればエクササイズに高度な要素が加味される。そうして難易度を上げていくことは、ピラーティス上級者への階段を一歩一歩上がっていくことにもなる。 また、呼吸・集中・自己認識のテクニックにも触れ、心身ともに鍛える独特のエクササイズを体験できるようになっている。 ピラーティスの美と恩恵を探求しはじめたばかりの人にとっても、何年もピラーティスを続けてきた人にとっても、本書はほかに類を見ない情報源であると確信できる。 『ピラーティスアナトミィ 第1 版』は2011 年の刊行後、世界中で読まれ、たくさんの言語に翻訳された。 第2版の本文は約80ページ増え、46種類のエクササイズには、難易度を下げる方法(モディフィケーション)、難易度を上げる方法(プログレッションとバリエーション)を含む「エクササイズのパーソナライズ」という項目が追加され、適用範囲が広がり、自分のレベルや目的に合わせて変化をつけられるように改良された。本書は、初版より9年の時を経て、おおいなる進化を遂げ、私たちを更なる深みへと到達させてくれる。 はじめに 第1章 ピラーティスの6つの原則 第2章 脊柱、コア、ボディ・アライメント 第3章 筋肉、動きの分析、マットワークを始める前に 第4章 マット・セッションの基本 第5章 動きと安定のための腹筋ワーク 第6章 柔軟な脊柱のための精密なアーティキュレーション 第7章 機能的な脊柱のためのブリッジング 第8章 効果的なコアのための体側のエクササイズ 第9章 強い背中のための伸展エクササイズ 第10章 ピラーティス・プログラムのカスタマイズ エクササイズ一覧 参考文献 著者・監訳者略歴 Earn Continuing Education Credits/Units
本書は、ピラティスの創始者ジョセフ・H・ピラティスの著作『YOUR HEALTH』と『Return to Life』を合本したもので、ピラティス・メソッド(コントロロジー)の理論と実践を深く理解するための内容が紹介されています。初の日本語版として、70年の歴史を持つ名著を通じて、ピラティスを学ぶ人々に向けた重要な一冊です。著者ジョセフ・H・ピラティスの背景や、ピラティスを広めた経緯も触れられています。
この書籍は、ピラティスの歴史や医療・コンディショニングにおける研究を紹介するPART I、部位別の機能改善を目的としたピラティスアプローチを解説するPART II、持ち運び可能な器具を用いた実践的なピラティス方法を紹介するPART IIIで構成されています。各章では、ピラティスの効果や応用方法が詳述され、スポーツ現場での活用法も含まれています。著者は近良明と桑原匠司です。
本書は、ラグビー日本代表も取り入れたピラティスを基にしたアスリート向けの運動療法プログラムを紹介しています。著者の本橋恵美が考案した43種のマットエクササイズは、怪我の予防やパフォーマンス向上に役立ち、体幹強化や左右差・痛みの軽減を目指します。最新のスポーツ医科学に基づく知識も提供され、プロ・アマ問わずスポーツに真剣に取り組む人にとっての必携書です。
この文章は、ピラティスに関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。書籍は三部構成で、第一部ではピラティスの科学的背景や指導原理、リハビリテーションへの統合について議論しています。第二部では、マットやリフォーマーなどのエクササイズを紹介し、第三部では特定の外傷や障害に対するピラティスエクササイズを取り上げています。著者は理学療法士であり、ピラティスと理学療法の統合に特化した専門家です。
マルマとは「ダメージを受けると死に至る急所」。ヨーガ、アーユルヴェーダ、インド古代武術との関連性や経穴との相違点を解説。 マルマとはダメージを受けると死に至る急所のことであり、アーユルヴェーダでは治療のポイントとして扱われる。本書はヨーガ、アーユルヴェーダ、インド古代武術とマルマの関連性などを解説し、マルマの全貌を明らかにする。 マルマとは「ダメージを受けると即死に至る臓器、急所」。アーユルヴェーダでは、マルマは治療ポイントとして扱われ、その位置は秘伝とされている。本書では、サンスクリット原典と解剖学を照らし合わせ、マルマの位置を特定。また、ヨーガ、アーユルヴェーダ、インド古代武術とマルマの関連性、マルマと混同されがちな経穴との相違点を解説する。ヴェールに包まれたマルマの全貌が今明らかになる……。 ヨーガ、アーユルヴェーダ、アロマセラピー、マッサージ、鍼灸、統合療法を学ぶ人、必携の書! 各章概説 第1章「マルマと経穴」では、マルマと鍼灸、経穴を対比しながら、類似点や相違点を解説。 第2章「インド古代武術とマルマ」では、インド古代武術で奥義とされるマルマの知識を取り上げる。 第3章「マルマとアーユルヴェーダ」では、マルマの診断法や治療法など、具体的なテクニックを紹介。 第4章「マルマの解剖学」では、サンスクリット原典と解剖学を照らし合わせながら、秘伝とされるマルマの位置を特定。著者作成の解剖イラストを掲載し、近接する経穴の名称も添えた。 第5章「マルマとヨーガ」では、マルマの知識を踏まえ、西洋化によって歪曲されたプラーナやチャクラなどのヨーガ固有の概念の真の姿に迫る。 巻末には、アーユルヴェーダ三大経典の一つ『スシュルタ・サンヒター』身体篇マルマ論のサンスクリット原文と著者による和訳を掲載。 はじめに マルマチャート 第1章 マルマと経穴 第2章 インド古代武術とマルマ 第3章 マルマとアーユルヴェーダ 第4章 マルマの解剖学 第5章 マルマとヨーガ 第6章 スシュルタ・サンヒター身体篇マルマ論 参考文献 おわりに
本書は、肉眼解剖学の専門家北村清一郎先生と工藤慎太郎先生が共同で執筆した運動器アトラスです。セラピストの視点から、結合組織や臨床での問題部位を新しい角度で解説し、運動療法の効果をエコーで可視化しています。内容は上肢、下肢、体幹に分かれ、それぞれの関節や筋肉の解剖学的な問題を詳細に説明しています。
この書籍は、運命を改善し幸運を引き寄せるための生き方を提案しています。著者は、ヨガの基本と究極のメソッドを紹介しており、特に「ヤマ」と「ニヤマ」という教えに焦点を当てています。これらは、非暴力や誠実さ、清浄さ、自己探求など、心と体を美しく磨くための指針です。著者は、インド政府公認のシッダーマスターであり、悟りを開いた経験を持つ人物です。
アーユルヴェーダ料理の決定版。食べることは生きること。なにをどう食べるかで人生が大きく左右されることを解き明かす叡智の結集。 私たちの体はすべて、私たちが「食べたもの」から作られる。そんな簡単なことを、なぜ私たちは忘れてしまったのか。スパイス(漢方薬)を日常食に取り入れ、体を健やかに整えつつ心まで癒すアーユルヴェーダ料理の決定版。 アーユヴェーダ料理の決定版。 食べることは生きること。 なにを食べるか、どう生きるか。 古代インドから届く、命を輝かせる美味しいメッセージ——。 私たちの身体はすべて、私たちが「食べるもの」で出来上がっている。 そんな簡単なことを、なぜ私たちは忘れてしまったのだろう。 日本のアーユルヴェーダ学会を牽引する重鎮イナムラ・ヒロエ・シャルマ医師——日本人で初めてインドのグジャラート・アーユルヴェーダ大学大学院を卒業。アーユルヴェーダ医師の資格を取得し現地で10年開業後帰国——が、アーユルヴェーダの食に対する思想・哲学を、わかりやすく解説。 日本のアーユルヴェーダ料理の第一人者、インド・スリランカのスパイス料理を日本に紹介し続けている香取薫が、現地で習得してきた本格的アーユルヴェーダ料理のレシピを惜しげなく公開。 アーユルヴェーダで使われる薬草の薬効などの解説を、日本でそれらを実際に育て、研究している彦田治正氏が執筆。 アーユルヴェーダは、なぜ「食べること」にこだわるのか……。 人生を明るく楽しく、そして正しく生きることは、なにをどう食べるかにかかっている。 食べることの意味を、とことん追求したアーユルヴェーダの叡智に触れてください。 はじめに イナムラ・ヒロエ・シャルマ 1 アーユルヴェーダ健美食 理論編 イナムラ・ヒロエ・シャルマ 第1章 アーユルヴェーダにとって健康とはなにか 11 人はなんのために生きているのか 12 健康とはどういう状態か 16 第2章 ドーシャ理論を知り、自分の体質を知る 21 トリ・ドーシャ理論とはなにか 22 ドーシャはどうやって作られ、どう変化していくか 26 ドーシャの乱れによって起きる病気 33 持って産まれた体質を知ろう 37 体質チェックテスト 40 第3章 食事について 43 食の原則 44 一日のなかでの食事法 45 季節による食べ方 49 オイルについて 51 肉について 53 有益な食べ物、無益な食べ物 54 気をつけるべき食べ合わせ 55 体質別食事法 57 酒について 60 感謝の気持ち 63 第4章 アーユルヴェーダ健美食 スパイスとレシピ 香取 薫 65 スパイスとその他の食材 66 ギーの作り方 78 タルカのやり方 クミンのタルカ/マスタードシードのタルカ/タルカの作り置き 80 基本のキチュリー アーユルヴェーダ食の優等生 82 大根たっぷりキチュリー しみじみ癒されたいときに 84 ドライフルーツキチュリー ほんのり甘い滋養粥 85 ポンガル 南インドの伝統料理、白い粥 86 プラウ スパイス入り炊き込みご飯 88 ムーングドライダール 緑豆のシンプルな炒めもの 90 基本のダール 毎日食べたい豆カレー 92 ウラド豆のにんにく味スープ 体力をつけ、体を芯から温める 94 ペサラットゥ 朝食に向く緑豆のドーサ 96 スパイスオイルをかけたサラダ クミンのタルカで消化に優しく 98 コラサンボーラ 葉野菜のココナッツ味サラダ 100 野菜を茹でたり蒸したり ギーソースをかけて 102 野菜を炒めて ギーとスパイスを使って 103 キャベツ ポリヤル 南インドの野菜炒め 基本 104 カリフラワー サブジ 北インドの野菜料理 基本 106 小松菜マッルン ココナッツ香る軽い青菜炒め 108 冬瓜サブジ とろりとした優しい味 110 冬瓜のココナッツ味スープ 食欲がない夏に 112 冬瓜のクールドリンク ココナッツウォーターを使って 113 ビーツのサーンバール 南インドの豆入り野菜カレー 114 ビーツクートゥー 南インドの代表的副菜をビーツで 116 肉入りルビースープ 比類なき最強滋養スープ 118 ヤギマトンのココナッツシチュー 肉の摂り方のお手本、ケーララの薬膳 120 トゥラシーの香りの蒸し魚 ハーブを使った香りも薬効も最高の時短料理 122 コラキャンダ ココナッツ入り青汁粥 124 コリアンダースープ 大好きな香菜をクミンの香りで 126 ハニーナッツデーツ 食べすぎ注意の美味しいスイーツ 128 黒ごまの鉄分補給菓子 女性を元気にする生薬スイーツ 129 アロエ入りクミン味くず湯 美味しい整腸剤 130 アロエ入りジュース アロエと果物をスパイスで 131 キャロットキール 心と体に幸せドリンク 132 シャターヴァリーを使って アーユルヴェーダの若返り生薬 133 ジャルジーラー 暑いインドの定番ドリンク 134 フルーツマサラのすすめ アジア流、フルーツの味わい方 135 バターミルク用の調合マサラ スパイス入り消化促進ドリンク 136 ヒーングアシュタクチュールナを常備しよう 調合スパイスの消化薬 137 パーパル 体によいアルカリ性食品 138 生姜&消化を助ける知恵 インド伝統のホームレメディー 139 アーユルヴェーダで特に推奨されるハーブなど 彦田治正 140 シャターバリー ツボクサ トゥラシー カレーリーフ コリアンダー(香菜) 鉢植えで育てる 144 ツボクサ トゥラシー カレーリーフ コリアンダー(香菜) 第5章 私のアーユルヴェーダ食 香取 薫 146 おわりに 香取 薫 157 プロフィール&参考文献 158
アーユルヴェーダで健康に良い果実として使われるアムラの栽培・使用法、またアーユルヴェーダの基礎知識を正しく伝える本。 アーユルヴェーダで使われる果実アムラは、脳活性化、神経滋養、皮膚病、食欲不振、虚弱体質や頭痛改善に効能があるとされる。そのアムラの栽培・使用法、また自然治癒力を生かすアーユルヴェーダの基礎知識を正しく伝える。 日本でも注目されて久しいインドの伝統的医学アーユルヴェーダ。 インドでは代表的果実として知られるアムラは、 脳の活性化、若返り、神経の滋養、せきを鎮める、皮膚病、食欲不振、 虚弱体質や頭痛の改善などの目的で使用されている。 化学薬品ではなく自然の力を取り入れるアーユルヴェーダの 基本知識からアムラの栽培と使用法までを、日本で正しく伝えるための本。 もくじ(抜粋) アーユルヴェーダとは アムラの植物学的分類 アムラ栽培の実践 (環境/土壌/農地の準備/品種/栽培方法(種子~苗作り)/ 植え付け/手入れと剪定(発芽の保護)etc…) 価値を高めるために アムラの使用法(乾燥方法/外用での使用 内服での使用) 様々な処方……
ヨーガの根本経典、『ヨーガ・スートラ』を、スワミ・サッチダーナンダ師が弟子たちにわかりやすく語った内容を一冊の本にしました。 4つのパダ、196のスートラから構成される「ヨーガ・スートラ」は、簡潔だが凝縮度の高い経典です。本書は著者のスワミ・サッチダーナンダ師が弟子たちにわかりやすく語った講話を基に、一冊の本にまとめたものです。 「ヨーガ・スートラ」は4つのパダ、196のスートラから構成された、簡潔ではあるが凝縮度が高い経典です。本書は著者であるスワミ・サッチダーナンダが弟子たちに行った講話の記録を基にしているため、その語り口はとてもやさしく、「ヨーガ・スートラ」を初めて学ぶ読者にとっても、解りやすいものになっています。 ◎初心者のために「サンスクリット語句の英語訳注」を収録。 ◎唱誦する人のためにヨーガ・スートラ全文をデーヴァナーガリーとローマ字で掲載。 序 はじめに 第一部 サマーディ・パダ(三昧部門) 第二部 サーダナ・パダ(実修部門) 第三部 ヴィブーティ・パダ(成就部門) 第四部 カイヴァリャ・パダ(絶対部門) サンスクリット語句の英語訳注 巻末付録 誦習のためのヨーガ・スートラ全文
ヨガの考え方の基本「ヤマ・ニヤマ」は、豊かな人生を送る手助けをしてくれ、実践により「気付き」のスキルを身につけることができる ヨガの考え方「ヤマ・ニヤマ」の10の教えを現代的で身近なたとえ話になぞらえて、読者の心にすっと入り込むよう、わかりやすく解説。「気付き」を持たせるスキルを実践により身につけることができる。 私たちは矛盾だらけの世の中で、人生をうまく舵取りしていかなければなりません。「ヤマ・ニヤマ」の10の教えが、そのサポートしてくれます。 ヤマ(制限)とニヤマ(観察)は、ヨガの考え方の基本であり、健康的に生きるための指針です。 教えの終わりにある問いを実践することで、日常の中に「気づき」を持たせるいくつかのスキルを、身につけることができます。真の自分を見つけ、いままで想像すらしなかった豊かで満ち足りた人生を送る手助けをしてくれます。 本書では、読者の心にすっと入り込むように、現代的で親しみやすくわかりやすいエピソードを用い、この古代の知恵を明らかにしています。 たとえば、執着についての章では、バナナを手放すか、手放さないか? 手放さないとどうなるのかを、インドの伝統的な猿猟の手法を例に出し説明しています。自分が執着しているものに気づき、それを手放し自由になるための実践を学ぶことができます。 10の教え [アヒムサ(傷つけない)/サティア(嘘をつかない)/アスティヤ(盗みをしない)/ブラフマチャリヤ(不節制をしない)/アパリグラハ(執着しない)/ソウチャ(身辺を綺麗にする)/サントーシャ(今あるものに感謝する)/タパス(自分を高める)/スワディヤーヤ(自分自身を知る)/イシュワラ・パラニダーナ(運命を受け入れる)] 本書は『ヤマ・ニヤマ ヨガの10の教え』(ISBN:978-4-88282-966-9)の新装改題版です。 ヤマ・ニヤマの教えは現代に生きる私たちにこそ必要です/序文/ヤマ・ニヤマとは アヒムサ(非暴力) 勇気を見つける/バランスを保つ/無力感の対処法/自分を愛する/他人への暴力/思いやりの心を広げる/探求のための問い サティア(不嘘) いい人ではなくリアルな人になる/自分を表現するvs.自分を甘やかす/何かに属するvs.成長する/最初から正しく行う/真実はいつも同じではない/真実の重さ/真実の力/探求のための問い アスティヤ(不盗) 他人から盗む/地球から盗む/未来から盗む/自分自身から盗む/意識の向け先を変える/能力を上げる/探求のための問い ブラフマチャリヤ(不過度) 不過度-怠け心の制御/神と歩く/探求のための問い アパリグラハ(不貪) 呼吸に教わる/空中でとどまる/バナナを諦めろ!/所有するものに所有される私たち/バッグをいくつ持っていくの?/気にするべき?/探求のための問い ヤマのまとめ ソウチャ(清浄) 浄化して純粋になる/関係に純粋である/自分の破片を集める/探求のための問い サントーシャ(満足) 準備だけは万端/喜びと逃避/心の乱れは自分の責任/感謝/軸を持つ/追いかけない/探求のための問い タパス(自己鍛錬) 日々の練習とタパス/しがみつく力とタパス/タパスを選ぶ/探求のための問い スワディヤーヤ(自我の探求) 投影/過去をたどる/怖がらずに見る/エゴの役割/傍観者の力/探求のための問い イシュワラ・パラニダーナ(降伏) 手放す/つながる/受け入れる/献身/探求のための問い ニヤマのまとめ これから/付録/著者について
ただ自然なままにリラックスし、身体、呼吸、ハートの相互関係に身をゆだねるヨーガを始められるようになるための1冊。 ヨーガの本当のメッセージとは?ただ自然なままにリラックスし、教義の拘束を解き本来の自分を呼び起こし、身体、呼吸、ハートの相互関係に身をゆだねるヨーガを始められるようになるための1冊。 ただ自然なままにリラックスし、身体、呼吸、ハートの相互関係に身をゆだねるヨーガを行いましょう。 著者・マーク・ウィットウェルは、すべての人のために、教義の拘束を解き、自然なままの私たちの中に存在する、平穏と力を慈しみ、すべてを教えてくれる効果的で完璧なヨーガを復元しました。あなたが師とめぐり会い、真のヨーガを学ぶための準備をサポートしてくれます。 本書は、マークがこれまでに学んだ叡智の結晶です。あなたが「唯一無二の自分自身を表現する生命」としてこの世界に存在していること、何も付け足さなくても、愛そのもの、神聖さそのものとして、今この瞬間に奇跡のように生きていることを実感できるはずです。 あなたの求めているものは、すでにあなたの中にあります。親密なるヨーガに触れ、精神の奥底にある本来の自分を呼び起こしましょう。 本書は『ヨーガの真実』(ISBN:978-4-88282-614-9)の新装版です。 新装版によせて 相互の友情に基づいたヨーガの学びをもう一度 はじめに 第1章 ほんとうのヨーガとは? ヨーギ(ヨーガ行者)とは一様に作り上げられるものではありません ヨーガのすべて あなたは今、ここにいます。(『ヨーガストラータ』にある言葉より) 生命のヨーガ ヨーガとは相互関係です 人から人へ 生命として生きるということ 上がらなくてはならない階段など、どこにもありません ヨーガ・サーダナ 生命の中で、男性と女性は対等です ほんとうのヨーガ あなたは今ここにいます 第2章 解き放たれて ごく普通の人こそ悟りの境地にあるのです 指導者とは 神聖な書 自分のための時間 マントラ ヨーガと宗教 第3章 あなたのヨーガ アーサナとプラーナーヤーマ、その原則 スティラ(安定)とスッカ(快適) 自分が経験した通りに、ヨーガを指導しましょう 基本のアーサナ 変型ポーズとヴィンヤサ プラーナーヤーマー 意識的呼吸、プラティヤハーラ(感覚遮断)、ダーラナー(集中)とバハーヴァナ(瞑想) 鼻孔を交互に使うプラーナーヤーマ 技術的なこと 速い呼吸と鼓動 エネルギーの流れる道と体の中の相互性 ダンス 食事と、生命の持つ知性 バンダ 第4章 瞑想 サンスクリット用語解説 Illustration Sources
この書籍は、基本から上級までのヨガポーズを流派を超えて学べる内容です。目次には立位、座位、四つ這い、臥位、腕立ちのポーズが含まれています。著者には、ヨガの世界大会で日本人初のワールドチャンピオンとなった三和由香利、アシュタンガヨガの正式指導資格を持つケン・ハラクマ、アイアンガーヨガの上級指導者である柳生直子がいます。
本書は、日本ヨーガ瞑想協会会長の綿本彰が、ヨガの重要な100のポーズを紹介する内容です。綿本氏のメソッドを基に、ポーズの写真と解説が掲載されており、初心者から上級者まで幅広い読者に向けて、正しいポーズの形や体の使い方をわかりやすく説明しています。ヨガの本質を理解し、より深く実践するための信頼できる教科書として位置付けられています。
決定版 ヨーガのポーズ集 決定版 ヨーガのポーズ集 ヨーガのポーズを170以上集めた、ヨーガを実践する人に最適なあらゆる情報を網羅した究極のバイブル。レベルや必要に応じて、知りたいポーズをすぐにみつけることができる。 1 ヨーガを始める前に 2 ヨーガの実践(準備運動 立位のポーズ 座位と床を使ったポーズ ねじりと腹部調整のポーズ バランス 後屈 逆転のポーズ リラクゼーション プラーナーヤーマ(調気法) ムドラー(印) ほか) 3 ヨーガを活用するには 4 自分のヨーガを見つけよう
この書籍は、アサナの実習を快適に行えるように、600枚の写真を大きく美しく掲載し、新たに「300週のアサナプログラム」と用語解説を追加しました。サンスクリット語のポーズ名も収録されており、目的のポーズを容易に見つけられ、理解を深めることができます。内容はヨガの基本、アサナの実践、プラーナーヤーマなどを網羅しています。著者は沖正弘をはじめとする専門家たちです。
『SCIENCE of YOGA』の日本版が登場し、ヨガ初心者からインストラクターまで必携の一冊です。本書では、人体解剖学を基に、ヨガのポーズを高品質なCGで解説し、動きや筋肉への効果を科学的に説明します。また、Q&Aセクションでヨガに関する疑問にも答えています。著者は理学修士のアン・スワンソンと産婦人科専門医の高尾美穂です。
460枚の解剖学習カードがポケットサイズの単行本として再登場し、筋の起始・停止・神経支配・作用に関する情報が追加されました。美しい解剖図に加え、オリジナルの索引や臨床的コメント、Q&Aも含まれており、持ち運びに便利で解剖用語の学習に役立ちます。
この書籍は、骨格筋をCGを用いて詳細に解説しており、筋肉の付着位置、形状、起始・停止位置、筋繊維のタイプや方向、長さなどを正確に理解できる内容です。最新の研究情報も含まれ、医療・介護・スポーツ関係者にとって必携の資料であり、暗記に役立つ赤シートも付属しています。著者は筋肉研究の権威である石井直方と、元プロ格闘家の荒川裕志です。
本書は、ヨガにおける重要な呼吸法「プラーナーヤーマ」と瞑想の基礎と応用を、著名な導師が実技指導する内容です。目次は、プラーナーヤーマの定義、基本、実践方法、瞑想(ディヤーナ)とリラクゼーション(シャヴァアサナ)に分かれています。著者の沖正弘は、様々な宗教や哲学を学んだ経験を持つ専門家です。
108種類のムドラと瞑想(音声付)を詳細に解説。健康と癒しと精神的な覚醒を深めるのに欠かせないムドラと瞑想を存分に堪能できる 108種類のムドラと瞑想を詳細に解説。ムドラを正しく実践するための詳細な手順、ムドラの主な効能、類似のムドラや注意・禁忌などを掲載。瞑想の手順は箇条書きでさらに音声つきなので、自然により深い瞑想へと入れます。 サンスクリット語の「mudrá」には、「身ぶり、印、態度、特性」などの意味があります。それぞれの印相の特性に応じた、心のあり方や精神的な態度を喚起してくれるジェスチャー、それがムドラです。 ・108種類の「ムドラ」とそれにあった深い「瞑想」を詳細に解説しています。 ・ムドラのイラストと、ムドラを正しく実践するための手順、ムドラの主な効能、核となる特性や注意・禁忌などを収録しています。 ・印の組み方の手順が丁寧に示されていますので、初心者でも簡単にムドラをつくることができます。 ・瞑想の手順は、箇条書きのテキストになっているため、順を追って行うことで自然に深い瞑想の世界へと誘ってくれます。 各瞑想には、「執着心のなくし方を学ぶ」、「活力のエネルギーを拡張する」、「内なる観察者を覚醒させる」、「消化機能を改善する」など、それぞれにタイトルがあり、「今の自分」にぴったりと合った「ムドラ瞑想」を選ぶことができます。また、効能別の索引もあり、その日の体調や気持ちの変化に合わせた「ムドラ瞑想」を選び、日々のセルフケアにも効果的に活用できます。 個々の特性を呼び覚まし、統合の世界的な地平へと自然に導いてくれる手段、それが「ムドラ瞑想」です。 体レベル、エネルギーレベル、心理・感情レベル、精神レベルそれぞれにおけるムドラと瞑想の効果を存分に感じてください。 ※付録に「ムドラの核となる特性」と「ムドラと健康上の問題」を収録。 さらに、よりムドラに集中し、深く心地よい瞑想へと入り込めるよう、108の瞑想を音声化し、書籍ご購入後にダウンロードいただけます。 目次 効能別目次 本書の使用法 はじめに ムドラの宇宙 1. カニシュタ・ムドラ 執着心のなくし方を学ぶ 2. アナーミカー・ムドラ 滋養と癒やしの海に浸される 3. マディヤマ・ムドラ エネルギーバランスを調える 4. タルジャニー・ムドラ 心のシンフォニーを奏でる 5. アングシュタ・ムドラ 内なる声を聴く空間を作る 6. ハーキニー・ムドラ 存在の全ての層を統合する 7. カニシュタ・シャリーラ・ムドラ 上体下部の呼吸を覚醒させる 8. マディヤマ・シャリーラ・ムドラ 上体中部の呼吸を覚醒させる 9. ジェシュタ・シャリーラ・ムドラ 上体上部の呼吸を覚醒させる 10. プールナ・スワラ・ムドラ 呼吸の全領域を覚醒させる 11. アディ・ムドラ 静寂の彫像と化す 12. アド・メルダンダ・ムドラ 中心軸を定める輪を広げる 13. メルダンダ・ムドラ 大地と空をつなぐ軸と一致する 14. ウールドヴァム・メルダンダ・ムドラ 背中側の呼吸を拡張する 15. プリティヴィ・ムドラ 身体に帰還する 16. ヴィッタム・ムドラ 活力のエネルギーを拡張する 17. プールナ・フリダヤ・ムドラ 感情の波に乗る 18. チッタ・ムドラ 内なる観察者を覚醒させる 19. ハンシー・ムドラ 本質的な好ましい特性を覚醒させる 20. ルーパ・ムドラ 大地の美酒に育まれる 21. アヌダンディ・ムドラ 呼吸の波で痛みとこりを緩和する 22. マツヤ・ムドラ 内なる潮だまりで痛みを緩和する 23. アパナヤナ・ムドラ 全ての活動のバランスを調える 24. ヴァールナ・ムドラ 内なる流れを新たにする 25. ヨニ・ムドラ 内なるリズムに同調する 26. シャーンカ・ムドラ 健やかさの泉に癒やされる 27. トリムールティ・ムドラ 内なるバランスの三角形に留まる 28. プーシャン・ムドラ 消化機能を改善する 29. ブラフマー・ムドラ 内なる太陽が輝く 30. ミーラ・ムドラ 楽な呼吸の波が打ち寄せる 31. ヴァーヤン・ムドラ 静穏な流れに満たされる 32. アパーナ・ヴァーユ・ムドラ 心臓の知恵に耳を傾ける 33. マハーシールシャ・ムドラ 緊張を下に向かってほぐす 34. ガルダ・ムドラ 翼のバランスを調える 35. ヴァジュラプラダマ・ムドラ 心臓の本質的な特性を育む 36. パーラ・ムドラ 静穏さの聖域に安らぐ 37. ヴィヤーナ・ヴァーユ・ムドラ 脳からの明快な情報伝達を再構築する 38. ブラーマラ・ムドラ 健全な境界線を築く 39. マニ・ラトナ・ムドラ 存在の全ての層を癒やす 40. ブー・ムドラ 山の安定性を身につける 41. ジャラ・ムドラ 人生の流れに身を任せる 42. スーリヤ・ムドラ 変容の陽光を浴びる 43. ヴァーユ・ムドラ 存在を軽やかにする 44. アーカーシャ・ムドラ 広々とした空間の感覚を高める 45. ダルマ・プラヴァルタナ・ムドラ 五大元素のバランスを調える 46. アチャラ・アグニ・ムドラ 消化を改善する 47. アバヤ・ヴァラダ・ムドラ 存在における中心軸を定める 48. ジャラーシャヤ・ムドラ 静かな湖に身を浸す 49. ラトナ・プラバー・ムドラ 活力の宝石を輝かせる 50. アパーナ・ムドラ 下向きのエネルギーの流れを浄化する 51. プラーナ・ムドラ 上向きのエネルギーの流れを活性化させる 52. マータンギー・ムドラ 輝くエネルギーが流れだす 53. リンガ・ムドラ 清澄さを覚醒させる 54. アヌシャーサナ・ムドラ 全方向へ広がるエネルギーを覚醒させる 55. チンマヤ・ムドラ 全き安心感を具現化する 56. スワディシュターナ・ムドラ 自己に帰還する 57. ヴァジュラ・ムドラ 内なる宝石を輝かせる 58. パドマ・ムドラ 心の庭園を歩く 59. カーリー・ムドラ 浄化の巡礼の旅に出る 60. トリシューラ・ムドラ 二元性を超越した見方をする 61. アナンタ・ムドラ 純粋意識を覚醒させる 62. ダルマ・チャクラ・ムドラ ビジョンを顕現させる 63. イダー・ムドラ 心安らぐ月光に養われる 64. ピンガラ・ムドラ 輝く陽光のエネルギーを浴びる 65. シャカタ・ムドラ 統合に覚醒する 66. ヴァイカーラ・ムドラ 五大元素の保護の特性を統合する 67. スワスティ・ムドラ 保護のエネルギーのオーラに包まれる 68. グプタ・ムドラ 内なる安全な聖域に入る 69. ガネーシャ・ムドラ 新たな始まりに向けた保護を得る 70. ドヴィムカム・ムドラ 静穏さの波に浸される 71. クールマ・ムドラ 五感を回復させる 72. プラニダーナ・ムドラ 執着心のなくし方を学ぶ 73. ウシャス・ムドラ 新たな一日の夜明けを迎える 74. カポタ・ムドラ 平和を誓う 75. サンプタ・ムドラ 内なる真実に同調する 76. ハスタプラ・ムドラ 与えることと受けとることのバランスを調える 77. クベラ・ムドラ 生命エネルギーを貯える 78. プシュパーンジャリ・ムドラ 人生を軽やかにとらえる 79. ヴィシュッダ・ムドラ 存在の全ての層を浄化する 80. チャトゥルムカム・ムドラ 充足感の波に浸される 81. ムシュティカーム・ムドラ 精神的鍛錬の火を燃やす 82. サークシー・ムドラ 自己探求の旅に出る 83. チン・ムドラ 万物に神を見出す 84. ムールティ・ムドラ 安定性と快適さのバランスを調える 85. ディールガ・スワラ・ムドラ 生命エネルギーを拡張する 86. イーシュヴァラ・ムドラ 五感を内向きにする 87. アビシェカ・ムドラ 集中力の内なる炎を燃やす 88. ダルマダートゥ・ムドラ 受け入れて観察する 89. マンダラ・ムドラ 統合の旅に出る 90. シヴァリンガム・ムドラ 精神修養の確かな基盤を築く 91. シューンヤ・ムドラ 変容への開放性を高める 92. パッリ・ムドラ 内なる導きを信頼する 93. アーヴァーハナ・ムドラ 心から受け入れる 94. カルナー・ムドラ 慈悲心を覚醒させる 95. プールナ・ジュニャーナム 洞察力を高める 96. ヴァラーカム・ムドラ 落ちつきをもたらす円環を作る 97. シャクティ・ムドラ 精神エネルギーを覚醒させる 98. ウッターラボディ・ムドラ 自らの主となる 99. カーレシュヴァラ・ムドラ 知恵と慈悲を統合する 100. プラージュナ・プラーナ・クリヤー 体と呼吸を安定させる 101. メダー・プラーナ・クリヤー 思考と感情を受け入れる 102. ジュニャーナ・ムドラ 清澄な眼力を覚醒させる 103. ディヤーナ・ムドラ 瞑想の流れを安定させる 104. バイラヴァ・ムドラ 統合を体験する 105. フリダヤ・ムドラ 神の保護を求める 106. アーダーラ・ムドラ 豊かに受けとるために心を開く 107. テジャス・ムドラ 信愛の光を覚醒させる 108. アンジャリ・ムドラ 統合を呼び覚ます 付録A ムドラの核となる特性 付録B ムドラと健康上の問題
本書は、安全かつ適切に生徒を導くためのヨガのアジャストメント技術を解説しています。アジャストメントとは、講師が生徒の身体に触れることでポーズの意図を示す手法です。内容は、アジャストメントの哲学や基本原則から始まり、各アーサナにおける具体的なテクニックを紹介しています。著者は日本ヨーガ瞑想協会の会長であり、多様なヨガスタイルの指導経験を持つ専門家です。
スヴァーミー・シヴァーナンダは現代インドのヨーガ聖者で、ディヴァイン・ライフ・ソサエティを創設し、様々なヨーガの教えを統合して社会に奉仕しました。彼はインド国民を精神的に目覚めさせる活動を行い、究極の愛について説いています。本書は彼の生涯やヨーガの理論と実践についての内容で構成されています。著者は成瀬貴良で、ヨーガの歴史と思想を講義しています。
『ヨガ数秘学』は、インド発祥のクンダリーニヨガを基に、マスター・タイラー・モンガが再構築した数秘学のガイドブックです。誕生日を元に9つのポジションと11の数字を組み合わせて個人の本質やライフストーリーを読み解く方法を紹介しています。人生の各段階(15歳、25歳、35歳、45歳など)によって異なる数字を読み取ることができ、個別の分析が可能です。著者はマダムYUKOで、数秘学のオンライン講座やリーディングセッションを提供しています。
108種類のムドラの、身体および微細なレベルにおける重要な効能がひと目でわかる本書は、健康と癒しを存分に得ることができる。 現代人に蔓延する健康上の問題(高血圧、消化器疾患、腰痛、関節炎、不安障害、うつ病)に対処する、健康と癒しを深める108種類のムドラを見開きオールカラーで詳細に解説。ムドラの効果を実感して心身の健康を取り戻す。 ムドラとは、体の健康や心のバランス、そして精神的な覚醒を促してくれる、手や顔や体を使ったジェスチャーのことです。 本書では、108種類のムドラを見開きオールカラーで詳細に解説しています。コーシャ(5つの鞘)の種類に従い、身体的なレベルから精神的なレベルへと徐々に高まるように組み込まれ、順を追って実践することで、初心者でも簡単に日常生活に取り入れることができます。 また、108種類のムドラによって活性化したりバランスが調ったりする、主要な器官系や微細な構造を、アイコンで表しています。その内訳は、人体の12の器官系、五大元素、5つのプラーナ・ヴァーユ、7つのチャクラ、アーユルヴェーダの3つのドーシャの5種類です。これらが一目で分かることで、様々な方向から自分自身を鍛え、癒すことができる本書は、まさにムドラを網羅した大全といえます。 ムドラの実践にあたって、本書では以下のようなユニークなアプローチを取っています。 ・108種類のムドラを詳細に解説。健康と癒しと精神的な覚醒を深めるのに欠かせない特性を目覚めさせる。 ・現代人に広く蔓延する健康上の問題(高血圧、消化器疾患、腰痛、関節炎、不安障害、うつ病など)に対処するムドラを紹介。 ・各ムドラの身体および微細なレベルにおける重要な効能がひと目でわかるよう、色分けされたアイコンを使用。 ・ヨガのポーズや呼吸法を補助するためのムドラの使用法や、マントラの詠唱を助ける一連のムドラなど、豊富な付録を記載。 「ヨガはハードルが高いし、通うのも億劫」だと思われている方、まずは簡単にできる「入門編ムドラ」で基礎を形作り、ムドラの効果を実感して心身の健康を取り戻してみませんか。 本書は、初心者はもちろんのこと、ヨガを学ぶ人やヨガインストラクターにとって貴重な支えとなるだけでなく、ヒーリングに携わるあらゆる専門家にとっても助けとなる書です。 Ⅰ 入門編ムドラ 第1章 はじめに 第2章 ハスタ・ムドラ 1.カニシュタ・ムドラ 2.アナーミカー・ムドラ 3.マディヤマ・ムドラ 4.タルジャニー・ムドラ 5.アングシュタ・ムドラ 6.ハーキニー・ムドラ 第3章 シャリーラ・ムドラ 7.カニシュタ・シャリーラ・ムドラ 8.マディヤマ・シャリーラ・ムドラ 9.ジェシュタ・シャリーラ・ムドラ 10.プールナ・スワラ・ムドラ 第4章 メルダンダ・ムドラ 11.アディ・ムドラ 12.アド・メルダンダ・ムドラ 13.メルダンダ・ムドラ 14.ウールドヴァム・メルダンダ・ムドラ 第5章 5つのコーシャのムドラ 15.プリティヴィ・ムドラ 16.ヴィッタム・ムドラ 17.プールナ・フリダヤ・ムドラ 18.チッタ・ムドラ 19.ハンシー・ムドラ Ⅱ アンナマヤ・コーシャ(食物鞘) 第6章 健康上の問題に効くムドラ 20.ルーパ・ムドラ 21.アヌダンディ・ムドラ 22.マツヤ・ムドラ 23.アパナヤナ・ムドラ 24.ヴァールナ・ムドラ 25.ヨニ・ムドラ 26.シャーンカ・ムドラ 27.トリムールティ・ムドラ 28.プーシャン・ムドラ 29.ブラフマー・ムドラ 30.ミーラ・ムドラ 31.ヴァーヤン・ムドラ 32.アパーナ・ヴァーユ・ムドラ 33.マハーシールシャ・ムドラ 34.ガルダ・ムドラ 35.ヴァジュラプラダマ・ムドラ 36.パーラ・ムドラ 37.ヴィヤーナ・ヴァーユ・ムドラ 38.ブラーマラ・ムドラ 39.マニ・ラトナ・ムドラ 第7章 五大元素のムドラ 40.ブー・ムドラ 41.ジャラ・ムドラ 42.スーリヤ・ムドラ 43.ヴァーユ・ムドラ 44.アーカーシャ・ムドラ 45.ダルマ・プラヴァルタナ・ムドラ 第8章 アーユルヴェーダの癒しのムドラ 46.アチャラ・アグニ・ムドラ 47.アバヤ・ヴァラダ・ムドラ 48.ジャラーシャヤ・ムドラ 49.ラトナ・プラバー・ムドラ Ⅲ プラーナマヤ・コーシャ(生気鞘) 第9章 プラーナ・ヴァーユのムドラ 50.アパーナ・ムドラ 51.プラーナ・ムドラ 52.マータンギー・ムドラ 53.リンガ・ムドラ 54.アヌシャーサナ・ムドラ 第10章 チャクラのムドラ 55.チンマヤ・ムドラ 56.スワディシュターナ・ムドラ 57.ヴァジュラ・ムドラ 58.パドマ・ムドラ 59.カーリー・ムドラ 60.トリシューラ・ムドラ 61.アナンタ・ムドラ 62.ダルマ・チャクラ・ムドラ 第11章 ナーディのムドラ 63.イダー・ムドラ 64.ピンガラ・ムドラ 65.シャカタ・ムドラ Ⅳ マノマヤ・コーシャ(意思鞘) 第12章 保護のムドラ 66.ヴァイカーラ・ムドラ 67.スワスティ・ムドラ 68.グプタ・ムドラ 69.ガネーシャ・ムドラ 第13章 回復のムドラ 70.ドヴィムカム・ムドラ 71.クールマ・ムドラ 72.プラニダーナ・ムドラ 73.ウシャス・ムドラ Ⅴ ヴィジュニャーナマヤ・コーシャ(理智鞘) 第14章 八支則のムドラ 74.カポタ・ムドラ 75.サンプタ・ムドラ 76.ハスタプラ・ムドラ 77.クベラ・ムドラ 78.プシュパーンジャリ・ムドラ 79.ヴィシュッダ・ムドラ 80.チャトゥルムカム・ムドラ 81.ムシュティカーム・ムドラ 82.サークシー・ムドラ 83.チン・ムドラ 84.ムールティ・ムドラ 85.ディールガ・スワラ・ムドラ 86.イーシュヴァラ・ムドラ 87.アビシェカ・ムドラ 88.ダルマダートゥ・ムドラ 89.マンダラ・ムドラ 第15章 精神覚醒のムドラ 90.シヴァリンガム・ムドラ 91.シューンヤ・ムドラ 92.パッリ・ムドラ 93.アーヴァーハナ・ムドラ 94.カルナー・ムドラ 95.プールナ・ジュニャーナム 96.ヴァラーカム・ムドラ 97.シャクティ・ムドラ 98.ウッターラボディ・ムドラ 99.カーレシュヴァラ・ムドラ Ⅵ アーナンダマヤ・コーシャ(歓喜鞘) 第16章 瞑想のムドラ 100.プラージュナ・プラーナ・クリヤー 101.メダー・プラーナ・クリヤー 102.ジュニャーナ・ムドラ 103.ディヤーナ・ムドラ 104.バイラヴァ・ムドラ 第17章 祈りと帰依のムドラ 105.フリダヤ・ムドラ 106.アーダーラ・ムドラ 107.テジャス・ムドラ 108.アンジャリ・ムドラ Ⅶ 付録
「アーユルヴェーダ」に関するよくある質問
Q. 「アーユルヴェーダ」の本を選ぶポイントは?
A. 「アーユルヴェーダ」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「アーユルヴェーダ」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ア-ユルヴェ-ダ: 日常と季節の過ごし方』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで86冊の中から厳選しています。
Q. 「アーユルヴェーダ」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「アーユルヴェーダ」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。









































































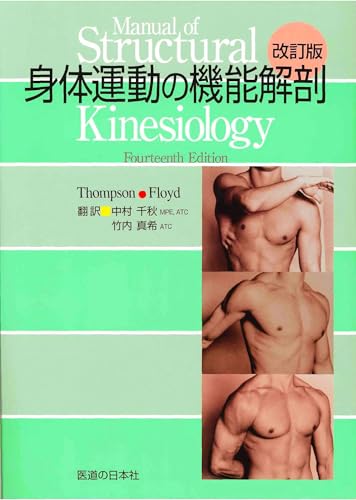







![『やさしく学ぶYOGAアジャストメント -基本アーサナ21選 [改訂版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51TO9gALwYL._SL500_.jpg)
















