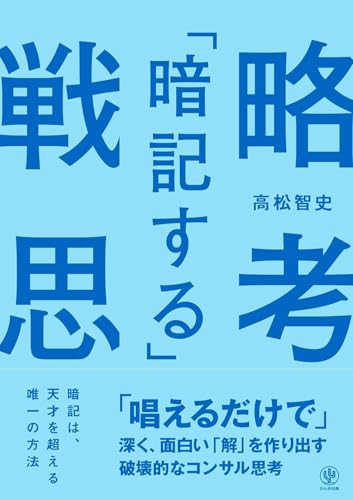【2025年】「仮説思考」のおすすめ 本 156選!人気ランキング
- 仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法
- 新版 考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則
- イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」
- ロジカル・シンキング (Best solution)
- 世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく
- マンガでわかる! 仮説思考
- 論点思考
- 紙と鉛筆で身につける データサイエンティストの仮説思考
- 問題解決力を高める「推論」の技術
- 右脳思考
この書籍は、仮説思考を用いることで作業効率を大幅に向上させる方法について解説しています。著者の内田和成は、BCGコンサルタントとしての経験を基に、仮説を立てることの重要性やその検証方法、思考力を高める方法を紹介しています。目次には、仮説思考の概念から始まり、実践的なステップが示されています。内田は東京大学卒で、経営戦略の専門家としての経歴を持っています。
バーバラ・ミントが著した本は、コミュニケーション力を向上させるための文章の書き方を紹介しています。内容は、書く技術、考える技術、問題解決の技術、表現の技術の4部構成で、特にピラミッド構造を活用した文書作成法に焦点を当てています。また、構造がない状況での問題解決や重要ポイントのまとめも含まれています。
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
本書は、体系的かつシンプルなロジカル・コミュニケーション技術を習得することを目的としています。著者たちは、訓練を通じて誰でもこの技術を身につけられると確信しています。内容は、伝えることの重要性や論理的思考の整理、構成技術に関する具体的な方法を提供しています。著者は共にマッキンゼーでの経験を持ち、コミュニケーション戦略やトレーニングに従事しています。
この本は、世界最高峰の経営コンサルティング会社で教えられている問題解決の考え方を、中高生向けに身近なストーリーとイラストを交えて解説しています。問題を小さく分けて考えることで解決策が見えてくることを学び、自ら考え行動する力を育む内容です。目次では、問題解決能力の習得、原因の見極め、目標設定と達成方法についての章が設けられています。著者は、経済を専攻した後にマッキンゼーでの経験を持つ渡辺健介氏です。
本書は、ビジネスパーソンが「仮説思考」を活用することで、情報収集や分析にかける時間を減らし、迅速な意思決定を可能にする方法をマンガ形式で紹介しています。著者の内田和成氏は、仮説を立てることが仕事の効率を上げる鍵であり、間違いから学びながら仮説を修正していくプロセスが重要であると述べています。また、論点思考を通じて真の問題を見つけることも強調されています。全体として、仮説思考を用いることで仕事のスピードを3倍にする方法を解説しています。
この本は、成果を上げるためには「正しい問い」を立てることが重要であると説いています。著者の内田和成は、問題解決力を向上させるための戦略思考や論点の絞り込み方法を解説しています。目次には、正しい問いの設定や論点の確認、ケーススタディを通じた思考の流れの理解、論点思考力を高めるための方法が含まれています。内田氏は早稲田大学ビジネススクール教授で、豊富なコンサルティング経験を持っています。
本書は、データサイエンティストの思考過程を紙と鉛筆を使って学ぶことを目的としています。PythonやRなどのプログラミング言語を使わず、40問のクイズを通じてデータの読み解き方や説明の仕方を体験できます。デジタル時代に必要なデータリテラシーを身につけたい人や、データを使って論理的に考えたい人におすすめです。各章では、データを読む、説明する、分類する、法則を見つける、予測する力を育む内容が展開されています。
本書は、問題解決のための思考法を提供し、経験がなくても効果的な仮説を立てる方法を解説しています。大前研一氏が推薦する通り、ビジネスリーダーが現場で使える実用的な内容で、全体を俯瞰して課題を発見する手法や、7つの問題解決ステップを紹介しています。著者は高松康平氏で、マッキンゼー出身の専門家です。
本書は、企業が直面する複雑な課題を解決するための思考法を提案しています。フレームワークやネット検索に依存せず、アップルやグーグルなどの成功事例を通じて、独自の解決策を見つける方法を示します。著者の高野研一氏は、キャリアアップや非連続な変化への対応に必要な「超仮説」を立てる力を強調し、実践を重視しています。
本書では、生産性の高いマネジャーが求められる問題解決力について、イシューの特定、考え方やロジック、伝え方の3つの要素を解説しています。働き方改革の中で、限られた時間で最善の解を導くために、戦略コンサルタントが実践する「ゴールから逆算した仮説」と「構造化したコミュニケーション」による効率的な解決方法を提案しています。また、ムダな会議や手戻りロスを減らし、チームの生産性を向上させるための改善策が示されています。著者はKPMGコンサルティングの執行役員で、多様な業界でのコンサルティング経験を持っています。
本書は、ビジネスにおける問題解決や戦略思考、データ分析などに役立つフレームワークを紹介しています。忙しいビジネスマンが収入を増やすために必要な知識やスキルを身につけるための内容で、具体的なフレームワークやアイデア発想法、データの魅力的な伝え方などが収録されています。著者は新規事業プロデューサーの永田豊志氏で、幅広いビジネス経験を持つ専門家です。
この書籍は、仕事の本質や「いい仕事」が生まれる過程、そしてそれを「自分の仕事」にするために必要な要素について探求しています。著者は八木保や柳宗理、パタゴニア社など、様々な成功事例を訪ねて記録を残し、多様化する働き方に対する指針を提供しています。また、文庫化にあたり10年後のインタビューも追加されています。著者は西村佳哲で、建築設計を経てデザインレーベル「リビングワールド」を代表しています。
この書籍は、10年後に後悔しないためのキャリアマネジメントについての指南書です。内容は、キャリアの位置づけや自己満足度を分析し、自己実現に向けた戦略を立てる方法を解説しています。また、実際のキャリア事例を通じて学ぶことができます。著者は村尾佳子で、経営学の専門家として多くの講義やNPO活動にも関与しています。
本書は、効率的な読書法や本の選び方、活用法を体系的に解説したもので、著者「ぶっくま」さんのオリジナルメソッドを紹介しています。読書を通じて人生や仕事を向上させたいが方法が分からない人に向けて、具体的な手法や習慣化のポイントを図解付きで提供。内容は、選書の重要性、効率的な読み方、アウトプットの方法、読書習慣の確立など多岐にわたり、誰でも実践可能な内容となっています。
この本は、まさに「本の使い方」を教えてくれる究極のガイドです!これまで私は、何となく興味のある本を手に取り、漫然と読んでいましたが、この本を読んでからは、自分が本に何を求めているのか、どう活用すれば良いのかがクリアになりました。特に、図解が豊富で、「ひと目でわかる」作りになっているので、文章だけでは掴みにくいコツやテクニックが直感的に理解できます。「目的別に読む方法」や「読んだ本を記憶に定着させるテクニック」など、実生活ですぐに試したくなるヒントが満載で、読書の楽しさと効率が倍増しました。本好きはもちろん、これから読書を始めたい人にもぜひおすすめです!
本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドブックで、ビジネス部門や情報システム、現場の人々に向けて、仮説検証とアジャイル開発を基にした基本的な知識を提供します。DXの成功には、戦略と現場活動の一致が重要で、その体制や進め方を提案します。DXを進める4つの段階(業務のデジタル化、スキルのトランスフォーメーション、ビジネスのトランスフォーメーション、組織のトランスフォーメーション)を詳述し、関連するキーワードや具体的な構成も示しています。著者は、実践的な経験を持つ専門家です。
この書籍は、経営コンサルティングの歴史や影響力、特に日本における展開について詳述しています。経営コンサルタントの役割や実務、業界の課題と変革の必要性についても触れています。著者は、マッキンゼーでの経験を持つ並木裕太氏で、様々な産業でコンサルタントとして活躍しています。
この書籍は、ビジネスパーソンの成長を加速させるための基礎トレーニングとスキルチェックを提案しています。著者たちは、論理思考力やコミュニケーション力、情報収集力など、どこに行っても通用するスキルを10項目にわたって解説しています。著者陣はグロービス経営大学院の教授や研究者であり、各自が多様なバックグラウンドを持っています。
この本は、情報を整理・分析し、図を使って考える技術を提供します。内容は「図解思考」の理論や、自分の考えを図でまとめる方法、効果を高めるフレームワークの活用法、実践例などを含んでいます。著者は知的生産研究家の永田豊志氏です。
この本は、「暗記する」戦略思考を学ぶための実用的なガイドです。戦略思考とは、解答や意見を生成するための考え方であり、著者は特定のフレーズを覚えることでこの技術を身につけることができると提唱しています。内容は、実際のビジネスや人生のシナリオを通じて思考を切り替える方法や、戦略思考のマップを提示し、考える力を強化するための具体的な手法を紹介しています。著者は、NTTデータやBCGでの経験を基に、面白くインパクトのある思考を追求しています。
この書籍は、グロービスの「思考領域トップ」によるロジカル・シンキングの入門書で、ビジネスマンに必要な20の技術を解説しています。難易度が徐々に上がる問題を通じて、思考力や伝達力、数字の扱い方を身につけることができます。特に、根拠を考えること、状況を正しく認識すること、数字を活用すること、効果的に伝えること、コンピュータを活用することが重要なテーマです。著者はグロービス経営大学院教授の岡重文氏です。
この書籍は、現代人が抱える時間に関する悩みを解決するためのガイドです。ストーリー仕立てで、時間の使い方や投資の重要性、優先順位の付け方、トラブルに時間を奪われない方法などを解説しています。著者は麗澤大学の教授で、実践的なアドバイスを提供し、読者が自分の時間を有効に活用できるよう導きます。
本書は、顧客に価値を提供するプロダクトを作るためのプロダクトマネジメントについて解説しています。プロダクトマネージャーの役割や戦略の立て方、実験と最適化のプロセスを紹介し、プロダクト主導の組織文化を支える方針についても触れています。企業が顧客のニーズに焦点を当て、成果を重視することの重要性を強調し、ビルドトラップを避けるための原則を提供します。全てのプロダクトチームや関係者にとって必携の一冊です。
本書は、プロダクトマネジメントとデジタルトランスフォーメーション(DX)を成功に導くための思考法「ラディカル・プロダクト・シンキング」を解説しています。イノベーションには明確なビジョンと戦略、優先順位の浸透が必要ですが、それを日常業務に落とし込むのは難しいとされています。著者は、組織と市場に合ったビジョンの作成、戦略の立案、優先順位付け、施策の仮説検証、ビジョンの浸透の5つのアプローチを提案し、特にプロダクトマネジメントやDXに関わるリーダーに向けての必読書としています。内容は新しいマインドセットや文化の形成、社会への影響についても触れています。
日本企業には戦略を実行できるリーダーが不足しており、36歳の変革リーダーが市場シェアを逆転させた実話を基に改革プロセスを描いたケースストーリーです。著者は三枝匡で、経営の実践や会社再建に豊富な経験を持っています。
スタートアップを立ち上げるために必要なリーンスタートアップという考え方を学ぶために読んだ。今の時代、スタートアップでも大企業でもどんな組織でもリーンスタートアップの考え方は重要で、小さいことをクイックに行い小さい成功をおさめてそこから雪だるま式に大きくしていくことが大事。小さい状態で失敗しても大きな痛手ではないので、とりあえず作ってみて検証する!ただ小さくはじめると小さくおさまってしまうという考え方も提唱している人がいて面白いと思った。イーロン・マスクなどはスペースXを起業する際に小さくなんか始めていない。出来るだけクイックに動いていたが最初から巨額の投資をしていた。イーロンはPaypalの売却益で巨額の富を得ていたからという人もいるが、それでも足りないくらいの額を突っ込んでいる。巨額の富を得ると、そこから小さく色んなところに投資してどれか当たればよいという考えてしまうケースが多い気がするが、本当に偉大なことを成し遂げたいのであれば小さく始めるという思考を取り払って大きく勝負に出ることも必要かもしれない。
この書籍は、ビジネスに必要な論理的思考力を豊富な演習と事例を通じて学ぶことを目的としています。斬新な発想や機会の発見、効果的なコミュニケーション、集団意思決定、説得・交渉・コーチングのスキル向上を促し、成功をつかむための手助けをします。内容は論理の構造化や思考の基本姿勢、現状分析、因果関係、仮説検証などを含む構成になっています。
本書は、新規事業やDXにおける成功の鍵である「プロダクトマーケットフィット(PMF)」について解説しています。多くの新規事業が市場に適した製品を提供できず失敗する中、PMFを達成するための具体的な方法や、14社の事例を通じた実践的なノウハウを紹介しています。新規事業の責任者やプロダクトマネージャーにとって必読の一冊です。
本書は、リーダーに必要な10のスキルを提示し、個人だけでなくチームとしての成果を重視する重要性を説いています。具体的なスキルには、環境理解、会計知識、組織文化の理解、目標設定、プランニング、段取り、伝達、セルフマネジメント、習慣づけ、メンバー育成が含まれ、これらを磨くことで、将来にわたって通用するリーダーシップを身につけることが目指されています。著者はグロービス経営大学院の専門家たちです。
本書『イノベーションの競争戦略』は、企業がイノベーションを成功させるために必要な行動変容に焦点を当てています。著者は、イノベーションは単なる技術革新ではなく、顧客の行動や価値観を変えることが本質であると主張します。内容は、イノベーションのフレームワークやドライバー、成功のメカニズムを解説し、企業が競争優位を築く方法を示しています。具体例としてZoomの普及や家事代行ロボットのルンバが挙げられ、顧客の心理や行動の変化が如何に新たな価値を創造するかが説明されています。
この書籍は、ボストン・コンサルティング・グループのノウハウを基に、勝てる戦略を生み出すための「イノベーション」を促進する発想法を解説しています。内容は、戦略に命を吹き込むインサイトの重要性、思考のスピードを上げる方法、三種類のレンズを用いた発想力の向上、インサイトを生み出すための頭の使い方、そしてチーム力を活かしたインサイト創出の方法について触れています。著者は御立尚資氏で、幅広い業界で事業戦略やイノベーションに関するプロジェクトを手掛けています。
この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。
本書は、ビジネスにおける「提案の技術」をテーマに、論理思考やプレゼンテーション能力を実践的に学ぶためのガイドです。著者は、外資コンサルや商社での経験を基に、提案を成功に導くための基本的なスキルを整理しています。内容は、論理思考力、仮説検証力、会議設計力、資料作成力の4つの能力に焦点を当て、各章がストーリー、解説、まとめで構成されています。ビジネス現場での実践的なスキルを身につけることができる内容です。
ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。
著者は、手本や解答がない現代において成功するための思考法を示し、戦略的思考の重要性を解説しています。内容は、戦略的思考の基礎や企業への応用、阻害要因、グループ形成、さらに戦略的経営計画の実践について詳細に述べています。
本書は、仕事や趣味での新しい知識や技術の習得が人生を豊かにすることをテーマに、上達の違いを記憶心理学や学習心理学の観点から分析しています。上達の力学は「スキーマ」や「コード化」にあり、独自の練習法やスランプ対策を提案しています。著者は社会心理学者の岡本浩一で、努力が報われるための指南書として、本人や教育者、コーチに向けた内容となっています。目次は能力主義、記憶のしくみ、上達の方法論、スランプの対策などを含みます。
この本は、統計学の基礎から応用までを網羅し、データ分析に必要な知識を一冊にまとめた教科書です。内容は、統計学の役割、母集団と標本、推測統計、仮説検定、回帰分析、統計モデリングなど多岐にわたります。著者は阿部真人で、幅広い研究分野での経験を持ち、初心者向けの講義でも高い評価を得ています。
本書『戦略フレームワークの思考法』は、経営戦略を策定するためのフレームワークを全面的にリニューアルしたもので、論理と直感を活用しながら問題解決やアイデア創出を支援します。著者は経営コンサルタントの手塚貞治氏で、伝統的なフレームワークから新しいものまで幅広く紹介。特に「並列化」「階層化」「二次元化」「時系列化」「円環化」という5つの思考パターンに基づき、各フレームワークの使い方やメリット・デメリットを具体例を交えて解説しています。初心者でも理解しやすく、実践的なノウハウが得られる内容です。
本書は、良質なアイデアを生み出すための練習帳で、具体例を交えた手法を提供します。著者は博報堂の専門家で、実際に使われているアイデア発想法や20の練習問題を通じて、アイデア力を強化します。難解な内容はなく、アイデア出しに不安がある人にも適しています。目次には、アイデアの仕組みや顧客行動の観察法、会議の進め方などが含まれています。
この書籍は、社会で騙されないための自己防衛の方法を解説した社会心理学の名著です。著者ロバート・B・チャルディーニは、影響力のメカニズムを8つの章に分けて説明し、具体的な戦略や心理的原理をユーモラスに描いています。新訳版では、マンガや事例が追加され、現代の広告戦略や社会問題についても触れられています。読者は、プロの手口を理解し、賢い消費者になるための知識を得ることができます。
ページ数が多く読み切るには根気がいるが、中身は目から鱗の内容ばかり。知っておくだけど対人関係が有利に働く法則などが多く学べる。
人間関係の悩みが尽きない社会において、思考が動く考えられる本となっていました。自分自身の行動を社会に当てはめ参考にしていけるので自分にとってポジティブな内容でした
この書籍は、人気ビジネススクール教授による「会計」と「経営戦略」の統合的な学習法を紹介しています。会計力と戦略思考力を同時に養うことを目指し、トヨタやニトリの決算書を通じて実践的に学ぶ内容です。内容は、損益計算書や貸借対照表の読み解き方、業界競争環境の理解、バリューチェーンやマーケティング戦略の分析など、多岐にわたります。最終的には、会計指標の活用やIFRS決算書の分析方法についても触れています。
本書は、現代におけるマインド・コントロールの危険性とその技術について解説するもので、カルトやテロ集団だけでなく、さまざまな組織や家庭においても利用されていることを指摘しています。著者は精神科医の岡田尊司氏で、彼は心の崩壊と戦う中で、マインド・コントロールの原理、騙されやすい人の特性、そしてその解決策について述べています。各章では、テロリズムや無意識の操作技術、行動心理学などが扱われ、現代社会における孤独や自己愛がもたらす影響が考察されています。
「直感」だけでは伝わらない。「データ」だけではイノベーションは生まれない。AI時代の人間が主役の考え方 ●直感をビジネスに生かせない●仮説とデータが一致しない●いくらデータ分析しても、成果が出ない●結局、データより直感で判断している……。「その根拠は?」「なぜ、そう思うの?」「裏付けはあるの?」こういう指摘を受けるのは、あなたが、正しいデータの見方・使い方をしていないから。文系コンサルタントによる、文系ビジネス人材のためのデータとの向き合い方 はじめに――あなたは本当にデータを「見て」いますか? 1章 爆発的に加速するデータ時代のなかで ――文系"ビジネス人材”のデータとのつき合い方 2章 データ活用、DX推進における誤解 ――あなたのデータ分析、データ活用がうまくいかないのはなぜか 3章 人間が主役のデータ活用 ――"ビジネス人材”だからこそ可能なデータインフォームドな思考法 4章 仮説思考でデータと向き合う技術 ――データ分析だけでは出てこない、自分なりの「仮の解」の導き方 5章 データインフォームド思考 実践編 ――「報告」「企画」「営業」……。 具体的シーンで"仮説とデータをつなぐ”技術 おわりに――「成功の再現性」に寄与するビジネス人材を目指そう
本書は、経済が縮小する中で短期的思考に陥る人々に対し、長期的思考の重要性を数理的に証明する内容です。著者の西成活裕は、目先の利益を優先することで技術の蓄積や次世代プロジェクトが疎かになる現状を指摘し、ビジネスに役立つ「四つの逆説の法則」を提唱しています。経営者や研究者にとって必読の書です。
「ブルー・オーシャン戦略」は、競争の激しい既存市場から脱却し、未開拓の市場を創出するための戦略を体系化した書籍です。著者は、世界で350万部以上が売れ、43カ国語に翻訳されたこのベストセラーを通じて、企業や非営利組織が新市場を開拓できる方法を示しています。内容は、戦略の策定と実行に関する具体的な手法やフレームワークを提供しており、幅広い組織に役立つものとなっています。著者は、国際的なビジネススクールの教授陣であり、戦略論や国際経営に精通しています。
本書は、ビジネスにおける問題解決の技術と実行方法を体系的に解説したテキストで、業種や立場を問わず活用できるスキルを提供します。問題解決の手順を明確にし、実践的な内容を重視。特に問題の特定能力を強調し、実例を交えた構成で理解を深めることを目指しています。全7章で、問題解決の手順を段階的に学び、結果の評価や定着化についても触れています。著者は経営コンサルタントとしての経験を活かし、実践的なビジネススキルを伝授します。
ボストン・コンサルティンググループの戦略理論を紹介する本で、世界のトップ企業が採用する競争原理について解説しています。目次には、競争優位の視点、株主価値、顧客価値、バリューチェーン、事業構造、コスト優位、時間優位などのテーマが含まれています。著者は水越豊氏で、幅広い業界で戦略や組織に関するプロジェクトを手掛けている専門家です。
本書では、日本の社会調査の多くが信頼性に欠ける「ゴミ」であり、これが次々と新たな誤情報を生み出していると指摘しています。これは、適切な方法論が認識されていないためであり、デタラメなデータが広まる現状を改善するためには、正しい情報を見分ける力を養い、方法論を学ぶ必要があると提案しています。目次では、豊かさ指標の失敗やマスコミの問題、バイアスの影響、リサーチ・リテラシーの重要性について論じています。
この書籍は、累計10万部を突破した「レスポンスアップの鬼」として知られる著者が、非対面・非接触で紙媒体やWEBで商品を効果的に売るための技術を紹介しています。内容は、売れるための前提や顧客の購買理由、ターゲットに応じた訴求方法、キャッチコピーの作成、広告テスト法、心理テクニックなど多岐にわたります。著者は、セールスコピーライターとして多くの成功事例を持つ専門家です。
フィールドワークには言わく言いがたいコツがあって、マニュアル化などできない、と言われます。しかし本書は、著者自身の調査体験を自ら吟味しながら述べるという、「フィールドワークのフィールドワーク」とも言えるユニークなスタイルによって、この難問に見事応えました。二十数年に及ぶ研究と、初心者が抱く疑問を知り尽くした教育経験豊かな著者にして初めて書くことができた、究極の入門書です。フィールドに赴く前に、調査の最中に、そして研究をレポートにまとめるときに、繰り返し読み直し、新たなアドバイスを発見できる、フィールドワーカー必携の書となるでしょう。 目次 用語解説 はじめに 謝 辞 第Ⅰ部 方法篇 第1章 暴走族から現代演劇へ――体験としてのフィールドワーク 対象(者)との出会い 矯正施設における聞きとり調査/暴走族についての民族誌的調査/現代演劇のフィールドワーク 方法・技法の模索 「黒い報告書」から民族誌的リサーチへ/リサーチツールの開発 語り口の変化 混成ジャンルとしての民族誌/語り口と読者のタイプ/フィールドワーカーのスタンス 結論 第2章 他者との出会いと別れ――人間関係としてのフィールドワーク アクセス 少年院――フォーマルな組織の場合 ツテをたどる/調査報告書のイメージ/フィールドワーカーの邪魔者性/交際範囲を拡げる/問題関心の推移と施設調査の限界 暴走族・右京連合――自然発生的な集団の場合 セイコとの出会い/初期のアクセスにおける失敗/エイジとの出会い/制度的関係とネットワーク的関係 まとめ 役割関係 インフォーマントとラポール 自己紹介と印象のマネジメント/友人としてのインフォーマント/師匠としてのインフォーマント/ 参与観察 役割関係のタイプ 異人性とストレス 第三の視点 人間関係とストレス オーバーラポールの問題/フィールド日記の効用 結論 第3章 「正しい答え」と「適切な問い」――問題構造化作業としてのフィールドワーク 問題解決から問題発見へ 暴走族――比較的順調に問題の構造化が進んだケース 少年院調査での思いつき(初発の問題関心)/ジャーナリスティックな本の功罪/リサーチクェスチョンの明確化/先行研究の検討と文献リストの効用/現場でリサーチクェスチョンを組み立てる/民族誌執筆と最終的な問題設定 現代演劇――大幅な「仕切直し」があったケース 敗因分析レポート/時間的余裕/仕切直し――問題設定の変更/初戦における敗退とリターンマッチ/調査対象に関する事前知識――現場についての土地勘 /理論と研究課題のマッチング データと仮説の二面性 データの二面性 問題発見のための材料/フィールドワークにおける問題構造化/サーベイにおける問題構造化/仮説の二つの意味/広義の仮説と狭義の仮説/フィールドワークにおける仮説検証法的アプローチ/問題設定と仮説についての問い/ フィールドワークにおける問いと答えの対応 結論 第Ⅱ部 技法篇 第4章 フィールドノートをつける――「物書きモード」と複眼的視点 フィールドノーツとは何か? フィールド@ノート@とフィールド@ノーツ@ RASHOMON 『羅生門』課題/学生のフィールドノーツ/佐藤のフィールドノーツ/未来の自分は他人 現場メモをとる いつどこで書くか――現場メモと役割関係 目ざわりな現場メモ/警戒的反応への対応 何についてどのように書くか――現場メモと「物書きモード」 清書の意味とメモをとる状況/視覚的記憶と聴覚的記憶/物書きモード フィールドノーツを清書する いつどこで書くか――忘却とのたたかい 何についてどのように書くか 「フィールドワーク初日」のパニック/日付と時間――出来事と観察行為の基本的な文脈/フィールドノーツのストーリー性/フィールドノーツのストーリー性と民族誌の文脈性/ふたたび物書きモード――現場調査におけるさまざまなテクストと読者 結論 第5章 聞きとりをする――「面接」と「問わず語り」のあいだ 問わず語りに耳を傾ける――インフォーマル・インタビュー 暴走族取材における失敗――「面接」と「インタビュー」のあいだ 面接とネクタイ/面接とインタビューの効率性/インタビューと現場観察/ ウィリアム・ホワイトの失敗――「インタビュー」と「問わず語り」のあいだ ホワイトの「失言」と方向転換/問わず語りの効用 インフォーマル・インタビューとは何か? 聞きとりのタイプと問題の構造化/インフォーマルな聞きとりと役割関係 インフォーマル・インタビューの記録法と注意点 フィールドノーツによる記録/直接話法と間接話法/信頼関係への配慮 あらたまって話を聞かせてもらう――フォーマル・インタビュー 下調べをして質問の内容を確定する 無神経な質問/下調べと仮説――「構造化されたインタビュー」の意味 劇団取材の例(1)――下調べ/劇団取材の例(2)――インタビューひな型/ アポイントメントをとる 聞きとりをする 服装・時間/聞き手の人数/質問リストと関連資料/テープレコーダ 聞きとりの内容を記録する インタビュー記録の種類/テープ起こしと電子小道具/インタビュー記録の整理法 結論 第6章 民族誌を書く――漸次構造化法のすすめ 理論とデータの「分離エラー」 「最後のハッタリ」 分離エラーの原因 問いと答えのチグハグな関係 問いと答えの対応/民族誌作成作業の位置づけ 漸次構造化法と「分厚い記述」 漸次構造化法的アプローチ 分厚い記述とトライアンギュレーション フィールドワーカーの挙証責任/漸次構造化法とトライアンギュレーション さまざまな書き物の集大成としての民族誌 調査データの分析(1)――わきゼリフ、注釈、同時進行的覚え書き わきゼリフ(つぶやき) 注釈(コメント) 同時進行的覚え書 き(総括ノート) 調査データの分析(2)――コーディングとデータベースの構築 準備作業 コーディング 編集作業としてのコーディング/「天下り式コーディング」と「たたき上げ式コーディング」/コーディングによるテーマのあぶり出し/コードの体系化と階層化――オープン・コーディングと焦点をしぼったコーディング コーディングのための専用ソフトウェア 資料のデータベース化/電子化の効用/アイディアツリーという福音 理論的覚え書き(理論的考察)・統合的覚え書き(総合的考察)・中間報告書 民族誌を読む 文章修業としての読書 シカゴ学派の都市民族誌/文章修業としての読書/ルポルタージュ批評課題/翻訳書の効用と限界/ 結論
この書籍は、戦略コンサルタントのスキルを学ぶための指南書で、問題解決の基本的な考え方をチャートを用いてわかりやすく説明しています。内容は、思考法(ゼロベース思考や仮説思考)、技術(MECEやロジックツリー)、プロセス(ソリューション・システム)、実践(具体的な活用方法)に分かれており、企業事例も新たに紹介されています。著者は齋藤嘉則で、経営コンサルタントとしての豊富な経験を持っています。
本書は、問題発見に関する技術を2部構成で解説している。前半の「問題発見構想編」では、全体的な問題の構想力を高める方法を探り、後半の「問題発見分析編」では、発見した問題を深掘りし、構造的に分析するテクニックを紹介している。著者は斎藤嘉則で、経営コンサルタントとして豊富な経験を有している。
『ゼミナール経営学入門』は、経営のダイナミズムを理解するためのテキストで、30年以上にわたり支持を受けてきた。新装版では21世紀の読者に合わせたレイアウトに改訂され、内容は企業のマネジメント、環境のマネジメント、組織のマネジメント、矛盾と発展のマネジメント、企業と経営者に関する多様なテーマを網羅。著者は伊丹敬之と加護野忠男で、いずれも経営学の専門家である。
クロネコヤマトの社長が宅急便にカジを切って大成功した時のことが書いてある。周りからは反対されて黒字になるわけないと言われていた個人宅配を見事に軌道にのせた先見の明には脱帽。ネットワーク効果を見越して必ず黒字転換点があるはずと見込んでの一手。経営者がぜひ読むべきオススメの1冊。
本書は、問題解決や企画提案において「良い仮説」を立てる重要性を説いています。情報収集やデータ分析を行う前に、的確な仮説を立てることが成功の鍵であり、仮説がなければ無駄な時間や誤った結論に繋がることを警告しています。著者は、仮説の立案から検証までのプロセスを具体的に解説し、ロジカル・シンキングやクリティカル・シンキングのテクニックを通じて、効果的な仮説作成法を示しています。全体を通じて、実践的な事例を用いながら、問題解決のための体系的なアプローチを提供しています。
この書籍は、効果的なスライド作成やグラフ・チャートの描き方を解説しており、シンプルなスライドにするためのテクニックを紹介しています。内容は、スライドの基本構成、視覚化のためのグラフ・チャート作成方法、シンプルさを追求するためのヒント、そして練習問題を含んでいます。著者は、コンサルティング業界での経験を活かし、わかりやすいスライド作成を教えてきた専門家です。
はしがき 3 第1話 仮説実験授業の授業運営法 ……………………… 11 「授業書」を使う(11) 授業書を読むことから授業がはじまる(12) 予想の選択肢(13) 予想分布を黒板上に集計(14) 理由の発表(15) 討論(15) 実験−その前に予想変更(17) 次の問題に (17) 読み物の役割(18) カリキュラムは作らない(19) まず一つの授業書だけやってみること(20) 感想文を書いてもらう(21) 第2話 仮説実験授業の発想と理論 …………………… 23 仮説実験授業の原則的な考え方(23) 「授業」と「学習」(25) 「予想」と「仮説」(27) 授業の法則性の追求と「授業書」(29)みんなの共有財産としての「授業書」(30) 仮説実験授業の骨組み(31) 教育の民主性と「○×」 式(33) 問題の意図を明確に(34) 頭のよさは着想の豊かさ(37) まちがえ方の教育を(39) 成功・失敗の基準をきめておく(41) 近代科学の成立に学ぶ(44) 第3話 評 価 論 ………………………………………………………… 47 ──なぜ,何を教育するかの原理論 1.誰が何を評価するのか ……………………………………………… 47 目標があれば評価もある(47) 教師の目標・子どもの目標−目的意識に合わせた自己評価(48) 2.相対評価の根源と効用 ……………………………………………… 51 相対評価の根源−ホンネとタテマエ(51) 強引な相対評価批判の誤り−点数のたし算のできる根拠(54) 選択があれば競争がおこる−合理的な相対評価もある(57) 「できる」と思われたいから「できる」−優等生的学習意欲(59) 3.教育内容の改変を …………………………………………………… 62 「みんながやらなければならないこと」は何か(62) 実用的価値と哲学的価値(64) 知らなくてもよいが知っていると楽しいこと(66) 4. 絶対評価の基本 …………………………………………………… 69 合格と不合格の2段階−目標がはっきりしていること(69) 自分のすばらしさがわかる評価−できないことがわかってから教える(72) 学びたいものを学ぶ−テストされたいことをテストする(73) 5. いろいろな場面での評価 ………………………………………… 76 評価は絶えず行われている(76) 感想文−おたがいに評価しあっている内容を知る(77) 孤立して孤立しない論理−自信をもって生きるために(79) 見えない心の動きを見る(80) 態度や探究心−大切だからこそ評価してはいけない(82) 第4話 仮説実験授業の理論の多様化 ……………… 85 ──イメージ検証授業・仮説証明授業・新総合読本・もの作りの授業 松本キミ子さんの絵の授業と仮説実験授業(86) 仮説実験授業とは何であったのか(87) 〈キミ子方式〉の絵の授業の特長(89) 『たのしい授業』の創刊と仮説実験授業(92) イメージ検証授業と仮説実験授業(93) 仮説証明授業と仮説実験授業(96) もの作りの授業と仮説実験授業(99) 新総合読本の作成運動と『社会の発明発見物語』の重要性(100) 授業書の作成について(100) 第5話 どんな授業書があるか …………………………… 104 ──授業書その他の教材一覧 授業書の作成は力学分野からはじまったが……(104) 統一カリキュラムは作らないのが原則(106) 検定教科書にヒントを求めるのも一便法(107) 授業書は途中をとばさないで用いること(108)完成度の高い授業書と教材の解説一覧(109) A.小学校低学年でもできる授業書 ………………………………… 110 足はなんぼん? 背骨のある動物たち にている親子・にてない親子 空気と水 ドライアイスであそぼう かげとひかり ふしぎな石−じしゃく,その他 タネと発芽 おもりのはたらき,その他 B.自然界の多様性をとりあげた基本的な授業書 ………………… 113 磁石 ふしぎな石じしゃく 電池と回路 自由電子が見えたなら ゼネコンで遊ぼう 光と虫めがね 宇宙への道 月と太陽と地球 花と実 30倍の世界 C.物性=原子分子の一般的な性質に関する授業書 ……………… 116 ものとその重さ 空気の重さ もしも原子が見えたなら 分子模型をつくろう 溶解 結晶 粒子と結晶 温度と沸とう 三態変化 水の表面 D.小学校でも教えられる力学関係の授業書 ……………………… 120 ばねと力 磁石と力 まさつ力と仕事量 滑車と仕事量 トルクと重心(てことりんじく・重心と物体のつりあい・天びんとさおばかり) 重さと力・浮力と密度 長い吹き矢,短い吹き矢 ふりこと振動 お茶の間仮説実験・ころりん サイエンスシアターシリーズ E.中学高校程度の物理学関係の授業書 …………………………… 123 速さと時間と距離 力と運動 電流 電流と磁石 ものとその電気 程度のもんだい 磁気カードの秘密 電子レンジと電磁波 偏光板の世界 光のスペクトルと原子 磁石につくコインつかないコイン サイエンスシアターシリーズ F.化学・生物・地学関係の授業書 …………………………………… 127 いろいろな気体 燃焼 錬金術入門 原子とその分類 熱はどこにたくわえられるか 生物と細胞 生物と種 地球 不思議な石,石灰石 G.社会の科学1 (日本の地理・歴史関係の授業書)……………… 129 日本の都道府県 ゆうびん番号 沖縄 日本歴史入門 歌って覚える歴史唱歌 日本歴史略年表 おかねと社会 鹿児島と明治維新 日本の戦争の歴史 えぞ地の和人とアイヌ 名産地・自給率・量率グラフの世界など 新総合読本の中の日本史関係の読み物教材 H.社会の科学2 (世界の地理・歴史関係の授業書)……………… 132 世界の国ぐに 世界の国旗 焼肉と唐辛子 はじめての世界史 世界が一つになってきた歴史 対数グラフの世界 コインと統計 オリンピックと平和 ハングルを読もう I.社会の科学3 (社会の科学・道徳・公害の授業書)…………… 134 社会にも法則があるか 三権分立 生類憐みの令 禁酒法と民主主義 差別と迷信 洗剤を洗う たべものとウンコ たべもの飲みものなんの色 ゴミドン 日本国憲法 靖国神社 道徳の授業プラン 新総合読本の中の〈社会の科学〉読み物 J.算数・数学の授業書 ………………………………………………… 137 つるかめ算 量の分数 分数の乗法 分数の除法 かけざん 2倍3倍の世界 電卓であそぼう 広さと面積 勾配と角度 図形と角度 図形と証明 落下運動の世界 K.国語・外国語などの授業書 ………………………………………… 140 漢字と漢和辞典 漢字の素粒子と原子 道路標識 変体仮名とその覚え方 読点の世界 たのしい授業プラン国語1〜3 1時間でできる国語 ことばの授業 新総合読本のリスト よみかた授業書案 検定国語教科書に収録されたことのある読み物 英語のこそあど 英語と国語のこぼれ話 読者指導に関するもの L.技術・体育・迷信・美術・その他の授業書 ……………………… 144 技術入門 物の投げ方の技術と技能 小久保式開脚とびの授業 コックリさんと遊ぼう 虹は七色か六色か キミ子方式の絵の授業 おやつだホイ! 煮干しの解剖 ベッコウあめ・折り染め・プラバン 仮説実験授業を受けた子どもたちへのメッセージ ……………… 147 たのしく学びつづけるために 予想・討論と実験と 心に残る思い出の授業 第6話 授業の進め方入門 藤森行人 …………………… 148 ──初めて仮説実験授業をする人のために 子どもに「先生」と思ってもらえるとき …………………………… 148 仮説実験授業の授業運営法 …………………………………………… 152 授業の評価は子どもが決める ………………………………………… 161 仮説実験授業研究会会則・趣旨説明 ……………………………………… 170 研究会の最近の活動 …………………………………………………………… 174 あとがき 176 授業書および実験器具等の価格一覧 178